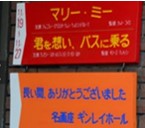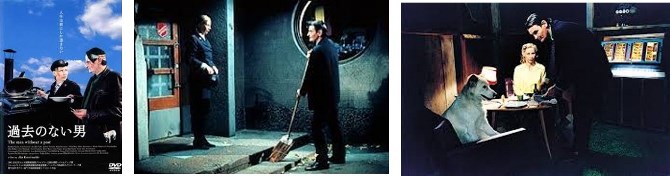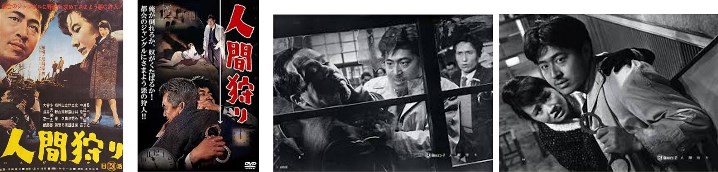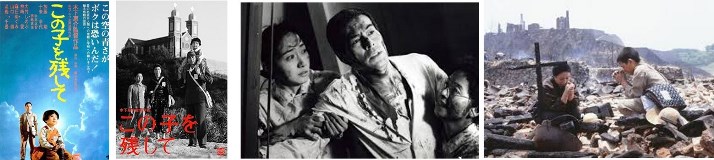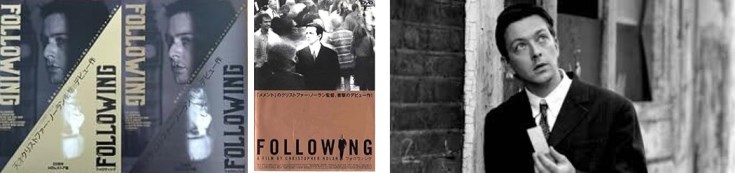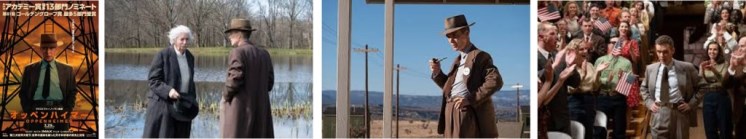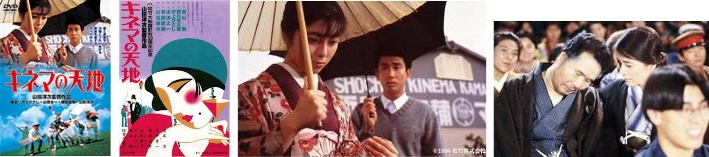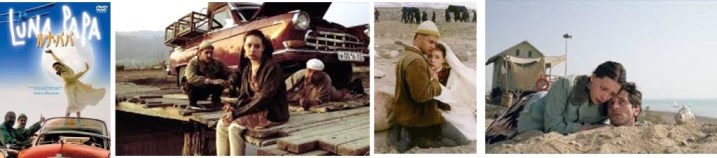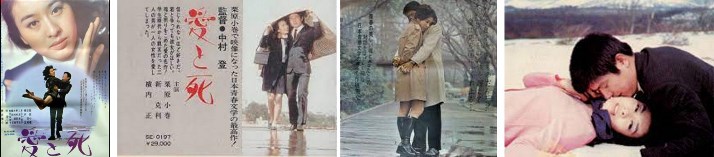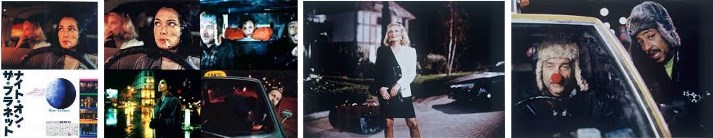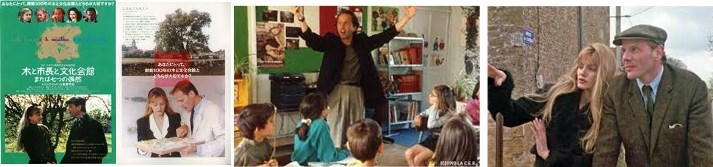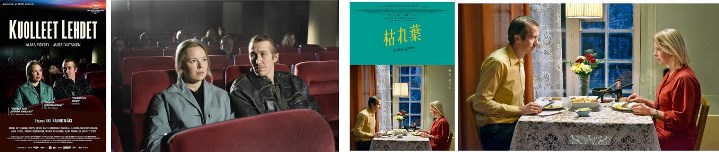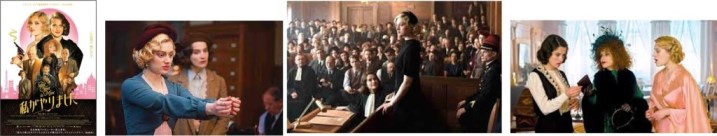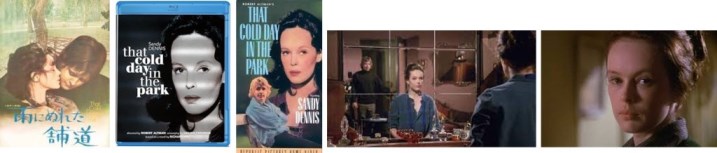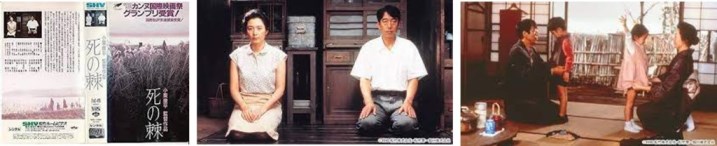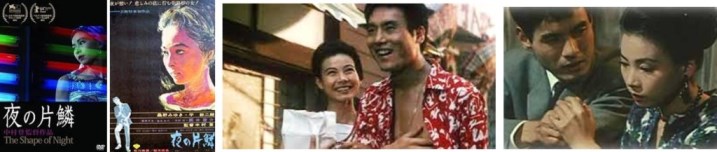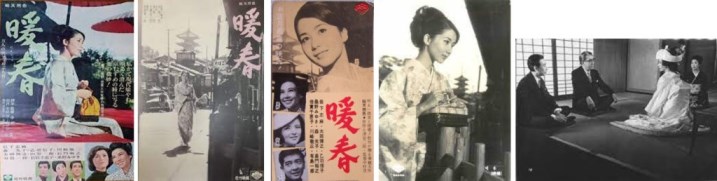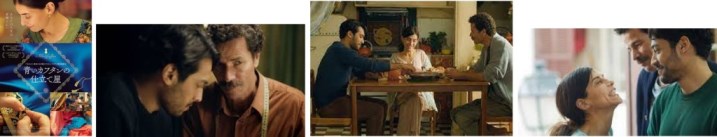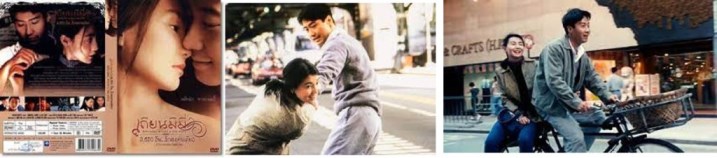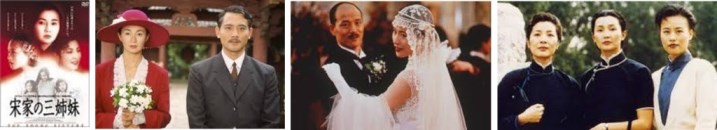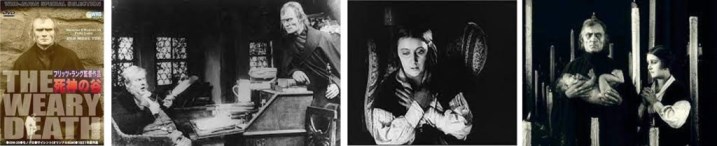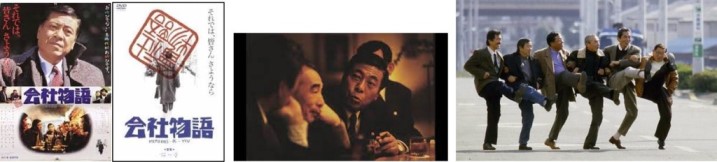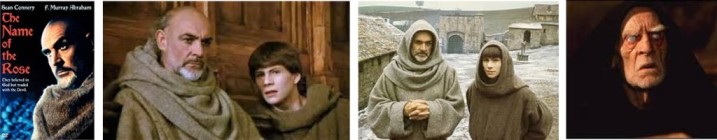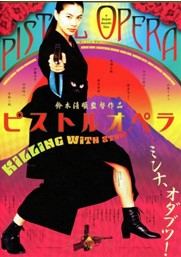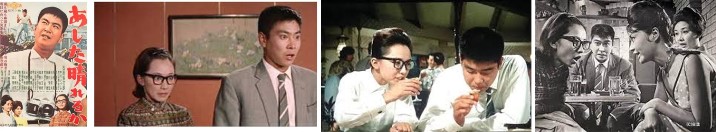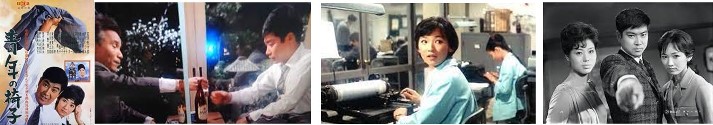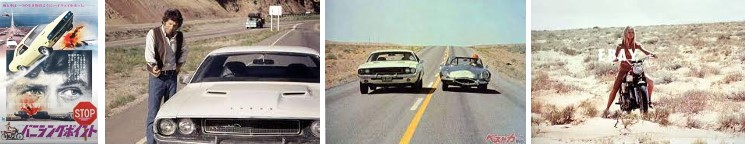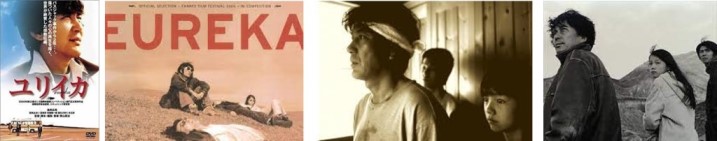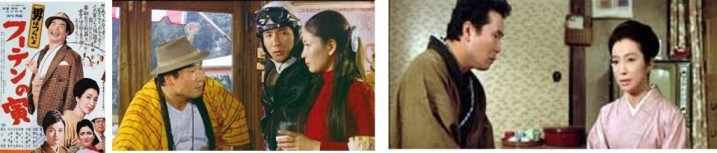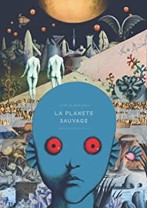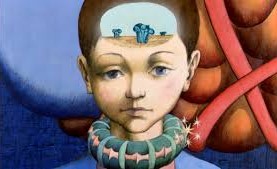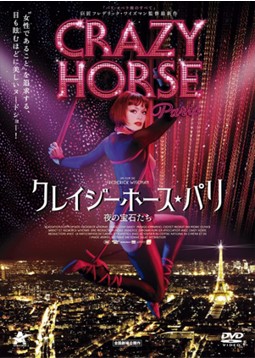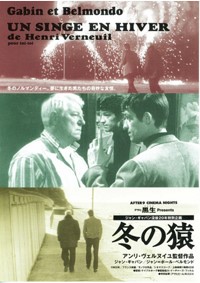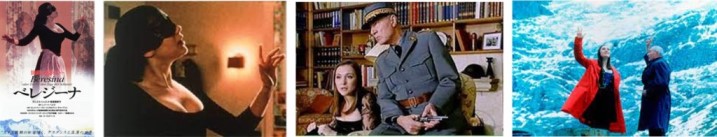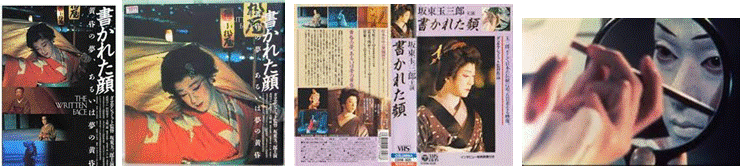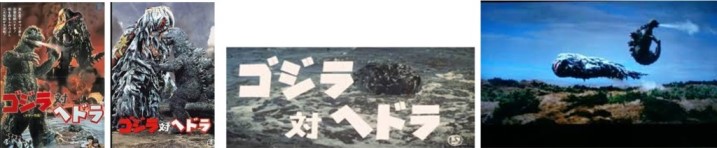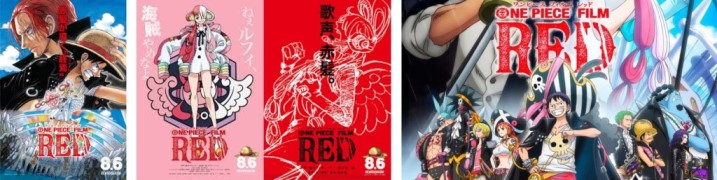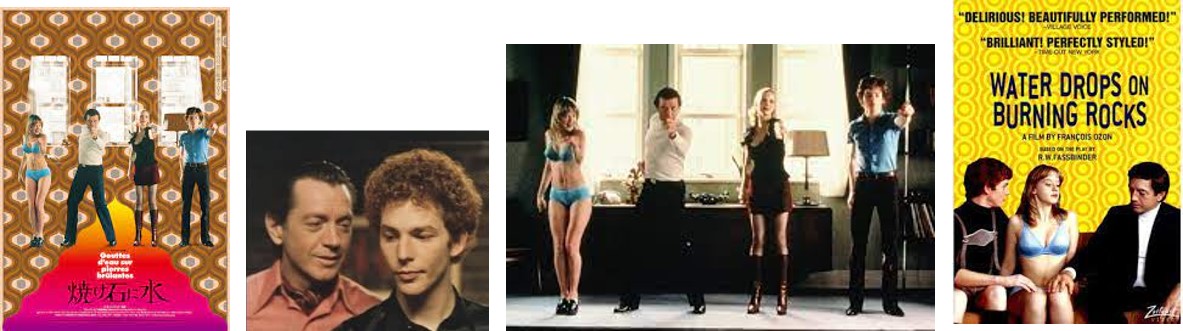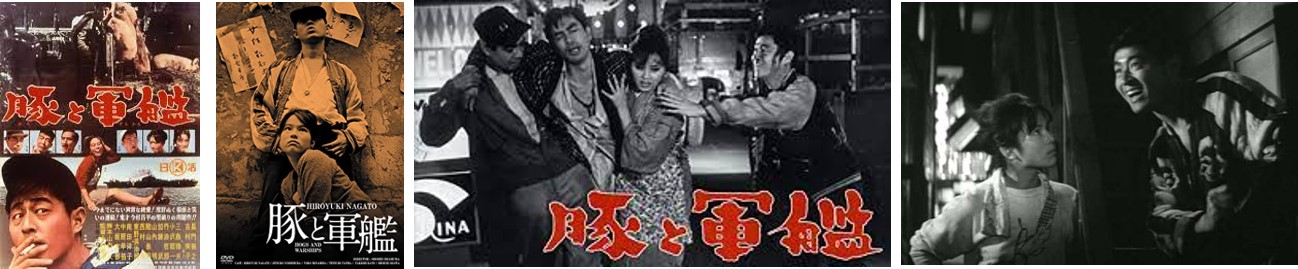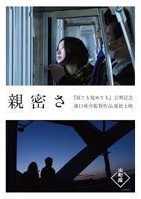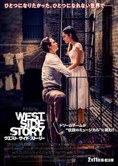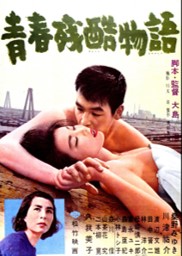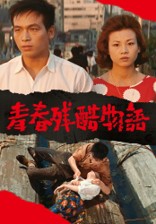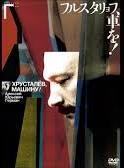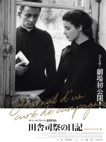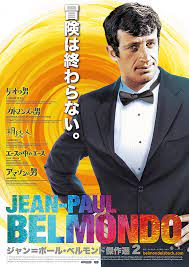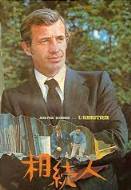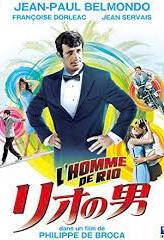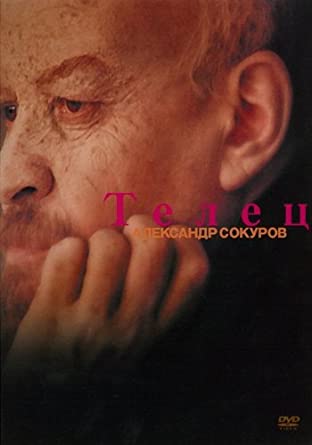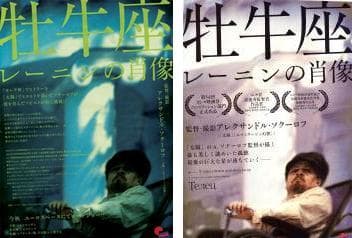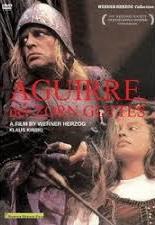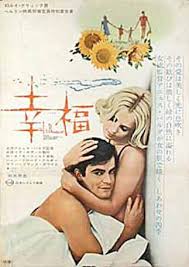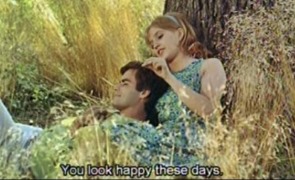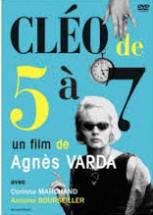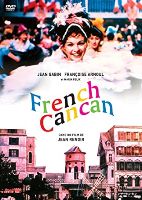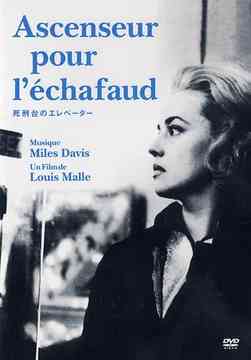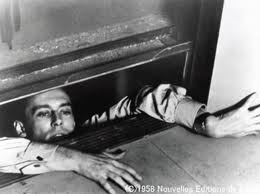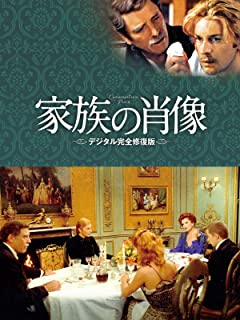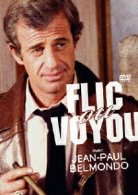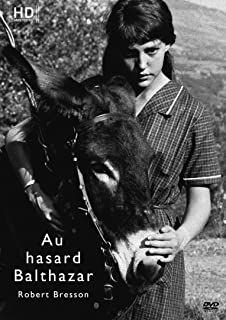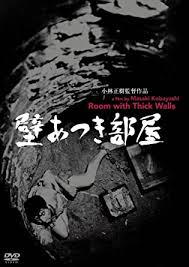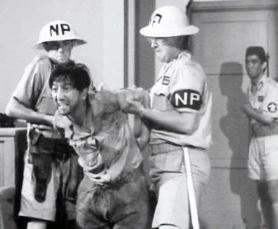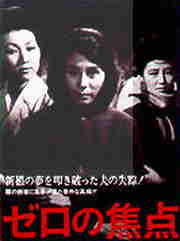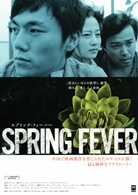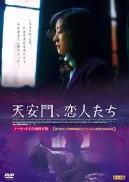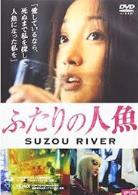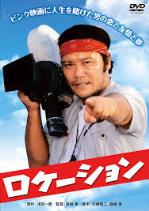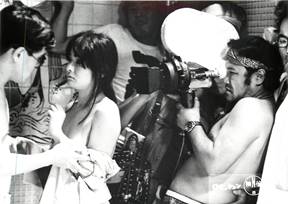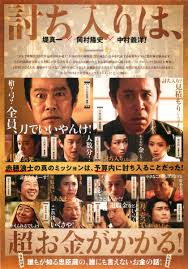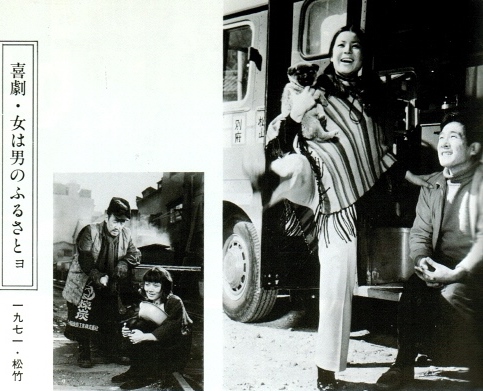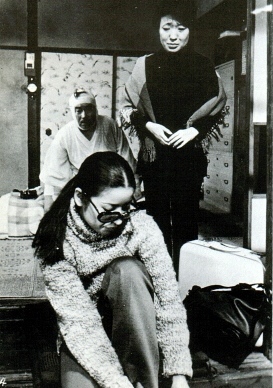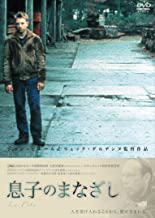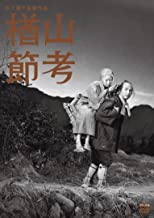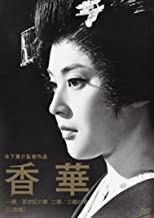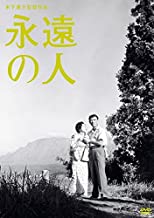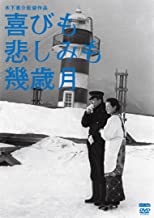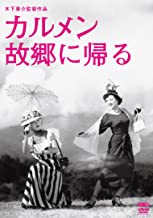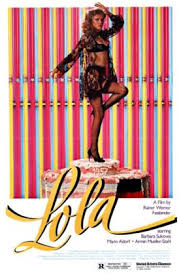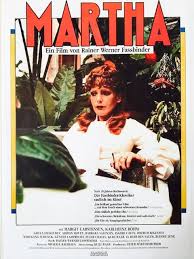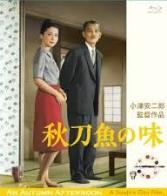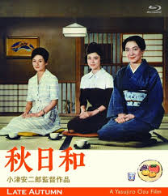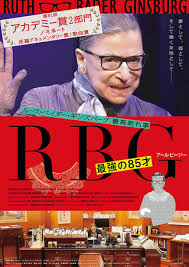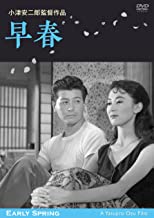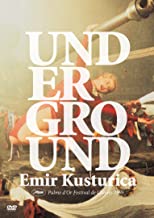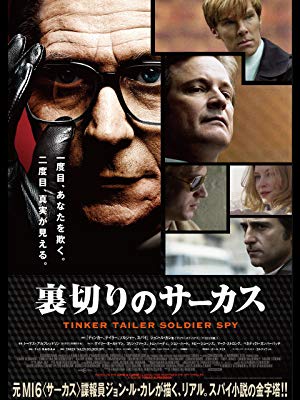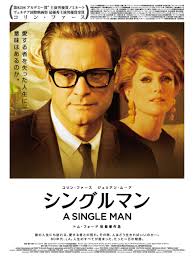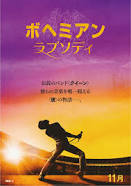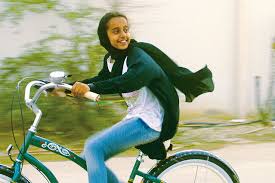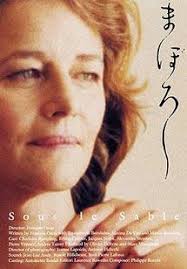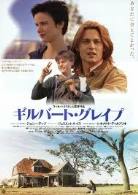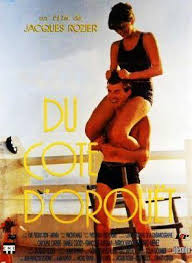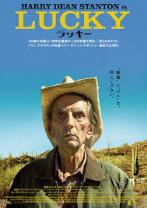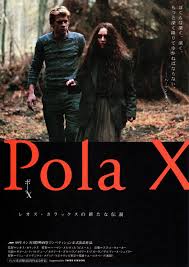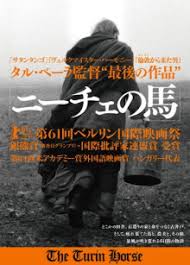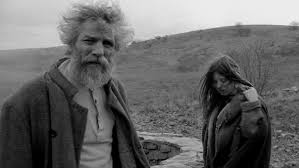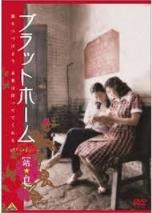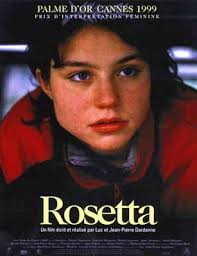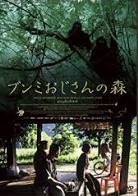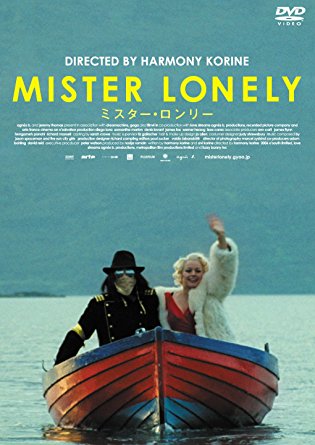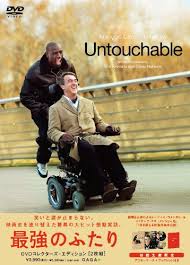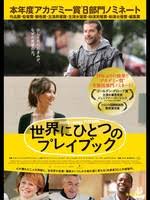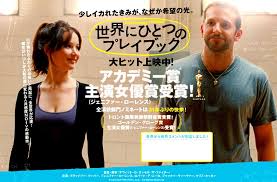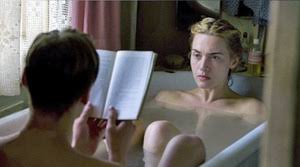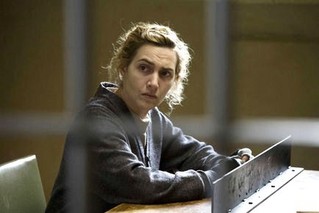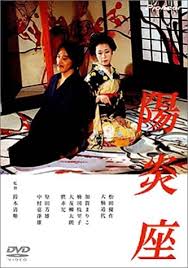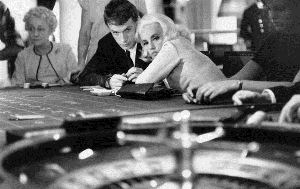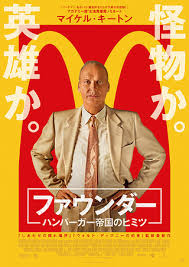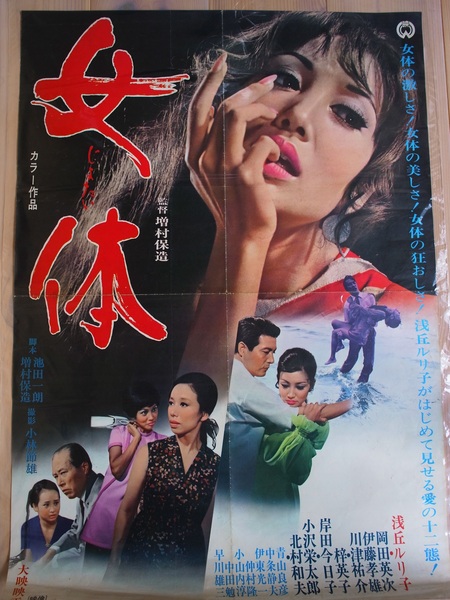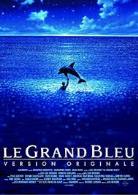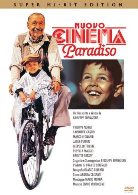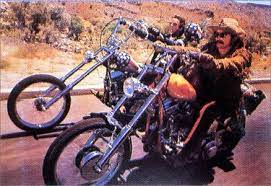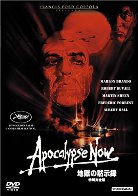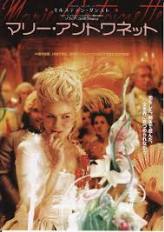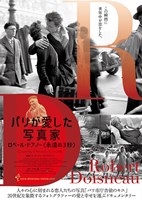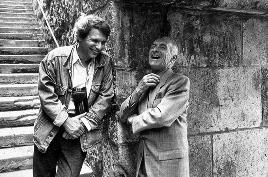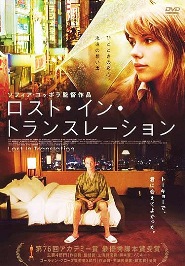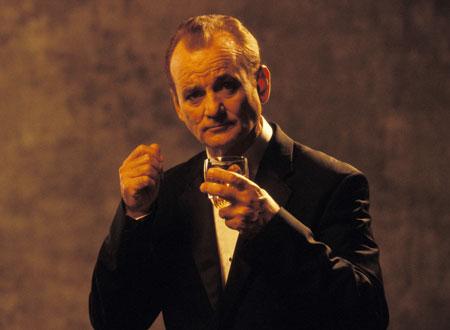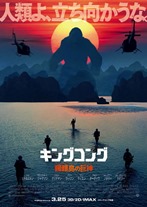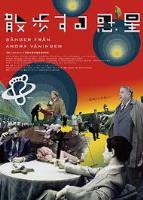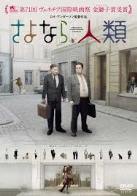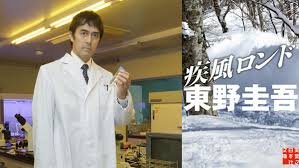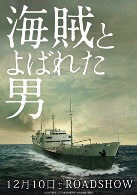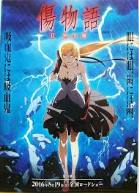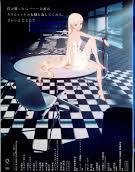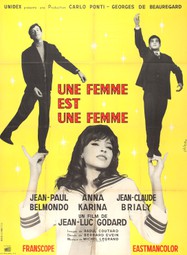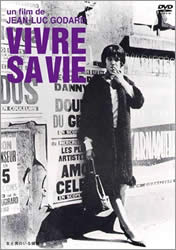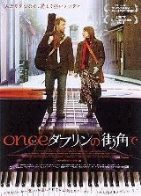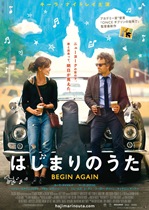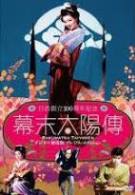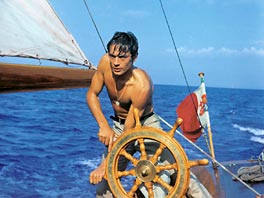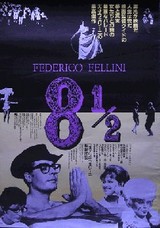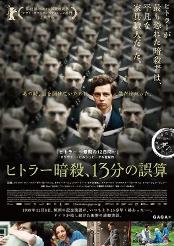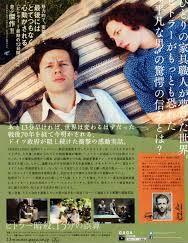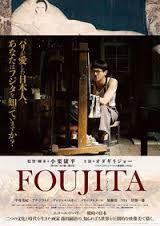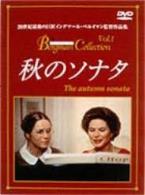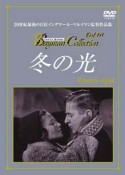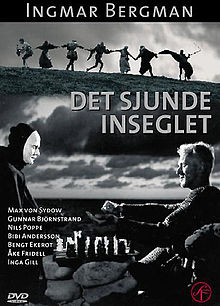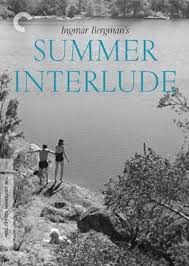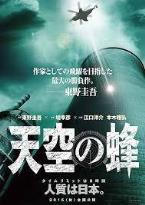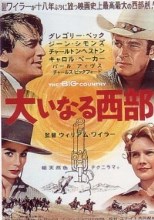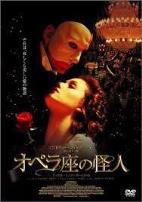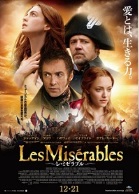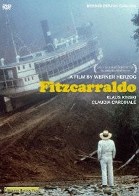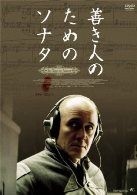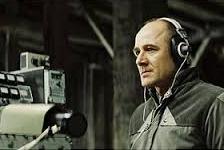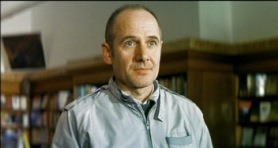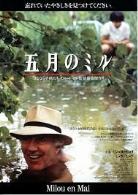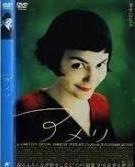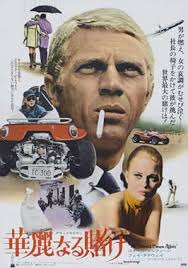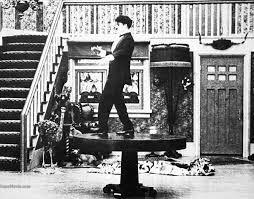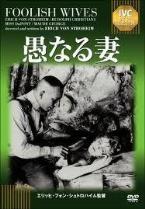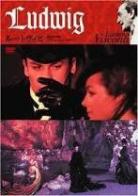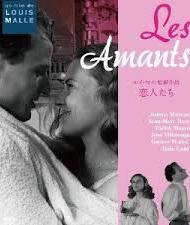「●教育」の インデックッスへ Prev|NEXT ⇒ 【1315】 瀬川 松子 『中学受験の失敗学』
平凡でも「ルール」として教え込むことで得られる効果。「ハリ・ポタ」のクラス間の点取り合戦みたいな感じも。
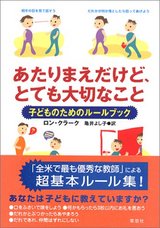 『あたりまえだけど、とても大切なこと
『あたりまえだけど、とても大切なこと』(2004/06 草思社)
 ロン・クラーク氏
ロン・クラーク氏
著者は大学を出て世界中を放浪した後、たまたま'95年に小学校教師となってハーレムの問題児が多い学級を担当しますが、学級を立て直すために、祖母から教わった礼儀作法をルールにして生徒たちに教え込みます。
この本にあるのはその50のルールなのですが、のっけから「大人の質問には礼儀正しく答えよう」といった平凡なものが出てきます。
これが最も重要なルール、ということですが、その「効果」(成果?)が凄くて、ニューヨーク市一帯から応募がある募集者数30の難関中学校の面接試験に、著者のクラスから12人受けて全員が合格したという。
こうした調子で、
「口をふさいで咳をしよう」
「何かもらったら3秒以内にお礼を言おう」
「だれかとぶつかったらあやまろう」
といったルールが、具体例やその「効果」(成果)とともに紹介されています。
著者の教室の子どもたちは、態度も変わり、成績も全米トップクラスとなり、地域貢献プロジェクトを実施し、ついにホワイトハウスにクラス全員が招かれるという...(少しアメリカン・ドリーム的な描き方ではあるのですが)。
日本にもそうした落ちこぼれ学級を活力と秩序ある学級に蘇らせた先生の話はありますが、放っておいても身につくような平凡なことでも(これが実際には身につかなかったりする)「ルール」として教え込むというところが著者の特徴でしょうか。
もちろん素早く態度で示す判断力、行動力も必要だし、継続する意志力も大切。こうなってくると教師個人の資質的なものを感じます。
著者は'00年に「全米最優秀教師賞」を受賞したそうですが、これは国ではなく民間(ディズニー)で定めた賞です。
日本でも民間で決めるならばあってもいいかなと思いますが(家庭教師派遣会社などで似たようなものがありますが、ほとんど販促用の人気投票みたいなものになっている)、まずムリでしょう。
また一方で、著者の教育法は旧来の「アメとムチ」方式に過ぎないのではないかという批判も米国ではあるようです。
自分自身もそのことは大いに感じ、自分が「ハリー・ポッター」シリーズのクラス間の点取り合戦的なところが好きになれない理由と同じような要素も、この本にはあると...。
でも、学校でカリキュラムをこなすことだけに汲々としながら授業をしている教師も多いわけで、家庭の役割か学校の役割かを問う前に、子どものために考えてみなければならないことも多いと思いました。


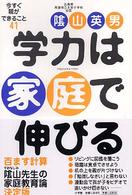
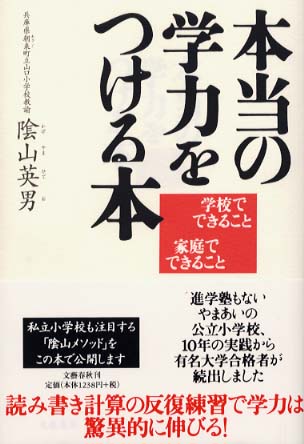
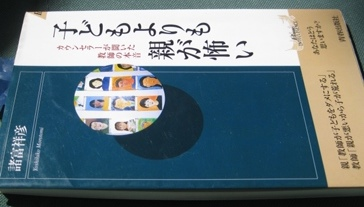



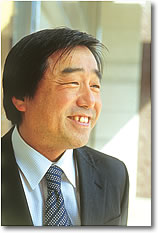 '02年出版の本書はベストセラーになり、著者である陰山英男氏の「百ます計算」や「陰山メッソッド」は広く世に知られることになりますが、本書執筆時には著者は未だ、兵庫の進学塾もない山あいの小学校の一教諭でした。
'02年出版の本書はベストセラーになり、著者である陰山英男氏の「百ます計算」や「陰山メッソッド」は広く世に知られることになりますが、本書執筆時には著者は未だ、兵庫の進学塾もない山あいの小学校の一教諭でした。
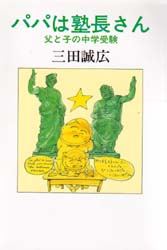
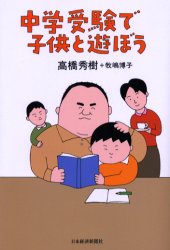
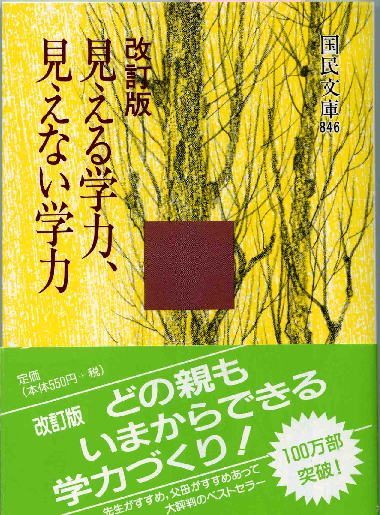
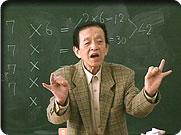 岸本 裕史 氏
岸本 裕史 氏

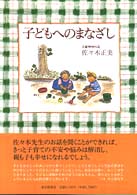


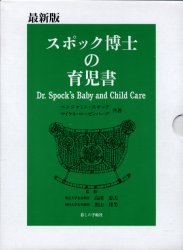
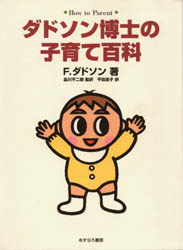
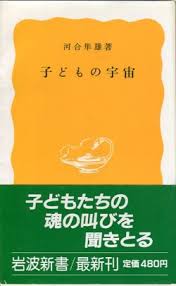
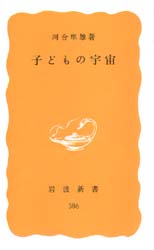
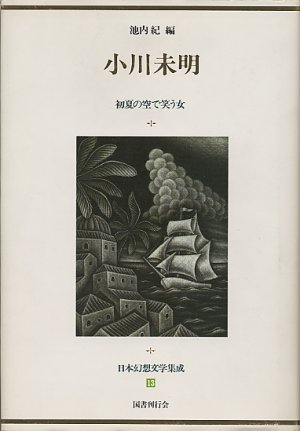
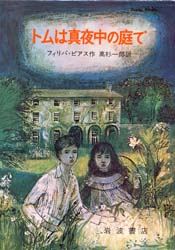

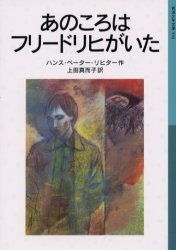

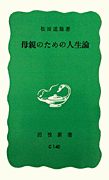
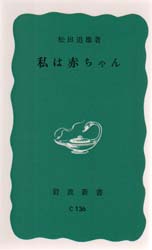

 松田道雄(1908‐1998/享年89)
松田道雄(1908‐1998/享年89)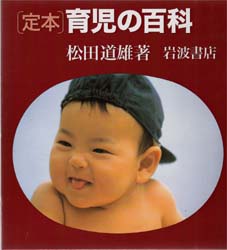
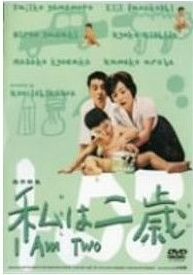
 因みに、映画「私は二歳」は、船越英二と山本富士子が演じる夫婦が子育てをする様が描かれていて、前半部分は新興団地が舞台で、後半は父方の祖母(浦辺粂子)と同居するために一軒家に移りますが、やがて祖母が亡くなるというもの。子育てを巡ってごく普通にありそうな夫婦の衝突などがテンポよく描かれていますが、とりたてて珍しい話はなく、1962年・第36回「キネマ旬報ベストテン」の日本映画第1位に選ばれてはいますが(1962年度「芸術選奨」受賞作でもあるのだが)、まあどうってことない映画でしょうか。ただ、こうして子育てする夫婦の日常を観察日記風に描いた作品はそうなく、また、今観ると昭和30年代の本格的な核家族社会に入った頃の家庭育児の風景として、風俗記録的な価値は年月とともに加わってきているようにも思われ、星半個プラスしました(因みに「核家族」という言葉は1963年の流行語だった)。
因みに、映画「私は二歳」は、船越英二と山本富士子が演じる夫婦が子育てをする様が描かれていて、前半部分は新興団地が舞台で、後半は父方の祖母(浦辺粂子)と同居するために一軒家に移りますが、やがて祖母が亡くなるというもの。子育てを巡ってごく普通にありそうな夫婦の衝突などがテンポよく描かれていますが、とりたてて珍しい話はなく、1962年・第36回「キネマ旬報ベストテン」の日本映画第1位に選ばれてはいますが(1962年度「芸術選奨」受賞作でもあるのだが)、まあどうってことない映画でしょうか。ただ、こうして子育てする夫婦の日常を観察日記風に描いた作品はそうなく、また、今観ると昭和30年代の本格的な核家族社会に入った頃の家庭育児の風景として、風俗記録的な価値は年月とともに加わってきているようにも思われ、星半個プラスしました(因みに「核家族」という言葉は1963年の流行語だった)。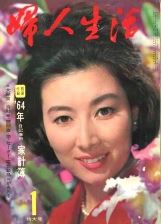 「婦人画報」'64年1月号(表紙:山本富士子)
「婦人画報」'64年1月号(表紙:山本富士子)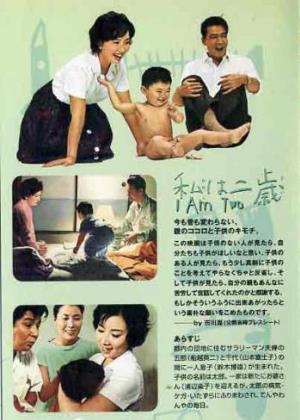
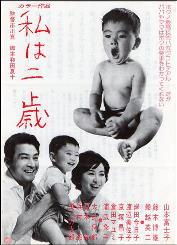
 「私は二歳」●制作年:1962年●監督:市川崑●製作:永田秀雅/市川崑●脚本:和田夏十●撮影:小林節雄●音
「私は二歳」●制作年:1962年●監督:市川崑●製作:永田秀雅/市川崑●脚本:和田夏十●撮影:小林節雄●音 楽:芥川也寸志●アニメーション:横山隆一●原作:松田道雄「私は二歳」●時間:88分●出演:船越英二/山本富士子/鈴木博雄/浦辺粂子/京塚昌子/渡辺美佐子/岸田今日子/倉田マユミ/大辻伺郎/浜村純/夏木章/潮
楽:芥川也寸志●アニメーション:横山隆一●原作:松田道雄「私は二歳」●時間:88分●出演:船越英二/山本富士子/鈴木博雄/浦辺粂子/京塚昌子/渡辺美佐子/岸田今日子/倉田マユミ/大辻伺郎/浜村純/夏木章/潮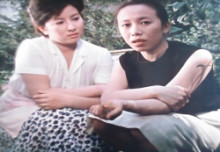 万太郎/(ぼくの声)中村メイ子●公開:1962/11●配給:大映(評価:★★★☆)
万太郎/(ぼくの声)中村メイ子●公開:1962/11●配給:大映(評価:★★★☆) 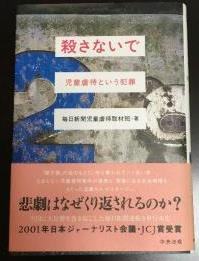

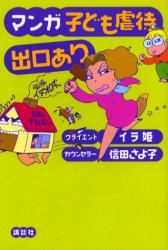
.jpg)
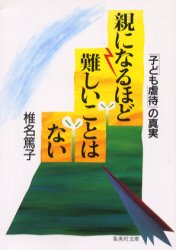


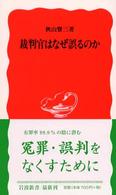
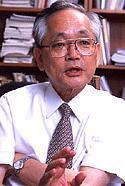 秋山 賢三 氏 (弁護士)
秋山 賢三 氏 (弁護士)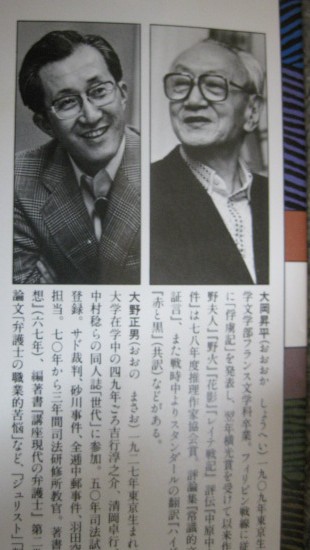
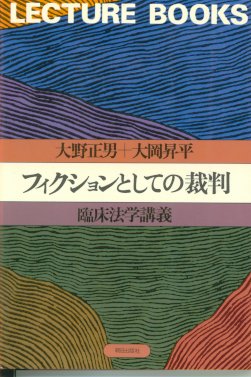
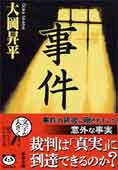
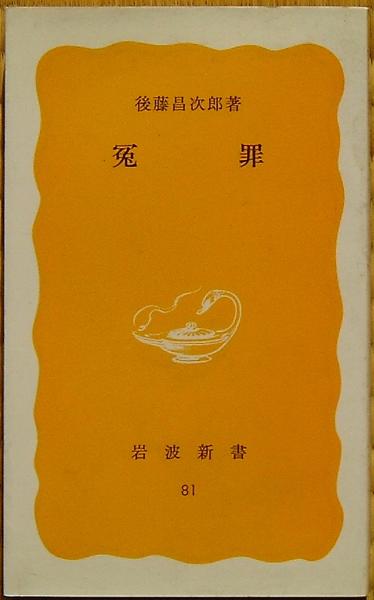

 この2事件に比べると、冒頭に取り上げられている〈清水(郵便局)事件〉というのは、郵便局員が書留から小切手を抜き取った容疑で起訴されたという、あまり知られていない "小粒の"事件ですが、ある局員が犯人であると誤認される発端が、たった1人の人間のカン違い証言にあり、まるでヒッチコックの 「間違えられた男」のような話。
この2事件に比べると、冒頭に取り上げられている〈清水(郵便局)事件〉というのは、郵便局員が書留から小切手を抜き取った容疑で起訴されたという、あまり知られていない "小粒の"事件ですが、ある局員が犯人であると誤認される発端が、たった1人の人間のカン違い証言にあり、まるでヒッチコックの 「間違えられた男」のような話。
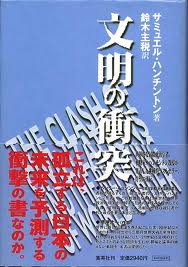
 社会学者である著者が、「イスラーム原理主義者」による9・11テロ後に、テロを前にしたときの社会哲学の無力を悟り、またこれが社会哲学の試金石となるであろうという思いで書き下ろした本で、テロとそれに対するアメリカの反攻に内在する思想的な問題を、「文明の衝突」というサミュエル・ハンチントンの概念を援用して読み説くとともに(ハンチントンは冷戦時代にこの概念を提唱したのだが)、テロがもたらした社会環境の閉塞状況に対しての「解決」の道(可能性)を著者なりに考察したもの。
社会学者である著者が、「イスラーム原理主義者」による9・11テロ後に、テロを前にしたときの社会哲学の無力を悟り、またこれが社会哲学の試金石となるであろうという思いで書き下ろした本で、テロとそれに対するアメリカの反攻に内在する思想的な問題を、「文明の衝突」というサミュエル・ハンチントンの概念を援用して読み説くとともに(ハンチントンは冷戦時代にこの概念を提唱したのだが)、テロがもたらした社会環境の閉塞状況に対しての「解決」の道(可能性)を著者なりに考察したもの。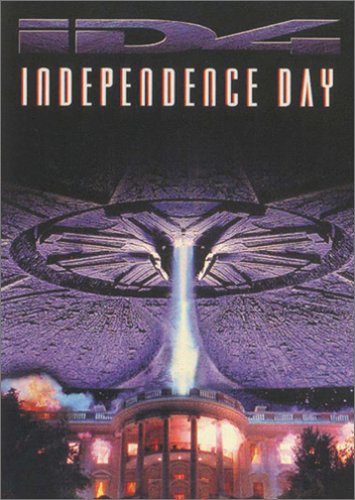
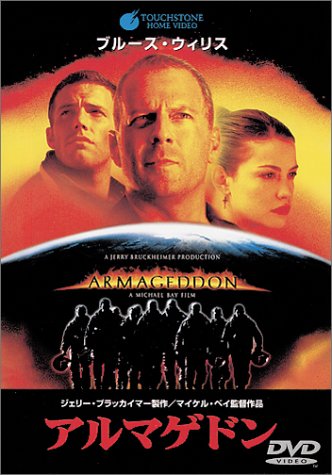
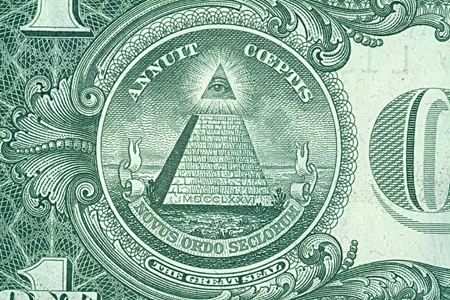 著者は、イスラームやキリスト教の中にある資本主義原理を指摘する一方、「資本主義は徹底的に宗教的な現象である」と見ており、そう捉えると、確かにいろいろなものが見えてくるという気がしました(確かに1ドル札の裏にピラミッドの絵がある なあ、と改めてビックリ)。
著者は、イスラームやキリスト教の中にある資本主義原理を指摘する一方、「資本主義は徹底的に宗教的な現象である」と見ており、そう捉えると、確かにいろいろなものが見えてくるという気がしました(確かに1ドル札の裏にピラミッドの絵がある なあ、と改めてビックリ)。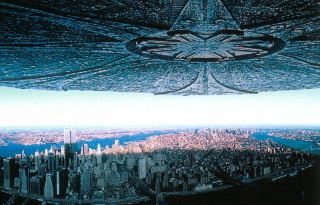
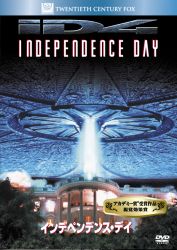

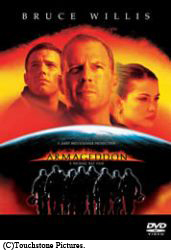

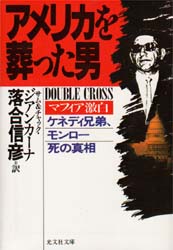


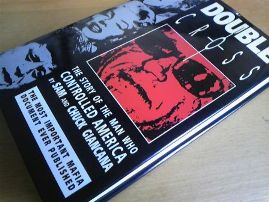
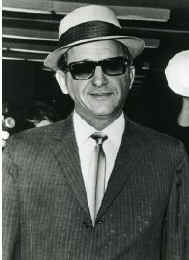 マフィアの大ボスだったサム・ジアンカーナが、自分はマリリン・モンローの死とケネディ兄弟の暗殺に深く関わったと語っていたのを、実の弟チャック・ジアンカーナが事件から30年近い時を経て本にしたもので、読んでビックリの内容で、本国でもかなり話題になりました。
マフィアの大ボスだったサム・ジアンカーナが、自分はマリリン・モンローの死とケネディ兄弟の暗殺に深く関わったと語っていたのを、実の弟チャック・ジアンカーナが事件から30年近い時を経て本にしたもので、読んでビックリの内容で、本国でもかなり話題になりました。

.jpg)
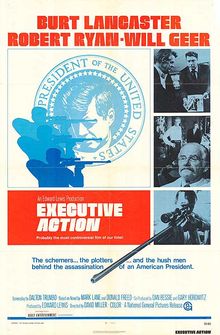 "
"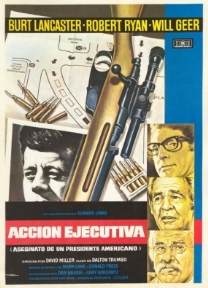

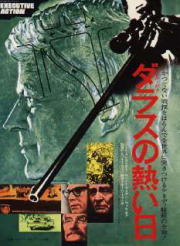

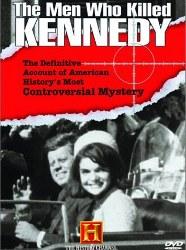
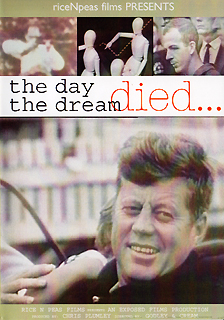
 「JFK」●原題:JFK●制作年:1991年●制作国:アメリカ●監督:オリバー・ストーン●製作:A・キットマン・ホー/オリバー・ストーン●脚本:オリバー・ストーン/ザカリー・スクラー●撮影:ロバート・リチャードソン●音楽:ジョン
「JFK」●原題:JFK●制作年:1991年●制作国:アメリカ●監督:オリバー・ストーン●製作:A・キットマン・ホー/オリバー・ストーン●脚本:オリバー・ストーン/ザカリー・スクラー●撮影:ロバート・リチャードソン●音楽:ジョン ・ウィリアムズ●原作:ジム・ギャリソンほか●時間:57分●出演:ケビン・コスナー/トミー・リー・ジョーンズ/ジョー・ペシ/ケヴィン・ベーコン/ローリー・メトカーフ/シシー・スペイセク/マイケル・ルーカー/ゲイリー・オールトコン/ドナルド・サザーランド/ジャック・レモン/ウォルター・マッソー/ジョン・キャンディ/ヴィンセント・ドノフリオ/デイル・ダイ/ジム・ギャリソン/(冒頭ナレーション)マーティン・シーン●日本公開:1992/03●配給:ワーナー・ブラザーズ(評価:★★★☆)
・ウィリアムズ●原作:ジム・ギャリソンほか●時間:57分●出演:ケビン・コスナー/トミー・リー・ジョーンズ/ジョー・ペシ/ケヴィン・ベーコン/ローリー・メトカーフ/シシー・スペイセク/マイケル・ルーカー/ゲイリー・オールトコン/ドナルド・サザーランド/ジャック・レモン/ウォルター・マッソー/ジョン・キャンディ/ヴィンセント・ドノフリオ/デイル・ダイ/ジム・ギャリソン/(冒頭ナレーション)マーティン・シーン●日本公開:1992/03●配給:ワーナー・ブラザーズ(評価:★★★☆)


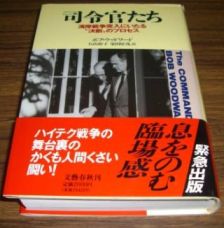

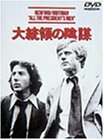

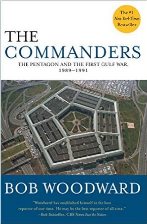 ても、'88年11月のジョージ・ブッシュ大統領就任から'91年1月の湾岸戦争突入までの話ですが、同年3月の停戦協定の2ヵ月後には本国出版されていて、短期間に(しかも戦争中に)よくこれだけの証言をまとめたなあと驚かされます。
ても、'88年11月のジョージ・ブッシュ大統領就任から'91年1月の湾岸戦争突入までの話ですが、同年3月の停戦協定の2ヵ月後には本国出版されていて、短期間に(しかも戦争中に)よくこれだけの証言をまとめたなあと驚かされます。 戦争に対して様々な考えを持った司令官たちの、彼らの会話や心理を再現する構成になっていて、小説のように面白く読めてしまいますが、大統領制とは言え、戦争がごく少数の人間の考えで実施に移されることも思い知らされ、その意味ではゾッとします。
戦争に対して様々な考えを持った司令官たちの、彼らの会話や心理を再現する構成になっていて、小説のように面白く読めてしまいますが、大統領制とは言え、戦争がごく少数の人間の考えで実施に移されることも思い知らされ、その意味ではゾッとします。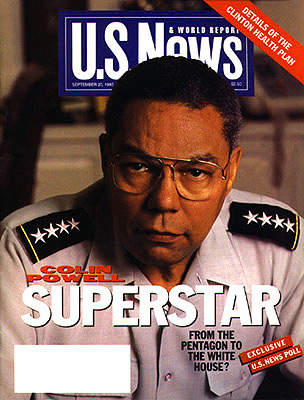
 また、本書で主戦派として描かれているスコウクロフトは、イラク戦争ではパウエルと協調し、息子の方のジョージ・ブッシュ(父親と同じ名前)の強硬姿勢にブレーキをかける立場に回っています。しかし、息子ブッシュは、パウエルの後任として自身が国務長官に指名したコンドリーザ・ライスの"攻撃的現実主義"になびいた―。最初から戦争するつもりでタカ派の彼女を登用したともとれますが...。
また、本書で主戦派として描かれているスコウクロフトは、イラク戦争ではパウエルと協調し、息子の方のジョージ・ブッシュ(父親と同じ名前)の強硬姿勢にブレーキをかける立場に回っています。しかし、息子ブッシュは、パウエルの後任として自身が国務長官に指名したコンドリーザ・ライスの"攻撃的現実主義"になびいた―。最初から戦争するつもりでタカ派の彼女を登用したともとれますが...。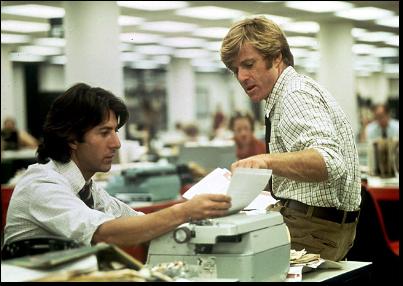 因みに、映画「大統領の陰謀」('76年/米)は、以前にテレビで観たのを最近またBS放送で再見したのですが(カール・バーンスタイン役のダスティン・ホフマンもボブ・ウッドワード役のロバート・レッドフォードも若い!)、複雑なウォーターゲート事件の全体像をかなり端折って、事件が明るみになる端緒となった共和党工作員の民主党本部への不法侵入の部分だけを取り上げており、侵入した5人組の工作員は誰かということと、それが分らないと事件を記事として公表できず、そのうち新聞社への政治的圧力も強まってきて、取材のために残された時間は限られているがあと1人がわからない―という、その辺りの葛藤、鬩ぎ合いの1点に絞って作られているように思いました。それなりに面白く、再度見入ってしまったこの作品の監督は、後に「推定無罪」などを撮るアラン・J・パクラで、やはりこの監督は、政治系ではなく、この頃からサスペンス系だと。「ディープ・スロート」という2人の記者に情報提供した人物が、後に実在かつ生存中の政府高官だと分った、その上で観るとまた興味深いです。
因みに、映画「大統領の陰謀」('76年/米)は、以前にテレビで観たのを最近またBS放送で再見したのですが(カール・バーンスタイン役のダスティン・ホフマンもボブ・ウッドワード役のロバート・レッドフォードも若い!)、複雑なウォーターゲート事件の全体像をかなり端折って、事件が明るみになる端緒となった共和党工作員の民主党本部への不法侵入の部分だけを取り上げており、侵入した5人組の工作員は誰かということと、それが分らないと事件を記事として公表できず、そのうち新聞社への政治的圧力も強まってきて、取材のために残された時間は限られているがあと1人がわからない―という、その辺りの葛藤、鬩ぎ合いの1点に絞って作られているように思いました。それなりに面白く、再度見入ってしまったこの作品の監督は、後に「推定無罪」などを撮るアラン・J・パクラで、やはりこの監督は、政治系ではなく、この頃からサスペンス系だと。「ディープ・スロート」という2人の記者に情報提供した人物が、後に実在かつ生存中の政府高官だと分った、その上で観るとまた興味深いです。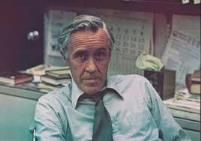 ジェイソン・ロバーズin「大統領の陰謀」[ワシントン・ポスト紙編集主幹ベン・ブラッドリー](1976年
ジェイソン・ロバーズin「大統領の陰謀」[ワシントン・ポスト紙編集主幹ベン・ブラッドリー](1976年

 同じ光文社新書の『温泉教授の温泉ゼミナール』('01年)、『これは、温泉ではない』('04年)の続編で、今回は信州の〈白骨温泉〉の「入浴剤混入問題」を受けての緊急出版ということですが、内容的には、「源泉100%かけ流し」にこだわり、日本の多くの温泉で行われている「循環風呂システム」や「塩素投入」を批判した前著までの流れを継いでいます(事件としても、循環風呂のレジオネラ菌で7名の死者を出した〈日向サンパーク事件〉の方を重視している)。
同じ光文社新書の『温泉教授の温泉ゼミナール』('01年)、『これは、温泉ではない』('04年)の続編で、今回は信州の〈白骨温泉〉の「入浴剤混入問題」を受けての緊急出版ということですが、内容的には、「源泉100%かけ流し」にこだわり、日本の多くの温泉で行われている「循環風呂システム」や「塩素投入」を批判した前著までの流れを継いでいます(事件としても、循環風呂のレジオネラ菌で7名の死者を出した〈日向サンパーク事件〉の方を重視している)。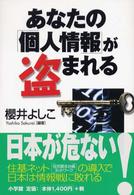
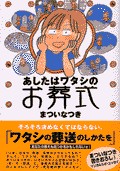
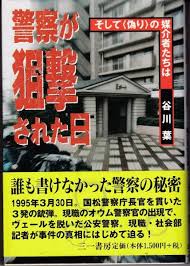

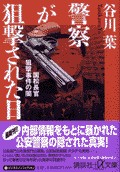
 '95年に起きた国松孝次警察庁長官狙撃事件は、オウム信者の現職警官・小杉敏行が書類送検されたものの結果的に証拠不十分で立件できず、今や事件そのものが風化しようとしています。本書は、国松長官はなぜ狙撃されたのか、なぜ犯人は逮捕されないのかを検証していますが、その過程で警察庁vs.警視庁、刑事部門vs.公安部門の確執を明らかにし、〈チヨダ〉なる警察内の闇組織の存在をあぶりだしています。複雑な警察組織の概要と権力抗争のダイナミズムがわかり面白く読めますが、警察内の権力闘争や組織防衛が、捜査ミスや事実の隠蔽に繋がっていると思うとやり切れない気持ちにもさせられます。
'95年に起きた国松孝次警察庁長官狙撃事件は、オウム信者の現職警官・小杉敏行が書類送検されたものの結果的に証拠不十分で立件できず、今や事件そのものが風化しようとしています。本書は、国松長官はなぜ狙撃されたのか、なぜ犯人は逮捕されないのかを検証していますが、その過程で警察庁vs.警視庁、刑事部門vs.公安部門の確執を明らかにし、〈チヨダ〉なる警察内の闇組織の存在をあぶりだしています。複雑な警察組織の概要と権力抗争のダイナミズムがわかり面白く読めますが、警察内の権力闘争や組織防衛が、捜査ミスや事実の隠蔽に繋がっていると思うとやり切れない気持ちにもさせられます。 しかし終盤にきて本書なりの事件に対する見解を示し、そこでは、「小杉犯行説」が濃厚視されることをベースに、現職警察官を実行者に選んだオウムの意図を推察するとともに、その場で捕まる「予定」だった犯人がなぜ逃げることが出来たかという大胆な想像的考察も行っています。
しかし終盤にきて本書なりの事件に対する見解を示し、そこでは、「小杉犯行説」が濃厚視されることをベースに、現職警察官を実行者に選んだオウムの意図を推察するとともに、その場で捕まる「予定」だった犯人がなぜ逃げることが出来たかという大胆な想像的考察も行っています。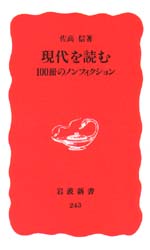
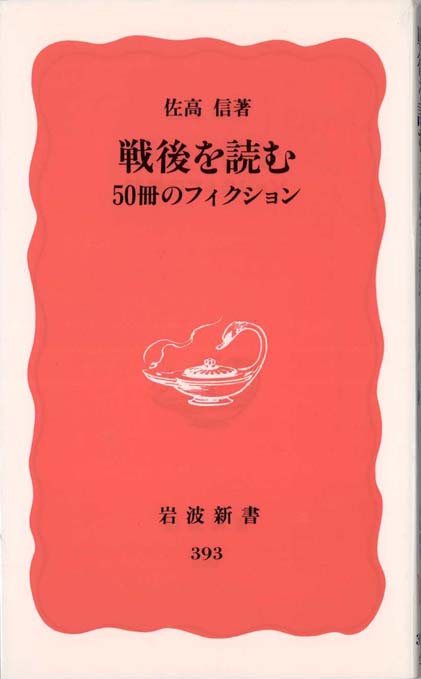
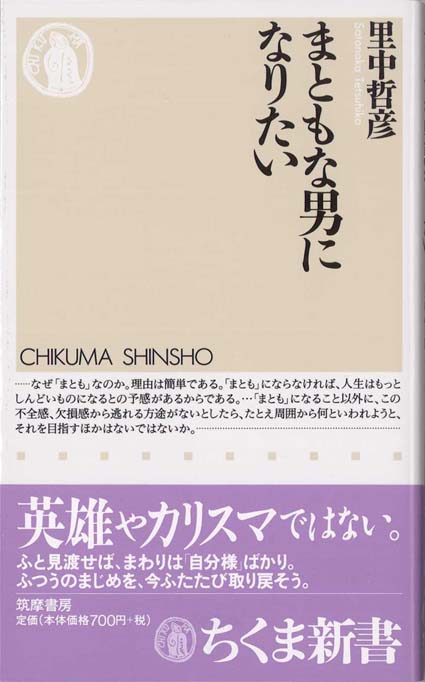
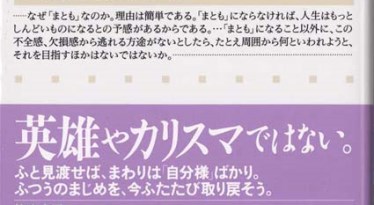
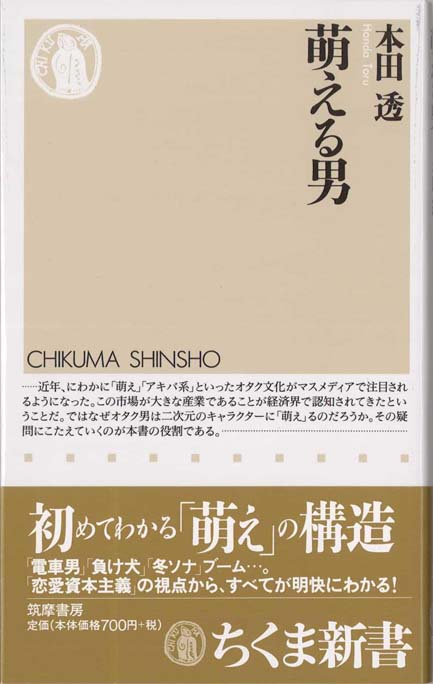
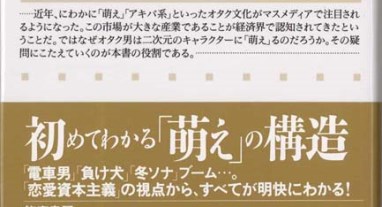
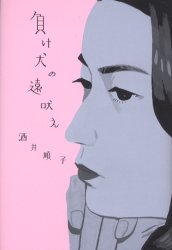


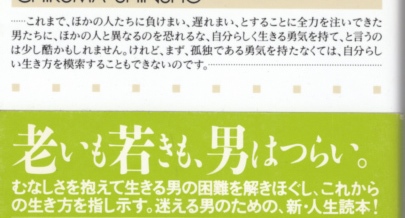

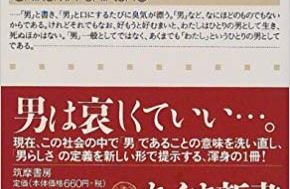

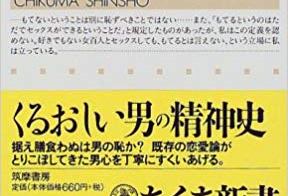
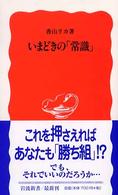
 香山 リカ 氏 (精神科医)
香山 リカ 氏 (精神科医)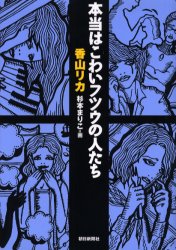

 日垣 隆 氏 (略歴下記)
日垣 隆 氏 (略歴下記)

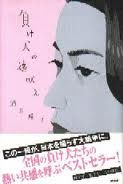
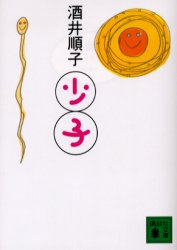
 酒井順子 氏(略歴下記)
酒井順子 氏(略歴下記)



 東 浩紀 氏
東 浩紀 氏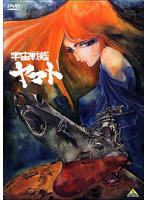
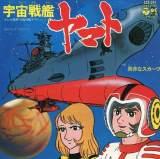


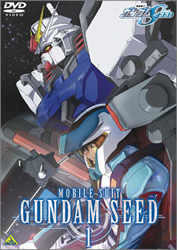
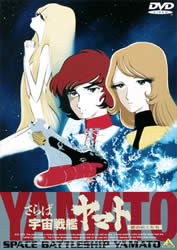

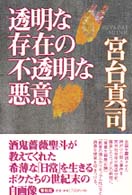
 宮台 真司 氏
宮台 真司 氏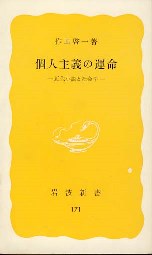
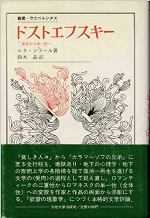
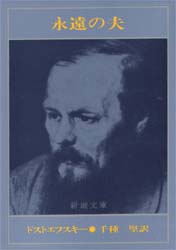
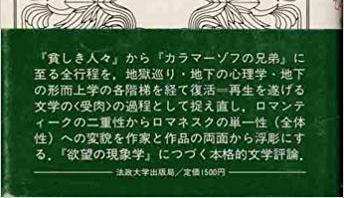 第1・第3章と第2章の繋がりが若干スムーズでないものの(「文芸」と「社会学」が切り離されている感じがする)、各章ごとに読み応えのある1冊でした。著者・作田啓一氏が参照しているルネ・ジラールの『ドストエフスキー―二重性から単一性へ』('83年/叢書・ウニベルシタス)と併せて読むとわかりよいと思います。ルネ・ジラールの『ドストエフスキー』は版元からみても学術書ではありますが(しかもこの叢書は翻訳本限定)、この本に限って言えば200ページ足らずで、箇所によっては作田氏よりもわかりやすく書いてあったりします(ルネ・ジラールは「永遠の夫」の主人公トルソーツキイを「マゾヒスト」であると断定している)。
第1・第3章と第2章の繋がりが若干スムーズでないものの(「文芸」と「社会学」が切り離されている感じがする)、各章ごとに読み応えのある1冊でした。著者・作田啓一氏が参照しているルネ・ジラールの『ドストエフスキー―二重性から単一性へ』('83年/叢書・ウニベルシタス)と併せて読むとわかりよいと思います。ルネ・ジラールの『ドストエフスキー』は版元からみても学術書ではありますが(しかもこの叢書は翻訳本限定)、この本に限って言えば200ページ足らずで、箇所によっては作田氏よりもわかりやすく書いてあったりします(ルネ・ジラールは「永遠の夫」の主人公トルソーツキイを「マゾヒスト」であると断定している)。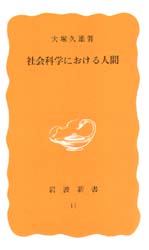
.jpg) 大塚久雄(1907-1996/享年89)
大塚久雄(1907-1996/享年89)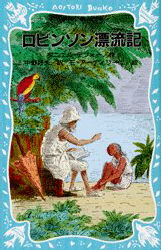

 「インフレ・ターゲット論」の代表的論客である著者による日本経済の入門書。
「インフレ・ターゲット論」の代表的論客である著者による日本経済の入門書。 (●2018年追記:著者は2013年に日銀副総裁に就任。この日銀副総裁人事案は事前に野党が反対したが、参院本会議で自由民主党、公明党、みんなの党など各党の賛成多数で可決した。しかし、日本におけるインフレターゲットは、結局、企業が内部留保に回って賃上げ率が抑制され、うまくいかなかったように思う。リフレ派の経済学者たちは著者を英雄視したが、麻生太郎財務大臣は著者が副総裁就任前に物価安定目標2%について「2年で達成できる」と述べたことについて「20年続いた一般人の気持ち(デフレ
(●2018年追記:著者は2013年に日銀副総裁に就任。この日銀副総裁人事案は事前に野党が反対したが、参院本会議で自由民主党、公明党、みんなの党など各党の賛成多数で可決した。しかし、日本におけるインフレターゲットは、結局、企業が内部留保に回って賃上げ率が抑制され、うまくいかなかったように思う。リフレ派の経済学者たちは著者を英雄視したが、麻生太郎財務大臣は著者が副総裁就任前に物価安定目標2%について「2年で達成できる」と述べたことについて「20年続いた一般人の気持ち(デフレ 期待)がいきなりインフレに変わるのは、そんなに簡単にはいかない」という認識を示した上で「私自身は『やっぱり学者というのはこんなものか、実体経済がわかっていない人はこういう発言をするんだな』と正直思った」と述べている。2018年に5年間の任期を終えて日銀副総裁を退任したが、その直後に、ニッポン放送のラジオ番組に出演し、「インフレ率2%の達成には財政政策との協調が不可欠だ」と述べ、暗に政府の財政政策を批判した。だったら初めからそう言うべきだった。後で言うのは責任転嫁である(当事者であるのに評論家みたいな口をきく麻生氏も同じく無責任なのだが)。本書と前著『
期待)がいきなりインフレに変わるのは、そんなに簡単にはいかない」という認識を示した上で「私自身は『やっぱり学者というのはこんなものか、実体経済がわかっていない人はこういう発言をするんだな』と正直思った」と述べている。2018年に5年間の任期を終えて日銀副総裁を退任したが、その直後に、ニッポン放送のラジオ番組に出演し、「インフレ率2%の達成には財政政策との協調が不可欠だ」と述べ、暗に政府の財政政策を批判した。だったら初めからそう言うべきだった。後で言うのは責任転嫁である(当事者であるのに評論家みたいな口をきく麻生氏も同じく無責任なのだが)。本書と前著『
 最初に一般論としてのエコノミストの分類をしていますが、「政策プロモーター型」の竹中平蔵氏について、度々の変節を揶揄して「カオナシ」と呼んでいるところは著者らしいユーモア。
最初に一般論としてのエコノミストの分類をしていますが、「政策プロモーター型」の竹中平蔵氏について、度々の変節を揶揄して「カオナシ」と呼んでいるところは著者らしいユーモア。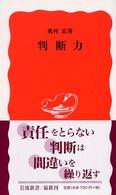
 奥村 宏 氏(経済評論家)
奥村 宏 氏(経済評論家)

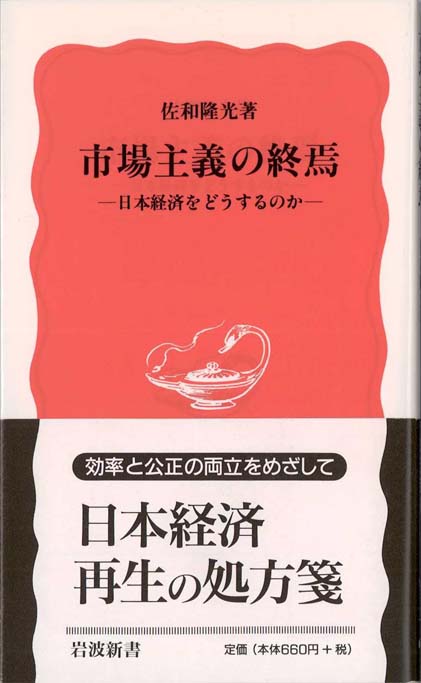
 佐和 隆光 氏
佐和 隆光 氏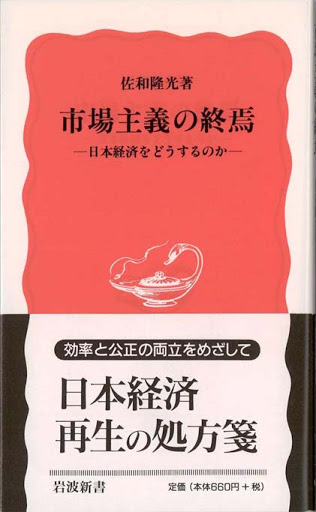 著者は本書で、市場主義を否定しているのではなく、「市場主義改革はあくまでも『必要な通過点』である」としながらも、市場の暴走による社会的な格差・不平等の拡大を避けるためには、「市場主義にも反市場主義にもくみしない、いってみれば、両者を止揚する革新的な体制」(140p)としての「第三の道」をとるべきだとしています。
著者は本書で、市場主義を否定しているのではなく、「市場主義改革はあくまでも『必要な通過点』である」としながらも、市場の暴走による社会的な格差・不平等の拡大を避けるためには、「市場主義にも反市場主義にもくみしない、いってみれば、両者を止揚する革新的な体制」(140p)としての「第三の道」をとるべきだとしています。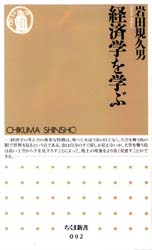
 岩田規久男 氏 (略歴下記)
岩田規久男 氏 (略歴下記)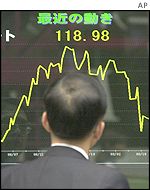 平易な言葉で書かれた経済の入門書で、学生時代に経済学を学ぶことなく社会に出た自分のような人間にも読みやすい本でした。
平易な言葉で書かれた経済の入門書で、学生時代に経済学を学ぶことなく社会に出た自分のような人間にも読みやすい本でした。
 佐和隆光 氏
佐和隆光 氏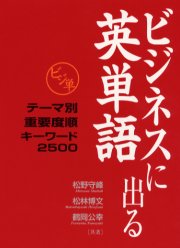
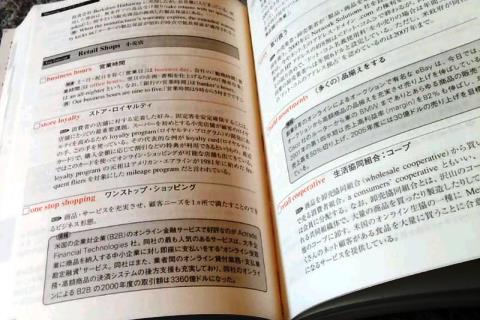 謳い文句どおり、"実践"ですぐに役立つビジネス英単語集。
謳い文句どおり、"実践"ですぐに役立つビジネス英単語集。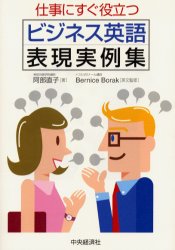
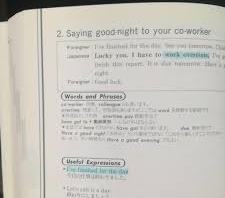
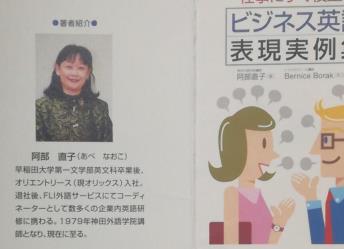 単行本や新書でベストセラーになったものから、NHKで出しているシリーズもの、TOEIC公式ガイドから果ては「超右脳式」とかいうものまで当たりましたが、結局スピーキングに関してはこの本が一番役に立ちました(CD付きではないので、発音は別として)。
単行本や新書でベストセラーになったものから、NHKで出しているシリーズもの、TOEIC公式ガイドから果ては「超右脳式」とかいうものまで当たりましたが、結局スピーキングに関してはこの本が一番役に立ちました(CD付きではないので、発音は別として)。
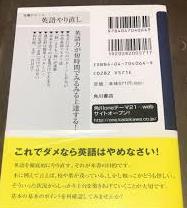

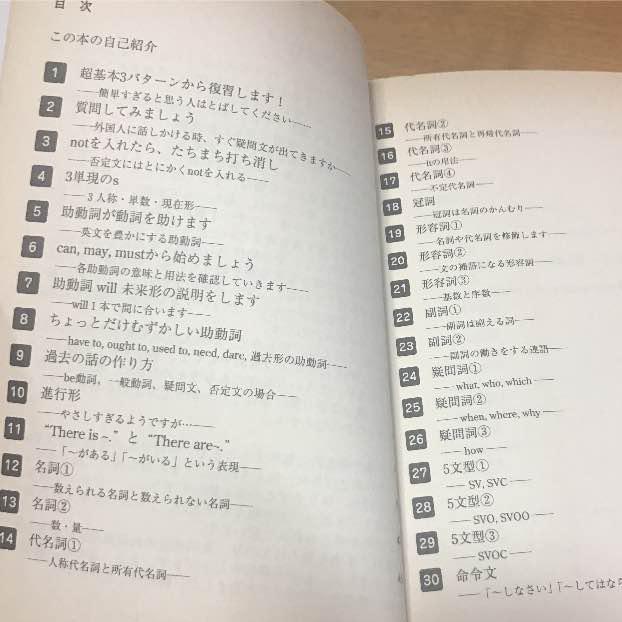 本書は「角川oneテーマ21」の1冊ですが、「英語やり直し」ということでテーマがはっきりしています。
本書は「角川oneテーマ21」の1冊ですが、「英語やり直し」ということでテーマがはっきりしています。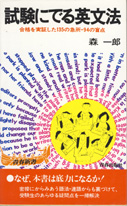
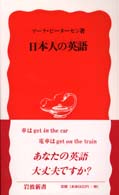

![『最新日米口語辞典 [増補改訂版]』.jpg](http://hurec.bz/book-movie/%E3%80%8E%E6%9C%80%E6%96%B0%E6%97%A5%E7%B1%B3%E5%8F%A3%E8%AA%9E%E8%BE%9E%E5%85%B8%20%EF%BC%BB%E5%A2%97%E8%A3%9C%E6%94%B9%E8%A8%82%E7%89%88%EF%BC%BD%E3%80%8F.jpg)
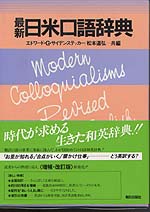
 初版が'77年、増補版が'82年とずいぶん以前であるのに古さを感じさせないのは、日本語の抽出の仕方が口語とは言えオーソドックスで、時代を経ても使われ続けられるものを選んでいるためと思われます。このあたりは、編纂者の識見のなせる技でしょうか。
初版が'77年、増補版が'82年とずいぶん以前であるのに古さを感じさせないのは、日本語の抽出の仕方が口語とは言えオーソドックスで、時代を経ても使われ続けられるものを選んでいるためと思われます。このあたりは、編纂者の識見のなせる技でしょうか。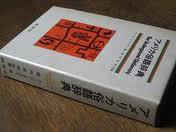
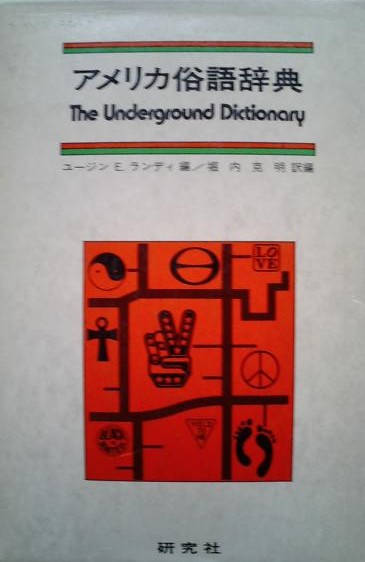
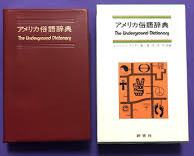
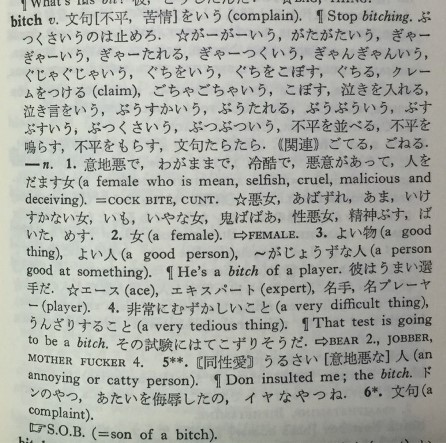 この辞典のもう1つの特徴は、アメリカ俗語に対応する日本の俗語のマニアックとも思える蒐集ぶりです(訳編者が70年代に大学生を中心に集めたという)。試しに bear とか bitch とか bush という語を引いて見ればわかりますが、完全に〈日本語俗語辞典〉と化しています。日本にだってこんなに俗語はあるぞ〜みたいな。多分〈日本語の俗語〉の方も、一般の読者には初めて知るものの方が圧倒的に多いかと思います。
この辞典のもう1つの特徴は、アメリカ俗語に対応する日本の俗語のマニアックとも思える蒐集ぶりです(訳編者が70年代に大学生を中心に集めたという)。試しに bear とか bitch とか bush という語を引いて見ればわかりますが、完全に〈日本語俗語辞典〉と化しています。日本にだってこんなに俗語はあるぞ〜みたいな。多分〈日本語の俗語〉の方も、一般の読者には初めて知るものの方が圧倒的に多いかと思います。



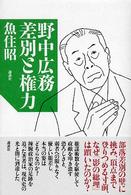




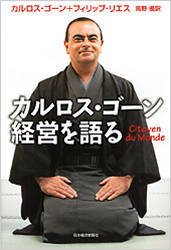




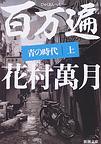
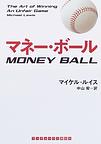



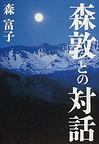


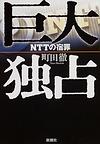

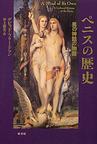






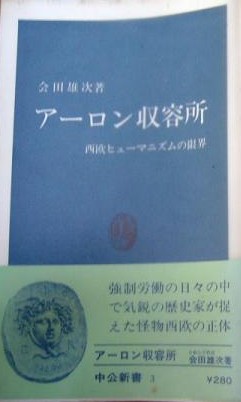


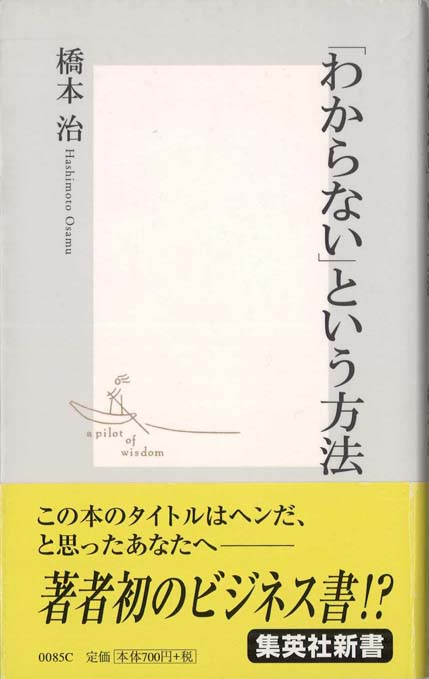
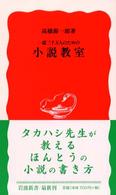
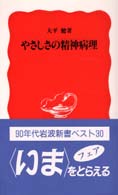

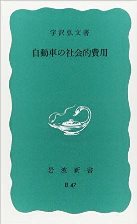

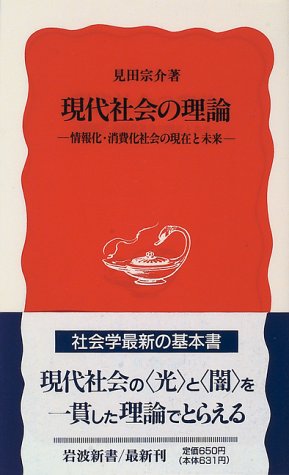
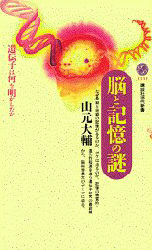






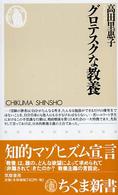


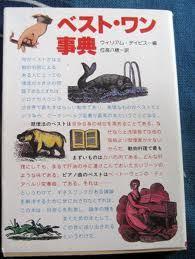
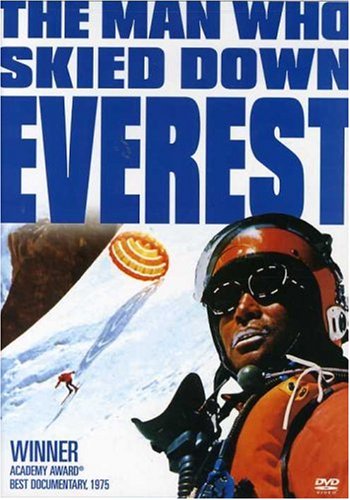
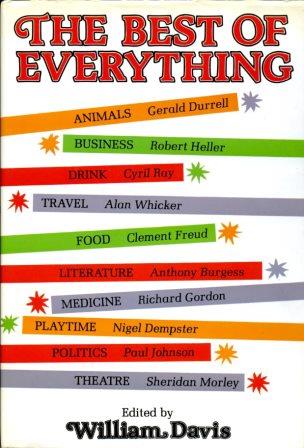
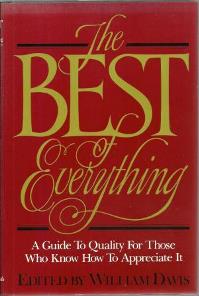 「ギネス・ブック」の客観的・量的ベストに対し、本書は主観的・質的ベストを追求していて、「絵画のベスト」とか「病院のベスト」などマトモなものから、「死体を強奪する方法のべスト」「上流階級に仲間入りできる場所のベスト」といったものまで何でもありなのが楽しいです。
「ギネス・ブック」の客観的・量的ベストに対し、本書は主観的・質的ベストを追求していて、「絵画のベスト」とか「病院のベスト」などマトモなものから、「死体を強奪する方法のべスト」「上流階級に仲間入りできる場所のベスト」といったものまで何でもありなのが楽しいです。

 芸術関連もヨーロッパ中心に「ベスト」が選出されている傾向はありますが、その中で「挿絵画家のベスト」に「北斎」が、「フラッシュバック映画のベスト」に「羅生門」が選ばれています(「日本の小説のベスト」には谷崎潤一郎の『瘋癲老人日記』が選ばれているが、「古今東西の小説のベスト」にはジェイムス・ジョイスの『ユリシーズ』が選ばれている)。
芸術関連もヨーロッパ中心に「ベスト」が選出されている傾向はありますが、その中で「挿絵画家のベスト」に「北斎」が、「フラッシュバック映画のベスト」に「羅生門」が選ばれています(「日本の小説のベスト」には谷崎潤一郎の『瘋癲老人日記』が選ばれているが、「古今東西の小説のベスト」にはジェイムス・ジョイスの『ユリシーズ』が選ばれている)。 三浦雄一郎がエベレスト滑降に挑んだのは'70年5月6日で、「エベレスト大滑降」('70年/松竹)という記録映画になりましたが(昔、学校の課外授業で観た)、これを観ると、当初エベレスト8000メートルのサウスコルから(そもそもここまで来るのが大変。シェルパ6名が遭難死している)3000メートルを滑走する予定だったのが、2000メートルぐらい滑って転倒したままアイスバーンに突入(何せスタートから5秒で時速150キロに達したという)、パラシュートの抑止力が効かないまま150メートルほど滑落し、露岩に激突して止まっています。
三浦雄一郎がエベレスト滑降に挑んだのは'70年5月6日で、「エベレスト大滑降」('70年/松竹)という記録映画になりましたが(昔、学校の課外授業で観た)、これを観ると、当初エベレスト8000メートルのサウスコルから(そもそもここまで来るのが大変。シェルパ6名が遭難死している)3000メートルを滑走する予定だったのが、2000メートルぐらい滑って転倒したままアイスバーンに突入(何せスタートから5秒で時速150キロに達したという)、パラシュートの抑止力が効かないまま150メートルほど滑落し、露岩に激突して止まっています。 3000メートル滑るところを2000メートルで転倒してこれを「成功」と言えるかどうか分かりませんが、標高6000メートルの急斜面でアイスバーンに突っ込んで転倒して更に露岩にぶつかって死ななかったのは「奇跡」とも言えます。この「エベレスト大滑降」を再編集した英語版作品"The Man Who Skied Down Everest"('75年/石原プロ・米→カナダ)は、カナダの映画会社が石原プロから版権を買い取り台本・音楽等を再編
3000メートル滑るところを2000メートルで転倒してこれを「成功」と言えるかどうか分かりませんが、標高6000メートルの急斜面でアイスバーンに突っ込んで転倒して更に露岩にぶつかって死ななかったのは「奇跡」とも言えます。この「エベレスト大滑降」を再編集した英語版作品"The Man Who Skied Down Everest"('75年/石原プロ・米→カナダ)は、カナダの映画会社が石原プロから版権を買い取り台本・音楽等を再編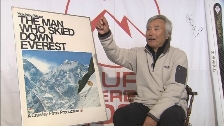 したもので、'75年に米ア
したもので、'75年に米ア
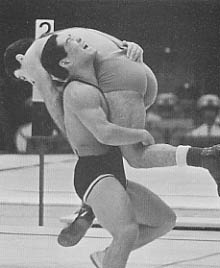 一方、渡辺長武の「186戦無敗」はギネスブックにも掲載されたことがあり(ウィキペディアでは189戦189勝となっている)、無敗記録としてみれば、後に柔道において、山下泰裕の「203戦無敗」という記録が生まれますが、山下泰裕の「203戦無敗」には7つの引き分けが
一方、渡辺長武の「186戦無敗」はギネスブックにも掲載されたことがあり(ウィキペディアでは189戦189勝となっている)、無敗記録としてみれば、後に柔道において、山下泰裕の「203戦無敗」という記録が生まれますが、山下泰裕の「203戦無敗」には7つの引き分けが 含まれているため、渡辺長武の記録はそれ以上に価値があるかも。世界選手権を連覇し('62年・'63年)、東京オリンピック('64年)でも金メダルを獲得しています(後に、女子レスリングで吉田沙保里の、2016年のリオ五輪決勝で敗れるまでの206連勝、オリンピック・世界選手権16連覇という記録が生まれることになるが)。
含まれているため、渡辺長武の記録はそれ以上に価値があるかも。世界選手権を連覇し('62年・'63年)、東京オリンピック('64年)でも金メダルを獲得しています(後に、女子レスリングで吉田沙保里の、2016年のリオ五輪決勝で敗れるまでの206連勝、オリンピック・世界選手権16連覇という記録が生まれることになるが)。 その渡辺長武は『アニマル1』(アニマルワン)というレスリング・アニメのモデルになりました(原作は「川崎のぼる」のコミック)。アニメ主題歌を、一昨年('04年)亡くなった朱里エイコが歌っていましたが、歌唱力のある人でした。「あの鐘を鳴らすのはあなた」を歌うと、このヒトがイチバン、相良直美が2番か3番、和田アキ子はそれらより落ちるという感じでした(個人的には)。
その渡辺長武は『アニマル1』(アニマルワン)というレスリング・アニメのモデルになりました(原作は「川崎のぼる」のコミック)。アニメ主題歌を、一昨年('04年)亡くなった朱里エイコが歌っていましたが、歌唱力のある人でした。「あの鐘を鳴らすのはあなた」を歌うと、このヒトがイチバン、相良直美が2番か3番、和田アキ子はそれらより落ちるという感じでした(個人的には)。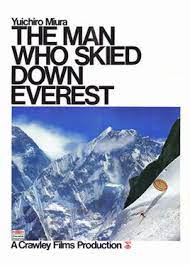
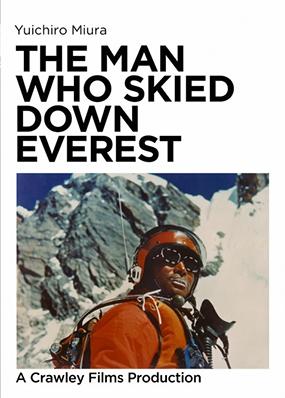 「エベレスト大滑降」●制作年:1970年●監督:銭谷功●製作:中井景/銭谷功●撮影:金宇満司●音楽:団伊玖磨●時間:119分●公開:1970/07●配給:松竹(評価:★★★☆)
「エベレスト大滑降」●制作年:1970年●監督:銭谷功●製作:中井景/銭谷功●撮影:金宇満司●音楽:団伊玖磨●時間:119分●公開:1970/07●配給:松竹(評価:★★★☆)


 パリ世界陸上('03年)の末続慎吾のスタート直前に与えられた不当な注意や、シドニー五輪('00年)柔道決勝の篠原信一・ドゥイエ戦の判定、日韓共催サッカー・ワールドカップ('02年)の韓国チームに有利に働いた判定、ソルトレイク冬期五輪('02年)フィギアの審判員の不正など、歴代の大きなスポーツ競技会での誤審や疑惑の判定が取りあげられていて、色々あったなあと思い出させてくれます。
パリ世界陸上('03年)の末続慎吾のスタート直前に与えられた不当な注意や、シドニー五輪('00年)柔道決勝の篠原信一・ドゥイエ戦の判定、日韓共催サッカー・ワールドカップ('02年)の韓国チームに有利に働いた判定、ソルトレイク冬期五輪('02年)フィギアの審判員の不正など、歴代の大きなスポーツ競技会での誤審や疑惑の判定が取りあげられていて、色々あったなあと思い出させてくれます。
 デイヴィッド・シールズ(略歴下記)
デイヴィッド・シールズ(略歴下記) 編者は―「イチローはグラウンドで超人的な離れ業、人間業とも思えない送球や捕球や盗塁やヒットなどを演じ、あとでそれについて質問されると、彼の答えときたら、驚くほかはない。そのプレーを問題にもしないか、否定するか、異を唱えるか、前提から否定してかかるか、あるいは他人の手柄にしてしまう」と驚き、「日本語から英語に訳される過程で、言葉が詩的な美しさを獲得したのだろうか?」と考察していますが、日本語に還元したものを我々が読むと、もっと自然な印象を受けます(彼のプロ意識の控えめな表現だったり、ちょっとマスコミに対して皮肉を言ってみたとか、或いはただインタビューを早く終らせたいだけだったとか)。それでも面白いのです。
編者は―「イチローはグラウンドで超人的な離れ業、人間業とも思えない送球や捕球や盗塁やヒットなどを演じ、あとでそれについて質問されると、彼の答えときたら、驚くほかはない。そのプレーを問題にもしないか、否定するか、異を唱えるか、前提から否定してかかるか、あるいは他人の手柄にしてしまう」と驚き、「日本語から英語に訳される過程で、言葉が詩的な美しさを獲得したのだろうか?」と考察していますが、日本語に還元したものを我々が読むと、もっと自然な印象を受けます(彼のプロ意識の控えめな表現だったり、ちょっとマスコミに対して皮肉を言ってみたとか、或いはただインタビューを早く終らせたいだけだったとか)。それでも面白いのです。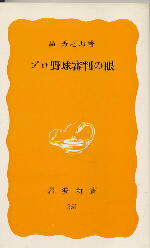
 島秀之助(1908-1995)
島秀之助(1908-1995)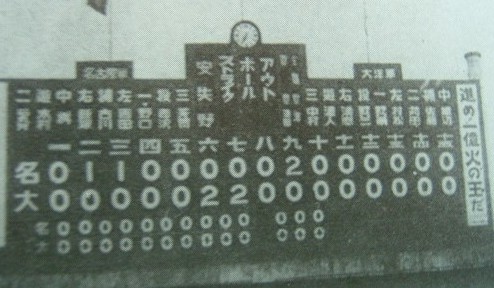 著者は初の日本シリーズや初の天覧試合の審判もしていますが、日本最多イニング試合の審判をした話がスゴイ。1942(昭和17)年の名古屋-大洋戦で、延長28回引き分けだったそうですが、大リーグでもこれを超える記録はありません。しかもその試合が"トリプル・ヘッダー"の第3試合だったというから、想像を絶する!(試合時間が3時間47分と"短い"のも意外。テンポいい試合だった?)。こうしたトリビアルなデータは、今はウェッブサイトなどでも見ることができますが、当事者の証言として語られているところがいいと思いました。
著者は初の日本シリーズや初の天覧試合の審判もしていますが、日本最多イニング試合の審判をした話がスゴイ。1942(昭和17)年の名古屋-大洋戦で、延長28回引き分けだったそうですが、大リーグでもこれを超える記録はありません。しかもその試合が"トリプル・ヘッダー"の第3試合だったというから、想像を絶する!(試合時間が3時間47分と"短い"のも意外。テンポいい試合だった?)。こうしたトリビアルなデータは、今はウェッブサイトなどでも見ることができますが、当事者の証言として語られているところがいいと思いました。
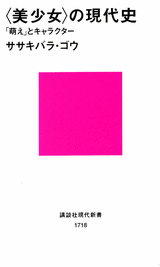

 『
『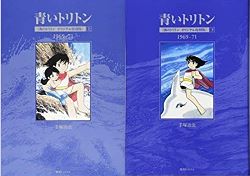


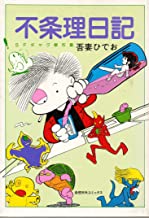
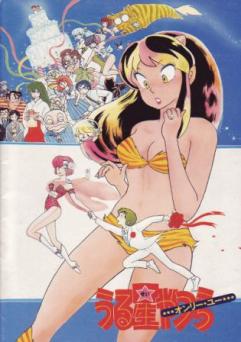
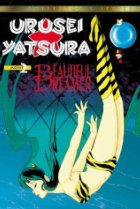
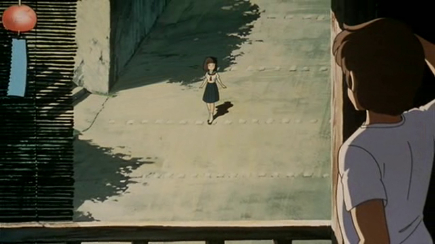
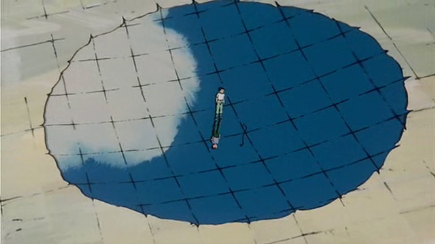
 一方、先に劇場映画作品として公開された「ルパン三世〜カリオストロの城」は、ヒロインのクラリス姫が特定のファンの間で非常に人気があるこ
一方、先に劇場映画作品として公開された「ルパン三世〜カリオストロの城」は、ヒロインのクラリス姫が特定のファンの間で非常に人気があるこ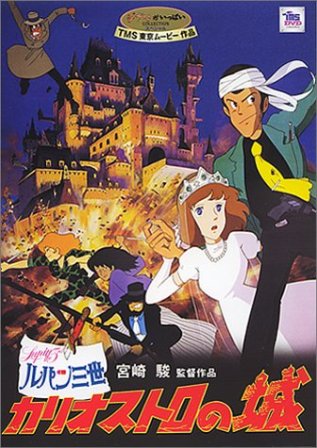
 のカッコ良さの方が個人的には印象に残ったかなあ。
のカッコ良さの方が個人的には印象に残ったかなあ。
 「カリオストロの城」のモデルと言われる(諸説あり)リヒテンシュタイン城。ドイツの南西部の都市・シュトゥットガルトの郊外にあり、映画と同じく古代ローマ様式の水道橋がある。
「カリオストロの城」のモデルと言われる(諸説あり)リヒテンシュタイン城。ドイツの南西部の都市・シュトゥットガルトの郊外にあり、映画と同じく古代ローマ様式の水道橋がある。
 第1シリーズ当初からのファンの中には、そのやや大人びた雰囲気が好きな層も多くいたようで、劇場版第1作「ルパン三世~ルパンVS複製人間」は、クローン人間をテーマとしたSFチックな壮大なストーリー(低年齢化したテレビ版の反動か。怪人「マモー」に果てしない人間の欲望を感じたこの作品が、個人的には一番面白かった)、それが第2作「ルパン三世~カリオストロの城」で、重厚な物語設定ながらも子どもにも分かり易い話になり(一方で「クラリス萌え」という密かなブームを引き起こしていたのだが)、更に、宮崎駿の推挙により押井守が監督した第3作「ルパン三世~バビロンの黄金伝説」('87年)では「うる星やつら」のようなギャグタッチが随所に見られるという、映画は結局6作まで作られていますが、こちらも監督が変わるごとにトーンがそれぞれに随分と違っている...。(2013年に17年ぶりの劇場版第7作「ルパン三世〜VSコナン THE MOVIE」が作られ、翌2014年に第8作「ルパン三世〜次元大介の墓標」も作られた。尚、TV版の単発スペシャル版は1989年から2013年までほぼ毎年1作のペースで作られ放映されている。)
第1シリーズ当初からのファンの中には、そのやや大人びた雰囲気が好きな層も多くいたようで、劇場版第1作「ルパン三世~ルパンVS複製人間」は、クローン人間をテーマとしたSFチックな壮大なストーリー(低年齢化したテレビ版の反動か。怪人「マモー」に果てしない人間の欲望を感じたこの作品が、個人的には一番面白かった)、それが第2作「ルパン三世~カリオストロの城」で、重厚な物語設定ながらも子どもにも分かり易い話になり(一方で「クラリス萌え」という密かなブームを引き起こしていたのだが)、更に、宮崎駿の推挙により押井守が監督した第3作「ルパン三世~バビロンの黄金伝説」('87年)では「うる星やつら」のようなギャグタッチが随所に見られるという、映画は結局6作まで作られていますが、こちらも監督が変わるごとにトーンがそれぞれに随分と違っている...。(2013年に17年ぶりの劇場版第7作「ルパン三世〜VSコナン THE MOVIE」が作られ、翌2014年に第8作「ルパン三世〜次元大介の墓標」も作られた。尚、TV版の単発スペシャル版は1989年から2013年までほぼ毎年1作のペースで作られ放映されている。)
 「海のトリトン」●演出:富野喜幸(富野由悠季)●制作:ア
「海のトリトン」●演出:富野喜幸(富野由悠季)●制作:ア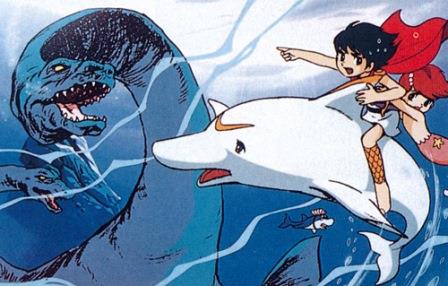 ニメーション・スタッフルーム●脚本:辻真先/松岡清治/宮田雪/松元力/斧谷稔●音楽:鈴木宏昌●原作:手塚治虫「青いトリトン」●出演(声):塩谷翼/広川あけみ/北浜晴子/八奈見乗児/野田圭一/沢田敏子/杉山佳寿子/北川国彦/渡部猛/増岡弘/渡辺毅/塩見龍助/滝口順平/矢田耕司/中西妙子/柴田秀勝●放映:1972/04~09(全27回)●放送局:朝日放送
ニメーション・スタッフルーム●脚本:辻真先/松岡清治/宮田雪/松元力/斧谷稔●音楽:鈴木宏昌●原作:手塚治虫「青いトリトン」●出演(声):塩谷翼/広川あけみ/北浜晴子/八奈見乗児/野田圭一/沢田敏子/杉山佳寿子/北川国彦/渡部猛/増岡弘/渡辺毅/塩見龍助/滝口順平/矢田耕司/中西妙子/柴田秀勝●放映:1972/04~09(全27回)●放送局:朝日放送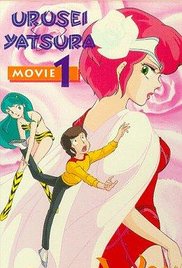

 色:押井守●製作:多賀英典●演出:安濃高志●脚本:金春智子●撮影監督:若菜章夫●音楽:小林泉美・安西史孝・天野正道●原作:高橋留美子●時間:80分●声の出演:平野文/古川登志夫/島津冴子/神谷明●公開:1983/02●配給:東宝●最初に観た場所:大井ロマン(85-05-05)(評価:★★☆)●併映:「うる星やつら2」(押井守)/「うる星やつら3」(やまざきかずお)
色:押井守●製作:多賀英典●演出:安濃高志●脚本:金春智子●撮影監督:若菜章夫●音楽:小林泉美・安西史孝・天野正道●原作:高橋留美子●時間:80分●声の出演:平野文/古川登志夫/島津冴子/神谷明●公開:1983/02●配給:東宝●最初に観た場所:大井ロマン(85-05-05)(評価:★★☆)●併映:「うる星やつら2」(押井守)/「うる星やつら3」(やまざきかずお) 「うる星やつら2/ ビューティフル・ドリーマー」●制作年:1984年●監督・脚本:押井守●製作:多賀英典●演出:西
「うる星やつら2/ ビューティフル・ドリーマー」●制作年:1984年●監督・脚本:押井守●製作:多賀英典●演出:西 村純二●撮影監督:若
村純二●撮影監督:若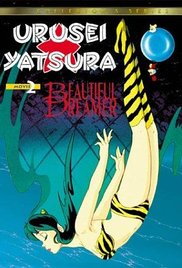

 子/田中真弓/藤岡琢也/千葉繁/村山明●公開:1984/02●配給:東宝●最初に観た場所:大井ロマン(85-05-05)(評価:★★★)●併映:「うる星やつら」(押井守)/「うる星やつら3」(やまざきかずお)
子/田中真弓/藤岡琢也/千葉繁/村山明●公開:1984/02●配給:東宝●最初に観た場所:大井ロマン(85-05-05)(評価:★★★)●併映:「うる星やつら」(押井守)/「うる星やつら3」(やまざきかずお)
 「うる星やつら3/リメンバー・マイ・ラブ」●制作年
「うる星やつら3/リメンバー・マイ・ラブ」●制作年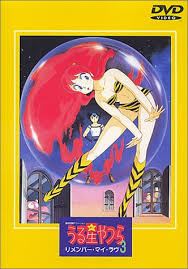
 「うる星やつら」(テレビアニメ版)●チーフディレクター:押井守(1話 - 129話)/やまざきかずお(130話 - 218話)●プロデューサー:布川ゆうじ/井上尭
「うる星やつら」(テレビアニメ版)●チーフディレクター:押井守(1話 - 129話)/やまざきかずお(130話 - 218話)●プロデューサー:布川ゆうじ/井上尭
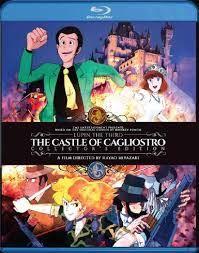
 「ルパン三世〜カリオストロの城」●制作年:1979年●監督:宮崎駿●製作:片山哲生●脚本:宮崎駿/山崎晴哉●作画監督:大塚康生●音楽:大野雄二 ●原作:モンキー・パンチ●時間:98分●声の出演:山田康雄(1932-1995)/島本須美/納谷悟朗(1929-2013)/小林清志/井上真樹夫/増山江威子/石田太郎/加藤正之/宮内幸平/寺島幹夫/山岡葉子/常泉忠通/平林尚三/松田重治/永井一郎/緑川稔/鎗田順吉/阪脩●公開:1979/12●配給:東宝 (評価:★★★☆)
「ルパン三世〜カリオストロの城」●制作年:1979年●監督:宮崎駿●製作:片山哲生●脚本:宮崎駿/山崎晴哉●作画監督:大塚康生●音楽:大野雄二 ●原作:モンキー・パンチ●時間:98分●声の出演:山田康雄(1932-1995)/島本須美/納谷悟朗(1929-2013)/小林清志/井上真樹夫/増山江威子/石田太郎/加藤正之/宮内幸平/寺島幹夫/山岡葉子/常泉忠通/平林尚三/松田重治/永井一郎/緑川稔/鎗田順吉/阪脩●公開:1979/12●配給:東宝 (評価:★★★☆)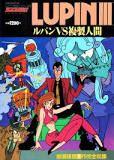
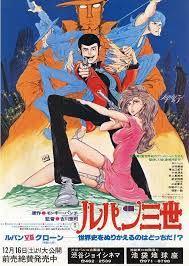

 「ルパン三世」(テレビアニメ版)●監督:(第1シリーズ)大隈正秋/(第3シリーズ)こだま兼嗣/鍋島修/亀垣一/奥脇雅晴ほか●プロデューサー:(第2シリーズ)高橋靖二(NTV)/高橋美光(TMS)/(第3シリーズ) 松元理人(東京ムービー新社)/佐野寿七(YTV)●音楽:山下毅雄/(第2シリーズ)大野雄二●原作:モンキー・パンチ●出演(声):山田康雄/小林清志/二階堂有希子/増山江威子/井上真樹夫/大塚周夫/納谷悟朗●放映:1971/10~1972/03(全23回)/1977/10~1980/10(全155回)/1984/03~1985/12(全50回)●放送局:読売テレビ(第1シリーズ)/日本テレビ(第2・第3シリーズ)
「ルパン三世」(テレビアニメ版)●監督:(第1シリーズ)大隈正秋/(第3シリーズ)こだま兼嗣/鍋島修/亀垣一/奥脇雅晴ほか●プロデューサー:(第2シリーズ)高橋靖二(NTV)/高橋美光(TMS)/(第3シリーズ) 松元理人(東京ムービー新社)/佐野寿七(YTV)●音楽:山下毅雄/(第2シリーズ)大野雄二●原作:モンキー・パンチ●出演(声):山田康雄/小林清志/二階堂有希子/増山江威子/井上真樹夫/大塚周夫/納谷悟朗●放映:1971/10~1972/03(全23回)/1977/10~1980/10(全155回)/1984/03~1985/12(全50回)●放送局:読売テレビ(第1シリーズ)/日本テレビ(第2・第3シリーズ)
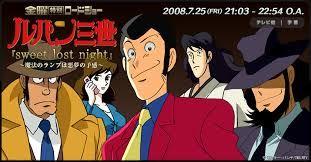






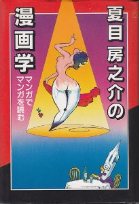

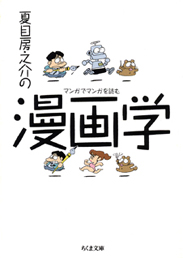
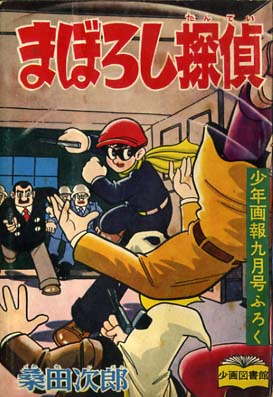

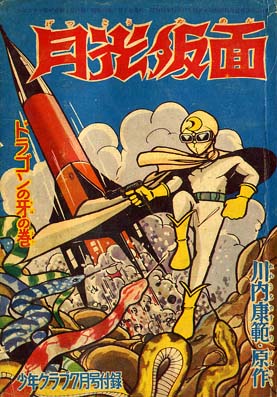
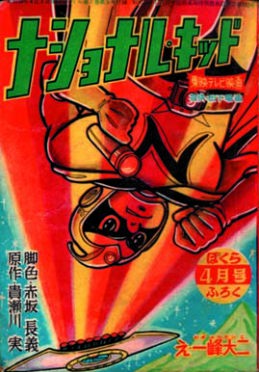 特に昭和30年代の「まぼろし探偵」「月光仮面」「ナショナルキッド」などについては詳しく書かれていて、楽しい"突っ込み"もいっぱい入れられており、団塊の世代(著者自身'50年生まれ)には楽しくまた懐かしく読めるものとなっているのではないでしょうか。
特に昭和30年代の「まぼろし探偵」「月光仮面」「ナショナルキッド」などについては詳しく書かれていて、楽しい"突っ込み"もいっぱい入れられており、団塊の世代(著者自身'50年生まれ)には楽しくまた懐かしく読めるものとなっているのではないでしょうか。 因みに、「まぼろし探偵」は、『少年画報』で'57(昭和32)年3月号から連載された桑田次郎(「8マン」の作画者でもある)原作の漫画で('61年に一旦終了し、'64年末から翌年4月号まで再連載)、テレビでは、'59(昭和34)年4月から1年間、KRT(現TBS)で放映されています。「月光仮面」はそれに先立ち、同じくKRTで、'58(昭和33)年2月から「赤胴鈴之助」の後番組として翌年7月まで放映され、一方「ナショナルキッド」はやや遅れて、'60(昭和35)年8月から翌年4月まで日本教育テレビ(現テレビ朝日)系で放送されています。
因みに、「まぼろし探偵」は、『少年画報』で'57(昭和32)年3月号から連載された桑田次郎(「8マン」の作画者でもある)原作の漫画で('61年に一旦終了し、'64年末から翌年4月号まで再連載)、テレビでは、'59(昭和34)年4月から1年間、KRT(現TBS)で放映されています。「月光仮面」はそれに先立ち、同じくKRTで、'58(昭和33)年2月から「赤胴鈴之助」の後番組として翌年7月まで放映され、一方「ナショナルキッド」はやや遅れて、'60(昭和35)年8月から翌年4月まで日本教育テレビ(現テレビ朝日)系で放送されています。






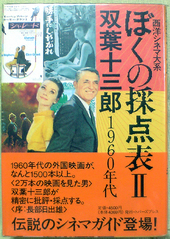
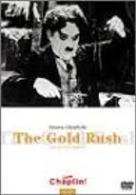
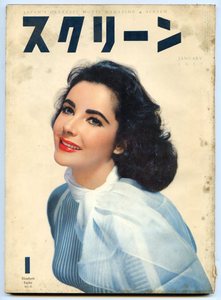
 映画雑誌「スクリーン」に長年にわたって映画評論を書き続けてきた著者による、20世紀に公開された外国映画500選の評論です。何しろ1910年生まれの著者は、見た洋画が1万数千本、邦画も含めると約2万本、1920年代中盤以降公開の作品はほとんどリアルタイムで見ているというからスゴイ!
映画雑誌「スクリーン」に長年にわたって映画評論を書き続けてきた著者による、20世紀に公開された外国映画500選の評論です。何しろ1910年生まれの著者は、見た洋画が1万数千本、邦画も含めると約2万本、1920年代中盤以降公開の作品はほとんどリアルタイムで見ているというからスゴイ!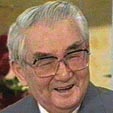 淀川長治(1909-1998)が「キネマ旬報」1980年12月下旬号に寄せた自らのベスト5が「黄金狂時代(チャールズ・チャップリン)」「戦艦ポチョムキン(セルゲイ・エイゼンシュテイン)」「グリード(エリッヒ・フォン・シュトロハイム)」「大いなる幻影(ジャン・ルノワール)」「ベニスに死す(ルキノ・ヴィスコンティ)」となっており、「黄金狂時代」と「大いなる幻影」が重なっています。年齢が近かったこともありますが(双葉氏が1歳年下)、意外と重なるなあという印象でしょうか。巻末の「ぼくの映画史」も、著者の人生と映画の変遷が重なり、その中で著者が、映画の過去・現在・将来にどういった思いを抱いているかが窺える味わい深いものでした。
淀川長治(1909-1998)が「キネマ旬報」1980年12月下旬号に寄せた自らのベスト5が「黄金狂時代(チャールズ・チャップリン)」「戦艦ポチョムキン(セルゲイ・エイゼンシュテイン)」「グリード(エリッヒ・フォン・シュトロハイム)」「大いなる幻影(ジャン・ルノワール)」「ベニスに死す(ルキノ・ヴィスコンティ)」となっており、「黄金狂時代」と「大いなる幻影」が重なっています。年齢が近かったこともありますが(双葉氏が1歳年下)、意外と重なるなあという印象でしょうか。巻末の「ぼくの映画史」も、著者の人生と映画の変遷が重なり、その中で著者が、映画の過去・現在・将来にどういった思いを抱いているかが窺える味わい深いものでした。 ストに挙げているのが興味を引きました(淀川長治は別のところでは、"生涯の一本"に「黄金狂時代」を挙げている)。「黄金狂時代」はチャップリン初の長編劇映画であり、ゴールドラッシュに沸くアラスカで一攫千金を夢見る男たちを描いたもので
ストに挙げているのが興味を引きました(淀川長治は別のところでは、"生涯の一本"に「黄金狂時代」を挙げている)。「黄金狂時代」はチャップリン初の長編劇映画であり、ゴールドラッシュに沸くアラスカで一攫千金を夢見る男たちを描いたもので すが、チャップリンの長編の中では最もスラップスティック感覚に溢れていて楽しめ(金鉱探しのチャーリーたちの寒さと飢えがピークに達して靴を食べるシーンも秀逸だが、その前の腹が減った仲間の目からはチャーリーがニワトリに見えてしまうシーンも可笑しかった)、個人的にもチャップリン作品のベストだと思います(後期の作品に見られるべとべとした感じが無い)。
すが、チャップリンの長編の中では最もスラップスティック感覚に溢れていて楽しめ(金鉱探しのチャーリーたちの寒さと飢えがピークに達して靴を食べるシーンも秀逸だが、その前の腹が減った仲間の目からはチャーリーがニワトリに見えてしまうシーンも可笑しかった)、個人的にもチャップリン作品のベストだと思います(後期の作品に見られるべとべとした感じが無い)。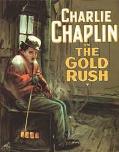

 「チャップリンの黄金狂時代(黄金狂時代)」●原題:THE GOLD RUSH●制作年:1936年●制作国:アメリカ●監督・製作・脚本:チャールズ・チャップリン●撮影:ローランド・トザロー●時間:82~96分(サウンド版73分)●出演:チャールズ・チャップリン/ビッグ・ジム・マッケイ/マック・スウェイン/トム・マレイ/ヘンリー・バーグマン/マルコム・ウエイト/スタンリー・J・サンフォード/アルバート・オースチン/アラン・ガルシア/トム・ウッド/チャールズ・コンクリン/ジョン・ランドなど●日本公開:1925/12●配給:ユナイテッド・アーティスツ●最初に観た場所:高田馬場パール座 (79-03-06)(評価:★★★★☆)●併映:「モダン・タイムス」(チャールズ・チャップリン)
「チャップリンの黄金狂時代(黄金狂時代)」●原題:THE GOLD RUSH●制作年:1936年●制作国:アメリカ●監督・製作・脚本:チャールズ・チャップリン●撮影:ローランド・トザロー●時間:82~96分(サウンド版73分)●出演:チャールズ・チャップリン/ビッグ・ジム・マッケイ/マック・スウェイン/トム・マレイ/ヘンリー・バーグマン/マルコム・ウエイト/スタンリー・J・サンフォード/アルバート・オースチン/アラン・ガルシア/トム・ウッド/チャールズ・コンクリン/ジョン・ランドなど●日本公開:1925/12●配給:ユナイテッド・アーティスツ●最初に観た場所:高田馬場パール座 (79-03-06)(評価:★★★★☆)●併映:「モダン・タイムス」(チャールズ・チャップリン)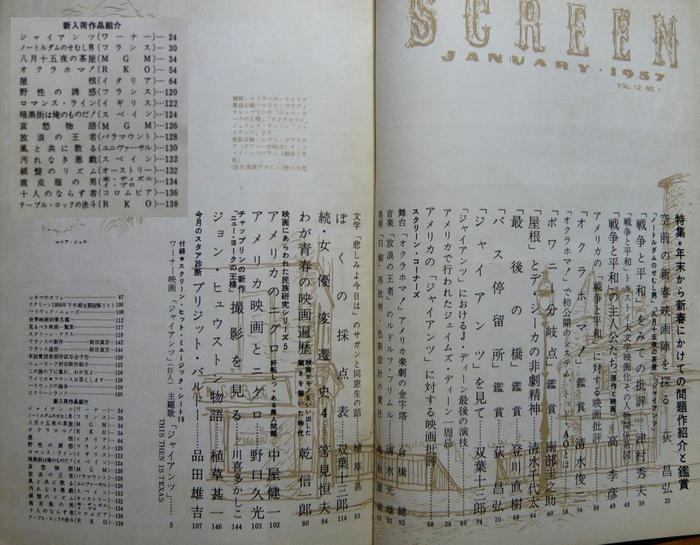
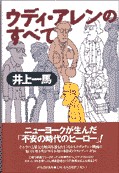
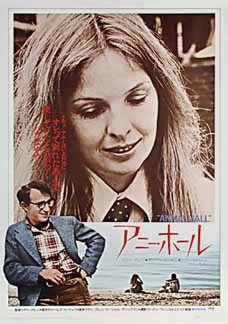
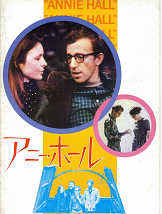
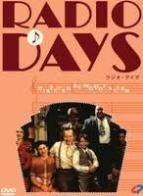
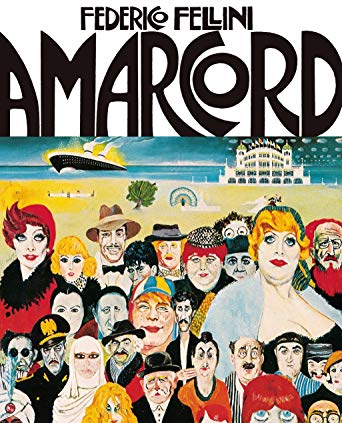

 ウディ・アレンがベルイマンの影響を受けているのは知っていましたが、フェリーニの影響を受けていたことは本書で知りました。「ラジオ・デイズ」('87年)は、第二次世界大戦開戦直後のニューヨーク・クイーンズ区ユダヤ系移民の大家族とその一員である少年を中心に、ラジオから流れる名曲の数々など当時の文化や市民生活を通じて、彼らの夢見がちな生き方や無邪気な時代の空気を表した作品でしたが、アレンの自伝的作品であることは確かで、著者はこの「ラジオ・デイズ」を、アカデミー外国語映画賞を
ウディ・アレンがベルイマンの影響を受けているのは知っていましたが、フェリーニの影響を受けていたことは本書で知りました。「ラジオ・デイズ」('87年)は、第二次世界大戦開戦直後のニューヨーク・クイーンズ区ユダヤ系移民の大家族とその一員である少年を中心に、ラジオから流れる名曲の数々など当時の文化や市民生活を通じて、彼らの夢見がちな生き方や無邪気な時代の空気を表した作品でしたが、アレンの自伝的作品であることは確かで、著者はこの「ラジオ・デイズ」を、アカデミー外国語映画賞を 受賞したフェリーニの「アマルコルド」('73年/伊・仏)にあたる作品であるとしています(これにはナルホドと思った)。どちらかと言うとベルイマン系と言える「ハンナとその姉妹」('86年)が傑作の誉れ高いですが、個人的には、最初に見た「アニー・ホール」('77年)の彼自身の神経症的な印象が強烈でした。
受賞したフェリーニの「アマルコルド」('73年/伊・仏)にあたる作品であるとしています(これにはナルホドと思った)。どちらかと言うとベルイマン系と言える「ハンナとその姉妹」('86年)が傑作の誉れ高いですが、個人的には、最初に見た「アニー・ホール」('77年)の彼自身の神経症的な印象が強烈でした。 ウディ・アレン演じるノイローゼ気味のコメディアン、アルビーと明るい性格のアニー・ホール(ダイアン・キートン)の2人の出会いと別れを描いた、コメディタッチでありながらもほろ苦い作品でした。因みに、"アニー・ホール"はダイアン・キートンの本名であり、これは、ダイアン・キートンに捧げた映画であるとも言えます。また、作中にべルイマンのこの映画製作時における最新作でイングリッド・バーグマン、リヴ・ウルマン主演の「鏡の中の女」('76年、米国での公開タイトルは"FACE TO FACE")のポスターが窺えますが、ダイアン・キートンはこの「アニー・ホール」で1977年アカデミー賞、1978年ゴールデングローブ賞の主演女優賞を受賞し、イングリッド・バーグマンが「白い恐怖」や「追想」で、リヴ・ウルマンがベルイマンの「叫びとささやき」で受賞しているニューヨーク映画批評家協会賞の主演女優賞も受賞しています(バーグマンはこの翌年ベルイマンの「
ウディ・アレン演じるノイローゼ気味のコメディアン、アルビーと明るい性格のアニー・ホール(ダイアン・キートン)の2人の出会いと別れを描いた、コメディタッチでありながらもほろ苦い作品でした。因みに、"アニー・ホール"はダイアン・キートンの本名であり、これは、ダイアン・キートンに捧げた映画であるとも言えます。また、作中にべルイマンのこの映画製作時における最新作でイングリッド・バーグマン、リヴ・ウルマン主演の「鏡の中の女」('76年、米国での公開タイトルは"FACE TO FACE")のポスターが窺えますが、ダイアン・キートンはこの「アニー・ホール」で1977年アカデミー賞、1978年ゴールデングローブ賞の主演女優賞を受賞し、イングリッド・バーグマンが「白い恐怖」や「追想」で、リヴ・ウルマンがベルイマンの「叫びとささやき」で受賞しているニューヨーク映画批評家協会賞の主演女優賞も受賞しています(バーグマンはこの翌年ベルイマンの「 有楽町の「ニュー東宝シネマ2」というややマイナーなロードショー館に観に行った際には外国人の観客が結構多く来ていて、笑いの起こるタイミングが字幕を読んでいる日本人はやや遅れがちで、しまいには外国人しか笑わないところもあったりして、会話が早すぎて、訳を端折っている感じもしました。当時は"入れ替え制"というものが無かったので、同じ劇場で2度観ましたが、アカデミー賞の最優秀作品賞、主演女優賞受賞、監督賞受賞、脚本賞の受賞が決まるやいなや「渋谷パンテオン」などの大劇場で再ロードされました。
有楽町の「ニュー東宝シネマ2」というややマイナーなロードショー館に観に行った際には外国人の観客が結構多く来ていて、笑いの起こるタイミングが字幕を読んでいる日本人はやや遅れがちで、しまいには外国人しか笑わないところもあったりして、会話が早すぎて、訳を端折っている感じもしました。当時は"入れ替え制"というものが無かったので、同じ劇場で2度観ましたが、アカデミー賞の最優秀作品賞、主演女優賞受賞、監督賞受賞、脚本賞の受賞が決まるやいなや「渋谷パンテオン」などの大劇場で再ロードされました。 この映画には、様々な役者がパーティ場面などでチラリと出ているほか、「トルーマン・カポーティのそっくりさん」役でトルーマン・カポーティ本人が出ていたり、映画館で文明批評家マクルーハンの著作を解説している男に対し、アレンが本物のマクルーハンを引っぱってきて、「君の解釈は間違っている」と本人に言わせるなど、遊びの要素もふんだんに取り入れられています。
この映画には、様々な役者がパーティ場面などでチラリと出ているほか、「トルーマン・カポーティのそっくりさん」役でトルーマン・カポーティ本人が出ていたり、映画館で文明批評家マクルーハンの著作を解説している男に対し、アレンが本物のマクルーハンを引っぱってきて、「君の解釈は間違っている」と本人に言わせるなど、遊びの要素もふんだんに取り入れられています。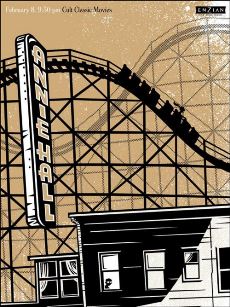 この映画で、アルビーは幼い頃ローラーコースター(和製英語で言えばジェットコースター)の下にある家で育ったことになっていますが(それが主人公が神経質な性格の原因だという)、これは撮影中のウディ・アレンの思いつきだったらしく、「ラジオ・デイズ」('87年)(こちらは劇場ではなく、知人宅でビデオで観た(89-05-02))でもその設定が踏襲されていたように思います(本当にウディ・アレンが子ども時代に遊園地の傍に住んでいたのかと思った)。
この映画で、アルビーは幼い頃ローラーコースター(和製英語で言えばジェットコースター)の下にある家で育ったことになっていますが(それが主人公が神経質な性格の原因だという)、これは撮影中のウディ・アレンの思いつきだったらしく、「ラジオ・デイズ」('87年)(こちらは劇場ではなく、知人宅でビデオで観た(89-05-02))でもその設定が踏襲されていたように思います(本当にウディ・アレンが子ども時代に遊園地の傍に住んでいたのかと思った)。 何でこのウディ・アレンという人はこんなに女性にもてるのかと、羨ましい気分も少し抱いてしまいますが、いろんな人がいろんな形で彼の映画に出演したり関わったりしていることがわかり、楽しい本でした。
何でこのウディ・アレンという人はこんなに女性にもてるのかと、羨ましい気分も少し抱いてしまいますが、いろんな人がいろんな形で彼の映画に出演したり関わったりしていることがわかり、楽しい本でした。
 (●2018年にフェリーニの「アマルコルド」('73年/伊・仏)を久しぶりに劇場で観ることができた。少年チッタ(ブルーノ・ザニン)とその家族を中心に、春の火祭り、豪華客船レックス号の寄港、年上の女性グラディスカ(マガリ・ノエル)への恋などが情感たっぷりに描かれる。
(●2018年にフェリーニの「アマルコルド」('73年/伊・仏)を久しぶりに劇場で観ることができた。少年チッタ(ブルーノ・ザニン)とその家族を中心に、春の火祭り、豪華客船レックス号の寄港、年上の女性グラディスカ(マガリ・ノエル)への恋などが情感たっぷりに描かれる。
 およそ高尚とは程遠い、庶民による祝祭」と言っていたが、確かにそうかも。1930年代に台頭してきたファシズム「黒シャツ党」にグラディスカら女性たちが嬌声を上げたり、チッタの父が拷問を受けるシーンが時代を感じさせるが、映画全体のトー
およそ高尚とは程遠い、庶民による祝祭」と言っていたが、確かにそうかも。1930年代に台頭してきたファシズム「黒シャツ党」にグラディスカら女性たちが嬌声を上げたり、チッタの父が拷問を受けるシーンが時代を感じさせるが、映画全体のトー ンは明るい。映像的にも美しいシ-ンが多いが、この映画で最も印象に残るシーンは、豪華客船レックス号が小船で沖へ出ていた町の人々の目の前に夜霧の中から忽然とその姿を現すシーンと、ラスト近くで、雪の日に街の真ん中で雪合戦をして遊ぶ少年達の目の前に白いクジャクが降り立つシーンだろう。ラストでチッタの母親は亡くなるが、イタリアでは孔雀は不吉なものとの迷信があり、後者のシーンは母親の死の前兆という位置づけにあることに改めて思い当たった。)
ンは明るい。映像的にも美しいシ-ンが多いが、この映画で最も印象に残るシーンは、豪華客船レックス号が小船で沖へ出ていた町の人々の目の前に夜霧の中から忽然とその姿を現すシーンと、ラスト近くで、雪の日に街の真ん中で雪合戦をして遊ぶ少年達の目の前に白いクジャクが降り立つシーンだろう。ラストでチッタの母親は亡くなるが、イタリアでは孔雀は不吉なものとの迷信があり、後者のシーンは母親の死の前兆という位置づけにあることに改めて思い当たった。)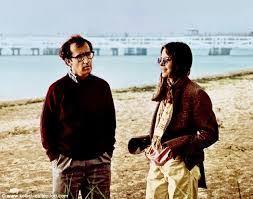 「アニー・ホール」●原題:ANNIE HALL●制作年:1977年●制作国:アメリカ●監督:ウディ・アレン●製作:チャールズ・ジョフィ/ジャック・ローリンズ●脚本:ウディ・アレン/マーシャル・ブリックマン●撮影:ゴードン・ウィリス ●時間:94分●出演:ウディ・アレン/ダイアン・キートン/トニー・ロバーツ/シェリー・デュバル/ポール・サイモン/シガニー・ウィーバー/クリストファー・ウォーケン/ジェフ・ゴールドブラム/ジョン・グローヴァー/トルーマン・カポーティ(ノンクレジット)●日本公開:1978/01●配給:オライオン映画●最初に観た場所:有楽町・ニュー東宝シネマ2(78-01-18)●2回目:有楽町・ニュー東宝シネマ2 (78-01-18)(評価:★★★★)
「アニー・ホール」●原題:ANNIE HALL●制作年:1977年●制作国:アメリカ●監督:ウディ・アレン●製作:チャールズ・ジョフィ/ジャック・ローリンズ●脚本:ウディ・アレン/マーシャル・ブリックマン●撮影:ゴードン・ウィリス ●時間:94分●出演:ウディ・アレン/ダイアン・キートン/トニー・ロバーツ/シェリー・デュバル/ポール・サイモン/シガニー・ウィーバー/クリストファー・ウォーケン/ジェフ・ゴールドブラム/ジョン・グローヴァー/トルーマン・カポーティ(ノンクレジット)●日本公開:1978/01●配給:オライオン映画●最初に観た場所:有楽町・ニュー東宝シネマ2(78-01-18)●2回目:有楽町・ニュー東宝シネマ2 (78-01-18)(評価:★★★★)


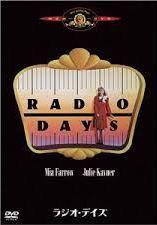
 アレン●製作:ロバート・グリーンハット●脚本:ウディ・アレン●撮影:カルロ・ディ・パルマ●音楽:ディッキー・ハイマン●時間:94分●出演:ミア・ファロー/ダイアン・ウィースト/セス・グリーン/ジュリー・カブナー/ジョシュ・モステル/マイケル・タッカー/ダイアン・キートン/ダニー・アイエロ/ジュディス・マリナ/ウィリアム・H・メイシー/リチャード・ポートナウ●日本公開:1987/10●配給:ワーナー・ブラザース (評価:★★★☆)
アレン●製作:ロバート・グリーンハット●脚本:ウディ・アレン●撮影:カルロ・ディ・パルマ●音楽:ディッキー・ハイマン●時間:94分●出演:ミア・ファロー/ダイアン・ウィースト/セス・グリーン/ジュリー・カブナー/ジョシュ・モステル/マイケル・タッカー/ダイアン・キートン/ダニー・アイエロ/ジュディス・マリナ/ウィリアム・H・メイシー/リチャード・ポートナウ●日本公開:1987/10●配給:ワーナー・ブラザース (評価:★★★☆)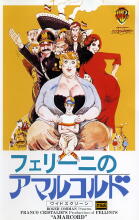
 「フェリーニのアマルコルド」●原題:FEDERICO FELLINI AMARCORD●制作年:1973年●制作国:イタリア・フランス●監督:フェデリコ・フェリーニ●製作:フランコ・クリスタルディ●脚本:フェデリコ・フェリーニ/トニーノ・グエッラ●撮影:ジュゼッペ・ロトゥンノ●音楽:ニーノ・ロータ●時間:124分●出演:ブルーノ・ザニン/マガリ
「フェリーニのアマルコルド」●原題:FEDERICO FELLINI AMARCORD●制作年:1973年●制作国:イタリア・フランス●監督:フェデリコ・フェリーニ●製作:フランコ・クリスタルディ●脚本:フェデリコ・フェリーニ/トニーノ・グエッラ●撮影:ジュゼッペ・ロトゥンノ●音楽:ニーノ・ロータ●時間:124分●出演:ブルーノ・ザニン/マガリ
 ・ノエル/プペラ・マッジオ/アルマンド・ブランチャ/チッチョ・イングラシア●日本公開:1974/11●配給:ワーナー・ブラザース●最初に観た場所:池袋・文芸座(78-02-07)●2回目:早稲田松竹(18-12-14)●併
・ノエル/プペラ・マッジオ/アルマンド・ブランチャ/チッチョ・イングラシア●日本公開:1974/11●配給:ワーナー・ブラザース●最初に観た場所:池袋・文芸座(78-02-07)●2回目:早稲田松竹(18-12-14)●併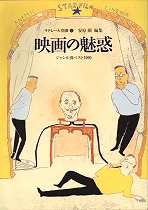

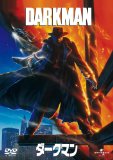





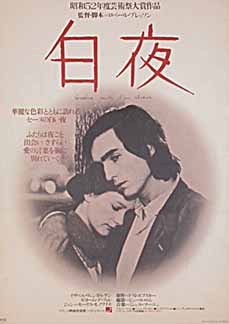
.jpg)
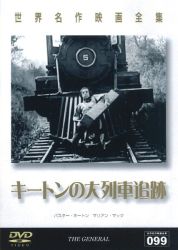


に体を張れ.jpg)

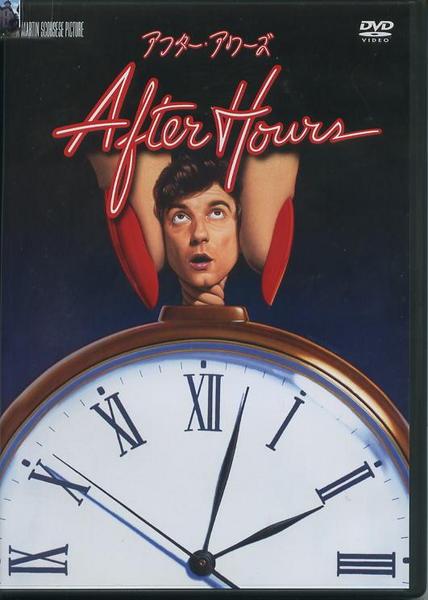
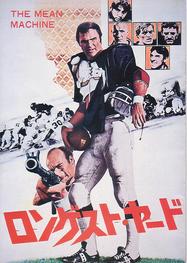
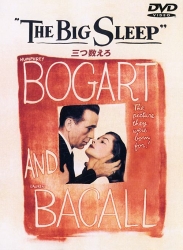

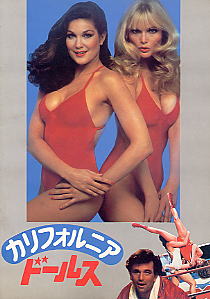 「カリフォルニア・ドールズ」は、男臭い世界を描いて定評のあるアルドリッチが女子プロレスの世界を描いた作品で、さえない女子プロのタッグ「カリフォルニア・ドールズ」のプロモーターを「刑事コロンボ」 のピーター・フォーク が好演しており、彼と2人の女性選手との心の通い合いが結構泣けます。
「カリフォルニア・ドールズ」は、男臭い世界を描いて定評のあるアルドリッチが女子プロレスの世界を描いた作品で、さえない女子プロのタッグ「カリフォルニア・ドールズ」のプロモーターを「刑事コロンボ」 のピーター・フォーク が好演しており、彼と2人の女性選手との心の通い合いが結構泣けます。
 「ダークマン」●原題:THE DARKMAN●制作年:1990年●制作国:アメリカ●監督・原作:サム・ライミ●製作:ロバート・タパート●脚本:チャック・ファーラー/サム・ライミ/アイヴァン・ライミ/ダニエル・ゴールディン/ジョシュア・ゴールディン●撮影:ビル・ポープ●音楽: ダニー・エルフマン●時間:96分●出演:リーアム・ニーソン/フランシス・マクドーマンド/ラリー・ドレイク/コリン・フリールズ/ネルソン・マシタ/ジェシー・ローレンス・ファーガソン/ラファエル・H・ロブレド/ダン・ヒックス/テッド・ライミ/ジョン・ランディス/ブルース・キャンベル●日本公開:1991/03●配給:ユニヴァーサル=UIP(評価:★★★★)
「ダークマン」●原題:THE DARKMAN●制作年:1990年●制作国:アメリカ●監督・原作:サム・ライミ●製作:ロバート・タパート●脚本:チャック・ファーラー/サム・ライミ/アイヴァン・ライミ/ダニエル・ゴールディン/ジョシュア・ゴールディン●撮影:ビル・ポープ●音楽: ダニー・エルフマン●時間:96分●出演:リーアム・ニーソン/フランシス・マクドーマンド/ラリー・ドレイク/コリン・フリールズ/ネルソン・マシタ/ジェシー・ローレンス・ファーガソン/ラファエル・H・ロブレド/ダン・ヒックス/テッド・ライミ/ジョン・ランディス/ブルース・キャンベル●日本公開:1991/03●配給:ユニヴァーサル=UIP(評価:★★★★).jpg) 「ロッキー・ホラー・ショー」●原題:THE ROCKY HORROR SHOW●制作年:1975年●制作国:イギリス●監督:ジム・シャーマン●製作:マイケル・ホワイト●脚本:ジム・シャーマン/リチャード・オブライエン●撮影:ピーター・サシツキー●音楽:リチャード・ハートレイ●時間:99分●出演:ティム・カリー/バリー・ボストウィック/スーザン・サランドン/リチャード・オブライエン/パトリシア・クイン/ジョナサン・アダムス/ミート・ローフ/チャールズ・グレイ●日本公開:1978/02●配給:20世紀フォックス●最初に観た場所:五反田TOEIシネマ(83-02-06)●2回目:シネマライズ渋谷(地下1階)(88-07-17)(評価:★★★?)●併映(1回目):「ファントム・オブ・パラダイス」(ブライアン・デ・パルマ)
「ロッキー・ホラー・ショー」●原題:THE ROCKY HORROR SHOW●制作年:1975年●制作国:イギリス●監督:ジム・シャーマン●製作:マイケル・ホワイト●脚本:ジム・シャーマン/リチャード・オブライエン●撮影:ピーター・サシツキー●音楽:リチャード・ハートレイ●時間:99分●出演:ティム・カリー/バリー・ボストウィック/スーザン・サランドン/リチャード・オブライエン/パトリシア・クイン/ジョナサン・アダムス/ミート・ローフ/チャールズ・グレイ●日本公開:1978/02●配給:20世紀フォックス●最初に観た場所:五反田TOEIシネマ(83-02-06)●2回目:シネマライズ渋谷(地下1階)(88-07-17)(評価:★★★?)●併映(1回目):「ファントム・オブ・パラダイス」(ブライアン・デ・パルマ)  「今宵かぎりは...」は、つい先だって('06年8月5日)亡くなった「ラ・パロマ」や「
「今宵かぎりは...」は、つい先だって('06年8月5日)亡くなった「ラ・パロマ」や「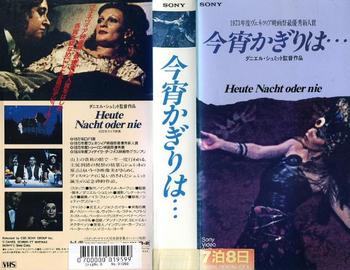
 「今宵かぎりは...」●原題:HEUTE HACHT ODER NIE●制作年:1972年●制作国:スイス●監督・脚本:ダニエル・シュミット●製作:イングリット・カーフェン●脚本:メル・フローマン●撮影:レナート・ベルタ ●時間:90分●出演:ペーター・カー
「今宵かぎりは...」●原題:HEUTE HACHT ODER NIE●制作年:1972年●制作国:スイス●監督・脚本:ダニエル・シュミット●製作:イングリット・カーフェン●脚本:メル・フローマン●撮影:レナート・ベルタ ●時間:90分●出演:ペーター・カー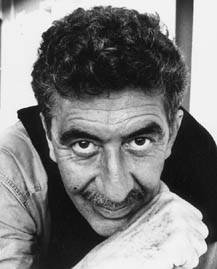 ン/イングリット・カーフェン/フォリ・ガイラー/ローズマリー・ハイニケル●日本公開:1986/11●配給:シネセゾン●最初に観た場所:シネヴィヴァン六本木(86-12-01)(評価:★★★?)
ン/イングリット・カーフェン/フォリ・ガイラー/ローズマリー・ハイニケル●日本公開:1986/11●配給:シネセゾン●最初に観た場所:シネヴィヴァン六本木(86-12-01)(評価:★★★?)

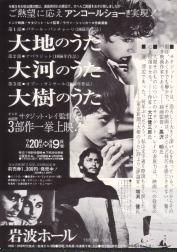
 総合ベスト10も、「天井桟敷の人々」「第三の男」「市民ケーン」「風と共に去りぬ」「大いなる幻影」「ウェストサイド物語」「2001年宇宙の旅」「カサブランカ」「駅馬車」「戦艦ポチョムキン」と"一昔前のオーソドックス"といった感じでしょうか(今でも名画であることには違いありませんが)。
総合ベスト10も、「天井桟敷の人々」「第三の男」「市民ケーン」「風と共に去りぬ」「大いなる幻影」「ウェストサイド物語」「2001年宇宙の旅」「カサブランカ」「駅馬車」「戦艦ポチョムキン」と"一昔前のオーソドックス"といった感じでしょうか(今でも名画であることには違いありませんが)。
 「禁じられた遊び」
「禁じられた遊び」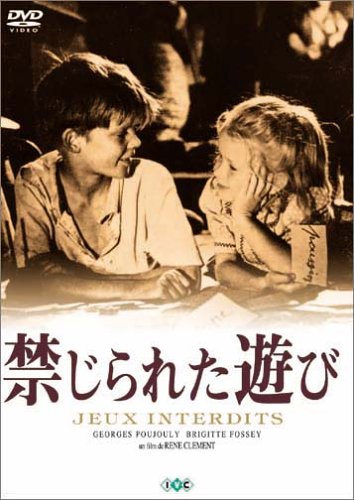
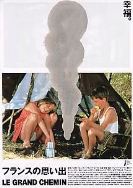

 「小さな悪の華」チラシ
「小さな悪の華」チラシ
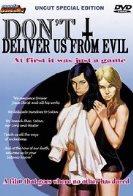
 一方、ジョエル・セリア監督の「小さな悪の華」('70年/仏)という作品は、早熟で魔性を持つ2人の15歳の少女が、ボードレールの「悪の華」を耽読し、農夫に裸を見せつけ、行きずりの男を誘拐して殺し、最後に焼身自殺するという衝撃的なものでしたが、祭壇作りにハマる少女たちには、「禁じられた遊び」の"十字架マニア"の少女ポーレットの"裏ヴァージョン"的なものを感じました。この作品は、"少女ポルノ"的描写であるともとれる場面があるため、製作当時、フランス本国では上映禁止となったとのことです。
一方、ジョエル・セリア監督の「小さな悪の華」('70年/仏)という作品は、早熟で魔性を持つ2人の15歳の少女が、ボードレールの「悪の華」を耽読し、農夫に裸を見せつけ、行きずりの男を誘拐して殺し、最後に焼身自殺するという衝撃的なものでしたが、祭壇作りにハマる少女たちには、「禁じられた遊び」の"十字架マニア"の少女ポーレットの"裏ヴァージョン"的なものを感じました。この作品は、"少女ポルノ"的描写であるともとれる場面があるため、製作当時、フランス本国では上映禁止となったとのことです。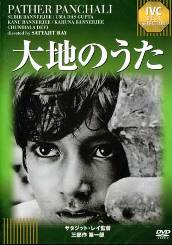

.jpg) 「大地のうた」('55年/インド)はサタジット・レイ監督の「オプー3部作」の第1作で、ベンガル地方の貧しい家庭の少年オプーの幼少期が描かれ、何と言っても、貧困のため雨中に肺炎で斃れたオプーの姉の挿話が哀しかったです。
「大地のうた」('55年/インド)はサタジット・レイ監督の「オプー3部作」の第1作で、ベンガル地方の貧しい家庭の少年オプーの幼少期が描かれ、何と言っても、貧困のため雨中に肺炎で斃れたオプーの姉の挿話が哀しかったです。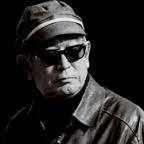 しかし、「大河のうた」は世界的には前作を上回る評価を得、1957年・第18回ヴェネツィア国際映画祭で金獅子賞を受賞、サタジット・レイは黒澤明を尊敬していましたが、同年にコンペティション部門に出品されていた黒澤明の「蜘蛛巣城」('57年/東宝)をコンペで破ったことになります。その黒澤明は、「サタジット・レイに会ったらあの人の作品が判ったね。眼光炯炯としていて、本当に立派な人なんだ。『蜘蛛巣城』がヴェネチア国際映画祭で『大河のうた』に負けた時、これはあたりまえだと思ったよ」と語っています。世界から喝采を浴びたサタジット・レイは、この作品を3部作とすることを決意、第3作「大樹のうた」('58年)は、青年となったオプーと、亡き妻の間に生まれ郷里に置いてきた息子との再会の物語になっています。
しかし、「大河のうた」は世界的には前作を上回る評価を得、1957年・第18回ヴェネツィア国際映画祭で金獅子賞を受賞、サタジット・レイは黒澤明を尊敬していましたが、同年にコンペティション部門に出品されていた黒澤明の「蜘蛛巣城」('57年/東宝)をコンペで破ったことになります。その黒澤明は、「サタジット・レイに会ったらあの人の作品が判ったね。眼光炯炯としていて、本当に立派な人なんだ。『蜘蛛巣城』がヴェネチア国際映画祭で『大河のうた』に負けた時、これはあたりまえだと思ったよ」と語っています。世界から喝采を浴びたサタジット・レイは、この作品を3部作とすることを決意、第3作「大樹のうた」('58年)は、青年となったオプーと、亡き妻の間に生まれ郷里に置いてきた息子との再会の物語になっています。.jpg)
.jpg)

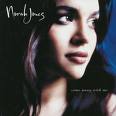 3作を通じて音楽にラヴィ・シャンカールのシタールが使われていることが、3部作に統一性を持たせることに繋がっていてるように思います。因みに、ラヴィ・シャンカールの2人の娘は、姉がジャズ歌手のノラ・ジョーンズ、妹がシタール奏者のアヌーシュカ・シャンカールで、この2人は異母姉妹です。なお、ラヴィ・シャンカールの演奏は、ジョージ・ハリスンの呼びかけで行われた飢饉救済コンサートのドキュメンタリー映画「
3作を通じて音楽にラヴィ・シャンカールのシタールが使われていることが、3部作に統一性を持たせることに繋がっていてるように思います。因みに、ラヴィ・シャンカールの2人の娘は、姉がジャズ歌手のノラ・ジョーンズ、妹がシタール奏者のアヌーシュカ・シャンカールで、この2人は異母姉妹です。なお、ラヴィ・シャンカールの演奏は、ジョージ・ハリスンの呼びかけで行われた飢饉救済コンサートのドキュメンタリー映画「 「
「
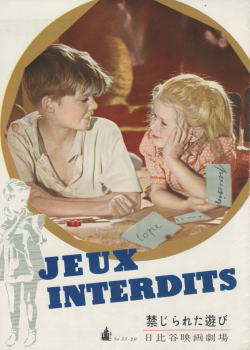 「禁じられた遊び」●原題:JEUX INTERDITS●制作年:1952年●制作国:フランス●監督:ルネ・クレマン●脚本:ジャン・オーランシュ/ピエール・ポスト●撮影:ロバート・ジュリアート●音楽:ナルシソ・イエペス●原作:フランソワ・ボワイエ●時間:86分●出演:ブリジッド・フォッセー/ジョルジュ・プージュリー/スザンヌ・クールタル/リュシアン・ユベール/ロランヌ・バディー/ジャック・マラン●日本公開:1953/09●配給:東和●最初に観た場所:早稲田松竹 (79-03-06)●2回目:高田馬場・ACTミニシアター (83-09-15)(評価:★★★★☆)●併映(1回目):「鉄道員」(ピエトロ・ジェルミ)●併映(2回目):「居酒屋」(ルネ・クレマン)
「禁じられた遊び」●原題:JEUX INTERDITS●制作年:1952年●制作国:フランス●監督:ルネ・クレマン●脚本:ジャン・オーランシュ/ピエール・ポスト●撮影:ロバート・ジュリアート●音楽:ナルシソ・イエペス●原作:フランソワ・ボワイエ●時間:86分●出演:ブリジッド・フォッセー/ジョルジュ・プージュリー/スザンヌ・クールタル/リュシアン・ユベール/ロランヌ・バディー/ジャック・マラン●日本公開:1953/09●配給:東和●最初に観た場所:早稲田松竹 (79-03-06)●2回目:高田馬場・ACTミニシアター (83-09-15)(評価:★★★★☆)●併映(1回目):「鉄道員」(ピエトロ・ジェルミ)●併映(2回目):「居酒屋」(ルネ・クレマン)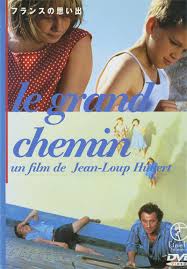
 「フランスの思い出」●原題:LE GRAND CHEMIN●制作年:1987年●制作国:フランス●監督・脚本:ジャン=ルー・ユベール●製作:パスカル・オメ/ジャン・フランソワ・ルプティ ●撮影:クロード・ルコント●音楽:ジョルジュ・グラニエ●時間:91分●出演:アネモーネ/リシャール・ボーランジェ/アントワーヌ・ユベール/ヴァネッサ・グジ/クリスチーヌ・パスカル/ラウール・ビイレー●日本公開:1988/08●配給:巴里映画●最初に観た場所:五反田TOEIシネマ (89-08-26)(評価:★★★★)●併映:「人生は長く静かな河」(エティエンヌ・シャティリエ)
「フランスの思い出」●原題:LE GRAND CHEMIN●制作年:1987年●制作国:フランス●監督・脚本:ジャン=ルー・ユベール●製作:パスカル・オメ/ジャン・フランソワ・ルプティ ●撮影:クロード・ルコント●音楽:ジョルジュ・グラニエ●時間:91分●出演:アネモーネ/リシャール・ボーランジェ/アントワーヌ・ユベール/ヴァネッサ・グジ/クリスチーヌ・パスカル/ラウール・ビイレー●日本公開:1988/08●配給:巴里映画●最初に観た場所:五反田TOEIシネマ (89-08-26)(評価:★★★★)●併映:「人生は長く静かな河」(エティエンヌ・シャティリエ)
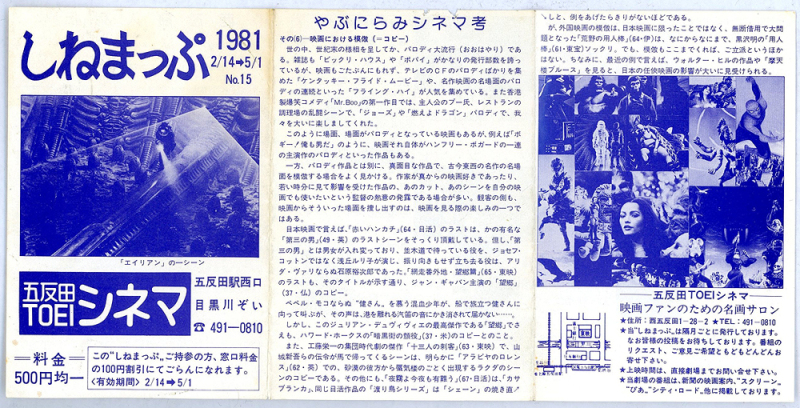




 「小さな悪の華」●原題:MAIS NE NOUS DELIVREZ PAS DU MAL●制作年:1970年●制作国:フランス●監督・脚本:ジョエル・セリア●撮影:マルセル・コンブ●音楽:ドミニク・ネイ●時間:103分●出演:ジャンヌ・グーピル/カトリーヌ・ワグナー/ベルナール・デラン/ミシェル・ロバン●日本公開:1972/03●配給:日本ヘラルド映画●最初に観た場所:中野武蔵野館 (77-12-12)(評価:★★★☆)●併映:「
「小さな悪の華」●原題:MAIS NE NOUS DELIVREZ PAS DU MAL●制作年:1970年●制作国:フランス●監督・脚本:ジョエル・セリア●撮影:マルセル・コンブ●音楽:ドミニク・ネイ●時間:103分●出演:ジャンヌ・グーピル/カトリーヌ・ワグナー/ベルナール・デラン/ミシェル・ロバン●日本公開:1972/03●配給:日本ヘラルド映画●最初に観た場所:中野武蔵野館 (77-12-12)(評価:★★★☆)●併映:「


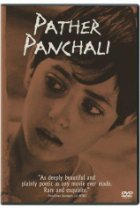
 「大地のうた」●原題:PATHER PANCHALI●制
「大地のうた」●原題:PATHER PANCHALI●制 作年:1955年●制作国:インド●監督・脚本:サタジット・レイ●撮影:スブラタ・ミットラ●音楽:ラヴィ・シャンカール●原作:ビブーティ・ブーション・バナージ●時間:125分●出演:カヌ・バナールジ/コルナ・バナールジ/スピール・バナールジ●日本公開:1966/10●配給ATG●最初に観た場
作年:1955年●制作国:インド●監督・脚本:サタジット・レイ●撮影:スブラタ・ミットラ●音楽:ラヴィ・シャンカール●原作:ビブーティ・ブーション・バナージ●時間:125分●出演:カヌ・バナールジ/コルナ・バナールジ/スピール・バナールジ●日本公開:1966/10●配給ATG●最初に観た場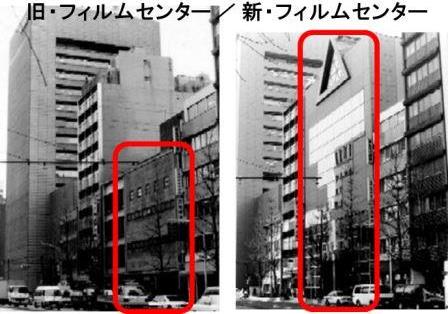

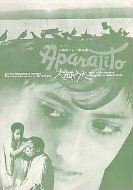
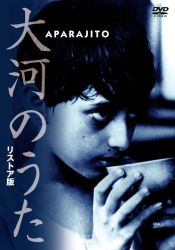
 「大河のうた」●原題:APARAJITO●制作年:1956年●制作国:インド●監督・脚本:サタジット・レイ●撮影:スブラタ・ミットラ●音楽:ラヴィ・シャンカール●原作:ビブーティ・ブーション・バナージ●時間:110分●出演:ピナキ・セン・グプタ/スマラン・ゴシャール/カヌ・バナールジ/コルナ・バナールジ ●日本公開:1970/11●配給:ATG●最初に観た場所:池袋テア
「大河のうた」●原題:APARAJITO●制作年:1956年●制作国:インド●監督・脚本:サタジット・レイ●撮影:スブラタ・ミットラ●音楽:ラヴィ・シャンカール●原作:ビブーティ・ブーション・バナージ●時間:110分●出演:ピナキ・セン・グプタ/スマラン・ゴシャール/カヌ・バナールジ/コルナ・バナールジ ●日本公開:1970/11●配給:ATG●最初に観た場所:池袋テア トルダイヤ (85-11-30)(評価:★★★★☆)●併映「大地のうた」「大樹のうた」(サタジット・レイ)
トルダイヤ (85-11-30)(評価:★★★★☆)●併映「大地のうた」「大樹のうた」(サタジット・レイ)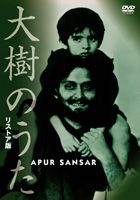
 「大樹のうた」●原題:APUR SANSAR●制作年:1958年●制作国:インド●監督・脚本:サタジット・レイ●撮影:スブラタ・ミットラ●音楽:ラヴィ・シャンカール●原作:ビブーティ・ブーション・バナージ●時間:105分●出演::ショウミットロ・チャテルジー /シャルミラ・タゴール/スワパン・ムカージ/アロク・チャクラバルティ●日本公開:1974/02●配給:ATG●最初に観た場所:池袋テアトルダイヤ (85-11-30)(評価:★★★★☆)●併映「大地のうた」「大河のうた」(サタジット・レイ)
「大樹のうた」●原題:APUR SANSAR●制作年:1958年●制作国:インド●監督・脚本:サタジット・レイ●撮影:スブラタ・ミットラ●音楽:ラヴィ・シャンカール●原作:ビブーティ・ブーション・バナージ●時間:105分●出演::ショウミットロ・チャテルジー /シャルミラ・タゴール/スワパン・ムカージ/アロク・チャクラバルティ●日本公開:1974/02●配給:ATG●最初に観た場所:池袋テアトルダイヤ (85-11-30)(評価:★★★★☆)●併映「大地のうた」「大河のうた」(サタジット・レイ)
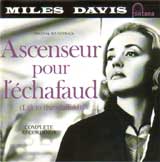
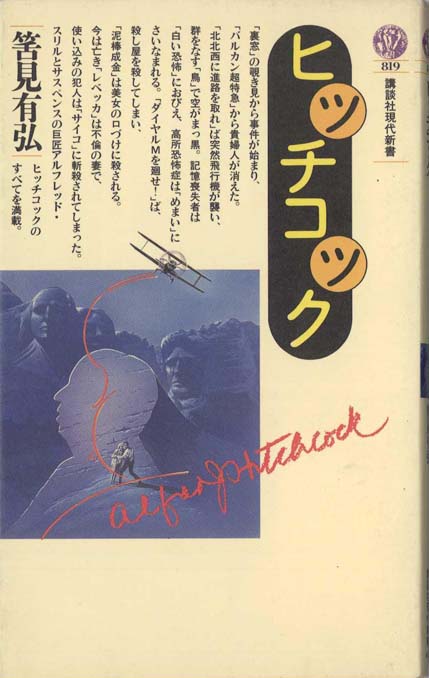


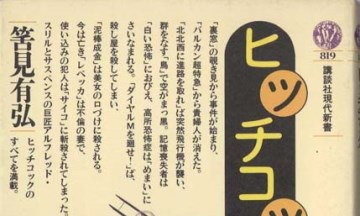
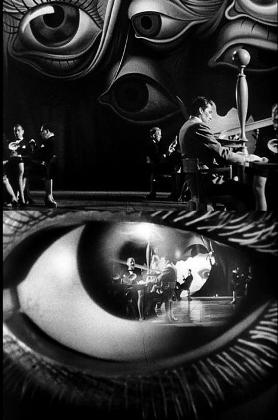
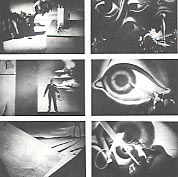 例えば、白と黒の縞模様を見ると発作を起こす医師をグレゴリー・ペック、彼を愛し発作の原因を探りだそうとする精神科医をイングリッド・バーグマンが演じた「白い恐怖」(原作はフランシス・ヒーディングの『白い恐怖』、本国での発表は1927年)では、グレゴリー・ペックの見る夢のシーンで用いられたサルバドール・ダリによるイメージ構成にダリの実験映画と同じような表現手法が見出せましたが(これにテルミンの音楽が被る)、この部分はあまりにストーレートで杓子定規な精神分析的解釈で、個人的にはさほどいいとは思えず、著者も「本来のヒチコックの映像造形とはかけ離れている」としています。
例えば、白と黒の縞模様を見ると発作を起こす医師をグレゴリー・ペック、彼を愛し発作の原因を探りだそうとする精神科医をイングリッド・バーグマンが演じた「白い恐怖」(原作はフランシス・ヒーディングの『白い恐怖』、本国での発表は1927年)では、グレゴリー・ペックの見る夢のシーンで用いられたサルバドール・ダリによるイメージ構成にダリの実験映画と同じような表現手法が見出せましたが(これにテルミンの音楽が被る)、この部分はあまりにストーレートで杓子定規な精神分析的解釈で、個人的にはさほどいいとは思えず、著者も「本来のヒチコックの映像造形とはかけ離れている」としています。 一方、イングリッド・バーグマンがはじめはメガネをかけていたことにはさほど気にとめていませんでしたが、他の作品では眼鏡をかけた女性が悪役で出てくるのに対し、この映画では、一見冷たさそうに見える女性が、恋をすると情熱的になることを効果的に表すために眼鏡を使っているとのことで、ナルホドと(イングリッド・バーグマンはこの作品で「全米映画批評家協会賞」の主演女優賞を受賞)。
一方、イングリッド・バーグマンがはじめはメガネをかけていたことにはさほど気にとめていませんでしたが、他の作品では眼鏡をかけた女性が悪役で出てくるのに対し、この映画では、一見冷たさそうに見える女性が、恋をすると情熱的になることを効果的に表すために眼鏡を使っているとのことで、ナルホドと(イングリッド・バーグマンはこの作品で「全米映画批評家協会賞」の主演女優賞を受賞)。
 一方、「白い恐怖」と同様に精神分析の要素が織り込まれていたのが「マーニー」('64年)でした(日本では「マーニー/赤い恐怖」の邦題でビデオ発売されたこともある)。ある会社の金庫が破られ、犯人は近頃雇い入れたばかりの女性事務員に違いないとういうことになるが、当の彼女はその頃ホテルでブルネットの髪を洗って黒い染髪料を洗い流すとブロンドに様変わり。よって、その行方は知れない―幼児期の体験がもとで盗みを繰り返し、男性やセックスにおびえる女性マーニーを「鳥」('63年)のティッピ・ヘドレンが演じ(彼女も血筋的にはバーグマンと同じ北欧系)、彼女と結婚して彼女を救おうとする夫を「
一方、「白い恐怖」と同様に精神分析の要素が織り込まれていたのが「マーニー」('64年)でした(日本では「マーニー/赤い恐怖」の邦題でビデオ発売されたこともある)。ある会社の金庫が破られ、犯人は近頃雇い入れたばかりの女性事務員に違いないとういうことになるが、当の彼女はその頃ホテルでブルネットの髪を洗って黒い染髪料を洗い流すとブロンドに様変わり。よって、その行方は知れない―幼児期の体験がもとで盗みを繰り返し、男性やセックスにおびえる女性マーニーを「鳥」('63年)のティッピ・ヘドレンが演じ(彼女も血筋的にはバーグマンと同じ北欧系)、彼女と結婚して彼女を救おうとする夫を「 著者はこの映画を初めて観たとき、ブルネットのときは盗みを働き、ブロンドの時は本質的に善であるマーニーから、ヒッチコックのブロンド贔屓もずいんぶん露骨だと思ったそうです。「裏窓」('54年)のグレース・ケリー、「
著者はこの映画を初めて観たとき、ブルネットのときは盗みを働き、ブロンドの時は本質的に善であるマーニーから、ヒッチコックのブロンド贔屓もずいんぶん露骨だと思ったそうです。「裏窓」('54年)のグレース・ケリー、「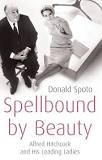
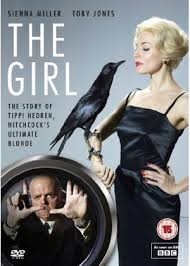 ますが、実際セクハラまがいのこともしたようです(ヒッチコックによるヘドレンへのセクハラを描いたドナルド・スポトの『Spellbound by Beauty: Alfred Hitchcock and His Leading Ladies』が、2012年に米・英・南アフリカ合作のテレビ映画「
ますが、実際セクハラまがいのこともしたようです(ヒッチコックによるヘドレンへのセクハラを描いたドナルド・スポトの『Spellbound by Beauty: Alfred Hitchcock and His Leading Ladies』が、2012年に米・英・南アフリカ合作のテレビ映画「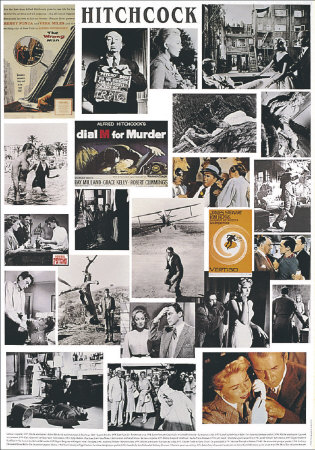 著者なりの作品のテーマ分析もありますが、「すべてエンターテイメントのために撮った」というヒチコックの言葉に沿ってか、それほど突っ込んで著者の考えを展開しているわけではありません。
著者なりの作品のテーマ分析もありますが、「すべてエンターテイメントのために撮った」というヒチコックの言葉に沿ってか、それほど突っ込んで著者の考えを展開しているわけではありません。
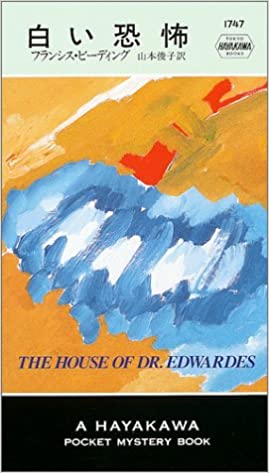

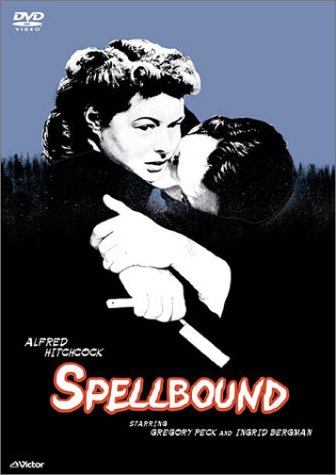
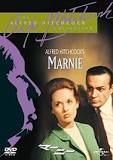
 「マーニー(マーニー/赤い恐怖)」●原題:MARNIE●制作年:1964年●制作国:アメリカ●監督・製作:アルフレッド・ヒッチコック●脚本:ジェイ・プレッソン・アレン●撮影:ロバート・バークス●音楽:バーナード・ハーマン●原作:ウィンストン・グレアム「マーニー」●時間:130分●出演:ショーン・コネリー/ティッピー・ヘドレン/マーティン・ガベル/ダイアン・ベイカー/ルイーズ・
「マーニー(マーニー/赤い恐怖)」●原題:MARNIE●制作年:1964年●制作国:アメリカ●監督・製作:アルフレッド・ヒッチコック●脚本:ジェイ・プレッソン・アレン●撮影:ロバート・バークス●音楽:バーナード・ハーマン●原作:ウィンストン・グレアム「マーニー」●時間:130分●出演:ショーン・コネリー/ティッピー・ヘドレン/マーティン・ガベル/ダイアン・ベイカー/ルイーズ・ ラサム/アラン・ネイピア/マリエット・ハートレイ/キンバリー・ベック/ブルース・ダーン●日本公開:1964/08●配給:ユニバーサル・ピクチャーズ(評価:★★★☆)
ラサム/アラン・ネイピア/マリエット・ハートレイ/キンバリー・ベック/ブルース・ダーン●日本公開:1964/08●配給:ユニバーサル・ピクチャーズ(評価:★★★☆)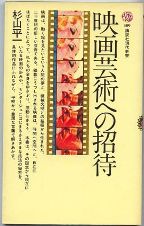
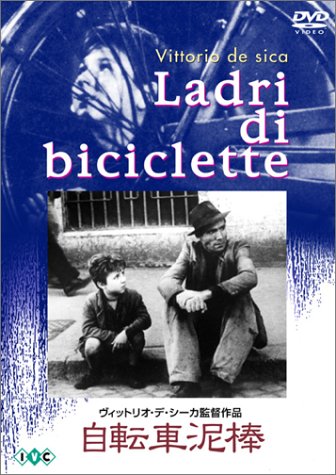
 ランベルト・マジョラーニ(右)
ランベルト・マジョラーニ(右)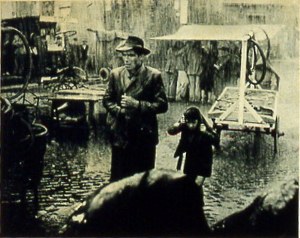 ビットリオ・デ・シーカ監督に「自転車泥棒」('48年/伊)という名画があり、世界中の人を感動させたわけですが、実際自分がフィルムセンター(焼失前の)でこの作品を観たときも、上映が終わって映画館から出てくる客がみんな泣いていました。
ビットリオ・デ・シーカ監督に「自転車泥棒」('48年/伊)という名画があり、世界中の人を感動させたわけですが、実際自分がフィルムセンター(焼失前の)でこの作品を観たときも、上映が終わって映画館から出てくる客がみんな泣いていました。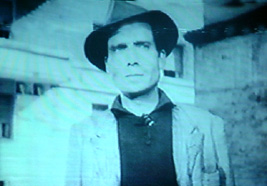 この映画の主人公を演じたランベルト・マジョラーニは、演技においては全くのズブの素人だったとのことで、ではなぜ、そんな素人が演じた映画が名画たりえたかと言うと、それは"モンタージュ"によるものであるとして、著者は、その"モンタージュ"という「魔法」を、この本でわかり易く解説しています(素人の演技が何故世界中の人々を泣かせるのかという導入自体がすでに"モンタージュ"の威力を示しており、効果的なイントロだと言える)。
この映画の主人公を演じたランベルト・マジョラーニは、演技においては全くのズブの素人だったとのことで、ではなぜ、そんな素人が演じた映画が名画たりえたかと言うと、それは"モンタージュ"によるものであるとして、著者は、その"モンタージュ"という「魔法」を、この本でわかり易く解説しています(素人の演技が何故世界中の人々を泣かせるのかという導入自体がすでに"モンタージュ"の威力を示しており、効果的なイントロだと言える)。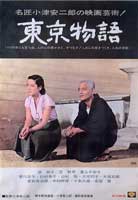
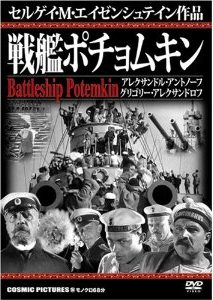



 エイゼンシュテインは更に歌舞伎の影響を強く受け、結局「イワン雷帝」(第1部'44年/第2部'46年/ソ連)などはその影響を受け過ぎて歌舞伎っぽくなってしまったとのことですが、確かに、あまりに大時代的で自分の肌に合わなかった...(この映画、ずーっと白黒で、第2部の途中からいきなり極彩色カラーになるのでビックリした。「民衆の支持を得た独裁者」というパラドクサルな主題のため、時の独裁者スターリンによって公開禁止になった作品。第3部は未完)。そのエイゼンシュテインに影響を与えた歌舞伎は、実は人形浄瑠璃の影響を受けているというのが興味深く、まさに「自然は芸術を模倣する」(人が人形の動きを真似する)という言葉の表れかと思います。
エイゼンシュテインは更に歌舞伎の影響を強く受け、結局「イワン雷帝」(第1部'44年/第2部'46年/ソ連)などはその影響を受け過ぎて歌舞伎っぽくなってしまったとのことですが、確かに、あまりに大時代的で自分の肌に合わなかった...(この映画、ずーっと白黒で、第2部の途中からいきなり極彩色カラーになるのでビックリした。「民衆の支持を得た独裁者」というパラドクサルな主題のため、時の独裁者スターリンによって公開禁止になった作品。第3部は未完)。そのエイゼンシュテインに影響を与えた歌舞伎は、実は人形浄瑠璃の影響を受けているというのが興味深く、まさに「自然は芸術を模倣する」(人が人形の動きを真似する)という言葉の表れかと思います。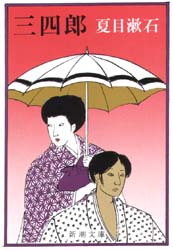
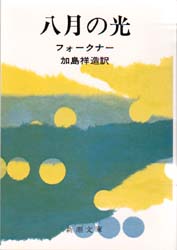
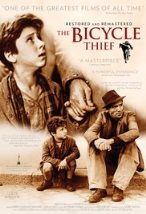

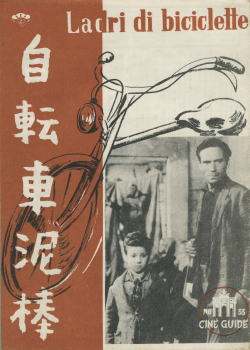 「自転車泥棒」●原題:LADRI DI BICICLETTE●制作年:1948年●制作国:イタリア●監督・製作:ビットリオ・デ・シーカ●脚本:チェーザレ・ザヴァッティーニ/オレステ・ビアンコーリ/スーゾ・チェッキ・ダミーコ/アドルフォ・フランチ/ジェラルド・グェリエリ●撮影:カルロ・モンテュオリ●音楽:アレッサンドロ・チコニーニ●原作:ルイジ
「自転車泥棒」●原題:LADRI DI BICICLETTE●制作年:1948年●制作国:イタリア●監督・製作:ビットリオ・デ・シーカ●脚本:チェーザレ・ザヴァッティーニ/オレステ・ビアンコーリ/スーゾ・チェッキ・ダミーコ/アドルフォ・フランチ/ジェラルド・グェリエリ●撮影:カルロ・モンテュオリ●音楽:アレッサンドロ・チコニーニ●原作:ルイジ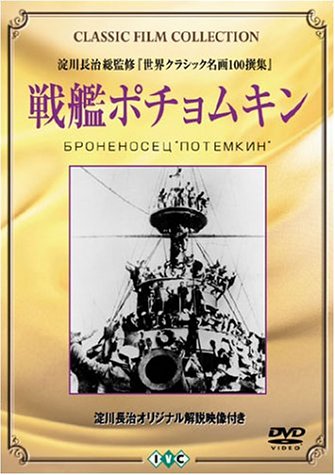

 「イワン雷帝」●原題:IVAN THE TERRIBLE IVAN GROZNYI●制作年:1946年(第1部・1944年)●制作国:ソ連●監督・脚本:セルゲイ・M・エイゼンシュテイン●撮影:アンドレイ・モスクヴィン/エドゥアルド・ティッセ ●音楽:セルゲイ・プロコフィエフ●時間:209分●出演:ニコライ・チェルカーソフ/リュドミラ・ツェリコフスカヤ/セラフィマ・ビルマン/パーヴェル・カドチニコフ/ミハイル・ジャーロフ●日本公開:1948/11●配給:東和●最初に観た場所:池袋文芸坐 (79-04-11) (評価:★★★)●併映:「戦艦ポチョムキン」(セルゲイ・エイゼンシュタイン)
「イワン雷帝」●原題:IVAN THE TERRIBLE IVAN GROZNYI●制作年:1946年(第1部・1944年)●制作国:ソ連●監督・脚本:セルゲイ・M・エイゼンシュテイン●撮影:アンドレイ・モスクヴィン/エドゥアルド・ティッセ ●音楽:セルゲイ・プロコフィエフ●時間:209分●出演:ニコライ・チェルカーソフ/リュドミラ・ツェリコフスカヤ/セラフィマ・ビルマン/パーヴェル・カドチニコフ/ミハイル・ジャーロフ●日本公開:1948/11●配給:東和●最初に観た場所:池袋文芸坐 (79-04-11) (評価:★★★)●併映:「戦艦ポチョムキン」(セルゲイ・エイゼンシュタイン) 杉山 平一(すぎやま へいいち、1914年11月2日 - 2012年5月19日)詩人、 映画評論家。2012年5月19日、肺炎のため死去。97歳。
杉山 平一(すぎやま へいいち、1914年11月2日 - 2012年5月19日)詩人、 映画評論家。2012年5月19日、肺炎のため死去。97歳。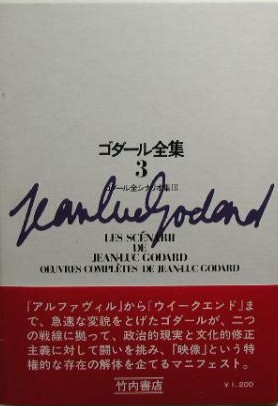
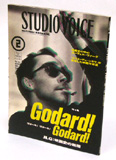
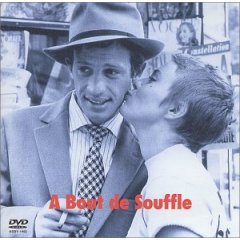

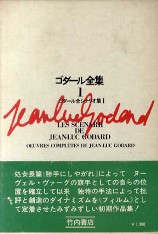
 面白いものが多く、またヴィヴィッドな印象を受けるのが意外かも知れません。よく知られているところでは、ジーン・セバーグ、ジャン=ポール・ベルモンド主演の「勝手にしやがれ」('59年)、アンナ・カリーナ、ベルモント主演の「気狂いピエロ」('65年)などの初期作品でしょうか。スチール写真が適度に配置され、読むと再度見たくなり、未見作品にも見てみたくなるものがありました。
面白いものが多く、またヴィヴィッドな印象を受けるのが意外かも知れません。よく知られているところでは、ジーン・セバーグ、ジャン=ポール・ベルモンド主演の「勝手にしやがれ」('59年)、アンナ・カリーナ、ベルモント主演の「気狂いピエロ」('65年)などの初期作品でしょうか。スチール写真が適度に配置され、読むと再度見たくなり、未見作品にも見てみたくなるものがありました。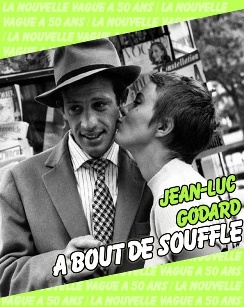


 パトリシアはミシェルとの愛を確認するため、ミシェルの居所をわざと警察に密告する―というもので、この不条理に満ちた話のオリジナル作者はフランソワ・トリュフォーですが、最終シナリオはゴーダルの頭の中にあったまま脚本化されずに撮影を開始したとのこと。台本無しの撮影にジャン=ポール・ベルモントは驚き、「どうせこの映画は公開されないだろうから、だったら好きなことを思い切りやってやろう」と思ったという逸話があります(1960年・第10回ベルリン国際映画祭「銀熊賞(監督賞)」受賞作)。
パトリシアはミシェルとの愛を確認するため、ミシェルの居所をわざと警察に密告する―というもので、この不条理に満ちた話のオリジナル作者はフランソワ・トリュフォーですが、最終シナリオはゴーダルの頭の中にあったまま脚本化されずに撮影を開始したとのこと。台本無しの撮影にジャン=ポール・ベルモントは驚き、「どうせこの映画は公開されないだろうから、だったら好きなことを思い切りやってやろう」と思ったという逸話があります(1960年・第10回ベルリン国際映画祭「銀熊賞(監督賞)」受賞作)。.jpg)
.jpg)


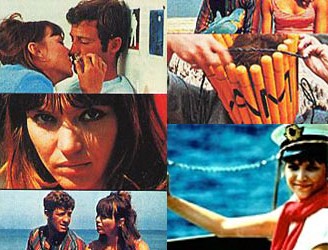
 「気狂いピエロ」は―、フェルディナン(ジャン=ポール・ベルモント)という男が、イタリア人の妻とパーティに行くが、パーティに退屈し戻ってきた家で、昔の恋人マリアンヌ(アンナ・カリーナ)と再会し、成り行きで彼女のアパートに泊まった翌朝、殺人事件に巻き込まれて、2人は逃避行を繰り返す羽目に。フェルディナンは孤島での生活を夢見るが、お互いにズレを感じたマリアンヌが彼を裏切って情夫の元へ行ったため、フェルディナンは彼女と情夫を射殺し、彼も自殺するというもの(1965年・第26回ヴェネチア国際映画祭「新鋭評論家賞」受賞作)。
「気狂いピエロ」は―、フェルディナン(ジャン=ポール・ベルモント)という男が、イタリア人の妻とパーティに行くが、パーティに退屈し戻ってきた家で、昔の恋人マリアンヌ(アンナ・カリーナ)と再会し、成り行きで彼女のアパートに泊まった翌朝、殺人事件に巻き込まれて、2人は逃避行を繰り返す羽目に。フェルディナンは孤島での生活を夢見るが、お互いにズレを感じたマリアンヌが彼を裏切って情夫の元へ行ったため、フェルディナンは彼女と情夫を射殺し、彼も自殺するというもの(1965年・第26回ヴェネチア国際映画祭「新鋭評論家賞」受賞作)。 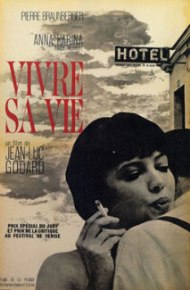

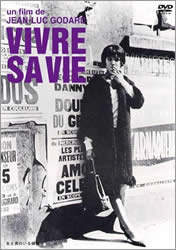
 「勝手にしやがれ」●原題:A BOUT DE SOUFFLE(英:BREATHLESS)●制作年:1959年●制作国:フランス●監督・脚本:ジャン=リュック・ゴダール●製作:ジョルジュ・ド・ボールガール●原作・原案・脚本:フランソワ・トリュフォー●撮
「勝手にしやがれ」●原題:A BOUT DE SOUFFLE(英:BREATHLESS)●制作年:1959年●制作国:フランス●監督・脚本:ジャン=リュック・ゴダール●製作:ジョルジュ・ド・ボールガール●原作・原案・脚本:フランソワ・トリュフォー●撮


 「気狂いピエロ」●原題:PIERROT LE FOU●制作年:1965年●制作国:フランス●監督・脚本:ジャン=リュック・ゴダール●製作:ジョルジュ・ド・ボールガール●撮影:ラウール・クタール●音楽:アントワース・デュアメル●原作:ライオネル・ホワイト「十一時の悪魔」●時間:109
「気狂いピエロ」●原題:PIERROT LE FOU●制作年:1965年●制作国:フランス●監督・脚本:ジャン=リュック・ゴダール●製作:ジョルジュ・ド・ボールガール●撮影:ラウール・クタール●音楽:アントワース・デュアメル●原作:ライオネル・ホワイト「十一時の悪魔」●時間:109 分●出演:ジャン=ポール・ベルモンド/アンナ・カリーナ/サミュエル・フラー /レイモン・ドボス/グラツィエッラ・ガルヴァーニ/ダーク・サンダース/ジミー・カルービ/ジャン=ピエール・レオ/アイシャ・アバディ/ラズロ・サボ●日本公開:1967/07●配給:セントラル●最初に観た場所:有楽シネマ (83-05-28) (評価★★★★)●併映:「彼女について私が知っている二、三の事柄」(ジャン=リュック・ゴダール)
分●出演:ジャン=ポール・ベルモンド/アンナ・カリーナ/サミュエル・フラー /レイモン・ドボス/グラツィエッラ・ガルヴァーニ/ダーク・サンダース/ジミー・カルービ/ジャン=ピエール・レオ/アイシャ・アバディ/ラズロ・サボ●日本公開:1967/07●配給:セントラル●最初に観た場所:有楽シネマ (83-05-28) (評価★★★★)●併映:「彼女について私が知っている二、三の事柄」(ジャン=リュック・ゴダール)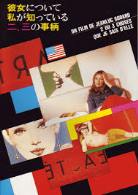 作国:フランス・イタリア●監督・脚本:ジャン=リュック・ゴダール●撮影:ラウール・クタール●音楽:ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン●原案:カトリーヌ・ヴィムネ●時間:90分●出演:ジョゼフ・ジェラール/マリナ・ヴラディ/アニー・デュプレー/ロジェ・モンソレ/ラウール・レヴィ/
作国:フランス・イタリア●監督・脚本:ジャン=リュック・ゴダール●撮影:ラウール・クタール●音楽:ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン●原案:カトリーヌ・ヴィムネ●時間:90分●出演:ジョゼフ・ジェラール/マリナ・ヴラディ/アニー・デュプレー/ロジェ・モンソレ/ラウール・レヴィ/ ジャン・ナルボニ/イヴ・ブネトン/エレナ・ビエリシック/クリストフ・ブルセイエ/マリー・ブルセイエ/マリー・カルディナル/ロベール・シュヴァシュー/ジャン=リュック・ゴダール(ナレーション)●日本公開:1970/10●配給:フランス映画社●最初に観た場所:有楽シネマ (83-05-28) (評価★★★)●併映:「気狂いピエロ 」(ジャン=リュック・ゴダール)
ジャン・ナルボニ/イヴ・ブネトン/エレナ・ビエリシック/クリストフ・ブルセイエ/マリー・ブルセイエ/マリー・カルディナル/ロベール・シュヴァシュー/ジャン=リュック・ゴダール(ナレーション)●日本公開:1970/10●配給:フランス映画社●最初に観た場所:有楽シネマ (83-05-28) (評価★★★)●併映:「気狂いピエロ 」(ジャン=リュック・ゴダール)



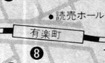 有楽シネマ (1955年11月14日オープン、1994年12月休館、1995年6月16日~シネマ有楽町(成人映画上映館)、1996年~銀座シネ・ラ・セット、159席) 2004(平成16)年1月31日閉館 跡地に建設のイトシアプラザ内に2007年10月シネカノン有楽町2丁目オープン、2009年12月4日ヒューマントラストシネマ有楽町に改称
有楽シネマ (1955年11月14日オープン、1994年12月休館、1995年6月16日~シネマ有楽町(成人映画上映館)、1996年~銀座シネ・ラ・セット、159席) 2004(平成16)年1月31日閉館 跡地に建設のイトシアプラザ内に2007年10月シネカノン有楽町2丁目オープン、2009年12月4日ヒューマントラストシネマ有楽町に改称


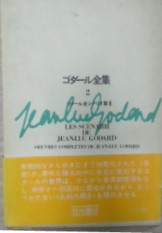
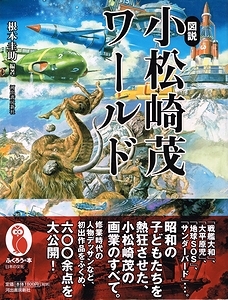

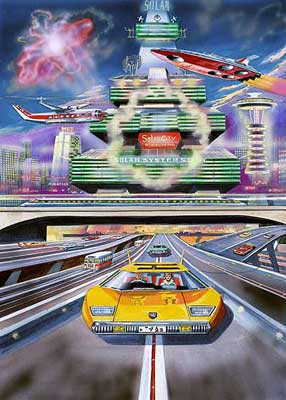 "ソーラー・シティ"
"ソーラー・シティ"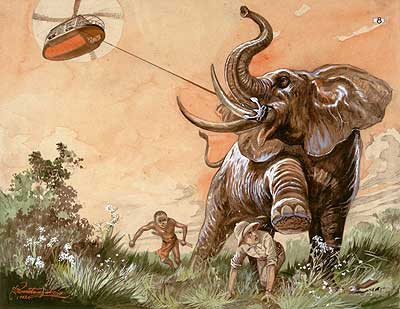 小松崎茂と言えば、サンダーバードのプラモデルのボックスアート(パッケージアート、箱絵)のイメージが強くあり、サンダーバードに限らず、タミヤのドイツ戦車やゼロ戦などのプラモデルのボックスアートも印象に残っていますが、本書を見て、ボックスアートばかりでなく、様々な仕事を手がけていたことを知りました。
小松崎茂と言えば、サンダーバードのプラモデルのボックスアート(パッケージアート、箱絵)のイメージが強くあり、サンダーバードに限らず、タミヤのドイツ戦車やゼロ戦などのプラモデルのボックスアートも印象に残っていますが、本書を見て、ボックスアートばかりでなく、様々な仕事を手がけていたことを知りました。 小松崎の活躍の始まりは昭和20年代の冒険活劇物語(いわゆる「絵物語」)で、作家として物語を書きつつ挿画も書いていたようですが、「大平原児」とかウェスタン調のものが多いのが面白い。
小松崎の活躍の始まりは昭和20年代の冒険活劇物語(いわゆる「絵物語」)で、作家として物語を書きつつ挿画も書いていたようですが、「大平原児」とかウェスタン調のものが多いのが面白い。 乱雑の極みでしたが、どうしてこういう環境でこのような垢抜けた絵が描けるのか不思議な気もしました。若いころの写真を見ると、小太りでオタクっぽい感じがあります。
乱雑の極みでしたが、どうしてこういう環境でこのような垢抜けた絵が描けるのか不思議な気もしました。若いころの写真を見ると、小太りでオタクっぽい感じがあります。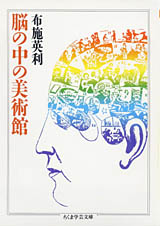
 布施 英利 氏(略歴下記)
布施 英利 氏(略歴下記)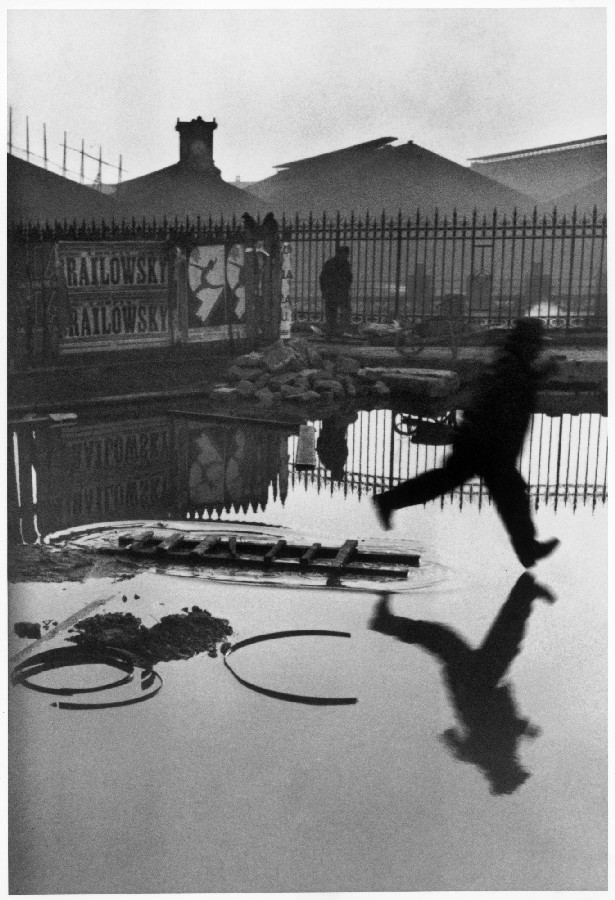 本書では、人体の視知覚形式を、ありのままの現実を見ることに徹する「目の視覚」(1次視覚)と再構成を通して共有化される観念的・抽象的な世界を映し出す「脳の視覚」(2次視覚)に分け、視覚芸術(写真・映画・マンガ・アニメ・絵画)の表現を、この区分に沿って解析しています。
本書では、人体の視知覚形式を、ありのままの現実を見ることに徹する「目の視覚」(1次視覚)と再構成を通して共有化される観念的・抽象的な世界を映し出す「脳の視覚」(2次視覚)に分け、視覚芸術(写真・映画・マンガ・アニメ・絵画)の表現を、この区分に沿って解析しています。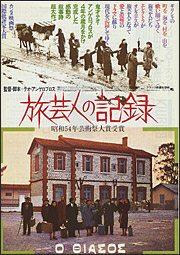


 杉山 平一 氏
杉山 平一 氏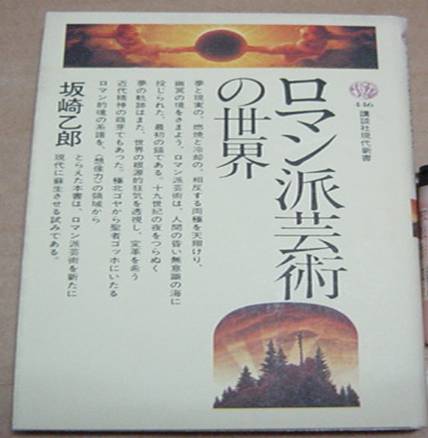
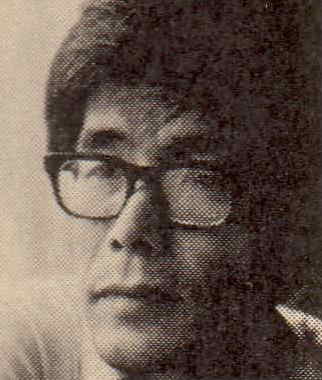 坂崎 乙郎 (1927-1985/享年57)
坂崎 乙郎 (1927-1985/享年57)
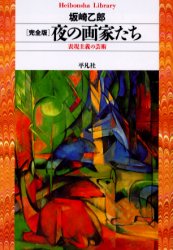
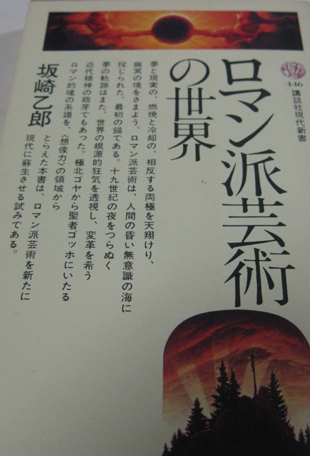 ロマン主義の画家にどのような人がいたかと調べてみれば、ブレーク、フリードリヒ、ターナー、ジェリコー、そして大御所ドラクロアなどが代表的画家であるようですが、著者はロマン主義の画家に見られる特質を分析し、背景としての「夜」の使われ方や、モチーフとしての「夢」の役割、分裂病質とも言える「狂気」の表れ、デフォルメなどの背後にある「美の計算」などを独自に解き明かしています。
ロマン主義の画家にどのような人がいたかと調べてみれば、ブレーク、フリードリヒ、ターナー、ジェリコー、そして大御所ドラクロアなどが代表的画家であるようですが、著者はロマン主義の画家に見られる特質を分析し、背景としての「夜」の使われ方や、モチーフとしての「夢」の役割、分裂病質とも言える「狂気」の表れ、デフォルメなどの背後にある「美の計算」などを独自に解き明かしています。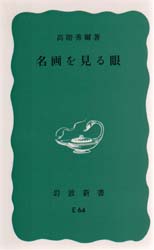

 ルネッサンス期から印象派の始まり(マネ)までの代表的な画家の作品15点選び、その絵の解説から入って、画家の意図や作風、歴史的背景や画家がどのような人生を送ったのかをわかりやすく解説した手引書です。高踏的にならず読みやすい文章に加え、まず1枚の名画を見て普通の人がちょっと変だなあと感じるところに着目して解説しているので、謎解きの感じで楽しめます。
ルネッサンス期から印象派の始まり(マネ)までの代表的な画家の作品15点選び、その絵の解説から入って、画家の意図や作風、歴史的背景や画家がどのような人生を送ったのかをわかりやすく解説した手引書です。高踏的にならず読みやすい文章に加え、まず1枚の名画を見て普通の人がちょっと変だなあと感じるところに着目して解説しているので、謎解きの感じで楽しめます。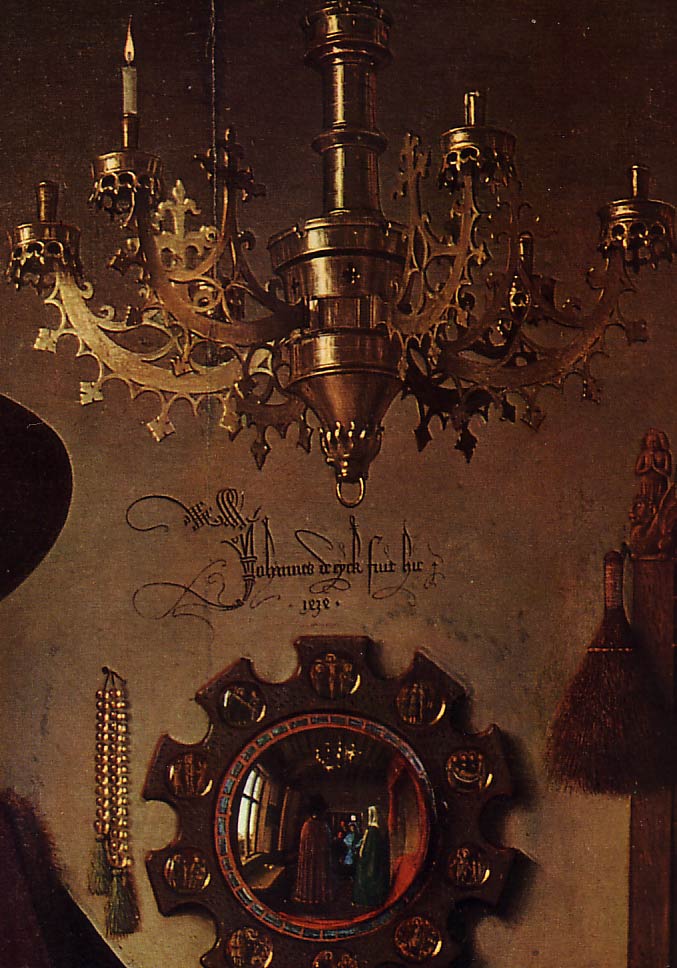 新書なので絵そのものの美しさは楽しめませんが、比較的有名な作品が多いので画集や教育用のサイトでも同じ作品を見つけることは可能だと思います。
新書なので絵そのものの美しさは楽しめませんが、比較的有名な作品が多いので画集や教育用のサイトでも同じ作品を見つけることは可能だと思います。1.jpg) ただし、例えばベラスケスの「宮廷の侍女たち」のような、離れて見ると柔らかい光沢を帯びた衣裳生地のように緻密に見えるのに、近づいてみるとラフな筆触で何が描かれているのか判らないという不思議さなどは、マドリッドのプラド美術館に行って実物を見ない限りは味わえないないわけですが...、これを200年後の印象主義の先駆けと見る著者の視点は面白いと思いました(というか、ベラスケス恐るべし!といったところでもある)。
ただし、例えばベラスケスの「宮廷の侍女たち」のような、離れて見ると柔らかい光沢を帯びた衣裳生地のように緻密に見えるのに、近づいてみるとラフな筆触で何が描かれているのか判らないという不思議さなどは、マドリッドのプラド美術館に行って実物を見ない限りは味わえないないわけですが...、これを200年後の印象主義の先駆けと見る著者の視点は面白いと思いました(というか、ベラスケス恐るべし!といったところでもある)。.jpg)
2.jpg)
3.jpg)



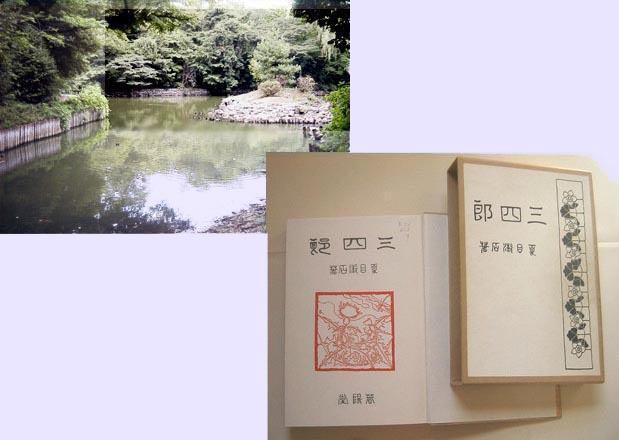




 橋本 治 氏
橋本 治 氏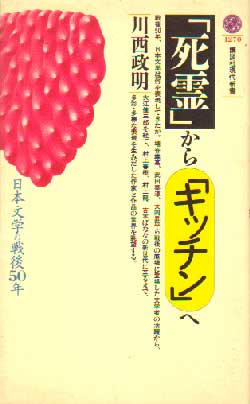
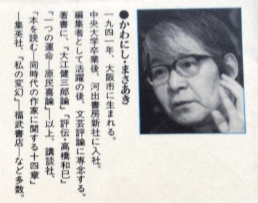
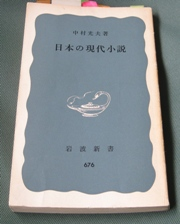
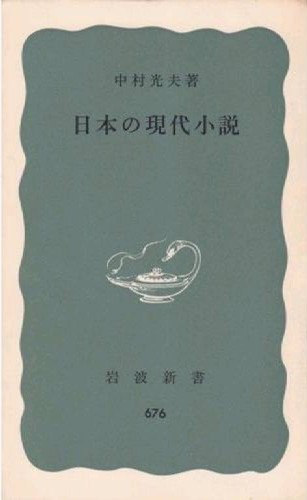
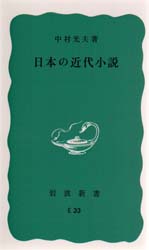
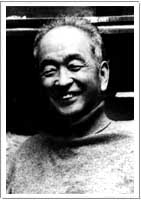 中村光夫 (1911‐1988/享年77)
中村光夫 (1911‐1988/享年77)
.jpg) 野口 恵子 氏 (略歴下記)
野口 恵子 氏 (略歴下記).jpg) 山口 仲美 氏(略歴下記)
山口 仲美 氏(略歴下記)
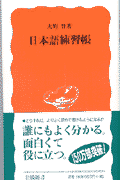
 大野 晋 氏(学習院大学名誉教授/略歴下記)
大野 晋 氏(学習院大学名誉教授/略歴下記)
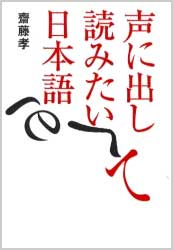
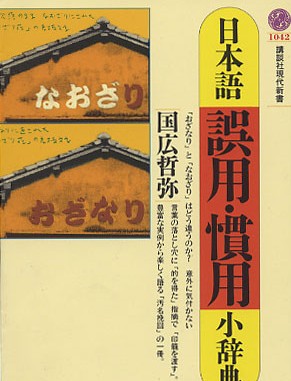

.jpg) 国広 哲弥 氏(東大名誉教授)
国広 哲弥 氏(東大名誉教授)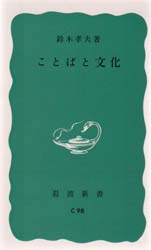
.jpg)

 言葉の意義や定義が、文化的背景によっていかに違ってくるかという観点から、中盤は「動物虐待」にたいする日英の違いなど比較文化論的な、ややエッセイ風の話になっていますが、本書の持ち味は、終盤の、対人関係・家族関係における「人称代名詞」の日本語独特の用法の指摘と、そこからの文化心理学的考察にあるかと思います。
言葉の意義や定義が、文化的背景によっていかに違ってくるかという観点から、中盤は「動物虐待」にたいする日英の違いなど比較文化論的な、ややエッセイ風の話になっていますが、本書の持ち味は、終盤の、対人関係・家族関係における「人称代名詞」の日本語独特の用法の指摘と、そこからの文化心理学的考察にあるかと思います。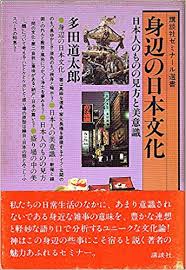
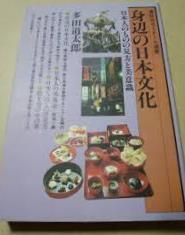
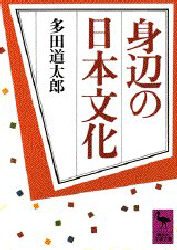
 多田 道太郎 氏
多田 道太郎 氏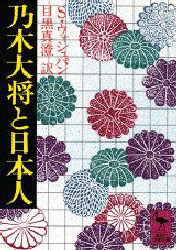
 Nogi, Maresuke (1849-1912)
Nogi, Maresuke (1849-1912)
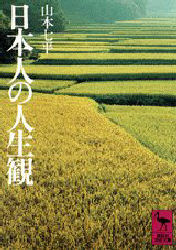
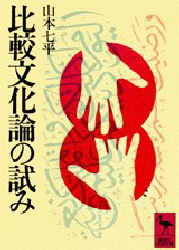
 山本 七平(1921-1991/享年69)
山本 七平(1921-1991/享年69)
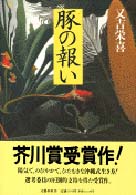
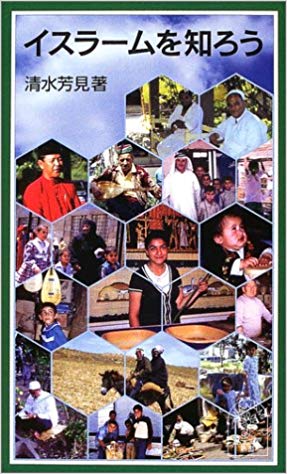
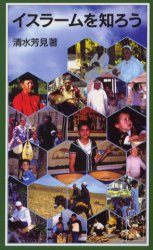
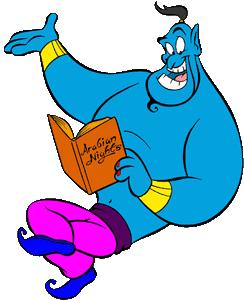 本書によれば、「アラジンと魔法のランプ」は、元々は中国の話だそうですが、語源である「ジン」(一種の妖怪)というのが、イスラームが宗教的版図を拡げていく過程で土着信仰を融合する際に生まれたものだというのは興味深いです。
本書によれば、「アラジンと魔法のランプ」は、元々は中国の話だそうですが、語源である「ジン」(一種の妖怪)というのが、イスラームが宗教的版図を拡げていく過程で土着信仰を融合する際に生まれたものだというのは興味深いです。
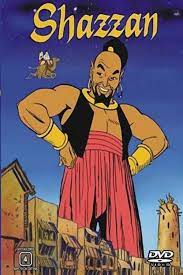 ディズニーアニメの「アラジン」が登場した際に日本のアニメ「ハクション大魔王」(1969-1970)を想起した人も多かったようですが、個人的にはアメリカのアニメ「大魔王シャザーン」(CBS1967年、NET(現テレビ朝日)1968年)を思い出しました。このシャザーンは「大魔王」と称されていますが、これも本来は精霊とも悪霊とも扱われるジンであり、双子の主人公チャックとナンシーの庇護者として召使い的に活躍するものの、本当は双子よりも上の位にいて、ちょうどリモコンを持った者が善であろうと悪であろうとリモコンの指示通りに動く「鉄人28号」と同じように、魔法の指輪を行使する者に服従する「使い魔」であるとのこと、ただしアニメでは、作中で悪人に指輪が奪われた際も、命令に反し「本当はいけないんですが、まあいいでしょう」とあっさり二人を助けたりしていたようです。
ディズニーアニメの「アラジン」が登場した際に日本のアニメ「ハクション大魔王」(1969-1970)を想起した人も多かったようですが、個人的にはアメリカのアニメ「大魔王シャザーン」(CBS1967年、NET(現テレビ朝日)1968年)を思い出しました。このシャザーンは「大魔王」と称されていますが、これも本来は精霊とも悪霊とも扱われるジンであり、双子の主人公チャックとナンシーの庇護者として召使い的に活躍するものの、本当は双子よりも上の位にいて、ちょうどリモコンを持った者が善であろうと悪であろうとリモコンの指示通りに動く「鉄人28号」と同じように、魔法の指輪を行使する者に服従する「使い魔」であるとのこと、ただしアニメでは、作中で悪人に指輪が奪われた際も、命令に反し「本当はいけないんですが、まあいいでしょう」とあっさり二人を助けたりしていたようです。
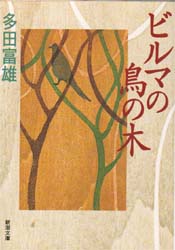

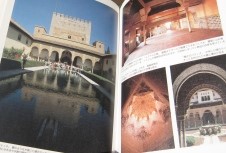

 海外に旅行し、または滞在する際に、少しでもよくその国の歴史や文化を知っておけば、その旅行や滞在の意義もより深いものになるかと思いますが、このシリーズはそうした要望に充分応えるものだと思います。
海外に旅行し、または滞在する際に、少しでもよくその国の歴史や文化を知っておけば、その旅行や滞在の意義もより深いものになるかと思いますが、このシリーズはそうした要望に充分応えるものだと思います。





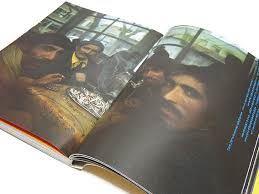
 写真家・藤原新也氏によるトルコ・イスタンブールからインド、チベットを経由して東南アジアに渡り、香港、上海を経て最後に日本・高野山で終る約400日の旅の記録で、「月刊PLAYBOY」の創刊5周年企画として1980年7月号から1981年6月号まで12回にわたって連載されたものがオリジナルですが、藤原氏の一方的な意見が通り実行された企画だそうで、そのせいか写真も文章もいいです。(1982(昭和57)年・第23回「毎日芸術賞」受賞)
写真家・藤原新也氏によるトルコ・イスタンブールからインド、チベットを経由して東南アジアに渡り、香港、上海を経て最後に日本・高野山で終る約400日の旅の記録で、「月刊PLAYBOY」の創刊5周年企画として1980年7月号から1981年6月号まで12回にわたって連載されたものがオリジナルですが、藤原氏の一方的な意見が通り実行された企画だそうで、そのせいか写真も文章もいいです。(1982(昭和57)年・第23回「毎日芸術賞」受賞) 旅の記録というものを通して、今自分が生きている世界や人生とはどういったものであるのか、その普遍性や特殊性(例えば日本という国で生活しているということ)を、また違った視点から考えさせられます。
旅の記録というものを通して、今自分が生きている世界や人生とはどういったものであるのか、その普遍性や特殊性(例えば日本という国で生活しているということ)を、また違った視点から考えさせられます。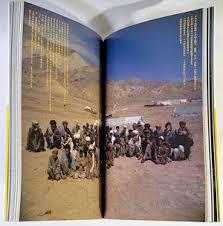 そうした非日常的"な感覚にどっぷり浸ることができるという意味では、東南アジアとかはともかく、トルコやチベットなど今後なかなか行けそうもないような地域の写真が、自分には特に興味深く印象に残りました。
そうした非日常的"な感覚にどっぷり浸ることができるという意味では、東南アジアとかはともかく、トルコやチベットなど今後なかなか行けそうもないような地域の写真が、自分には特に興味深く印象に残りました。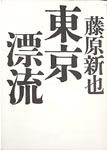
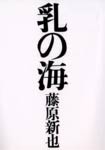




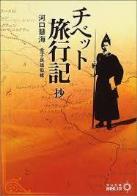
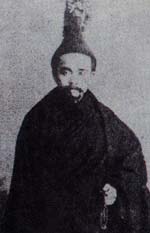 インド仏典の原初の形をとどめるチベット語訳「大蔵経」を求めて、100年前に鎖国状態のチベットに渡った河口慧海(1866-1945)のことを知ったのは、中学校の「国語」の教科書だったと記憶しています。雪のヒマラヤを這っている"不屈の求道者"慧海の挿絵が印象的でした。
インド仏典の原初の形をとどめるチベット語訳「大蔵経」を求めて、100年前に鎖国状態のチベットに渡った河口慧海(1866-1945)のことを知ったのは、中学校の「国語」の教科書だったと記憶しています。雪のヒマラヤを這っている"不屈の求道者"慧海の挿絵が印象的でした。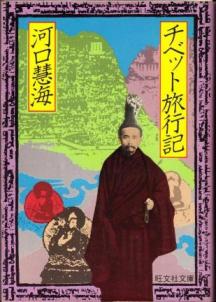


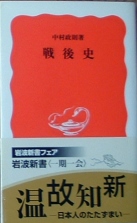
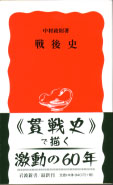
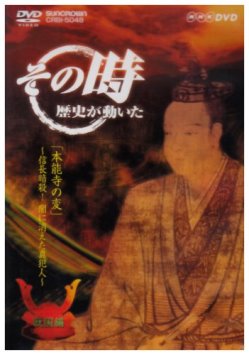


 確かに、智将・光秀が何の後ろ盾も将来展望もなくクーデーターに及んだというのは考えにくいのかも知れません。しかし、都を追われ遠く中国地方に居候の身でいた抜け殻のような将軍が、光秀の後ろ盾になるのかどうか疑問を感じます。著者は本書刊行の前年にNHKの「その時歴史が動いた」('02年7月24日放送分)にゲスト出演し、松平定知アナの前ですでにこの「足利義昭黒幕説」という自説を展開していたのですが、あのときの番組の反響はどうだったのでしょうか。
確かに、智将・光秀が何の後ろ盾も将来展望もなくクーデーターに及んだというのは考えにくいのかも知れません。しかし、都を追われ遠く中国地方に居候の身でいた抜け殻のような将軍が、光秀の後ろ盾になるのかどうか疑問を感じます。著者は本書刊行の前年にNHKの「その時歴史が動いた」('02年7月24日放送分)にゲスト出演し、松平定知アナの前ですでにこの「足利義昭黒幕説」という自説を展開していたのですが、あのときの番組の反響はどうだったのでしょうか。
 ('07年7月刊行の学研の新・歴史群像シリーズ『本能寺の変―時代が一変した戦国最大の事変』でも、この「足利義昭黒幕説」は「朝廷関与説」などと並んで3大有力説の1つとしてとりあげられている。)
('07年7月刊行の学研の新・歴史群像シリーズ『本能寺の変―時代が一変した戦国最大の事変』でも、この「足利義昭黒幕説」は「朝廷関与説」などと並んで3大有力説の1つとしてとりあげられている。)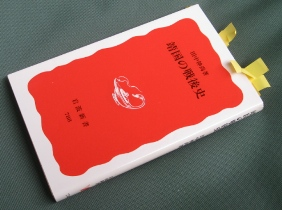
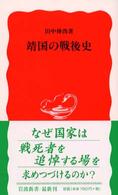
 '05年に入り、『靖国問題』(高橋哲哉/ちくま新書)、『靖国神社』(赤澤史朗/岩波書店)、『国家戦略からみた靖国問題』(岡崎久彦/PHP新書)、『首相が靖国参拝してどこが悪い!!』(新田均/PHP研究所)、『靖国問題の原点』(三土修平/日本評論社)など「靖国」関連本の刊行が相次ぎ、'06年に入っても『戦争を知らない人のための靖国問題』(上坂冬子/文春新書)などの、この問題の関連本の出版は続きました。
'05年に入り、『靖国問題』(高橋哲哉/ちくま新書)、『靖国神社』(赤澤史朗/岩波書店)、『国家戦略からみた靖国問題』(岡崎久彦/PHP新書)、『首相が靖国参拝してどこが悪い!!』(新田均/PHP研究所)、『靖国問題の原点』(三土修平/日本評論社)など「靖国」関連本の刊行が相次ぎ、'06年に入っても『戦争を知らない人のための靖国問題』(上坂冬子/文春新書)などの、この問題の関連本の出版は続きました。
 坂本 多加雄 (1950−2002/享年52)
坂本 多加雄 (1950−2002/享年52) 『国家学のすすめ』('01年/ちくま新書)などの著者があり、52歳で亡くなった坂本多加雄は「新しい歴史教科書をつくる会」のメンバーでもあったし、秦郁彦は「南京事件」に関しては中間派(大虐殺はあったとしているが、犠牲者数は学者の中で最も少ない数字を唱えている)、半藤一利は『ノモンハンの夏』('98年/文藝春秋)などの著書がある作家で、保阪正康は『きけわだつみのこえ』に根拠なき改訂や恣意的な削除があったことを指摘したノンフィクション作家です。
『国家学のすすめ』('01年/ちくま新書)などの著者があり、52歳で亡くなった坂本多加雄は「新しい歴史教科書をつくる会」のメンバーでもあったし、秦郁彦は「南京事件」に関しては中間派(大虐殺はあったとしているが、犠牲者数は学者の中で最も少ない数字を唱えている)、半藤一利は『ノモンハンの夏』('98年/文藝春秋)などの著書がある作家で、保阪正康は『きけわだつみのこえ』に根拠なき改訂や恣意的な削除があったことを指摘したノンフィクション作家です。

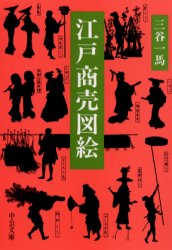
 三谷 一馬(1912-2005/享年93)
三谷 一馬(1912-2005/享年93)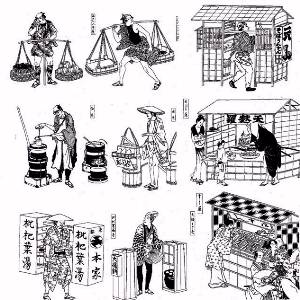
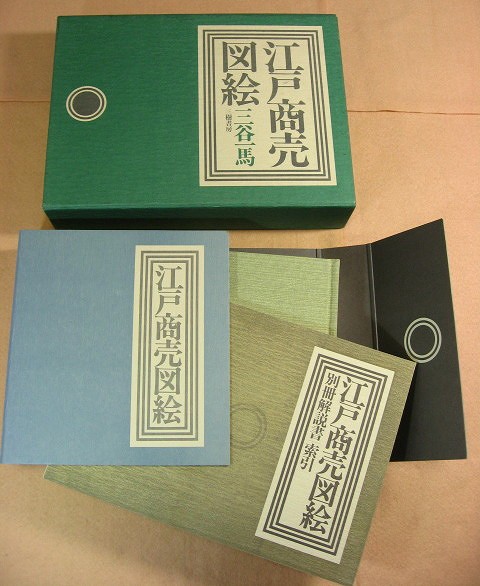 物売りにしても多彩で、「ビードロ売り」とか「水売り」とか風流で、「八百屋」「魚屋」などが江戸と大阪で格好が違ったりするのも面白し、「熊の膏薬売り」が熊の剥製を被っているのは笑えて、「物貰い」というのがちゃんとした職業ジャンルであったことには驚かされます(掛け声や独特のパフォーマンスなども紹介されています)。
物売りにしても多彩で、「ビードロ売り」とか「水売り」とか風流で、「八百屋」「魚屋」などが江戸と大阪で格好が違ったりするのも面白し、「熊の膏薬売り」が熊の剥製を被っているのは笑えて、「物貰い」というのがちゃんとした職業ジャンルであったことには驚かされます(掛け声や独特のパフォーマンスなども紹介されています)。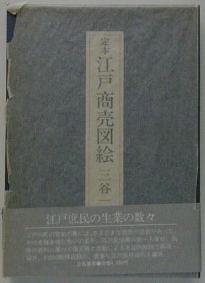 青蛙房から出版された元本の初版は'63年で'75年に三樹書房から新装版が出されましたが、古書店で5万円という稀こう本的な値がついたらしく、やはり小説家とか劇画家には重宝したのかも...。
青蛙房から出版された元本の初版は'63年で'75年に三樹書房から新装版が出されましたが、古書店で5万円という稀こう本的な値がついたらしく、やはり小説家とか劇画家には重宝したのかも...。



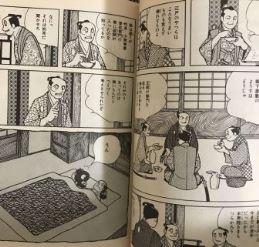
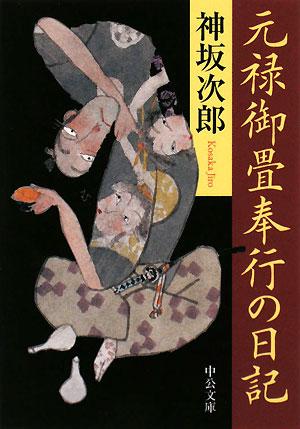
.jpg)

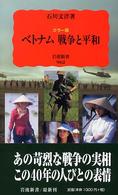
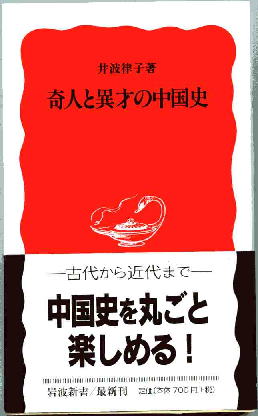
 井波律子氏(国際日本文化研究センター教授)
井波律子氏(国際日本文化研究センター教授) 孔子は55歳からスタートした14年間の諸国遊説によって自らの思想を充実させたとのことで、もし彼がどこかに任官できていれば、逆に一国の補佐役で終わったかもしれず、弟子もそんなに各地にできなかっただろうと(因みに彼の身長は216cmあったとか)。
孔子は55歳からスタートした14年間の諸国遊説によって自らの思想を充実させたとのことで、もし彼がどこかに任官できていれば、逆に一国の補佐役で終わったかもしれず、弟子もそんなに各地にできなかっただろうと(因みに彼の身長は216cmあったとか)。  明代中期に陽明学を起こした王陽明は、軍功を挙げる一方で、朱子学を20年研究し、自己の外にある事物それ自体について研究し事物の理に格(いた)ることで認識が定成するという朱子学のその考えを結局は彼自身は受け入れられず、転じて自らの心の中に知を極めることにして〈知行合一〉の考えに至ったとか―。
明代中期に陽明学を起こした王陽明は、軍功を挙げる一方で、朱子学を20年研究し、自己の外にある事物それ自体について研究し事物の理に格(いた)ることで認識が定成するという朱子学のその考えを結局は彼自身は受け入れられず、転じて自らの心の中に知を極めることにして〈知行合一〉の考えに至ったとか―。
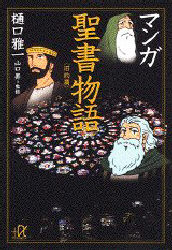


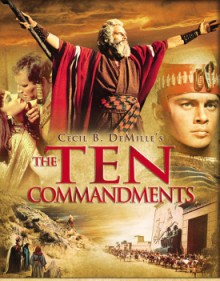
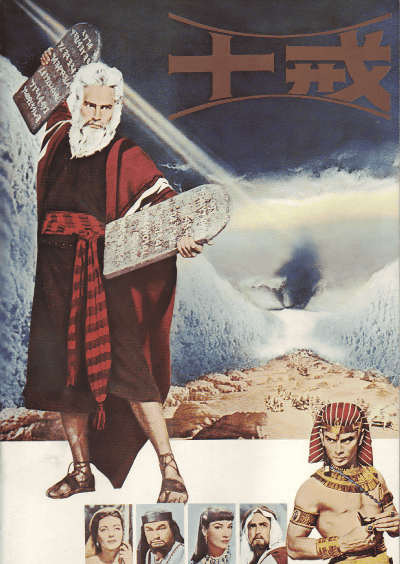 冒頭に挙げた映画「十戒」('57年/米)は、セシル・B・デミル監督が自らが手がけたサイレント大作「十誡」('23年/米)を、10年の製作期間と1350万ドル(当時)を投じて自らリメイクしたもので、製作費の10倍もの興行収入を上げ、パラマウント映画としてのそれまでの最高記録を更新しました(2020年現在、
冒頭に挙げた映画「十戒」('57年/米)は、セシル・B・デミル監督が自らが手がけたサイレント大作「十誡」('23年/米)を、10年の製作期間と1350万ドル(当時)を投じて自らリメイクしたもので、製作費の10倍もの興行収入を上げ、パラマウント映画としてのそれまでの最高記録を更新しました(2020年現在、 紅海が真っ二つに割れるシーンなどのスペクタルもさることながら(滝の落下を逆さまに映している?)、モーセが杖を蛇に変えるシーンなどの細かい特殊撮影も当時にしてはなかなかのもの(CGの無い時代に頑張っている)。
紅海が真っ二つに割れるシーンなどのスペクタルもさることながら(滝の落下を逆さまに映している?)、モーセが杖を蛇に変えるシーンなどの細かい特殊撮影も当時にしてはなかなかのもの(CGの無い時代に頑張っている)。 モーセを演じたチャールトン・ヘストン(1924-2008/享年84)の演技は大味ですが、それがスペクタクル映画にはむしろ合っている感じで、一方、もう1人の主役ラメセスを演じたユル・ブリンナー(1920-1985/享年65)は、父親がスイス系モンゴル人で母親はルーマニア系ジプシーであるという、ファラオ(エジプト王)を演じるに相応しい(?)ユニヴァーサルな血統(「王様と私」('56年/米)ではシャム王を演じている)。更に、癖のあるキャラクターを演じるのが巧みなエドワード・G・ロビンソン(1893-1973/享年79)、「イヴの総て」('50年)のアン・バクスター(1923-1985/享年62)などの名優が脇を固めていました。何れにせよ、もう1度観るにしても、劇場などの大スクリーンで観たい作品です。
モーセを演じたチャールトン・ヘストン(1924-2008/享年84)の演技は大味ですが、それがスペクタクル映画にはむしろ合っている感じで、一方、もう1人の主役ラメセスを演じたユル・ブリンナー(1920-1985/享年65)は、父親がスイス系モンゴル人で母親はルーマニア系ジプシーであるという、ファラオ(エジプト王)を演じるに相応しい(?)ユニヴァーサルな血統(「王様と私」('56年/米)ではシャム王を演じている)。更に、癖のあるキャラクターを演じるのが巧みなエドワード・G・ロビンソン(1893-1973/享年79)、「イヴの総て」('50年)のアン・バクスター(1923-1985/享年62)などの名優が脇を固めていました。何れにせよ、もう1度観るにしても、劇場などの大スクリーンで観たい作品です。
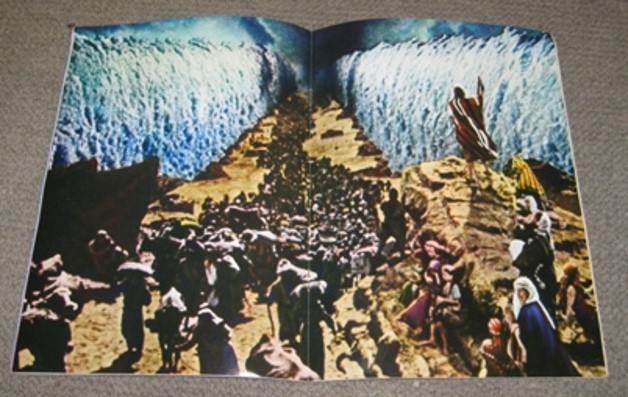
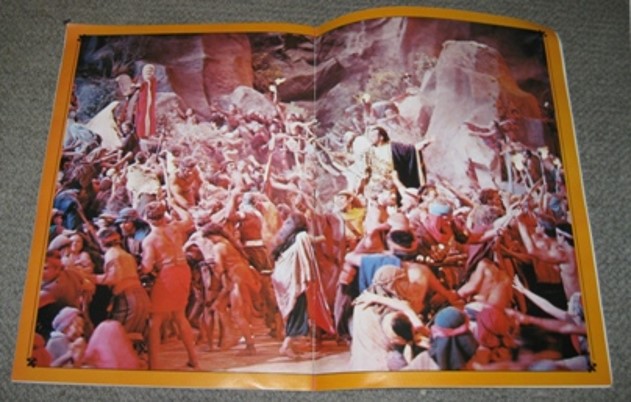


 ミル●脚本:イーニアス・マッケンジー/ジェシー・L・ラスキー・Jr/ジャック・ガリス/フレドリック・M・フランク●撮影:ロイヤル・グリッグス●音楽:エルマー・バーンスタイン●時間:222分●出演:チャールトン・ヘストン/ユル・ブリンナー/アン・バクスター/エドワード・G・ロビンソン/ジョ
ミル●脚本:イーニアス・マッケンジー/ジェシー・L・ラスキー・Jr/ジャック・ガリス/フレドリック・M・フランク●撮影:ロイヤル・グリッグス●音楽:エルマー・バーンスタイン●時間:222分●出演:チャールトン・ヘストン/ユル・ブリンナー/アン・バクスター/エドワード・G・ロビンソン/ジョ


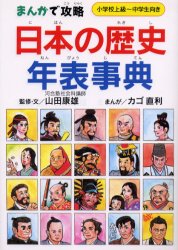
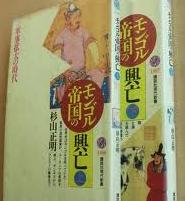
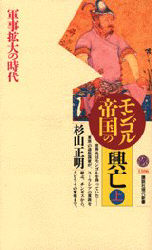

 クビライの時代には帝国は、教科書によく出てくる「元国及び四汁(カン)国」という形になっていたわけですが、本書では一貫して「国」と呼ばず、遊牧民共同体から来た「ウルス」という表現を用いており、また、ウルス間の対立過程において、それらの興亡や版図が極めて流動的であったことを詳細に示しています。
クビライの時代には帝国は、教科書によく出てくる「元国及び四汁(カン)国」という形になっていたわけですが、本書では一貫して「国」と呼ばず、遊牧民共同体から来た「ウルス」という表現を用いており、また、ウルス間の対立過程において、それらの興亡や版図が極めて流動的であったことを詳細に示しています。

 鈴木董(すずき・ただし)氏 (東大東洋文化研究所教授)
鈴木董(すずき・ただし)氏 (東大東洋文化研究所教授)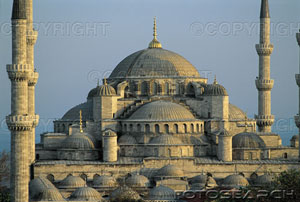 オスマン帝国と言えばスレイマン大帝(スレイマン1世)ですが、1453年にビザンツ(東ローマ)の千年帝都コンスタンティノープルを無傷のまま陥落させたメフメット2世というのも、軍才だけでなく、多言語を操り西洋文化に関心を示した才人で、宗教を超えた能力主義の人材登用と開放経済で世界帝国への道を拓いた人だったのだなあと。
オスマン帝国と言えばスレイマン大帝(スレイマン1世)ですが、1453年にビザンツ(東ローマ)の千年帝都コンスタンティノープルを無傷のまま陥落させたメフメット2世というのも、軍才だけでなく、多言語を操り西洋文化に関心を示した才人で、宗教を超えた能力主義の人材登用と開放経済で世界帝国への道を拓いた人だったのだなあと。

 謝世輝 氏(元東海大学文明史教授)
謝世輝 氏(元東海大学文明史教授)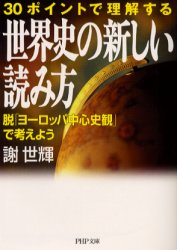
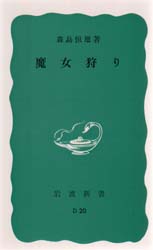
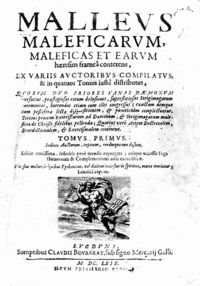



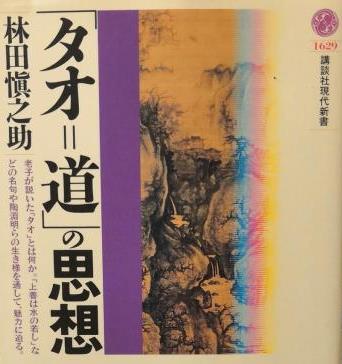 『「タオ=道」の思想』は、中国文学者による「老子」の入門書で、その思想をわかりやすく紹介し、終章には「老子」の思想の影響を受けた、司馬遷や陶淵明ら中国史上の人物の紹介があります。
『「タオ=道」の思想』は、中国文学者による「老子」の入門書で、その思想をわかりやすく紹介し、終章には「老子」の思想の影響を受けた、司馬遷や陶淵明ら中国史上の人物の紹介があります。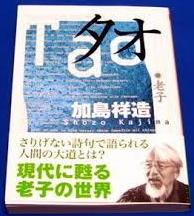 英米文学者・加島祥造氏(1923-2015/享年92)の『タオ―老子』('00年/筑摩書房)における「老子」の名訳(超"意訳"?)ぐらいに突き抜けてしまえばいいのかも知れませんが(「加島本」の"抽象"を自分はまだ理解できるレベルにないのですが)、本書も含め入門書として良いかというと別問題で、入門段階では「中国思想」の専門家の著作も読んでおいた方がいいかも知れません。
英米文学者・加島祥造氏(1923-2015/享年92)の『タオ―老子』('00年/筑摩書房)における「老子」の名訳(超"意訳"?)ぐらいに突き抜けてしまえばいいのかも知れませんが(「加島本」の"抽象"を自分はまだ理解できるレベルにないのですが)、本書も含め入門書として良いかというと別問題で、入門段階では「中国思想」の専門家の著作も読んでおいた方がいいかも知れません。

 河合隼雄氏/福永光司氏
河合隼雄氏/福永光司氏 
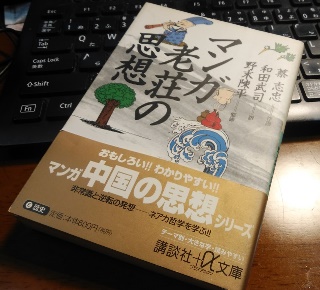

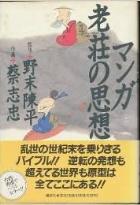
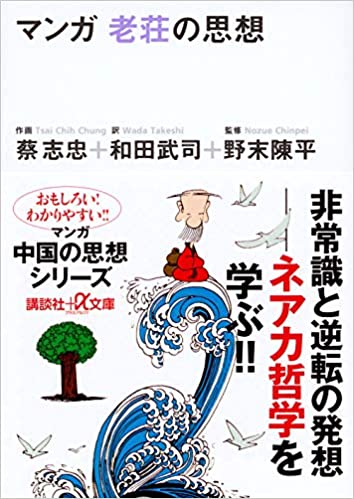 哲学や思想の解説書をマンガ仕立てにしてしまうと、エッセンス部分が抜け落ちて何だか俗っぽくなってしまうということはママあることですが、「講談社+α文庫」のこの台湾の漫画家による「マンガ中国の思想シリーズ」は、古典の捉え方がしっかりしていて、比較的そうしたマイナス面が少なくて済んでいるかも知れません。このシリーズは世界各国で翻訳されているそうです。
哲学や思想の解説書をマンガ仕立てにしてしまうと、エッセンス部分が抜け落ちて何だか俗っぽくなってしまうということはママあることですが、「講談社+α文庫」のこの台湾の漫画家による「マンガ中国の思想シリーズ」は、古典の捉え方がしっかりしていて、比較的そうしたマイナス面が少なくて済んでいるかも知れません。このシリーズは世界各国で翻訳されているそうです。
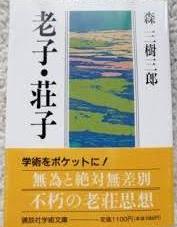
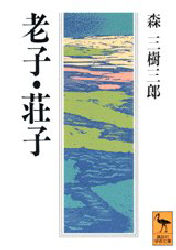
 森 三樹三郎(1909-1986、略歴下記)
森 三樹三郎(1909-1986、略歴下記)
 荘子(前369-前286).
荘子(前369-前286). 道教思想研究の第一人者・福永光司(ふくなが・みつじ 1918‐2001)による本書は、初版出版が'64年で、中公新書の中でもロングセラーにあたります。
道教思想研究の第一人者・福永光司(ふくなが・みつじ 1918‐2001)による本書は、初版出版が'64年で、中公新書の中でもロングセラーにあたります。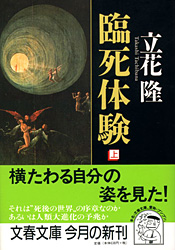
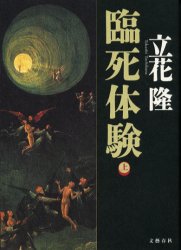



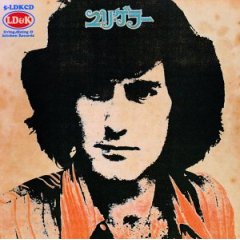
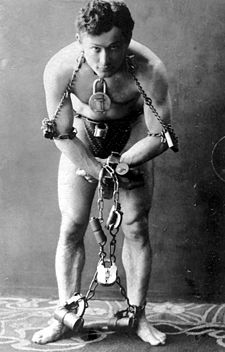 Houdini
Houdini 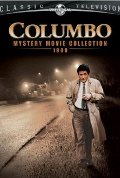

 そう言えば、「刑事コロンボ」が新シリーズで11年ぶりに再開した際の第1弾(通算では第46話)が「汚れた超能力」(「超魔術への招待」)というもので
そう言えば、「刑事コロンボ」が新シリーズで11年ぶりに再開した際の第1弾(通算では第46話)が「汚れた超能力」(「超魔術への招待」)というもので
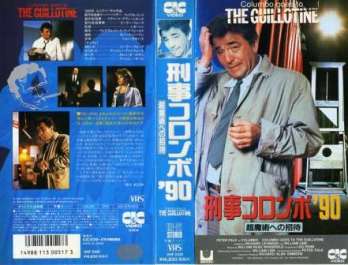 「新・刑事コロンボ(第46話)/汚れた超能力」 (「刑事コロンボ'90/超魔術への招待」)●原題:COLUMBO: COLUMBO GOES TO THE GUILLOTINE●制作年:1989年●制作国:アメリカ●監督:レオ・ペン●製作:スタンリー・カリス/ジョン・A・マルティネリ/リチャード・アラン・シモンズ/ピーター・V・ウェア●脚本:ウィリアム・リード・ウッドフィールド●撮影:ロバート・シーマン●音楽:ジョン・カカヴァス●時間:93分●出演:ピーター・フォーク/アンソニー・アンドリュース/カレン・オースティン/ジェームズ・グリーン/アラン・ファッジ/ダナ・アンダーセン/ロバート・コンスタンツォ/アンソニー・ザーブ●日本放映:1993/05 (NTV)●最初に観た場所:自宅(VHS)(91-09-04)(評価:★★★)
「新・刑事コロンボ(第46話)/汚れた超能力」 (「刑事コロンボ'90/超魔術への招待」)●原題:COLUMBO: COLUMBO GOES TO THE GUILLOTINE●制作年:1989年●制作国:アメリカ●監督:レオ・ペン●製作:スタンリー・カリス/ジョン・A・マルティネリ/リチャード・アラン・シモンズ/ピーター・V・ウェア●脚本:ウィリアム・リード・ウッドフィールド●撮影:ロバート・シーマン●音楽:ジョン・カカヴァス●時間:93分●出演:ピーター・フォーク/アンソニー・アンドリュース/カレン・オースティン/ジェームズ・グリーン/アラン・ファッジ/ダナ・アンダーセン/ロバート・コンスタンツォ/アンソニー・ザーブ●日本放映:1993/05 (NTV)●最初に観た場所:自宅(VHS)(91-09-04)(評価:★★★)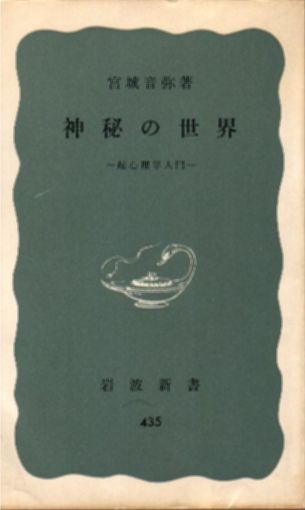

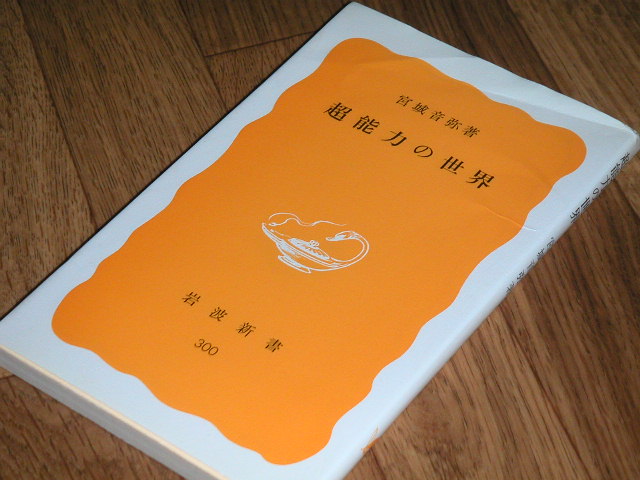
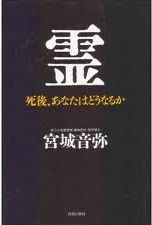
 パイパー夫人 (レオノーラ・パイパー)
パイパー夫人 (レオノーラ・パイパー)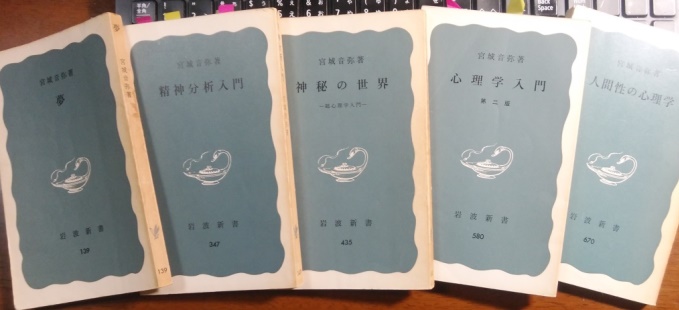
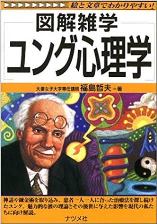

 Carl Gustav Jung (1875‐1961)
Carl Gustav Jung (1875‐1961)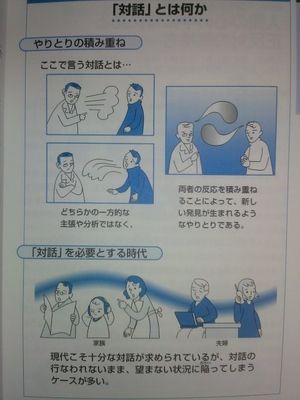 第1章と第3章が「対話のためのユング心理学」「病者との対話」となっていて、「対話」というキーワードを切り口にコンプレックス、元型論(アニマとアニムスなど)、集合的無意識といった概念や、夢分析、箱庭療法などの心理療法についての解説がされています。
第1章と第3章が「対話のためのユング心理学」「病者との対話」となっていて、「対話」というキーワードを切り口にコンプレックス、元型論(アニマとアニムスなど)、集合的無意識といった概念や、夢分析、箱庭療法などの心理療法についての解説がされています。

.jpg)


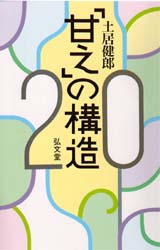




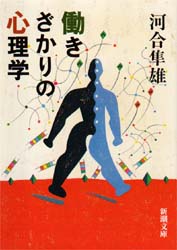
 働きざかりのミドルが家庭や社会の中で遭遇する様々な課題を心理学的に考察し、わかりやすく解説した本で、中心となるテーマは「中年の危機」。しかし、幅広い世代に対しての示唆に富む本だと思います。40歳から50歳の間に"思秋期"が来るという本書の考えのベースになっているのは、ユングの「人生の正午」という概念です。日常生活の人と人の繋がりにおける諸事象から、より根源的な心理学のテーマを抽出する著者の眼力は、この頃からすごかったのだなあと、改めて感じました(単行本は1981年刊)。 者論における、「場の倫理」に対する「個の倫理」という切り口などが、個人的にはとりわけ秀逸だと思えました。
働きざかりのミドルが家庭や社会の中で遭遇する様々な課題を心理学的に考察し、わかりやすく解説した本で、中心となるテーマは「中年の危機」。しかし、幅広い世代に対しての示唆に富む本だと思います。40歳から50歳の間に"思秋期"が来るという本書の考えのベースになっているのは、ユングの「人生の正午」という概念です。日常生活の人と人の繋がりにおける諸事象から、より根源的な心理学のテーマを抽出する著者の眼力は、この頃からすごかったのだなあと、改めて感じました(単行本は1981年刊)。 者論における、「場の倫理」に対する「個の倫理」という切り口などが、個人的にはとりわけ秀逸だと思えました。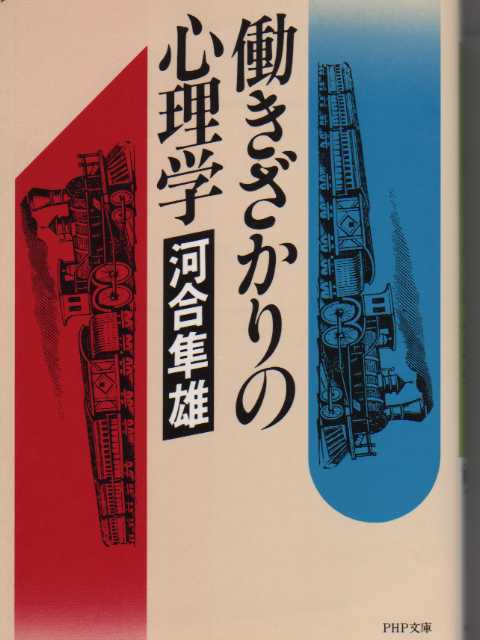 また、主に年長者が重視するという「場の倫理」にも、微妙な側面があることを指摘しています。「場の倫理」というのは、日本は欧米に比べ企業などで特に強く働くのでしょうが(企業のトップなどは、それなりに年齢のいった人が多いということもある)、「場に対する忠誠心は、その場においては満場一致の絶対性を要求しながら、場が変わったときには態度の変更のあり得ることを認めるというのは不思議だ」と著者は述べています。確かに日本の場合、「決議は百パーセントは人を拘束せず」(山本七平)というのは、企業でよくあることではないかという気がしました。役員会での決定事項が簡単に覆ったりするのは、会議の後でそれぞれのメンバーはまた別の「場」へいくと、そちらの「場」の平衡を保つことがより重要事項となる―そこで役員会ともう1つの「場」との調整が再度図られるということなのでしょうか(自分の見た例だと、連日にわたり"最終決定"役員会を開いていた会社があった)。
また、主に年長者が重視するという「場の倫理」にも、微妙な側面があることを指摘しています。「場の倫理」というのは、日本は欧米に比べ企業などで特に強く働くのでしょうが(企業のトップなどは、それなりに年齢のいった人が多いということもある)、「場に対する忠誠心は、その場においては満場一致の絶対性を要求しながら、場が変わったときには態度の変更のあり得ることを認めるというのは不思議だ」と著者は述べています。確かに日本の場合、「決議は百パーセントは人を拘束せず」(山本七平)というのは、企業でよくあることではないかという気がしました。役員会での決定事項が簡単に覆ったりするのは、会議の後でそれぞれのメンバーはまた別の「場」へいくと、そちらの「場」の平衡を保つことがより重要事項となる―そこで役員会ともう1つの「場」との調整が再度図られるということなのでしょうか(自分の見た例だと、連日にわたり"最終決定"役員会を開いていた会社があった)。
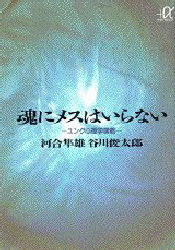
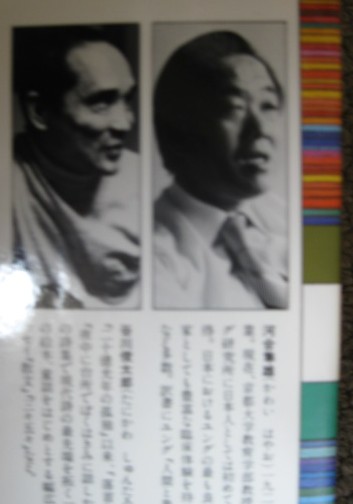 本書は、詩人・谷川俊太郎が河合隼雄にユング心理学について話を聞くというスタイルになっています。河合氏によるユング研究所に学んだ時の話から始まり、夢分析などに見るユング心理学の考え方、箱庭療法の実際、分析家としての姿勢などが語られ、最後はイメージとシンボル、自我と自己の違いの話から、谷川氏との間での創作や世界観の話にまで話題が及び、内容的にも深いと思いました。
本書は、詩人・谷川俊太郎が河合隼雄にユング心理学について話を聞くというスタイルになっています。河合氏によるユング研究所に学んだ時の話から始まり、夢分析などに見るユング心理学の考え方、箱庭療法の実際、分析家としての姿勢などが語られ、最後はイメージとシンボル、自我と自己の違いの話から、谷川氏との間での創作や世界観の話にまで話題が及び、内容的にも深いと思いました。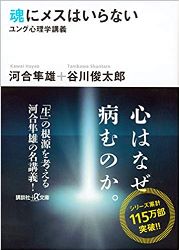 本書は「朝日レクチャーブックス」(朝日出版社)の1冊で、'79年に刊行されたものです('93年に「講談社+α文庫」の創刊ラインナップの1冊として文庫化)。この「朝日レクチャーブックス」のシリーズは全30冊あり、廣松渉←五木寛之、今西錦司←吉本隆明、岸田秀←伊丹十三など、学者に作家が話を聞くというパターンがほとんどですが、いずれも内容が濃いものばかりです(その割に文庫化されているものが少ないのが残念)。その中でも本書は、聞き手(谷川)のレベルが高く、語り手と聞き手が対等な立場となっている稀なケースだと思われます。
本書は「朝日レクチャーブックス」(朝日出版社)の1冊で、'79年に刊行されたものです('93年に「講談社+α文庫」の創刊ラインナップの1冊として文庫化)。この「朝日レクチャーブックス」のシリーズは全30冊あり、廣松渉←五木寛之、今西錦司←吉本隆明、岸田秀←伊丹十三など、学者に作家が話を聞くというパターンがほとんどですが、いずれも内容が濃いものばかりです(その割に文庫化されているものが少ないのが残念)。その中でも本書は、聞き手(谷川)のレベルが高く、語り手と聞き手が対等な立場となっている稀なケースだと思われます。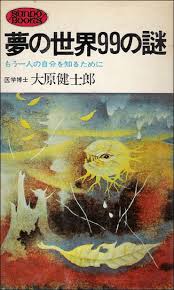
 大原 健士郎 氏 (略歴下記)
大原 健士郎 氏 (略歴下記)
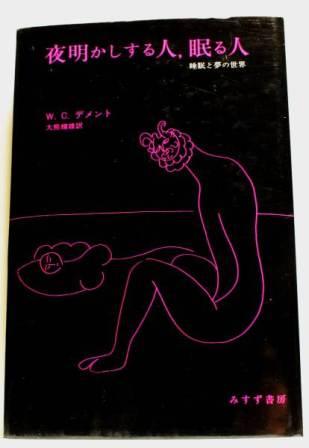

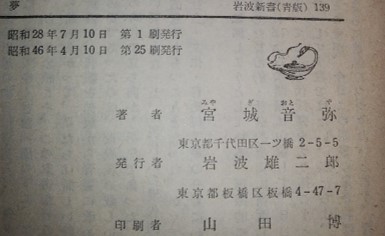
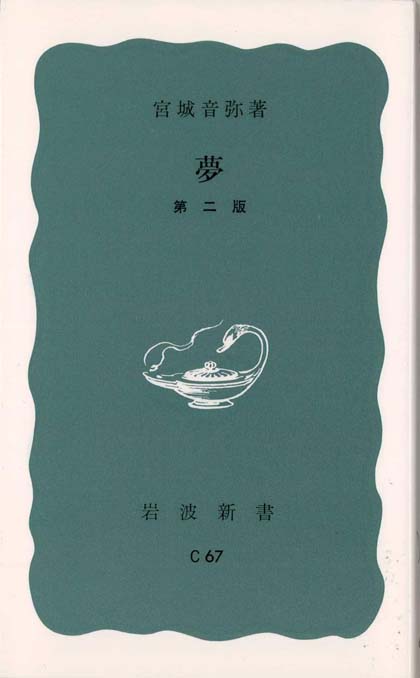
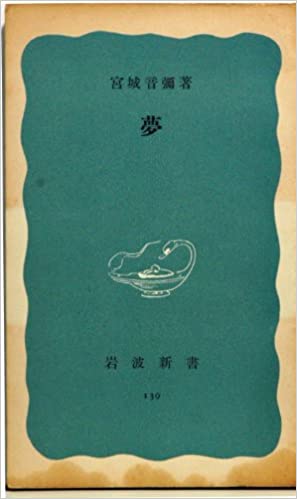

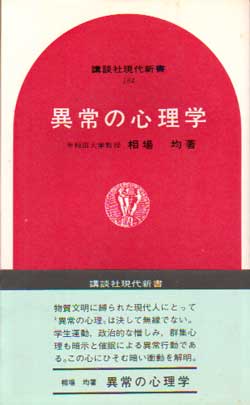

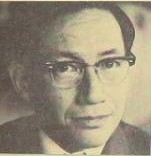 本書では、魔女狩りから説き起こし現代の精神医学に至るまで異常心理の歴史とでも言うべきもの述べたうえで、群集心理、催眠現象、記憶喪失、知覚のゆがみ、異常性格などさまざま事象・症例をあげて考察し、人の心の中に潜む異常性を浮き彫りにしています。
本書では、魔女狩りから説き起こし現代の精神医学に至るまで異常心理の歴史とでも言うべきもの述べたうえで、群集心理、催眠現象、記憶喪失、知覚のゆがみ、異常性格などさまざま事象・症例をあげて考察し、人の心の中に潜む異常性を浮き彫りにしています。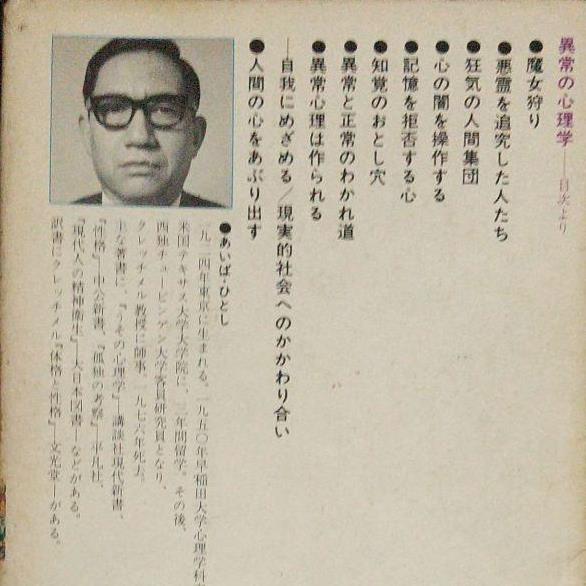

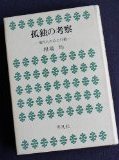

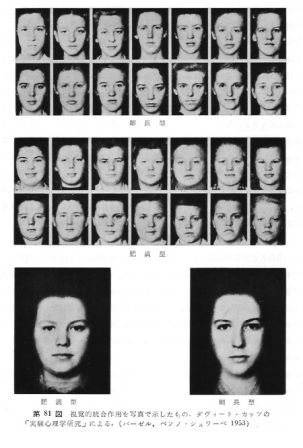 著者の相場均は、『孤独の考察』('73年/平凡社)などの名著がある心理学者で、エルンスト・クレッチメル(クレッチマー)の『体格と性格』('78年/文光堂)の訳者でもあります。
著者の相場均は、『孤独の考察』('73年/平凡社)などの名著がある心理学者で、エルンスト・クレッチメル(クレッチマー)の『体格と性格』('78年/文光堂)の訳者でもあります。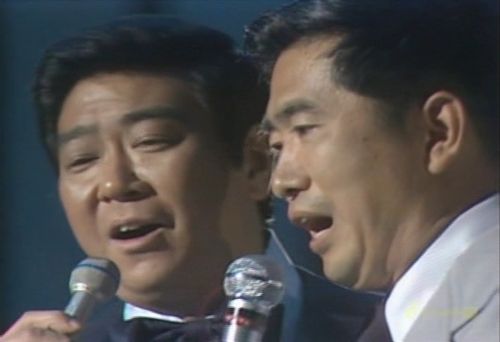 学生の前で、石原慎太郎・裕次郎兄弟の性格の違いを分析してみせたりもしていました。慎太郎氏がやたら瞬き(正確には"しばたき")することが多いのは、作家特有の神経症的気質からきていると...。素質的に豪放磊落な弟に比べると、実は兄貴の方はずっと神経質で防衛機制が強く働くタイプであると言っていましたが、当たっている?
学生の前で、石原慎太郎・裕次郎兄弟の性格の違いを分析してみせたりもしていました。慎太郎氏がやたら瞬き(正確には"しばたき")することが多いのは、作家特有の神経症的気質からきていると...。素質的に豪放磊落な弟に比べると、実は兄貴の方はずっと神経質で防衛機制が強く働くタイプであると言っていましたが、当たっている?
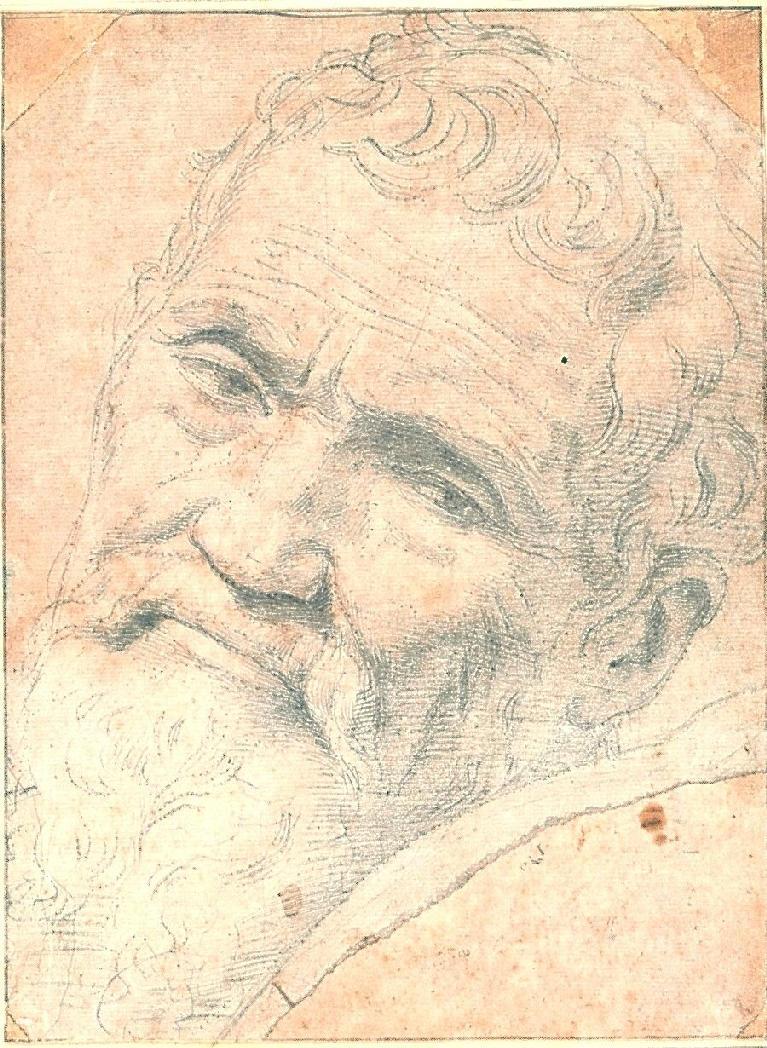
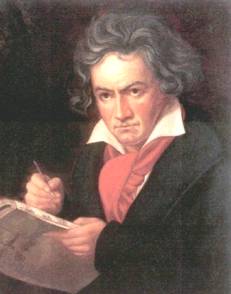

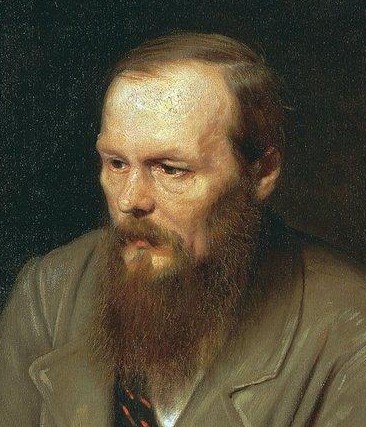
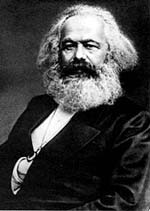
 興味深いのは、ラファエロのように、推定知能指数が110程度の「天才」もいることで、「天才」の1割は"正常"(?)だったという研究もあり、彼もその1人ということになるようです。ラファエロは14歳ですでに画家として有名でしたが、画風や仕事ぶりは職人(または親方)タイプだったそうです。「天才」グループに紛れ込んだ"偉大なる職人"とでも言うべきでしょうか。
興味深いのは、ラファエロのように、推定知能指数が110程度の「天才」もいることで、「天才」の1割は"正常"(?)だったという研究もあり、彼もその1人ということになるようです。ラファエロは14歳ですでに画家として有名でしたが、画風や仕事ぶりは職人(または親方)タイプだったそうです。「天才」グループに紛れ込んだ"偉大なる職人"とでも言うべきでしょうか。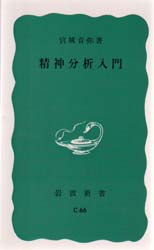
 宮城 音弥 (1908-2005/享年97)
宮城 音弥 (1908-2005/享年97) '05年に97歳で逝去した心理学者・宮城音弥氏の著作。初版が1959年という古い本ですが、精神分析の入門書としてはオーソドックスな内容だと思います。
'05年に97歳で逝去した心理学者・宮城音弥氏の著作。初版が1959年という古い本ですが、精神分析の入門書としてはオーソドックスな内容だと思います。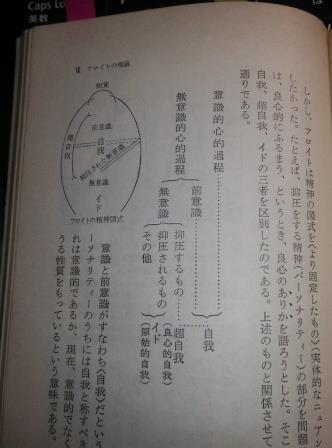
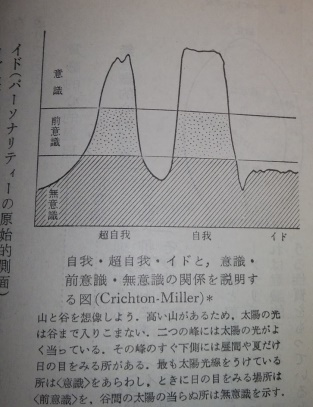
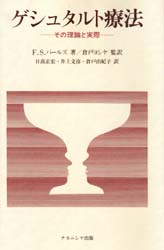
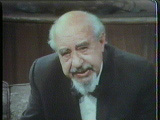 フレデリック・パールズ (1893‐1970)
フレデリック・パールズ (1893‐1970)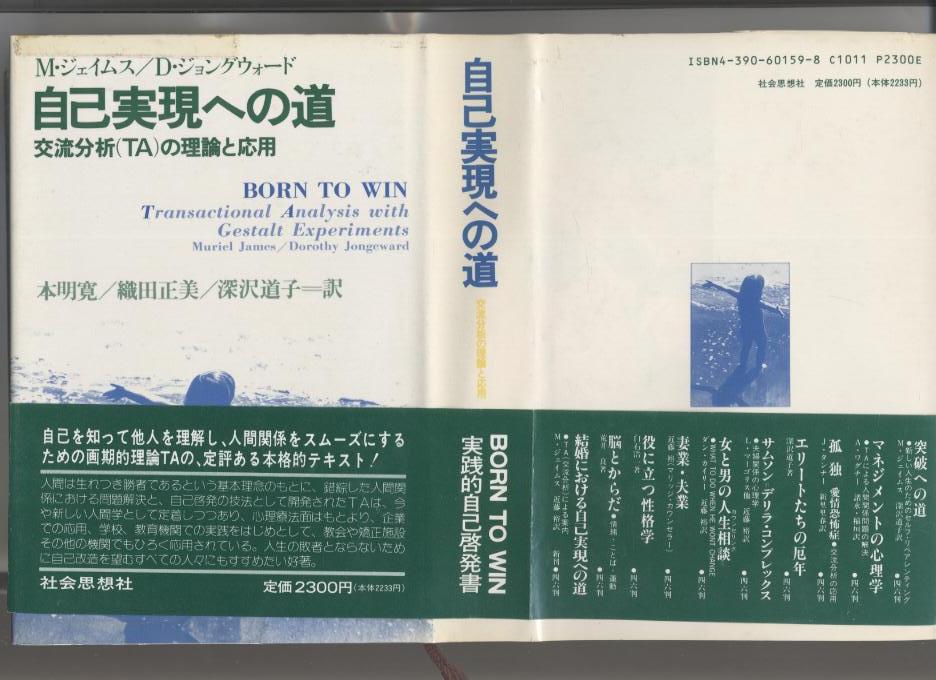

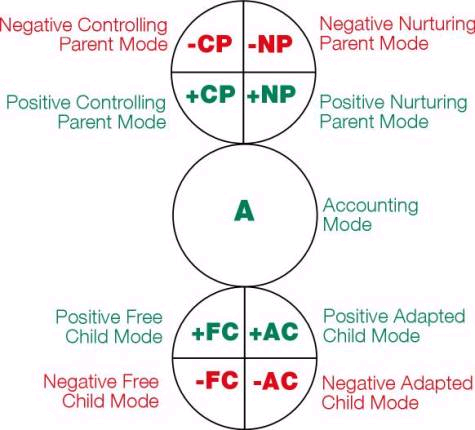
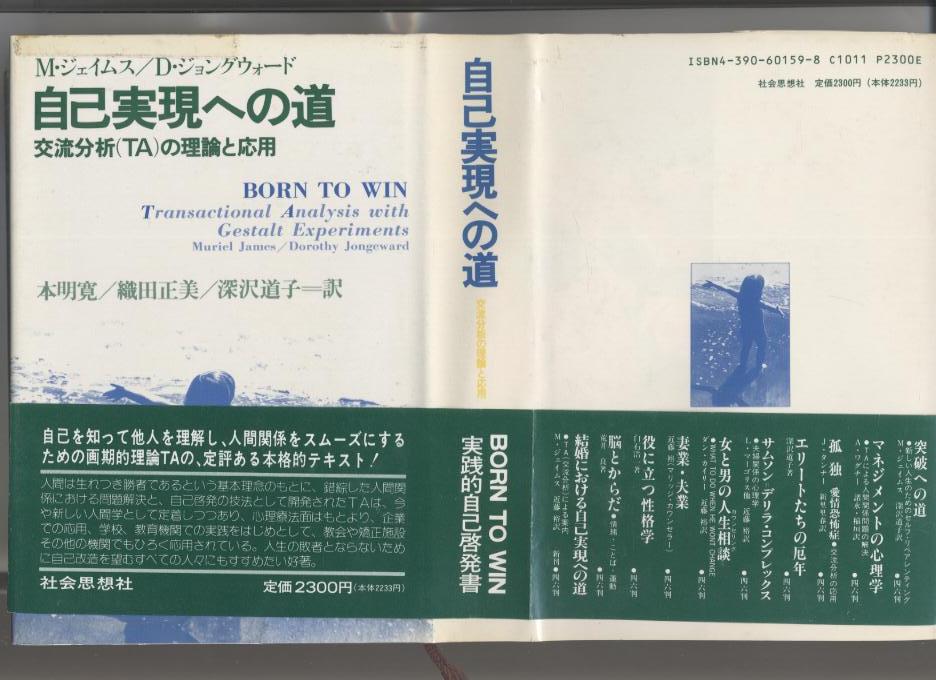
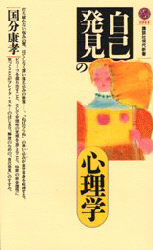

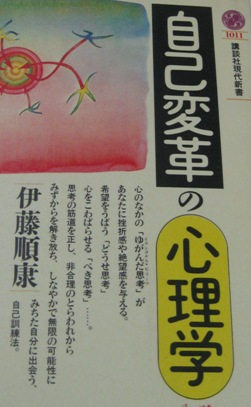

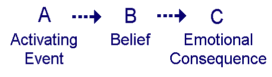 論理療法でいうイラショナル・ビリーフやABC理論(ABCDE理論)をわかりやすく説くために著者の経験やマンガを引いたりしていますが、内容的にはオーソドックスで、最後に「論理療法のまとめ」と「実践のためのアドバイス」を配しており、入門書として丁寧な構成になっています。
論理療法でいうイラショナル・ビリーフやABC理論(ABCDE理論)をわかりやすく説くために著者の経験やマンガを引いたりしていますが、内容的にはオーソドックスで、最後に「論理療法のまとめ」と「実践のためのアドバイス」を配しており、入門書として丁寧な構成になっています。

 アルバート・エリス(Albert Ellis)
アルバート・エリス(Albert Ellis)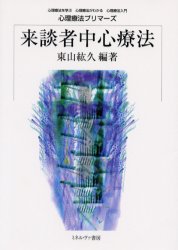
 Carl Rogers
Carl Rogers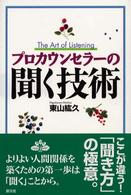
 東山 紘久 氏(経歴下記)
東山 紘久 氏(経歴下記)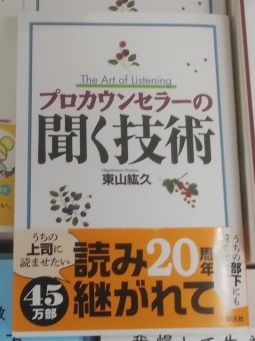
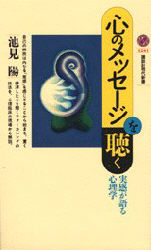

 池見 陽(あきら) 氏 (略歴下記)
池見 陽(あきら) 氏 (略歴下記) 本書自体は、E・ジェンドリンにより「心の実感」に触れるための方法として開発された「フォーカシング(focusing)」の技法について解説した入門書ですが、「フォーカシング」は、ジェンドリン自身が彼の師にあたるC・ロジャーズとのカウンセリングの共同研究を通して、その成功・不成功例の比較からから開発した技法であるため、本書ではそのベースとなった「ロジャーズ理論」(来談者中心療法)の解説もなされています(著者自身もジェンドリンの弟子であると同時に、ロジャーズの孫弟子にあたる)。
本書自体は、E・ジェンドリンにより「心の実感」に触れるための方法として開発された「フォーカシング(focusing)」の技法について解説した入門書ですが、「フォーカシング」は、ジェンドリン自身が彼の師にあたるC・ロジャーズとのカウンセリングの共同研究を通して、その成功・不成功例の比較からから開発した技法であるため、本書ではそのベースとなった「ロジャーズ理論」(来談者中心療法)の解説もなされています(著者自身もジェンドリンの弟子であると同時に、ロジャーズの孫弟子にあたる)。
 カウンセリングの入門書ですが、カウセリングの働きが、カウンセラー自身にとっての深い意味の発見であることを示唆する本となっています。
カウンセリングの入門書ですが、カウセリングの働きが、カウンセラー自身にとっての深い意味の発見であることを示唆する本となっています。
 矢幡洋 氏 (臨床心理士)
矢幡洋 氏 (臨床心理士) 本書ではまず、「心の病気」を、
本書ではまず、「心の病気」を、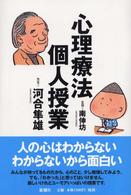


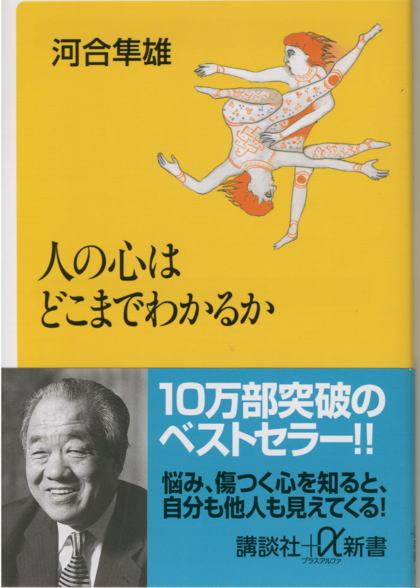
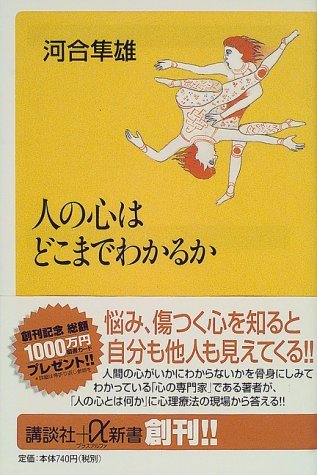
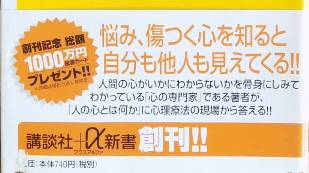




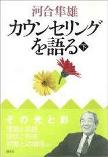


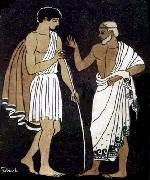 「メンタリング」について書かれた本の中には、リーダーシップ論やコーチングの技法論とまったく同じになってしまっているものも散見し、「高成果型人材を育成する」といった、短期間でパフォーマンスの向上を求めることが直接目的であるかのような書かれ方をしているものもあります。
「メンタリング」について書かれた本の中には、リーダーシップ論やコーチングの技法論とまったく同じになってしまっているものも散見し、「高成果型人材を育成する」といった、短期間でパフォーマンスの向上を求めることが直接目的であるかのような書かれ方をしているものもあります。

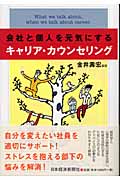
 金井壽宏 氏
金井壽宏 氏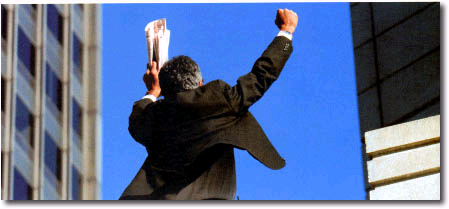 個人は当然、自らのキャリアや価値観を重視するわけで、そうしたなかで企業は、企業のアイデンティと個人のアイデンティの調和をいかに図るかが大きな課題になってくるに違いなく、そのことを意識した場合において(まだそういう意識を持てないでいる企業経営者も多いけれど)、キャリアカウンセリングというのは会社生活と個人生活を調和した状態に近づけるひとつの手立てになると思われます。
個人は当然、自らのキャリアや価値観を重視するわけで、そうしたなかで企業は、企業のアイデンティと個人のアイデンティの調和をいかに図るかが大きな課題になってくるに違いなく、そのことを意識した場合において(まだそういう意識を持てないでいる企業経営者も多いけれど)、キャリアカウンセリングというのは会社生活と個人生活を調和した状態に近づけるひとつの手立てになると思われます。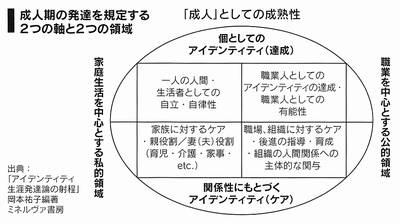 岡本祐子氏の「アイデンティの螺旋式モデル」は厚労省のキャリア・コンサルティング技法報告書にも採用されたものであるし、「成人期の発達を規定する2軸・2領域」論は是非多くの人に触れて欲しいものです。
岡本祐子氏の「アイデンティの螺旋式モデル」は厚労省のキャリア・コンサルティング技法報告書にも採用されたものであるし、「成人期の発達を規定する2軸・2領域」論は是非多くの人に触れて欲しいものです。
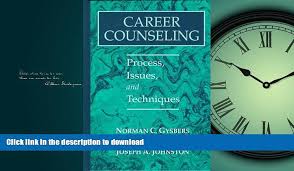
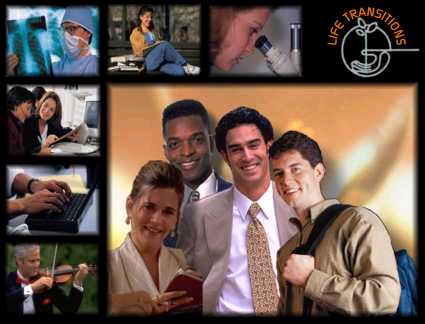 原題は"Career Counseling: Process, Issues, and Techniques"(1997)。キャリアカウンセリングを"ライフキャリア"という観点(個人の役割・環境・出来事など、人生における重要な要素すべてを考慮して最適な選択を行おうとする考え方)から理論的に整理し、さらにオープニングから、情報収集、理解/仮定、行動化、目標/行動計画、評価/終了までの6段階に構造化して、各段階の実践的アプローチを具体的に解説しています。
原題は"Career Counseling: Process, Issues, and Techniques"(1997)。キャリアカウンセリングを"ライフキャリア"という観点(個人の役割・環境・出来事など、人生における重要な要素すべてを考慮して最適な選択を行おうとする考え方)から理論的に整理し、さらにオープニングから、情報収集、理解/仮定、行動化、目標/行動計画、評価/終了までの6段階に構造化して、各段階の実践的アプローチを具体的に解説しています。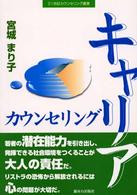
 宮城まり子氏(略歴下記)
宮城まり子氏(略歴下記) キャリアカウンセリングの入門書に触れ、もう少し突っ込んだ標準テキストを求める人には格好の本だと思います。歴史や背景理論から援助の具体的技法まで広く触れていますが、随所に明快な考察が見られます。
キャリアカウンセリングの入門書に触れ、もう少し突っ込んだ標準テキストを求める人には格好の本だと思います。歴史や背景理論から援助の具体的技法まで広く触れていますが、随所に明快な考察が見られます。


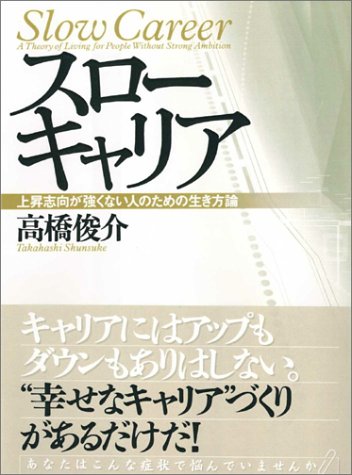

 著者の提唱する"スローキャリア"というのは、"上昇志向でない動機によってドライブされる"キャリアのことを指すらしいのですが、この定義がわかりにくい。
著者の提唱する"スローキャリア"というのは、"上昇志向でない動機によってドライブされる"キャリアのことを指すらしいのですが、この定義がわかりにくい。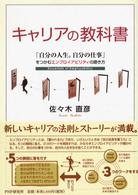
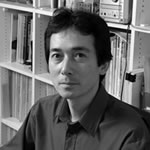 佐々木直彦 氏(略歴下記)
佐々木直彦 氏(略歴下記) 本論では、エンプロイアビリティ向上のために実践し(フィールドワーク)考え(コンセプトワーク)人とつながる(ネットワーク)ことの重要性を、図解やケーススタディと併せ、またキャリア行動に関する理論を引きながら、わかりやすく具体的に説いていています。
本論では、エンプロイアビリティ向上のために実践し(フィールドワーク)考え(コンセプトワーク)人とつながる(ネットワーク)ことの重要性を、図解やケーススタディと併せ、またキャリア行動に関する理論を引きながら、わかりやすく具体的に説いていています。
 サブタイトルからは窺えますが、"会社側は"何をすべきなのかという本で、そのあたりが「キャリア論」というタイトルからは少しわかりにくく、それでも個人として買っても役に立ったという人も少なからずいるらしいのは、本書が〈自律的キャリア(CSR=Career Self Reliance)〉を形成・促進することを説いているためだろうと思われます。
サブタイトルからは窺えますが、"会社側は"何をすべきなのかという本で、そのあたりが「キャリア論」というタイトルからは少しわかりにくく、それでも個人として買っても役に立ったという人も少なからずいるらしいのは、本書が〈自律的キャリア(CSR=Career Self Reliance)〉を形成・促進することを説いているためだろうと思われます。 ただし、そのことを説明するためにクラスター分析の手法を使って多くのページを割いていますが、学術論文か、その手前のゼミ論文のような生硬さで、一般読者はもちろん企業の担当者にとっても、読んでいて何故こんなゼミの講義みたいな話に付き合わさればならないのかという気分になってきます。
ただし、そのことを説明するためにクラスター分析の手法を使って多くのページを割いていますが、学術論文か、その手前のゼミ論文のような生硬さで、一般読者はもちろん企業の担当者にとっても、読んでいて何故こんなゼミの講義みたいな話に付き合わさればならないのかという気分になってきます。
 金井教授の「一皮むける」という表現は、その仕事上の経験を通して、ひと回り大きな人間になり、自分らしいキャリア形成につながった経験のことを指し、ニコルソンのトランジッション論などのキャリア理論がその裏づけ理論としてあるようです。直接的には南カリフォルニア大の経営・組織学教授モーガン・マッコールが著書『ハイ・フライヤー』('02年/プレジデント社)の中で述べている"クォンタム・リープ(量子的跳躍)"という概念と同じようですが、"クォンタム・リープ"といった言葉よりは"一皮むける"の方がずっとわかりやすいかと思います(一方で、"ターニング・ポイント"という言葉でもいいのではないかとも思うが、ここでは"キャリア"ということを敢えて意識したうえでの用語選びなのだろう)。その言葉のわかりやすさと、金井氏の思い入れが、本書を単なる報告書レベルを超えたまとまりのあるものにしています。
金井教授の「一皮むける」という表現は、その仕事上の経験を通して、ひと回り大きな人間になり、自分らしいキャリア形成につながった経験のことを指し、ニコルソンのトランジッション論などのキャリア理論がその裏づけ理論としてあるようです。直接的には南カリフォルニア大の経営・組織学教授モーガン・マッコールが著書『ハイ・フライヤー』('02年/プレジデント社)の中で述べている"クォンタム・リープ(量子的跳躍)"という概念と同じようですが、"クォンタム・リープ"といった言葉よりは"一皮むける"の方がずっとわかりやすいかと思います(一方で、"ターニング・ポイント"という言葉でもいいのではないかとも思うが、ここでは"キャリア"ということを敢えて意識したうえでの用語選びなのだろう)。その言葉のわかりやすさと、金井氏の思い入れが、本書を単なる報告書レベルを超えたまとまりのあるものにしています。
 小杉俊哉 氏 (略歴下記)
小杉俊哉 氏 (略歴下記)
 キャリア理論を学ぶうえでも、シャインの何が得意か、何がやりたいか、何をやっているときに意味を感じ社会に役立っていると実感できるかという〈3つの問い〉や、ブリッジスの、キャリアにおける危機の一つとしての転機は、一方で躍進・前進に繋がる可能性もあるという〈トランジッション論〉、クランボルツの、キャリアの節目さえデザインしていれば、それ以外はドリフトしていいとして、偶然性や不確実性の効用を説いた〈キャリア・ドリフト〉といったキャリア行動や意思決定に関する理論や概念が、最近のものまでバランス良くカバーされており、役に立つのではないでしょうか。
キャリア理論を学ぶうえでも、シャインの何が得意か、何がやりたいか、何をやっているときに意味を感じ社会に役立っていると実感できるかという〈3つの問い〉や、ブリッジスの、キャリアにおける危機の一つとしての転機は、一方で躍進・前進に繋がる可能性もあるという〈トランジッション論〉、クランボルツの、キャリアの節目さえデザインしていれば、それ以外はドリフトしていいとして、偶然性や不確実性の効用を説いた〈キャリア・ドリフト〉といったキャリア行動や意思決定に関する理論や概念が、最近のものまでバランス良くカバーされており、役に立つのではないでしょうか。 またそれらの解説が大変わかりやすいうえに、著者の「この理論を自分のキャリアを決める際に生かしてほしい」という熱意が伝わってきます。
またそれらの解説が大変わかりやすいうえに、著者の「この理論を自分のキャリアを決める際に生かしてほしい」という熱意が伝わってきます。
 自分の思い描いていたキャリアの将来像が予期しない環境変化により崩壊してしまうことを「キャリアショック」とし、そうしたことが起こりうる現代において自分のキャリアをどう捉え、どう開発していくかを説いています。
自分の思い描いていたキャリアの将来像が予期しない環境変化により崩壊してしまうことを「キャリアショック」とし、そうしたことが起こりうる現代において自分のキャリアをどう捉え、どう開発していくかを説いています。 高橋 俊介 氏 (略歴下記)
高橋 俊介 氏 (略歴下記)


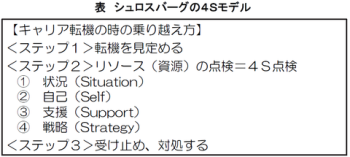 全米キャリア開発協会(NCDA)の会長などを務めた著者による本書は、人が人生の転機やキャリアの節目にぶつかったとき、それをどう乗り越え、どうすれば豊かな人生が送れるかということをテーマとしています。
全米キャリア開発協会(NCDA)の会長などを務めた著者による本書は、人が人生の転機やキャリアの節目にぶつかったとき、それをどう乗り越え、どうすれば豊かな人生が送れるかということをテーマとしています。
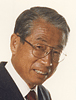 岡本義幸 氏(略歴下記)
岡本義幸 氏(略歴下記)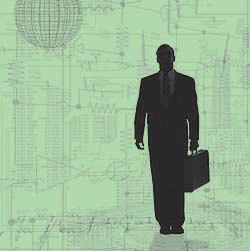 本書は'87(昭和62)年の出版であり、人材会社(人材斡旋会社)の社長が書いた「転職」のためのガイドブックです。
本書は'87(昭和62)年の出版であり、人材会社(人材斡旋会社)の社長が書いた「転職」のためのガイドブックです。




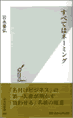


 中川佳子 氏 (略歴下記)
中川佳子 氏 (略歴下記)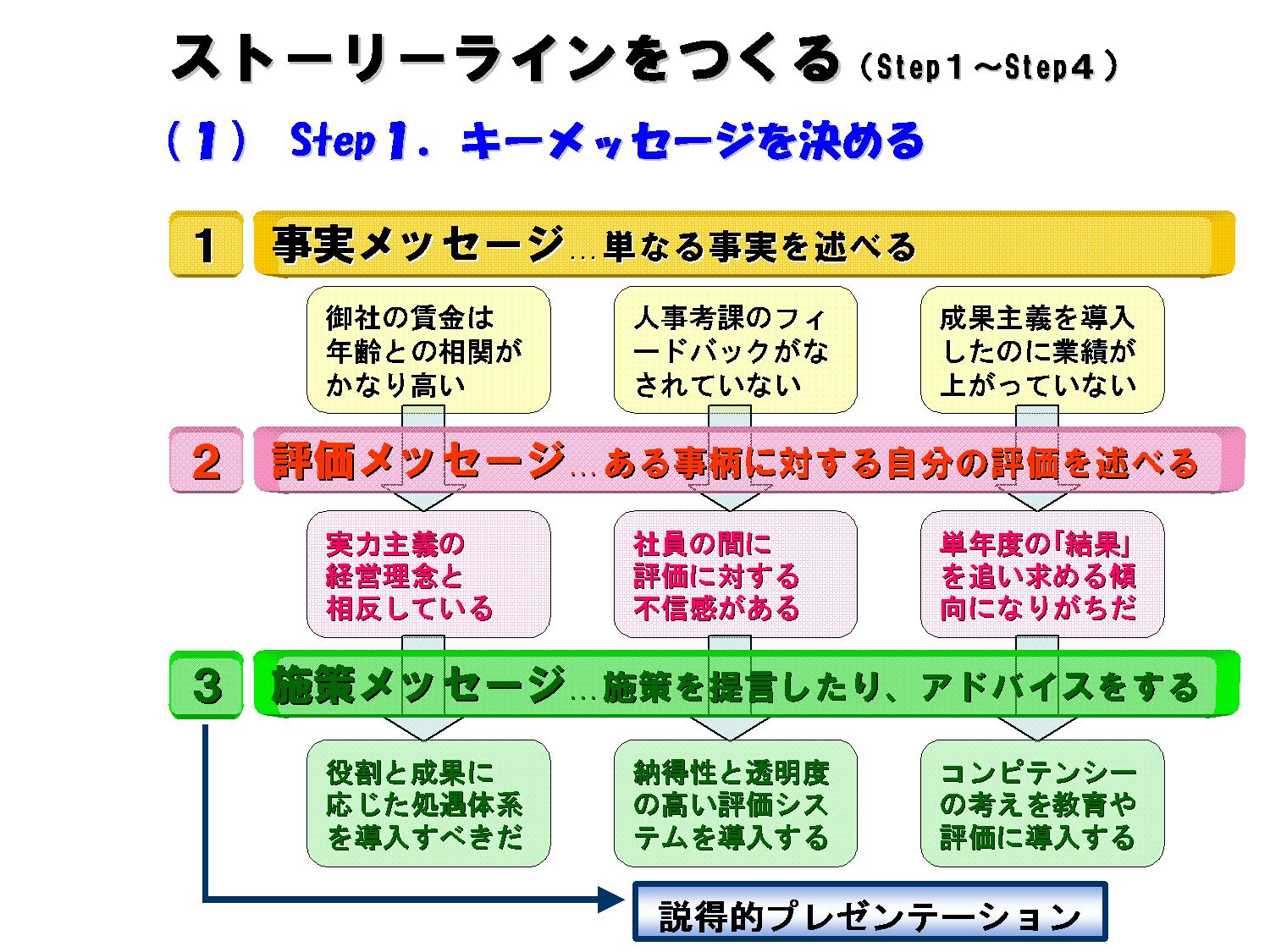
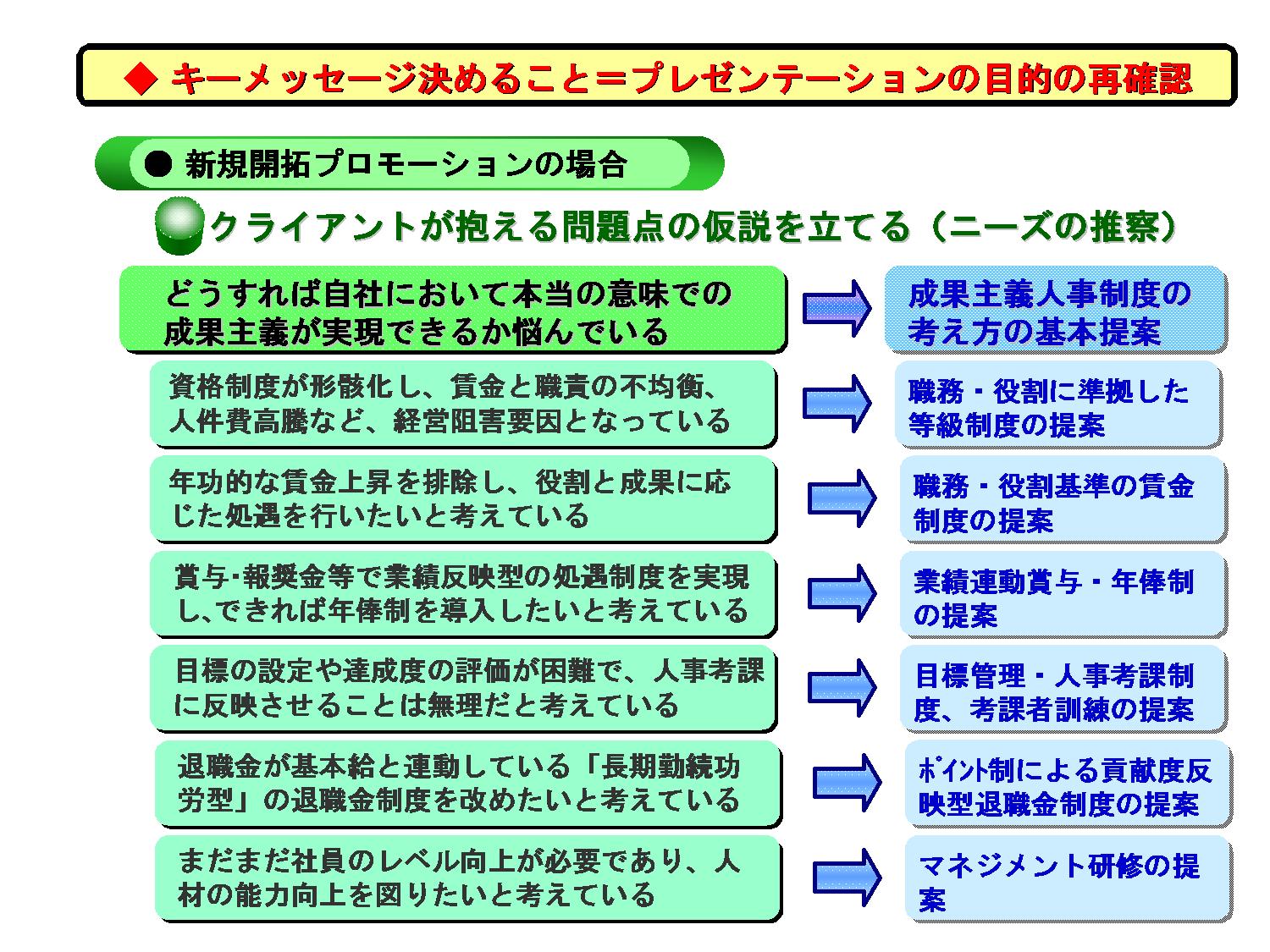
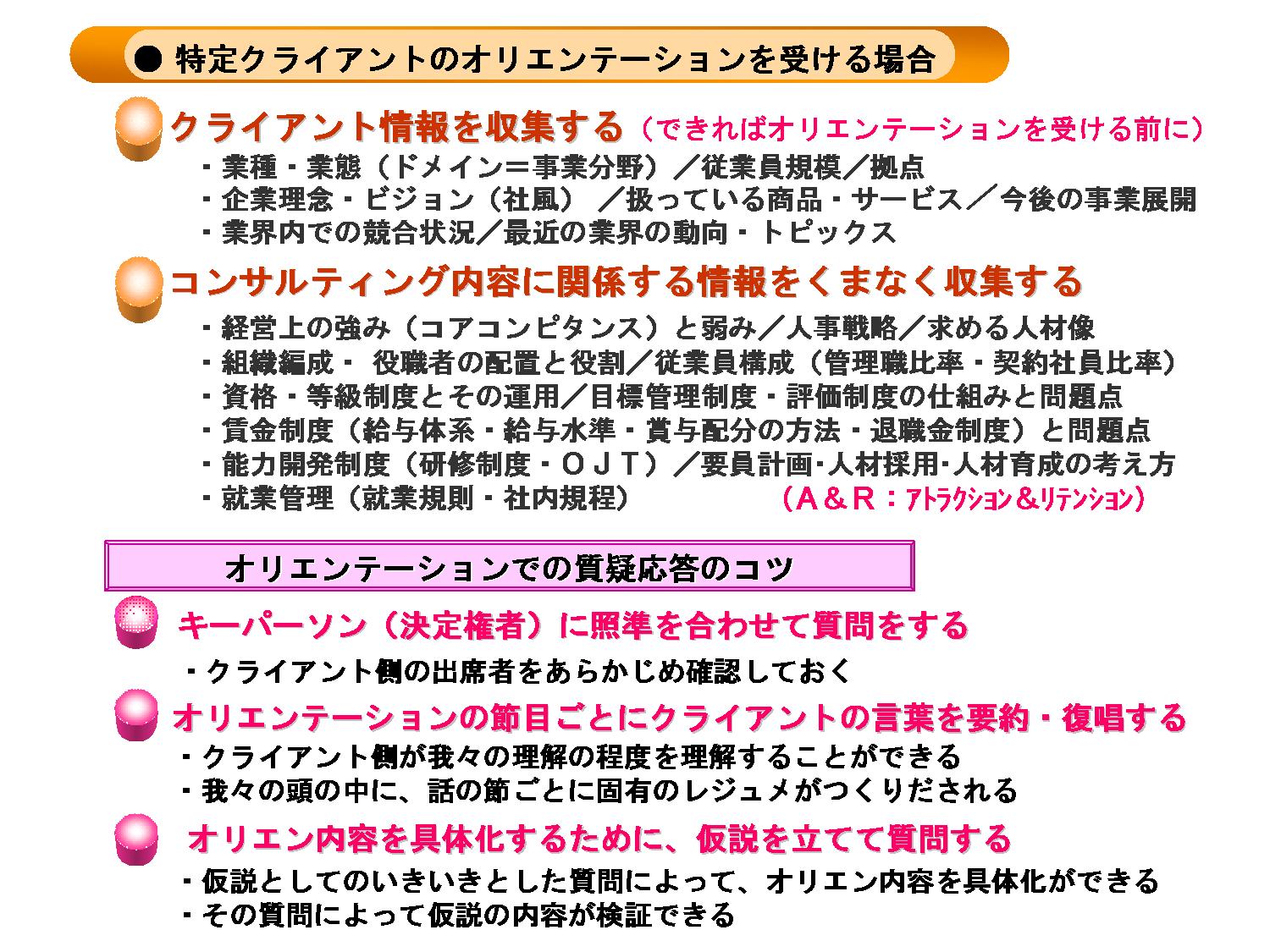
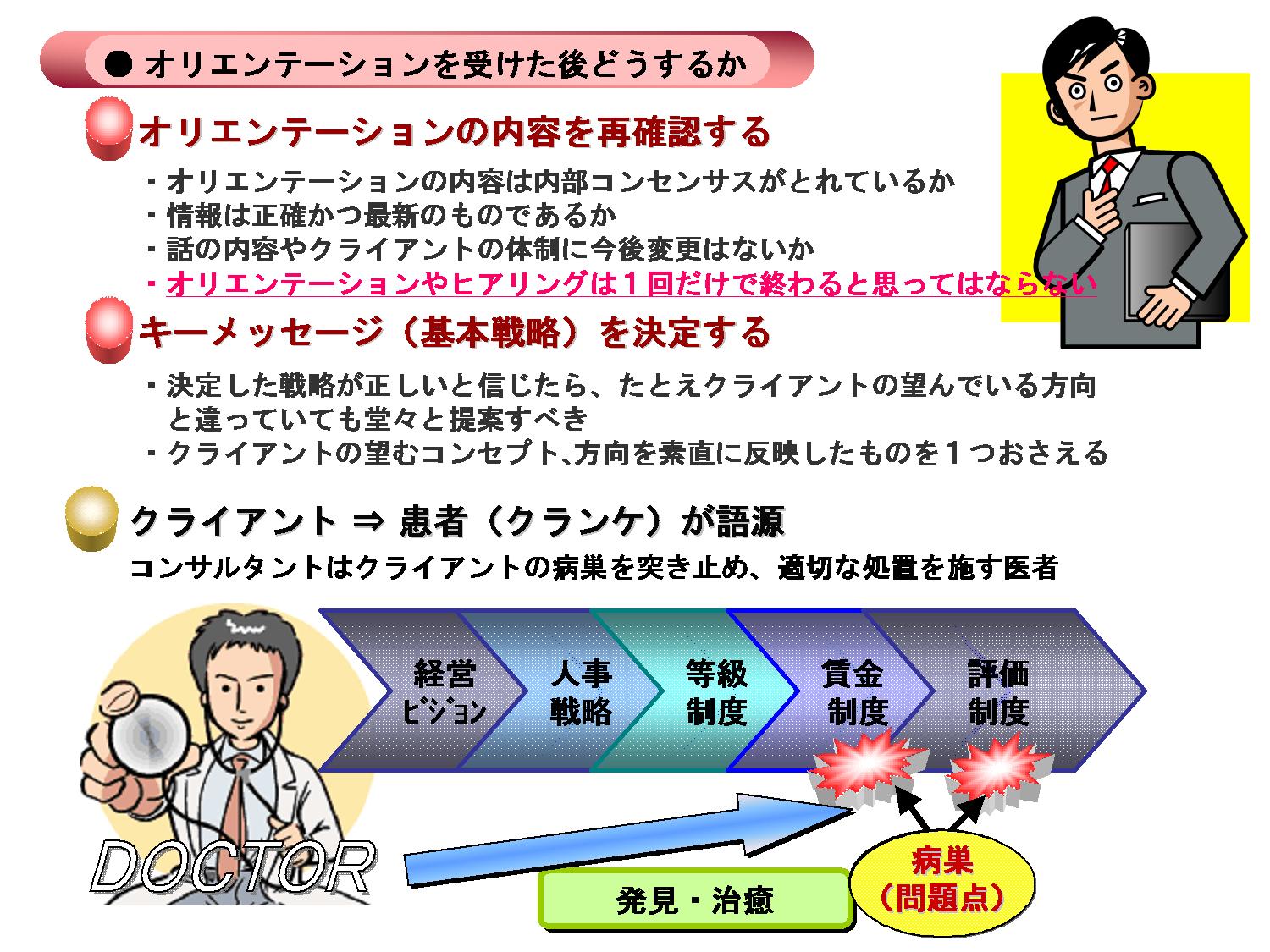
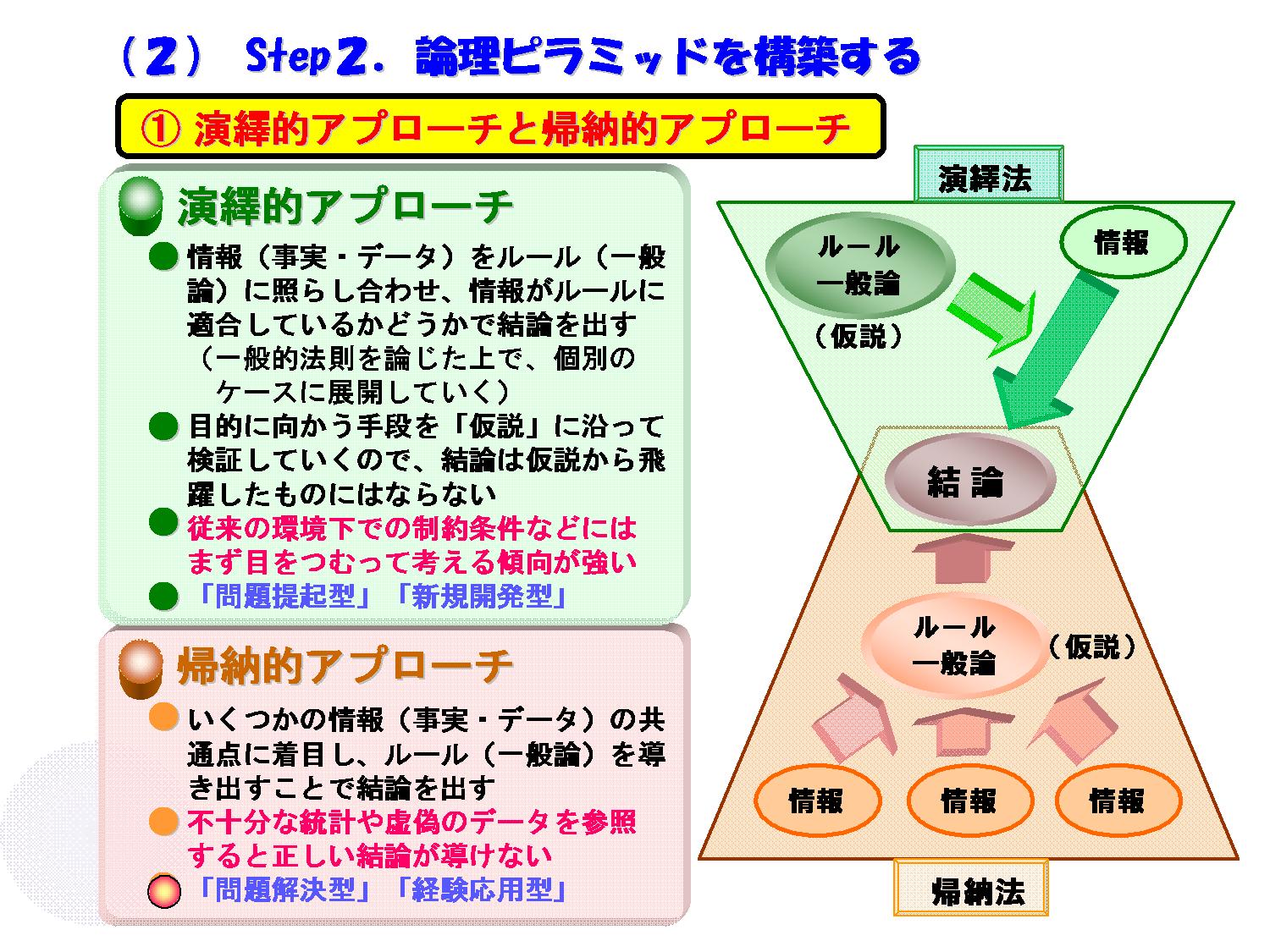
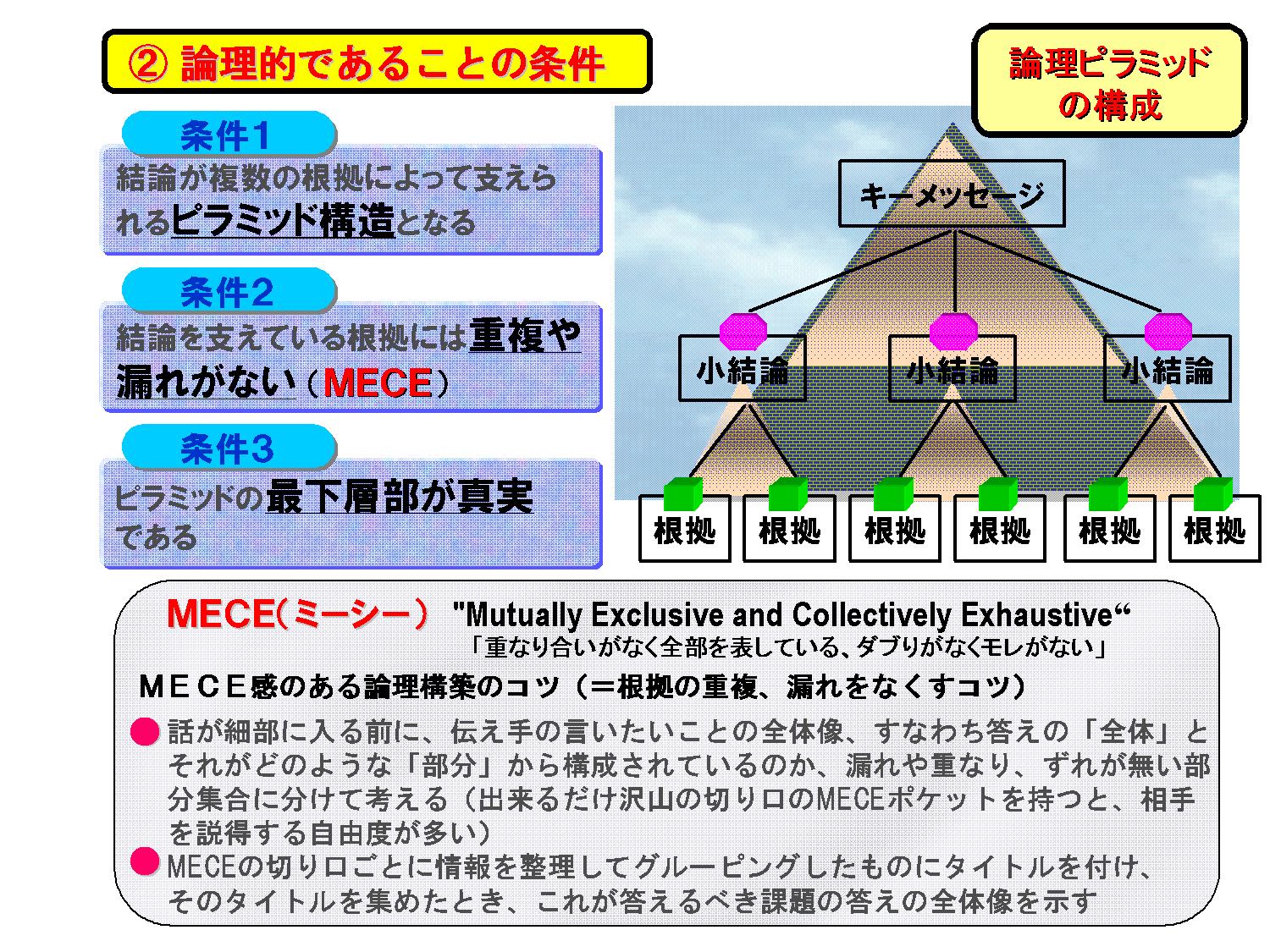
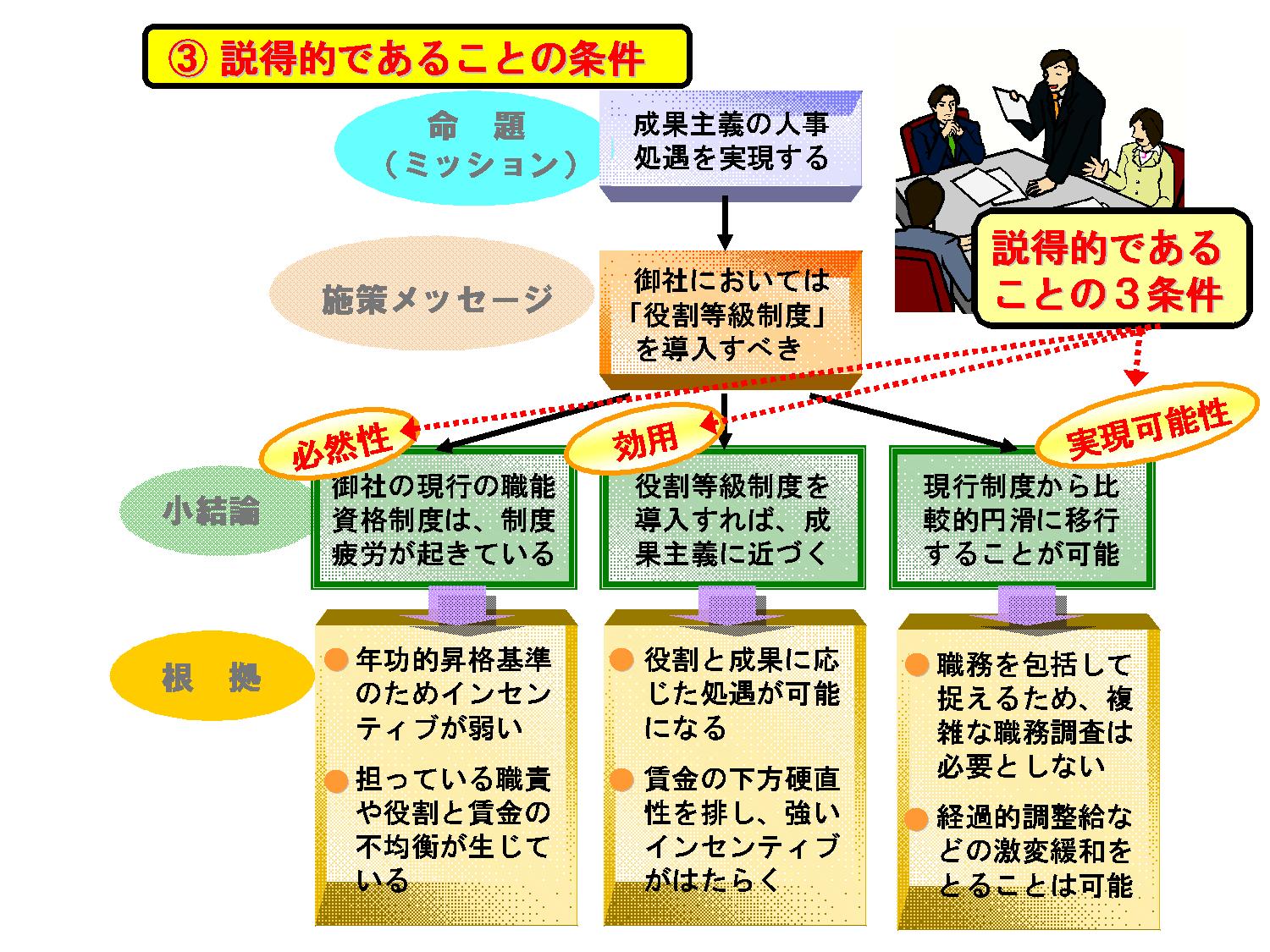
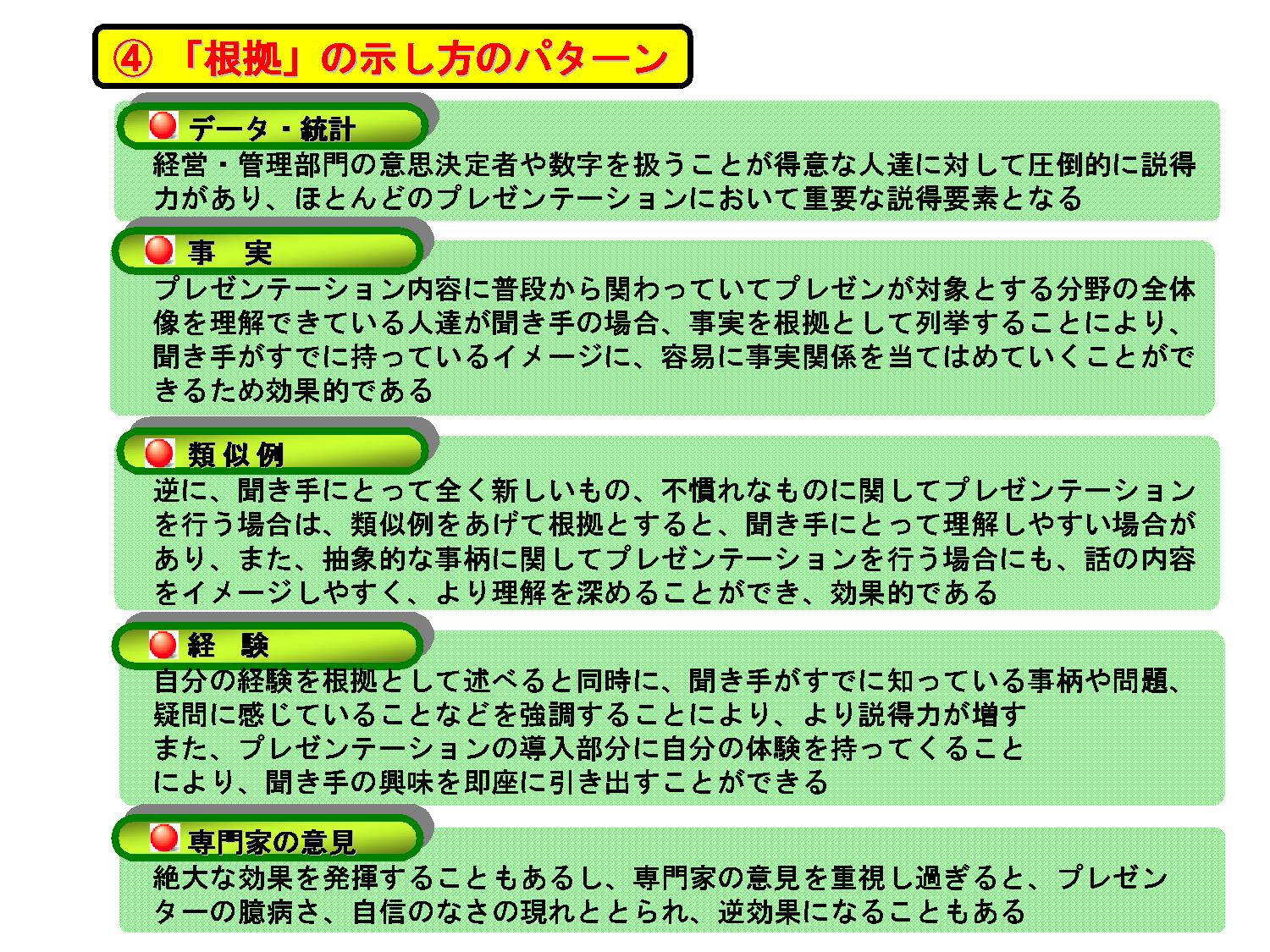
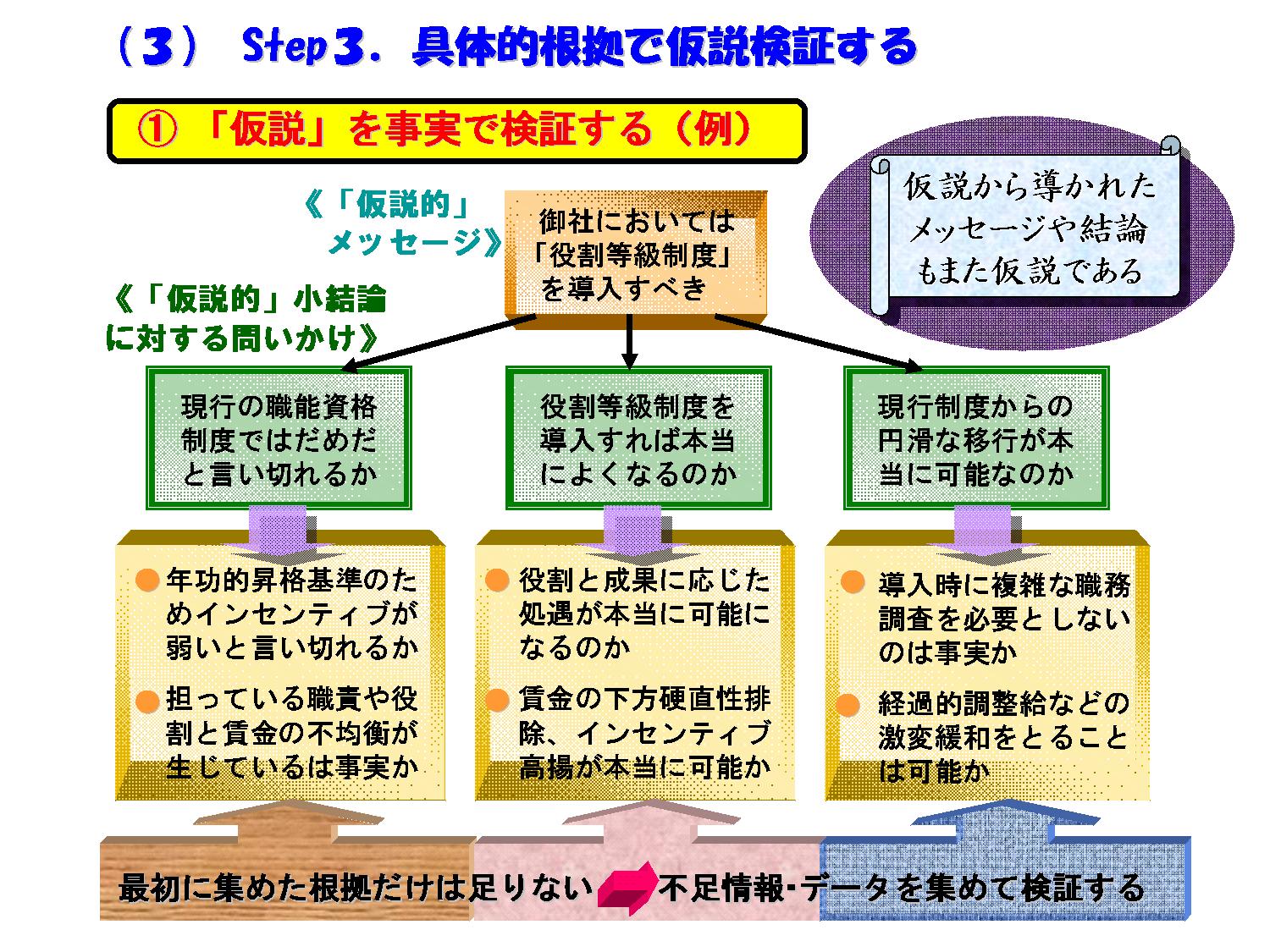
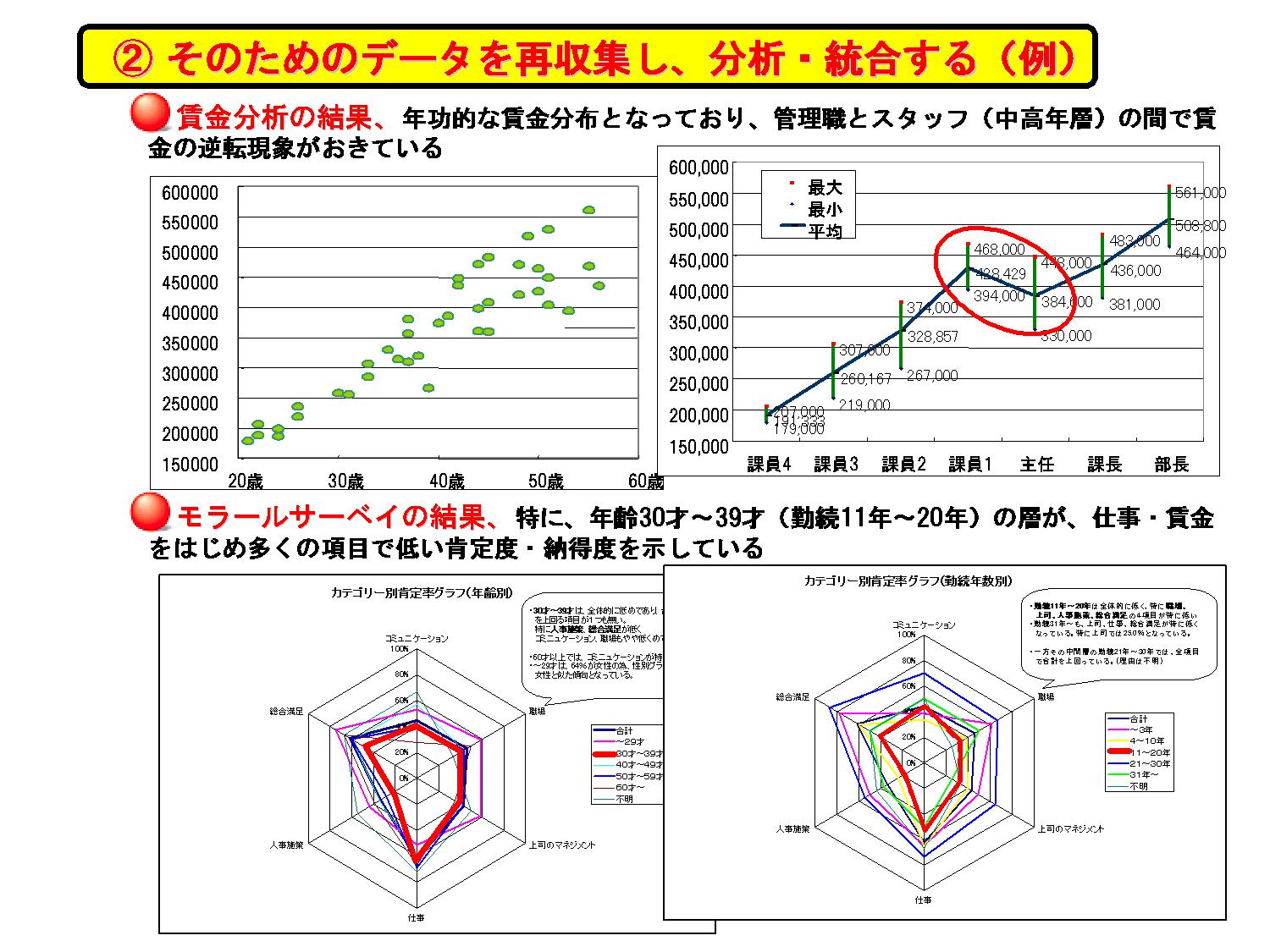
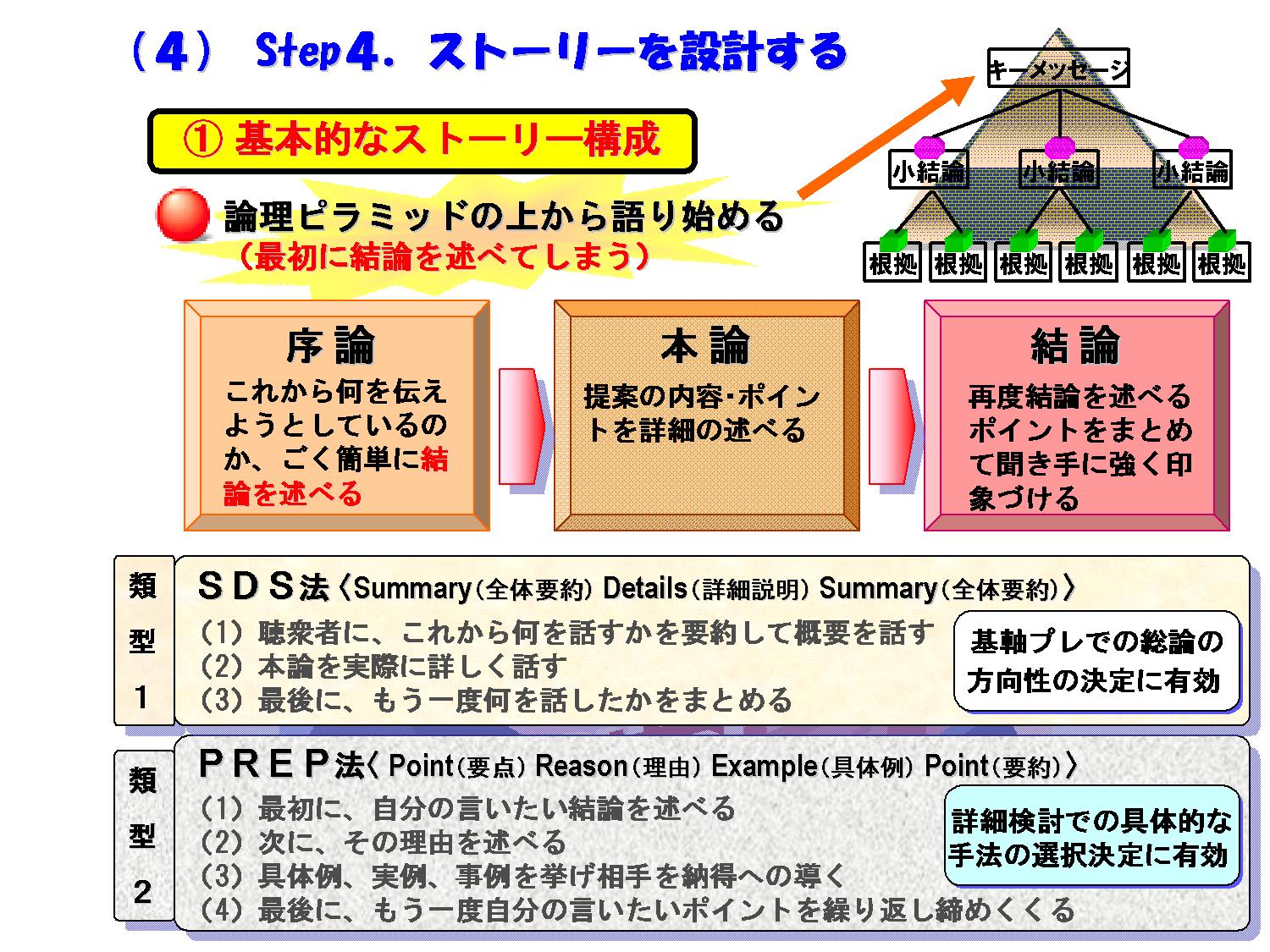
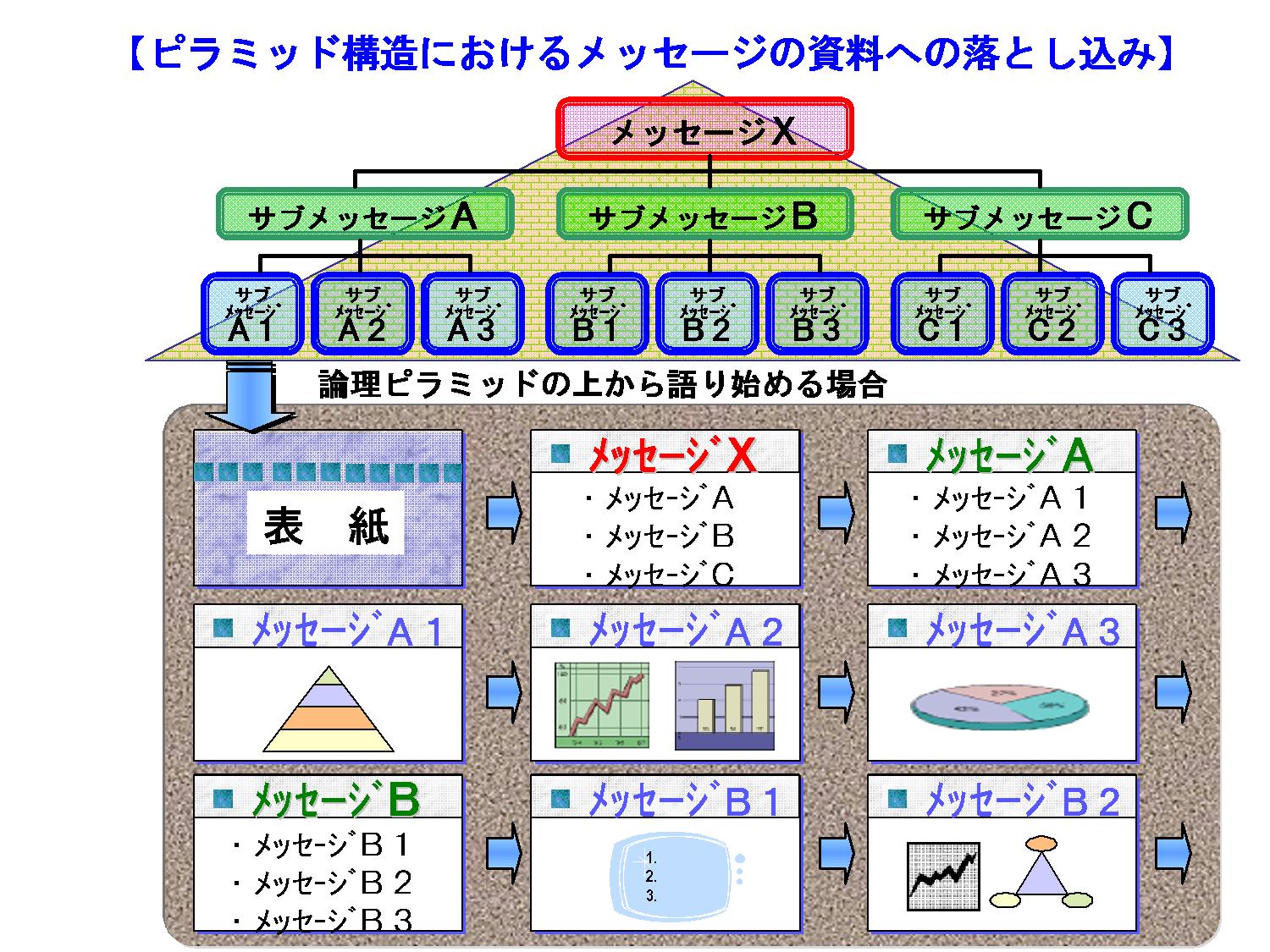
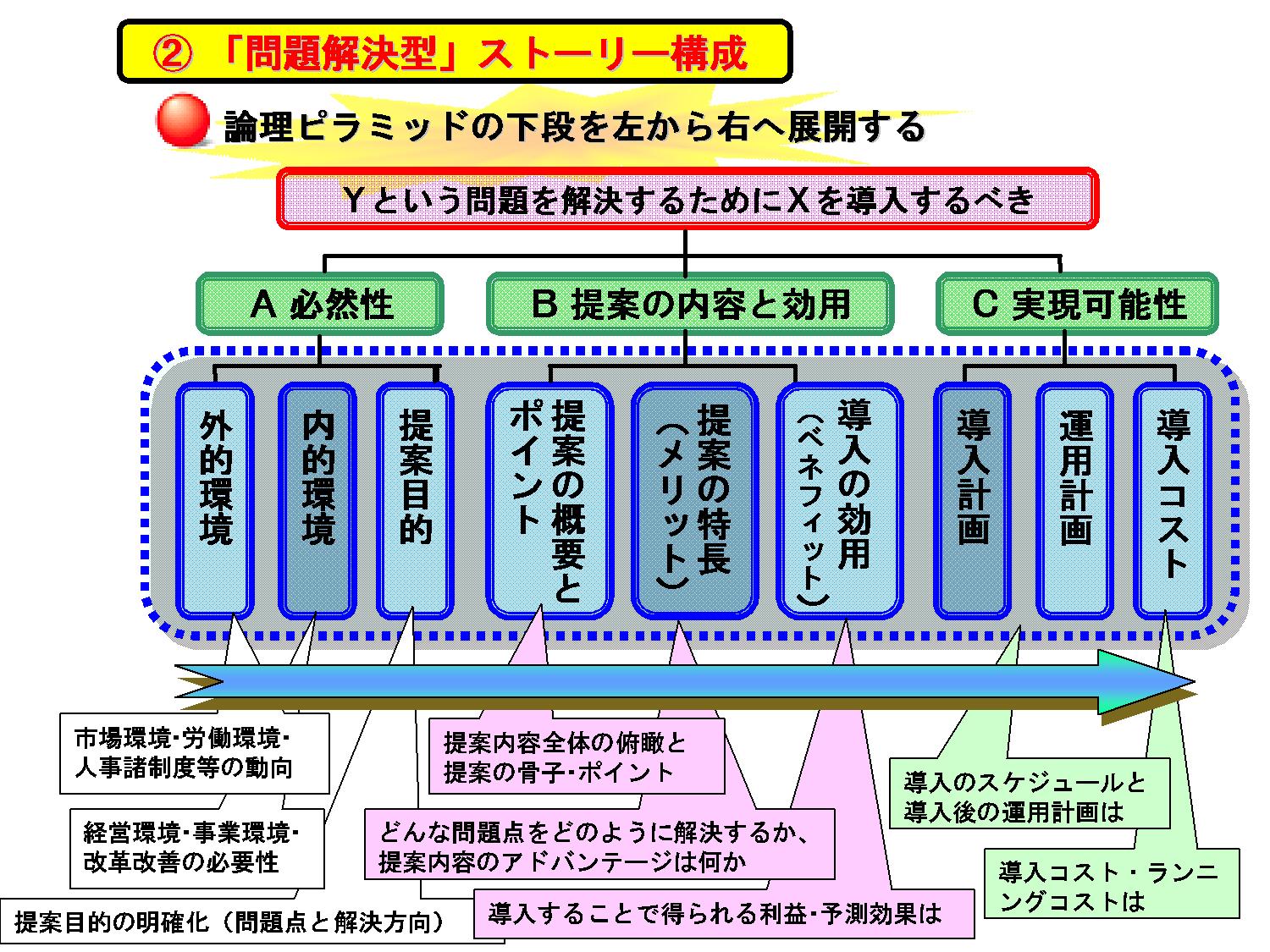
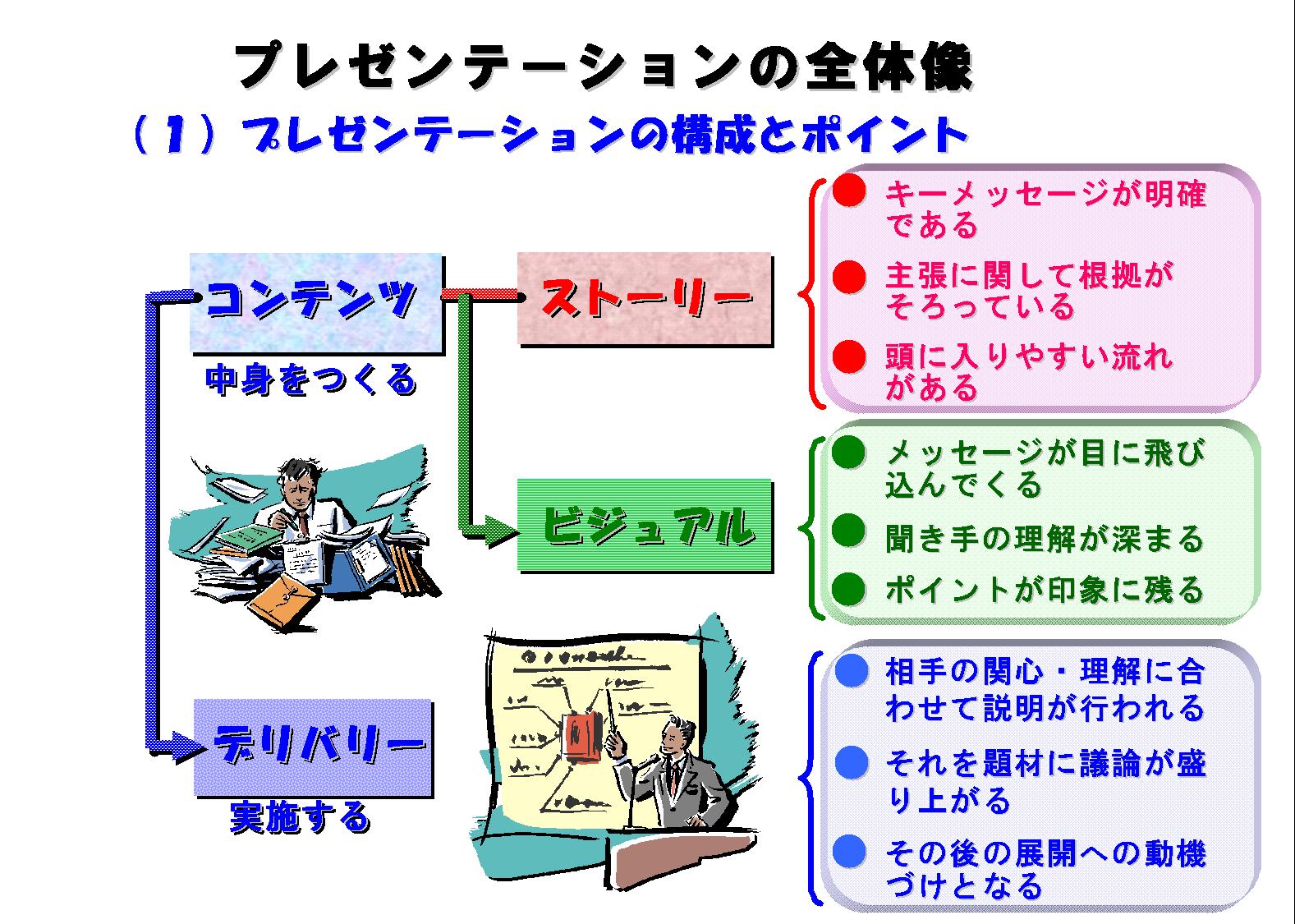
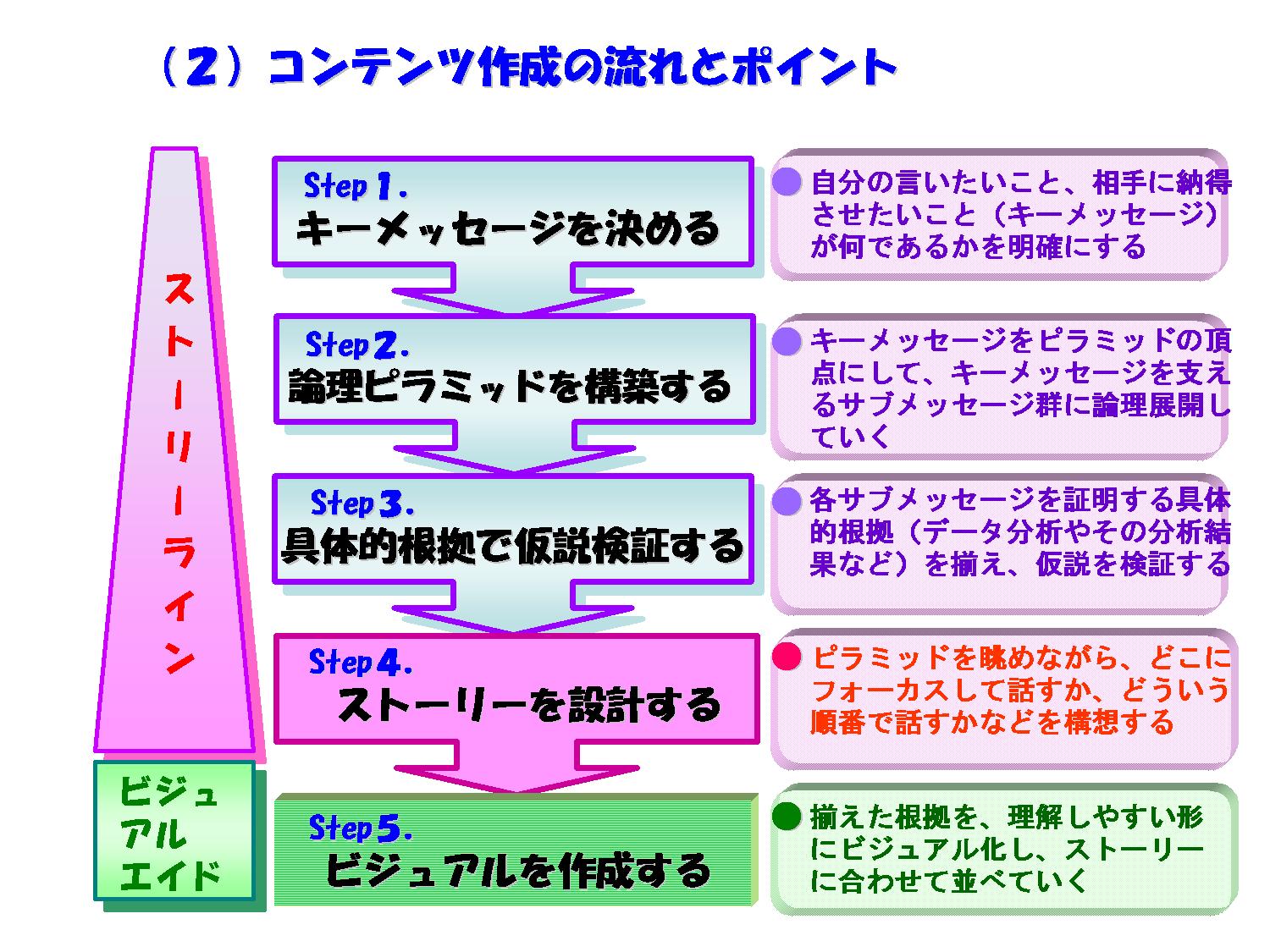



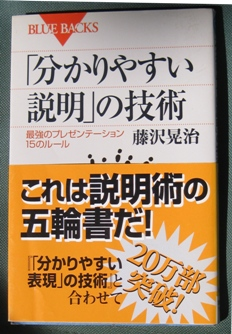

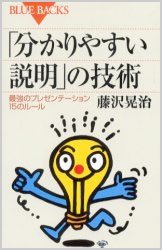
 藤沢 晃治 氏
藤沢 晃治 氏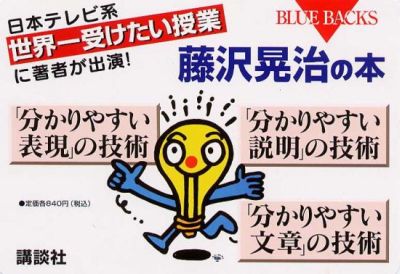 著者のブルーバックスにおける「分かりやすい」シリーズ3冊のうちの1冊で、 この本の前後に、『「分かりやすい表現」の技術-意図を正しく伝えるための16のルール』('99年)、『「分かりやすい文章」の技術-読み手を説得する18のテクニック』('04年) がそれぞれ出ています(この他にPHP新書で『
著者のブルーバックスにおける「分かりやすい」シリーズ3冊のうちの1冊で、 この本の前後に、『「分かりやすい表現」の技術-意図を正しく伝えるための16のルール』('99年)、『「分かりやすい文章」の技術-読み手を説得する18のテクニック』('04年) がそれぞれ出ています(この他にPHP新書で『 何れもスラスラ読めて、書いてあることも至極まっとうです。それで、いざ実践場面になると、すでにやっていることはやっているし、分かっていてもできないことはなかなかできない、という感じではないでしょうか。
何れもスラスラ読めて、書いてあることも至極まっとうです。それで、いざ実践場面になると、すでにやっていることはやっているし、分かっていてもできないことはなかなかできない、という感じではないでしょうか。 
 杉田 敏 氏(プラップジャパン副社長)
杉田 敏 氏(プラップジャパン副社長)  著者はNHKラジオ「やさしいビジネス英語」の講師として知られるとともに、外資系のPR会社の副社長でもあります。ですから、基本的にはプレゼンテーションの本でありながらも、コミュニケーションということを広く捉え、その中での広告、オンライン、対面、媒体を使った様々なコミュニケーションの、それぞれのポイントの説明がなされており、内容的にも的を射ています。
著者はNHKラジオ「やさしいビジネス英語」の講師として知られるとともに、外資系のPR会社の副社長でもあります。ですから、基本的にはプレゼンテーションの本でありながらも、コミュニケーションということを広く捉え、その中での広告、オンライン、対面、媒体を使った様々なコミュニケーションの、それぞれのポイントの説明がなされており、内容的にも的を射ています。

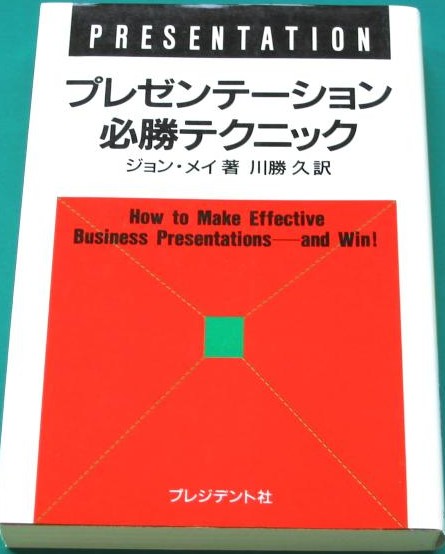

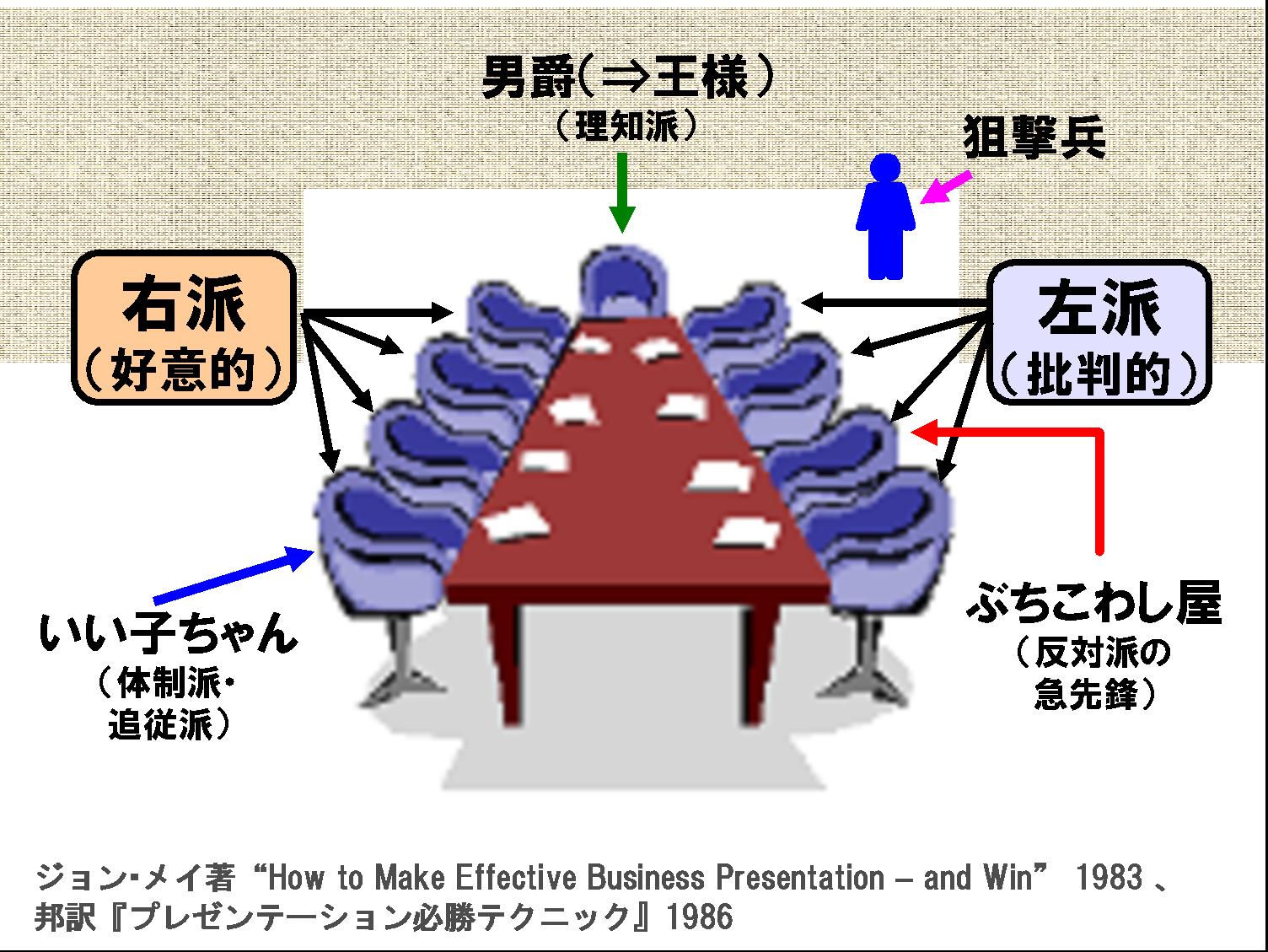 それと、本自体が面白く読めるというのもいいです。例えば〈MAP理論〉というのを紹介していて、聴き手の座る位置によってその態度は決まるという。話し手から見て向かって左側に座るのが支持派、同意しそうもない人は右側に座り、プレゼンをメチャクチャにする人がいるとすればその真中あたりにいる。正面に座る人は"男爵"と呼ばれ、話し手が良ければ理性的だが、ダメだと思うと話し手にとって代わる。右列後方の壁際にいるのは"狙撃兵"で、仲間外れにすると銃弾を撃ち込んでくる...。
それと、本自体が面白く読めるというのもいいです。例えば〈MAP理論〉というのを紹介していて、聴き手の座る位置によってその態度は決まるという。話し手から見て向かって左側に座るのが支持派、同意しそうもない人は右側に座り、プレゼンをメチャクチャにする人がいるとすればその真中あたりにいる。正面に座る人は"男爵"と呼ばれ、話し手が良ければ理性的だが、ダメだと思うと話し手にとって代わる。右列後方の壁際にいるのは"狙撃兵"で、仲間外れにすると銃弾を撃ち込んでくる...。
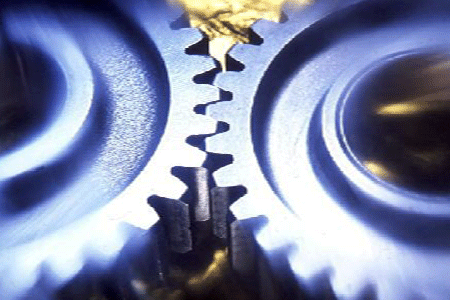 「話が通じない人」とコミュニケーションする場合、言葉や論理に頼りすぎない方が良い場合もあり、それが著者の言う「非・論理コミュニケーション」ですが、「なぜ話が通じないのか」という切り口から、コミュニケーション・トラブルの対処法、背後にある力関係、日本的な"面子"の問題、非言語コミュニケーションの役割、「聴く」ことの重要性、異価値に対する柔軟さの必要性などを指摘し、コミュニケーション能力を高める様々なヒントを提示しています。
「話が通じない人」とコミュニケーションする場合、言葉や論理に頼りすぎない方が良い場合もあり、それが著者の言う「非・論理コミュニケーション」ですが、「なぜ話が通じないのか」という切り口から、コミュニケーション・トラブルの対処法、背後にある力関係、日本的な"面子"の問題、非言語コミュニケーションの役割、「聴く」ことの重要性、異価値に対する柔軟さの必要性などを指摘し、コミュニケーション能力を高める様々なヒントを提示しています。 中西 雅之 氏
中西 雅之 氏
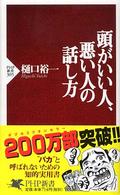
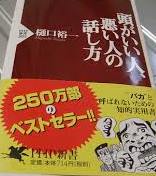
 どうして本書がベストセラーになったのか、読み終えて(途中から通読になってしまった)今ひとつピンとこなかったのですが(でも家人は読んで「続編」ともいえる『頭がいい人、悪い人の<言い訳>術』という本まで買った)、よくよく考えると、方法論的な何かを得るというよりも、読み手によってはカタルシス効果のようなものがあるのではないかと思った次第です。"充分なカタルシス効果"を得るための、本書の「使用書」と「注意書」を皮肉を込めてを付けるとすれば、こうなるのでは...。
どうして本書がベストセラーになったのか、読み終えて(途中から通読になってしまった)今ひとつピンとこなかったのですが(でも家人は読んで「続編」ともいえる『頭がいい人、悪い人の<言い訳>術』という本まで買った)、よくよく考えると、方法論的な何かを得るというよりも、読み手によってはカタルシス効果のようなものがあるのではないかと思った次第です。"充分なカタルシス効果"を得るための、本書の「使用書」と「注意書」を皮肉を込めてを付けるとすれば、こうなるのでは...。
 山田ズーニー氏(略歴下記)
山田ズーニー氏(略歴下記) ちょっと引き気味になりそうなタイトルですが、読んで見るとなかなかでした。
ちょっと引き気味になりそうなタイトルですが、読んで見るとなかなかでした。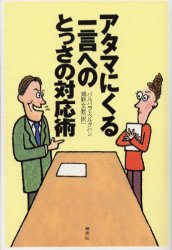

 著者はドイツ人で、大学で心理学を学び、今はコミュニケーショントレーナーであるということですが、タイトルに惹かれた人が多かったのか、かなり売れた本です。
著者はドイツ人で、大学で心理学を学び、今はコミュニケーショントレーナーであるということですが、タイトルに惹かれた人が多かったのか、かなり売れた本です。
 鬼才コラムニストとして知られる著者が「危険な」と冠するからには一体どんな内容かと思いきや、技術論よりも、文章を書く際に邪魔になる囚われから読者を解き放つことに主眼を置いた真面目な文章論でした。「批判」と「悪口」の違いを述べた部分など、啓蒙書としての倫理性すら感じます。
鬼才コラムニストとして知られる著者が「危険な」と冠するからには一体どんな内容かと思いきや、技術論よりも、文章を書く際に邪魔になる囚われから読者を解き放つことに主眼を置いた真面目な文章論でした。「批判」と「悪口」の違いを述べた部分など、啓蒙書としての倫理性すら感じます。
 本書は、講談社ブルーバックスの『「分かりやすい表現」の技術』シリーズの著者によるものですが、今度は大量の情報から必要なものを抽出するテクニックを説明しています。
本書は、講談社ブルーバックスの『「分かりやすい表現」の技術』シリーズの著者によるものですが、今度は大量の情報から必要なものを抽出するテクニックを説明しています。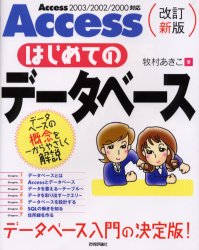
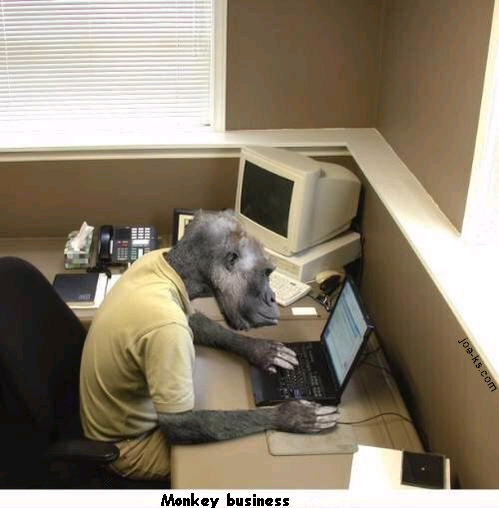

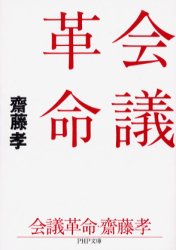
 齋藤 孝 氏 (略歴下記)
齋藤 孝 氏 (略歴下記) さらに、会議を変えるための具体的方法を提示しています。
さらに、会議を変えるための具体的方法を提示しています。

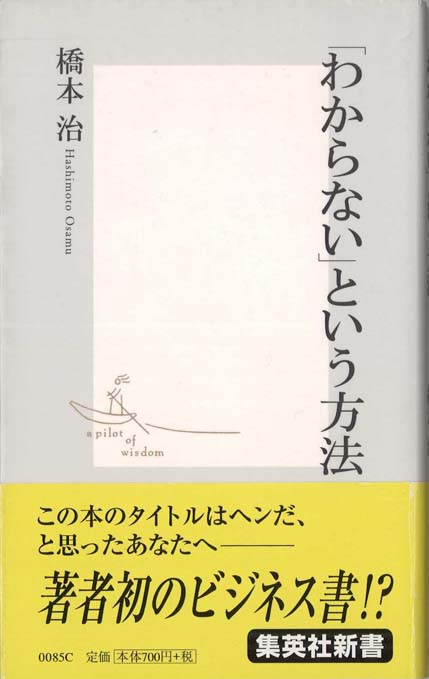



 「押し出しファイリング」で溜まってきた情報を捨てるノウハウとして、"とりあえず捨てる仕組み"である「バッファー・ボックス」を提唱しています。さらに「バッファー・ボックス」には、「受入れバッファー」と「廃棄バッファー」があると。
「押し出しファイリング」で溜まってきた情報を捨てるノウハウとして、"とりあえず捨てる仕組み"である「バッファー・ボックス」を提唱しています。さらに「バッファー・ボックス」には、「受入れバッファー」と「廃棄バッファー」があると。


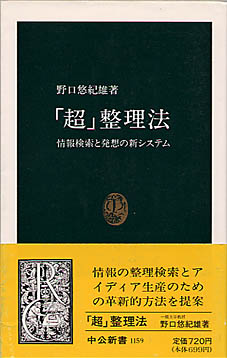

 野口悠紀雄 氏
野口悠紀雄 氏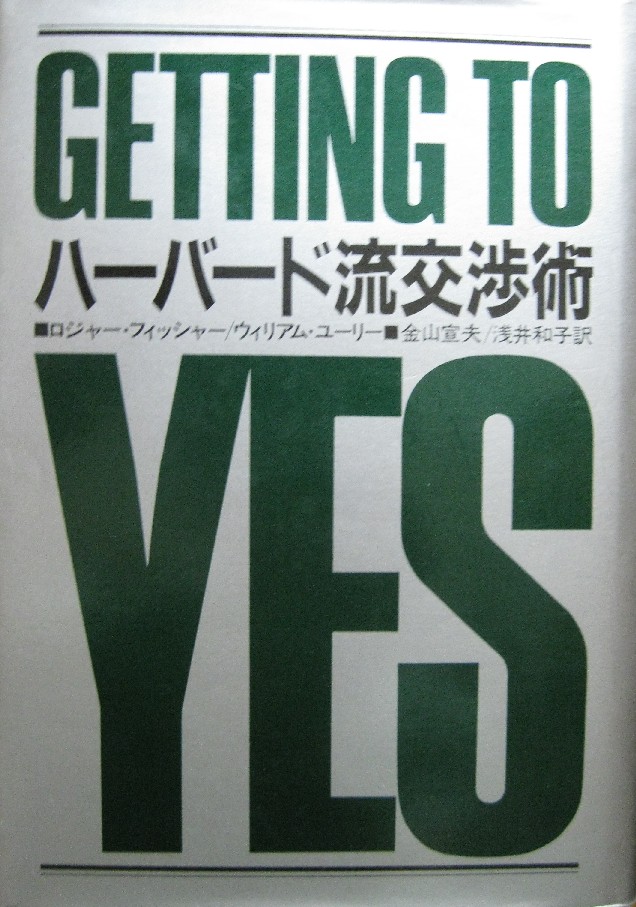
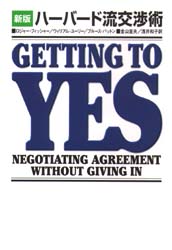
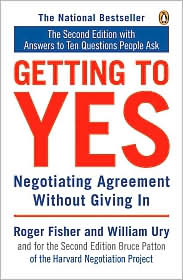
 日本人の場合、「交渉」というとすぐに「権謀術数」とか「手練手管」という言葉を思い浮かべ、交渉問題そのものよりも相手の性格や立場のことを考えがちではないでしょうか。本書は特に日本人向けに書かれたものではありませんが、ここに示されている交渉の戦術は、そうした日本的な交渉とは対照的で、要約すれば、
日本人の場合、「交渉」というとすぐに「権謀術数」とか「手練手管」という言葉を思い浮かべ、交渉問題そのものよりも相手の性格や立場のことを考えがちではないでしょうか。本書は特に日本人向けに書かれたものではありませんが、ここに示されている交渉の戦術は、そうした日本的な交渉とは対照的で、要約すれば、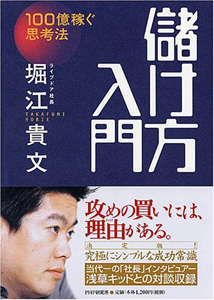
 『
『
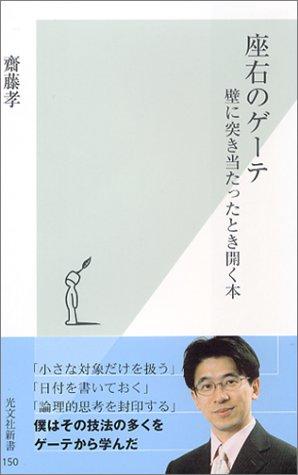
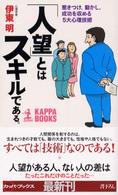

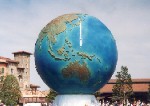 「第2パーク」構想でディズニー側が最初に示したプランは、MGM(映画)だったんですね。でも、日本人は米国人ほど映画文化に執着は無く、そこで〈シー(海)〉になったとのこと。
「第2パーク」構想でディズニー側が最初に示したプランは、MGM(映画)だったんですね。でも、日本人は米国人ほど映画文化に執着は無く、そこで〈シー(海)〉になったとのこと。
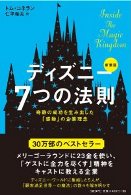


 来園者を〈ゲスト〉、従業員を〈キャスト〉と呼ぶディズニーの経営姿勢が、どういった形でテーマパークに生かされているかがよくわかり、「顧客満足」とは何かということをテーマとした本ですが、ビジネス全般に通じる示唆を含んでいて、また読み物として感動させられる箇所も多くありました。
来園者を〈ゲスト〉、従業員を〈キャスト〉と呼ぶディズニーの経営姿勢が、どういった形でテーマパークに生かされているかがよくわかり、「顧客満足」とは何かということをテーマとした本ですが、ビジネス全般に通じる示唆を含んでいて、また読み物として感動させられる箇所も多くありました。 そして、それらが〈ゲスト〉のためだけでなく、むしろ〈キャスト〉へ向けてのメッセージであるという点が、個人的には最も興味深く思われ("隠れミッキー"なども元は内輪受けからスタートしているようです)、そうした配慮やこだわりが、結果的には〈ゲスト〉の満足度にもつながっていくのだということがよくわかりました。
そして、それらが〈ゲスト〉のためだけでなく、むしろ〈キャスト〉へ向けてのメッセージであるという点が、個人的には最も興味深く思われ("隠れミッキー"なども元は内輪受けからスタートしているようです)、そうした配慮やこだわりが、結果的には〈ゲスト〉の満足度にもつながっていくのだということがよくわかりました。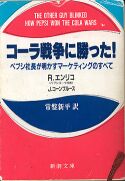
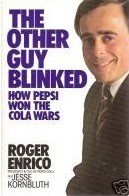


 ペプシとコカ・コーラの売上げシェアが拮抗しているアメリカではともかく、日本ではシェアは圧倒的にコカ・コーラの方が勝っているので、その点では本書の内容は少しピンとこない部分もあるかも知れません。
ペプシとコカ・コーラの売上げシェアが拮抗しているアメリカではともかく、日本ではシェアは圧倒的にコカ・コーラの方が勝っているので、その点では本書の内容は少しピンとこない部分もあるかも知れません。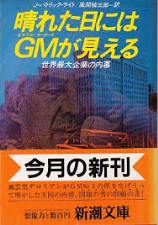
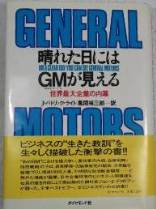
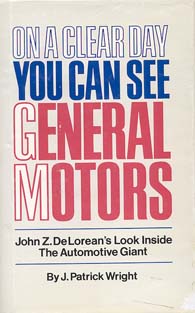
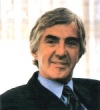
 DMC‐12(通称デロリアン)
DMC‐12(通称デロリアン)
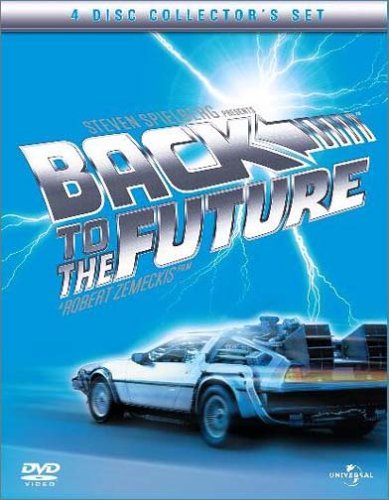
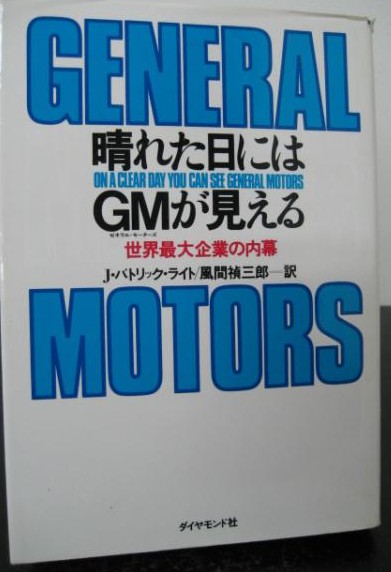 暴露本であるとも言え、その分、経営書と言うよりはビジネス書、ビジネス書と言うよりは小説のように面白く読めます。私企業でも大きくなると役所と変わらぬ官僚主義が横行することがよくわかり、それに驚き、怒り、呆れるデロリアン氏に共感しますが、彼自身も自分の考えを通す上で強引過ぎる点は無かったのかという疑問も湧き、この点でアメリカでも本書に対する評価は割れるようです。それでも、大企業の役員が保守的で内向きな視点しか持てない傾向に陥りがちなのがよくわかって興味深く、これは'70年代のGM社内の話ですが、今でも実際にGMは大企業病に喘いでいるわけです。
暴露本であるとも言え、その分、経営書と言うよりはビジネス書、ビジネス書と言うよりは小説のように面白く読めます。私企業でも大きくなると役所と変わらぬ官僚主義が横行することがよくわかり、それに驚き、怒り、呆れるデロリアン氏に共感しますが、彼自身も自分の考えを通す上で強引過ぎる点は無かったのかという疑問も湧き、この点でアメリカでも本書に対する評価は割れるようです。それでも、大企業の役員が保守的で内向きな視点しか持てない傾向に陥りがちなのがよくわかって興味深く、これは'70年代のGM社内の話ですが、今でも実際にGMは大企業病に喘いでいるわけです。
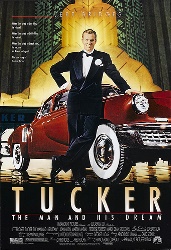

 むしろこの人、フランシス・F・コッポラ 監督の映画「タッカー」('88年/米)(製作総指揮ジョージ・ルーカス、コレ、知人宅でビデオで観た(89-08-19))のモデルにもなったブレストン・タッカーに近いかも。ブレストン・タッカーは軍需工場を経営していましたが、来るべき現代にふさわしい新しい新車の設計、開発を自ら計画し、1945年に「タッカー・トーペード」という自動車を生産します。最終的には、こうした彼の動きに警戒感を抱いたGMなどの「ビッグ3」に潰されてしまうものの、独力でクルマの生産まで漕ぎつけるところが、いかにも起業家という感じで、しかも今時流行のITとかではなくクルマづくりである点を考えてもスゴイ。但し、この「タッカー・トーペード」は50台しか生産されませんでした(映画では現存する47台が愛好家の全面協力により使われた)。一方、デロリアンの手による「DMC‐12」は約9,000台生産されています。
むしろこの人、フランシス・F・コッポラ 監督の映画「タッカー」('88年/米)(製作総指揮ジョージ・ルーカス、コレ、知人宅でビデオで観た(89-08-19))のモデルにもなったブレストン・タッカーに近いかも。ブレストン・タッカーは軍需工場を経営していましたが、来るべき現代にふさわしい新しい新車の設計、開発を自ら計画し、1945年に「タッカー・トーペード」という自動車を生産します。最終的には、こうした彼の動きに警戒感を抱いたGMなどの「ビッグ3」に潰されてしまうものの、独力でクルマの生産まで漕ぎつけるところが、いかにも起業家という感じで、しかも今時流行のITとかではなくクルマづくりである点を考えてもスゴイ。但し、この「タッカー・トーペード」は50台しか生産されませんでした(映画では現存する47台が愛好家の全面協力により使われた)。一方、デロリアンの手による「DMC‐12」は約9,000台生産されています。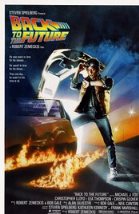

 「バック・トゥ・ザ・フューチャー」●原題:BACK TO THE FUTURE●制作年:1985年●制作国:アメリカ●監督:ロバート・ゼメキス●製作総指揮:スティーヴン・スピルバーグ/キャスリーン・ケネディ/フランク・マーシャル●製作:ボブ・ゲイル/ニール・カントン●脚本:ロバート・ゼメキス/ボブ・ゲイル●撮影:ディーン・カンディ●音楽:アラン・シルヴェストリ●時間:116分●出演:マイケル・J・フォックス/クリストファー・ロイド/リー・トンプソン/クリスピン・グローヴァー/トーマス・F・ウィルソン/クローディア・ウェルズ/マーク・マクルーア/ウェンディ・ジョー・スパーバー/ジェームズ・トールカン/
「バック・トゥ・ザ・フューチャー」●原題:BACK TO THE FUTURE●制作年:1985年●制作国:アメリカ●監督:ロバート・ゼメキス●製作総指揮:スティーヴン・スピルバーグ/キャスリーン・ケネディ/フランク・マーシャル●製作:ボブ・ゲイル/ニール・カントン●脚本:ロバート・ゼメキス/ボブ・ゲイル●撮影:ディーン・カンディ●音楽:アラン・シルヴェストリ●時間:116分●出演:マイケル・J・フォックス/クリストファー・ロイド/リー・トンプソン/クリスピン・グローヴァー/トーマス・F・ウィルソン/クローディア・ウェルズ/マーク・マクルーア/ウェンディ・ジョー・スパーバー/ジェームズ・トールカン/



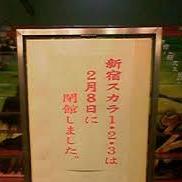 価★★★)
価★★★)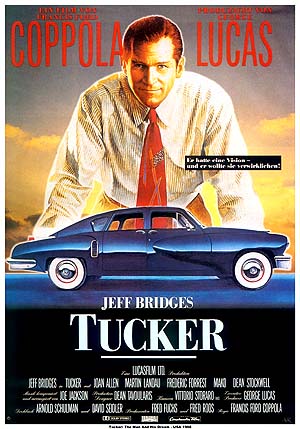
.jpg) 「タッカー」●原題:TUCKER●制作年:1988年●制作国:アメリ
「タッカー」●原題:TUCKER●制作年:1988年●制作国:アメリ カ●監督:フランシス・フォード・コッポラ●製作:フレッド・ルース/フレッド・フックス●製作総指揮:ジョージ・ルーカス●脚本 アーノルド・シュルマン/ディビッド・セイドラー●撮影:ヴィットリオ・ストラーロ●音楽:ジョー・ジャクソン●時間:111分●出演:ジェフ・ブリッジス/ジョアン・アレン/マーティン・ランドー/フレデリック・フォレスト/マコ岩松/イライアス・コティーズ/
カ●監督:フランシス・フォード・コッポラ●製作:フレッド・ルース/フレッド・フックス●製作総指揮:ジョージ・ルーカス●脚本 アーノルド・シュルマン/ディビッド・セイドラー●撮影:ヴィットリオ・ストラーロ●音楽:ジョー・ジャクソン●時間:111分●出演:ジェフ・ブリッジス/ジョアン・アレン/マーティン・ランドー/フレデリック・フォレスト/マコ岩松/イライアス・コティーズ/

 教育研修コンサルタントによって書かれた本書は、働く個々人に対し「ビジョン」、「ミッション」、「バリュー」を創ることで、生きていく方向性や指針が見つかるとし、とりわけビジョニング(自分自身のマイビジョンを創ること)が自己改革をもたらすと説いていますが、併せて、企業を活性化するためには「組織ビジョン」と「個人ビジョン」の相乗効果が大切であると言っていて、組織論の書としても読めます。
教育研修コンサルタントによって書かれた本書は、働く個々人に対し「ビジョン」、「ミッション」、「バリュー」を創ることで、生きていく方向性や指針が見つかるとし、とりわけビジョニング(自分自身のマイビジョンを創ること)が自己改革をもたらすと説いていますが、併せて、企業を活性化するためには「組織ビジョン」と「個人ビジョン」の相乗効果が大切であると言っていて、組織論の書としても読めます。
 太田 肇 氏
太田 肇 氏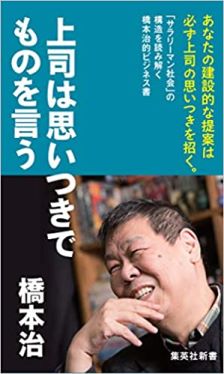
 橋本 治 氏 (略歴下記)
橋本 治 氏 (略歴下記)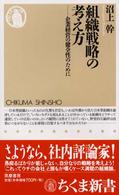
.jpg) 沼上 幹 (ぬまがみ つよし)氏 (一橋大教授)
沼上 幹 (ぬまがみ つよし)氏 (一橋大教授) むしろ、組織にいる人に働く組織心理の傾向の分析や説明には、誰もが思い当たるものが多くあるのではないかと思われます(まるで企業小説のように書かれていて、しかも現実味がある!)。
むしろ、組織にいる人に働く組織心理の傾向の分析や説明には、誰もが思い当たるものが多くあるのではないかと思われます(まるで企業小説のように書かれていて、しかも現実味がある!)。
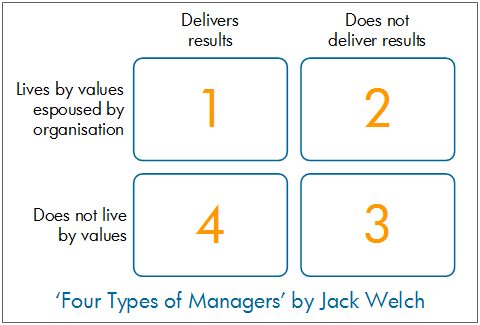 また、マネジャーを、タイプA(右図1)「価値観に忠実で成果を上げる」、タイプB(右図2)「価値観に忠実だが必ずしも成果を上げるとは限らない」、タイプC(右図4)「価値観に忠実ではないが成果を上げる可能性がある」の3タイプに分け、タイプBやCをタイプAに変身させるのは困難で、試みる価値もなく、将来的にはよその企業へ押し付けるべき人材だとしています。
また、マネジャーを、タイプA(右図1)「価値観に忠実で成果を上げる」、タイプB(右図2)「価値観に忠実だが必ずしも成果を上げるとは限らない」、タイプC(右図4)「価値観に忠実ではないが成果を上げる可能性がある」の3タイプに分け、タイプBやCをタイプAに変身させるのは困難で、試みる価値もなく、将来的にはよその企業へ押し付けるべき人材だとしています。
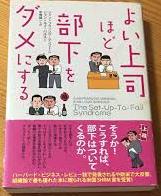
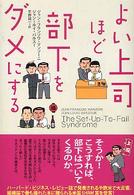

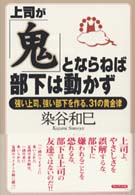
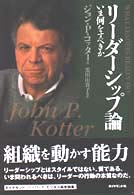



 1999年に原著刊行の本書(原題:John P. Kotter on What Leaders Really Do)は、リーダーシップ論のバイブルとまで言われている本です。本書の要諦は序章にまとめられていて、つまり、リーダーシップとマネジメントは別物であり、「マネジメントの仕事は、計画と予算を策定し、階層を活用して職務遂行に必要な人脈を構築し、コントロールによって任務をまっとうすること」であるのに対し、「リーダーとしての仕事は、ビジョンと戦略をつくりあげ、複雑ではあるが同じベクトルを持つ人脈を背景とした実行力を築き、社員のやる気を引き出すことでビジョンと戦略を遂行することである」ということです(25p)。
1999年に原著刊行の本書(原題:John P. Kotter on What Leaders Really Do)は、リーダーシップ論のバイブルとまで言われている本です。本書の要諦は序章にまとめられていて、つまり、リーダーシップとマネジメントは別物であり、「マネジメントの仕事は、計画と予算を策定し、階層を活用して職務遂行に必要な人脈を構築し、コントロールによって任務をまっとうすること」であるのに対し、「リーダーとしての仕事は、ビジョンと戦略をつくりあげ、複雑ではあるが同じベクトルを持つ人脈を背景とした実行力を築き、社員のやる気を引き出すことでビジョンと戦略を遂行することである」ということです(25p)。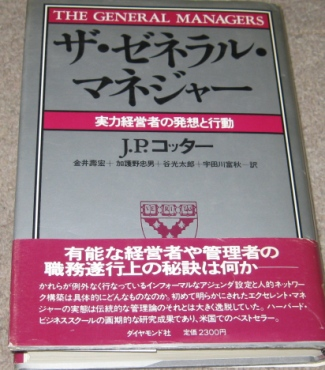

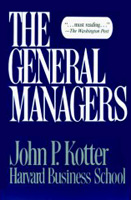

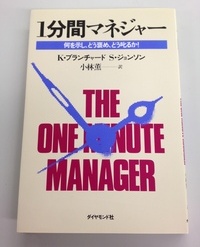
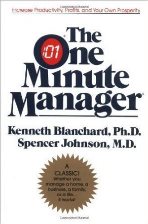

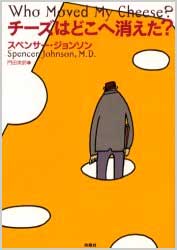


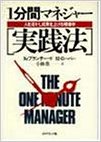

 森生 明 氏 (株)M・R・O代表取締役
森生 明 氏 (株)M・R・O代表取締役
 なぜM&Aが行われるかその目的を示し、狙われやすい会社や、買収が実際にどのように進められ防衛策はどのようなものがあるのかを、事例をあげながら解説しています。
なぜM&Aが行われるかその目的を示し、狙われやすい会社や、買収が実際にどのように進められ防衛策はどのようなものがあるのかを、事例をあげながら解説しています。

 読んで面白いのは海外のもので、とりわけRJRナビスコの、〈経営陣によるMBO〉vs.〈投資顧問会社によるLBO〉の対決劇と、その後フィリップ・モリスに買収されるまでの顛末を追った第1章の「タバコとビスケット」は、スケールの大きさと逆転に次ぐ逆転劇で引き込まれるように読めます。
読んで面白いのは海外のもので、とりわけRJRナビスコの、〈経営陣によるMBO〉vs.〈投資顧問会社によるLBO〉の対決劇と、その後フィリップ・モリスに買収されるまでの顛末を追った第1章の「タバコとビスケット」は、スケールの大きさと逆転に次ぐ逆転劇で引き込まれるように読めます。

 M&Aの実務を中心に解説したもので、自分のレベルが『図解雑学M&A』('00年/ナツメ社)という入門書と併読という感じで選んだぐらいのレベルだったので、本書はやや難しかったし、「戦略」といっても、経営戦略としては抽象的なもので、具体的に詳しく述べられているのは「法務の戦略」ではないかと思ったりして...。
M&Aの実務を中心に解説したもので、自分のレベルが『図解雑学M&A』('00年/ナツメ社)という入門書と併読という感じで選んだぐらいのレベルだったので、本書はやや難しかったし、「戦略」といっても、経営戦略としては抽象的なもので、具体的に詳しく述べられているのは「法務の戦略」ではないかと思ったりして...。
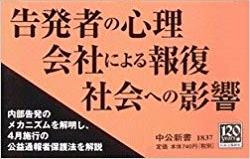

 「公益通報者保護法」は、通報先に優先順位(内部→行政機関→マスコミ等)が定められていて、保護対象も労働者に限られている(派遣労働者や取引先労働者も保護対象に含むが、取引先事業主などは含まない)ことなどから、内部告発を抑制するのではとの批判も多い法律ですが、著者は "公益"という前向きのネーミングを評価し、冷静に条文内容を検証してその意図を汲むとともに、曖昧部分などの問題点も指摘しています。
「公益通報者保護法」は、通報先に優先順位(内部→行政機関→マスコミ等)が定められていて、保護対象も労働者に限られている(派遣労働者や取引先労働者も保護対象に含むが、取引先事業主などは含まない)ことなどから、内部告発を抑制するのではとの批判も多い法律ですが、著者は "公益"という前向きのネーミングを評価し、冷静に条文内容を検証してその意図を汲むとともに、曖昧部分などの問題点も指摘しています。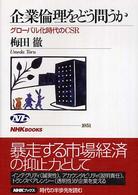


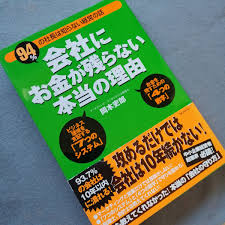
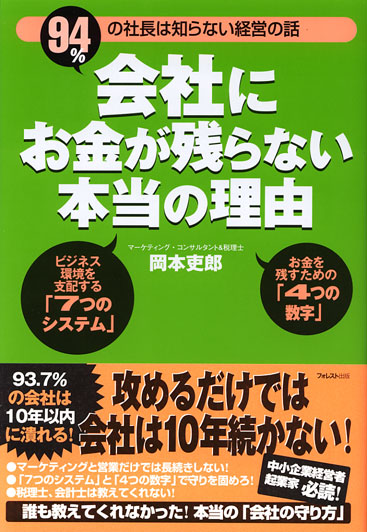
 岡本 吏郎 氏(税理士)
岡本 吏郎 氏(税理士)
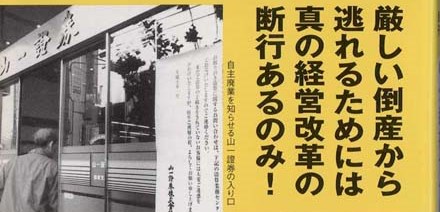

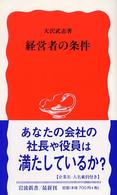
 大沢 武志(1935-2012)
大沢 武志(1935-2012)
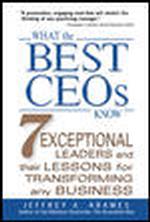
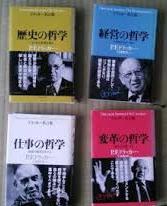


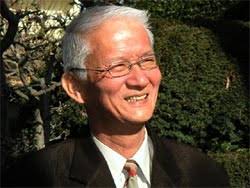 上田 惇生氏(1938-2019)
上田 惇生氏(1938-2019)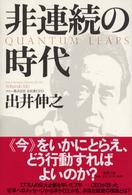

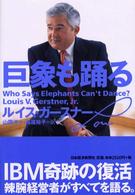
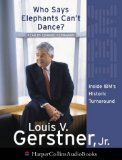




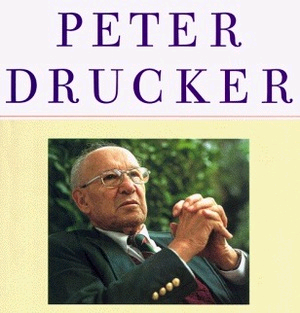 ドラッカーは'70年代に既に、「経済学のフリードマン」と並び称される「経営学の泰斗」としてその名を馳せており、経営に「マネジメント」という考え方を入れたのも、「目標管理」という概念を開発したのもこの人ですが、にも関わらず「経営学者」というより「思想家」に近いかも知れず、'80年に出版されたThe Best of Everything という本では「教祖のベスト」としてその名が挙げられていて、本書なども「啓蒙書」的な感じがします。
ドラッカーは'70年代に既に、「経済学のフリードマン」と並び称される「経営学の泰斗」としてその名を馳せており、経営に「マネジメント」という考え方を入れたのも、「目標管理」という概念を開発したのもこの人ですが、にも関わらず「経営学者」というより「思想家」に近いかも知れず、'80年に出版されたThe Best of Everything という本では「教祖のベスト」としてその名が挙げられていて、本書なども「啓蒙書」的な感じがします。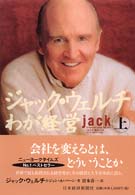

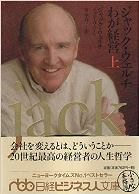
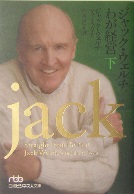
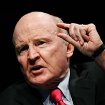


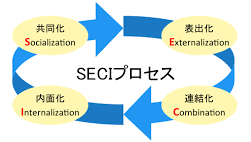
 野中郁次郎・一橋大名誉教授
野中郁次郎・一橋大名誉教授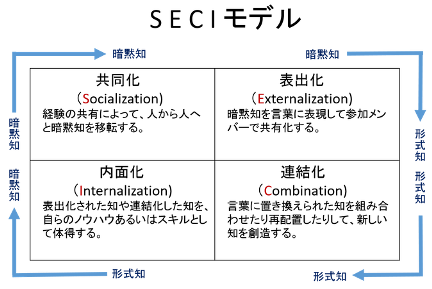 本来の「知識経営」における知識創造のプロセスは、「暗黙知」と「形式知」の相互作用であるべきで、そこで出てくるのが有名な野中理論、「SECI(セキ)」という共同化・表出化・統合化・内面化から成る暗黙知・形式知の変換プロセスですが(「統合化」を「結合化」や「連結化」とすることもある―この理論は先に英文で発表された)、この辺りから、理論的にはきれいだが、実際の経営現場での応用イメージが涌きにくくなるような気がしなくもありません。
本来の「知識経営」における知識創造のプロセスは、「暗黙知」と「形式知」の相互作用であるべきで、そこで出てくるのが有名な野中理論、「SECI(セキ)」という共同化・表出化・統合化・内面化から成る暗黙知・形式知の変換プロセスですが(「統合化」を「結合化」や「連結化」とすることもある―この理論は先に英文で発表された)、この辺りから、理論的にはきれいだが、実際の経営現場での応用イメージが涌きにくくなるような気がしなくもありません。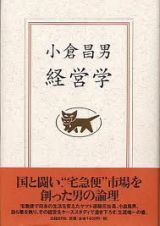
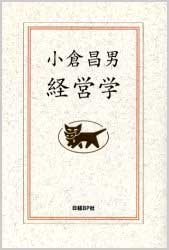
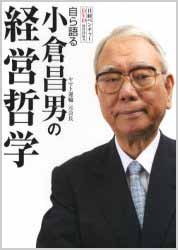

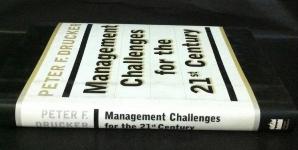

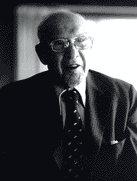
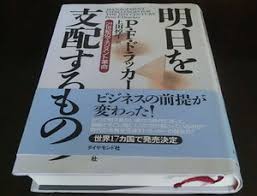 昨年['06年]11月に95歳で亡くなったピーター・F・ドラッカー(1909‐2005)の1999年の著作で(「原題は"Management Challenges for the 21st Century")、世界17カ国で同時出版されベストセラーとなったものですが、章立ては次の通りとなっています。
昨年['06年]11月に95歳で亡くなったピーター・F・ドラッカー(1909‐2005)の1999年の著作で(「原題は"Management Challenges for the 21st Century")、世界17カ国で同時出版されベストセラーとなったものですが、章立ては次の通りとなっています。
 ロナルド・ドーア
ロナルド・ドーア

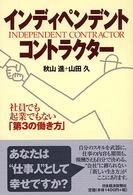

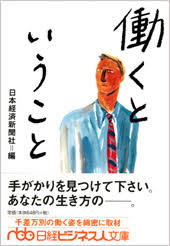
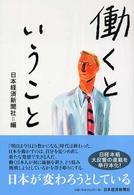
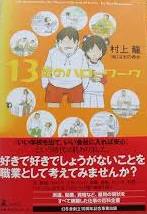

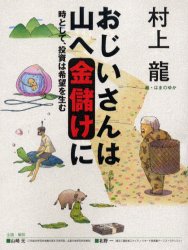
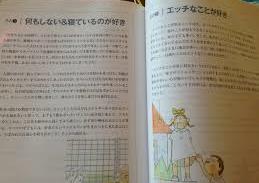 親たちは何故こんなデカくて高い本を買って狭いウチに置いておくのでしょうか?(広いウチに住んでいて大きな書架があるという人もいるだろうし、買わずに図書館で借りたという人も多いとは思うが)
親たちは何故こんなデカくて高い本を買って狭いウチに置いておくのでしょうか?(広いウチに住んでいて大きな書架があるという人もいるだろうし、買わずに図書館で借りたという人も多いとは思うが)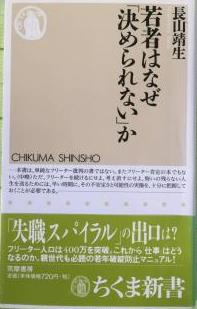
.jpg)

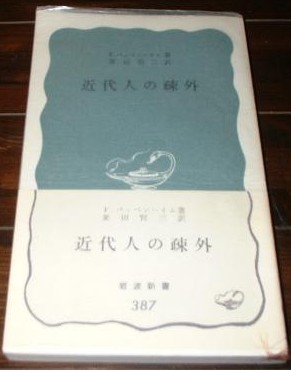 原著は'59年の出版。著者はドイツで経済学、社会学、哲学を学んだ後、ナチスに追われ米国に亡命した人で、本書で展開される著者の「疎外論」は、アメリカ社会心理学の系譜にあるかと思われますが、哲学的かつ広い視野での社会分析がされています。
原著は'59年の出版。著者はドイツで経済学、社会学、哲学を学んだ後、ナチスに追われ米国に亡命した人で、本書で展開される著者の「疎外論」は、アメリカ社会心理学の系譜にあるかと思われますが、哲学的かつ広い視野での社会分析がされています。


 著者は作家であり、東大経済学部を卒業後富士重工業に入社し15年勤務しましたが、在職中に芥川賞候補になった人で、企業とその中で働く個人の人間性や生きることの意味を問う作品を書いていました。
著者は作家であり、東大経済学部を卒業後富士重工業に入社し15年勤務しましたが、在職中に芥川賞候補になった人で、企業とその中で働く個人の人間性や生きることの意味を問う作品を書いていました。
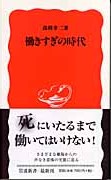
 森岡 孝二 氏(略歴下記)
森岡 孝二 氏(略歴下記) わが国の労働の現場における「働きすぎ」の実態とその原因を、グローバル化、情報時代化、消費資本主義化、規制緩和など様々な観点から分析しています。
わが国の労働の現場における「働きすぎ」の実態とその原因を、グローバル化、情報時代化、消費資本主義化、規制緩和など様々な観点から分析しています。
 橘木俊詔 氏(略歴下記)
橘木俊詔 氏(略歴下記)
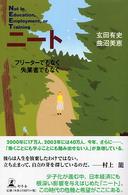

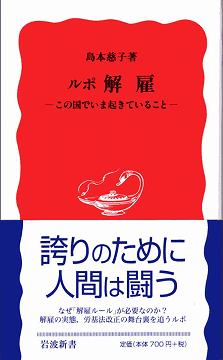
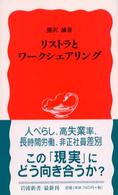
 熊沢 誠 ・甲南大名誉教授
熊沢 誠 ・甲南大名誉教授 日本のワークシェアが難しいと認識しながらも、「同一職種同一賃金」による〈一律型〉ワークシェア(時短)のイメージのもと、男性正社員・女性正社員・女性パートの賃金格差を縮めることを実現可能な範囲で具体的に提示するなど、問題解決に向けた真摯な姿勢が窺えます
日本のワークシェアが難しいと認識しながらも、「同一職種同一賃金」による〈一律型〉ワークシェア(時短)のイメージのもと、男性正社員・女性正社員・女性パートの賃金格差を縮めることを実現可能な範囲で具体的に提示するなど、問題解決に向けた真摯な姿勢が窺えます


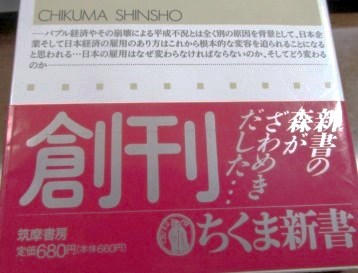
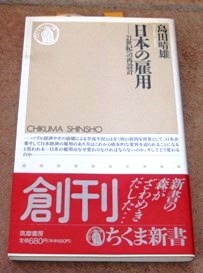
 島田晴雄 氏(略歴下記)
島田晴雄 氏(略歴下記) 平成不況で雇用リストラが進行し、「終身雇用」が崩れるというのが一般的な見方だとすれば、著者はまず「終身雇用」は法的にも制度的にも保障されていたものではない一種の〈幻想〉であるとし、さらに、不況のためと言うよりも、日本経済が成熟段階にきたこと、円高の進行、高齢化社会の到来などのメガトレンドが、従来の雇用システムの見直しを迫っているのだとしています。
平成不況で雇用リストラが進行し、「終身雇用」が崩れるというのが一般的な見方だとすれば、著者はまず「終身雇用」は法的にも制度的にも保障されていたものではない一種の〈幻想〉であるとし、さらに、不況のためと言うよりも、日本経済が成熟段階にきたこと、円高の進行、高齢化社会の到来などのメガトレンドが、従来の雇用システムの見直しを迫っているのだとしています。
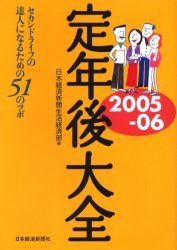
 本書は「定年前」というのがひとつミソですが、その時になって慌てるのではなく、まだ時間のあるうちに予め知識を蓄え、心構えないし準備をしておく、つまり"自分でやる危機管理"という切り口で、今考えておくべき問題をとり上げていて、リストラへの対処から退職後の失業保険や健康保険、マネープラン、年金や生命保険に関すること、さらには老親・妻子を含めた家庭問題や生き方の指針まで、その内容は至れり尽くせりです。
本書は「定年前」というのがひとつミソですが、その時になって慌てるのではなく、まだ時間のあるうちに予め知識を蓄え、心構えないし準備をしておく、つまり"自分でやる危機管理"という切り口で、今考えておくべき問題をとり上げていて、リストラへの対処から退職後の失業保険や健康保険、マネープラン、年金や生命保険に関すること、さらには老親・妻子を含めた家庭問題や生き方の指針まで、その内容は至れり尽くせりです。


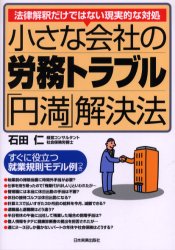


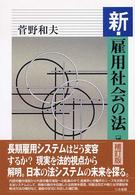


 弁護士グループによる著作で、実務家向けにわかりやすいQ&A方式で書かれています。
弁護士グループによる著作で、実務家向けにわかりやすいQ&A方式で書かれています。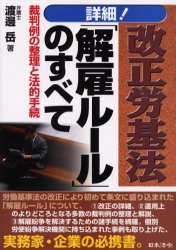
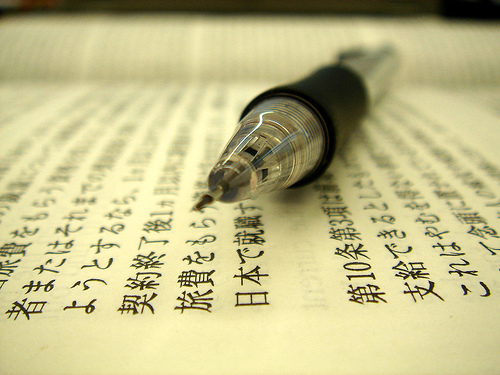

 雇用リストラを行ったり成果主義の浸透する企業内では、窒息するかのようにトラブルや問題行動を起こす社員が増えている傾向を生じやすく、企業側としてはそれらへの対応を一歩誤ると、不当解雇とされて訴訟問題に発展したりする恐れもありますし、セクハラ問題などが表ざたになれば企業イメージや社員のモラールの低下にもつながりかねません。
雇用リストラを行ったり成果主義の浸透する企業内では、窒息するかのようにトラブルや問題行動を起こす社員が増えている傾向を生じやすく、企業側としてはそれらへの対応を一歩誤ると、不当解雇とされて訴訟問題に発展したりする恐れもありますし、セクハラ問題などが表ざたになれば企業イメージや社員のモラールの低下にもつながりかねません。
 前著『Q&A人事労務相談室』('02年/生産性出版)が労務問題全般を扱った「基礎編」であったとすれば、第2弾の本書では、特に賃金・諸手当・退職金にまつわる問題やトラブルにターゲットを絞り、その法規上の扱いや現実の対応を、より突っ込んでわかりやすく書いています。
前著『Q&A人事労務相談室』('02年/生産性出版)が労務問題全般を扱った「基礎編」であったとすれば、第2弾の本書では、特に賃金・諸手当・退職金にまつわる問題やトラブルにターゲットを絞り、その法規上の扱いや現実の対応を、より突っ込んでわかりやすく書いています。
 企業には当然のことながらいろいろな社員がいるもので、何かと人事部にクレームをつけてくる社員の中には、「六法」や労基法関連書籍を肌身離さず持っている社員もいて、総務や人事の担当者の方がこうした社員に対して苦手意識を抱き、及び腰になっているケースが、中小企業などで時々あります。
企業には当然のことながらいろいろな社員がいるもので、何かと人事部にクレームをつけてくる社員の中には、「六法」や労基法関連書籍を肌身離さず持っている社員もいて、総務や人事の担当者の方がこうした社員に対して苦手意識を抱き、及び腰になっているケースが、中小企業などで時々あります。 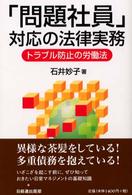

 法律家が「問題社員」という的の絞り方で書いたものとしては嚆矢となったもので、もちろん今でもその内容は古くありません。
法律家が「問題社員」という的の絞り方で書いたものとしては嚆矢となったもので、もちろん今でもその内容は古くありません。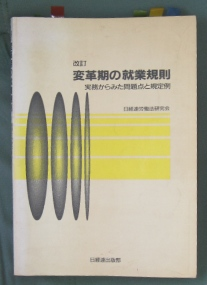

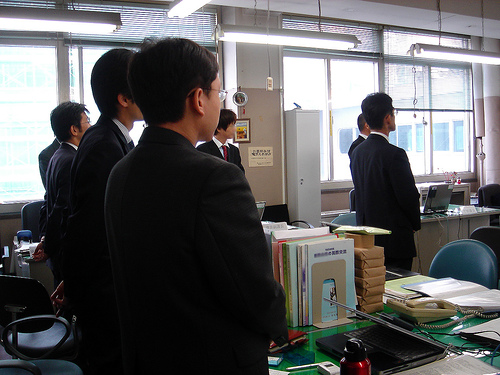

 安西 愈(まさる)弁護士
安西 愈(まさる)弁護士

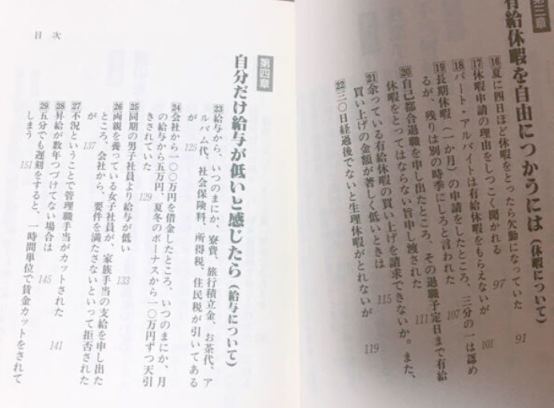 主に社員向けに書かれた労働法入門書で、日常起こりうる労務問題についてアドバイスするという立場で平易に書かれていますが、同時に、使用者たる企業に対しても、従業員を雇用する限りはこれだけのことは知っておいた方がいいですよ、というニュアンスが含まれています。
主に社員向けに書かれた労働法入門書で、日常起こりうる労務問題についてアドバイスするという立場で平易に書かれていますが、同時に、使用者たる企業に対しても、従業員を雇用する限りはこれだけのことは知っておいた方がいいですよ、というニュアンスが含まれています。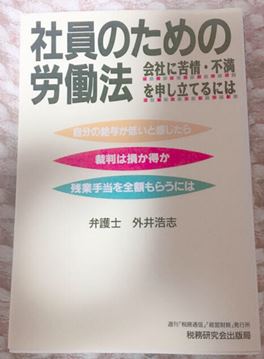 労働法は以降、(本書に書かれている内容レベルではさほど影響がないものの)細部においては改正部分が多くあるので、今時点でこの本自体をわざわざ古書市場に探し求めたりする必要は無いかと思いますが、こうした社員向けに向けたスタンスで書かれたものは、人事部に新たに配属された管理者やスタッフなど、初学者が最初に読む本としても入りやすいのではないかと思います。
労働法は以降、(本書に書かれている内容レベルではさほど影響がないものの)細部においては改正部分が多くあるので、今時点でこの本自体をわざわざ古書市場に探し求めたりする必要は無いかと思いますが、こうした社員向けに向けたスタンスで書かれたものは、人事部に新たに配属された管理者やスタッフなど、初学者が最初に読む本としても入りやすいのではないかと思います。 外井 浩志 氏 (弁護士)
外井 浩志 氏 (弁護士)
 ITエンジニアがとりつかれやすい30の疾患を解説し、症例と対応策を述べています。その中にはITエンてんかん、VDT症候群、ドライアイ、手根管症候群など特にITエンジニアが罹りやすい病気もありますが、頭痛、慢性疲労症候群、自律神経失調症、社会不安障害(対人恐怖症)、うつ病、適応障害、インターネット依存症、過敏性大腸症候群、ディスペプシア(胃のもたれ)、狭心症・心筋梗塞、脳梗塞など、ITエンジニアに限らず働く人のすべてが「心の病」が昂進して発症するおそれがあるものが多く含まれていることがわかります。
ITエンジニアがとりつかれやすい30の疾患を解説し、症例と対応策を述べています。その中にはITエンてんかん、VDT症候群、ドライアイ、手根管症候群など特にITエンジニアが罹りやすい病気もありますが、頭痛、慢性疲労症候群、自律神経失調症、社会不安障害(対人恐怖症)、うつ病、適応障害、インターネット依存症、過敏性大腸症候群、ディスペプシア(胃のもたれ)、狭心症・心筋梗塞、脳梗塞など、ITエンジニアに限らず働く人のすべてが「心の病」が昂進して発症するおそれがあるものが多く含まれていることがわかります。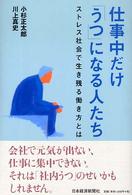
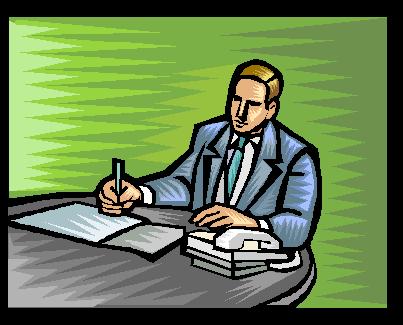 小杉氏は本書で、本当のうつ病(内因性うつ病)は人口の0.3%に過ぎず、今ビジネスの世界で起きているのは「心因性うつ状態」と「適応障害」であるとし、「心因性うつ状態」は死別体験や社会的立場の危機などで生じるが、「適応障害」は特定の人物や状況に遭遇した時だけ生じると言っています。
小杉氏は本書で、本当のうつ病(内因性うつ病)は人口の0.3%に過ぎず、今ビジネスの世界で起きているのは「心因性うつ状態」と「適応障害」であるとし、「心因性うつ状態」は死別体験や社会的立場の危機などで生じるが、「適応障害」は特定の人物や状況に遭遇した時だけ生じると言っています。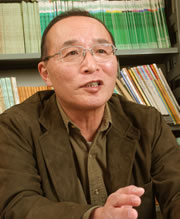 小杉正太郎 氏 (心理学者/略歴下記)
小杉正太郎 氏 (心理学者/略歴下記)  川上 真史 氏 (ワトソン・ワイアット)
川上 真史 氏 (ワトソン・ワイアット)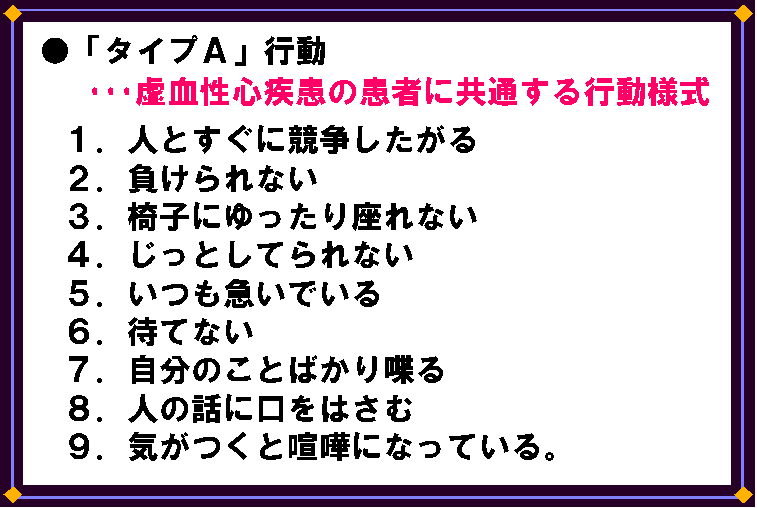

 米国で、虚血性心疾患の患者に共通する行動様式として発見され、カウンセリングの本などにも出てくる言葉ですが、本書では擬人化された動物のイラスト入りでたいへん分かりやすく紹介されていて、思わず笑いそうになりながら、かつ参考になりました。
米国で、虚血性心疾患の患者に共通する行動様式として発見され、カウンセリングの本などにも出てくる言葉ですが、本書では擬人化された動物のイラスト入りでたいへん分かりやすく紹介されていて、思わず笑いそうになりながら、かつ参考になりました。

 経営環境が悪くなり、会社の役員会で「リストラするしかない」「いや、ウチは終身雇用だから...」「じゃあ、退職勧奨ではどうか」などの会話が飛び交うとき、そもそもそうした雇用リストラに関するタームを、役員が共通した正しい認識で用いているかどうか、まず懸念される場合があります。
経営環境が悪くなり、会社の役員会で「リストラするしかない」「いや、ウチは終身雇用だから...」「じゃあ、退職勧奨ではどうか」などの会話が飛び交うとき、そもそもそうした雇用リストラに関するタームを、役員が共通した正しい認識で用いているかどうか、まず懸念される場合があります。
 林 明文 氏
林 明文 氏 雇用調整の考え方と進め方が分かりやすく書かれて、出来ればお世話になりたくない本ではありますが、雇用調整をせざるをえない状況になった時には役立つ実務書です。
雇用調整の考え方と進め方が分かりやすく書かれて、出来ればお世話になりたくない本ではありますが、雇用調整をせざるをえない状況になった時には役立つ実務書です。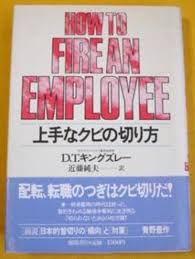
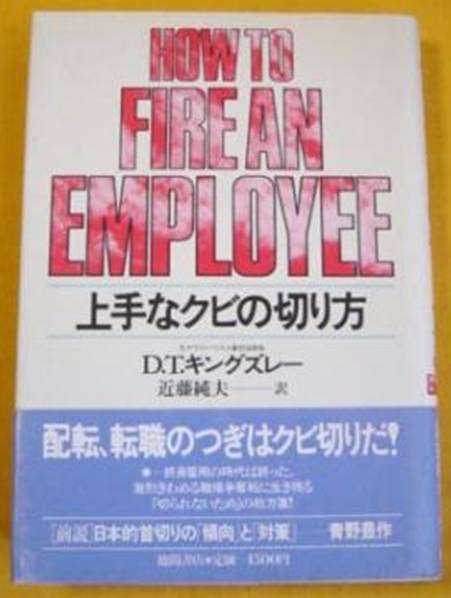
 原題は"How to fire an employee (社員の解雇の仕方)"で、社員側から見れば「冗談じゃないよ」というタイトルですが、前説で経営評論家の青野豊作氏も、この「いかにもアメリカ的な奇書」と言い方をしています。
原題は"How to fire an employee (社員の解雇の仕方)"で、社員側から見れば「冗談じゃないよ」というタイトルですが、前説で経営評論家の青野豊作氏も、この「いかにもアメリカ的な奇書」と言い方をしています。
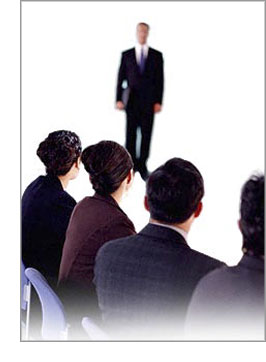

 梅森 浩一 氏 (略歴下記)
梅森 浩一 氏 (略歴下記) 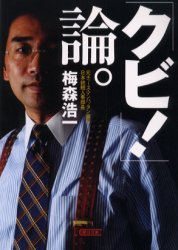

 清水 佑三 氏(日本エス・エイチ・エル社長)
清水 佑三 氏(日本エス・エイチ・エル社長)

 Bill Gates
Bill Gates 米国のコンピュータ会社の採用面接において「パズル問題」が用いられることは伝統的なもののようですが、マイクロソフトのそれは、ビル・ゲイツのパズル好き、パズルによって人の思考能力が測れるという信念に負うところ大であるという印象を、本書を読んで受けました。
米国のコンピュータ会社の採用面接において「パズル問題」が用いられることは伝統的なもののようですが、マイクロソフトのそれは、ビル・ゲイツのパズル好き、パズルによって人の思考能力が測れるという信念に負うところ大であるという印象を、本書を読んで受けました。 面接の第一印象は、はじめの数秒で決まり、その印象が変わることはほとんど無いということはよく言われますが、それを実験データーで示しているのには説得力があり、また、面接の指針として「ストレス面接はしない」「面接評価は申し送りしない」など共感できる部分もありましたが、全体には今ひとつまとまりがなく、本書が結構売れたのはタイトルのお陰ではないかと思います。
面接の第一印象は、はじめの数秒で決まり、その印象が変わることはほとんど無いということはよく言われますが、それを実験データーで示しているのには説得力があり、また、面接の指針として「ストレス面接はしない」「面接評価は申し送りしない」など共感できる部分もありましたが、全体には今ひとつまとまりがなく、本書が結構売れたのはタイトルのお陰ではないかと思います。
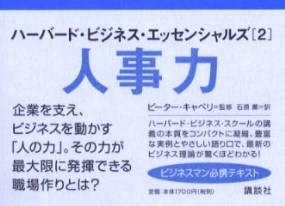


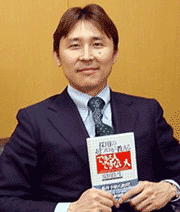 安田佳生 氏
安田佳生 氏 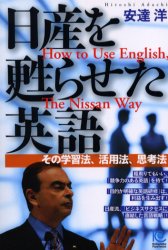


 本書の興味深い特徴の1つは、上司や部下といった年功序列的な階級意識の強い言葉を使うのをできるだけ避けているということです。
本書の興味深い特徴の1つは、上司や部下といった年功序列的な階級意識の強い言葉を使うのをできるだけ避けているということです。 パフォーマンス・コーチング及びメンタリングについての理解を(理論上)深める上で、よく整理された本だと思います。
パフォーマンス・コーチング及びメンタリングについての理解を(理論上)深める上で、よく整理された本だと思います。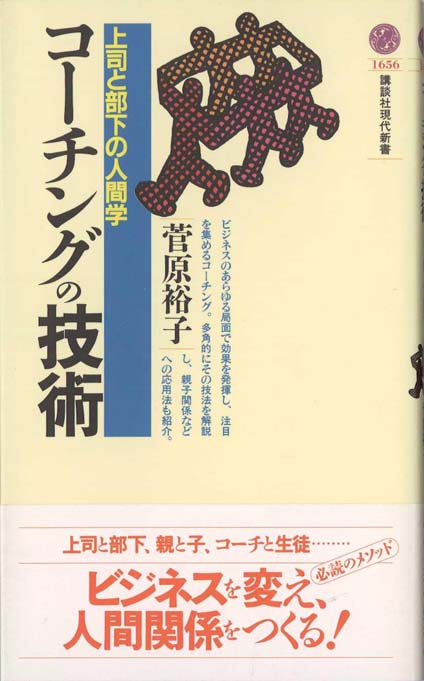
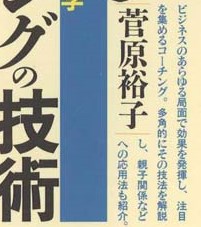

.jpg) 菅原 裕子氏(ワイズコミュニケーション代表取締役)
菅原 裕子氏(ワイズコミュニケーション代表取締役) こうした前提を踏まえたうえで、実践的な事例を挙げつつ、ミラーリング、ベーシング、バックトラッキングといった"技術"論に入る姿勢には好感が持てました。さらに応用として、グループ・コーチング(ファシリテーション)やセルフコーチングにも触れています。結果として網羅する範囲が広い分、それぞれの突っ込みは浅くなったような気がしますが、それはあくまでも入門書であるから仕方がないのかも。
こうした前提を踏まえたうえで、実践的な事例を挙げつつ、ミラーリング、ベーシング、バックトラッキングといった"技術"論に入る姿勢には好感が持てました。さらに応用として、グループ・コーチング(ファシリテーション)やセルフコーチングにも触れています。結果として網羅する範囲が広い分、それぞれの突っ込みは浅くなったような気がしますが、それはあくまでも入門書であるから仕方がないのかも。 コーチングの人間観は、相手をまず「能力を有する存在であると捉える」ということだと著者は述べていますが、カウンセリングとの共通点を感じました(カウンセリングの立場では、コーチングは「職場」への適応を通して個人の発達を支援するものという捉え方をし、一方カウンセリングの場合は、個人の発達を通して、仕事や職場への適応を促進するとされているのですが)。
コーチングの人間観は、相手をまず「能力を有する存在であると捉える」ということだと著者は述べていますが、カウンセリングとの共通点を感じました(カウンセリングの立場では、コーチングは「職場」への適応を通して個人の発達を支援するものという捉え方をし、一方カウンセリングの場合は、個人の発達を通して、仕事や職場への適応を促進するとされているのですが)。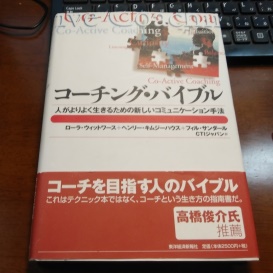

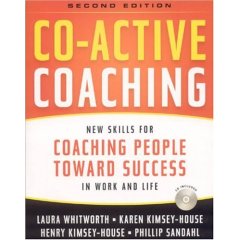
 毎週1回、30分から1時間ぐらいのセッションを繰り返し、それを3ヶ月から半年続けるような"有料"のスタイルが前提となっているようで(休憩の取り方まで書いてある)、プロのコーチを目指す人にとっては良書だと思いますし、将来こうした職業的コーチの需要は増えるでしょう。
毎週1回、30分から1時間ぐらいのセッションを繰り返し、それを3ヶ月から半年続けるような"有料"のスタイルが前提となっているようで(休憩の取り方まで書いてある)、プロのコーチを目指す人にとっては良書だと思いますし、将来こうした職業的コーチの需要は増えるでしょう。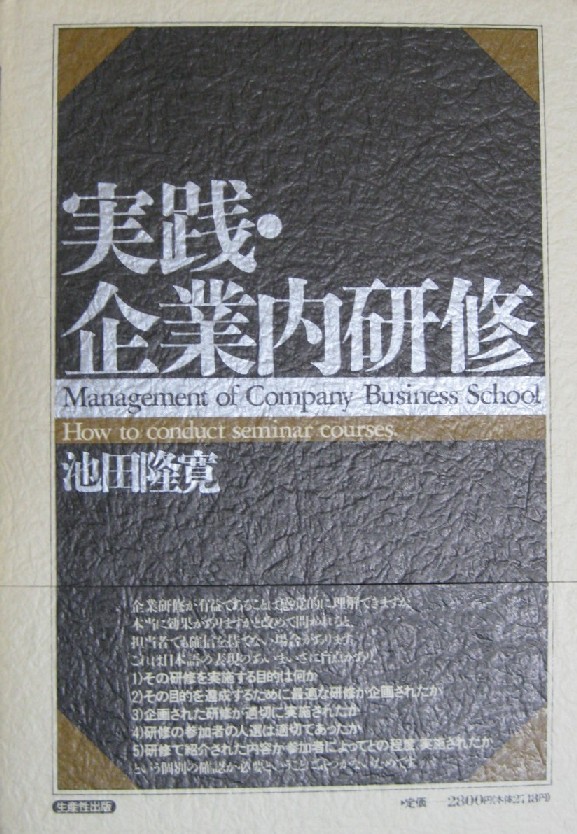

 本書の特徴は、あくまでも"企業内"で独自に研修を企画し実施することを前提にしていることで、それは「企業文化を創造し発展するも目的を外部者に依存するわけにはいかない」という考え方に基づいています。
本書の特徴は、あくまでも"企業内"で独自に研修を企画し実施することを前提にしていることで、それは「企業文化を創造し発展するも目的を外部者に依存するわけにはいかない」という考え方に基づいています。
 「目標管理制度」を「制度」としてだけ導入しても、設定された目標の内容やレベル、評価のあり方等についてスタッフの充分な理解が得られていなければ、運用に際して支障をきたすというのはよく言われることです。
「目標管理制度」を「制度」としてだけ導入しても、設定された目標の内容やレベル、評価のあり方等についてスタッフの充分な理解が得られていなければ、運用に際して支障をきたすというのはよく言われることです。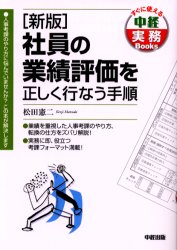
 人事考課は(1)業績考課、(2)意欲・態度考課、(3)能力考課の3つから成るとし、ベースになっているのが職能資格制度であるようなので、後半では業績重視へ転換とその方法を説くものの、全体的にはトラディッショナルな考え方に基づく解説書という印象でした。
人事考課は(1)業績考課、(2)意欲・態度考課、(3)能力考課の3つから成るとし、ベースになっているのが職能資格制度であるようなので、後半では業績重視へ転換とその方法を説くものの、全体的にはトラディッショナルな考え方に基づく解説書という印象でした。
 目標管理について書かれた実務書といえば、まず目標管理とは何かという話が序章にあって、導入方法やシートの作成方法などが述べられていたりするのですが、本書は、その「目標管理とは何か」ということにほぼ丸々1冊費やしており、そうした意味では、タイトルに沿った理論書です。内容の堅さはありますが、成果主義に対する批判のなかで目標管理こそ元凶ではないかという声もある中、今一度その本質を理解しておくことは意味があるのではないかと思われます。
目標管理について書かれた実務書といえば、まず目標管理とは何かという話が序章にあって、導入方法やシートの作成方法などが述べられていたりするのですが、本書は、その「目標管理とは何か」ということにほぼ丸々1冊費やしており、そうした意味では、タイトルに沿った理論書です。内容の堅さはありますが、成果主義に対する批判のなかで目標管理こそ元凶ではないかという声もある中、今一度その本質を理解しておくことは意味があるのではないかと思われます。




 コンピテンシーをベースとした評価制度の設計が中心で、その他に業績評価の方法や基本給の設計方法にも触れ、米国型のベースサラリーの作成方法なども紹介しています。
コンピテンシーをベースとした評価制度の設計が中心で、その他に業績評価の方法や基本給の設計方法にも触れ、米国型のベースサラリーの作成方法なども紹介しています。

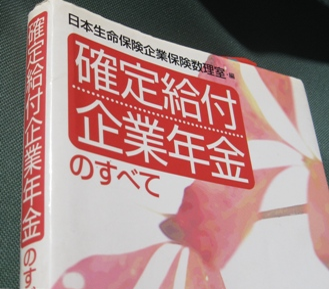
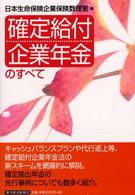




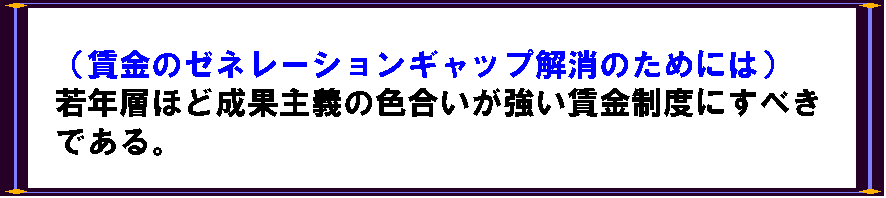



 著者は、中堅・中小企業に適合する人事・賃金制度を紹介した書籍などで定評のある人事コンサルタントですが、本書では、成果主義の問題点を解消する切り札として「職種別賃金」制度の導入を提唱しています。
著者は、中堅・中小企業に適合する人事・賃金制度を紹介した書籍などで定評のある人事コンサルタントですが、本書では、成果主義の問題点を解消する切り札として「職種別賃金」制度の導入を提唱しています。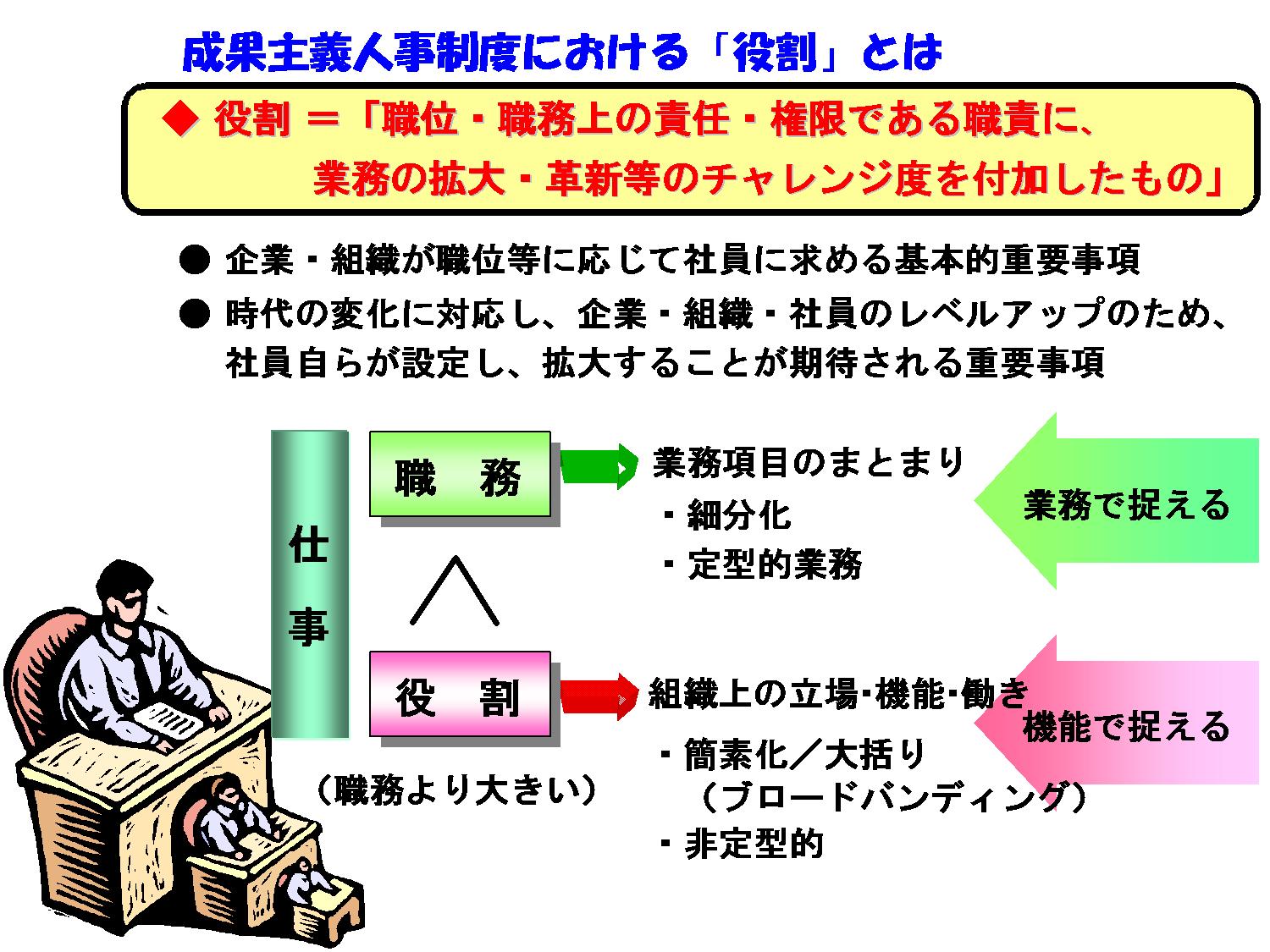
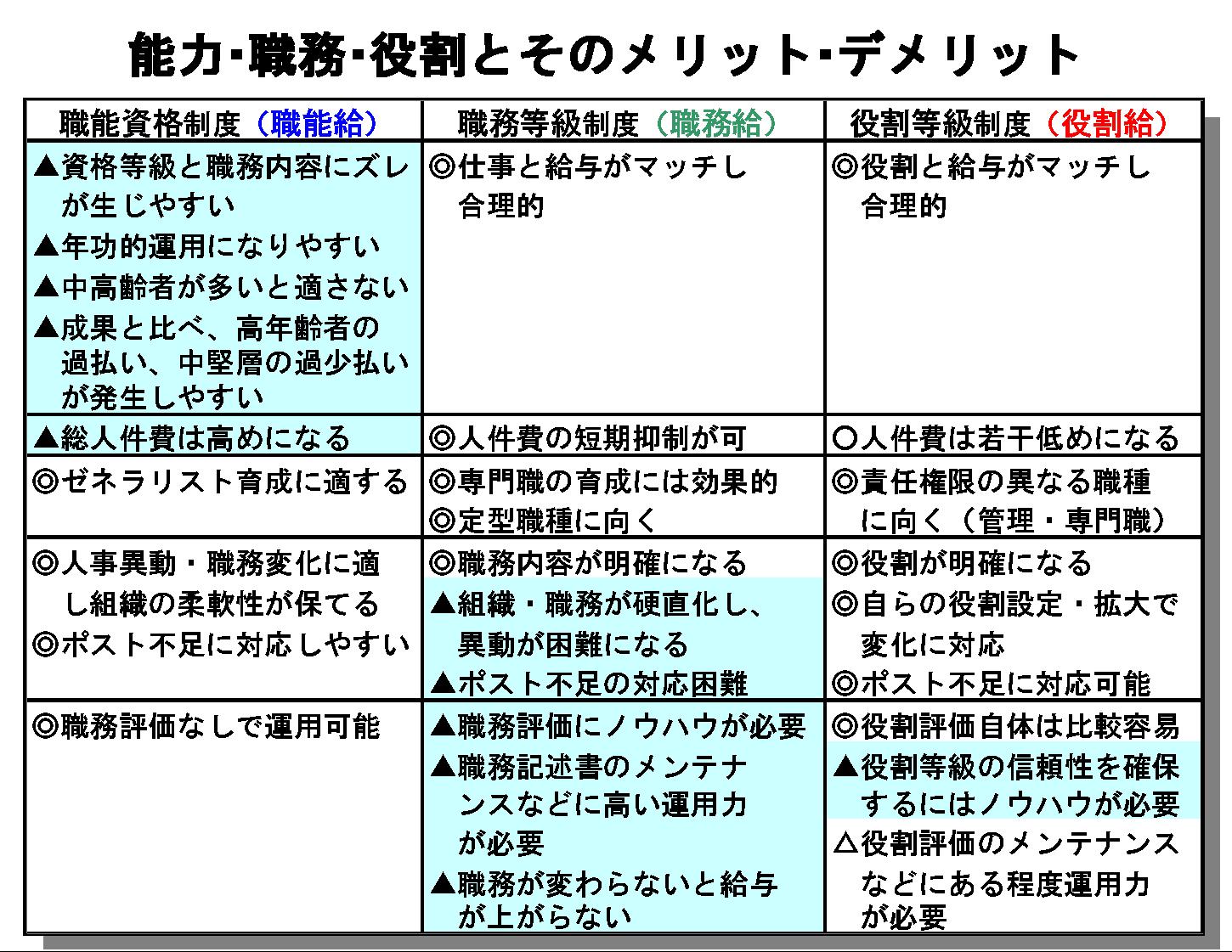 by wadamy
by wadamy 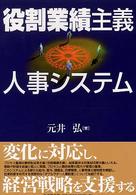


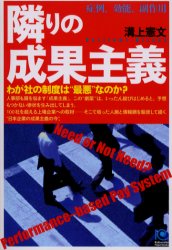
 普段は人事専門誌に賃金・人事制度の取材記事を執筆している著者が、一般向けに書き下ろしたものですが、内容的にはやはり賃金人事制度の"取材記事"であり、端的に言えば「事例集」です。
普段は人事専門誌に賃金・人事制度の取材記事を執筆している著者が、一般向けに書き下ろしたものですが、内容的にはやはり賃金人事制度の"取材記事"であり、端的に言えば「事例集」です。
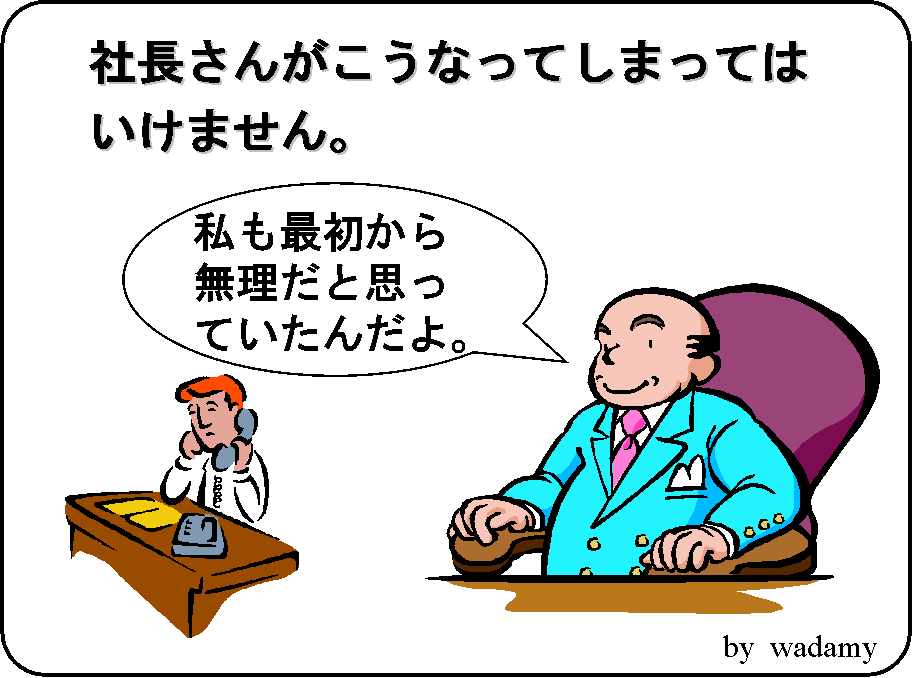 そうした考えに沿って、管理者のレベルアップやトップの強いリーダーシップ、社員との信頼関係などが必要であるとし、プロジェクト方式での人事制度改革の導入の進め方や、成果を出せる風土・環境はどうやって作るのか、目標管理制度や人事考課はどうあるべきかなどを説いています。
そうした考えに沿って、管理者のレベルアップやトップの強いリーダーシップ、社員との信頼関係などが必要であるとし、プロジェクト方式での人事制度改革の導入の進め方や、成果を出せる風土・環境はどうやって作るのか、目標管理制度や人事考課はどうあるべきかなどを説いています。
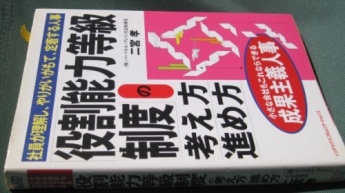
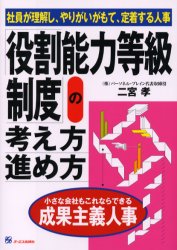

.jpg) 浜辺 陽一郎 氏(弁護士・早稲田大学大学院法務研究科教授)
浜辺 陽一郎 氏(弁護士・早稲田大学大学院法務研究科教授)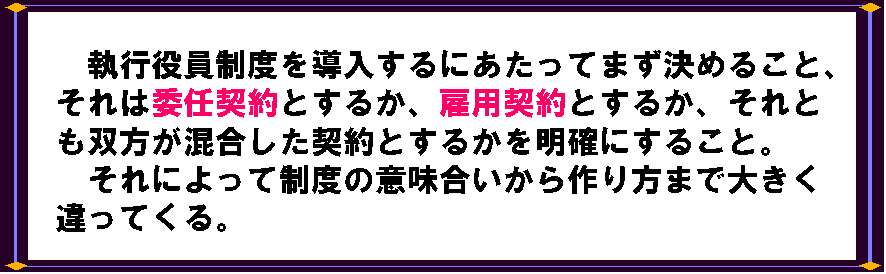 執行役員制度について、執行役との違いも含めた法的な位置づけから、規程の策定など導入の実務までが、詳しくわかりやすく書かれています。
執行役員制度について、執行役との違いも含めた法的な位置づけから、規程の策定など導入の実務までが、詳しくわかりやすく書かれています。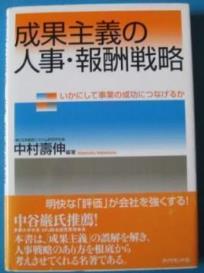

 本書では、成果主義の人事・報酬システムをいかにして成功させるかということを「戦略」的視点から捉え、業績と人件費のバランスを図り、適正総額人件費の枠内で報酬を支払うためには、資格・等級はどうすべきか、賞与や月例給与はどうすべきか、業績評価はどう改革すべきかなどについて、具体的な制度策定や運用に踏み込んで述べられています。
本書では、成果主義の人事・報酬システムをいかにして成功させるかということを「戦略」的視点から捉え、業績と人件費のバランスを図り、適正総額人件費の枠内で報酬を支払うためには、資格・等級はどうすべきか、賞与や月例給与はどうすべきか、業績評価はどう改革すべきかなどについて、具体的な制度策定や運用に踏み込んで述べられています。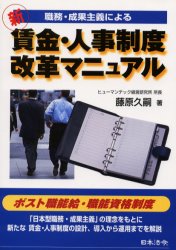
 本書は、アメリカの賃金・人事制度の特長から積極的に学びつつ、日本的な伝統を生かした日本型職務・成果主義を、豊富なコンサルティング経験に基づいて具体的に提唱しています。
本書は、アメリカの賃金・人事制度の特長から積極的に学びつつ、日本的な伝統を生かした日本型職務・成果主義を、豊富なコンサルティング経験に基づいて具体的に提唱しています。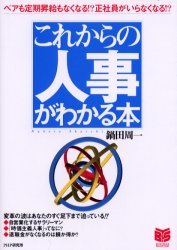
 本書前書きにもありますが、人事制度の中でも特に賃金制度(報酬政策)の紹介に重点を置いて書かれています。
本書前書きにもありますが、人事制度の中でも特に賃金制度(報酬政策)の紹介に重点を置いて書かれています。
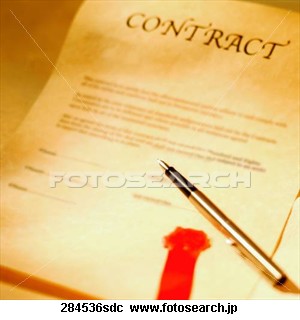 著者は本書において、人件費の構造改革の要を「人件費の変動費化」に置き、契約社員制度、社内請負契約、社内自立法人化、戦略的配置転換、戦略別会社設立などを提唱しています。
著者は本書において、人件費の構造改革の要を「人件費の変動費化」に置き、契約社員制度、社内請負契約、社内自立法人化、戦略的配置転換、戦略別会社設立などを提唱しています。
 本書では、人事・賃金制度のこれからを展望したうえで(第1章)、人事制度を策定するにあたっては、まず仕事をベースとする「職務基準」でいくのか能力をベースとする「職能基準」でいくのか、両者をミックスさせたものにするかを決めなければならないとし、それぞれの等級制度の具体例で説明しています(第2章)。
本書では、人事・賃金制度のこれからを展望したうえで(第1章)、人事制度を策定するにあたっては、まず仕事をベースとする「職務基準」でいくのか能力をベースとする「職能基準」でいくのか、両者をミックスさせたものにするかを決めなければならないとし、それぞれの等級制度の具体例で説明しています(第2章)。
 戦略人材コンサルのウイリアムマーサー社(現マーサーヒューマンリソースコンサルティング社)による本書は、SHRM(戦略的人材マネジメント)がテーマですが、制度に踏み込んで書かれているため、書名どおり実践的です。
戦略人材コンサルのウイリアムマーサー社(現マーサーヒューマンリソースコンサルティング社)による本書は、SHRM(戦略的人材マネジメント)がテーマですが、制度に踏み込んで書かれているため、書名どおり実践的です。
 執行役員制=大企業のものというイメージがある中で、中堅・中小企業に対する経営改革、取締役制度改革の一環としての執行役員制を、そのメリットや形態と併せて提唱しています。
執行役員制=大企業のものというイメージがある中で、中堅・中小企業に対する経営改革、取締役制度改革の一環としての執行役員制を、そのメリットや形態と併せて提唱しています。
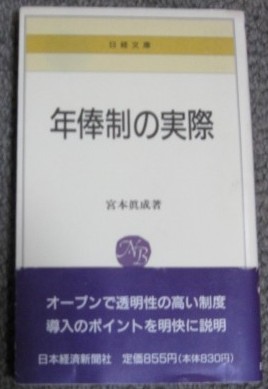

 年俸制は、大企業の管理職層を中心に'90年代中盤から2000年にかけて一気に導入が進みましたが、年俸制にテーマを絞った実務者向けの書籍は意外に少ないのではないかと思います。
年俸制は、大企業の管理職層を中心に'90年代中盤から2000年にかけて一気に導入が進みましたが、年俸制にテーマを絞った実務者向けの書籍は意外に少ないのではないかと思います。
 大久保幸夫 氏
大久保幸夫 氏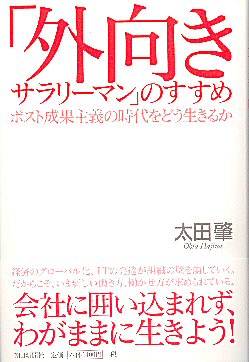
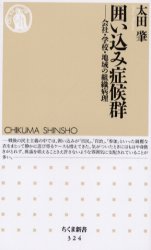

 舞田竜宣 氏
舞田竜宣 氏 "10年後"と言うよりは、現在の人事制度の方向性とこれからの人事部のあり方といったところでしょうか。
"10年後"と言うよりは、現在の人事制度の方向性とこれからの人事部のあり方といったところでしょうか。
 著者は本書で、成果主義は人材育成機能を破壊し、すべての成果主義は失敗すると断定し、 〈育てる経営〉を目ざすならば、社員の生活を守り、次の仕事の内容で報いるシステム「日本型年功制」を再構築すべきだと主張しています。
著者は本書で、成果主義は人材育成機能を破壊し、すべての成果主義は失敗すると断定し、 〈育てる経営〉を目ざすならば、社員の生活を守り、次の仕事の内容で報いるシステム「日本型年功制」を再構築すべきだと主張しています。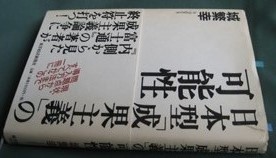
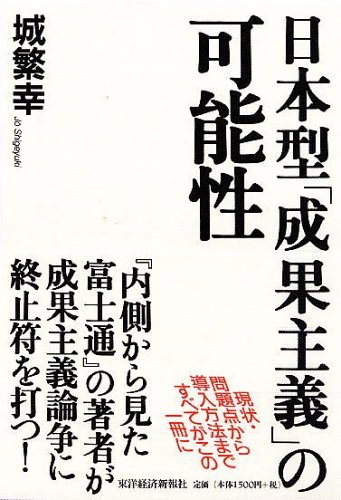
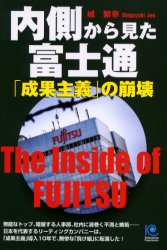
 城 繁幸 氏
城 繁幸 氏 
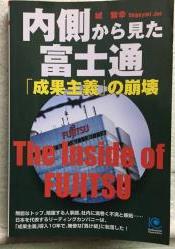
 城繁幸氏
城繁幸氏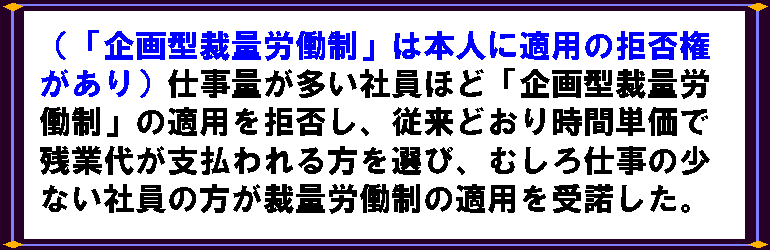 元富士通の人事部社員の手によるもので暴露本という見方もできますが、「成果主義」の導入に伴う様々な問題点を具体的に指摘していて参考になりました。著者自身は「成果主義」を否定しているのではなく(冒頭にはそのメリットが述べられている)、ただそれが富士通の中ではうまくいかなかったと...。
元富士通の人事部社員の手によるもので暴露本という見方もできますが、「成果主義」の導入に伴う様々な問題点を具体的に指摘していて参考になりました。著者自身は「成果主義」を否定しているのではなく(冒頭にはそのメリットが述べられている)、ただそれが富士通の中ではうまくいかなかったと...。
 産学協同(主催は人材会社)で行われたCHO(チーフ・ヒューマン・オフィサー)研究会の成果をまとめたものです。
産学協同(主催は人材会社)で行われたCHO(チーフ・ヒューマン・オフィサー)研究会の成果をまとめたものです。 基本的には、これからのCHO(「人事部(長)」と言った方がいい)の役割が、「管理エキスパート」であることに加えて、「戦略パートナー・変革エージェント」であるべきだという本書の趣旨には賛同します(「サーバント・リーダー」という言葉は、あまり好きになれない。一方で「従業員チャンピオン」であるべきも言っているし)。
基本的には、これからのCHO(「人事部(長)」と言った方がいい)の役割が、「管理エキスパート」であることに加えて、「戦略パートナー・変革エージェント」であるべきだという本書の趣旨には賛同します(「サーバント・リーダー」という言葉は、あまり好きになれない。一方で「従業員チャンピオン」であるべきも言っているし)。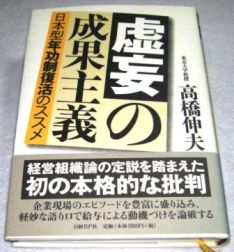
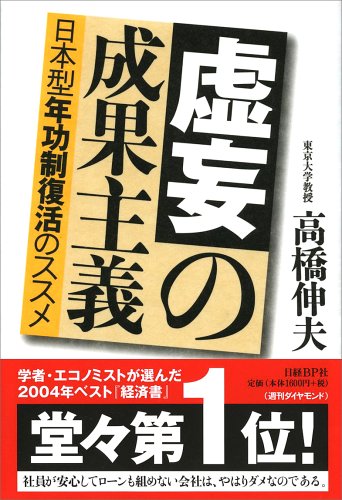
 高橋 伸夫 氏(略歴下記)
高橋 伸夫 氏(略歴下記)





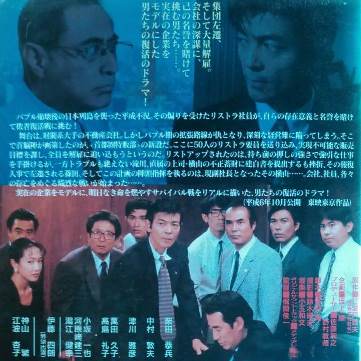

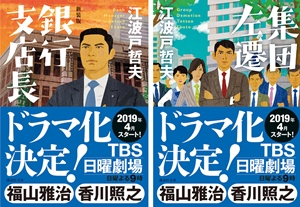
 「集団左遷」TBS系日曜劇場(2019年4月21日~6月23日(全10話)
「集団左遷」TBS系日曜劇場(2019年4月21日~6月23日(全10話)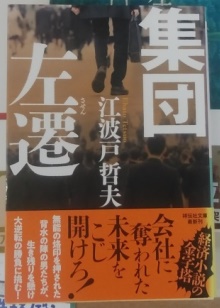 『集団左遷』...【2018年文庫化[祥伝社文庫]/2019年文庫化[講談社文庫]】
『集団左遷』...【2018年文庫化[祥伝社文庫]/2019年文庫化[講談社文庫]】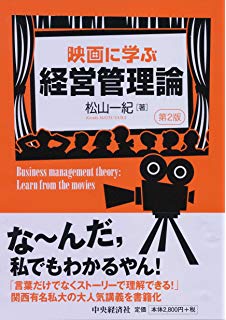

 内容は、前半7割が成果主義について、後半3割がキャリア創造についてといったところです。成果主義が陥りやすい過ちを、米国の職務主義の失敗やビジョニングによる成功例などを引き合いにしながら指摘しています。
内容は、前半7割が成果主義について、後半3割がキャリア創造についてといったところです。成果主義が陥りやすい過ちを、米国の職務主義の失敗やビジョニングによる成功例などを引き合いにしながら指摘しています。 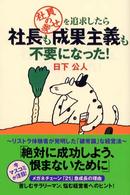
 日下 公人 氏
日下 公人 氏 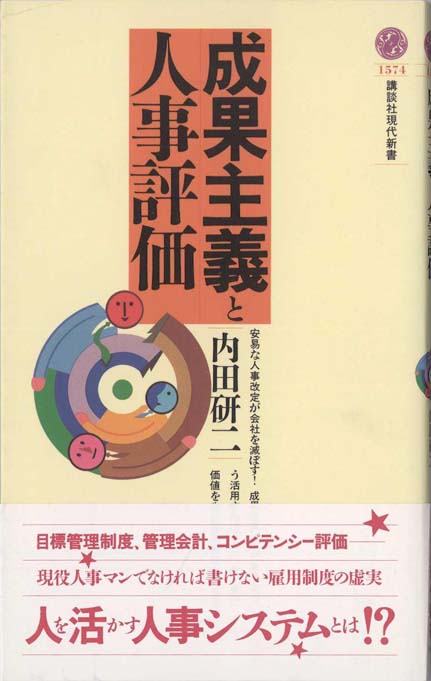

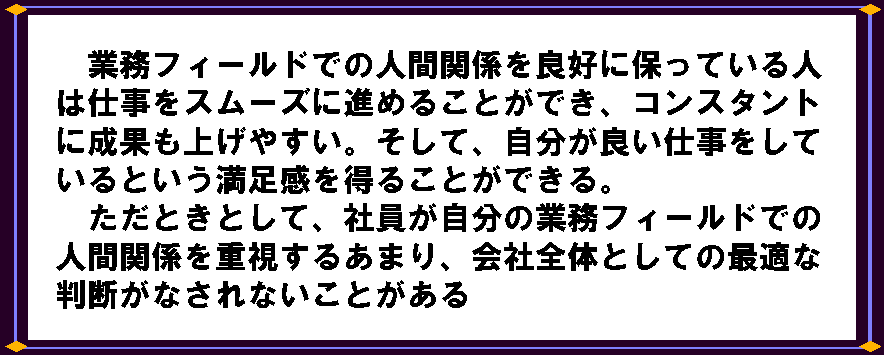
 企業内での人事実務の経験者の手による本で、内容は、著者が都銀から証券子会社に人事部課長として出向していたときの経験がベースになっているのではないかと思われますが、「成果主義」や「人事評価」に派生する問題に対しての、担当者として真摯な取り組み姿勢を感じます。
企業内での人事実務の経験者の手による本で、内容は、著者が都銀から証券子会社に人事部課長として出向していたときの経験がベースになっているのではないかと思われますが、「成果主義」や「人事評価」に派生する問題に対しての、担当者として真摯な取り組み姿勢を感じます。
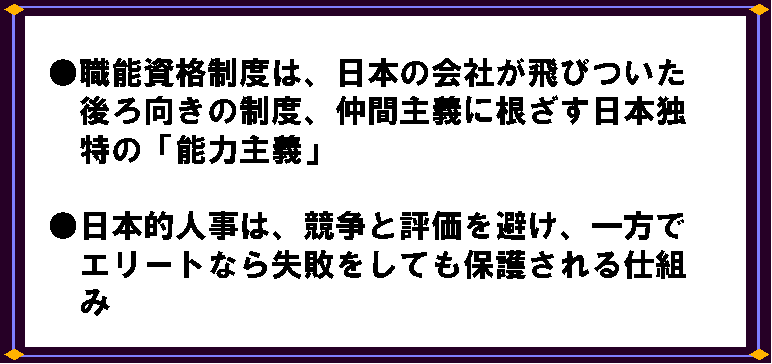


.gif) 清家 篤 氏 (略歴下記)
清家 篤 氏 (略歴下記) 著者は「生涯現役社会」の提唱者であり、本書でも定年制の非合理性とそれを廃止することのメリットを説いています。では定年制がなぜあるかというと、年功賃金での長期の収支勘定合わせのためにあり、また企業に雇用調整の自由度が少ないのもその理由であると。
著者は「生涯現役社会」の提唱者であり、本書でも定年制の非合理性とそれを廃止することのメリットを説いています。では定年制がなぜあるかというと、年功賃金での長期の収支勘定合わせのためにあり、また企業に雇用調整の自由度が少ないのもその理由であると。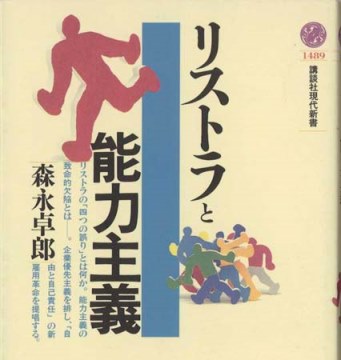
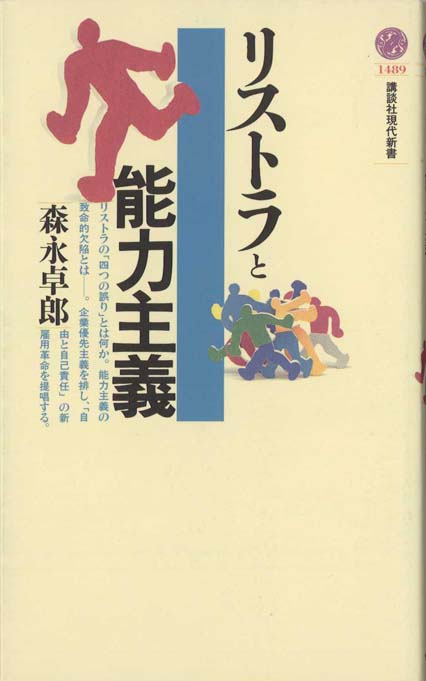

 森永 卓郎 氏(略歴下記)
森永 卓郎 氏(略歴下記) 本書で言う「能力主義」とは、本文中にもある通り「成果主義」のことを指しています。どうしてこういうタイトルにしたかと言うと、出版当時においては「成果主義」という言葉がまだ"市民権"を得ていないという著者の判断だったそうです。
本書で言う「能力主義」とは、本文中にもある通り「成果主義」のことを指しています。どうしてこういうタイトルにしたかと言うと、出版当時においては「成果主義」という言葉がまだ"市民権"を得ていないという著者の判断だったそうです。
 牧野 昇 氏 (略歴下記)
牧野 昇 氏 (略歴下記) 本書は'99年の出版ですが、終身雇用・年功序列の崩壊、失業率の上昇、転職・独立の気運、雇用の流動化により変化していく会社と社員の関係、多様化するだろう就業形態を見据え、そうした中で企業はどうすれば良いのか、また個人は「プロ人材」としてどう生きていくかを提唱したものでした。
本書は'99年の出版ですが、終身雇用・年功序列の崩壊、失業率の上昇、転職・独立の気運、雇用の流動化により変化していく会社と社員の関係、多様化するだろう就業形態を見据え、そうした中で企業はどうすれば良いのか、また個人は「プロ人材」としてどう生きていくかを提唱したものでした。  これを読み、なるほど、わかりやすく的確な指摘だと思った記憶があります。
これを読み、なるほど、わかりやすく的確な指摘だと思った記憶があります。


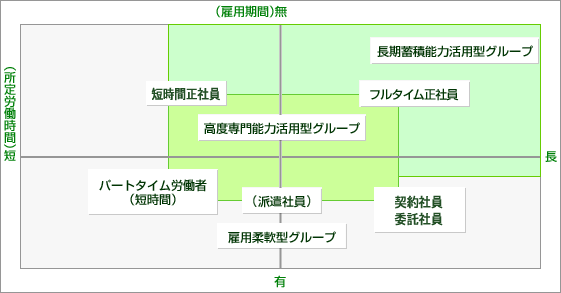 この中で最も知られるところとなったのが、
この中で最も知られるところとなったのが、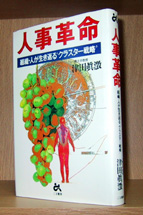
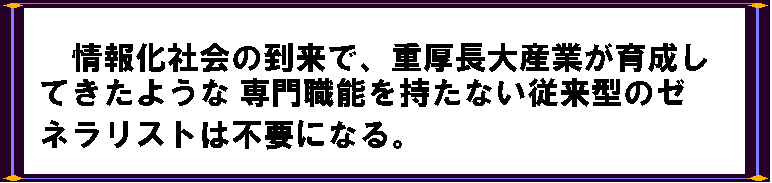


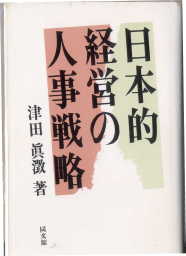

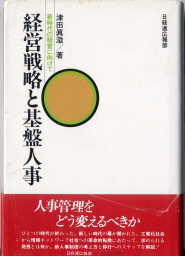
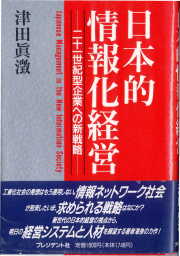


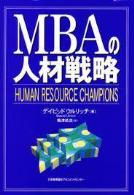
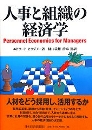
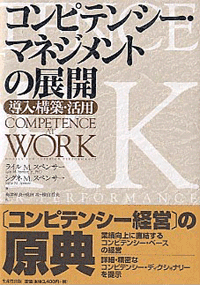


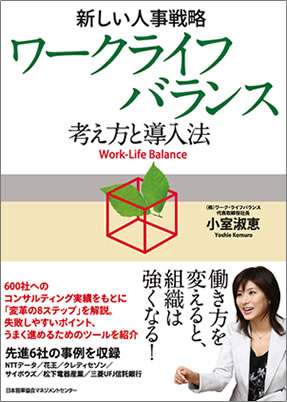


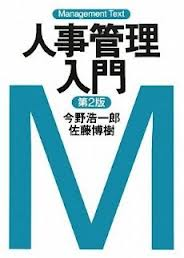


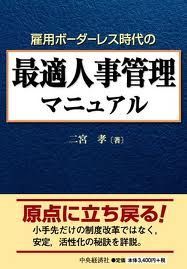



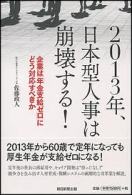







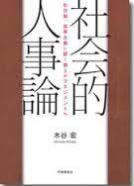
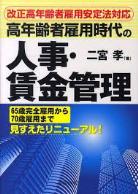
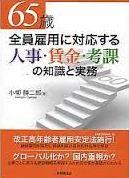




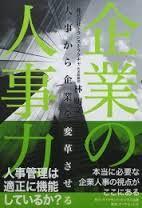

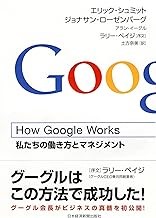

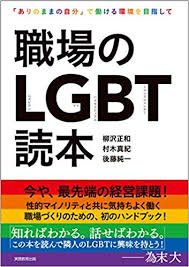
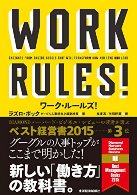

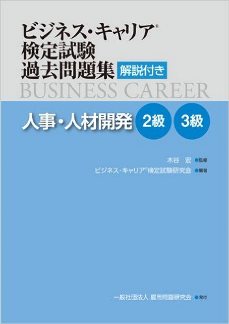
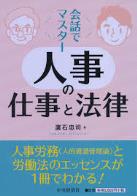


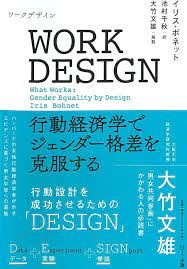
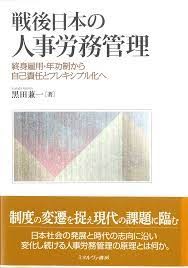
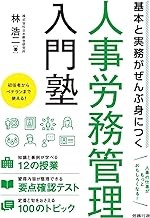



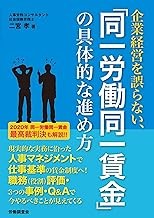



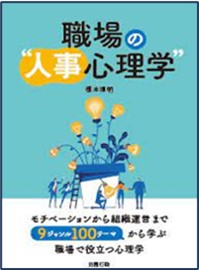
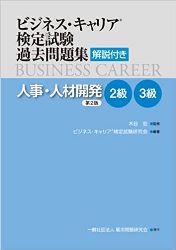

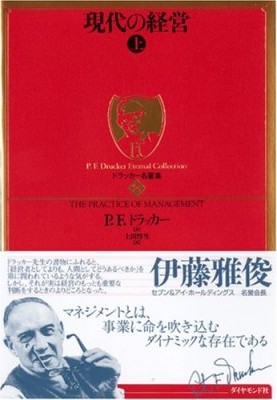
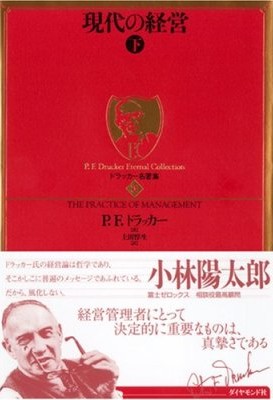

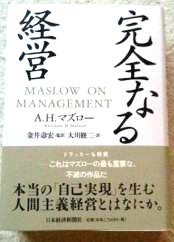

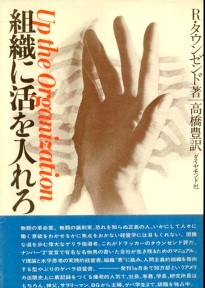

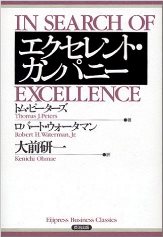
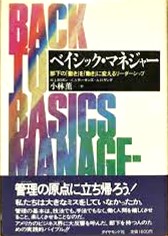
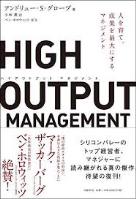

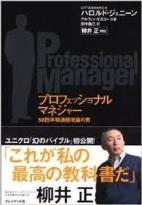


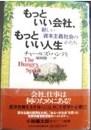
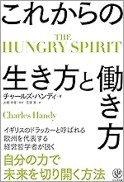






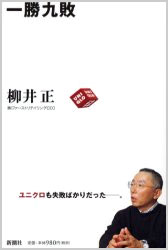

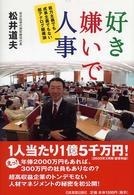




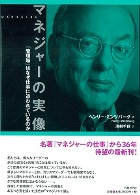


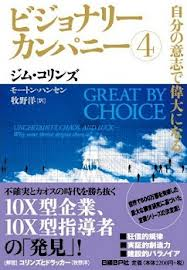


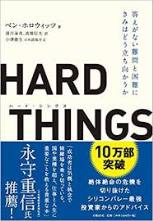

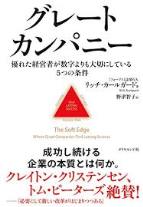

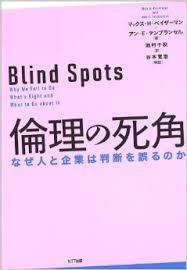








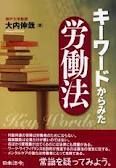
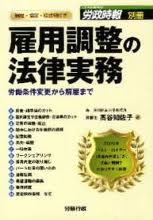






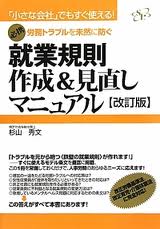




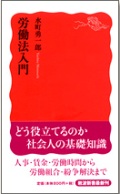
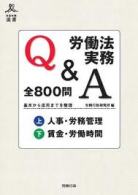








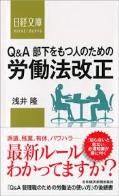
![プレップ労働法 [第5版].jpg](http://hurec.bz/book-movie/%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%97%E5%8A%B4%E5%83%8D%E6%B3%95%20%EF%BC%BB%E7%AC%AC%EF%BC%95%E7%89%88%EF%BC%BD.jpg)
![水町 勇一郎 『労働法 [第7版]』.jpg](http://hurec.bz/book-movie/%E6%B0%B4%E7%94%BA%20%E5%8B%87%E4%B8%80%E9%83%8E%20%20%E3%80%8E%E5%8A%B4%E5%83%8D%E6%B3%95%20%EF%BC%BB%E7%AC%AC%EF%BC%97%E7%89%88%EF%BC%BD%E3%80%8F.jpg)
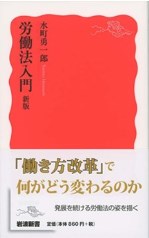


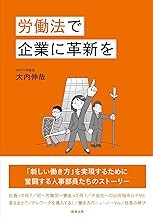

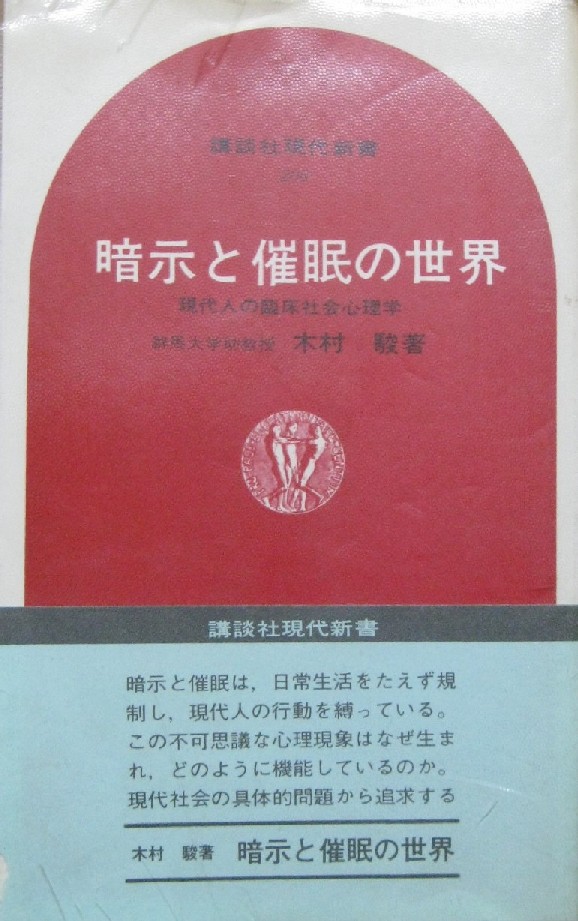

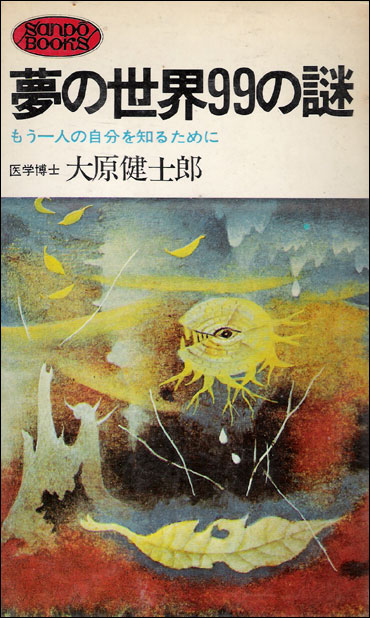
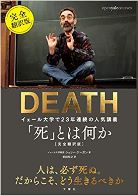
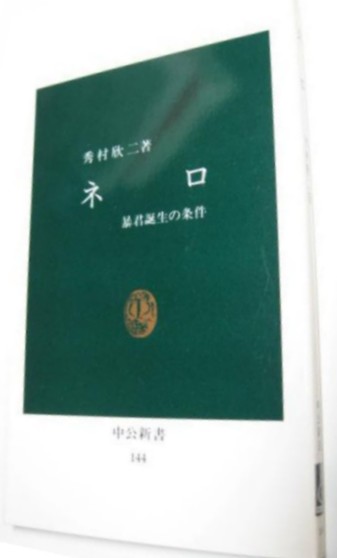

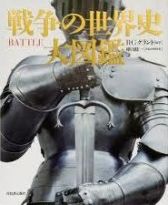

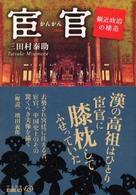
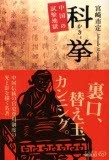
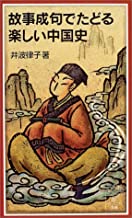


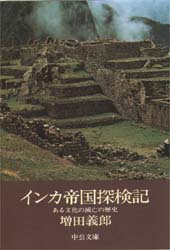


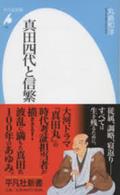

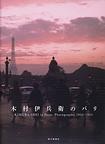
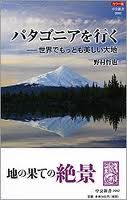
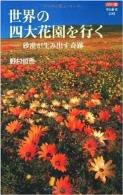
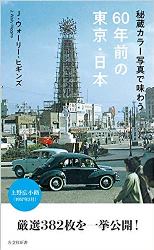
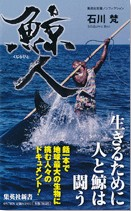

.jpg)

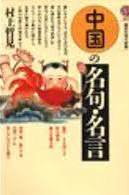
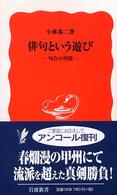
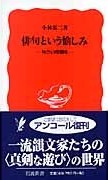
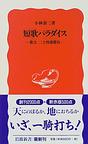



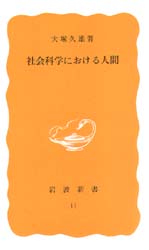
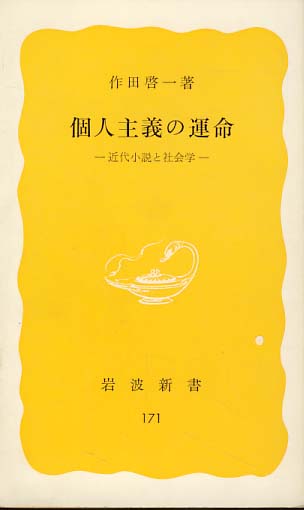
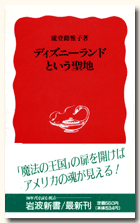
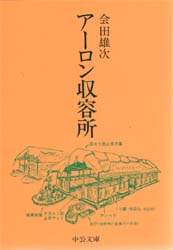
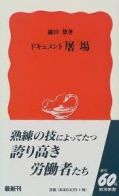

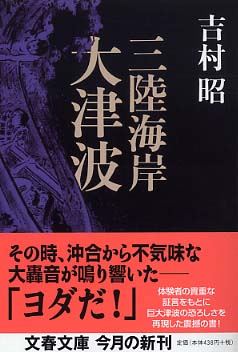
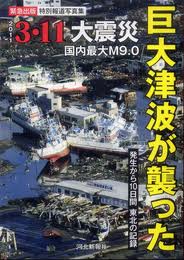
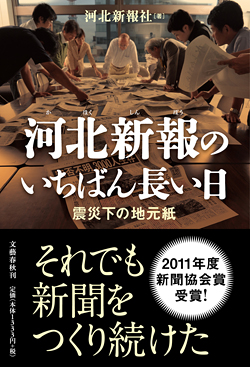

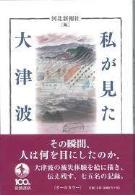
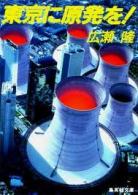
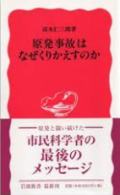




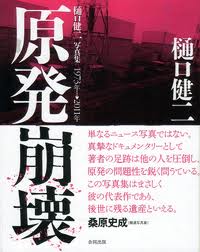

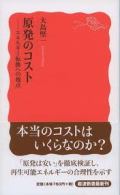
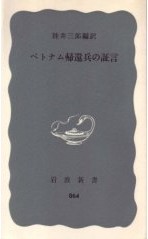

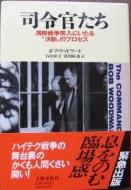
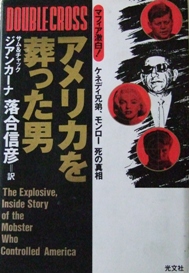
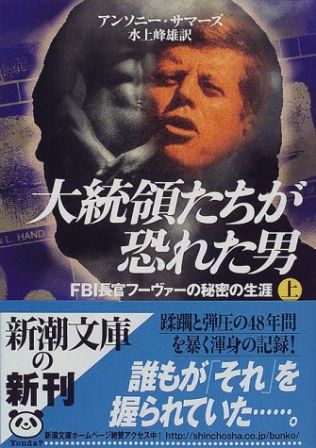
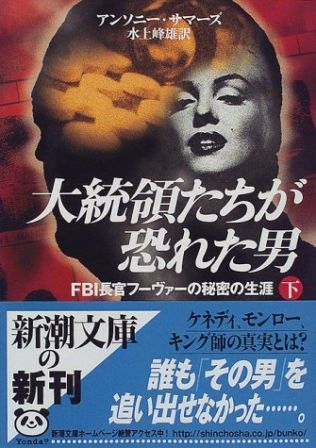
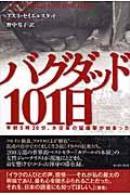
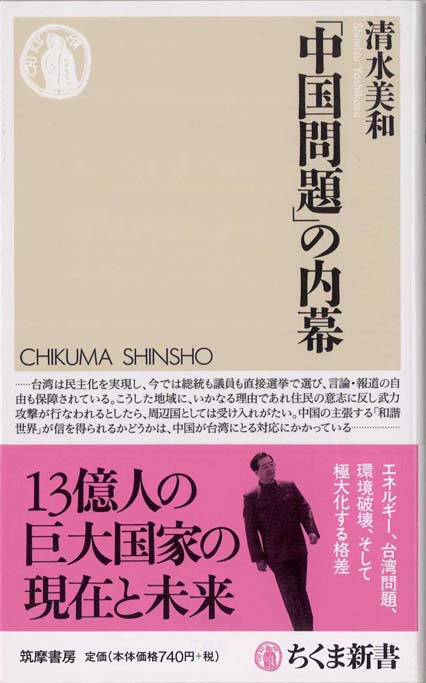
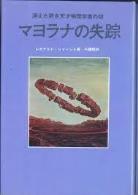
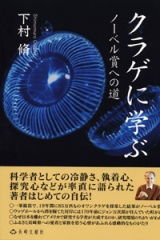
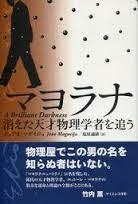
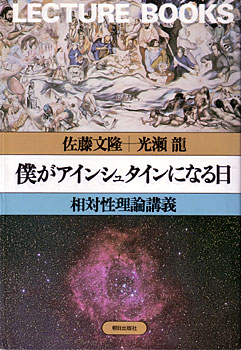






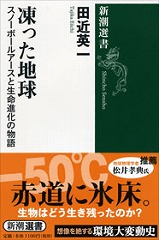


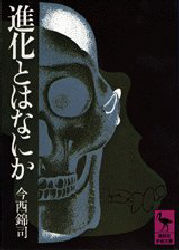



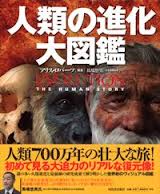
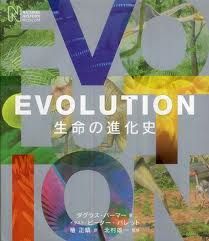
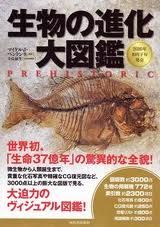

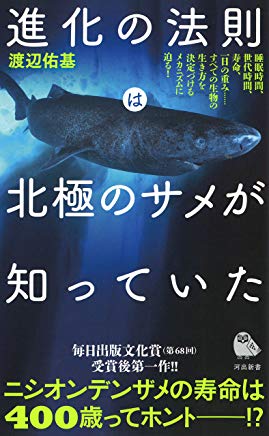


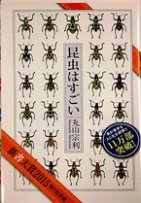



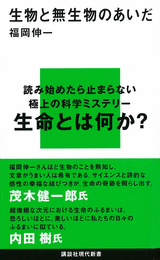
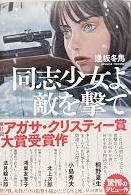

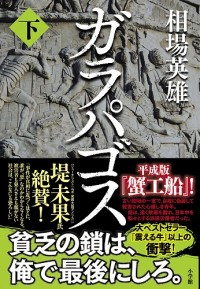

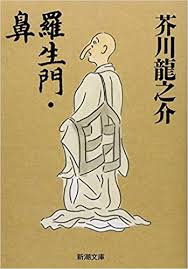
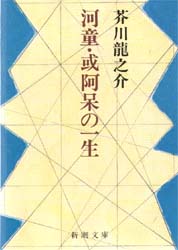

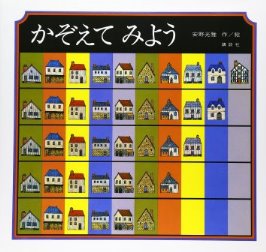
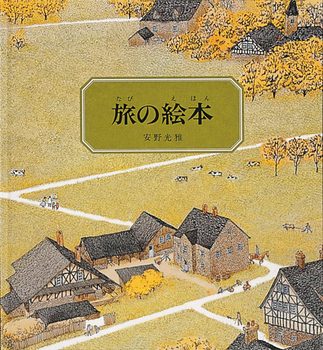

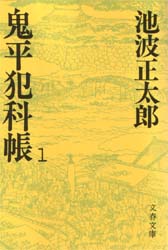
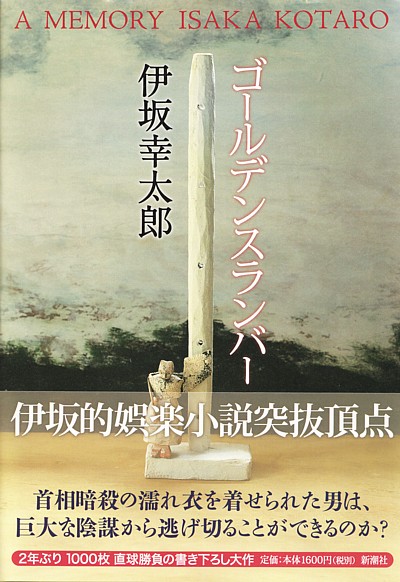
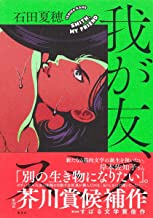
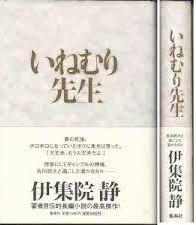
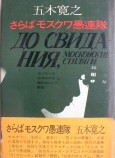

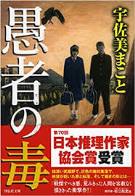


.jpg)
.jpg)

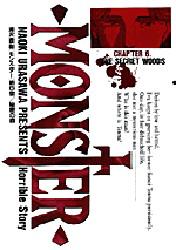






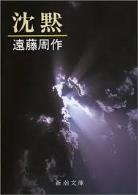

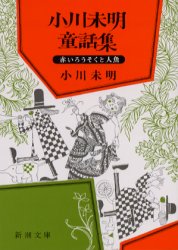
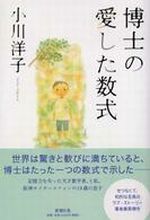
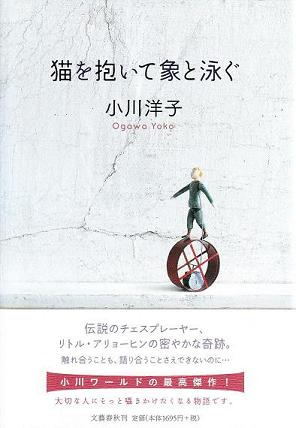
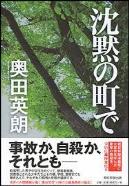
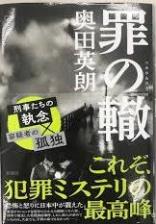
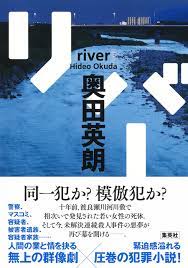
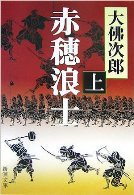
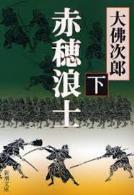
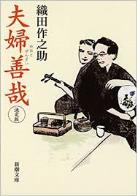
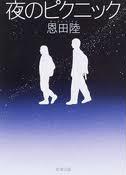

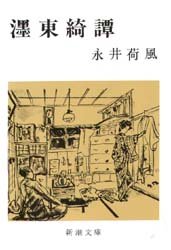
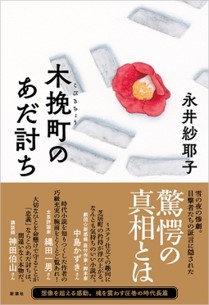

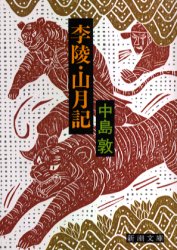
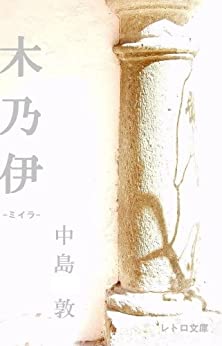
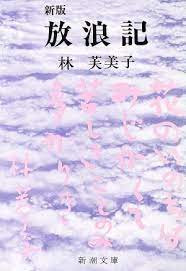
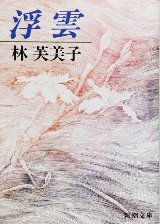
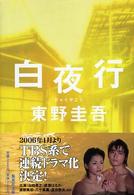

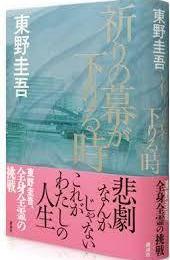
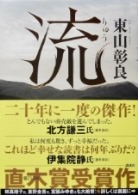
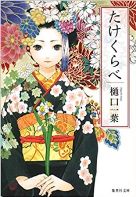


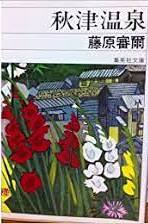
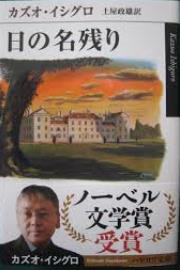
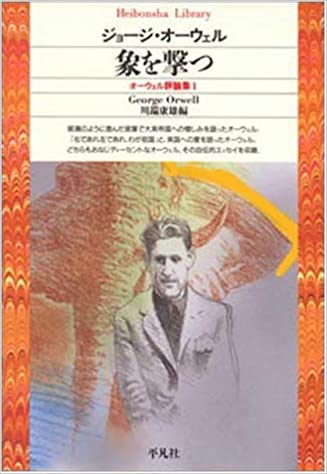

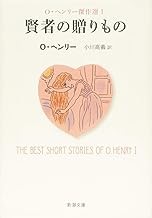
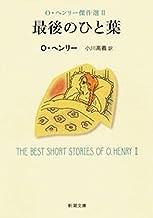



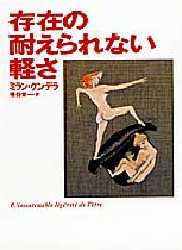



上.jpg)
下.jpg)
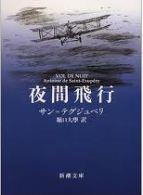
.jpg)
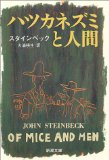
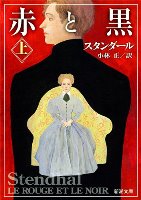
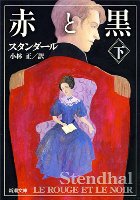

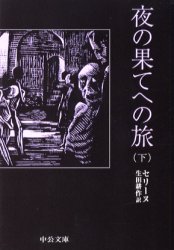

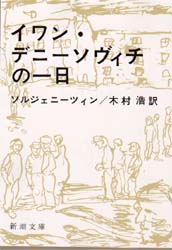
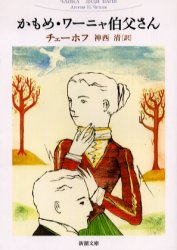
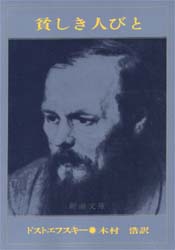

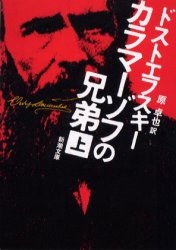

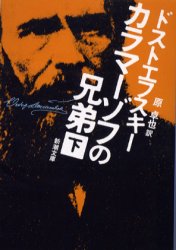

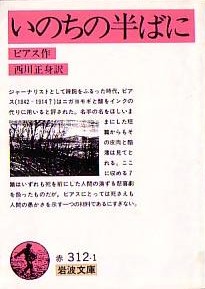

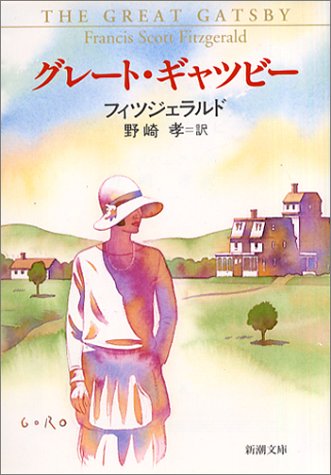
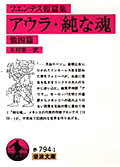


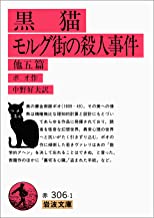
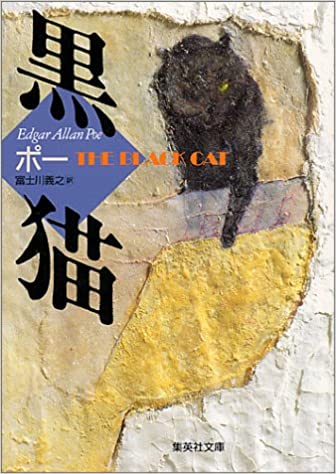
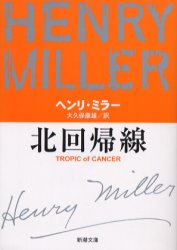

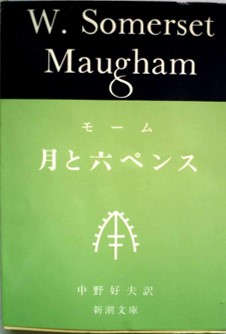
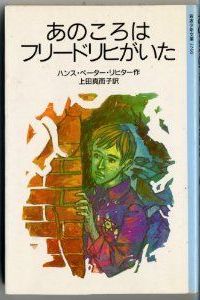

.jpg)
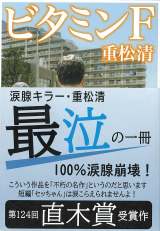

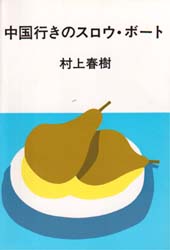

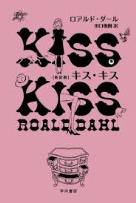
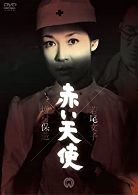
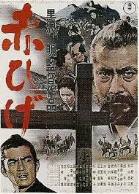
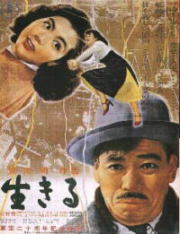
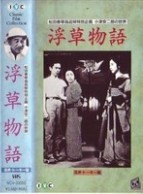


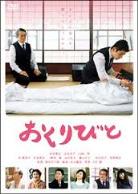

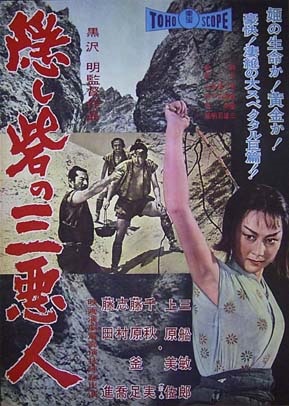
.jpg)


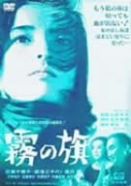
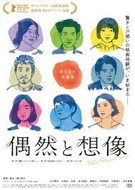
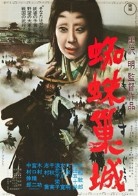
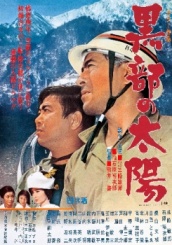



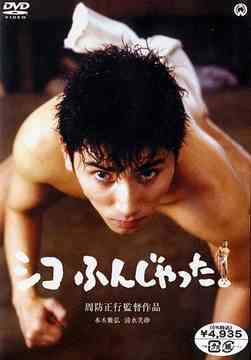


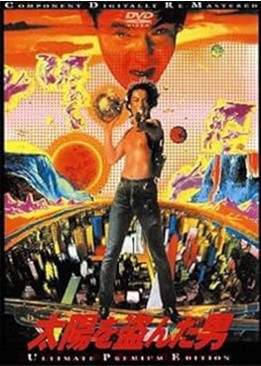
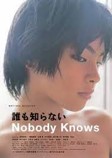

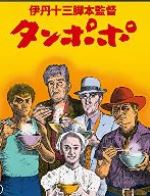
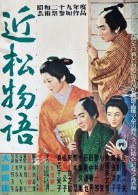

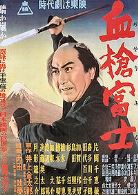
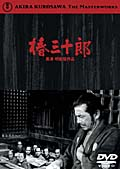
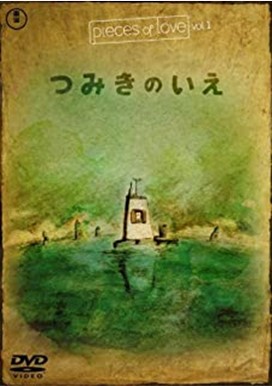
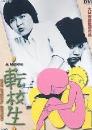
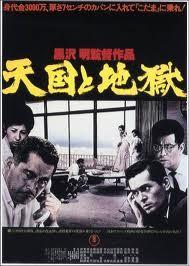
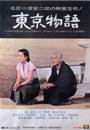
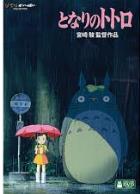
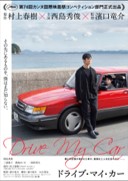

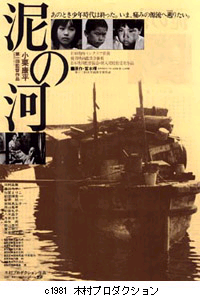

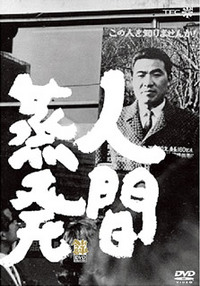
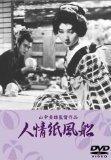

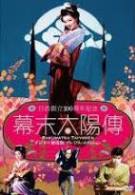

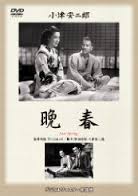
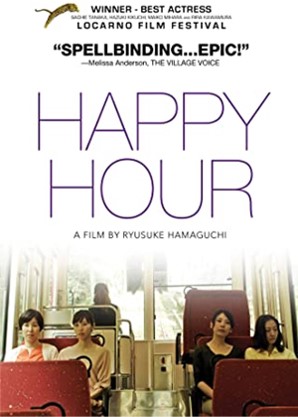
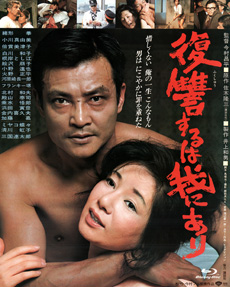
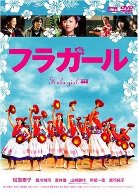
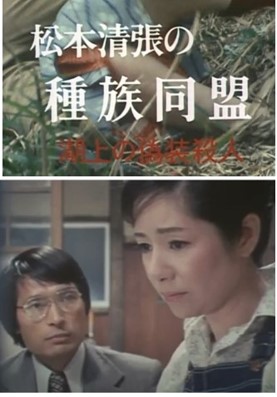



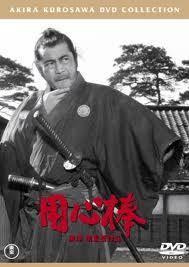


.jpg)

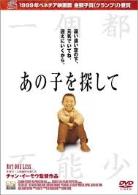
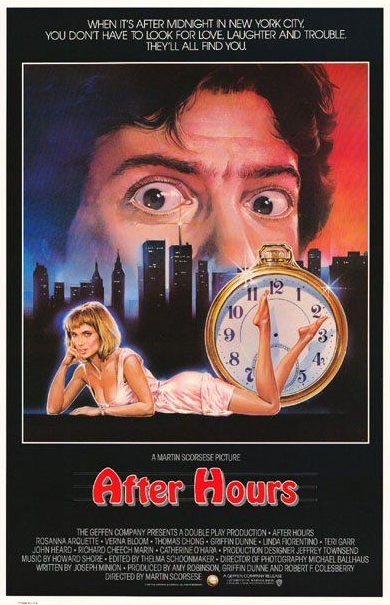

.jpg)
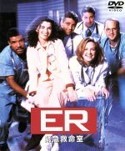


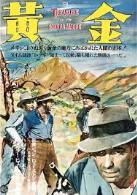
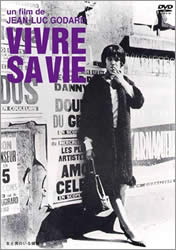
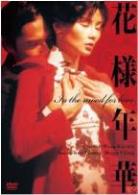

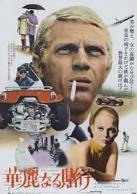
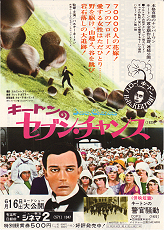
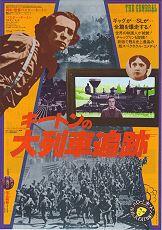
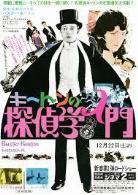
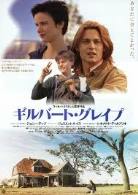

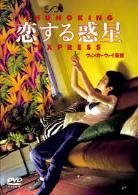
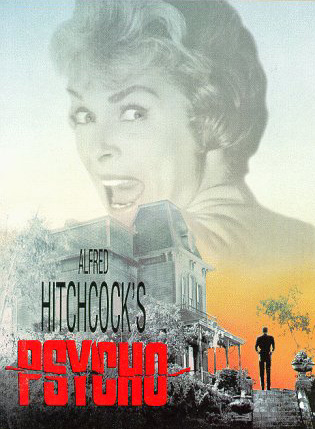
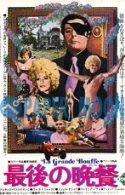
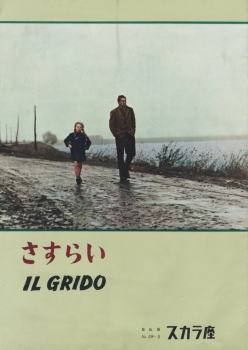
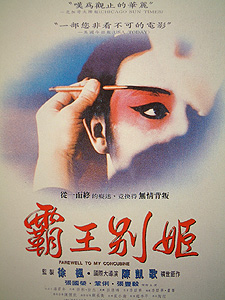
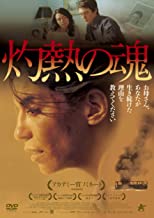


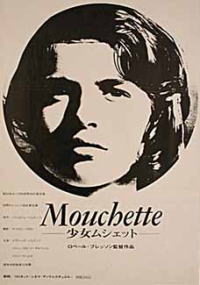

![ジョンとメリー [DVD].jpg](http://hurec.bz/book-movie/%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%81%A8%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%83%BC%20%5BDVD%5D.jpg)
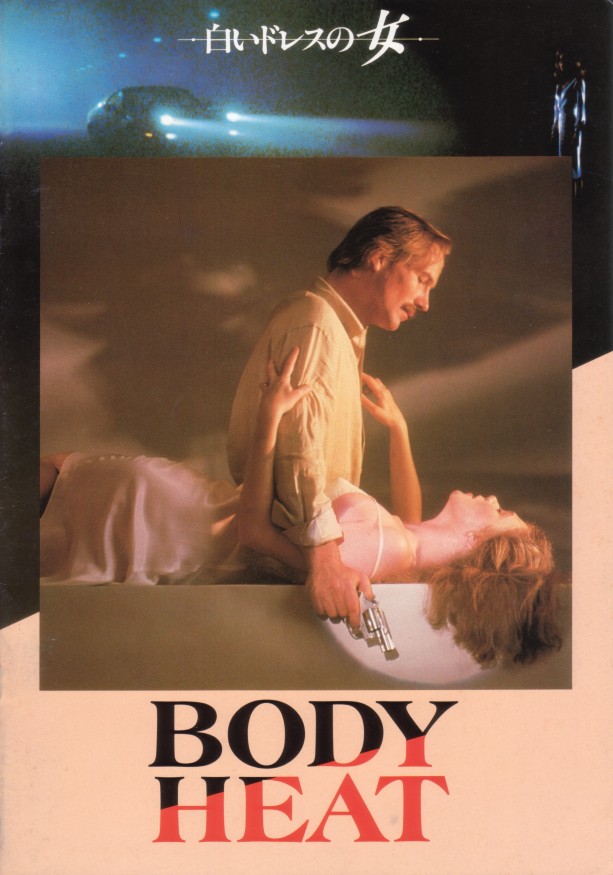
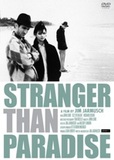
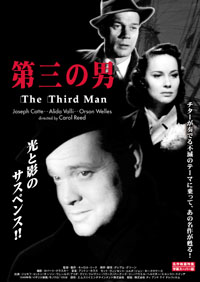
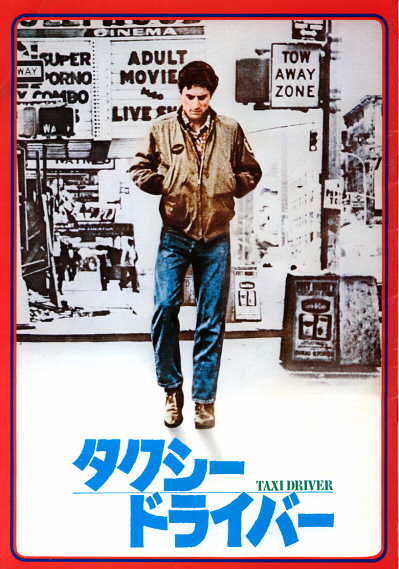

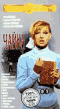
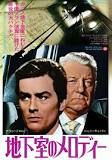


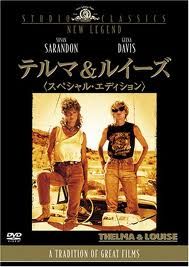
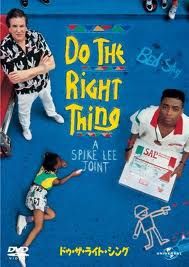

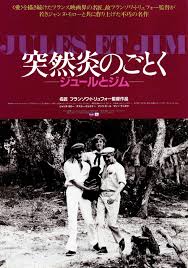
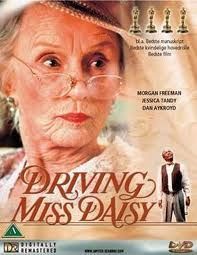
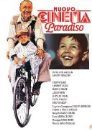

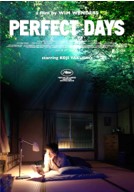
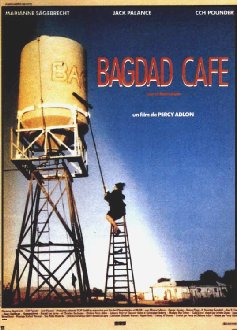

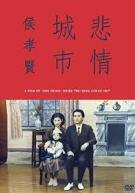
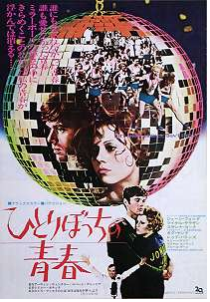



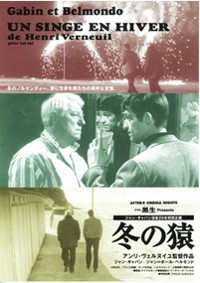


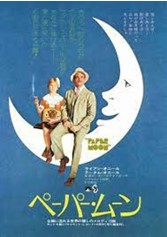

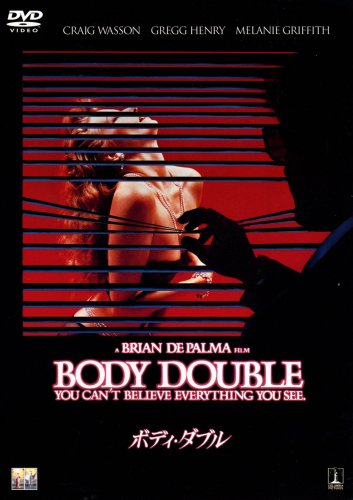


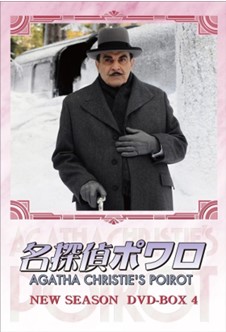
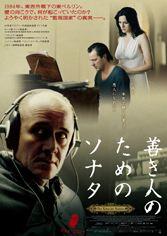
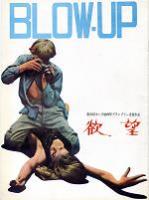
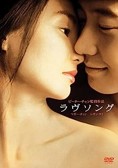




.jpg)
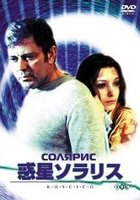
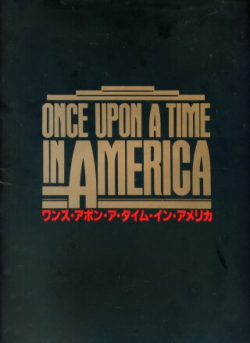

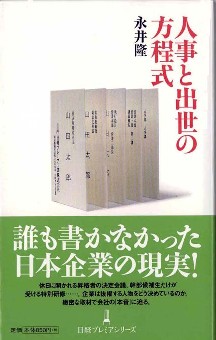
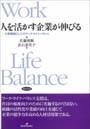
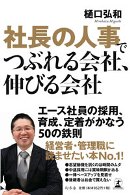








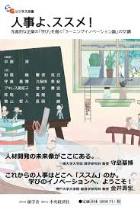


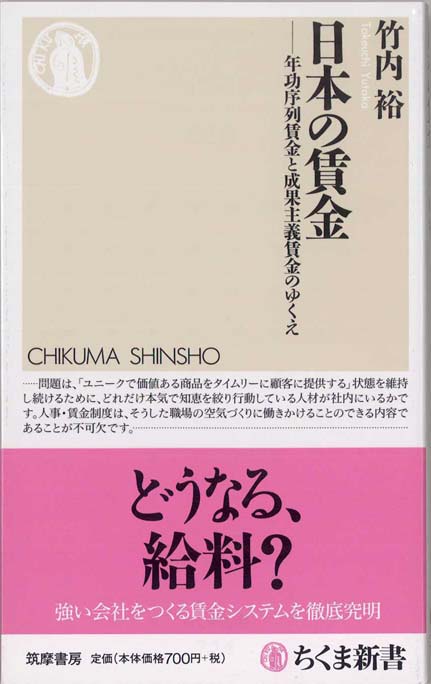


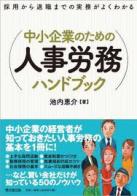


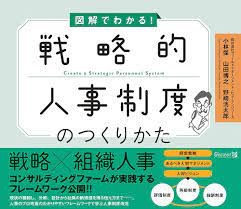


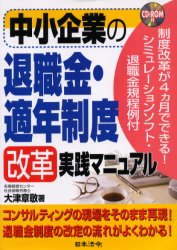
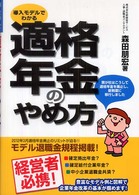


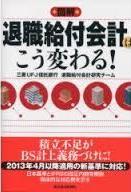
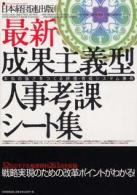
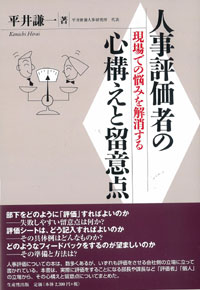



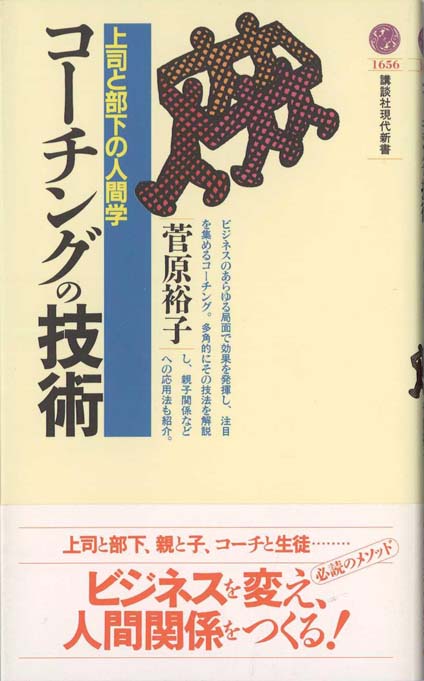
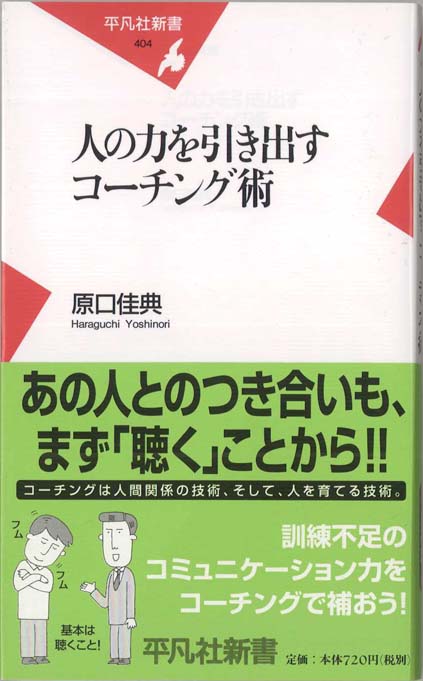
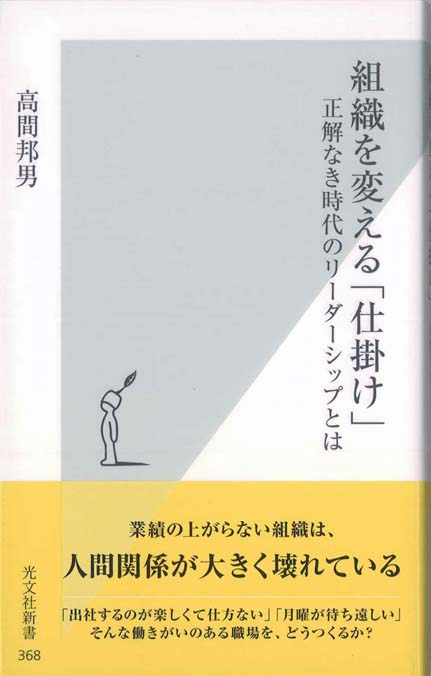
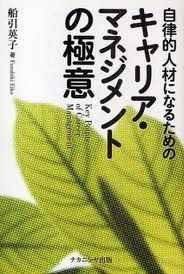

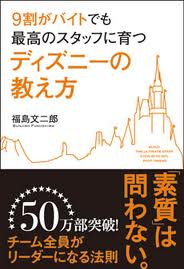
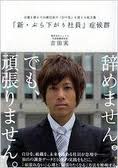

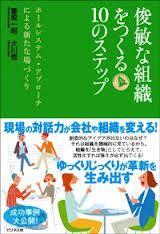


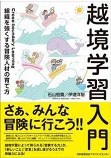
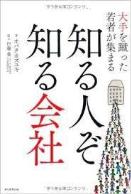
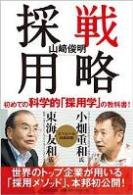




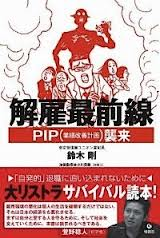
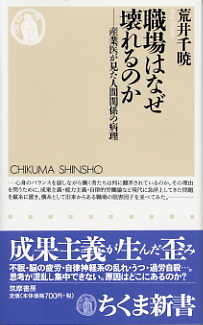







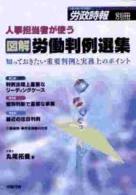



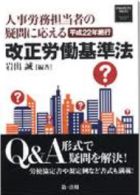
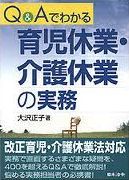
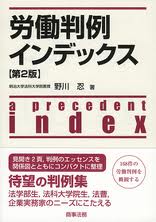

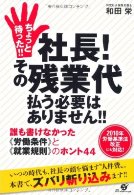



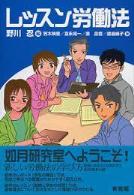
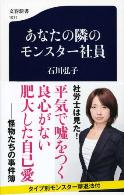

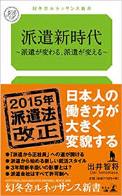
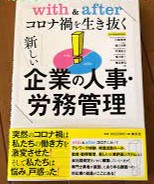


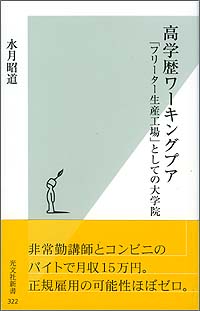




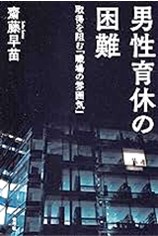
 ●ロジャー・マーティン(Roger Martin)トロント大学ロットマン・スクール・オブ・マネジメント学長。主著に『インテグレーティブ・シンキング―優れた意思決定の秘密』がある。(2009-第32位/2011 -第6位/2013-第3位
●ロジャー・マーティン(Roger Martin)トロント大学ロットマン・スクール・オブ・マネジメント学長。主著に『インテグレーティブ・シンキング―優れた意思決定の秘密』がある。(2009-第32位/2011 -第6位/2013-第3位 ●エイミー・C・エドモンドソン(Amy C. Edmondson)ハーバード・ビジネススクール教授。リーダーシップと経営論担当。(2011-第35位/2013-第15位/2015-第16位/2017-第13位/2019-第3位
●エイミー・C・エドモンドソン(Amy C. Edmondson)ハーバード・ビジネススクール教授。リーダーシップと経営論担当。(2011-第35位/2013-第15位/2015-第16位/2017-第13位/2019-第3位 ●チャールズ・ハンディ(Charles Handy)イギリスの経営思想家。「イギリスのドラッカー」とも呼ばれる。(2001-第2位
●チャールズ・ハンディ(Charles Handy)イギリスの経営思想家。「イギリスのドラッカー」とも呼ばれる。(2001-第2位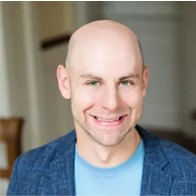 ●アダム・グラント(Adam Grant)ペンシルベニア大学ウォートン校教授。組織心理学者。(2015-第25位/2017-第8位/2019-第10位/2021-第6位/2023-第2位
●アダム・グラント(Adam Grant)ペンシルベニア大学ウォートン校教授。組織心理学者。(2015-第25位/2017-第8位/2019-第10位/2021-第6位/2023-第2位 ●トム・ピーターズ(Tom Peters) トム・ピーターズ・カンパニー会長。(2001-第5位/2003-第3位
●トム・ピーターズ(Tom Peters) トム・ピーターズ・カンパニー会長。(2001-第5位/2003-第3位 ●ゲイリー・ハメル(Gary Hamel) ロンドン・ビジネススクール客員教授。コンサルティング会社ストラテゴスの創設者。(2001-第4位/2003-第4位/2005-第14位/2007-第5位/2009-第10位/2011-第15位/2013-第19位/2015-第30位/2017-第32位/2019-第31位/
●ゲイリー・ハメル(Gary Hamel) ロンドン・ビジネススクール客員教授。コンサルティング会社ストラテゴスの創設者。(2001-第4位/2003-第4位/2005-第14位/2007-第5位/2009-第10位/2011-第15位/2013-第19位/2015-第30位/2017-第32位/2019-第31位/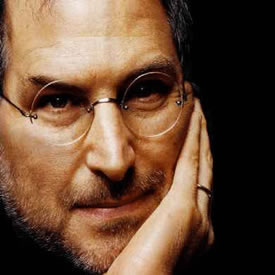 ●
●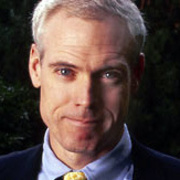 ●ジム・コリンズ(Jim Collins)(2003年-第10位/2005-第6位/2007-第10位/2009-第17位/2011-第4位/2013-第12位/2015-第28位/2017-第31位)
●ジム・コリンズ(Jim Collins)(2003年-第10位/2005-第6位/2007-第10位/2009-第17位/2011-第4位/2013-第12位/2015-第28位/2017-第31位)  ●マーシャル・ゴールドスミス(Marshall Goldsmith)エグゼクティブ・コーチングの世界的な第一人者。360度評価をいち早く取り入れたことでも知られる。(2007-第34位/2009-第14位/2011-第7位/2013-第10位/2015-第5位/2017-第6位/
●マーシャル・ゴールドスミス(Marshall Goldsmith)エグゼクティブ・コーチングの世界的な第一人者。360度評価をいち早く取り入れたことでも知られる。(2007-第34位/2009-第14位/2011-第7位/2013-第10位/2015-第5位/2017-第6位/ ●リンダ・A・ヒル(Linda A. Hill) ハーバード・ビジネススクール教授。経営管理論を担当。同スクールのリーダーシップ・イニシアチブの主任も務める。(2011-第16位/2013-第8位/2015-第6位/2017-第15位/2019-第22位/2021-第10位/2023-11位以下)
●リンダ・A・ヒル(Linda A. Hill) ハーバード・ビジネススクール教授。経営管理論を担当。同スクールのリーダーシップ・イニシアチブの主任も務める。(2011-第16位/2013-第8位/2015-第6位/2017-第15位/2019-第22位/2021-第10位/2023-11位以下) ●ダニエル・ピンク(Daniel Pink) 著述家、ジャーナリスト、スピーチライター、大臣補佐官、ビジネストレンド評論家。(2011-第29位/2013-第13位/2015-第10位/2017-第11位/2019-第6位/2021-第9位/2023-11位以下)
●ダニエル・ピンク(Daniel Pink) 著述家、ジャーナリスト、スピーチライター、大臣補佐官、ビジネストレンド評論家。(2011-第29位/2013-第13位/2015-第10位/2017-第11位/2019-第6位/2021-第9位/2023-11位以下) ●ヘンリー・ミンツバーグ(Henry Mintzberg)(2001-第7位/2003-第7位/2005-第8位/2007-第16位/2009-第33位/2011-第30位/
●ヘンリー・ミンツバーグ(Henry Mintzberg)(2001-第7位/2003-第7位/2005-第8位/2007-第16位/2009-第33位/2011-第30位/ ●マーカス・バッキンガム(Marcus Buckingham) 自己啓発トレーナー。ザ・マーカス・バッキンガム・カンパニー(TMBC)。(2007-第38位/2009-第25位/2011-第8位/2013-第18位/2019-第38位)
●マーカス・バッキンガム(Marcus Buckingham) 自己啓発トレーナー。ザ・マーカス・バッキンガム・カンパニー(TMBC)。(2007-第38位/2009-第25位/2011-第8位/2013-第18位/2019-第38位)  ●ハーミニア・イバーラ(Herminia Ibarra) INSEAD教授(コラ記念講座リーダーシップ・アンド・ラーニング教授兼組織行動論教授)。研究領域はプロフェッショナルとリーダーシップの育成。(2011-第28位/2013-第9位/2015-第8位/2017-第20位/2019-第18位/2021-11位以下/2023-11位以下)
●ハーミニア・イバーラ(Herminia Ibarra) INSEAD教授(コラ記念講座リーダーシップ・アンド・ラーニング教授兼組織行動論教授)。研究領域はプロフェッショナルとリーダーシップの育成。(2011-第28位/2013-第9位/2015-第8位/2017-第20位/2019-第18位/2021-11位以下/2023-11位以下) ●ロザベス・モス・カンター(Rosabeth Moss Kanter)ハーバード・ビジネススクール(アーネスト・L・アーバックル記念講座)教授。ハーバード大学アドバンスト・リーダーシップ・イニシアティブ会長。(2001-第14位/2003-第9位/2005-第19位/2007-第28位/2009-第27位/2011-第25位/2013-第38位/
●ロザベス・モス・カンター(Rosabeth Moss Kanter)ハーバード・ビジネススクール(アーネスト・L・アーバックル記念講座)教授。ハーバード大学アドバンスト・リーダーシップ・イニシアティブ会長。(2001-第14位/2003-第9位/2005-第19位/2007-第28位/2009-第27位/2011-第25位/2013-第38位/ ●ピーター・M・センゲ(Peter M. Senge) マサチューセッツ工科大学(MIT)スローン経営大学院の組織学習センターの責任者。「学習する組織」という理論を世に広めた。(2001-第11位/2003-第14位/2005-第23位/2007-第47位)
●ピーター・M・センゲ(Peter M. Senge) マサチューセッツ工科大学(MIT)スローン経営大学院の組織学習センターの責任者。「学習する組織」という理論を世に広めた。(2001-第11位/2003-第14位/2005-第23位/2007-第47位) スマントラ・ゴシャール(Sumantra Ghoshal)インド出身の経営学者。組織戦略論、国際的経営戦略論。(2001-第12位/2003-第11位/2004年没/
スマントラ・ゴシャール(Sumantra Ghoshal)インド出身の経営学者。組織戦略論、国際的経営戦略論。(2001-第12位/2003-第11位/2004年没/ ロバート・キャプラン(Robert Kaplan)ハーバード・ビジネススクール教授。/デビッド・ノートン(David Norton)戦略コンサルティング会社パラディアム・グループの創設者。(2003-第15位/2005-第22位/2007-第12位/2009-第37位/2009-第14位/
ロバート・キャプラン(Robert Kaplan)ハーバード・ビジネススクール教授。/デビッド・ノートン(David Norton)戦略コンサルティング会社パラディアム・グループの創設者。(2003-第15位/2005-第22位/2007-第12位/2009-第37位/2009-第14位/ ●スコット・アダムス(Scott Adams) 『ディルバート』で知られるアメリカの漫画家。(2001-第31位/2003-第27位/2005-第12位/2007-第21位)
●スコット・アダムス(Scott Adams) 『ディルバート』で知られるアメリカの漫画家。(2001-第31位/2003-第27位/2005-第12位/2007-第21位) ●リンダ・グラットン(Lynda Gratton) ロンドン・ビジネススクール教授。(2003-第41位/2005-第34位/2007-第19位/2009-第18位/2011-第12位/2013-第14位/2015-第31位/2017-第29位/2019-第13位/2021-11位以下/2023-11位以下)
●リンダ・グラットン(Lynda Gratton) ロンドン・ビジネススクール教授。(2003-第41位/2005-第34位/2007-第19位/2009-第18位/2011-第12位/2013-第14位/2015-第31位/2017-第29位/2019-第13位/2021-11位以下/2023-11位以下) 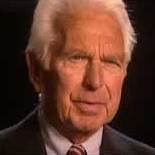 ●ウォーレン・ベニス(Warren Bennis) アメリカの経営学者。リーダーシップ論で有名。(2001-第13位/2003-第13位/2005-第27位/2007-第24位/2009-第36位/
●ウォーレン・ベニス(Warren Bennis) アメリカの経営学者。リーダーシップ論で有名。(2001-第13位/2003-第13位/2005-第27位/2007-第24位/2009-第36位/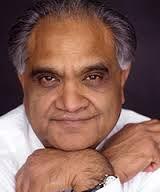 ●ラム・チャラン(Ram Charan)アメリカの人材育成コンサルタント。(2005-第24位/2007-第22位/2009-第13位/
●ラム・チャラン(Ram Charan)アメリカの人材育成コンサルタント。(2005-第24位/2007-第22位/2009-第13位/ ●エドガー・H・シャイン(Edgar Henry Schein) マサチューセッツ工科大学スローンスクール名誉教授。組織開発、キャリア開発、組織文化。(2001-第21位/2003-第17位/2005-第36位/
●エドガー・H・シャイン(Edgar Henry Schein) マサチューセッツ工科大学スローンスクール名誉教授。組織開発、キャリア開発、組織文化。(2001-第21位/2003-第17位/2005-第36位/ ●ジェフリー・フェッファー(Jeffrey Pfeffer) スタンフォード大学経営大学院教授。組織行動論。(2007-第49位/2011-第22位/2013-第24位/2015-第17位/
●ジェフリー・フェッファー(Jeffrey Pfeffer) スタンフォード大学経営大学院教授。組織行動論。(2007-第49位/2011-第22位/2013-第24位/2015-第17位/ ●リズ・ワイズマン(Liz Wiseman) ワイズマン・グループ社長。元オラクル幹部。17年間、企業内大学副学長や人的資源開発責任者を務めた。(2013-第48位/2015-第43位/2017-第35位/2019-第17位/2021-11位以下/2023-11位以下)
●リズ・ワイズマン(Liz Wiseman) ワイズマン・グループ社長。元オラクル幹部。17年間、企業内大学副学長や人的資源開発責任者を務めた。(2013-第48位/2015-第43位/2017-第35位/2019-第17位/2021-11位以下/2023-11位以下) ●テレサ・アマビール(Teresa Amabile)ハーバード・ビジネススクール教授。ベンチャー経営学を担当。(2011-第18位/2013-第22位/2015-第21位)
●テレサ・アマビール(Teresa Amabile)ハーバード・ビジネススクール教授。ベンチャー経営学を担当。(2011-第18位/2013-第22位/2015-第21位) ●エリック・シュミット(Eric Schmidt) 技術者、経営者で、Googleの元CEO。(2009-第21位)
●エリック・シュミット(Eric Schmidt) 技術者、経営者で、Googleの元CEO。(2009-第21位)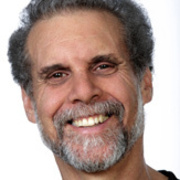 ●ダニエル・ゴールマン(Daniel Goleman) 心理学者、作家、ジャーナリスト。(2003-第29位/2005-第42位/2007-第37位/2009-第34位/2011-第39位/2013-第36位/2015-第22位/
●ダニエル・ゴールマン(Daniel Goleman) 心理学者、作家、ジャーナリスト。(2003-第29位/2005-第42位/2007-第37位/2009-第34位/2011-第39位/2013-第36位/2015-第22位/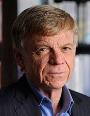 ●ジョン・P・コッター(John Kotter)ハーバード・ビジネススクール名誉教授。(2001-第40位/2003-第23位/2007-第30位/2009-41位/2011-第34位/2013-第32位/2015-第37位/
●ジョン・P・コッター(John Kotter)ハーバード・ビジネススクール名誉教授。(2001-第40位/2003-第23位/2007-第30位/2009-41位/2011-第34位/2013-第32位/2015-第37位/ ●デイビッド・ウルリッチ(Dave Ulrich) ミシガン大学スティーブン・M・ロス・スクール・オブ・ビジネス教授。(2007-第42位/2009-第31位/2011-第23位/2013-第30位/2015-第27位/
●デイビッド・ウルリッチ(Dave Ulrich) ミシガン大学スティーブン・M・ロス・スクール・オブ・ビジネス教授。(2007-第42位/2009-第31位/2011-第23位/2013-第30位/2015-第27位/ ●シドニー・フィンケルシュタイン (Sydney Finkelstein)ダートマス大学タック・スクール・オブ・ビジネス、スティーブン・ロス経営学教授。同スクールのリーダーシップ研究所の所長も務める。(2013-第43位/2015-第41位/2017-第23位/2019-第44位)
●シドニー・フィンケルシュタイン (Sydney Finkelstein)ダートマス大学タック・スクール・オブ・ビジネス、スティーブン・ロス経営学教授。同スクールのリーダーシップ研究所の所長も務める。(2013-第43位/2015-第41位/2017-第23位/2019-第44位) ●アンドリュー・S・グローブ(Andrew S. Grove)インテル創業者(2001-第24位/2003-第26位/2005-第41位/2016年没)
●アンドリュー・S・グローブ(Andrew S. Grove)インテル創業者(2001-第24位/2003-第26位/2005-第41位/2016年没) ●モートン・ハンセン(Morten Hansen)UCBerkeleyおよびINSEAD教授。ボストンコンサルティング出身。(2013-第28位/2015-第34位/2017-第41位/2019-第26位/2021-11位以下)
●モートン・ハンセン(Morten Hansen)UCBerkeleyおよびINSEAD教授。ボストンコンサルティング出身。(2013-第28位/2015-第34位/2017-第41位/2019-第26位/2021-11位以下) ●スチュワート・D・フリードマン(Stewart Friedman) ペンシルベニア大学ウォートン・スクール教授。リーダーシップ、ワーク・ライフ・バランスの第一人者。(2011-第45位/2013-第27位/2015-第29位/2017-第38位/2019-第43位/
●スチュワート・D・フリードマン(Stewart Friedman) ペンシルベニア大学ウォートン・スクール教授。リーダーシップ、ワーク・ライフ・バランスの第一人者。(2011-第45位/2013-第27位/2015-第29位/2017-第38位/2019-第43位/ ●マイケル・ワトキンス(Michael D Watkins)スイス・ローザンヌのIMDビジネススクールのリーダーシップ学教授として、上級管理者課程で教鞭を執る。ハーバード・ビジネススクールとハーバード・ケネディ・スクール・オブ・ガバメントの教授も歴任。(2019-第29位/2021-11位以下)
●マイケル・ワトキンス(Michael D Watkins)スイス・ローザンヌのIMDビジネススクールのリーダーシップ学教授として、上級管理者課程で教鞭を執る。ハーバード・ビジネススクールとハーバード・ケネディ・スクール・オブ・ガバメントの教授も歴任。(2019-第29位/2021-11位以下) ●マンフレッド・ケッツ・ド・ブリース(Manfred F. R. Kets de Vries)/オランダの経営学者であり、精神分析医、コンサルタント、INSEAD のリーダーシップ開発と組織変革の教授。(2003-第43位/2005-第32位/2007-無し/2009-第45位)
●マンフレッド・ケッツ・ド・ブリース(Manfred F. R. Kets de Vries)/オランダの経営学者であり、精神分析医、コンサルタント、INSEAD のリーダーシップ開発と組織変革の教授。(2003-第43位/2005-第32位/2007-無し/2009-第45位) ●ロブ・ゴーフィー(Rob Goffee)/ガレス・ジョーンズ(Gareth Jones)ロンドン・ビジネススクール教授。(2005-第45位/2007-第32位/2009-第49位/
●ロブ・ゴーフィー(Rob Goffee)/ガレス・ジョーンズ(Gareth Jones)ロンドン・ビジネススクール教授。(2005-第45位/2007-第32位/2009-第49位/ ●シェリル・サンドバーグ(Sheryl Sandberg) Facebook(フェイスブック)社COO(最高執行責任者)。(2013-第34位)
●シェリル・サンドバーグ(Sheryl Sandberg) Facebook(フェイスブック)社COO(最高執行責任者)。(2013-第34位)  ●ビル・ジョージ(Bill George)メドトロニック・インク元CEO、ハーバード・ビジネス・スクール教授。(2007-第35位)
●ビル・ジョージ(Bill George)メドトロニック・インク元CEO、ハーバード・ビジネス・スクール教授。(2007-第35位) ●ラリー・ボシディ(ローレンス・ボサイディー)(Lawrence A. ("Larry") Bossidy)ハネウエル・インターナショナルの前会長兼最高経営責任者(CEO)。GE(ゼネラルエレクトリック)元副会長。(2005-第48位/2007-第36位)
●ラリー・ボシディ(ローレンス・ボサイディー)(Lawrence A. ("Larry") Bossidy)ハネウエル・インターナショナルの前会長兼最高経営責任者(CEO)。GE(ゼネラルエレクトリック)元副会長。(2005-第48位/2007-第36位)  ●ヴィニート・ナイアー(Vineet Nayar)インドのグローバルIT企業HCLテクノロジーズ元CEO。「従業員第一、顧客第二」主義という経営思想を提唱。(2011-第40位)
●ヴィニート・ナイアー(Vineet Nayar)インドのグローバルIT企業HCLテクノロジーズ元CEO。「従業員第一、顧客第二」主義という経営思想を提唱。(2011-第40位) ●アル・ゴア(Al Gore) ビル・クリントン政権下の副大統領、環境活動家、ノーベル平和賞受賞者。環境問題の論客として知られる。(2007-第41位)
●アル・ゴア(Al Gore) ビル・クリントン政権下の副大統領、環境活動家、ノーベル平和賞受賞者。環境問題の論客として知られる。(2007-第41位) ●ロバート・ウォーターマン(Robert Waterman) アメリカ合衆国の経営コンサルタント。トム・ピーターズとの共著『エクセレント・カンパニー』で知られる。(2003-第44位)
●ロバート・ウォーターマン(Robert Waterman) アメリカ合衆国の経営コンサルタント。トム・ピーターズとの共著『エクセレント・カンパニー』で知られる。(2003-第44位) ●バーバラ・ケラーマン(Barbara Kellerman)ハーバード大学ケネディスクールでの社会リーダーシップの授業で、ジェームズ・マグレガー・バーンズ論を担当。(2009-第48位)
●バーバラ・ケラーマン(Barbara Kellerman)ハーバード大学ケネディスクールでの社会リーダーシップの授業で、ジェームズ・マグレガー・バーンズ論を担当。(2009-第48位)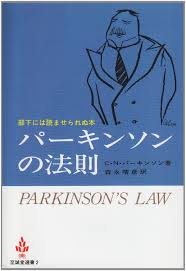













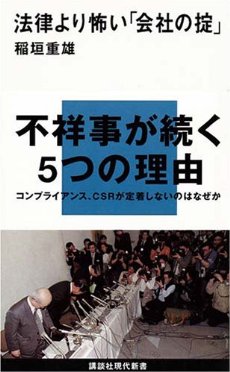

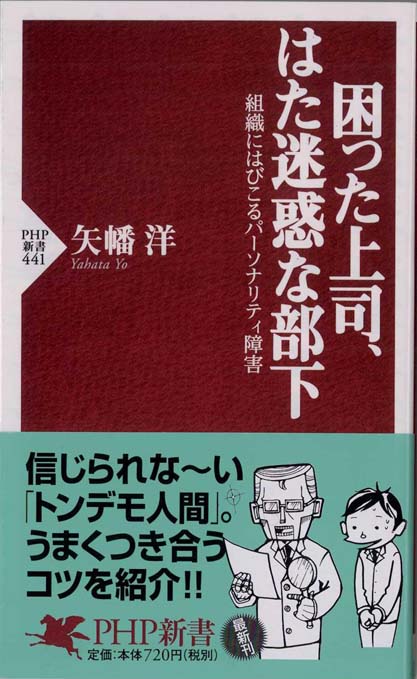
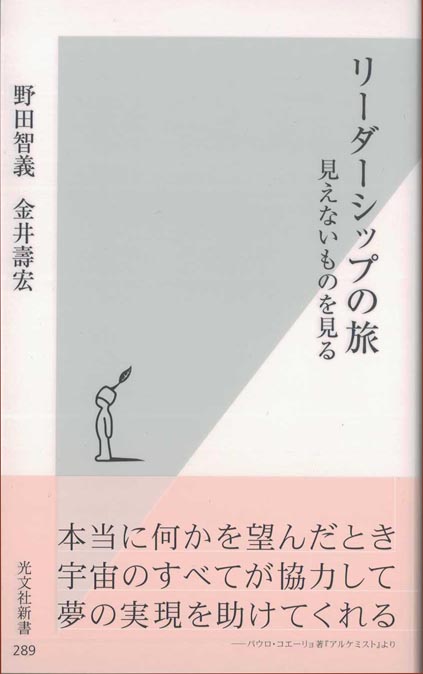







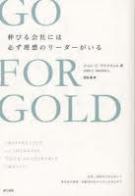


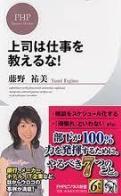
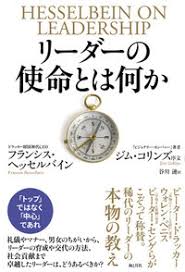

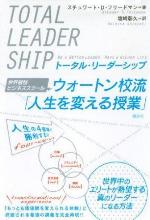
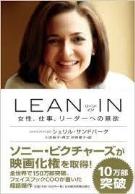
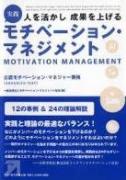
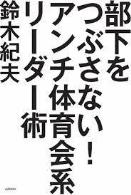
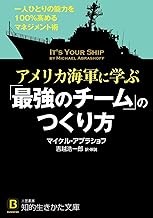




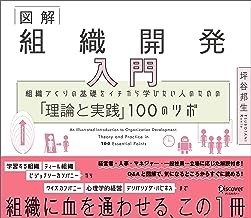
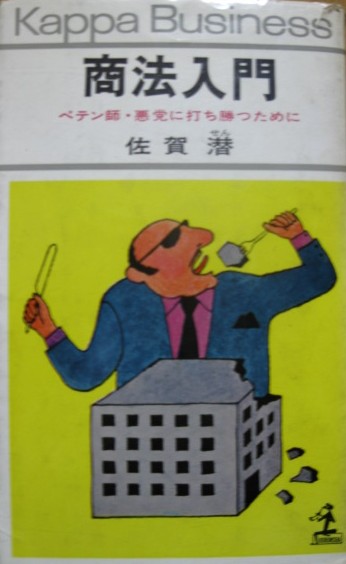
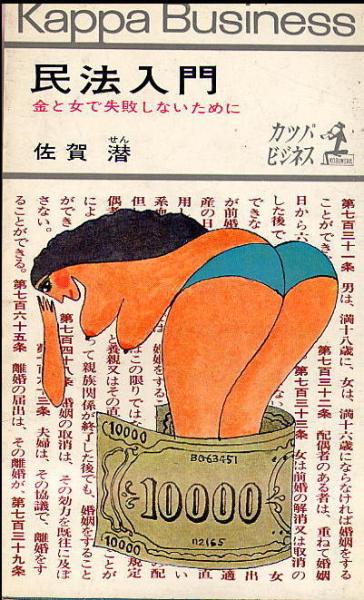
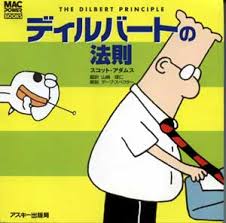
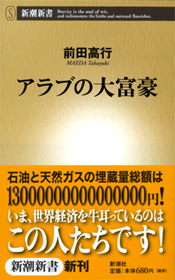

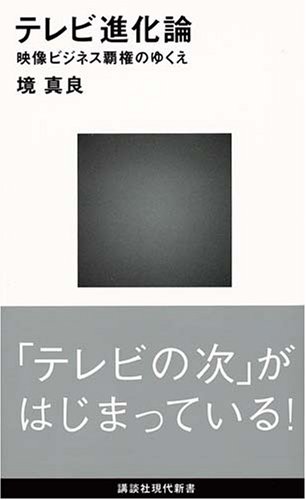

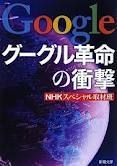

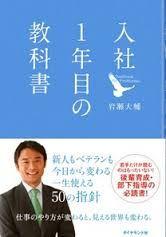
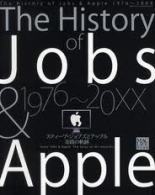



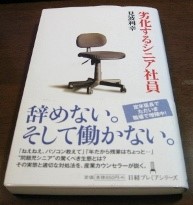
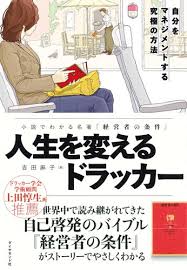



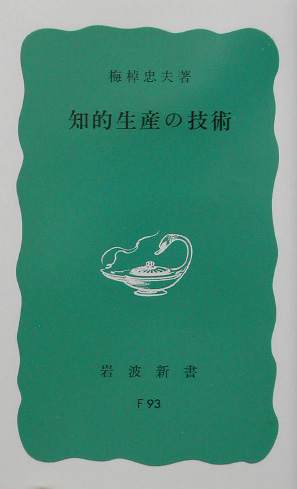



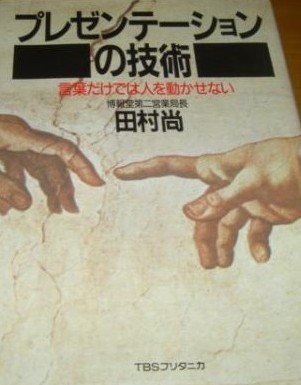

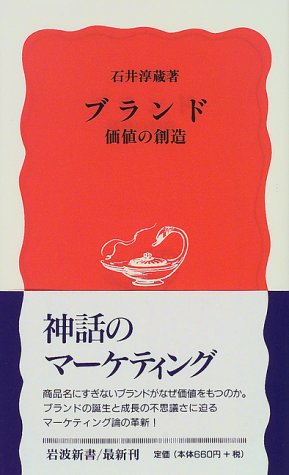

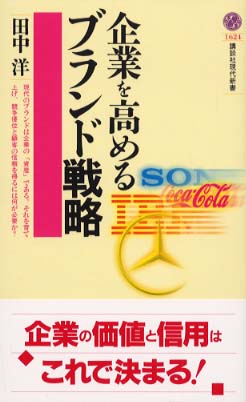
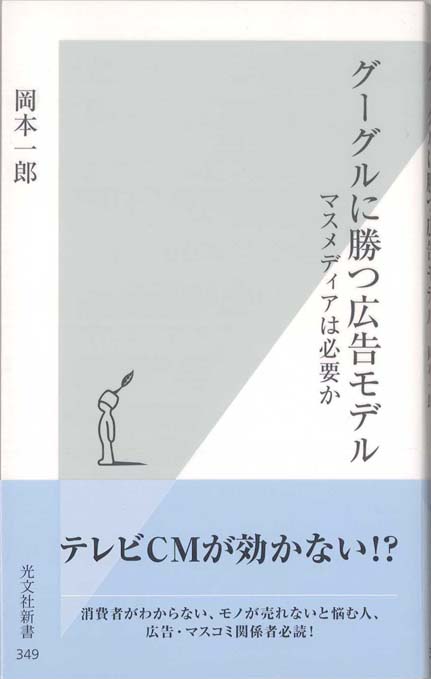
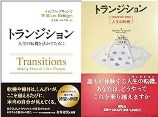
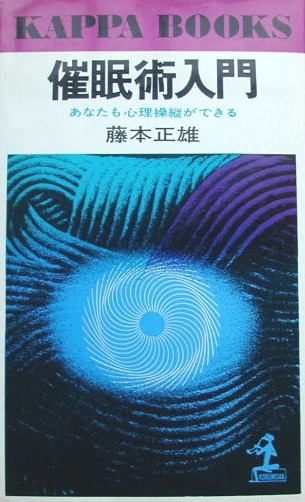


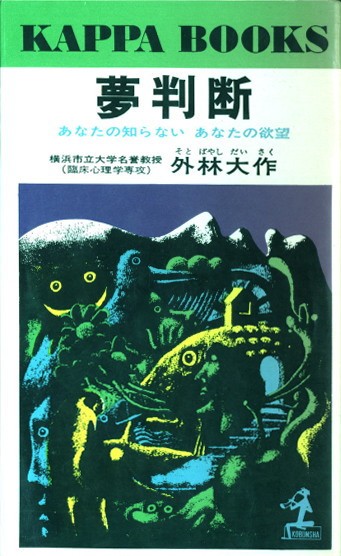
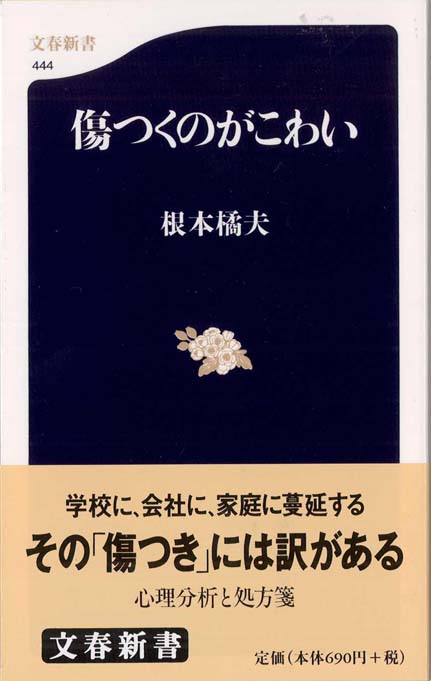


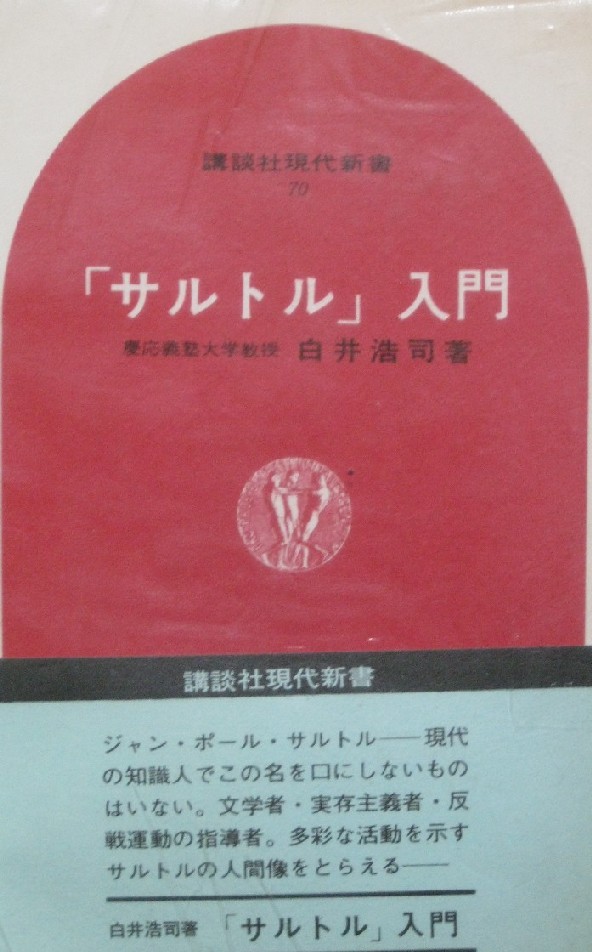




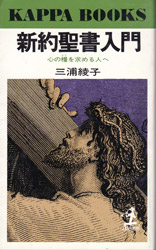

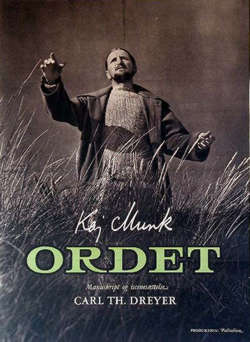
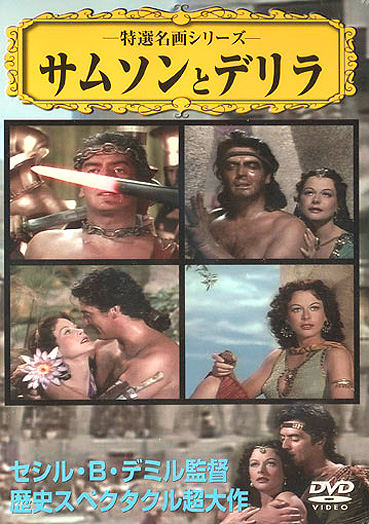
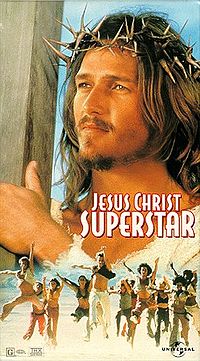
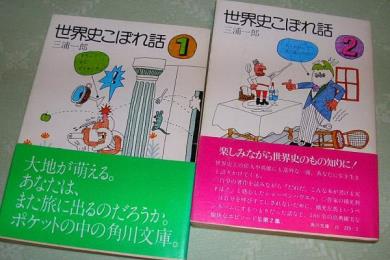

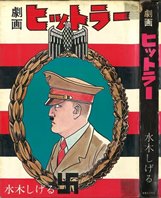

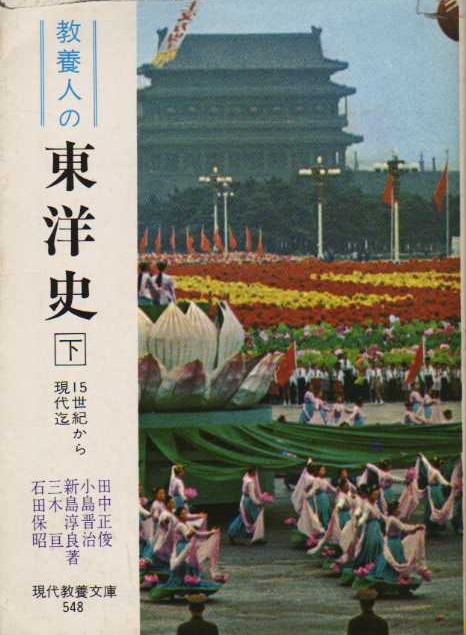



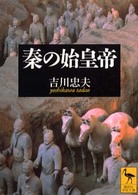
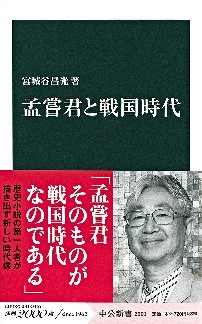

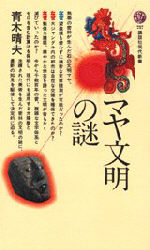
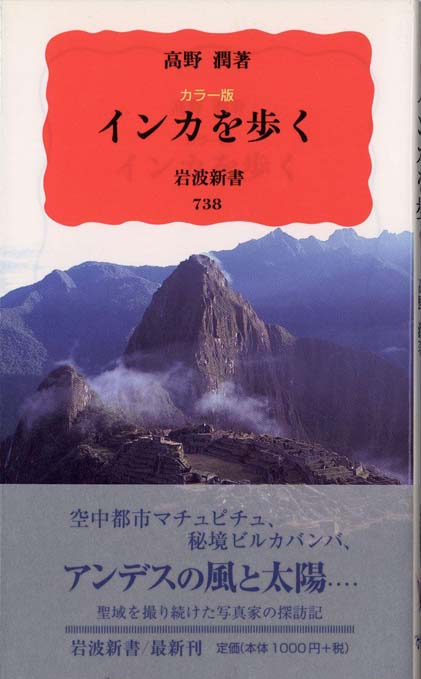


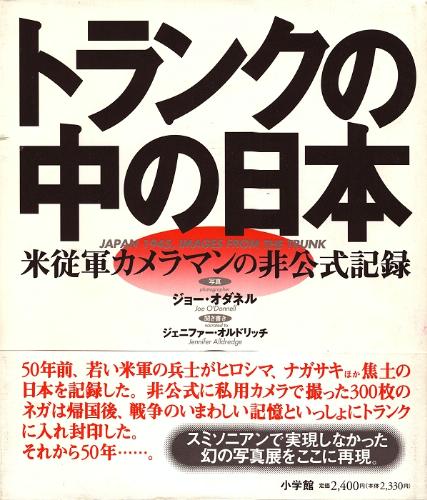


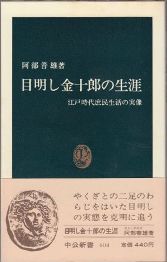

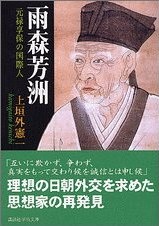




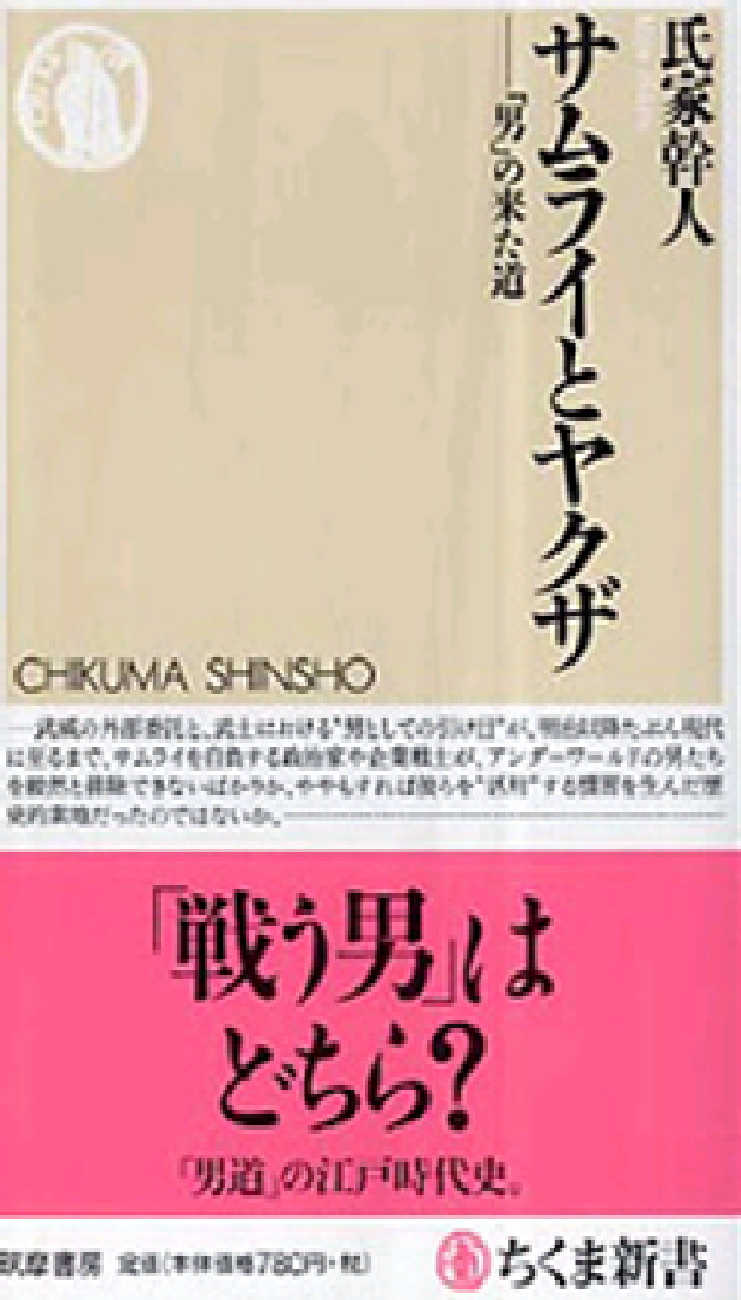

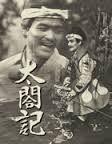


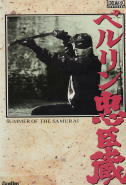



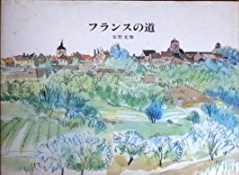
日記.jpg)

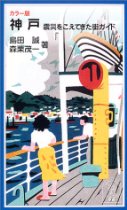
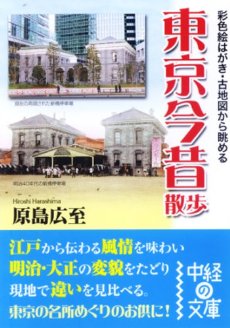



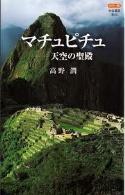
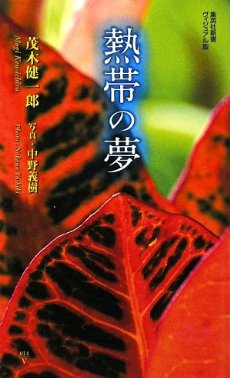


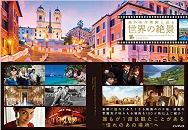

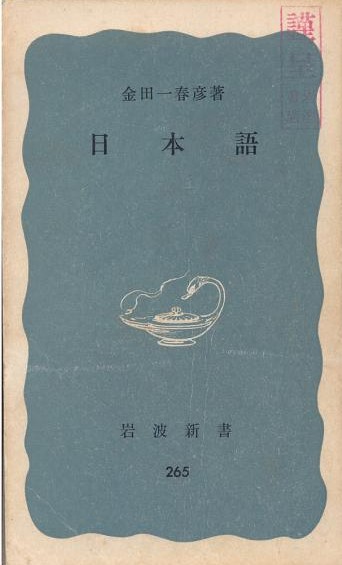


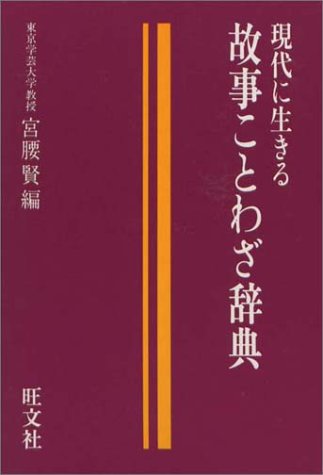
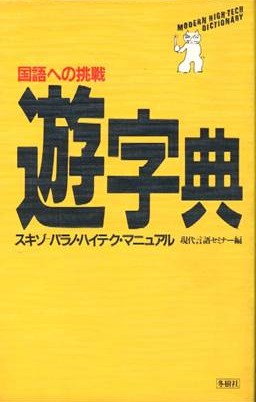

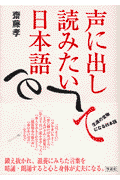

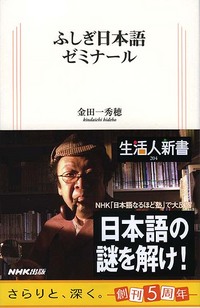
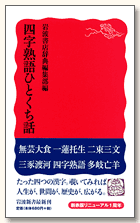



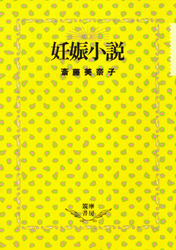
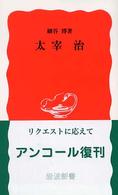

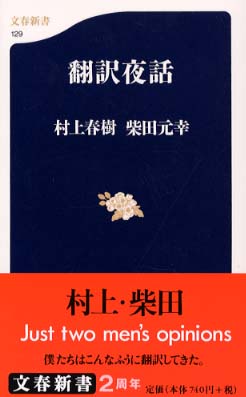
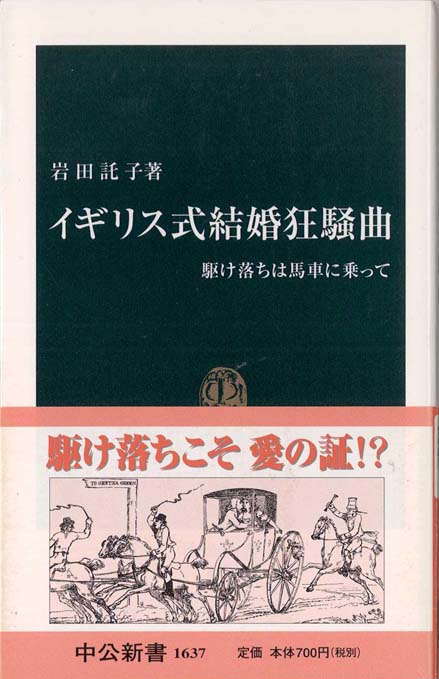
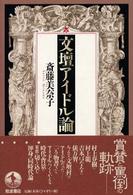
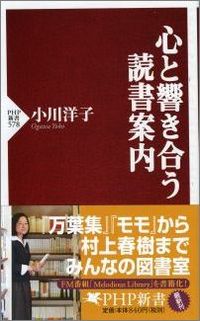


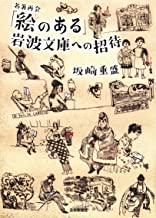




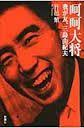

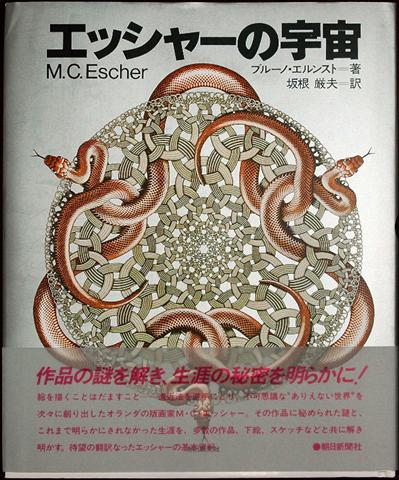
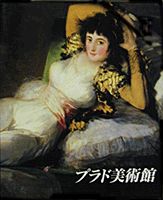
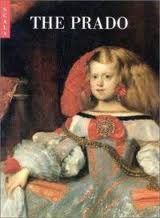

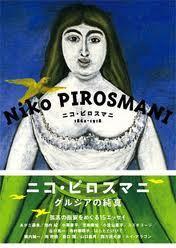
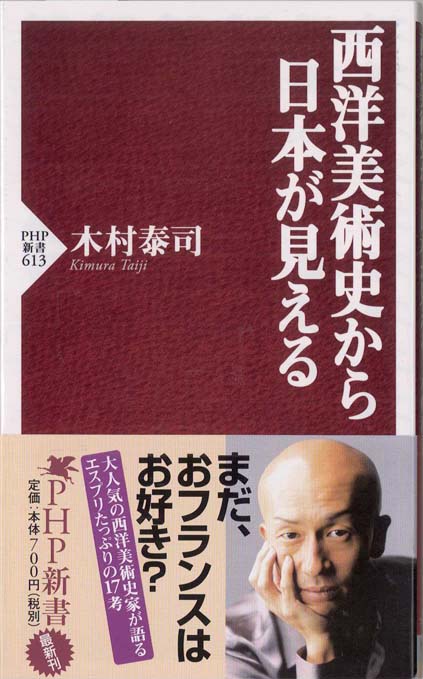
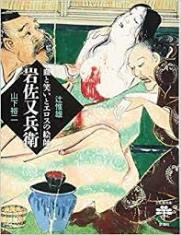

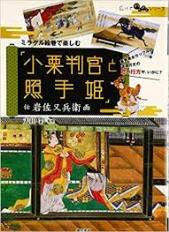
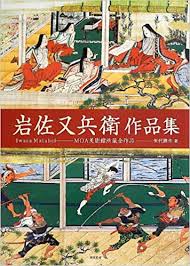

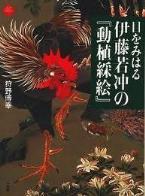
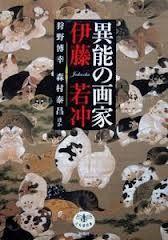
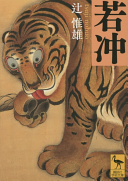
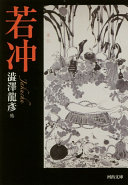

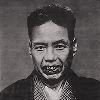
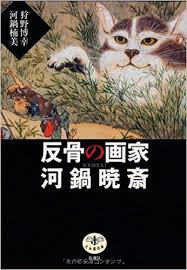
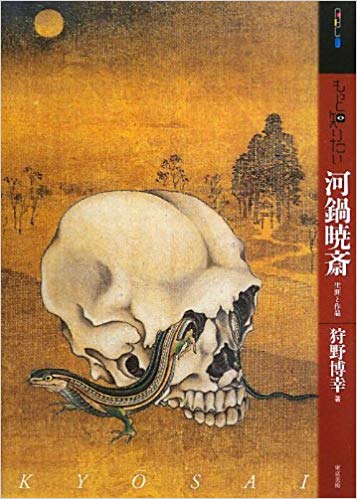

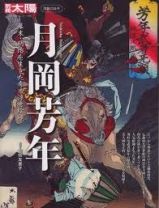
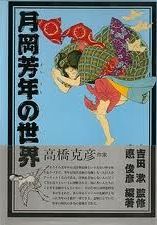
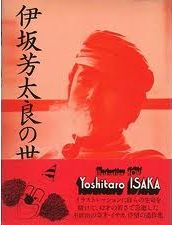
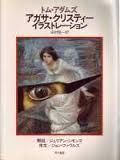



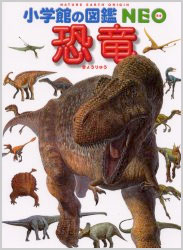
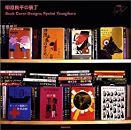

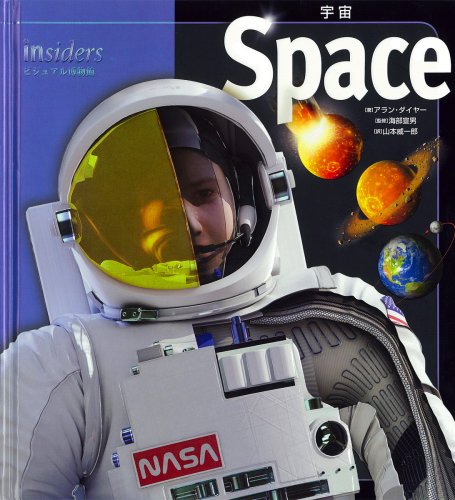


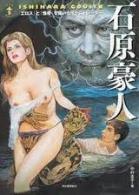
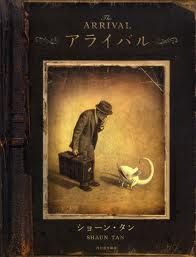
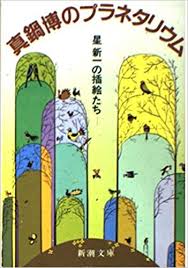
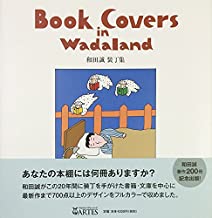
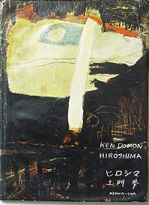
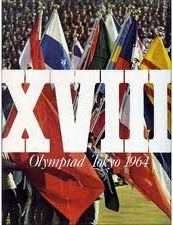




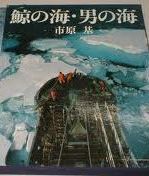
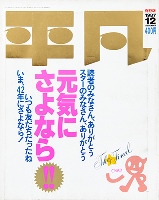
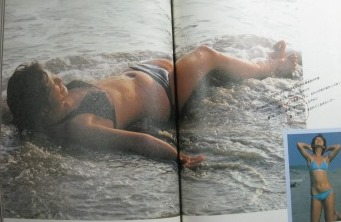
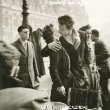
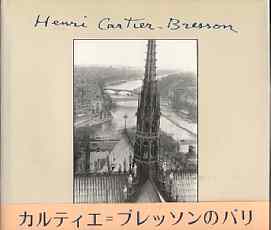
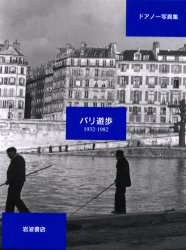






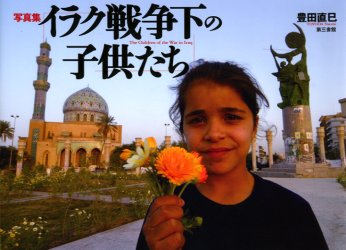
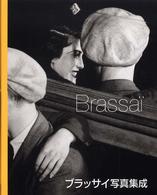
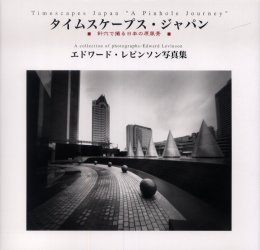


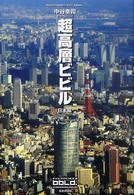


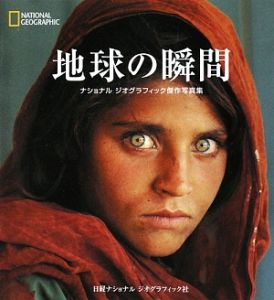
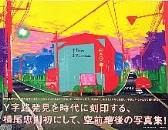
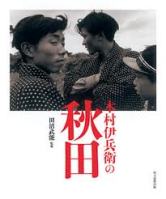
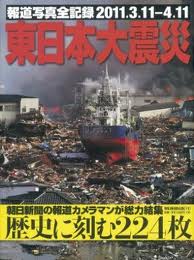
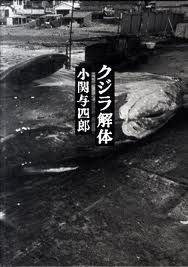
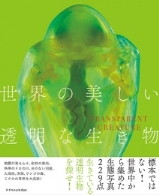


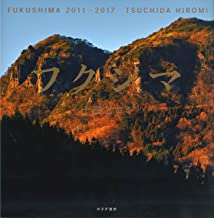

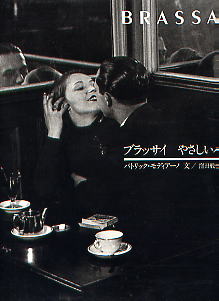

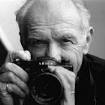

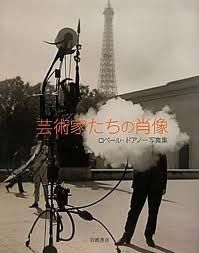
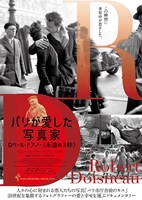
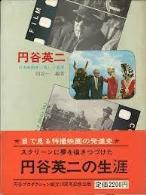
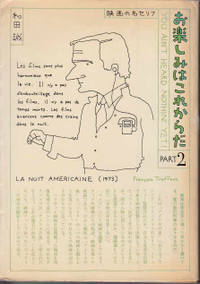



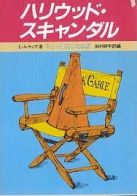

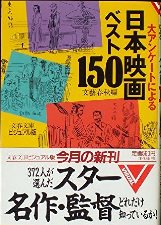
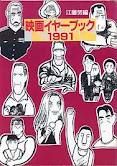
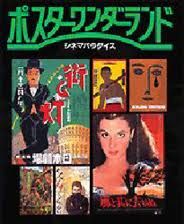
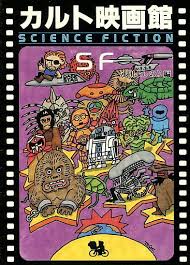

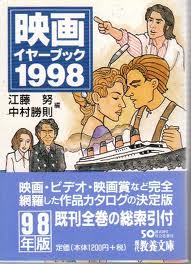

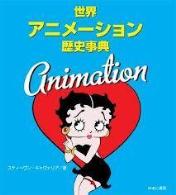
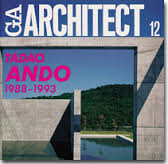
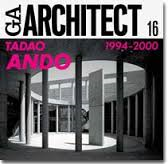
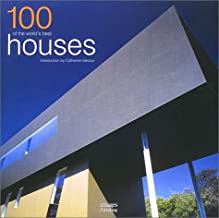
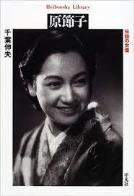

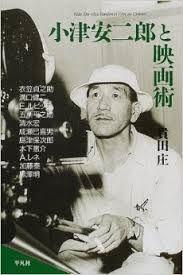

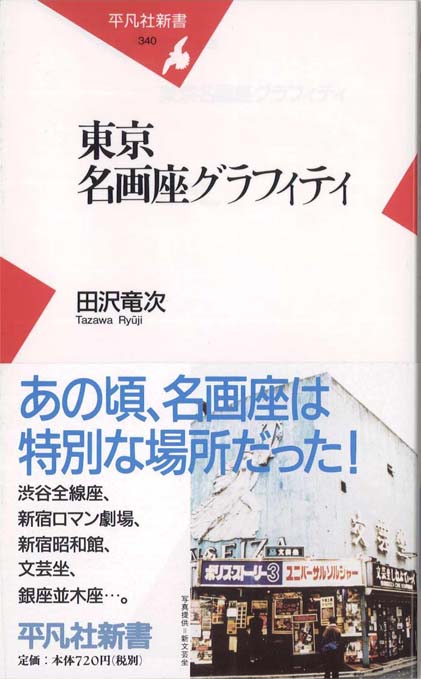
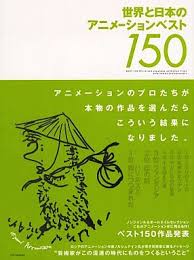
![死の教室 [THE DEAD CLASS] vhs 小.jpg](http://hurec.bz/book-movie/%E6%AD%BB%E3%81%AE%E6%95%99%E5%AE%A4%20%5BTHE%20DEAD%20CLASS%5D%20vhs%20%E5%B0%8F.jpg)




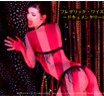



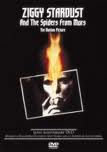
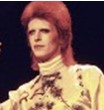


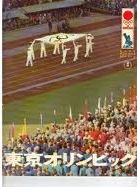
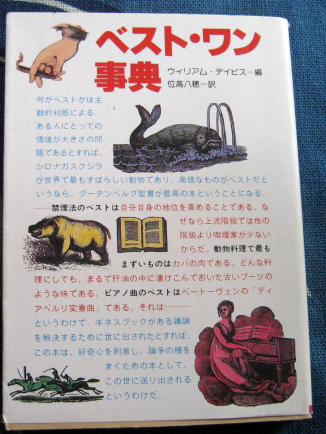
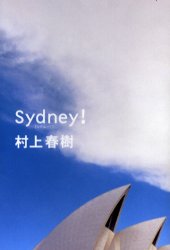





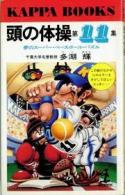

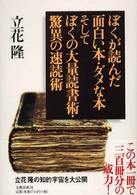
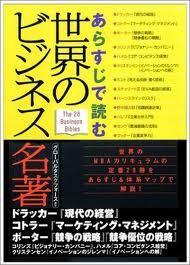

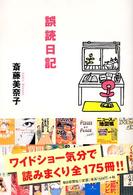
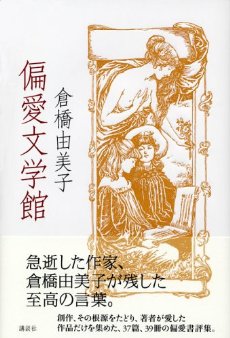



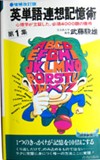
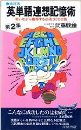

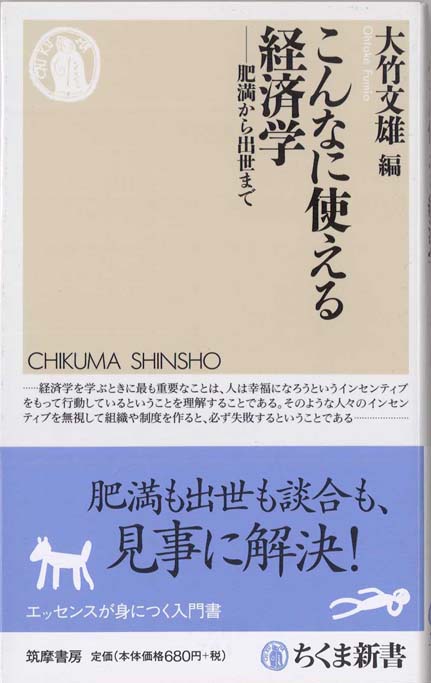




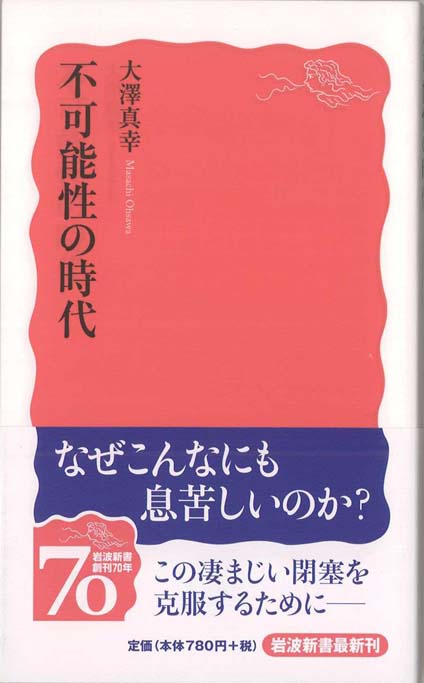
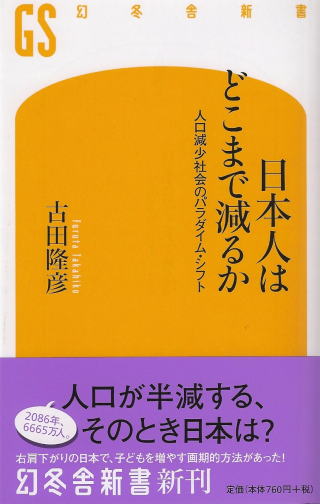



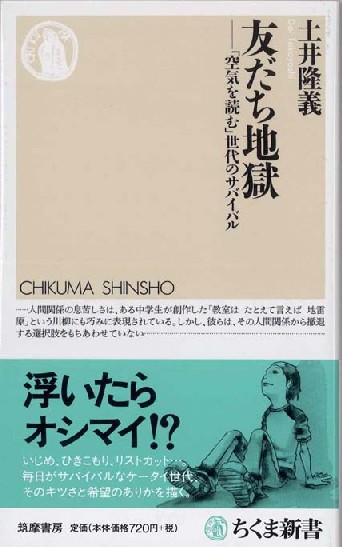
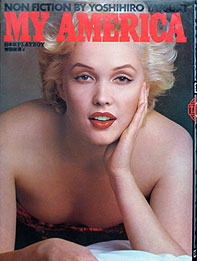
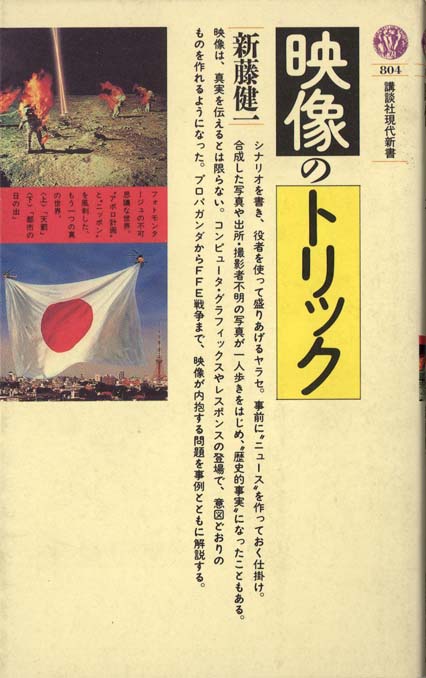

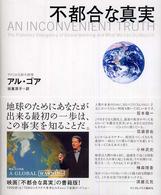
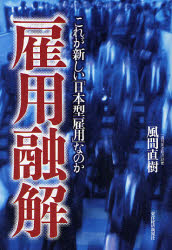
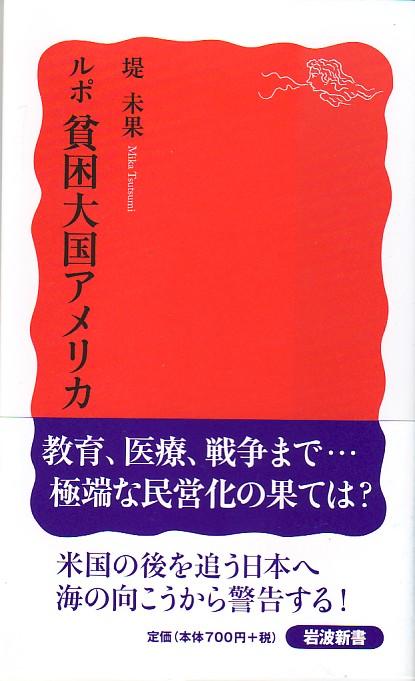
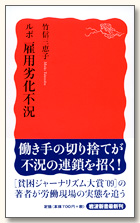
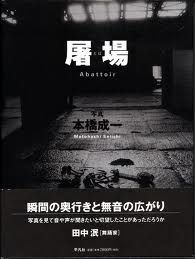

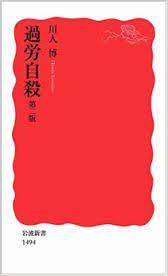
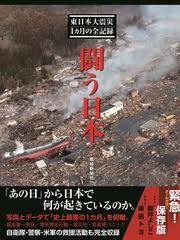

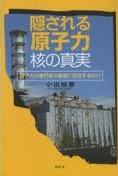
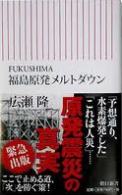


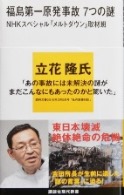






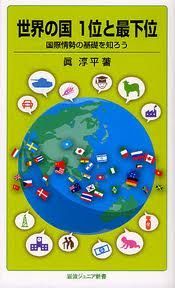





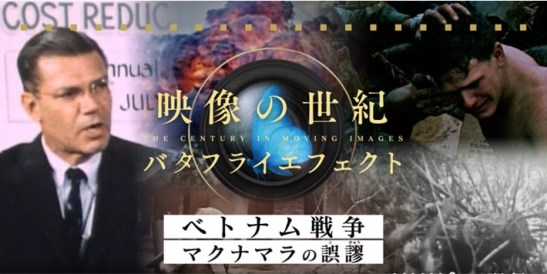

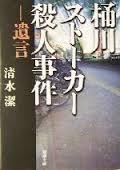
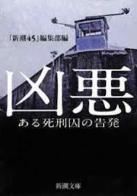
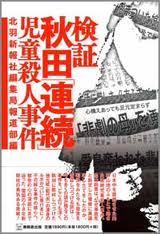
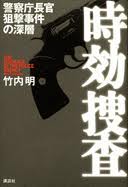
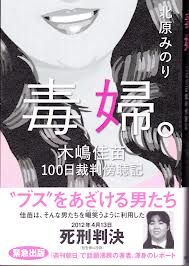
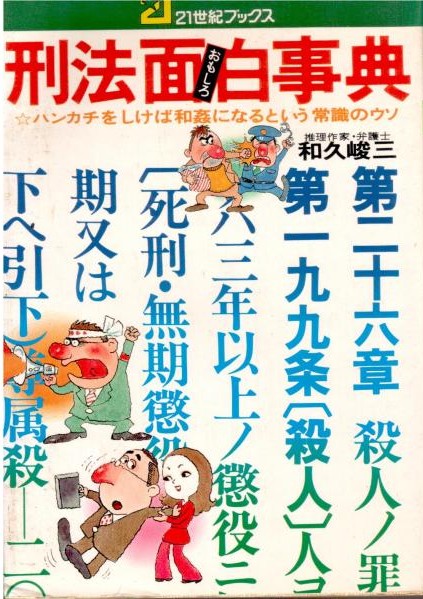




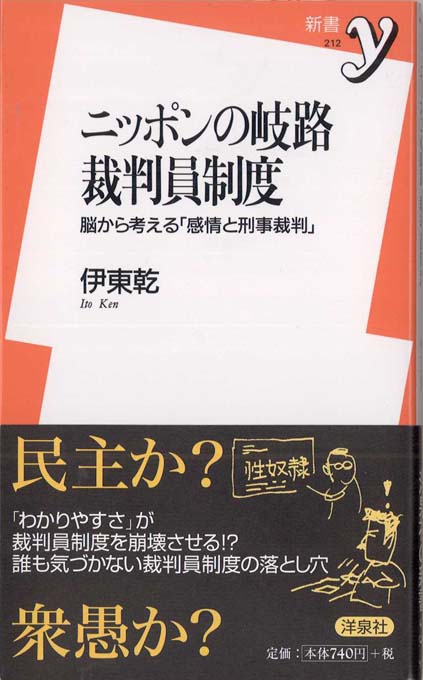
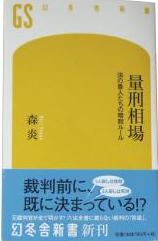


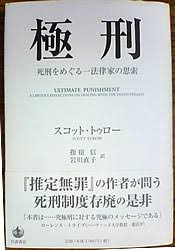

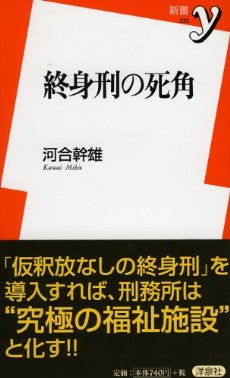
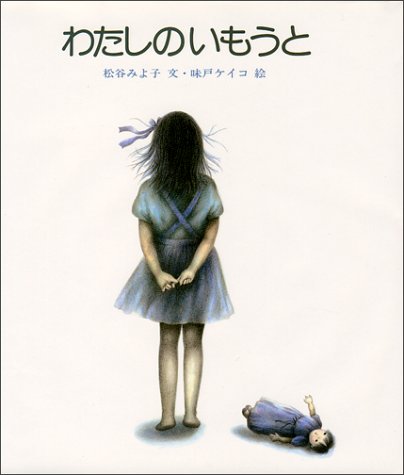
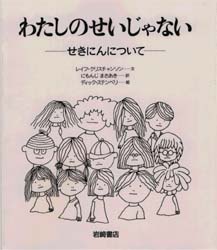

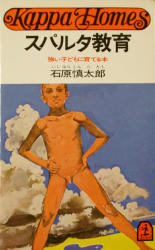
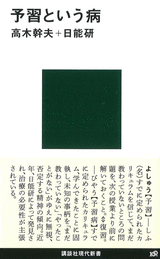





 2008年(平成20年)物理学賞/益川 敏英 名古屋大学理学部卒、同大学院博士課程修了 (小林・益川理論とCP対称性の破れの起源の発見による素粒子物理学への貢献・1/4)
2008年(平成20年)物理学賞/益川 敏英 名古屋大学理学部卒、同大学院博士課程修了 (小林・益川理論とCP対称性の破れの起源の発見による素粒子物理学への貢献・1/4) 2008年(平成20年)化学賞/下村 脩 旧制長崎医科大学附属薬学専門部卒、名古屋大学理学部研究生を経て博士号取得 (緑色蛍光タンパク質 (GFP) の発見と生命科学への貢献・1/3)
2008年(平成20年)化学賞/下村 脩 旧制長崎医科大学附属薬学専門部卒、名古屋大学理学部研究生を経て博士号取得 (緑色蛍光タンパク質 (GFP) の発見と生命科学への貢献・1/3)


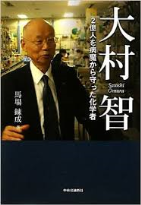

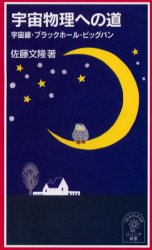
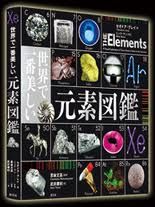
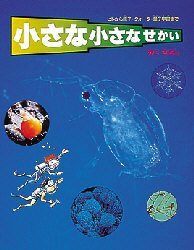
.gif)
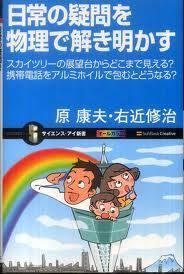
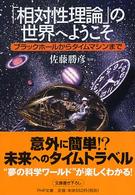
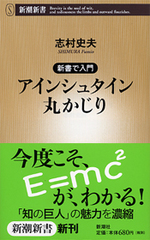
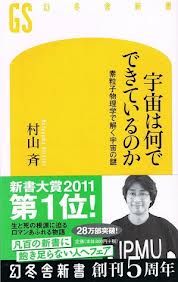


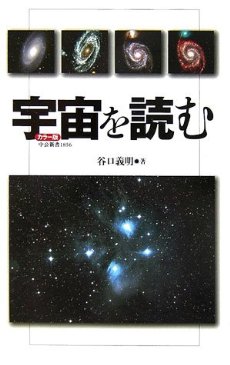

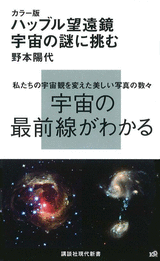
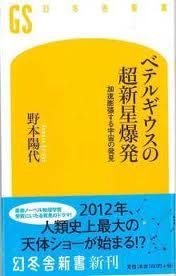
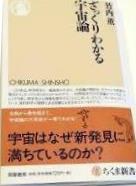


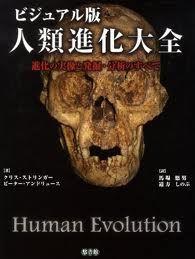

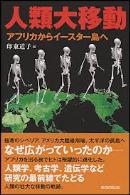
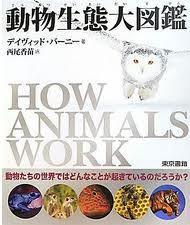




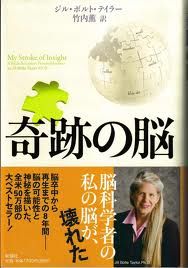


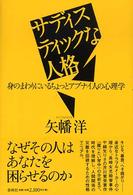



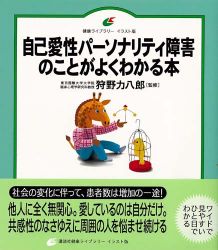

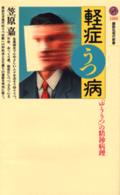



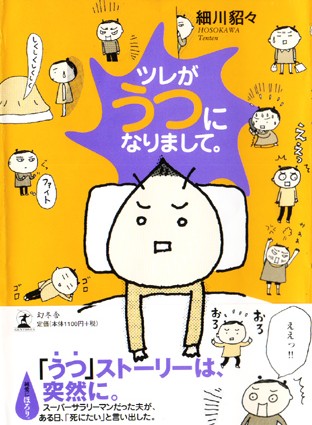





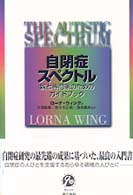

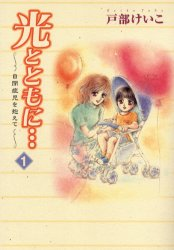

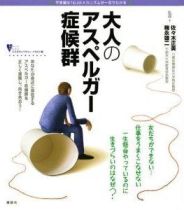
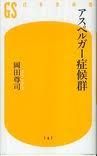
の子どもたち.jpg)




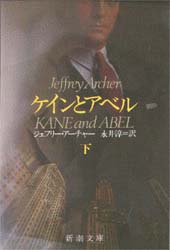
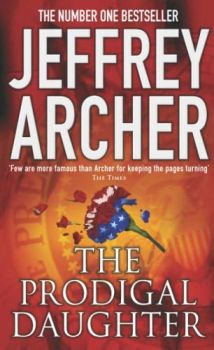
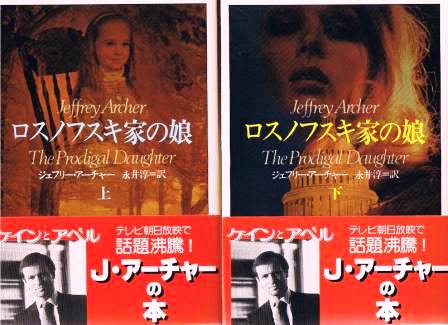
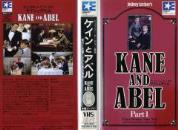




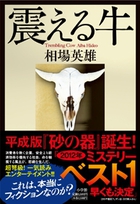
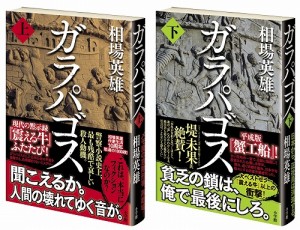
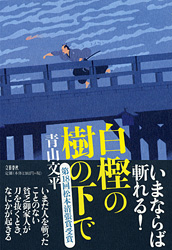
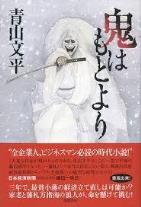

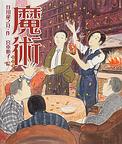
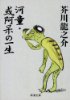

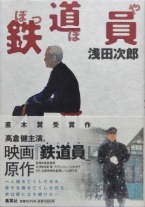

.jpg)

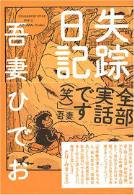


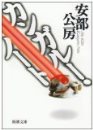







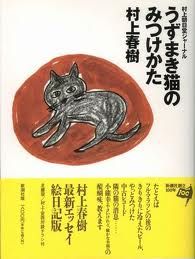

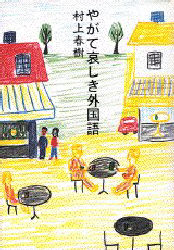
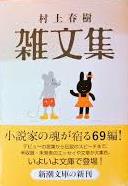
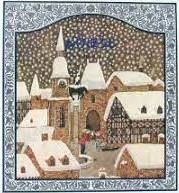
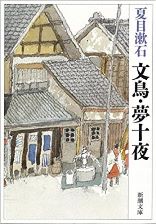
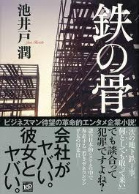
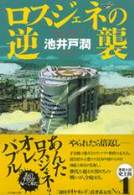
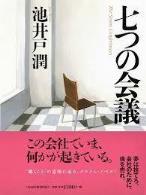




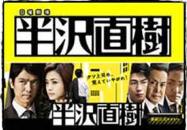






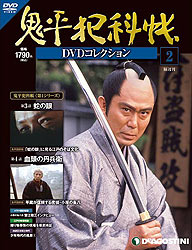





 3 関連
3 関連 
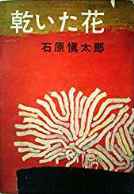
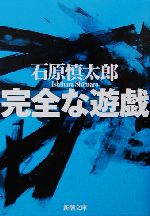


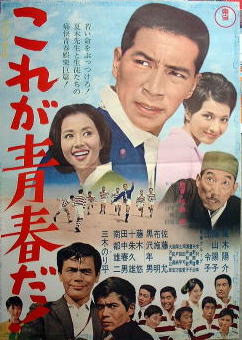

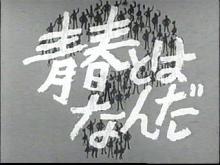
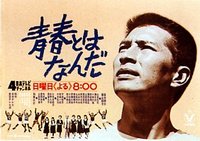
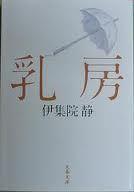
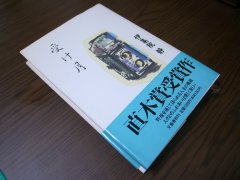
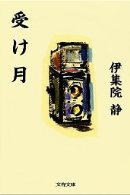
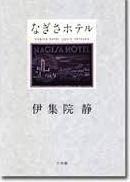








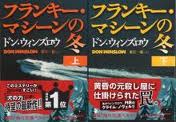


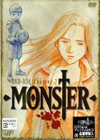


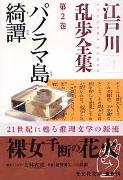

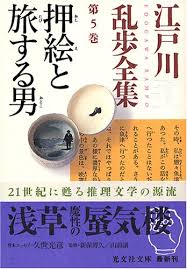
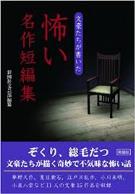



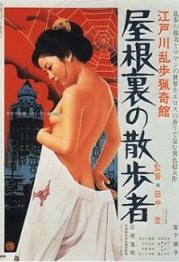





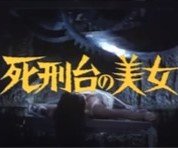

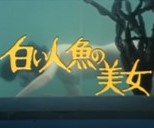

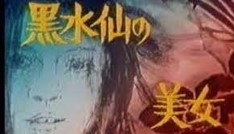







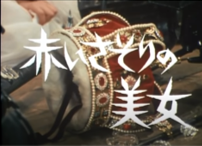

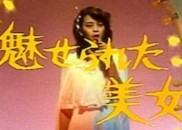

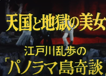

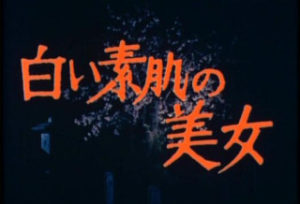

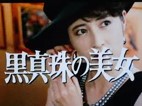
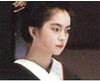



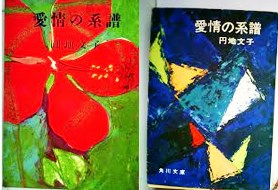
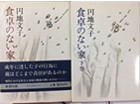




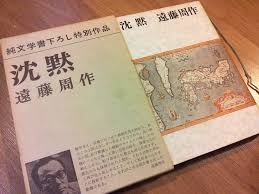

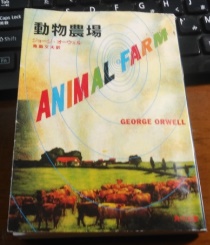
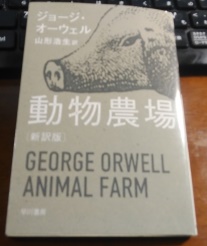



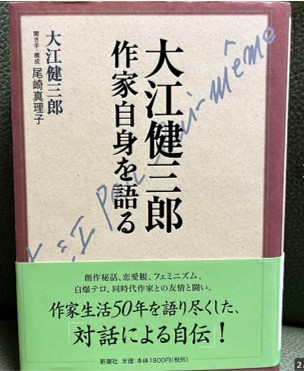
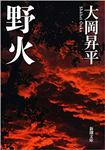




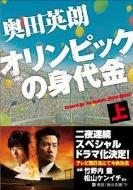
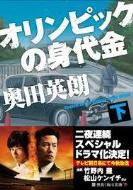



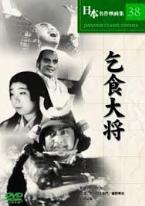




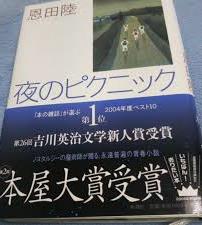

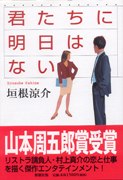
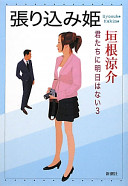
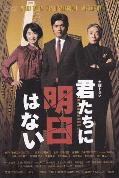

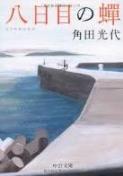



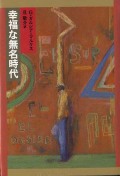
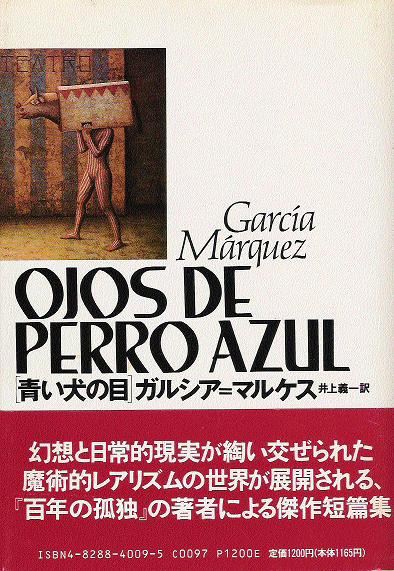
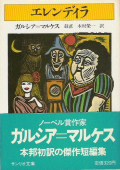
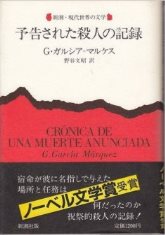

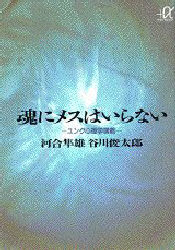
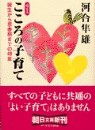
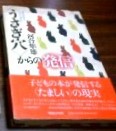
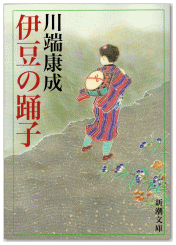

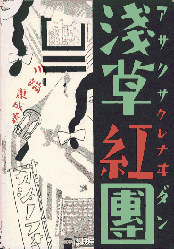




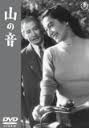

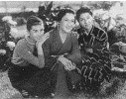
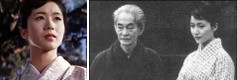
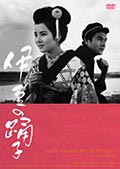



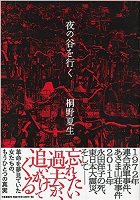
![魂萌え! [DVD].jpg](/book-movie/archives/魂萌え! [DVD].jpg)
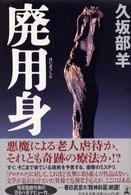
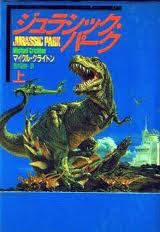
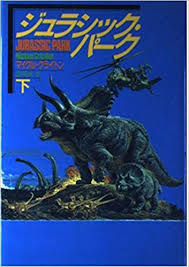




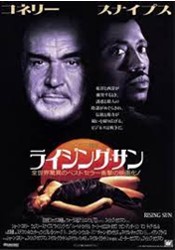

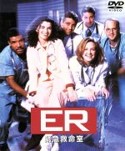





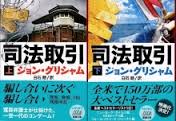



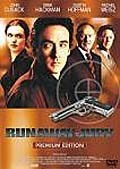


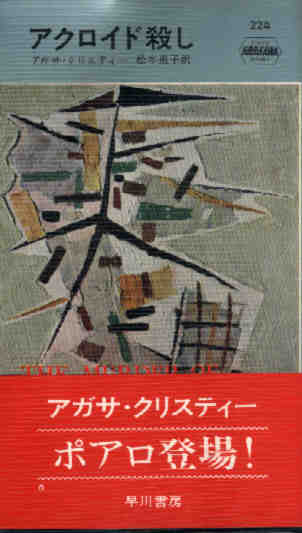
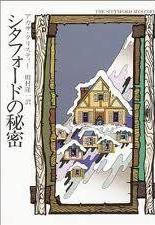



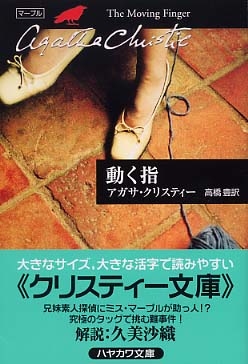
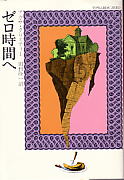
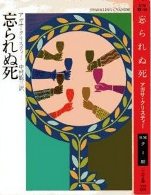
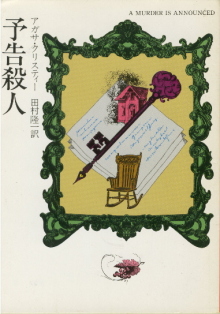

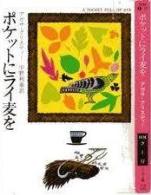
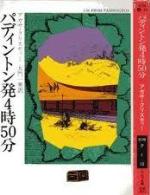


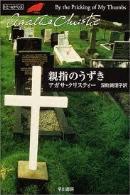


















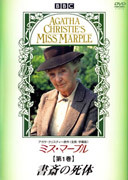
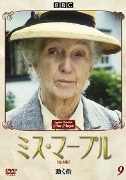
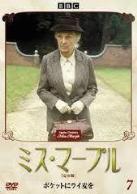
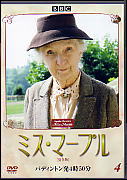

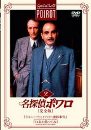
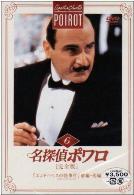

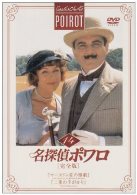
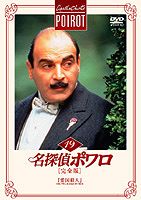
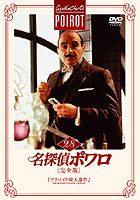
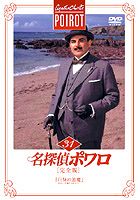
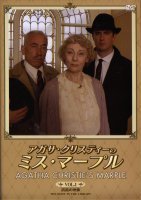

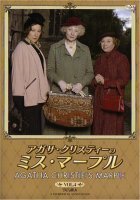
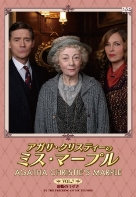
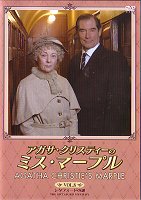
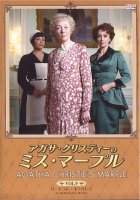
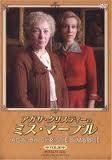
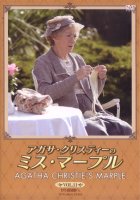
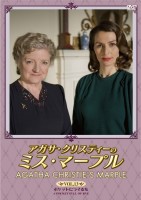
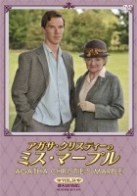
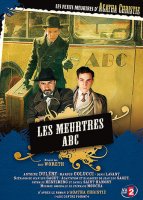
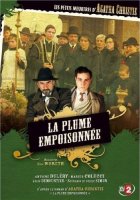
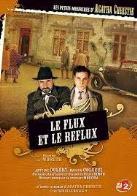
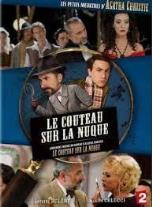
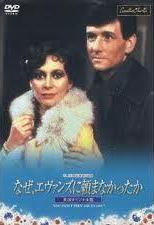



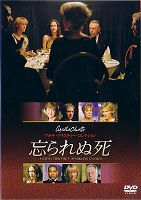

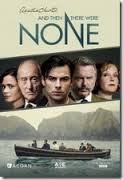





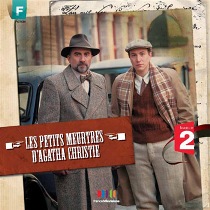
![名探偵ポワロ [レンタル落ち] 全52巻.jpg](http://hurec.bz/book-movie/%E5%90%8D%E6%8E%A2%E5%81%B5%E3%83%9D%E3%83%AF%E3%83%AD%20%5B%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%AB%E8%90%BD%E3%81%A1%5D%20%E5%85%A852%E5%B7%BB.jpg)


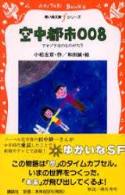
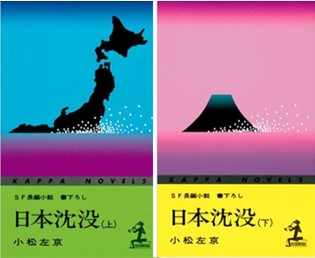
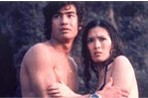


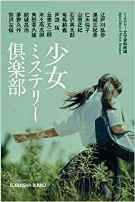
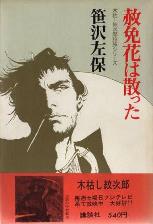
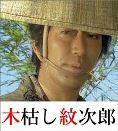
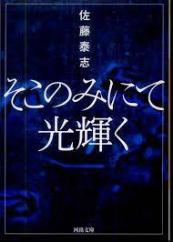

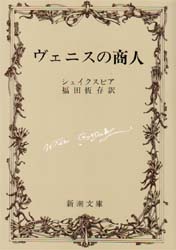
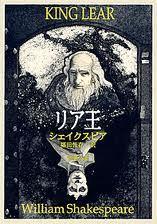






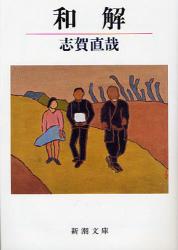
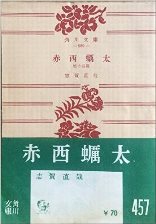
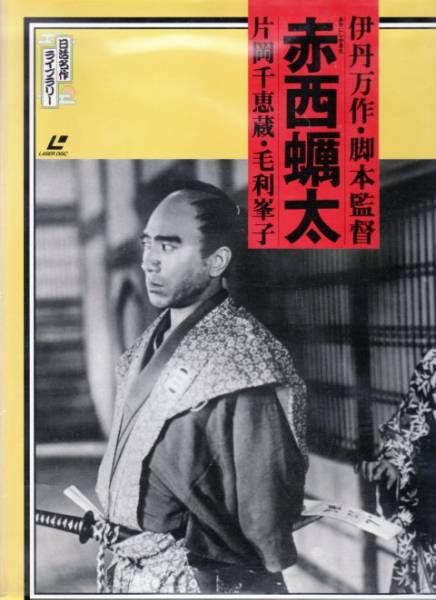

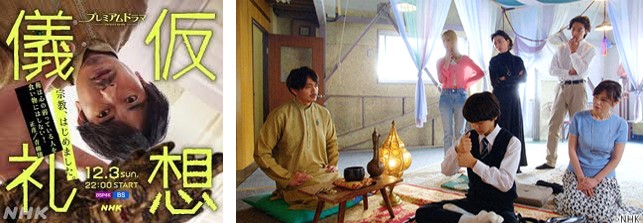

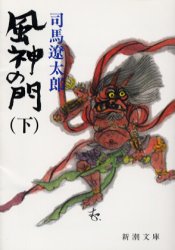
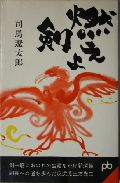

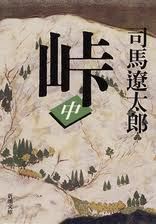
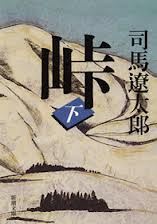
.png)

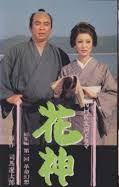
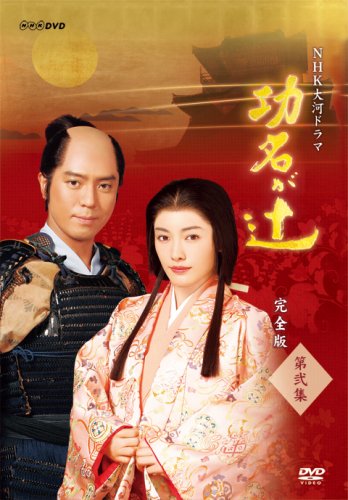


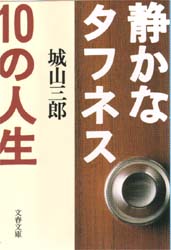
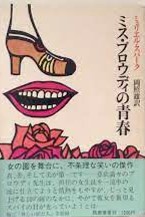
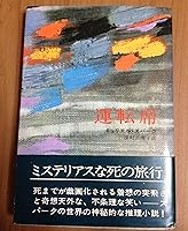 映
映 



















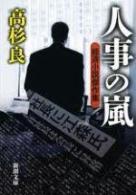



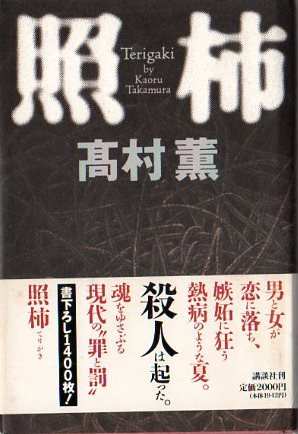
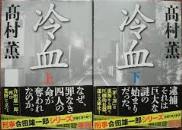


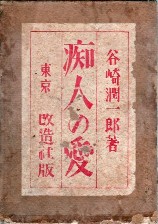
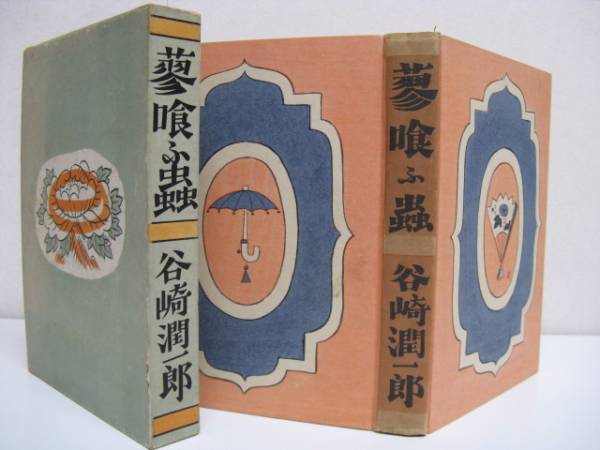


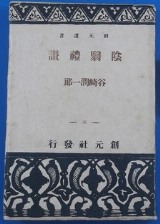


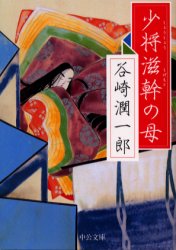

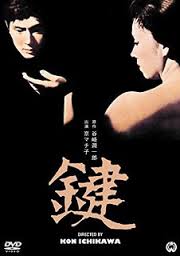



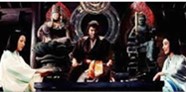

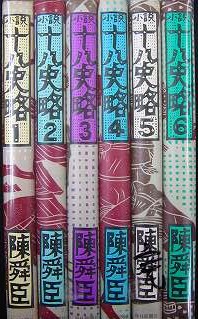
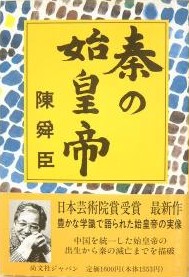
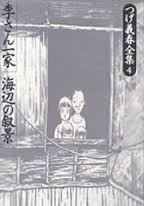



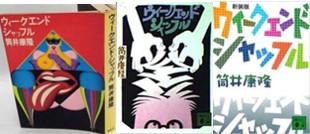
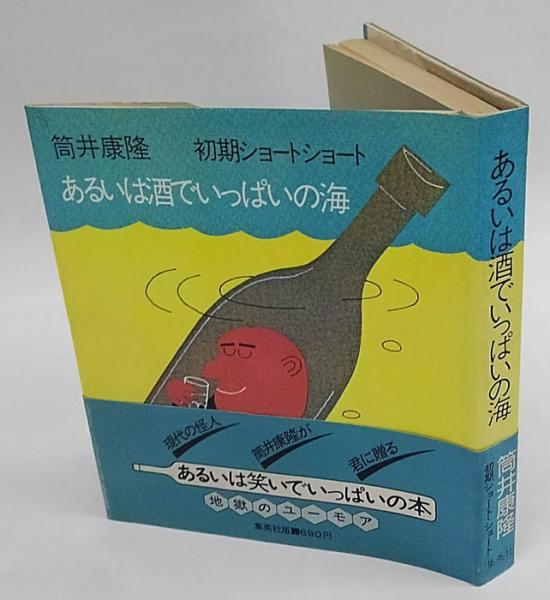
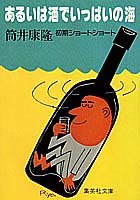
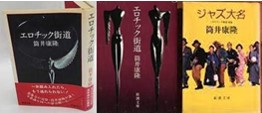
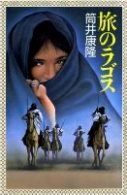
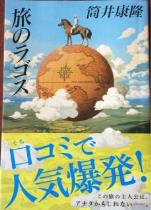
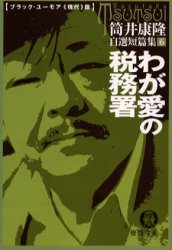
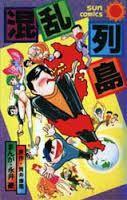


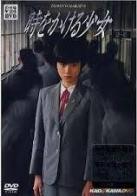






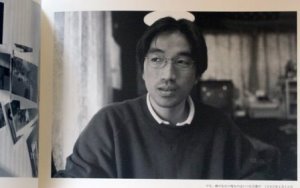
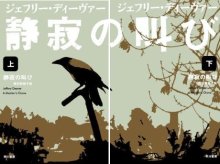
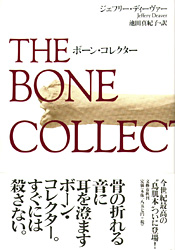
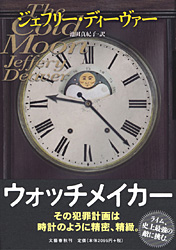
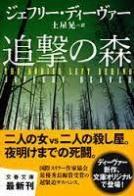
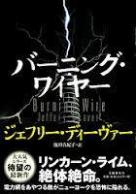
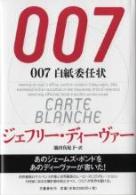
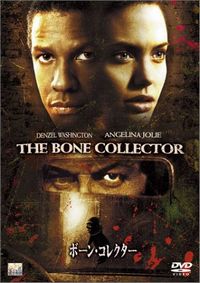

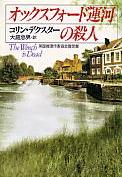


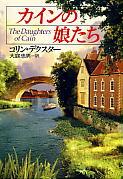
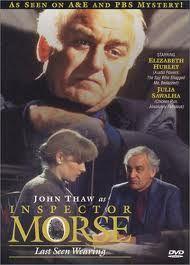





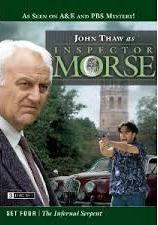






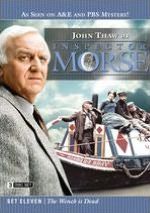

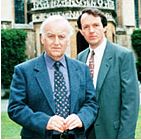
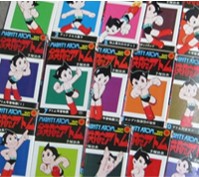
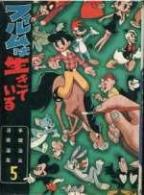
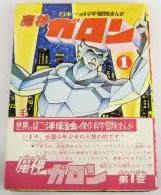

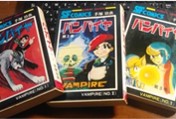
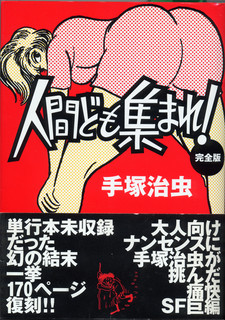
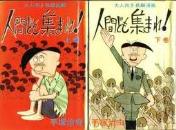


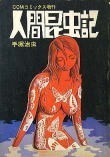
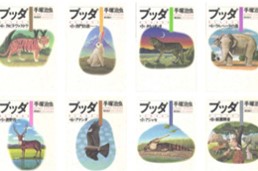
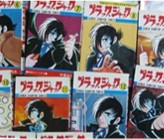

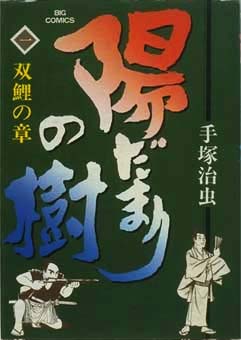






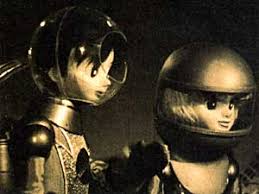



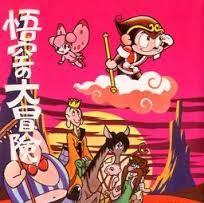
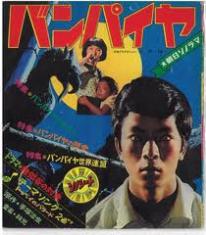







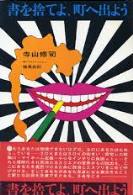
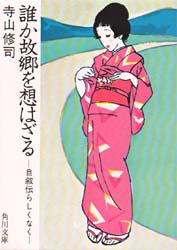
.jpg)

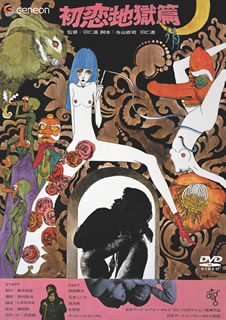


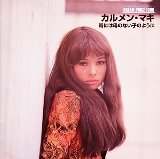
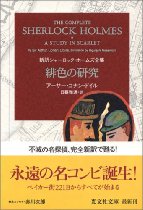









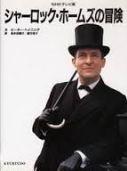



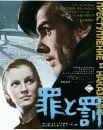


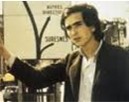

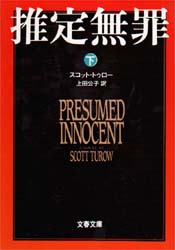
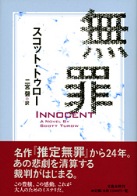

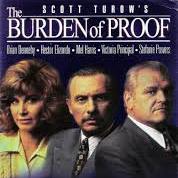

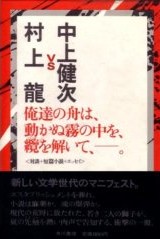
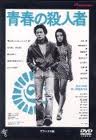



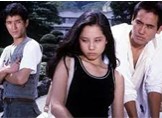
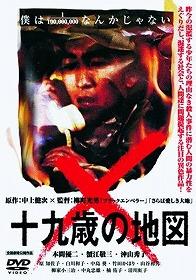


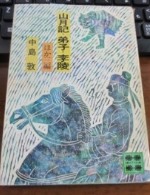


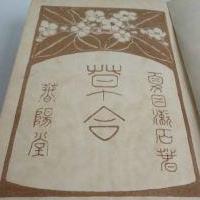
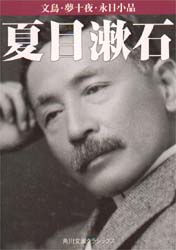












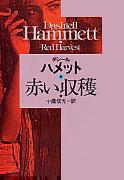
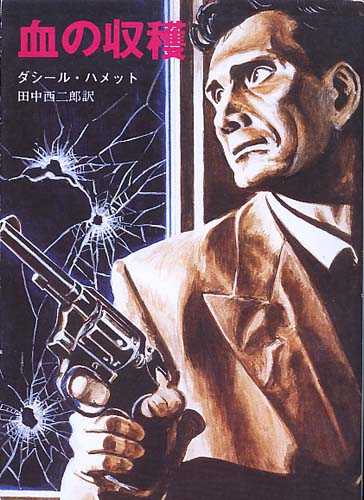
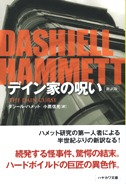

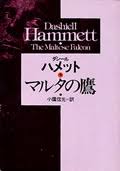





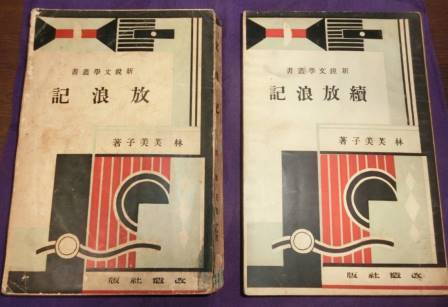
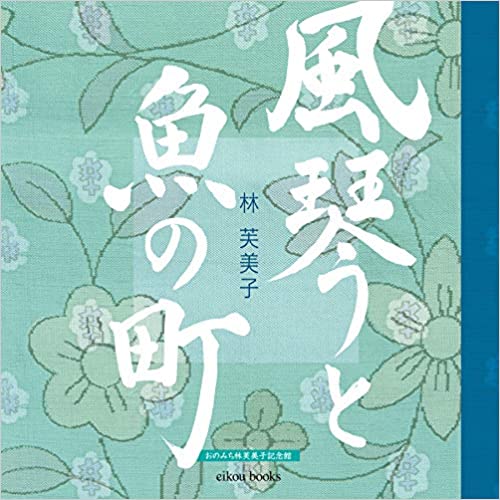






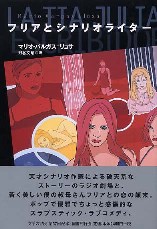

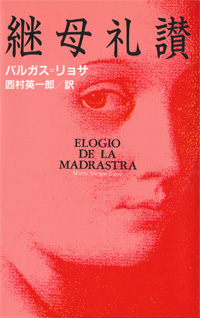
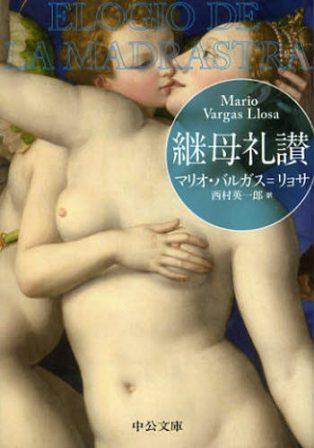
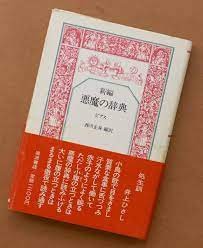 映
映 


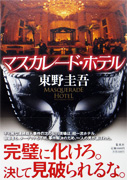
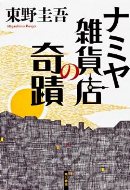
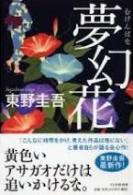


![「真夏の方程式]000jpg.jpg](http://hurec.bz/book-movie/%E3%80%8C%E7%9C%9F%E5%A4%8F%E3%81%AE%E6%96%B9%E7%A8%8B%E5%BC%8F%5D%EF%BC%90%EF%BC%90%EF%BC%90jpg.jpg)



.jpg)








![御宿かわせみ 選集 第一巻 [VHS].jpg](http://hurec.bz/book-movie/%E5%BE%A1%E5%AE%BF%E3%81%8B%E3%82%8F%E3%81%9B%E3%81%BF%20%E9%81%B8%E9%9B%86%20%E7%AC%AC%E4%B8%80%E5%B7%BB%20%5BVHS%5D.jpg)
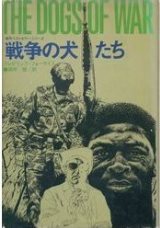

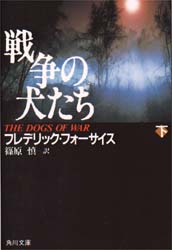

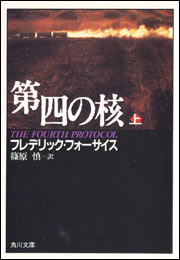
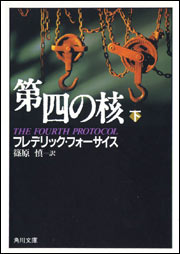


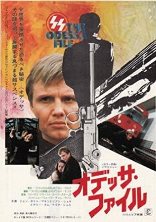


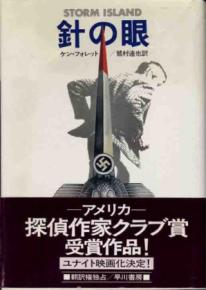

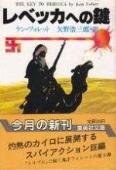
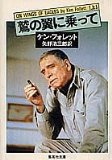
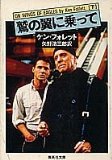





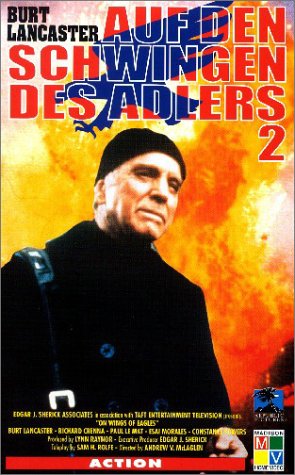

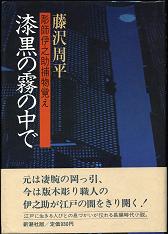
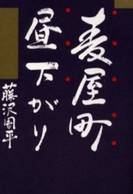
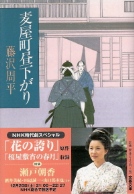
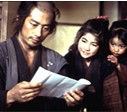


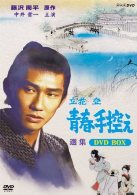






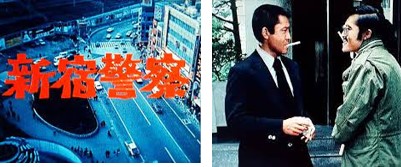


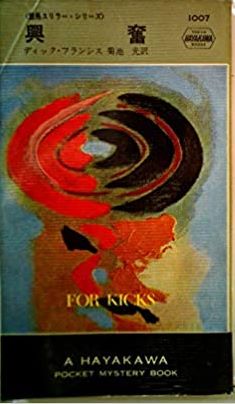
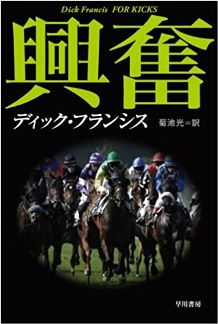
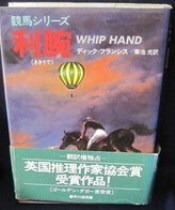
.bmp)
.gif)
.gif)
.jpg)
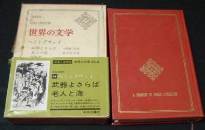


.jpg)




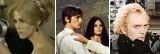


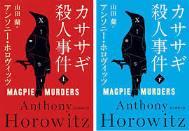
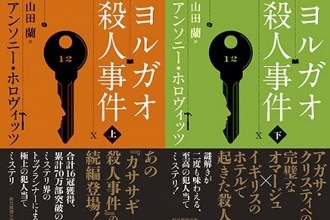





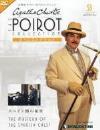




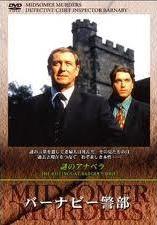

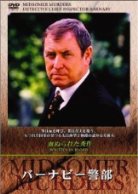

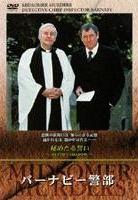

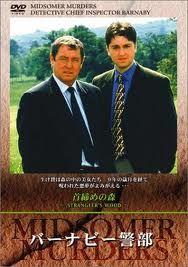


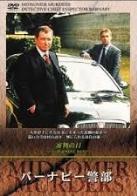



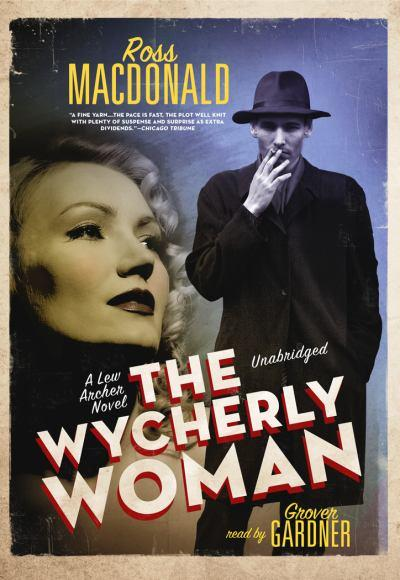



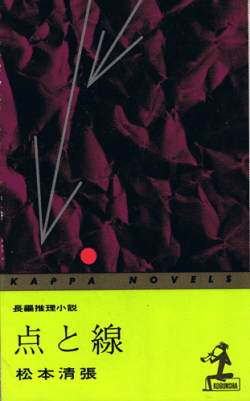



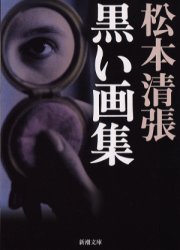
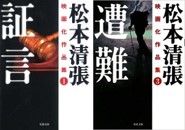
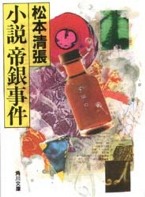
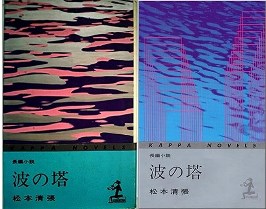
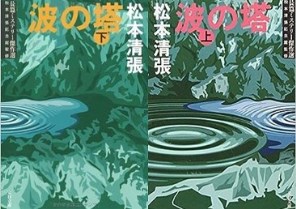

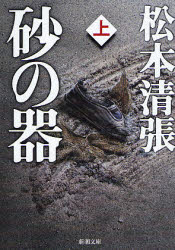

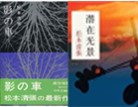

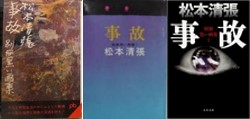
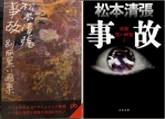

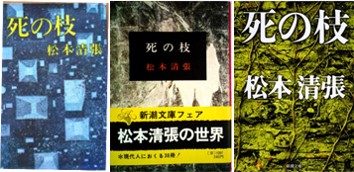

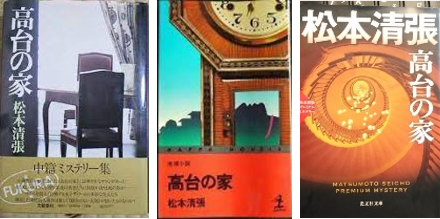

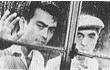












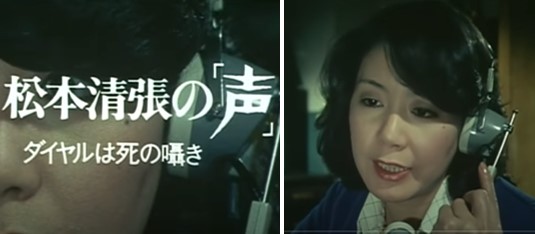

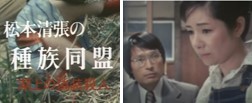



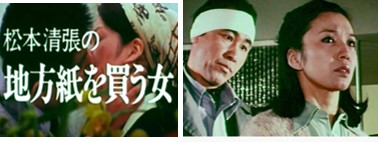
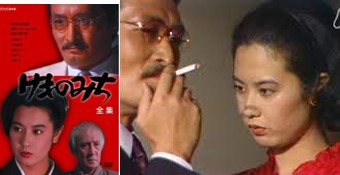

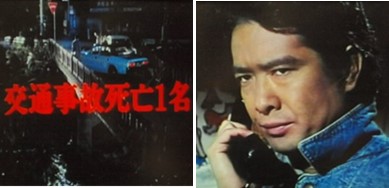












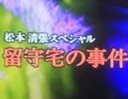





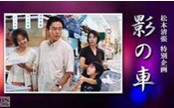
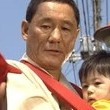







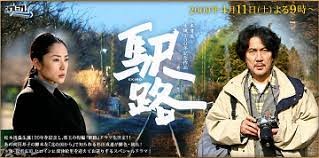



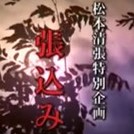




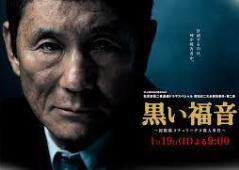

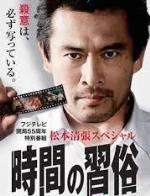







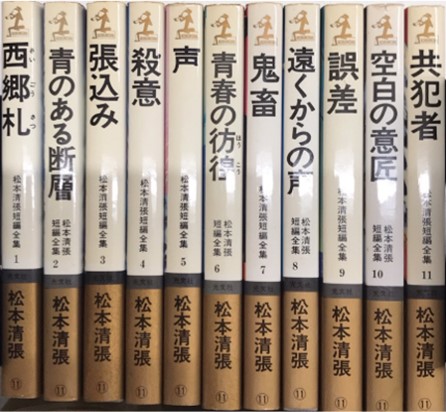
 【2976】 ○ 松本 清張 「顔」―『顔』 (1956/10 講談社ロマン・ブックス)/「顔」―『声―松本清張短編全集〈➎〉』 (1964/03 カッパ・ノベルス) ★★★★
【2976】 ○ 松本 清張 「顔」―『顔』 (1956/10 講談社ロマン・ブックス)/「顔」―『声―松本清張短編全集〈➎〉』 (1964/03 カッパ・ノベルス) ★★★★ 【2975】 ○ 松本 清張 「声」「白い闇」―『白い闇』 (1957/08 角川小説新書)/「声」―『声―松本清張短編全集〈➎〉』 (1964/03 カッパ・ノベルス) ★★★★
【2975】 ○ 松本 清張 「声」「白い闇」―『白い闇』 (1957/08 角川小説新書)/「声」―『声―松本清張短編全集〈➎〉』 (1964/03 カッパ・ノベルス) ★★★★ 【3092】 ○ 松本 清張 「事故」―『事故―別冊黒い画集』 (1963/09 ポケット文春) ★★★★
【3092】 ○ 松本 清張 「事故」―『事故―別冊黒い画集』 (1963/09 ポケット文春) ★★★★ 【3056】 ○ 松本 清張 「種族同盟」―『火と汐』 (1968/07 ポケット文春)《松本 清張ほか(著)/日本推理作家協会(編)『種族同盟―現代ミステリー傑作選1〈策謀・黒いユーモア編〉』 (1969/01 カッパ・ノベルス)》 ★★★★
【3056】 ○ 松本 清張 「種族同盟」―『火と汐』 (1968/07 ポケット文春)《松本 清張ほか(著)/日本推理作家協会(編)『種族同盟―現代ミステリー傑作選1〈策謀・黒いユーモア編〉』 (1969/01 カッパ・ノベルス)》 ★★★★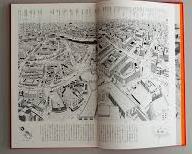
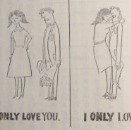


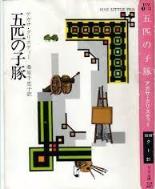
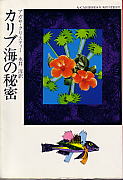


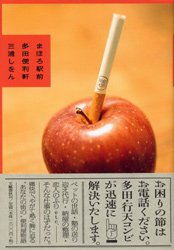
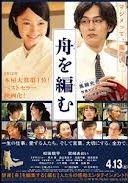




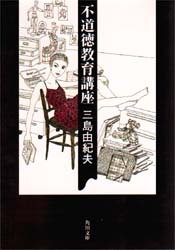
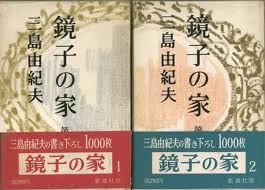
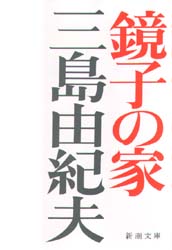
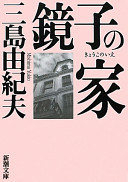

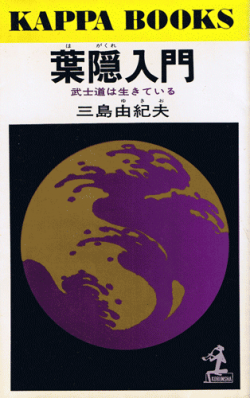
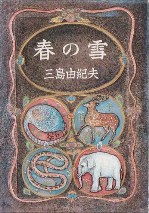


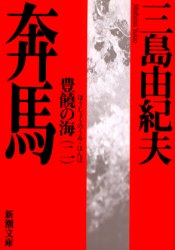



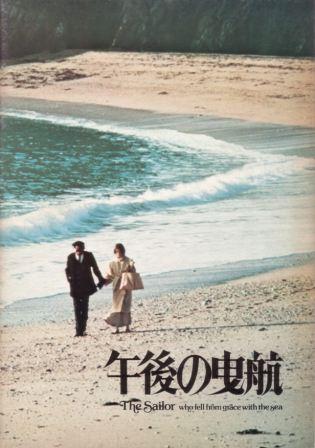





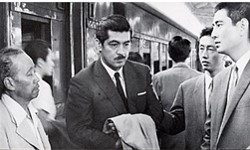


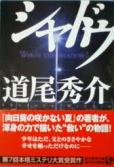
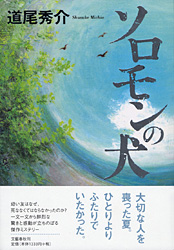



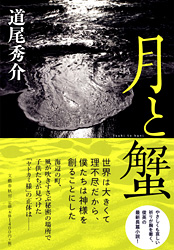








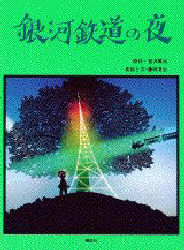
.jpg)




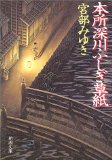
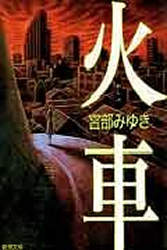
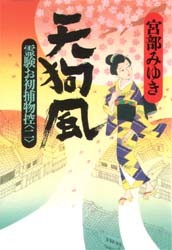
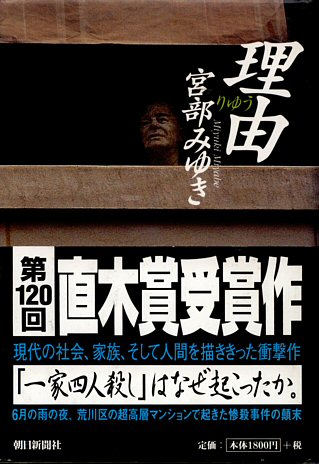



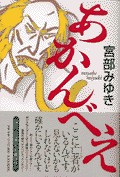
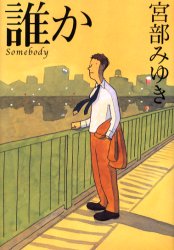


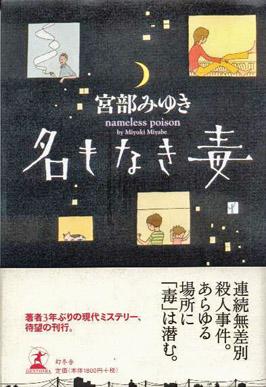

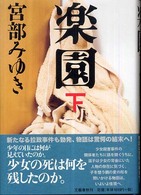
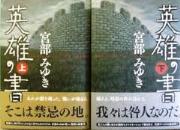
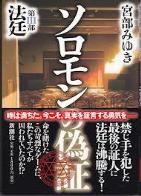


.bmp)



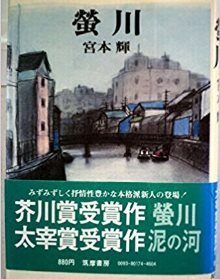


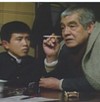


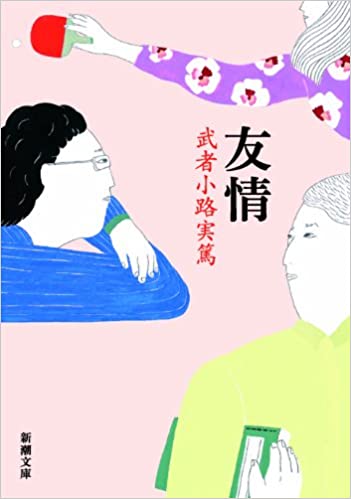
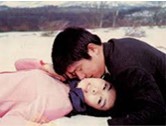
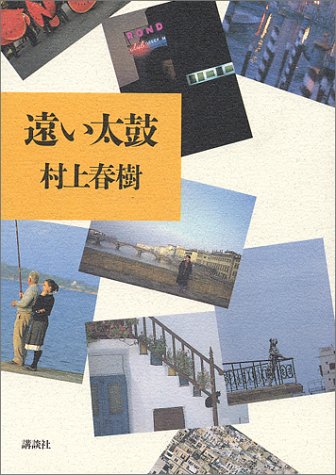

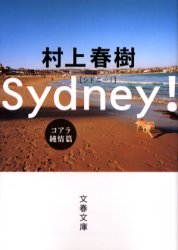





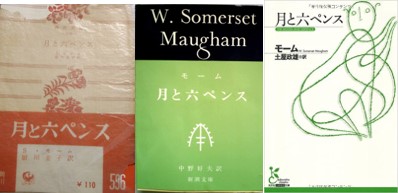
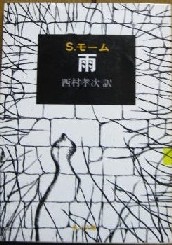

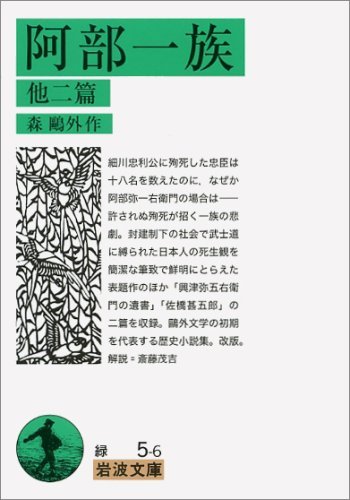

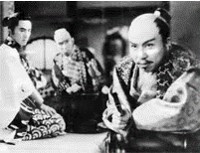



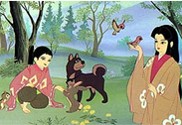
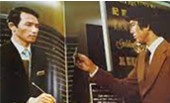
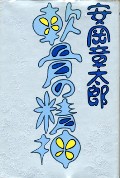
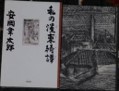


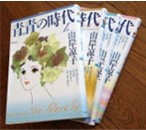
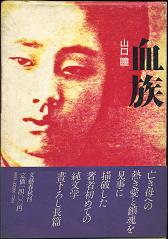

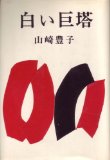









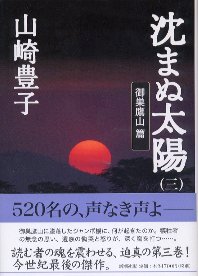

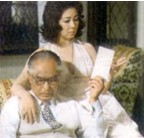


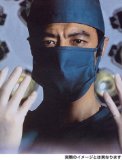




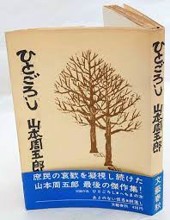






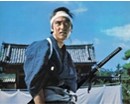
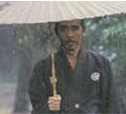


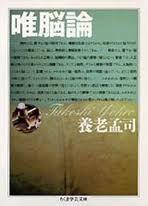
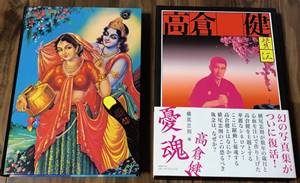

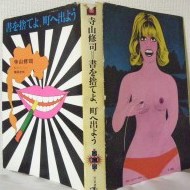


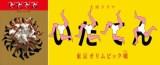


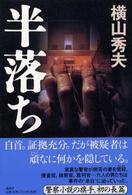
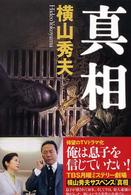
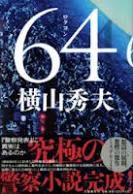

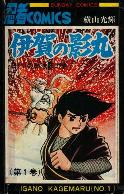
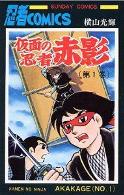



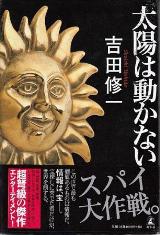
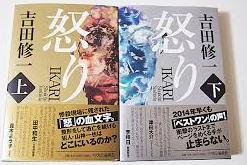




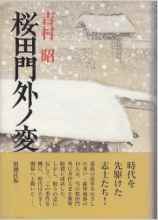
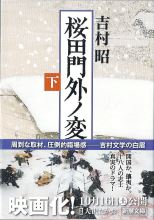




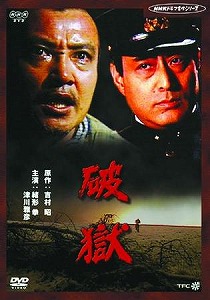


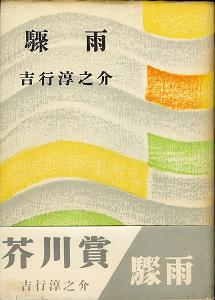

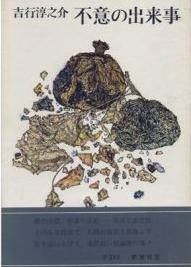
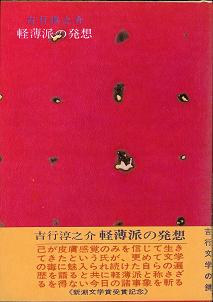
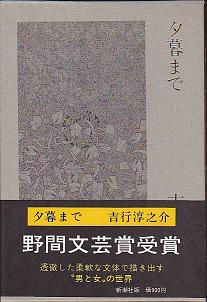

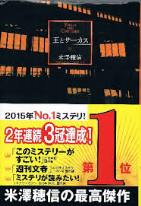
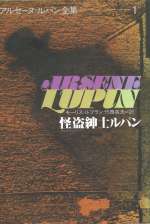
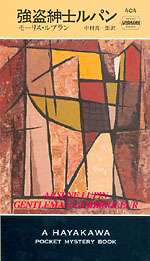

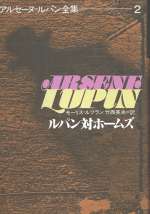
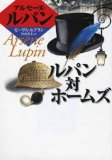




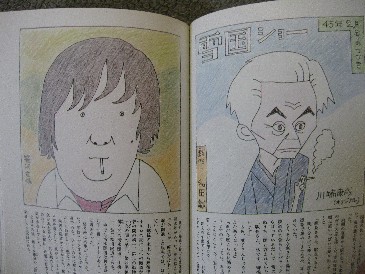


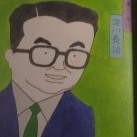


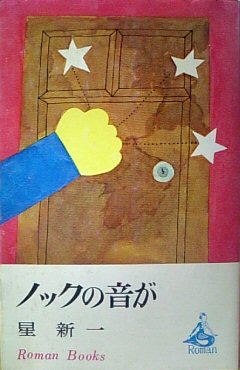
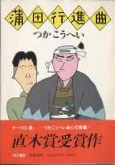
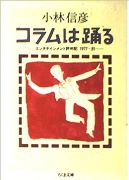








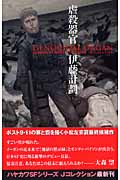

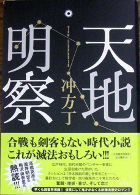

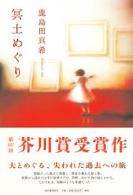





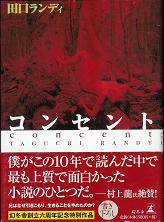



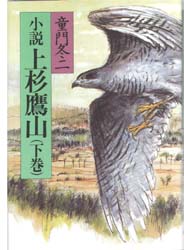

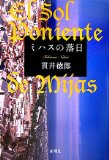
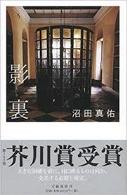

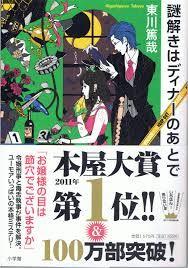
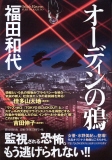



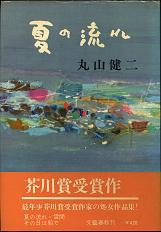

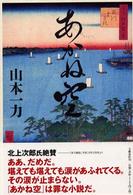

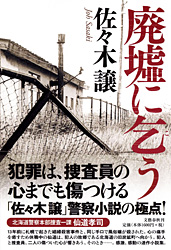
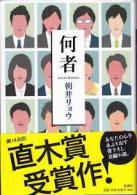
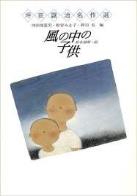



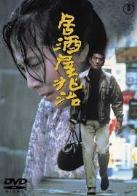


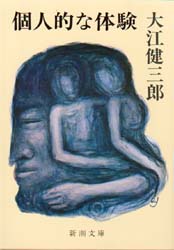
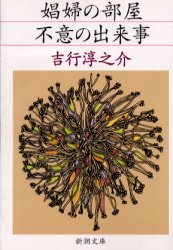

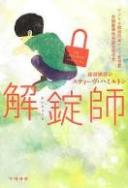
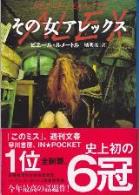
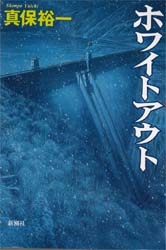

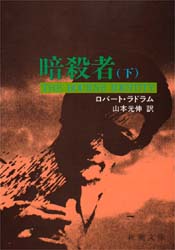
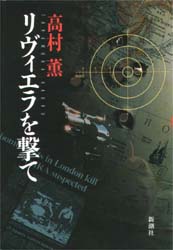
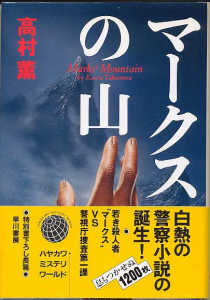
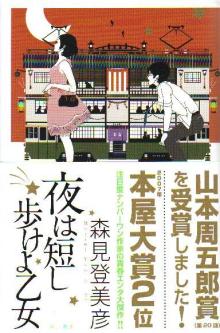
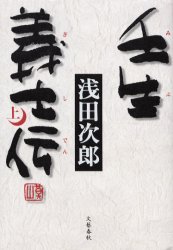

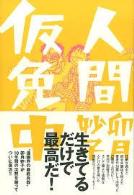
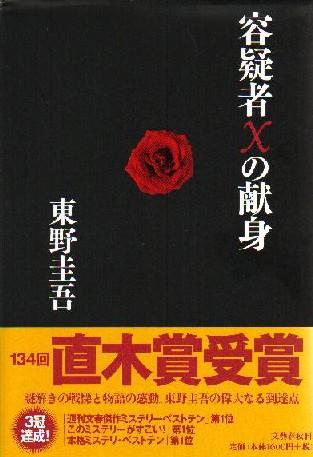
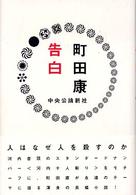

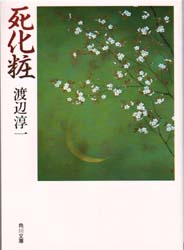

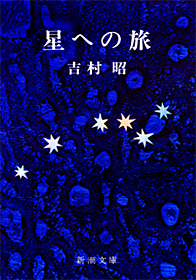
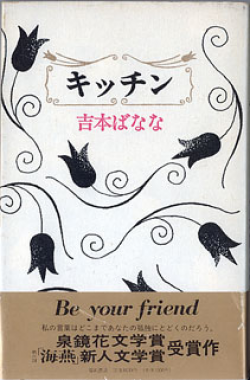

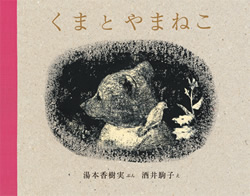
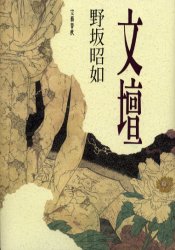
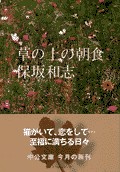
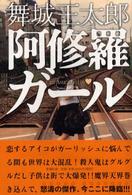
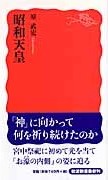

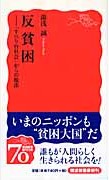

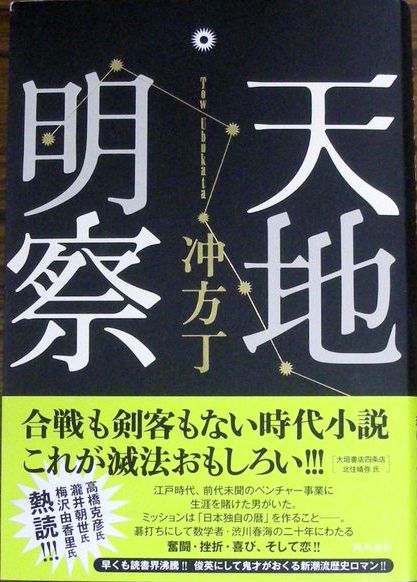
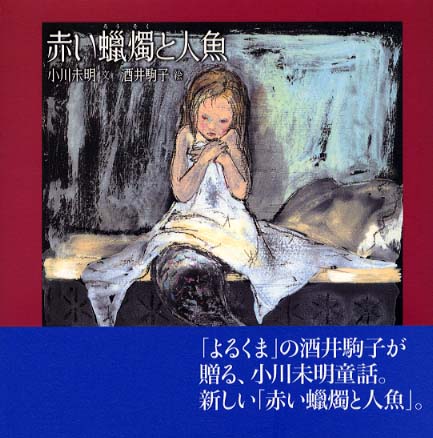
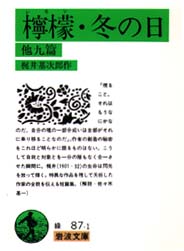

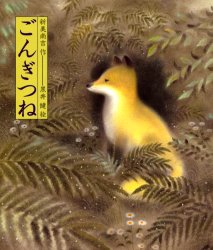
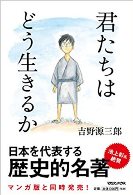


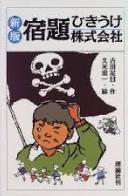
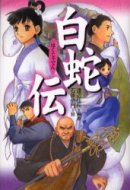
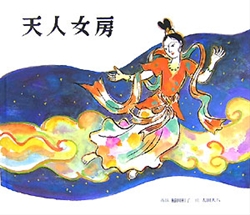
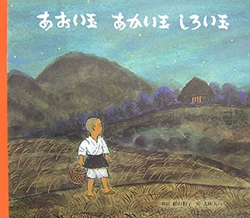
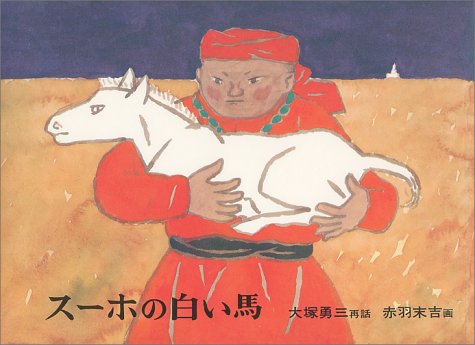
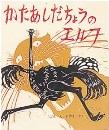
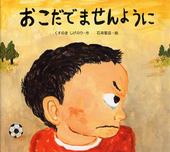
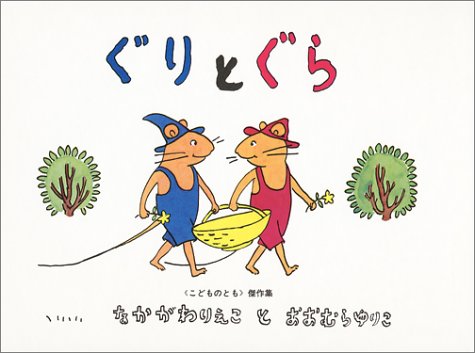
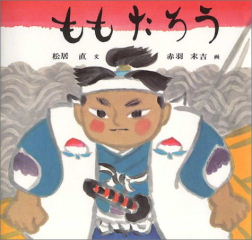
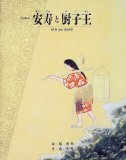
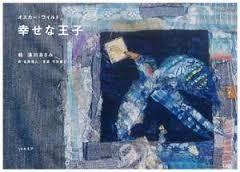
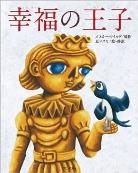
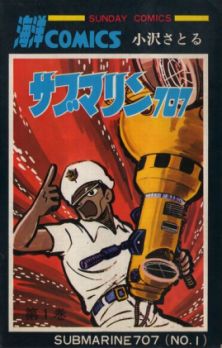
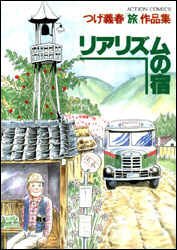
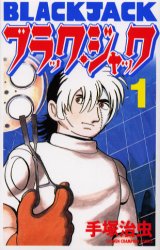

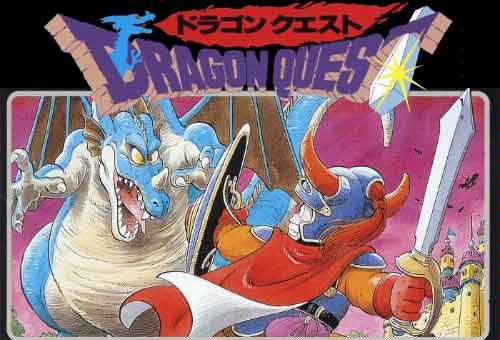

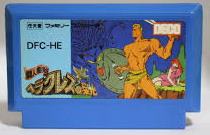

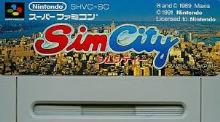


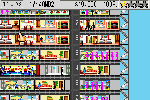
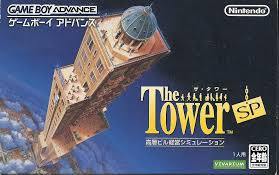
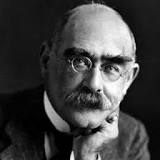 ●1907年
●1907年 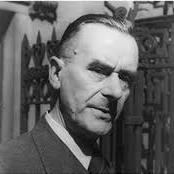 ●1929年
●1929年 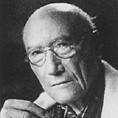 ●1947年
●1947年  ●1949年
●1949年  ●1954年
●1954年  ●1957年
●1957年  ●1962年
●1962年  ●1964年
●1964年  ●1965年
●1965年  ●1968年
●1968年  ●1970年
●1970年  ●1976年
●1976年  ●1982年
●1982年  ●1994年
●1994年 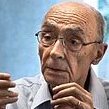 ●1998年
●1998年 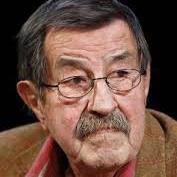 ●1999年
●1999年  ●2005年
●2005年  ●2010年
●2010年  ●2012年
●2012年  ●2014年
●2014年  ●2015年
●2015年  ●2016年
●2016年  ●2017年
●2017年  ●2019年
●2019年 
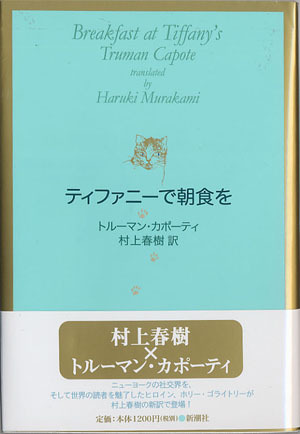


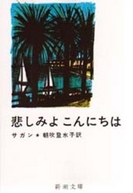

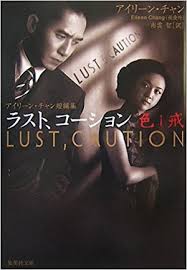


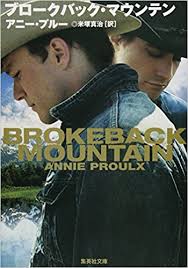
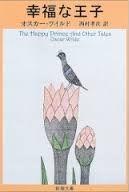

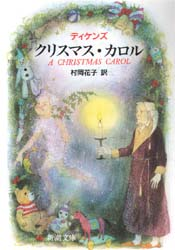
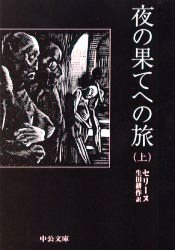
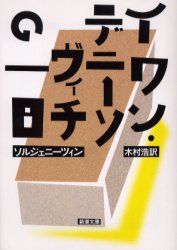
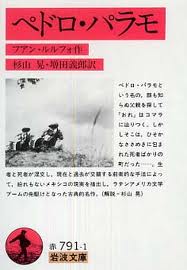
.jpg)

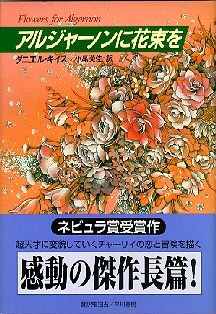
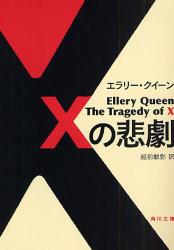
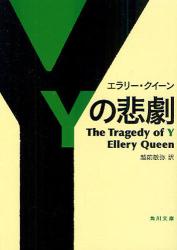

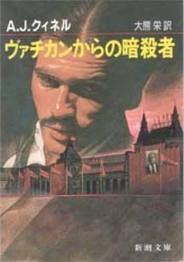


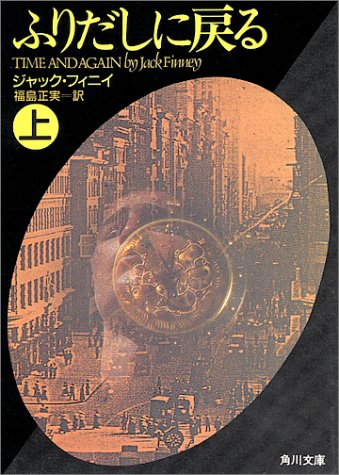
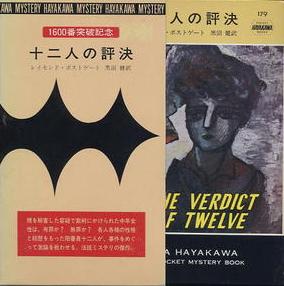
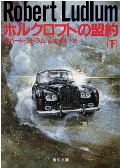
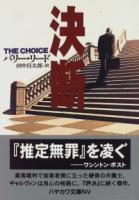




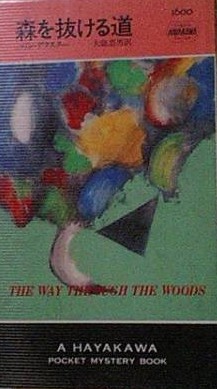
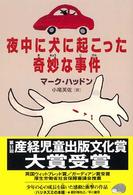
![異邦人[上].gif](/book-movie/archives/異邦人[上].gif)

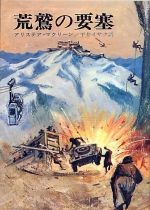
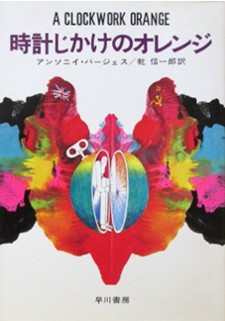

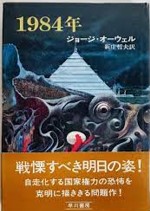
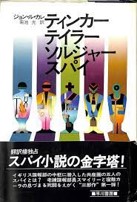
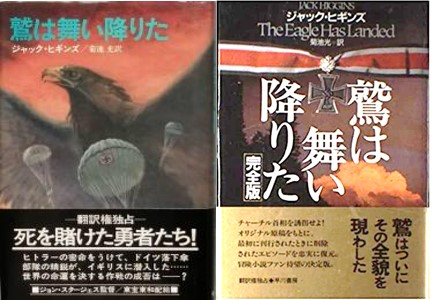
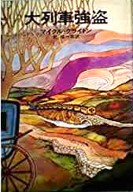
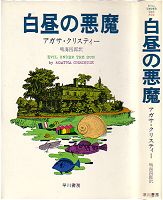
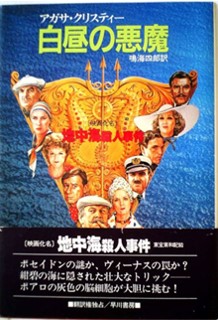
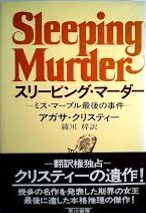
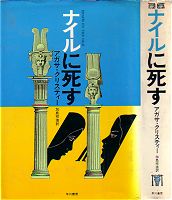
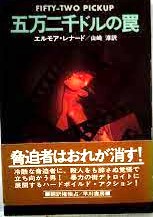
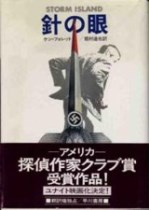
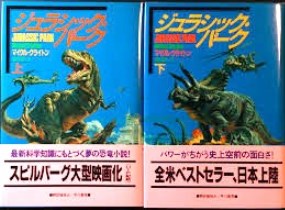

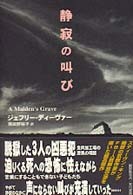

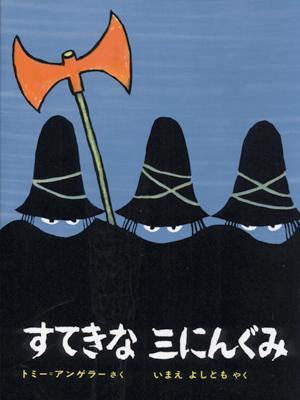
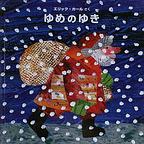
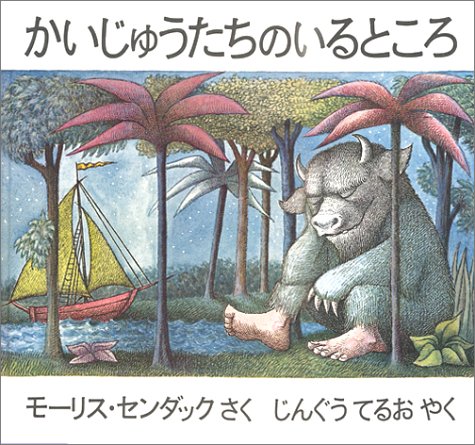
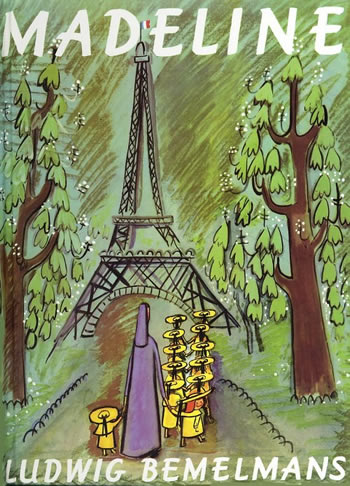
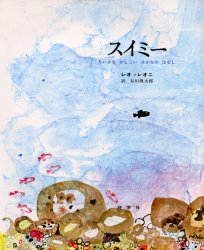
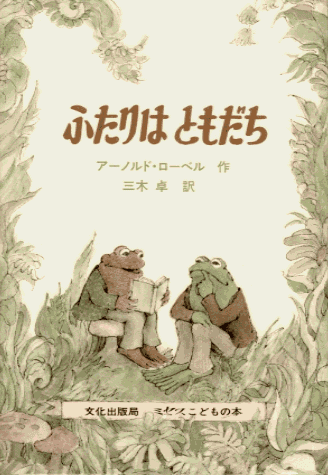

![東京の合唱(吹替・活弁版) [VHS] - 2.jpg](http://hurec.bz/book-movie/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E3%81%AE%E5%90%88%E5%94%B1%28%E5%90%B9%E6%9B%BF%EF%BD%A5%E6%B4%BB%E5%BC%81%E7%89%88%29%20%5BVHS%5D%20-%202.jpg)






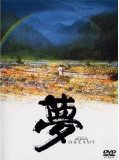
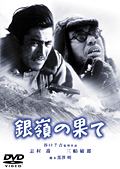


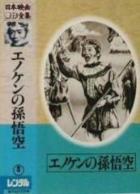
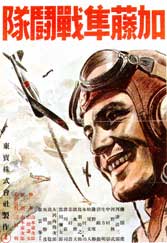
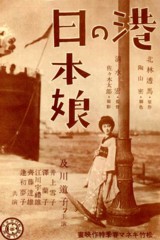

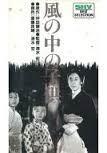
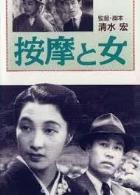



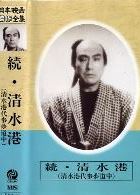
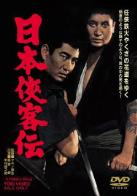

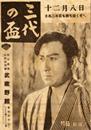

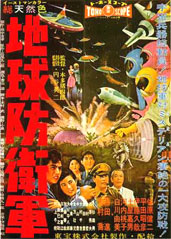
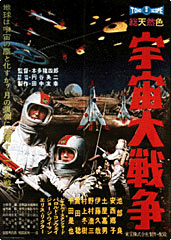

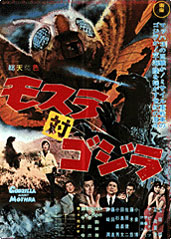
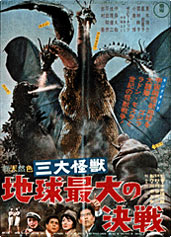
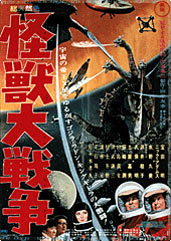
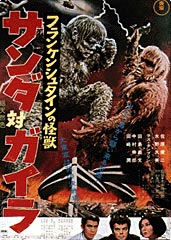
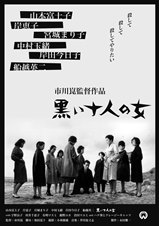
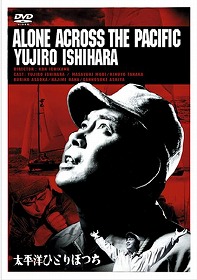
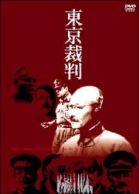


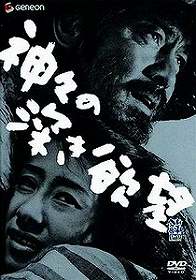




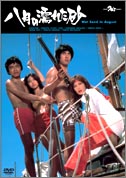
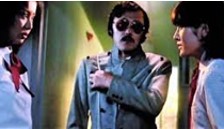


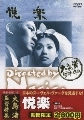

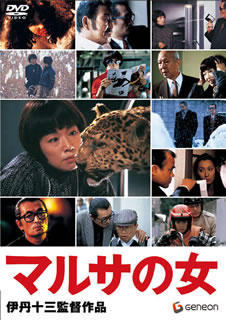
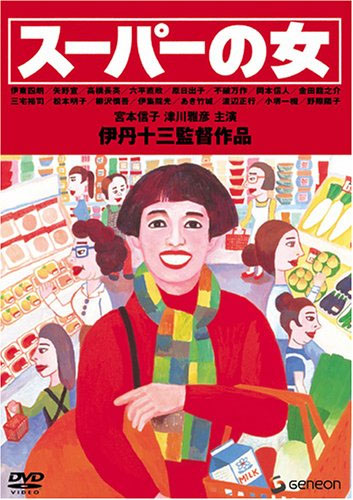









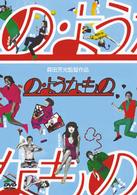
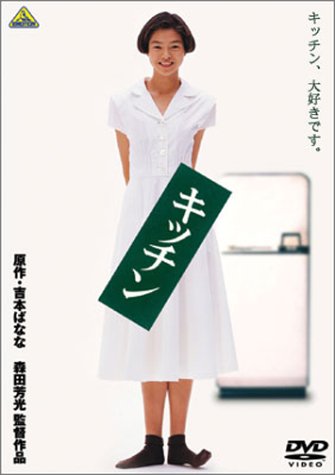

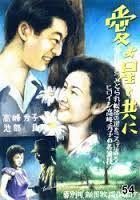
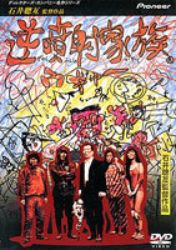

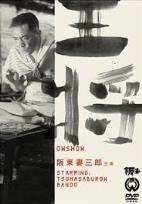

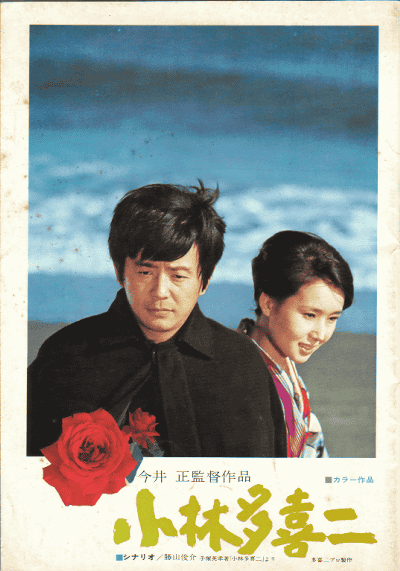


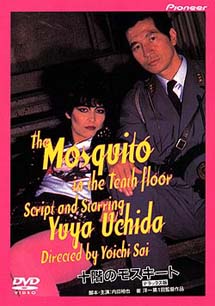
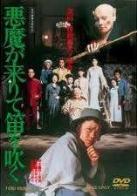
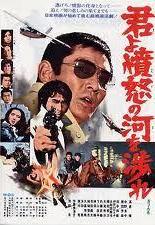
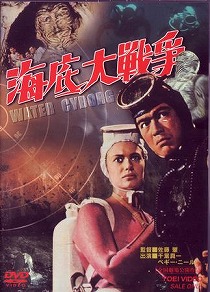
![Wの悲劇 [DVD].jpg](/book-movie/archives/Wの悲劇 [DVD].jpg)
.jpg)
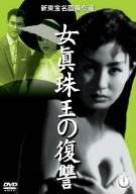
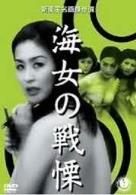

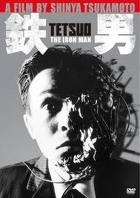


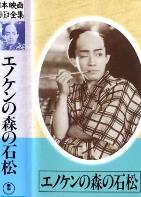
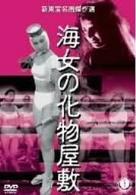
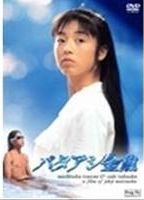
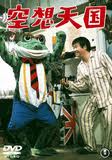

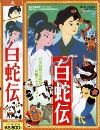

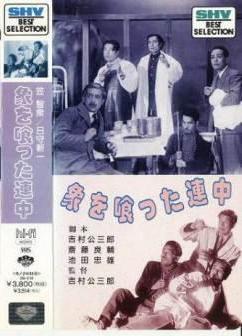
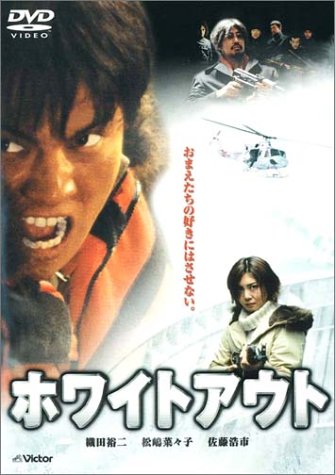


















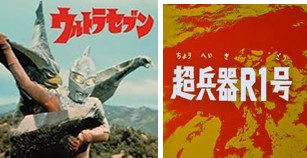



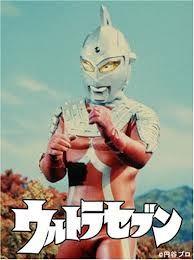


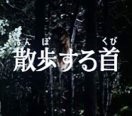

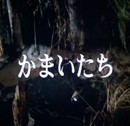















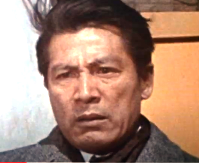










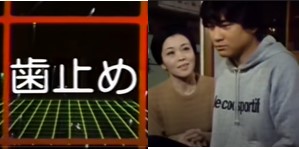








 『有りがたうさん』
『有りがたうさん』
 『按摩と女』
『按摩と女』
 『風の中の子供』
『風の中の子供』
 『大人の見る繪本 生れてはみたけれど』
『大人の見る繪本 生れてはみたけれど』
 『一人息子』
『一人息子』
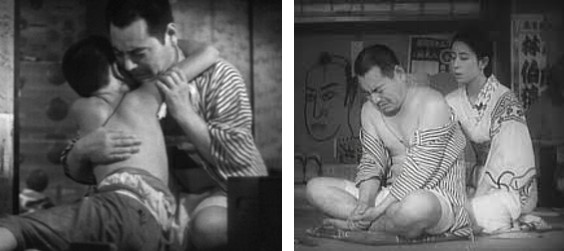 『出来ごころ/浮草物語(2枚組)』
『出来ごころ/浮草物語(2枚組)』
 『その夜の妻/非常線の女(2枚組)』
『その夜の妻/非常線の女(2枚組)』
 『東京の合唱/淑女と髯(2枚組)』
『東京の合唱/淑女と髯(2枚組)』
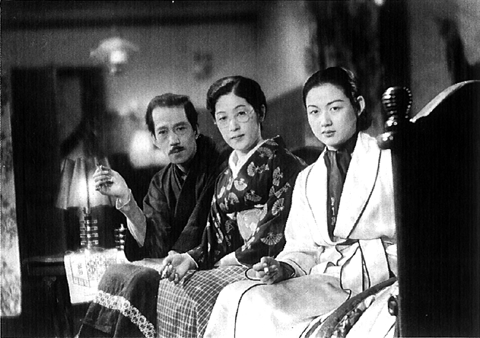 『淑女は何を忘れたか』
『淑女は何を忘れたか』
 『残菊物語』
『残菊物語』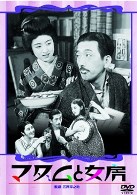
 『マダムと女房/春琴抄 お琴と佐助』
『マダムと女房/春琴抄 お琴と佐助』 『残菊物語』デジタル修復版
『残菊物語』デジタル修復版
 『簪(かんざし)』
『簪(かんざし)』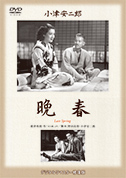
 『晩春』
『晩春』
 『風の中の牝雞』
『風の中の牝雞』
 『父ありき』
『父ありき』
 『誘惑』
『誘惑』
 『元禄忠臣藏(前篇・後篇)』
『元禄忠臣藏(前篇・後篇)』
 『晩春』デジタル修復版
『晩春』デジタル修復版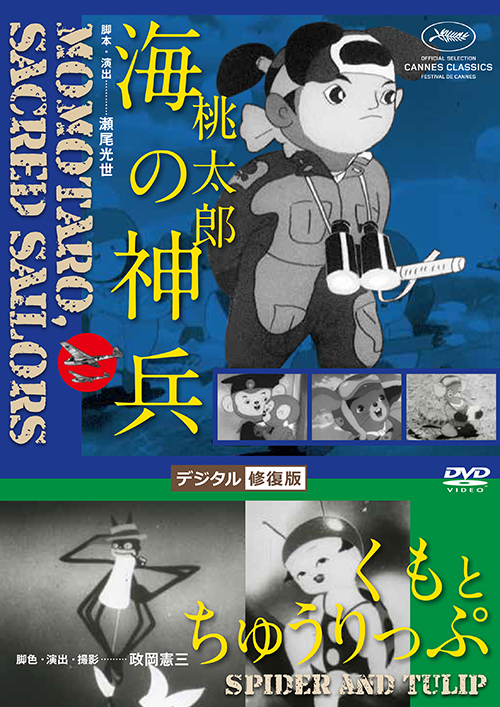
 『桃太郎 海の神兵&くもとちゅうりっぷ』デジタル修復版
『桃太郎 海の神兵&くもとちゅうりっぷ』デジタル修復版
 『顔』
『顔』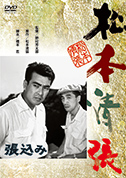
 『張込み』
『張込み』
 『本日休診』
『本日休診』
 『朝を呼ぶ口笛』
『朝を呼ぶ口笛』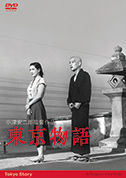
 『東京物語 小津安二郎生誕110年・ニューデジタルリマスター』
『東京物語 小津安二郎生誕110年・ニューデジタルリマスター』
 『彼岸花』
『彼岸花』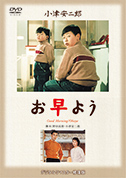
 『お早よう』
『お早よう』
 『麦秋』
『麦秋』
 『お茶漬の味』
『お茶漬の味』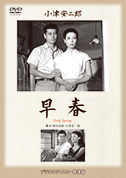
 『早春』
『早春』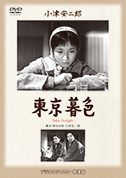
 『東京暮色』
『東京暮色』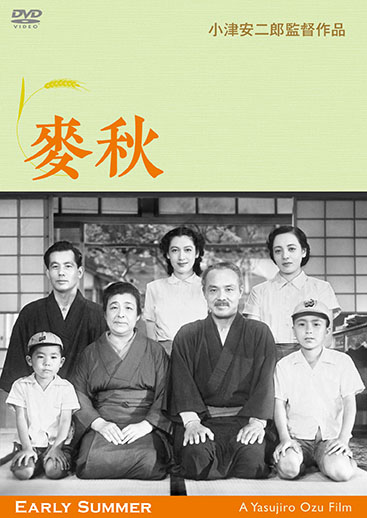
 『麦秋』デジタル修復版
『麦秋』デジタル修復版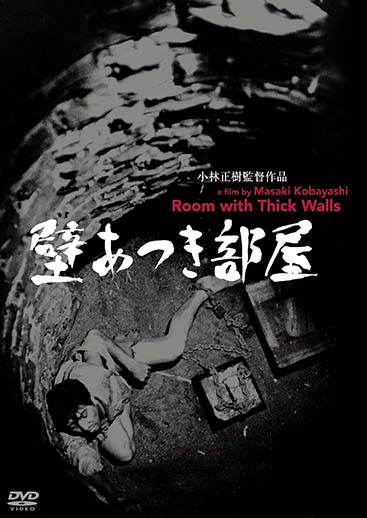
 『壁あつき部屋』
『壁あつき部屋』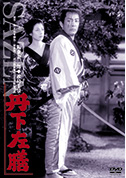
 『丹下左膳』
『丹下左膳』
 『白昼堂々』
『白昼堂々』
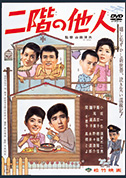 『二階の他人』
『二階の他人』
 『霧の旗』
『霧の旗』
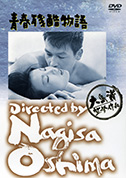 『青春残酷物語』
『青春残酷物語』
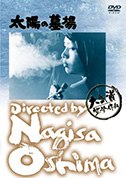 『太陽の墓場』
『太陽の墓場』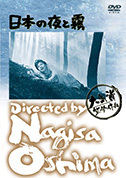
 『日本の夜と霧』
『日本の夜と霧』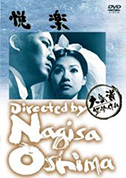
 『悦楽』
『悦楽』
 『切腹』
『切腹』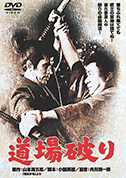
 『道場破り』
『道場破り』
 『波の塔』
『波の塔』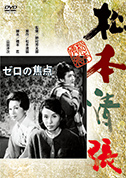
 『ゼロの焦点』
『ゼロの焦点』
 『古都』
『古都』
 『乾いた花』
『乾いた花』
 『秋日和』
『秋日和』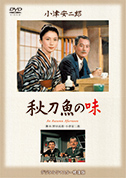
 『秋刀魚の味』
『秋刀魚の味』
 『秋津温泉』
『秋津温泉』 
 『青春残酷物語』デジタル修復版
『青春残酷物語』デジタル修復版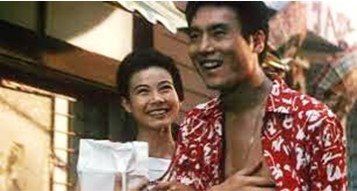
 『夜の片鱗』
『夜の片鱗』
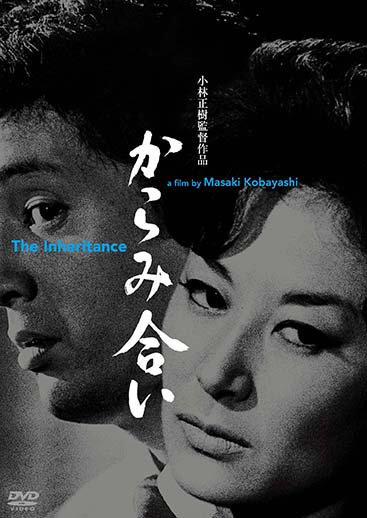 『からみ合い』
『からみ合い』
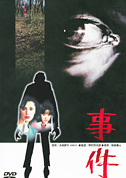 『事件』
『事件』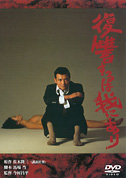
 『復讐するは我にあり』
『復讐するは我にあり』
 『幸福の黄色いハンカチ デジタルリマスター』
『幸福の黄色いハンカチ デジタルリマスター』
 『家族』
『家族』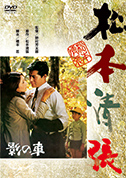 『影の車』
『影の車』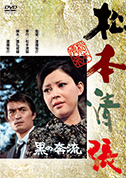
 『黒の奔流』
『黒の奔流』
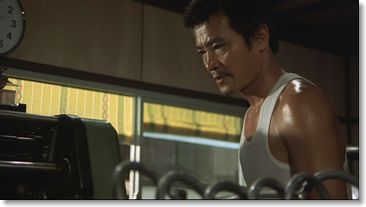 『鬼畜』
『鬼畜』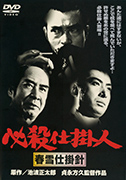
 『必殺仕掛人 春雪仕掛針』
『必殺仕掛人 春雪仕掛針』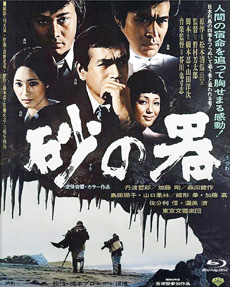
 『砂の器』
『砂の器』
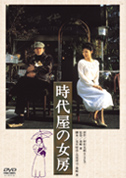 『時代屋の女房』
『時代屋の女房』
 『魚影の群れ』
『魚影の群れ』
 『道頓堀川』
『道頓堀川』
 『蒲田行進曲』
『蒲田行進曲』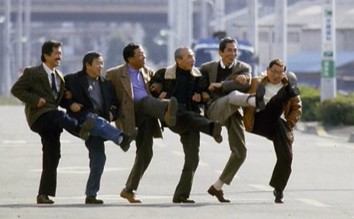
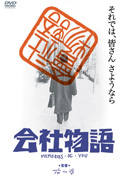 『会社物語 MEMORIES OF YOU』
『会社物語 MEMORIES OF YOU』
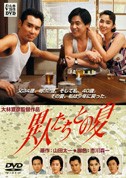 『異人たちとの夏』
『異人たちとの夏』
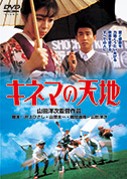 『キネマの天地』
『キネマの天地』
 『疑惑』
『疑惑』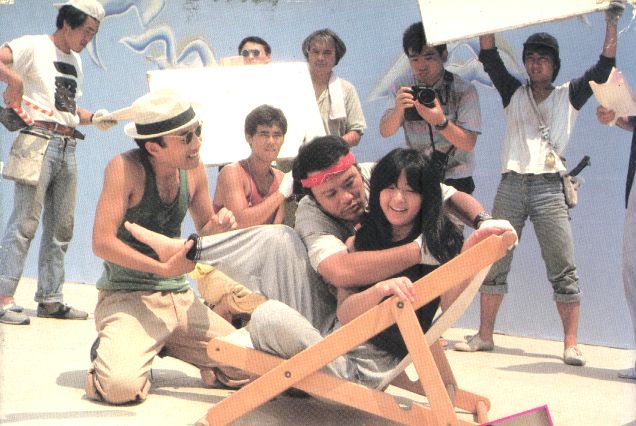
 『ロケーション』
『ロケーション』
 『GONIN』
『GONIN』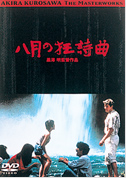
 『八月の狂詩曲』
『八月の狂詩曲』
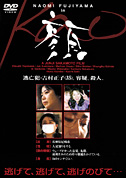 『顔』
『顔』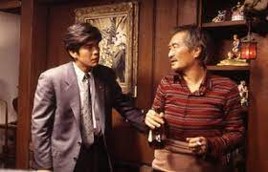
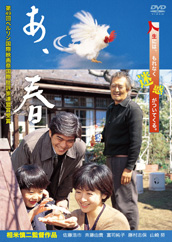 『あ、春』
『あ、春』
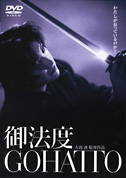 『御法度 GOHATTO』
『御法度 GOHATTO』
 『息子』
『息子』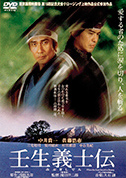
 『壬生義士伝』
『壬生義士伝』 『恋愛寫眞』
『恋愛寫眞』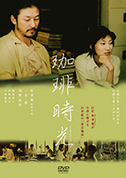
 『珈琲時光』
『珈琲時光』 『天国の本屋〜恋火』
『天国の本屋〜恋火』
 『おとうと』
『おとうと』
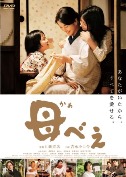 『母べえ』
『母べえ』
 『東京家族』
『東京家族』
 『家族はつらいよ』
『家族はつらいよ』 
 『小さいおうち』
『小さいおうち』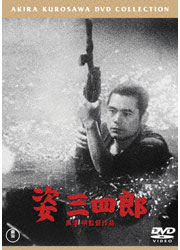
 姿三四郎
姿三四郎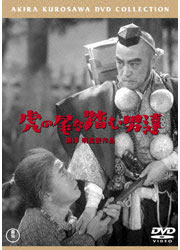
 虎の尾を踏む男達
虎の尾を踏む男達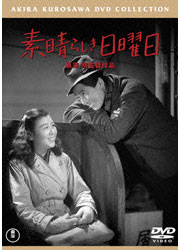
 素晴らしき日曜日
素晴らしき日曜日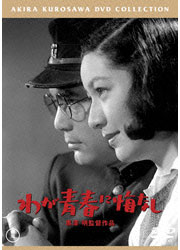
 わが青春に悔なし
わが青春に悔なし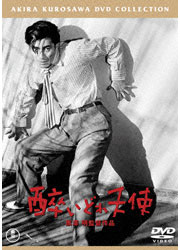
 酔いどれ天使
酔いどれ天使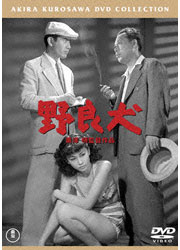
 野良犬
野良犬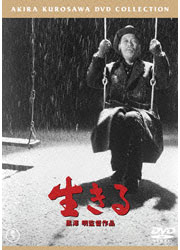
 生きる
生きる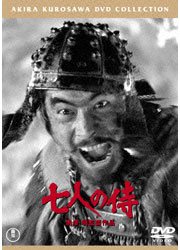
 七人の侍
七人の侍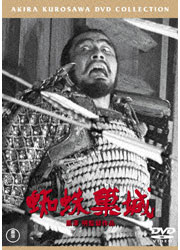
 蜘蛛巣城
蜘蛛巣城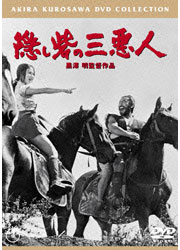
 隠し砦の三悪人
隠し砦の三悪人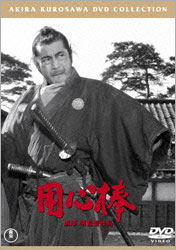
 用心棒
用心棒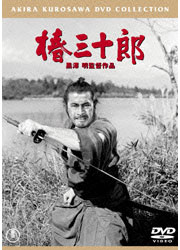
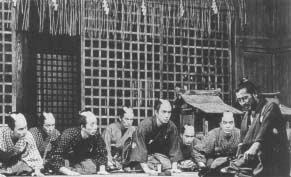 椿三十郎
椿三十郎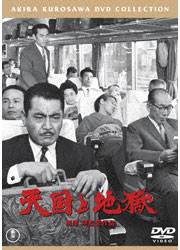
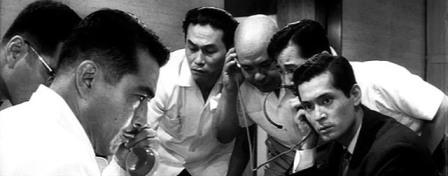 天国と地獄
天国と地獄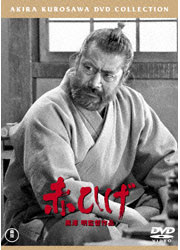
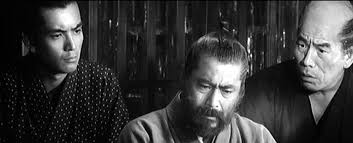 赤ひげ
赤ひげ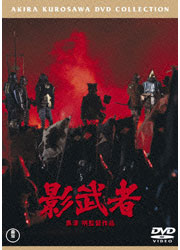
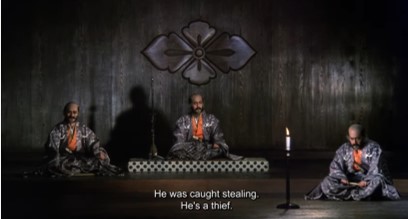 影武者
影武者 乙女ごころ三人姉妹
乙女ごころ三人姉妹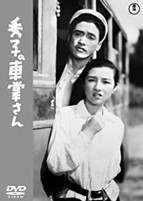 秀子の車掌さん
秀子の車掌さん めし
めし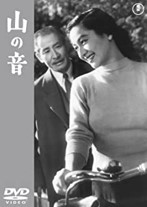 山の音
山の音 浮雲
浮雲 流れる
流れる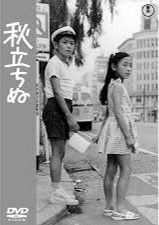 秋立ちぬ
秋立ちぬ 放浪記
放浪記 洲崎パラダイス 赤信号
洲崎パラダイス 赤信号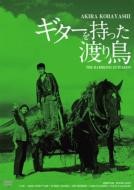
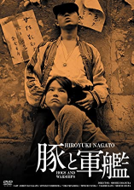
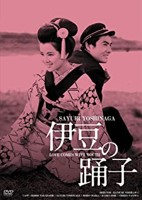
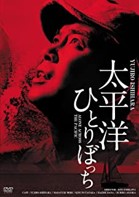

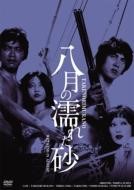
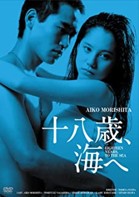


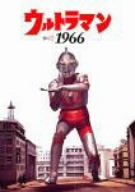
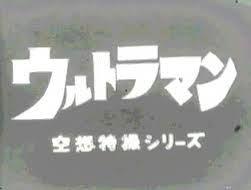
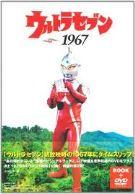
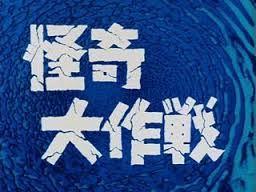
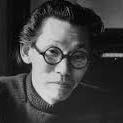 ①早坂 文雄(1914-1955/享年41) 音楽作品(10)
①早坂 文雄(1914-1955/享年41) 音楽作品(10)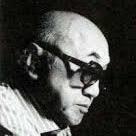 ②佐藤 勝(1928-1999/享年71) 音楽作品(20)
②佐藤 勝(1928-1999/享年71) 音楽作品(20)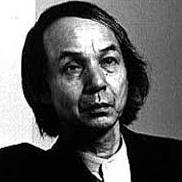 ③武満 徹(1930-1996/享年65) 音楽作品(9)
③武満 徹(1930-1996/享年65) 音楽作品(9) ④古関 裕而(1909-1989/享年80) 音楽作品(5)
④古関 裕而(1909-1989/享年80) 音楽作品(5)
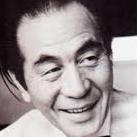 ⑤伊福部 昭(1914-2006/享年91) 音楽作品(20) ●過去作品の音楽を流用
⑤伊福部 昭(1914-2006/享年91) 音楽作品(20) ●過去作品の音楽を流用 ⑥芥川 也寸志(1925-1989/享年63) 音楽作品(12)
⑥芥川 也寸志(1925-1989/享年63) 音楽作品(12)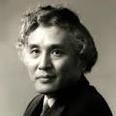 ⑦黛 敏郎(1929-1997/享年68) 音楽作品(16)
⑦黛 敏郎(1929-1997/享年68) 音楽作品(16)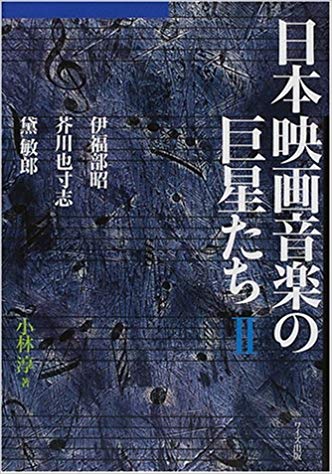
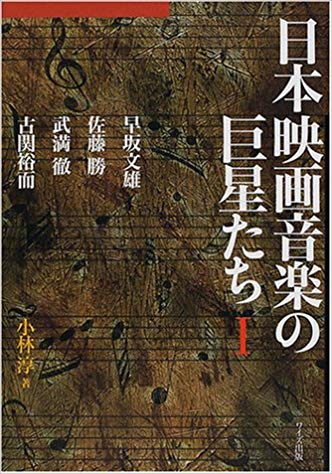
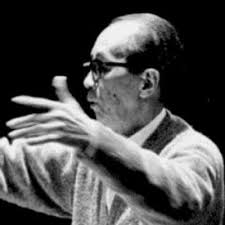 ①鈴木 静一(1901-1980/享年79) 音楽作品(9)
①鈴木 静一(1901-1980/享年79) 音楽作品(9)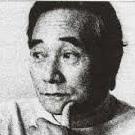 ③木下 忠司(1916-2018/享年102) 音楽作品(14)
③木下 忠司(1916-2018/享年102) 音楽作品(14)

 ④斎藤 高順(1924-2004/享年79) 音楽作品(6)
④斎藤 高順(1924-2004/享年79) 音楽作品(6)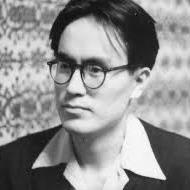 ⑤山内(やまのうち) 正(1927-1980/享年53) 音楽作品(3)
⑤山内(やまのうち) 正(1927-1980/享年53) 音楽作品(3)
 ⑥林 光(1931-2012/享年80) 音楽作品(8)
⑥林 光(1931-2012/享年80) 音楽作品(8)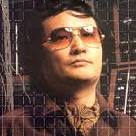 ⑦冨田 勲(1932-2016/享年84) 音楽作品(14)
⑦冨田 勲(1932-2016/享年84) 音楽作品(14)

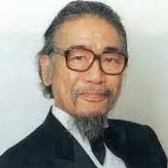 ⑧山本 直純(1932-2002/享年69) 音楽作品(11)
⑧山本 直純(1932-2002/享年69) 音楽作品(11)
 ⑨池辺 晋一郎(1943- ) 音楽作品(9)
⑨池辺 晋一郎(1943- ) 音楽作品(9)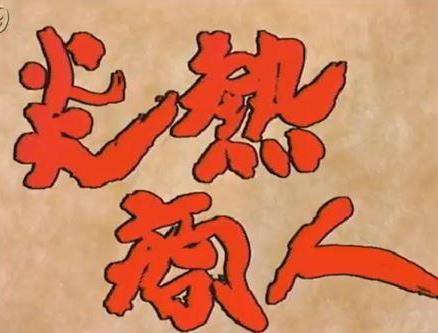

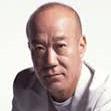 ⑩久石 譲(1950- ) 音楽作品(11)
⑩久石 譲(1950- ) 音楽作品(11) ⑪坂本 龍一(1952-2023/享年71)音楽作品(7)
⑪坂本 龍一(1952-2023/享年71)音楽作品(7)

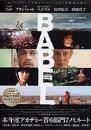

![狐の呉れた赤ん坊 [DVD].jpg](http://hurec.bz/book-movie/%E7%8B%90%E3%81%AE%E5%91%89%E3%82%8C%E3%81%9F%E8%B5%A4%E3%82%93%E5%9D%8A%20%5BDVD%5D.jpg)
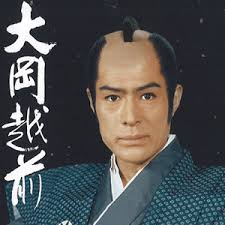











































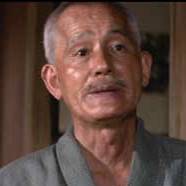



















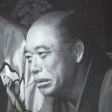

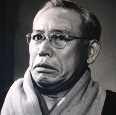










































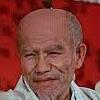


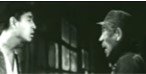








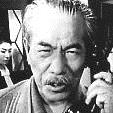

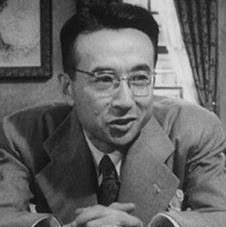
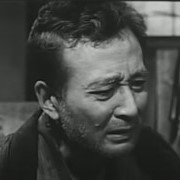
















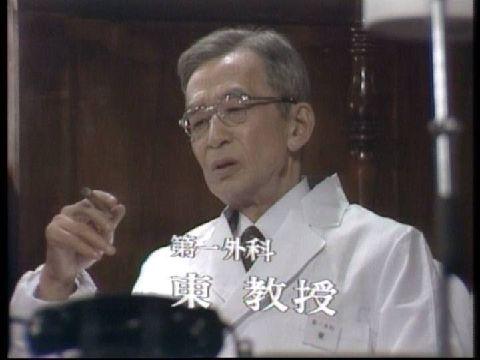








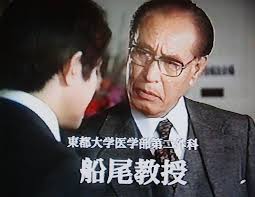








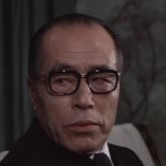































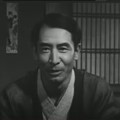



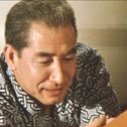



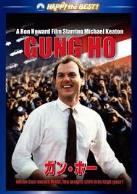





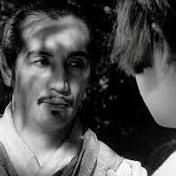




































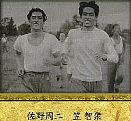






















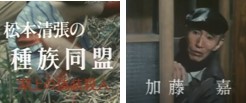

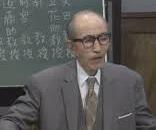




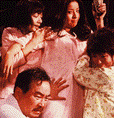

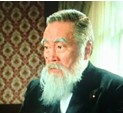










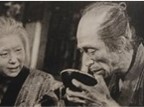













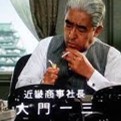








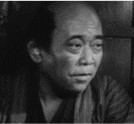






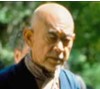



























































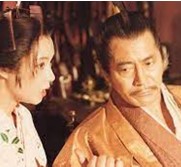


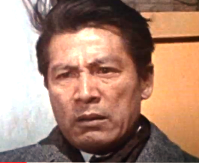

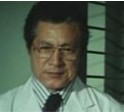























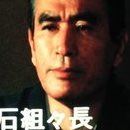









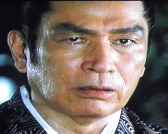



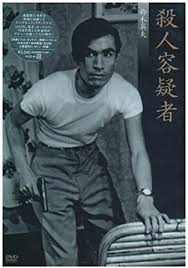








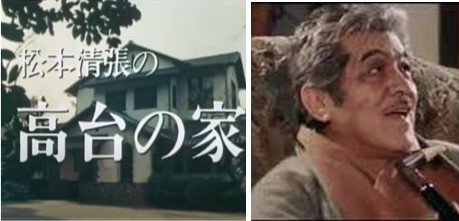





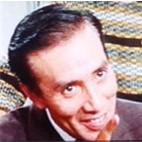









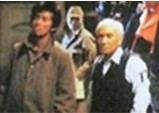


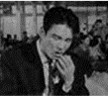



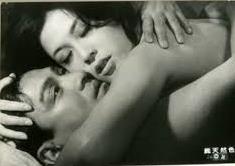





















































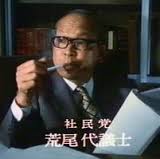
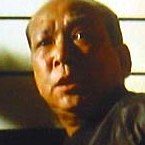

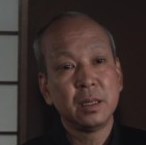































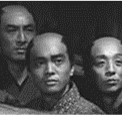





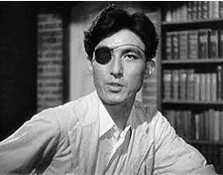



















![「寅次郎相合傘].jpg](http://hurec.bz/book-movie/%E3%80%8C%E5%AF%85%E6%AC%A1%E9%83%8E%E7%9B%B8%E5%90%88%E5%82%98%5D.jpg)
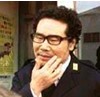










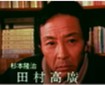
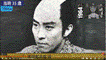
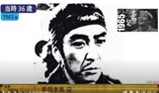






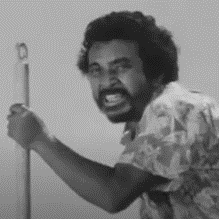












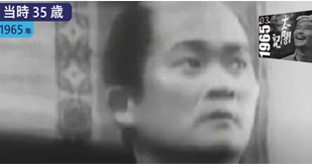
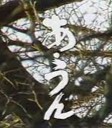

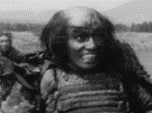




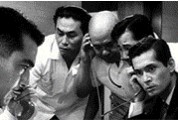







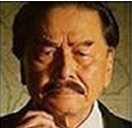































































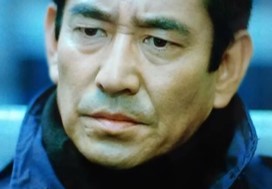














































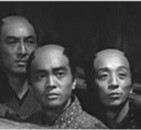

















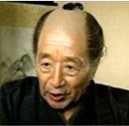

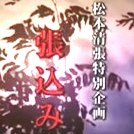

































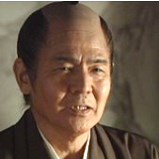








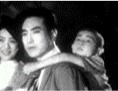









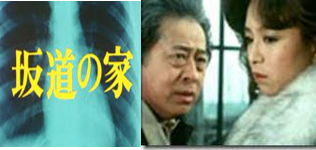

















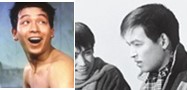









 (TV) 9 TV
(TV) 9 TV 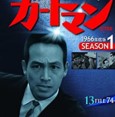




























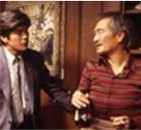









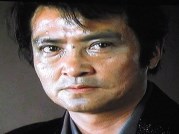

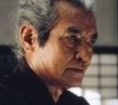


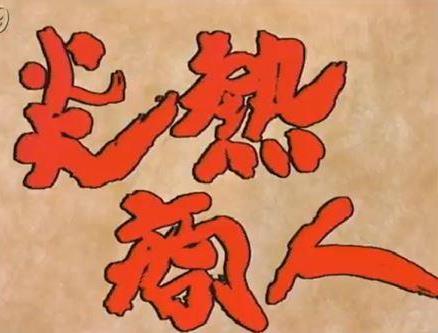



















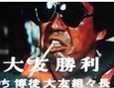









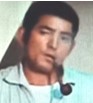





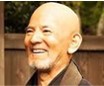

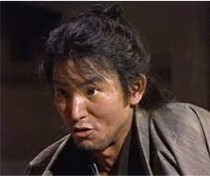







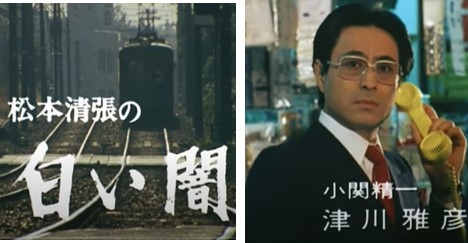






















































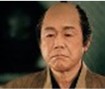


















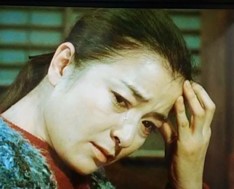




















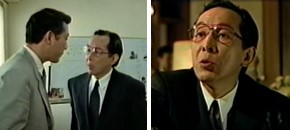























































![「真夏の方程式]201前田2.jpg](http://hurec.bz/book-movie/%E3%80%8C%E7%9C%9F%E5%A4%8F%E3%81%AE%E6%96%B9%E7%A8%8B%E5%BC%8F%5D201%E5%89%8D%E7%94%B02.jpg)



















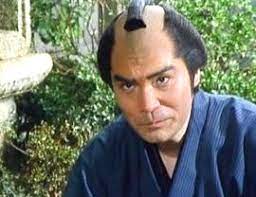








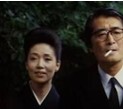












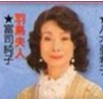











 10 TV
10 TV 




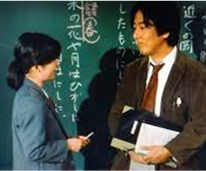




























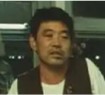









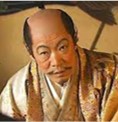










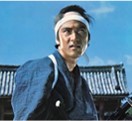

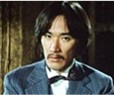


















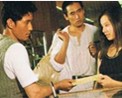





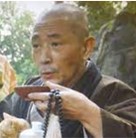













![0真夏の方程式].jpg](http://hurec.bz/book-movie/%EF%BC%90%E7%9C%9F%E5%A4%8F%E3%81%AE%E6%96%B9%E7%A8%8B%E5%BC%8F%5D.jpg)









































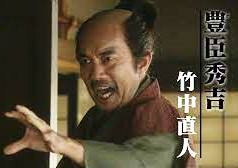





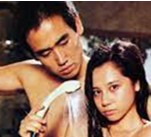

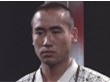
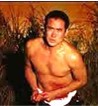

![gomin]nagashima.jpg](http://hurec.bz/book-movie/gomin%5Dnagashima.jpg)

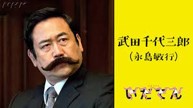
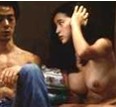





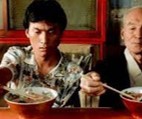

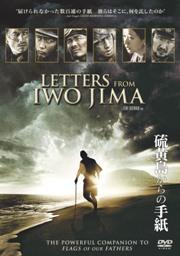





 2
2













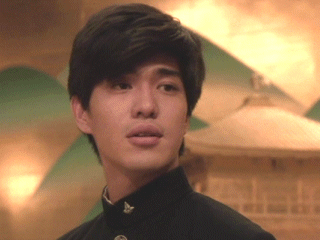















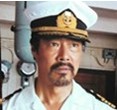
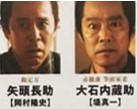











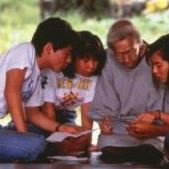































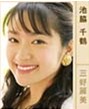





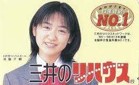





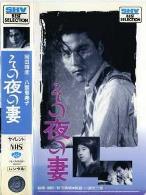


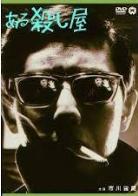

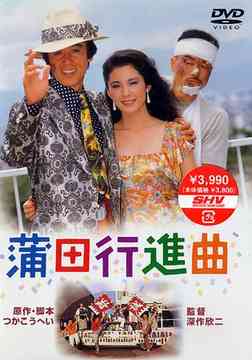
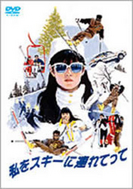
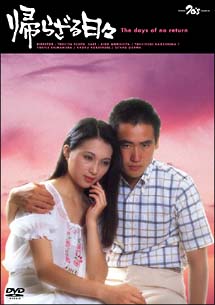
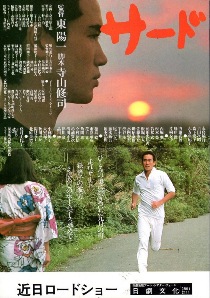
![西遊記 [DVD].jpg](http://hurec.bz/book-movie/%E8%A5%BF%E9%81%8A%E8%A8%98%20%5BDVD%5D.jpg)
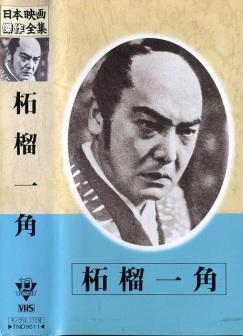
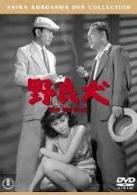
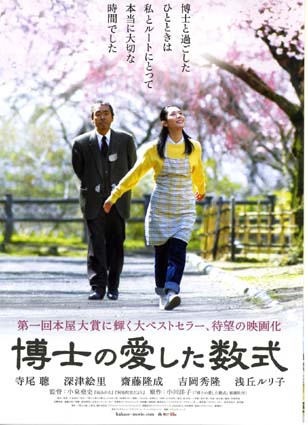
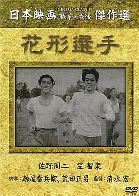
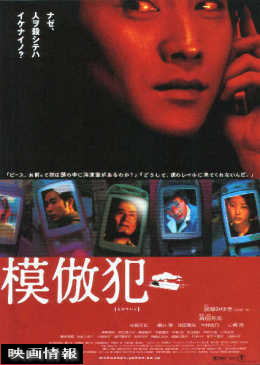
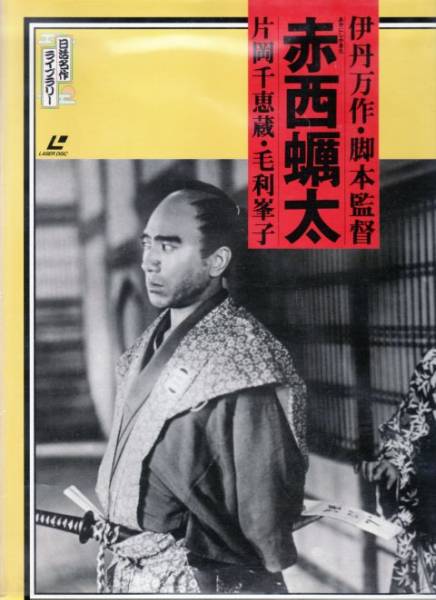
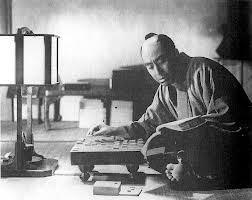






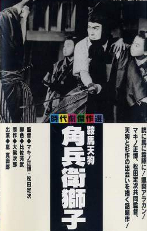
![鞍馬天狗 角兵衛獅子 [VHS].jpg](http://hurec.bz/book-movie/%E9%9E%8D%E9%A6%AC%E5%A4%A9%E7%8B%97%20%E8%A7%92%E5%85%B5%E8%A1%9B%E7%8D%85%E5%AD%90%20%5BVHS%5D.jpg)

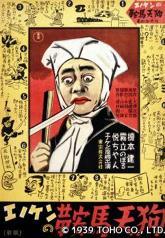
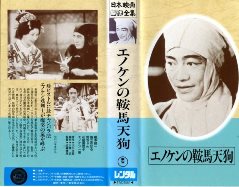

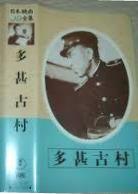

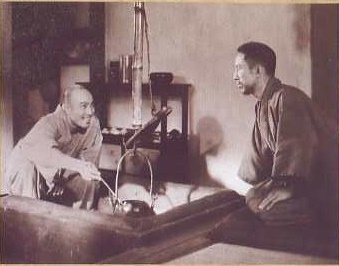
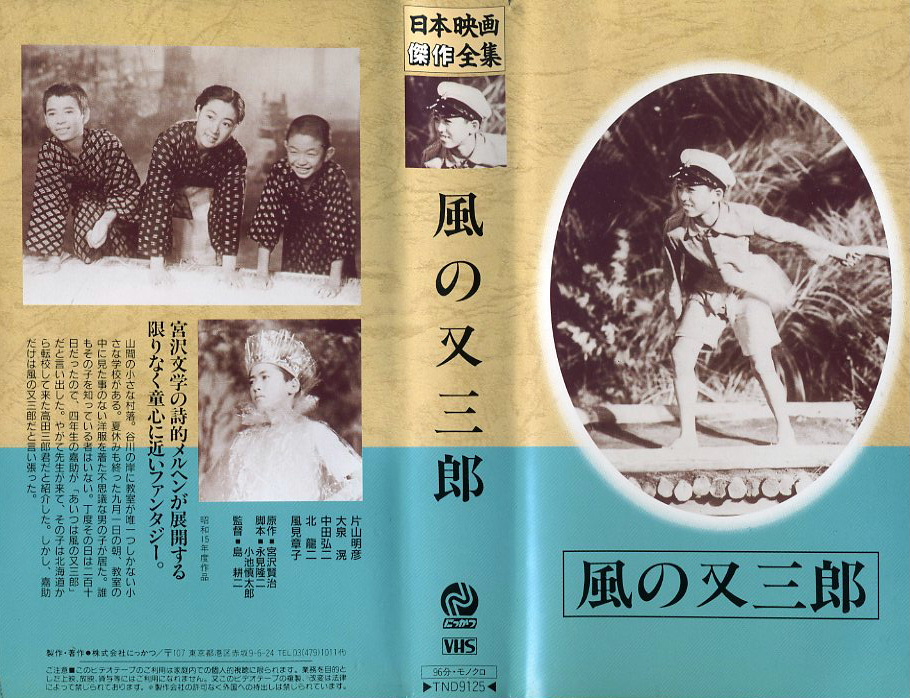





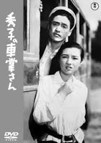



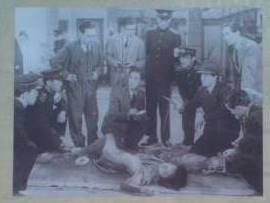
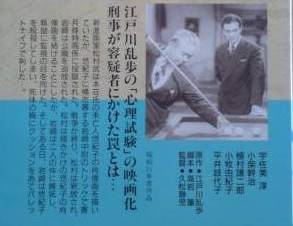



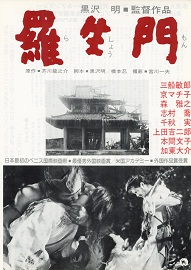





![雁 (1953) [DVD].jpg](http://hurec.bz/book-movie/%E9%9B%81%20%281953%29%20%5BDVD%5D.jpg)
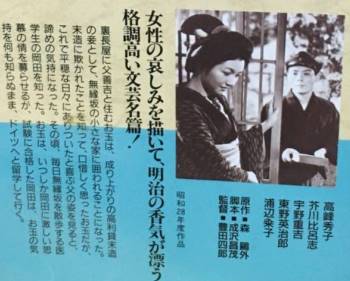


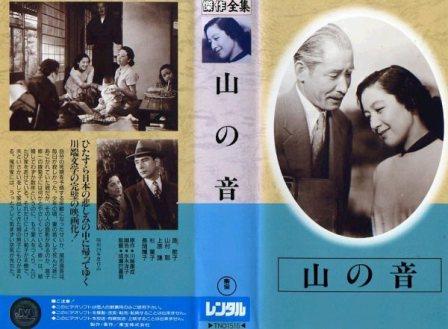






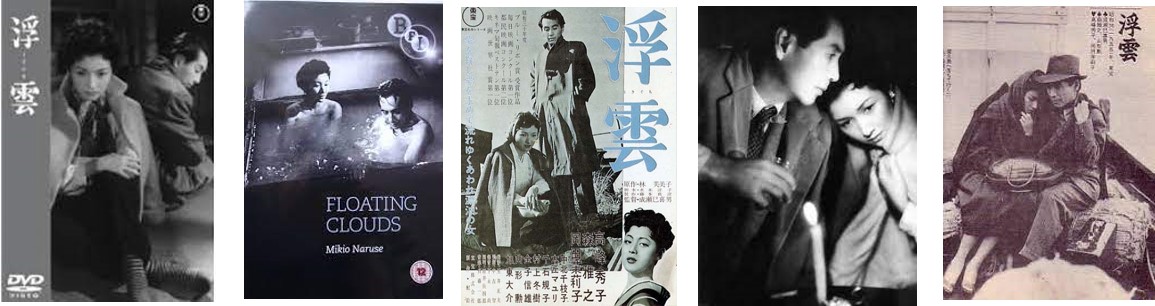
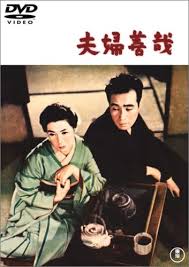


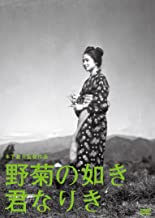


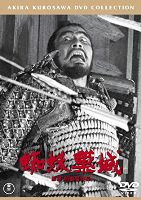



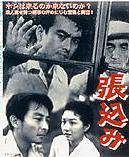
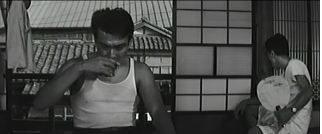

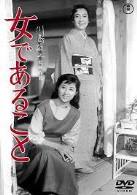
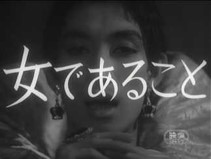


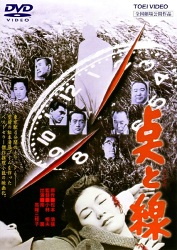





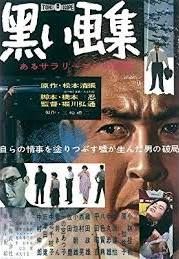
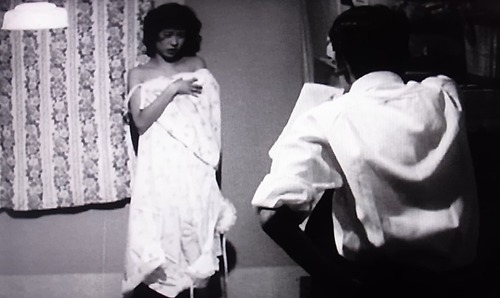

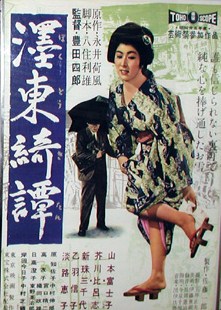



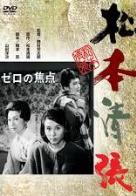


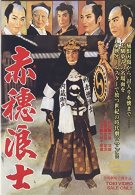


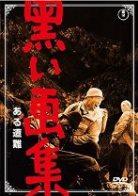
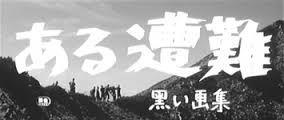

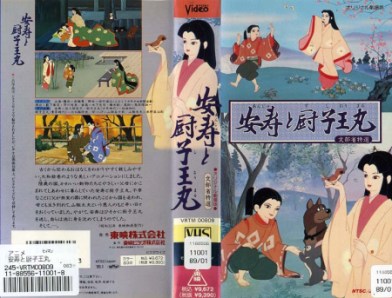
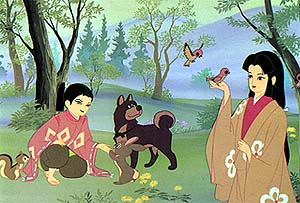
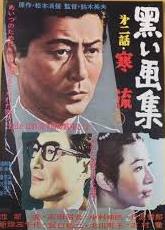


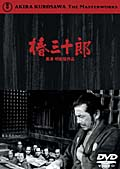

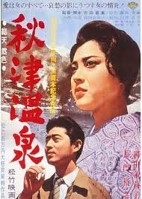
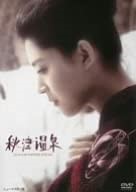

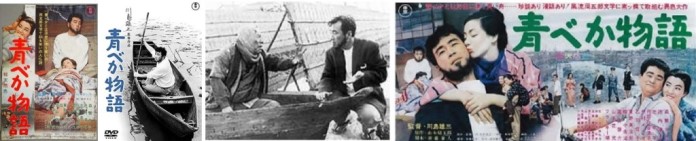
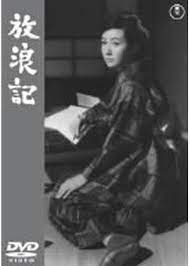






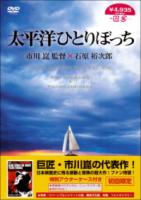
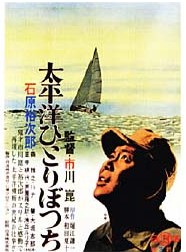


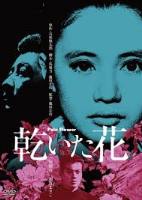







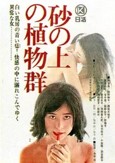




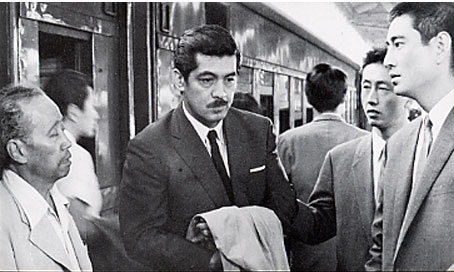
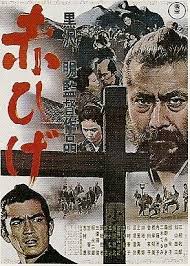


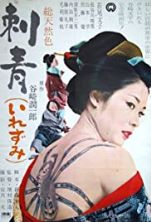

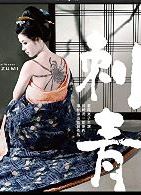

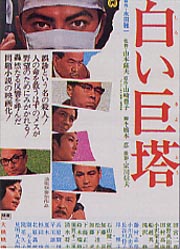





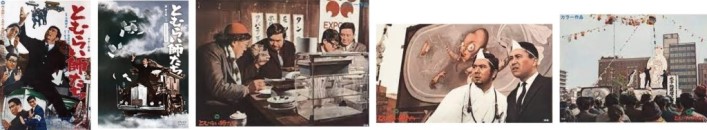

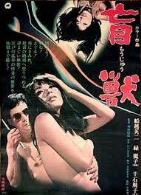




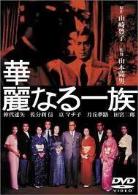


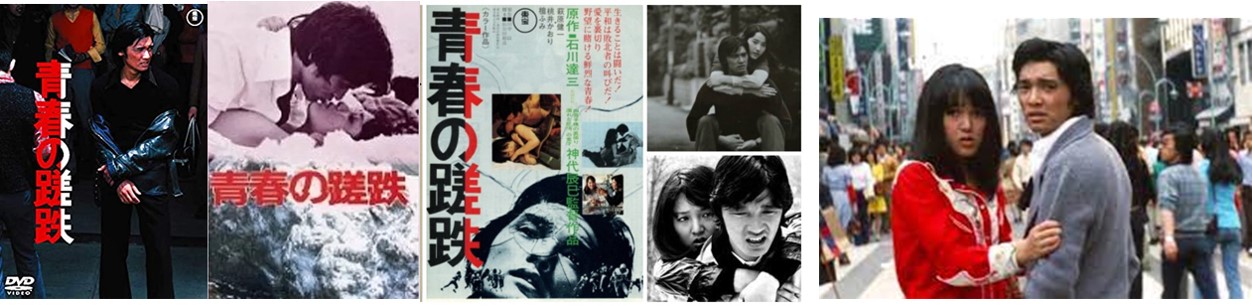
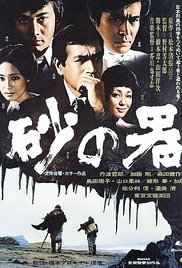





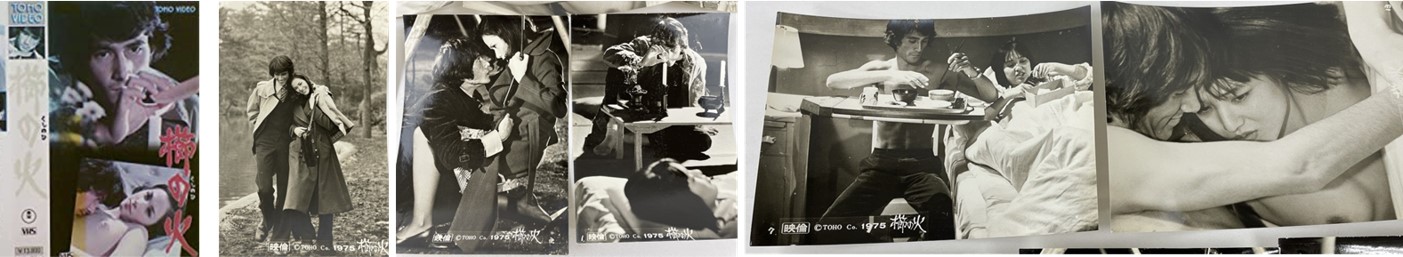


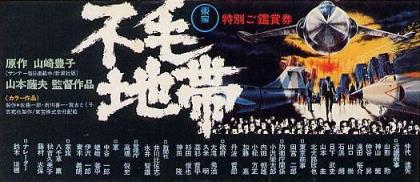

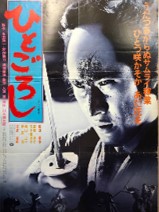
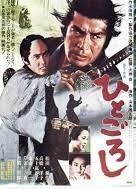

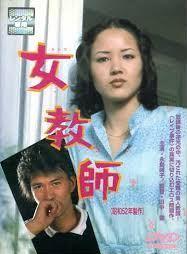



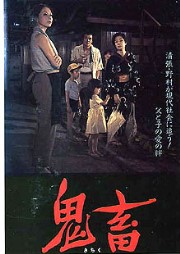




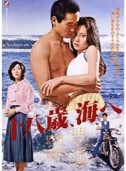
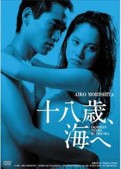




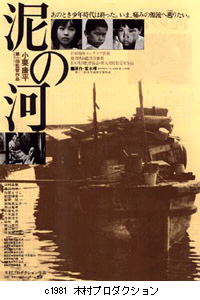


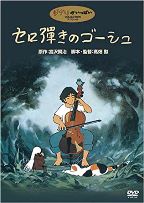


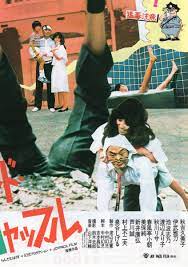


![疑惑 [DVD].jpg](http://hurec.bz/book-movie/%E7%96%91%E6%83%91%20%5BDVD%5D.jpg)

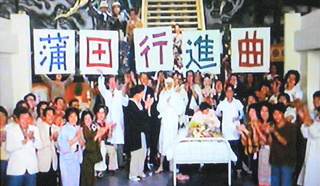






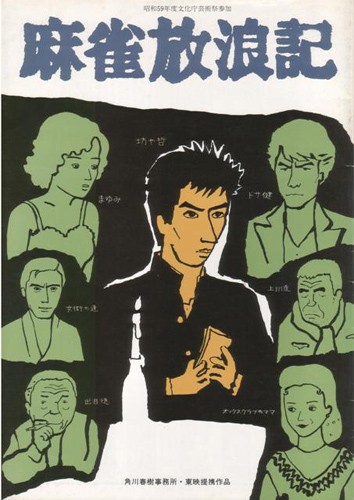




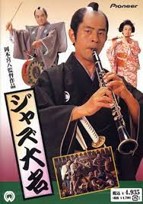
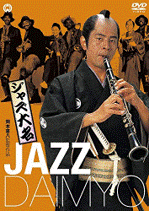
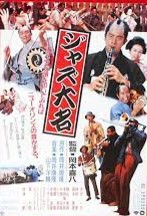

![蛍川 [DVD].jpg](http://hurec.bz/book-movie/%E8%9B%8D%E5%B7%9D%20%5BDVD%5D.jpg)
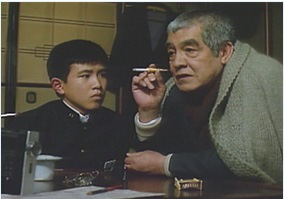




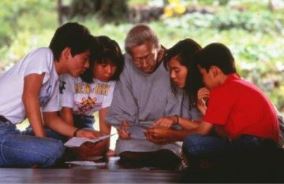


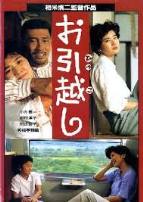


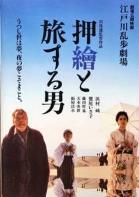
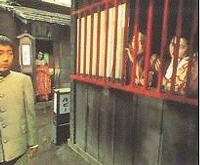


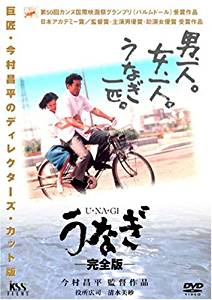


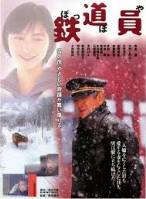


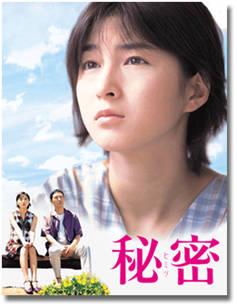


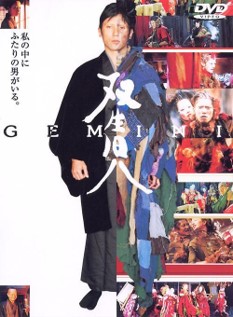


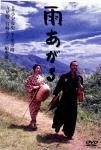


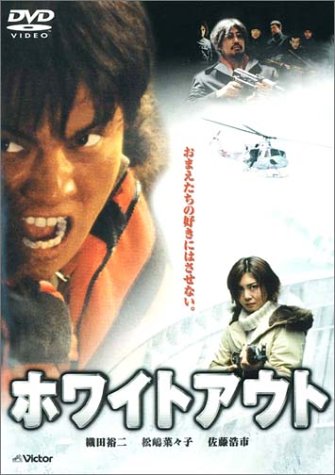



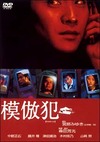





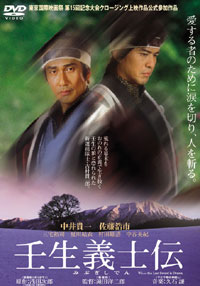

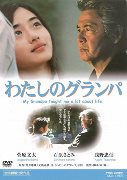


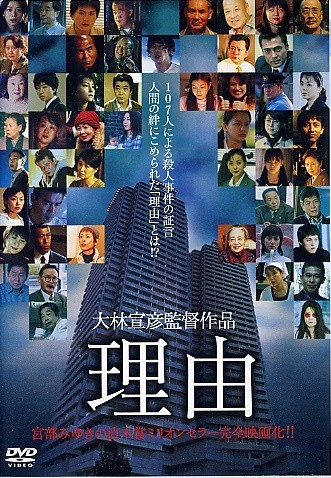


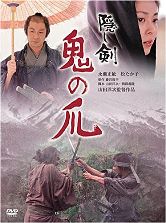


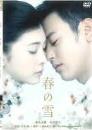


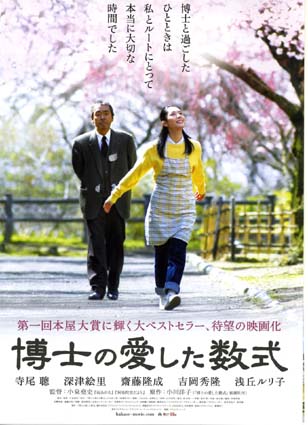


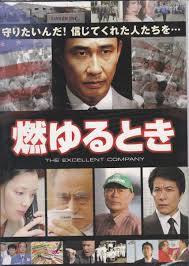


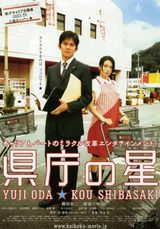








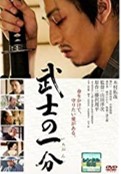




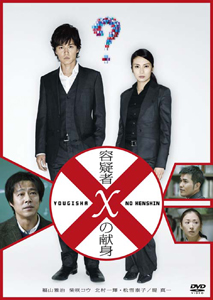


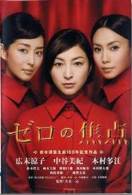


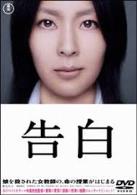








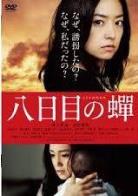



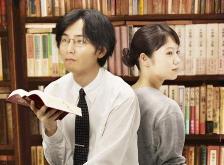

![「真夏の方程式]2013.jpg](http://hurec.bz/book-movie/%E3%80%8C%E7%9C%9F%E5%A4%8F%E3%81%AE%E6%96%B9%E7%A8%8B%E5%BC%8F%5D2013.jpg)


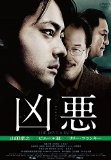




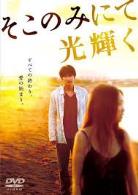


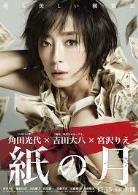






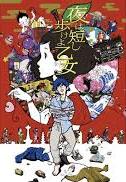


![七つの会議 通常版 [DVD].jpg](http://hurec.bz/book-movie/%E4%B8%83%E3%81%A4%E3%81%AE%E4%BC%9A%E8%AD%B0%20%E9%80%9A%E5%B8%B8%E7%89%88%20%5BDVD%5D.jpg)



















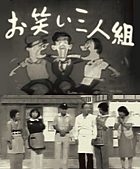
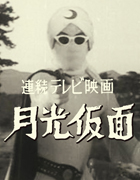













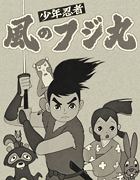


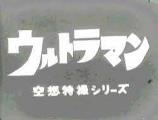

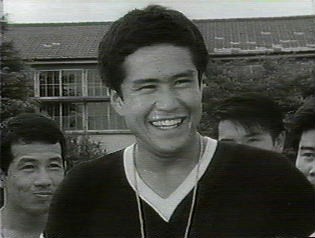
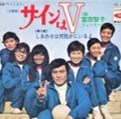
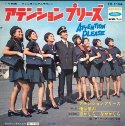




![女検死官%20天海1-thumb].jpg](http://hurec.bz/book-movie/%E5%A5%B3%E6%A4%9C%E6%AD%BB%E5%AE%98%2520%E5%A4%A9%E6%B5%B7%EF%BC%91-thumb%5D.jpg)










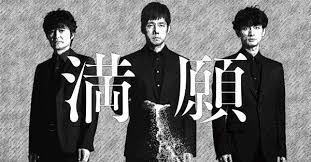


































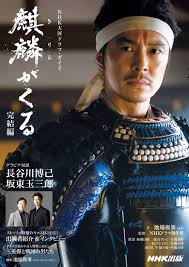












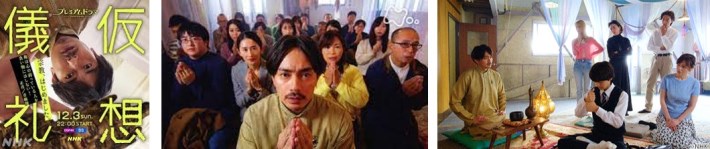
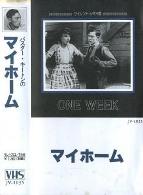
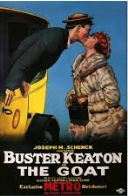
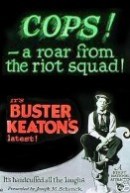
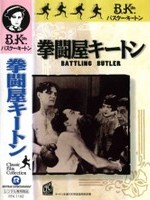
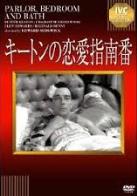
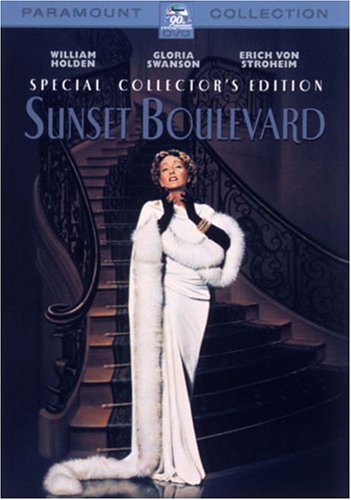
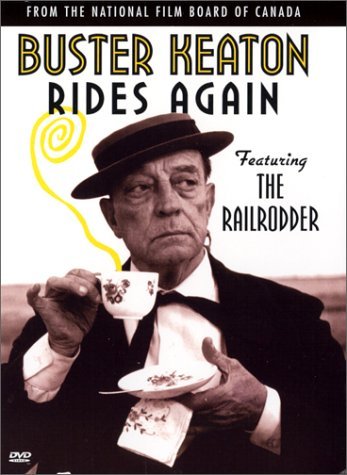
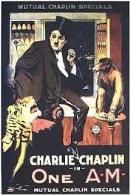



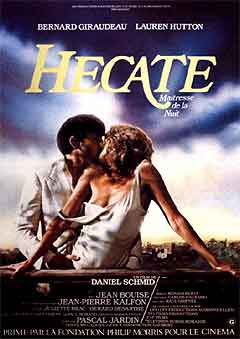
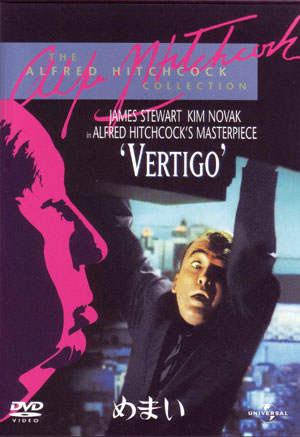
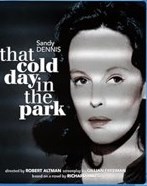
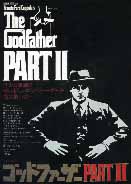
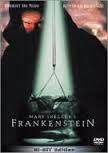
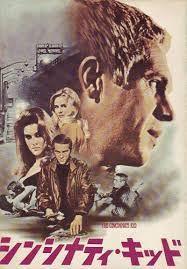
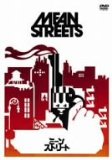
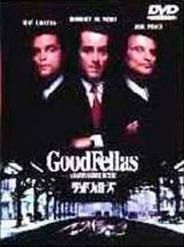




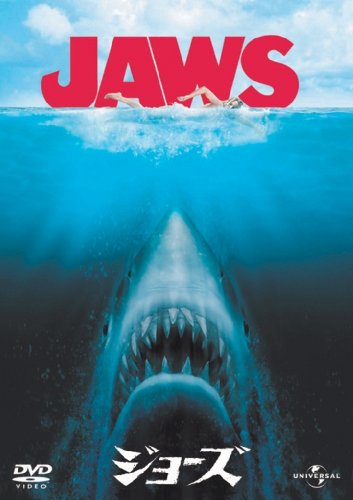
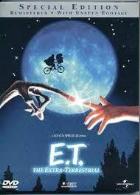
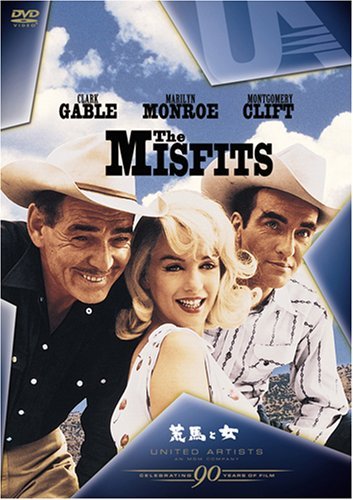

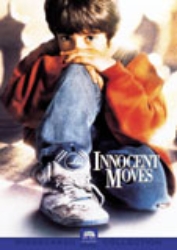


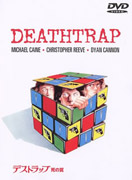
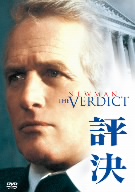
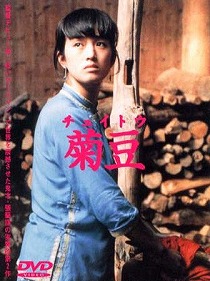
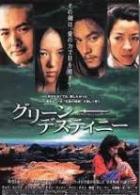

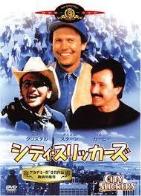
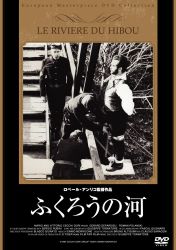
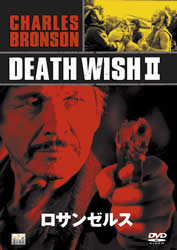
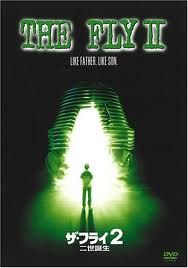

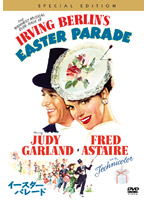
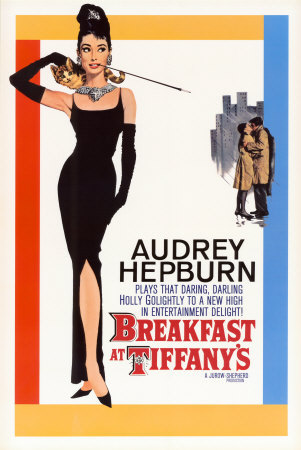
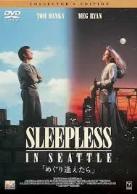
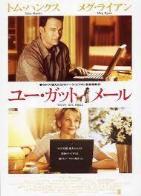
![Ben Hur [VHS] [Import] (1907).jpg](http://hurec.bz/book-movie/Ben%20Hur%20%5BVHS%5D%20%5BImport%5D%20%281907%29.jpg)


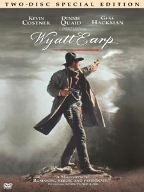

.jpg)
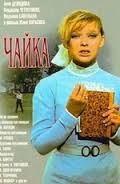
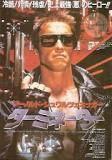

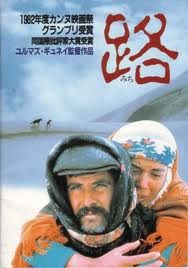
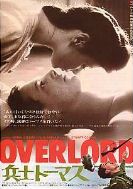



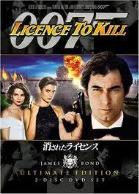
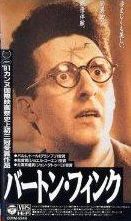
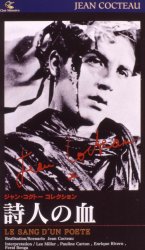

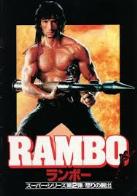

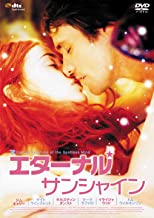
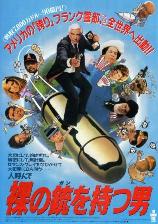
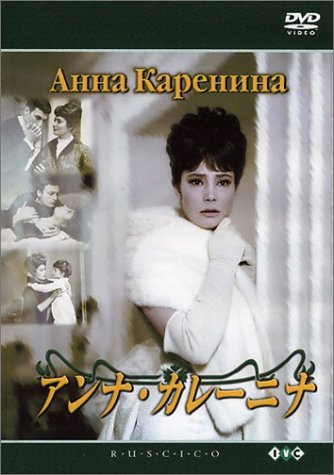
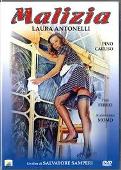



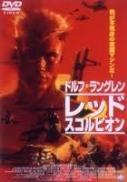
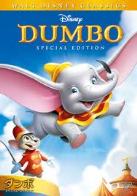
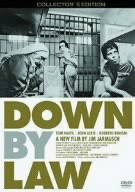
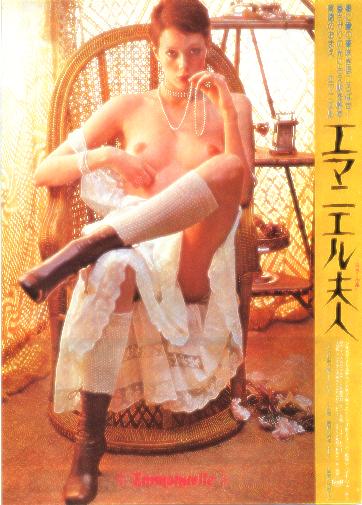
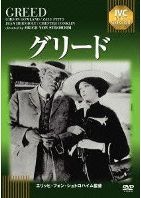
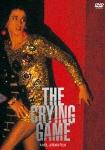
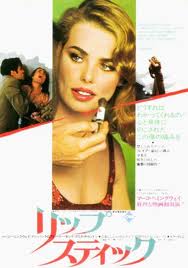
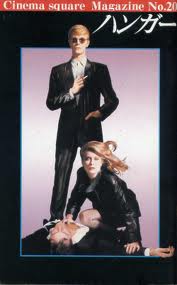
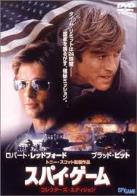

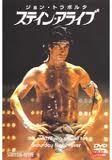
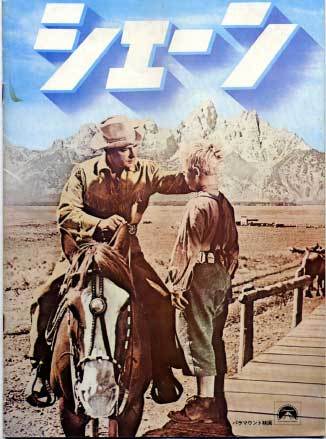

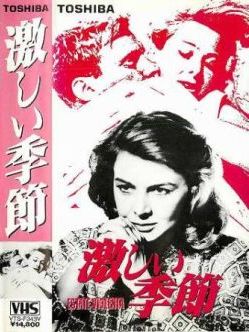

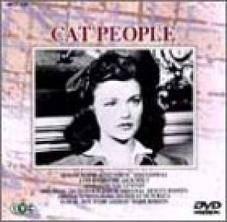
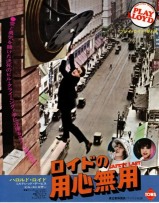
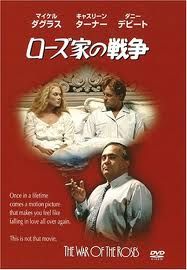
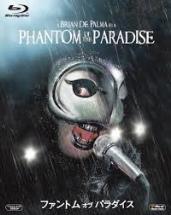
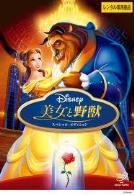

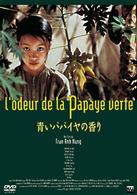
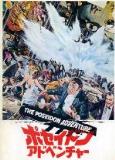

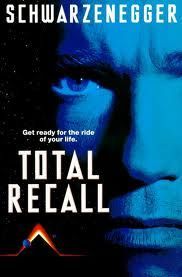

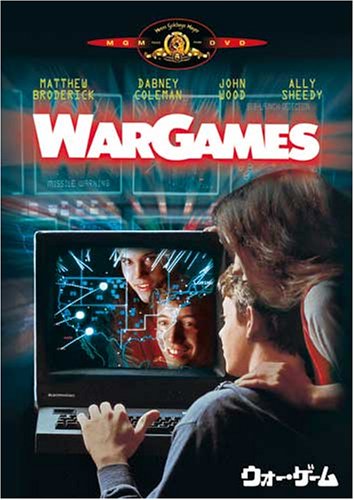

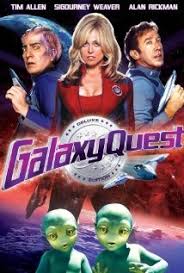
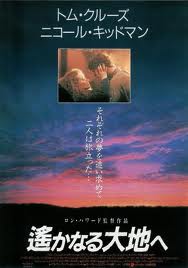
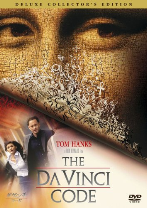
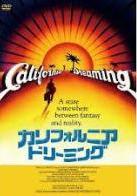
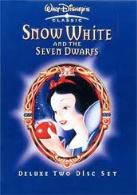
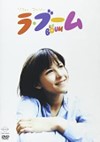

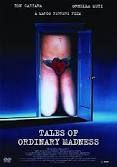


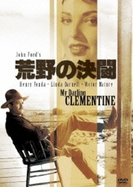

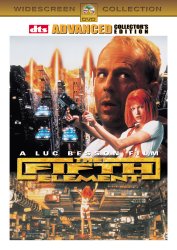
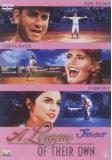


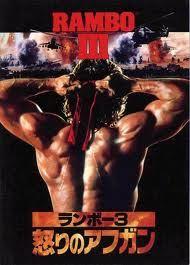
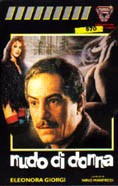

![バンド・ワゴン 特別版 [DVD].jpg](/book-movie/archives/バンド・ワゴン 特別版 [DVD].jpg)
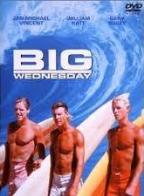
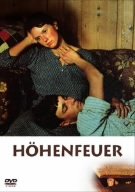


.jpg)
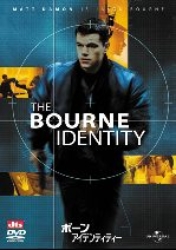

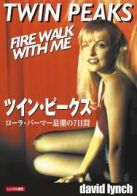



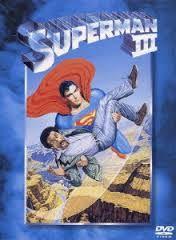

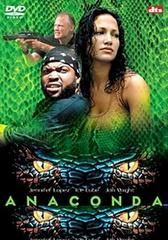
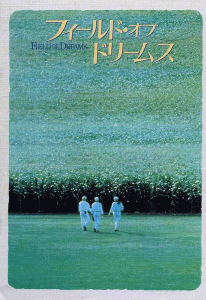

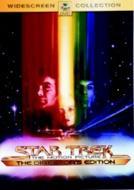
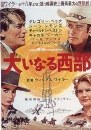
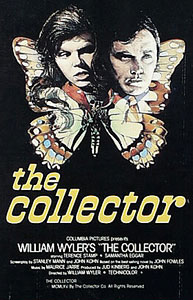
























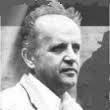 ①
① ②
②
 ③
③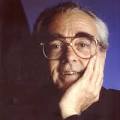 ④
④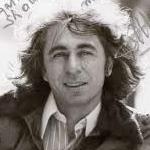 ⑤
⑤




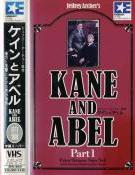
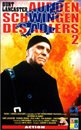
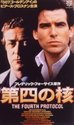


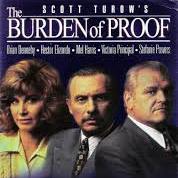



















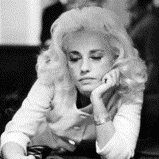


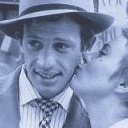
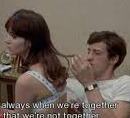




























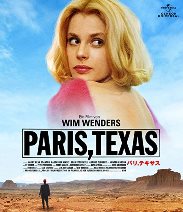














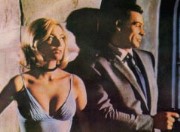































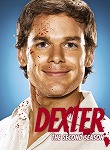


































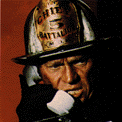
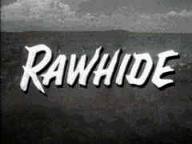












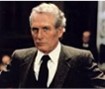








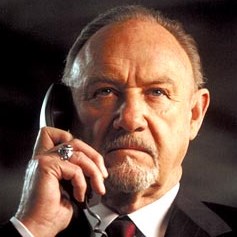
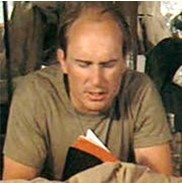








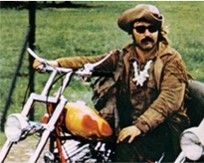



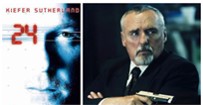










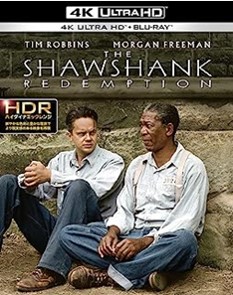












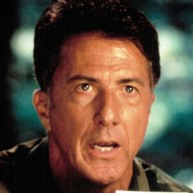


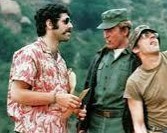

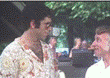

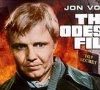






















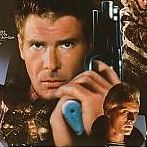






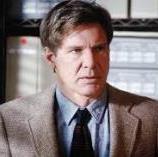









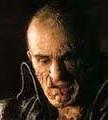














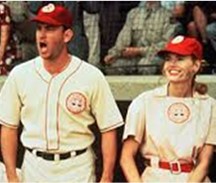












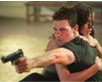




















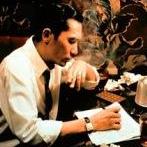











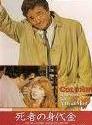


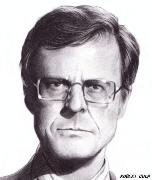










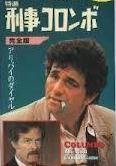









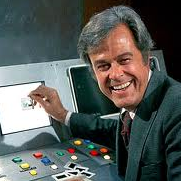
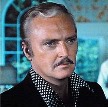






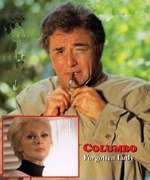





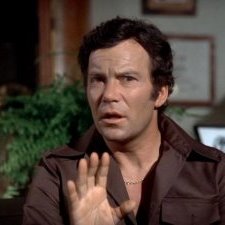






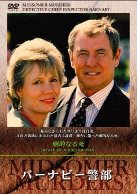



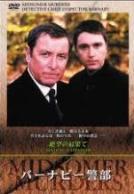

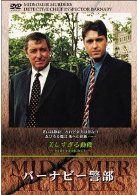


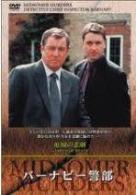







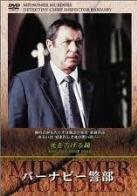
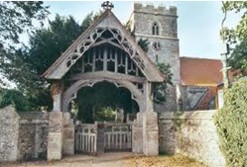







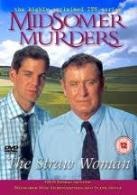

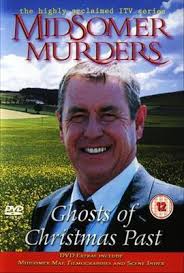










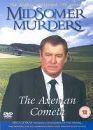

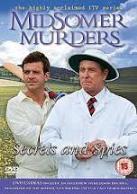





























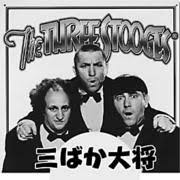





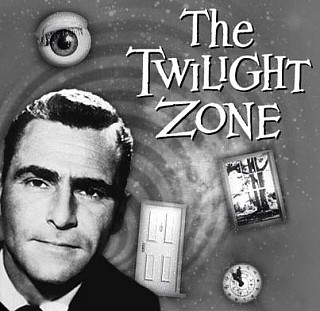





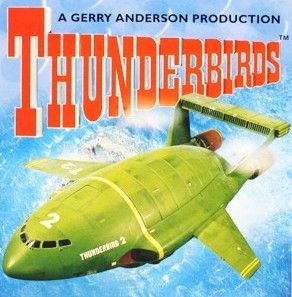








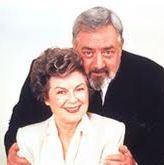
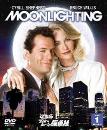

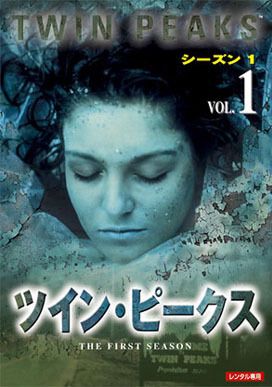
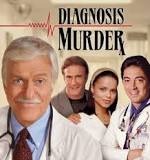
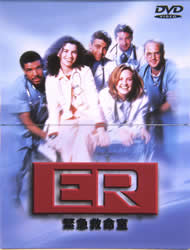


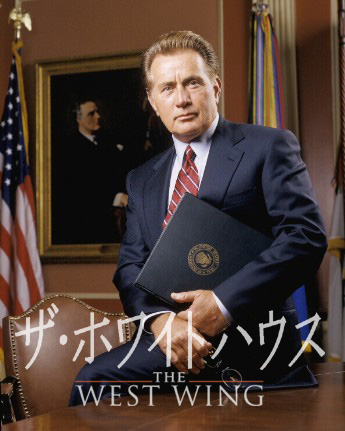
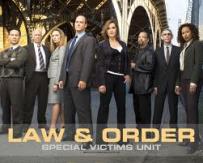
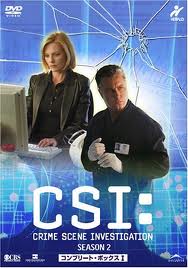
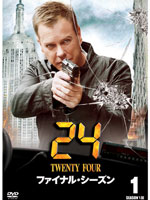
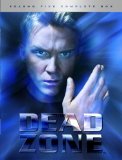
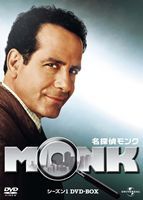



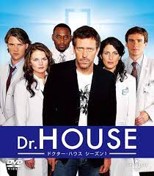

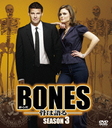
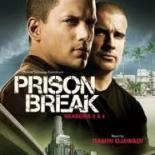


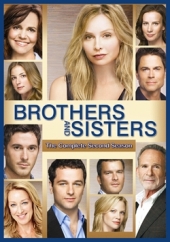



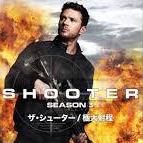

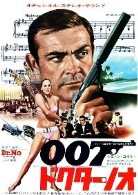

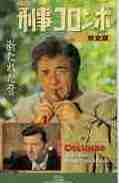

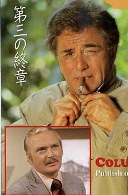




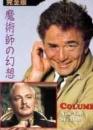
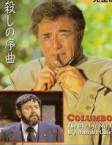
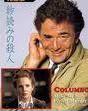
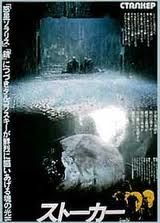
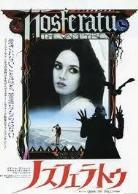


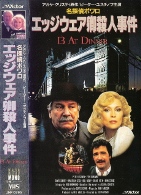

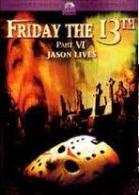
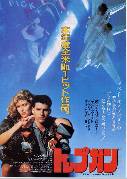
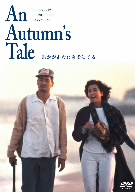
![100万ドルをとり返せ! [VHS].jpg](http://hurec.bz/book-movie/100%E4%B8%87%E3%83%89%E3%83%AB%E3%82%92%E3%81%A8%E3%82%8A%E8%BF%94%E3%81%9B%EF%BC%81%20%5BVHS%5D.jpg)
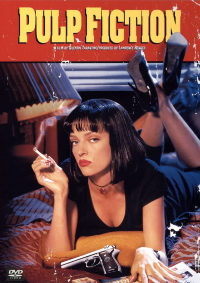
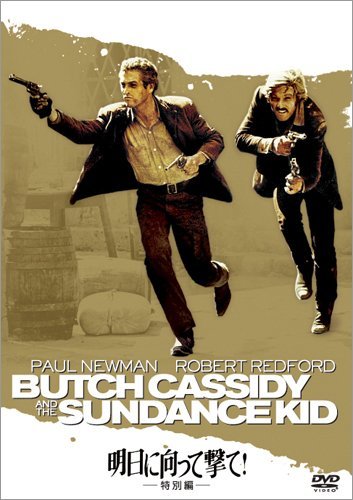
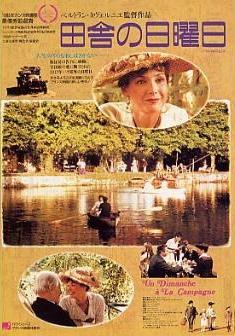






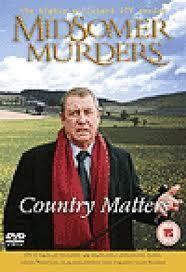
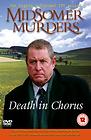
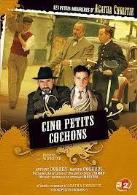
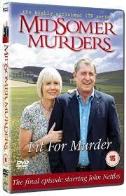

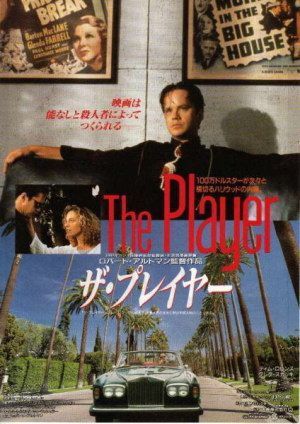
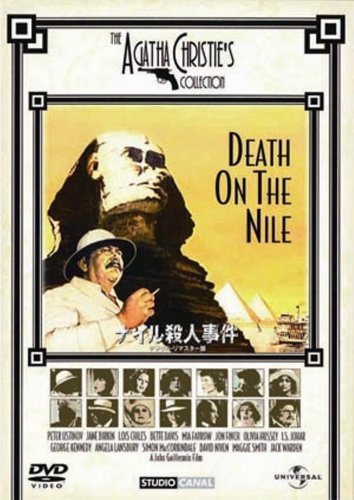


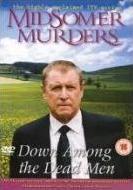
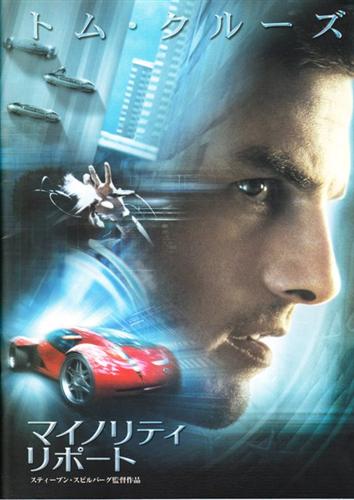

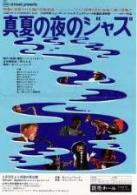

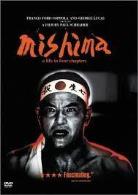
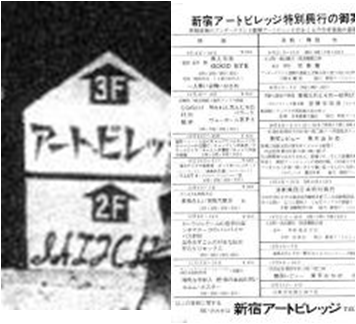







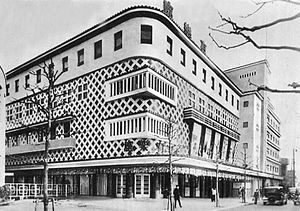



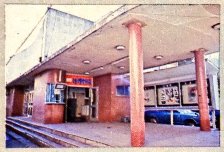








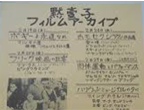




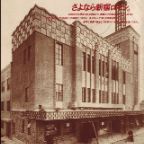


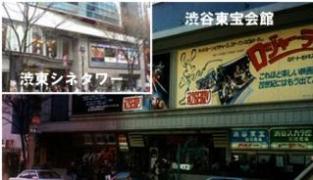






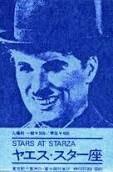





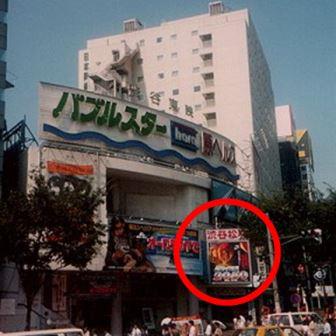



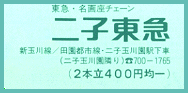


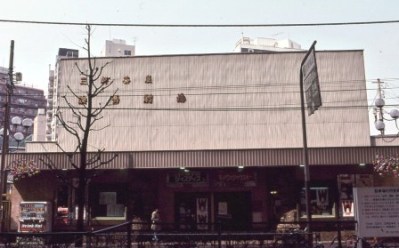

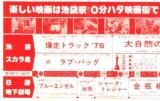

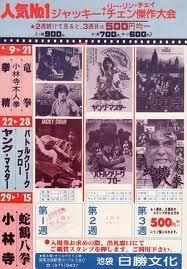








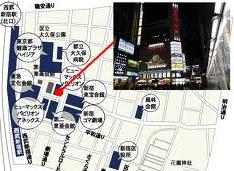








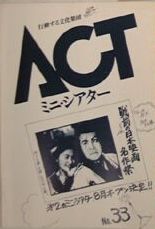
























































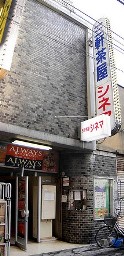
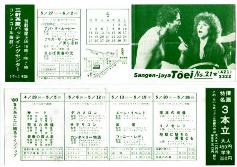









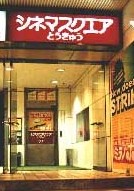













 (旧) ⑨
(旧) ⑨