「●い 五木 寛之」の インデックッスへ Prev|NEXT ⇒ 【411】 五木 寛之/野坂 昭如 『対論 野坂昭如 X 五木寛之』
「艶歌」「涙の河をふり返れ」は藤圭子"前"、「艶歌と援歌と怨歌」「怨歌の誕生」は藤圭子"後"。





『涙の河をふり返れ―五木寛之作品集 (1970年)』『涙の河をふり返れ (1973年) (五木寛之作品集〈6〉)
』『涙の河をふり返れ (文春文庫 100-8)
』『怨歌の誕生 (双葉文庫)
』['13年]
大学講師の「私」は、同じ大学で学究の道に進みながらも研究費流用事件で大学を追われて歌手のマネージャーに転じた「黒木」が、才能のある女性演歌歌手を世に出すためにどうすればよいか相談してきたため、マスメディアからの一方的な押し付けではなく、大衆の側からアプローチさせればどうかとアドバイスする。黒木は私の助言に従って、新興宗教団体に絡めてその演歌歌手「水沢忍」を売り出し一時は成功するが、やがて彼女の人気に陰りが見え始める。更に助言を求める黒木に、私は、彼女が売れたことが大衆の反発を招いたとし、大衆は彼女にある種の「不幸」の影を求めているとアバイスをすると、やがて実際に水沢忍を不幸が襲い、彼女の人気は前にも増して高騰するが、その「不幸」は黒木の仕組んだものだった。黒木のことを親よりも信じていた水沢忍はそれを知り衝撃を受けるが、黒木は、彼女への最後のプレゼントとして、人を信じられないという「不幸」をその心に刻印したのだと言って去る―(「涙の河をふり返れ」)。
 私(五木寛之)は、自宅で原稿が一枚も書けない日の深夜、原稿になりそうな考えが浮かばないので、音楽を聞こうとそこらにある流行歌のレコードを探し、ごく軽い気持ちで、最近人気が出てきた17歳の女性歌手の最初のLPをかける。藤圭子の歌はそれまでに何度か聞いたことがあったが、特別な印象があったわけではなかった。しかし、「かけたレコードは、これまでに聞いたどんな流行歌にも似ていず、その歌い手の声は私の耳でなくて体の奥のほうにまで、深くつき刺さってくるような感じを与えたのだった。私は思わず坐りなおして、そのレコードを二度、三度と聞き返した」。私は居眠りしていた細君を叩きおこし、二人でくり返しそのLPを聞く。そして私は久しぶりで熱っぽい内側からの衝動につき動かされて鉛筆を走らせたのだった―(「怨歌の誕生」)。
私(五木寛之)は、自宅で原稿が一枚も書けない日の深夜、原稿になりそうな考えが浮かばないので、音楽を聞こうとそこらにある流行歌のレコードを探し、ごく軽い気持ちで、最近人気が出てきた17歳の女性歌手の最初のLPをかける。藤圭子の歌はそれまでに何度か聞いたことがあったが、特別な印象があったわけではなかった。しかし、「かけたレコードは、これまでに聞いたどんな流行歌にも似ていず、その歌い手の声は私の耳でなくて体の奥のほうにまで、深くつき刺さってくるような感じを与えたのだった。私は思わず坐りなおして、そのレコードを二度、三度と聞き返した」。私は居眠りしていた細君を叩きおこし、二人でくり返しそのLPを聞く。そして私は久しぶりで熱っぽい内側からの衝動につき動かされて鉛筆を走らせたのだった―(「怨歌の誕生」)。
藤 圭子(本名:宇多田純子、1951- 2013.8.22/享年62)
「涙の河をふり返れ」は1967(昭和42)年11月発表で、1970(昭45)年3月刊行の短編集『涙の河をふり返れ』(文芸春秋)に収められました(この短編集はその他に「われはうたへど」「人情ブラウン管」「望郷七月歌」「深く暗い海」を所収)。
作者は「涙の河をふり返れ」発表の前年の1966年に、新
 人演歌歌手の売り出しに奔走する音楽プロデューサーらを描いた「艶歌」という中編も書いており、「不幸」を"仕掛けた"ことでその新人は爆発的に売れるというプロットは「涙の河をふり返れ」とよく似ています。これが藤圭子をモデルにしたものとされて後に話題になりますが、藤圭子が「新宿の女」でデビューしたのは3年後の1969(昭和44)年9月であり(翌1970年には「圭子の夢は夜ひらく」が爆発的にヒットする)、まだデビューしていない藤圭子を、デビューの3年前にモデルには出来ないわけで、作者もあり得ないと否定しています。
人演歌歌手の売り出しに奔走する音楽プロデューサーらを描いた「艶歌」という中編も書いており、「不幸」を"仕掛けた"ことでその新人は爆発的に売れるというプロットは「涙の河をふり返れ」とよく似ています。これが藤圭子をモデルにしたものとされて後に話題になりますが、藤圭子が「新宿の女」でデビューしたのは3年後の1969(昭和44)年9月であり(翌1970年には「圭子の夢は夜ひらく」が爆発的にヒットする)、まだデビューしていない藤圭子を、デビューの3年前にモデルには出来ないわけで、作者もあり得ないと否定しています。
 一方、「怨歌の誕生」は1970(昭和45)年8月発表で、1971(昭46)年7月刊行の短編集『四月の海賊たち』(文芸春秋)に収められました(この短編集はその他に「悪い夏悪い旅」「ヘアピン・サーカス」「Qの世界」「バルカンの星の下に」「四月の海賊たち」を所収)。
一方、「怨歌の誕生」は1970(昭和45)年8月発表で、1971(昭46)年7月刊行の短編集『四月の海賊たち』(文芸春秋)に収められました(この短編集はその他に「悪い夏悪い旅」「ヘアピン・サーカス」「Qの世界」「バルカンの星の下に」「四月の海賊たち」を所収)。
こちらは、発表時のタイトルが「実録・怨歌の誕生」であったことからも窺えるように、小説ではなく実録の読み物の形をとっていますが、藤圭子の育ての親である作詞家・石坂まさを氏を「沢ノ井氏」として登場させるなど、藤圭子の関係者がぞろぞろ出てきます(石坂まさを氏の本名は「澤之井龍二」、初期のペンネームは「沢ノ井千江児」。28歳で藤圭子をプロデュースしミリオンセラーとなる直前に「石坂まさを」に改名した)。 テレビ番組の打ち合わせの席に現れた、藤圭子の歌の歌詞から
テレビ番組の打ち合わせの席に現れた、藤圭子の歌の歌詞から プランニングまでを一手に仕切っているという沢ノ井氏の"独演"に、その場に居合わせた「私」たちが戸惑う場面があります。沢ノ井氏は、「できるだけ暗く暗く持って行こうとしているんですがね。ちょっと目を離すとすぐ明るくなっちゃう」と言って周囲を煙に巻き、その場を去っていきます。
プランニングまでを一手に仕切っているという沢ノ井氏の"独演"に、その場に居合わせた「私」たちが戸惑う場面があります。沢ノ井氏は、「できるだけ暗く暗く持って行こうとしているんですがね。ちょっと目を離すとすぐ明るくなっちゃう」と言って周囲を煙に巻き、その場を去っていきます。
石坂まさを(本名:澤ノ井龍二、1941- 2013.3.9/享年71)
石坂まさを(左)と藤圭子(中央)SANSPO.COM(サンスポ)[撮影日:1970.11.9]
この「怨歌の誕生」の中には書かれていませんが、後日譚として知られているのは、その「沢ノ井氏」こと石坂まさを氏が、自分が藤圭子を売り出す際にやったことは「五木さんに責任がある」と作者に言ったというもので、彼は「涙の河をふり返れ」の一節を諳んじていたそうです。つまり、「涙の河をふり返れ」は藤圭子をモデルにしたものではなく(こちらも藤圭子デビューの2年前に書かれており、時間的順序からしてそれは不可能)、藤圭子の売り出しに際して「涙の河をふり返れ」というフィクションが参照された―「現実」が「虚構」を模倣した―というのが興味深いと思います。

 「怨歌の誕生」の中に出てくる「私」が以前に書いた小文とは、毎日新聞連載のエッセイ「ゴキブリの歌」で作者が1970年夏に書いた「艶歌と援歌と怨歌」であり、「怨歌の誕生」で「原稿が一枚も書けない」で行き詰った状況とは、この連載エッセイの原稿締切りで作者が煮詰まっていたことを指しています。従って、「怨歌の誕生」には、「艶歌と援歌と怨歌」という小文を書いた際の周辺状況を"メタ・エッセイ"として再構築している面もあるとも言えるのではないかと思います(『ゴキブリの歌』は作者の第一エッセイ集『風に吹かれて』('68年/読売新聞社)に続くものとして1971年刊行。『風に吹かれて』は非常に良かったが、これも手練れ感があって悪くない)。
「怨歌の誕生」の中に出てくる「私」が以前に書いた小文とは、毎日新聞連載のエッセイ「ゴキブリの歌」で作者が1970年夏に書いた「艶歌と援歌と怨歌」であり、「怨歌の誕生」で「原稿が一枚も書けない」で行き詰った状況とは、この連載エッセイの原稿締切りで作者が煮詰まっていたことを指しています。従って、「怨歌の誕生」には、「艶歌と援歌と怨歌」という小文を書いた際の周辺状況を"メタ・エッセイ"として再構築している面もあるとも言えるのではないかと思います(『ゴキブリの歌』は作者の第一エッセイ集『風に吹かれて』('68年/読売新聞社)に続くものとして1971年刊行。『風に吹かれて』は非常に良かったが、これも手練れ感があって悪くない)。
『ゴキブリの歌 (1971年)』『ゴキブリの歌 (講談社文庫)
』
個人的にはエッセイ集の中の一文に過ぎない「艶歌と援歌と怨歌」が意外と印象に残っているのですが、「怨歌の誕生」では、その小文を書いたその時の自分や世間の状況を再検証している面があるのが興味深い一方で、エッセイと言うより"読み物"として再構築されているようにも感じられました。社会批評的な要素も含んでいますが、"メタ・エッセイ"ではなく、自らのエッセイをベースにした"メタ小説"とみる見方も成り立つように思います。或いは、「艶歌と援歌と怨歌」の方がそもそも、エッセイのスタイルをとった"メタ小説"であり、その"創作"の部分を「怨歌の誕生」で解き明かしていると言った方がより正確なのかもしれません。
 もう一度おさらいするならば、「艶歌」(1966)、「涙の河をふり返れ」(1967)は藤圭子登場"前"であり(したがって作者にとって「藤圭子」は意識されていない)、「艶歌と援歌と怨歌」(1970)、「怨歌の誕生」(1970)は藤圭子登場"後"或いは"リアルタイム"である(実際に藤圭子のことが書かれている)ことになるわけです。
もう一度おさらいするならば、「艶歌」(1966)、「涙の河をふり返れ」(1967)は藤圭子登場"前"であり(したがって作者にとって「藤圭子」は意識されていない)、「艶歌と援歌と怨歌」(1970)、「怨歌の誕生」(1970)は藤圭子登場"後"或いは"リアルタイム"である(実際に藤圭子のことが書かれている)ことになるわけです。
2013年8月の藤圭子の転落死(新宿警察署により自殺と断定されている)による急逝を受け、双葉文庫より『怨歌の誕生』(2013年12月刊)が刊行されました。この中に「艶歌」「涙の河をふり返れ」「われはうたえど」「怨歌の誕生」が所収されているほか、「藤圭子モデル説を訂正」という作者が1976年に日刊ゲンダイ連載エッセイ「流されゆく日々」に書いた小文や、更には「あとがきにかえて」の中で当時の経緯が解説されていて、整理がつきやすくなっています。
2013年8月22日「東京新聞」夕刊
その中で著者は、「怨歌」という言葉が一人歩きしてしまったが、自分は藤圭子へのオマージュを書いたのではなく、「この歌い手がこういった歌をうたえるのは、たった今この数カ月ではないか、という不吉な予感があった」と当時書いた文章を引いて、不吉な予言を込めたことを示唆していますが、その予言は、「藤圭子のその後の人生はどうだったか」という長い目で見れば当たったと言えなくもないように思いました。
安西水丸:画


 余談ですが、村上春樹氏の最初のエッセイ集『村上朝日堂』('84年/若林出版企画) に、かつて村上春樹氏が働いていた新宿のレコード店に藤圭子がやって来たことが一度あって、すごくすまなそう感じで「あの、売れてます?」とニコッと笑って彼に訊ねたという話があったのを思い出しました。藤圭子は1970年3月にはシングル2作目となる「女のブルース」がオリコン・シングル・チャートで1位を獲得し、同時にファースト・アルバム『新宿の女/演歌の星 藤圭子のすべて』もオリコン・アルバム・チャートで1位を獲得して、記録的スピードで2冠を達成しています。村上春樹氏が働いていた店に来たのは、1969(昭和44)年9月に「新宿の女」でデビューして、それから間もない頃なのでしょうか。
余談ですが、村上春樹氏の最初のエッセイ集『村上朝日堂』('84年/若林出版企画) に、かつて村上春樹氏が働いていた新宿のレコード店に藤圭子がやって来たことが一度あって、すごくすまなそう感じで「あの、売れてます?」とニコッと笑って彼に訊ねたという話があったのを思い出しました。藤圭子は1970年3月にはシングル2作目となる「女のブルース」がオリコン・シングル・チャートで1位を獲得し、同時にファースト・アルバム『新宿の女/演歌の星 藤圭子のすべて』もオリコン・アルバム・チャートで1位を獲得して、記録的スピードで2冠を達成しています。村上春樹氏が働いていた店に来たのは、1969(昭和44)年9月に「新宿の女」でデビューして、それから間もない頃なのでしょうか。
『涙の河をふり返れ』...【1970年単行本[文藝春秋]/1976年文庫化[文春文庫]】
『四月の海賊たち』...【1971年単行本[文藝春秋]/1975年文庫化[文春文庫]】
『ゴキブリの歌』...【1971年単行本[毎日新聞社]/1972年文庫化[角川文庫]/1975年再文庫化[講談社文庫]】



 金沢では、現在の金沢市民芸術村(旧大和紡績金沢工場)付近や犀川べり犀川神社付近に住みましたが、自分が通った、元々は金沢の伝統的な長い土塀で囲まれていたという小学校も、尾山神社のすぐ近くあった中学校も今は無く、それぞれ市民体育館とホテルになってしまいました。
金沢では、現在の金沢市民芸術村(旧大和紡績金沢工場)付近や犀川べり犀川神社付近に住みましたが、自分が通った、元々は金沢の伝統的な長い土塀で囲まれていたという小学校も、尾山神社のすぐ近くあった中学校も今は無く、それぞれ市民体育館とホテルになってしまいました。 そもそも自分は、金沢市と石川県の地歴を学校で教わる小学校の3、4年生の時には金沢にいなかったのですが、「加賀百万石まつり」の前夜祭には提灯行列に5、6年生の生徒が駆り出され(これは今でも変わっていないみたい)、「二つの流れ遠長く 麗澤清んで涌くところ 甍の波 の日に沿いて 自ずからなる大都会」という金沢市歌を歌いながら金沢城付近を練り歩き、歴史を体感した(?)記憶があります(歌詞二番の「眺め尽きせぬ兼六の 園には人の影絶えず」って「その庭人の影絶えず」だとずっと思っていた(笑))。
そもそも自分は、金沢市と石川県の地歴を学校で教わる小学校の3、4年生の時には金沢にいなかったのですが、「加賀百万石まつり」の前夜祭には提灯行列に5、6年生の生徒が駆り出され(これは今でも変わっていないみたい)、「二つの流れ遠長く 麗澤清んで涌くところ 甍の波 の日に沿いて 自ずからなる大都会」という金沢市歌を歌いながら金沢城付近を練り歩き、歴史を体感した(?)記憶があります(歌詞二番の「眺め尽きせぬ兼六の 園には人の影絶えず」って「その庭人の影絶えず」だとずっと思っていた(笑))。 本書は金沢という街をいろいろな角度から百景ほど紹介していますが、タイトルを「百景」としなかったのは、番組の方がまだ続いているからでしょうか。
本書は金沢という街をいろいろな角度から百景ほど紹介していますが、タイトルを「百景」としなかったのは、番組の方がまだ続いているからでしょうか。





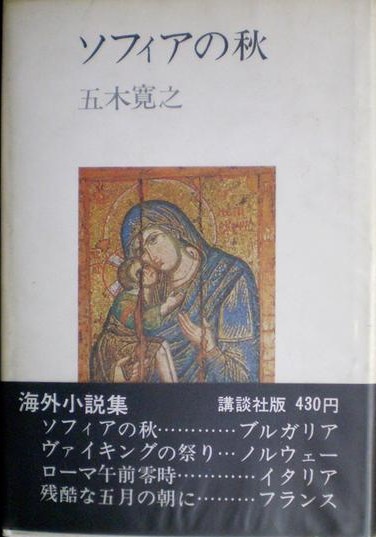





 五木寛之氏の奥さんが女医さんで、五木氏は、自分が70歳になったら奥さんに注射してもらって死ぬのだと言っています。
五木寛之氏の奥さんが女医さんで、五木氏は、自分が70歳になったら奥さんに注射してもらって死ぬのだと言っています。

 1932(昭和7)年生まれの著者が、'66年に『さらばモスクワ愚連隊』、『蒼ざめた馬を見よ』を発表した後の処女エッセイ集(『蒼ざめた馬を見よ』は'67年1月に直木賞を受賞)。'67年1月から「週刊読売」に連載され、1年間の連載の後'68年に単行本化、その後、新潮文庫、講談社文庫、角川文庫などにおいて何度も文庫化され、総計400万部以上売れました。
1932(昭和7)年生まれの著者が、'66年に『さらばモスクワ愚連隊』、『蒼ざめた馬を見よ』を発表した後の処女エッセイ集(『蒼ざめた馬を見よ』は'67年1月に直木賞を受賞)。'67年1月から「週刊読売」に連載され、1年間の連載の後'68年に単行本化、その後、新潮文庫、講談社文庫、角川文庫などにおいて何度も文庫化され、総計400万部以上売れました。 金沢という街をに対する愛着も随所に見られますが、「私はやはり基地を失ったジェット機でありたいと思う。港を持たぬヨット、故郷を失った根なし草でありたいと感じる」という言葉が最終回にあり、金沢を離れることを予感させています。
金沢という街をに対する愛着も随所に見られますが、「私はやはり基地を失ったジェット機でありたいと思う。港を持たぬヨット、故郷を失った根なし草でありたいと感じる」という言葉が最終回にあり、金沢を離れることを予感させています。
