「●よ 吉行 淳之介」の インデックッスへ Prev|NEXT ⇒ 【540】 吉行 淳之介 『失敗を恐れないのが若さの特権である』
「●「野間文芸賞」受賞作」の インデックッスへ
40代前半に書き始め、54歳で完結した連作。女性に対する不可知論を素直に告白している作品。
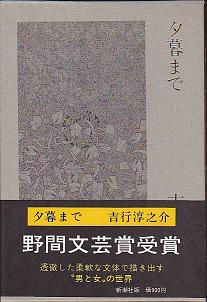 『夕暮まで
『夕暮まで』(1978/09 新潮社)
 『夕暮まで (新潮文庫)
『夕暮まで (新潮文庫)』
 1978(昭和53)年・第31回「野間文芸賞」受賞作。
1978(昭和53)年・第31回「野間文芸賞」受賞作。
主人公の妻子ある中年男・佐々と、若い女性・杉子の歳差のある男女の微妙な関係を描いた作品で、単行本化されるや当時のベストセラーとなり、黒木和雄監督、桃井かおり・伊丹十三主演で映画化されもしました('80年/東宝、主演:桃井かおり、伊丹十三)。
作者の作品で、いろいろな意味で世間を賑わしたものと言えば、前期では『砂の上の植物群』('66年/新潮社)、中期ではこの作品になるのではないかと思われますが、この作品は元々は別に発表された短篇の連作であり、各発表年を見ると、「公園で」('65年)、「網目のなか」('71年)、「傷」('76年)、「夜の警官」('77年)、「血」('77年)、「すでにそこにある黒」('77年)、「夕暮まで」('78年)となっています。
吉行淳之介(1977年ごろ)
つまり、書き始めは『砂の上の植物群』と同じく作者40代初めの頃で、作者は主人公とほぼ同年齢だったのが(主人公の佐々は40代前半の中年で、彼の不倫相手である杉子は22歳の独身女性)、書き終えた時には54歳になっていたことになります。
冒頭の「公園で」は非常に幻想的なタッチであり、まだ「佐々」「杉子」といった連作における登場人物の名前さえも出てきませんが、70年代初めの「網目のなか」からリアリスティックな描写になり、70代中盤の「傷」から「夕暮まで」にかけて、現実的なストーリー性を帯びてきます(と言っても、ドラマ的な展開を見せるわけではなく、2人の関係性の変化を断章的に描いていくという感じ)。
そのストーリーを追っていくと、杉子の自分の処女性へのこだわりというのが浮かび上がり(杉子は佐々に身体は許すが接合は許さない)、また、杉子が佐々の知らない何者かによって処女を喪失し、そのことが2人の別れの契機になったともとれることからも、その見方を強化することが出来るのですが、個人的には作者がそんな古風なテーマを物語の中心に据えようとしたようには思えませんでした。
研ぎ澄まされた文章で知られる作家ですが、この作品は簡潔な会話が主体の部分が多く、確かにとっつき易いかも。但し、ところどころにある主人公の女性に対する観察眼の鋭さや、男女の間にある深い溝のようなものを映し出すような文章は、やはりこの作者ならではのものと思われました。
簡潔な部分はあまりに簡潔に描かれているため、ともすると即物的に不倫を描いたような作品にも見えるかも知れず(映画化作品は観てないが、映像化するとますますそうなるのでは)、また、まるで「これが大人の男女の会話ですよ」みたいなフレーズが連なり、中年男性の"テキスト"みたいな読まれ方もされかねない作品でもあるかも。
実際には、主人公の内的風景を核とした吉行文学に共通する心理小説だと思いますが、そういう自分も"テキスト"として読んでしまっている部分があったりして...(作者は『砂の上の植物群』を書いた時に、その種の世俗的エンタテイメント性も意識したと言っていたが、この作品はどうなのか)。
そうした意味では、個人的には、読んでいて何となく落ち着かない作品でしたが、結論的には、女性をコントロールしているようで実は曖昧模糊の状態に置かれている主人公を通して、女性に対する不可知論のようなものを作者が素直に告白している作品のように思えました。
 映画「夕暮まで」('80年/東宝、主演:桃井かおり、伊丹十三)
映画「夕暮まで」('80年/東宝、主演:桃井かおり、伊丹十三)
【1982年文庫化[新潮文庫]】
