「●か行外国映画の監督」の インデックッスへ Prev|NEXT ⇒ 【1450】 J・P・コスマトス「トゥームストーン」
「●た‐な行の外国映画の監督」の インデックッスへ 「●は行の外国映画の監督①」の インデックッスへ 「●は行の外国映画の監督②」の インデックッスへ 「○外国映画 【制作年順】」の インデックッスへ 「●О・ヘンリー」の インデックッスへ
O・ヘンリーの代表的短編5編のオムニバスで映画化。安心して観られる。
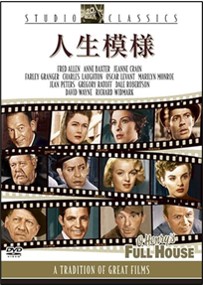
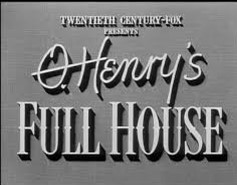

「人生模様 [DVD]」O'Henry's Full House (1952) 進行役:ジョン・スタインベック
「最後の一葉」「賢者の贈物」など、O・ヘンリーの代表的短編5編を原作とする、5人の監督による全5話のオムニバス映画で、進行役を作家のジョン・スタインベックが務めてます。
第1話「警官と聖歌」
 紳士気取りで人の善いルンペン男ソーピイ(チャールズ・ロートン)は、夏は涼しいセントラル・パークで、冬は暖かい留置所で暮らすことにしていた。ある年の冬、彼は仲間のホレス(デイヴィッド・ウェイン)に、留置所に入る秘術を伝授しようとしたが、どうも
紳士気取りで人の善いルンペン男ソーピイ(チャールズ・ロートン)は、夏は涼しいセントラル・パークで、冬は暖かい留置所で暮らすことにしていた。ある年の冬、彼は仲間のホレス(デイヴィッド・ウェイン)に、留置所に入る秘術を伝授しようとしたが、どうも うまく警官に捕まらない。ソーピイは街の女(マリリン・モンロー)に声を掛けたが、かえって彼女に好意を寄せられ面喰らって逃げ出す始末。ある教会に入り、オルガンの響きに心打たれて、ルンペン渡世から足を洗おうと決心したが―。
うまく警官に捕まらない。ソーピイは街の女(マリリン・モンロー)に声を掛けたが、かえって彼女に好意を寄せられ面喰らって逃げ出す始末。ある教会に入り、オルガンの響きに心打たれて、ルンペン渡世から足を洗おうと決心したが―。
主演のチャールズ・ロートン(「情婦」('57年))がさすがに旨い。レストランでたらふく食べて、食後の葉巻のサービスに堂々と応えているところなどは、偽紳士役が似合う。マリリン・モンローはまだ「グラマーなだけの女優」というイメージしか持たれていなかった頃だが、こうして観るとその演技は悪くない。
第2話「クラリオン・コール新聞」
 刑事のバーニイ(デール・ロバートソン)は、迷宮入り殺人事件の犯人をヤクザ者のジョニイ(リチャード・ウィドマーク)だと睨んだ。バーニイとジョニイは幼な友達で、2人は十数年ぶりで再会したのだ。バーニイはジョニイに証拠を突きつけ迫るが、ジョニイはバーニイに昔千ドル貸したことを持ち出した。バーニイはジョニイを一応見逃し、千ドルの工面を考えた。すると町の新聞「クラリオン・コール」が、犯人の名前を通告した者に千ドル出すという懸賞を―。
刑事のバーニイ(デール・ロバートソン)は、迷宮入り殺人事件の犯人をヤクザ者のジョニイ(リチャード・ウィドマーク)だと睨んだ。バーニイとジョニイは幼な友達で、2人は十数年ぶりで再会したのだ。バーニイはジョニイに証拠を突きつけ迫るが、ジョニイはバーニイに昔千ドル貸したことを持ち出した。バーニイはジョニイを一応見逃し、千ドルの工面を考えた。すると町の新聞「クラリオン・コール」が、犯人の名前を通告した者に千ドル出すという懸賞を―。
 最後の格闘シーンは要らなかったが、新聞記事で見せる終わり方は旨かった。リチャード・ウィドマークのヤクザ者の役が嵌っている。晩年は大御所的存在だったが、若い頃は、冷やかな笑顔をトレードマークに、
最後の格闘シーンは要らなかったが、新聞記事で見せる終わり方は旨かった。リチャード・ウィドマークのヤクザ者の役が嵌っている。晩年は大御所的存在だったが、若い頃は、冷やかな笑顔をトレードマークに、
 ギャング映画の非情な殺し屋、戦争映画の冷徹で人望のない指揮官役などで持ち味を発揮していた人だ。「オリエント急行殺人事件」('74年)で殺人事件の被害者役をやっていた(殺害されても致し方のない男の役なのだが)。手塚治虫の作品にしばしば登場する冷酷な悪役キャラクター〈スカンク草井〉のモデルでもある。
ギャング映画の非情な殺し屋、戦争映画の冷徹で人望のない指揮官役などで持ち味を発揮していた人だ。「オリエント急行殺人事件」('74年)で殺人事件の被害者役をやっていた(殺害されても致し方のない男の役なのだが)。手塚治虫の作品にしばしば登場する冷酷な悪役キャラクター〈スカンク草井〉のモデルでもある。
第3話「最後の一葉」
 恋人に捨てられた若い女画学生ジョアンナ(アン・バクスター)は、失望し、寒いニューヨークの街を彷徨った末、姉スーザン(ジーンン・ピータース)と一緒に住むアパートに辿り着くと、そのまま病の床に伏す。医師は肺炎と診断し、ジョアンナが生きる希望を取り戻さなければ助からないと言った。彼女は自分の部屋の窓ぎわに生えている蔦にある21枚の葉が、その1枚ごとに彼女の1年間の生命を意味し、最後に残った葉が風に吹き落とされたら、自分は死ぬと思い込んでいる。容態は悪化し、ある朝、蔦も葉も最後の1枚になっ
恋人に捨てられた若い女画学生ジョアンナ(アン・バクスター)は、失望し、寒いニューヨークの街を彷徨った末、姉スーザン(ジーンン・ピータース)と一緒に住むアパートに辿り着くと、そのまま病の床に伏す。医師は肺炎と診断し、ジョアンナが生きる希望を取り戻さなければ助からないと言った。彼女は自分の部屋の窓ぎわに生えている蔦にある21枚の葉が、その1枚ごとに彼女の1年間の生命を意味し、最後に残った葉が風に吹き落とされたら、自分は死ぬと思い込んでいる。容態は悪化し、ある朝、蔦も葉も最後の1枚になっ た。途方にくれたスーザンは、バーマン(グレゴリー・ラトフ)という自分の才能に自信を失った画家に悩みを訴える―。
た。途方にくれたスーザンは、バーマン(グレゴリー・ラトフ)という自分の才能に自信を失った画家に悩みを訴える―。
何度も映像化されている話だが、このジーン・ネグレスコ監督作は美術が
 評価されているようだ。他のカラー作品も観たが、「葉っぱ」がダメなものが多い。白黒が幸いしたかも。アン・バクスターと言えば「イブの総て」('50年)だが、「十戒」('56年)の王女ネフレテリ役や「刑事コロンボ/偶像のレクイエム」('73年)の犯人役も懐かしい。
評価されているようだ。他のカラー作品も観たが、「葉っぱ」がダメなものが多い。白黒が幸いしたかも。アン・バクスターと言えば「イブの総て」('50年)だが、「十戒」('56年)の王女ネフレテリ役や「刑事コロンボ/偶像のレクイエム」('73年)の犯人役も懐かしい。
第4話「酋長の身代金」

 サム(フレッド・アレン)と相棒のビル(オスカー・レヴァント)は、金持ちの子を誘拐して身代金を稼ごうとアラバマの村へやって来た。2人はうまく少年を誘拐する
サム(フレッド・アレン)と相棒のビル(オスカー・レヴァント)は、金持ちの子を誘拐して身代金を稼ごうとアラバマの村へやって来た。2人はうまく少年を誘拐する ことに成功、身代金請求の手紙を少年の両親宛てに出した。ところが、この少年、インディアンの酋長気どりの腕白小僧で2人はほとほと手を焼く。そのうち、両親から手紙が来たが、それには身代金を払わないと言うばかりか、どうしても少年を返したいなら250ドルよこせと書いてあった―。
ことに成功、身代金請求の手紙を少年の両親宛てに出した。ところが、この少年、インディアンの酋長気どりの腕白小僧で2人はほとほと手を焼く。そのうち、両親から手紙が来たが、それには身代金を払わないと言うばかりか、どうしても少年を返したいなら250ドルよこせと書いてあった―。
元祖「ホーム・アローン」('90年/米)みたいなテイスト。監督はハンフリー・ボガート主演の「脱出」('44年)、「三つ数えろ」('46年)のハワード・ホークスなのだが、あんなハードボイルドを撮っている監督が、こんな喜劇も撮っているのかといういう感じ(でも、この作品の翌年にマリリン・モンローが主演してブレイクした「紳士は金髪がお好き」('53年)やロック・ハドソン主演「男性の好きなスポーツ」('64年)のようなコメディもあったか)。二人組が「ホーム・アローン」調のどたばた喜劇で(「ホーム・アローン」の方がこの作品からヒントを得た?)、これって、このオムニバス映画全体の流れの中でどうなのか(ただし、チャールズ・ロートン主演の第1話も喜劇調ではあった)。
第5話「賢者の贈物」
 愛し合う若夫婦デラ(ジーン・クレイン)とジム(ファーリー・グレンジャー)は、貧乏なのでクリマス・イヴが来るのにお互いの贈物を買うことができなかった。デラは出勤するジムを送りながら一緒に街に出、途中で2人はある宝
愛し合う若夫婦デラ(ジーン・クレイン)とジム(ファーリー・グレンジャー)は、貧乏なのでクリマス・イヴが来るのにお互いの贈物を買うことができなかった。デラは出勤するジムを送りながら一緒に街に出、途中で2人はある宝 石商のウィンドウの前に立ち止まる。ジムは素敵な櫛に目をつけ、これがデラのふさふさした金髪を飾ったらさぞ美くしかろうと考えた。一方デラはプラチナの時計入れを見て、これはジムの骨董的な金の懐中時計を入れるのにふさわしいと思った―。
石商のウィンドウの前に立ち止まる。ジムは素敵な櫛に目をつけ、これがデラのふさふさした金髪を飾ったらさぞ美くしかろうと考えた。一方デラはプラチナの時計入れを見て、これはジムの骨董的な金の懐中時計を入れるのにふさわしいと思った―。
役者はそう有名ではないが、ヘンリー・キング監督の演出が旨くいっているのではないか。結末は分かっていても、ラストは泣かせる(ヘンリー・キングは「慕情」('55年/米)など情話ものを得意とする監督だった)。
演出は多少ムラがあるものの、全体としてはまずますで、これは原作の良さに助けられている部分もあると思います。ただ、原作のテイストをよく伝えているのは役者のお陰かもしれず、昔の俳優は演技が旨かったなあとも思います。「最後の一葉」にしても「賢者の贈物」にしても、ちょっとでも下手な俳優が演じると逆に白けてしまうところ、個々の演技ではしっかり見せて(魅せて)いたように思います。5編とも楽しく、と言うか、原作を読んだ者としては安心して観られました。

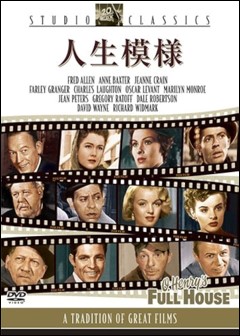 「人生模様」●原題:O. HENRY'S FULL HOUSE●制作年:1952年●制作国:アメリカ●監督:(第1話)ヘンリー・コスター/(第2話)ヘンリー・ハサウェイ/(第3話)ジーン・ネグレスコ/(第4話)/ハワード・ホークス/(第5話)ヘンリー・キング●脚本:(第1話)ラマー・トロッティ/(第2話)リチャード・L・ブリーン/(第3話)アイヴァン・ゴッフ/ベン・ロバーツ/(第4話)チャールズ・レデラー/ベン・ヘクト/ナナリー・ジョンソン/(第5話)ヘンリー・キング/ウォルター・バロック/フィリップ・ダン●撮影:(第1話)ロイド・エイハーン/(第2話)ルシアン・バラード/(第3話)ジョセフ・マクドナルド/(第4話)ミルトン・R・クラスナー/(第5話)ジョセフ・マクドナルド●音楽:アルフレッド・ニューマン●原作:原作:О・ヘンリー●時間:117分●出演:(第1話)チャールズ・ロートン/マリリン・モンロー/デヴィッド・ウェイン/(第2話)デイル・ロバートソン/リチャード・ウィドマーク/(第3話)アン・バクスター/ジーン・ピーターズ/グレゴリー・ラトフ/(第4話)フレッド・アレン/オスカー・レヴァント/リー・アーカー/(第5話)ジーン・クレイン/ファーリー・グレンジャー/(進行役)ジョン・スタインベック●日本公開:1953/06●配給:20世紀フォックス(評価:★★★★)
「人生模様」●原題:O. HENRY'S FULL HOUSE●制作年:1952年●制作国:アメリカ●監督:(第1話)ヘンリー・コスター/(第2話)ヘンリー・ハサウェイ/(第3話)ジーン・ネグレスコ/(第4話)/ハワード・ホークス/(第5話)ヘンリー・キング●脚本:(第1話)ラマー・トロッティ/(第2話)リチャード・L・ブリーン/(第3話)アイヴァン・ゴッフ/ベン・ロバーツ/(第4話)チャールズ・レデラー/ベン・ヘクト/ナナリー・ジョンソン/(第5話)ヘンリー・キング/ウォルター・バロック/フィリップ・ダン●撮影:(第1話)ロイド・エイハーン/(第2話)ルシアン・バラード/(第3話)ジョセフ・マクドナルド/(第4話)ミルトン・R・クラスナー/(第5話)ジョセフ・マクドナルド●音楽:アルフレッド・ニューマン●原作:原作:О・ヘンリー●時間:117分●出演:(第1話)チャールズ・ロートン/マリリン・モンロー/デヴィッド・ウェイン/(第2話)デイル・ロバートソン/リチャード・ウィドマーク/(第3話)アン・バクスター/ジーン・ピーターズ/グレゴリー・ラトフ/(第4話)フレッド・アレン/オスカー・レヴァント/リー・アーカー/(第5話)ジーン・クレイン/ファーリー・グレンジャー/(進行役)ジョン・スタインベック●日本公開:1953/06●配給:20世紀フォックス(評価:★★★★)


 世界的歌姫のカット・ヴァルデス(ジェニファー・ロペス)は、新曲「マリー・ミー」を携え、大観衆の前で音楽界の超新星バスティアン(マルーマ)と華々しく結婚式を挙げる予定だった。しかしショーの直前、婚約者バスティアンの浮気がスクープされる。失意のままステージに登壇した彼女は、観客の中から一人の男を指名、突然プロポーズするという驚きの行動に出る。新たなお相手は、平凡な数学教師とあって、前代未聞のギャップ婚に取り巻きのスタッフやマスコミ、ファンは大混乱となり、早くも離婚の噂が噴出する始末。お互いを知るところから始まった結婚生活は前途多難な道のりだった。そんな矢先、バスティアンとのデュエット曲だった「マリー・ミー」がグラミー賞にノミネートされたことで、カットとバスティアンの関係は、再び親密になっていくのだった―。
世界的歌姫のカット・ヴァルデス(ジェニファー・ロペス)は、新曲「マリー・ミー」を携え、大観衆の前で音楽界の超新星バスティアン(マルーマ)と華々しく結婚式を挙げる予定だった。しかしショーの直前、婚約者バスティアンの浮気がスクープされる。失意のままステージに登壇した彼女は、観客の中から一人の男を指名、突然プロポーズするという驚きの行動に出る。新たなお相手は、平凡な数学教師とあって、前代未聞のギャップ婚に取り巻きのスタッフやマスコミ、ファンは大混乱となり、早くも離婚の噂が噴出する始末。お互いを知るところから始まった結婚生活は前途多難な道のりだった。そんな矢先、バスティアンとのデュエット曲だった「マリー・ミー」がグラミー賞にノミネートされたことで、カットとバスティアンの関係は、再び親密になっていくのだった―。 飯田橋の名画座ギンレイホールの閉館最終上映の1本目、カット・コイロ監督の「マリー・ミー」('22年/米)は、女優で歌手でもあるジェニファー・ロペスが製作・主演を務め、ポップスターと平凡な数学教師の恋の行方を描いたラブストーリーで、原作はボビー・クロスビーの同名グラフィックノベル。見方によっては、ご都合主義的な能天気映画ですが(ラブコメって大体がそうだが)、ハリウッド映画流に泣かせどころのツボは押さえていました。
飯田橋の名画座ギンレイホールの閉館最終上映の1本目、カット・コイロ監督の「マリー・ミー」('22年/米)は、女優で歌手でもあるジェニファー・ロペスが製作・主演を務め、ポップスターと平凡な数学教師の恋の行方を描いたラブストーリーで、原作はボビー・クロスビーの同名グラフィックノベル。見方によっては、ご都合主義的な能天気映画ですが(ラブコメって大体がそうだが)、ハリウッド映画流に泣かせどころのツボは押さえていました。 ジェニファー・ロペス自身の恋愛遍歴と重なるような虚実皮膜を地で行く設定が面白く、しかも、この映画が日本公開された月[2022年4月]に、一度破局した俳優のベン・アフレックと20年の歳月を超えて再び婚約したことを発表しており、彼女の人生のプロモーション映画のような印象もあります。
ジェニファー・ロペス自身の恋愛遍歴と重なるような虚実皮膜を地で行く設定が面白く、しかも、この映画が日本公開された月[2022年4月]に、一度破局した俳優のベン・アフレックと20年の歳月を超えて再び婚約したことを発表しており、彼女の人生のプロモーション映画のような印象もあります。 妻を亡くしたばかりの90歳のトム・ハーパー(ティモシー・スポ―ル)は、50年暮らした家を離れ、ローカルバスのフリーパスを利用してイギリス縦断の壮大な旅に出ることを決意する。 目指すは愛する妻と出会い、二人の人生が始まった場所。 行く先々で様々な人と出会い、トラブルに巻き込まれながらも、妻と交わしたある"約束"を胸に時間・年齢・運命に抗い旅を続ける―。
妻を亡くしたばかりの90歳のトム・ハーパー(ティモシー・スポ―ル)は、50年暮らした家を離れ、ローカルバスのフリーパスを利用してイギリス縦断の壮大な旅に出ることを決意する。 目指すは愛する妻と出会い、二人の人生が始まった場所。 行く先々で様々な人と出会い、トラブルに巻き込まれながらも、妻と交わしたある"約束"を胸に時間・年齢・運命に抗い旅を続ける―。 飯田橋ギンレイホールの閉館最終上映の2本目、ギリーズ・マッキノン監督の「君を想い、バスに乗る」('21 年/ 英)は、これも「マリー・ミー」とはまた違った意味で泣ける作品でした。
飯田橋ギンレイホールの閉館最終上映の2本目、ギリーズ・マッキノン監督の「君を想い、バスに乗る」('21 年/ 英)は、これも「マリー・ミー」とはまた違った意味で泣ける作品でした。 これって実話なのかなと思いましたが、脚本を手掛けたジョー・エインズワースが、彼の父と義父の「高齢者向けの無料バス乗車券を使ってどこに旅をするか」という会話から着想を得て作った物語だそうです。因みに、本作で主人公トムが目指すのはイギリス旅行者憧れの聖地"ランズエンド"です。
これって実話なのかなと思いましたが、脚本を手掛けたジョー・エインズワースが、彼の父と義父の「高齢者向けの無料バス乗車券を使ってどこに旅をするか」という会話から着想を得て作った物語だそうです。因みに、本作で主人公トムが目指すのはイギリス旅行者憧れの聖地"ランズエンド"です。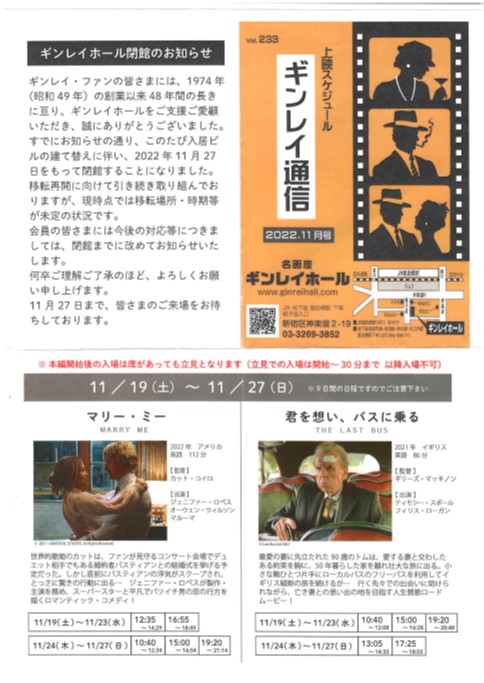 結局、ギンレイホールの最終上映作品は、今年['22年]公開された米・英の泣かせの2本だったということになります。この映画を観た先月[2022年11月]の27日(日)をもって同館は1974(昭和49)年の創業以来48年間の歴史に幕を閉じました。個人的には最後から3回目と2回目の上映を観たのですが、行った時は8割程度の入りだったのが、その次の回は立ち見が出ていて、最終回は、付近の地下鉄飯田橋駅の地下階段の一番下まで入場待ちの列でした(全員入れたのかなあ)。
結局、ギンレイホールの最終上映作品は、今年['22年]公開された米・英の泣かせの2本だったということになります。この映画を観た先月[2022年11月]の27日(日)をもって同館は1974(昭和49)年の創業以来48年間の歴史に幕を閉じました。個人的には最後から3回目と2回目の上映を観たのですが、行った時は8割程度の入りだったのが、その次の回は立ち見が出ていて、最終回は、付近の地下鉄飯田橋駅の地下階段の一番下まで入場待ちの列でした(全員入れたのかなあ)。
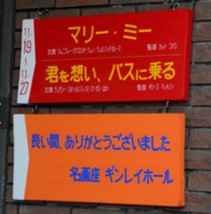


 2007年、ロンドン。1000年生きたと称するパルナサス博士(クリストファー・プラマー)は、下僕の侏儒パーシー(ヴァーン・J・トロイヤー)、若い団員アントン(アンドリュー・ガーフィールド)、そして自分の娘のヴァレンティナ(リリー・コール)の4人で旅を続けながら、鏡の中に客を誘い、人の心の中の欲望の世界を見せるという「パルナサス博士のイマジナリウム」の公演を行っていた。実は、博士は鏡の中でどちらが客を誘惑できるか
2007年、ロンドン。1000年生きたと称するパルナサス博士(クリストファー・プラマー)は、下僕の侏儒パーシー(ヴァーン・J・トロイヤー)、若い団員アントン(アンドリュー・ガーフィールド)、そして自分の娘のヴァレンティナ(リリー・コール)の4人で旅を続けながら、鏡の中に客を誘い、人の心の中の欲望の世界を見せるという「パルナサス博士のイマジナリウム」の公演を行っていた。実は、博士は鏡の中でどちらが客を誘惑できるか 、悪魔のMr.ニック(トム・ウェイツ)と賭けをしていた。そして、かつて悪魔との賭けにより不死の命を手に入れたパルナサス博士だったが、その代償にヴァレンティーナを16歳の誕生日に悪魔に引き渡さねばならなくなっていた。そんな折、一行は橋の上から吊るされた若者トニー(ヒース・レジャー/ジョニー・デップ/ジュード・ロウ/コリン・ファレル)を救い上げる。助けられた男トニーは一行の仲間になり、商才を発揮して見世物を繁盛させる。だが、悪魔との賭けのタイムリミットは目前に迫っていた。それぞれの思惑が交錯するなか、悪魔と一行は鏡の中の世界でヴァレンティナを巡る駆け引きを繰り広げる―。
、悪魔のMr.ニック(トム・ウェイツ)と賭けをしていた。そして、かつて悪魔との賭けにより不死の命を手に入れたパルナサス博士だったが、その代償にヴァレンティーナを16歳の誕生日に悪魔に引き渡さねばならなくなっていた。そんな折、一行は橋の上から吊るされた若者トニー(ヒース・レジャー/ジョニー・デップ/ジュード・ロウ/コリン・ファレル)を救い上げる。助けられた男トニーは一行の仲間になり、商才を発揮して見世物を繁盛させる。だが、悪魔との賭けのタイムリミットは目前に迫っていた。それぞれの思惑が交錯するなか、悪魔と一行は鏡の中の世界でヴァレンティナを巡る駆け引きを繰り広げる―。 シネマブルースタジオの2022年「異世界へようこそ vol.2」特集の1作目。「モンティ・パイソン・アンド・ホーリー・グレイル」('75年/英)など「モンティ・パイソン」シリーズの監督で、自身もコメディグループ「モンティ・パイソン」のメンバーの一人であるテリー・ギリアム監督の2009年公開作。「
シネマブルースタジオの2022年「異世界へようこそ vol.2」特集の1作目。「モンティ・パイソン・アンド・ホーリー・グレイル」('75年/英)など「モンティ・パイソン」シリーズの監督で、自身もコメディグループ「モンティ・パイソン」のメンバーの一人であるテリー・ギリアム監督の2009年公開作。「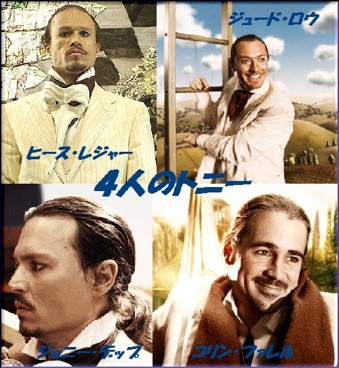 期せずしてこの映画の見所となった部分があり、それは、この映画の撮影中の2008年1月にトニーを演じるヒース・レジャーが急逝、撮影が中断し一時完成が危ぶまれたものの、彼と親交のあったジョニー・デップ、ジュード・ロウ、コリン・ファレルの3人が別世界にトリップしたトニーを演じて映画が完成したという経緯があって(3人はヒース・レジャーの娘に出演料を寄付しているトム・クルーズも自分から出演を申し込んだが、テリー・ギリアム監督は「ヒースをよく理解している本当の友だちに演じてほしい」と断っている)、トニーが鏡の中に入る度に演じる俳優が変わるという設定になっている点です。
期せずしてこの映画の見所となった部分があり、それは、この映画の撮影中の2008年1月にトニーを演じるヒース・レジャーが急逝、撮影が中断し一時完成が危ぶまれたものの、彼と親交のあったジョニー・デップ、ジュード・ロウ、コリン・ファレルの3人が別世界にトリップしたトニーを演じて映画が完成したという経緯があって(3人はヒース・レジャーの娘に出演料を寄付しているトム・クルーズも自分から出演を申し込んだが、テリー・ギリアム監督は「ヒースをよく理解している本当の友だちに演じてほしい」と断っている)、トニーが鏡の中に入る度に演じる俳優が変わるという設定になっている点です。 物語の方は終盤、父親が悪魔と取引したことを隠し続けてきたことに怒ったヴァレンティナは、自らの魂を悪魔(ニック)に捧げますが、安易な勝利に幻滅した悪魔は、パルナサスに、トニーを地獄に落とせば娘を返すという別の賭けを持ち掛けます。そして暴徒がトニーを吊るすために近づいてきたとき、吊るされても生き残れる黄金のパイプ(飲み込んで首吊りから喉を防御するという単純な仕掛けだが)をパルナサスは差し出し、その際、ひとつは真の頑丈な黄金のパイプで、もう一つは偽物の脆いパイプを選ばせますが、パルナサスはトニーが間違った選択をすることを望み、実際に、トニーは偽物のパイプを選び、死して地獄に落ちる―。
物語の方は終盤、父親が悪魔と取引したことを隠し続けてきたことに怒ったヴァレンティナは、自らの魂を悪魔(ニック)に捧げますが、安易な勝利に幻滅した悪魔は、パルナサスに、トニーを地獄に落とせば娘を返すという別の賭けを持ち掛けます。そして暴徒がトニーを吊るすために近づいてきたとき、吊るされても生き残れる黄金のパイプ(飲み込んで首吊りから喉を防御するという単純な仕掛けだが)をパルナサスは差し出し、その際、ひとつは真の頑丈な黄金のパイプで、もう一つは偽物の脆いパイプを選ばせますが、パルナサスはトニーが間違った選択をすることを望み、実際に、トニーは偽物のパイプを選び、死して地獄に落ちる―。 一見アンハッピーエンドに見えますが、エピローグでは、娘を失ったパルナサスがロンドンで物乞いになって身を窶(やつ)していると、ヴァレンティナが偶然に傍を通りかかり、彼は娘がアントンと幸せな結婚生活を送っていて、二人の間に女の子がいることを知ります。かつての下僕である侏儒のパーシーに、ヴァレンティナの新たな生活を邪魔しないよう諭され、声は掛けられないものの、彼は娘の幸せを知ってようやく心の平穏を得ます。博士とパーシーの二人は再び手を組み、街角のおもちゃの劇場を基に事業を始めるようで、悪魔が新しい賭けにパルナサスを誘惑しますが、パーシーがそれを制します(トニーの後日譚は無いのか? 彼の役割は何だったのか?)。
一見アンハッピーエンドに見えますが、エピローグでは、娘を失ったパルナサスがロンドンで物乞いになって身を窶(やつ)していると、ヴァレンティナが偶然に傍を通りかかり、彼は娘がアントンと幸せな結婚生活を送っていて、二人の間に女の子がいることを知ります。かつての下僕である侏儒のパーシーに、ヴァレンティナの新たな生活を邪魔しないよう諭され、声は掛けられないものの、彼は娘の幸せを知ってようやく心の平穏を得ます。博士とパーシーの二人は再び手を組み、街角のおもちゃの劇場を基に事業を始めるようで、悪魔が新しい賭けにパルナサスを誘惑しますが、パーシーがそれを制します(トニーの後日譚は無いのか? 彼の役割は何だったのか?)。
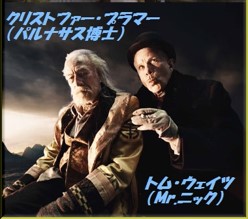 トニー役のヒース・レジャーら4人とアントン役のアメリカ合衆国生まれのイギリス人俳優アンドリュー・ガーフィールド(彼はこの作品以降の活躍が目覚ましい)は好演していますが、パルナサス博士役のカナダ人俳優クリストファー・プラマー(1929-2021/91歳没、「
トニー役のヒース・レジャーら4人とアントン役のアメリカ合衆国生まれのイギリス人俳優アンドリュー・ガーフィールド(彼はこの作品以降の活躍が目覚ましい)は好演していますが、パルナサス博士役のカナダ人俳優クリストファー・プラマー(1929-2021/91歳没、「


 「Dr.パルナサスの鏡」●原題:THE IMAGINARIUM OF DOCTOR PARNASSUS●制作年: 2009年●制作国:イギリス・カナダ●監督:テリー・ギリアム●製作:ウィリアム・ヴィンス/エイミー・ギリアム/サミュエル・ハディダ/テリー・ギリアム●脚本:テリー・ギリアム/チャールズ・マッケオン●撮影:ニコラ・ペコリーニ●音楽:マイ
「Dr.パルナサスの鏡」●原題:THE IMAGINARIUM OF DOCTOR PARNASSUS●制作年: 2009年●制作国:イギリス・カナダ●監督:テリー・ギリアム●製作:ウィリアム・ヴィンス/エイミー・ギリアム/サミュエル・ハディダ/テリー・ギリアム●脚本:テリー・ギリアム/チャールズ・マッケオン●撮影:ニコラ・ペコリーニ●音楽:マイ ケル・ダナ/ジェフ・ダナ●時間:124分●出演:ヒース・レジャー/ジョニー・デップ/ジュード・ロウ/コリン・ファレル/クリストファー・プラマー/トム・ウェイツ/リリー・コール/アンドリュー・ガーフィールド/ヴァーン・J・トロイヤー/ピーター・ストーメア●日本公開:2010/01●配給:ショウゲート●最初に観た場所:北千住・シネマブルースタジオ(22-11-15)●2回目:北千住・シネマブルースタジオ(22-11-21)((評価:★★★☆)
ケル・ダナ/ジェフ・ダナ●時間:124分●出演:ヒース・レジャー/ジョニー・デップ/ジュード・ロウ/コリン・ファレル/クリストファー・プラマー/トム・ウェイツ/リリー・コール/アンドリュー・ガーフィールド/ヴァーン・J・トロイヤー/ピーター・ストーメア●日本公開:2010/01●配給:ショウゲート●最初に観た場所:北千住・シネマブルースタジオ(22-11-15)●2回目:北千住・シネマブルースタジオ(22-11-21)((評価:★★★☆)
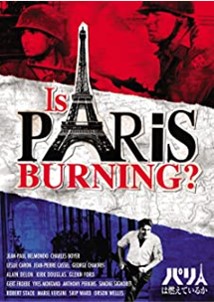
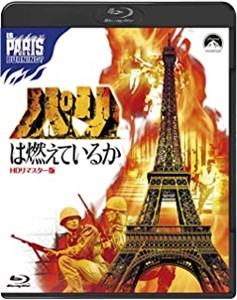
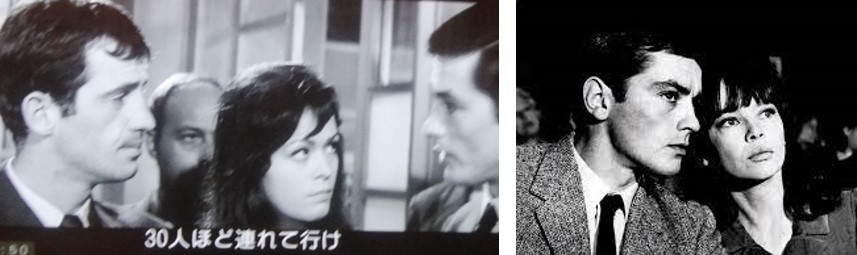
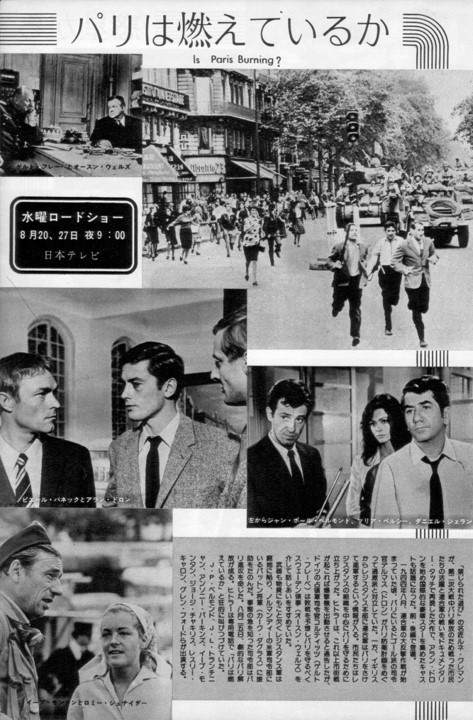 1944年8月、第2次世界大戦の連合軍の反撃作戦が始まっていた頃、フランスの装甲師団とアメリカの第4師団がパリ進撃を開始する命令を待っていた。独軍下のパリでは地下組織に潜ってレジスタンスを指導するドゴール将軍の幕僚デルマ(アラン・ドロン)と自由フランス軍=FFIの首領ロル大佐(ブリュノ・クレメール)が会見、パリ防衛について意見を闘わしていた。左翼のFFIは武器弾薬が手に入りしだい決起すると主張、ドゴール派は連合軍到着まで待つという意見だった。パリをワルシャワのように廃墟にしたくなかったからだ。一方独軍のパリ占領軍司令官コルティッツ将軍(ゲルト・フレーベ)は連合軍の進攻と同時に、パリを破壊せよという総統命令を受けていた。将軍は工作隊に命じて、工場、記念碑、橋梁、地下水道など、ありとあらゆる建造物に対して地雷を敷設させていた。このような時に、イギリス軍諜報部から"連合軍はパリを迂回して進攻する"というメッセージがレジスタンス派に届いた。ロル大佐は自力でパリを奪回しようと決意し、これを知ったデルマは、これをやめさせる人間は政治犯として独軍に捕らえられているラベしかないと考え、ラベの妻フランソワーズ(レスリー・キャロン)とスウェーデン領事ノルドリンク(オーソン・ウェルズ)を動かして、ラベ救出を図ったが失敗、結局、ドゴール派と左翼派の会議の結果、決起が決まった。ドゴール派は市の要所を占領し、
1944年8月、第2次世界大戦の連合軍の反撃作戦が始まっていた頃、フランスの装甲師団とアメリカの第4師団がパリ進撃を開始する命令を待っていた。独軍下のパリでは地下組織に潜ってレジスタンスを指導するドゴール将軍の幕僚デルマ(アラン・ドロン)と自由フランス軍=FFIの首領ロル大佐(ブリュノ・クレメール)が会見、パリ防衛について意見を闘わしていた。左翼のFFIは武器弾薬が手に入りしだい決起すると主張、ドゴール派は連合軍到着まで待つという意見だった。パリをワルシャワのように廃墟にしたくなかったからだ。一方独軍のパリ占領軍司令官コルティッツ将軍(ゲルト・フレーベ)は連合軍の進攻と同時に、パリを破壊せよという総統命令を受けていた。将軍は工作隊に命じて、工場、記念碑、橋梁、地下水道など、ありとあらゆる建造物に対して地雷を敷設させていた。このような時に、イギリス軍諜報部から"連合軍はパリを迂回して進攻する"というメッセージがレジスタンス派に届いた。ロル大佐は自力でパリを奪回しようと決意し、これを知ったデルマは、これをやめさせる人間は政治犯として独軍に捕らえられているラベしかないと考え、ラベの妻フランソワーズ(レスリー・キャロン)とスウェーデン領事ノルドリンク(オーソン・ウェルズ)を動かして、ラベ救出を図ったが失敗、結局、ドゴール派と左翼派の会議の結果、決起が決まった。ドゴール派は市の要所を占領し、 市街戦が始まった。パリ占領司令部は、独軍総司令部からパリを廃墟にせよという命令を受けていた上、市街戦が長びけば爆撃機が出動すると告げられていた。コルティッツ将軍は、すでにドイツ敗戦を予想していて、パリを破壊することは全く無用なことと思っていた。そこでノルドリンク領事を呼び、一時休戦をしてパリを爆撃から守り、その間に連合軍を呼べと遠回しに謎をかける。ノルドリンクから事情を知ったデルマは、ガロア少佐(ピエール・ヴァネック)を連合軍司令部に送った。ガロアはパリを脱出、ノルマンディの米軍司令部に到着した。パットン将軍(カーク・ダグラス)はパリ解放は米軍の任務ではないと告げ、ガロアを最前線のルクレク将軍(クロード・リッシュ)に送る。ルクレク将軍は事態の急を知ってシーバート将軍(ロバート・スタック)を動かし、ブラドリー将軍(グレン・フォード)を説いた。ブラドリーは全軍にパリ進攻を命令した。8月25日、ヒットラーの専用電話はパリにかかっていて"パリは燃えているか"と叫び続けていた―。
市街戦が始まった。パリ占領司令部は、独軍総司令部からパリを廃墟にせよという命令を受けていた上、市街戦が長びけば爆撃機が出動すると告げられていた。コルティッツ将軍は、すでにドイツ敗戦を予想していて、パリを破壊することは全く無用なことと思っていた。そこでノルドリンク領事を呼び、一時休戦をしてパリを爆撃から守り、その間に連合軍を呼べと遠回しに謎をかける。ノルドリンクから事情を知ったデルマは、ガロア少佐(ピエール・ヴァネック)を連合軍司令部に送った。ガロアはパリを脱出、ノルマンディの米軍司令部に到着した。パットン将軍(カーク・ダグラス)はパリ解放は米軍の任務ではないと告げ、ガロアを最前線のルクレク将軍(クロード・リッシュ)に送る。ルクレク将軍は事態の急を知ってシーバート将軍(ロバート・スタック)を動かし、ブラドリー将軍(グレン・フォード)を説いた。ブラドリーは全軍にパリ進攻を命令した。8月25日、ヒットラーの専用電話はパリにかかっていて"パリは燃えているか"と叫び続けていた―。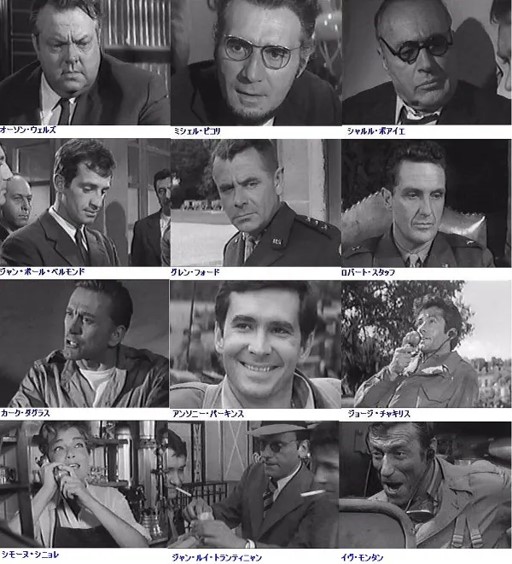 1966年の米・仏合作のオールスターキャスト戦争映画で、原作はラリー・コリンズ、ドミニク・ラピエールによるレジスタンスとパリの解放を描いたノンフィクション作品。「
1966年の米・仏合作のオールスターキャスト戦争映画で、原作はラリー・コリンズ、ドミニク・ラピエールによるレジスタンスとパリの解放を描いたノンフィクション作品。「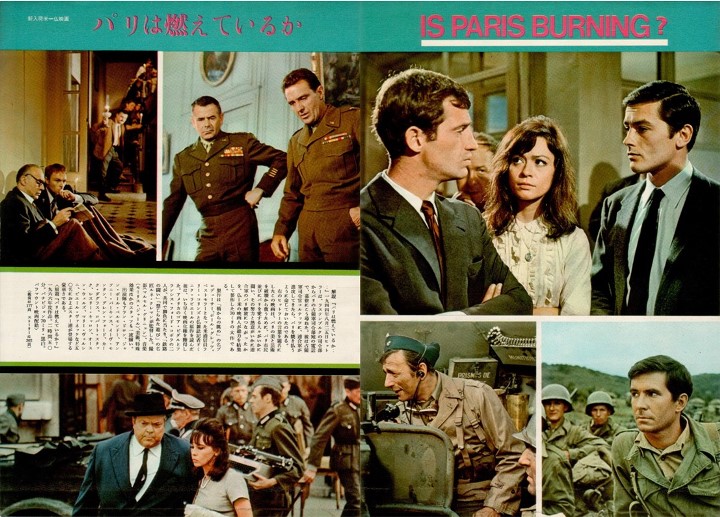
 群像劇の中で誰が主人公か敢えて言えば、ゲルト・フレーベが演じた"独軍のパリ占領軍司令官コルティッツ将軍だったかも。ヒトラーの信任が厚い人物ながら、パリの破壊と市民の人命を救うべく、ナチ親衛隊の命令を聞き流すなど面従腹背の腹芸をしたことが描かれています。ラストの方で、フランス軍の中尉が降伏要求と身柄確保に乗り込んで来るシーンがありますが、伝わるところでは、仏軍中尉は、司令官室に乗り込むと緊張のあまり「ドイツ語を話せるか」とドイツ語で叫んでしまい、それに対してコルティッツ将軍は「貴官よりいくらか上手だと思う」と余裕で答えたそうです。ただし、この逸話は映画では描かれていませんでした(代わりに、中尉が自分が敵将軍を逮捕するまでの人間になったと親に電話で報告する場面が描かれている)。
群像劇の中で誰が主人公か敢えて言えば、ゲルト・フレーベが演じた"独軍のパリ占領軍司令官コルティッツ将軍だったかも。ヒトラーの信任が厚い人物ながら、パリの破壊と市民の人命を救うべく、ナチ親衛隊の命令を聞き流すなど面従腹背の腹芸をしたことが描かれています。ラストの方で、フランス軍の中尉が降伏要求と身柄確保に乗り込んで来るシーンがありますが、伝わるところでは、仏軍中尉は、司令官室に乗り込むと緊張のあまり「ドイツ語を話せるか」とドイツ語で叫んでしまい、それに対してコルティッツ将軍は「貴官よりいくらか上手だと思う」と余裕で答えたそうです。ただし、この逸話は映画では描かれていませんでした(代わりに、中尉が自分が敵将軍を逮捕するまでの人間になったと親に電話で報告する場面が描かれている)。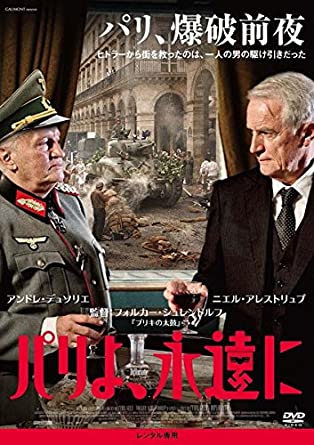
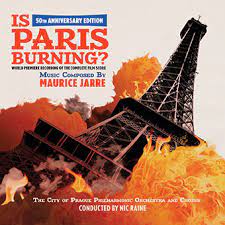
 「パリは燃えているか」●原題:PARIS BRULE-T-IL ?/IS PARIS BURNING?●制作年: 1966年●制作国:アメリカ・フランス●監督:ルネ・クレマン●製作:ポール・グレッツ●脚本:ゴア・ヴィダル/
「パリは燃えているか」●原題:PARIS BRULE-T-IL ?/IS PARIS BURNING?●制作年: 1966年●制作国:アメリカ・フランス●監督:ルネ・クレマン●製作:ポール・グレッツ●脚本:ゴア・ヴィダル/
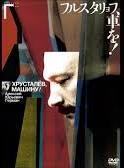


 1953年、スターリン政権下ソビエトでは不穏な空気が立ちこめていた。モスクワの大病院の脳外科医にして赤軍の将軍でもあるクレンスキー(ユーリー・アレクセーヴィチ・ツリロ)は、病院と家庭と、愛人のところを行き来する毎日を送っ
1953年、スターリン政権下ソビエトでは不穏な空気が立ちこめていた。モスクワの大病院の脳外科医にして赤軍の将軍でもあるクレンスキー(ユーリー・アレクセーヴィチ・ツリロ)は、病院と家庭と、愛人のところを行き来する毎日を送っ ている。そんな中、スターリンの指示の元
ている。そんな中、スターリンの指示の元 、KGBはユダヤ人医師の迫害計画である「医師団陰謀事件」を発動する。事態を察したクレンスキーは逃亡を試みるが、すぐに捕らえられ強制収容所に送られ拷問を受ける。しかしそこにはもう一つの陰謀が動いていた。クレンスキーは突然釈放され、山奥の別荘に連れて行かれる。そこにいたのは重い病にふせっているスターリンその人であった。すでに手遅れであることを悟ったクレンスキーは、スターリンに最後の放屁をさせる。家に戻ったクレンスキーは家族の前から姿を消す。10年後、マフィアと
、KGBはユダヤ人医師の迫害計画である「医師団陰謀事件」を発動する。事態を察したクレンスキーは逃亡を試みるが、すぐに捕らえられ強制収容所に送られ拷問を受ける。しかしそこにはもう一つの陰謀が動いていた。クレンスキーは突然釈放され、山奥の別荘に連れて行かれる。そこにいたのは重い病にふせっているスターリンその人であった。すでに手遅れであることを悟ったクレンスキーは、スターリンに最後の放屁をさせる。家に戻ったクレンスキーは家族の前から姿を消す。10年後、マフィアと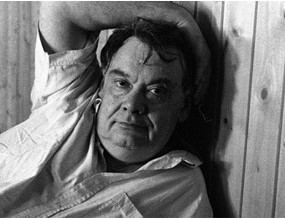 なってたくましく生き抜くクレンスキーの姿があった―。
なってたくましく生き抜くクレンスキーの姿があった―。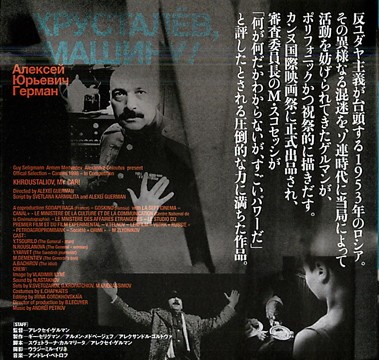
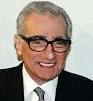 1999年のカンヌ国際映画祭正式出品作で、審査委員を務めたマーティン・スコセッシ監督が、「わけがわからないがすごい」と言ったというのも頷けます(なのに無冠で終ったのは、スコセッシ監督曰く「困ったことになにがなんだかさっぱり理解できなかったのだ。だから他の審査員を説得できなくて」とのこと)。
1999年のカンヌ国際映画祭正式出品作で、審査委員を務めたマーティン・スコセッシ監督が、「わけがわからないがすごい」と言ったというのも頷けます(なのに無冠で終ったのは、スコセッシ監督曰く「困ったことになにがなんだかさっぱり理解できなかったのだ。だから他の審査員を説得できなくて」とのこと)。 映画はこうした混沌のまま進んでいくため、時に一体今どこにいるのかさえ分からなくなります。部屋を横切ってゆく人物をカメラで背中から追いかけていく、或いはいつも移動する車の前にカメラを置くといった手法で撮影された画面が、こうした迷宮めいた空間を作り出すことに一役買っています。
映画はこうした混沌のまま進んでいくため、時に一体今どこにいるのかさえ分からなくなります。部屋を横切ってゆく人物をカメラで背中から追いかけていく、或いはいつも移動する車の前にカメラを置くといった手法で撮影された画面が、こうした迷宮めいた空間を作り出すことに一役買っています。 彼は列車の中で再び頭を殴られ、「どうして俺ばっかりこんな目に遭うんだ」とつぶやくのですが、その列車には主人公の将軍&脳外科医クレンスキーが、偶然乗り合わせていて、つるつる頭にウォッカを満たしたコップを載せ、両手に大きなスプリングを持ってバランスを崩さないでいる賭けゲームをしています。列車がやがてカーブにさしかかろうとする瞬間、「くだらねえ」というユーリーの声が聞こえてきたところで、映画は終わっています。家族で田舎にでも疎開するのかなと思ったら、解説を読んだら、今やマフィアのボスとなっていたとのこと。彼は、家族を捨ててまったく別の人生を生きることにしたのかあと、解説を読んで分かった次第です(笑)。
彼は列車の中で再び頭を殴られ、「どうして俺ばっかりこんな目に遭うんだ」とつぶやくのですが、その列車には主人公の将軍&脳外科医クレンスキーが、偶然乗り合わせていて、つるつる頭にウォッカを満たしたコップを載せ、両手に大きなスプリングを持ってバランスを崩さないでいる賭けゲームをしています。列車がやがてカーブにさしかかろうとする瞬間、「くだらねえ」というユーリーの声が聞こえてきたところで、映画は終わっています。家族で田舎にでも疎開するのかなと思ったら、解説を読んだら、今やマフィアのボスとなっていたとのこと。彼は、家族を捨ててまったく別の人生を生きることにしたのかあと、解説を読んで分かった次第です(笑)。 1953年2月の夜、あるボイラーマンが路上駐車していた車から現れた男たちによって、公園の焼却装置に閉じ込められる。男たちは黙っていないと舌を抜くぞと彼を脅すと、再び車の中に戻る。路上で人が撥ねられ、現場に居合わせた女医のマルメラードワは被害者の男を介抱する。クレンスキー少将の息子リョーシカ(ミハイル・デメンティエフ)の従姉はユダヤ人だが、父が軍に根回しをしていたおかげで、当局の追及を受け
1953年2月の夜、あるボイラーマンが路上駐車していた車から現れた男たちによって、公園の焼却装置に閉じ込められる。男たちは黙っていないと舌を抜くぞと彼を脅すと、再び車の中に戻る。路上で人が撥ねられ、現場に居合わせた女医のマルメラードワは被害者の男を介抱する。クレンスキー少将の息子リョーシカ(ミハイル・デメンティエフ)の従姉はユダヤ人だが、父が軍に根回しをしていたおかげで、当局の追及を受け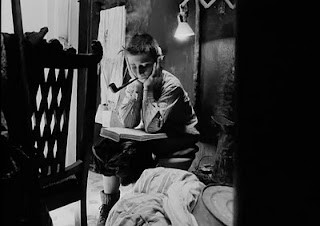 ることなく暮らすことができた。公園で遊ぶ子供たちの中に、赤旗の新聞記事のことをふれて回る少年がいた。少年のことを鬱陶しく思った者たちが少年に暴力を振るう。そこにクレンスキーが割って入り、騒動を納める。自分が院長を務める精神病院にクレンスキーが出勤すると、自分のもとに持ち込まれる様々な問題を次々に問題を片付け、クレンスキーは地下に向かう。そこには彼と同じ顔をして、自分こそが本物のクレンスキーだと訴える男がいた。クレンスキーの家ではリョーシカの成績の悪さが問題視されていた。母親(ニーナ・ルスラノヴァ)に叱られるリョーシカだが、クレンスキーは学業が駄目なら職業学校に進学すればいいと励ます。そこに、ストックホルムにいるクレンスキーの妹から言伝を預かってきたと言う男が来る。しかし、クレンスキーはストックホルムに妹などいないと男を追い出しす。男は秘密警察だった。マルメラードワと患者の男が夜道を歩いていると、車に乗ったマルメラードワの夫、ドミトリィ・カラマーゾフがやってきて、患者の男から旅券を没収するとマルメラードワを連れて行ってしまう。患者は旅券を取り戻そうとするが、返り討ちに遭う。クレンスキーの家に医者や軍人が招かれ、パーティーが催されるが、妻はまるで動物園だと悪態をつく。パーティーを抜け出したクレンスキーは真夜中の病院にやってくる。隠し通路から病院の裏口を出て、門の上で暫し物思いに耽った後、失踪したと思わせる痕跡を残して病院を後にする。そこにトラックに乗った大勢の男たちが病院に押し寄せる。クレンスキーは愛人ワルワーラの家を訪ねて泊めてくれと頼む。クレンスキーの家に秘密警察がやって来て、リョーシカは怯え、捜査員は父親が戻ってきたら電話をしろと言う。結局、クレンスキーは秘密警察に囚われ、ユダヤ人と共に強制収容所へ連行される。そこでクレンスキーは、彼のユダヤ人保護を快く思っていない同胞や、自分たちを虐げてきたロシア人のことを恨むユダヤ人から暴行を受けて苦痛に喘ぐが、秘密警察の捜査員は彼を嘲笑う。護送車両が休憩のために山中で停車していると、そこに軍の上層部の車が通りがかる。軍の上層部の男たちは秘密警察の捜査員を捕え、クレンスキーを解放する。彼は自分そっくりの男が自分に成り変わろうとしていたことを知る。軍の上層部の者たちは秘密警察が仕掛けていった彼の財産の封印を解き、彼を復職させる。復職したクレンスキーは病床に伏したある人物の診察を命じられる。クレンスキーにその人物スターリンのことを「あなたのお父上ですか」と聞かれた秘密警察長官ベリアは、最初「馬鹿な」と答えたあとで、思い直したように、「そうだ、父だ」と言い直す―。
ることなく暮らすことができた。公園で遊ぶ子供たちの中に、赤旗の新聞記事のことをふれて回る少年がいた。少年のことを鬱陶しく思った者たちが少年に暴力を振るう。そこにクレンスキーが割って入り、騒動を納める。自分が院長を務める精神病院にクレンスキーが出勤すると、自分のもとに持ち込まれる様々な問題を次々に問題を片付け、クレンスキーは地下に向かう。そこには彼と同じ顔をして、自分こそが本物のクレンスキーだと訴える男がいた。クレンスキーの家ではリョーシカの成績の悪さが問題視されていた。母親(ニーナ・ルスラノヴァ)に叱られるリョーシカだが、クレンスキーは学業が駄目なら職業学校に進学すればいいと励ます。そこに、ストックホルムにいるクレンスキーの妹から言伝を預かってきたと言う男が来る。しかし、クレンスキーはストックホルムに妹などいないと男を追い出しす。男は秘密警察だった。マルメラードワと患者の男が夜道を歩いていると、車に乗ったマルメラードワの夫、ドミトリィ・カラマーゾフがやってきて、患者の男から旅券を没収するとマルメラードワを連れて行ってしまう。患者は旅券を取り戻そうとするが、返り討ちに遭う。クレンスキーの家に医者や軍人が招かれ、パーティーが催されるが、妻はまるで動物園だと悪態をつく。パーティーを抜け出したクレンスキーは真夜中の病院にやってくる。隠し通路から病院の裏口を出て、門の上で暫し物思いに耽った後、失踪したと思わせる痕跡を残して病院を後にする。そこにトラックに乗った大勢の男たちが病院に押し寄せる。クレンスキーは愛人ワルワーラの家を訪ねて泊めてくれと頼む。クレンスキーの家に秘密警察がやって来て、リョーシカは怯え、捜査員は父親が戻ってきたら電話をしろと言う。結局、クレンスキーは秘密警察に囚われ、ユダヤ人と共に強制収容所へ連行される。そこでクレンスキーは、彼のユダヤ人保護を快く思っていない同胞や、自分たちを虐げてきたロシア人のことを恨むユダヤ人から暴行を受けて苦痛に喘ぐが、秘密警察の捜査員は彼を嘲笑う。護送車両が休憩のために山中で停車していると、そこに軍の上層部の車が通りがかる。軍の上層部の男たちは秘密警察の捜査員を捕え、クレンスキーを解放する。彼は自分そっくりの男が自分に成り変わろうとしていたことを知る。軍の上層部の者たちは秘密警察が仕掛けていった彼の財産の封印を解き、彼を復職させる。復職したクレンスキーは病床に伏したある人物の診察を命じられる。クレンスキーにその人物スターリンのことを「あなたのお父上ですか」と聞かれた秘密警察長官ベリアは、最初「馬鹿な」と答えたあとで、思い直したように、「そうだ、父だ」と言い直す―。
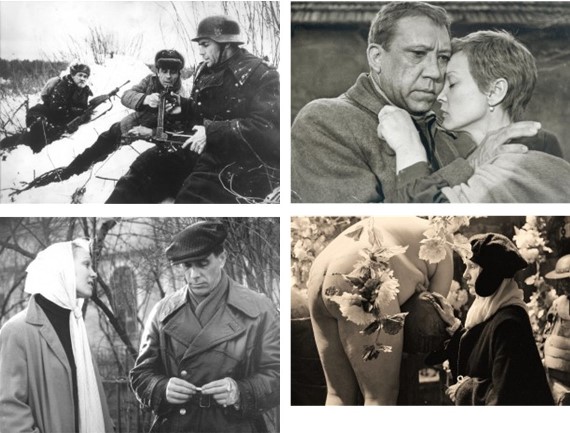
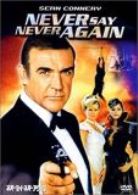

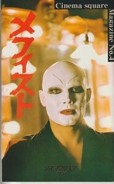
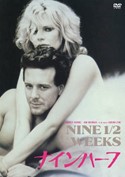
 時は冷戦最中、元英国秘密情報部MI6の諜報員ジェームズ・ボンド(ショーン・コネリー)は、スパイ活動を一時引退していが、新たな上司のM(エドワード・フォックス)から新たに命令を受ける。国際的犯罪組織"スペクター"のNo.1メンバー、マキシミリアン・ラルゴ(クラウス・マリア・ブランダウアー)が、2つの核弾頭を強奪したのだ。これは、スペクターの首領で、No.2のブロフェルド(マックス・フォン・シドー)の新
時は冷戦最中、元英国秘密情報部MI6の諜報員ジェームズ・ボンド(ショーン・コネリー)は、スパイ活動を一時引退していが、新たな上司のM(エドワード・フォックス)から新たに命令を受ける。国際的犯罪組織"スペクター"のNo.1メンバー、マキシミリアン・ラルゴ(クラウス・マリア・ブランダウアー)が、2つの核弾頭を強奪したのだ。これは、スペクターの首領で、No.2のブロフェルド(マックス・フォン・シドー)の新 たな作戦「アラーの涙」の一環だった。核弾頭を取り戻す命令を受けたボンドは、ラルゴを追ってバハマへ向かうことに。バハマに到着したボンドは、ラルゴの部下で殺し屋ファティマ(バーバラ・カレラ)に殺されそうになる。しかし、2度の暗殺の危機を切り抜けて、なんとか生き残る。さらに、ニースのカジノでドミノ(キム・ベイシンガー)という女性に出会ったボンドは、ドミノの兄ジャック(ギャヴァン・オハーリー)が、核弾頭を手に入れるためにラルゴに殺されたことを明かす。その後、ミサイルの一つがワシントンの大統領のもとにあると知ったボンドは本部に通報、引き続きもう一つのミサイルの行方を追うが―。
たな作戦「アラーの涙」の一環だった。核弾頭を取り戻す命令を受けたボンドは、ラルゴを追ってバハマへ向かうことに。バハマに到着したボンドは、ラルゴの部下で殺し屋ファティマ(バーバラ・カレラ)に殺されそうになる。しかし、2度の暗殺の危機を切り抜けて、なんとか生き残る。さらに、ニースのカジノでドミノ(キム・ベイシンガー)という女性に出会ったボンドは、ドミノの兄ジャック(ギャヴァン・オハーリー)が、核弾頭を手に入れるためにラルゴに殺されたことを明かす。その後、ミサイルの一つがワシントンの大統領のもとにあると知ったボンドは本部に通報、引き続きもう一つのミサイルの行方を追うが―。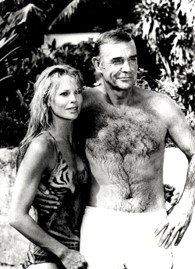
 1983年公開のアーヴィン・カーシュナー監督作で、ジェームズ・ボンドの映画の制作会社イーオン・プロダクションズとは別の会社の制作であるため。007シリーズとしては番外編になります。初代ジェームズ・ボンドを演じたショーン・コネリー(1930 - 2020/90歳没)が「007 ダイヤモンドは永遠に」('71年/英・米)から12年ぶりの復活、7回目にして最後のボンド役を演じました(原題の意味は「ボンド、やめるなんて言わないで」ということらしい)。内容は1965年に公開された4作目「007 サンダーボール作戦」のリメイクですが、使用権の問題のためか、いつものシリーズとオープニングが違ったり(ガンバレル(銃口)のシークエンスが無い)、音楽が
1983年公開のアーヴィン・カーシュナー監督作で、ジェームズ・ボンドの映画の制作会社イーオン・プロダクションズとは別の会社の制作であるため。007シリーズとしては番外編になります。初代ジェームズ・ボンドを演じたショーン・コネリー(1930 - 2020/90歳没)が「007 ダイヤモンドは永遠に」('71年/英・米)から12年ぶりの復活、7回目にして最後のボンド役を演じました(原題の意味は「ボンド、やめるなんて言わないで」ということらしい)。内容は1965年に公開された4作目「007 サンダーボール作戦」のリメイクですが、使用権の問題のためか、いつものシリーズとオープニングが違ったり(ガンバレル(銃口)のシークエンスが無い)、音楽が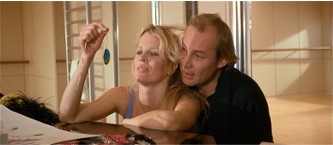
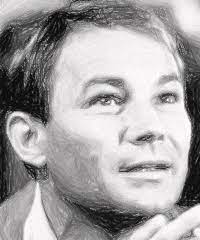 敵のラルゴ役のクラウス・マリア・ブランダウアーは、主演作であるイシュトバーン・サボー監督の「メフィスト」('81年/西独・ハンガリー)を新宿のシネマスクウェア東急で'82年に観ました。ナチス政権下で権力に翻弄される実在した「ファウスト」の名優グリュントゲンスをモデルにしたクラウス
敵のラルゴ役のクラウス・マリア・ブランダウアーは、主演作であるイシュトバーン・サボー監督の「メフィスト」('81年/西独・ハンガリー)を新宿のシネマスクウェア東急で'82年に観ました。ナチス政権下で権力に翻弄される実在した「ファウスト」の名優グリュントゲンスをモデルにしたクラウス ・マンの小説の映画化作品(第34回カンヌ国際映画祭「脚本賞」受賞作)でしたが、そうした芸術色の強い映画(個人的評価は★★★☆)に出ていた俳優が、まさかその後すぐジェームズ・ボンド映画に出るとは思ってもみませんでした(言語も違ったし)。ただし、この作品では、彼、クラウス・マリア・ブランダウアーとショーン・コネリーとの心理戦的演技が、当時の典型的なボンド映画よりも感情に訴えかけるものがあると評価されて好評を博し、映画の商業的な成功にも繋がっています。クラウス・マリア・ブランダウアーはその後も活躍を続け、シドニー・ポラック監督の「
・マンの小説の映画化作品(第34回カンヌ国際映画祭「脚本賞」受賞作)でしたが、そうした芸術色の強い映画(個人的評価は★★★☆)に出ていた俳優が、まさかその後すぐジェームズ・ボンド映画に出るとは思ってもみませんでした(言語も違ったし)。ただし、この作品では、彼、クラウス・マリア・ブランダウアーとショーン・コネリーとの心理戦的演技が、当時の典型的なボンド映画よりも感情に訴えかけるものがあると評価されて好評を博し、映画の商業的な成功にも繋がっています。クラウス・マリア・ブランダウアーはその後も活躍を続け、シドニー・ポラック監督の「
 スペクターの首領ブロフェルドにマックス・フォン・シドー(1929 - 2020/90歳没)で、ドナルド・プレザンス(「
スペクターの首領ブロフェルドにマックス・フォン・シドー(1929 - 2020/90歳没)で、ドナルド・プレザンス(「 サバラス(「女王陛下の007」)('69年))、チャールズ・グレイ(「ダイヤモンドは永遠に」('71年))に続いての配役。マックス・フォンシドーも「
サバラス(「女王陛下の007」)('69年))、チャールズ・グレイ(「ダイヤモンドは永遠に」('71年))に続いての配役。マックス・フォンシドーも「 教の王と対峙する善の王オズリック王の役でしたが、スティーヴン・スピルバーグ監督、トム・クルーズ主演の「
教の王と対峙する善の王オズリック王の役でしたが、スティーヴン・スピルバーグ監督、トム・クルーズ主演の「
 ボンドガールの一人は、スペクターの女殺し屋(スペクターNo.12)ファティマを演じたバーバラ・カレラ(1951年生まれ)。ファティマは最後までボンドを追い回して危機に落とし入れる
ボンドガールの一人は、スペクターの女殺し屋(スペクターNo.12)ファティマを演じたバーバラ・カレラ(1951年生まれ)。ファティマは最後までボンドを追い回して危機に落とし入れる も、Q(アレック・マッコーエン)が開発した万年筆型ロケットで爆殺されます。ボンドを追いつめた際に、自分が最高の女だったとボンドに書き付けを要求す
も、Q(アレック・マッコーエン)が開発した万年筆型ロケットで爆殺されます。ボンドを追いつめた際に、自分が最高の女だったとボンドに書き付けを要求す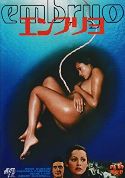
 るシーンが見せ場でしたが、結局それが仇となった(笑)。バーバラ・カレラはこの「ネバーセイ・ネバーアゲイン」の出演が一番のキャリアとされていますが、「エンブリヨ」('76年)、「ドクター・モローの島」('77年)といった作品の彼女に思い入れがある人もいるかと思います。
るシーンが見せ場でしたが、結局それが仇となった(笑)。バーバラ・カレラはこの「ネバーセイ・ネバーアゲイン」の出演が一番のキャリアとされていますが、「エンブリヨ」('76年)、「ドクター・モローの島」('77年)といった作品の彼女に思い入れがある人もいるかと思います。
 もう一人は、ラルゴの愛人でどうやらラルゴに殺害されたジャックの妹ドミノを演じたキム・ベイシンガー(1953年生まれ)で、こちらは敵側からボンド側に寝返る(これはシリーズのいつものお約束通り)言わ
もう一人は、ラルゴの愛人でどうやらラルゴに殺害されたジャックの妹ドミノを演じたキム・ベイシンガー(1953年生まれ)で、こちらは敵側からボンド側に寝返る(これはシリーズのいつものお約束通り)言わ
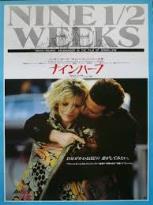
 個人的には「ナインハーフ」はイマイチだったかも。原題は「9週間半」。監督は「フラッシュダンス」('83年)のエイドリアン・ラインで、相変わらず映像には凝っていて、哲学的な語り口を装っていますが、本質はエンターテイメントではなかったかなあ(キム・ベイシンガーのボディにばかり目が行く。この頃のミッキー・ロークってなぜか好きになれない)。
個人的には「ナインハーフ」はイマイチだったかも。原題は「9週間半」。監督は「フラッシュダンス」('83年)のエイドリアン・ラインで、相変わらず映像には凝っていて、哲学的な語り口を装っていますが、本質はエンターテイメントではなかったかなあ(キム・ベイシンガーのボディにばかり目が行く。この頃のミッキー・ロークってなぜか好きになれない)。
 キム・ベイシンガーはその25年後、ギジェルモ・アリアガ監督の「
キム・ベイシンガーはその25年後、ギジェルモ・アリアガ監督の「 そう言えばキム・ベイシンガーは、アカデミー賞の授賞式でのプレゼンターとして舞台に立った際に(その年の作品賞は「
そう言えばキム・ベイシンガーは、アカデミー賞の授賞式でのプレゼンターとして舞台に立った際に(その年の作品賞は「
 この「ネバーセイ・ネバーアゲイン」では、これら準主役級のほかに、Mの役が「
この「ネバーセイ・ネバーアゲイン」では、これら準主役級のほかに、Mの役が「

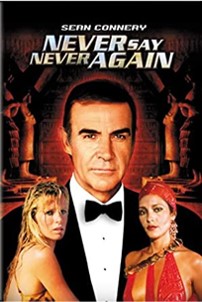
 「ネバーセイ・ネバーアゲイン」●原題:NEVER SAY NEVER AGAIN●制作年:1983年●制作国:アメリカ・イギリス●監督:アーヴィン・カーシュナー●製作:ジャック・シュワルツマン●脚本:ロレンツォ・センプル・ジュニア●撮影:ダグラス・スローカム●音楽:ミシェル・ルグラン●原作:イアン・フレミング●時間:134分●出演:ショーン・コネリー/クラウス・マリア・ブランダウアー/マックス・フォン・シドー/バーバラ・カレラ/キム・ベイシンガー/バーニー・ケイシー/アレック・マッコーエン/エドワード・フォックス/ギャヴァン・オハーリー/ローワン・アトキンソン/ロナルド・ピックアップ/ヴァレリー・レオン/ミロス・キレク/パット・ローチ/アンソニー・シャープ/プルネラ・ジー●日本公開:1983/12●配給:松竹富士=ヘラルド●最初に観た場
「ネバーセイ・ネバーアゲイン」●原題:NEVER SAY NEVER AGAIN●制作年:1983年●制作国:アメリカ・イギリス●監督:アーヴィン・カーシュナー●製作:ジャック・シュワルツマン●脚本:ロレンツォ・センプル・ジュニア●撮影:ダグラス・スローカム●音楽:ミシェル・ルグラン●原作:イアン・フレミング●時間:134分●出演:ショーン・コネリー/クラウス・マリア・ブランダウアー/マックス・フォン・シドー/バーバラ・カレラ/キム・ベイシンガー/バーニー・ケイシー/アレック・マッコーエン/エドワード・フォックス/ギャヴァン・オハーリー/ローワン・アトキンソン/ロナルド・ピックアップ/ヴァレリー・レオン/ミロス・キレク/パット・ローチ/アンソニー・シャープ/プルネラ・ジー●日本公開:1983/12●配給:松竹富士=ヘラルド●最初に観た場


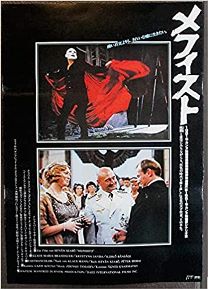
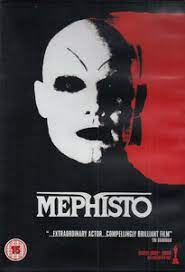 「メフィスト」●原題:MEPHISTO●制作年:1981年●制作国:西独・ハンガリー●監督:イシュトバン・サボー●脚本:イシュトバン・サボー/ペーテル・ドバイ●撮影:ラホス・コルタイ●音楽:ゼンコ・タルナシ●原作:クラウス・マン●
「メフィスト」●原題:MEPHISTO●制作年:1981年●制作国:西独・ハンガリー●監督:イシュトバン・サボー●脚本:イシュトバン・サボー/ペーテル・ドバイ●撮影:ラホス・コルタイ●音楽:ゼンコ・タルナシ●原作:クラウス・マン●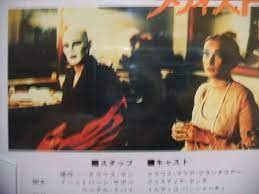 時間:145 分●出演:クラウス・マリア・ブランダウアー/クリスティナ・ヤンダ/イルディコ・バンシャーギィ/カーリン・ボイド/ロルフ・ホッペ/ペーター・アンドライ/クリスティーネ・ハルボルト●日本公開:1982/04●配給:大映インターナショナル●最初に観た場所:新宿・シネマスクウェア東急(82-05-01)(評価:★★★☆)
時間:145 分●出演:クラウス・マリア・ブランダウアー/クリスティナ・ヤンダ/イルディコ・バンシャーギィ/カーリン・ボイド/ロルフ・ホッペ/ペーター・アンドライ/クリスティーネ・ハルボルト●日本公開:1982/04●配給:大映インターナショナル●最初に観た場所:新宿・シネマスクウェア東急(82-05-01)(評価:★★★☆)
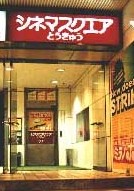

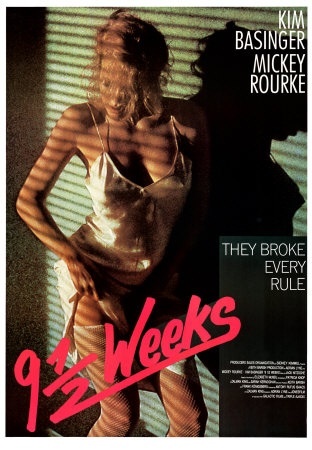
 「ナインハーフ」●原題:NINE 1/2 WEEKS●制作年:1985年●制作国:アメリカ●監督:エイドリアン・ライン●製作:アンソニー・ルーファス・アイザック/キース・バリッシュ●脚本:パトリシア・ノップ/ザルマン・キング●撮影:ピーター・ビジウ●音楽:ジャック・ニッチェ●原作:エリザベス・マクニール●時間:117分●出演:ミッキー・ロー/キム・ベイシンガー/マーガレット・ホイットンン/ドワイト・ワイスト/クリスティーン・バランスキー/カレン・ヤング/ロン・ウッド●日本公開:1986/04●配給:日本ヘラルド(評価:★★★)
「ナインハーフ」●原題:NINE 1/2 WEEKS●制作年:1985年●制作国:アメリカ●監督:エイドリアン・ライン●製作:アンソニー・ルーファス・アイザック/キース・バリッシュ●脚本:パトリシア・ノップ/ザルマン・キング●撮影:ピーター・ビジウ●音楽:ジャック・ニッチェ●原作:エリザベス・マクニール●時間:117分●出演:ミッキー・ロー/キム・ベイシンガー/マーガレット・ホイットンン/ドワイト・ワイスト/クリスティーン・バランスキー/カレン・ヤング/ロン・ウッド●日本公開:1986/04●配給:日本ヘラルド(評価:★★★)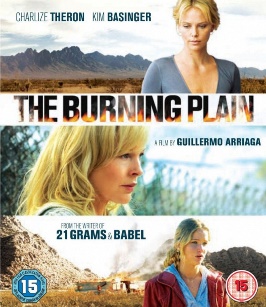
 「あの日、欲望の大地で」●原題:THE BURNING PLAIN●制作年:2008年●制作国:アメリカ●監督・脚本:ギジェルモ・アリアガ●製作:ウォルター・パークス/ローリー・マクドナルド●撮影:ロバート・エルスウィット●音楽:ハンス・ジマー/オマール・ロドリゲス=ロペス●時間:106分●出演:シャーリーズ・セロン/キム・ベイシンガー/ジェニファー・ローレンス/ホセ・マリア・ヤスピク/ジョン・コーベット/ダニー・ピノ/テッサ・イア/ジョアキム・デ・アルメイダ/J・D・パルド/ブレット・カレン●日本公開:2009/09●配給:東北新社●最初に観た場所:北千住・シネマブルースタジオ(18-09-07)(評価:★★★★)
「あの日、欲望の大地で」●原題:THE BURNING PLAIN●制作年:2008年●制作国:アメリカ●監督・脚本:ギジェルモ・アリアガ●製作:ウォルター・パークス/ローリー・マクドナルド●撮影:ロバート・エルスウィット●音楽:ハンス・ジマー/オマール・ロドリゲス=ロペス●時間:106分●出演:シャーリーズ・セロン/キム・ベイシンガー/ジェニファー・ローレンス/ホセ・マリア・ヤスピク/ジョン・コーベット/ダニー・ピノ/テッサ・イア/ジョアキム・デ・アルメイダ/J・D・パルド/ブレット・カレン●日本公開:2009/09●配給:東北新社●最初に観た場所:北千住・シネマブルースタジオ(18-09-07)(評価:★★★★)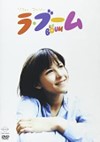
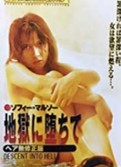

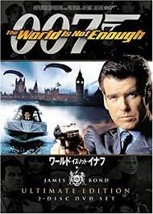

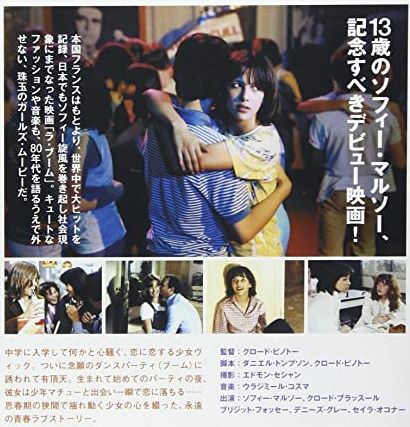
 「ブーム」とはパーティーのこと。ブームに誘われることを夢見る13歳のヴィック(ソフィー・マルソー)が、自分の14歳の誕生日ブームを開くまでの物語。リセの新学期(夏のバカンス明け)に始まり、歯科医の父親(クロード・ブラッスール)とイラストレーターである母親(ブリジッド・フォッセー)の別居騒動、ハープ奏者の曾祖母プペット(ドゥニーズ・グレイ)の折々の助言を背景に、ブームで出会ったマチュー(アレクサンドル・スターリング)との恋模様、春休み明けに自身が開く誕生日ブームまでを描く。
「ブーム」とはパーティーのこと。ブームに誘われることを夢見る13歳のヴィック(ソフィー・マルソー)が、自分の14歳の誕生日ブームを開くまでの物語。リセの新学期(夏のバカンス明け)に始まり、歯科医の父親(クロード・ブラッスール)とイラストレーターである母親(ブリジッド・フォッセー)の別居騒動、ハープ奏者の曾祖母プペット(ドゥニーズ・グレイ)の折々の助言を背景に、ブームで出会ったマチュー(アレクサンドル・スターリング)との恋模様、春休み明けに自身が開く誕生日ブームまでを描く。
 「ラ・ブーム」('80年/仏)はクロード・ピノトー(1925-2012/87歳没)監督によるフランス映画で、個人的にはこの映画で「
「ラ・ブーム」('80年/仏)はクロード・ピノトー(1925-2012/87歳没)監督によるフランス映画で、個人的にはこの映画で「 (1966年生まれ)のデビュー作であり(日本で言えば"中一"だが高校生くらいに見えたりもする)、ブリジッド・フォッセーはソフィー・マルソー演じる思春期の娘をも持つ母親役。個人的にはどうってことない映画でしたが、ヨーロッパ各国や日本を含むアジアでヒット作となりました。
(1966年生まれ)のデビュー作であり(日本で言えば"中一"だが高校生くらいに見えたりもする)、ブリジッド・フォッセーはソフィー・マルソー演じる思春期の娘をも持つ母親役。個人的にはどうってことない映画でしたが、ヨーロッパ各国や日本を含むアジアでヒット作となりました。 娘の恋愛だけでなく、親夫婦の倦怠期とそこからの脱脚を
娘の恋愛だけでなく、親夫婦の倦怠期とそこからの脱脚を も描いているところがフランス映画らしく、改めて観ると、フランス的文化・恋愛価値観が垣間見られた作品だったように思います。映画パーソナリティの襟川クロ(1950年生まれ)氏が「おもちゃ箱的青春ムービー。(中略)ごく普通の少女達が、普通の恋をして、またひとつ大人になるのでありました、とりまく大人は大人でイロイロあり、ひとつ年をとりましたとさ。といった、よくあるパターンではありますが、しかし、その味つけがなかなかのもの」と評価したほか、映画評論
も描いているところがフランス映画らしく、改めて観ると、フランス的文化・恋愛価値観が垣間見られた作品だったように思います。映画パーソナリティの襟川クロ(1950年生まれ)氏が「おもちゃ箱的青春ムービー。(中略)ごく普通の少女達が、普通の恋をして、またひとつ大人になるのでありました、とりまく大人は大人でイロイロあり、ひとつ年をとりましたとさ。といった、よくあるパターンではありますが、しかし、その味つけがなかなかのもの」と評価したほか、映画評論 家の
家の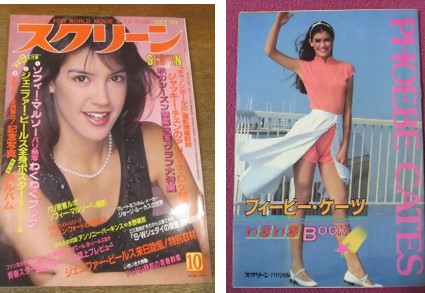 この映画は高田馬場パール座で観て、併映がフィービー・ケイツ(1963年生まれ)の19歳の時の
この映画は高田馬場パール座で観て、併映がフィービー・ケイツ(1963年生まれ)の19歳の時の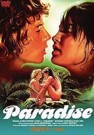 デビュー作である「パラダイス」('82年/米)(公開時のタイトルは「フィービー・ケイツのパラダイス」)でしたが、こちらは当時のメモを見ると「フィービー・ケイツのアイドル映画。中身がない」(評価★☆)とだけありました(笑)。フィービー・ケイツとソフィー・マルソーは当時、米仏2大アイドルだったのかもしれません。米国にはあと1人、二人
デビュー作である「パラダイス」('82年/米)(公開時のタイトルは「フィービー・ケイツのパラダイス」)でしたが、こちらは当時のメモを見ると「フィービー・ケイツのアイドル映画。中身がない」(評価★☆)とだけありました(笑)。フィービー・ケイツとソフィー・マルソーは当時、米仏2大アイドルだったのかもしれません。米国にはあと1人、二人 と同年代のブルック・シールズ(1963年生まれ)がいましたが、ルイ・マル監督の「プリティ・ベイビー」('78年/米)も観ました(これも高田馬場パール座で、併映はダイアン・レイン主演の「リトル・ロマンス」('79年/米))。ニューオリンズの娼館が舞台のこの作品に、ルイ・マル監督が渡米して自ら発掘した彼女を起用したもので、ブルック・シールズは11歳で娼婦(12歳)を演じてセンセーションを巻き起こしましたが、ルイ・マル作品としてはイマイチだったかも(評価★★★)。フィービー・ケイツについては「
と同年代のブルック・シールズ(1963年生まれ)がいましたが、ルイ・マル監督の「プリティ・ベイビー」('78年/米)も観ました(これも高田馬場パール座で、併映はダイアン・レイン主演の「リトル・ロマンス」('79年/米))。ニューオリンズの娼館が舞台のこの作品に、ルイ・マル監督が渡米して自ら発掘した彼女を起用したもので、ブルック・シールズは11歳で娼婦(12歳)を演じてセンセーションを巻き起こしましたが、ルイ・マル作品としてはイマイチだったかも(評価★★★)。フィービー・ケイツについては「 結構、アイドル映画を観ていたのだなあと今になって思います。「プリティ・ベイビー」はブルック・シールズのアイドル映画ではありませんが(彼女の出たアイドル映画と言えば17歳の時の「青い珊瑚礁」('80年/米)あたりか)、彼女を一気にアイドルに押し上げた映画でしょう。フィービー・ケイツとソフィー・マルソーを比べると、米国型アイドルとフランス型アイドルとではやはり違うなあと思わされます(映画雑誌「スクリーン」だと、ソフィー・マルソーが表紙向きで、フィービー・ケイツがグラビア向きと言ったところか)。フランス人監督のルイ・マルが見出したブルック・シールズはどちらか。天皇徳仁(今上天皇)が皇太子時代、日本人では柏原芳恵、外国人ではブルック・シールズの熱烈なファンであったとされていましたが、プリンストン大学を首席で卒業するような才女でした。
結構、アイドル映画を観ていたのだなあと今になって思います。「プリティ・ベイビー」はブルック・シールズのアイドル映画ではありませんが(彼女の出たアイドル映画と言えば17歳の時の「青い珊瑚礁」('80年/米)あたりか)、彼女を一気にアイドルに押し上げた映画でしょう。フィービー・ケイツとソフィー・マルソーを比べると、米国型アイドルとフランス型アイドルとではやはり違うなあと思わされます(映画雑誌「スクリーン」だと、ソフィー・マルソーが表紙向きで、フィービー・ケイツがグラビア向きと言ったところか)。フランス人監督のルイ・マルが見出したブルック・シールズはどちらか。天皇徳仁(今上天皇)が皇太子時代、日本人では柏原芳恵、外国人ではブルック・シールズの熱烈なファンであったとされていましたが、プリンストン大学を首席で卒業するような才女でした。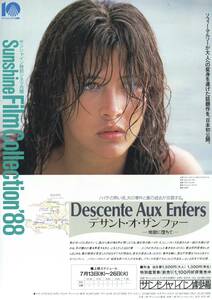
 「ラ・ブーム」で父親と娘の役だったクロード・ブラッスールとソフィー・マルソーが、この作品の6年後、フランシス・ジロー監督の「デサント・オ・ザンファー 地獄に堕ちて」('86年/仏)では年齢の離れた夫と妻を演じましたが、これも夫婦の危機を打開しようとする話で、ただし、結構どろっとした話になっています。滞在先のリゾートホテルで殺人事件が起きる犯罪ミステリ仕様ですが、やや猟奇的側面も(原作は『狼は天使の匂い』『ピアニストを撃て』『華麗なる大泥棒』のデイビッド・グーディス)。さらには、「ラ・ブーム」の父親役と裸で激しいラブシーンを演じたりしていることもあり、そうした映画を企画する側も企画する側だが、「みんな父娘相姦みたいな目で私たちを見たがってるのよね」と自分でも承知していながら、こうした作品に簡単に出演してしまうソフィー・マルソーもソフィー・マルソーだとの批判と言うか苦言もあったようです。やはり、「ラ・ブーム」のソフィー・マルソーのイメージを壊されたくないファンがいるのだろうなあ(タイトルが何のことだかよく分からないのが難。ビデオタイトルは「地獄に墜ちて」)。
「ラ・ブーム」で父親と娘の役だったクロード・ブラッスールとソフィー・マルソーが、この作品の6年後、フランシス・ジロー監督の「デサント・オ・ザンファー 地獄に堕ちて」('86年/仏)では年齢の離れた夫と妻を演じましたが、これも夫婦の危機を打開しようとする話で、ただし、結構どろっとした話になっています。滞在先のリゾートホテルで殺人事件が起きる犯罪ミステリ仕様ですが、やや猟奇的側面も(原作は『狼は天使の匂い』『ピアニストを撃て』『華麗なる大泥棒』のデイビッド・グーディス)。さらには、「ラ・ブーム」の父親役と裸で激しいラブシーンを演じたりしていることもあり、そうした映画を企画する側も企画する側だが、「みんな父娘相姦みたいな目で私たちを見たがってるのよね」と自分でも承知していながら、こうした作品に簡単に出演してしまうソフィー・マルソーもソフィー・マルソーだとの批判と言うか苦言もあったようです。やはり、「ラ・ブーム」のソフィー・マルソーのイメージを壊されたくないファンがいるのだろうなあ(タイトルが何のことだかよく分からないのが難。ビデオタイトルは「地獄に墜ちて」)。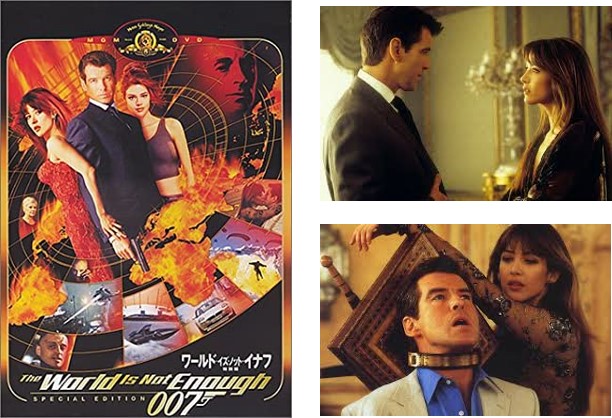 さらにその13年後、ソフィー・マルソーはマイケル・アプテッド監督の007シリーズシリーズ第19作「007 ワールド・イズ・ノット・イナフ」('99年/英)(公開時タイトルは「ワールド・イズ・ノット・イナフ」)でボンドガールとなり、当時で32歳ぐらいでしょうか、役どころは、ピアース・ブロスナン演じるジェームズ・ボンドを翻弄する悪役エレクトラ・キングで、結構ボンドと微妙な関係になりながらも、やがて本性を現しサディスティックにボンドを苛め倒していましたが(やや変態性欲気味)、詰まるところ悪役なのでやはり最期は...。彼女は、1996年に、半自伝的小説『うそをつく女』を刊行し、作品は「女性のアイデンティティの探求」と評され、フランスでは大きくとりあげられたとのことですが、こうした有名人女優がボンドガールになるのは当時としては珍しかったのではないでしょうか。その後、2002年に、長編映画監督としてのデビュー作「聞かせてよ、愛の言葉を」('01年)でモントリオール世界映画祭の最優秀監督賞を受賞するなどの活躍を遂げています。
さらにその13年後、ソフィー・マルソーはマイケル・アプテッド監督の007シリーズシリーズ第19作「007 ワールド・イズ・ノット・イナフ」('99年/英)(公開時タイトルは「ワールド・イズ・ノット・イナフ」)でボンドガールとなり、当時で32歳ぐらいでしょうか、役どころは、ピアース・ブロスナン演じるジェームズ・ボンドを翻弄する悪役エレクトラ・キングで、結構ボンドと微妙な関係になりながらも、やがて本性を現しサディスティックにボンドを苛め倒していましたが(やや変態性欲気味)、詰まるところ悪役なのでやはり最期は...。彼女は、1996年に、半自伝的小説『うそをつく女』を刊行し、作品は「女性のアイデンティティの探求」と評され、フランスでは大きくとりあげられたとのことですが、こうした有名人女優がボンドガールになるのは当時としては珍しかったのではないでしょうか。その後、2002年に、長編映画監督としてのデビュー作「聞かせてよ、愛の言葉を」('01年)でモントリオール世界映画祭の最優秀監督賞を受賞するなどの活躍を遂げています。
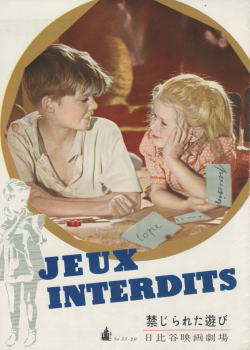 「禁じられた遊び」●原題:JEUX INTERDITS●制作年:1952年●制作国:フランス●監督:ルネ・クレマン●脚本:ジャン・オーランシュ/ピエール・ポスト●撮影:ロバート・ジュリアート●音楽:ナルシソ・イエペス●原作:フランソワ・ボワイエ●時間:86分●出演:ブリジッド・フォッセー/ジョルジュ・プージュリー/スザンヌ・クールタル/リュシアン・ユベール/ロランヌ・バディー/ジャック・マラン●日本公開:1953/09●配給:東和●最初に観た場所:早稲田松竹 (79-03-06)●2回目:高田馬場・ACTミニシアター (83-09-15)(評価:★★★★☆)●併映(1回目):「鉄道員」(ピエトロ・ジェルミ)●併映(2回目):「居酒屋」(ルネ・クレマン)
「禁じられた遊び」●原題:JEUX INTERDITS●制作年:1952年●制作国:フランス●監督:ルネ・クレマン●脚本:ジャン・オーランシュ/ピエール・ポスト●撮影:ロバート・ジュリアート●音楽:ナルシソ・イエペス●原作:フランソワ・ボワイエ●時間:86分●出演:ブリジッド・フォッセー/ジョルジュ・プージュリー/スザンヌ・クールタル/リュシアン・ユベール/ロランヌ・バディー/ジャック・マラン●日本公開:1953/09●配給:東和●最初に観た場所:早稲田松竹 (79-03-06)●2回目:高田馬場・ACTミニシアター (83-09-15)(評価:★★★★☆)●併映(1回目):「鉄道員」(ピエトロ・ジェルミ)●併映(2回目):「居酒屋」(ルネ・クレマン)
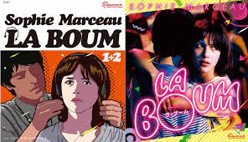
 「ラ・ブーム」●原題:LA BOUM●制作年:1980年●制作国:フランス●監督:クロード・ピノトー●製作:アラン・ポワレ●脚本:ダニエル・トンプソン/クロード・ピノトー●撮影:エドモン・セシャン●音楽:ウラジミール・コスマ(主題歌:「愛のファンタジー」歌:リチャード・サンダーソン)●時間:110分●出演:クロード・ブラッスール/ブリジッド・フォッセー/ソフィー・マルソー/ドゥニーズ・グレイ/ アレクサンドル・スターリング/ ベルナール・ジラルドー/シェイラ・オコナー/アレクサンドラ・ゴナン/ジーン=フィリップ・レオナール/リシャール・ボーランジェ/ウラジミール・コスマ●日本公開:1982/03●配給:松竹=富士映画●最初に観た場所:高田馬場パール座(82-09-15)(評価:★★★☆)●併映:「フィービー・ケイツのパラダイス」(スチュワート・ジラード)
「ラ・ブーム」●原題:LA BOUM●制作年:1980年●制作国:フランス●監督:クロード・ピノトー●製作:アラン・ポワレ●脚本:ダニエル・トンプソン/クロード・ピノトー●撮影:エドモン・セシャン●音楽:ウラジミール・コスマ(主題歌:「愛のファンタジー」歌:リチャード・サンダーソン)●時間:110分●出演:クロード・ブラッスール/ブリジッド・フォッセー/ソフィー・マルソー/ドゥニーズ・グレイ/ アレクサンドル・スターリング/ ベルナール・ジラルドー/シェイラ・オコナー/アレクサンドラ・ゴナン/ジーン=フィリップ・レオナール/リシャール・ボーランジェ/ウラジミール・コスマ●日本公開:1982/03●配給:松竹=富士映画●最初に観た場所:高田馬場パール座(82-09-15)(評価:★★★☆)●併映:「フィービー・ケイツのパラダイス」(スチュワート・ジラード)
 「パラダイス」●原題:PARADISE●制作年:1982年●制作国:カナダ●監督・脚本:スチュアート・ギラード●製作:ロバート・ラントス/スティーブン・J・ロス●撮影:アダム・グリーンバーグ●音楽:ポール・ホファート●時間:95分●出演:フィービー・ケイツ/ウィリー・エイムス/リチャード・カーノック/チュヴィア・タヴィ/ニール・ヴィポンド●日本公開:1982/06●配給:松竹富士(評価:★☆)●併映:「ラ・ブーム」(クロード・ピノトー)
「パラダイス」●原題:PARADISE●制作年:1982年●制作国:カナダ●監督・脚本:スチュアート・ギラード●製作:ロバート・ラントス/スティーブン・J・ロス●撮影:アダム・グリーンバーグ●音楽:ポール・ホファート●時間:95分●出演:フィービー・ケイツ/ウィリー・エイムス/リチャード・カーノック/チュヴィア・タヴィ/ニール・ヴィポンド●日本公開:1982/06●配給:松竹富士(評価:★☆)●併映:「ラ・ブーム」(クロード・ピノトー)
 「プリティ・ベビー」●原題:PRETTY BABY●制作年:1978年●制作国:アメリカ●監督・製作:ルイ・マル●脚本:ポリー・プラット●撮影:スヴェン・ニクヴィスト●音楽:ジェリー・ウェクスラー●時間:110分●出演:ブルック・シールズ/E.J.ベロッ/キース・キャラダイン/スーザン・サランドン/アントニオ・ファーガス/マシュー・アントン/ダイアナ・スカーウィッド/バーバラ・スティール/ドン・フッド●日本公開:1978/10●配給:パラマウント●最初に観た場所:高田馬場パール座(80-01-16)(評価:★★★)●併映:「リトル・ロマンス」(ジョージ・ロイ・ヒル)
「プリティ・ベビー」●原題:PRETTY BABY●制作年:1978年●制作国:アメリカ●監督・製作:ルイ・マル●脚本:ポリー・プラット●撮影:スヴェン・ニクヴィスト●音楽:ジェリー・ウェクスラー●時間:110分●出演:ブルック・シールズ/E.J.ベロッ/キース・キャラダイン/スーザン・サランドン/アントニオ・ファーガス/マシュー・アントン/ダイアナ・スカーウィッド/バーバラ・スティール/ドン・フッド●日本公開:1978/10●配給:パラマウント●最初に観た場所:高田馬場パール座(80-01-16)(評価:★★★)●併映:「リトル・ロマンス」(ジョージ・ロイ・ヒル)
 「デサント・オ・ザンファー 地獄に墜ちて」●原題:DESCENTE AUX ENFERS●制作年:1986年●制作国:フランス●監督:フランシス・ジロー●製作:アリエル・ゼイトゥン●脚本:フランシス・ジロー/ジャン=ルー・ダバディ●撮影:シャルリー・ヴァン・ダム●音楽:ジョルジュ・ドルリュー●原作:デイビッド・グーディス●時間:88分●出演:ソフィー・マルソー/クロード・ブラッスール /ベッツィ・ブ
「デサント・オ・ザンファー 地獄に墜ちて」●原題:DESCENTE AUX ENFERS●制作年:1986年●制作国:フランス●監督:フランシス・ジロー●製作:アリエル・ゼイトゥン●脚本:フランシス・ジロー/ジャン=ルー・ダバディ●撮影:シャルリー・ヴァン・ダム●音楽:ジョルジュ・ドルリュー●原作:デイビッド・グーディス●時間:88分●出演:ソフィー・マルソー/クロード・ブラッスール /ベッツィ・ブ

 「007 ワールド・イズ・ノット・イナフ」●原題:THE WORLD IS NOT ENOUGH●制作年:1999年●制作国:イギリス・アメリカ●監督:マイケル・アプテッド●製作:マイケル・G・ウィルソン/バーバラ・ブロッコリ●脚本:ニール・パーヴィス/ロバート・ウェイド●撮影:エイドリアン・ビドル●音楽:デヴィッド・アーノルド(主題歌:「The World is Not Enough」ガービッジ)●原作:イアン・フレミング●時間:127分●出演:ピアース・ブロスナン/ソフィー・マルソー/ロバート・カーライル/デニス・リチャーズ/ロビー・コルトレーン/デスモンド・リュウェリン/マリア・グラツィア・クチノッタ/サマンサ・ボンド/マイケル・キッチン/コリン・サーモン/セレナ・スコット・トーマス/ウルリク・トムセン/ゴールディ/ジョン・セル/クロード=オリビエ・ルドルフ/ジュディ・デンチ●日本公開:2000/02●配給:UIP(評価:★★★☆)
「007 ワールド・イズ・ノット・イナフ」●原題:THE WORLD IS NOT ENOUGH●制作年:1999年●制作国:イギリス・アメリカ●監督:マイケル・アプテッド●製作:マイケル・G・ウィルソン/バーバラ・ブロッコリ●脚本:ニール・パーヴィス/ロバート・ウェイド●撮影:エイドリアン・ビドル●音楽:デヴィッド・アーノルド(主題歌:「The World is Not Enough」ガービッジ)●原作:イアン・フレミング●時間:127分●出演:ピアース・ブロスナン/ソフィー・マルソー/ロバート・カーライル/デニス・リチャーズ/ロビー・コルトレーン/デスモンド・リュウェリン/マリア・グラツィア・クチノッタ/サマンサ・ボンド/マイケル・キッチン/コリン・サーモン/セレナ・スコット・トーマス/ウルリク・トムセン/ゴールディ/ジョン・セル/クロード=オリビエ・ルドルフ/ジュディ・デンチ●日本公開:2000/02●配給:UIP(評価:★★★☆)
 作:エリッ
作:エリッ ク・アルトメイヤー/ニコラス・アルトメイヤー●撮影:イシャーム・アラウィエ●音楽:ニコラス・コンタン●原作:エマニュエル・ベルンエイム●時間:113分●出演:ソフィー・マルソー
ク・アルトメイヤー/ニコラス・アルトメイヤー●撮影:イシャーム・アラウィエ●音楽:ニコラス・コンタン●原作:エマニュエル・ベルンエイム●時間:113分●出演:ソフィー・マルソー /アンドレ・デュソリエ/ジェラルディーヌ・ペラス/シャーロット・ランプリング/エリック・カラヴァカ/ハンナ・シグラ/グレゴリー・ガドゥボワ/ジャック・ノロ/ジュディット・マーレ/ダニエル・メズギッシュ/ナタリー・リシャール●日本公開:2023/02●配給:キノフィルムズ●最初に観た場所:ヒューマントラストシネマ有楽町(シアター2)(23-02-17)(評価:★★★★)
/アンドレ・デュソリエ/ジェラルディーヌ・ペラス/シャーロット・ランプリング/エリック・カラヴァカ/ハンナ・シグラ/グレゴリー・ガドゥボワ/ジャック・ノロ/ジュディット・マーレ/ダニエル・メズギッシュ/ナタリー・リシャール●日本公開:2023/02●配給:キノフィルムズ●最初に観た場所:ヒューマントラストシネマ有楽町(シアター2)(23-02-17)(評価:★★★★)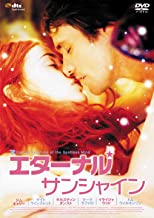


 バレンタイン目前のある日、ジョエル(ジム・キャリー)は、最近ケンカ別れした恋人のクレメンタイン(ケイト・ウィンスレット)が、自分との記憶を全部消してしまったという不思議な手紙を受け取る。ショックを受けたジョエルは、自らもクレメンタインとの波乱に満ちた日々を忘れようと、記憶除去を専門とするラクーナ医院の門を叩く。ハワード・ミュージワック博士(トム・ウィルキンソン)が開発したその手術法は
バレンタイン目前のある日、ジョエル(ジム・キャリー)は、最近ケンカ別れした恋人のクレメンタイン(ケイト・ウィンスレット)が、自分との記憶を全部消してしまったという不思議な手紙を受け取る。ショックを受けたジョエルは、自らもクレメンタインとの波乱に満ちた日々を忘れようと、記憶除去を専門とするラクーナ医院の門を叩く。ハワード・ミュージワック博士(トム・ウィルキンソン)が開発したその手術法は 、一晩寝ている間に、脳の中の特定の記憶だけを消去できるというもの。さっそく施術を受けるジョエル。技師のパトリック(イライジャ・ウッド)、スタン(マーク・ラファロ)、メアリー(キルスティン・ダンス
、一晩寝ている間に、脳の中の特定の記憶だけを消去できるというもの。さっそく施術を受けるジョエル。技師のパトリック(イライジャ・ウッド)、スタン(マーク・ラファロ)、メアリー(キルスティン・ダンス ト)が記憶を消していく間、無意識のジョエルは、クレメンタインと過ごした日々を逆回転で体験する。しかしやがて、ジョエルは忘れたくない素敵な時間の存在に気づき、手術を止めたいと思うようになるが、そのまま手術は終わる。そして朝。家を出たジョエルは、衝動的に仕事をさぼって海辺へと向かい、そこでクレメンタインと出会う。二人は互いに惹かれ合うが、彼らのもとに、消された記憶について二人がそれぞれ語っているテープが届く。自分と博士との不倫の記憶を消されたと知ったメアリーが、彼らに送ったのだ。テープから聞こえてくるお互いの悪口。しかし二人は、それでも改めて恋に落ちるのだった―。
ト)が記憶を消していく間、無意識のジョエルは、クレメンタインと過ごした日々を逆回転で体験する。しかしやがて、ジョエルは忘れたくない素敵な時間の存在に気づき、手術を止めたいと思うようになるが、そのまま手術は終わる。そして朝。家を出たジョエルは、衝動的に仕事をさぼって海辺へと向かい、そこでクレメンタインと出会う。二人は互いに惹かれ合うが、彼らのもとに、消された記憶について二人がそれぞれ語っているテープが届く。自分と博士との不倫の記憶を消されたと知ったメアリーが、彼らに送ったのだ。テープから聞こえてくるお互いの悪口。しかし二人は、それでも改めて恋に落ちるのだった―。
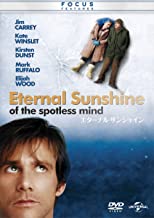 2004年公開のミシェル・ゴンドリー監督作で、アカデミー賞脚本賞、放送映画批評家協会賞作品賞などを受賞していますが、確かに脚本が巧みでした。「記憶除去」を扱った映画SFでもあり、サターン賞の最高賞である「SF映画賞」も受賞していますが、SFチックな部分はわざとキッチュに作っている感じで、やはり、サターン賞も含め、評価されたのは脚本の面白さだったのではないでしょうか(映像も、金をかけないなりに撮り方に凝っていた)。
2004年公開のミシェル・ゴンドリー監督作で、アカデミー賞脚本賞、放送映画批評家協会賞作品賞などを受賞していますが、確かに脚本が巧みでした。「記憶除去」を扱った映画SFでもあり、サターン賞の最高賞である「SF映画賞」も受賞していますが、SFチックな部分はわざとキッチュに作っている感じで、やはり、サターン賞も含め、評価されたのは脚本の面白さだったのではないでしょうか(映像も、金をかけないなりに撮り方に凝っていた)。 冒頭にジム・キャリー演じるジョエルとケイト・ウィンスレット演じるクレメンタインの列車での出会いの場面があります。朝、家を出て職場に向かおうとしたジョエルは、衝動的に仕事をさぼってロングアイランドの果て「モントーク」の海辺へと向かい、そこでクレメンタインと出会う―クレメンタインがかなり積極的にジョエルにアプローチしていて、ちょっとエキセントリックですらありましたが、これ全部、伏線があったのだなあ。思えば、映画の構成自体が、推理小説で言うところの"叙述トリック"と言うか、観客に対する一つのトリックみたいになって、そのことに気づいたのは観始めてかなり経ってからでした。
冒頭にジム・キャリー演じるジョエルとケイト・ウィンスレット演じるクレメンタインの列車での出会いの場面があります。朝、家を出て職場に向かおうとしたジョエルは、衝動的に仕事をさぼってロングアイランドの果て「モントーク」の海辺へと向かい、そこでクレメンタインと出会う―クレメンタインがかなり積極的にジョエルにアプローチしていて、ちょっとエキセントリックですらありましたが、これ全部、伏線があったのだなあ。思えば、映画の構成自体が、推理小説で言うところの"叙述トリック"と言うか、観客に対する一つのトリックみたいになって、そのことに気づいたのは観始めてかなり経ってからでした。 二度目の二人の出会いのシーンが出てきて、「えっ、何これ」という感じになりましたが、それこそがこの映画の画期的にユニークな点だったわけです。要するに、観ている観客がいつの間にか主人公と同じ"記憶喪失"状態を体験していたということです(「何、言っているか分からない」って、分からない方が幸せ。実際に映画を観て味わって欲しい)。コレ、この方法が使えるのはこの作品1回きりだろなあという気がします。誰かが後から真似ようと思っても、この映画から「盗んだ」という捉え方しかされないのではないでしょうか。
二度目の二人の出会いのシーンが出てきて、「えっ、何これ」という感じになりましたが、それこそがこの映画の画期的にユニークな点だったわけです。要するに、観ている観客がいつの間にか主人公と同じ"記憶喪失"状態を体験していたということです(「何、言っているか分からない」って、分からない方が幸せ。実際に映画を観て味わって欲しい)。コレ、この方法が使えるのはこの作品1回きりだろなあという気がします。誰かが後から真似ようと思っても、この映画から「盗んだ」という捉え方しかされないのではないでしょうか。 ラブ・ストーリーとしても良く出来ていますが、ジム・キャリー演じるジョエルとケイト・ウィンスレット演じるクレメンタインでは、後者の方が完全に"キャラ立ち"しており、ケイト・ウィンスレットはこの作品で、ロンドン映画批評家協会賞「英国主演女優賞」、放送映画批評家協会賞「主演女優賞」などを受賞しています(アカデミー「主演女優賞」、ゴールデングローブ賞「主演女優賞(ドラマ部門)」にもノミネート)。彼女は2年後の「
ラブ・ストーリーとしても良く出来ていますが、ジム・キャリー演じるジョエルとケイト・ウィンスレット演じるクレメンタインでは、後者の方が完全に"キャラ立ち"しており、ケイト・ウィンスレットはこの作品で、ロンドン映画批評家協会賞「英国主演女優賞」、放送映画批評家協会賞「主演女優賞」などを受賞しています(アカデミー「主演女優賞」、ゴールデングローブ賞「主演女優賞(ドラマ部門)」にもノミネート)。彼女は2年後の「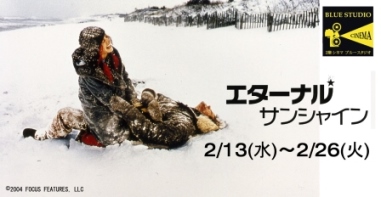 「エターナル・サンシャイン」●原題:ETERNAL SUNSHINE OF THE SPOTLESS MIND●制作年:2004年●制作国:アメリカ●監督:ミシェル・ゴンドリー●製作:スティーヴ・ゴリン/アンソニー・ブレグマン●脚本:チャーリ
「エターナル・サンシャイン」●原題:ETERNAL SUNSHINE OF THE SPOTLESS MIND●制作年:2004年●制作国:アメリカ●監督:ミシェル・ゴンドリー●製作:スティーヴ・ゴリン/アンソニー・ブレグマン●脚本:チャーリ
 ー・カウフマン●撮影:エレン・クラス●音楽:ジョン・ブライオン●時間:107分●出演:ジム・キャリー/ケイト・ウィンスレット/イライジャ・ウッド/キルスティン・ダンスト/マーク・ラファロ/トム・ウィルキンソン/デヴィッド・クロス●日本公開:2005/03●配給:ギャガ=ヒューマックス●最初に観た場所:北千住・シネマブルースタジオ(19-02-26)(評価:★★★★)
ー・カウフマン●撮影:エレン・クラス●音楽:ジョン・ブライオン●時間:107分●出演:ジム・キャリー/ケイト・ウィンスレット/イライジャ・ウッド/キルスティン・ダンスト/マーク・ラファロ/トム・ウィルキンソン/デヴィッド・クロス●日本公開:2005/03●配給:ギャガ=ヒューマックス●最初に観た場所:北千住・シネマブルースタジオ(19-02-26)(評価:★★★★)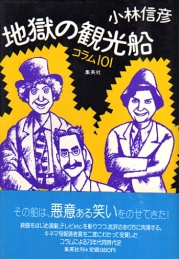
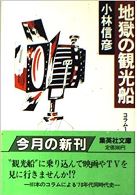
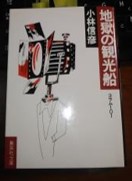
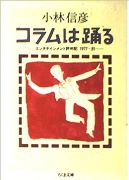
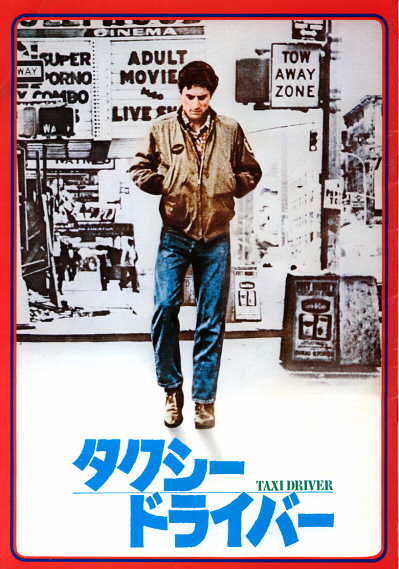
 #2.「
#2.「
 #9.「
#9.「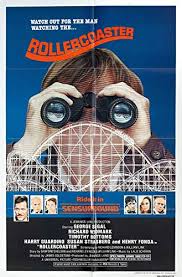
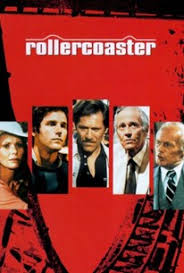 #16.「ジェット・ローラー・コースター」は集団捜査劇めかしているが、保安基準局役人のジョージ・シーガルと爆発狂のティモシイ・ボトムズの対決であるとしています(53p)。この点においては「真昼の決闘」や「ジャッカルの日」などと同系譜で、特徴的なのは、敵味方がモノマニアックである点だと。なるほど。アメリカ人は大体「個対組織」より「個対個」の対決が好きなのかも。著者はこの映画のジョージ・シーガルの演技を絶賛しています。個人的には、パニック映画としては懐かしい作品ですが、「
#16.「ジェット・ローラー・コースター」は集団捜査劇めかしているが、保安基準局役人のジョージ・シーガルと爆発狂のティモシイ・ボトムズの対決であるとしています(53p)。この点においては「真昼の決闘」や「ジャッカルの日」などと同系譜で、特徴的なのは、敵味方がモノマニアックである点だと。なるほど。アメリカ人は大体「個対組織」より「個対個」の対決が好きなのかも。著者はこの映画のジョージ・シーガルの演技を絶賛しています。個人的には、パニック映画としては懐かしい作品ですが、「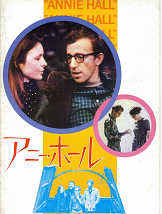
 #24.「
#24.「 #32.「
#32.「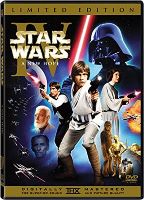
 #32.「スター・ウォーズ」で、「二つのロボットが砂漠をとぼとぼ行く場面で、こんなシーンを観たことがあったな、と思った。黒澤明の「
#32.「スター・ウォーズ」で、「二つのロボットが砂漠をとぼとぼ行く場面で、こんなシーンを観たことがあったな、と思った。黒澤明の「 囲気出ていた。ルーク役は奥田瑛二!)。悪くはないけれど、十分満足したかと言うとイマイチだったというのが当時の印象で(評価★★★☆)、前年公開の「
囲気出ていた。ルーク役は奥田瑛二!)。悪くはないけれど、十分満足したかと言うとイマイチだったというのが当時の印象で(評価★★★☆)、前年公開の「
 「引き裂かれたカーテン」('66年)を、著者は、作品は失敗だったけれど、ヒッチコック好みの俳優を使ったという意味では、この作品のポール・ニューマンがそうだとしているのに対し、和田誠は、この作品を好きだとし、ポール・ニューマンには「逆転」('63年)などのようにスリラーが似合うと言っています(143p)(「
「引き裂かれたカーテン」('66年)を、著者は、作品は失敗だったけれど、ヒッチコック好みの俳優を使ったという意味では、この作品のポール・ニューマンがそうだとしているのに対し、和田誠は、この作品を好きだとし、ポール・ニューマンには「逆転」('63年)などのようにスリラーが似合うと言っています(143p)(「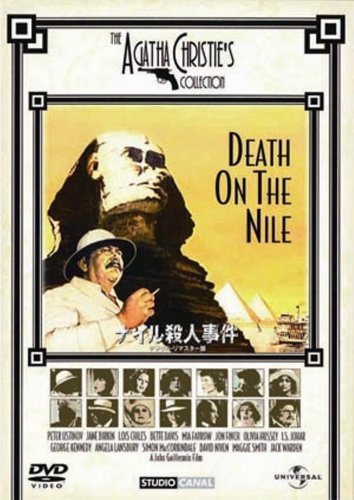
 #49.「
#49.「
 #52.「
#52.「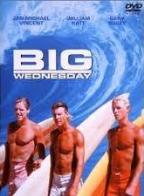
 #53.「
#53.「 #55.「
#55.「 日記風の話も多くなり、この様式も「週刊文春」の連載のエッセイ「本音を申せば」に受け継がれている)。二日目から色川武大氏が加わったというからスゴイ面子。それにしても「エノケンの頑張り戦術」を「博覧強記の色川さんが、題名さえも知らなかった」とは意外。そう言う著者も、「頑張り戦術」は知らなかったとのこと。按摩に化けたエノケンが如月寛多を「もみくちゃ」にし、取っ組み合いになるところを、カメラ据えっぱなしのワンショットで撮っているいるところが飛びぬけて面白かったとしていますが、「エノケンの近藤勇」にもそうした撮り方をしている場面があります。
日記風の話も多くなり、この様式も「週刊文春」の連載のエッセイ「本音を申せば」に受け継がれている)。二日目から色川武大氏が加わったというからスゴイ面子。それにしても「エノケンの頑張り戦術」を「博覧強記の色川さんが、題名さえも知らなかった」とは意外。そう言う著者も、「頑張り戦術」は知らなかったとのこと。按摩に化けたエノケンが如月寛多を「もみくちゃ」にし、取っ組み合いになるところを、カメラ据えっぱなしのワンショットで撮っているいるところが飛びぬけて面白かったとしていますが、「エノケンの近藤勇」にもそうした撮り方をしている場面があります。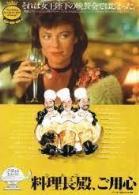
 #58.「
#58.「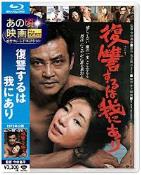
 #61.「
#61.「
 #62.「
#62.「
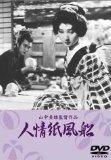 #63.「
#63.「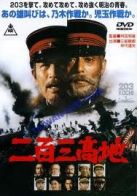 #90.「
#90.「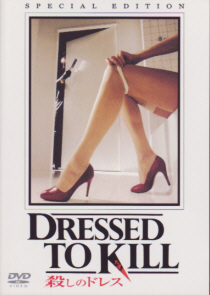
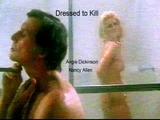

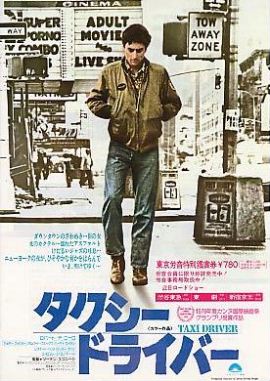 「タクシードライバー」●原題:TAXI DRIVER●制作年:1976年●制作国:アメリカ●監督:マーティン・スコセッシ●製作:マイケル・フィリップス/ジュリア・フィリップス●脚本:ポール・シュレイダー●撮影:マイケル・チャップマン●音楽:バーナード・ハーマン●時間:114分●出演:ロバート・デ・ニーロ/シビル・シェパード/ジョディ・フォスター/ハーヴェイ・カイテル/ピーター・ボイル/アルバート・ブルックス/マーティン・スコセッシ/ジョー・スピネル/ダイアン・アボット/レナード・ハリス/ヴィクター・アルゴ/ガース・エイヴァリー/リチャード・ヒッグス/ロバート・マルコフ、/ハリー・ノーサップ/スティーブン・
「タクシードライバー」●原題:TAXI DRIVER●制作年:1976年●制作国:アメリカ●監督:マーティン・スコセッシ●製作:マイケル・フィリップス/ジュリア・フィリップス●脚本:ポール・シュレイダー●撮影:マイケル・チャップマン●音楽:バーナード・ハーマン●時間:114分●出演:ロバート・デ・ニーロ/シビル・シェパード/ジョディ・フォスター/ハーヴェイ・カイテル/ピーター・ボイル/アルバート・ブルックス/マーティン・スコセッシ/ジョー・スピネル/ダイアン・アボット/レナード・ハリス/ヴィクター・アルゴ/ガース・エイヴァリー/リチャード・ヒッグス/ロバート・マルコフ、/ハリー・ノーサップ/スティーブン・ プリンス●日本公開:1976/09●配給:コロムビア映画●最初に観た場所:早稲田松竹(77-11-05)●2回目:池袋文芸坐(79-02-11)●3回目:三鷹オスカー(81-03-18)●4回目:早稲田松竹(85-03-23)(評価:★★★★★)●併映(1回目):「アメリカングラフィティ」(ジョージ・ルーカス)●併映(2回目):「ローリング・サンダー」(ジョン・フリン)●併映(3回目):「アリスの恋」(マーティン・スコセッシ)/「ミーン・ストリート」(マーティン・スコセッシ)●併映(4回目):「ミッドナイト・エクスプレス」(アラン・パーカー)
プリンス●日本公開:1976/09●配給:コロムビア映画●最初に観た場所:早稲田松竹(77-11-05)●2回目:池袋文芸坐(79-02-11)●3回目:三鷹オスカー(81-03-18)●4回目:早稲田松竹(85-03-23)(評価:★★★★★)●併映(1回目):「アメリカングラフィティ」(ジョージ・ルーカス)●併映(2回目):「ローリング・サンダー」(ジョン・フリン)●併映(3回目):「アリスの恋」(マーティン・スコセッシ)/「ミーン・ストリート」(マーティン・スコセッシ)●併映(4回目):「ミッドナイト・エクスプレス」(アラン・パーカー)
![ネットワーク [DVD].jpg](http://hurec.bz/book-movie/%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%20%5BDVD%5D.jpg)
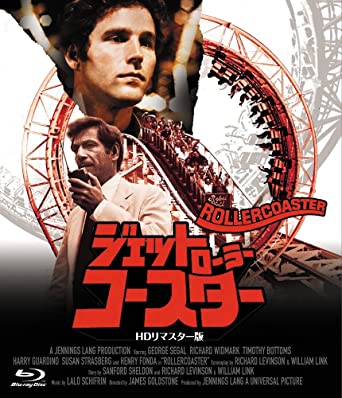
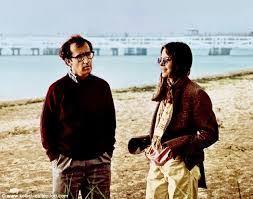 「アニー・ホール」●原題:ANNIE HALL●制作年:1977年●制作国:アメリカ●監督:ウディ・アレン●製作:チャールズ・ジョフィ/ジャック・ローリンズ●脚本:ウディ・アレン/マーシャル・ブリックマン●撮影:ゴードン・ウィリス ●時間:94分●出演:ウディ・アレン/ダイアン・キートン/トニー・ロバーツ/シェリー・デュバル/ポール・サイモン/シガニー・ウィーバー/クリストファー・ウォーケン/ジェフ・ゴールドブラム/ジョン・グローヴァー/トルーマン・カポーティ(ノンクレジット)●日本公開:1978/01●配給:オライオン映画●最初に観た場所:有楽町・ニュー東宝シネマ2(78-01-18)●2回目:有楽町・ニュー東宝シネマ2 (78-01-18)(評価:★★★★)
「アニー・ホール」●原題:ANNIE HALL●制作年:1977年●制作国:アメリカ●監督:ウディ・アレン●製作:チャールズ・ジョフィ/ジャック・ローリンズ●脚本:ウディ・アレン/マーシャル・ブリックマン●撮影:ゴードン・ウィリス ●時間:94分●出演:ウディ・アレン/ダイアン・キートン/トニー・ロバーツ/シェリー・デュバル/ポール・サイモン/シガニー・ウィーバー/クリストファー・ウォーケン/ジェフ・ゴールドブラム/ジョン・グローヴァー/トルーマン・カポーティ(ノンクレジット)●日本公開:1978/01●配給:オライオン映画●最初に観た場所:有楽町・ニュー東宝シネマ2(78-01-18)●2回目:有楽町・ニュー東宝シネマ2 (78-01-18)(評価:★★★★)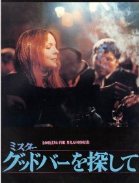
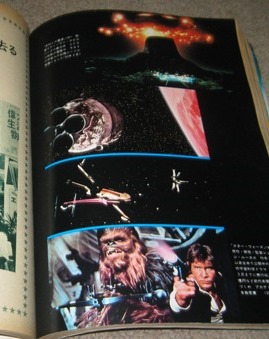
 「スター・ウォーズ(「スター・ウォーズ エピソード4/新たなる希望」)」●原題:THE STAR WARS●制作年:1977年●制作国:アメリカ●監督・脚本:ジョージ・ルーカス●製作: ゲイリー・カーツ●撮影:ギルバート・テイラー●音楽:ジョン・ウィリアムズ●時間:121分(特別編:125分)●出演:マーク・ハミル/ハリソン・フォード/キャリー・フィッシャー/デヴィッド・プラウズ/ジェームズ・アール・ジョーンズ(声)/アレック・ギネス/アンソニー・ダニエルズ/ケニー・ベイカー/ピーター・メイヒュー/ピーター・カッシング/フィル・ブラウン/シラー・フレイザー/ジェレミー・ブロック/ポール・ブレイク/ローリー・グード/アンソニー・フォレスト/ドリュー・ヘンレイ/アンガス・マッキネ/デニス・ローソン/ギャリック・ヘイゴン/ローリー・グード/パム・ローズ/リチャード・ルパルメンティエ/デレック・ライオンズ●日本公開:1978/06●配給:20世紀フォックス映画●最初に観た場所:飯田橋・佳作座(82-07-11)(評価:★★★☆)●併映:「レイダース 失われた《聖櫃》」(スティーブン・スピルバーグ)
「スター・ウォーズ(「スター・ウォーズ エピソード4/新たなる希望」)」●原題:THE STAR WARS●制作年:1977年●制作国:アメリカ●監督・脚本:ジョージ・ルーカス●製作: ゲイリー・カーツ●撮影:ギルバート・テイラー●音楽:ジョン・ウィリアムズ●時間:121分(特別編:125分)●出演:マーク・ハミル/ハリソン・フォード/キャリー・フィッシャー/デヴィッド・プラウズ/ジェームズ・アール・ジョーンズ(声)/アレック・ギネス/アンソニー・ダニエルズ/ケニー・ベイカー/ピーター・メイヒュー/ピーター・カッシング/フィル・ブラウン/シラー・フレイザー/ジェレミー・ブロック/ポール・ブレイク/ローリー・グード/アンソニー・フォレスト/ドリュー・ヘンレイ/アンガス・マッキネ/デニス・ローソン/ギャリック・ヘイゴン/ローリー・グード/パム・ローズ/リチャード・ルパルメンティエ/デレック・ライオンズ●日本公開:1978/06●配給:20世紀フォックス映画●最初に観た場所:飯田橋・佳作座(82-07-11)(評価:★★★☆)●併映:「レイダース 失われた《聖櫃》」(スティーブン・スピルバーグ)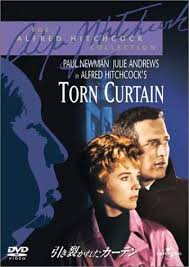
 「引き裂かれたカーテン」●原題:TORN CURTAIN●制作年:1966年●制作国:アメリカ●監督・製作:アルフレッド・ヒッチコック●ジェニングス・ラング●脚本:ブライアン・ムーア/ウィリス・ホール/キース・ウォーターハウス●撮影:ジョン・F・ウォーレン●音楽:ジョン・アディソン●時間:128分●出演:ポール・ニューマン /ジュリー・アンドリュース/ハンスイェルク・フェルミー/ギュンター・シュトラック/ルドウィヒ・ドナート/ヴォルフガン
「引き裂かれたカーテン」●原題:TORN CURTAIN●制作年:1966年●制作国:アメリカ●監督・製作:アルフレッド・ヒッチコック●ジェニングス・ラング●脚本:ブライアン・ムーア/ウィリス・ホール/キース・ウォーターハウス●撮影:ジョン・F・ウォーレン●音楽:ジョン・アディソン●時間:128分●出演:ポール・ニューマン /ジュリー・アンドリュース/ハンスイェルク・フェルミー/ギュンター・シュトラック/ルドウィヒ・ドナート/ヴォルフガン グ・キーリング/リラ・ケドロヴ/モート・ミルズ/ギゼラ・フィッシャー/デヴィッド・オパトッシュ/タマラ・トゥマノワ/モーリス・ドナー/ロバート・ブーン/ノーバート・シラー/ハロルド・ディレンフォース/アーサー・グールド=ポーター/ピーター・ローレ・Jr/アンドレア・ダルビー/エリック・ホランド/レスター・フレッチャー●日本公開:1966/10●配給:ユニバーサル・ピクチャーズ.(評価:★★★★)
グ・キーリング/リラ・ケドロヴ/モート・ミルズ/ギゼラ・フィッシャー/デヴィッド・オパトッシュ/タマラ・トゥマノワ/モーリス・ドナー/ロバート・ブーン/ノーバート・シラー/ハロルド・ディレンフォース/アーサー・グールド=ポーター/ピーター・ローレ・Jr/アンドレア・ダルビー/エリック・ホランド/レスター・フレッチャー●日本公開:1966/10●配給:ユニバーサル・ピクチャーズ.(評価:★★★★)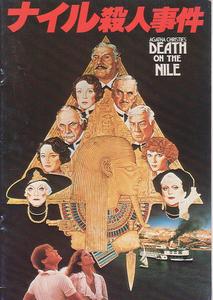


 「ナイル殺人事件」●原題:DEATH ON THE NILE●制作年:1978年●制作国:イギリス●監督:ジョン・ギラーミン●製作:ジョン・ブラボーン/リチャード・グッドウィン●脚本:アンソニー・シェーファー●撮影:ジャック・カーディフ●音楽:ニーノ・ロータ●原作:アガサ・クリスティ「ナイルに死す」●時間:140分●出演:ピーター・ユスティノフ/ミア・ファロー/ベティ・デイヴィス/アンジェラ・ランズベリー/ジョージ・ケネ
「ナイル殺人事件」●原題:DEATH ON THE NILE●制作年:1978年●制作国:イギリス●監督:ジョン・ギラーミン●製作:ジョン・ブラボーン/リチャード・グッドウィン●脚本:アンソニー・シェーファー●撮影:ジャック・カーディフ●音楽:ニーノ・ロータ●原作:アガサ・クリスティ「ナイルに死す」●時間:140分●出演:ピーター・ユスティノフ/ミア・ファロー/ベティ・デイヴィス/アンジェラ・ランズベリー/ジョージ・ケネ ディ/オリヴィア・ハッセー/ジョン・フィンチ/マギー・スミス/デヴィッド・ニーヴ
ディ/オリヴィア・ハッセー/ジョン・フィンチ/マギー・スミス/デヴィッド・ニーヴ ン/ジャック・ウォーデン/ロイス・チャイルズ/サイモン・マッコーキンデール/ジェーン・バーキン/サム・ワナメイカー/ハリー・アンドリュース●日本公開:1978/12●配給:東宝東和●最初に観た場所:日比谷映画劇場(78-12-17)(評価:★★★☆)
ン/ジャック・ウォーデン/ロイス・チャイルズ/サイモン・マッコーキンデール/ジェーン・バーキン/サム・ワナメイカー/ハリー・アンドリュース●日本公開:1978/12●配給:東宝東和●最初に観た場所:日比谷映画劇場(78-12-17)(評価:★★★☆) 「麦秋」●制作年:1953年●監督:小津安二郎●製作:山本武●脚本:野田高梧/小津安二郎●撮影:厚田
「麦秋」●制作年:1953年●監督:小津安二郎●製作:山本武●脚本:野田高梧/小津安二郎●撮影:厚田 雄春●音楽:伊藤宣二●時間:124分●出演:原節子/笠智衆/淡島千景/三宅邦子/菅井一郎/東山千栄子/杉村春子/二本柳寛/佐野周二/村瀬禪/城澤勇夫/高堂国典/高橋とよ/宮内精二/井川邦子/志賀真津子/伊藤和代/山本多美/谷よしの/寺田佳世子/長谷部朋香/山田英子/田代芳子/谷崎純●公開:1951/03●配給:松竹(評価:★★★★☆)
雄春●音楽:伊藤宣二●時間:124分●出演:原節子/笠智衆/淡島千景/三宅邦子/菅井一郎/東山千栄子/杉村春子/二本柳寛/佐野周二/村瀬禪/城澤勇夫/高堂国典/高橋とよ/宮内精二/井川邦子/志賀真津子/伊藤和代/山本多美/谷よしの/寺田佳世子/長谷部朋香/山田英子/田代芳子/谷崎純●公開:1951/03●配給:松竹(評価:★★★★☆)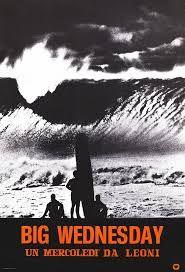

 「ビッグ・ウェンズデー」●原題:BIG WENSDAY●制作年:1978年●制作国:アメリカ●監督:ジョン・ミリアス●製作:バズ・フェイトシャンズ/アレクサンドラ・ローズ●脚本:ジョン・ミリアス/デニス・アーバーグ●撮影:ブルース・サーティース●音楽:ベイ
「ビッグ・ウェンズデー」●原題:BIG WENSDAY●制作年:1978年●制作国:アメリカ●監督:ジョン・ミリアス●製作:バズ・フェイトシャンズ/アレクサンドラ・ローズ●脚本:ジョン・ミリアス/デニス・アーバーグ●撮影:ブルース・サーティース●音楽:ベイ ジル・ポールドゥリス●時間:119分●出演:ジャン=マイケル・ヴィンセント/ウィリアム・カット
ジル・ポールドゥリス●時間:119分●出演:ジャン=マイケル・ヴィンセント/ウィリアム・カット /ゲイリー・ビジー/リー・パーセル/サム・メルヴィル/パティ・ダーバンヴィル/ダレル・フェティ/ジェフ・パークス/レブ・ブラウン/デニス・アーバーグ/リック・ダノ/バーバラ・ヘイル/ジョー・スピネル/ロバート・イングランド●日本公開:1979/04●配給:ワーナー・ブラザーズ●最初に観た場所:テアトル吉祥寺(82>-03-13)(評価:★★★☆)●併映:「カッコーの巣の上で」(ミロシュ・フォアマン)
/ゲイリー・ビジー/リー・パーセル/サム・メルヴィル/パティ・ダーバンヴィル/ダレル・フェティ/ジェフ・パークス/レブ・ブラウン/デニス・アーバーグ/リック・ダノ/バーバラ・ヘイル/ジョー・スピネル/ロバート・イングランド●日本公開:1979/04●配給:ワーナー・ブラザーズ●最初に観た場所:テアトル吉祥寺(82>-03-13)(評価:★★★☆)●併映:「カッコーの巣の上で」(ミロシュ・フォアマン) 「エノケンの近藤勇」●制作年:1935年●監督:山本嘉次郎●脚本・原作:ピエル・ブリヤント/P.C.L.文芸部●撮影:唐沢弘光●音楽:栗原重一●時間:81分●出演:榎本健一/二村定一/中村是好/柳田貞一/如月寛多/田島辰夫/丸山定夫/伊藤薫/花島喜世子/宏川光子/北村季佐江/
「エノケンの近藤勇」●制作年:1935年●監督:山本嘉次郎●脚本・原作:ピエル・ブリヤント/P.C.L.文芸部●撮影:唐沢弘光●音楽:栗原重一●時間:81分●出演:榎本健一/二村定一/中村是好/柳田貞一/如月寛多/田島辰夫/丸山定夫/伊藤薫/花島喜世子/宏川光子/北村季佐江/ 千川輝美/高尾光子/夏目初子●公開:1935/10●配給:P.C.L.(評価:★★★)
千川輝美/高尾光子/夏目初子●公開:1935/10●配給:P.C.L.(評価:★★★)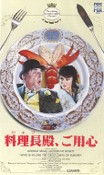
 「料理長(シェフ)殿、ご用心」●原題:SOMEONE IS KILLING THE GREAT CHEFS OF EUROPE●制作年:ヴァン・ライアンズ/ナン・ラ1978年●制作国:アメリカ●監督:テッド・コチェフ●脚本:ピーター・ストーン●撮影:ジョン・オルコット●音楽:ヘンリー・マンシーニ●原作:アイヴァン・ライアンズ/
「料理長(シェフ)殿、ご用心」●原題:SOMEONE IS KILLING THE GREAT CHEFS OF EUROPE●制作年:ヴァン・ライアンズ/ナン・ラ1978年●制作国:アメリカ●監督:テッド・コチェフ●脚本:ピーター・ストーン●撮影:ジョン・オルコット●音楽:ヘンリー・マンシーニ●原作:アイヴァン・ライアンズ/ ナン・ライアンズ●時間:112分●出演:ジャクリーン・ビセット/ジョージ・シーガル/ロバート・モーレイ/ジャン=ピエール・カッセル/フィリップ・ノワレ/ジャン・ロシュフォール/ルイージ・プロイェッティ/ステファノ・サッタ・フロレス●日本公開:1979/05●配給:日本ヘラルド映画●最初に観た場所:五反田TOEIシネマ(80-02-18)(評価:★★★)●併映「セント・アイブス」(J・リー・トンプソン)/「クリスチーヌの性愛記」(アロイス・ブルマー)
ナン・ライアンズ●時間:112分●出演:ジャクリーン・ビセット/ジョージ・シーガル/ロバート・モーレイ/ジャン=ピエール・カッセル/フィリップ・ノワレ/ジャン・ロシュフォール/ルイージ・プロイェッティ/ステファノ・サッタ・フロレス●日本公開:1979/05●配給:日本ヘラルド映画●最初に観た場所:五反田TOEIシネマ(80-02-18)(評価:★★★)●併映「セント・アイブス」(J・リー・トンプソン)/「クリスチーヌの性愛記」(アロイス・ブルマー)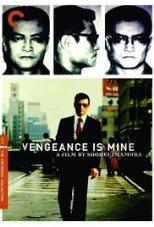
 「復讐するは我にあり」●制作年:1979年●監督:今村昌平●製作:井上和男●脚本:馬場当/池端俊策●撮影:姫田真佐久●音楽:池辺晋一郎●原作:佐木隆三●時間:140分●出演:緒形拳/三國連太郎/ミヤコ蝶々/倍賞美津子/小川真由美/
「復讐するは我にあり」●制作年:1979年●監督:今村昌平●製作:井上和男●脚本:馬場当/池端俊策●撮影:姫田真佐久●音楽:池辺晋一郎●原作:佐木隆三●時間:140分●出演:緒形拳/三國連太郎/ミヤコ蝶々/倍賞美津子/小川真由美/ 清川虹子/殿山泰司/垂水悟郎/絵沢萠子/白川和子/フランキー堺/北村和夫/火野正平/根岸とし江(根岸李江)/河原崎長一郎/菅井きん/石堂淑郎/加藤嘉/佐木隆三●公開:1979/04●配給:松竹●最初に観た場所(再見):新宿ピカデリー(緒形拳追悼特集)(08-11-23)●2回目:北千住・シネマブルースタジオ(10-01-17)(評価:★★★★☆)
清川虹子/殿山泰司/垂水悟郎/絵沢萠子/白川和子/フランキー堺/北村和夫/火野正平/根岸とし江(根岸李江)/河原崎長一郎/菅井きん/石堂淑郎/加藤嘉/佐木隆三●公開:1979/04●配給:松竹●最初に観た場所(再見):新宿ピカデリー(緒形拳追悼特集)(08-11-23)●2回目:北千住・シネマブルースタジオ(10-01-17)(評価:★★★★☆)
 「エイリアン」●原題:ALIEN●制作年:1979年●制作国:アメリカ●監督:リドリー・スコット●製作:ゴードン・キャロル/デヴィッド・ガイラー/ウォルター・ヒル●脚本:ダン・オバノン●撮影:デレク・ヴァンリント●音楽:ジェリー・ゴールドスミス●時間:117分●出演:トム・スケリット/シガニー・ウィーバー/ヴェロニカ・カートライト/ハリー・ディーン・スタントン/ジョン・ハート/イアン・ホルム/ヤフェット・コットー●日本公開:1979/07●配給:20世紀フォックス●最初に観た場所:三軒茶屋東映(84-07-22)(評価:★★★★)●併映:「遊星からの物体X」(ジョン・カーペンター)
「エイリアン」●原題:ALIEN●制作年:1979年●制作国:アメリカ●監督:リドリー・スコット●製作:ゴードン・キャロル/デヴィッド・ガイラー/ウォルター・ヒル●脚本:ダン・オバノン●撮影:デレク・ヴァンリント●音楽:ジェリー・ゴールドスミス●時間:117分●出演:トム・スケリット/シガニー・ウィーバー/ヴェロニカ・カートライト/ハリー・ディーン・スタントン/ジョン・ハート/イアン・ホルム/ヤフェット・コットー●日本公開:1979/07●配給:20世紀フォックス●最初に観た場所:三軒茶屋東映(84-07-22)(評価:★★★★)●併映:「遊星からの物体X」(ジョン・カーペンター)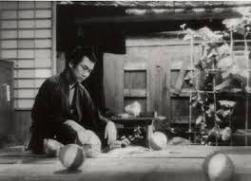
 「人情紙風船」●制作年:1937年●監督:山中貞雄●製作:P.C.L.●脚本:三村伸太郎●撮影:三村明●音楽:太田忠郎●美術考証:岩田専太郎●原作:河竹黙阿弥(『梅雨小袖昔八丈』、通称『髪結新三』)●時間:86分●出演:河原崎長十郎(海野又十郎)/中村翫右衛門(髪結新三)/山岸しづ江(又十郎の女房おたき)/霧立のぼる(白子屋の娘お駒)/助高屋助蔵(家主長兵衛)/市川笑太朗(弥太五郎源七)/中村鶴蔵 (金魚売源公)/市川莚司[加東大介])(猪助)/橘小三郎[藤川八蔵](毛利三左衛門)/御橋公(白子屋久左衛門)/瀬川菊乃丞(忠七)/市川扇升(長松)/原緋紗子(源公の女房おてつ)/坂東調右衛門/市川樂三郎/市川菊之助/岬たか子●公開:1937/08●配給:東宝映画●最初に観た場所:早稲田松竹(07-08-12)(評価:★★★★☆)●併映:「丹下左膳餘話 百萬兩の壺」(山中貞雄)
「人情紙風船」●制作年:1937年●監督:山中貞雄●製作:P.C.L.●脚本:三村伸太郎●撮影:三村明●音楽:太田忠郎●美術考証:岩田専太郎●原作:河竹黙阿弥(『梅雨小袖昔八丈』、通称『髪結新三』)●時間:86分●出演:河原崎長十郎(海野又十郎)/中村翫右衛門(髪結新三)/山岸しづ江(又十郎の女房おたき)/霧立のぼる(白子屋の娘お駒)/助高屋助蔵(家主長兵衛)/市川笑太朗(弥太五郎源七)/中村鶴蔵 (金魚売源公)/市川莚司[加東大介])(猪助)/橘小三郎[藤川八蔵](毛利三左衛門)/御橋公(白子屋久左衛門)/瀬川菊乃丞(忠七)/市川扇升(長松)/原緋紗子(源公の女房おてつ)/坂東調右衛門/市川樂三郎/市川菊之助/岬たか子●公開:1937/08●配給:東宝映画●最初に観た場所:早稲田松竹(07-08-12)(評価:★★★★☆)●併映:「丹下左膳餘話 百萬兩の壺」(山中貞雄)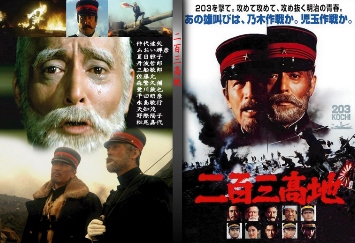 「二百三高地」●制作年:1980年●監督:舛田利雄●脚本:笠原和夫●撮影:飯村雅彦●音楽:山本直純●主題曲:さだまさし●時間:181分●出演:仲代達矢/あおい輝彦/新沼謙治/湯原昌幸/佐藤允/永島敏行/長谷川明男/稲葉義男/新克利/矢吹二朗/船戸順/浜田寅彦/近藤宏/伊沢一郎/玉川伊佐男/名和宏/横森久/武藤章生/浜田晃/三南道郎/
「二百三高地」●制作年:1980年●監督:舛田利雄●脚本:笠原和夫●撮影:飯村雅彦●音楽:山本直純●主題曲:さだまさし●時間:181分●出演:仲代達矢/あおい輝彦/新沼謙治/湯原昌幸/佐藤允/永島敏行/長谷川明男/稲葉義男/新克利/矢吹二朗/船戸順/浜田寅彦/近藤宏/伊沢一郎/玉川伊佐男/名和宏/横森久/武藤章生/浜田晃/三南道郎/ 北村晃一/木村四郎/中田博久/南廣/河原崎次郎/市川好朗/山田光一/磯村健治/相馬剛三/高月忠/亀山達也/清水照夫/桐原信介/原田力/久地明/秋山敏/金子吉延/森繁久彌/天知茂/神山繁/平田昭彦/若林豪/野口元夫/土山登士幸/川合伸旺/久遠利三/須藤健/吉原正皓/愛川欽也/夏目雅子/野際陽子/桑山正一/赤木春恵/原田清人/北林早苗/土方弘/小畠絹子/河合絃司/須賀良/石橋雅史/村井国夫/早川純一/尾形伸之介/青木義朗/三船敏郎/松尾嘉代/内藤武敏/丹波哲郎●公開:1980/08●配給:東映●最初に観た場所:飯田橋・佳作座 (81-01-24)(評価:★★)●併映:「将軍 SHOGUN」(ジェリー・ロンドン)
北村晃一/木村四郎/中田博久/南廣/河原崎次郎/市川好朗/山田光一/磯村健治/相馬剛三/高月忠/亀山達也/清水照夫/桐原信介/原田力/久地明/秋山敏/金子吉延/森繁久彌/天知茂/神山繁/平田昭彦/若林豪/野口元夫/土山登士幸/川合伸旺/久遠利三/須藤健/吉原正皓/愛川欽也/夏目雅子/野際陽子/桑山正一/赤木春恵/原田清人/北林早苗/土方弘/小畠絹子/河合絃司/須賀良/石橋雅史/村井国夫/早川純一/尾形伸之介/青木義朗/三船敏郎/松尾嘉代/内藤武敏/丹波哲郎●公開:1980/08●配給:東映●最初に観た場所:飯田橋・佳作座 (81-01-24)(評価:★★)●併映:「将軍 SHOGUN」(ジェリー・ロンドン) 「殺しのドレス」●原題:DRESSED TO KILL●制作年:1980年●制作国:アメリカ●監督・脚本:ブライアン・デ・パルマ●製作:ジョージ・リットー●撮影:ラルフ・ボード●音楽:ピノ・ドナッジオ●時間:114分●出演:マイケル・ケイン/アンジー・ディキンソン/ナンシー・アレン/キース・ゴードン/デニス・フランツ/デヴィッド・ マーグリーズ/ブランドン・マガート●日本公開:1981/04●配給:日本ヘラルド映画●最初に観た場所:六本木・俳優座シネマテン(81-04-03)●2回目:テアトル吉祥寺 (86-02-15)(評価:★★★★)●併映(2回目):「デストラップ 死の罠」(シドニー・ルメット)/「日曜日が待ち遠しい!」(フランソワ・トリュフォー)/「ハメット」(ヴィム・ヴェンダース)
「殺しのドレス」●原題:DRESSED TO KILL●制作年:1980年●制作国:アメリカ●監督・脚本:ブライアン・デ・パルマ●製作:ジョージ・リットー●撮影:ラルフ・ボード●音楽:ピノ・ドナッジオ●時間:114分●出演:マイケル・ケイン/アンジー・ディキンソン/ナンシー・アレン/キース・ゴードン/デニス・フランツ/デヴィッド・ マーグリーズ/ブランドン・マガート●日本公開:1981/04●配給:日本ヘラルド映画●最初に観た場所:六本木・俳優座シネマテン(81-04-03)●2回目:テアトル吉祥寺 (86-02-15)(評価:★★★★)●併映(2回目):「デストラップ 死の罠」(シドニー・ルメット)/「日曜日が待ち遠しい!」(フランソワ・トリュフォー)/「ハメット」(ヴィム・ヴェンダース)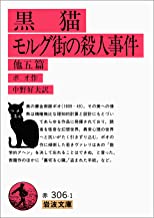
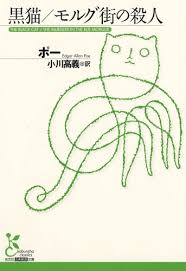
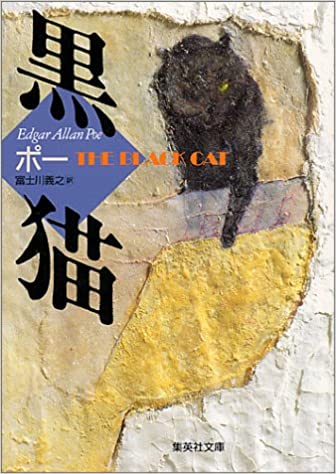
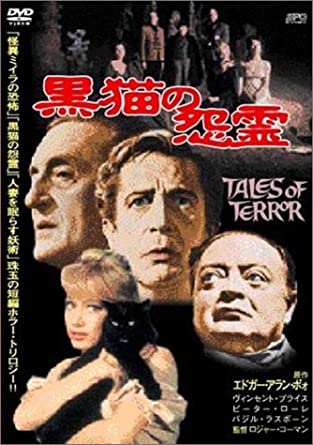
 この作品は1934年にベラ・ルゴシおよびボリス・カーロフ主演で映画化されており、1941年にもベラ・ルゴシとベイジル・ラスボーン主演のものが製作されていますが、これらはどちらも原作にそれほど忠実ではなく(ベラ・ルゴシ主演ものは「
この作品は1934年にベラ・ルゴシおよびボリス・カーロフ主演で映画化されており、1941年にもベラ・ルゴシとベイジル・ラスボーン主演のものが製作されていますが、これらはどちらも原作にそれほど忠実ではなく(ベラ・ルゴシ主演ものは「 (「
(「 酒好きのモントレソー(ピーター・ローレ)は妻のアナベル(ジョイス・ジェイムソン)と二人暮らしの気易さから、毎夜酒場で大酒を呑んでいた。ある夜、酒代を妻に押さえられた彼は利き酒の会場にまぎれ込み、その名人フォルチュナト(ヴィンセント・プライス)に挑戦して酔い潰れてしまう。一方、淋しさのあまり黒猫を溺愛していたアナベルは、夫を送って来てくれたフォルチュナトと深い仲になってしまった。それを夫モントレソーに見つかり、二人は殺害された上、地下室の壁に塗り込まれてしまう―。
酒好きのモントレソー(ピーター・ローレ)は妻のアナベル(ジョイス・ジェイムソン)と二人暮らしの気易さから、毎夜酒場で大酒を呑んでいた。ある夜、酒代を妻に押さえられた彼は利き酒の会場にまぎれ込み、その名人フォルチュナト(ヴィンセント・プライス)に挑戦して酔い潰れてしまう。一方、淋しさのあまり黒猫を溺愛していたアナベルは、夫を送って来てくれたフォルチュナトと深い仲になってしまった。それを夫モントレソーに見つかり、二人は殺害された上、地下室の壁に塗り込まれてしまう―。 ということで、ヴィンセント・プライスはここでは、原作に全く登場しない、主人公の妻と一緒に殺害される間男という風にされています(笑)。しかしながら、これでも、20世紀に作られた数ある「黒猫」を原作とする映画の中で、最も原作に忠実に作られている作品だそうです(Sova, Dawn B. (2001). Edgar Allan Poe, A to Z)。ピーター・ローレの終始酔っぱらっている演技はなんだかゆったりしていて、殺害されるヴィンセント・プライスの方もどこかユーモラスと言うか悲喜劇風で、3部作の中でもコミカルに仕上がっています。
ということで、ヴィンセント・プライスはここでは、原作に全く登場しない、主人公の妻と一緒に殺害される間男という風にされています(笑)。しかしながら、これでも、20世紀に作られた数ある「黒猫」を原作とする映画の中で、最も原作に忠実に作られている作品だそうです(Sova, Dawn B. (2001). Edgar Allan Poe, A to Z)。ピーター・ローレの終始酔っぱらっている演技はなんだかゆったりしていて、殺害されるヴィンセント・プライスの方もどこかユーモラスと言うか悲喜劇風で、3部作の中でもコミカルに仕上がっています。 ラストも全く気色悪さは無く(壁に塗り込められるというより、煉瓦壁で覆い隠しているだけであるため、壁の向こう側に隙間があって、猫はしっかり生きている。何らかの機会に壁の向こう側にいったと推察可能か)、ホラーが苦手な人にもお薦めです。ピーター・ローレ、ヴィンセント・プライスの演技が愉しめる作品で、残り2つの短編の主人公はヴィンセント・プライスで、内容的には結構おどろおどろしいのですが、この第2話「黒猫の怨霊」は完全にピーター・ローレが主人公と言え、しか
ラストも全く気色悪さは無く(壁に塗り込められるというより、煉瓦壁で覆い隠しているだけであるため、壁の向こう側に隙間があって、猫はしっかり生きている。何らかの機会に壁の向こう側にいったと推察可能か)、ホラーが苦手な人にもお薦めです。ピーター・ローレ、ヴィンセント・プライスの演技が愉しめる作品で、残り2つの短編の主人公はヴィンセント・プライスで、内容的には結構おどろおどろしいのですが、この第2話「黒猫の怨霊」は完全にピーター・ローレが主人公と言え、しか
 も、ユーモラスなブラック・コメディ仕様で、出来栄え的には三作の中で頭一つ抜きん出ています。因みに、殺される妻を演じたジョイス・ジェイムソンは、「
も、ユーモラスなブラック・コメディ仕様で、出来栄え的には三作の中で頭一つ抜きん出ています。因みに、殺される妻を演じたジョイス・ジェイムソンは、「

 「黒猫の怨霊」●原題:TALES OF TERROR●制作年:1962年●制作国:アメリカ●監督・製作:ロジャー・コーマン●脚本:リチャード・マシスン●撮影:フロイド・クロスビー●音楽:レス・バクスター●原作:エドガー・アラン・ポー「モレラ」、「黒猫」、「ヴァルデマー氏の症例」●時間:88分●出演:ヴィンセント・プライス/マギー・ピアース/ピーター・ローレ/ベイジル・ラスボーン/ジョイス・ジェイムソン/デブラ・パジェット●日本公開:1964/05●配給:大蔵(評価:★★★☆)
「黒猫の怨霊」●原題:TALES OF TERROR●制作年:1962年●制作国:アメリカ●監督・製作:ロジャー・コーマン●脚本:リチャード・マシスン●撮影:フロイド・クロスビー●音楽:レス・バクスター●原作:エドガー・アラン・ポー「モレラ」、「黒猫」、「ヴァルデマー氏の症例」●時間:88分●出演:ヴィンセント・プライス/マギー・ピアース/ピーター・ローレ/ベイジル・ラスボーン/ジョイス・ジェイムソン/デブラ・パジェット●日本公開:1964/05●配給:大蔵(評価:★★★☆)
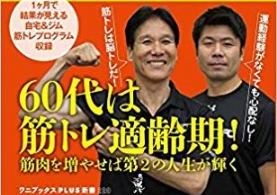

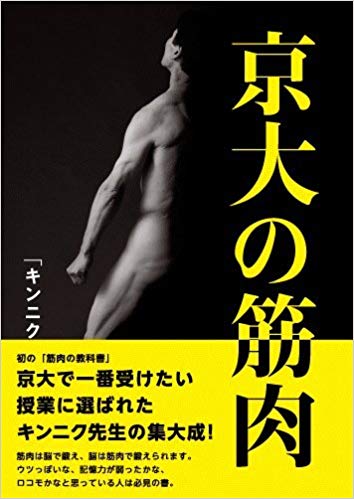
 60歳前後は「筋トレ適齢期」であるとともに、時間が自由に使えるようになる定年前後は、まさに「はじめどき」でもあると説いた本。シニアの運動は「ウオーキング」ばかりになりがちだが、ウオーキングばかりしていても筋肉は増えず、きちんとした知識を身につけて行えば、少々ハードな筋トレをやっても大丈夫とのことです。去年['19年]観た映画で、「RBG 最強の85才」('18年/米)という米国で最高齢の女性最高裁判事として国民的アイコンとなったRBGことルース・ベイダー・ギンズバーグを追ったドキュメンタリー映画がありましたが、その中でギンズバーグが85歳にしてパーソナルトレーナーをつけてがんがん筋トレしていたのを思い出しました。
60歳前後は「筋トレ適齢期」であるとともに、時間が自由に使えるようになる定年前後は、まさに「はじめどき」でもあると説いた本。シニアの運動は「ウオーキング」ばかりになりがちだが、ウオーキングばかりしていても筋肉は増えず、きちんとした知識を身につけて行えば、少々ハードな筋トレをやっても大丈夫とのことです。去年['19年]観た映画で、「RBG 最強の85才」('18年/米)という米国で最高齢の女性最高裁判事として国民的アイコンとなったRBGことルース・ベイダー・ギンズバーグを追ったドキュメンタリー映画がありましたが、その中でギンズバーグが85歳にしてパーソナルトレーナーをつけてがんがん筋トレしていたのを思い出しました。 著者は京大名誉教授であり、「京大の筋肉」のキャッチとヌード写真で一躍注目を浴びましたが(当時64歳)、個人的にどんな人か知ったのは、NHK-BSプレミアムのフットボールアワーがMCを務める「美と若さの新常識〜カラダのヒミツ〜」で"実践!おサボり筋トレ"というテーマの時にコメンテーターとして出演しているのを見たのが最初だったでしょうか。自分で実践しているので、言っていることに説得力がありました(同じ番組に出ていたフィットネスビキニの日本女王・安井友梨などにも言えることだが)。
著者は京大名誉教授であり、「京大の筋肉」のキャッチとヌード写真で一躍注目を浴びましたが(当時64歳)、個人的にどんな人か知ったのは、NHK-BSプレミアムのフットボールアワーがMCを務める「美と若さの新常識〜カラダのヒミツ〜」で"実践!おサボり筋トレ"というテーマの時にコメンテーターとして出演しているのを見たのが最初だったでしょうか。自分で実践しているので、言っていることに説得力がありました(同じ番組に出ていたフィットネスビキニの日本女王・安井友梨などにも言えることだが)。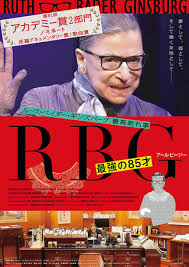
 冒頭に挙げた「RBG 最強の85才」は、米国では関連本が何冊も出版され、Tシャツやマグカップといったグッズまで作られるほどの知名度と人気を誇る、RBGことルース・ベイダー・ギンズバーグの若い頃から現在までを二人の女性監督が描いたドキュメンタリーで、85歳(映画製作時)で現役の最
冒頭に挙げた「RBG 最強の85才」は、米国では関連本が何冊も出版され、Tシャツやマグカップといったグッズまで作られるほどの知名度と人気を誇る、RBGことルース・ベイダー・ギンズバーグの若い頃から現在までを二人の女性監督が描いたドキュメンタリーで、85歳(映画製作時)で現役の最 高裁判所判事として活躍する彼女は、ニューヨークのユダヤ系の家に生まれ、苦学の末に判司となり、1980年にカーター大統領によってコロンビア特別区巡回区連邦控訴裁判所判事に指名され、1993年に
高裁判所判事として活躍する彼女は、ニューヨークのユダヤ系の家に生まれ、苦学の末に判司となり、1980年にカーター大統領によってコロンビア特別区巡回区連邦控訴裁判所判事に指名され、1993年に はビル・クリントン大統領政権下で女性としては2人目のアメリカ最高裁判事(長官を含めて9人で構成される)に任命されています。85歳の年齢で現職にあるので保守派かというと、実はその逆で、これまでも女性やマイノリティへの差別撤廃に寄与した判決を多く出しているリベラル派です(だか
はビル・クリントン大統領政権下で女性としては2人目のアメリカ最高裁判事(長官を含めて9人で構成される)に任命されています。85歳の年齢で現職にあるので保守派かというと、実はその逆で、これまでも女性やマイノリティへの差別撤廃に寄与した判決を多く出しているリベラル派です(だか ら若者に人気がある)。映画の中でも一部解説されていますが、ドナルド・トランプは2017年1月大統領就任後、引退する連邦最高裁判事の後任として保守派の判事を次々に任命しているため、リベラル派のギンズバーグはこれ以上の連邦最高裁の保守化を食い止めるために、少なくともトランプが退陣して新たな民主党出身の大統領が現れるまでは、引退を見送ると見られているようです。現職に留まっているのには理由があり、また、職務継続のため「筋トレ」で健康を維持しているということになるかと思います(もうすぐ87歳になるなあ)。
ら若者に人気がある)。映画の中でも一部解説されていますが、ドナルド・トランプは2017年1月大統領就任後、引退する連邦最高裁判事の後任として保守派の判事を次々に任命しているため、リベラル派のギンズバーグはこれ以上の連邦最高裁の保守化を食い止めるために、少なくともトランプが退陣して新たな民主党出身の大統領が現れるまでは、引退を見送ると見られているようです。現職に留まっているのには理由があり、また、職務継続のため「筋トレ」で健康を維持しているということになるかと思います(もうすぐ87歳になるなあ)。





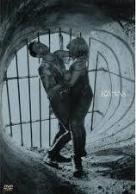

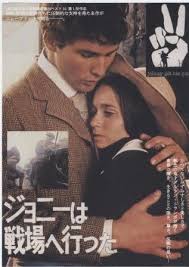 第1章「悲劇」では、「
第1章「悲劇」では、「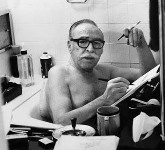 行った」('71年/米)も相当なもの。カンヌ国際映画祭 審査員特別グランプリ受賞作でありながら、殆どホラー映画に近い戦慄を覚えましたが、選者の森達也氏が、映画を通して主人公の苦痛を一度は体験すべきだと述べているのには賛同します。監督は「ローマの休日」('53年/米)の脚本家ドルトン・トランボで(原作もドルトン・トランボで発表は1938年)、第二次世界大戦後に「赤狩り」の標的とされ投獄された経験もあり(そう言えば「
行った」('71年/米)も相当なもの。カンヌ国際映画祭 審査員特別グランプリ受賞作でありながら、殆どホラー映画に近い戦慄を覚えましたが、選者の森達也氏が、映画を通して主人公の苦痛を一度は体験すべきだと述べているのには賛同します。監督は「ローマの休日」('53年/米)の脚本家ドルトン・トランボで(原作もドルトン・トランボで発表は1938年)、第二次世界大戦後に「赤狩り」の標的とされ投獄された経験もあり(そう言えば「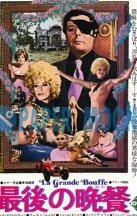

![ジョニーは戦場へ行った [DVD].jpg](http://hurec.bz/book-movie/%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%8B%E3%83%BC%E3%81%AF%E6%88%A6%E5%A0%B4%E3%81%B8%E8%A1%8C%E3%81%A3%E3%81%9F%20%5BDVD%5D.jpg)
 「ジョニーは戦場に行った」●原題:JOHNNY GOT HIS GUN●制作年:1971年●制作国:アメリカ●監督:ダルトン・トランボ●製作ブルース・キャンベル●脚本:ダルトン・トランボ●撮影: ジュールス・ブレンナー●音楽:ジェリー・フィールデ
「ジョニーは戦場に行った」●原題:JOHNNY GOT HIS GUN●制作年:1971年●制作国:アメリカ●監督:ダルトン・トランボ●製作ブルース・キャンベル●脚本:ダルトン・トランボ●撮影: ジュールス・ブレンナー●音楽:ジェリー・フィールデ ィング●原作:ダルトン・トランボ●時間:112分●出演:ティモシー・ボトムズ/キャシー・フィールズ/ドナルド・サザーランド/ジェイソン・ロバーズ/マーシャ・ハント/ チャールズ・マッグロー/ダイアン・ヴァーシ/エドワード・フランツ/ ケリー・マクレーン●日本公開:1973/04●配給:ヘラルド映画●最初に観た場所:新宿アートビレッジ(79-02-24)(評価:★★★★)
ィング●原作:ダルトン・トランボ●時間:112分●出演:ティモシー・ボトムズ/キャシー・フィールズ/ドナルド・サザーランド/ジェイソン・ロバーズ/マーシャ・ハント/ チャールズ・マッグロー/ダイアン・ヴァーシ/エドワード・フランツ/ ケリー・マクレーン●日本公開:1973/04●配給:ヘラルド映画●最初に観た場所:新宿アートビレッジ(79-02-24)(評価:★★★★)![未来世紀ブラジル [DVD].jpg](http://hurec.bz/book-movie/%E6%9C%AA%E6%9D%A5%E4%B8%96%E7%B4%80%E3%83%96%E3%83%A9%E3%82%B8%E3%83%AB%20%5BDVD%5D.jpg)
 「未来世紀ブラジル」●原題:BRAZIL●制作年:1985年●制作国:イギリス●監督:テリー・ギリアム●製作:アーノン・ミルチャン●脚本:テリー・ギリアム/チャールズ・マッケオン/トム・ストッパード●撮影:ロジャー・プラット●音楽:マイケル・ケイメン●時間:142分●出演:ジョナサン・プライス/ロバート・デ・ニーロ/キ
「未来世紀ブラジル」●原題:BRAZIL●制作年:1985年●制作国:イギリス●監督:テリー・ギリアム●製作:アーノン・ミルチャン●脚本:テリー・ギリアム/チャールズ・マッケオン/トム・ストッパード●撮影:ロジャー・プラット●音楽:マイケル・ケイメン●時間:142分●出演:ジョナサン・プライス/ロバート・デ・ニーロ/キ ム・グライスト/マイケル・ペイリン/キャサリン・ヘルモンド/ボブ・ホスキンス/デリック・オコナー/イアン・ホルム/イアン・リチャードソン/ピーター・ヴォーン/ジム・ブロードベント●日本公開:1986/10●配給:20世紀フォックス●最初に観た場所:大井武蔵野舘(87-07-19)(評価:★★★★)●併映:「ザ・フライ」(デビッド・クローネンバーグ)
ム・グライスト/マイケル・ペイリン/キャサリン・ヘルモンド/ボブ・ホスキンス/デリック・オコナー/イアン・ホルム/イアン・リチャードソン/ピーター・ヴォーン/ジム・ブロードベント●日本公開:1986/10●配給:20世紀フォックス●最初に観た場所:大井武蔵野舘(87-07-19)(評価:★★★★)●併映:「ザ・フライ」(デビッド・クローネンバーグ) 蝶々/倍賞美津子/小川真由美/清川虹子/殿山泰司/垂水悟郎/絵沢萠子/白川和子/フランキー堺/北村和夫/火野正平/根岸とし江(根岸李江)/河原崎長一郎/菅井きん/石堂淑郎/加藤嘉/佐木隆三●公開:1979/04●配給:松竹●最初に観た場所(再見):新宿ピカデリー(緒形拳追悼特集)(08-11-23)●2回目:北千住・シネマブルースタジオ(10-01-17)(評価:★★★★☆)
蝶々/倍賞美津子/小川真由美/清川虹子/殿山泰司/垂水悟郎/絵沢萠子/白川和子/フランキー堺/北村和夫/火野正平/根岸とし江(根岸李江)/河原崎長一郎/菅井きん/石堂淑郎/加藤嘉/佐木隆三●公開:1979/04●配給:松竹●最初に観た場所(再見):新宿ピカデリー(緒形拳追悼特集)(08-11-23)●2回目:北千住・シネマブルースタジオ(10-01-17)(評価:★★★★☆) ン=ピエール・ラッサム●撮影:マリオ・ヴルピアーニ●音楽:フィリップ・サルド●時間:130分●出演:マルチェロ・マストロヤンニ/ウーゴ・トニャッツィ/フィリップ・ノワレ/ミシェル・ピッコリ/アンドレア・フェレオル●日本公開:1974/11●最初に観た場所:大塚名画座 (78-11-07) (評価★★★★☆)●併映:「糧なき土地」(ルイス・ブニュエル)/「自由の幻想」(ルイス・ブニュエル)
ン=ピエール・ラッサム●撮影:マリオ・ヴルピアーニ●音楽:フィリップ・サルド●時間:130分●出演:マルチェロ・マストロヤンニ/ウーゴ・トニャッツィ/フィリップ・ノワレ/ミシェル・ピッコリ/アンドレア・フェレオル●日本公開:1974/11●最初に観た場所:大塚名画座 (78-11-07) (評価★★★★☆)●併映:「糧なき土地」(ルイス・ブニュエル)/「自由の幻想」(ルイス・ブニュエル)
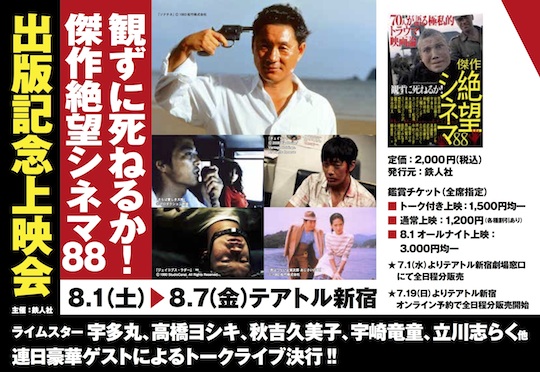



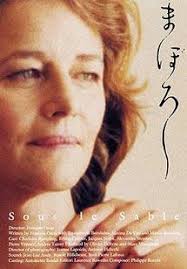

 シルヴィア(シャーリーズ・セロン)は、ポートランドの海辺に建つ高級レストランのマネージャーとして働いている。だが、ひとたび職場を離れると、行きずりの男と安易に関係を持ち、自傷行為に走る。そんな彼女の前に、カルロス(ホセ・マリア・ヤスピク)と名乗るメキシコ人男性が現れ、彼が連れてきた12歳の少女マリア(テッサ・イア)の姿にシルヴィアは動揺し、思わず逃げ出す。その胸に、砂漠の中で真っ赤に燃え上がるトレーラーハウスの幻影が浮かび上がる...。シルヴィアがマリアーナと呼ばれていた10代の頃、彼女の一家はニ
シルヴィア(シャーリーズ・セロン)は、ポートランドの海辺に建つ高級レストランのマネージャーとして働いている。だが、ひとたび職場を離れると、行きずりの男と安易に関係を持ち、自傷行為に走る。そんな彼女の前に、カルロス(ホセ・マリア・ヤスピク)と名乗るメキシコ人男性が現れ、彼が連れてきた12歳の少女マリア(テッサ・イア)の姿にシルヴィアは動揺し、思わず逃げ出す。その胸に、砂漠の中で真っ赤に燃え上がるトレーラーハウスの幻影が浮かび上がる...。シルヴィアがマリアーナと呼ばれていた10代の頃、彼女の一家はニ ューメキシコ州の国境の町で暮らしていた。病気を克服したばかりの母親ジーナ(キム・ベイシンガー)に代わって、父親ロバート(ブレット・カレン)と3人の幼い兄弟の面倒を見るのはマリアーナ(ジェニファー・ローレンス)の役目だった。そんな中、ジーナは隣町に住むメキシコ
ューメキシコ州の国境の町で暮らしていた。病気を克服したばかりの母親ジーナ(キム・ベイシンガー)に代わって、父親ロバート(ブレット・カレン)と3人の幼い兄弟の面倒を見るのはマリアーナ(ジェニファー・ローレンス)の役目だった。そんな中、ジーナは隣町に住むメキシコ なった。母の事故死は、多感なマリアーナの心に大きな傷跡を残したが、それはニックの息子・サンティアゴ(J・D・パルド)にとっても同様だった。やがて、両親を真似るように密会を重ねるようになった二人は、本気で恋に落ちていく―。それから12年、シルヴィアは、マリアーナの名前と共に置き去りにした過去と向き合うべき時が来たことを悟る―。
なった。母の事故死は、多感なマリアーナの心に大きな傷跡を残したが、それはニックの息子・サンティアゴ(J・D・パルド)にとっても同様だった。やがて、両親を真似るように密会を重ねるようになった二人は、本気で恋に落ちていく―。それから12年、シルヴィアは、マリアーナの名前と共に置き去りにした過去と向き合うべき時が来たことを悟る―。 "脚本家"監督のまさに脚本の上手さを感じさせますが、驚くべきは、重要な役どころであるシルヴィアの娘マリアーナを演じたジェニファー・ローレンス(1990年生まれ)の演技力で、当時17歳にして、2人のオスカー女優の体当たり演技(これはこれで流石と言うべき好演)に拮抗する演技となっています。ギジェルモ・アリアガ監督には「メリル・ストリープの再来かと思った」と言わしめ、2008年・第65回ヴェネツィア
"脚本家"監督のまさに脚本の上手さを感じさせますが、驚くべきは、重要な役どころであるシルヴィアの娘マリアーナを演じたジェニファー・ローレンス(1990年生まれ)の演技力で、当時17歳にして、2人のオスカー女優の体当たり演技(これはこれで流石と言うべき好演)に拮抗する演技となっています。ギジェルモ・アリアガ監督には「メリル・ストリープの再来かと思った」と言わしめ、2008年・第65回ヴェネツィア 国際映画祭ではマルチェロ・マストロヤンニ賞(新人俳優賞)を受賞しました。その4年後、コメディ映画「
国際映画祭ではマルチェロ・マストロヤンニ賞(新人俳優賞)を受賞しました。その4年後、コメディ映画「 大学で英文学を教えるマリー(シャーロット・ランプリング)は、夫ジャン(ブリュノ・クレメール)とは結婚して25年になる50代の夫婦。子どもはいないが幸せな生活を送っている。毎年夏になると、フランス南西部・ランド地方の別荘で過ごし、今夏も同様にヴァカンスを楽しみに来た。昼間、マリーが浜辺でうたた寝する間、ジャンは海に泳ぎに行く。目を覚ましたマリーは、ジャンがまだ海から戻っていないことに気づく。気を揉みながらも平静を装うマリーだが、不安は現実のものとなる。ヘリコプターまで出動した大がかりな捜索にもかかわらずジャンの行方は不明のまま。数日後、マリーはひとりパリへと戻るが―。
大学で英文学を教えるマリー(シャーロット・ランプリング)は、夫ジャン(ブリュノ・クレメール)とは結婚して25年になる50代の夫婦。子どもはいないが幸せな生活を送っている。毎年夏になると、フランス南西部・ランド地方の別荘で過ごし、今夏も同様にヴァカンスを楽しみに来た。昼間、マリーが浜辺でうたた寝する間、ジャンは海に泳ぎに行く。目を覚ましたマリーは、ジャンがまだ海から戻っていないことに気づく。気を揉みながらも平静を装うマリーだが、不安は現実のものとなる。ヘリコプターまで出動した大がかりな捜索にもかかわらずジャンの行方は不明のまま。数日後、マリーはひとりパリへと戻るが―。 シャーロット・ランプリング(1946年生まれ)が演じる、夫の死を受け入れられないマリーが、"壊れている"感がある分、どこかいじらしさもありました。彼女がパリに戻って最初の方のシーンで夫が出てくるため、その部分はカットバックかと思ったら、どうやらそうではなかったみたい。すでに「まぼろし」は始まっていた?(原題: Sous le sableは「砂の下」の意)。そう言えば、すでに女友達のアマンダ(アレクサンドラ・スチュワルト)に精神科に診てもらうよう勧められていました。
シャーロット・ランプリング(1946年生まれ)が演じる、夫の死を受け入れられないマリーが、"壊れている"感がある分、どこかいじらしさもありました。彼女がパリに戻って最初の方のシーンで夫が出てくるため、その部分はカットバックかと思ったら、どうやらそうではなかったみたい。すでに「まぼろし」は始まっていた?(原題: Sous le sableは「砂の下」の意)。そう言えば、すでに女友達のアマンダ(アレクサンドラ・スチュワルト)に精神科に診てもらうよう勧められていました。
 彼女にとって夫は生きているわけで、女友達のアマンダはヴァンサン(ジャック・ノロ)を再婚相手として紹介したつもりなのだろうけれども(一見カットバック・シーンと思われた食事会は、二人をくっつけるためのものだったわけか)、彼女自身は不倫のスリルと快感を味わっているような
彼女にとって夫は生きているわけで、女友達のアマンダはヴァンサン(ジャック・ノロ)を再婚相手として紹介したつもりなのだろうけれども(一見カットバック・シーンと思われた食事会は、二人をくっつけるためのものだったわけか)、彼女自身は不倫のスリルと快感を味わっているような 感じでした(やや滑稽にも見える)。夫の薬棚からうつ病の薬を見つけて夫が自殺することを心配し、医者に行ってヴァカンス以降は薬を受け取りに来ていないことを知っても、あくまでも自殺を心配しています。仕舞には、ラスト近くで夫と思しき水死体が揚がって自ら検死に行くも、腕時計が違うという理由だけで(それが正確かどうかも怪しいが)夫とは認めようとしない―精神分析でいう"合理化"なのでしょうが、やっぱり"壊れている"!
感じでした(やや滑稽にも見える)。夫の薬棚からうつ病の薬を見つけて夫が自殺することを心配し、医者に行ってヴァカンス以降は薬を受け取りに来ていないことを知っても、あくまでも自殺を心配しています。仕舞には、ラスト近くで夫と思しき水死体が揚がって自ら検死に行くも、腕時計が違うという理由だけで(それが正確かどうかも怪しいが)夫とは認めようとしない―精神分析でいう"合理化"なのでしょうが、やっぱり"壊れている"! アメリカでも好評を得た理由の1つは、シャーロット・ランプリングがアメリカ映画にもよく出ていることもあるのでは。まさにシャーロット・ランプリングの演技を観る映画になっているような感じですが、彼女はその負託に応えている感じで、この作品の演技が、「さざなみ」('15年/英)などでの高い評価を得た近年の演技の下地として連なっているのではないかと思います。かつて「愛の嵐」('74年/伊)の頃は、こんなに息の長い女優になるとは思われていなかったように思います。また、彼女は実際に活動が一時低調であったわけで、フランソワ・オゾン監督にこの作品で起用されたことで、再び注目を集めることになったとも言えます。
アメリカでも好評を得た理由の1つは、シャーロット・ランプリングがアメリカ映画にもよく出ていることもあるのでは。まさにシャーロット・ランプリングの演技を観る映画になっているような感じですが、彼女はその負託に応えている感じで、この作品の演技が、「さざなみ」('15年/英)などでの高い評価を得た近年の演技の下地として連なっているのではないかと思います。かつて「愛の嵐」('74年/伊)の頃は、こんなに息の長い女優になるとは思われていなかったように思います。また、彼女は実際に活動が一時低調であったわけで、フランソワ・オゾン監督にこの作品で起用されたことで、再び注目を集めることになったとも言えます。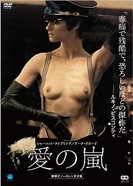
 「愛の嵐」は、リリアーナ・カヴァーニ監督の1973年のイタリア映画。ウィーンのとあるホテルの夜番のフロント係兼ポーターとして働くマクシミリアン(ダーク・ボガード)は、実は元ナチス親衛隊の将校で収容所の所長だった人物。アメリカから有名なオペラ指揮者がホテルに泊り客としてやってきますが、その妻ルチア(シャーロット・ランプリング)は、13年前マックスが強制収容所でその権力を使って倒錯した愛の生活を送ったユダヤ人の少女で、二人は再び倒錯した愛欲
「愛の嵐」は、リリアーナ・カヴァーニ監督の1973年のイタリア映画。ウィーンのとあるホテルの夜番のフロント係兼ポーターとして働くマクシミリアン(ダーク・ボガード)は、実は元ナチス親衛隊の将校で収容所の所長だった人物。アメリカから有名なオペラ指揮者がホテルに泊り客としてやってきますが、その妻ルチア(シャーロット・ランプリング)は、13年前マックスが強制収容所でその権力を使って倒錯した愛の生活を送ったユダヤ人の少女で、二人は再び倒錯した愛欲 の世界にのめり込んでいくという話です。この映画において、主人公マックスはじめとして元ナチ党員たちが孤立せずに、横のつながりを持ちながら生きていることが描かれていて(この部分は実際の社会や政治を反映している)、そうした輩にとってルチアは危険な存在になっていくが―。
の世界にのめり込んでいくという話です。この映画において、主人公マックスはじめとして元ナチ党員たちが孤立せずに、横のつながりを持ちながら生きていることが描かれていて(この部分は実際の社会や政治を反映している)、そうした輩にとってルチアは危険な存在になっていくが―。 「美しい」とか「醜い」とか様々な評価のある映画ですが、シャーロット・ランプリングの美貌が光る作品であったには違いなく、上半身裸にサスペンダーでナチ帽をかぶって踊る場面は、映画史に残る有名なシーンの1つとなりました。原題は「ナイトポーター」。昔観たときは、ヨーロッパのホテルにはダーク・ボガードみたいな顔のポーターがよくいるけれど、みんなスゴイ過去を持っているのかも...とも思ったりしました。
「美しい」とか「醜い」とか様々な評価のある映画ですが、シャーロット・ランプリングの美貌が光る作品であったには違いなく、上半身裸にサスペンダーでナチ帽をかぶって踊る場面は、映画史に残る有名なシーンの1つとなりました。原題は「ナイトポーター」。昔観たときは、ヨーロッパのホテルにはダーク・ボガードみたいな顔のポーターがよくいるけれど、みんなスゴイ過去を持っているのかも...とも思ったりしました。 (●2023年・第80回「ヴェネチア国際映画祭」にて、リリアーナ・カヴァーニ監督は、俳優のトニー・レオンとともに栄誉金獅子賞を受賞した。)
(●2023年・第80回「ヴェネチア国際映画祭」にて、リリアーナ・カヴァーニ監督は、俳優のトニー・レオンとともに栄誉金獅子賞を受賞した。) 「あの日、欲望の大地で」●原題:THE BURNING PLAIN●制作年:2008年●制作国:アメリカ●監督・脚本:ギジェルモ・アリアガ●製作:ウォルター・パークス/
「あの日、欲望の大地で」●原題:THE BURNING PLAIN●制作年:2008年●制作国:アメリカ●監督・脚本:ギジェルモ・アリアガ●製作:ウォルター・パークス/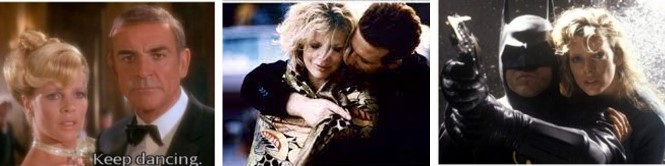

 「まぼろし」●原題:SOUS LE SABLE/(英)UNDER THE SAND●制作年:2000年●制作国:フランス●監督:フランソワ・オゾン●製作:オリヴィエ・デルボス/マルク・ミソニエ●脚本:フランソワ・オゾン/エマニュエル・ベルンエイム/マリナ・ドゥ・ヴァン/マルシア・ロマーノ●撮影:アントワーヌ・エベルレ/ジャンヌ・ラポワリー●音楽:フィリップ・ロンビ●時間:95分●出演:シャーロット・ランプリング/ブリュノ・クレメール/ジャック・ノロ/アレクサンドラ・スチュワルト/ピエール・ヴェルニエ/アンドレ・タンジー●日本公開:2002/09●配給:ユーロスペース●最初に観た場所:北千住・シネマブルースタジオ(18-09-03)(評価:★★★☆)
「まぼろし」●原題:SOUS LE SABLE/(英)UNDER THE SAND●制作年:2000年●制作国:フランス●監督:フランソワ・オゾン●製作:オリヴィエ・デルボス/マルク・ミソニエ●脚本:フランソワ・オゾン/エマニュエル・ベルンエイム/マリナ・ドゥ・ヴァン/マルシア・ロマーノ●撮影:アントワーヌ・エベルレ/ジャンヌ・ラポワリー●音楽:フィリップ・ロンビ●時間:95分●出演:シャーロット・ランプリング/ブリュノ・クレメール/ジャック・ノロ/アレクサンドラ・スチュワルト/ピエール・ヴェルニエ/アンドレ・タンジー●日本公開:2002/09●配給:ユーロスペース●最初に観た場所:北千住・シネマブルースタジオ(18-09-03)(評価:★★★☆)
 「愛の嵐」●原題:IL PORTIERE DI NOTTE/(英)THE NIGHT POTER●制作年:1974年●制作
「愛の嵐」●原題:IL PORTIERE DI NOTTE/(英)THE NIGHT POTER●制作年:1974年●制作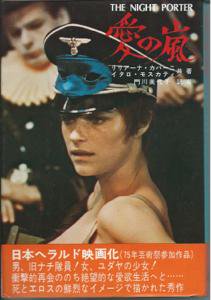 国:イタリア●監督:リリアーナ・カヴァーニ●製作:ロバート・ゴードン・エドワーズ●脚本:リリアーナ・カヴァーニ/イタロ・モスカーティ●撮影:アルフィーオ・コンティーニ●音楽:ダニエレ・パリス●原作:リリアーナ・カヴァーニ/バルバラ・アルベルティ/アメディオ・パガーニ●時間:117分●出演:ダーク・ボガード/シャーロット・ランプリング/フィリップ・ルロワ/ガブリエル・フェルゼッティ/マリノ・マッセ/ウーゴ・カルデア/イザ・ミランダ/カイ・ジークフリート・シーフィルド●日本公開:1975/11/(ノーカット完全版)1997/03●配給:日本ヘラルド映画/(ノーカット完全版)彩プロ●最初に観た場所:八重洲スター座(79-02-01) (評価:★★★★)●併映:「ルシアンの青春」(ルイ・マル)
国:イタリア●監督:リリアーナ・カヴァーニ●製作:ロバート・ゴードン・エドワーズ●脚本:リリアーナ・カヴァーニ/イタロ・モスカーティ●撮影:アルフィーオ・コンティーニ●音楽:ダニエレ・パリス●原作:リリアーナ・カヴァーニ/バルバラ・アルベルティ/アメディオ・パガーニ●時間:117分●出演:ダーク・ボガード/シャーロット・ランプリング/フィリップ・ルロワ/ガブリエル・フェルゼッティ/マリノ・マッセ/ウーゴ・カルデア/イザ・ミランダ/カイ・ジークフリート・シーフィルド●日本公開:1975/11/(ノーカット完全版)1997/03●配給:日本ヘラルド映画/(ノーカット完全版)彩プロ●最初に観た場所:八重洲スター座(79-02-01) (評価:★★★★)●併映:「ルシアンの青春」(ルイ・マル)


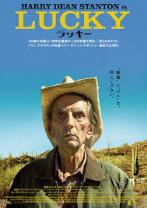

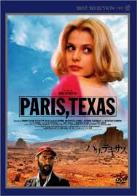
 90歳の通称"ラッキー"(ハリー・ディーン・スタントン)は、今日も一人で住むアパートで目を覚まし、コーヒーを飲みタバコをふかす。ヨガをこなしたあと、テンガロンハットを被って行きつけのダイナーに行き、店主のジョー(バリー・シャバカ・ヘンリー)と無駄話をかわし、ウェイトレスのロレッタ(イヴォンヌ・ハフ・リー)が注いだミルクと砂糖多めのコーヒーを飲みながら新聞のクロスワード・パズルを解く。夜はバーでブラッディ・マリーを飲み、馴染み客たちと過ごす。そんな毎日の中で、ある朝突然気を失ったラッキーは、人生の終わりが近いことを思い知らされ、「死」について考え始める。子供の頃怖かった暗闇、逃げた100歳の亀、"生餌"として売られるコオロギ―小さな町の、風変わりな人々との会話の中で、ラッキーは「それ」を悟っていく―。
90歳の通称"ラッキー"(ハリー・ディーン・スタントン)は、今日も一人で住むアパートで目を覚まし、コーヒーを飲みタバコをふかす。ヨガをこなしたあと、テンガロンハットを被って行きつけのダイナーに行き、店主のジョー(バリー・シャバカ・ヘンリー)と無駄話をかわし、ウェイトレスのロレッタ(イヴォンヌ・ハフ・リー)が注いだミルクと砂糖多めのコーヒーを飲みながら新聞のクロスワード・パズルを解く。夜はバーでブラッディ・マリーを飲み、馴染み客たちと過ごす。そんな毎日の中で、ある朝突然気を失ったラッキーは、人生の終わりが近いことを思い知らされ、「死」について考え始める。子供の頃怖かった暗闇、逃げた100歳の亀、"生餌"として売られるコオロギ―小さな町の、風変わりな人々との会話の中で、ラッキーは「それ」を悟っていく―。
 昨年[2017年]9月に91歳で亡くなったハリー・ディーン・スタントン主演のジョン・キャロル・リンチ監督作品で、ハリー・ディーン・スタントンの遺作となりました。ジョン・キャロル・リンチは本来は俳優で(最近では「
昨年[2017年]9月に91歳で亡くなったハリー・ディーン・スタントン主演のジョン・キャロル・リンチ監督作品で、ハリー・ディーン・スタントンの遺作となりました。ジョン・キャロル・リンチは本来は俳優で(最近では「 」の創始者マクドナルド兄弟の兄モーリスを演じていた)、この「ラッキー」が初監督作品になります。一方、2017年のTV版「ツイン・ピークス」でハリー・ディーン・スタントンを使ったデヴィッド・リンチ監督が、主人公ラッキーの友人で、逃げてしまったペットの100歳の陸ガメ"ルーズベルト"に遺産相続させようとしとする変な男ハワード役で出演しています(役者として目いっぱい演技している)。
」の創始者マクドナルド兄弟の兄モーリスを演じていた)、この「ラッキー」が初監督作品になります。一方、2017年のTV版「ツイン・ピークス」でハリー・ディーン・スタントンを使ったデヴィッド・リンチ監督が、主人公ラッキーの友人で、逃げてしまったペットの100歳の陸ガメ"ルーズベルト"に遺産相続させようとしとする変な男ハワード役で出演しています(役者として目いっぱい演技している)。 ントンは太平洋戦争時に、映画の中でダイナーの客が語る沖縄戦に実際に従軍している)、映画では少々偏屈で気難しいところのあるキャラクターとして描かれています。自分の言いたいことを言い、そのため周囲の人々と小さな衝突をすることもありますが、でも、ラッキーは周囲の人々から気に掛けられ、愛されていて、彼を受け容れる友人・知人・コミニュティもあるといった
ントンは太平洋戦争時に、映画の中でダイナーの客が語る沖縄戦に実際に従軍している)、映画では少々偏屈で気難しいところのあるキャラクターとして描かれています。自分の言いたいことを言い、そのため周囲の人々と小さな衝突をすることもありますが、でも、ラッキーは周囲の人々から気に掛けられ、愛されていて、彼を受け容れる友人・知人・コミニュティもあるといった 具合で、むしろこれって"ラッキー"な老人の話なのかもと思いました。但し、彼自身はウェット感はなく、どうやら無神論者らしいですが、そう遠くないであろう自らの死に、自らの信念である"リアリズム"(ニヒリズムとも言える)を保ちつつ向き合おうしています。ある意味、精神的"終活映画"と言えるでしょうか。その姿が、ハリー・ディーン・スタントン自身と重なるのですが、孤独でドライな生き方や考え方と、それでも他者と関わりを持ち続ける態度の、その両者のバランスがなかなか微妙と言うか絶妙かと思いました。
具合で、むしろこれって"ラッキー"な老人の話なのかもと思いました。但し、彼自身はウェット感はなく、どうやら無神論者らしいですが、そう遠くないであろう自らの死に、自らの信念である"リアリズム"(ニヒリズムとも言える)を保ちつつ向き合おうしています。ある意味、精神的"終活映画"と言えるでしょうか。その姿が、ハリー・ディーン・スタントン自身と重なるのですが、孤独でドライな生き方や考え方と、それでも他者と関わりを持ち続ける態度の、その両者のバランスがなかなか微妙と言うか絶妙かと思いました。 ハリー・ディーン・スタントンはこの映画撮影時は90歳で、「八月の鯨」('87年/米)で主演したリリアン・ギッシュ(1893-1993)が撮影当時93歳であったのには及びませんが、「サウンド・オブ・ミュージック」('65年/米)のクリストファー・プラマーが「手紙は憶えている」('15年/カナダ・ドイツ)で主演した際の年齢85歳を5歳上回っています(クリストファー・プラマーはその後「ゲティ家の身代金」('17年/米)で第90回アカデミー賞助演男優賞に88歳でノミネートされ、アカデミー賞の演技部門でのノミネート最高齢記録を更新した)。
ハリー・ディーン・スタントンはこの映画撮影時は90歳で、「八月の鯨」('87年/米)で主演したリリアン・ギッシュ(1893-1993)が撮影当時93歳であったのには及びませんが、「サウンド・オブ・ミュージック」('65年/米)のクリストファー・プラマーが「手紙は憶えている」('15年/カナダ・ドイツ)で主演した際の年齢85歳を5歳上回っています(クリストファー・プラマーはその後「ゲティ家の身代金」('17年/米)で第90回アカデミー賞助演男優賞に88歳でノミネートされ、アカデミー賞の演技部門でのノミネート最高齢記録を更新した)。 ハリー・ディーン・スタントンがこれまでの出演した作品と言えば、SF映画の傑作「エイリアン」や、準主役の「レポマン」、主役を演じた「パリ、テキサス」など多数ありますが、第37回カンヌ国際映画祭でパルム・ドールを受賞した、ヴィム・ヴェンダース監督の「パリ、テキサス」が特に印象深いでしょうか。この「ラッキー」のエンディング・ロールで流れる彼に捧げる歌の歌詞に「レポマン」「パリ、テキサス」と出てきます。また、米国中西部らしい舞台背景は「パリ、テキサス」を想起させます(ジョン・キャロル・リンチ監督は
ハリー・ディーン・スタントンがこれまでの出演した作品と言えば、SF映画の傑作「エイリアン」や、準主役の「レポマン」、主役を演じた「パリ、テキサス」など多数ありますが、第37回カンヌ国際映画祭でパルム・ドールを受賞した、ヴィム・ヴェンダース監督の「パリ、テキサス」が特に印象深いでしょうか。この「ラッキー」のエンディング・ロールで流れる彼に捧げる歌の歌詞に「レポマン」「パリ、テキサス」と出てきます。また、米国中西部らしい舞台背景は「パリ、テキサス」を想起させます(ジョン・キャロル・リンチ監督は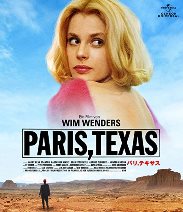


 「パリ、テキサス」('84年/独・仏)は、失踪した妻を探し求めテキサス州の町パリをめざす男(スタントン)が、4年間置き去りにしていた幼い息子と再会して親子の情を取り戻し、やがて巡り会った妻(ナスターシャ・キンスキー)に愛するがゆえの苦悩を打ち明ける―というロード・ムービーであり、当時まだアイドルっぽいイメージの残っていたナスターシャ・キンスキーに、「のぞき部屋」で働いている生活疲れした人妻を演じさせ新境地を開拓させたヴィム・ヴェンダース監督もさることながら、ハリー・ディーン・スタントンの静かな存在感も作品を根底で支えていたように思いま
「パリ、テキサス」('84年/独・仏)は、失踪した妻を探し求めテキサス州の町パリをめざす男(スタントン)が、4年間置き去りにしていた幼い息子と再会して親子の情を取り戻し、やがて巡り会った妻(ナスターシャ・キンスキー)に愛するがゆえの苦悩を打ち明ける―というロード・ムービーであり、当時まだアイドルっぽいイメージの残っていたナスターシャ・キンスキーに、「のぞき部屋」で働いている生活疲れした人妻を演じさせ新境地を開拓させたヴィム・ヴェンダース監督もさることながら、ハリー・ディーン・スタントンの静かな存在感も作品を根底で支えていたように思いま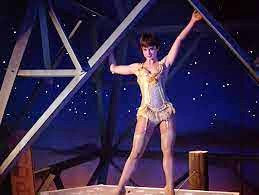 す。ヴィム・ヴェンダース監督は、ロマン・ポランスキー監督が文豪トマス・ハーディの文芸大作を忠実に映画化した作品「
す。ヴィム・ヴェンダース監督は、ロマン・ポランスキー監督が文豪トマス・ハーディの文芸大作を忠実に映画化した作品「 ハリー・ディーン・スタントンは、主役だった「パリ、テキサス」に比べると、リドリー・スコット監督の「エイリアン」('79年/米)では、"怪物"に「繭」にされてしまい、最後は味方に火炎放射器で焼かれて
ハリー・ディーン・スタントンは、主役だった「パリ、テキサス」に比べると、リドリー・スコット監督の「エイリアン」('79年/米)では、"怪物"に「繭」にされてしまい、最後は味方に火炎放射器で焼かれて
 この恐れは、シガニー・ウィーバー演じるリプリーが完全に主人公となったシリーズ第2作以降、リプリー自身の見る「悪夢」として継承されていきます。「エイリアン2」('86年/米)の監督は、「ターミネーター」のジェームズ・キャメロン。ラストでエイリアンと戦うリプリーが突如「機動戦士ガンダム」風に変身する場面に象徴されるように、SF映画というよりは戦争アクション映
この恐れは、シガニー・ウィーバー演じるリプリーが完全に主人公となったシリーズ第2作以降、リプリー自身の見る「悪夢」として継承されていきます。「エイリアン2」('86年/米)の監督は、「ターミネーター」のジェームズ・キャメロン。ラストでエイリアンと戦うリプリーが突如「機動戦士ガンダム」風に変身する場面に象徴されるように、SF映画というよりは戦争アクション映 画風で、「1」に比べ大味になったように思います(海兵隊のバスケスという男まさりの女兵士は良かった)。デヴィッド・フィンチャー監督の「エイリアン3」('92年/米)になると、リドリー・スコット監督がシンプルな怖さを前面に押し出した第1作に比べてそう恐ろしくもないし(馴れた?)、ジェームズ・キャメロン監督がエイリアンを次々と繰り出した第2作に較べても出てくるエイリアンは1匹で物足りないし、ラストの宗教的結末も、このシリーズに似合わない感じがしました(「エイリアン」「エイリアン2」は共に優れたSF映画に与えられる「サターンSF映画賞」を受賞している)。
画風で、「1」に比べ大味になったように思います(海兵隊のバスケスという男まさりの女兵士は良かった)。デヴィッド・フィンチャー監督の「エイリアン3」('92年/米)になると、リドリー・スコット監督がシンプルな怖さを前面に押し出した第1作に比べてそう恐ろしくもないし(馴れた?)、ジェームズ・キャメロン監督がエイリアンを次々と繰り出した第2作に較べても出てくるエイリアンは1匹で物足りないし、ラストの宗教的結末も、このシリーズに似合わない感じがしました(「エイリアン」「エイリアン2」は共に優れたSF映画に与えられる「サターンSF映画賞」を受賞している)。
 チェスト・バスターの出現がシリーズを象徴する場面として印象に残るという意味では、「エイリアン」でのジョン・ハートの役は、エグいけれどもオイシイ役だったかも。この人、「
チェスト・バスターの出現がシリーズを象徴する場面として印象に残るという意味では、「エイリアン」でのジョン・ハートの役は、エグいけれどもオイシイ役だったかも。この人、「
 そのジョン・ハートも「ウィンストン・チャーチル/ヒトラーから世界を救った男」('17年/英)のチェンバレン役を降板したと思ったら、昨年['17年]1月に膵臓ガンで77歳で亡くなっています。「ウィンストン・チャーチル」ではゲイリー・オールドマンがアカデミー賞の主演男優層を受賞していますが、そのゲイリー・オールドマンと、第22回「サテライト・アワード」(エンターテインメント記者が所属する国際プレス・アカデミが選ぶ映画賞)の主演男優賞を分け合ったのがハリー・ディーン・スタントンです。但し、スタントンは"死後受賞"でした。遅ればせながらこれを機に、ジョン・ハートとハリー・ディーン・スタントンに追悼の意を捧げます(「冥福を祈る」と言うと、"ラッキー"から「冥土なんて存在しない」と言われそう)。
そのジョン・ハートも「ウィンストン・チャーチル/ヒトラーから世界を救った男」('17年/英)のチェンバレン役を降板したと思ったら、昨年['17年]1月に膵臓ガンで77歳で亡くなっています。「ウィンストン・チャーチル」ではゲイリー・オールドマンがアカデミー賞の主演男優層を受賞していますが、そのゲイリー・オールドマンと、第22回「サテライト・アワード」(エンターテインメント記者が所属する国際プレス・アカデミが選ぶ映画賞)の主演男優賞を分け合ったのがハリー・ディーン・スタントンです。但し、スタントンは"死後受賞"でした。遅ればせながらこれを機に、ジョン・ハートとハリー・ディーン・スタントンに追悼の意を捧げます(「冥福を祈る」と言うと、"ラッキー"から「冥土なんて存在しない」と言われそう)。 そう言えば、ハリー・ディーン・スタントンは生前、"The Harry Dean Stanton Band"というバンドで歌とギターも担当していて、2016年に第1回「ハリー・ディーン・スタントン・アウォード」というイベントが開催され、ホストが今回の作品にも出ているデヴィッド・リンチで、ゲストが「沈黙の断崖」('97年)でハリー・ディーン・スタントンと共演したクリス・クリストファーソンや、「ラスベガスをやっつけろ」('98年)などで共演経験のあるジョニー・デップでしたが(ジョニー・デップの登場はハリー・ディーン・スタントンにとってはサプラズ演出だったようだ)、この「ハリー・ディーン・スタントン賞」って誰か"受賞者"いたのかなあ。
そう言えば、ハリー・ディーン・スタントンは生前、"The Harry Dean Stanton Band"というバンドで歌とギターも担当していて、2016年に第1回「ハリー・ディーン・スタントン・アウォード」というイベントが開催され、ホストが今回の作品にも出ているデヴィッド・リンチで、ゲストが「沈黙の断崖」('97年)でハリー・ディーン・スタントンと共演したクリス・クリストファーソンや、「ラスベガスをやっつけろ」('98年)などで共演経験のあるジョニー・デップでしたが(ジョニー・デップの登場はハリー・ディーン・スタントンにとってはサプラズ演出だったようだ)、この「ハリー・ディーン・スタントン賞」って誰か"受賞者"いたのかなあ。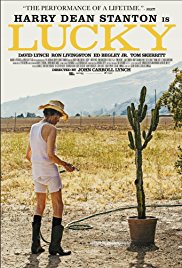

 公開:2018/03●配給:アップリンク●最初に観た場所:ヒューマントラストシネマ有楽町(シアター2)(18-04-13)(評価:★★★★)
公開:2018/03●配給:アップリンク●最初に観た場所:ヒューマントラストシネマ有楽町(シアター2)(18-04-13)(評価:★★★★)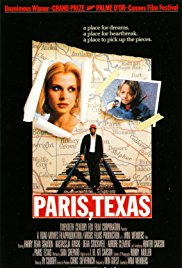
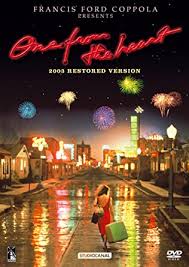
 「ワン・フロム・ザ・ハート」●原題:ONE FROM THE Heart●制作年:1982年●制作国:アメリカ●監督:フランシス・フォード・コッポラ●製作:グレイ・フレデリクソン/フレッド・ルース●脚本:アーミアン・バーンスタイン/フランシス・フォード・コッポラ●撮影:ロナルド・V・ガーシア/ヴィットリオ・ストラーロ●音楽:トム・ウェイツ●時間:107分●出演:フレデリック・フォレスト/テリー・ガー/ラウル・ジュリア/ナスターシャ・キンスキー/レイニー・カザン/ハリー・ディーン・スタントン /アレン・ガーフィールド/カーマイン・コッポラ/イタリア・コッポラ/レベッカ・デモーネイ●日本公開:1982/08●配給:東宝東和●最初に観た場所:目黒シネマ(83-05-01)(評価:★★★)●併映:「ひまわり」(ビットリオ・デ・シーカ)
「ワン・フロム・ザ・ハート」●原題:ONE FROM THE Heart●制作年:1982年●制作国:アメリカ●監督:フランシス・フォード・コッポラ●製作:グレイ・フレデリクソン/フレッド・ルース●脚本:アーミアン・バーンスタイン/フランシス・フォード・コッポラ●撮影:ロナルド・V・ガーシア/ヴィットリオ・ストラーロ●音楽:トム・ウェイツ●時間:107分●出演:フレデリック・フォレスト/テリー・ガー/ラウル・ジュリア/ナスターシャ・キンスキー/レイニー・カザン/ハリー・ディーン・スタントン /アレン・ガーフィールド/カーマイン・コッポラ/イタリア・コッポラ/レベッカ・デモーネイ●日本公開:1982/08●配給:東宝東和●最初に観た場所:目黒シネマ(83-05-01)(評価:★★★)●併映:「ひまわり」(ビットリオ・デ・シーカ)

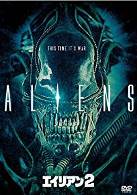
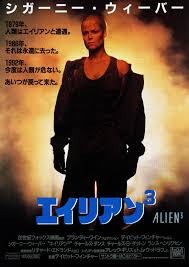
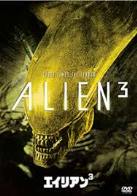
 「エレファント・マン」●原題:THE ELEPHANT MAN●制作年:1980年●制作国:イギリス●監督:デヴィッド・リンチ●製作:ジョナサン・サンガー●脚色:クリストファー・デヴォア/エリック・バーグレン/デヴィッド・リンチ●撮影:フレディ・フランシス●音楽:ジョン・モリス●時間:124分●出演:ジョン・ハート/アンソニー・ホプキンス/ジョン・ギールグッド/アン・バンクロフト●日本公開:1981/05●配給:東宝東和●最初に観た場所:不明 (82-10-04)(評価:★★★☆)
「エレファント・マン」●原題:THE ELEPHANT MAN●制作年:1980年●制作国:イギリス●監督:デヴィッド・リンチ●製作:ジョナサン・サンガー●脚色:クリストファー・デヴォア/エリック・バーグレン/デヴィッド・リンチ●撮影:フレディ・フランシス●音楽:ジョン・モリス●時間:124分●出演:ジョン・ハート/アンソニー・ホプキンス/ジョン・ギールグッド/アン・バンクロフト●日本公開:1981/05●配給:東宝東和●最初に観た場所:不明 (82-10-04)(評価:★★★☆)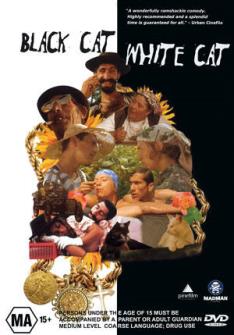
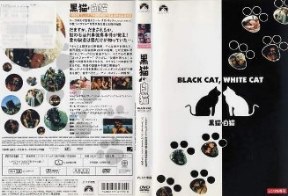
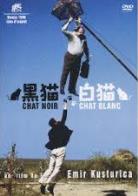
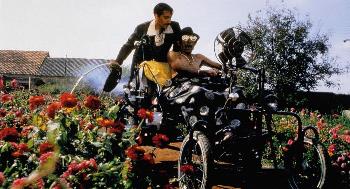 ユーゴスラヴィア・ドナウ川沿いのロマの住む田舎町。自称天才詐欺師のマトゥコ(バイラム・セヴェルジャン)は、ロシアの密輸船から石油を買うが、騙されて大金を失う。起死回生を狙って、ブルガリアからの石油運搬車両の強盗を計画、息子ザーレ(フロリアン・アイディーニ)を伴って "ゴッドファーザー"グルガ(サブリ・スレジマニ)のもとへ行き、計画への出資を依頼する。かつてグルガを助けた自分の父ザーリェ(ザビット・メフメトフスキー)が亡くなったことにして、グルガから香典としての資
ユーゴスラヴィア・ドナウ川沿いのロマの住む田舎町。自称天才詐欺師のマトゥコ(バイラム・セヴェルジャン)は、ロシアの密輸船から石油を買うが、騙されて大金を失う。起死回生を狙って、ブルガリアからの石油運搬車両の強盗を計画、息子ザーレ(フロリアン・アイディーニ)を伴って "ゴッドファーザー"グルガ(サブリ・スレジマニ)のもとへ行き、計画への出資を依頼する。かつてグルガを助けた自分の父ザーリェ(ザビット・メフメトフスキー)が亡くなったことにして、グルガから香典としての資 金援助を得るが、計画は新興ヤクザのダダン(スルジャン・トドロヴィッチ)の奸計により失敗し、ダダンに全財産を奪われる。困り果てたマトゥコは、嫁に行きそびれていたダダンの妹アフロディタ(サリア・イブライモヴァ)と自分の17歳の息子ザーレを結婚させる話を呑んでしま
金援助を得るが、計画は新興ヤクザのダダン(スルジャン・トドロヴィッチ)の奸計により失敗し、ダダンに全財産を奪われる。困り果てたマトゥコは、嫁に行きそびれていたダダンの妹アフロディタ(サリア・イブライモヴァ)と自分の17歳の息子ザーレを結婚させる話を呑んでしま う。ザーレは、川沿いでレストランを営むスイカ(リュビシャ・アジョヴィッチ)の孫娘で、年上の恋人イダ(ブランカ・カティッチ)からその話を聞かされるが何も出来ない。ザーリエは、息子マトゥコは見限っているが、孫のザーレには幸せになって欲しい。結婚
う。ザーレは、川沿いでレストランを営むスイカ(リュビシャ・アジョヴィッチ)の孫娘で、年上の恋人イダ(ブランカ・カティッチ)からその話を聞かされるが何も出来ない。ザーリエは、息子マトゥコは見限っているが、孫のザーレには幸せになって欲しい。結婚 式当日、元アコーディオン奏者だったザーリェは一計を案じ、アコーディオンにヘソクリを隠して、自ら心臓を止める。祖父が死んだと思ったマトゥコは、ダダンに式の中止を訴えるが
式当日、元アコーディオン奏者だったザーリェは一計を案じ、アコーディオンにヘソクリを隠して、自ら心臓を止める。祖父が死んだと思ったマトゥコは、ダダンに式の中止を訴えるが 、マトゥコは式を強行、ザーレは、アフロディタに式から脱出するよう促す。花嫁が消えて式は大混乱となり、ダダンをはじめ参列者総出の捜索が始まる。逃げるアフロディタは道中でノッポの男に助けられ、運命
、マトゥコは式を強行、ザーレは、アフロディタに式から脱出するよう促す。花嫁が消えて式は大混乱となり、ダダンをはじめ参列者総出の捜索が始まる。逃げるアフロディタは道中でノッポの男に助けられ、運命 を感じた二人はその場で結婚を約束。ダダンたちが追いついたところへやって来たノッポ男の祖父が、"ゴッドファーザー"グルガで、彼らはザーリェの"墓参り"に向かうところだった。ダダンはかつて彼の見習だったので、何も口出しできない。"死んだ"はずのザーリェも生き返り、グルガとザーリェは旧交を温め、晴れて二組のカップルが誕生。ザーリェは孫のザーレにヘソクリを託して二人の門出を祝う―。
を感じた二人はその場で結婚を約束。ダダンたちが追いついたところへやって来たノッポ男の祖父が、"ゴッドファーザー"グルガで、彼らはザーリェの"墓参り"に向かうところだった。ダダンはかつて彼の見習だったので、何も口出しできない。"死んだ"はずのザーリェも生き返り、グルガとザーリェは旧交を温め、晴れて二組のカップルが誕生。ザーリェは孫のザーレにヘソクリを託して二人の門出を祝う―。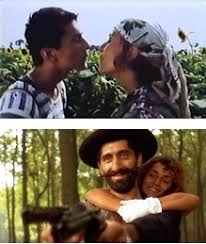 ユーゴスラビアのサラエヴォ(現在はボスニア・ヘルツェゴビナの首都)出身のエミール・クリトリッツァ監督の1998年作。愛人に漏らしたちょっとした国家批判が政府側の人物に漏れてしまったために父親が当局に捕まってしまう「パパは、出張中!」('85年/ユーゴスラビア)でカンヌ国際映画祭パルム・ドールを受賞し、更に、ユーゴスラビアの50年に渡る紛争の歴史を寓話的に描いた「アンダーグラウンド」('95年/仏・独・ハンガリー・ユーゴスラビア・ ブルガリア)で2度目となるカンヌ国際映画祭パルム・ドールを受賞しながらも、その後政治的なしがらみに巻き込まれ、一度は引退を決意した同監督は、メッセージ性を徹底的に排除した、それまでと全く趣の異なるスタイルのコメディ映画であるこの作品で、1998年第55回ヴェネチア国際映画祭「銀獅子賞」を受賞し、復活を果たしています(1993年「アリゾナ・ドリーム」でベルリン国際映画祭「銀熊賞」を受賞しているため、三大映画祭の全てで受賞したことになる)。
ユーゴスラビアのサラエヴォ(現在はボスニア・ヘルツェゴビナの首都)出身のエミール・クリトリッツァ監督の1998年作。愛人に漏らしたちょっとした国家批判が政府側の人物に漏れてしまったために父親が当局に捕まってしまう「パパは、出張中!」('85年/ユーゴスラビア)でカンヌ国際映画祭パルム・ドールを受賞し、更に、ユーゴスラビアの50年に渡る紛争の歴史を寓話的に描いた「アンダーグラウンド」('95年/仏・独・ハンガリー・ユーゴスラビア・ ブルガリア)で2度目となるカンヌ国際映画祭パルム・ドールを受賞しながらも、その後政治的なしがらみに巻き込まれ、一度は引退を決意した同監督は、メッセージ性を徹底的に排除した、それまでと全く趣の異なるスタイルのコメディ映画であるこの作品で、1998年第55回ヴェネチア国際映画祭「銀獅子賞」を受賞し、復活を果たしています(1993年「アリゾナ・ドリーム」でベルリン国際映画祭「銀熊賞」を受賞しているため、三大映画祭の全てで受賞したことになる)。 前半はややゆったりしていますが、これは複雑な登場人物の相関を分かりやすくするためだったのかも。ある程度、主要登場人物のバックグラウンドが明らかになると、それまでのラテン的な明るさに加えて話のテンポ自体も良くなり、終盤に向けては加速的にノンストップ・コメディの様相を呈してきます。エンディングで「ハッピーエンド」という字幕が出て来るのは、エミール・クストリッツァ監督初めてのハッピーエンド映画だったためではないでしょうか。
前半はややゆったりしていますが、これは複雑な登場人物の相関を分かりやすくするためだったのかも。ある程度、主要登場人物のバックグラウンドが明らかになると、それまでのラテン的な明るさに加えて話のテンポ自体も良くなり、終盤に向けては加速的にノンストップ・コメディの様相を呈してきます。エンディングで「ハッピーエンド」という字幕が出て来るのは、エミール・クストリッツァ監督初めてのハッピーエンド映画だったためではないでしょうか。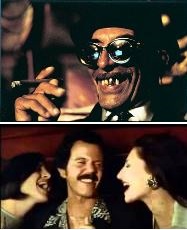
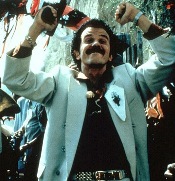 ハチャメチャなヤクザ・ダダンを演じたスルジャン・トドロヴィッチは喜劇役者かと思ってしまいますが、そうではなく、政治色の濃い前作「アンダーグラウンド」にも出演しているようだし(クロを演じたラザル・リストフスキーに似ている気がするのだが)、スルジャン・スパソイェヴィッチ監督の「セルビアン・フィルム」('10年/セルビア)のようなハードゴア・サスペンスに主演したりもしているようなので、相当に演技の幅が広いのではないでしょうか(でもこの作品では歌って踊って超ノリノリの演技をしていてハマリ役?)。このダダン役のスルジャン・トドロヴィッチとザーレの父マトゥコ役のバイラム・セヴェルジャン、恋人イダ役の女優ブランカ・カティチの3人以外は全てロマの人々だそうで、ザーレを演じたキアヌ・リーブス似のフロリアン・アイディーニもこの映画しか出ていないようです。
ハチャメチャなヤクザ・ダダンを演じたスルジャン・トドロヴィッチは喜劇役者かと思ってしまいますが、そうではなく、政治色の濃い前作「アンダーグラウンド」にも出演しているようだし(クロを演じたラザル・リストフスキーに似ている気がするのだが)、スルジャン・スパソイェヴィッチ監督の「セルビアン・フィルム」('10年/セルビア)のようなハードゴア・サスペンスに主演したりもしているようなので、相当に演技の幅が広いのではないでしょうか(でもこの作品では歌って踊って超ノリノリの演技をしていてハマリ役?)。このダダン役のスルジャン・トドロヴィッチとザーレの父マトゥコ役のバイラム・セヴェルジャン、恋人イダ役の女優ブランカ・カティチの3人以外は全てロマの人々だそうで、ザーレを演じたキアヌ・リーブス似のフロリアン・アイディーニもこの映画しか出ていないようです。 予定調和型の"結婚狂騒曲"風ドタバタ喜劇ですが、ロマの人々の生活や文化、ものの考え方がしっかりバックグラウンドに描かれていて、これまで触れたことのないようなものに触れた気がし、同時に、どこの世界も同じなのだなと思わせるものもありました。飛ぶ鳥を落とす勢いのダダンにとって、妹がいまだに結婚できないのが頭痛の種で、"ゴッドファーザー"グルガにとっても息子がなかなか結婚しないのが悩みの種だというのは、ある種"体面"を重んじる閉鎖的な社会を映しているのかも。"ゴッドファーザー"をユーモラスに描いていますが、その実態は一帯の支配者であって、現実はこうはいかないだろうなあと(ダダンのようなヤクザはいそう)。最後に結婚したザーレが旅に出ると決心した時に「ここには太陽がない」と言い残すところに、監督の真意があるのかも。その上で、この作品は敢えてコメディとして完結させたというのが、エンディングの「ハッピーエンド」という字幕に込められた意味ではないか思ったりもしました。
予定調和型の"結婚狂騒曲"風ドタバタ喜劇ですが、ロマの人々の生活や文化、ものの考え方がしっかりバックグラウンドに描かれていて、これまで触れたことのないようなものに触れた気がし、同時に、どこの世界も同じなのだなと思わせるものもありました。飛ぶ鳥を落とす勢いのダダンにとって、妹がいまだに結婚できないのが頭痛の種で、"ゴッドファーザー"グルガにとっても息子がなかなか結婚しないのが悩みの種だというのは、ある種"体面"を重んじる閉鎖的な社会を映しているのかも。"ゴッドファーザー"をユーモラスに描いていますが、その実態は一帯の支配者であって、現実はこうはいかないだろうなあと(ダダンのようなヤクザはいそう)。最後に結婚したザーレが旅に出ると決心した時に「ここには太陽がない」と言い残すところに、監督の真意があるのかも。その上で、この作品は敢えてコメディとして完結させたというのが、エンディングの「ハッピーエンド」という字幕に込められた意味ではないか思ったりもしました。![黒猫・白猫【字幕ワイド版】 [VHS].jpg](http://hurec.bz/book-movie/%E9%BB%92%E7%8C%AB%E3%83%BB%E7%99%BD%E7%8C%AB%E3%80%90%E5%AD%97%E5%B9%95%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%89%E7%89%88%E3%80%91%20%5BVHS%5D.jpg)
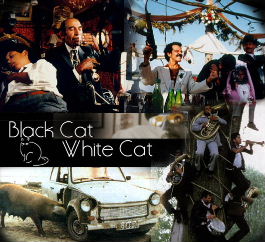 「黒猫・白猫」●原題:CHAT NOIR, CHAT BLANC/CRNA MACKA, BELI MACOR●制作年:1998年●制作国:フランス・ドイツ・ユーゴスラビア●監督:エミール・クストリッツァ●製作:マクサ・チャトヴィッチ/カール・バウムガルトナー●脚本:ゴルダン・ミヒッチ●撮影:ティエリー・アルボガスト●音楽:ネレ・カライリチ/ヴォイスラフ・アラリカ/デーシャン・スパラヴァロ●時間:130分●出演:バイラム・セヴェルジャン/フロリアン・アイディーニ/スルジャン・トドロヴィッチ/ブランカ・カティッチ/サリア・イブライモヴァ/ザビット・メフメトフスキー/サブリ・スレジマニ/リュビシャ・アジョヴィッチ/ジャセール・デスタニ/アドナン・ベキールストジャン・ソティロフ/ゼダ・ハルテカコヴァ/プレドラグ・ペピ・ラコビッチ/プレグラグ・ミキ・マノジョロビッチ●日本公開:1999/08●配給:フランス映画社(評価:★★★★)
「黒猫・白猫」●原題:CHAT NOIR, CHAT BLANC/CRNA MACKA, BELI MACOR●制作年:1998年●制作国:フランス・ドイツ・ユーゴスラビア●監督:エミール・クストリッツァ●製作:マクサ・チャトヴィッチ/カール・バウムガルトナー●脚本:ゴルダン・ミヒッチ●撮影:ティエリー・アルボガスト●音楽:ネレ・カライリチ/ヴォイスラフ・アラリカ/デーシャン・スパラヴァロ●時間:130分●出演:バイラム・セヴェルジャン/フロリアン・アイディーニ/スルジャン・トドロヴィッチ/ブランカ・カティッチ/サリア・イブライモヴァ/ザビット・メフメトフスキー/サブリ・スレジマニ/リュビシャ・アジョヴィッチ/ジャセール・デスタニ/アドナン・ベキールストジャン・ソティロフ/ゼダ・ハルテカコヴァ/プレドラグ・ペピ・ラコビッチ/プレグラグ・ミキ・マノジョロビッチ●日本公開:1999/08●配給:フランス映画社(評価:★★★★)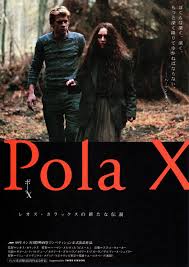
![ポーラX [DVD].jpg](http://hurec.bz/book-movie/%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%A9X%20%5BDVD%5D.jpg)

 変名で新人小説家として作品を発表したばかりの青年ピエール(ギヨーム・ドパルデュー)は、外交官だった父の亡き後、美しい母マリー(カトリーヌ・ドヌーヴ)と城館で何不自由なく暮らしていた。そんな彼の前に突然、異母姉と名乗る難民女性イザベル
変名で新人小説家として作品を発表したばかりの青年ピエール(ギヨーム・ドパルデュー)は、外交官だった父の亡き後、美しい母マリー(カトリーヌ・ドヌーヴ)と城館で何不自由なく暮らしていた。そんな彼の前に突然、異母姉と名乗る難民女性イザベル (カテリーナ・ベルゴワ)が現れる。彼女の出現で、前から渇望していた"この世を越える"きっかけを得たと感じたピエールは、母マリーも婚約者リュシー(
(カテリーナ・ベルゴワ)が現れる。彼女の出現で、前から渇望していた"この世を越える"きっかけを得たと感じたピエールは、母マリーも婚約者リュシー( デルフィーヌ・シェイヨー)も捨ててイザベルとパリヘ出る。パリで従兄のティボー(ローラン・リュカ)を訪ねるが、すげなく追い立てられ、やがて二人は音楽活動と武装訓練に余念がないアングラ集団が巣くう廃墟のロフトに棲み家を定める。二人はほどなくそこで結ばれ、創作活動に打ち込み始めたピエールだが、やがて母のバイク事故死とリュシーが病気であるとの報が入る。そのリュシーは、彼女を看病をしてくれたティボーの制止を振り切り、婚約者であることは秘されたまま、ピエールとイザベルの元に身を寄せるが―。
デルフィーヌ・シェイヨー)も捨ててイザベルとパリヘ出る。パリで従兄のティボー(ローラン・リュカ)を訪ねるが、すげなく追い立てられ、やがて二人は音楽活動と武装訓練に余念がないアングラ集団が巣くう廃墟のロフトに棲み家を定める。二人はほどなくそこで結ばれ、創作活動に打ち込み始めたピエールだが、やがて母のバイク事故死とリュシーが病気であるとの報が入る。そのリュシーは、彼女を看病をしてくれたティボーの制止を振り切り、婚約者であることは秘されたまま、ピエールとイザベルの元に身を寄せるが―。 レオス・カラックス監督の1999年の作品で、第52回カンヌ国際映画祭コンペティション部門正式出品作。「ボーイ・ミーツ・ガール」('83年)、「汚れた血」('86年)に続く連作の終止符として「ポンヌフの恋人」('91年)を撮ってから、レオス・カラックス監督の長編としては8年を経ての作品です。ハーマン・メルヴィルの『ピエール』(邦訳・『メルヴィル全集 第9巻』所収、国書刊行会)をベースに、舞台をフランスのノルマンディにしています。タイトルは原作の題名の仏語訳"Pierre ou les ambiguites"の頭文字に字"Pola"に解かれぬ謎を示すXを加えたものですが、映画に使われた10番目の草稿を示すローマ数字「Ⅹ」であるとも(従って、映画でポーラという人物が出てくるわけではない)。
レオス・カラックス監督の1999年の作品で、第52回カンヌ国際映画祭コンペティション部門正式出品作。「ボーイ・ミーツ・ガール」('83年)、「汚れた血」('86年)に続く連作の終止符として「ポンヌフの恋人」('91年)を撮ってから、レオス・カラックス監督の長編としては8年を経ての作品です。ハーマン・メルヴィルの『ピエール』(邦訳・『メルヴィル全集 第9巻』所収、国書刊行会)をベースに、舞台をフランスのノルマンディにしています。タイトルは原作の題名の仏語訳"Pierre ou les ambiguites"の頭文字に字"Pola"に解かれぬ謎を示すXを加えたものですが、映画に使われた10番目の草稿を示すローマ数字「Ⅹ」であるとも(従って、映画でポーラという人物が出てくるわけではない)。 主要な登場人物である男女が皆"神経症"乃至"分裂症"気味で、観ていて疲れました。主人公のピエールは、一緒に城館で暮らす母マリー(カトリーヌ・ドヌーヴが貫禄十分の演技)と「姉、弟」と呼び合う関係であるところから既に親子共々"危ない"印象を受けるし、自分の前に突然現れた異母姉イザベルとあっさり性愛関係になってしまうし(性愛を超えた魂の伴侶ということなのだろうが、男女の関係になるのもメルヴィルの原作通りなのか?)、後半のピエール、イザベル、リュシーの3人での生活はどうみても上手くいくはずもなく(ピエールは母親の遺産相続を拒否した挙句に金に困っているわけで、彼の諸々の行動には脈絡がない)、ラストは自殺未遂あり殺人ありのカタストロフィ的状況に。でも、これも"劇的"と言うより"劇画的"とでも言うか、ちょっと安易な終わり方のような気がしました(この結末もメルヴィルの原作通りなの?)。
主要な登場人物である男女が皆"神経症"乃至"分裂症"気味で、観ていて疲れました。主人公のピエールは、一緒に城館で暮らす母マリー(カトリーヌ・ドヌーヴが貫禄十分の演技)と「姉、弟」と呼び合う関係であるところから既に親子共々"危ない"印象を受けるし、自分の前に突然現れた異母姉イザベルとあっさり性愛関係になってしまうし(性愛を超えた魂の伴侶ということなのだろうが、男女の関係になるのもメルヴィルの原作通りなのか?)、後半のピエール、イザベル、リュシーの3人での生活はどうみても上手くいくはずもなく(ピエールは母親の遺産相続を拒否した挙句に金に困っているわけで、彼の諸々の行動には脈絡がない)、ラストは自殺未遂あり殺人ありのカタストロフィ的状況に。でも、これも"劇的"と言うより"劇画的"とでも言うか、ちょっと安易な終わり方のような気がしました(この結末もメルヴィルの原作通りなの?)。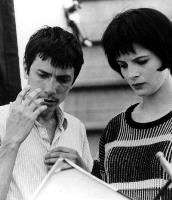 いて、"アレックス"と"カラックス"は語感が似ている)、この「ポーラX」はどうなの
いて、"アレックス"と"カラックス"は語感が似ている)、この「ポーラX」はどうなの でしょうか。「汚れた血」と「ポンヌフの恋人」でヒロインを演じたジュリエット・ビノシュとは実生活でも恋人同士であったのが、困難が多発し多額の費用と膨大な時間を要した「ポンヌフの恋人」の撮影中に破局し、「ポーラX」まで8年間レオス・カラックスの沈黙が続いたのは、彼女との破局が大きく影響していると言われています。でも、この作品を観ると、まだ何か引き摺っているよような...。結局、次の長編「ホーリー・モーターズ」('12年)を撮るまで更にまた10数年、長編は撮っていません(ハーモニー・コリン監督の「
でしょうか。「汚れた血」と「ポンヌフの恋人」でヒロインを演じたジュリエット・ビノシュとは実生活でも恋人同士であったのが、困難が多発し多額の費用と膨大な時間を要した「ポンヌフの恋人」の撮影中に破局し、「ポーラX」まで8年間レオス・カラックスの沈黙が続いたのは、彼女との破局が大きく影響していると言われています。でも、この作品を観ると、まだ何か引き摺っているよような...。結局、次の長編「ホーリー・モーターズ」('12年)を撮るまで更にまた10数年、長編は撮っていません(ハーモニー・コリン監督の「 主人公のピエールを演じたギヨーム・ドパルデューは、名優ジェラール・ドパルデューの息子で、この「ポーラX」の日本公開の時にレオス・カラックス監督らとともに来日していますが、2008年に急性肺炎のため37歳で急死しています。また、イザベルを演じたカテリーナ・ベルゴワはロシアのサンクトペテルブルク出身の女優ですが(レオス・カラックスにとって彼女との出会いが8年ぶりに映画を撮るきっかけになったとも言われる)、彼女も2011年にパリにて44歳で亡くなっており、「死因不明」とされています(自殺説あり)。
主人公のピエールを演じたギヨーム・ドパルデューは、名優ジェラール・ドパルデューの息子で、この「ポーラX」の日本公開の時にレオス・カラックス監督らとともに来日していますが、2008年に急性肺炎のため37歳で急死しています。また、イザベルを演じたカテリーナ・ベルゴワはロシアのサンクトペテルブルク出身の女優ですが(レオス・カラックスにとって彼女との出会いが8年ぶりに映画を撮るきっかけになったとも言われる)、彼女も2011年にパリにて44歳で亡くなっており、「死因不明」とされています(自殺説あり)。
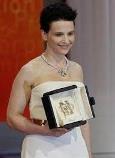 一方、レオス・カラックスと別れたジュリエット・ビノシュはその後、「トリコロール/青の愛」('93年)でヴェネツィア国際映画祭女優賞とセザール賞主演女優賞を受賞、「イングリッシュ・ペイシェント」('96年)でベルリン国際映画祭銀熊賞女優賞とアカデミー助演女優賞を受賞、「トスカーナの贋作」('10年)で第63回カンヌ国際映画祭女優賞を受賞と、世界三大映画祭の女優賞を受賞しており(三大映画祭の女優賞制覇は彼女が初で、ジュリアン・ムーアがこれに続いた)、やはりジュリエット・ビノシュを失ったのはレオス・カラックスにとっては大きかったのではないかと思わざるをえません。
一方、レオス・カラックスと別れたジュリエット・ビノシュはその後、「トリコロール/青の愛」('93年)でヴェネツィア国際映画祭女優賞とセザール賞主演女優賞を受賞、「イングリッシュ・ペイシェント」('96年)でベルリン国際映画祭銀熊賞女優賞とアカデミー助演女優賞を受賞、「トスカーナの贋作」('10年)で第63回カンヌ国際映画祭女優賞を受賞と、世界三大映画祭の女優賞を受賞しており(三大映画祭の女優賞制覇は彼女が初で、ジュリアン・ムーアがこれに続いた)、やはりジュリエット・ビノシュを失ったのはレオス・カラックスにとっては大きかったのではないかと思わざるをえません。
 高く評価する人もいる作品ですが(その気持ちも分からなくもない)、個人的にはやはり、この"神経症"&"分裂症"的な暗さと、ラストの急展開にややついていけなかったでしょうか。カトリーヌ・ドヌーヴ演じるマリーの自殺とも思えるバイク事故死は、ピエール喪失感によるものなのか。ピエールを巡る"四角関係"の話だったのか。その辺りもよく分からなかったです。
高く評価する人もいる作品ですが(その気持ちも分からなくもない)、個人的にはやはり、この"神経症"&"分裂症"的な暗さと、ラストの急展開にややついていけなかったでしょうか。カトリーヌ・ドヌーヴ演じるマリーの自殺とも思えるバイク事故死は、ピエール喪失感によるものなのか。ピエールを巡る"四角関係"の話だったのか。その辺りもよく分からなかったです。 「ポーラX」●原題:POLA X●制作年:1999年●制作国:フランス・ドイツ・日本・スイス●監督:レオス・カラックス●製作:ブリュノ・ペズリー●脚本:レオス・カラックス/ジャン・ポール・ファルゴー/ローラン・セドフスキー●撮影:エリック・ゴーティエ●音楽:スコット・ウォーカー●原作:ハーマン・メルヴィル「ピエール」●時間:134分●出演:ギョーム・ドパルデュー/カテリーナ・ゴルベワ/カトリーヌ・ドヌーヴ/デルフィーヌ・シェイヨー/ローラン・リュカ/パタシュー/ペトルータ・カターナ/ミハエラ・シラギ●日本公開:1999/10●配給:ユーロスペース●最初に観た場所:北千住・シネマブルースタジオ(18-03-30)(評価:★★★)
「ポーラX」●原題:POLA X●制作年:1999年●制作国:フランス・ドイツ・日本・スイス●監督:レオス・カラックス●製作:ブリュノ・ペズリー●脚本:レオス・カラックス/ジャン・ポール・ファルゴー/ローラン・セドフスキー●撮影:エリック・ゴーティエ●音楽:スコット・ウォーカー●原作:ハーマン・メルヴィル「ピエール」●時間:134分●出演:ギョーム・ドパルデュー/カテリーナ・ゴルベワ/カトリーヌ・ドヌーヴ/デルフィーヌ・シェイヨー/ローラン・リュカ/パタシュー/ペトルータ・カターナ/ミハエラ・シラギ●日本公開:1999/10●配給:ユーロスペース●最初に観た場所:北千住・シネマブルースタジオ(18-03-30)(評価:★★★)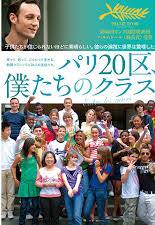


 新学年を迎えた。移民も多いこのクラスの生徒たちは、出身国、生い立ち、将来の夢もみんな異なる。フランソワは語尾変化もを書けない生徒たちに正しく美しいフランス語を教えようとするが、スラングに
新学年を迎えた。移民も多いこのクラスの生徒たちは、出身国、生い立ち、将来の夢もみんな異なる。フランソワは語尾変化もを書けない生徒たちに正しく美しいフランス語を教えようとするが、スラングに 慣れた生徒たちは接続法半過去など文語で金持ちの言葉だと反発する。しかし、フランソワは国語を、生きるための言葉を学ぶこと、他人とのコミュニケーションを学び、社会で生き抜く手段を身につけることだと考えている。そこで「アンネの日記」を読ませた後に、生徒たちに自己紹介文を書かせる。最初は高圧的だったフランソワも、彼らとの何気ない対話の一つ一つが授業であり、真剣勝負ということが分かり、24人の生徒に真正面から対峙し、悩んだり葛藤する―。
慣れた生徒たちは接続法半過去など文語で金持ちの言葉だと反発する。しかし、フランソワは国語を、生きるための言葉を学ぶこと、他人とのコミュニケーションを学び、社会で生き抜く手段を身につけることだと考えている。そこで「アンネの日記」を読ませた後に、生徒たちに自己紹介文を書かせる。最初は高圧的だったフランソワも、彼らとの何気ない対話の一つ一つが授業であり、真剣勝負ということが分かり、24人の生徒に真正面から対峙し、悩んだり葛藤する―。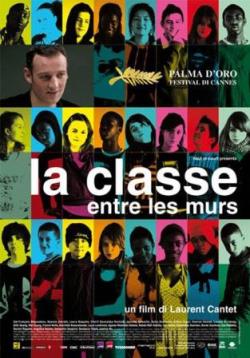
 2008年のローラン・カンテ監督作で、2008年・第61回カンヌ国際映画祭で、純粋なフランスの映画としては「悪魔の陽の下に」('87年/仏)以来21年ぶりとなるパルム・ドール受賞作となりました。審査委員長のショーン・ペンは「作品は完璧に一体化されている。演技、脚本、挑発、寛大さすべてが魔法だ」と評しています。原作は、フランソワ・ベゴドーが実体験に基づいて2006年に発表した小説『教室へ』(早川書房)であり、そのフランソワ・ベゴドー自身が脚本及び主演を務めています(フランソワ・ベゴドーの本職はあくまで作家であり、映画出演はこの作品のみ)。
2008年のローラン・カンテ監督作で、2008年・第61回カンヌ国際映画祭で、純粋なフランスの映画としては「悪魔の陽の下に」('87年/仏)以来21年ぶりとなるパルム・ドール受賞作となりました。審査委員長のショーン・ペンは「作品は完璧に一体化されている。演技、脚本、挑発、寛大さすべてが魔法だ」と評しています。原作は、フランソワ・ベゴドーが実体験に基づいて2006年に発表した小説『教室へ』(早川書房)であり、そのフランソワ・ベゴドー自身が脚本及び主演を務めています(フランソワ・ベゴドーの本職はあくまで作家であり、映画出演はこの作品のみ)。

 勿論、この作品は、日本における中学校等の"学級崩壊"問題と対比させて観ることも可能で、そこから色々な示唆も得られるかもしれません。しかし、一方で、フランス特有の移民社会の問題とそこから派生する生活や教育の格差の問題を分かりやすく反映させたものでもあります(しかしながらその解決は大変難しい)。一説には、カンヌ国際映画祭でパルム・ドールを受賞した背後には、「排除」の問題がフランスで重要な問題になっていたという事情があったと言われています。映画の中でスレイマンという少年が行きがかりから先生に暴言を吐いたことにより、退学処分になるという結果を招きますが、彼が退学になることで学校側は規律を保つことになり、退学になった彼は新たな転校先で受け入れられる―或いはフランソワ先生が危惧するように彼の父親(映画には姿を見せない)によってアフリカの故国に送り還される―ということでいいのだろうか、という問題提起がなされているように思いました。ラストもいわばアンチクライマックスで、"感動作"と言うより"考えさせられる映画"です。
勿論、この作品は、日本における中学校等の"学級崩壊"問題と対比させて観ることも可能で、そこから色々な示唆も得られるかもしれません。しかし、一方で、フランス特有の移民社会の問題とそこから派生する生活や教育の格差の問題を分かりやすく反映させたものでもあります(しかしながらその解決は大変難しい)。一説には、カンヌ国際映画祭でパルム・ドールを受賞した背後には、「排除」の問題がフランスで重要な問題になっていたという事情があったと言われています。映画の中でスレイマンという少年が行きがかりから先生に暴言を吐いたことにより、退学処分になるという結果を招きますが、彼が退学になることで学校側は規律を保つことになり、退学になった彼は新たな転校先で受け入れられる―或いはフランソワ先生が危惧するように彼の父親(映画には姿を見せない)によってアフリカの故国に送り還される―ということでいいのだろうか、という問題提起がなされているように思いました。ラストもいわばアンチクライマックスで、"感動作"と言うより"考えさせられる映画"です。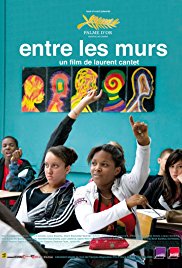
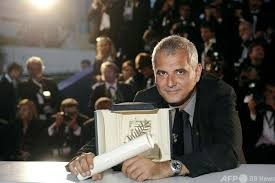 【4月26日 AFP】カンヌ映画祭(Cannes Film Festival)の最高賞受賞経験もあるフランス人映画監督ローラン・カンテ(Laurent Cantet)氏が25日、死去した。63歳だった。
【4月26日 AFP】カンヌ映画祭(Cannes Film Festival)の最高賞受賞経験もあるフランス人映画監督ローラン・カンテ(Laurent Cantet)氏が25日、死去した。63歳だった。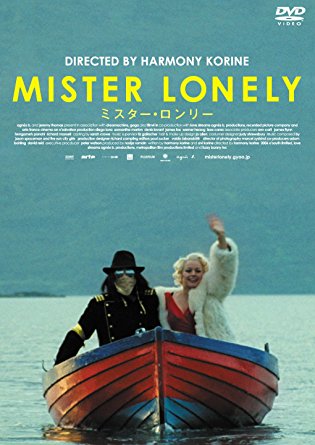
 大道芸人のマイケル(ディエゴ・ルナ)はマ
大道芸人のマイケル(ディエゴ・ルナ)はマ イケル・ジャクソンのインパーソネーターとしてパリの路上で生計を立てるも、一向に生活が苦しくなるばかり。ある時、マリリン・モンローのような彼女(サマンサ・モートン)に出会う。彼女もマイケルと同じインパーソネーターであり、不器用で有名人になりきる事でしか生きられないのだった。そんな彼女に惹かれたマイケルはある日、彼女からスコットランドの古城に誘われる。そこには自分たちと同じようになりきる事でしか生きられない、様々なインパーソネーターたちによるコミュニティがあった。チャップリン、マドンナ、リンカーン大統領、ローマ法王、エリザベス女王、サミー・デイヴィスJr.、ジェームズ・ディーン、シャーリー・テンプルなどがいる夢のような理想郷だったが―。
イケル・ジャクソンのインパーソネーターとしてパリの路上で生計を立てるも、一向に生活が苦しくなるばかり。ある時、マリリン・モンローのような彼女(サマンサ・モートン)に出会う。彼女もマイケルと同じインパーソネーターであり、不器用で有名人になりきる事でしか生きられないのだった。そんな彼女に惹かれたマイケルはある日、彼女からスコットランドの古城に誘われる。そこには自分たちと同じようになりきる事でしか生きられない、様々なインパーソネーターたちによるコミュニティがあった。チャップリン、マドンナ、リンカーン大統領、ローマ法王、エリザベス女王、サミー・デイヴィスJr.、ジェームズ・ディーン、シャーリー・テンプルなどがいる夢のような理想郷だったが―。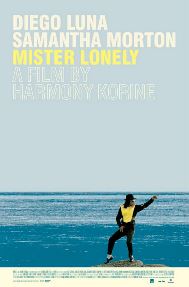 「KIDS/キッズ」('95年)の脚本で世界中にセンセーショナルを巻き起こし、その後「ガンモ」('97年)や「ジュリアン」('99年)などで映画監督として活躍してきた(共に脚本も担当)ハーモニー・コリンによる2007年の監督作で、
「KIDS/キッズ」('95年)の脚本で世界中にセンセーショナルを巻き起こし、その後「ガンモ」('97年)や「ジュリアン」('99年)などで映画監督として活躍してきた(共に脚本も担当)ハーモニー・コリンによる2007年の監督作で、 更には、マイケルを演じたディエゴ・ルナはメキシコ出身の俳優、マリリンを演じたサマンサ・モートンは英国出身(「
更には、マイケルを演じたディエゴ・ルナはメキシコ出身の俳優、マリリンを演じたサマンサ・モートンは英国出身(「 北千住のシネマブルースタジオで「自分の人生を生きる 特集」のラストを締め括る1本として上映されたのを観ましたが、この作品が最も特集のタイトルに沿っていました。主人公はマイケル・ジャクソンに憧れ、焦がれ、いつしか「マイケル」としてしか生きられなくなってしまってアイデンティティを見失い、日々ストリート・パフォーマーとして物真似をしながら生きている孤独な若者であり、そんな彼がマリリン・モンローのインパーソネーターと出会って、彼女の導きでコミュニティを訪れます。
北千住のシネマブルースタジオで「自分の人生を生きる 特集」のラストを締め括る1本として上映されたのを観ましたが、この作品が最も特集のタイトルに沿っていました。主人公はマイケル・ジャクソンに憧れ、焦がれ、いつしか「マイケル」としてしか生きられなくなってしまってアイデンティティを見失い、日々ストリート・パフォーマーとして物真似をしながら生きている孤独な若者であり、そんな彼がマリリン・モンローのインパーソネーターと出会って、彼女の導きでコミュニティを訪れます。
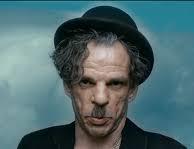 当初は理想郷のようにも思えたコミュニ>ティでしたが、次第にそうでもないらしことが窺えるようになります。そこにいる"他者としてしか生きられない"インパーソネーターたちは常に神経症的であり、コミュニティがある種ヘイブン(避難所)乃至サナトリウ
当初は理想郷のようにも思えたコミュニ>ティでしたが、次第にそうでもないらしことが窺えるようになります。そこにいる"他者としてしか生きられない"インパーソネーターたちは常に神経症的であり、コミュニティがある種ヘイブン(避難所)乃至サナトリウ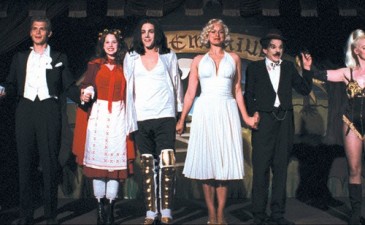 ム(療養所)のような機能を果たしているようにも見えます。彼らは、メンバー総出演の「史上最大のショー」を企画しますが、実施されたショーは、楽しいものというより、インパーソネーターがひたむきさに演じれば演じるほど、彼らの哀しみが滲み出てくるようなものでした(チャップリンのインパーソネーターが演じたのは「
ム(療養所)のような機能を果たしているようにも見えます。彼らは、メンバー総出演の「史上最大のショー」を企画しますが、実施されたショーは、楽しいものというより、インパーソネーターがひたむきさに演じれば演じるほど、彼らの哀しみが滲み出てくるようなものでした(チャップリンのインパーソネーターが演じたのは「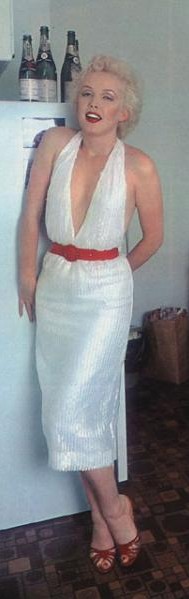
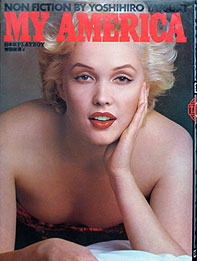

 タイトル通りの「ミスター・ロンリー」の曲がオープニングシーンからよくマッチしています。予告編のキャッチは「かりものの人生の、ほんものの幸せ」。月並みですが、人は皆、いつか自らの孤独と向き合わなければならない時が来るといったところでしょうか。たとえ、コミュニティで"永遠の子供"のように暮らしていたとしても。但し、ハーモニー・コリン監督は、コミュニティに残るの者や死んでいった者
タイトル通りの「ミスター・ロンリー」の曲がオープニングシーンからよくマッチしています。予告編のキャッチは「かりものの人生の、ほんものの幸せ」。月並みですが、人は皆、いつか自らの孤独と向き合わなければならない時が来るといったところでしょうか。たとえ、コミュニティで"永遠の子供"のように暮らしていたとしても。但し、ハーモニー・コリン監督は、コミュニティに残るの者や死んでいった者 にも、暖かい視線を注いでいるように思えました。いい映画でしたが、ところどころで挿入されるノン・パラシュートでスカイダイビングする修道院のシスターたちの"奇跡"と"悲劇"のエピソードは、やや寓話的すぎて理解しにくかったでしょうか(ヴェルナー・ヘルツォークが神父役で出ている)。
にも、暖かい視線を注いでいるように思えました。いい映画でしたが、ところどころで挿入されるノン・パラシュートでスカイダイビングする修道院のシスターたちの"奇跡"と"悲劇"のエピソードは、やや寓話的すぎて理解しにくかったでしょうか(ヴェルナー・ヘルツォークが神父役で出ている)。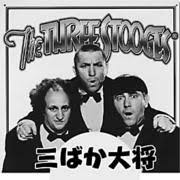



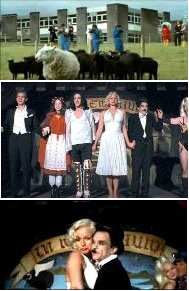 「ミスター・ロンリー」●原題:MISTER LONELY●制作年:2007年●制作国:イギリス・フランス・アメリカ●監督:ハーモニー・コリン●製作:ナージャ・ロメイン●脚本:ハーモニー・コリン/アヴィ・コーリン●撮影:マルセル・ザイスキンド●音楽:ジェイソン・スペースマン/サン・シティ・ガールズ(イメージソング:「ミスター・ロンリー」(1964年発売)ボビー・ヴィントン)●時間:1
「ミスター・ロンリー」●原題:MISTER LONELY●制作年:2007年●制作国:イギリス・フランス・アメリカ●監督:ハーモニー・コリン●製作:ナージャ・ロメイン●脚本:ハーモニー・コリン/アヴィ・コーリン●撮影:マルセル・ザイスキンド●音楽:ジェイソン・スペースマン/サン・シティ・ガールズ(イメージソング:「ミスター・ロンリー」(1964年発売)ボビー・ヴィントン)●時間:1 11分●出演:ディエゴ・ルナ/サマンサ・モートン/ドニ・ラヴァン
11分●出演:ディエゴ・ルナ/サマンサ・モートン/ドニ・ラヴァン /
/ サマンサ・モートン in 「
サマンサ・モートン in 「
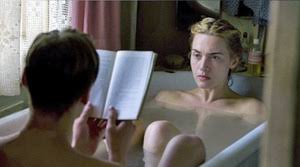
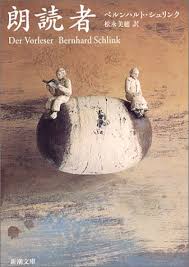
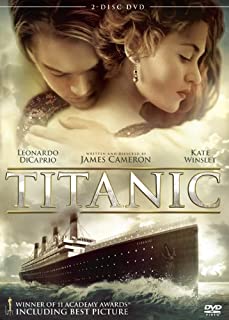
 第二次世界大戦後のドイツ。15歳のマイケル(ダフィット・クロス)は、体調が優れず気分が悪かった自分を偶然助けてくれた21歳も年上の女性ハンナ(ケイト・ウィンスレット)と知り合う。猩紅熱にかかったマイケルは、回復後に毎日のように彼女のアパートに通い、いつしか彼女と男女の関係になる。ハンナはマイケ
第二次世界大戦後のドイツ。15歳のマイケル(ダフィット・クロス)は、体調が優れず気分が悪かった自分を偶然助けてくれた21歳も年上の女性ハンナ(ケイト・ウィンスレット)と知り合う。猩紅熱にかかったマイケルは、回復後に毎日のように彼女のアパートに通い、いつしか彼女と男女の関係になる。ハンナはマイケ ルが本を沢山読む子だと知り、本の朗読を頼むようになる。彼はハンナのために『オデュッセイア』や『犬を連れた奥さん』などを朗読する。ある日、ハンナは働いていた市鉄での働きぶりを評価され、事務職への昇進を言い渡されると、マイケルの前から姿を消
ルが本を沢山読む子だと知り、本の朗読を頼むようになる。彼はハンナのために『オデュッセイア』や『犬を連れた奥さん』などを朗読する。ある日、ハンナは働いていた市鉄での働きぶりを評価され、事務職への昇進を言い渡されると、マイケルの前から姿を消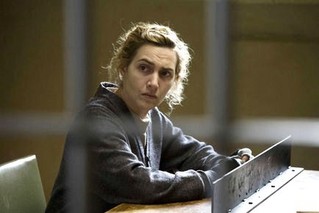 してしまう。理由がわからずにハンナに捨てられて8年が経ったある日、ハイデルベルク大学法学部生となったマイケルは、ロール教授(ブルーノ・ガンツ)のゼミ研究のためにナチスの戦犯を裁くアウシュビッツ裁判を傍聴し、被告席の一つにハンナの姿を見つける。彼女は第二次世界大戦中に強制収容所で看守をしていたのである。裁判はハンナに不利に進み、彼女は無期懲役の判決を受ける―。
してしまう。理由がわからずにハンナに捨てられて8年が経ったある日、ハイデルベルク大学法学部生となったマイケルは、ロール教授(ブルーノ・ガンツ)のゼミ研究のためにナチスの戦犯を裁くアウシュビッツ裁判を傍聴し、被告席の一つにハンナの姿を見つける。彼女は第二次世界大戦中に強制収容所で看守をしていたのである。裁判はハンナに不利に進み、彼女は無期懲役の判決を受ける―。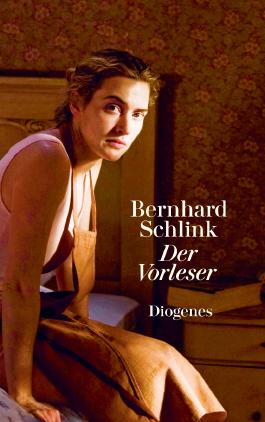
 2008年のアメリカ・ドイツ合作映画で、監督は英国人のスティーブン・ダルドリー、原作は1995年に出版されたベルンハルト・シュリンク(Bernhard Schlink)の長編小説『朗読者』('00年/新潮社、原題:Der Vorleser/The Reader)です。映画は(終盤に主人公がニューヨークへ行く場面を除き)ドイツで撮影されていますが、英語による製作であるため、主人公の名前も、原作のミヒャエルからマイケルになっています。但し、少年時代のマイケルを演じたダフィット・クロスはドイツの俳優、母親を演じたズザンネ・ロータもドイツ人女優、法学部のロール教授はスイス出身のブルーノ・ガンツが演じていてます。ハンナ役のケイト・ウィンスレットは英国人女優、成人してからのマイケルを演じたレイフ・ファインズも英国人俳優、アウシュヴィッツの生存者母子ローゼ・マーターとイラーナ・マーターの二役を演じたレナ・オリンはスウェーデン出身、若き日のイラーナを演じたアレクサンドラ・マリア・ララはルーマニア人、成人したマイケルの娘を演じたハンナー・ヘルツシュプルングは、これまたドイツ人女優です(アメリカ人、いないね)。
2008年のアメリカ・ドイツ合作映画で、監督は英国人のスティーブン・ダルドリー、原作は1995年に出版されたベルンハルト・シュリンク(Bernhard Schlink)の長編小説『朗読者』('00年/新潮社、原題:Der Vorleser/The Reader)です。映画は(終盤に主人公がニューヨークへ行く場面を除き)ドイツで撮影されていますが、英語による製作であるため、主人公の名前も、原作のミヒャエルからマイケルになっています。但し、少年時代のマイケルを演じたダフィット・クロスはドイツの俳優、母親を演じたズザンネ・ロータもドイツ人女優、法学部のロール教授はスイス出身のブルーノ・ガンツが演じていてます。ハンナ役のケイト・ウィンスレットは英国人女優、成人してからのマイケルを演じたレイフ・ファインズも英国人俳優、アウシュヴィッツの生存者母子ローゼ・マーターとイラーナ・マーターの二役を演じたレナ・オリンはスウェーデン出身、若き日のイラーナを演じたアレクサンドラ・マリア・ララはルーマニア人、成人したマイケルの娘を演じたハンナー・ヘルツシュプルングは、これまたドイツ人女優です(アメリカ人、いないね)。 先に原作を読みましたが、かつて齋藤美奈子氏が「包茎小説」と呼んでいたのを思い出しました。15歳のミヒャエルと21歳年上のハンナが出会い、男女の関係を持って別れるまでを描いた第1章だけならば、確かに"筆おろし"小説と言えなくもなく、元判事で法学部教授である作者がこういうの書くのが興味深いと思いました。しかし、第2章の裁判の場面はまさにキャリアに裏打ちされたもので、作品に深みを与えることにも繋がっているように思いました。小説はこれに、裁判以降の主人公とハンナの話を描いた第3章を加えた3つの章から成ります。
先に原作を読みましたが、かつて齋藤美奈子氏が「包茎小説」と呼んでいたのを思い出しました。15歳のミヒャエルと21歳年上のハンナが出会い、男女の関係を持って別れるまでを描いた第1章だけならば、確かに"筆おろし"小説と言えなくもなく、元判事で法学部教授である作者がこういうの書くのが興味深いと思いました。しかし、第2章の裁判の場面はまさにキャリアに裏打ちされたもので、作品に深みを与えることにも繋がっているように思いました。小説はこれに、裁判以降の主人公とハンナの話を描いた第3章を加えた3つの章から成ります。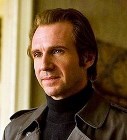
 一方の映画の方は、1995年の主人公マイケルの「現在」を軸に、1958年の15歳の時にハンナと出会った少年期、1966年のハンナの裁判を偶然傍聴することになった法学部生
一方の映画の方は、1995年の主人公マイケルの「現在」を軸に、1958年の15歳の時にハンナと出会った少年期、1966年のハンナの裁判を偶然傍聴することになった法学部生 時代、1976年のマイケルが本を朗読しテープに録音して、それを獄中のハンナに送ることを思いついた時期、1980年のハンナから届いた短い文章の礼状にマイケルが感動した出来事、1988年の20年の刑に減刑されたハンナが釈放されることが決まった時などとの
時代、1976年のマイケルが本を朗読しテープに録音して、それを獄中のハンナに送ることを思いついた時期、1980年のハンナから届いた短い文章の礼状にマイケルが感動した出来事、1988年の20年の刑に減刑されたハンナが釈放されることが決まった時などとの 間を行き来する形をとっていますが、概ね原作に忠実であるといっていいでしょう(マイケルが離婚して娘となかなか会えないでいるといった現況は映画のオリジナル。あとは、ブルーノ・ガンツ演じる教授のウェイトが原作より大きくなって、主人公に精神的に導き支えるという点で、原作における主人公の父親である哲学教授の役割を一部代替していたりする)。
間を行き来する形をとっていますが、概ね原作に忠実であるといっていいでしょう(マイケルが離婚して娘となかなか会えないでいるといった現況は映画のオリジナル。あとは、ブルーノ・ガンツ演じる教授のウェイトが原作より大きくなって、主人公に精神的に導き支えるという点で、原作における主人公の父親である哲学教授の役割を一部代替していたりする)。 原作でも言えるのは、ハンナが幾つか謎を抱えている女性であるという点であり、①なぜマイケルと交わるようになったのか?(単なる気まぐれ?)、②なぜ裁判で不利になることを承知で自らの"秘密"を明かさなかったのか?(主人公がその"秘密"に気づく場面は、ミステリの謎が明かされるようで、原作でも映画でも白眉)、③そして最後に彼女がとった行動の理由は?―等々。映画を観て、①の理由は、マイケルが彼女にとっての癒しとなる"朗読者"であり、自らを成長させるパートナーであったことが窺えましたが
原作でも言えるのは、ハンナが幾つか謎を抱えている女性であるという点であり、①なぜマイケルと交わるようになったのか?(単なる気まぐれ?)、②なぜ裁判で不利になることを承知で自らの"秘密"を明かさなかったのか?(主人公がその"秘密"に気づく場面は、ミステリの謎が明かされるようで、原作でも映画でも白眉)、③そして最後に彼女がとった行動の理由は?―等々。映画を観て、①の理由は、マイケルが彼女にとっての癒しとなる"朗読者"であり、自らを成長させるパートナーであったことが窺えましたが

 こうした"秘密"を持つ女性を演じるのは難しいだろうなあと思いますが、それだけ魅力的でもあり、ケイト・ウィンスレット(1975年生まれ)はそこに上手く嵌ったように思います(ニコール・キッドマンが妊娠で降板し、当初の候補だったケイト・ウィンスレットが結局演じることになった)。ケイト・ウィンスレットは、この作品で「タイタニック」('97年)以来4度目のアカデミー賞主演女優賞ノミネート(「助演賞」ノミネートを含むと6度目)にして、初の受賞を果たしています。「タイタニック」で共演したレオナルド・ディカプリオ(1974年生まれ)も、「レヴェナント:蘇えりし者」('15年)で4度目のアカデミー賞主演男優賞ノミネート(「助演賞」ノミネートを含むと5度目)にして初受賞していますが、若い頃から演技の天才などと呼ばれたレオナルド・デカプリオよりもケイト・ウィンスレットの方が受賞は7年早かったことになります。
こうした"秘密"を持つ女性を演じるのは難しいだろうなあと思いますが、それだけ魅力的でもあり、ケイト・ウィンスレット(1975年生まれ)はそこに上手く嵌ったように思います(ニコール・キッドマンが妊娠で降板し、当初の候補だったケイト・ウィンスレットが結局演じることになった)。ケイト・ウィンスレットは、この作品で「タイタニック」('97年)以来4度目のアカデミー賞主演女優賞ノミネート(「助演賞」ノミネートを含むと6度目)にして、初の受賞を果たしています。「タイタニック」で共演したレオナルド・ディカプリオ(1974年生まれ)も、「レヴェナント:蘇えりし者」('15年)で4度目のアカデミー賞主演男優賞ノミネート(「助演賞」ノミネートを含むと5度目)にして初受賞していますが、若い頃から演技の天才などと呼ばれたレオナルド・デカプリオよりもケイト・ウィンスレットの方が受賞は7年早かったことになります。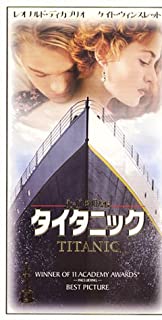 「タイタニック」の興行収入は、全米で6.6億ドル、日本で262.0億円(配給収入160.0億円)、全世界で21.9億ドルに達し、「ジュラシック・パーク」('93年)を抜いて当時の世界最高興行収入を記録し、この記録は同じジェームズ・キャメロン監督作品の「アバター」('09年)に抜かれるまで保持され、日本でも「もののけ姫」('97年)を抜いて日本歴代興行収入記録を更新し、「千と千尋の神隠し」('01年)に抜かれるまで記録を保持していました。逆に、これほどヒットすると劇場に観に行かなかったりして、結局ビデオで観てしまいましたが、「アビス」('89年)の監督によるCG映画だと思って軽く見ていてのが、結構ドラマ部分もしっかりしていて、事前の予想よりも良かったです。
「タイタニック」の興行収入は、全米で6.6億ドル、日本で262.0億円(配給収入160.0億円)、全世界で21.9億ドルに達し、「ジュラシック・パーク」('93年)を抜いて当時の世界最高興行収入を記録し、この記録は同じジェームズ・キャメロン監督作品の「アバター」('09年)に抜かれるまで保持され、日本でも「もののけ姫」('97年)を抜いて日本歴代興行収入記録を更新し、「千と千尋の神隠し」('01年)に抜かれるまで記録を保持していました。逆に、これほどヒットすると劇場に観に行かなかったりして、結局ビデオで観てしまいましたが、「アビス」('89年)の監督によるCG映画だと思って軽く見ていてのが、結構ドラマ部分もしっかりしていて、事前の予想よりも良かったです。


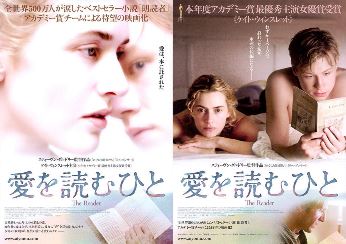 「愛を読むひと」●原題:THE READER●制作年:2008年●制作国:アメリカ・ドイツ●監督:スティーブン・ダルドリー●製作:アンソニー・ミンゲラ/
「愛を読むひと」●原題:THE READER●制作年:2008年●制作国:アメリカ・ドイツ●監督:スティーブン・ダルドリー●製作:アンソニー・ミンゲラ/
 「タイタニック」●原題:TITANIC●制作年:1997年●制作国:アメリカ●監督・脚本:ジェームズ・キャメロン●製作:ジェームズ・キャメロン/ジョン・ランドー●撮影:ラッセ
「タイタニック」●原題:TITANIC●制作年:1997年●制作国:アメリカ●監督・脚本:ジェームズ・キャメロン●製作:ジェームズ・キャメロン/ジョン・ランドー●撮影:ラッセ ル・カーペンター●音楽:ジェームズ・ホーナー(主題歌:セリーヌ・ディオン「マイ・ハート・ウィル・ゴー・オン」●時間:194分●出演:レオナルド・ディカプリオ/ケイト・ウィンスレット/ビリー・ゼイン /デビッド・ワーナー/フランシス・フィッシャー/ダニー・ヌッチ/ジェイソン・ベリー/エイミー・ガイバ/ビル・パクストン/グロリア・スチュアート/ス
ル・カーペンター●音楽:ジェームズ・ホーナー(主題歌:セリーヌ・ディオン「マイ・ハート・ウィル・ゴー・オン」●時間:194分●出演:レオナルド・ディカプリオ/ケイト・ウィンスレット/ビリー・ゼイン /デビッド・ワーナー/フランシス・フィッシャー/ダニー・ヌッチ/ジェイソン・ベリー/エイミー・ガイバ/ビル・パクストン/グロリア・スチュアート/ス ージー・エイミス/ルイス・アバナシー/キャシー・ベイツ/バーナード・ヒル /ジョナサン・ハイド/ヴィクター・ガーバー/マーク・リンゼイ・チャップマン/ヨアン・グリフィズ/エドワード・フレッチャー /エリック・ブレーデン/マイケル・エンサイン/バーナード・フォックス/●日本公開:1997/12●配給:20世紀フォックス(評価★★★★)
ージー・エイミス/ルイス・アバナシー/キャシー・ベイツ/バーナード・ヒル /ジョナサン・ハイド/ヴィクター・ガーバー/マーク・リンゼイ・チャップマン/ヨアン・グリフィズ/エドワード・フレッチャー /エリック・ブレーデン/マイケル・エンサイン/バーナード・フォックス/●日本公開:1997/12●配給:20世紀フォックス(評価★★★★)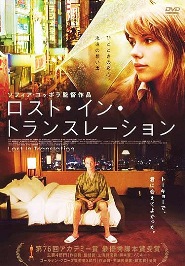
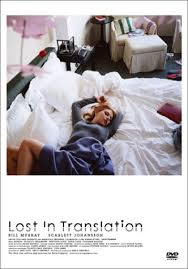

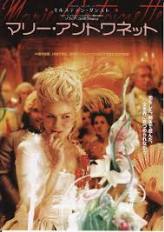
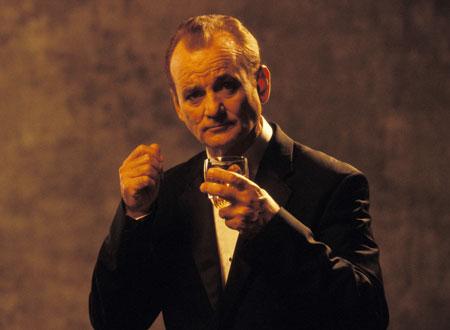 サントリーウイスキーのテレビCMに200万ドルで出演するために来日した年配のハリウッド俳優ボブ・ハリス(ビル・マーレイ)は、異国で言葉も通じず孤独を感じていた。同じホテルに滞在していた
サントリーウイスキーのテレビCMに200万ドルで出演するために来日した年配のハリウッド俳優ボブ・ハリス(ビル・マーレイ)は、異国で言葉も通じず孤独を感じていた。同じホテルに滞在していた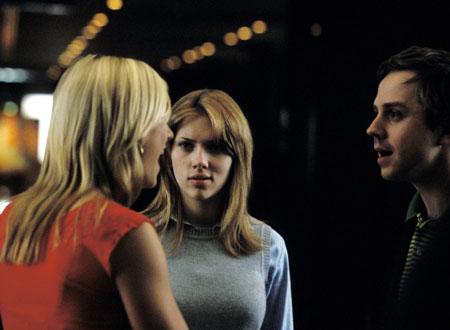 シャーロット(スカーレット・ヨハンソン)は大学を卒業したてで結婚したばかりだが、セレブ写真家の夫ジョン(ジョバンニ・リビシ)は仕事に忙しく、彼女もボブと同じく孤独だった。シャーロットは夫が自分よりも、若く人気のある女優ケリー(アンナ・ファリス)のようなセレブなモデルに興味があるのではないかと不安を抱く。ボブの方は、長年の夫婦生活に疲れ、"中年の危機"にある。ある晩、長時間の撮影を終え、ホテルのバーで
シャーロット(スカーレット・ヨハンソン)は大学を卒業したてで結婚したばかりだが、セレブ写真家の夫ジョン(ジョバンニ・リビシ)は仕事に忙しく、彼女もボブと同じく孤独だった。シャーロットは夫が自分よりも、若く人気のある女優ケリー(アンナ・ファリス)のようなセレブなモデルに興味があるのではないかと不安を抱く。ボブの方は、長年の夫婦生活に疲れ、"中年の危機"にある。ある晩、長時間の撮影を終え、ホテルのバーで 疲れを癒していたボブに、ジョンや友人達といたシャーロットが気づき、ウエイターに日本酒を渡してもらう。2人はホテル内で顔を合わせる内に親しくなる。シャーロットは日本の友人に会う時にボブを誘い、二人は共に日米の文化の違い、世代間のギャップを経験しながら
疲れを癒していたボブに、ジョンや友人達といたシャーロットが気づき、ウエイターに日本酒を渡してもらう。2人はホテル内で顔を合わせる内に親しくなる。シャーロットは日本の友人に会う時にボブを誘い、二人は共に日米の文化の違い、世代間のギャップを経験しながら 東京の夜を冒険する。ボブが発つ前々夜、彼はホテルのバーのバンド歌手にアプローチされ、翌朝目を覚ますと彼女が部屋にいて、どうやら一夜を共にしたらしい。シャーロットがボブを朝食に誘いに部屋に行くとその女性がいたため、しゃぶしゃぶの昼食時の空気が悪くなる。その夜、ホテルの火災報知機が鳴るアクシデントがあり、ボブとシャーロットはお互いが寂しかったことを伝えて和解する。そして翌朝、ボブは米国へ帰ることになっていた―。
東京の夜を冒険する。ボブが発つ前々夜、彼はホテルのバーのバンド歌手にアプローチされ、翌朝目を覚ますと彼女が部屋にいて、どうやら一夜を共にしたらしい。シャーロットがボブを朝食に誘いに部屋に行くとその女性がいたため、しゃぶしゃぶの昼食時の空気が悪くなる。その夜、ホテルの火災報知機が鳴るアクシデントがあり、ボブとシャーロットはお互いが寂しかったことを伝えて和解する。そして翌朝、ボブは米国へ帰ることになっていた―。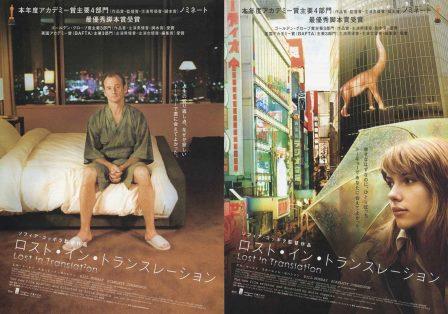 2003年公開の「ロスト・イン・トランスレーション」は、ソフィア・コッポラ監督の、ジェフリー・ユージェニデスの『ヘビトンボの季節に自殺した五人姉妹』('01年/ハヤカワepi文庫)を原作とする「ヴァージン・スーサイズ」('99年)に次ぐ第2作で、400万ドルの少予算と27日間で撮影されたこの作品は、本国で4400万ドルの興業収入という成功を収め、2004年のゴールデングローブ賞の脚本賞(ソフィア・コッポラ)、ミュージカル・コメディ部門の作品賞、同主演男優賞(ビル・マーレイ)の3部門で受賞、アカデミー賞では主要4部門(作品賞・監督賞・主演男優賞・オリジナル脚本賞)にノミネートされて脚本賞を受賞し、
2003年公開の「ロスト・イン・トランスレーション」は、ソフィア・コッポラ監督の、ジェフリー・ユージェニデスの『ヘビトンボの季節に自殺した五人姉妹』('01年/ハヤカワepi文庫)を原作とする「ヴァージン・スーサイズ」('99年)に次ぐ第2作で、400万ドルの少予算と27日間で撮影されたこの作品は、本国で4400万ドルの興業収入という成功を収め、2004年のゴールデングローブ賞の脚本賞(ソフィア・コッポラ)、ミュージカル・コメディ部門の作品賞、同主演男優賞(ビル・マーレイ)の3部門で受賞、アカデミー賞では主要4部門(作品賞・監督賞・主演男優賞・オリジナル脚本賞)にノミネートされて脚本賞を受賞し、 新宿のパークハイアットホテルのスィート・ルームやバーから始まって、渋谷のクラブやカラオケボックスなど主人公の2人が巡る先々において、外国人から見たTOKYOという都市の生態が上手く描かれているように思いました。また、それが、共にエトランゼである2人の孤独を映し出し、孤独な者同士であるゆえに2人が接近していくプロセスも自然であるし、ところどころにユーモアも織り込まれていたりして、その分、ラストの別れの切なさも際立っています。2人の関係がプラトニックなまま続き、そのままで終わるのもいいです。
新宿のパークハイアットホテルのスィート・ルームやバーから始まって、渋谷のクラブやカラオケボックスなど主人公の2人が巡る先々において、外国人から見たTOKYOという都市の生態が上手く描かれているように思いました。また、それが、共にエトランゼである2人の孤独を映し出し、孤独な者同士であるゆえに2人が接近していくプロセスも自然であるし、ところどころにユーモアも織り込まれていたりして、その分、ラストの別れの切なさも際立っています。2人の関係がプラトニックなまま続き、そのままで終わるのもいいです。
 ビル・マーレイの演技も渋いし、スカーレット・ヨハンソンも悪くないです。ビル・マーレイは喜劇のイメージがあるので、演技の幅の広さを感じました。スカーレット・ヨハンソンは、今やすっかり肉体派アクション女優になってしまいましたが、幼い頃から演劇教室(リーストラスバーグ・シアターインスティテュート・フォー・ヤングピープル)に通い、8歳のときオフ・ブロードウェイにデビュー、10歳で映画デビューし、本作出演時は(シャーロットは大学を卒業したてという設定だが)まだ18歳でした。スカーレット・ヨハンソンは、女優人生のこの時でないと出来ない演技をしているように思います。
ビル・マーレイの演技も渋いし、スカーレット・ヨハンソンも悪くないです。ビル・マーレイは喜劇のイメージがあるので、演技の幅の広さを感じました。スカーレット・ヨハンソンは、今やすっかり肉体派アクション女優になってしまいましたが、幼い頃から演劇教室(リーストラスバーグ・シアターインスティテュート・フォー・ヤングピープル)に通い、8歳のときオフ・ブロードウェイにデビュー、10歳で映画デビューし、本作出演時は(シャーロットは大学を卒業したてという設定だが)まだ18歳でした。スカーレット・ヨハンソンは、女優人生のこの時でないと出来ない演技をしているように思います。 この映画に関しては、日本人を上から目線で戯画化していて、日本や日本人を馬鹿にしているといった批判も一部にあるようですが、その点はそれほど気になりませんでした。例えば、ボブがシャーロットとしゃぶしゃぶ料理店に行って、「自分で料理する店だなんて」と憤慨しているのも、歌手の女性と一夜を共にしてしまったことをシャーロットに知られた気まずさから、しゃぶしゃぶ料理店に八つ当たりしているという、いわばユーモアの構図なのでしょう(「ぐるなび」の渋谷「しゃぶ禅」のページに「ロストイントランスレーションで使われた席」という写真が今も出ている)。
この映画に関しては、日本人を上から目線で戯画化していて、日本や日本人を馬鹿にしているといった批判も一部にあるようですが、その点はそれほど気になりませんでした。例えば、ボブがシャーロットとしゃぶしゃぶ料理店に行って、「自分で料理する店だなんて」と憤慨しているのも、歌手の女性と一夜を共にしてしまったことをシャーロットに知られた気まずさから、しゃぶしゃぶ料理店に八つ当たりしているという、いわばユーモアの構図なのでしょう(「ぐるなび」の渋谷「しゃぶ禅」のページに「ロストイントランスレーションで使われた席」という写真が今も出ている)。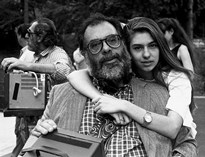
 佳作ではありますが、そんなにたくさん賞を獲るほどの映画かなあという気もします。ソフィア・コッポラ監督の才能は、他の作品をもっと観てみないと分からないといった感じでしょうか。スカーレット・ヨハンソンを見るとソフィア・コッポラ監督の演出力を感じますが、ビル・マーレイを見ると、俳優が元々有している実力のような気もします。
佳作ではありますが、そんなにたくさん賞を獲るほどの映画かなあという気もします。ソフィア・コッポラ監督の才能は、他の作品をもっと観てみないと分からないといった感じでしょうか。スカーレット・ヨハンソンを見るとソフィア・コッポラ監督の演出力を感じますが、ビル・マーレイを見ると、俳優が元々有している実力のような気もします。 そこで、ソフィア・コッポラ監督の次の作品「マリー・アントワネット」('06年)も観てみましたが、何でこんな駄作を撮ってしまったのかなあという感じでした。主演は「ヴァージン・スーサイズ」のキルスティン・ダンストで、撮影はフランスのヴェルサイユ宮殿で行われましたが(撮影料は1日1万6千ユーロで、3か月かかったという。製作費は4000万ドルで前作の10倍)、カンヌ国際映画祭に出品された際に、プレス試写ではブーイングが起き、フランスのマリー・アントワネット協会の会長も「この映画のせいで、アントワネットのイメージを改善しようとしてきた我々の努力が水の泡だ」とコメントしたとのことです。
そこで、ソフィア・コッポラ監督の次の作品「マリー・アントワネット」('06年)も観てみましたが、何でこんな駄作を撮ってしまったのかなあという感じでした。主演は「ヴァージン・スーサイズ」のキルスティン・ダンストで、撮影はフランスのヴェルサイユ宮殿で行われましたが(撮影料は1日1万6千ユーロで、3か月かかったという。製作費は4000万ドルで前作の10倍)、カンヌ国際映画祭に出品された際に、プレス試写ではブーイングが起き、フランスのマリー・アントワネット協会の会長も「この映画のせいで、アントワネットのイメージを改善しようとしてきた我々の努力が水の泡だ」とコメントしたとのことです。 ものすごく時代がかった背景でしたが(アカデミー賞衣装デザイン賞を受賞)、14歳から33歳までのマリー・アントワネットを演じたキルスティン・ダンストは当時24歳で、一人その演技だけが現代の女子大生みたいで、周囲からすごく浮いていたように思います。Wikipediaによると、「根本的なテーマが誰も知る人のいない異国にわずか14歳で単身やってきた少女の孤独である点は、監督の前作の『ロスト・イン・トランスレーション』と類似している」とのことで、ナルホドね。どうやらソフィア・コッポラ監督はこうしたテーマを追い続けているようですが、この作品に関して言えば、オーストリアからフランスにやって来た少女というより、21世紀のアメリカから18世紀のフランスにタイムスリップした女子大生といった感じでしょうか。「ヴァージン・スーサイズ」から連なる"ガーリームービー"の系譜ともとれます。この作品を支持する人もいますが、個人的には、ソフィア・コッポラ監督の作品は、出来不出来のムラが大きいのかもしれないと思いました(この作品を支持する人はおそらく、歴史モノとしてではなく、ガーリームービーとしてこの作品をとらえたのではないか)。
ものすごく時代がかった背景でしたが(アカデミー賞衣装デザイン賞を受賞)、14歳から33歳までのマリー・アントワネットを演じたキルスティン・ダンストは当時24歳で、一人その演技だけが現代の女子大生みたいで、周囲からすごく浮いていたように思います。Wikipediaによると、「根本的なテーマが誰も知る人のいない異国にわずか14歳で単身やってきた少女の孤独である点は、監督の前作の『ロスト・イン・トランスレーション』と類似している」とのことで、ナルホドね。どうやらソフィア・コッポラ監督はこうしたテーマを追い続けているようですが、この作品に関して言えば、オーストリアからフランスにやって来た少女というより、21世紀のアメリカから18世紀のフランスにタイムスリップした女子大生といった感じでしょうか。「ヴァージン・スーサイズ」から連なる"ガーリームービー"の系譜ともとれます。この作品を支持する人もいますが、個人的には、ソフィア・コッポラ監督の作品は、出来不出来のムラが大きいのかもしれないと思いました(この作品を支持する人はおそらく、歴史モノとしてではなく、ガーリームービーとしてこの作品をとらえたのではないか)。![「マリー・アントワネット].jpg](http://hurec.bz/book-movie/%E3%80%8C%E3%83%9E%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%5D.jpg)
![「マリー・アントワネット]2.jpg](http://hurec.bz/book-movie/%E3%80%8C%E3%83%9E%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%5D%EF%BC%92.jpg) マリー・アントワネットのウィーン時代の飼い犬、パグ犬モップス(映画では、お輿入れの際にマリーとモップスは引き離されてしまうが、それがフランスに行ってからのマリーの夢の中に現れて、却ってマリーがつらい思いをする)が、2001年から始まったカンヌ国際映画祭で優秀な演技を披露した犬に贈られる賞「
マリー・アントワネットのウィーン時代の飼い犬、パグ犬モップス(映画では、お輿入れの際にマリーとモップスは引き離されてしまうが、それがフランスに行ってからのマリーの夢の中に現れて、却ってマリーがつらい思いをする)が、2001年から始まったカンヌ国際映画祭で優秀な演技を披露した犬に贈られる賞「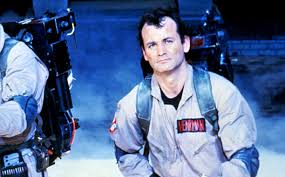
 ビル・マーレイ in「ゴーストバスターズ」(1984)/「
ビル・マーレイ in「ゴーストバスターズ」(1984)/「
 スカーレット・ヨハンソン in「ママの遺したラヴソング」(2004)ゴールデングローブ賞 主演女優賞(ドラマ部門)ノミネート/「マッチポイント」(2005)ゴールデングローブ賞 助演女優賞ノミネート
スカーレット・ヨハンソン in「ママの遺したラヴソング」(2004)ゴールデングローブ賞 主演女優賞(ドラマ部門)ノミネート/「マッチポイント」(2005)ゴールデングローブ賞 助演女優賞ノミネート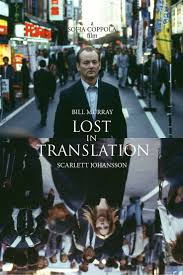
 「ロスト・イン・トランスレーション」●原題:LOST IN TRANSLATION●制作年:2003年●制作国:アメリカ●監督・脚本:ソフィア・コッポラ●製作:ソフィア・コッポラ/ロス・カッツ(製作総指揮:
「ロスト・イン・トランスレーション」●原題:LOST IN TRANSLATION●制作年:2003年●制作国:アメリカ●監督・脚本:ソフィア・コッポラ●製作:ソフィア・コッポラ/ロス・カッツ(製作総指揮: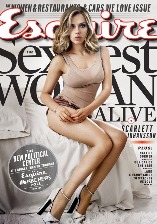
 /ジョバンニ・リビシ/アンナ・ファリス/フランソワ・デュ・ボワ/キャサリン・ランバート/ティム・レフマン/藤
/ジョバンニ・リビシ/アンナ・ファリス/フランソワ・デュ・ボワ/キャサリン・ランバート/ティム・レフマン/藤 井隆●日本公開:2004/04●配給:東北新社●最初に観た場所:北千住・シネマブルースタジオ(17-04-17)(評価★★★☆)
井隆●日本公開:2004/04●配給:東北新社●最初に観た場所:北千住・シネマブルースタジオ(17-04-17)(評価★★★☆)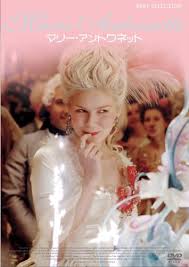
 「マリー・アントワネット」●原題:MARIE-ANTOINETTE●制作年:2006年●制作国:アメリカ●監督・脚本:ソフィア・コッポラ●製作:ソフィア・コッポ
「マリー・アントワネット」●原題:MARIE-ANTOINETTE●制作年:2006年●制作国:アメリカ●監督・脚本:ソフィア・コッポラ●製作:ソフィア・コッポ![「マリー・アントワネット]3.jpg](http://hurec.bz/book-movie/%E3%80%8C%E3%83%9E%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%5D%EF%BC%93.jpg) ラ/ロス・カッツ(製作総指揮:
ラ/ロス・カッツ(製作総指揮: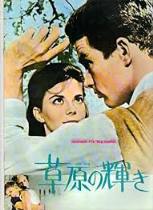
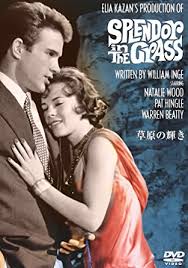

 1928年、カンサスの高校3年生バッド(ウォーレン・ベイティ)とディーン(ディーニー)(ナタリー・ウッド)は愛し合っているが、保守的な倫理観の持ち主であるディーンの母親(オードリー・クリスティ)の言い草もあって、ディーンはバッドを受け入れるに至らない。バッドの父で石油業者のエイス(パット・ヒングル)はフットボール選手である息子が自慢で、イェール大学に入れたがっているが、バッドには父親の期待が負担になっている。父は理解あるように振舞うが実態は暴君で、反発した姉ジェニー(バーバラ・ローデン)は家出して堕落してしまっていた。バッドは、ディーンが自分を受け入れてくれないイライラから、
1928年、カンサスの高校3年生バッド(ウォーレン・ベイティ)とディーン(ディーニー)(ナタリー・ウッド)は愛し合っているが、保守的な倫理観の持ち主であるディーンの母親(オードリー・クリスティ)の言い草もあって、ディーンはバッドを受け入れるに至らない。バッドの父で石油業者のエイス(パット・ヒングル)はフットボール選手である息子が自慢で、イェール大学に入れたがっているが、バッドには父親の期待が負担になっている。父は理解あるように振舞うが実態は暴君で、反発した姉ジェニー(バーバラ・ローデン)は家出して堕落してしまっていた。バッドは、ディーンが自分を受け入れてくれないイライラから、 同級生でコケティッシュな娘ファニタ(ジャン・ノリス)の誘惑に負けてしまう。ディーンはこのことにショックを受け、ワーズワースの詩の授業中に教室を抜け出し、川に身を投げる。何とか死を免
同級生でコケティッシュな娘ファニタ(ジャン・ノリス)の誘惑に負けてしまう。ディーンはこのことにショックを受け、ワーズワースの詩の授業中に教室を抜け出し、川に身を投げる。何とか死を免 れたディーンは精神病院に入院する。父の希望通りイェール大学に入ったバッドは、勉強に身が入らず、酒ばかり飲み、結局アンジェリーナ(ゾーラ・ランパート)というイタ
れたディーンは精神病院に入院する。父の希望通りイェール大学に入ったバッドは、勉強に身が入らず、酒ばかり飲み、結局アンジェリーナ(ゾーラ・ランパート)というイタ リア娘と結ばれてしまい、学校は退学寸前のところまでいっている。やがて世間は、1929年の世界大恐慌に見舞われ、エイスは大打撃を隠して息子に会い、ディーン似の女をバッドの寝室に送り込んだりするが、その夜窓から飛び降り自殺する。ディーンは病院で知り合ったジョニー(チャールズ・ロビンソン)という若い医師と婚約する。退院後、バッドが田舎へ引込んで牧場をやっていることを知り、訪ねて行くと、彼はアンジェリーナとつつましく暮らしていた。2人は静かな気持ちで再会する―。
リア娘と結ばれてしまい、学校は退学寸前のところまでいっている。やがて世間は、1929年の世界大恐慌に見舞われ、エイスは大打撃を隠して息子に会い、ディーン似の女をバッドの寝室に送り込んだりするが、その夜窓から飛び降り自殺する。ディーンは病院で知り合ったジョニー(チャールズ・ロビンソン)という若い医師と婚約する。退院後、バッドが田舎へ引込んで牧場をやっていることを知り、訪ねて行くと、彼はアンジェリーナとつつましく暮らしていた。2人は静かな気持ちで再会する―。 1961年のエリア・カザン(1909-2003/享年94)監督によるアメリカの青春映画。ウォーレン・ベイティ(1937年生まれ)のデビュ
1961年のエリア・カザン(1909-2003/享年94)監督によるアメリカの青春映画。ウォーレン・ベイティ(1937年生まれ)のデビュ ー作で、ウォーレン・ベイティはこの作品で、既にジェームズ・ディーンと「
ー作で、ウォーレン・ベイティはこの作品で、既にジェームズ・ディーンと「
 恋愛を軸とした青春物語に、親と子の葛藤を織り込むところが、「
恋愛を軸とした青春物語に、親と子の葛藤を織り込むところが、「 技も良かったです。彼女は43歳で撮影中に入江で水死し(他殺説、自殺説もある)、アカデミー賞に関しては無冠で終わりましたが、この作品が一番近かったのではないでしょうか(主演女優賞にノミネートされたが受賞は成らなかった)。一方のウォー
技も良かったです。彼女は43歳で撮影中に入江で水死し(他殺説、自殺説もある)、アカデミー賞に関しては無冠で終わりましたが、この作品が一番近かったのではないでしょうか(主演女優賞にノミネートされたが受賞は成らなかった)。一方のウォー レン・ベイティは「
レン・ベイティは「 作家の村上春樹氏は川本三郎氏との共著『映画をめぐる冒険』('85年/講談社)の中で「この映画のことを想うとき、いつも哀しい気持ちになる」「あるいは僕の涙腺が弱すぎるせいかもしれないが、観るたびに胸打たれる映画というのがある。『草原の輝き』もそのひとつである」と書いていて、ナタリー・ウッドについては「青春というものの発する理不尽な力に打ちのめされていく傷つきやすい少女の心の動きを彼女は実に見事に表現している」としていますが、まさにその通りと言えるでしょう。
作家の村上春樹氏は川本三郎氏との共著『映画をめぐる冒険』('85年/講談社)の中で「この映画のことを想うとき、いつも哀しい気持ちになる」「あるいは僕の涙腺が弱すぎるせいかもしれないが、観るたびに胸打たれる映画というのがある。『草原の輝き』もそのひとつである」と書いていて、ナタリー・ウッドについては「青春というものの発する理不尽な力に打ちのめされていく傷つきやすい少女の心の動きを彼女は実に見事に表現している」としていますが、まさにその通りと言えるでしょう。 この映画に対する個人的な印象として、60年代っぽいイメージが
この映画に対する個人的な印象として、60年代っぽいイメージが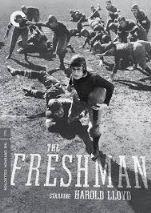

 エリア・カザンはトルコ生まれのギリシャ系アメリカ人でイェール大学で演劇を学んでいます。巨匠が丹念に作った作品であり、ナタリー・ウッドッはやはりこの作品が一番。村上春樹の涙腺を緩めるだけのことはある―といった感じでしょうか。
エリア・カザンはトルコ生まれのギリシャ系アメリカ人でイェール大学で演劇を学んでいます。巨匠が丹念に作った作品であり、ナタリー・ウッドッはやはりこの作品が一番。村上春樹の涙腺を緩めるだけのことはある―といった感じでしょうか。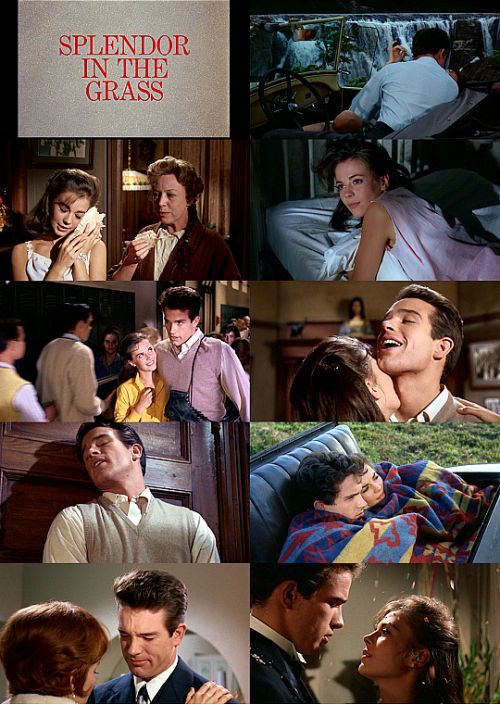
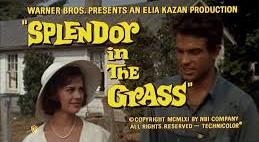 「草原の輝き」●原題:SPLENDOR IN THE GRASS●制作年:1961年●制作国:アメリカ●監督・製作:エリア・カザン●脚本:ウィリアム・インジ●撮影:ボリス・カウフマン●音楽:デヴィッド・アムラム●原作:ウィリアム・インジ●時間:124分●出演:ナタリー・ウ
「草原の輝き」●原題:SPLENDOR IN THE GRASS●制作年:1961年●制作国:アメリカ●監督・製作:エリア・カザン●脚本:ウィリアム・インジ●撮影:ボリス・カウフマン●音楽:デヴィッド・アムラム●原作:ウィリアム・インジ●時間:124分●出演:ナタリー・ウ ッド/ウォーレン・ベイティ/パット・ヒングル/ゾーラ・ランパート/サンディ・デニス/ショーン・ギャリソン/オードリー・クリスティー/フィリス・ディラー/バーバラ・ローデン/ゲイリー・ロックウッド●日本公開:1961/11●配給:ワーナー・ブラザース映画●最初に観た場所:三鷹東映(78-01-17)(評価★★★★)●併映:「ジョンとメリー」(ピーター・イェイツ)/「ひとりぼっちの青春」(シドニー・ポラック)
ッド/ウォーレン・ベイティ/パット・ヒングル/ゾーラ・ランパート/サンディ・デニス/ショーン・ギャリソン/オードリー・クリスティー/フィリス・ディラー/バーバラ・ローデン/ゲイリー・ロックウッド●日本公開:1961/11●配給:ワーナー・ブラザース映画●最初に観た場所:三鷹東映(78-01-17)(評価★★★★)●併映:「ジョンとメリー」(ピーター・イェイツ)/「ひとりぼっちの青春」(シドニー・ポラック)
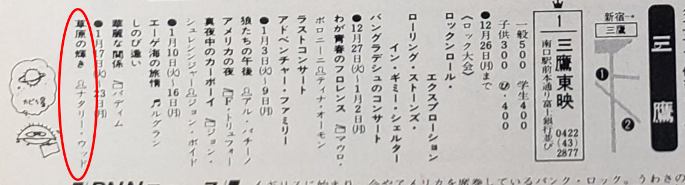
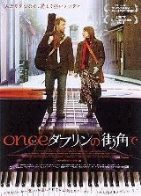


 ダブリンの街中、ストリートミュージシャンの男(グレン・ハンサード)が誰もが知る曲を弾いている。夜になると自分の書いた曲を歌うが、足を止めるものはいない。そこへ、雑誌や花を売っている女(マルケタ・イルグロヴァ)が現れ、小銭をギターケースに入れる。男は皮肉交じりに礼を言うが、女の「お金のため?誰のための歌?恋人はいない
ダブリンの街中、ストリートミュージシャンの男(グレン・ハンサード)が誰もが知る曲を弾いている。夜になると自分の書いた曲を歌うが、足を止めるものはいない。そこへ、雑誌や花を売っている女(マルケタ・イルグロヴァ)が現れ、小銭をギターケースに入れる。男は皮肉交じりに礼を言うが、女の「お金のため?誰のための歌?恋人はいない の?」という問いかけを疎ましく思いながらも相手するうちに、彼の昼の本業である掃除機修理を約束されてしまう。翌日、演奏する男の前に掃除機を引き摺った彼女が現れ、昼食を共にする。女はチェコからきた移民で、父
の?」という問いかけを疎ましく思いながらも相手するうちに、彼の昼の本業である掃除機修理を約束されてしまう。翌日、演奏する男の前に掃除機を引き摺った彼女が現れ、昼食を共にする。女はチェコからきた移民で、父 親が音楽家だったという。2人は女がピアノを弾かせてもらっているという楽器店に立ち寄り、メンデルスゾーンを弾く彼女のピアノの腕を確信した男も一緒に演奏、2人のセッションは美しいハーモニーを生む。男はその演奏に自身の喜びを感じ、女に惹かれていく。翌日、男は街で花を売り歩く女を見つけ声をかけるが、前日彼女を短絡的に誘ったため女の態度はそっけない。男は謝り、自分の曲が入ったCDとプレイヤーを渡す。強引に彼女を家まで送ると、家へあがらないかと誘われる。家では母親と幼い娘を紹介され、厳しい移民の生活を目の当たりにする。男は、自分の曲に詞をつけてみないかと提案する。女はその夜、働くばかりの生活を忘れ、心に抱えていた想いを詞に込める―。
親が音楽家だったという。2人は女がピアノを弾かせてもらっているという楽器店に立ち寄り、メンデルスゾーンを弾く彼女のピアノの腕を確信した男も一緒に演奏、2人のセッションは美しいハーモニーを生む。男はその演奏に自身の喜びを感じ、女に惹かれていく。翌日、男は街で花を売り歩く女を見つけ声をかけるが、前日彼女を短絡的に誘ったため女の態度はそっけない。男は謝り、自分の曲が入ったCDとプレイヤーを渡す。強引に彼女を家まで送ると、家へあがらないかと誘われる。家では母親と幼い娘を紹介され、厳しい移民の生活を目の当たりにする。男は、自分の曲に詞をつけてみないかと提案する。女はその夜、働くばかりの生活を忘れ、心に抱えていた想いを詞に込める―。 ジョン・カーニー監督・脚本による2007年公開のアイルランドの音楽映画。アイルランド映画局の出資を受けつつも製作費10万ドルという低予算で作られた作品で、撮影期間も17日間という短さだったそうです。2007年1月のサンダンス映画祭で観客賞を受賞し、同年3月からの全米一般公開での上映劇場数はたった2館だったのが口コミで話題になり、140館まで劇場数を増やしたとのことで、アカデミー賞の歌曲賞を受賞し(授賞式で主演の1人マルケタ・イルグロヴァが「低予算でも良いものを作れば必ず認めてもらえる」とスピーチを行い、会場から大喝采を受けた)、ミュージカル化されるまでに至っています。自身の監督第2作となるカーニー監督は「ザ・フレイムズ」の元ベース奏者であり、主演のグレン・ハンサードとマルケタ・イルグロヴァの2人も共にプロのミュージシ
ジョン・カーニー監督・脚本による2007年公開のアイルランドの音楽映画。アイルランド映画局の出資を受けつつも製作費10万ドルという低予算で作られた作品で、撮影期間も17日間という短さだったそうです。2007年1月のサンダンス映画祭で観客賞を受賞し、同年3月からの全米一般公開での上映劇場数はたった2館だったのが口コミで話題になり、140館まで劇場数を増やしたとのことで、アカデミー賞の歌曲賞を受賞し(授賞式で主演の1人マルケタ・イルグロヴァが「低予算でも良いものを作れば必ず認めてもらえる」とスピーチを行い、会場から大喝采を受けた)、ミュージカル化されるまでに至っています。自身の監督第2作となるカーニー監督は「ザ・フレイムズ」の元ベース奏者であり、主演のグレン・ハンサードとマルケタ・イルグロヴァの2人も共にプロのミュージシ ャンです。コスト削減のために自然光や友人達の家を使用したりし、パーティのシーンはハンサード自身のアパートが使われ、ハンサードの実際の友人がパーティ参加者および演奏者として出演したとのこと、パーティの席上で歌を披露た婦人はハンサードの母親だそうです。ダブリンの街角でのシーンは許可無しのゲリラ撮影で、望遠レンズを使うことで役者はカメラを意識することなく演技が出来たとのこと、勿論、通行人の多くも自分が映画に映り込んでいることを知らず映っていたわけで、全体として、ドキュメンタリー映画のような雰囲気があります(カメラがずっと細かく揺れていて、アドリブにカメラマンが笑って大きく揺れている場面もある)。
ャンです。コスト削減のために自然光や友人達の家を使用したりし、パーティのシーンはハンサード自身のアパートが使われ、ハンサードの実際の友人がパーティ参加者および演奏者として出演したとのこと、パーティの席上で歌を披露た婦人はハンサードの母親だそうです。ダブリンの街角でのシーンは許可無しのゲリラ撮影で、望遠レンズを使うことで役者はカメラを意識することなく演技が出来たとのこと、勿論、通行人の多くも自分が映画に映り込んでいることを知らず映っていたわけで、全体として、ドキュメンタリー映画のような雰囲気があります(カメラがずっと細かく揺れていて、アドリブにカメラマンが笑って大きく揺れている場面もある)。 ストーリー的には所謂"ボーイ・ミーツ・ガール"の物語ですが、主人公の男女(最後まで名前で呼ばれることはなく、エンドロールでの役名が'guy''giri'となっているのが洒落ている)が互いに惹かれ合いながらも普通の恋愛映画みたに一緒にはならず、最後は(最後も行き違いのようになってしまうのだが)爽やかに別れるのが却っていいです(ロンドン行きを決めた自分に対する父親からの選別でチェコ製のピアノを買ったのかあ)。
ストーリー的には所謂"ボーイ・ミーツ・ガール"の物語ですが、主人公の男女(最後まで名前で呼ばれることはなく、エンドロールでの役名が'guy''giri'となっているのが洒落ている)が互いに惹かれ合いながらも普通の恋愛映画みたに一緒にはならず、最後は(最後も行き違いのようになってしまうのだが)爽やかに別れるのが却っていいです(ロンドン行きを決めた自分に対する父親からの選別でチェコ製のピアノを買ったのかあ)。 ニューヨークに来たという設定ですが、この作品のマルケタ・イルグロヴァ演じる女性は、チェコからダブリンに来た移民という設定で、共に'異邦人'であることで共通しています(イルグロヴァ自身がチェコのモラヴィア出身)。そうした意味では、カーニー監督の原点的な映画でしょうか。男女のロマンスの部分もカーニー監督の実体験がモチーフになっているとのことです(通りで演奏中にお金が盗まれるシーン、銀行でお金を借りるシーンなどは、グレン・ハンサードの下積み時代の実話だそうだ)。
ニューヨークに来たという設定ですが、この作品のマルケタ・イルグロヴァ演じる女性は、チェコからダブリンに来た移民という設定で、共に'異邦人'であることで共通しています(イルグロヴァ自身がチェコのモラヴィア出身)。そうした意味では、カーニー監督の原点的な映画でしょうか。男女のロマンスの部分もカーニー監督の実体験がモチーフになっているとのことです(通りで演奏中にお金が盗まれるシーン、銀行でお金を借りるシーンなどは、グレン・ハンサードの下積み時代の実話だそうだ)。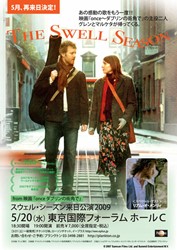
 主演のハンサードとイルグロヴァは映画を通して実生活でも交際を始め、カーニー監督によれば、そのことが2006年1月のダブリンでの僅か17日での撮影を容易にしたとのことですが(1988年生まれのイルグロヴァは当時18歳だった)、2人はその年デュオ・アルバム「The Swell Season」を発表、その後私生活上は別れたものの、「スウェル・シーズン」というデュオは継続しており、2009年には初来日して公演をしています。
主演のハンサードとイルグロヴァは映画を通して実生活でも交際を始め、カーニー監督によれば、そのことが2006年1月のダブリンでの僅か17日での撮影を容易にしたとのことですが(1988年生まれのイルグロヴァは当時18歳だった)、2人はその年デュオ・アルバム「The Swell Season」を発表、その後私生活上は別れたものの、「スウェル・シーズン」というデュオは継続しており、2009年には初来日して公演をしています。
 「ONCE ダブリンの街角で」●原題:ONCE●制作年:2007年●制作国:アイルランド●監督・脚本:ジョン・カーニー●製作:マルティナ・ニーランド●撮影:ティム・フレミング●87分●出演:グレン・ハンサード/マルケタ・イルグロヴァ/ ヒュー・ウォルシュ/ゲリー・ヘンドリック/アラスター・フォーリー/ゲオフ・ミノゲ/ ビル・ホドネット/ダヌシュ・クトレストヴァ/ダレン・ヒーリー/ マル・ワイト/ マルチェラ・プランケット/ ニーアル・クリアリー●日本公開:2007/11●配給:ショウゲート●最初に観た場所:北千住・シネマブルースタジオ(16-07-02)(評価:★★★★)
「ONCE ダブリンの街角で」●原題:ONCE●制作年:2007年●制作国:アイルランド●監督・脚本:ジョン・カーニー●製作:マルティナ・ニーランド●撮影:ティム・フレミング●87分●出演:グレン・ハンサード/マルケタ・イルグロヴァ/ ヒュー・ウォルシュ/ゲリー・ヘンドリック/アラスター・フォーリー/ゲオフ・ミノゲ/ ビル・ホドネット/ダヌシュ・クトレストヴァ/ダレン・ヒーリー/ マル・ワイト/ マルチェラ・プランケット/ ニーアル・クリアリー●日本公開:2007/11●配給:ショウゲート●最初に観た場所:北千住・シネマブルースタジオ(16-07-02)(評価:★★★★)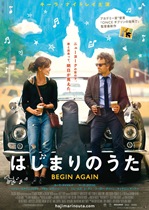



 ミュージシャンの恋人デイヴ(アダム・レヴィーン)と共作した曲が映画の主題歌に採用されたのを機に、イギリスからニューヨークへやってきて彼とニューヨークで暮らすことにしたシンガーソングライターのグレタ(キーラ・ナイトレイ)だったが、デイヴがスターとなって二人の関係の歯車に狂いが生じ始め、デイヴの浮気により彼と別れて、旧友の売れないミュージシャンのスティーブ(ジェームズ・コーデン)の家に居候する。スティーブは失意のグレタを励まそうとライブ・バーに連れていき、彼女を無理やりステージに上げる。歌い終わると、音楽プロデューサーを名乗るダン(マーク・ラファロ)にアルバムを作ろうと持ち掛けられる―。
ミュージシャンの恋人デイヴ(アダム・レヴィーン)と共作した曲が映画の主題歌に採用されたのを機に、イギリスからニューヨークへやってきて彼とニューヨークで暮らすことにしたシンガーソングライターのグレタ(キーラ・ナイトレイ)だったが、デイヴがスターとなって二人の関係の歯車に狂いが生じ始め、デイヴの浮気により彼と別れて、旧友の売れないミュージシャンのスティーブ(ジェームズ・コーデン)の家に居候する。スティーブは失意のグレタを励まそうとライブ・バーに連れていき、彼女を無理やりステージに上げる。歌い終わると、音楽プロデューサーを名乗るダン(マーク・ラファロ)にアルバムを作ろうと持ち掛けられる―。 カリビアン」シリーズの第1作('03年)から第3作('07年)に出ていたことで知られているが)、ダン役のマーク・ラファロは米国俳優、デイヴ役のアダム・レヴィーンは米国のシンガーソングライター、ギタリストでロックバンド「マルーン5」のボーカル、ということで、英国的雰囲気と米国的雰囲気が入り交じったような映画だったでしょうか(グレタのことを励ます旧友スティーブ役の ジェームズ・コーデンもイングランド出身の俳優・コメディアン)。ジョン・カーニー監督の前作「ONCE ダブリンの街角で」もそうですが、最初は公開館数が非常に少なかったのが、口コミでその良さが伝わり大ヒットを記録したようです。
カリビアン」シリーズの第1作('03年)から第3作('07年)に出ていたことで知られているが)、ダン役のマーク・ラファロは米国俳優、デイヴ役のアダム・レヴィーンは米国のシンガーソングライター、ギタリストでロックバンド「マルーン5」のボーカル、ということで、英国的雰囲気と米国的雰囲気が入り交じったような映画だったでしょうか(グレタのことを励ます旧友スティーブ役の ジェームズ・コーデンもイングランド出身の俳優・コメディアン)。ジョン・カーニー監督の前作「ONCE ダブリンの街角で」もそうですが、最初は公開館数が非常に少なかったのが、口コミでその良さが伝わり大ヒットを記録したようです。 冒頭のライブ会場の場面で、スティーブがグレタを無理矢理ライブのステージに上げて歌わせ、それにダンが聞き入ってしまうところから始まって、そこからフラッシュバックしてグレタの失意に至る道のりを振り返り、今度はダンの失意への道のりを振り返るという映画の前半部分の構成が、「倒叙法」とでも言うか、「長い導入部」とでも言うか実に巧みであり、しかも、技巧が勝ちすぎることなく、前半部分だけでもしっかり感動させてくれます(誰かが「開始3分で泣ける」と言っていたが確かに。しかも同じ場面で3回泣ける(?)というのはスゴイ)。
冒頭のライブ会場の場面で、スティーブがグレタを無理矢理ライブのステージに上げて歌わせ、それにダンが聞き入ってしまうところから始まって、そこからフラッシュバックしてグレタの失意に至る道のりを振り返り、今度はダンの失意への道のりを振り返るという映画の前半部分の構成が、「倒叙法」とでも言うか、「長い導入部」とでも言うか実に巧みであり、しかも、技巧が勝ちすぎることなく、前半部分だけでもしっかり感動させてくれます(誰かが「開始3分で泣ける」と言っていたが確かに。しかも同じ場面で3回泣ける(?)というのはスゴイ)。 ここまでしっかり作られてしまうと、後半はもう予定調和でメデタシメデタシしかないのではないかと思ってしまいましたが、物語がグレタの"再生"に止まらずダンの"再生"も描いていて、これがグレタの"再生"だけだと単なる敏腕プロデューサーの話になってしまうところを、途中からダンの"再生"も描くことでバランスが良くなっています。
ここまでしっかり作られてしまうと、後半はもう予定調和でメデタシメデタシしかないのではないかと思ってしまいましたが、物語がグレタの"再生"に止まらずダンの"再生"も描いていて、これがグレタの"再生"だけだと単なる敏腕プロデューサーの話になってしまうところを、途中からダンの"再生"も描くことでバランスが良くなっています。 しかも、グレタは、ダン〈個人〉を"再生"させると言うよりは、過去の出来事によりダンとそれまでうまくいっていなかった彼の妻や娘との〈関係性〉を再生させます(それによってダン自身も再生する)。これはスゴいなあと思って観ていたら、今度はグレタと別れた恋人デイヴの〈関係性〉が"再生"されるのです。相互に関係性が"再生"される物語なんだなあと(原題タイトル'BEGIN AGAIN'の'AGAIN'に意味がある)。
しかも、グレタは、ダン〈個人〉を"再生"させると言うよりは、過去の出来事によりダンとそれまでうまくいっていなかった彼の妻や娘との〈関係性〉を再生させます(それによってダン自身も再生する)。これはスゴいなあと思って観ていたら、今度はグレタと別れた恋人デイヴの〈関係性〉が"再生"されるのです。相互に関係性が"再生"される物語なんだなあと(原題タイトル'BEGIN AGAIN'の'AGAIN'に意味がある)。 従って、グレタとダンはあくまで仕事上のパートナーに止まり、再会を約して「爽やかに」別れることになるわけですが、観ていていいなあという感じでした。やや出来過ぎた話との印象もありますが、ダンがバックバンドのメンバーを集めるところなどはコミカルで面白かったし、路上でのゲリラ・ライブはシズル感満点だったし(タイムズ・スクエアやエンパイア・ステート・ビルなどマンハッタンの名所巡りも味わえる)、「プライドと偏見」でアカデミー主演女優賞にノミネートされたキーラ・ナイトレイの演技力は、この現代劇でも発揮されていたように思います。
従って、グレタとダンはあくまで仕事上のパートナーに止まり、再会を約して「爽やかに」別れることになるわけですが、観ていていいなあという感じでした。やや出来過ぎた話との印象もありますが、ダンがバックバンドのメンバーを集めるところなどはコミカルで面白かったし、路上でのゲリラ・ライブはシズル感満点だったし(タイムズ・スクエアやエンパイア・ステート・ビルなどマンハッタンの名所巡りも味わえる)、「プライドと偏見」でアカデミー主演女優賞にノミネートされたキーラ・ナイトレイの演技力は、この現代劇でも発揮されていたように思います。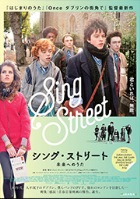
 今月 ['16年7月]9日からは渋谷・シネクイントで、カーニー監督の最新作「シング・ストリート 未来へのうた」('15年/アイルランド・英・米)の上映が始まります。80年代半ばのダブリンが舞台のカーニー監督の自伝的要素も含んだ作品のようですが、シネクイントが「パルコ・パート3」の建て替えに伴う一時休業(?)で8月7日をもって最終上映となるため、シネクイントの実質ラストショーになるのではないだろうか。(実際その通りになった。ジョン・カーニーに着眼したシネクイントらしいラストショーか)
今月 ['16年7月]9日からは渋谷・シネクイントで、カーニー監督の最新作「シング・ストリート 未来へのうた」('15年/アイルランド・英・米)の上映が始まります。80年代半ばのダブリンが舞台のカーニー監督の自伝的要素も含んだ作品のようですが、シネクイントが「パルコ・パート3」の建て替えに伴う一時休業(?)で8月7日をもって最終上映となるため、シネクイントの実質ラストショーになるのではないだろうか。(実際その通りになった。ジョン・カーニーに着眼したシネクイントらしいラストショーか) 「はじまりのうた」●原題:BEGIN AGAIN●制作年:2014年●制作国:アメリカ●監督・脚本:ジョン・カーニー●製作:アンソニー・ブレグマン/トビン・アームブラ
「はじまりのうた」●原題:BEGIN AGAIN●制作年:2014年●制作国:アメリカ●監督・脚本:ジョン・カーニー●製作:アンソニー・ブレグマン/トビン・アームブラ スト(英語版)/ジャド・アパトー●撮影:ヤーロン・オーバック●音楽:グレッグ・アレキサンダー●104分●出演:キーラ・ナイトレイ/マーク・ラファロ/ヘイリー・スタインフェルド/アダム・レヴィーン/ジェームズ・コーデン/ヤシーン・ベイ/シーロー・グリーン/キャサリン・キーナー●日本公開:2015/02●配給:ポニーキャニオン●最初に観た場所:北千住・シネマブルースタジオ(16-06-27)(評価:★★★★)
スト(英語版)/ジャド・アパトー●撮影:ヤーロン・オーバック●音楽:グレッグ・アレキサンダー●104分●出演:キーラ・ナイトレイ/マーク・ラファロ/ヘイリー・スタインフェルド/アダム・レヴィーン/ジェームズ・コーデン/ヤシーン・ベイ/シーロー・グリーン/キャサリン・キーナー●日本公開:2015/02●配給:ポニーキャニオン●最初に観た場所:北千住・シネマブルースタジオ(16-06-27)(評価:★★★★)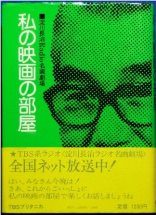
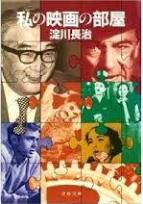
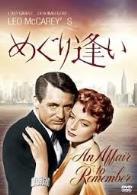
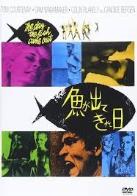
 個人的には、昔は淀川長冶ってそれほどスゴイとは思っていなかったのですが、今になってやはりスゴイ人だったんだなあと思ったりもします。作品解説もさることながら、作品を要約し、その見所となるポイントを抽出する技は絶妙という感じです。本書で言えば、例えば、レオ・マッケリー監督、ケーリー・グラント、デボラ・カー主演の「めぐり逢い」('57年、原題:An Affair to Remember)のラストシーンのエンパイアステートビルで出会えなかった2人が最後の最後に出会うシーンの解説などは、何だか今目の前に映画のスクリーンがあるような錯覚に陥りました。この映画、最初観た時はハーレクイン・ロマンスみたいと思ったけれど、今思えばよく出来ていたと(著者に指摘されて)思い直したりして...。これ自体が同じレオ・マッケリー監督作でシャルル・ボワイエ、アイリーン・ダン主演の「邂逅(めぐりあい)」('39年、原題:Love Affair)のリメイクで(ラストを見比べてみるとその忠実なリメイクぶりが窺える)、その後も別監督により何度かリメイクされています。トム・ハンクス、メグ・ライアン主演の「
個人的には、昔は淀川長冶ってそれほどスゴイとは思っていなかったのですが、今になってやはりスゴイ人だったんだなあと思ったりもします。作品解説もさることながら、作品を要約し、その見所となるポイントを抽出する技は絶妙という感じです。本書で言えば、例えば、レオ・マッケリー監督、ケーリー・グラント、デボラ・カー主演の「めぐり逢い」('57年、原題:An Affair to Remember)のラストシーンのエンパイアステートビルで出会えなかった2人が最後の最後に出会うシーンの解説などは、何だか今目の前に映画のスクリーンがあるような錯覚に陥りました。この映画、最初観た時はハーレクイン・ロマンスみたいと思ったけれど、今思えばよく出来ていたと(著者に指摘されて)思い直したりして...。これ自体が同じレオ・マッケリー監督作でシャルル・ボワイエ、アイリーン・ダン主演の「邂逅(めぐりあい)」('39年、原題:Love Affair)のリメイクで(ラストを見比べてみるとその忠実なリメイクぶりが窺える)、その後も別監督により何度かリメイクされています。トム・ハンクス、メグ・ライアン主演の「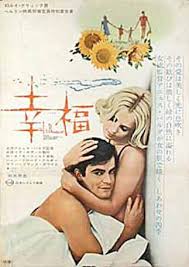
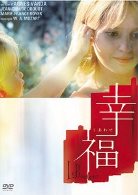
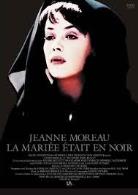
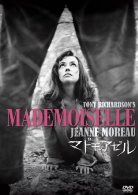
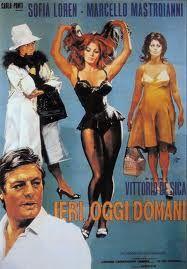

 イタリア映画では、ビットリオ・デ・シーカの「昨日・今日・明日」('63年)、「
イタリア映画では、ビットリオ・デ・シーカの「昨日・今日・明日」('63年)、「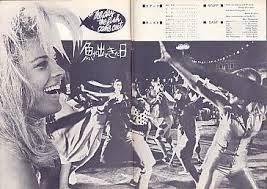
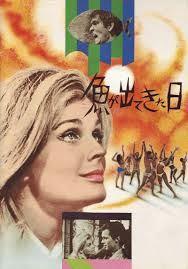
 づいていない)を扱ったブラックコメディで、ちょっと世に出るのが早すぎたような作品でもあります。
づいていない)を扱ったブラックコメディで、ちょっと世に出るのが早すぎたような作品でもあります。 トム・コートネイ、サム・ワナメイカー、キャンディス・バーゲンが出演。キャンディス・バーゲンって映画に出たての頃からインテリっぽい役を地でやっていて、しかも同時に、健康的なセクシーさがありました。
トム・コートネイ、サム・ワナメイカー、キャンディス・バーゲンが出演。キャンディス・バーゲンって映画に出たての頃からインテリっぽい役を地でやっていて、しかも同時に、健康的なセクシーさがありました。
 「めぐり逢い」●原題:AN AFFAIR TO REMEMBER●制作年:1957年●制作国:アメリカ●監督:レオ・マッケリー●製作:ジェリー・ウォルド●脚本:レオ・マッケリー/デルマー・デイヴィス/ドナルド・オグデン・ステュワート●撮影:ミルトン・クラスナー●音楽:ヒューゴ・フリードホーファー●原案:レオ・マッケリー/ミルドレッド・クラム●時間:119分●出演:ケーリー・グラント/デボラ・カー/リチャード・デニング/ネヴァ・パターソン/キャスリーン・ネスビット/ロバート・Q・ルイス/チャールズ・ワッツ/フォーチュニオ・ボナノヴァ●日本公開:1957/10●配給:20世紀フォックス●最初に観た場所:高田馬場・ACTミニシアター(85-11-03)(評価:★★★☆)●併映:「ティファニーで朝食を」(ブレイク・エドワーズ)
「めぐり逢い」●原題:AN AFFAIR TO REMEMBER●制作年:1957年●制作国:アメリカ●監督:レオ・マッケリー●製作:ジェリー・ウォルド●脚本:レオ・マッケリー/デルマー・デイヴィス/ドナルド・オグデン・ステュワート●撮影:ミルトン・クラスナー●音楽:ヒューゴ・フリードホーファー●原案:レオ・マッケリー/ミルドレッド・クラム●時間:119分●出演:ケーリー・グラント/デボラ・カー/リチャード・デニング/ネヴァ・パターソン/キャスリーン・ネスビット/ロバート・Q・ルイス/チャールズ・ワッツ/フォーチュニオ・ボナノヴァ●日本公開:1957/10●配給:20世紀フォックス●最初に観た場所:高田馬場・ACTミニシアター(85-11-03)(評価:★★★☆)●併映:「ティファニーで朝食を」(ブレイク・エドワーズ)
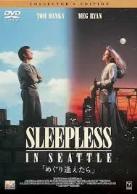

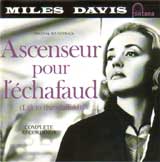
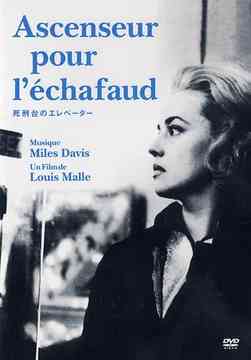

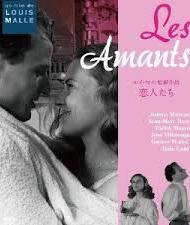
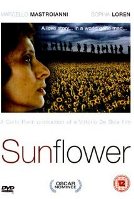
 「ひまわり」●原題:I GIRASOLI(SUNFLOWER)●制作年:1970年●制作国:イタリア・フランス・ソ連●監督:ヴィッ
「ひまわり」●原題:I GIRASOLI(SUNFLOWER)●制作年:1970年●制作国:イタリア・フランス・ソ連●監督:ヴィッ トリオ・デ・シーカ●製作:カルロ・ポンティ/アーサー・コーン●脚本:チェザーレ・ザ
トリオ・デ・シーカ●製作:カルロ・ポンティ/アーサー・コーン●脚本:チェザーレ・ザ バッティーニ/アントニオ・グエラ/ゲオルギス・ムディバニ●撮影:ジュゼッペ・ロトゥンノ●音楽:ヘンリー・マンシーニ●時間:107分●出演:マルチェロ・マストロヤンニ/ソフィア・ローレン/リュドミラ・サベーリエワ/アンナ・カレーナ/ジェルマーノ・ロンゴ/グラウコ・オノラート/カルロ・ポンティ・ジュニア●日本公開:1970/09●配給:日本ヘラルド映画●最初に観た場所:目黒シネマ(83-05-01)(評価:★★★★)●併映:「ワン・フロム・ザ・ハート」(フランシス・フォード・コッポラ)
バッティーニ/アントニオ・グエラ/ゲオルギス・ムディバニ●撮影:ジュゼッペ・ロトゥンノ●音楽:ヘンリー・マンシーニ●時間:107分●出演:マルチェロ・マストロヤンニ/ソフィア・ローレン/リュドミラ・サベーリエワ/アンナ・カレーナ/ジェルマーノ・ロンゴ/グラウコ・オノラート/カルロ・ポンティ・ジュニア●日本公開:1970/09●配給:日本ヘラルド映画●最初に観た場所:目黒シネマ(83-05-01)(評価:★★★★)●併映:「ワン・フロム・ザ・ハート」(フランシス・フォード・コッポラ) 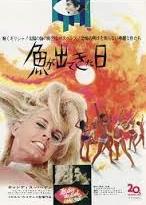

 「魚が出てきた日」●原題:THE DAY THE FISH COME OUT●制作年:1967年●制作国:アメリカ●監督・製作・脚本:マイケル・
「魚が出てきた日」●原題:THE DAY THE FISH COME OUT●制作年:1967年●制作国:アメリカ●監督・製作・脚本:マイケル・
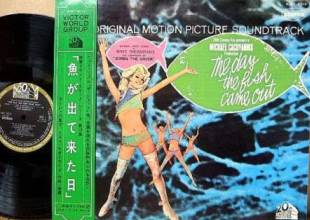 カコヤニス●撮影:ウォルター・ラサリー●音楽:ミキス・テオドラキス●時間:110分●出演:コリン・ブレークリー/サム・ワナメーカー/トム・コートネイ/キャンディス・バーゲン/
カコヤニス●撮影:ウォルター・ラサリー●音楽:ミキス・テオドラキス●時間:110分●出演:コリン・ブレークリー/サム・ワナメーカー/トム・コートネイ/キャンディス・バーゲン/
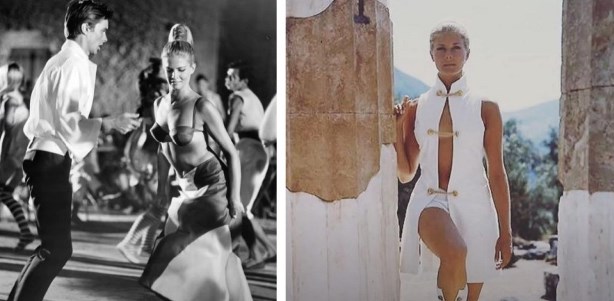
 キャンディス・バーゲン in 「ボストン・リーガル」 with
キャンディス・バーゲン in 「ボストン・リーガル」 with 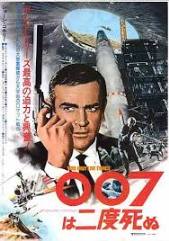


 アメリカとソ連の宇宙船が謎の飛行物体に捉えられるという事件が起こり、米ソ間が一触即発の状態になるものの、英国の情報機関である MI6はその宇宙船が日本周辺から飛び立っているという情報を掴み、その真偽を確かめるために、ジェームズ・ボンド(ショーン・コネリー)が日本に派遣されることになる。ボンドは敵の目を欺くため、英国の植民地の香港の売春宿で、情報部により用意された現地の女性リン(ツァイ・チン)の手引きによって、寝室になだれ込んだ殺し屋にマシンガンで銃撃され死んだことに。その後ビクトリア・ハーバー内に
アメリカとソ連の宇宙船が謎の飛行物体に捉えられるという事件が起こり、米ソ間が一触即発の状態になるものの、英国の情報機関である MI6はその宇宙船が日本周辺から飛び立っているという情報を掴み、その真偽を確かめるために、ジェームズ・ボンド(ショーン・コネリー)が日本に派遣されることになる。ボンドは敵の目を欺くため、英国の植民地の香港の売春宿で、情報部により用意された現地の女性リン(ツァイ・チン)の手引きによって、寝室になだれ込んだ殺し屋にマシンガンで銃撃され死んだことに。その後ビクトリア・ハーバー内に 停泊するイギリス海軍の巡洋艦上で水葬され、その遺体を回収したイギリス海軍の潜水艦で隠密裏に日本へ。日本上陸後は、蔵前国技館で謎の女アキ(若林映(あき)子)と会い、彼女を通じて日本の公
停泊するイギリス海軍の巡洋艦上で水葬され、その遺体を回収したイギリス海軍の潜水艦で隠密裏に日本へ。日本上陸後は、蔵前国技館で謎の女アキ(若林映(あき)子)と会い、彼女を通じて日本の公 安のトップ・タイガー田中(丹波哲郎)に会うが、在日オーストラリア人の捜査協力者のヘンダーソンは直後に殺されてしまう。その殺し屋は大里化学工業の本社から送られた者だと知ったボンドは、化学薬品を取り扱うビジネスマンを装って大里化学工業の東京本社に赴き、大里社長とその秘書ヘルガ・ブラント(カリン・ドール)と接触する―。 (右:サンヨー・テレビ「日本」の梱包)
安のトップ・タイガー田中(丹波哲郎)に会うが、在日オーストラリア人の捜査協力者のヘンダーソンは直後に殺されてしまう。その殺し屋は大里化学工業の本社から送られた者だと知ったボンドは、化学薬品を取り扱うビジネスマンを装って大里化学工業の東京本社に赴き、大里社長とその秘書ヘルガ・ブラント(カリン・ドール)と接触する―。 (右:サンヨー・テレビ「日本」の梱包)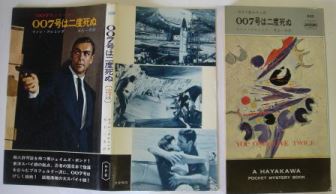
 事件の背後にはスペクターの影があり、ボンドはタイガー田中の助けを得てスペクターの秘密基地に潜入、宿敵ブロフェルド(「大脱走」('63年)、「
事件の背後にはスペクターの影があり、ボンドはタイガー田中の助けを得てスペクターの秘密基地に潜入、宿敵ブロフェルド(「大脱走」('63年)、「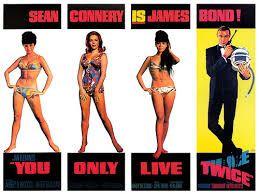 Mie Hama as Kissy Suzuki in "You Only Live Twice"(1967)
Mie Hama as Kissy Suzuki in "You Only Live Twice"(1967) 最初は日本に潜入したボンドをリードする公安エージェントの女性役が浜美枝で、ボンドが地方に行って出会う海女のキッシー鈴木の役が若林映子だったそうで、この配役は「キングコング対ゴジラ」('62年/東宝)を観て浜を知ったスタッフからの若林映子と併せての指名だったとのことです(若林映子は個人的
最初は日本に潜入したボンドをリードする公安エージェントの女性役が浜美枝で、ボンドが地方に行って出会う海女のキッシー鈴木の役が若林映子だったそうで、この配役は「キングコング対ゴジラ」('62年/東宝)を観て浜を知ったスタッフからの若林映子と併せての指名だったとのことです(若林映子は個人的 には「
には「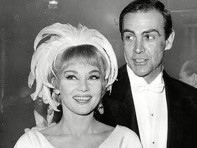 ということで、若林映子がエージェント(アキという役名になった)を演じ、浜美枝の方がキッシー鈴木役になったとのこと。但し、海女役になった浜美枝は、ロケ地に来て潜れないということが判明し、ショーン・コネリーに同伴していた妻の
ということで、若林映子がエージェント(アキという役名になった)を演じ、浜美枝の方がキッシー鈴木役になったとのこと。但し、海女役になった浜美枝は、ロケ地に来て潜れないということが判明し、ショーン・コネリーに同伴していた妻の
 キッシーが潜るシーンはスタントするなどしたとのことで、撮影に際しては結構ドタバタだった面もあったようです。
キッシーが潜るシーンはスタントするなどしたとのことで、撮影に際しては結構ドタバタだった面もあったようです。 点では、昭和40年代前半の日本の風景を映し出していて貴重かも。都内では、旧蔵前国技館、銀座四丁目交差点、ホテルニューオータニなどで、地方では富士スピードウェイ、神戸港、 姫路城、鹿児島県坊津町などでロケをしています。日本的なものを都会と地方、現代と伝統の両面からピックアップしている意欲は買えますが、一方で、姫路城で手裏剣で塀を傷つけたりするなどのトラブルも生じさせています。
点では、昭和40年代前半の日本の風景を映し出していて貴重かも。都内では、旧蔵前国技館、銀座四丁目交差点、ホテルニューオータニなどで、地方では富士スピードウェイ、神戸港、 姫路城、鹿児島県坊津町などでロケをしています。日本的なものを都会と地方、現代と伝統の両面からピックアップしている意欲は買えますが、一方で、姫路城で手裏剣で塀を傷つけたりするなどのトラブルも生じさせています。 オープニングの影絵は浮世絵のイメージ? イアン・フレミングは親日家ではあったものの、日本文化に対する外国人特有の偏見や誤解もあり、あまりに奇異な見方であると思われる部分は丹波哲郎が撮影陣に進言して直させたりもしたようですが、ボンドと若林演じるアキや丹波演じるタイガーなど日本の公安との橋渡し役が横綱・佐田の山(!)だったり、タイガーの移動手段が地下鉄「丸ノ内線」の深夜の
オープニングの影絵は浮世絵のイメージ? イアン・フレミングは親日家ではあったものの、日本文化に対する外国人特有の偏見や誤解もあり、あまりに奇異な見方であると思われる部分は丹波哲郎が撮影陣に進言して直させたりもしたようですが、ボンドと若林演じるアキや丹波演じるタイガーなど日本の公安との橋渡し役が横綱・佐田の山(!)だったり、タイガーの移動手段が地下鉄「丸ノ内線」の深夜の 専用車両(!)だったり(中野坂上駅でロケ。タイガーのオフィスは地下鉄の駅の「地下」にある。公安は顔を知られてはならず、そのため下手に地上を歩けないからというその理由がこじつけ気味)、さらに公安所属の特殊部隊が全員忍者装束(!)で日本刀を背負っていたりと、ち
専用車両(!)だったり(中野坂上駅でロケ。タイガーのオフィスは地下鉄の駅の「地下」にある。公安は顔を知られてはならず、そのため下手に地上を歩けないからというその理由がこじつけ気味)、さらに公安所属の特殊部隊が全員忍者装束(!)で日本刀を背負っていたりと、ち ょっ
ょっ と飛躍し過ぎていて、さすがの丹波哲郎でも口を挟みにくかった部分もあったのか(まあ、いいかみたいな感じもあったのか)、結果として「!」連続の珍品で、ボンドが日本人に変装することなども含
と飛躍し過ぎていて、さすがの丹波哲郎でも口を挟みにくかった部分もあったのか(まあ、いいかみたいな感じもあったのか)、結果として「!」連続の珍品で、ボンドが日本人に変装することなども含 め、現実味という観点からするとどうかなあと思わざるを得ません(非現実性はロアルド・ダールらしく、また007らしくもあるのだが。因みに丹波哲郎は、英語が不得手な浜美枝の降板を要請する英国側スタッフに対し、ここまできたらそれは難しいと交渉するくらいの英語力はあったが、発音は日本語訛りであったため、作中での本人の英語の台詞は吹き替えられている)。
め、現実味という観点からするとどうかなあと思わざるを得ません(非現実性はロアルド・ダールらしく、また007らしくもあるのだが。因みに丹波哲郎は、英語が不得手な浜美枝の降板を要請する英国側スタッフに対し、ここまできたらそれは難しいと交渉するくらいの英語力はあったが、発音は日本語訛りであったため、作中での本人の英語の台詞は吹き替えられている)。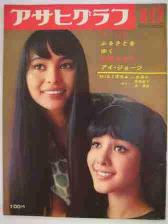 まあ、かなりの部分を日本で撮影しているということで、映像的価値並びに珍品的価値(?)を加味して星半個オマケといったところでしょうか。アジア人が最初にボンド・ガ
まあ、かなりの部分を日本で撮影しているということで、映像的価値並びに珍品的価値(?)を加味して星半個オマケといったところでしょうか。アジア人が最初にボンド・ガ ールになった作品であり、この次にアジア人ボンド・ガールが誕生したのは「
ールになった作品であり、この次にアジア人ボンド・ガールが誕生したのは「 若林映子は、
若林映子は、 ホテルのパーティに招かれた6人の男女客たちが、霧深い夜道を車を連ねて帰路に着く途中、竹原(鶴賀二郎)が誤って沼に落ちる。助けようとした
ホテルのパーティに招かれた6人の男女客たちが、霧深い夜道を車を連ねて帰路に着く途中、竹原(鶴賀二郎)が誤って沼に落ちる。助けようとした 一平(西條康彦)も深みにはまり、後続車の万城目淳(佐原健二)と江戸川由利子(桜井浩子)、葉山(滝田裕介)と今日子(若林映子)が辛じて救出。霧が深くこれ以上車で先へ進めないので、淳たちはずぶ濡れの北原と一平をかかえて途方に暮れるが、沼の向う側に灯のついた洋館を発見、そちらに向かう。洋館の中は何十年も放置され荒れていたが、階上の方へ淳が行ってみると、そこで巨大なクモに突然襲われる。驚いて階投を転がり降りた淳は、九十年前いたという蜘蛛男爵の館みたいだと言う。その頃、地下のワイン倉庫にいっていた葉山は、例の巨大なクモに襲われ傷つく。淳たちは、はじめてここがまさに蜘蛛男爵の館であることに気づき、館から逃げ出そうとするが―。
一平(西條康彦)も深みにはまり、後続車の万城目淳(佐原健二)と江戸川由利子(桜井浩子)、葉山(滝田裕介)と今日子(若林映子)が辛じて救出。霧が深くこれ以上車で先へ進めないので、淳たちはずぶ濡れの北原と一平をかかえて途方に暮れるが、沼の向う側に灯のついた洋館を発見、そちらに向かう。洋館の中は何十年も放置され荒れていたが、階上の方へ淳が行ってみると、そこで巨大なクモに突然襲われる。驚いて階投を転がり降りた淳は、九十年前いたという蜘蛛男爵の館みたいだと言う。その頃、地下のワイン倉庫にいっていた葉山は、例の巨大なクモに襲われ傷つく。淳たちは、はじめてここがまさに蜘蛛男爵の館であることに気づき、館から逃げ出そうとするが―。 洋館は、コラムニストの泉麻人氏も言っていましたが、アルフレッド・ヒッチコックの映画「レベッカ」('40年/米)に出てくる邸宅みたいな雰
洋館は、コラムニストの泉麻人氏も言っていましたが、アルフレッド・ヒッチコックの映画「レベッカ」('40年/米)に出てくる邸宅みたいな雰 囲気があって良かったですが、男爵の死んだ娘がクモになり、娘の死を悲しんだ男爵自身もクモになっていまったという話はやや強引か(まあ、「ウルトラQ」は"強引"なスト-リーが多いのだが)。この回の視聴率は35.7%と(「ウルトラQ伝説」等による)シリーズ全27話の中では上位にくる数字を出しています。このシリーズ、総天然色版でDVDが出ているので、それでもう一度作品を鑑賞するとともに、若林映子や桜井浩子のファッションを見直してみるのもいいかも。
囲気があって良かったですが、男爵の死んだ娘がクモになり、娘の死を悲しんだ男爵自身もクモになっていまったという話はやや強引か(まあ、「ウルトラQ」は"強引"なスト-リーが多いのだが)。この回の視聴率は35.7%と(「ウルトラQ伝説」等による)シリーズ全27話の中では上位にくる数字を出しています。このシリーズ、総天然色版でDVDが出ているので、それでもう一度作品を鑑賞するとともに、若林映子や桜井浩子のファッションを見直してみるのもいいかも。
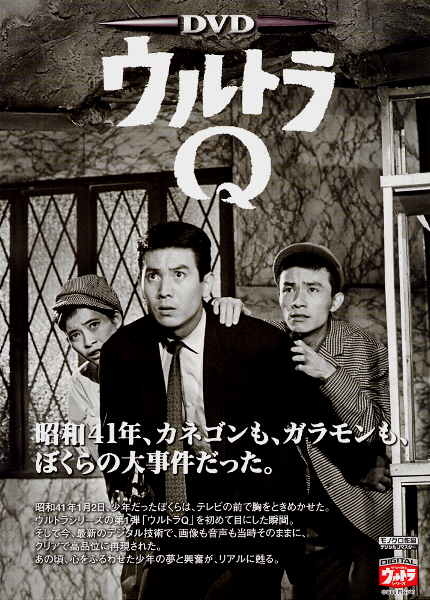
 「ウルトラQ(第9話)/クモ男爵」●制作年:1965年●監督:円谷一●監修:円谷英二●制作:円谷プロダクション●脚本:金城哲夫●撮影:内海正治●音楽:宮内国郎●特技監督:小泉一●出演:佐原健二/西條
「ウルトラQ(第9話)/クモ男爵」●制作年:1965年●監督:円谷一●監修:円谷英二●制作:円谷プロダクション●脚本:金城哲夫●撮影:内海正治●音楽:宮内国郎●特技監督:小泉一●出演:佐原健二/西條
 康彦/桜井浩子/若林映子/滝田裕介/鶴賀二郎/永井柳太郎/岩本弘司/石坂浩二(ナレーター)●放送:1966/02/17●放送局:TBS(評価:★★★)
康彦/桜井浩子/若林映子/滝田裕介/鶴賀二郎/永井柳太郎/岩本弘司/石坂浩二(ナレーター)●放送:1966/02/17●放送局:TBS(評価:★★★) 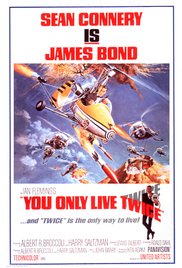
 作:ハリー・サルツマン/アルバート・R・ブロッコリ●脚本:
作:ハリー・サルツマン/アルバート・R・ブロッコリ●脚本:
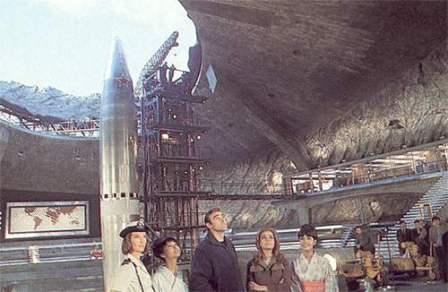
 ●原作:イアン・フレミング●時間:117分●出演:ショーン・コネリー/丹波哲郎/若林映子/浜美枝/ドナルド・プレザンス/島田テル/カリン・ドール/チャールズ・グレイ/ツァイ・チン/ロイス・マクスウェル/デスモンド・リュウェリン/バーナード・リー●公開:1967/06●配給:ユナイテッド・アーティスツ (評価:★★★☆)
●原作:イアン・フレミング●時間:117分●出演:ショーン・コネリー/丹波哲郎/若林映子/浜美枝/ドナルド・プレザンス/島田テル/カリン・ドール/チャールズ・グレイ/ツァイ・チン/ロイス・マクスウェル/デスモンド・リュウェリン/バーナード・リー●公開:1967/06●配給:ユナイテッド・アーティスツ (評価:★★★☆)


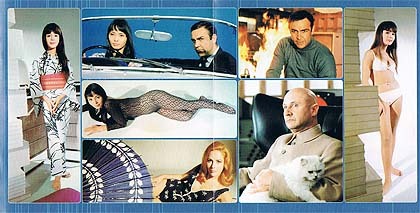



 「キングコング対ゴジラ」('62年/東宝) 若林映子/浜 美枝(共演:高島忠夫)
「キングコング対ゴジラ」('62年/東宝) 若林映子/浜 美枝(共演:高島忠夫) 








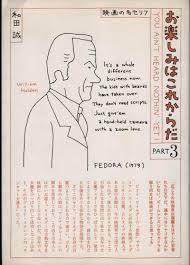

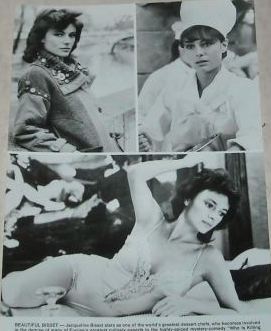 ジャクリーン・ビセットがジョージ・シーガルと共演した「料理長(シェフ)殿、ご用心」('78年)なんて、何てことはない映画だけれどよくできていたのでは(監督は4年後に「
ジャクリーン・ビセットがジョージ・シーガルと共演した「料理長(シェフ)殿、ご用心」('78年)なんて、何てことはない映画だけれどよくできていたのでは(監督は4年後に「
 因みに、「クリスチーヌの性愛記」('72年)は、そのタイトルやチラシなどからポルノ映画と思われているフシがありますが、下にあらすじを書いたように、自分の気の赴くままに生きる若い女性の運命とその悲劇をテーマとしています。ジャクリーン・ビセット演じる、田舎の退屈から抜け出し、刺激と幸せを掴めると期待しながらカナダからラスベガスにやってきた19歳の若い女性が、ホテルのショー
因みに、「クリスチーヌの性愛記」('72年)は、そのタイトルやチラシなどからポルノ映画と思われているフシがありますが、下にあらすじを書いたように、自分の気の赴くままに生きる若い女性の運命とその悲劇をテーマとしています。ジャクリーン・ビセット演じる、田舎の退屈から抜け出し、刺激と幸せを掴めると期待しながらカナダからラスベガスにやってきた19歳の若い女性が、ホテルのショー ・ガールとしてせっせと働くも、結婚相手が殺害されて生活のためコール・ガールとなり、さらには男に貯めた金を持ち逃げ
・ガールとしてせっせと働くも、結婚相手が殺害されて生活のためコール・ガールとなり、さらには男に貯めた金を持ち逃げ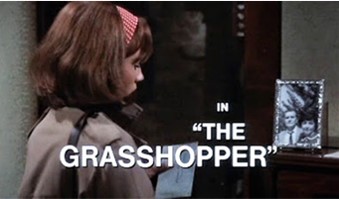 されたりして、最後は夢破れては田舎に戻るという社会派女性映画です。ただ、そう多くの人がこうした映画を見たいとは思わないわけで、そこで原題("The Grasshopper"「バッタ」。次々に世の中を渡り歩く主人公を示していると思われる)を外れて「性愛記」みたいなタイトルにしたのでしょう(ところがポルノチックな場面はほとんど無いため、日本でもヒットしなかった)。(演出面などから)佳作とまでは言えないものの、今思えば多くの点で当時の米国の世相の一端を映し出していた作品でした。
されたりして、最後は夢破れては田舎に戻るという社会派女性映画です。ただ、そう多くの人がこうした映画を見たいとは思わないわけで、そこで原題("The Grasshopper"「バッタ」。次々に世の中を渡り歩く主人公を示していると思われる)を外れて「性愛記」みたいなタイトルにしたのでしょう(ところがポルノチックな場面はほとんど無いため、日本でもヒットしなかった)。(演出面などから)佳作とまでは言えないものの、今思えば多くの点で当時の米国の世相の一端を映し出していた作品でした。 あと、個人的な収穫は、「
あと、個人的な収穫は、「
 「料理長(シェフ)殿、ご用心」●原題:SOMEONE IS KILLING THE GREAT CHEFS OF EUROPE●制作年:1978年●制作国:アメリカ●監督:テッド・コチェフ●脚本:ピーター・ストーン●撮影:ジョン・オルコット
「料理長(シェフ)殿、ご用心」●原題:SOMEONE IS KILLING THE GREAT CHEFS OF EUROPE●制作年:1978年●制作国:アメリカ●監督:テッド・コチェフ●脚本:ピーター・ストーン●撮影:ジョン・オルコット ●音楽:
●音楽:
 ヘラルド映画●最初に観た場所:五反田TOEIシネマ(80-02-18)(評価:★★★☆)●併映「セント・アイブス」(J・リー・トンプソン)/「クリスチーヌの性愛記」(アロイス・ブルマー)
ヘラルド映画●最初に観た場所:五反田TOEIシネマ(80-02-18)(評価:★★★☆)●併映「セント・アイブス」(J・リー・トンプソン)/「クリスチーヌの性愛記」(アロイス・ブルマー)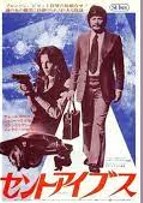


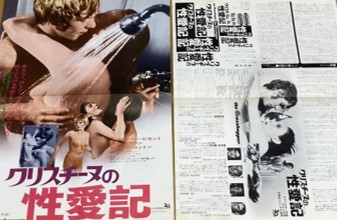
 「クリスチーヌの性愛記」●原題:THE GRASSHOPPER●制作年:1969年●制作国:アメリカ●監督:ジェリー・パリス●製作:ジェリー・ベルソン●脚本:ジェリー・ベルソン/イリー・マーシャル●撮影:サム・リーヴィット●音楽:ビリー・ゴールデンバーグ●原作:マーク・マクシェイン「通り魔」●時間:96分●出演:ジャクリーン・ビセット/ジム・ブラウン/ジョセフ・コットン/コーベット・モニカ/クリストファー・ストーン●日本公開:1972/02●配給:フォックス●最初に観た場所:五反田TOEIシネマ(80-02-18) (評価★★★)●併映「セント・アイブス」(J・リー・トンプソン)/「料理長(シェフ)殿、ご用心」(テッド・コチェフ)
「クリスチーヌの性愛記」●原題:THE GRASSHOPPER●制作年:1969年●制作国:アメリカ●監督:ジェリー・パリス●製作:ジェリー・ベルソン●脚本:ジェリー・ベルソン/イリー・マーシャル●撮影:サム・リーヴィット●音楽:ビリー・ゴールデンバーグ●原作:マーク・マクシェイン「通り魔」●時間:96分●出演:ジャクリーン・ビセット/ジム・ブラウン/ジョセフ・コットン/コーベット・モニカ/クリストファー・ストーン●日本公開:1972/02●配給:フォックス●最初に観た場所:五反田TOEIシネマ(80-02-18) (評価★★★)●併映「セント・アイブス」(J・リー・トンプソン)/「料理長(シェフ)殿、ご用心」(テッド・コチェフ)
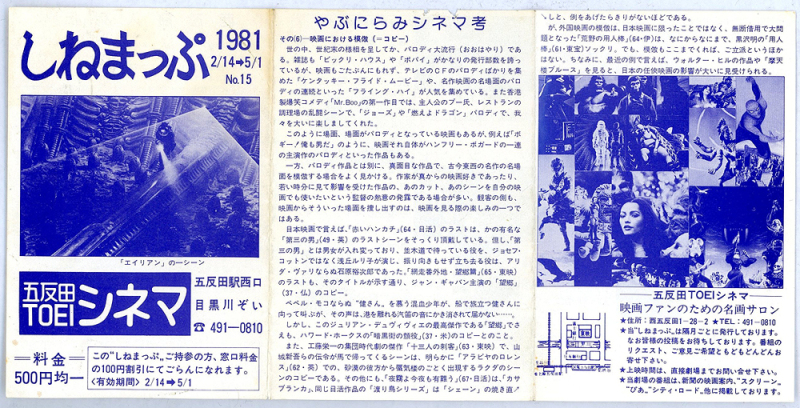


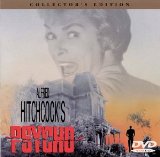

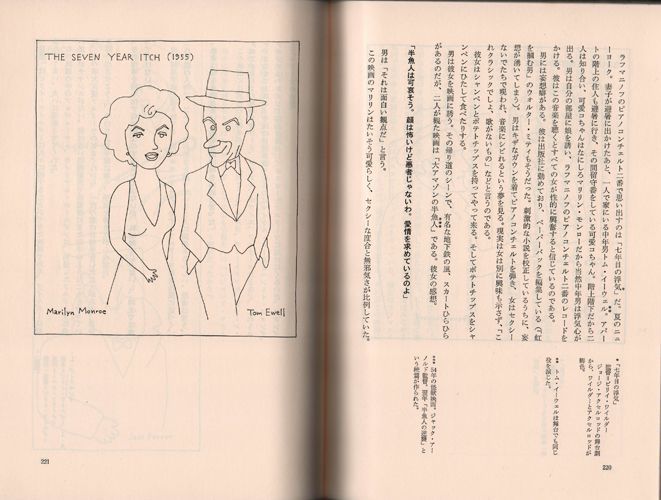
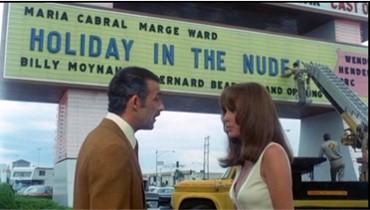 大学生のクリスチーヌ・アダムス(ジャクリーン・ビセット)はカナダの田舎の生活に退屈し、恋人のエディを訪ねてロサンゼルスに向ったが、途中、有名なコメディアンのダニー(コーベット・モニカ)と知り合い華やかなラスベガスを案内してもらった。やっとのこ
大学生のクリスチーヌ・アダムス(ジャクリーン・ビセット)はカナダの田舎の生活に退屈し、恋人のエディを訪ねてロサンゼルスに向ったが、途中、有名なコメディアンのダニー(コーベット・モニカ)と知り合い華やかなラスベガスを案内してもらった。やっとのこ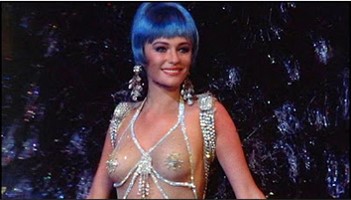 とでエディに会い、しばらく生活したが、ここでも退屈はついてまわった。彼女は再びラスベガスを訪れ、ホテルのショー・ガールとして生活するようになつた。バンドマンのジョイや、支配人トミー(ジム・ブラウン)と知り合い、クリスチーヌはトミーと結婚した。二人はやがてロサンゼルスに移ったが、トミーは、以前クリスチーヌに手を出そうとして喧嘩したデッカーの部下に殺された。失意のどん底に落とされたクリスチーヌはコール・ガールとなり、モーガンという金持の老人の面倒を受けるようになったが、ジェイと再会し、彼との幸福な家庭を夢見てせっせと働いた。ところが、田舎で牧場を経営するためにためた金をジェイに持ち去られ、彼女の夢は一瞬にして消えた。短期間ではあったが、彼女は人生の表裏を見た。22歳の彼女は田舎に戻るより外はなかった。
とでエディに会い、しばらく生活したが、ここでも退屈はついてまわった。彼女は再びラスベガスを訪れ、ホテルのショー・ガールとして生活するようになつた。バンドマンのジョイや、支配人トミー(ジム・ブラウン)と知り合い、クリスチーヌはトミーと結婚した。二人はやがてロサンゼルスに移ったが、トミーは、以前クリスチーヌに手を出そうとして喧嘩したデッカーの部下に殺された。失意のどん底に落とされたクリスチーヌはコール・ガールとなり、モーガンという金持の老人の面倒を受けるようになったが、ジェイと再会し、彼との幸福な家庭を夢見てせっせと働いた。ところが、田舎で牧場を経営するためにためた金をジェイに持ち去られ、彼女の夢は一瞬にして消えた。短期間ではあったが、彼女は人生の表裏を見た。22歳の彼女は田舎に戻るより外はなかった。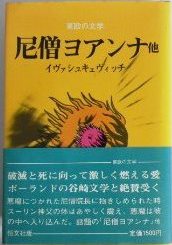

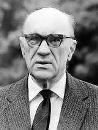
![尼僧ヨアンナ [DVD].jpg](http://hurec.bz/book-movie/%E5%B0%BC%E5%83%A7%E3%83%A8%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%8A%20%5BDVD%5D.jpg)
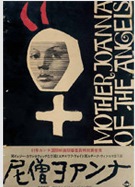

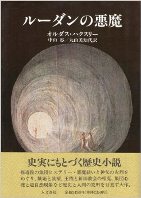

 個人的にもイェジー・カヴァレロヴィッチの映画の方を先に観て(1962年に発足した日本アート・シアター・ギルド(ATG)の配給第1作でもある)、やや内容を忘れかけた頃に原作を読みましたが、そのことにより改めて映画のシーンが甦ってきました。映画を観た際は、ストーリー面で、ラストでスリン神父(ミエチスワフ・ウォイト)がヨアンナ(ルチーナ・ヴィニエツカ)を悪魔から守ることと引き換えに自らが悪魔を引きうけ殺戮を行うというのは、やや映画的な作り方をしているのではないかとも思いましたが、読んでみたら原作もその通りでした。
個人的にもイェジー・カヴァレロヴィッチの映画の方を先に観て(1962年に発足した日本アート・シアター・ギルド(ATG)の配給第1作でもある)、やや内容を忘れかけた頃に原作を読みましたが、そのことにより改めて映画のシーンが甦ってきました。映画を観た際は、ストーリー面で、ラストでスリン神父(ミエチスワフ・ウォイト)がヨアンナ(ルチーナ・ヴィニエツカ)を悪魔から守ることと引き換えに自らが悪魔を引きうけ殺戮を行うというのは、やや映画的な作り方をしているのではないかとも思いましたが、読んでみたら原作もその通りでした。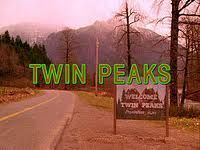

 個人的には「原作が映画と同じ展開だった」のがやや意外であり、岩波文庫版の翻訳者・関口時正氏の解説でも、スーリンに重罪を犯させる結末ではなく、"小説的筋書きとしての効果の成否"についてはともかく、自殺させることでも足りたのではないか
個人的には「原作が映画と同じ展開だった」のがやや意外であり、岩波文庫版の翻訳者・関口時正氏の解説でも、スーリンに重罪を犯させる結末ではなく、"小説的筋書きとしての効果の成否"についてはともかく、自殺させることでも足りたのではないか (自殺も罪ではあるが)と書いているのは、文学作品を読んだつもりが結構"ホラー"だったかもしれないという自分の読後感をある部分代弁してくれているようにも思えました(ヨアンナが突然表情を変え、悪魔の語り口で話し始めるのはまるで映画「エクソシスト」みたい)。
(自殺も罪ではあるが)と書いているのは、文学作品を読んだつもりが結構"ホラー"だったかもしれないという自分の読後感をある部分代弁してくれているようにも思えました(ヨアンナが突然表情を変え、悪魔の語り口で話し始めるのはまるで映画「エクソシスト」みたい)。 因みに、小説は前任者の司祭が火刑に処せられ、若き神父スーリンが悪魔祓いのため派遣されるところから始まりますが、ヨアンナにはジャンヌという実在のモデルがいる一方、このスーリンにもスュランという実在のモデルがいて、1634年、34歳の時に悪魔祓いのため修道院に派遣されて、ジャンヌの悪魔をわが身に引き受けた結果としてボロボロになり、殺人を犯したり自殺したりするまでには至らなかったけれど(自殺未遂はあった)、20年近く闘病・治療生活を送って、60歳を過ぎてやっとジャンヌと過ごした濃密な時間を書き記したものを完成させたようです(内容は、宗教的な矩を超えない範囲で、神秘主義的色合いの濃いものらしい)。
因みに、小説は前任者の司祭が火刑に処せられ、若き神父スーリンが悪魔祓いのため派遣されるところから始まりますが、ヨアンナにはジャンヌという実在のモデルがいる一方、このスーリンにもスュランという実在のモデルがいて、1634年、34歳の時に悪魔祓いのため修道院に派遣されて、ジャンヌの悪魔をわが身に引き受けた結果としてボロボロになり、殺人を犯したり自殺したりするまでには至らなかったけれど(自殺未遂はあった)、20年近く闘病・治療生活を送って、60歳を過ぎてやっとジャンヌと過ごした濃密な時間を書き記したものを完成させたようです(内容は、宗教的な矩を超えない範囲で、神秘主義的色合いの濃いものらしい)。 1961年に作られた映画「尼僧ヨアンナ」は、スターリン主義の抑圧を受けていた当時のポーランド情勢を、戒律下に置かれた修道尼らの性的抑圧として表したと解されることが多いようですが、イエジー・カヴァレロヴィッチ監督には、社会派サスペンス映画「影」('56年)など、ポーランドの政治情勢を反映させながらも娯楽性を含んだ作品も撮っており(この作品と「夜行列車」('59年)、「尼僧ヨアンナ」の3本が最高傑作とされている)、また、「尼僧ヨアンナ」において修道尼たちが一斉に地面に倒れ込むのを俯瞰で撮るなど、カメラワークにも非常に洗練されたものがあって、芸術的完成度は高いように思います(その分、"政治"が後退する? 少なくとも個人的にはあまりプロパガンダ性を感じなかった)。
1961年に作られた映画「尼僧ヨアンナ」は、スターリン主義の抑圧を受けていた当時のポーランド情勢を、戒律下に置かれた修道尼らの性的抑圧として表したと解されることが多いようですが、イエジー・カヴァレロヴィッチ監督には、社会派サスペンス映画「影」('56年)など、ポーランドの政治情勢を反映させながらも娯楽性を含んだ作品も撮っており(この作品と「夜行列車」('59年)、「尼僧ヨアンナ」の3本が最高傑作とされている)、また、「尼僧ヨアンナ」において修道尼たちが一斉に地面に倒れ込むのを俯瞰で撮るなど、カメラワークにも非常に洗練されたものがあって、芸術的完成度は高いように思います(その分、"政治"が後退する? 少なくとも個人的にはあまりプロパガンダ性を感じなかった)。 また、イヴァシュキェヴィッチの原作の方も、1943年という、ポーランドのユダヤ人や知識層が厳しい弾圧を受けていた時期に書かれたものですが(イヴァシュキェヴィッチは既にポーランドを代表する文人であったとともにレジスタンス運動を指揮していた)、岩波文庫版解説で関口時正氏は、「尼僧ヨアンナ」にしてもその他の作品にしても、彼の作品はポーランド現代文学の中では珍しく「徹底的に非政治的で、官能的な小説」であるとしています。
また、イヴァシュキェヴィッチの原作の方も、1943年という、ポーランドのユダヤ人や知識層が厳しい弾圧を受けていた時期に書かれたものですが(イヴァシュキェヴィッチは既にポーランドを代表する文人であったとともにレジスタンス運動を指揮していた)、岩波文庫版解説で関口時正氏は、「尼僧ヨアンナ」にしてもその他の作品にしても、彼の作品はポーランド現代文学の中では珍しく「徹底的に非政治的で、官能的な小説」であるとしています。 この関口時正氏の本作に対する見方には痛く共感しました。イヴァシュキェヴィッチという人は政治と文学を分けて考えていたのではないか。そうして考えると、映画「尼僧ヨアンナ」も、いろいろと背景はあるのかもしれませんが、先ずは、観たままの通り感じればよい作品なのかもしれません。
この関口時正氏の本作に対する見方には痛く共感しました。イヴァシュキェヴィッチという人は政治と文学を分けて考えていたのではないか。そうして考えると、映画「尼僧ヨアンナ」も、いろいろと背景はあるのかもしれませんが、先ずは、観たままの通り感じればよい作品なのかもしれません。  「尼僧ヨアンナ」●原題:MATKA JOANNA OD ANIOLOW(MOTHER JOAN OF THE ANGELS)●制作年:1960年●制作国:アメリカ●監督:イェジー・カヴァレロヴィッチ●脚本:タデウシュ・コンビッキ/イェジー・カヴァレロヴィッチ●撮影:イェジー・ウォイチック●音楽:アダム・ワラチニュスキー●原作:ヤロスワフ・イヴァシュキェヴィッチ●時間:110分●出演:ルチーナ・ウィンニッカ/ミエチスワフ・ウォイト/ミエチスワフ・ウォイト/アンナ・チェピェレフスカ/マリア・フヴァリブク/スタニスラフ・ヤシュキェヴィッチ●日本公開:1962/04●配給:東和/ATG(共同配給)●最初に観た場所:カトル・ド・シネマ上映会(79-04-18)●2回目:北千住・シネマブルースタジオ(10-07-03)(評価:★★★★)●併映:「パサジェルカ」(アンジェイ・ムンク)
「尼僧ヨアンナ」●原題:MATKA JOANNA OD ANIOLOW(MOTHER JOAN OF THE ANGELS)●制作年:1960年●制作国:アメリカ●監督:イェジー・カヴァレロヴィッチ●脚本:タデウシュ・コンビッキ/イェジー・カヴァレロヴィッチ●撮影:イェジー・ウォイチック●音楽:アダム・ワラチニュスキー●原作:ヤロスワフ・イヴァシュキェヴィッチ●時間:110分●出演:ルチーナ・ウィンニッカ/ミエチスワフ・ウォイト/ミエチスワフ・ウォイト/アンナ・チェピェレフスカ/マリア・フヴァリブク/スタニスラフ・ヤシュキェヴィッチ●日本公開:1962/04●配給:東和/ATG(共同配給)●最初に観た場所:カトル・ド・シネマ上映会(79-04-18)●2回目:北千住・シネマブルースタジオ(10-07-03)(評価:★★★★)●併映:「パサジェルカ」(アンジェイ・ムンク)
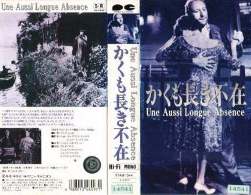

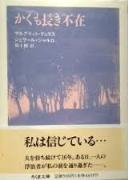
 パリ郊外でカフェを営むテレーズ(アリダ・ヴァリ)はある日、店の前を通る浮浪者に目を止める。その男(ジョルジュ・ウィルソン)は16年前に行方不明になった彼女の夫アルベールにそっくりであった。テレーズはその男とコンタクトをとるが、その男は記憶喪失だった―。
パリ郊外でカフェを営むテレーズ(アリダ・ヴァリ)はある日、店の前を通る浮浪者に目を止める。その男(ジョルジュ・ウィルソン)は16年前に行方不明になった彼女の夫アルベールにそっくりであった。テレーズはその男とコンタクトをとるが、その男は記憶喪失だった―。 の小説『モデラートカンタービレ』(原題:Moderato Cantabile, 1958年)を原作としジャンヌ・モロー、ジャン=ポール・ベルモンドが主演した「雨のしのび逢い」('60年/仏・伊)の脚本家ジェラール・ジャルロと共同でいきなり脚本から書き起こしていて、それは「ちくま文庫」に所収されています。
の小説『モデラートカンタービレ』(原題:Moderato Cantabile, 1958年)を原作としジャンヌ・モロー、ジャン=ポール・ベルモンドが主演した「雨のしのび逢い」('60年/仏・伊)の脚本家ジェラール・ジャルロと共同でいきなり脚本から書き起こしていて、それは「ちくま文庫」に所収されています。
 アリダ・ヴァリはキャロル・リード監督の「第三の男」('49年/英)が有名ですが、この作品を観ると、ミケランジェロ・アントニオーニ監督の「
アリダ・ヴァリはキャロル・リード監督の「第三の男」('49年/英)が有名ですが、この作品を観ると、ミケランジェロ・アントニオーニ監督の「 この「かくも長き不在」においても、アリダ・ヴァリ演じるテレーズには日常においては暗さは無く、16年前にゲシュタポに捕えられたまま消息を絶った夫の帰りを待ちながらも店を営んで逞しく生活しており、若い恋人までいるような様子であって、そこへ抜け殻のようになって現れた"夫かもしれない男"との対比が、逆に男の心的外傷によるトラウマの闇の深さを際立たせています。テレーズが男とぎこちないダンスをした際に、男の頭部の傷に気づく場面はぞっとさせられますが、一方で、そのことにより"夫かもしれない男"に憐れみと慈しみを覚えるテレーズの表情は、まさにアリダ・ヴァリにしか出来ないような演技であり、この作品の白眉と言えます。
この「かくも長き不在」においても、アリダ・ヴァリ演じるテレーズには日常においては暗さは無く、16年前にゲシュタポに捕えられたまま消息を絶った夫の帰りを待ちながらも店を営んで逞しく生活しており、若い恋人までいるような様子であって、そこへ抜け殻のようになって現れた"夫かもしれない男"との対比が、逆に男の心的外傷によるトラウマの闇の深さを際立たせています。テレーズが男とぎこちないダンスをした際に、男の頭部の傷に気づく場面はぞっとさせられますが、一方で、そのことにより"夫かもしれない男"に憐れみと慈しみを覚えるテレーズの表情は、まさにアリダ・ヴァリにしか出来ないような演技であり、この作品の白眉と言えます。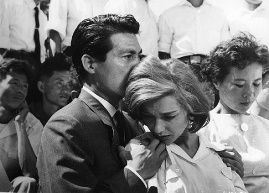 マルグリット・デュラスは多くの作品を残しながら自身も監督業を手掛けていますが、どちらかと言うと原作や脚本を書いたものを別の映画監督が映画化したものの方が知られており、有名なものでは原作・脚本を書き、アラン・レネが監督してカンヌ国際映画祭FIPRESCI(国際映画批評家連盟)賞を受賞した「二十四時間の情事」('59年/仏・日)がありますが、こちらもモチーフとしてナチの収容所体験を持つ女性が出てきます。ヌーヴェル・ヴァーグの色合いを感じる作品で、観念的な原作の文脈でそのまま映像化するとこんな感じかなという作品ですが、これもオリジナルよりは分かり易くなっています。同じアラン・レネ監督の、後にノーベル文学賞を受
マルグリット・デュラスは多くの作品を残しながら自身も監督業を手掛けていますが、どちらかと言うと原作や脚本を書いたものを別の映画監督が映画化したものの方が知られており、有名なものでは原作・脚本を書き、アラン・レネが監督してカンヌ国際映画祭FIPRESCI(国際映画批評家連盟)賞を受賞した「二十四時間の情事」('59年/仏・日)がありますが、こちらもモチーフとしてナチの収容所体験を持つ女性が出てきます。ヌーヴェル・ヴァーグの色合いを感じる作品で、観念的な原作の文脈でそのまま映像化するとこんな感じかなという作品ですが、これもオリジナルよりは分かり易くなっています。同じアラン・レネ監督の、後にノーベル文学賞を受 賞する作家アラン・ロブ=グリエ(1922-2008/享年85)原作の「去年マリエンバートで」('61年/仏)ほどには前衛的ではなく、デュラスの小説の映画化作品は、小説より分かり易くなる傾向にあるように思います(それでもまだ難解な面もあるが、「去年マリエンバートで」のように観ていて眠くなる(?)ことはない)。デュラスの小説『ジブラルタルから来た水夫』を原作とするトニー・リチャードソン監督の「ジブラルタルの追想」('67年/英)なども、えーっ、原作ってこんなラブロマンスなの、というようなハーレクイン風の仕上がりで、ここまで噛み砕いてしまうとどうかなというのはありますが、さすがにこの作品は自身で脚本までは書いていないようです。
賞する作家アラン・ロブ=グリエ(1922-2008/享年85)原作の「去年マリエンバートで」('61年/仏)ほどには前衛的ではなく、デュラスの小説の映画化作品は、小説より分かり易くなる傾向にあるように思います(それでもまだ難解な面もあるが、「去年マリエンバートで」のように観ていて眠くなる(?)ことはない)。デュラスの小説『ジブラルタルから来た水夫』を原作とするトニー・リチャードソン監督の「ジブラルタルの追想」('67年/英)なども、えーっ、原作ってこんなラブロマンスなの、というようなハーレクイン風の仕上がりで、ここまで噛み砕いてしまうとどうかなというのはありますが、さすがにこの作品は自身で脚本までは書いていないようです。 「かくも長き不在」のちくま文庫版の原作脚本を読むと、自身で監督したものに有名な作品は無いけれど、(脚本家の協力・示唆はあったにせよ)小説的効果と映画的効果の違いはわかっていた人ではないかという気がします。特に、この映画のラストの男を呼ぶ声が伝言のように街中を伝わっていく場面は、映画的シチュエーションの極致と言ってよいかと思います。
「かくも長き不在」のちくま文庫版の原作脚本を読むと、自身で監督したものに有名な作品は無いけれど、(脚本家の協力・示唆はあったにせよ)小説的効果と映画的効果の違いはわかっていた人ではないかという気がします。特に、この映画のラストの男を呼ぶ声が伝言のように街中を伝わっていく場面は、映画的シチュエーションの極致と言ってよいかと思います。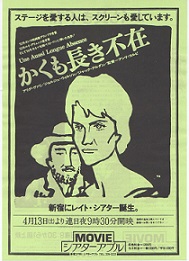
 「かくも長き不在」●原題:UNE AUSSI LONGUE ABSENCE●制作年:1960年●制作国:フランス●監督:アンリ・コルピ●脚本:マルグリット・デュラス/ジェラール・ジャルロ●撮影:マルセル・ウェイス●音楽:ジョルジュ・ドルリュー●時間:98分●出演:アリダ・ヴァリ/ジョルジュ・ウィルソン/シャルル・ブラヴェット/ジャック・アルダン/アナ・レペグリエ●日本公開:1964/08●配給:東和●最初に観た場所:新宿シアターアプル(85-04-21)(評価:★★★★)
「かくも長き不在」●原題:UNE AUSSI LONGUE ABSENCE●制作年:1960年●制作国:フランス●監督:アンリ・コルピ●脚本:マルグリット・デュラス/ジェラール・ジャルロ●撮影:マルセル・ウェイス●音楽:ジョルジュ・ドルリュー●時間:98分●出演:アリダ・ヴァリ/ジョルジュ・ウィルソン/シャルル・ブラヴェット/ジャック・アルダン/アナ・レペグリエ●日本公開:1964/08●配給:東和●最初に観た場所:新宿シアターアプル(85-04-21)(評価:★★★★)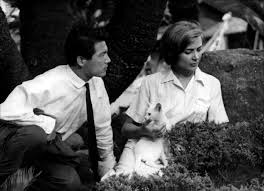


 「去年マリエンバートで」●原題:L'ANNEE DERNIERE A MARIENBAT●制作年:1961年●制作国:フランス・イタリア●監督:アラン・レネ●製作:ピエール・クーロー/レイモン・フロマン●脚本:アラン・ロブ=グリエ●撮影:サッシャ・ヴィエルニ●音楽:フランシス・セイリグ●時間:94分●出演:デルフィー
「去年マリエンバートで」●原題:L'ANNEE DERNIERE A MARIENBAT●制作年:1961年●制作国:フランス・イタリア●監督:アラン・レネ●製作:ピエール・クーロー/レイモン・フロマン●脚本:アラン・ロブ=グリエ●撮影:サッシャ・ヴィエルニ●音楽:フランシス・セイリグ●時間:94分●出演:デルフィー ヌ・セイリグ/ ジョルジュ・アルベルタッツィ(ジョルジョ・アルベルタッツィ)/ サッシャ・ピトエフ/(淑女たち)フランソワーズ・ベルタン/ルーチェ・ガルシア=ヴィレ/エレナ・コルネル/フランソワーズ・スピラ/カリン・トゥーシュ=ミトラー/(紳士たち)ピエール・バルボー/ヴィルヘルム・フォン・デーク/ジャン・ラニエ/ジェラール・ロラン/ダビデ・モンテムーリ/ジル・ケアン/ガブリエル・ヴェルナー/アルフレッド・ヒッチコック●日本公開:1964/05●配給:東和●最初に観た場所:カトル・ド・シネマ上映会(81-05-23)(評価★★★?)●併映:「アンダルシアの犬」(ルイス・ブニュエル)
ヌ・セイリグ/ ジョルジュ・アルベルタッツィ(ジョルジョ・アルベルタッツィ)/ サッシャ・ピトエフ/(淑女たち)フランソワーズ・ベルタン/ルーチェ・ガルシア=ヴィレ/エレナ・コルネル/フランソワーズ・スピラ/カリン・トゥーシュ=ミトラー/(紳士たち)ピエール・バルボー/ヴィルヘルム・フォン・デーク/ジャン・ラニエ/ジェラール・ロラン/ダビデ・モンテムーリ/ジル・ケアン/ガブリエル・ヴェルナー/アルフレッド・ヒッチコック●日本公開:1964/05●配給:東和●最初に観た場所:カトル・ド・シネマ上映会(81-05-23)(評価★★★?)●併映:「アンダルシアの犬」(ルイス・ブニュエル) 「ジブラルタルの追想」●原題:THE SAILOR FROM GIBRALTAR PERFORMER●制作年:1967年●制作国:イギリス●監督:トニー・リチャードソン●製作:オスカー・リュウェンスティン●脚本:クリストファー・イシャーウッド/ドン・マグナー/
「ジブラルタルの追想」●原題:THE SAILOR FROM GIBRALTAR PERFORMER●制作年:1967年●制作国:イギリス●監督:トニー・リチャードソン●製作:オスカー・リュウェンスティン●脚本:クリストファー・イシャーウッド/ドン・マグナー/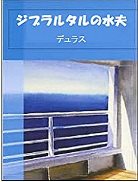
![ジョンとメリー [VHS].jpg](http://hurec.bz/book-movie/%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%81%A8%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%83%BC%20%5BVHS%5D.jpg)
![ジョンとメリー [DVD].jpg](http://hurec.bz/book-movie/%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%81%A8%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%83%BC%20%5BDVD%5D.jpg)
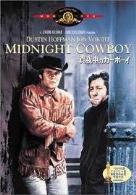
![卒業 [DVD] L.jpg](http://hurec.bz/book-movie/%E5%8D%92%E6%A5%AD%20%5BDVD%5D%20L.jpg)
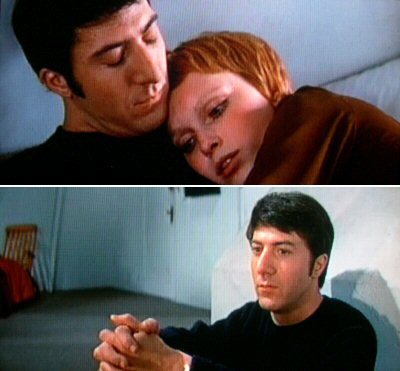 マンハッタンに住む建築技師ジョン(ダスティン・ホフマン)のマンションで目覚めたメリー(ミア・ファロー)は、自分がどこにいるのか暫くの間分からなかった。昨晩、独身男女が集まるバーで2人は出会い、互いの名前も聞かないまま一夜を共にしたのだった。メリーは、整頓されたジョンの家を見て女の影を感じる。ジョンはかつてファッションモデルと同棲していた過去があり、メリーはある有力政治家と愛人関係にあった。朝食を食べ、昼食まで共にした2人は、とりとめのない会話をしながらも、次第に惹かれ合っていくが、ちょっとした出来事のためメリーは帰ってしまう―。
マンハッタンに住む建築技師ジョン(ダスティン・ホフマン)のマンションで目覚めたメリー(ミア・ファロー)は、自分がどこにいるのか暫くの間分からなかった。昨晩、独身男女が集まるバーで2人は出会い、互いの名前も聞かないまま一夜を共にしたのだった。メリーは、整頓されたジョンの家を見て女の影を感じる。ジョンはかつてファッションモデルと同棲していた過去があり、メリーはある有力政治家と愛人関係にあった。朝食を食べ、昼食まで共にした2人は、とりとめのない会話をしながらも、次第に惹かれ合っていくが、ちょっとした出来事のためメリーは帰ってしまう―。 脚本は「シャレード」('63年)の原作者ジョン・モーティマーですが、構成の巧みさもさることながら、演じているダスティン・ホフマンとミア・ファローがそもそも演技達者、とりわけダスティン・ホフマン演じるジョンの、そのままメリーに居ついて欲しいような欲しくないようなその辺りの微妙に揺れる心情が可笑しく(ジョンの方に感情移入して観たというのもあるが)ホントにこの人上手いなあと思いました(でも、ミア・ファローも良かった)。
脚本は「シャレード」('63年)の原作者ジョン・モーティマーですが、構成の巧みさもさることながら、演じているダスティン・ホフマンとミア・ファローがそもそも演技達者、とりわけダスティン・ホフマン演じるジョンの、そのままメリーに居ついて欲しいような欲しくないようなその辺りの微妙に揺れる心情が可笑しく(ジョンの方に感情移入して観たというのもあるが)ホントにこの人上手いなあと思いました(でも、ミア・ファローも良かった)。 最後に互いの気持ちを理解し合えた2人が、そこで初めて「ぼくはジョンだ」「私はメリーよ」という名乗り合う終わり方もお洒落(その時に大方の日本人の観客は初めて、そっか、2人はまだ名前も教え合っていなかったのかと気づいたのでは。アメリカ人だったら普通は最初に名乗るけれど、アメリカ人が見たらどう感じるのだろうか)。観た当時は、これが日本映画だったら、もっとウェットな感じになってしまうのだろうなあと思って、ニューヨークでの一人暮らしに憧れたりもしましたが、逆に、ニューヨークのような大都会で恋人も無く一人で暮らすということになると、(日本以上に)とことん"孤独"に陥るのかも知れないなあとも思ったりして。
最後に互いの気持ちを理解し合えた2人が、そこで初めて「ぼくはジョンだ」「私はメリーよ」という名乗り合う終わり方もお洒落(その時に大方の日本人の観客は初めて、そっか、2人はまだ名前も教え合っていなかったのかと気づいたのでは。アメリカ人だったら普通は最初に名乗るけれど、アメリカ人が見たらどう感じるのだろうか)。観た当時は、これが日本映画だったら、もっとウェットな感じになってしまうのだろうなあと思って、ニューヨークでの一人暮らしに憧れたりもしましたが、逆に、ニューヨークのような大都会で恋人も無く一人で暮らすということになると、(日本以上に)とことん"孤独"に陥るのかも知れないなあとも思ったりして。 そうした大都会での孤独をより端的に描いた作品が、ダスティン・ホフマンがこの作品の前に出演した同年公開のジョン・シュレシンジャー(1926-2003/享年77)監督の「真夜中のカーボーイ」('69年)であり、ジョン・ヴォイトが、"いい男ぶり"で名を挙げようとテキサスからニューヨークに出てきて娼婦に金を巻き上げられてしまう青年ジョーを演じ、一方のダスティン・ホフマンは、スラム街に住む怪しいホームレスのリコ(一旦は、こちらもジョーから金を巻き上げる)役という、その前のダスティン・ホフマンの
そうした大都会での孤独をより端的に描いた作品が、ダスティン・ホフマンがこの作品の前に出演した同年公開のジョン・シュレシンジャー(1926-2003/享年77)監督の「真夜中のカーボーイ」('69年)であり、ジョン・ヴォイトが、"いい男ぶり"で名を挙げようとテキサスからニューヨークに出てきて娼婦に金を巻き上げられてしまう青年ジョーを演じ、一方のダスティン・ホフマンは、スラム街に住む怪しいホームレスのリコ(一旦は、こちらもジョーから金を巻き上げる)役という、その前のダスティン・ホフマンの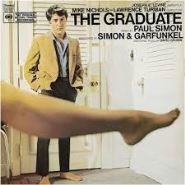 主演作であり、彼自身の主演第1作だったマイク・ニコルズ監督の「卒業」('67年)の優等生役とはうって変った役柄を演じました(「卒業」で主人公が通うコロンビア大学もニューヨーク・マンハッタンにある)。
主演作であり、彼自身の主演第1作だったマイク・ニコルズ監督の「卒業」('67年)の優等生役とはうって変った役柄を演じました(「卒業」で主人公が通うコロンビア大学もニューヨーク・マンハッタンにある)。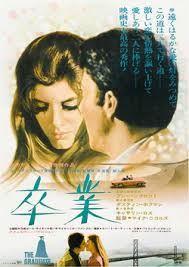 映画デビューした年に「卒業」でアカデミー主演男優賞ノミネートを受け(この作品、今観ると「サウンド・オブ・サイレンス」をはじめ「スカボロ・フェアー」「ミセス・ロビンソン」等々、サイモン&ガー
映画デビューした年に「卒業」でアカデミー主演男優賞ノミネートを受け(この作品、今観ると「サウンド・オブ・サイレンス」をはじめ「スカボロ・フェアー」「ミセス・ロビンソン」等々、サイモン&ガー ファンクルのヒット曲のオン・パレードで、そちらの懐かしさの方が先に立つ)、主演第2作・第3作が「真夜中のカーボーイ」(これもアカデミー主演男優賞ノミネート)と「ジョンとメリー」であるというのもスゴイですが、ゴールデングローブ
ファンクルのヒット曲のオン・パレードで、そちらの懐かしさの方が先に立つ)、主演第2作・第3作が「真夜中のカーボーイ」(これもアカデミー主演男優賞ノミネート)と「ジョンとメリー」であるというのもスゴイですが、ゴールデングローブ 賞新人賞を受賞した「卒業」の、その演技スタイルとは全く異なる演技をその後次々にみせているところがまたスゴイです(「卒業」で英国アカデミー賞新人賞を受賞し、「真夜中のカーボーイ」と「ジョンとメリー」で同賞主演男優賞を受賞している)。
賞新人賞を受賞した「卒業」の、その演技スタイルとは全く異なる演技をその後次々にみせているところがまたスゴイです(「卒業」で英国アカデミー賞新人賞を受賞し、「真夜中のカーボーイ」と「ジョンとメリー」で同賞主演男優賞を受賞している)。 3作品共にアメリカン・ニュー・シネマと呼ばれる作品ですが、その代表作として最も挙げられるのは「真夜中のカーボーイ」でしょう。ニューヨークを逃れ南国のフロリダへ旅立つ乗り合いバスの中でリコが息を引き取るという終わり方も、その系譜を強く打ち出しているように思われます。「真夜中のカーボーイ」も「ジョンとメ
3作品共にアメリカン・ニュー・シネマと呼ばれる作品ですが、その代表作として最も挙げられるのは「真夜中のカーボーイ」でしょう。ニューヨークを逃れ南国のフロリダへ旅立つ乗り合いバスの中でリコが息を引き取るという終わり方も、その系譜を強く打ち出しているように思われます。「真夜中のカーボーイ」も「ジョンとメ リー」も傑作であり、ダスティン・ホフマンはこの主演第2作と第3作で演技派としての名声を確立してしまったわけですが、個人的には「ジョンとメリー」の方が、ラストの明るさもあってかしっくりきました。一方の「真夜中のカーボーイ」の方は、ジョーとリコの奇妙な友情関係にホモセクシュアルの臭いが感じられ、当時としてはやや引いた印象を個人的には抱きましたが、2人の関係を精神的なホモセクシュアルと見る見方は今や当たり前のものとなっており、その分だけ、今観ると逆に抵抗は感じられないかも(但し、原作者のジェームズ・レオ・ハーリヒー自身はゲイだったようだ)。
リー」も傑作であり、ダスティン・ホフマンはこの主演第2作と第3作で演技派としての名声を確立してしまったわけですが、個人的には「ジョンとメリー」の方が、ラストの明るさもあってかしっくりきました。一方の「真夜中のカーボーイ」の方は、ジョーとリコの奇妙な友情関係にホモセクシュアルの臭いが感じられ、当時としてはやや引いた印象を個人的には抱きましたが、2人の関係を精神的なホモセクシュアルと見る見方は今や当たり前のものとなっており、その分だけ、今観ると逆に抵抗は感じられないかも(但し、原作者のジェームズ・レオ・ハーリヒー自身はゲイだったようだ)。![ミスター・グッドバーを探して [VHS].jpg](http://hurec.bz/book-movie/%E3%83%9F%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%82%B0%E3%83%83%E3%83%89%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%92%E6%8E%A2%E3%81%97%E3%81%A6%20%5BVHS%5D.jpg)
 何れもニューヨークを舞台にそこに生きる人間の孤独を描いたものですが、ニューヨークを舞台に男女の出会いを描いた作品がその後は暗いものばかりなっているかと言えばそうでもなく、ロバート・デ・ニーロとメリル・ストリープの演技派2人が共演した「恋におちて」('84年)や、メグ・ライアンとトム・ハンクスによるマンハッタンのアッパーウエストを舞台にしたラブコメディ「ユー・ガット・メール」('98年)など、明るいラブストーリーの系譜は生きています(「ユー・ガット・メール」は1940年に製作されたエルンスト・ルビッチ監督の「街角/桃色(ピンク)の店」のリメイク)。
何れもニューヨークを舞台にそこに生きる人間の孤独を描いたものですが、ニューヨークを舞台に男女の出会いを描いた作品がその後は暗いものばかりなっているかと言えばそうでもなく、ロバート・デ・ニーロとメリル・ストリープの演技派2人が共演した「恋におちて」('84年)や、メグ・ライアンとトム・ハンクスによるマンハッタンのアッパーウエストを舞台にしたラブコメディ「ユー・ガット・メール」('98年)など、明るいラブストーリーの系譜は生きています(「ユー・ガット・メール」は1940年に製作されたエルンスト・ルビッチ監督の「街角/桃色(ピンク)の店」のリメイク)。 「恋におちて」はグランド・セントラル駅の書店での出会いと通勤電車での再会、「ユー・ガット・メール」はインターネット上での出会いと、両作の間にも時の流れを感じますが、前者はクリスマス・プレゼントとして買った本を2人が取り違えてしまうという偶然に端を発し、後者は、メグ・ライアン演じる主人公は絵本書店主、トム・ハンクス演じる男は安売り書店チェーンの御曹司と、実は2人は商売敵だったという偶然のオマケ付き。そのことに起因するバッドエンドの原作を、ハッピーエンドに改変しています。
「恋におちて」はグランド・セントラル駅の書店での出会いと通勤電車での再会、「ユー・ガット・メール」はインターネット上での出会いと、両作の間にも時の流れを感じますが、前者はクリスマス・プレゼントとして買った本を2人が取り違えてしまうという偶然に端を発し、後者は、メグ・ライアン演じる主人公は絵本書店主、トム・ハンクス演じる男は安売り書店チェーンの御曹司と、実は2人は商売敵だったという偶然のオマケ付き。そのことに起因するバッドエンドの原作を、ハッピーエンドに改変しています。 トム・ハンクスとメグ・ライアンは「めぐり逢えたら」('93年)の時と同じ顔合わせで、こちらもレオ・マッケリー監督、ケーリー・グラント、デボラ・カー主演の
トム・ハンクスとメグ・ライアンは「めぐり逢えたら」('93年)の時と同じ顔合わせで、こちらもレオ・マッケリー監督、ケーリー・グラント、デボラ・カー主演の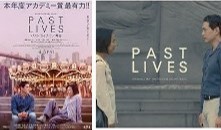
 (●今度は韓国系の男女を主人公にした、ニューヨークでの再会物語が作られた。海外移住のため離れ離れになった幼なじみの2人が、24年の時を経てニューヨークで再会する7日間を描いた、セリーヌ・ソン監督のラブストーリー作品「パスト ライブス/再会」('23年)である。
(●今度は韓国系の男女を主人公にした、ニューヨークでの再会物語が作られた。海外移住のため離れ離れになった幼なじみの2人が、24年の時を経てニューヨークで再会する7日間を描いた、セリーヌ・ソン監督のラブストーリー作品「パスト ライブス/再会」('23年)である。 とソウルでそれぞれの人生を歩んでいた。2人は、オンラインで再会を果たすが、互いを思い合っていながらも再びすれ違ってしまう。そして12年後の36歳、ノラは作家のアーサー(ジョン・マガロ)と結婚していた。ヘソンはそのことを知りながらも、ノラに会うためにニューヨークを訪れ、2人はやっと巡り合うのだが―。
とソウルでそれぞれの人生を歩んでいた。2人は、オンラインで再会を果たすが、互いを思い合っていながらも再びすれ違ってしまう。そして12年後の36歳、ノラは作家のアーサー(ジョン・マガロ)と結婚していた。ヘソンはそのことを知りながらも、ノラに会うためにニューヨークを訪れ、2人はやっと巡り合うのだが―。

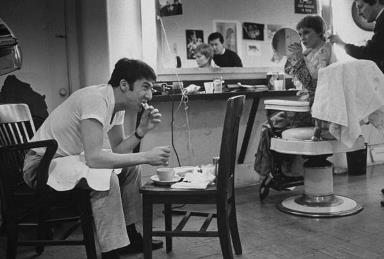 公開:1969/12●配給:20世紀フォックス●最初に観た場所:三鷹東映(78-01-17)(評価:★★★★☆)●併映:「ひとりぼっちの青春」(シドニー・ポラック)/「草原の輝き」(エリア・カザン)三鷹東映 1977年9月3日、それまであった東映系封切館「三鷹東映」が3本立名画座として再スタート。1978年5月に「三鷹オスカー」に改称。1990(平成2)年12月30日閉館。
公開:1969/12●配給:20世紀フォックス●最初に観た場所:三鷹東映(78-01-17)(評価:★★★★☆)●併映:「ひとりぼっちの青春」(シドニー・ポラック)/「草原の輝き」(エリア・カザン)三鷹東映 1977年9月3日、それまであった東映系封切館「三鷹東映」が3本立名画座として再スタート。1978年5月に「三鷹オスカー」に改称。1990(平成2)年12月30日閉館。 「真夜中のカーボーイ」●原題:MIDNIGHT COWBOY●制作年:1969年●制作国:アメリカ●監督:ジョン・シュレシンジャー●製作:ジェローム・ヘルマン●脚本:ウォルド・ソルト●撮影:アダム・ホレンダー●音楽:ジョン・バリー(主題曲「真夜中のカーボーイ」ハーモニカ演奏:トゥーツ・シールマンス)●原作:ジェームズ・レオ・ハーリヒー「真夜中のカーボーイ」●時間:113分●出演:ジョン・ヴ
「真夜中のカーボーイ」●原題:MIDNIGHT COWBOY●制作年:1969年●制作国:アメリカ●監督:ジョン・シュレシンジャー●製作:ジェローム・ヘルマン●脚本:ウォルド・ソルト●撮影:アダム・ホレンダー●音楽:ジョン・バリー(主題曲「真夜中のカーボーイ」ハーモニカ演奏:トゥーツ・シールマンス)●原作:ジェームズ・レオ・ハーリヒー「真夜中のカーボーイ」●時間:113分●出演:ジョン・ヴ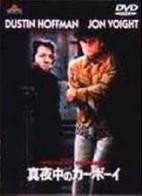
 ファー・ソルト/ボブ・バラバン●日本公開:1969/10●配給:ユナイテッド・アーティスツ●最初に観た場所:早稲田松竹(78-05-20)(評価:★★★★)●併映:「俺たちに明日はない」(アーサー・ペン)
ファー・ソルト/ボブ・バラバン●日本公開:1969/10●配給:ユナイテッド・アーティスツ●最初に観た場所:早稲田松竹(78-05-20)(評価:★★★★)●併映:「俺たちに明日はない」(アーサー・ペン)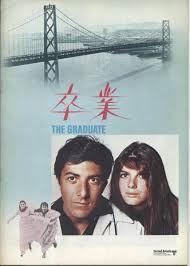 マン●脚本:バック・ヘンリー/カルダー・ウィリンガム●撮影:ロバート・サーティース●音楽:ポール・サイモン
マン●脚本:バック・ヘンリー/カルダー・ウィリンガム●撮影:ロバート・サーティース●音楽:ポール・サイモン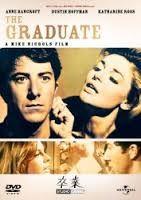
 ニエルズ/エリザベス・ウィルソン/バック・ヘンリー/エドラ・ゲイル/リチャード・ドレイファス●日本公開:1968/06●配給:ユナイテッド・アーティスツ●最初に観た場所:池袋・テアトルダイヤ(83-02-05)(評価:★★★★)●併映:「帰郷」(ハル・アシュビー)
ニエルズ/エリザベス・ウィルソン/バック・ヘンリー/エドラ・ゲイル/リチャード・ドレイファス●日本公開:1968/06●配給:ユナイテッド・アーティスツ●最初に観た場所:池袋・テアトルダイヤ(83-02-05)(評価:★★★★)●併映:「帰郷」(ハル・アシュビー)
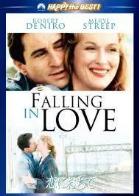
 キー●音楽:デイヴ・グルーシン●時間:106分●出演:ロバート・デ・ニーロ/メリル・ストリープ/ハーヴェイ・カイテル/ジェーン・カツマレク/ジョージ・マーティン/デイヴィッド・クレノン/ダイアン・ウィースト/ヴィクター・アルゴ●日本公開:1985/03●配給:ユニヴァーサル映画配給●最初に観た場所:テアトル池袋(86-10-12)(評価:★★★)●併映:「愛と哀しみの果て」(シドニー・ポラック)
キー●音楽:デイヴ・グルーシン●時間:106分●出演:ロバート・デ・ニーロ/メリル・ストリープ/ハーヴェイ・カイテル/ジェーン・カツマレク/ジョージ・マーティン/デイヴィッド・クレノン/ダイアン・ウィースト/ヴィクター・アルゴ●日本公開:1985/03●配給:ユニヴァーサル映画配給●最初に観た場所:テアトル池袋(86-10-12)(評価:★★★)●併映:「愛と哀しみの果て」(シドニー・ポラック)

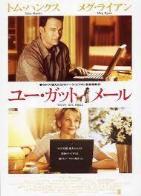
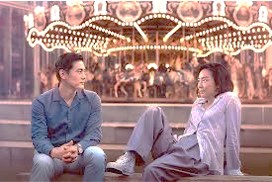 「パスト ライブス/再会」●原題:PAST LIVES●制作年:2023年●制作国:アメリカ●監督・脚本:セリーン・ソン●製作:デイヴィッド・イノヨーサ/クリス
「パスト ライブス/再会」●原題:PAST LIVES●制作年:2023年●制作国:アメリカ●監督・脚本:セリーン・ソン●製作:デイヴィッド・イノヨーサ/クリス チン・ヴァション/パメラ・コフラー●撮影:シャビエル・キーシュナー●音楽:クリストファー・ベア/ダニエル・ローセン●時間:106分●出演:グレタ・リー/ユ・テオ/ジョン・マガロ/ユン・ジヘ/チェ・ウォニョン●日本公開:2024/04●配給:ハピネットファントム・スタジオ●最初に観た場所:Bunkamura ル・シネマ渋谷宮下(24-05-06)((評価:★★☆)
チン・ヴァション/パメラ・コフラー●撮影:シャビエル・キーシュナー●音楽:クリストファー・ベア/ダニエル・ローセン●時間:106分●出演:グレタ・リー/ユ・テオ/ジョン・マガロ/ユン・ジヘ/チェ・ウォニョン●日本公開:2024/04●配給:ハピネットファントム・スタジオ●最初に観た場所:Bunkamura ル・シネマ渋谷宮下(24-05-06)((評価:★★☆)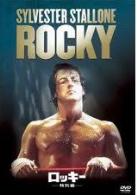
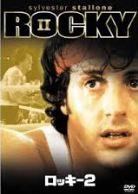
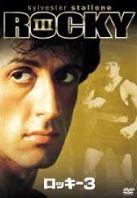
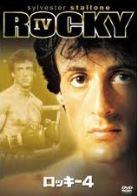
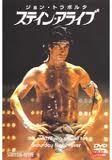
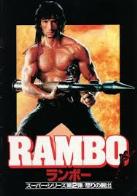
 「ロッキー」('76年)は、シルヴェスター・スタローン(1946年生まれ)が当時、映画オーディションに50回以上落選し、ポルノ映画への出演や用心棒などをして日々の生活費を稼ぐ暮らしの中で、プロボクシングのヘビー級タイトルマッチ「モハメド・アリ対チャック・ウェプナー戦」をテレビで観てウェプナーの善戦に感激し、それに触発されて3日間で脚本を書き上げプロダクションに売り込んだもので、プロダクション側はその脚本に7万5千ドルという、当時としては破格の値をつけたということですから、脚本自体が良かったのでしょう(アカデミー賞作品賞・監督賞、ゴールデングローブ賞作品賞、ロサンゼルス映画批評家協会賞作品賞などを受賞)。
「ロッキー」('76年)は、シルヴェスター・スタローン(1946年生まれ)が当時、映画オーディションに50回以上落選し、ポルノ映画への出演や用心棒などをして日々の生活費を稼ぐ暮らしの中で、プロボクシングのヘビー級タイトルマッチ「モハメド・アリ対チャック・ウェプナー戦」をテレビで観てウェプナーの善戦に感激し、それに触発されて3日間で脚本を書き上げプロダクションに売り込んだもので、プロダクション側はその脚本に7万5千ドルという、当時としては破格の値をつけたということですから、脚本自体が良かったのでしょう(アカデミー賞作品賞・監督賞、ゴールデングローブ賞作品賞、ロサンゼルス映画批評家協会賞作品賞などを受賞)。 プロダクション側は主演にポール・ニューマン、ロバート・レッドフォード、アル・パチーノなどの有名スターを想定していたのに対し(ジェームズ・カーンなども有力な主演候補だった)、スタローンはあくまで自分が主演することに固執したため、最終的に36万ドルまで高騰した脚本は、スタローンの主演と引き換え条件に2万ドルまで減額されたそうな。でも、結果的にスタローンは無名俳優から一躍スターダムに躍り出たわけで、主演に固執して良かった...(逆に言えば、窮乏生活に慣れていたので、カネには固執していなかった)。
プロダクション側は主演にポール・ニューマン、ロバート・レッドフォード、アル・パチーノなどの有名スターを想定していたのに対し(ジェームズ・カーンなども有力な主演候補だった)、スタローンはあくまで自分が主演することに固執したため、最終的に36万ドルまで高騰した脚本は、スタローンの主演と引き換え条件に2万ドルまで減額されたそうな。でも、結果的にスタローンは無名俳優から一躍スターダムに躍り出たわけで、主演に固執して良かった...(逆に言えば、窮乏生活に慣れていたので、カネには固執していなかった)。 日本でも公開当時、誰もがこの作品を観に映画館に押し掛ける状況で、アカデミー賞作品賞受賞、キネマ旬報でも年間1位と高評価。こうなると逆に事前に情報が入り過ぎてしまい、結局個人的にはロードでは観に行かなかったのですが、後で「ロッキー2」('78年)と併せて名画座に降りてきた頃になって遅ればせながら観て、筋書きは分かっていても、やはり感動させられました。
日本でも公開当時、誰もがこの作品を観に映画館に押し掛ける状況で、アカデミー賞作品賞受賞、キネマ旬報でも年間1位と高評価。こうなると逆に事前に情報が入り過ぎてしまい、結局個人的にはロードでは観に行かなかったのですが、後で「ロッキー2」('78年)と併せて名画座に降りてきた頃になって遅ればせながら観て、筋書きは分かっていても、やはり感動させられました。 但し、シルヴェスター・スタローン自身が監督した「ロッキー2」の方はイマイチ、更に、今度こそロードでと観に行った「ロッキー3」('82年)では、対戦相手クラバー(ミスター・T)が全然強そうに見えないのが難で、これもイマイチ。それに比べると、「ロッキー4 炎の友情」('85年)は、ドラゴ(ドルフ・ラングレン)の登場で、多少シリーズ最後を盛り上げたという印象で、個人的にはまあまあ許せるかなという感じでしたが、スタローン自身はこの「ロッキー4 炎の友情」で、ゴールデンラズベリー賞の最低主演男優賞を受賞しています。
但し、シルヴェスター・スタローン自身が監督した「ロッキー2」の方はイマイチ、更に、今度こそロードでと観に行った「ロッキー3」('82年)では、対戦相手クラバー(ミスター・T)が全然強そうに見えないのが難で、これもイマイチ。それに比べると、「ロッキー4 炎の友情」('85年)は、ドラゴ(ドルフ・ラングレン)の登場で、多少シリーズ最後を盛り上げたという印象で、個人的にはまあまあ許せるかなという感じでしたが、スタローン自身はこの「ロッキー4 炎の友情」で、ゴールデンラズベリー賞の最低主演男優賞を受賞しています。 一方、ロッキーより強そうに見えたドラゴを演じたドルフ・ラングレンは、その後「レッド・スコルピオン」('88年/米)に主演。アフリカ南部の共産主義国家に潜入したソ連の特殊部隊兵士の活躍を描くアクション映画でしたが、何だか動きが鈍くなったような...。空手家としての実績もあり、6か国語を話すインテリでもあるそうですが、シルヴェスター・スタローン同様に監督業に進出する傍ら併せて俳優業を続けているものの、B級映画ばかり出ている印象でしょうか。因みに、「レッド・スコルピオン
一方、ロッキーより強そうに見えたドラゴを演じたドルフ・ラングレンは、その後「レッド・スコルピオン」('88年/米)に主演。アフリカ南部の共産主義国家に潜入したソ連の特殊部隊兵士の活躍を描くアクション映画でしたが、何だか動きが鈍くなったような...。空手家としての実績もあり、6か国語を話すインテリでもあるそうですが、シルヴェスター・スタローン同様に監督業に進出する傍ら併せて俳優業を続けているものの、B級映画ばかり出ている印象でしょうか。因みに、「レッド・スコルピオン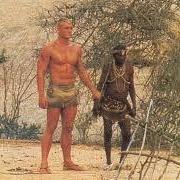
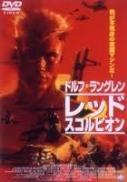
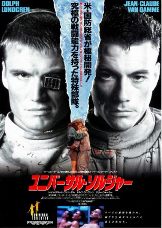
 士を演じていますが、ジャン=クロード・ヴァン・ダム演じる同じく甦ったもう一人の兵士の方が善玉なのに対し、ドルフ・ラングレンの方はヒール役(悪玉)というのが相変わらずでした(まあ、ドルフ・ラングレンの方が見た目が強そうだというのもあるかもしれないが、妥当な配役か)。観た時は可もなく不可もない娯楽作品という印象でしたがそこそこ人気があったのか、その後「ユニバーサル・ソルジャー/ザ・リターン」('99年)、「ユニバーサル・ソルジャー:リジェネレーション」('09年)が作られ、ジャン=クロード・ヴァン・ダムは両方に主演、ドルフ・ラングレンは'09年の方に出ています(2人とも中年にして頑張っている?)。
士を演じていますが、ジャン=クロード・ヴァン・ダム演じる同じく甦ったもう一人の兵士の方が善玉なのに対し、ドルフ・ラングレンの方はヒール役(悪玉)というのが相変わらずでした(まあ、ドルフ・ラングレンの方が見た目が強そうだというのもあるかもしれないが、妥当な配役か)。観た時は可もなく不可もない娯楽作品という印象でしたがそこそこ人気があったのか、その後「ユニバーサル・ソルジャー/ザ・リターン」('99年)、「ユニバーサル・ソルジャー:リジェネレーション」('09年)が作られ、ジャン=クロード・ヴァン・ダムは両方に主演、ドルフ・ラングレンは'09年の方に出ています(2人とも中年にして頑張っている?)。 「ロッキー2」以降はシルヴェスター・スタローン自身が監督しているのですが、ボディビルダーから俳優に転じ、更には州知事も務めたアーノルド・シュワルツェネッガー(1947年生まれ)と比べると、シルヴェスター・スタローンという人は根っから映画が好きなんだなあという気がします。二人が今年['13年]になって初めて本格共演を果たした「大脱出」('13年)のプレミアで、シルヴェスター・スタローンは アーノルド・シュワルツェネッガーについて「20年間、本当に互いを激しく嫌い合っていたんだ」と告白していますが、とはいえ、「それはいいライバルはなかなか見つからないということの証。次第にその存在に感謝するようになる。そうやって競い合ってきたから、こうして二人ここにいるのかも」と今は互いの存在を 認め合っていることを明かしています。個人的には、そもそも映画への関わり方が二人は違うのではないかと。アーノルド・シュワルツェネッガーが「俳優」であるのに対し、シルヴェスター・スタローンは「映画人」という印象であり、脚本を書くか書かないかの違いは大きいように思います。
「ロッキー2」以降はシルヴェスター・スタローン自身が監督しているのですが、ボディビルダーから俳優に転じ、更には州知事も務めたアーノルド・シュワルツェネッガー(1947年生まれ)と比べると、シルヴェスター・スタローンという人は根っから映画が好きなんだなあという気がします。二人が今年['13年]になって初めて本格共演を果たした「大脱出」('13年)のプレミアで、シルヴェスター・スタローンは アーノルド・シュワルツェネッガーについて「20年間、本当に互いを激しく嫌い合っていたんだ」と告白していますが、とはいえ、「それはいいライバルはなかなか見つからないということの証。次第にその存在に感謝するようになる。そうやって競い合ってきたから、こうして二人ここにいるのかも」と今は互いの存在を 認め合っていることを明かしています。個人的には、そもそも映画への関わり方が二人は違うのではないかと。アーノルド・シュワルツェネッガーが「俳優」であるのに対し、シルヴェスター・スタローンは「映画人」という印象であり、脚本を書くか書かないかの違いは大きいように思います。 但し、シルヴェスター・スタローンの映画監督としての力量はどうなのかはやや疑問符も...。作品への思い入れが先行しているような感じもあり、ついていけない人もいるのではないでしょうか。「ロッキー」に関しては、シリーズを通しての熱烈なファンが多くいるようですが、「ロッキー3」と「ロッキー4」の間の時期に、「サタデー・ナイト・フィーバー」('77年)の続編としてシルヴェスター・スタローンが監督した「ステイン・アライブ」('83年、脚本もシルヴェスター・スタローン)は特に見るべきものの無い作品で、この映画に主演したジョン・トラボルタの長期低迷のきっかけになった作品とも言えるのではないかと思います。
但し、シルヴェスター・スタローンの映画監督としての力量はどうなのかはやや疑問符も...。作品への思い入れが先行しているような感じもあり、ついていけない人もいるのではないでしょうか。「ロッキー」に関しては、シリーズを通しての熱烈なファンが多くいるようですが、「ロッキー3」と「ロッキー4」の間の時期に、「サタデー・ナイト・フィーバー」('77年)の続編としてシルヴェスター・スタローンが監督した「ステイン・アライブ」('83年、脚本もシルヴェスター・スタローン)は特に見るべきものの無い作品で、この映画に主演したジョン・トラボルタの長期低迷のきっかけになった作品とも言えるのではないかと思います。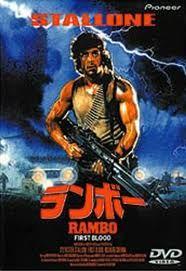
 因みに「ランボー」('82年)のシリーズ作も、全4作全てシルヴェスター・スタローンの脚本または彼が脚本参加しているものでしたが、第1作(「ロッキー3」と同じ年に作られている)の「ランボー1人 vs. 警官千人」に始まり、「ランボー/怒りの脱出」('85年)では「ランボー1人vs.ベトナム軍」、
因みに「ランボー」('82年)のシリーズ作も、全4作全てシルヴェスター・スタローンの脚本または彼が脚本参加しているものでしたが、第1作(「ロッキー3」と同じ年に作られている)の「ランボー1人 vs. 警官千人」に始まり、「ランボー/怒りの脱出」('85年)では「ランボー1人vs.ベトナム軍」、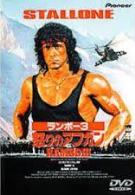 「ランボー3/怒りのアフガン」('88年)では「ランボー1人vs.ソ連軍10万人」とスケール・アップするにつれて、当初のランボーのアウトローの孤独と哀しみは消え、すっかり超人ヒーローになってしまい、「ランボー3/怒りのアフガン」などは、見ていてちっともハラハラしない...。しかも、今思えば皮肉なことに、この作品は、ランボーがアフガン・ゲリラと協力してソ連軍と戦う内容になっていて、当時のアフガン・ゲリラの一派が後のタリバン内の過激武装勢力になっていくわけです。
「ランボー3/怒りのアフガン」('88年)では「ランボー1人vs.ソ連軍10万人」とスケール・アップするにつれて、当初のランボーのアウトローの孤独と哀しみは消え、すっかり超人ヒーローになってしまい、「ランボー3/怒りのアフガン」などは、見ていてちっともハラハラしない...。しかも、今思えば皮肉なことに、この作品は、ランボーがアフガン・ゲリラと協力してソ連軍と戦う内容になっていて、当時のアフガン・ゲリラの一派が後のタリバン内の過激武装勢力になっていくわけです。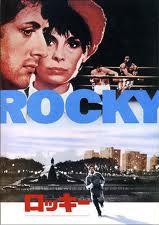

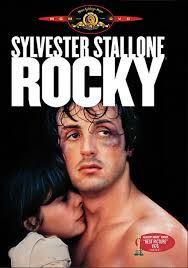 「ロッキー」●原題:ROCKY●制作年:1976年●制作国:アメリカ●監督:ジョン・G・アヴィルドセン●製作:アーウィン・ウィンクラー/ロバート・チャートフ●脚本:シルヴェスター・スタローン●撮影:ジェームズ・グレイブ●音楽:ビル・コンティ●時間:119分●出演:シルヴェスター・スタローン/タリア・シャイア/バート・ヤング/バージェス・メレディス/カール・ウェザース●日本公開:1977/04●配給:ユナイテッド・アーティスツ●最初に観た場所:池袋・文芸坐(81-01-22)(評価:★★★★)●併映:「ロッキー2」(シルヴェスター・スタローン)
「ロッキー」●原題:ROCKY●制作年:1976年●制作国:アメリカ●監督:ジョン・G・アヴィルドセン●製作:アーウィン・ウィンクラー/ロバート・チャートフ●脚本:シルヴェスター・スタローン●撮影:ジェームズ・グレイブ●音楽:ビル・コンティ●時間:119分●出演:シルヴェスター・スタローン/タリア・シャイア/バート・ヤング/バージェス・メレディス/カール・ウェザース●日本公開:1977/04●配給:ユナイテッド・アーティスツ●最初に観た場所:池袋・文芸坐(81-01-22)(評価:★★★★)●併映:「ロッキー2」(シルヴェスター・スタローン)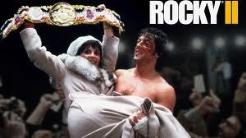 「ロッキー2」●原題:ROCKYⅡ●制作年:1979年●制作国:アメリカ●監督:シルヴェスター・スタローン●製作:アーウィン・ウィンクラー/ロバート・チャートフ●脚本:シルヴェスター・スタローン●撮影:ビル・バトラー●音楽:ビル・コンティ●時間:119分●出演:シルヴェスター・スタローン/タリア・シャイア/バート・ヤング/カール・ウェザース/バージェス・メレディス●日本公開:1979/09●配給:ユナイテッド・アーティスツ●最初に観た場所:池袋・文芸坐(81-01-22)(評価:★★)●併映:「ロッキー」(シルヴェスター・スタローン)
「ロッキー2」●原題:ROCKYⅡ●制作年:1979年●制作国:アメリカ●監督:シルヴェスター・スタローン●製作:アーウィン・ウィンクラー/ロバート・チャートフ●脚本:シルヴェスター・スタローン●撮影:ビル・バトラー●音楽:ビル・コンティ●時間:119分●出演:シルヴェスター・スタローン/タリア・シャイア/バート・ヤング/カール・ウェザース/バージェス・メレディス●日本公開:1979/09●配給:ユナイテッド・アーティスツ●最初に観た場所:池袋・文芸坐(81-01-22)(評価:★★)●併映:「ロッキー」(シルヴェスター・スタローン) 「ロッキー3」●原題:ROCKYⅢ●制作年:1982年●制作国:アメリカ●監督:シルヴェスター・スタローン●製作:アーウィン・ウィンクラー/ロバート・チャートフ●脚本:シルヴェスター・スタローン●撮影:ビル・バトラー●音楽:ビル・コンティ●時間:99分●出演:シルヴェスター・スタローン/タリア・シャイア/バート・ヤング/カール・ウェザース/ミスター・T/ハルク・ホーガン/バージェス・メレディス/トニー・バートン/イアン・フリード/ウォーリー・テイラー/ジム・ヒル/ドン・シャーマン●日本公開:1982/07●配給:ユナイテッド・アーティスツ●最初に観た場所:有楽町・丸の内松竹(82-10-22)(評価:★★)
「ロッキー3」●原題:ROCKYⅢ●制作年:1982年●制作国:アメリカ●監督:シルヴェスター・スタローン●製作:アーウィン・ウィンクラー/ロバート・チャートフ●脚本:シルヴェスター・スタローン●撮影:ビル・バトラー●音楽:ビル・コンティ●時間:99分●出演:シルヴェスター・スタローン/タリア・シャイア/バート・ヤング/カール・ウェザース/ミスター・T/ハルク・ホーガン/バージェス・メレディス/トニー・バートン/イアン・フリード/ウォーリー・テイラー/ジム・ヒル/ドン・シャーマン●日本公開:1982/07●配給:ユナイテッド・アーティスツ●最初に観た場所:有楽町・丸の内松竹(82-10-22)(評価:★★)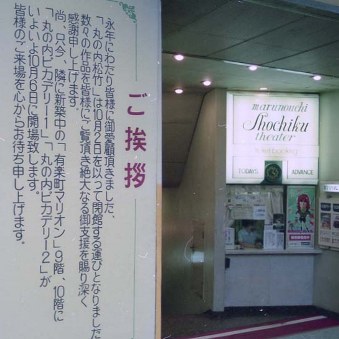



 旧・丸の内松竹 前身は1925年オープンの「邦楽座」(後の「丸の内松竹」)。1957年7月、旧朝日新聞社裏手に「丸の内ピカデリー」オープン(地下に「丸の内松竹」再オープン)。1984年10月2日閉館。1987年10月3日 有楽町マリオン新館5階に後継館として新生「丸の内松竹」(現:丸の内ピカデリー3)がオープン。 2018(平成26)年12月2日「丸の内ピカデリー3」休館。
旧・丸の内松竹 前身は1925年オープンの「邦楽座」(後の「丸の内松竹」)。1957年7月、旧朝日新聞社裏手に「丸の内ピカデリー」オープン(地下に「丸の内松竹」再オープン)。1984年10月2日閉館。1987年10月3日 有楽町マリオン新館5階に後継館として新生「丸の内松竹」(現:丸の内ピカデリー3)がオープン。 2018(平成26)年12月2日「丸の内ピカデリー3」休館。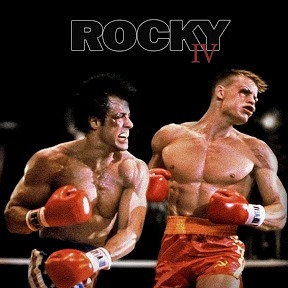 「ロッキー4 炎の友情」●原題:ROCKYⅣ●制作年:1985年●制作国:アメリカ●監督:シルヴェスター・スタローン●製作:アーウィン・ウィンクラー/ロバート・チャートフ●脚本:シルヴェスター・スタローン●撮影:ビル・バトラー●音楽:ビル・コンティ●時間:91分●出演:シルヴェスター・スタローン/タリア・シャイア
「ロッキー4 炎の友情」●原題:ROCKYⅣ●制作年:1985年●制作国:アメリカ●監督:シルヴェスター・スタローン●製作:アーウィン・ウィンクラー/ロバート・チャートフ●脚本:シルヴェスター・スタローン●撮影:ビル・バトラー●音楽:ビル・コンティ●時間:91分●出演:シルヴェスター・スタローン/タリア・シャイア


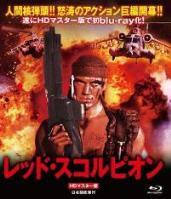
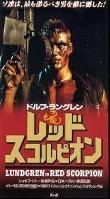 「レッド・スコルピオン」●原題:RED SCORPION●制作年:1989年●制作国:アメリカ●監督:ジョセフ・ジトー●製作:ジャック・エイブラモフ●脚本:アーン・オルセン●撮影:ホアオ・フェルナンデス●音楽:ジェイ・チャタウェイ●時間:106分●出演:ドルフ・ラングレン/M・エメット・ウォルシュ、アル・ホワイト/T・P・マッケンナ/カーメン・アルジェンツィアノ/ブライオン・ジェームズ/ジョセフ・ビッグウッド/ジェイ・チャタウエイ●日本公開:1989/01●配給:日本ヘラルド●最初に観た場所:三軒茶屋映劇(89-07-01)(評価:★★)●併映:「ダイ・ハード」(ジョン・マクティアナン)「
「レッド・スコルピオン」●原題:RED SCORPION●制作年:1989年●制作国:アメリカ●監督:ジョセフ・ジトー●製作:ジャック・エイブラモフ●脚本:アーン・オルセン●撮影:ホアオ・フェルナンデス●音楽:ジェイ・チャタウェイ●時間:106分●出演:ドルフ・ラングレン/M・エメット・ウォルシュ、アル・ホワイト/T・P・マッケンナ/カーメン・アルジェンツィアノ/ブライオン・ジェームズ/ジョセフ・ビッグウッド/ジェイ・チャタウエイ●日本公開:1989/01●配給:日本ヘラルド●最初に観た場所:三軒茶屋映劇(89-07-01)(評価:★★)●併映:「ダイ・ハード」(ジョン・マクティアナン)「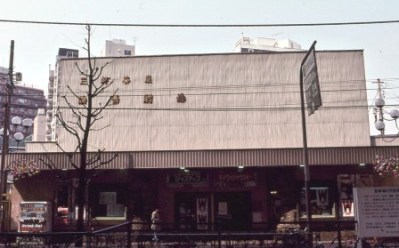


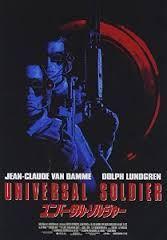
 「ユニバーサル・ソルジャー」●原題:UNIVERSAL SOLDIER●制作年:1992年●制作国:アメリカ●監督:ローランド・エメリッヒ●製作:アレン・シャピロ/クレイグ・ボームガーテン/ジョエル・B・マイケルズ●脚本:リチャード・ロススタイン/クリストファー・レイッチ/ディーン・デヴリン●撮影:カール・W・リンデンローブ●音楽:クリストファー・フランケ●時間:102分●出演:ジャン=クロード・ヴァン・ダム/ドルフ・ラングレン/アリー・ウォーカー/ジョセフ・マローン/エド・オロス/ジーン・デイヴィス/レオン・リッピー/ランス・ハワード/リリアン・ショウバン/チコ・ウェルズ/ジェリー・オーバック●日本公開:1992/11●配給:東宝東和(評価:★★★)
「ユニバーサル・ソルジャー」●原題:UNIVERSAL SOLDIER●制作年:1992年●制作国:アメリカ●監督:ローランド・エメリッヒ●製作:アレン・シャピロ/クレイグ・ボームガーテン/ジョエル・B・マイケルズ●脚本:リチャード・ロススタイン/クリストファー・レイッチ/ディーン・デヴリン●撮影:カール・W・リンデンローブ●音楽:クリストファー・フランケ●時間:102分●出演:ジャン=クロード・ヴァン・ダム/ドルフ・ラングレン/アリー・ウォーカー/ジョセフ・マローン/エド・オロス/ジーン・デイヴィス/レオン・リッピー/ランス・ハワード/リリアン・ショウバン/チコ・ウェルズ/ジェリー・オーバック●日本公開:1992/11●配給:東宝東和(評価:★★★) 「ステイン・アライブ」●原題:STAYING ALIVE●制作年:1983年●制作国:アメリカ●監督:シルヴェスター・スタローン●製作:シルヴェスター・スタローン/ロバート・スティグウッド●脚本:シルヴェスター・スタローン/ノーマン・ウェクスラー●撮影:ニック・マクリーン●音楽:ビージーズ/フランク・スタローン●時間:96分●出演:ジョン・トラボルタ/シンシア・ローズ/フィノラ・ヒューズ/スティーヴ・
「ステイン・アライブ」●原題:STAYING ALIVE●制作年:1983年●制作国:アメリカ●監督:シルヴェスター・スタローン●製作:シルヴェスター・スタローン/ロバート・スティグウッド●脚本:シルヴェスター・スタローン/ノーマン・ウェクスラー●撮影:ニック・マクリーン●音楽:ビージーズ/フランク・スタローン●時間:96分●出演:ジョン・トラボルタ/シンシア・ローズ/フィノラ・ヒューズ/スティーヴ・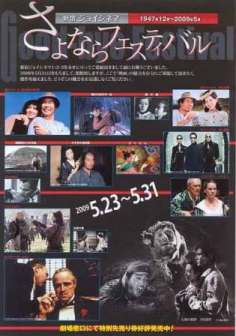 インウッド/ジュリー・ボヴァッソ/チャールズ・ウォード●日本公開:1983/12●配給:パラマウント映画=CIC●最初に観た場所:新宿ジョイシネマ(84-04-07)(評価:★★★)
インウッド/ジュリー・ボヴァッソ/チャールズ・ウォード●日本公開:1983/12●配給:パラマウント映画=CIC●最初に観た場所:新宿ジョイシネマ(84-04-07)(評価:★★★)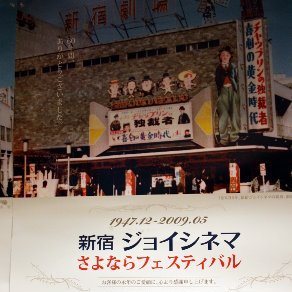

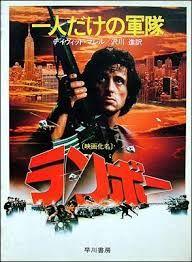
 「ランボー」●原題:FIRST BLOOD●制作年:1982年●制作国:アメリカ●監督:テッド・コッチェフ●製作:バズ・フェイシャンズ●脚本:マイケル・コゾル/ウィリアム・サックハイム/シルヴェスター・スタローン●撮影:アンドリュー・ラズロ●音楽:ジェリー・ゴールドスミス●原作:ディヴィッド・マレル「一人だけの軍隊」●時間:97分●出演:シルヴェスター・スタローン/リチャード・クレンナ/ブライアン・デネヒー/デビッド・カルーソ/ジャック・スターレット/マイケル・タルボット/デビッド・クロウレイ●日本公開:1982/10●配給:東宝東和●最初に観た場所:新宿ローヤル(84-09-24)(評価:★★★)『
「ランボー」●原題:FIRST BLOOD●制作年:1982年●制作国:アメリカ●監督:テッド・コッチェフ●製作:バズ・フェイシャンズ●脚本:マイケル・コゾル/ウィリアム・サックハイム/シルヴェスター・スタローン●撮影:アンドリュー・ラズロ●音楽:ジェリー・ゴールドスミス●原作:ディヴィッド・マレル「一人だけの軍隊」●時間:97分●出演:シルヴェスター・スタローン/リチャード・クレンナ/ブライアン・デネヒー/デビッド・カルーソ/ジャック・スターレット/マイケル・タルボット/デビッド・クロウレイ●日本公開:1982/10●配給:東宝東和●最初に観た場所:新宿ローヤル(84-09-24)(評価:★★★)『
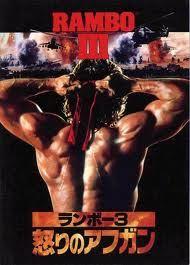 「ランボー3/怒りのアフガン」●原題:RAMBO 3●制作年:1988年●制作国:アメリカ●監督:ピーター・マクドナルド●製作:バズ・フェイシャンズ●脚本:シルヴェスター・スタローン/シェルドン・レティック●撮影:ジョン・スタニアー●音楽:ジェリー・ゴールドスミス●原作:ディヴィッド・マレル●時間:97分●出演:シルヴェスター・スタローン/リチャード・クレンナ/カートウッド・スミス●日本公開:1988/06●配給:東宝東和●最初に観た場所:歌舞伎町・新宿プラザ(88-07-10)(評価:★★)
「ランボー3/怒りのアフガン」●原題:RAMBO 3●制作年:1988年●制作国:アメリカ●監督:ピーター・マクドナルド●製作:バズ・フェイシャンズ●脚本:シルヴェスター・スタローン/シェルドン・レティック●撮影:ジョン・スタニアー●音楽:ジェリー・ゴールドスミス●原作:ディヴィッド・マレル●時間:97分●出演:シルヴェスター・スタローン/リチャード・クレンナ/カートウッド・スミス●日本公開:1988/06●配給:東宝東和●最初に観た場所:歌舞伎町・新宿プラザ(88-07-10)(評価:★★)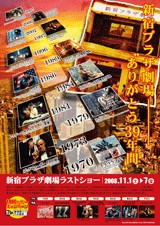


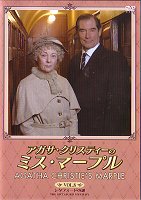

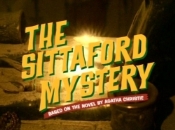
 プロローグで、エジプトの秘宝発掘現場で2人の男が王の墓から財宝を見つける。その25年後、「シタフォード荘」に住むトレヴェリアン大佐(ティモシー・ダルトン)は、現首相チャーチルの後継と目されている。彼が後見人となっているジム・ピアソン(ローレンス・フォックス)は、素
プロローグで、エジプトの秘宝発掘現場で2人の男が王の墓から財宝を見つける。その25年後、「シタフォード荘」に住むトレヴェリアン大佐(ティモシー・ダルトン)は、現首相チャーチルの後継と目されている。彼が後見人となっているジム・ピアソン(ローレンス・フォックス)は、素 行不良のため遺産相続人から外す旨の手紙を大佐から受け取ったとして怒っているが、大佐は、自分がその手紙を書いたことを否定する。酔い潰れたジムを、その婚約者エミリー(ゾーイ・テルフォード)は、パーティーで偶然知り合った新聞記者チャールズ・バーナビー(ジェームズ・マリー)とともに家に送り届けるが、翌日ジムは大佐に会うと言って、降りしきる雪の中、シタフォード荘に向かう。ミス・マープル(
行不良のため遺産相続人から外す旨の手紙を大佐から受け取ったとして怒っているが、大佐は、自分がその手紙を書いたことを否定する。酔い潰れたジムを、その婚約者エミリー(ゾーイ・テルフォード)は、パーティーで偶然知り合った新聞記者チャールズ・バーナビー(ジェームズ・マリー)とともに家に送り届けるが、翌日ジムは大佐に会うと言って、降りしきる雪の中、シタフォード荘に向かう。ミス・マープル( ジェラルディン・マクイーワン)は甥で作家のレイモンドの別荘を訪ねてシタフォードに来たが、レイモンドは戻れず、彼女は、近くの「シタフォード荘」に泊めてもらうことになる。大佐の親友エンダービー(メル・スミス)は、大佐の政務官であり「シタフォード荘」を管理している。大佐は、そのエンダービーにも行先を告げずに山荘を出るが、ミス・マープルは彼が、ホテル「スリークラウン館」に偽名で予約を入れるのを聞いていた。エンダービーは、山荘に送り届けられたゼリーを食べた飼い鷹が死んだのを見て、大佐の身を案じて吹雪の中「スリークラウン館」に向
ジェラルディン・マクイーワン)は甥で作家のレイモンドの別荘を訪ねてシタフォードに来たが、レイモンドは戻れず、彼女は、近くの「シタフォード荘」に泊めてもらうことになる。大佐の親友エンダービー(メル・スミス)は、大佐の政務官であり「シタフォード荘」を管理している。大佐は、そのエンダービーにも行先を告げずに山荘を出るが、ミス・マープルは彼が、ホテル「スリークラウン館」に偽名で予約を入れるのを聞いていた。エンダービーは、山荘に送り届けられたゼリーを食べた飼い鷹が死んだのを見て、大佐の身を案じて吹雪の中「スリークラウン館」に向 かうが、歩いて2時間はかかる。更にそれを案じたチャールズが後を追う。「スリークラウン館」は、カークウッド(ジェームズ・ウィルビー)が昨年ここを買い取ったもの
かうが、歩いて2時間はかかる。更にそれを案じたチャールズが後を追う。「スリークラウン館」は、カークウッド(ジェームズ・ウィルビー)が昨年ここを買い取ったもの で、ミセス・ウィレット(パトリシア・ホッジ)と娘のヴァイオレット(キャリー・マリガン)、ミス・パークハウス(リタ・トゥシンハム)ら何人かの客がいて、ウィレット夫人の提案で、ホテルの客たちを集めての心霊占いが始まるが、占いの結果「今夜トレヴェリアン大佐が死ぬ」という言葉が現れる。エンダービーが到着し、途中で彼に追いついたチャールズと共に大佐の部屋に行くと、彼は胸を刺されて死んでいた。大雪で警察が来られないため、エンダービーが捜査に当たる―。
で、ミセス・ウィレット(パトリシア・ホッジ)と娘のヴァイオレット(キャリー・マリガン)、ミス・パークハウス(リタ・トゥシンハム)ら何人かの客がいて、ウィレット夫人の提案で、ホテルの客たちを集めての心霊占いが始まるが、占いの結果「今夜トレヴェリアン大佐が死ぬ」という言葉が現れる。エンダービーが到着し、途中で彼に追いついたチャールズと共に大佐の部屋に行くと、彼は胸を刺されて死んでいた。大雪で警察が来られないため、エンダービーが捜査に当たる―。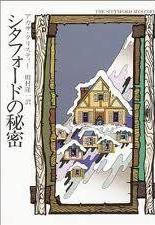
 2006年に本国イギリスで放映されたジェラルディン・マクイーワン主演のグラナダ版で、シーズン2の第4話(通算第8話)。日本ではNHK‐BS2で2008年6月26日に初放映。
2006年に本国イギリスで放映されたジェラルディン・マクイーワン主演のグラナダ版で、シーズン2の第4話(通算第8話)。日本ではNHK‐BS2で2008年6月26日に初放映。 降霊会の行われるのが原作の「シタフォード荘」でではなく、「スリークラウン館」に改変されていて、「シタフォード荘」の降霊会で「大佐が死ぬ」というお告げがあったちょうどその頃、「スリークラウン館」で大佐は殺害されたらしい、というのが原作のミソであるのに対し、「スリークラウン館」で行われた降霊会に大佐自身が加わっていて、その後で殺害されるので、その分、ミステリアスな雰囲気は削がれてしまっています。
降霊会の行われるのが原作の「シタフォード荘」でではなく、「スリークラウン館」に改変されていて、「シタフォード荘」の降霊会で「大佐が死ぬ」というお告げがあったちょうどその頃、「スリークラウン館」で大佐は殺害されたらしい、というのが原作のミソであるのに対し、「スリークラウン館」で行われた降霊会に大佐自身が加わっていて、その後で殺害されるので、その分、ミステリアスな雰囲気は削がれてしまっています。 原作では、事件を解決したエミリーが、頼りない男である婚約者ジムと、事件を通して距離の狭まった新聞記者チャールズのどちらを選ぶかが1つの見所で、最終的にはやはり婚約者の方を選んで、出来る女性というのは意外と頼りない男の方を選んだりするものだなあと思わせる面がありましたが、この映像化作品に登場するジム・ピアソンは最初からどうしようもない男で、そもそもなぜエミリーはこんな男と婚約したのかと思わざるをえません(そのエミリーも、やや高慢ちきで、原作ほど魅力的な女性にはなっていないのだが)。 エミリー(ゾーイ・テルフォード)
原作では、事件を解決したエミリーが、頼りない男である婚約者ジムと、事件を通して距離の狭まった新聞記者チャールズのどちらを選ぶかが1つの見所で、最終的にはやはり婚約者の方を選んで、出来る女性というのは意外と頼りない男の方を選んだりするものだなあと思わせる面がありましたが、この映像化作品に登場するジム・ピアソンは最初からどうしようもない男で、そもそもなぜエミリーはこんな男と婚約したのかと思わざるをえません(そのエミリーも、やや高慢ちきで、原作ほど魅力的な女性にはなっていないのだが)。 エミリー(ゾーイ・テルフォード) 「この線でいくと、こっちは最後、チャールズの方を選ぶだろうなあ」と思わせるのが1つの引っ掛けだったわけかと。原作の真犯人バーナビー少佐がエンダービーに改名され、新聞記者のチャールズ・"エンダビー"の名前がチャールズ・"バーナビー" に改名されていることが「伏線」だったわけですが、凝り過ぎていて分かんないよ、そんな細かいところは...(因みに、ミセス・ウィレットの娘で原作のヴァイリットも"ヴァイオレット"に改変され、トレヴェリアン大佐がエジプト時代に愛した娘と同名という設定になっているが、こんな話は原作には元々は無い)。 トレヴェリアン(ティモシー・ダルトン)/ヴァイオレット(キャリー・マリガン)
「この線でいくと、こっちは最後、チャールズの方を選ぶだろうなあ」と思わせるのが1つの引っ掛けだったわけかと。原作の真犯人バーナビー少佐がエンダービーに改名され、新聞記者のチャールズ・"エンダビー"の名前がチャールズ・"バーナビー" に改名されていることが「伏線」だったわけですが、凝り過ぎていて分かんないよ、そんな細かいところは...(因みに、ミセス・ウィレットの娘で原作のヴァイリットも"ヴァイオレット"に改変され、トレヴェリアン大佐がエジプト時代に愛した娘と同名という設定になっているが、こんな話は原作には元々は無い)。 トレヴェリアン(ティモシー・ダルトン)/ヴァイオレット(キャリー・マリガン)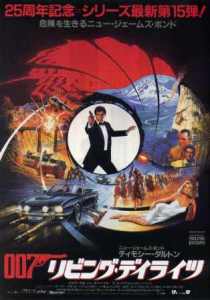
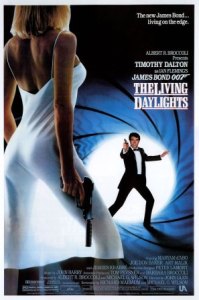 ティモシー・ダルトンは007シリーズの4代目ジェームズ・ボンド役で、シリーズ第15作、第16作に主演(原作は共にイアン・フレミングの短編、監督は共にジョン・グレン)。第15作「007 リビング・デイライツ」('87年)は、高齢
ティモシー・ダルトンは007シリーズの4代目ジェームズ・ボンド役で、シリーズ第15作、第16作に主演(原作は共にイアン・フレミングの短編、監督は共にジョン・グレン)。第15作「007 リビング・デイライツ」('87年)は、高齢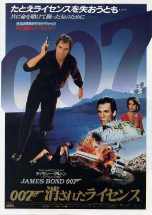
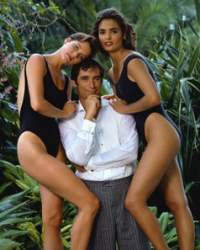 続く第16作「007 消されたライセンス」('89年)は、'89年11月にベルリンの壁が崩壊したこともあり、冷戦下で作られた最後の007シリーズ作品です。ストーリー的も冷戦の要素が組み込まれた最後の作品とされていますが、ボンドの実質的な敵役は既に、前作のKGBから麻薬王へと変わっています。「古い時代の名残を感じられる最後のボンド映画」との見方もありますが、個人的には、ティモシー・ダルトンになってアメリカのアクション映画とあまり変わらなくなってきた印象を受けました。麻薬王の役は前年に「ダイ・ハード」('88年)でFBI特別捜査官を演
続く第16作「007 消されたライセンス」('89年)は、'89年11月にベルリンの壁が崩壊したこともあり、冷戦下で作られた最後の007シリーズ作品です。ストーリー的も冷戦の要素が組み込まれた最後の作品とされていますが、ボンドの実質的な敵役は既に、前作のKGBから麻薬王へと変わっています。「古い時代の名残を感じられる最後のボンド映画」との見方もありますが、個人的には、ティモシー・ダルトンになってアメリカのアクション映画とあまり変わらなくなってきた印象を受けました。麻薬王の役は前年に「ダイ・ハード」('88年)でFBI特別捜査官を演 じたロバート・デヴィ、ボンド・ガールはキャリー・ローウェル(味方側)とタリサ・ソト(敵側)でこちらも共に米国出身、ティモシー・ダルトン"ボンド"は、この敵味方二人の女性に助けられてばかりだったなあ。
じたロバート・デヴィ、ボンド・ガールはキャリー・ローウェル(味方側)とタリサ・ソト(敵側)でこちらも共に米国出身、ティモシー・ダルトン"ボンド"は、この敵味方二人の女性に助けられてばかりだったなあ。 ティモシー・ダルトンは、'71年にショーン・コネリーの後任としてボンド役を依頼されていますが、ボンドを演じるには若すぎるという理由で辞退し、'79年にロジャー・ムーアが降板を考えていたために来た依頼も断っており、3度目の依頼でようやく引き受けたとのことです。但し、この2作でボンド役を降ろされてしまい、次回作からボンド役は
ティモシー・ダルトンは、'71年にショーン・コネリーの後任としてボンド役を依頼されていますが、ボンドを演じるには若すぎるという理由で辞退し、'79年にロジャー・ムーアが降板を考えていたために来た依頼も断っており、3度目の依頼でようやく引き受けたとのことです。但し、この2作でボンド役を降ろされてしまい、次回作からボンド役は
 「アガサ・クリスティー ミス・マープル(第8話)/シタフォードの謎」●原題:THE SITTAFORD MYSTERY, AGATHA CHRISTIE`S MARPLE SEASON 2●制作年:2006年●制作国:イギリス●演出:ポール・アンウィン●脚本:スティーヴン・チャーチェット●原作:アガサ・クリスティ●時間:93分●出演:ジェラルディン・マクイーワン/ティモシー・ダルトン/マイケル・ブランドン/ローレンス・フォックス/ロバート・ハーディ/パトリシア・ホッジ/ポ
「アガサ・クリスティー ミス・マープル(第8話)/シタフォードの謎」●原題:THE SITTAFORD MYSTERY, AGATHA CHRISTIE`S MARPLE SEASON 2●制作年:2006年●制作国:イギリス●演出:ポール・アンウィン●脚本:スティーヴン・チャーチェット●原作:アガサ・クリスティ●時間:93分●出演:ジェラルディン・マクイーワン/ティモシー・ダルトン/マイケル・ブランドン/ローレンス・フォックス/ロバート・ハーディ/パトリシア・ホッジ/ポ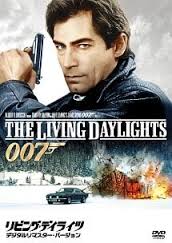
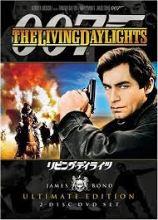
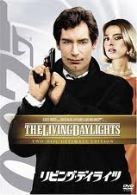 ●監督:ジョン・グレン●製作:マイケル・G・ウィルソン/アルバート・R・ブロッコリ●脚本:リチャード・メイボーム/マイケル・G・ウィルソン●撮影:アレック・ミルズ●音楽:ジョン・バリー●原作:イアン・フレミング●時間:130分●出演:ティモシー・ダルトン/マリアム・ダボ/ジェローン・クラッベ/ジョー・ドン・ベイカー/ジョン・リス=デイヴィス/アート・マリック/ジョン・テリー/アンドレアス・ウィズニュースキー/デスモンド・リュウェリン/ロバート・ブラウン/キャロライン・ブリス●日本公開:1987/12●配給:MGM=ユナイテッド・アーティスツ(評価:★★★) 「
●監督:ジョン・グレン●製作:マイケル・G・ウィルソン/アルバート・R・ブロッコリ●脚本:リチャード・メイボーム/マイケル・G・ウィルソン●撮影:アレック・ミルズ●音楽:ジョン・バリー●原作:イアン・フレミング●時間:130分●出演:ティモシー・ダルトン/マリアム・ダボ/ジェローン・クラッベ/ジョー・ドン・ベイカー/ジョン・リス=デイヴィス/アート・マリック/ジョン・テリー/アンドレアス・ウィズニュースキー/デスモンド・リュウェリン/ロバート・ブラウン/キャロライン・ブリス●日本公開:1987/12●配給:MGM=ユナイテッド・アーティスツ(評価:★★★) 「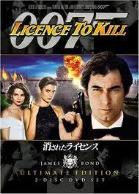
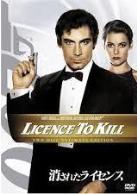 消されたライセンス」●原題:JAMES BOND 007 LICENCE TO KILL●制作年:1989年●制作国:イギリス・アメリカ●監督:ジョン・グレン●製作:マイケル・G・ウィルソン/アルバート・R・ブロッコリ●脚本:リチャード・メイボーム/マイケル・G・ウィルソン●撮影:アレック・マイルズ●音楽:マイケル・ケイメン●原作:イアン・フレミング●時間:133分●出演:ティモシー・ダルトン/キャリー・ローウェル/ロバート・ダヴィ/タリサ・ソトアンソニー・ザーブ/フランク・マクレイ/エヴェレット・マッギル/ウェイン・ニュートン/デスモンド・リュウェリン●日本公開:1989/09●配給:MGM=ユナイテッド・アーティスツ(評価:★★★) 「
消されたライセンス」●原題:JAMES BOND 007 LICENCE TO KILL●制作年:1989年●制作国:イギリス・アメリカ●監督:ジョン・グレン●製作:マイケル・G・ウィルソン/アルバート・R・ブロッコリ●脚本:リチャード・メイボーム/マイケル・G・ウィルソン●撮影:アレック・マイルズ●音楽:マイケル・ケイメン●原作:イアン・フレミング●時間:133分●出演:ティモシー・ダルトン/キャリー・ローウェル/ロバート・ダヴィ/タリサ・ソトアンソニー・ザーブ/フランク・マクレイ/エヴェレット・マッギル/ウェイン・ニュートン/デスモンド・リュウェリン●日本公開:1989/09●配給:MGM=ユナイテッド・アーティスツ(評価:★★★) 「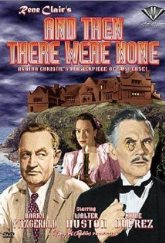
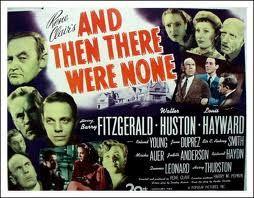

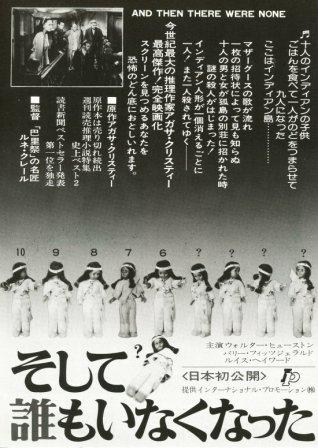
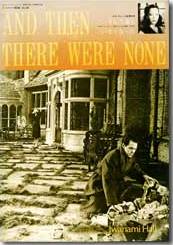 孤島の別荘に8人の男女が招待されてやって来るが、別荘には主人の姿が見えず、執事のロジャース夫婦がいるだけだった。彼らは皆、手紙で招かれたのだが、差出人のユー・エヌ・オーエン(U. N. Owen)氏を誰も知らず、執事夫婦も手紙で雇われ、つい先日島に来たばかりだった。本土との連絡は数日後に来るボートのみで、それ迄彼らは島に閉じ込められたことになる。ホールの10体のインディアンの置物を見てヴェラ(ジューン・デュプレ)は、10人のインディアンが最後は「誰もいなくなった」という古い子守唄を思い出す。彼らがくつろいでいる時、執事がかけたレコードから声がして、10人はいずれも過去に殺人を犯したと告発、全員がそれを否定する。判事(バリー・フィッツジェラルド)は U. N. Owen が Unknown(名無し者)と発音できることに気づく。一人が毒入る酒を飲んで咽喉をつまらせて死んだのを皮切りに、彼らは唄の文句通りに次々殺されてゆき、殺人の後は必ずインディアンの人形が1体壊されていた。殺人者は彼らの中にいることは明らかである。判事、アームストロング医師(ウォルター・ヒューストン)、ブロア、ロンバード(ルイス・ヘイワード)、ヴェラの5人が残る。4人は罪を認めるがヴェラは無実を主張する。更に3人が殺され、残りはヴェラとロンバードの2人となる―。
孤島の別荘に8人の男女が招待されてやって来るが、別荘には主人の姿が見えず、執事のロジャース夫婦がいるだけだった。彼らは皆、手紙で招かれたのだが、差出人のユー・エヌ・オーエン(U. N. Owen)氏を誰も知らず、執事夫婦も手紙で雇われ、つい先日島に来たばかりだった。本土との連絡は数日後に来るボートのみで、それ迄彼らは島に閉じ込められたことになる。ホールの10体のインディアンの置物を見てヴェラ(ジューン・デュプレ)は、10人のインディアンが最後は「誰もいなくなった」という古い子守唄を思い出す。彼らがくつろいでいる時、執事がかけたレコードから声がして、10人はいずれも過去に殺人を犯したと告発、全員がそれを否定する。判事(バリー・フィッツジェラルド)は U. N. Owen が Unknown(名無し者)と発音できることに気づく。一人が毒入る酒を飲んで咽喉をつまらせて死んだのを皮切りに、彼らは唄の文句通りに次々殺されてゆき、殺人の後は必ずインディアンの人形が1体壊されていた。殺人者は彼らの中にいることは明らかである。判事、アームストロング医師(ウォルター・ヒューストン)、ブロア、ロンバード(ルイス・ヘイワード)、ヴェラの5人が残る。4人は罪を認めるがヴェラは無実を主張する。更に3人が殺され、残りはヴェラとロンバードの2人となる―。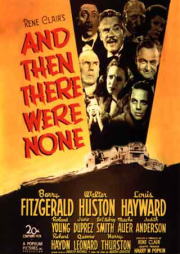
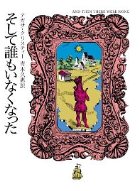
 他の映画化作品と比べ、最も「戯曲」に忠実に作られているとのことですが、戯曲では、ヴェラとロンバードは実は無実だったということになっているのに対し、この映像化作品では、ヴェラに関して本当はどうだったのか明確ではなく、ロンバードに至っては、ロンバートという人物は既に自殺していて、彼の正体はロンバートの友人で彼に成りすましたチャーリー・モーレイという探偵であったとされています。その彼が、いわばその通り"探偵"となって犯人を炙り出すという構図になっていて、但し、そのこと自体は観終わった後に判るようになっています(彼がチャーリー・モーレイであることは、トランクのイニシャルで示唆されている。但し、これも最後の方で判ることだが)。
他の映画化作品と比べ、最も「戯曲」に忠実に作られているとのことですが、戯曲では、ヴェラとロンバードは実は無実だったということになっているのに対し、この映像化作品では、ヴェラに関して本当はどうだったのか明確ではなく、ロンバードに至っては、ロンバートという人物は既に自殺していて、彼の正体はロンバートの友人で彼に成りすましたチャーリー・モーレイという探偵であったとされています。その彼が、いわばその通り"探偵"となって犯人を炙り出すという構図になっていて、但し、そのこと自体は観終わった後に判るようになっています(彼がチャーリー・モーレイであることは、トランクのイニシャルで示唆されている。但し、これも最後の方で判ることだが)。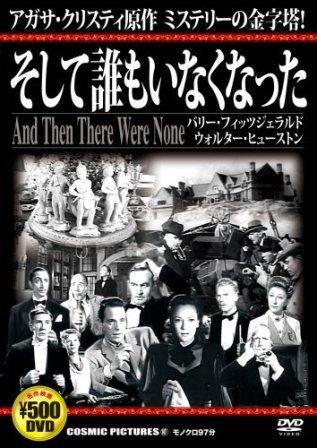
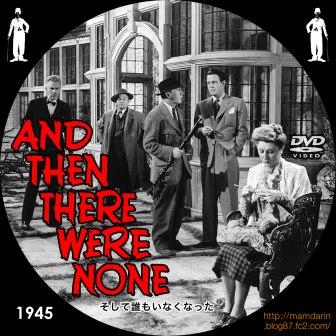

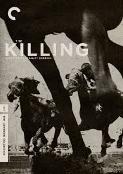
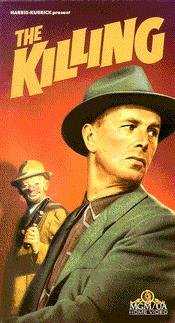

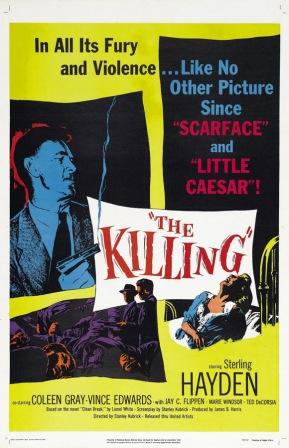
 集めて再び犯罪に手を染めようとしていた。それは、ダービーの行われる日に競馬場の売上金を強奪しようというもので、集まったのは、ジョニーの他に、軍資金を出すマーヴィン(ジェイ・C・フリッペン)、競馬場の馬券売場の現金係ジョージ(エライシャ・クック)、競馬場のバーのバーテンダーのマイク( ジョー・ソウヤー)、競馬場の整備を担当している悪徳警官ランディ(テッド・デコルシア)、元レスラーのモーリス(コーラ・クワリアーニ)の5人。ジョニーは更に射撃の名手ニッキを雇う。競馬場近くのモーテルの一室借りて犯行当日の根城とし、決行の前日、一味は最後の打合せをしたが、警官まで仲間に引き込んだ計画に隙はないように思われた。しかし、妻シェリー(マリー・ウィンザー)の尻に敷かれっぱなしのジョーが、妻から嘲りの言葉を浴びてプライドを踏みにじられ
集めて再び犯罪に手を染めようとしていた。それは、ダービーの行われる日に競馬場の売上金を強奪しようというもので、集まったのは、ジョニーの他に、軍資金を出すマーヴィン(ジェイ・C・フリッペン)、競馬場の馬券売場の現金係ジョージ(エライシャ・クック)、競馬場のバーのバーテンダーのマイク( ジョー・ソウヤー)、競馬場の整備を担当している悪徳警官ランディ(テッド・デコルシア)、元レスラーのモーリス(コーラ・クワリアーニ)の5人。ジョニーは更に射撃の名手ニッキを雇う。競馬場近くのモーテルの一室借りて犯行当日の根城とし、決行の前日、一味は最後の打合せをしたが、警官まで仲間に引き込んだ計画に隙はないように思われた。しかし、妻シェリー(マリー・ウィンザー)の尻に敷かれっぱなしのジョーが、妻から嘲りの言葉を浴びてプライドを踏みにじられ 、思わず計画のことを口にしてしまう。彼女からそれを聞いた彼女の不倫相手のヴァル(ヴィンス・エドワーズ)は、彼らが奪った金をさらに強奪する計画を立てる―。
、思わず計画のことを口にしてしまう。彼女からそれを聞いた彼女の不倫相手のヴァル(ヴィンス・エドワーズ)は、彼らが奪った金をさらに強奪する計画を立てる―。 決行の日、先ずモーリスがバーに来て飲物を注文、マイクの出した飲物に因縁をつけ暴れ始める。彼を押さえようとする警備員を大男のモーリスは次々と投げ飛ばして騒ぎは拡がり、競馬場の金庫室を見張っていた警官まで出てくる。一方、ニッキは競馬場の外側コースからレース中の馬を一発で倒してレースを混乱させるが、来合せた警官の銃弾に倒れる。競馬場の騒ぎの間にジョニーはジョージの合図で金庫室に入り、職員を機関銃で脅して200万ドルの紙幣を袋に詰込ませ、それを窓から投げて表へ出る。袋はランディが自分のパトカーに積んでモーテルの一室へ一旦放り込む。先に戻ったジョージら5人は別のホテルの一室で金を持って現れるはずのジョニーを待つが、そこへ現れたのは機関銃を構えたヴァルとその仲間で、その場で銃撃戦となり、重傷のジョージ以外は敵味方とも全員死んでしまう。ジョージは血まみれのまま車で自分のアパートへ戻り、ヴァルとの高跳びのための荷造りしていたシェリーを射殺、自身も息絶える。ジョージが血まみれになって車で行くのを、ホテルへ急ぐ途中で見つけたジョニーは、危険を覚ってフェイの待つ飛行場へ直行する―。
決行の日、先ずモーリスがバーに来て飲物を注文、マイクの出した飲物に因縁をつけ暴れ始める。彼を押さえようとする警備員を大男のモーリスは次々と投げ飛ばして騒ぎは拡がり、競馬場の金庫室を見張っていた警官まで出てくる。一方、ニッキは競馬場の外側コースからレース中の馬を一発で倒してレースを混乱させるが、来合せた警官の銃弾に倒れる。競馬場の騒ぎの間にジョニーはジョージの合図で金庫室に入り、職員を機関銃で脅して200万ドルの紙幣を袋に詰込ませ、それを窓から投げて表へ出る。袋はランディが自分のパトカーに積んでモーテルの一室へ一旦放り込む。先に戻ったジョージら5人は別のホテルの一室で金を持って現れるはずのジョニーを待つが、そこへ現れたのは機関銃を構えたヴァルとその仲間で、その場で銃撃戦となり、重傷のジョージ以外は敵味方とも全員死んでしまう。ジョージは血まみれのまま車で自分のアパートへ戻り、ヴァルとの高跳びのための荷造りしていたシェリーを射殺、自身も息絶える。ジョージが血まみれになって車で行くのを、ホテルへ急ぐ途中で見つけたジョニーは、危険を覚ってフェイの待つ飛行場へ直行する―。 スタンリー・キューブリック(1928-1999/享年70)監督の劇場公開第1作で(原題:THE KILLING)、この時彼は28歳でしたが、自ら脚本も手掛けたこの作品の完成度の高さには目を瞠るものがあります。前年作で同じくフィルム・ノワール系の「非情の罠」('55年)も観ましたが、1年で格段の進歩という感じです(まあ、この「現金に体を張れ」は「非情の罠」より以前から彼が構想を暖めていたものだそうだが)。
スタンリー・キューブリック(1928-1999/享年70)監督の劇場公開第1作で(原題:THE KILLING)、この時彼は28歳でしたが、自ら脚本も手掛けたこの作品の完成度の高さには目を瞠るものがあります。前年作で同じくフィルム・ノワール系の「非情の罠」('55年)も観ましたが、1年で格段の進歩という感じです(まあ、この「現金に体を張れ」は「非情の罠」より以前から彼が構想を暖めていたものだそうだが)。
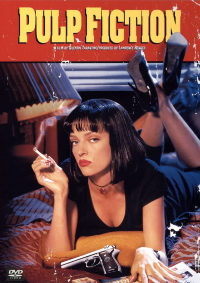

 「現金に体を張れ」の前年作の「非情の罠」('55年、原題:THE KILLER'S KISS)は、スタンリー・キューブリックの長編第2作で、商業映画では第1作に当たる作品で、キューブリックは撮影、編集なども兼ねています。絶頂期を過ぎたのボクサーのデイヴィー(ジャミー・スミス)が、向かい隣りのアパートに住むダンスホールで働くみじめな踊り子グロリア(アイリーン・ケイン)を彼女の情婦ヴィンセント・ラパロ(フランク・シルヴェラ)から救い出そうとするが、実は大物ギャングであったラパロに殺られてしまというだけのB級映画ですが(Wikipediaではデイヴィーはラパロ
「現金に体を張れ」の前年作の「非情の罠」('55年、原題:THE KILLER'S KISS)は、スタンリー・キューブリックの長編第2作で、商業映画では第1作に当たる作品で、キューブリックは撮影、編集なども兼ねています。絶頂期を過ぎたのボクサーのデイヴィー(ジャミー・スミス)が、向かい隣りのアパートに住むダンスホールで働くみじめな踊り子グロリア(アイリーン・ケイン)を彼女の情婦ヴィンセント・ラパロ(フランク・シルヴェラ)から救い出そうとするが、実は大物ギャングであったラパロに殺られてしまというだけのB級映画ですが(Wikipediaではデイヴィーはラパロ を倒し、グロリアと結ばれるというストーリーになっているけれど、そうだったかなあ)、ストーリーはさることながら、凝った画面構成などにはキューブリックらしさが感じられます。特に、マネキン倉庫で迎えるクライマックスの格闘シーンなどは、マネキンの手足があちこちに転がって、異様な雰囲気を醸し出しています。44分に短縮されて'60年に劇場公開されたままだったのが、'93年にJSB日本衛星放送(WOWOWの前身)が全編を放映、67分の完全版としてはこれが日本初公開となりましたが、個人的にはまだ短縮版しか観ていません。1959年のロカルノ国際映画祭でグランプリを獲っている作品。個人的評価は△ですが、完全版を観れば○に変わるかもしれません。
を倒し、グロリアと結ばれるというストーリーになっているけれど、そうだったかなあ)、ストーリーはさることながら、凝った画面構成などにはキューブリックらしさが感じられます。特に、マネキン倉庫で迎えるクライマックスの格闘シーンなどは、マネキンの手足があちこちに転がって、異様な雰囲気を醸し出しています。44分に短縮されて'60年に劇場公開されたままだったのが、'93年にJSB日本衛星放送(WOWOWの前身)が全編を放映、67分の完全版としてはこれが日本初公開となりましたが、個人的にはまだ短縮版しか観ていません。1959年のロカルノ国際映画祭でグランプリを獲っている作品。個人的評価は△ですが、完全版を観れば○に変わるかもしれません。
 「現金に体を張れ」●原題:THE KILLING●制作年:1956年●制作国:アメリカ●監督:スタンリー・キューブリック●製作:ジェームス・B・ハリス●脚本:スタンリー・キューブリック/ジム・トンプスン●撮影:ルシエン・バラード●音楽:ジェラルド・フリード●原作:ライオネル・ホワイト「見事な結末」●時間:83分●出演:スターリング・ヘイドン/ジェイ・C・フリッペン/メアリ・ウィンザー/コリーン・グレイ/エライシャ・クック/マリー・ウィンザー/テッド・デコルシア/ ジョー・ソウヤー/コーラ・クワリアーニ/ヴィンス・エドワーズ●日本
「現金に体を張れ」●原題:THE KILLING●制作年:1956年●制作国:アメリカ●監督:スタンリー・キューブリック●製作:ジェームス・B・ハリス●脚本:スタンリー・キューブリック/ジム・トンプスン●撮影:ルシエン・バラード●音楽:ジェラルド・フリード●原作:ライオネル・ホワイト「見事な結末」●時間:83分●出演:スターリング・ヘイドン/ジェイ・C・フリッペン/メアリ・ウィンザー/コリーン・グレイ/エライシャ・クック/マリー・ウィンザー/テッド・デコルシア/ ジョー・ソウヤー/コーラ・クワリアーニ/ヴィンス・エドワーズ●日本


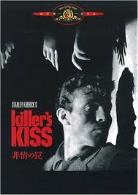
 「非情の罠」●原題:THE KILLER'S KISS●制作年:1956年●制作国:アメリカ●監督:スタンリー・キューブリック●製作:スタンリー・キューブリック/モリス・ブーゼル●脚本:スタンリー・キューブリック/ハワード・サックラー●撮影:スタンリー・キューブリック●音楽:ジェラルド・フリード●編集:スタンリー・キューブリック●時間:67分(短縮版:44分)●出演:フランク・シルヴェラ/ジャミー・スミス/アイリーン・ケイン/ジェリー・ジャレット/ルース・ソボトゥカ●日本公開:1960/09●配給:ユナイト映画●最初に観た場所:三鷹オスカー(80-02-09) (評価:★★★)●併映:「時計じかけのオレンジ」(スタンリー・キューブリック)「
「非情の罠」●原題:THE KILLER'S KISS●制作年:1956年●制作国:アメリカ●監督:スタンリー・キューブリック●製作:スタンリー・キューブリック/モリス・ブーゼル●脚本:スタンリー・キューブリック/ハワード・サックラー●撮影:スタンリー・キューブリック●音楽:ジェラルド・フリード●編集:スタンリー・キューブリック●時間:67分(短縮版:44分)●出演:フランク・シルヴェラ/ジャミー・スミス/アイリーン・ケイン/ジェリー・ジャレット/ルース・ソボトゥカ●日本公開:1960/09●配給:ユナイト映画●最初に観た場所:三鷹オスカー(80-02-09) (評価:★★★)●併映:「時計じかけのオレンジ」(スタンリー・キューブリック)「


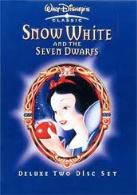
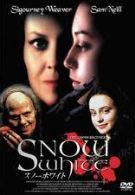
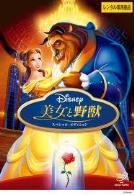
 個人的には、映画「白雪姫」を観て、これがディズニーの最初の「長編カラー」アニメーションですが、1937年の作品だと思うとやはりスゴイなあと。白雪姫や継母である后の登場する場面は実際に俳優を使って撮影し、その動作を分解して絵を描くという手法はこの頃からやっていたわけです。因みに、7人の小人は、原作ではゴブリン(ドラクエのキャラにもある小鬼風悪魔)であるのに対し、ディズニーによって、サンタクロースのイメージに変えられたとのことです。
個人的には、映画「白雪姫」を観て、これがディズニーの最初の「長編カラー」アニメーションですが、1937年の作品だと思うとやはりスゴイなあと。白雪姫や継母である后の登場する場面は実際に俳優を使って撮影し、その動作を分解して絵を描くという手法はこの頃からやっていたわけです。因みに、7人の小人は、原作ではゴブリン(ドラクエのキャラにもある小鬼風悪魔)であるのに対し、ディズニーによって、サンタクロースのイメージに変えられたとのことです。 原作では、王子が初めて白雪姫に合った時、姫は死んでいたため、本書では、王子はネクロフィリア(死体に性的興奮を感じる異常性欲)であるとしています(半分冗談を込めてか?)。ディズニー版では王子を最初から登場させることで純愛物語に変えていますが、原作の基調にあるのは、白雪姫の后に対する復讐物語であり(結婚式で、継母=魔女は真っ赤に焼けた鋼鉄の靴を履かされて、死ぬまで踊り続けさせられた)、ヒロインが自分の婚礼の席で、自分を苛め続けてきた義姉妹の両眼を潰して復讐する「シンデレラ」の原作「灰かぶり姫」にも通じるものがあります。
原作では、王子が初めて白雪姫に合った時、姫は死んでいたため、本書では、王子はネクロフィリア(死体に性的興奮を感じる異常性欲)であるとしています(半分冗談を込めてか?)。ディズニー版では王子を最初から登場させることで純愛物語に変えていますが、原作の基調にあるのは、白雪姫の后に対する復讐物語であり(結婚式で、継母=魔女は真っ赤に焼けた鋼鉄の靴を履かされて、死ぬまで踊り続けさせられた)、ヒロインが自分の婚礼の席で、自分を苛め続けてきた義姉妹の両眼を潰して復讐する「シンデレラ」の原作「灰かぶり姫」にも通じるものがあります。
 むしろ、本書にも紹介されている、シガーニー・ウィーヴァーが継母の后を演じたTV実写版「スノーホワイト」('97年)が比較的オリジナルに忠実に作られている分だけ、よりホラー仕立てであり、'99年の年末の深夜にテレビで何気なく見て、そのダークさについつい引き込まれて最後まで観てしまいました。これ、継母が完全に主人公っぽい。ホラー風だがそんなに怖くなく、但し、雰囲気的には完全に大人向きか(昨年('12年)テレビ東京「午後のロードショー」で再放映された)。
むしろ、本書にも紹介されている、シガーニー・ウィーヴァーが継母の后を演じたTV実写版「スノーホワイト」('97年)が比較的オリジナルに忠実に作られている分だけ、よりホラー仕立てであり、'99年の年末の深夜にテレビで何気なく見て、そのダークさについつい引き込まれて最後まで観てしまいました。これ、継母が完全に主人公っぽい。ホラー風だがそんなに怖くなく、但し、雰囲気的には完全に大人向きか(昨年('12年)テレビ東京「午後のロードショー」で再放映された)。
 本書の最後に取り上げられている「美女と野獣」は、個人的には90年代のディズニー・アニメの頂点を成している作品だと思うのですが、原作では、ヒロインであるベルは妬み深い二人の姉に苛められていて、グリムの「灰かぶり姫」のような状況だったみたいです。ディズニー・アニメでは、この姉たちは出てこず、代わりに、強引にベルに言い寄るガストンなる自信過剰のマッチョ男が出てきますが、これは、グリムのオリジナルには全く無いディズニー独自のキャラクター。
本書の最後に取り上げられている「美女と野獣」は、個人的には90年代のディズニー・アニメの頂点を成している作品だと思うのですが、原作では、ヒロインであるベルは妬み深い二人の姉に苛められていて、グリムの「灰かぶり姫」のような状況だったみたいです。ディズニー・アニメでは、この姉たちは出てこず、代わりに、強引にベルに言い寄るガストンなる自信過剰のマッチョ男が出てきますが、これは、グリムのオリジナルには全く無いディズニー独自のキャラクター。 本書によれば、オリジナルは、ベルの成長物語であるのに対し、ディズニー版ではベースト(野獣)の成長物語になっているとのことで、「美女と野獣」ではなく「野獣と美女」であると。そう考えれば、「悔い改めたセクシスト」であるビスーストと対比させるための「悔い改めざるセクシスト」ガストンという配置は、確かにぴったり嵌る気もしました。
本書によれば、オリジナルは、ベルの成長物語であるのに対し、ディズニー版ではベースト(野獣)の成長物語になっているとのことで、「美女と野獣」ではなく「野獣と美女」であると。そう考えれば、「悔い改めたセクシスト」であるビスーストと対比させるための「悔い改めざるセクシスト」ガストンという配置は、確かにぴったり嵌る気もしました。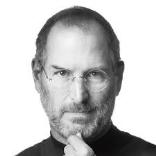 '05年にディズニーのアイズナー会長は経営責任をとって退任し、'06年にはディズニーとの交渉不調からディズニーへのピクサー作品提供を打ち切るかに思われていたスティーブ・ジョブズが一転してピクサーをディズニーに売却し、同社はディズニーの完全子会社となり、ジョブズはディズニーの筆頭株主に。「トイ・ストーリー」などを監督したピクサーのジョン・ラセターは、ディズニーに請われ、ピクサーとディズニー・アニメーション・スタジオの両方のチーフ・クリエイティブ・オフィサーを兼任することに。'06年にピクサー制作の「カーズ」('06年)を監督するなどしながらも、「ルイスと未来泥棒」('07年)などの以降のディズニー・アニメの制作総指揮にあたっています(ディズニー作品も3D化が進むと、ディズニー・アニメのピクサー・アニメ化が進むのではないかなあ)。
'05年にディズニーのアイズナー会長は経営責任をとって退任し、'06年にはディズニーとの交渉不調からディズニーへのピクサー作品提供を打ち切るかに思われていたスティーブ・ジョブズが一転してピクサーをディズニーに売却し、同社はディズニーの完全子会社となり、ジョブズはディズニーの筆頭株主に。「トイ・ストーリー」などを監督したピクサーのジョン・ラセターは、ディズニーに請われ、ピクサーとディズニー・アニメーション・スタジオの両方のチーフ・クリエイティブ・オフィサーを兼任することに。'06年にピクサー制作の「カーズ」('06年)を監督するなどしながらも、「ルイスと未来泥棒」('07年)などの以降のディズニー・アニメの制作総指揮にあたっています(ディズニー作品も3D化が進むと、ディズニー・アニメのピクサー・アニメ化が進むのではないかなあ)。
 「白雪姫」●原題:SNOW WHITE AND THE SEVEN DWARFS●制作年:1937年●制作国:アメリカ●監督:デイヴィッド・ハンド●製作:ウォルト・ディズニー●脚本:テッド・シアーズ/オットー・イングランダー/ アール・ハード/ドロシー・アン・ブランク/ リチャード・クリードン/メリル・デ・マリス/ディック・リカード/ウェッブ・スミス●撮影:ボブ・ブロートン●音楽:フランク・チャーチル/レイ・ハーライン/ポール・J・スミス●原作:グリム兄弟●時間:83分●声の出演:アドリアナ・カセロッティハリー・ストックウェル/ルシール・ラ・バーン/ロイ・アトウェル/ピント・コルヴィグ/ビリー・ギルバート/スコッティ・マットロー/オーティス・ハーラン/エディ・コリンズ●日本公開:1950/09●配給:RKO(評価:★★★★)
「白雪姫」●原題:SNOW WHITE AND THE SEVEN DWARFS●制作年:1937年●制作国:アメリカ●監督:デイヴィッド・ハンド●製作:ウォルト・ディズニー●脚本:テッド・シアーズ/オットー・イングランダー/ アール・ハード/ドロシー・アン・ブランク/ リチャード・クリードン/メリル・デ・マリス/ディック・リカード/ウェッブ・スミス●撮影:ボブ・ブロートン●音楽:フランク・チャーチル/レイ・ハーライン/ポール・J・スミス●原作:グリム兄弟●時間:83分●声の出演:アドリアナ・カセロッティハリー・ストックウェル/ルシール・ラ・バーン/ロイ・アトウェル/ピント・コルヴィグ/ビリー・ギルバート/スコッティ・マットロー/オーティス・ハーラン/エディ・コリンズ●日本公開:1950/09●配給:RKO(評価:★★★★) 「スノーホワイト(グリム・ブラザーズ スノーホワイト)」
「スノーホワイト(グリム・ブラザーズ スノーホワイト)」 ●原題:SNOW WHITE: A TALE OF TERROR(THE GRIMM BROTHERS' SNOW WHITE)●制作年:1997年●制作国:アメリカ●監督:マイケル・コーン●製作:トム・エンゲルマン●脚本:トム・スゾロッシ/デボラ・セラズ●撮影:マイク・サウソン●音楽:ジョン・オットマン●原作:グリム兄弟●時間:100分●出演:シガーニー・ウィーヴァー/サム・ニール/モニカ・キーナ/ギル・ベローズ/デヴィッド・コンラッド/ジョアンナ・ロス/タリン・デイヴィス/ブライアン・プリングル●日本公開:1997/10●配給:ギャガ=ヒューマックス(評価:★★★)
●原題:SNOW WHITE: A TALE OF TERROR(THE GRIMM BROTHERS' SNOW WHITE)●制作年:1997年●制作国:アメリカ●監督:マイケル・コーン●製作:トム・エンゲルマン●脚本:トム・スゾロッシ/デボラ・セラズ●撮影:マイク・サウソン●音楽:ジョン・オットマン●原作:グリム兄弟●時間:100分●出演:シガーニー・ウィーヴァー/サム・ニール/モニカ・キーナ/ギル・ベローズ/デヴィッド・コンラッド/ジョアンナ・ロス/タリン・デイヴィス/ブライアン・プリングル●日本公開:1997/10●配給:ギャガ=ヒューマックス(評価:★★★)
 「美女と野獣」●原題:BEAUTY AND THE BEAST●制作年:1991年●制作国:アメリカ●監督:ゲーリー・トゥルースデイル/カーク・ワイズ●製作:ドン・ハーン●脚本:リンダ・ウールヴァートン●撮影:ディーン・カンディ●音楽:アラン・メンケン●原作:ジャンヌ・マリー・ルプランス・ド・ボーモン●時間:84分●声の出演:ペイジ・オハラ/ロビー・ベンソン/リチャード・ホワイト/レックス・エヴァーハート/ジェリー・オーバック/アンジェラ・ランズベリー/デイヴィッド・オグデン・スティアーズ●日本公開:1992/09●配給:ブエナ・ビスタ(評価:★★★★)
「美女と野獣」●原題:BEAUTY AND THE BEAST●制作年:1991年●制作国:アメリカ●監督:ゲーリー・トゥルースデイル/カーク・ワイズ●製作:ドン・ハーン●脚本:リンダ・ウールヴァートン●撮影:ディーン・カンディ●音楽:アラン・メンケン●原作:ジャンヌ・マリー・ルプランス・ド・ボーモン●時間:84分●声の出演:ペイジ・オハラ/ロビー・ベンソン/リチャード・ホワイト/レックス・エヴァーハート/ジェリー・オーバック/アンジェラ・ランズベリー/デイヴィッド・オグデン・スティアーズ●日本公開:1992/09●配給:ブエナ・ビスタ(評価:★★★★)
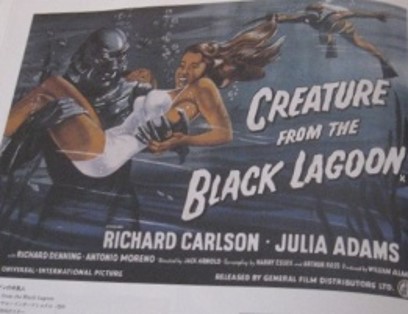
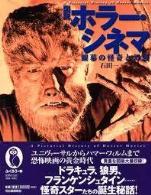
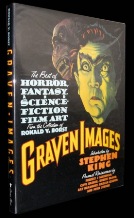
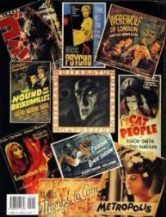
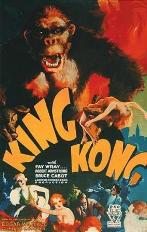
 ポスターに関して言えば、60年代よりも前のものの方がいいものが多いような印象を受けました。個人的には、「キング・コング」('33年)のポスターが見開き4ページにわたり紹介されているのが嬉しく、「『美女と野獣』をフロイト的に改作」したものとの解説にもナルホドと思いました。映画の方は、最近のリメイクのようにすぐにコングが出てくるのではなく、結構ドラマ部分で引っ張っていて、コングが出てくるまでにかなり時間がかかったけれど、これはこれで良かったのでは。当のコングは、ストップ・アニメーションでの動きはぎこちないものであるにも関わらず、観ている不思議と慣れてきて、ティラノサウルスっぽい「暴君竜」との死闘はまるでプロレスを観ているよう(コマ撮りでよくここまでやるなあ)。比較的自然にコングに感情移入してしまいましたが、意外とこの時のコングは小さかったかも...現代的感覚から見るとそう迫力は感じられません。但し、当時は興業的に大成功を収め(ポスターも数多く作られたが、本書によれば、実際の映画の中での
ポスターに関して言えば、60年代よりも前のものの方がいいものが多いような印象を受けました。個人的には、「キング・コング」('33年)のポスターが見開き4ページにわたり紹介されているのが嬉しく、「『美女と野獣』をフロイト的に改作」したものとの解説にもナルホドと思いました。映画の方は、最近のリメイクのようにすぐにコングが出てくるのではなく、結構ドラマ部分で引っ張っていて、コングが出てくるまでにかなり時間がかかったけれど、これはこれで良かったのでは。当のコングは、ストップ・アニメーションでの動きはぎこちないものであるにも関わらず、観ている不思議と慣れてきて、ティラノサウルスっぽい「暴君竜」との死闘はまるでプロレスを観ているよう(コマ撮りでよくここまでやるなあ)。比較的自然にコングに感情移入してしまいましたが、意外とこの時のコングは小さかったかも...現代的感覚から見るとそう迫力は感じられません。但し、当時は興業的に大成功を収め(ポスターも数多く作られたが、本書によれば、実際の映画の中での コングの姿を忠実に描いたのは1点[左上]のみとのこと)、その年の内に「コングの復讐」('33年)が作られ(原題は「SON OF KONG(コングの息子)」)公開されました。 「コングの復讐」('33年)[上]
コングの姿を忠実に描いたのは1点[左上]のみとのこと)、その年の内に「コングの復讐」('33年)が作られ(原題は「SON OF KONG(コングの息子)」)公開されました。 「コングの復讐」('33年)[上]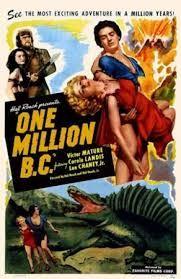
 因みに、アメリカやイギリスでは「怪獣映画」よりも「恐竜映画」の方が主に作られたようですが、日本のように着ぐるみではなく、模型を使って1コマ1コマ撮影していく方式で、ハル・ローチ監督、ヴィクター・マチュア、キャロル・ランディス主演の「紀元前百万年」('40年)ではトカゲやワニに作り物の角やヒレをつけて撮る所謂「トカゲ特撮」なんていう方法も用いられましたが、何れにしても動きの不自然さは目立ちます。そもそも恐竜と人類が同じ時代にいるという状況自体が進化の歴史からみてあり得ない話なのですが...。
因みに、アメリカやイギリスでは「怪獣映画」よりも「恐竜映画」の方が主に作られたようですが、日本のように着ぐるみではなく、模型を使って1コマ1コマ撮影していく方式で、ハル・ローチ監督、ヴィクター・マチュア、キャロル・ランディス主演の「紀元前百万年」('40年)ではトカゲやワニに作り物の角やヒレをつけて撮る所謂「トカゲ特撮」なんていう方法も用いられましたが、何れにしても動きの不自然さは目立ちます。そもそも恐竜と人類が同じ時代にいるという状況自体が進化の歴史からみてあり得ない話なのですが...。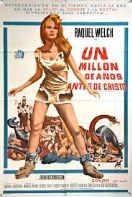 この作品のリメイク作品が「恐竜100万年」('66年)で、"全身整形美女"などと言われたラクエル・ウェルチが主演でしたが(100万年前なのに
この作品のリメイク作品が「恐竜100万年」('66年)で、"全身整形美女"などと言われたラクエル・ウェルチが主演でしたが(100万年前なのに ラクェル・ウェルチがバッチリ完璧にハリウッド風のメイキャップをしているのはある種"お約束ごと"か)、やはりここでも模型を使っています。結果的に、ラクエル・ウェルチの今風のメイキャップでありながらも、何となくノスタルジックな印象を受けて、すごく昔の映画のように見えてしまいます(CGの出始めの頃の映画とも言え、なかなか微妙な味わいのある作品?)。
ラクェル・ウェルチがバッチリ完璧にハリウッド風のメイキャップをしているのはある種"お約束ごと"か)、やはりここでも模型を使っています。結果的に、ラクエル・ウェルチの今風のメイキャップでありながらも、何となくノスタルジックな印象を受けて、すごく昔の映画のように見えてしまいます(CGの出始めの頃の映画とも言え、なかなか微妙な味わいのある作品?)。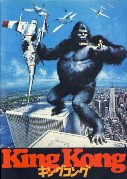

 それが、その10年後の、ジョン・ギラーミン監督のリメイク版「キングコング」('76年)(こちらは邦題タイトル表記に中黒が無い)では、キング・コングの全身像が出てくる殆どのシーンは、リック・ベイカーという特殊メイクアーティストが自らスーツアクターとなって体当たり演技したものであったとのことで、ここにきてアメリカも、「ゴジラ」('54年)以来の日本の怪獣映画の伝統である"着ぐるみ方式"を採り入れたことになります(別資料によれば、実物大のロボット・コング(20メートル)も作られたが、腕や顔の向きを変える程度しか動かせず、結局映画では、コングがイベント会場で檻を破るワンシーンしか使われなかったという)。
それが、その10年後の、ジョン・ギラーミン監督のリメイク版「キングコング」('76年)(こちらは邦題タイトル表記に中黒が無い)では、キング・コングの全身像が出てくる殆どのシーンは、リック・ベイカーという特殊メイクアーティストが自らスーツアクターとなって体当たり演技したものであったとのことで、ここにきてアメリカも、「ゴジラ」('54年)以来の日本の怪獣映画の伝統である"着ぐるみ方式"を採り入れたことになります(別資料によれば、実物大のロボット・コング(20メートル)も作られたが、腕や顔の向きを変える程度しか動かせず、結局映画では、コングがイベント会場で檻を破るワンシーンしか使われなかったという)。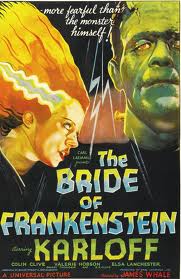 「
「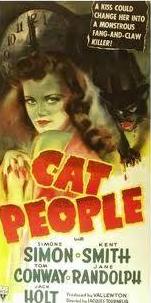
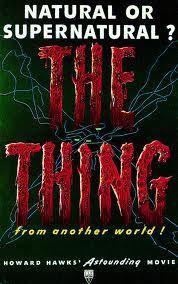
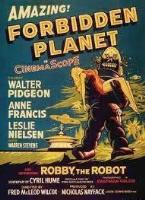 代では「遊星よりの物体X」('51年)や「大アマゾンの半魚人」('54年)などのポスターがあるのが楽しく、50年代では日本の「ゴジラ」('54年)のポスターもあれば、「
代では「遊星よりの物体X」('51年)や「大アマゾンの半魚人」('54年)などのポスターがあるのが楽しく、50年代では日本の「ゴジラ」('54年)のポスターもあれば、「
 「キャット・ピープル」はポール・シュレイダー監督、ナスターシャ・キンスキー主演で同タイトル「キャット・ピープル」('81年)としてリメイクされ(オリジナルは日本では長らく劇場未公開だったが1988年にようやく劇場公開が実現したため、多くの人がリメイク版を先に観たことと思う)、「遊星よりの物体X」は、ジョン・カーペンター監督によりカート・ラッセル主演で「遊星からの物体X」('82年)としてリメイクされています。
「キャット・ピープル」はポール・シュレイダー監督、ナスターシャ・キンスキー主演で同タイトル「キャット・ピープル」('81年)としてリメイクされ(オリジナルは日本では長らく劇場未公開だったが1988年にようやく劇場公開が実現したため、多くの人がリメイク版を先に観たことと思う)、「遊星よりの物体X」は、ジョン・カーペンター監督によりカート・ラッセル主演で「遊星からの物体X」('82年)としてリメイクされています。
 前者「キャット・ピープル」は、オリジナルでは、猫顔のシモーヌ・シモンが男性とキスするだけで黒豹に変身してしまう主人公を演じていますが、ストッキングを脱ぐシーンとか入浴シーン、プールでの水着シーンなどは当時としてはかなりエロチックな方だったのだろうなあと。実際に黒豹になる
前者「キャット・ピープル」は、オリジナルでは、猫顔のシモーヌ・シモンが男性とキスするだけで黒豹に変身してしまう主人公を演じていますが、ストッキングを脱ぐシーンとか入浴シーン、プールでの水着シーンなどは当時としてはかなりエロチックな方だったのだろうなあと。実際に黒豹になる 場面は夢の中で暗示されているのみで、それが主人公の妄想であることを示唆しているのに対し、リメイク版では、ナスターシャ・キンスキーが男性と交わると実際に黒豹に変身します。ナスターシャ・キンスキーの猫女(豹女?)はハマリ役で、後日
場面は夢の中で暗示されているのみで、それが主人公の妄想であることを示唆しているのに対し、リメイク版では、ナスターシャ・キンスキーが男性と交わると実際に黒豹に変身します。ナスターシャ・キンスキーの猫女(豹女?)はハマリ役で、後日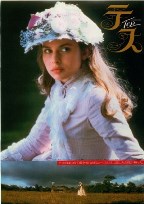 「あの映画では肌を露出する場面が多すぎた」と述懐している通りの内容でもありますが、むしろ構成がイマイチのため、ストーリーがだらだらしている上に分かりにくいのが難点でしょうか。ナスターシャ・キンスキー自身は、「テス」('79年)で"演技開眼"した後の作品であるため、「肌を出し過ぎた」発言に至っているのではないでしょうか。「テス」は、19世紀のイギリスの片田舎を舞台に2人の男の間で揺れ動きながらも愛を貫く女性を描いた、文豪トマス・ハーディの文芸大作をロマン・ポランスキーが忠実に映画化した作品で、ナスターシャ・キンスキーの演技が冴え短く感じた3時間でした(ナスターシャ・キンスキーはこの作品でゴールデングローブ賞新人女優賞を受賞)。一方、「テス」に出る前年にナスターシャ・キンスキーは、スイスの全寮制寄宿学校を舞台に、そこにやって来たアメリカ人少女という
「あの映画では肌を露出する場面が多すぎた」と述懐している通りの内容でもありますが、むしろ構成がイマイチのため、ストーリーがだらだらしている上に分かりにくいのが難点でしょうか。ナスターシャ・キンスキー自身は、「テス」('79年)で"演技開眼"した後の作品であるため、「肌を出し過ぎた」発言に至っているのではないでしょうか。「テス」は、19世紀のイギリスの片田舎を舞台に2人の男の間で揺れ動きながらも愛を貫く女性を描いた、文豪トマス・ハーディの文芸大作をロマン・ポランスキーが忠実に映画化した作品で、ナスターシャ・キンスキーの演技が冴え短く感じた3時間でした(ナスターシャ・キンスキーはこの作品でゴールデングローブ賞新人女優賞を受賞)。一方、「テス」に出る前年にナスターシャ・キンスキーは、スイスの全寮制寄宿学校を舞台に、そこにやって来たアメリカ人少女という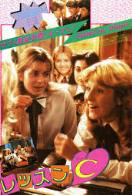
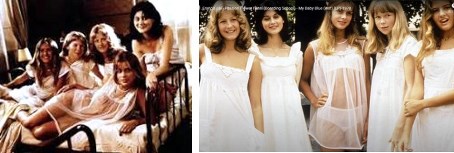 設定の青春ラブ・コメディ「レッスンC」('78年)に出演していて、そこでは結構「しっかり肌を出して」いたように思います。「レッスンC」は音楽は
設定の青春ラブ・コメディ「レッスンC」('78年)に出演していて、そこでは結構「しっかり肌を出して」いたように思います。「レッスンC」は音楽は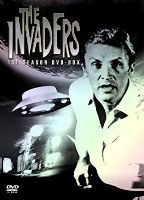
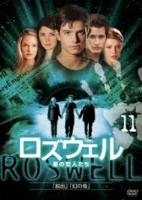


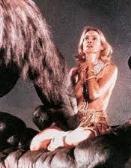 「キング・コング」('33年)のリメイク、ジョン・ギラーミン監督の「キングコング」('76年)は、オリジナルは、ヒロイン(フェイ・レイ)に一方的に恋したコングが、ヒロインをさらってエンパイアステートビルによじ登り、コングの手の中フェイ・レイは恐怖のあまりただただ絶叫するばかりでしたが(このため、フェイ・レイ"絶叫女優"などと呼ばれた)、
「キング・コング」('33年)のリメイク、ジョン・ギラーミン監督の「キングコング」('76年)は、オリジナルは、ヒロイン(フェイ・レイ)に一方的に恋したコングが、ヒロインをさらってエンパイアステートビルによじ登り、コングの手の中フェイ・レイは恐怖のあまりただただ絶叫するばかりでしたが(このため、フェイ・レイ"絶叫女優"などと呼ばれた)、 リメイク版のヒロイン(ジェシカ・ラング)は最初こそコングを恐れるものの、途中からコングを慈しむかのように心情が変化し、世界貿易センタービルの屋上でヘリからの銃撃を受けるコングに対して「私といれば狙われないから」と言うまでになるなど、コングといわば"男女間的コミュにケーション"をするようになっています(そうしたセリフ自体は観客に向けての解説か?)。但し、「美女と野獣」のモチーフが、それ自体は「キング・コング」の"正統的"なモチーフであるにしてもここまで前面に出てしまうと、もう怪獣映画ではなくなってしまっている印象も。個人的には懐かしい映画であり、
リメイク版のヒロイン(ジェシカ・ラング)は最初こそコングを恐れるものの、途中からコングを慈しむかのように心情が変化し、世界貿易センタービルの屋上でヘリからの銃撃を受けるコングに対して「私といれば狙われないから」と言うまでになるなど、コングといわば"男女間的コミュにケーション"をするようになっています(そうしたセリフ自体は観客に向けての解説か?)。但し、「美女と野獣」のモチーフが、それ自体は「キング・コング」の"正統的"なモチーフであるにしてもここまで前面に出てしまうと、もう怪獣映画ではなくなってしまっている印象も。個人的には懐かしい映画であり、 興業的にもアメリカでも日本でも大ヒットしましたが、後に観直してみると、そうしたこともあってイマイチの作品のように思われました。ジェシカ・ラングも「郵便配達は二度ベルを鳴らす」('81年)で一皮むける前の演技であるし...2005年にナオミ・ワッツ主演の再リメイク作品が作られましたが、ナオミ・ワッツもジェシカ・ラング同様、以降の作品において"演技派女優"への転身を遂げています。
興業的にもアメリカでも日本でも大ヒットしましたが、後に観直してみると、そうしたこともあってイマイチの作品のように思われました。ジェシカ・ラングも「郵便配達は二度ベルを鳴らす」('81年)で一皮むける前の演技であるし...2005年にナオミ・ワッツ主演の再リメイク作品が作られましたが、ナオミ・ワッツもジェシカ・ラング同様、以降の作品において"演技派女優"への転身を遂げています。
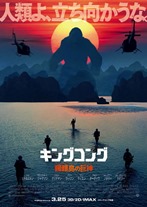 (●2017年に32歳のジョーダン・ヴォート=ロバーツ監督による「キングコング:髑髏島の巨神」('17年/米)が作られた。シリーズのスピンオフにあたる作品とのことだが、主役はあくまでキングコング。1973年の未知の島髑髏島が
(●2017年に32歳のジョーダン・ヴォート=ロバーツ監督による「キングコング:髑髏島の巨神」('17年/米)が作られた。シリーズのスピンオフにあたる作品とのことだが、主役はあくまでキングコング。1973年の未知の島髑髏島が 舞台で、一応、コングが島の守り神であったり、主人公の女性を救ったりと、オリジナルのコングに回帰している(一方で、随所にフランシス・フォード・コッポラ監督の「
舞台で、一応、コングが島の守り神であったり、主人公の女性を救ったりと、オリジナルのコングに回帰している(一方で、随所にフランシス・フォード・コッポラ監督の「 込められているようだ)。ヴォート=ロバーツ監督自らが来日して行われた本作のプレゼンテーションに参加した
込められているようだ)。ヴォート=ロバーツ監督自らが来日して行われた本作のプレゼンテーションに参加した 「
「

 「キング・コング」●原題:KING KONG●制作年:1933年●制作国:アメリカ●監督:メリアン・C・クーパー/アーネスト・B・シェードサ
「キング・コング」●原題:KING KONG●制作年:1933年●制作国:アメリカ●監督:メリアン・C・クーパー/アーネスト・B・シェードサ ック●製作:マーセル・デルガド●脚本:ジェームス・クリールマン/ルース・ローズ●撮影:エドワード・リンドン/バーノン・L・ウォーカー●音楽:マックス・スタイナー●時間:100分●出演:フェイ・レイ/ロバート・アームストロング/ブルース・キャボット/フランク・ライチャー/サム・ハーディー/ノーブル・ジョンソン●日本公開:1933/09●配給:ユニヴァーサル映画●最初に観た場所:池袋・文芸座ル・ピリエ(84-06-30)(評価:★★★☆)●併映:「紀元前百万年」(ハル・ローチ&ジュニア)
ック●製作:マーセル・デルガド●脚本:ジェームス・クリールマン/ルース・ローズ●撮影:エドワード・リンドン/バーノン・L・ウォーカー●音楽:マックス・スタイナー●時間:100分●出演:フェイ・レイ/ロバート・アームストロング/ブルース・キャボット/フランク・ライチャー/サム・ハーディー/ノーブル・ジョンソン●日本公開:1933/09●配給:ユニヴァーサル映画●最初に観た場所:池袋・文芸座ル・ピリエ(84-06-30)(評価:★★★☆)●併映:「紀元前百万年」(ハル・ローチ&ジュニア)

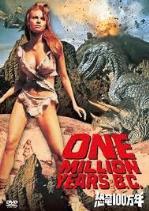
 「恐竜100万年」●原
「恐竜100万年」●原 題:ONE MILLION YEARS B.C.●制作年:1966年●制作国:イギリス・アメリカ●監督:ドン・チャフィ●製作:マイケル・カレラス●脚本:ミッケル・ノバック/ジョージ・ベイカー/ジョセフ・フリッカート●撮影:ウィルキー・クーパー●音楽:マリオ・ナシンベーネ●時間:105分●出演:ラクエル・ウェルチ/ジョン・リチャードソン/パーシー・ハーバート/ロバート・ブラウン/マルティーヌ=ベズウィック/ジェーン・ウラドン●日本公開:1967/02●配給:20世紀フォックス●最初に観た場所:杉本保男氏邸 (81-02-06) (評価:★★★) Raquel Welch age71
題:ONE MILLION YEARS B.C.●制作年:1966年●制作国:イギリス・アメリカ●監督:ドン・チャフィ●製作:マイケル・カレラス●脚本:ミッケル・ノバック/ジョージ・ベイカー/ジョセフ・フリッカート●撮影:ウィルキー・クーパー●音楽:マリオ・ナシンベーネ●時間:105分●出演:ラクエル・ウェルチ/ジョン・リチャードソン/パーシー・ハーバート/ロバート・ブラウン/マルティーヌ=ベズウィック/ジェーン・ウラドン●日本公開:1967/02●配給:20世紀フォックス●最初に観た場所:杉本保男氏邸 (81-02-06) (評価:★★★) Raquel Welch age71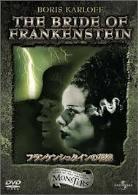
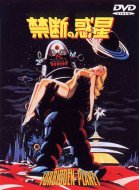
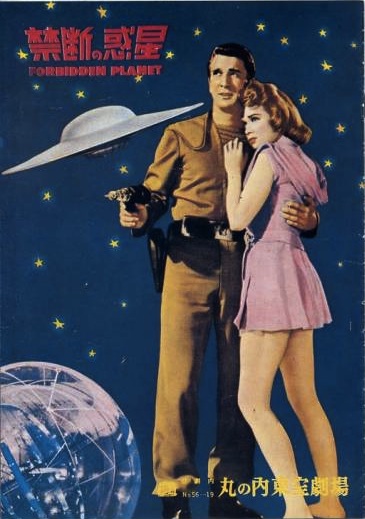 「禁断の惑星」●原題:FORBIDDEN EARTH●制作年:1956年●制作国:アメリカ●監督:フレッド・マクラウド・ウィルコックス●製作:ニコラス・ネイファック●脚本:シリル・ヒューム●撮影:ジョージ・J・フォルシー●音楽:ルイス・アンド・ベベ・バロン●原作:アーヴィング・ブロック/アレン・アドラー「運命の惑星」●時間:98分●出演:ウォルター・ピジョン/アン・フランシス/レスリー・ニールセン/ウォーレン・スティーヴンス/ジャック・ケリー/リチャード・アンダーソン/アール・ホリマン/ジョージ・ウォレス●日本公開:1956/09●配給:MGM●最初に観た場所:新宿・名画座ミラノ(87-04-29)(評価:★★★☆)
「禁断の惑星」●原題:FORBIDDEN EARTH●制作年:1956年●制作国:アメリカ●監督:フレッド・マクラウド・ウィルコックス●製作:ニコラス・ネイファック●脚本:シリル・ヒューム●撮影:ジョージ・J・フォルシー●音楽:ルイス・アンド・ベベ・バロン●原作:アーヴィング・ブロック/アレン・アドラー「運命の惑星」●時間:98分●出演:ウォルター・ピジョン/アン・フランシス/レスリー・ニールセン/ウォーレン・スティーヴンス/ジャック・ケリー/リチャード・アンダーソン/アール・ホリマン/ジョージ・ウォレス●日本公開:1956/09●配給:MGM●最初に観た場所:新宿・名画座ミラノ(87-04-29)(評価:★★★☆)
 「宇宙水爆戦」●原題:THIS ISLAND EARTH●制作年:1955年●制作国:アメリカ●監督:ジョセフ・ニューマン●製作:ウィリアム・アランド●脚本:フランクリン・コーエン/エドワード・G・オキャラハン●撮影:クリフォード・スタイン/デビッド・S・ホスリー●音楽:ジョセフ・ガ―シェンソン●原作:レイモンド・F・ジョーンズ●時間:86分●出演:フェイス・ドマーグ/レックス・リーズン/ジェフ・モロー/ラッセル・ジョンソン/ランス・フラー●配給:ユニバーサル・ピクチャーズ●日本公開:1955/12)●最初に観た場所:新宿・名画座ミラノ(87-05-17)(評価:★★★☆)
「宇宙水爆戦」●原題:THIS ISLAND EARTH●制作年:1955年●制作国:アメリカ●監督:ジョセフ・ニューマン●製作:ウィリアム・アランド●脚本:フランクリン・コーエン/エドワード・G・オキャラハン●撮影:クリフォード・スタイン/デビッド・S・ホスリー●音楽:ジョセフ・ガ―シェンソン●原作:レイモンド・F・ジョーンズ●時間:86分●出演:フェイス・ドマーグ/レックス・リーズン/ジェフ・モロー/ラッセル・ジョンソン/ランス・フラー●配給:ユニバーサル・ピクチャーズ●日本公開:1955/12)●最初に観た場所:新宿・名画座ミラノ(87-05-17)(評価:★★★☆)
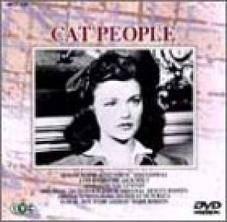

 ズビー●撮影:ジョン・ベイリー●音楽:ジョルジ
ズビー●撮影:ジョン・ベイリー●音楽:ジョルジ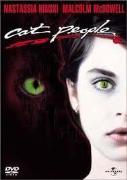
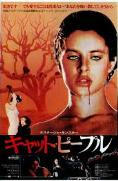 オ・モロダー(主題歌:デヴィッド・ボウイ(作詞・歌)●原作(オリジナル脚本):ドゥイット・ボディーン●時間:118分●出演:ナスターシャ・キンスキー/マルコムジョン・ハード/ アネット・オトウール/ルビー・ディー●日本公開:1982/07●配給:IP●最初に観た場所:新宿(文化?)シネマ2(82-07-18)(評価:★★☆)
オ・モロダー(主題歌:デヴィッド・ボウイ(作詞・歌)●原作(オリジナル脚本):ドゥイット・ボディーン●時間:118分●出演:ナスターシャ・キンスキー/マルコムジョン・ハード/ アネット・オトウール/ルビー・ディー●日本公開:1982/07●配給:IP●最初に観た場所:新宿(文化?)シネマ2(82-07-18)(評価:★★☆)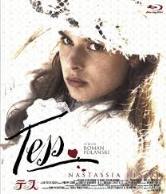

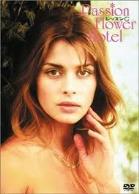


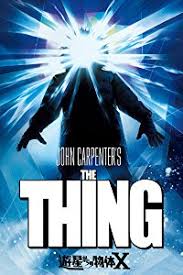


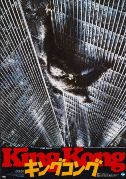
 「キングコング」●原題:KING KONG●制作年:1976年●制作国:アメリカ●監督:ジョン・ギラーミン●製作:ディノ・デ・ラウレンティス●脚本:ロレンツォ・センプル・ジュニア●撮影:リチャード・H・クライン●音楽:ジョン・バリー●時間:134分●出演:ジェフ・ブリッジス/ジェシカ・ラング/チャールズ・グローディン/ジャック・オハローラン /ジョン・ランドルフ/ルネ・オーベルジョノワ/ジュリアス・ハリス/ジョン・ローン/ジョン・エイガー/コービン・バーンセン/エド・ローター ●日本公開:1976/12●配給:東宝東和●最初に観た場所:新宿プラザ劇場(77-01-04)(評価:★★★)
「キングコング」●原題:KING KONG●制作年:1976年●制作国:アメリカ●監督:ジョン・ギラーミン●製作:ディノ・デ・ラウレンティス●脚本:ロレンツォ・センプル・ジュニア●撮影:リチャード・H・クライン●音楽:ジョン・バリー●時間:134分●出演:ジェフ・ブリッジス/ジェシカ・ラング/チャールズ・グローディン/ジャック・オハローラン /ジョン・ランドルフ/ルネ・オーベルジョノワ/ジュリアス・ハリス/ジョン・ローン/ジョン・エイガー/コービン・バーンセン/エド・ローター ●日本公開:1976/12●配給:東宝東和●最初に観た場所:新宿プラザ劇場(77-01-04)(評価:★★★)![郵便配達は二度ベルを鳴らす [DVD].jpg](http://hurec.bz/book-movie/%E9%83%B5%E4%BE%BF%E9%85%8D%E9%81%94%E3%81%AF%E4%BA%8C%E5%BA%A6%E3%83%99%E3%83%AB%E3%82%92%E9%B3%B4%E3%82%89%E3%81%99%20%5BDVD%5D.jpg)
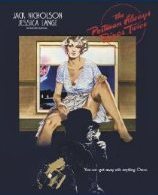
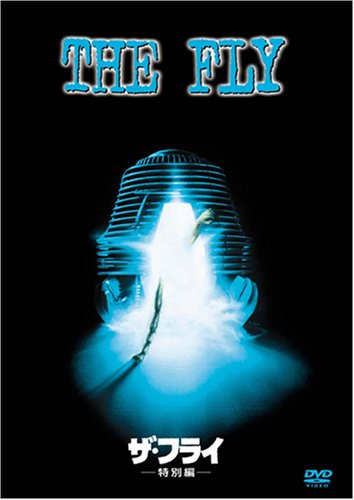
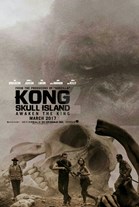
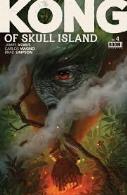
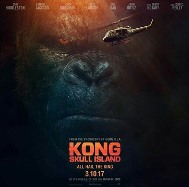 「キングコング:髑髏島の巨神」●原題:KONG:SKULL ISLAND●制作年:2017年●制作国:アメリカ●監督:ジョーダン・ヴォート=ロバーツ●脚本:ダン・ギルロイ/マックス・ボレンスタイン/デレク・コノリー●原案:ジョン・ゲイティンズ/ダン・ギルロイ●製作:トーマス・タル/ジョン・ジャシュー/アレックス・ガルシア/メアリー・ペアレント●撮影:ラリー・フォン●音楽:ヘンリー・ジャックマン●時間:118分●出演:トム・ヒドルストン/
「キングコング:髑髏島の巨神」●原題:KONG:SKULL ISLAND●制作年:2017年●制作国:アメリカ●監督:ジョーダン・ヴォート=ロバーツ●脚本:ダン・ギルロイ/マックス・ボレンスタイン/デレク・コノリー●原案:ジョン・ゲイティンズ/ダン・ギルロイ●製作:トーマス・タル/ジョン・ジャシュー/アレックス・ガルシア/メアリー・ペアレント●撮影:ラリー・フォン●音楽:ヘンリー・ジャックマン●時間:118分●出演:トム・ヒドルストン/
 サミュエル・L・ジャクソン/ジョン・グッドマン/ブリー・ラーソン/ジン・ティエン/トビー・ケベル/ジョン・オーティス/コーリー・ホーキンズ/ジェイソン・ミッチェル/シェー・ウィガム/トーマス・マン/テリー・ノタリー/ジョン・C・ライリー●日本公開:2017/03●配給:ワーナー・ブラザース●最初に観た場所:OSシネマズ ミント神戸 (17-03-29)(評価★★☆)
サミュエル・L・ジャクソン/ジョン・グッドマン/ブリー・ラーソン/ジン・ティエン/トビー・ケベル/ジョン・オーティス/コーリー・ホーキンズ/ジェイソン・ミッチェル/シェー・ウィガム/トーマス・マン/テリー・ノタリー/ジョン・C・ライリー●日本公開:2017/03●配給:ワーナー・ブラザース●最初に観た場所:OSシネマズ ミント神戸 (17-03-29)(評価★★☆)

 OSシネマズ ミント神戸 神戸三宮・ミント神戸(正式名称「神戸新聞会館」。阪神・淡路大震災で全壊した旧・神戸新聞会館跡地に2006年10月完成)9F~12F。全8スクリーン総座席数1,631席。
OSシネマズ ミント神戸 神戸三宮・ミント神戸(正式名称「神戸新聞会館」。阪神・淡路大震災で全壊した旧・神戸新聞会館跡地に2006年10月完成)9F~12F。全8スクリーン総座席数1,631席。

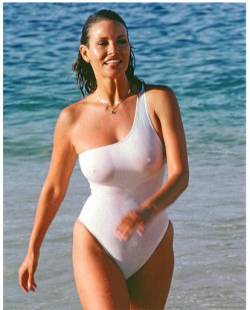

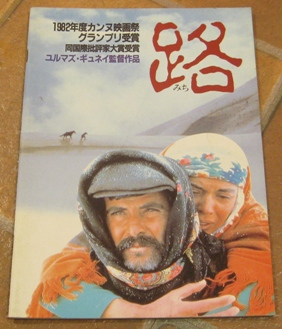
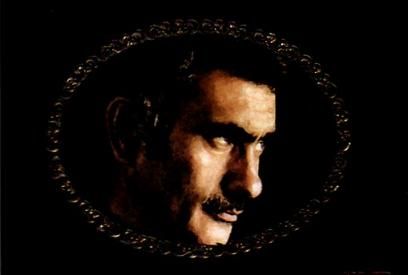
 朝日新聞社の中東アフリカ総局長などを務めたベテラン記者の川上洋一氏(本書執筆時は既に新聞社を退職し大学教授)がクルド人問題について書いたもので、'02年の刊行ですが、その後最近まであまりこうしたクルド人にフォーカスした本がそう多く出されていなかったため、クルド人問題の入門書としては定番的位置付けになっているのではないでしょうか。
朝日新聞社の中東アフリカ総局長などを務めたベテラン記者の川上洋一氏(本書執筆時は既に新聞社を退職し大学教授)がクルド人問題について書いたもので、'02年の刊行ですが、その後最近まであまりこうしたクルド人にフォーカスした本がそう多く出されていなかったため、クルド人問題の入門書としては定番的位置付けになっているのではないでしょうか。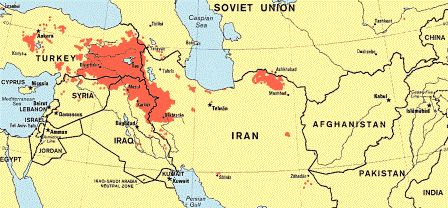 本書によれば、「祖国なき最大の民」と言われるクルド人の居住地域(クルディスタン)は主にトルコ、イラン、イラクにまたがり、面積はフランス一国にも匹敵、人口は2500万人とも推定され、パレスチナ人約800万を大きく凌ぐとのことです。
本書によれば、「祖国なき最大の民」と言われるクルド人の居住地域(クルディスタン)は主にトルコ、イラン、イラクにまたがり、面積はフランス一国にも匹敵、人口は2500万人とも推定され、パレスチナ人約800万を大きく凌ぐとのことです。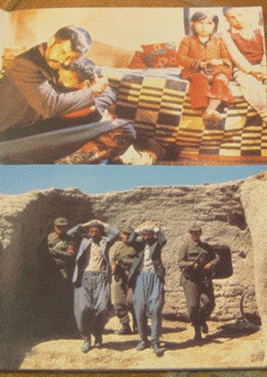 本書を読んで思い出されるのは、クルド人であるユルマズ・ギュネイ(1937-1984)監督の映画「路<みち>」('82年/トルコ・スイス)でした(この人、元は二枚目俳優。反体制作家でもあり、獄中から代理監督を立てて映画を作っていた)。
本書を読んで思い出されるのは、クルド人であるユルマズ・ギュネイ(1937-1984)監督の映画「路<みち>」('82年/トルコ・スイス)でした(この人、元は二枚目俳優。反体制作家でもあり、獄中から代理監督を立てて映画を作っていた)。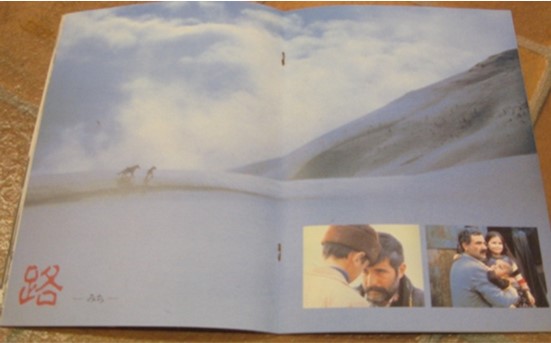 最初の男がやっと故郷に戻ってみると、妻は彼が入獄中に売春した咎で実家に戻され鎖に繋がれていて、しかも、掟により家名を汚した妻を自ら殺さなければならず、彼は妻を背負って山中へ逃げるが、鎖で繋がれていた間パンと水しか与えられていなかった妻は、雪の中で衰弱死する―。
最初の男がやっと故郷に戻ってみると、妻は彼が入獄中に売春した咎で実家に戻され鎖に繋がれていて、しかも、掟により家名を汚した妻を自ら殺さなければならず、彼は妻を背負って山中へ逃げるが、鎖で繋がれていた間パンと水しか与えられていなかった妻は、雪の中で衰弱死する―。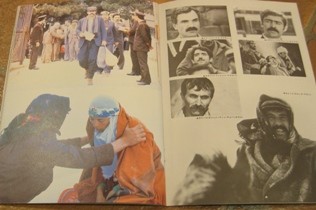 クルド人の圧政に対する不屈の精神と家族愛、男女愛を描く一方で、クルド人自らが、旧弊な因習により自らを縛っている面もあること如実に示した作品で、本国(クルド社会)内でも評価が割れたのではないかなあ。いや、そもそも、ギュネイ監督の作品は国内上映が禁止されているか(国際的にはカンヌ国際映画祭で最高賞であるパルム・ドールを受賞)。
クルド人の圧政に対する不屈の精神と家族愛、男女愛を描く一方で、クルド人自らが、旧弊な因習により自らを縛っている面もあること如実に示した作品で、本国(クルド社会)内でも評価が割れたのではないかなあ。いや、そもそも、ギュネイ監督の作品は国内上映が禁止されているか(国際的にはカンヌ国際映画祭で最高賞であるパルム・ドールを受賞)。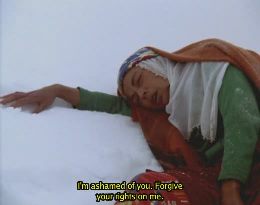
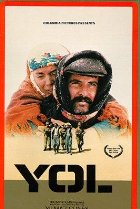
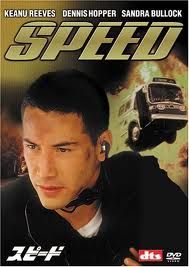
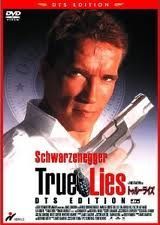

 ハリウッド映画のアクション系で、「ダイ・ハード」('88年)、「氷の微笑」('92年)のカメラマンだったヤン・デ・ボン(「トータル・リコール」「氷の微笑」のポール・バーホーベン監督と同じくオランダ人)の初監督作品「スピード」('94年)が気を吐きました。
ハリウッド映画のアクション系で、「ダイ・ハード」('88年)、「氷の微笑」('92年)のカメラマンだったヤン・デ・ボン(「トータル・リコール」「氷の微笑」のポール・バーホーベン監督と同じくオランダ人)の初監督作品「スピード」('94年)が気を吐きました。 時速を80キロ以下に落とすと爆発する爆弾を仕掛けたバスの疾走が迫力満点のノンストップアクションで、バスが街中を車をはじき飛ばしながら爆走したり、キアヌ・リーブスが爆弾を解除するために高速で走るバスの下にもぐりこむシーン、或いは、地下鉄の車両が工事現場を破壊しながら地上に突き抜けるシーンなどは実写中心であるため見応えはありました。
時速を80キロ以下に落とすと爆発する爆弾を仕掛けたバスの疾走が迫力満点のノンストップアクションで、バスが街中を車をはじき飛ばしながら爆走したり、キアヌ・リーブスが爆弾を解除するために高速で走るバスの下にもぐりこむシーン、或いは、地下鉄の車両が工事現場を破壊しながら地上に突き抜けるシーンなどは実写中心であるため見応えはありました。 脚本を書いたグレアム・ヨストは、 アンドレイ・コンチャロフスキー監督の「暴走機関車」('86年/米)の原
脚本を書いたグレアム・ヨストは、 アンドレイ・コンチャロフスキー監督の「暴走機関車」('86年/米)の原 案である黒澤明のオリジナル脚本を読んで着想を得たと述懐していますが、その脚本もまずまずではないでしょうか。但し、脚本を含めてよく出来ていた「ダイ・ハード」と比べるのと、トータルではやや落ちるか。キアヌ・リーブス、サンドラ・ブロック共に頑張っているけれど、爆弾魔のデニス・ホッパー(1936-2010)は、クイズ好きのオタクみたいで、それほど凄味がないような....。デニス・ホッパーということで、期待し過ぎてしまったのかもしれませんが(結局、大掛かりなアクションで見せる映画だった。元々の狙いも概ねそうだとは思うが)。
案である黒澤明のオリジナル脚本を読んで着想を得たと述懐していますが、その脚本もまずまずではないでしょうか。但し、脚本を含めてよく出来ていた「ダイ・ハード」と比べるのと、トータルではやや落ちるか。キアヌ・リーブス、サンドラ・ブロック共に頑張っているけれど、爆弾魔のデニス・ホッパー(1936-2010)は、クイズ好きのオタクみたいで、それほど凄味がないような....。デニス・ホッパーということで、期待し過ぎてしまったのかもしれませんが(結局、大掛かりなアクションで見せる映画だった。元々の狙いも概ねそうだとは思うが)。
 ということで、個人的にはヤン・デ・ボン監督には次に期待、というところだったのですが、その続編「スピード2」('97年/米)であっさりコケてしまった感じでした(既に同年の「ツイスター」('97年/米)を観れば、この監督の力量の限度は窺い知れたのだが。因みに、竜巻パニック
ということで、個人的にはヤン・デ・ボン監督には次に期待、というところだったのですが、その続編「スピード2」('97年/米)であっさりコケてしまった感じでした(既に同年の「ツイスター」('97年/米)を観れば、この監督の力量の限度は窺い知れたのだが。因みに、竜巻パニック
 「スピード」の「四つ星」評価に対し、本書で星3つの評価となっている「ターミネーター」シリーズのジェームズ・キャメロンが監督した「トゥルーライズ」('94年)の方が、ユーモアの要素があって個人的な評価はやや上になります。
「スピード」の「四つ星」評価に対し、本書で星3つの評価となっている「ターミネーター」シリーズのジェームズ・キャメロンが監督した「トゥルーライズ」('94年)の方が、ユーモアの要素があって個人的な評価はやや上になります。 アガサ・クリスティの「おしどり探偵」シリーズの現代アクション版みたいで、アーノルド・シュワルツェネッガーはコメディも充分にこなすし、スタント無しのジェイミー・リー・カーティスも良かったです(アクションでもそれ以外でも身体を張った演技をしていたなあ)。
アガサ・クリスティの「おしどり探偵」シリーズの現代アクション版みたいで、アーノルド・シュワルツェネッガーはコメディも充分にこなすし、スタント無しのジェイミー・リー・カーティスも良かったです(アクションでもそれ以外でも身体を張った演技をしていたなあ)。 カーチェイスの場面で実際に橋を爆破したというのもスゴいですが、一方で、シュワちゃんがゴールデン・ゲート・ブリッジにしがみつくシーンやハリヤー・ジェット機上でのテロリストとの"生身"のバトルシーンなど、デジタル合成のSFXをふんだんに使っています。
カーチェイスの場面で実際に橋を爆破したというのもスゴいですが、一方で、シュワちゃんがゴールデン・ゲート・ブリッジにしがみつくシーンやハリヤー・ジェット機上でのテロリストとの"生身"のバトルシーンなど、デジタル合成のSFXをふんだんに使っています。 「トゥルーライズ」ではそのほかに、ハリヤー・ジェット機の熱で空気が揺らぐシーンなどにもデジタル・ドメイン社が開発したCGが初めて使われていて、この技術は「アポロ13」('95年)のロケット発射シーンなどにも使われました(ジェームズ・キャメロンはデジタル・ドメイン社の初代共同経営者)。
「トゥルーライズ」ではそのほかに、ハリヤー・ジェット機の熱で空気が揺らぐシーンなどにもデジタル・ドメイン社が開発したCGが初めて使われていて、この技術は「アポロ13」('95年)のロケット発射シーンなどにも使われました(ジェームズ・キャメロンはデジタル・ドメイン社の初代共同経営者)。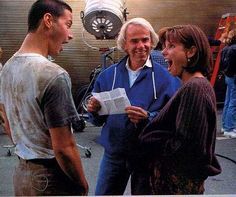
 「スピード」●原題:SPEED●制作年:1994年●制作国:アメリカ●監督:
「スピード」●原題:SPEED●制作年:1994年●制作国:アメリカ●監督: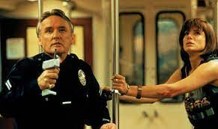 ヤン・デ・ボン●製作:マーク・ゴードン●脚本:ランダル・マコーミック/ジェフ・ナサンソン●撮影:アンジェイ・バートコウィアク●音楽:マーク・マンシーナ/ビリー・アイドル●時間:115分●出演:キアヌ・リーブス/デニス・ホッパー/サンドラ・ブロック/ジョー・モートン/ジェフ・ダニエルズ/アラン・ラック●日本公開:1994/12●配給:20世紀フォックス映画●最初に観た場所:有楽町・日本劇場(94-12-17)(評価:★★★☆)
ヤン・デ・ボン●製作:マーク・ゴードン●脚本:ランダル・マコーミック/ジェフ・ナサンソン●撮影:アンジェイ・バートコウィアク●音楽:マーク・マンシーナ/ビリー・アイドル●時間:115分●出演:キアヌ・リーブス/デニス・ホッパー/サンドラ・ブロック/ジョー・モートン/ジェフ・ダニエルズ/アラン・ラック●日本公開:1994/12●配給:20世紀フォックス映画●最初に観た場所:有楽町・日本劇場(94-12-17)(評価:★★★☆)
 「スピード2」●原題:SPEED:CRUISE CONTROL●制作年:1997年●制作国:アメリカ●監督:ヤン・デ・ボン●製作:マーク・ゴードン●脚本:グレアム・ヨスト●撮影:ジャック・N・グリーン●音楽:マーク・マンシーナ●時間:121分●出演:サンドラ・ブロック/ジェイソン・パトリック/ウィレム・デフォー/テムエラ・モリソン/ブライアン・マッカーディー/グレン・プラマー/コリーン・キャンプ/ロイス・チャイルズ/マイケル・G・ハガーティー/ボー・スヴェンソン/フランシス・ギナン/ジェレミー・ホッツ●日本公開:1997/08●配給:20世紀フォックス映画(評価:★★☆)
「スピード2」●原題:SPEED:CRUISE CONTROL●制作年:1997年●制作国:アメリカ●監督:ヤン・デ・ボン●製作:マーク・ゴードン●脚本:グレアム・ヨスト●撮影:ジャック・N・グリーン●音楽:マーク・マンシーナ●時間:121分●出演:サンドラ・ブロック/ジェイソン・パトリック/ウィレム・デフォー/テムエラ・モリソン/ブライアン・マッカーディー/グレン・プラマー/コリーン・キャンプ/ロイス・チャイルズ/マイケル・G・ハガーティー/ボー・スヴェンソン/フランシス・ギナン/ジェレミー・ホッツ●日本公開:1997/08●配給:20世紀フォックス映画(評価:★★☆)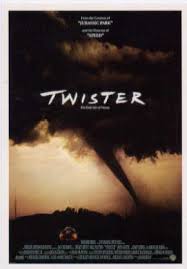
 「ツイスター」●原題:TWISTER●制作年:1996年●制作国:アメリカ●監督:ヤン・デ・ボン●製作:キャスリーン・ケネディ/イアン・ブライス/
「ツイスター」●原題:TWISTER●制作年:1996年●制作国:アメリカ●監督:ヤン・デ・ボン●製作:キャスリーン・ケネディ/イアン・ブライス/
 「トゥルーライズ」●原題:TRUE LIES●制作年:1994年●制作国:アメリカ●監督・脚本:ジェームズ・キャメロン●製作:ジェームズ・キャメロン/ステファニー・オースティン●オリジナル脚本:クロード・ジディ/シモン・ミシェル/ディディエ・カミンカ●撮影:ラッセル・カーペンター●音楽:ブラッド・フィーデル●時間:144分●出演:アーノルド・シュワルツェネッガー/ジェイミー・リー・カーティス/トム・アーノルド/ビル・パクストン/ティア・カレル/アート・マリック
「トゥルーライズ」●原題:TRUE LIES●制作年:1994年●制作国:アメリカ●監督・脚本:ジェームズ・キャメロン●製作:ジェームズ・キャメロン/ステファニー・オースティン●オリジナル脚本:クロード・ジディ/シモン・ミシェル/ディディエ・カミンカ●撮影:ラッセル・カーペンター●音楽:ブラッド・フィーデル●時間:144分●出演:アーノルド・シュワルツェネッガー/ジェイミー・リー・カーティス/トム・アーノルド/ビル・パクストン/ティア・カレル/アート・マリック
 /エリザ・ドゥシュク/グラント・ヘスロヴ/チャールトン・ヘストン●日本公開:1994/09●配給:日本ヘラルド映画●最初に観た場所:有楽町・日本劇場(94-09-25)(評価:★★★★)
/エリザ・ドゥシュク/グラント・ヘスロヴ/チャールトン・ヘストン●日本公開:1994/09●配給:日本ヘラルド映画●最初に観た場所:有楽町・日本劇場(94-09-25)(評価:★★★★)
 「ラスト・アクション・ヒーロー」●原題:LAST ACTION HERO●制作年:1993年●制作国:アメリカ●監督:ジョン・マクティアナン●製作:スティーヴ・ロス/ジョン・マクティアナン●脚本:デヴィッド・アーノット/シェーン・ブラック●撮影ディーン・セムラー●音楽:マイケル・ケイメン●時間:131分●出演:アーノルド・シュワルツェネッガー/オースティン・オブライエン/チャールズ・ダンス/ロバート・プロスキー/トム・ヌーナン/フランク・マクレー/アンソニー・クイン/ブリジット・ウィルソン/F・マーリー・エイブラハム/マーセデス・ルール/アート・カーニー/イアン・マッケラン/プロフェッサー・トオル・タナカ/ジョーン・プロウライト/ノア・エメリッヒ●日本公開:1993/08●配給:コロンビア映画(評価:★★★)
「ラスト・アクション・ヒーロー」●原題:LAST ACTION HERO●制作年:1993年●制作国:アメリカ●監督:ジョン・マクティアナン●製作:スティーヴ・ロス/ジョン・マクティアナン●脚本:デヴィッド・アーノット/シェーン・ブラック●撮影ディーン・セムラー●音楽:マイケル・ケイメン●時間:131分●出演:アーノルド・シュワルツェネッガー/オースティン・オブライエン/チャールズ・ダンス/ロバート・プロスキー/トム・ヌーナン/フランク・マクレー/アンソニー・クイン/ブリジット・ウィルソン/F・マーリー・エイブラハム/マーセデス・ルール/アート・カーニー/イアン・マッケラン/プロフェッサー・トオル・タナカ/ジョーン・プロウライト/ノア・エメリッヒ●日本公開:1993/08●配給:コロンビア映画(評価:★★★)

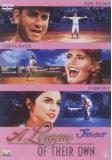
 結局、邦画界は1月に公開された周防正行監督の「シコふんじゃった。」がその年の映画賞を総ナメした形になりましたが、これ、意外と穴だったと言うか、実際に面白く(個人的にもこの年のナンバー1作品。但し、これだけ賞を獲ると、日本映画は他にいい作品がないのかという気も)、一方、洋画も例年の大作とは一味違ったものがじわじわ人気を呼んだりして、その典型が
結局、邦画界は1月に公開された周防正行監督の「シコふんじゃった。」がその年の映画賞を総ナメした形になりましたが、これ、意外と穴だったと言うか、実際に面白く(個人的にもこの年のナンバー1作品。但し、これだけ賞を獲ると、日本映画は他にいい作品がないのかという気も)、一方、洋画も例年の大作とは一味違ったものがじわじわ人気を呼んだりして、その典型が 1941年、場末の安ホテルに籠って脚本を書いていた劇作家バートン・フィンク(ジョン・タトゥーロ)は、隣室のセールス男メドウズ(ジョン・グッドマン)と親しくなるが、フィンク自身は脚本が書けなくなるスランプに陥り、更には自分の部屋で殺人事件が起きて、メドウズが死体を片付けてくれたものの、彼は完全に神経症に陥る―。
1941年、場末の安ホテルに籠って脚本を書いていた劇作家バートン・フィンク(ジョン・タトゥーロ)は、隣室のセールス男メドウズ(ジョン・グッドマン)と親しくなるが、フィンク自身は脚本が書けなくなるスランプに陥り、更には自分の部屋で殺人事件が起きて、メドウズが死体を片付けてくれたものの、彼は完全に神経症に陥る―。 もう一つ、同じく'92年公開のジョン・アヴネット監督の「フライド・グリーン・トマト」('91年/米)は、「ドライビング・ミス・デージー」のジェシカ・タンディが演じる元カフェ経営者の昔話を、「ミザリー」のキャシー・ベイツ演じる夫に愛想をつかされた女性が聴くという展開でしたが(アカデミー主演賞女優同士!)、ジェシカ婆さんが淡々と語る話の内容が、ある種、女性たちの人間として生きる権利を求めての闘いの軌跡というか、感動ストーリーでありながらも、合間に入るエピソードがグリム童話みたいに残酷(猟奇的)だったりして、この取り合わせの妙が何とも言えない作品でした。
もう一つ、同じく'92年公開のジョン・アヴネット監督の「フライド・グリーン・トマト」('91年/米)は、「ドライビング・ミス・デージー」のジェシカ・タンディが演じる元カフェ経営者の昔話を、「ミザリー」のキャシー・ベイツ演じる夫に愛想をつかされた女性が聴くという展開でしたが(アカデミー主演賞女優同士!)、ジェシカ婆さんが淡々と語る話の内容が、ある種、女性たちの人間として生きる権利を求めての闘いの軌跡というか、感動ストーリーでありながらも、合間に入るエピソードがグリム童話みたいに残酷(猟奇的)だったりして、この取り合わせの妙が何とも言えない作品でした。 女流監督ペニー・マーシャルが「レナードの朝」('90年)の次に撮った「プリティ・リーグ」('91年/米)のあらすじは―、1943年、男たちが戦争に駆り出され、プロ野球閉鎖の危機が訪れる中、全米女子プロ野球リーグが結成され、最強チーム"ピーチズ"のメンバーは、田舎の主婦からホール・ダンサーまで、野球を愛する男顔負けのスーパー・レディースで構成さ
女流監督ペニー・マーシャルが「レナードの朝」('90年)の次に撮った「プリティ・リーグ」('91年/米)のあらすじは―、1943年、男たちが戦争に駆り出され、プロ野球閉鎖の危機が訪れる中、全米女子プロ野球リーグが結成され、最強チーム"ピーチズ"のメンバーは、田舎の主婦からホール・ダンサーまで、野球を愛する男顔負けのスーパー・レディースで構成さ れていたが、汗と埃にまみれて白球を追う彼女たちの力強く美しい姿には全米が拍手を贈った―という感動もので、一見すると漫画的題材ですが、実話がベースになっているというのはやはり強いなあと。監督役のトム・ハンクスの演技が冴え、痛快スポーツ・ドラマとなっていますが、最後の同窓会的にかつてのメンバーが集う場面は、賛否があるものの個人的には良かったです。スーパースターのマドンナがナインの一員として(エース役のジーナ・デイビスの助演として)しっかり演技しているという点で興味深い作品でもあります。マドンナはハマリ役でした。
れていたが、汗と埃にまみれて白球を追う彼女たちの力強く美しい姿には全米が拍手を贈った―という感動もので、一見すると漫画的題材ですが、実話がベースになっているというのはやはり強いなあと。監督役のトム・ハンクスの演技が冴え、痛快スポーツ・ドラマとなっていますが、最後の同窓会的にかつてのメンバーが集う場面は、賛否があるものの個人的には良かったです。スーパースターのマドンナがナインの一員として(エース役のジーナ・デイビスの助演として)しっかり演技しているという点で興味深い作品でもあります。マドンナはハマリ役でした。 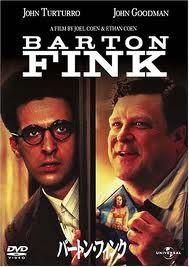

 「バートン・フィンク」●原題:BARTON FINK●制作年:1991年●制作国:アメリカ●監督:ジョエル・コーエン●製作:イーサン・コーエン●脚本:ジョエル&イーサン・コーエン●撮影:ロジャー・ディーキンス●音楽:カーター・パウエル●時間:116分●出演:ジョン・タトゥーロ/ジョン・グッドマン/ジュディ・デイヴィス/マイケル・ラーナー/ジョン・マホーニー/トニー・シャルーブ●日本公開:1992/03●配給:KUZUIエンタープライズ(評価:★★★★)
「バートン・フィンク」●原題:BARTON FINK●制作年:1991年●制作国:アメリカ●監督:ジョエル・コーエン●製作:イーサン・コーエン●脚本:ジョエル&イーサン・コーエン●撮影:ロジャー・ディーキンス●音楽:カーター・パウエル●時間:116分●出演:ジョン・タトゥーロ/ジョン・グッドマン/ジュディ・デイヴィス/マイケル・ラーナー/ジョン・マホーニー/トニー・シャルーブ●日本公開:1992/03●配給:KUZUIエンタープライズ(評価:★★★★) 「フライド・グリーン・トマト」●原題:FRIED GREEN TOMATO●制作年:1991年●制作国:アメリカ●監督:ジョン・アヴネット●製作:ジョン・アヴネット/ジョーダン・カーナー●脚本:キャロル・ソビエス
「フライド・グリーン・トマト」●原題:FRIED GREEN TOMATO●制作年:1991年●制作国:アメリカ●監督:ジョン・アヴネット●製作:ジョン・アヴネット/ジョーダン・カーナー●脚本:キャロル・ソビエス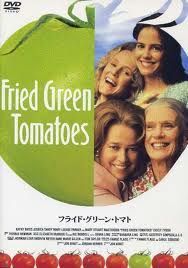
![プリティ・リーグ [DVD].jpg](http://hurec.bz/book-movie/%E3%83%97%E3%83%AA%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%BB%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%B0%20%5BDVD%5D.jpg)
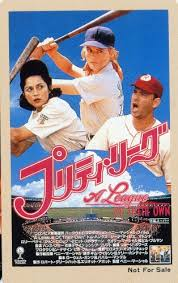 「プリティ・リーグ」●原題:A LEAGUE OF THEIR OWN●制作年:1991年●制作国:アメリカ●監督:ペニー・マーシャル●製作:ロバート・グリーンハット/エリオット・アボット●脚本:ババルー・マンデル/ローウェル・ガンツ●撮影:ミロスラフ・オンドリチェク●音楽:ハンス・ジマー●時間:116分●出演:トム・ハンクス/ジーナ・デイヴィス/マドンナ/ロリー・ペティ/ロージー・オドネル/ジョン・ロビッツ/デヴィッド・ストラザーン/ゲイリー・マーシャル/ビル・プルマン/ティア・レオーニ/アン・キューザック/エディ・ジョーンズ/アン・ラムゼイ/ポーリン・ブレイスフォード/ミーガン・カヴァナグ/トレイシー・ライナー/ビッティ・シュラム/ドン・S・デイヴィス/グレゴリー・スポーレダー●日本公開:1992/10●配給:コロンビア・トライスター映画社(評価:★★★★)
「プリティ・リーグ」●原題:A LEAGUE OF THEIR OWN●制作年:1991年●制作国:アメリカ●監督:ペニー・マーシャル●製作:ロバート・グリーンハット/エリオット・アボット●脚本:ババルー・マンデル/ローウェル・ガンツ●撮影:ミロスラフ・オンドリチェク●音楽:ハンス・ジマー●時間:116分●出演:トム・ハンクス/ジーナ・デイヴィス/マドンナ/ロリー・ペティ/ロージー・オドネル/ジョン・ロビッツ/デヴィッド・ストラザーン/ゲイリー・マーシャル/ビル・プルマン/ティア・レオーニ/アン・キューザック/エディ・ジョーンズ/アン・ラムゼイ/ポーリン・ブレイスフォード/ミーガン・カヴァナグ/トレイシー・ライナー/ビッティ・シュラム/ドン・S・デイヴィス/グレゴリー・スポーレダー●日本公開:1992/10●配給:コロンビア・トライスター映画社(評価:★★★★)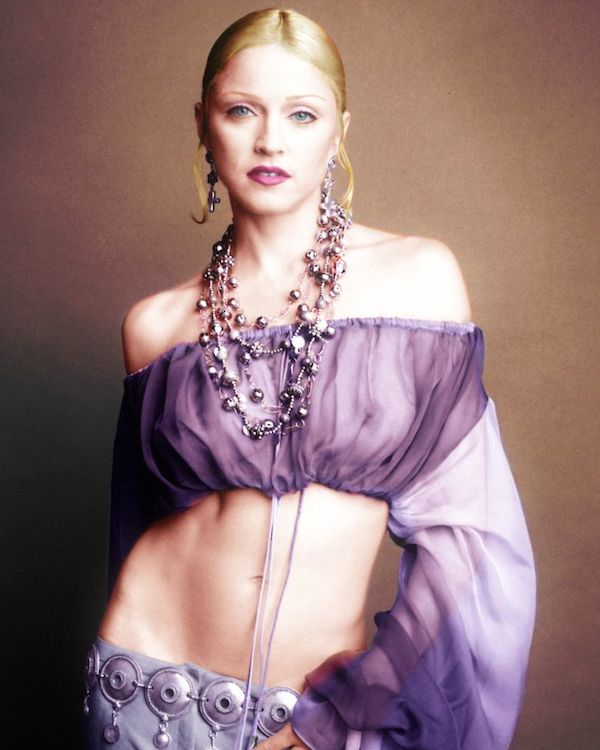
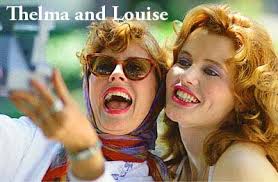

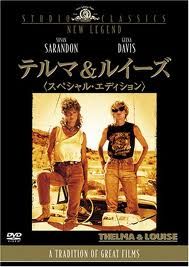
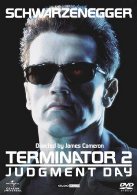
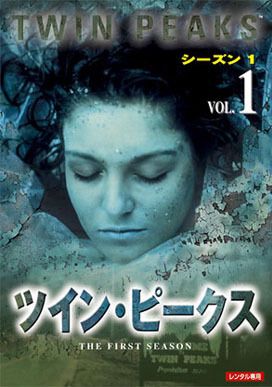 『
『 個人的なイチオシは、リドリー・スコット監督の「テルマ&ルイーズ」('91年/米)で、専業主婦のテルマ(ジーナ・デイヴィス)とレストランでウエイトレスとして働く独身女性のルイーズ(スーザン・サランドン)の親友同士が週末旅行に出掛けた先で、自分たちをレイプしようとした男を射殺したことから、転じて逃走劇になるという話(ロンドン映画批評家協会賞「作品賞」「女優賞(スーザン・サランドン)」受賞作)。
個人的なイチオシは、リドリー・スコット監督の「テルマ&ルイーズ」('91年/米)で、専業主婦のテルマ(ジーナ・デイヴィス)とレストランでウエイトレスとして働く独身女性のルイーズ(スーザン・サランドン)の親友同士が週末旅行に出掛けた先で、自分たちをレイプしようとした男を射殺したことから、転じて逃走劇になるという話(ロンドン映画批評家協会賞「作品賞」「女優賞(スーザン・サランドン)」受賞作)。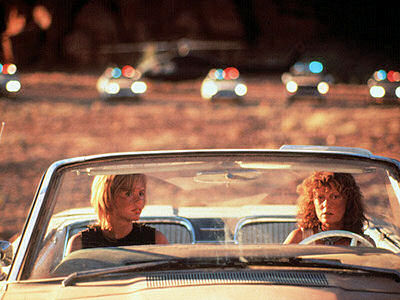 リドリー・スコットが女性映画を撮ったという意外性もありましたが、ジーナ・デイヴィスとスーザン・サランドンが、どんどん破局に向かいつつも、その過程においてこれまでの束縛や因習から解放され自由になっていく女性を好演し、彼女ら追いつつも彼女らの心情を理解し、何とか連れ戻したいと
リドリー・スコットが女性映画を撮ったという意外性もありましたが、ジーナ・デイヴィスとスーザン・サランドンが、どんどん破局に向かいつつも、その過程においてこれまでの束縛や因習から解放され自由になっていく女性を好演し、彼女ら追いつつも彼女らの心情を理解し、何とか連れ戻したいと
 思う警部役のハーベイ・カイテルの演技も良かったです(まださほど知られていない頃のブラッド・ピットが、彼女らの金を持ち逃げするヒッチハイカー役で出ていたりもした)。
思う警部役のハーベイ・カイテルの演技も良かったです(まださほど知られていない頃のブラッド・ピットが、彼女らの金を持ち逃げするヒッチハイカー役で出ていたりもした)。 「ダンス・ウィズ・ウルブス」といったアカデミー賞受賞作品と並んで「羊たちの沈黙」や「ターミネーター2」が星4つの評価を得ているというのがこの年の特徴でしょうか。
「ダンス・ウィズ・ウルブス」といったアカデミー賞受賞作品と並んで「羊たちの沈黙」や「ターミネーター2」が星4つの評価を得ているというのがこの年の特徴でしょうか。 ジェームズ・キャメロン監督の「ターミネーター2」('91年/米)は、形状記憶疑似合金でできたT1000型ターミネーターが登場したものでしたが、この作品の前に「アビス」('89年)を撮り、ずっと後に「アバター」('09年)を撮ることになる
ジェームズ・キャメロン監督の「ターミネーター2」('91年/米)は、形状記憶疑似合金でできたT1000型ターミネーターが登場したものでしたが、この作品の前に「アビス」('89年)を撮り、ずっと後に「アバター」('09年)を撮ることになる ジェームズ・キャメロン監督らしい特撮CGが冴えていたように思われ、T1000型を演じるロバート・パトリックも、華奢なところがかえって凄味がありました。一方、アーノルド・シュワルツネッガーが演じる旧タイプのT800型ターミネーターを善玉にまわしてヒューマンにした分、前作「ターミネーター」に比べ甘さがあるように思いました(これ、本書において山口猛氏が書いている批評とほぼ同じなのだが、山口氏の評価は最高評価になる星4つ)。IMDb評価は、「ターミネーター」が[8.1]、「ターミネーター2」が[8.6]で、「2」が上になっています。後からまとめて観た人は「2」の方がいいのかもしれないけれど、それぞれリルタイムで観た自分の場合、「1」のインパクトが大きかったです。
ジェームズ・キャメロン監督らしい特撮CGが冴えていたように思われ、T1000型を演じるロバート・パトリックも、華奢なところがかえって凄味がありました。一方、アーノルド・シュワルツネッガーが演じる旧タイプのT800型ターミネーターを善玉にまわしてヒューマンにした分、前作「ターミネーター」に比べ甘さがあるように思いました(これ、本書において山口猛氏が書いている批評とほぼ同じなのだが、山口氏の評価は最高評価になる星4つ)。IMDb評価は、「ターミネーター」が[8.1]、「ターミネーター2」が[8.6]で、「2」が上になっています。後からまとめて観た人は「2」の方がいいのかもしれないけれど、それぞれリルタイムで観た自分の場合、「1」のインパクトが大きかったです。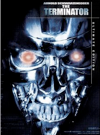 督デビュー作「殺人魚
督デビュー作「殺人魚 フライング・キラー」(81年)に続く監督2作目であり、彼の出世作と言えます。ジェームズ・キャメロン監督はシュワルツネッガーと1度会食をしただけで、キャリアが浅く当初脇役で出演の予定だった彼をT800型ターミネーター役に抜擢することを決めたそうですが、シュワルツネッガーの全裸での登場シーンから始まって、そのストロングタイプのヒールぶりは今振り返っても
フライング・キラー」(81年)に続く監督2作目であり、彼の出世作と言えます。ジェームズ・キャメロン監督はシュワルツネッガーと1度会食をしただけで、キャリアが浅く当初脇役で出演の予定だった彼をT800型ターミネーター役に抜擢することを決めたそうですが、シュワルツネッガーの全裸での登場シーンから始まって、そのストロングタイプのヒールぶりは今振り返っても 強烈なインパクトがあったように思います。ただ、この作品の後、「ターミネーター2」との間の7年間の間隔があり(ヒットしたB級映画にありがちだが、すぐにでも続編を撮りたいところが版権が複数社に跨っており、撮ろうにもなかなか撮れなかった)、その間に
強烈なインパクトがあったように思います。ただ、この作品の後、「ターミネーター2」との間の7年間の間隔があり(ヒットしたB級映画にありがちだが、すぐにでも続編を撮りたいところが版権が複数社に跨っており、撮ろうにもなかなか撮れなかった)、その間に シュワルツネッガーは「レッドソニア」「コマンドー」「ゴリラ」「プレデター」「バトルランナー」「レッドブル」「ツインズ」「
シュワルツネッガーは「レッドソニア」「コマンドー」「ゴリラ」「プレデター」「バトルランナー」「レッドブル」「ツインズ」「 ビデオ14巻、全29話(パイロット版を含めると30話)、24時間強のサスペンス・ミステリーですが、毎回毎回いつもいいところで終わるので、続きを観るまで禁断症状になるという(あの村上春樹も米国でリアルタイムでハマったという)―ラストは腑に落ちなかったけれども(「えーっ、これが結末?」という感じか)、そのことを割り引いてもテレビ・ムービーの金字塔と
ビデオ14巻、全29話(パイロット版を含めると30話)、24時間強のサスペンス・ミステリーですが、毎回毎回いつもいいところで終わるので、続きを観るまで禁断症状になるという(あの村上春樹も米国でリアルタイムでハマったという)―ラストは腑に落ちなかったけれども(「えーっ、これが結末?」という感じか)、そのことを割り引いてもテレビ・ムービーの金字塔と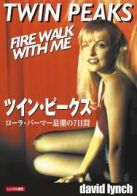
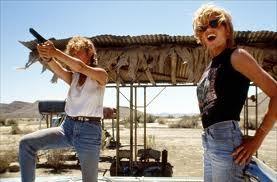
 「テルマ&ルイーズ」●原題:THELMA & LOUISE●制作年:1989年●制作国:アメリカ●監督:リドリー・スコット●製作:リドリー・スコット/ミミ・ポーク●脚本:カーリー・クーリ●撮影:エイドリアン・ビドル●音楽:ハンス・ジマー●時間:129分●出演:スーザン・サランドン/ジーナ・デイヴィス/ハーヴェイ・カイテル/マイケル・マドセン/ブラッド・ピット●日本公開:1991/10●配給:松竹富士(評価:★★★★☆)
「テルマ&ルイーズ」●原題:THELMA & LOUISE●制作年:1989年●制作国:アメリカ●監督:リドリー・スコット●製作:リドリー・スコット/ミミ・ポーク●脚本:カーリー・クーリ●撮影:エイドリアン・ビドル●音楽:ハンス・ジマー●時間:129分●出演:スーザン・サランドン/ジーナ・デイヴィス/ハーヴェイ・カイテル/マイケル・マドセン/ブラッド・ピット●日本公開:1991/10●配給:松竹富士(評価:★★★★☆) 「ターミネーター2」●原題:TERMINATOR2:JUDGMENT DAY●制作年:1991
「ターミネーター2」●原題:TERMINATOR2:JUDGMENT DAY●制作年:1991 年●制作国:アメリカ●監督・製作:ジェームズ・キャメロン●脚本ジェームズ・キャメロン/ウィリアム・ウィッシャー●撮影:アダム・グリーンバーグ●音楽:ブラッド・フィーデル●時間:137分(公開版)/154分(完全版)●出演:アーノルド・シュワルツェネッガー/リンダ・ハミルトン/エドワード・ファーロング/ロバート・パトリック/アール・ボーエン/ジョー・モートン/ジャネット・ゴールドスタイン●日本公開:1991/08●配給:東宝東和(評価:★★★)
年●制作国:アメリカ●監督・製作:ジェームズ・キャメロン●脚本ジェームズ・キャメロン/ウィリアム・ウィッシャー●撮影:アダム・グリーンバーグ●音楽:ブラッド・フィーデル●時間:137分(公開版)/154分(完全版)●出演:アーノルド・シュワルツェネッガー/リンダ・ハミルトン/エドワード・ファーロング/ロバート・パトリック/アール・ボーエン/ジョー・モートン/ジャネット・ゴールドスタイン●日本公開:1991/08●配給:東宝東和(評価:★★★)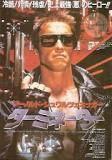
 「ターミネーター」●原題:THE TERMINATOR●制作年:1984年●制作国:アメリカ/イギリス●監督:ジェームズ・キャメロン●製作:ゲイル・アン・ハード●脚本:ジェームズ・キャメロン/ゲイル・アン・ハード
「ターミネーター」●原題:THE TERMINATOR●制作年:1984年●制作国:アメリカ/イギリス●監督:ジェームズ・キャメロン●製作:ゲイル・アン・ハード●脚本:ジェームズ・キャメロン/ゲイル・アン・ハード ●撮影:アダム・グリーンバーグ●音楽:ブラッド・フィーデル●時間:108分●出演:
●撮影:アダム・グリーンバーグ●音楽:ブラッド・フィーデル●時間:108分●出演:
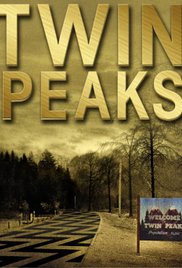



 992年●制作国:アメリカ●監督:デイヴィッド・リンチ●製作:グレッグ・ファインバーグ●脚本:デイヴィッド・リンチ/ロバート・エンゲルス●撮影:ロン・ガルシア●音楽:アンジェロ・バダラメンティ●時間:135分●出演:シェリル・リー/レイ・ワイズ/カイル・マクラクラン/デヴィッド・ボウイ/キーファー・サザーランド●日本公開:1992/05●配給:日本ヘラルド映画(評価:★★★?)
992年●制作国:アメリカ●監督:デイヴィッド・リンチ●製作:グレッグ・ファインバーグ●脚本:デイヴィッド・リンチ/ロバート・エンゲルス●撮影:ロン・ガルシア●音楽:アンジェロ・バダラメンティ●時間:135分●出演:シェリル・リー/レイ・ワイズ/カイル・マクラクラン/デヴィッド・ボウイ/キーファー・サザーランド●日本公開:1992/05●配給:日本ヘラルド映画(評価:★★★?)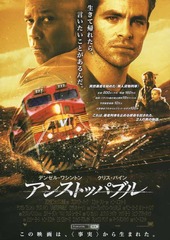
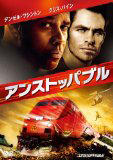
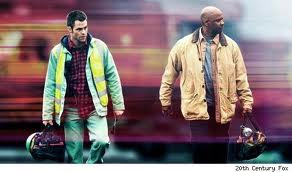

 ペンシルバニア州のある操車場に停車中の最新式貨物列車が、整備士の人為的ミスによって無人のまま走り出してしまうが、積荷は大量の化学薬品とディーゼル燃料であることが判明、操車場長のコニー・フーパー(ロザリオ・ドーソン)は極めて深刻な事態が発生
ペンシルバニア州のある操車場に停車中の最新式貨物列車が、整備士の人為的ミスによって無人のまま走り出してしまうが、積荷は大量の化学薬品とディーゼル燃料であることが判明、操車場長のコニー・フーパー(ロザリオ・ドーソン)は極めて深刻な事態が発生 したことを認識し、州警察に緊急配備を依頼する。フランク・バーンズ(デンゼル・ワシントン)と職務経験4ヵ月のその頃、勤続28年のベテラン機関士車掌ウィル・コルソン(クリス・パイン)は、この日初めてコンビを組み、旧式機関車に乗り込み職務に就いていた―。
したことを認識し、州警察に緊急配備を依頼する。フランク・バーンズ(デンゼル・ワシントン)と職務経験4ヵ月のその頃、勤続28年のベテラン機関士車掌ウィル・コルソン(クリス・パイン)は、この日初めてコンビを組み、旧式機関車に乗り込み職務に就いていた―。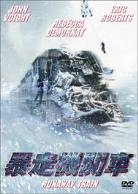



 にしているところに興味を惹かれました(「リスク管理」の教材?この作品の日本初試写会は鉄道高校として有名な東京・上野の岩倉高等学校の体育館で行われ、ゲストにAKB48のメンバーが登場した(2010年11月17日) )。
にしているところに興味を惹かれました(「リスク管理」の教材?この作品の日本初試写会は鉄道高校として有名な東京・上野の岩倉高等学校の体育館で行われ、ゲストにAKB48のメンバーが登場した(2010年11月17日) )。 デンゼル・ワシントンは、同じくトニー・スコット監督作品の「サブウェイ123 激突」('09年)でも鉄道員の役を演じていて、前回は運行司令官役でしたが、今回は運転士役。デンゼル・ワシントンが、妻と死別し2人の難しい年頃の娘がいる寡男で会社からは退職勧告を受けていて、クリス・パインの方は、妻の浮気疑惑で離婚争議中のため接近禁止命令が出ている男といった具合に、共に仕事や家庭生活に難点を抱える者同士の組み合わせですが、映画の主役は、劇薬を積んで市街地へ向かって暴走する800メートルの貨物列車でしょうか。
デンゼル・ワシントンは、同じくトニー・スコット監督作品の「サブウェイ123 激突」('09年)でも鉄道員の役を演じていて、前回は運行司令官役でしたが、今回は運転士役。デンゼル・ワシントンが、妻と死別し2人の難しい年頃の娘がいる寡男で会社からは退職勧告を受けていて、クリス・パインの方は、妻の浮気疑惑で離婚争議中のため接近禁止命令が出ている男といった具合に、共に仕事や家庭生活に難点を抱える者同士の組み合わせですが、映画の主役は、劇薬を積んで市街地へ向かって暴走する800メートルの貨物列車でしょうか。
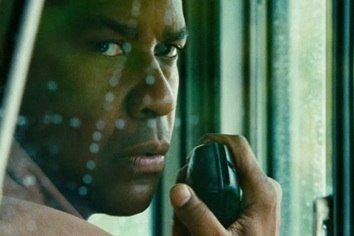 鉄道会社の上層部の見通しの甘い事故対応が更に
鉄道会社の上層部の見通しの甘い事故対応が更に 事態を悪化させるといった社会批判も織り交ぜ、また、アクション映画としてもよく出来ているけれども、最初からデンゼル・ワシントン(観ていて安心感あり過ぎ)らが事態を収束するであろうことが見えていて、あまりドキドキしなかった感じも(むしろ、デンゼル・ワシントンは彼自身のアクション・シーンが危なっかしい感じだったけれど、勿論これは演技のうち?)。
事態を悪化させるといった社会批判も織り交ぜ、また、アクション映画としてもよく出来ているけれども、最初からデンゼル・ワシントン(観ていて安心感あり過ぎ)らが事態を収束するであろうことが見えていて、あまりドキドキしなかった感じも(むしろ、デンゼル・ワシントンは彼自身のアクション・シーンが危なっかしい感じだったけれど、勿論これは演技のうち?)。



 女性操車場長のロザリオ・ドーソンは、リー・ストラスバーグ演劇学校で学んだ演技派で、この作品でも好演(「メン・イン・ブラック2」('02年)の店員役の頃に比べると随分貫禄がついた?)。但し、事故の収束とともに2人の男がヒーローになるのは"予定調和"の内だけれど、それで両者の仕事や家庭問題まで一気に解決されてしまったとなると、"事故様様"みたいな感じもしてしまいました(1人犠牲者が出ている。「危機管理」の観点からももっと反省すべきケースではないか)。
女性操車場長のロザリオ・ドーソンは、リー・ストラスバーグ演劇学校で学んだ演技派で、この作品でも好演(「メン・イン・ブラック2」('02年)の店員役の頃に比べると随分貫禄がついた?)。但し、事故の収束とともに2人の男がヒーローになるのは"予定調和"の内だけれど、それで両者の仕事や家庭問題まで一気に解決されてしまったとなると、"事故様様"みたいな感じもしてしまいました(1人犠牲者が出ている。「危機管理」の観点からももっと反省すべきケースではないか)。
 トニー・スコット監督、デンゼル・ワシントンの組み合わせでは、米軍原子力潜水艦を舞台にした「クリムゾン・タイド」('95年)が傑作でしょうか。
トニー・スコット監督、デンゼル・ワシントンの組み合わせでは、米軍原子力潜水艦を舞台にした「クリムゾン・タイド」('95年)が傑作でしょうか。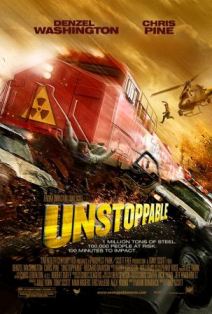
 「アンストッパブル」●原題:UNSTOPPABLE●制作年:2010年●制作国:アメリカ●監督:トニー・スコット●製作:ジュリー・ヨーン/トニー・スコット/ミミ・ロジャース/エリック・
「アンストッパブル」●原題:UNSTOPPABLE●制作年:2010年●制作国:アメリカ●監督:トニー・スコット●製作:ジュリー・ヨーン/トニー・スコット/ミミ・ロジャース/エリック・ マクレオド/アレックス・ヤング●脚本:マーク・ボンバック●撮影:ベン・セレシン●音楽:ハリー・グレッグソン=ウィリアムズ●時間:98分●出演:デンゼル・ワシントン/クリス・パイン/ロザリオ・ドーソン/ケヴィン・ダン/イーサン・サプリー/T・J・ミラー/リュー・テンプル/ジェシー・シュラム/ケヴィン・チャップマン/ケヴィン・コリガン/デヴィッド・ウォーショフスキー●日本公開:2011/01●配給:20世紀フォックス(評価:★★★) 東京・上野の岩倉高等学校での公開記念イベント(AKB48高橋みなみ、渡辺麻友、宮澤佐江)
マクレオド/アレックス・ヤング●脚本:マーク・ボンバック●撮影:ベン・セレシン●音楽:ハリー・グレッグソン=ウィリアムズ●時間:98分●出演:デンゼル・ワシントン/クリス・パイン/ロザリオ・ドーソン/ケヴィン・ダン/イーサン・サプリー/T・J・ミラー/リュー・テンプル/ジェシー・シュラム/ケヴィン・チャップマン/ケヴィン・コリガン/デヴィッド・ウォーショフスキー●日本公開:2011/01●配給:20世紀フォックス(評価:★★★) 東京・上野の岩倉高等学校での公開記念イベント(AKB48高橋みなみ、渡辺麻友、宮澤佐江)

 「暴走機関車」●原題:RUNAWAY TRAIN●制作年:1985年●制作国:アメリカ●監督:アンドレ・ミハルコフ=コンチャロフスキー●製
「暴走機関車」●原題:RUNAWAY TRAIN●制作年:1985年●制作国:アメリカ●監督:アンドレ・ミハルコフ=コンチャロフスキー●製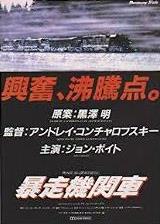 作:ヨーラン・グローバス/メナハム・ゴーラン●脚本:ジョルジェ・ミリチェヴィク/ポール・ジンデル/エドワード・バンカート●撮影:アラン・ヒューム●音楽:トレヴァー・ジョーンズ●原案:
作:ヨーラン・グローバス/メナハム・ゴーラン●脚本:ジョルジェ・ミリチェヴィク/ポール・ジンデル/エドワード・バンカート●撮影:アラン・ヒューム●音楽:トレヴァー・ジョーンズ●原案:
 「恐怖の報酬」●原題:LE SALAIRE DELA PEUR●制作年:1953年●制作国:フランス●監督・脚本:アンリ・ジョルジュ・クルーゾー●撮影:アルマン・ティラール●音楽:ジョルジュ・オーリック●原作:ジョルジュ・アルノー●時間:131分●出演:イヴ・モンタン/シャルル・ヴァネル/ヴェラ・クルーゾー/フォルコ・ルリ●日本公開:1954/07●配給:東和●最初に観た場所:新宿アートビレッジ (79-02-10)(評価:★★★★)●併映:「死刑台のエレベーター」(ルイ・マル)
「恐怖の報酬」●原題:LE SALAIRE DELA PEUR●制作年:1953年●制作国:フランス●監督・脚本:アンリ・ジョルジュ・クルーゾー●撮影:アルマン・ティラール●音楽:ジョルジュ・オーリック●原作:ジョルジュ・アルノー●時間:131分●出演:イヴ・モンタン/シャルル・ヴァネル/ヴェラ・クルーゾー/フォルコ・ルリ●日本公開:1954/07●配給:東和●最初に観た場所:新宿アートビレッジ (79-02-10)(評価:★★★★)●併映:「死刑台のエレベーター」(ルイ・マル) 
 ジットなし)●撮影:ダリウス・ウォルスキー●音楽:ハンス・ジマー●時間:116分●出演:デンゼル・ワシントン/ジーン・ハックマン/ジョージ・ズンザ/ヴィゴ・モーテンセン/ジェームズ・ガンドルフィーニ/リロ・ブランカート.Jr/ダニー・ヌッチ/スティーヴ・ザーン/リッキー・シュローダー/ロッキー・キャロル/ヴァネッサ・ベル・キャロウェイ●日本公開:1995/10●配給:ブエナ・ビスタ(評価:★★★★)
ジットなし)●撮影:ダリウス・ウォルスキー●音楽:ハンス・ジマー●時間:116分●出演:デンゼル・ワシントン/ジーン・ハックマン/ジョージ・ズンザ/ヴィゴ・モーテンセン/ジェームズ・ガンドルフィーニ/リロ・ブランカート.Jr/ダニー・ヌッチ/スティーヴ・ザーン/リッキー・シュローダー/ロッキー・キャロル/ヴァネッサ・ベル・キャロウェイ●日本公開:1995/10●配給:ブエナ・ビスタ(評価:★★★★)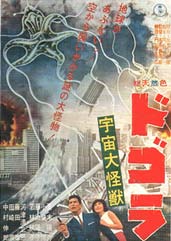
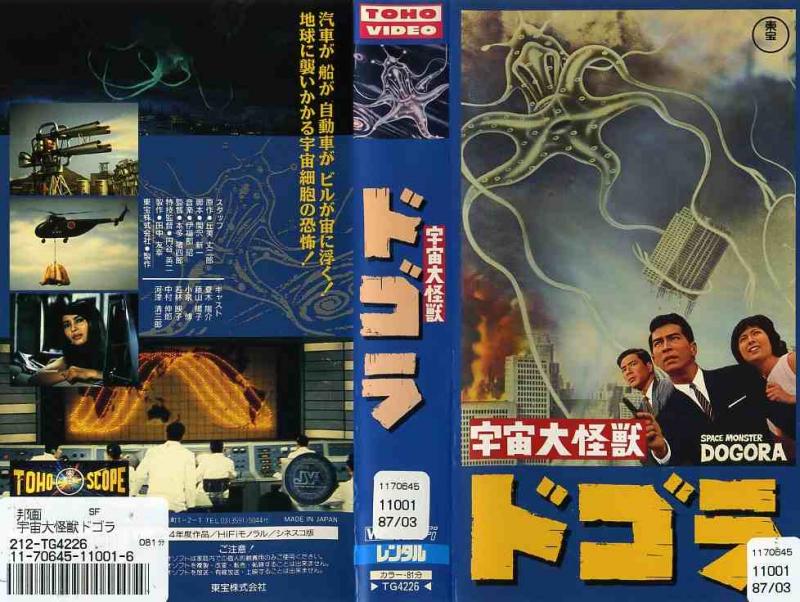
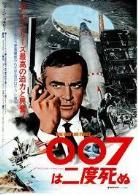
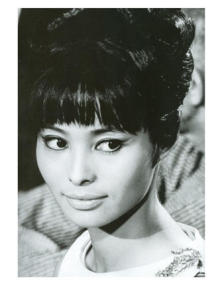
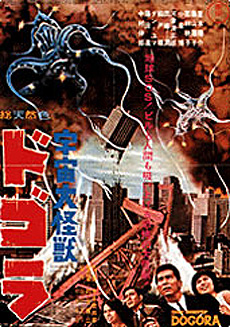 日本上空を周回中のテレビ中継衛星が突然消え、時を同じくして世界各国の宝石店が襲われて多量のダイヤモンドが盗まれる事件が頻発し、警視庁は宝石強盗団一味の仕業として捜査を開始、警視庁の駒井刑事(夏木陽介)は、ダイヤの研究を行なっている宗方博士(中村伸郎)のもとを訪れるが、マークという謎の外国人(ダン・ユマ)に襲撃されてダイヤを奪われ、そのマークも強盗団にダイヤを奪われる。一方の強盗団も、盗んだダイヤを積んだトラックが突如浮遊して落下するという異常事態に見舞われる―。
日本上空を周回中のテレビ中継衛星が突然消え、時を同じくして世界各国の宝石店が襲われて多量のダイヤモンドが盗まれる事件が頻発し、警視庁は宝石強盗団一味の仕業として捜査を開始、警視庁の駒井刑事(夏木陽介)は、ダイヤの研究を行なっている宗方博士(中村伸郎)のもとを訪れるが、マークという謎の外国人(ダン・ユマ)に襲撃されてダイヤを奪われ、そのマークも強盗団にダイヤを奪われる。一方の強盗団も、盗んだダイヤを積んだトラックが突如浮遊して落下するという異常事態に見舞われる―。 1960年代半ばの東宝映画は、「ゴジラ」シリーズの全盛期で
1960年代半ばの東宝映画は、「ゴジラ」シリーズの全盛期で したが、この頃東宝はゴジラを主役にした映画ばかりではなく、こんなのも撮っていました。こんなのと言ってもどう言えば良いのか。クラゲのお化けみたいな巨大宇宙生物が出てくる作品です。
したが、この頃東宝はゴジラを主役にした映画ばかりではなく、こんなのも撮っていました。こんなのと言ってもどう言えば良いのか。クラゲのお化けみたいな巨大宇宙生物が出てくる作品です。
 クラゲの全体像がなかなか見えないのもイマジネーションを駆りたてるし、実はこのクラゲ、ビニール製だそうですが、CGの無い時代にジェームズ・キャメロンの「アビス」('89年/米)顔負けの映像作りをしているなあと感心しました(「ドゴラ」の原案イメージは小松崎茂)。
クラゲの全体像がなかなか見えないのもイマジネーションを駆りたてるし、実はこのクラゲ、ビニール製だそうですが、CGの無い時代にジェームズ・キャメロンの「アビス」('89年/米)顔負けの映像作りをしているなあと感心しました(「ドゴラ」の原案イメージは小松崎茂)。 映画の大部分は、地上で繰り広げられる警察と強盗団のダイヤ争奪・奪回戦に費やされ、盗んだのがダイヤだと思ったら氷砂糖だったとか、ドタバタ喜劇調でもあります。主演の夏木陽介や、3年後に「
映画の大部分は、地上で繰り広げられる警察と強盗団のダイヤ争奪・奪回戦に費やされ、盗んだのがダイヤだと思ったら氷砂糖だったとか、ドタバタ喜劇調でもあります。主演の夏木陽介や、3年後に「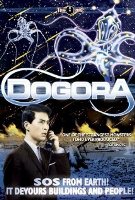
 今観ると、ストーリー映画としては星3つに届くか届かないですが、ドゴラだけはなかなかいいと思います。この作品を最初に観たのは学校の「課外授業」としてで、併映は家城巳代治監督、池田秀一主演の「路傍の石」('64年/東映)でしたが、その後の授業で感想文を書けと言われて「路傍の石」ではなく「ドゴラ」の方の感想文を書きました。
今観ると、ストーリー映画としては星3つに届くか届かないですが、ドゴラだけはなかなかいいと思います。この作品を最初に観たのは学校の「課外授業」としてで、併映は家城巳代治監督、池田秀一主演の「路傍の石」('64年/東映)でしたが、その後の授業で感想文を書けと言われて「路傍の石」ではなく「ドゴラ」の方の感想文を書きました。 



 「宇宙大怪獣ドゴラ」●制作年:1964年●監督:本多猪四郎●特撮監督:円谷英二●製作:田中友幸/田実泰
「宇宙大怪獣ドゴラ」●制作年:1964年●監督:本多猪四郎●特撮監督:円谷英二●製作:田中友幸/田実泰 良●脚本:関沢新一●撮影:小泉一●音楽:伊福部昭●時間:81分●出演:夏木陽介/ダン・ユマ/小泉博/藤山陽子/若林映子/藤田進/中村伸郎/河津清三郎/田島義文/天本英世/田崎潤/加藤春哉/桐野洋雄/若松明/篠原正記/堤康久/岩本弘司/津田光男/熊谷卓三/当銀長太郎/広瀬正一/中山豊/上村幸之●公開:1964/08●配給:東宝 (評価:★★★☆)●併映:「路傍の石」(家城巳代治)
良●脚本:関沢新一●撮影:小泉一●音楽:伊福部昭●時間:81分●出演:夏木陽介/ダン・ユマ/小泉博/藤山陽子/若林映子/藤田進/中村伸郎/河津清三郎/田島義文/天本英世/田崎潤/加藤春哉/桐野洋雄/若松明/篠原正記/堤康久/岩本弘司/津田光男/熊谷卓三/当銀長太郎/広瀬正一/中山豊/上村幸之●公開:1964/08●配給:東宝 (評価:★★★☆)●併映:「路傍の石」(家城巳代治)
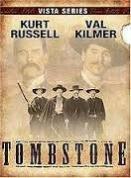
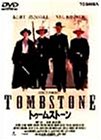
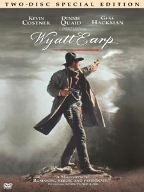
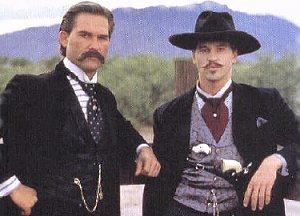 トゥームストーンへ平穏な暮らしを求めやって来た元保安官のワイアット・アープ(カート・ラッセル)は、町がクラントン兄弟や凄腕のガンマン、ジョニー・リンゴ(マイケル・ビーン)らカウボーイズと名乗る無法者集団に牛耳られていることを知る。ワイアットは旧友ドク・ホリデ
トゥームストーンへ平穏な暮らしを求めやって来た元保安官のワイアット・アープ(カート・ラッセル)は、町がクラントン兄弟や凄腕のガンマン、ジョニー・リンゴ(マイケル・ビーン)らカウボーイズと名乗る無法者集団に牛耳られていることを知る。ワイアットは旧友ドク・ホリデ イ(ヴァル・キルマー)と再会したが、彼は結核に冒されていて、恋人のケイト(ジョアンナ・パクラ)が彼の生き方を全うさせようと寄り添っている。一方ワイアットは、舞台女優のジョセフィーヌ(ダナ・デラニー)と知り合う。カウボーイズの無法ぶりを抑えようと、ワイアットの兄と弟は保安官となり、アープ兄弟は一味からOKコラルでの決闘を申し込まれるが、ドクの加勢を得て勝利する。しかし、敵の報復により兄が重体に、弟が殺されるに及んで、ワイアットは再び保安官のバッジを付け、ドクと共に立ち上がる―。
イ(ヴァル・キルマー)と再会したが、彼は結核に冒されていて、恋人のケイト(ジョアンナ・パクラ)が彼の生き方を全うさせようと寄り添っている。一方ワイアットは、舞台女優のジョセフィーヌ(ダナ・デラニー)と知り合う。カウボーイズの無法ぶりを抑えようと、ワイアットの兄と弟は保安官となり、アープ兄弟は一味からOKコラルでの決闘を申し込まれるが、ドクの加勢を得て勝利する。しかし、敵の報復により兄が重体に、弟が殺されるに及んで、ワイアットは再び保安官のバッジを付け、ドクと共に立ち上がる―。 「トゥームストーン」('93年/米)の監督は「ランボー 怒りの脱出」のジョージ
「トゥームストーン」('93年/米)の監督は「ランボー 怒りの脱出」のジョージ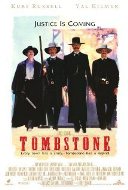
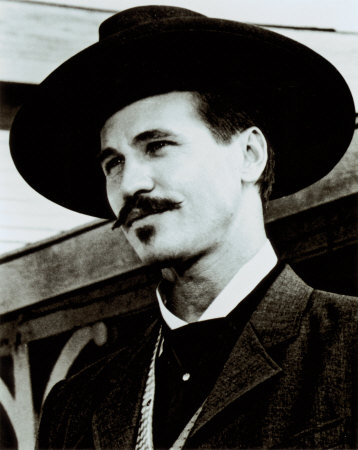 この作品でみると、敵役のリンゴなどはワイアット・アープの手に余る相手で、ワイアットを助太刀したのがドグ・ホリディという構図になっているのが興味深いです(一番の拳銃使いはドグ・ホリディということか)。
この作品でみると、敵役のリンゴなどはワイアット・アープの手に余る相手で、ワイアットを助太刀したのがドグ・ホリディという構図になっているのが興味深いです(一番の拳銃使いはドグ・ホリディということか)。 同じ頃に公開された「ワイアット・アープ」('94年/米)は、「シルバラード」のローレンス・カスダン監督ということで期待しましたが、こちらは完全にケヴィン・コスナーの映画という感じ。ケヴィン・コスナーはやりたかったんだろうなあ、この役を。
同じ頃に公開された「ワイアット・アープ」('94年/米)は、「シルバラード」のローレンス・カスダン監督ということで期待しましたが、こちらは完全にケヴィン・コスナーの映画という感じ。ケヴィン・コスナーはやりたかったんだろうなあ、この役を。 こちらも「史実に忠実」が謳い文句で、同じくOKコラルの決闘の後にもう一度、ワイアット・アープ(ケヴィン・コスナー)とドグ・ホリディ(デニス・クエイド)はカウボーイズ一味を相手にワイアットの弟の弔い合戦をやっています。
こちらも「史実に忠実」が謳い文句で、同じくOKコラルの決闘の後にもう一度、ワイアット・アープ(ケヴィン・コスナー)とドグ・ホリディ(デニス・クエイド)はカウボーイズ一味を相手にワイアットの弟の弔い合戦をやっています。 デニス・クエイドのドグ・ホリディは、ヴァル・キルマーより更に線が細い、というより病的。事実、結核病みだったから、リアルと言えばリアルなのかも(自分の頭の中にある「
デニス・クエイドのドグ・ホリディは、ヴァル・キルマーより更に線が細い、というより病的。事実、結核病みだったから、リアルと言えばリアルなのかも(自分の頭の中にある「 3時間11分の大作になっているのは、ワイアット・アープの生涯を通しで描いているためで、若い頃に身重の妻を病気で喪って酒浸りの日々を送り、馬泥棒で留置所に入れられたりもしたのだなあと(よくぞ立ち直った)。但し、決闘に至るまでがあまりに長く(これはある種「伝記映画」か?)、ケヴィン・コスナーの熱演(?)にもかかわらず(コスナーはこの作品で「ゴールデン・ラズベリー賞」の最低主演男優賞を受賞している)冗長な感は否めませんでした(この人が製作に関わった作品は、長尺になる傾向がある。カットするのが惜しい?)。
3時間11分の大作になっているのは、ワイアット・アープの生涯を通しで描いているためで、若い頃に身重の妻を病気で喪って酒浸りの日々を送り、馬泥棒で留置所に入れられたりもしたのだなあと(よくぞ立ち直った)。但し、決闘に至るまでがあまりに長く(これはある種「伝記映画」か?)、ケヴィン・コスナーの熱演(?)にもかかわらず(コスナーはこの作品で「ゴールデン・ラズベリー賞」の最低主演男優賞を受賞している)冗長な感は否めませんでした(この人が製作に関わった作品は、長尺になる傾向がある。カットするのが惜しい?)。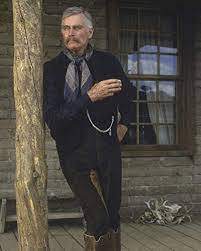
 「トゥームストーン」●原題:TOMBSTONE●制作年:1993年●制作国:アメリカ●監督:ジョージ・P・コスマトス●製作:ジェームズ・ジャックス/ショーン・ダニエル/ボブ・ミシオロウスキ●脚本:ケヴィン・ジャール●撮影:ウィリアム・A・フレイカー●音楽:ブルース・ブロートン●時間:130分●出演:カート・ラッセル/ヴァル・キルマー/サム・エリオット/ビル・パクストン/ダナ・デラニー/ジョアナ・パクラ/パワーズ・ブース/マイケル・ビーン/チャールトン・ヘストン/ジェイソン・プリーストリー/マイケル・ルーカー/ビリー・ゼーン/ロバート・ミッチャム●日本公開:1994/05●配給:東宝東和(評価:★★★★)
「トゥームストーン」●原題:TOMBSTONE●制作年:1993年●制作国:アメリカ●監督:ジョージ・P・コスマトス●製作:ジェームズ・ジャックス/ショーン・ダニエル/ボブ・ミシオロウスキ●脚本:ケヴィン・ジャール●撮影:ウィリアム・A・フレイカー●音楽:ブルース・ブロートン●時間:130分●出演:カート・ラッセル/ヴァル・キルマー/サム・エリオット/ビル・パクストン/ダナ・デラニー/ジョアナ・パクラ/パワーズ・ブース/マイケル・ビーン/チャールトン・ヘストン/ジェイソン・プリーストリー/マイケル・ルーカー/ビリー・ゼーン/ロバート・ミッチャム●日本公開:1994/05●配給:東宝東和(評価:★★★★)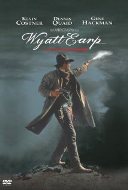
 「ワイアット・アープ」●原題:WYATT EARP●制作年:1994年●制作国:アメリカ●監督:ローレンス・カスダン●製作:ケヴィン・コスナー/ ジム・ウィルソン/ローレンス・カスダン●脚本: ローレンス・カスダン/ダン・ゴードン●撮影:オーウェン・ロイズマン●音楽:楽:ジェームズ・ニュートン・ハワード●時間:191分●出演:ケヴィン・コスナー/デニス・クエイド/ジーン・ハックマン/イザベラ・ロッセリーニ/マイケル・マドセン/デヴィッド・アンドリュース/リンデン・アシュビー/トム・サイズモア/ビル・プルマン/マーク・ハーモン/ジェフ・フェイヒー/アダム・ボールドウィン/アナベス・ギッシュ/メア・ウィニンガム/ジョアンナ・ゴーイング/キャサリン・オハラ/ジョベス・ウィリアムズ/アリソン・エリオット/ベティ・バックリー/ジェームズ・カヴィーゼル/ランドル・メル/レックス・リン/ルイス・スミス/トッド・アレン●日本公開:1994/07●配給:ワーナー・ブラザース映画(評価:★★★)
「ワイアット・アープ」●原題:WYATT EARP●制作年:1994年●制作国:アメリカ●監督:ローレンス・カスダン●製作:ケヴィン・コスナー/ ジム・ウィルソン/ローレンス・カスダン●脚本: ローレンス・カスダン/ダン・ゴードン●撮影:オーウェン・ロイズマン●音楽:楽:ジェームズ・ニュートン・ハワード●時間:191分●出演:ケヴィン・コスナー/デニス・クエイド/ジーン・ハックマン/イザベラ・ロッセリーニ/マイケル・マドセン/デヴィッド・アンドリュース/リンデン・アシュビー/トム・サイズモア/ビル・プルマン/マーク・ハーモン/ジェフ・フェイヒー/アダム・ボールドウィン/アナベス・ギッシュ/メア・ウィニンガム/ジョアンナ・ゴーイング/キャサリン・オハラ/ジョベス・ウィリアムズ/アリソン・エリオット/ベティ・バックリー/ジェームズ・カヴィーゼル/ランドル・メル/レックス・リン/ルイス・スミス/トッド・アレン●日本公開:1994/07●配給:ワーナー・ブラザース映画(評価:★★★)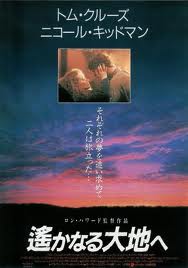
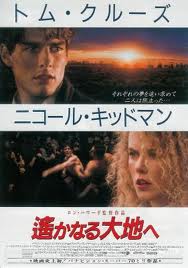
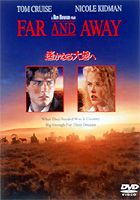
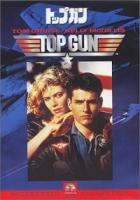
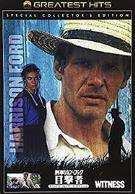
 農民が地主の横暴に苦し
農民が地主の横暴に苦し められた19世紀末のアイルランド、農夫ジョセフ(トム・クルーズ)の父も、厳しい地代の取立ての混乱で事故死する。更に地主の配下に家を焼かれ、怒ったジョセフは地主を射殺しようと地主邸に向かうが失敗、銃の暴発のため負傷し、復
められた19世紀末のアイルランド、農夫ジョセフ(トム・クルーズ)の父も、厳しい地代の取立ての混乱で事故死する。更に地主の配下に家を焼かれ、怒ったジョセフは地主を射殺しようと地主邸に向かうが失敗、銃の暴発のため負傷し、復 讐相手の邸で介抱を受けるという間抜けな結果となる。そこには、放火の張本人で地主令嬢と結婚を図るスティーブン(トーマス・ギブソン)がいて、ジョセフは彼を襲うも再度失敗し、彼と決闘させられることに。そこへ、実はスティーブンのお高くとまった性格が嫌いで、堅苦しい生活を捨てアメリカ行きを望む地主令嬢のシャノン(ニコール・キッドマン)が現れ、ジョセフを攫うように連れ去り、二人のアメリカ行きの旅が始まる―。
讐相手の邸で介抱を受けるという間抜けな結果となる。そこには、放火の張本人で地主令嬢と結婚を図るスティーブン(トーマス・ギブソン)がいて、ジョセフは彼を襲うも再度失敗し、彼と決闘させられることに。そこへ、実はスティーブンのお高くとまった性格が嫌いで、堅苦しい生活を捨てアメリカ行きを望む地主令嬢のシャノン(ニコール・キッドマン)が現れ、ジョセフを攫うように連れ去り、二人のアメリカ行きの旅が始まる―。 アイルランド系移民の苦労を描いたロン・ハワード監督の'92年作品で、トム・クルーズとニコール・キッドマンが仲良かった頃、と言うか、結婚したての頃の作品ですが、映画の中に出てくる「オクラホマ・ランドラッシュ」というのが印象深かったです。
アイルランド系移民の苦労を描いたロン・ハワード監督の'92年作品で、トム・クルーズとニコール・キッドマンが仲良かった頃、と言うか、結婚したての頃の作品ですが、映画の中に出てくる「オクラホマ・ランドラッシュ」というのが印象深かったです。 1889年4月22日の正午を境にオクラホマへの白人の入植が認められた。同年同月日には15ドルの入植手続き料を支払った人々がオクラホマとの境界に集まり、正午を告げる号砲が鳴ると一斉にオクラホマへと乗り込んでいった。彼らは一人当たり160エーカー(65ヘクタール)の土地を手に入れることができた――これは、新大陸のフロンティア時代の入植者に土地を無料で配るというもので、移民たちが白線に並んで「用意ドン!」で駆けっこして、ここからここまでは自分の土地だと主張した範囲の土地が与えられるというスゴイものなのですが(当然、そこで醜い争いも生じる)、お嬢さんだが気が強いシャノンと、自分の土地を得るにはこの方法しかないと考えるジョセフは、このレースに参加する―。
1889年4月22日の正午を境にオクラホマへの白人の入植が認められた。同年同月日には15ドルの入植手続き料を支払った人々がオクラホマとの境界に集まり、正午を告げる号砲が鳴ると一斉にオクラホマへと乗り込んでいった。彼らは一人当たり160エーカー(65ヘクタール)の土地を手に入れることができた――これは、新大陸のフロンティア時代の入植者に土地を無料で配るというもので、移民たちが白線に並んで「用意ドン!」で駆けっこして、ここからここまでは自分の土地だと主張した範囲の土地が与えられるというスゴイものなのですが(当然、そこで醜い争いも生じる)、お嬢さんだが気が強いシャノンと、自分の土地を得るにはこの方法しかないと考えるジョセフは、このレースに参加する―。 ロン・ハワードにはアイルランド人の血が流れていて、祖先にはこのオクラホマのランド・ラッシュに実際に参加した人もいたとのことで、随分前からこの映画の構想は練っていたそうです。ニコール・キッドマンをヒロインに想定していたところに、トム・クルーズが出演の名乗りを上げたそうですが、ロン・ハワードは当時二人が交際していることを知らなかったそうです。因みに、トム・クルーズ自身にもアイルランド人の血が流れています。
ロン・ハワードにはアイルランド人の血が流れていて、祖先にはこのオクラホマのランド・ラッシュに実際に参加した人もいたとのことで、随分前からこの映画の構想は練っていたそうです。ニコール・キッドマンをヒロインに想定していたところに、トム・クルーズが出演の名乗りを上げたそうですが、ロン・ハワードは当時二人が交際していることを知らなかったそうです。因みに、トム・クルーズ自身にもアイルランド人の血が流れています。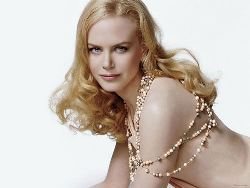 2人ともいい演技をしています。特に、上流意識を持ち、気位が高いながらも、ボディガード代わりに連れてきたトム・クルーズに内心では惹かれていくニコール・キッドマンの演技がいい(トム・クルーズはこの映画の随所で、状況の急な変化に振り回される、三枚目的な味を出している)。
2人ともいい演技をしています。特に、上流意識を持ち、気位が高いながらも、ボディガード代わりに連れてきたトム・クルーズに内心では惹かれていくニコール・キッドマンの演技がいい(トム・クルーズはこの映画の随所で、状況の急な変化に振り回される、三枚目的な味を出している)。 移民たちが駆けっこして奪い合っている土地は、元々は北米原住民のものであるはずという批判的な見方も出来ますが、この映画が日本でも本国でもあまりヒットしなかったことを思うと、もう少し注目されても良かったのでないかと。ロン・ハワードは両親とも俳優だったので、子役の頃から多くのテレビドラマや映画に出演していましたが(「
移民たちが駆けっこして奪い合っている土地は、元々は北米原住民のものであるはずという批判的な見方も出来ますが、この映画が日本でも本国でもあまりヒットしなかったことを思うと、もう少し注目されても良かったのでないかと。ロン・ハワードは両親とも俳優だったので、子役の頃から多くのテレビドラマや映画に出演していましたが(「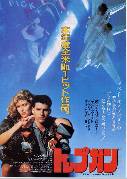

 一方のトム・クルーズは、それ以前に「トップガン」('86年)で一躍世界的なスターになっていたわけで、日本でもこの映画は大ヒットしました。まあ、米海軍が協力を惜しまない "USネイビィのリクルート戦略"の一環のような映画でした。「
一方のトム・クルーズは、それ以前に「トップガン」('86年)で一躍世界的なスターになっていたわけで、日本でもこの映画は大ヒットしました。まあ、米海軍が協力を惜しまない "USネイビィのリクルート戦略"の一環のような映画でした。「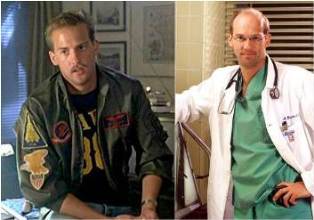 ヴァル・キルマー、メグ・ライアン、ティム・ロビンスら若手俳優の出世作としても知られ、「ER 緊急救命室」の"グリーン先生"ことアンソニー・エドワーズがトム・クルーズの同僚パイロット役で出てましたが、出ていた記憶が薄いのはまだ髪の毛が濃かったせいでしょうか。ともかく、トム・クルーズ人気を一気に高めた作品であって、その分だけ相対的に他の俳優の影が薄い? 後になって、あの人も出ていた、この人も出ていたと言われる映画です(当時まだ皆さほど名が知れてなかったということもあるが)。
ヴァル・キルマー、メグ・ライアン、ティム・ロビンスら若手俳優の出世作としても知られ、「ER 緊急救命室」の"グリーン先生"ことアンソニー・エドワーズがトム・クルーズの同僚パイロット役で出てましたが、出ていた記憶が薄いのはまだ髪の毛が濃かったせいでしょうか。ともかく、トム・クルーズ人気を一気に高めた作品であって、その分だけ相対的に他の俳優の影が薄い? 後になって、あの人も出ていた、この人も出ていたと言われる映画です(当時まだ皆さほど名が知れてなかったということもあるが)。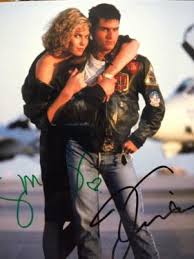 トム・クルーズの当時の人気はすさまじく、その勢いで「トップガン」と同年にマーティン・スコセッシ監督の「ハスラー2」('86年)に出演、翌々年にはロジャー・ドナルドソン監督の「カクテル」('88年)、バリー・レヴィンソン監督の「
トム・クルーズの当時の人気はすさまじく、その勢いで「トップガン」と同年にマーティン・スコセッシ監督の「ハスラー2」('86年)に出演、翌々年にはロジャー・ドナルドソン監督の「カクテル」('88年)、バリー・レヴィンソン監督の「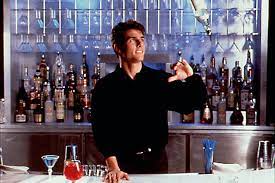 ューマンに初のアカデミー主演男優賞をもたらし、ダスティン・ホフマンと共演した「レインマン」は第61回アカデミー賞と第46回ゴールデングローブ賞(ドラマ部門)、さらに第39回ベルリン国際映画祭においてそれぞれ作品賞を受賞しました。一方、トム・クルーズのスマイルと、フレアバーテンディングによるカクテル作りの派手なパフォーマンスでヒットを博した「カクテル」は、(一応"原作"はあるようだが)完全なトム・クルーズ・ファンのためのアイドル映画でした。これ、ビデオパーティで観た(90-04-01)のですが(自分で選んではいない)、当時の日本のバブリーな雰囲気にマッチしていた面もあったかも。
ューマンに初のアカデミー主演男優賞をもたらし、ダスティン・ホフマンと共演した「レインマン」は第61回アカデミー賞と第46回ゴールデングローブ賞(ドラマ部門)、さらに第39回ベルリン国際映画祭においてそれぞれ作品賞を受賞しました。一方、トム・クルーズのスマイルと、フレアバーテンディングによるカクテル作りの派手なパフォーマンスでヒットを博した「カクテル」は、(一応"原作"はあるようだが)完全なトム・クルーズ・ファンのためのアイドル映画でした。これ、ビデオパーティで観た(90-04-01)のですが(自分で選んではいない)、当時の日本のバブリーな雰囲気にマッチしていた面もあったかも。

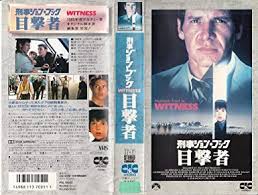
 ケリー・マクギリスは1982年に映画デビューしていますが、彼女を一躍有名にしたのは、ハリソン・フォードと共演し、アーミッシュの女性を演じた「刑事ジョン・ブック 目撃者」('85年)でしょう(これも知人宅でのビデオパーティで観た(89-05-03))。ハリソン・フォード演じる警察の不正を知ったために警察に追われること
ケリー・マクギリスは1982年に映画デビューしていますが、彼女を一躍有名にしたのは、ハリソン・フォードと共演し、アーミッシュの女性を演じた「刑事ジョン・ブック 目撃者」('85年)でしょう(これも知人宅でのビデオパーティで観た(89-05-03))。ハリソン・フォード演じる警察の不正を知ったために警察に追われること になった刑事が主人公で、警察を舞台にした犯罪サスペンスかと思ったら、そのジョン・ブック刑事が匿われたアーミッシュの村の暮らしぶり(と言うより、アーミッシュの人々の考え方)が描かれていて、ある種カルチャーショック映画のようになっていました。ハリソン・フォードはアカデミー主演男優賞にノミネートされましたが、来日した時に、今まで出演した中で一番印象に残っている作品として、この「刑事ジョン・ブック 目撃者」を挙げていました。この作品でのハリソン・フォードの演技の延長上に、後の「
になった刑事が主人公で、警察を舞台にした犯罪サスペンスかと思ったら、そのジョン・ブック刑事が匿われたアーミッシュの村の暮らしぶり(と言うより、アーミッシュの人々の考え方)が描かれていて、ある種カルチャーショック映画のようになっていました。ハリソン・フォードはアカデミー主演男優賞にノミネートされましたが、来日した時に、今まで出演した中で一番印象に残っている作品として、この「刑事ジョン・ブック 目撃者」を挙げていました。この作品でのハリソン・フォードの演技の延長上に、後の「 ました。女性がアレクサンドル・ゴドゥノフ演じる許嫁候補(?)と仮に結婚したとしても、ずっとジョン・ブックのことを思い続けるのでしょう(「シェーン」にも同じことが言えるが、旦那または許
ました。女性がアレクサンドル・ゴドゥノフ演じる許嫁候補(?)と仮に結婚したとしても、ずっとジョン・ブックのことを思い続けるのでしょう(「シェーン」にも同じことが言えるが、旦那または許 嫁は"立場ない"なあ)。それにしてもケリー・マクギリス、最初の主演作がハリソン・フォードの相手役で、次がトム・クルーズの相手役であったわけで、当時の圧倒的な美貌のせいもあってか、キャリアの最初の方がとりわけ華々しかったです。
嫁は"立場ない"なあ)。それにしてもケリー・マクギリス、最初の主演作がハリソン・フォードの相手役で、次がトム・クルーズの相手役であったわけで、当時の圧倒的な美貌のせいもあってか、キャリアの最初の方がとりわけ華々しかったです。 (●2022年にジョセフ・コジンスキー監督による「トップガン マーヴェリック」('22年/米)が公開され
(●2022年にジョセフ・コジンスキー監督による「トップガン マーヴェリック」('22年/米)が公開され た。「トップガン」から36年ぶりの続編で、トム・クルーズが前回同様マーヴェリック役を演じ、米海軍パイロットのエリート養成学校、通称"トップガン"に教官として戻ってくることになるも、結局、自らチームを率いて敵地へウラン濃縮施設撃破のために飛ぶことになるというもの。トム・クルーズは60歳で頑張っているなあという感じで、映画もヒットしているようだ。日本でも世代を問わず絶賛する声が多い。ただ、前作と異なり、映画評論家までが褒めていたりするのには違和感を感じる。俳優のミッキー・ロークが、トム・クルーズが「トップガン マーヴェリック」で米国
た。「トップガン」から36年ぶりの続編で、トム・クルーズが前回同様マーヴェリック役を演じ、米海軍パイロットのエリート養成学校、通称"トップガン"に教官として戻ってくることになるも、結局、自らチームを率いて敵地へウラン濃縮施設撃破のために飛ぶことになるというもの。トム・クルーズは60歳で頑張っているなあという感じで、映画もヒットしているようだ。日本でも世代を問わず絶賛する声が多い。ただ、前作と異なり、映画評論家までが褒めていたりするのには違和感を感じる。俳優のミッキー・ロークが、トム・クルーズが「トップガン マーヴェリック」で米国 で興行収入1位になったことについてどう思うかとの質問に、「あいつは35年間あんな同じ役を演じてるんだ。尊敬に値しないね」と言っており、そちらの方がまともなマトモな見方とも言える。ヒロイン役はジェニファー・コネリー(51歳)。ケリー・マクギリスは、自分のところには出演オファーが無かったと言っている(笑)。気になったのはストーリーで、教官が部下を救い、今度は部下が教官を救うという話は美しいが、敵地に不時着して、"たまたま近くあった"敵の戦闘機を強奪して帰還するというのはあまりに話が出来過ぎているように思った。かつて、クリント・イーストウッドが監督・主演した「ファイヤーフォックス」('82年)で、イーストウ
で興行収入1位になったことについてどう思うかとの質問に、「あいつは35年間あんな同じ役を演じてるんだ。尊敬に値しないね」と言っており、そちらの方がまともなマトモな見方とも言える。ヒロイン役はジェニファー・コネリー(51歳)。ケリー・マクギリスは、自分のところには出演オファーが無かったと言っている(笑)。気になったのはストーリーで、教官が部下を救い、今度は部下が教官を救うという話は美しいが、敵地に不時着して、"たまたま近くあった"敵の戦闘機を強奪して帰還するというのはあまりに話が出来過ぎているように思った。かつて、クリント・イーストウッドが監督・主演した「ファイヤーフォックス」('82年)で、イーストウ

 ッド演じる元米空軍パイロットがNATOの秘密ミッションでソ連に潜入し、最新鋭戦闘機「MiG-31 ファイヤーフォックス」を盗み出すという映画があったが、あれは最初から周到な計画のもとに敵地に潜入しているわけであって、しかも、
ッド演じる元米空軍パイロットがNATOの秘密ミッションでソ連に潜入し、最新鋭戦闘機「MiG-31 ファイヤーフォックス」を盗み出すという映画があったが、あれは最初から周到な計画のもとに敵地に潜入しているわけであって、しかも、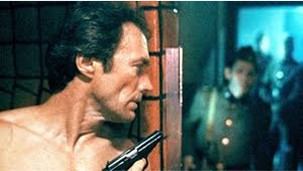 当時の〈東西冷戦〉状況を背景としているとはいえ戦闘機自体はパイロットの意志を感知してオートマチックに敵を攻撃する機能を搭載しているといった半ばSF仕立てでもあった(この機能は実際に研究されているが、まだ実現していない)。苦心惨憺の末に敵戦闘機に辿り着いたイーストウッドとの比較でみると、トム・クルーズの、不時着した付近にたまたま敵の戦闘機があったというのは、あまりにご都合主義的な話だったように思う。
当時の〈東西冷戦〉状況を背景としているとはいえ戦闘機自体はパイロットの意志を感知してオートマチックに敵を攻撃する機能を搭載しているといった半ばSF仕立てでもあった(この機能は実際に研究されているが、まだ実現していない)。苦心惨憺の末に敵戦闘機に辿り着いたイーストウッドとの比較でみると、トム・クルーズの、不時着した付近にたまたま敵の戦闘機があったというのは、あまりにご都合主義的な話だったように思う。 「トップガン マーヴェリック」には、トム・クルーズが前作と同じ"マーヴェリック"役で出ているほかに、ヴァル・キルマーが前作と同じ"アイスマン"役で出ていて、個人的には「
「トップガン マーヴェリック」には、トム・クルーズが前作と同じ"マーヴェリック"役で出ているほかに、ヴァル・キルマーが前作と同じ"アイスマン"役で出ていて、個人的には「 「遥かなる大地へ」●原題:FAR AND AWAY●制作年:1992年●制作国:アメリカ●監督:ロン・ハワード●製作:ブライアン・グレイザー/ロン・ハワード●脚本:ボブ・ドルマン●撮影:ミカエル・サロモン●音楽:ジョン・ウィリアムズ●時間:140分●出演:トム・クルーズ/ニコール・キッドマン/トーマス・ギブソン/バーバラ・バブコック/シリル・キューザック/ロバート・プロスキー/コルム・ミーニー/アイリーン・ポロック/ミシェル・ジョンソン/ダグラス・ジリソン/ウェイン・グレイス/バリー・マクガヴァン●日本公開:1992/07●配給:ユニヴァーサル映画=UIP(評価:★★★☆)
「遥かなる大地へ」●原題:FAR AND AWAY●制作年:1992年●制作国:アメリカ●監督:ロン・ハワード●製作:ブライアン・グレイザー/ロン・ハワード●脚本:ボブ・ドルマン●撮影:ミカエル・サロモン●音楽:ジョン・ウィリアムズ●時間:140分●出演:トム・クルーズ/ニコール・キッドマン/トーマス・ギブソン/バーバラ・バブコック/シリル・キューザック/ロバート・プロスキー/コルム・ミーニー/アイリーン・ポロック/ミシェル・ジョンソン/ダグラス・ジリソン/ウェイン・グレイス/バリー・マクガヴァン●日本公開:1992/07●配給:ユニヴァーサル映画=UIP(評価:★★★☆) 「トップガン」●原題:TOP GUN●制作年:1986年●制作国:アメリカ●監督:トニー・スコット●製作:ドン・シンプソン/ジェリー・ブラッカイマー●脚本:ジム・キャッシュ/ジャック・エップス・Jr●撮影:ジェフリー・キンボール●音楽:ハロルド・ファルターメイヤー/ジョルジオ・モロダー●時間:110分●出演:トム・クルーズ/ケリー・マクギリス/ヴァル・キルマー/アンソニー・エドワーズ/トム・スケリット/マイケル・ アイアンサイド/ジョン・ストックウェル/リック・ロソビ
「トップガン」●原題:TOP GUN●制作年:1986年●制作国:アメリカ●監督:トニー・スコット●製作:ドン・シンプソン/ジェリー・ブラッカイマー●脚本:ジム・キャッシュ/ジャック・エップス・Jr●撮影:ジェフリー・キンボール●音楽:ハロルド・ファルターメイヤー/ジョルジオ・モロダー●時間:110分●出演:トム・クルーズ/ケリー・マクギリス/ヴァル・キルマー/アンソニー・エドワーズ/トム・スケリット/マイケル・ アイアンサイド/ジョン・ストックウェル/リック・ロソビ

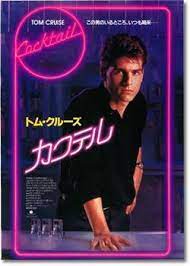
 「カクテル」●原題:COCKTALEN●制作年:1988年●制作国:アメリカ●監督:ロジャー・ドナルドソン●製作:テッド・フィールド/ロバート・W・コート●脚本:ヘイウッド・グールド●撮影:ディーン・セムラー●音楽:ピーター・ロビンソン(主題歌:ザ・ビーチ・ボーイズ「ココモ」)●原作:ヘイウッド・グールド●時間:104分●出演:トム・クルーズ/ブライアン・ブラウン/エリザベス・シュー/ケリー・リンチ●日本公開:1989/03●配給:ワーナー・ブラザース(評価:★★★)
「カクテル」●原題:COCKTALEN●制作年:1988年●制作国:アメリカ●監督:ロジャー・ドナルドソン●製作:テッド・フィールド/ロバート・W・コート●脚本:ヘイウッド・グールド●撮影:ディーン・セムラー●音楽:ピーター・ロビンソン(主題歌:ザ・ビーチ・ボーイズ「ココモ」)●原作:ヘイウッド・グールド●時間:104分●出演:トム・クルーズ/ブライアン・ブラウン/エリザベス・シュー/ケリー・リンチ●日本公開:1989/03●配給:ワーナー・ブラザース(評価:★★★)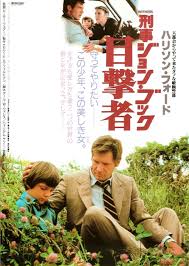
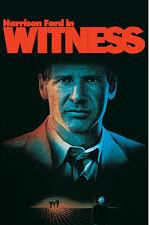
 「刑事ジョン・ブック 目撃者」●原題:WITNESS●制作年:1985年●制作国:アメリカ●監督:ピーター・ウィアー●製作:エドワード・S・フェルドマン●脚本:ウィリアム・ケリー/アール・W・ウォレス●撮影:ジョン・シール●音楽:モーリス・ジャール●時間:113分●出演:ハリソン・フォード/ケリー・マクギリス/ルーカス・ハース/ジョセフ・ソマー/ダニー・グローヴァー/ヤン・ルーベス/アレクサンドル・ゴドゥノフ/パティ・ルポーン/ブレント・ジェニングス/アンガス・マッキネス/フレデリック・ロルフ/ヴィゴ・モーテンセン●日本公開:1985/06●配給:UIP(評価:★★★☆)
「刑事ジョン・ブック 目撃者」●原題:WITNESS●制作年:1985年●制作国:アメリカ●監督:ピーター・ウィアー●製作:エドワード・S・フェルドマン●脚本:ウィリアム・ケリー/アール・W・ウォレス●撮影:ジョン・シール●音楽:モーリス・ジャール●時間:113分●出演:ハリソン・フォード/ケリー・マクギリス/ルーカス・ハース/ジョセフ・ソマー/ダニー・グローヴァー/ヤン・ルーベス/アレクサンドル・ゴドゥノフ/パティ・ルポーン/ブレント・ジェニングス/アンガス・マッキネス/フレデリック・ロルフ/ヴィゴ・モーテンセン●日本公開:1985/06●配給:UIP(評価:★★★☆) 「トップガン マーヴェリック」●原題:TOP GUN: MAVERICK●制作年:2022年●制作国:アメリカ●監督:ジョセフ
「トップガン マーヴェリック」●原題:TOP GUN: MAVERICK●制作年:2022年●制作国:アメリカ●監督:ジョセフ ・コシンスキー●製作:ジェリー・ブラッカイマー/トム・クルーズ/クリストファー・マッカリ
・コシンスキー●製作:ジェリー・ブラッカイマー/トム・クルーズ/クリストファー・マッカリ ー/デヴィッド・エリソン●脚本:アーレン・クルーガー/エリック・ウォーレン・シンガー/クリストファー・マッカリー●撮影:クラウディオ・ミランダ●音楽:ハロルド・フォルターメイヤー/レディー・ガガ/ハンス・ジマー●時間:131分●出演:トム・クルーズ/マイルズ・テラー/ジェニファー・コネリー/ジョン・ハム/グレン・パウエル/ルイス・プルマン/エド・ハリス/ヴァル・キルマー●日本公開:2022/05●配給:東和ピクチャーズ●最初に観た場所:TOHOシネマズ上野(スクリーン2)(22-07-12)(評価:★★☆)
ー/デヴィッド・エリソン●脚本:アーレン・クルーガー/エリック・ウォーレン・シンガー/クリストファー・マッカリー●撮影:クラウディオ・ミランダ●音楽:ハロルド・フォルターメイヤー/レディー・ガガ/ハンス・ジマー●時間:131分●出演:トム・クルーズ/マイルズ・テラー/ジェニファー・コネリー/ジョン・ハム/グレン・パウエル/ルイス・プルマン/エド・ハリス/ヴァル・キルマー●日本公開:2022/05●配給:東和ピクチャーズ●最初に観た場所:TOHOシネマズ上野(スクリーン2)(22-07-12)(評価:★★☆)
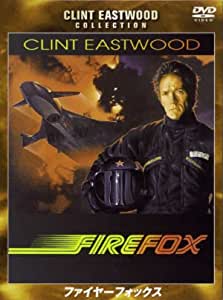

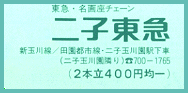
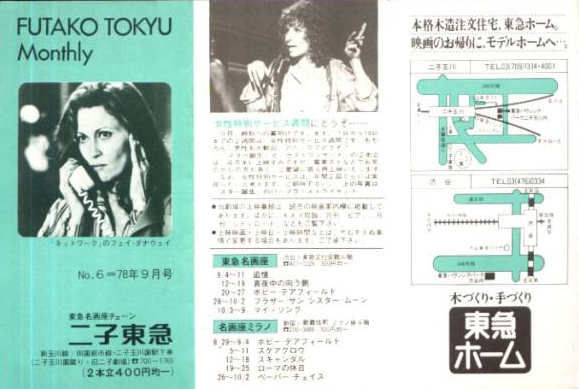
 二子東急 1957年9月30日 開館(「二子玉川園」(1985年3月閉園)そば) 1991(平成3)年1月15日閉館
二子東急 1957年9月30日 開館(「二子玉川園」(1985年3月閉園)そば) 1991(平成3)年1月15日閉館 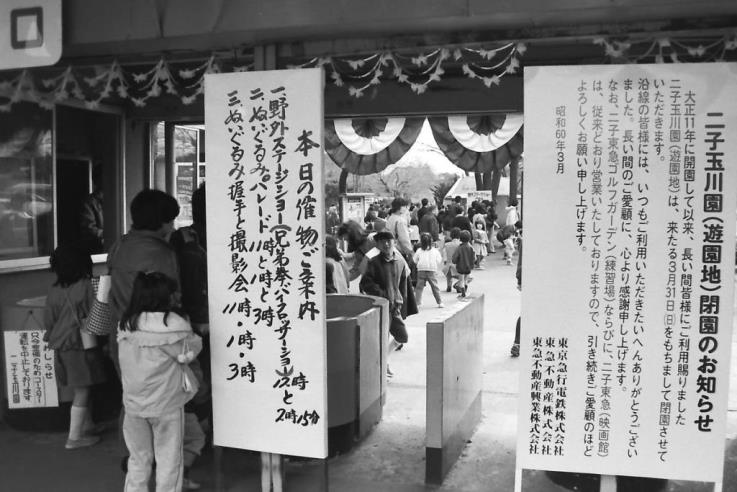
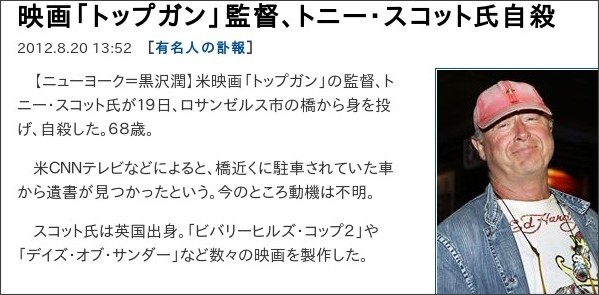
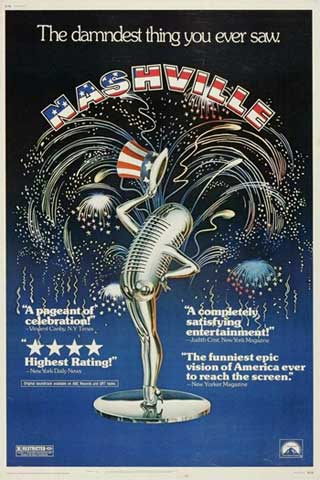
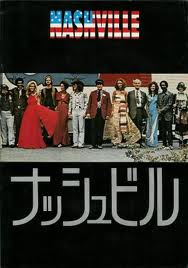
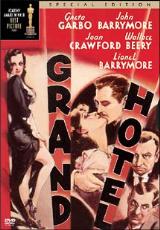
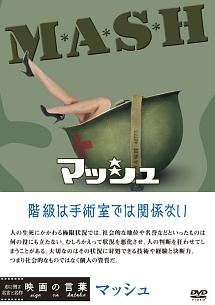
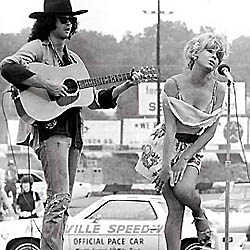 カントリー音楽のメッカ、ナッシュビルで、ある大統領候補のキャンペーンのためにコンサートが行われる準備が進められていて、町には、イベント関係者や働き口
カントリー音楽のメッカ、ナッシュビルで、ある大統領候補のキャンペーンのためにコンサートが行われる準備が進められていて、町には、イベント関係者や働き口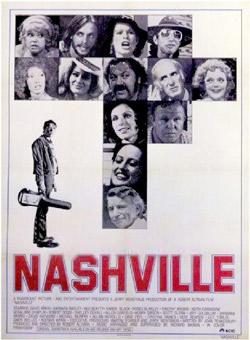 を求める者、野次馬、音楽ファンなど、多くの人間が集まってきていた。その中には、自分がカントリー歌手であることに疑問を感じている黒人や、芸能界で生きることを夢見る運転手、歌手希望の音痴のウエイトレス、家出してきたノイローゼ青年、カントリー歌手になりたくて田舎の農家の夫から逃れきた女など、様々な人間がいた―。
を求める者、野次馬、音楽ファンなど、多くの人間が集まってきていた。その中には、自分がカントリー歌手であることに疑問を感じている黒人や、芸能界で生きることを夢見る運転手、歌手希望の音痴のウエイトレス、家出してきたノイローゼ青年、カントリー歌手になりたくて田舎の農家の夫から逃れきた女など、様々な人間がいた―。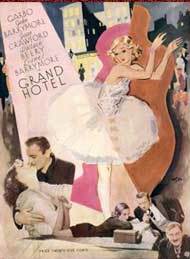
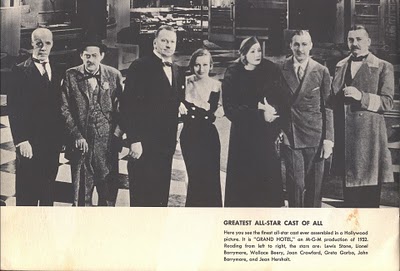 「グランド・ホテル」形式という呼び方の起源となった、エドマンド・グールディング監督の「グランド・ホテル」('32年/米)を後に観ましたが、ベルリンの一流ホテルのそれぞれの部屋で1日の間に起きる人間ドラマを描いた映画で、旧い映画のわりには面白かったです。但し、この"元祖"作品よりも、新「グランド・ホテル」形式とも言われた「ナッシュビル」の方がより面白かったと言うか、インパクトありました。
「グランド・ホテル」形式という呼び方の起源となった、エドマンド・グールディング監督の「グランド・ホテル」('32年/米)を後に観ましたが、ベルリンの一流ホテルのそれぞれの部屋で1日の間に起きる人間ドラマを描いた映画で、旧い映画のわりには面白かったです。但し、この"元祖"作品よりも、新「グランド・ホテル」形式とも言われた「ナッシュビル」の方がより面白かったと言うか、インパクトありました。
 「グランド・ホテル」は、オーストリアの作家ヴィッキー・バウム(Vicki Baum、1888-1960)の小説『ホテルの人びと』を、アメリカで舞台化した戯曲に基づき映画化したもので、ヴィッキー・バウムはこの小説を書くために実際にホテルでメイド(客室係)として働いたそうな(実際にあった有名企業経営者と速記者とのスキャンダルがストーリーに使われているが、ホテル従業員としての守秘義務違反にならないのか?)。映画は第5回アカデミー賞の作品賞を受賞しましたが、他部門でのノミネートは無く作品賞でしか候補に挙がらずに受賞を果たした珍しいケースです(主演○○賞とか助演○○賞とかを与えようとしても、誰が主演で誰が助演なのか判別しにいくい作品であるというのも一因か)。
「グランド・ホテル」は、オーストリアの作家ヴィッキー・バウム(Vicki Baum、1888-1960)の小説『ホテルの人びと』を、アメリカで舞台化した戯曲に基づき映画化したもので、ヴィッキー・バウムはこの小説を書くために実際にホテルでメイド(客室係)として働いたそうな(実際にあった有名企業経営者と速記者とのスキャンダルがストーリーに使われているが、ホテル従業員としての守秘義務違反にならないのか?)。映画は第5回アカデミー賞の作品賞を受賞しましたが、他部門でのノミネートは無く作品賞でしか候補に挙がらずに受賞を果たした珍しいケースです(主演○○賞とか助演○○賞とかを与えようとしても、誰が主演で誰が助演なのか判別しにいくい作品であるというのも一因か)。

 但し、「雨」におけるジョーン・クロフォードが演じた娼婦サディ・トンプソン役は、後の高評価はともかく、公開当時は評判が良くなくて、興行的にも失敗作となっています。一方、「雨」の1ヵ月前に公開され、第5回アカデミー作品賞を受賞した「グランド・ホテル」は1932年度のMGMで興行成績ナンバー1作品であり、この年に「モーション・ピクチャー・ヘラルド誌」が実施した「もっとも興行成績をあげられるスター」の投票企画で、ジョーン・クロフォードはマリー・ドレスラー、ジャネット・ゲイナーに続く3位となっています。マリー・ドレスラーは1931年に、ジャネット・ゲイナーは1928年に、それぞれアカデミー主演女優賞を獲得していましたが、クロフォードはその後も映画に出続けるも傑作に恵まれない状態が続きます。
但し、「雨」におけるジョーン・クロフォードが演じた娼婦サディ・トンプソン役は、後の高評価はともかく、公開当時は評判が良くなくて、興行的にも失敗作となっています。一方、「雨」の1ヵ月前に公開され、第5回アカデミー作品賞を受賞した「グランド・ホテル」は1932年度のMGMで興行成績ナンバー1作品であり、この年に「モーション・ピクチャー・ヘラルド誌」が実施した「もっとも興行成績をあげられるスター」の投票企画で、ジョーン・クロフォードはマリー・ドレスラー、ジャネット・ゲイナーに続く3位となっています。マリー・ドレスラーは1931年に、ジャネット・ゲイナーは1928年に、それぞれアカデミー主演女優賞を獲得していましたが、クロフォードはその後も映画に出続けるも傑作に恵まれない状態が続きます。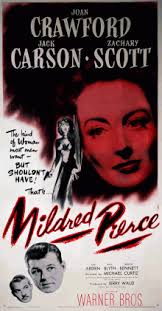
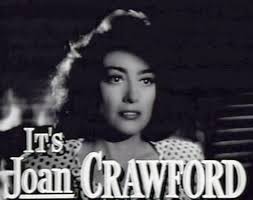 作品です。クロフォードはこの作品で初のノミネートでアカデミー主演女優賞を獲得、女優としての評価を蘇らせ、その後の数年間、ハリウッドで最も成功した女優として君臨することになります。(2011年にケイト・ウィンス
作品です。クロフォードはこの作品で初のノミネートでアカデミー主演女優賞を獲得、女優としての評価を蘇らせ、その後の数年間、ハリウッドで最も成功した女優として君臨することになります。(2011年にケイト・ウィンス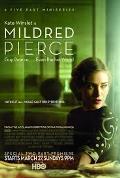 レット主演でテレビドラマ化され、同年10月15日と16日にWOWOWで「ミルドレッド・ピアース 幸せの代償」(全5話)とし
レット主演でテレビドラマ化され、同年10月15日と16日にWOWOWで「ミルドレッド・ピアース 幸せの代償」(全5話)とし![ミルドレッド・ピアース [DVD].jpg](http://hurec.bz/book-movie/%E3%83%9F%E3%83%AB%E3%83%89%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%89%E3%83%BB%E3%83%94%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%82%B9%20%5BDVD%5D.jpg)
 (●映画「ミルドレッド・ピアース」は『郵便配達は二度ベルを鳴らす』『殺人保険』の作者ジェイムズ・M・ケインの1941年発表の同名小説が原作のフィルム・ノワールであり、深夜のビーチハウスでひとりの男が銃撃され、やがて警察の取調室で、殺された男性モンティの妻ミルドレッド(ジョーン・クロフォード)が自らの過
(●映画「ミルドレッド・ピアース」は『郵便配達は二度ベルを鳴らす』『殺人保険』の作者ジェイムズ・M・ケインの1941年発表の同名小説が原作のフィルム・ノワールであり、深夜のビーチハウスでひとりの男が銃撃され、やがて警察の取調室で、殺された男性モンティの妻ミルドレッド(ジョーン・クロフォード)が自らの過 去を振り返りつつ、供述を始めるという構成(但し、原作には殺人事件は無く、サスペンスでもなく、純粋な人間ドラマである)。彼女は、最初の夫と別れた後、苦しい家計を支えるために外で働き出し、やがて自分のレストランを経営、チェーン店化するまでに成功し、モンティと再婚しやっと幸せを手に入れたものの、娘のケイが考えもしなかったようなわが
去を振り返りつつ、供述を始めるという構成(但し、原作には殺人事件は無く、サスペンスでもなく、純粋な人間ドラマである)。彼女は、最初の夫と別れた後、苦しい家計を支えるために外で働き出し、やがて自分のレストランを経営、チェーン店化するまでに成功し、モンティと再婚しやっと幸せを手に入れたものの、娘のケイが考えもしなかったようなわが まま娘に育ってしまう(この流れ自体は原作通り)。ビジネス界での成功と引き換えに、母親の役割に失敗して娘を思わぬ悪女へと成長させ、苦悩するヒロインをジョーン・クロフォードが熱演している。ジョーン・クロフォードはこの映画出演の10年後に後にペプシコの会長CEOとなるアルフレッド・スティールと4度目の結婚をし、その夫の死後もペプシコ社で重役として経営に関わっていた期間があるすが、実人生でそうなる前に「ミルドレッド・ピアース」でやり手実業家を演じていて、それが板についているというのが興味深い。因みに、ジェイムズ・M・ケイン原作、ローレンス・カスダン監督の映画「
まま娘に育ってしまう(この流れ自体は原作通り)。ビジネス界での成功と引き換えに、母親の役割に失敗して娘を思わぬ悪女へと成長させ、苦悩するヒロインをジョーン・クロフォードが熱演している。ジョーン・クロフォードはこの映画出演の10年後に後にペプシコの会長CEOとなるアルフレッド・スティールと4度目の結婚をし、その夫の死後もペプシコ社で重役として経営に関わっていた期間があるすが、実人生でそうなる前に「ミルドレッド・ピアース」でやり手実業家を演じていて、それが板についているというのが興味深い。因みに、ジェイムズ・M・ケイン原作、ローレンス・カスダン監督の映画「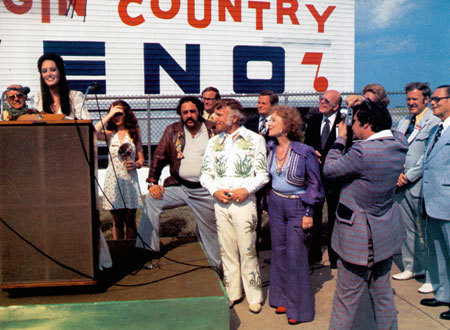
 「グランド・ホテル」からジョーン・クロフォードの話になりましたが、 話を戻して、ロバート・アルトマン監督の「ナッシュビル」はどのようにして作られたかと言うと、アルトマン監督がスタッフをナッシュビルに滞在させて毎日日記を書かせ、それを繋ぎ合せてストーリーを作り上げたのだそうで、ナッシュビルでの撮影期間中も、スタッフやキャストは全員同じモーテルに泊まっていたそうです(出演者のギャラ
「グランド・ホテル」からジョーン・クロフォードの話になりましたが、 話を戻して、ロバート・アルトマン監督の「ナッシュビル」はどのようにして作られたかと言うと、アルトマン監督がスタッフをナッシュビルに滞在させて毎日日記を書かせ、それを繋ぎ合せてストーリーを作り上げたのだそうで、ナッシュビルでの撮影期間中も、スタッフやキャストは全員同じモーテルに泊まっていたそうです(出演者のギャラ は均一だった)。そのためか、観ていてアドリブ感があると言うか、いかにも撮りながら作り、作りながら撮っていったという感じがします。カレン・ブラックがグラマーな「二流カントリー歌手」(触れ込みは「カントリーの女王」)役で、ロニー・ブレイクリー演じる「貧血を起こしやすい歌手」バーバラのライバルという役どころで自作の歌を歌ったり、エリオット・グールドが「M★A★S★H マッシュ」の時と同じシャツ着て本人役
は均一だった)。そのためか、観ていてアドリブ感があると言うか、いかにも撮りながら作り、作りながら撮っていったという感じがします。カレン・ブラックがグラマーな「二流カントリー歌手」(触れ込みは「カントリーの女王」)役で、ロニー・ブレイクリー演じる「貧血を起こしやすい歌手」バーバラのライバルという役どころで自作の歌を歌ったり、エリオット・グールドが「M★A★S★H マッシュ」の時と同じシャツ着て本人役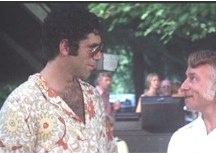 でカメオ出演するなどのお遊びも。当時としては抜きん出て有名なスター俳優は(カメオ出演以外は)使っていないということもあって(当時無名で、後に有名になる役者も多く出ているが)、結果として「集団主人公」という映画の特質がよく出ているように思いました。
でカメオ出演するなどのお遊びも。当時としては抜きん出て有名なスター俳優は(カメオ出演以外は)使っていないということもあって(当時無名で、後に有名になる役者も多く出ているが)、結果として「集団主人公」という映画の特質がよく出ているように思いました。 ロバート・アルトマンは「M★A★S★H マッシュ」('70年/米)の監督でもあり、ある意味、ベトナム戦争終結当時の「病めるアメリカ社会」の断片像ともとれますが、オーデション歌番組「アメリカン・アイドル」の地方予選などは、いまだにこの「ナッシュビル」という映画の雰囲気と重なる部分があるような気もします。
ロバート・アルトマンは「M★A★S★H マッシュ」('70年/米)の監督でもあり、ある意味、ベトナム戦争終結当時の「病めるアメリカ社会」の断片像ともとれますが、オーデション歌番組「アメリカン・アイドル」の地方予選などは、いまだにこの「ナッシュビル」という映画の雰囲気と重なる部分があるような気もします。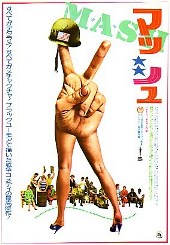
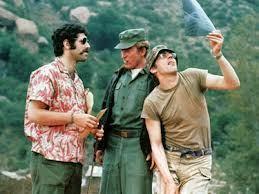 「M★A★S★H」は、朝鮮戦争を舞台にしたブラック・コメディで、野戦病院(マッシュ)に派遣されたドナルド・サザーランド、エリオット・グールド、トム・スケリット演じる3人の医師が、軍規を無視して婦長の尻を追いかけたり、女性将校(サリー・ケラーマン)をからかったりとやりたい放題をやる話。でも、この3人、実は極めて優秀な外科医であって、負傷して血だらけの患者を面白可笑しく冗談を言いながら手術するけれど、結局は治してしまうし、いたずらや悪
「M★A★S★H」は、朝鮮戦争を舞台にしたブラック・コメディで、野戦病院(マッシュ)に派遣されたドナルド・サザーランド、エリオット・グールド、トム・スケリット演じる3人の医師が、軍規を無視して婦長の尻を追いかけたり、女性将校(サリー・ケラーマン)をからかったりとやりたい放題をやる話。でも、この3人、実は極めて優秀な外科医であって、負傷して血だらけの患者を面白可笑しく冗談を言いながら手術するけれど、結局は治してしまうし、いたずらや悪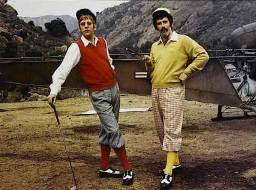 事を企んだりはするけれど、人情味もあるということで、ちょっと憎めない...コメディ部分にもやや毒気のある鬼才ロバート・アルトマンらしい作品でしたが(1970年の第23回カンヌ国際映画祭でグランプリ受賞(現在の最高賞パルム・ドールに該当))、個人的には「ナッシュビル」の方がやや上でしょうか(「ナッシュビル」は全米映画批評家協会賞・作品賞&監督賞受賞)。両作品について言えることですが、アルトマンの社会批判精神はストレートな表され方をするのはでなく、ユーモアを介するなどして屈折した形で表現されるので、背景が掴めていないと、ただ面白かったで終わってしまうこともあるかもしれません(その面白さにもクセがあって、人や作品によって評価が分かれるが)。
事を企んだりはするけれど、人情味もあるということで、ちょっと憎めない...コメディ部分にもやや毒気のある鬼才ロバート・アルトマンらしい作品でしたが(1970年の第23回カンヌ国際映画祭でグランプリ受賞(現在の最高賞パルム・ドールに該当))、個人的には「ナッシュビル」の方がやや上でしょうか(「ナッシュビル」は全米映画批評家協会賞・作品賞&監督賞受賞)。両作品について言えることですが、アルトマンの社会批判精神はストレートな表され方をするのはでなく、ユーモアを介するなどして屈折した形で表現されるので、背景が掴めていないと、ただ面白かったで終わってしまうこともあるかもしれません(その面白さにもクセがあって、人や作品によって評価が分かれるが)。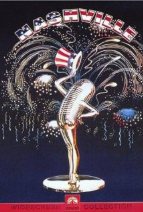

 「ナッシュビル」●原題:NASHVILLE●制作年:1975年●制作国:アメリカ●監督・製作:ロバート・アルトマン●脚本:ジョーン・テューケスベリー●撮影:ポール・ローマン●音楽:リチャード・バスキン/キース・キャラダイン●時間:160分●出演:ヘンリー・ギブソン/カレン・ブラック/アレン・ガーフィールド/ネッド・ビーティー/マイケル・マーフィー/ジェフ・ゴールドブラム/リリー・トムリン/ジェラルディン・チャップリン/キース・キャラダイン/ロニー・ブレイクリー/グウェン・ウェルズ/バーバラ・ハリス/スコット・グレン/エリオット・グールド/ジュディー・クリスティー/デイヴィッド・アーキン/バーバラ・バクスレイ/ティモシー・ブラウン/ロバート・ドキ/シェリー・デュヴァル/アラン・ニコルズ/デイヴィッド・ピール/バート・レムゼン/キーナン・ウィン●日本公開:1976/04●配給:パラマウント映画=CIC●最初に観た場所:新宿西口・新宿(西口)パレス(78-02-08)(評価:★★★★)●併映:「バーブラ・ストライサンド スター誕生」(フランク・ピアスン)
「ナッシュビル」●原題:NASHVILLE●制作年:1975年●制作国:アメリカ●監督・製作:ロバート・アルトマン●脚本:ジョーン・テューケスベリー●撮影:ポール・ローマン●音楽:リチャード・バスキン/キース・キャラダイン●時間:160分●出演:ヘンリー・ギブソン/カレン・ブラック/アレン・ガーフィールド/ネッド・ビーティー/マイケル・マーフィー/ジェフ・ゴールドブラム/リリー・トムリン/ジェラルディン・チャップリン/キース・キャラダイン/ロニー・ブレイクリー/グウェン・ウェルズ/バーバラ・ハリス/スコット・グレン/エリオット・グールド/ジュディー・クリスティー/デイヴィッド・アーキン/バーバラ・バクスレイ/ティモシー・ブラウン/ロバート・ドキ/シェリー・デュヴァル/アラン・ニコルズ/デイヴィッド・ピール/バート・レムゼン/キーナン・ウィン●日本公開:1976/04●配給:パラマウント映画=CIC●最初に観た場所:新宿西口・新宿(西口)パレス(78-02-08)(評価:★★★★)●併映:「バーブラ・ストライサンド スター誕生」(フランク・ピアスン) 





 「ミルドレッド・ピアース」●原題:MILDRED PIERCE●制作年:1945年●制作国:アメリカ●監督:マイケル・カーティス●製作:ジェリー・ウォルド●脚本:ラナルド・マクドゥガル●撮影:アーネスト・ホーラー●音楽:マックス・スタイナー●原作:ジェイムズ・M・ケイン●時間:111分●出演:ジョーン・クロフォード/ブルース・ベネット/ザカリー・スコット/アン・ブライス/ジャック・カーソン/イヴ・アーデン●DVD発売:2013/05●発売元:ブロードウェイ(評価:★★★★)
「ミルドレッド・ピアース」●原題:MILDRED PIERCE●制作年:1945年●制作国:アメリカ●監督:マイケル・カーティス●製作:ジェリー・ウォルド●脚本:ラナルド・マクドゥガル●撮影:アーネスト・ホーラー●音楽:マックス・スタイナー●原作:ジェイムズ・M・ケイン●時間:111分●出演:ジョーン・クロフォード/ブルース・ベネット/ザカリー・スコット/アン・ブライス/ジャック・カーソン/イヴ・アーデン●DVD発売:2013/05●発売元:ブロードウェイ(評価:★★★★)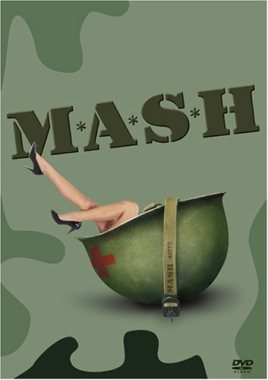
 「M★A★S★H マッシュ」●原題:M*A*S*H●制作年:1975年●制作国:アメリカ●監督:ロバート・アルトマン●製作:インゴ・プレミンジャー●脚本:リング・ランドナーJr.●撮影:ハロルド・E・スタイン●音楽:ジョニー・マンデル●時間:116分●出演:ドナルド・サザーランド/トム・スケリット/エリオット・グールド/ロバート・デュヴァル/サリー・ケラーマン●日本公開:1970/07●配給:20世紀フォックス●最初に観た場所:三鷹オスカー(79-05-13)(評価:★★★★)●併映:「まぼろしの市街戦」(フィリプド・ロカ)/「博士の異常な愛情」(スタンリー・キューブリック)
「M★A★S★H マッシュ」●原題:M*A*S*H●制作年:1975年●制作国:アメリカ●監督:ロバート・アルトマン●製作:インゴ・プレミンジャー●脚本:リング・ランドナーJr.●撮影:ハロルド・E・スタイン●音楽:ジョニー・マンデル●時間:116分●出演:ドナルド・サザーランド/トム・スケリット/エリオット・グールド/ロバート・デュヴァル/サリー・ケラーマン●日本公開:1970/07●配給:20世紀フォックス●最初に観た場所:三鷹オスカー(79-05-13)(評価:★★★★)●併映:「まぼろしの市街戦」(フィリプド・ロカ)/「博士の異常な愛情」(スタンリー・キューブリック)
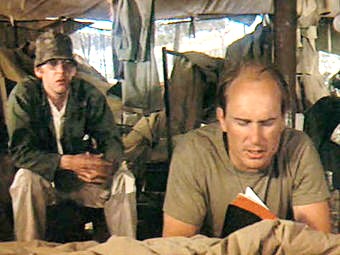


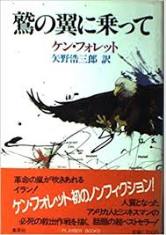
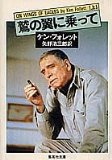
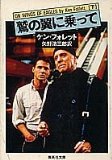
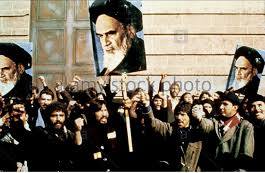
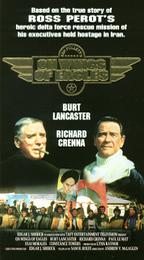
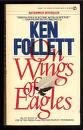 1983年に英国の作家ケン・フォレットが発表した小説で(原題:On Wings of Eagles)、実際にあった事件を取材して作品化したものであり(単行本帯には「ケン・フォレット初のノンフィクション」とあるが、"ノンフィクション小説"という感じか)、本書に登場するEDS会長ロス・ペローという人物は、1992年の大統領選に民主・共和両党とは別に第3政党を立ち上げ立候補したあのロス・ペロー氏です(小柄だが気骨ありそうな老人という印象)。
1983年に英国の作家ケン・フォレットが発表した小説で(原題:On Wings of Eagles)、実際にあった事件を取材して作品化したものであり(単行本帯には「ケン・フォレット初のノンフィクション」とあるが、"ノンフィクション小説"という感じか)、本書に登場するEDS会長ロス・ペローという人物は、1992年の大統領選に民主・共和両党とは別に第3政党を立ち上げ立候補したあのロス・ペロー氏です(小柄だが気骨ありそうな老人という印象)。 この選挙は、一般投票率が、ビル・クリントン43%、ジョージ・ブッシュ37%、ペロー19%という結果で、彼の善戦は、パパ・ブッシュの票を獲り込んだため、クリントン大統領誕生の副次的要因となったと言われていますが、自分で傭兵部隊を作って直接行動に出るというのは、一部のアメリカ人にはいかにも受けそうだなあと思います。
この選挙は、一般投票率が、ビル・クリントン43%、ジョージ・ブッシュ37%、ペロー19%という結果で、彼の善戦は、パパ・ブッシュの票を獲り込んだため、クリントン大統領誕生の副次的要因となったと言われていますが、自分で傭兵部隊を作って直接行動に出るというのは、一部のアメリカ人にはいかにも受けそうだなあと思います。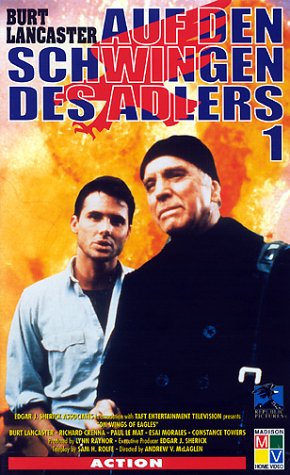
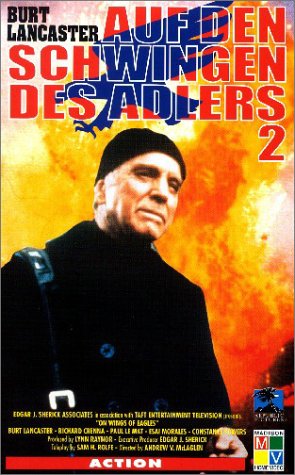 '86年にアンドリュー・V・マクラグレン監督によってTⅤ映画化されており、サイモンズ大佐を演じたバート・ランカスターは貫禄の演技で、ああ、この人なら部下はついてくるなあと。
'86年にアンドリュー・V・マクラグレン監督によってTⅤ映画化されており、サイモンズ大佐を演じたバート・ランカスターは貫禄の演技で、ああ、この人なら部下はついてくるなあと。 慎重なサイモンズは、社員たちに様々な事態を想定した訓練を施しますが、イランに入ってからの交渉は難航し、革命に乗じて何とか刑務所から2人を脱獄させた後も、トルコへの脱出行の最中に不測の事態が次々発生し、そうした際にそれらの訓練が役立つ―では、サイモンズは超人的な予言者のような人物なのかというとそうではなく、結果的に実行されることの無かった作戦の訓練も数多くこなしていたわけで、要するに、あらゆる不測の事態を想定して、入念に計画し、備えたということことなのでしょう。
慎重なサイモンズは、社員たちに様々な事態を想定した訓練を施しますが、イランに入ってからの交渉は難航し、革命に乗じて何とか刑務所から2人を脱獄させた後も、トルコへの脱出行の最中に不測の事態が次々発生し、そうした際にそれらの訓練が役立つ―では、サイモンズは超人的な予言者のような人物なのかというとそうではなく、結果的に実行されることの無かった作戦の訓練も数多くこなしていたわけで、要するに、あらゆる不測の事態を想定して、入念に計画し、備えたということことなのでしょう。
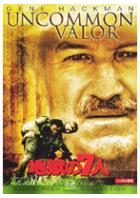
 「地獄の7人」では、男たちの友情や親子の愛情がテーマとなっていましたが、年寄りにアクションはキツいんじゃないかとつい余計な心配してしまったりするのは、元になっているのがフィクションだからでしょう。そうした意味では、「鷲の翼に乗って」のような「事実に立脚した」とか「実話に基づく」という謳い文句は強みだなあと(それさえ信じ込ませれば怖いもの無し?)。原作も映画も共に大いに楽しめたのは、自分がその"ノンフィクション効果"を、大いに受けたからかも。
「地獄の7人」では、男たちの友情や親子の愛情がテーマとなっていましたが、年寄りにアクションはキツいんじゃないかとつい余計な心配してしまったりするのは、元になっているのがフィクションだからでしょう。そうした意味では、「鷲の翼に乗って」のような「事実に立脚した」とか「実話に基づく」という謳い文句は強みだなあと(それさえ信じ込ませれば怖いもの無し?)。原作も映画も共に大いに楽しめたのは、自分がその"ノンフィクション効果"を、大いに受けたからかも。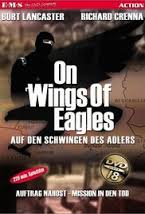
 「鷲の翼に乗って」●原題:ON WING OF EAGLES●制作年:1986年●制作国:アメリカ●監督:アンドリュー・V・マクラグレン●音楽:ローレンス・ローゼンタール●原作:ケン・フォレット●時間:235分●出演:バート・ランカスター/リチャード・クレンナ/ポール・ル・マット/ジム・メッツラー/イーサイ・モラレス/ジェームズ・ストリウス/ローレンス・プレスマン/コンスタンス・タワーズ/カレン・カールソン/シリル・オライリー●テレビ映画:1990/10 テレビ東京(評価:★★★★)
「鷲の翼に乗って」●原題:ON WING OF EAGLES●制作年:1986年●制作国:アメリカ●監督:アンドリュー・V・マクラグレン●音楽:ローレンス・ローゼンタール●原作:ケン・フォレット●時間:235分●出演:バート・ランカスター/リチャード・クレンナ/ポール・ル・マット/ジム・メッツラー/イーサイ・モラレス/ジェームズ・ストリウス/ローレンス・プレスマン/コンスタンス・タワーズ/カレン・カールソン/シリル・オライリー●テレビ映画:1990/10 テレビ東京(評価:★★★★) 「地獄の7人」●原題:UNCOMMON VALOR●制作年:1983年●制作国:アメリカ●監督:テッド・コッチェフ●製作:ジョン・ミリアス/バズ・フェイトシャンズ●脚本:ジョー・ゲイトン●撮影:スティーヴン・H・ブラム●音楽:ジェームズ・ホーナー●時間:105分●出演:ジーン・ハックマン/ロバート・スタック/フレッド・ウォード/レブ・ブラウン,/パトリック・スウェイジ●日本公開:1984/06●配給/パラマウント映画●最初に観た場所:三軒茶屋映劇(85-05-25)(評価★★★)●併映:「ゴールド・パピヨン」(ジュスト・ジャキャン)
「地獄の7人」●原題:UNCOMMON VALOR●制作年:1983年●制作国:アメリカ●監督:テッド・コッチェフ●製作:ジョン・ミリアス/バズ・フェイトシャンズ●脚本:ジョー・ゲイトン●撮影:スティーヴン・H・ブラム●音楽:ジェームズ・ホーナー●時間:105分●出演:ジーン・ハックマン/ロバート・スタック/フレッド・ウォード/レブ・ブラウン,/パトリック・スウェイジ●日本公開:1984/06●配給/パラマウント映画●最初に観た場所:三軒茶屋映劇(85-05-25)(評価★★★)●併映:「ゴールド・パピヨン」(ジュスト・ジャキャン)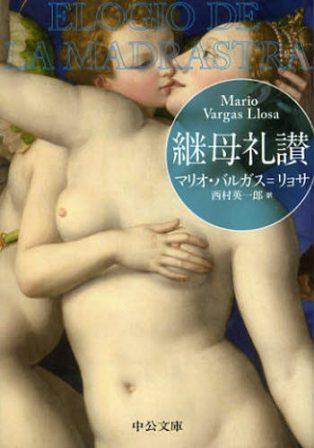
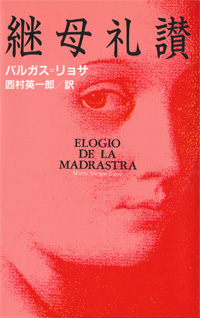

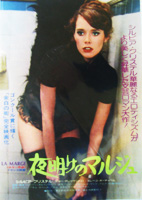
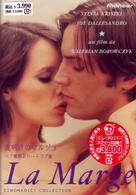
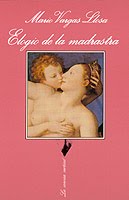 バルガス=リョサが1988年に発表した作品で(原題:Elogio de La Madrastra)、父親と息子、そして継母という3人家族が、息子であるアルフォンソ少年が継母のルクレシアに性愛の念を抱いたことで崩壊していく、ある種アブノーマル且つ"悲劇"的なストーリーの話。
バルガス=リョサが1988年に発表した作品で(原題:Elogio de La Madrastra)、父親と息子、そして継母という3人家族が、息子であるアルフォンソ少年が継母のルクレシアに性愛の念を抱いたことで崩壊していく、ある種アブノーマル且つ"悲劇"的なストーリーの話。 当時からガルシア=マルケス、ホルヘ・ルイス・ボルヘス、フリオ・コルタサルと並んでラテンアメリカ文学の四天王とでもいうべき位置づけにあった作家が、こうしたタブーに満ちた一見ポルノチックともとれる作品を書いたことで、発表時は相当に物議を醸したそうですが、バルガス=リョサの描く官能の世界は、その高尚な文学的表現のため、どことなく宗教的な崇高ささえ漂っており、「神話の世界」の話のようでもあります。そのことは、現在の家族の物語と並行して、ヘロドトスの『史記』にある、自分の妻の裸を自慢したいがために家臣に覗き見をさせ、そのことが引き金となって家臣に殺され、妻を奪われた、リディア王カンダウレスの物語や、ギリシャ神話の「狩りの女神」の物語が挿入されていることでより強まっており、更に、物語の展開の最中に、関連する古典絵画を解説的に挿入していることによっても補強されているように思いました。
当時からガルシア=マルケス、ホルヘ・ルイス・ボルヘス、フリオ・コルタサルと並んでラテンアメリカ文学の四天王とでもいうべき位置づけにあった作家が、こうしたタブーに満ちた一見ポルノチックともとれる作品を書いたことで、発表時は相当に物議を醸したそうですが、バルガス=リョサの描く官能の世界は、その高尚な文学的表現のため、どことなく宗教的な崇高ささえ漂っており、「神話の世界」の話のようでもあります。そのことは、現在の家族の物語と並行して、ヘロドトスの『史記』にある、自分の妻の裸を自慢したいがために家臣に覗き見をさせ、そのことが引き金となって家臣に殺され、妻を奪われた、リディア王カンダウレスの物語や、ギリシャ神話の「狩りの女神」の物語が挿入されていることでより強まっており、更に、物語の展開の最中に、関連する古典絵画を解説的に挿入していることによっても補強されているように思いました。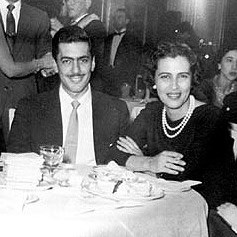 ただ、個人的には、バルガス=リョサの他の作品にもこうした熟女がしばしば登場し、また、彼自身、19歳の時に義理の叔母と結婚しているという経歴などから、この人の"熟女指向"が色濃く出た作品のようにも思いました。それがあまりにストレートだと辟易してしまうのでしょうが、「現代の物語」の方は、ルクレシアの視点を中心に、第三者の視点など幾つかに視点をばらして描いていて、少年自身の視点は無く、少年はあくまでも無垢の存在として描かれており、この手法が、「穢れを知らない無垢な天使と肉感的な美の象徴であるヴィーナスが出会えばどうなるのか」というモチーフを構成することに繋がっているように思いました。
ただ、個人的には、バルガス=リョサの他の作品にもこうした熟女がしばしば登場し、また、彼自身、19歳の時に義理の叔母と結婚しているという経歴などから、この人の"熟女指向"が色濃く出た作品のようにも思いました。それがあまりにストレートだと辟易してしまうのでしょうが、「現代の物語」の方は、ルクレシアの視点を中心に、第三者の視点など幾つかに視点をばらして描いていて、少年自身の視点は無く、少年はあくまでも無垢の存在として描かれており、この手法が、「穢れを知らない無垢な天使と肉感的な美の象徴であるヴィーナスが出会えばどうなるのか」というモチーフを構成することに繋がっているように思いました。
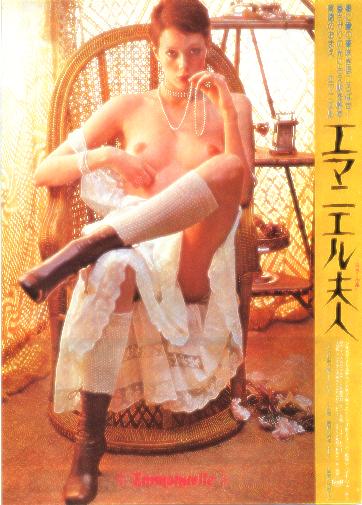
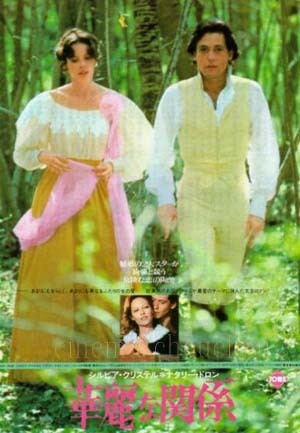

 「エマニエル夫人」はいかにもファッション写真家から転身した監督(ジュスト・ジャカン)の作品という感じで、モデル出身のシルヴィア・クリステル(1952-2012/60歳没)が、演技は素人であるにしても、もう少し上手ければなあと思われる凡作でしたが、フランシス・ジャコベッティが監督した「続エマニュエル夫人」('75年)になっても彼女の演技力は上がらず、結局は上手くならないまま、シリーズ2作目、3作目(「さよならエマニュエル夫人」('77年))と駄作化していきました。内容的にも、第1作にみられた性に対する哲学的な考察姿勢は第2作、第3作となるにつれて影を潜めていきます。その間に舞台はタイ → 香港・ジャワ → セイシェルと変わり「観光映画」としては楽しめるかも知れないけれども...。でもあのシリーズがある年代の(男女問わず)日本人の性意識にかなりの影響を及ぼした作品であることも事実なのでしょう。
「エマニエル夫人」はいかにもファッション写真家から転身した監督(ジュスト・ジャカン)の作品という感じで、モデル出身のシルヴィア・クリステル(1952-2012/60歳没)が、演技は素人であるにしても、もう少し上手ければなあと思われる凡作でしたが、フランシス・ジャコベッティが監督した「続エマニュエル夫人」('75年)になっても彼女の演技力は上がらず、結局は上手くならないまま、シリーズ2作目、3作目(「さよならエマニュエル夫人」('77年))と駄作化していきました。内容的にも、第1作にみられた性に対する哲学的な考察姿勢は第2作、第3作となるにつれて影を潜めていきます。その間に舞台はタイ → 香港・ジャワ → セイシェルと変わり「観光映画」としては楽しめるかも知れないけれども...。でもあのシリーズがある年代の(男女問わず)日本人の性意識にかなりの影響を及ぼした作品であることも事実なのでしょう。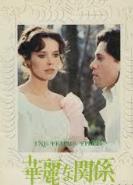
 同じくシルヴィア・クリステル主演の、ロジェ・ヴァディムが監督した「華麗な関係」('76年/仏)も、かつてジェラール・フィリップ、ジャンヌ・モロー、ジャン=ルイ・トランティニャンを配したロジェ・ヴァディム自身の「危険な関係」('59年/仏)のリメイクでしたが、原作者のラクロが墓の下で嘆きそうな出来でした。
同じくシルヴィア・クリステル主演の、ロジェ・ヴァディムが監督した「華麗な関係」('76年/仏)も、かつてジェラール・フィリップ、ジャンヌ・モロー、ジャン=ルイ・トランティニャンを配したロジェ・ヴァディム自身の「危険な関係」('59年/仏)のリメイクでしたが、原作者のラクロが墓の下で嘆きそうな出来でした。 同じ年にシルヴィア・クリステルは、ヴァレリアン・ボロヴズィック監督の「夜明けのマルジュ」('76年/仏)にも出演していて(実はこれを最初に観たのだが)、アンドレイ・ピエール・マンディアルグ(1909 -1991)のゴンクール賞受賞作「余白の街」が原作で、1人のセールスマンが、出張先のパリで娼婦と一夜を共にした翌朝、妻と息子の急死の知らせを受け自殺するというストーリー。メランコリックな脚本やしっとりしたカメラワーク自体は悪くないのですが、「世界一美しい娼婦」という触れ込みのシルヴィア・クリステルが、残念ながら演技し切れていない...。
同じ年にシルヴィア・クリステルは、ヴァレリアン・ボロヴズィック監督の「夜明けのマルジュ」('76年/仏)にも出演していて(実はこれを最初に観たのだが)、アンドレイ・ピエール・マンディアルグ(1909 -1991)のゴンクール賞受賞作「余白の街」が原作で、1人のセールスマンが、出張先のパリで娼婦と一夜を共にした翌朝、妻と息子の急死の知らせを受け自殺するというストーリー。メランコリックな脚本やしっとりしたカメラワーク自体は悪くないのですが、「世界一美しい娼婦」という触れ込みのシルヴィア・クリステルが、残念ながら演技し切れていない...。
 何故この女優が日本で受けたのかよく解らない...と言いつつ、自分自身もシルヴィア・クリステルの出演作品を5本以上観ているわけですが、個人的には公開から3年以上経って観た「エマニエル夫人」に関して言えば、シルヴィア・クリステルという女優そのものが受けたと言うより、ピエール・バシュレの甘い音楽とか(「続エマニュエル夫人」ではフランシス・レイ、「さよならエマニュエル夫人」ではセルジュ・ゲンズブールが音楽を担当、セルジュ・ゲンズブールは主題歌歌唱も担当)、女性でも観ることが出来るポルノであるとか、商業映画として受ける付加価値的な要素が背景にあったように思います(合計320万人の観客のうち女性が8割を占めたという(『
何故この女優が日本で受けたのかよく解らない...と言いつつ、自分自身もシルヴィア・クリステルの出演作品を5本以上観ているわけですが、個人的には公開から3年以上経って観た「エマニエル夫人」に関して言えば、シルヴィア・クリステルという女優そのものが受けたと言うより、ピエール・バシュレの甘い音楽とか(「続エマニュエル夫人」ではフランシス・レイ、「さよならエマニュエル夫人」ではセルジュ・ゲンズブールが音楽を担当、セルジュ・ゲンズブールは主題歌歌唱も担当)、女性でも観ることが出来るポルノであるとか、商業映画として受ける付加価値的な要素が背景にあったように思います(合計320万人の観客のうち女性が8割を占めたという(『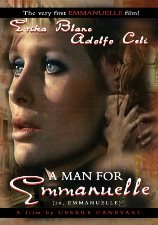 バルガス=リョサの熟女指向から始まって、殆どシルヴィア・クリステル談義になってしまいましたが、シルヴィア・クリステルの「エマニュエル夫人」はエマニュエル・シリーズの初映像化ではなく、実際はこの作品の5年前にイタリアで作られたチェザーレ・カネバリ監督、エリカ・ブラン主演の「アマン・フォー・エマニュエル(A Man for Emmanuelle)」('69年/伊)が最初の映画化作品です(日本未公開)。
バルガス=リョサの熟女指向から始まって、殆どシルヴィア・クリステル談義になってしまいましたが、シルヴィア・クリステルの「エマニュエル夫人」はエマニュエル・シリーズの初映像化ではなく、実際はこの作品の5年前にイタリアで作られたチェザーレ・カネバリ監督、エリカ・ブラン主演の「アマン・フォー・エマニュエル(A Man for Emmanuelle)」('69年/伊)が最初の映画化作品です(日本未公開)。 
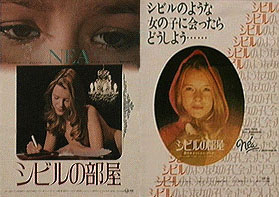 「シビルの部屋」のストーリーは、シビルという16歳の少女がポルノ小説を書こうと思い立って、憧れの中年男に性の手ほどきを受け、その体験を本にしたところベストセラーになってしまい、執筆に協力してくれた男を真剣に愛するようになった彼女は、今度は手を切ろうとする男に巧妙な罠をしかけて陥落させようとする...というもので、原作はエマニュエル・アルサンの半自伝的小説であり、アルサンは実際にこの作品に出てくる「ネア」という小説も書いている-と言うより、この映画の原作が「ネア」であるという、ちょっとした入れ子構造。映画化作品は、少女の情感がしっとりと描かれている反面、目的のために手段を選ばないやり方には共感しにくかったように思います。
「シビルの部屋」のストーリーは、シビルという16歳の少女がポルノ小説を書こうと思い立って、憧れの中年男に性の手ほどきを受け、その体験を本にしたところベストセラーになってしまい、執筆に協力してくれた男を真剣に愛するようになった彼女は、今度は手を切ろうとする男に巧妙な罠をしかけて陥落させようとする...というもので、原作はエマニュエル・アルサンの半自伝的小説であり、アルサンは実際にこの作品に出てくる「ネア」という小説も書いている-と言うより、この映画の原作が「ネア」であるという、ちょっとした入れ子構造。映画化作品は、少女の情感がしっとりと描かれている反面、目的のために手段を選ばないやり方には共感しにくかったように思います。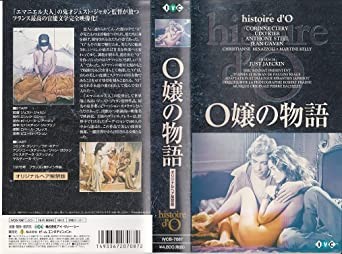
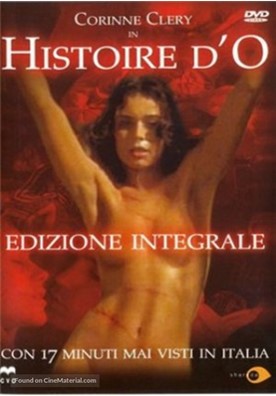 「エマニエル夫人」のジュスト・ジャカン監督は、ポーリーヌ・レアージュのポルノグラフィー文学として名高い、SM文学小説『O嬢の物語』の映画化していて(「O嬢の物語」('75年/仏))、ヒロインO(コリンヌ・クレリー)が、恋人のルネ(ウド・キア)と、ロワッシー館に入り、そこで、Oは全裸になり皮手錠と首輪をはめられ、着衣の男の愛撫を受けて鞭を打たれ、ルネはただ見守るだけ。あるとき全裸のままのOが紅茶を飲んでいる最中に、ルネと一緒に見知らぬ男がやってきて3人で―と、裸のヒロインと着衣の男姓とが絡むCMNFシーンが目立った作品でした(焼きゴテが熱そうで、あまり文学の香りはしなかった(笑))。
「エマニエル夫人」のジュスト・ジャカン監督は、ポーリーヌ・レアージュのポルノグラフィー文学として名高い、SM文学小説『O嬢の物語』の映画化していて(「O嬢の物語」('75年/仏))、ヒロインO(コリンヌ・クレリー)が、恋人のルネ(ウド・キア)と、ロワッシー館に入り、そこで、Oは全裸になり皮手錠と首輪をはめられ、着衣の男の愛撫を受けて鞭を打たれ、ルネはただ見守るだけ。あるとき全裸のままのOが紅茶を飲んでいる最中に、ルネと一緒に見知らぬ男がやってきて3人で―と、裸のヒロインと着衣の男姓とが絡むCMNFシーンが目立った作品でした(焼きゴテが熱そうで、あまり文学の香りはしなかった(笑))。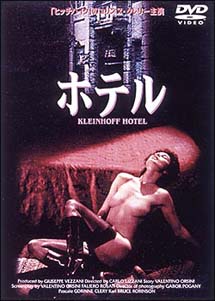
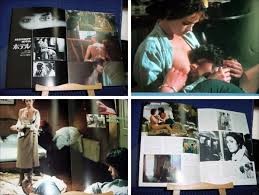 O嬢を演じたコリンヌ・クレリーが出た映画では、「ホテル」('77年/伊・西独)というものがあり、あらすじは以下の通り。
O嬢を演じたコリンヌ・クレリーが出た映画では、「ホテル」('77年/伊・西独)というものがあり、あらすじは以下の通り。 て「僕は観てないよ。要は、高級なポルノグラフィさ」と述べている)。全体の暗い雰囲気はいかにもドイツという感じ。これを観た「新橋文化」は山手線のガード下にあり、列車が通る度にガタガタうるさい音がするのが記憶に残っています。コリンヌ・クレリーは、この作品の後「007 ムーンレイカー」('79年/英)にも出演し、ロイス・チャイルズに次ぐ"第2のボンド・ガール"となりますが、歴代で最もセクシーなボンド・ガールだったとの声も一部にあるようです。
て「僕は観てないよ。要は、高級なポルノグラフィさ」と述べている)。全体の暗い雰囲気はいかにもドイツという感じ。これを観た「新橋文化」は山手線のガード下にあり、列車が通る度にガタガタうるさい音がするのが記憶に残っています。コリンヌ・クレリーは、この作品の後「007 ムーンレイカー」('79年/英)にも出演し、ロイス・チャイルズに次ぐ"第2のボンド・ガール"となりますが、歴代で最もセクシーなボンド・ガールだったとの声も一部にあるようです。
 「エマニエル夫人」●原題:EMMANUELLE●制作年:1974年●制作国:フランス●監督:ジュスト・ジャカン●製作:イヴ・ルッセ=ルアール●脚本:ジャン=ルイ・リシャール●撮影:リシャール・スズキ●音楽:ピエール・バシュレ●原作:エマニュエル・アルサン「エマニュエル」●時間:91分●出演:シルヴィア・クリステル/アラン・キューリー/ダニエル・サーキー/クリスティーヌ・ボワッソン/マリカ・グリーン●日本公開:1974/12●配給:日本ヘラルド映画●最初に観た場所:三鷹オスカー(78-07-17)(評価:★★)●併映:「続・エマニエル夫人」(フランシス・ジャコベッティ)/「さよならエマニエル夫人」(フランソワ・ルテリエ)
「エマニエル夫人」●原題:EMMANUELLE●制作年:1974年●制作国:フランス●監督:ジュスト・ジャカン●製作:イヴ・ルッセ=ルアール●脚本:ジャン=ルイ・リシャール●撮影:リシャール・スズキ●音楽:ピエール・バシュレ●原作:エマニュエル・アルサン「エマニュエル」●時間:91分●出演:シルヴィア・クリステル/アラン・キューリー/ダニエル・サーキー/クリスティーヌ・ボワッソン/マリカ・グリーン●日本公開:1974/12●配給:日本ヘラルド映画●最初に観た場所:三鷹オスカー(78-07-17)(評価:★★)●併映:「続・エマニエル夫人」(フランシス・ジャコベッティ)/「さよならエマニエル夫人」(フランソワ・ルテリエ)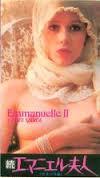
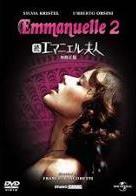
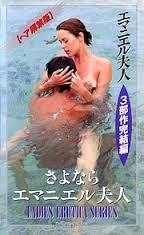 「さよならエマニエル夫人」●原題:GOOD-BYE, EMMANUELLE●制作年:1977年●制作国:フランス●監督:フランソワ・ルテリエ●製作:イヴ・ルッセ=ルアール●脚本:
「さよならエマニエル夫人」●原題:GOOD-BYE, EMMANUELLE●制作年:1977年●制作国:フランス●監督:フランソワ・ルテリエ●製作:イヴ・ルッセ=ルアール●脚本: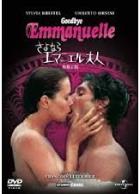
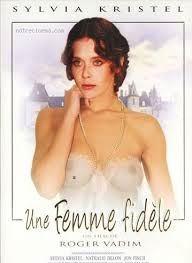
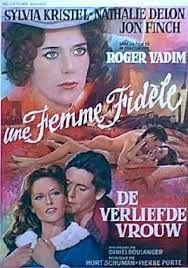
 「華麗な関係」●原題:UNE FEMME FIDELE●制作年:1976年●制作国:フランス●監督:ロジェ・ヴァディム●製作:フランシス・コーヌ/レイモン・エジェ●脚本:ロジェ・ヴァディム/ダニエル・ブーランジェル●撮影:クロード・ルノワ●音楽:モルト・シューマン/ピエール・ポルト●原作:ピエール・コデルロス・ド・ラクロ「危険な関係」●時間:91分●出演:シルヴィア・クリステル/ジョン・フィンチ/ナタリー・ドロン/ジゼール・カサドジュ/ジャック・ベルティエ/アンヌ・マリー・デスコット/セルジュ・マルカン●日本公開:1977/05●配給:東宝東和●最初に観た場所:三鷹東映(78-01-16)(評価:★☆)●併映:「エーゲ海の旅情」(ミルトン・カトセラス)/「しのび逢い」(ケビン・ビリングトン)
「華麗な関係」●原題:UNE FEMME FIDELE●制作年:1976年●制作国:フランス●監督:ロジェ・ヴァディム●製作:フランシス・コーヌ/レイモン・エジェ●脚本:ロジェ・ヴァディム/ダニエル・ブーランジェル●撮影:クロード・ルノワ●音楽:モルト・シューマン/ピエール・ポルト●原作:ピエール・コデルロス・ド・ラクロ「危険な関係」●時間:91分●出演:シルヴィア・クリステル/ジョン・フィンチ/ナタリー・ドロン/ジゼール・カサドジュ/ジャック・ベルティエ/アンヌ・マリー・デスコット/セルジュ・マルカン●日本公開:1977/05●配給:東宝東和●最初に観た場所:三鷹東映(78-01-16)(評価:★☆)●併映:「エーゲ海の旅情」(ミルトン・カトセラス)/「しのび逢い」(ケビン・ビリングトン)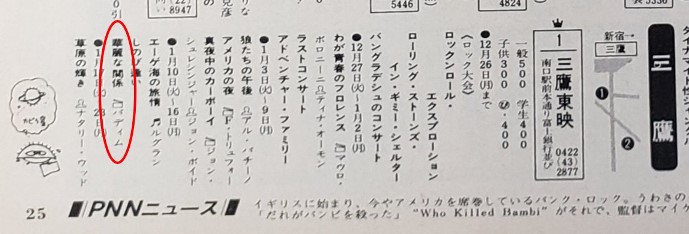
 「夜明けのマルジュ」●原題:LA MARGE●制作年:1976年●制作国:フランス●監督:ヴァレリアン・ボロヴズィック●製作:ロベール・アキム/レイモン・アキム●撮影:ベルナール・ダイレ
「夜明けのマルジュ」●原題:LA MARGE●制作年:1976年●制作国:フランス●監督:ヴァレリアン・ボロヴズィック●製作:ロベール・アキム/レイモン・アキム●撮影:ベルナール・ダイレ
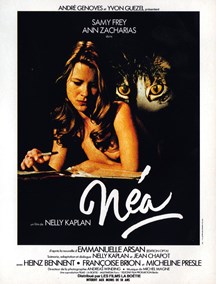
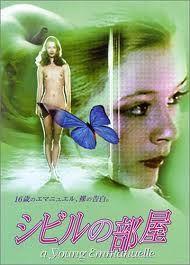
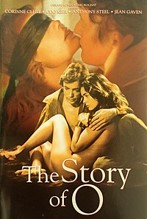
 「O嬢の物語」●原題:HISTOIRE D'O●制作年:1975年●制作国:フランス●監督:ジュスト・ジャカン●製作:エリック・ローシャ●脚本:セバスチャン・ジャプリゾ●撮影:ロベール・フレース●音楽:ピエール・バシュレ●原作:ポーリーヌ・レアージュ●時間:105分●出演:コリンヌ・クレリー/ウド・キア/アンソニー・スティール/ジャン・ギャバン/クリスチアーヌ・ミナッツォリ/マルティーヌ・ケリー/リ・セルグリーン/アラン・ヌーリー●日本公開:1976/03●配給:東宝東和●最初に観た場所:三鷹東映(78-02-04)(評価:★★)●併映:「ラストタンゴ・イン・パリ」(ベルナルド・ベルトリッチ)/「スキャンダル」(サルバトーレ・サンペリ)
「O嬢の物語」●原題:HISTOIRE D'O●制作年:1975年●制作国:フランス●監督:ジュスト・ジャカン●製作:エリック・ローシャ●脚本:セバスチャン・ジャプリゾ●撮影:ロベール・フレース●音楽:ピエール・バシュレ●原作:ポーリーヌ・レアージュ●時間:105分●出演:コリンヌ・クレリー/ウド・キア/アンソニー・スティール/ジャン・ギャバン/クリスチアーヌ・ミナッツォリ/マルティーヌ・ケリー/リ・セルグリーン/アラン・ヌーリー●日本公開:1976/03●配給:東宝東和●最初に観た場所:三鷹東映(78-02-04)(評価:★★)●併映:「ラストタンゴ・イン・パリ」(ベルナルド・ベルトリッチ)/「スキャンダル」(サルバトーレ・サンペリ)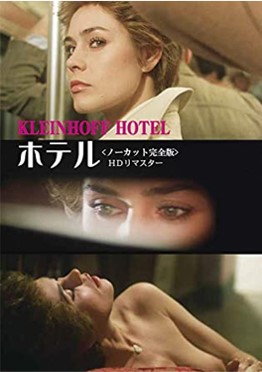
 「ホテル」●原題:KLEINHOFF HOTEL●制作年:1975年●制作国:イタリア・西ドイツ●監督:カルロ・リッツァーニ●製作:ジュゼッペ・ベッツァーニ●脚本:セバスチャン・ジャプリゾ●撮影:ガボール・ポガニー●音楽:ジョルジオ・ガスリーニ●原案:バレンティーノ・オルシーニ●時間:105分●出演:コリンヌ・クレリー/ブルース・ロビンソン/ケイチャ・ルペ/ウェルナー・ポチャス/ペーター・カーン/ミケーレ・プラチド - ペドロ ●日本公開:1981/05●配給:日本ヘラルド映画●最初に観た場所:新橋文
「ホテル」●原題:KLEINHOFF HOTEL●制作年:1975年●制作国:イタリア・西ドイツ●監督:カルロ・リッツァーニ●製作:ジュゼッペ・ベッツァーニ●脚本:セバスチャン・ジャプリゾ●撮影:ガボール・ポガニー●音楽:ジョルジオ・ガスリーニ●原案:バレンティーノ・オルシーニ●時間:105分●出演:コリンヌ・クレリー/ブルース・ロビンソン/ケイチャ・ルペ/ウェルナー・ポチャス/ペーター・カーン/ミケーレ・プラチド - ペドロ ●日本公開:1981/05●配給:日本ヘラルド映画●最初に観た場所:新橋文


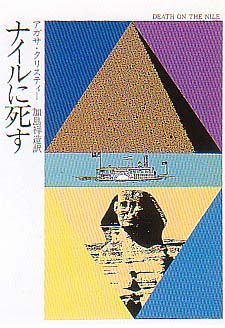


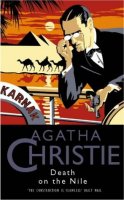 ハネムーンをエジプトに決めた大富豪の娘リンネットは、ナイル河で遊覧船の旅を楽しんでいたが、そこには夫のかつての婚約者ジャクリーンの不気味な影が...果たして、乗り合わせたポワロの目の前でリンネットは殺され、さらに続く殺人の連鎖反応が起きるが、ジャクリーンには文句無しのアリバイが―。
ハネムーンをエジプトに決めた大富豪の娘リンネットは、ナイル河で遊覧船の旅を楽しんでいたが、そこには夫のかつての婚約者ジャクリーンの不気味な影が...果たして、乗り合わせたポワロの目の前でリンネットは殺され、さらに続く殺人の連鎖反応が起きるが、ジャクリーンには文句無しのアリバイが―。 "Death on the Nile" ハ―パーコリンズ版
"Death on the Nile" ハ―パーコリンズ版 '78年の公開時に、今は無きマンモス映画館「日比谷映画劇場」で観て、90年代初めにビデオでも観ましたが、映画は、原作をやや端折ったような部分もあり、最後はちょっとドタバタのうちにポアロの謎解きが始まって、原作との間に多少距離を感じました。
'78年の公開時に、今は無きマンモス映画館「日比谷映画劇場」で観て、90年代初めにビデオでも観ましたが、映画は、原作をやや端折ったような部分もあり、最後はちょっとドタバタのうちにポアロの謎解きが始まって、原作との間に多少距離を感じました。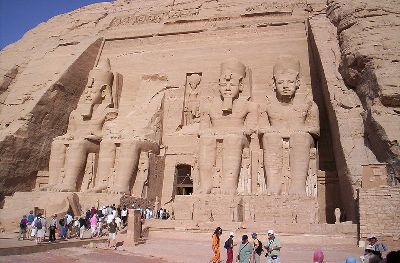 また、この映画に関して言えば、本場エジプトでのオールロケで撮影されているため(同じナイル川でも原作の場所とはやや違っているようだが)、ある種"観光映画"(?)としても楽しめたというのがメリットでしょうか。行ってみたいね、ナイル川クルーズ。雪中で止まってしまった「オリエント急行」と違って、ナイルの川面を船が「動いている」という実感もあるし、途中で下船していろいろ観光もするし...。
また、この映画に関して言えば、本場エジプトでのオールロケで撮影されているため(同じナイル川でも原作の場所とはやや違っているようだが)、ある種"観光映画"(?)としても楽しめたというのがメリットでしょうか。行ってみたいね、ナイル川クルーズ。雪中で止まってしまった「オリエント急行」と違って、ナイルの川面を船が「動いている」という実感もあるし、途中で下船していろいろ観光もするし...。
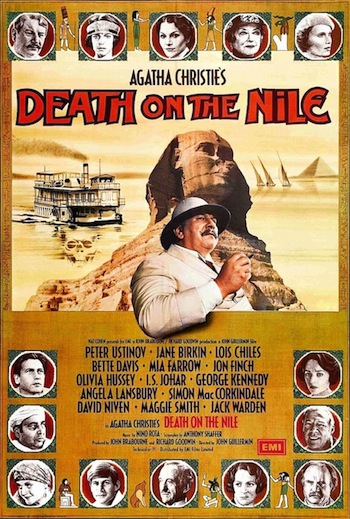 ベティ・デイヴィスなんて往年の名女優も出ていたりして名優揃いの作品ですが、やはり何と言ってもオリジナルがいいんだろうなあ。この意外性のあるパターン、男女の関係なんて、傍目ではワカラナイ...。クリスティが最初の考案者かどうかは別として、この手の「人間関係トリック」は、その後も英国ミステリで何度か使われているみたいです。
ベティ・デイヴィスなんて往年の名女優も出ていたりして名優揃いの作品ですが、やはり何と言ってもオリジナルがいいんだろうなあ。この意外性のあるパターン、男女の関係なんて、傍目ではワカラナイ...。クリスティが最初の考案者かどうかは別として、この手の「人間関係トリック」は、その後も英国ミステリで何度か使われているみたいです。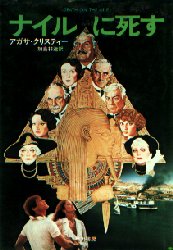 「ナイル殺人事件」●原題:DEATH ON THE NILE●制作
「ナイル殺人事件」●原題:DEATH ON THE NILE●制作


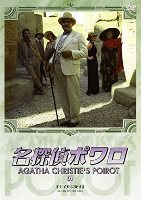

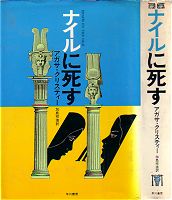




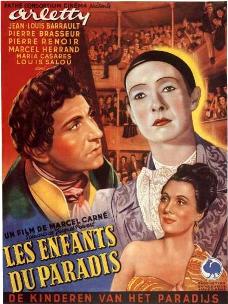 著者独自の「星」による採点は上の方が厳しくて、100点満点換算すると100点に該当する作品は無く、最高は90点で「天井桟敷の人々」('45年)と「ザッツ・エンタテインメント」('74年)の2作か(但し、個人的には、「天井桟敷の人々」は、一般的な「ミュージカル映画」というイメージからはやや外れているようにも思う)。
著者独自の「星」による採点は上の方が厳しくて、100点満点換算すると100点に該当する作品は無く、最高は90点で「天井桟敷の人々」('45年)と「ザッツ・エンタテインメント」('74年)の2作か(但し、個人的には、「天井桟敷の人々」は、一般的な「ミュージカル映画」というイメージからはやや外れているようにも思う)。



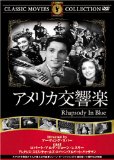


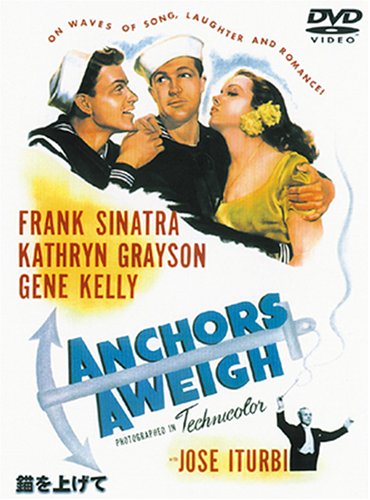


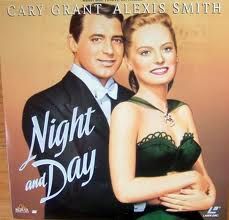

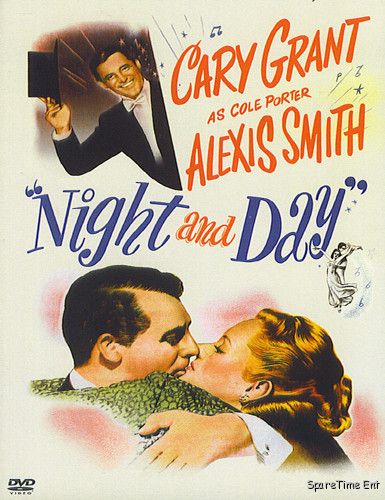 アメリカの作曲家コール・ポーターの伝記作品。著者の言う通り、「ポーターの佳曲の数々を聴かせ唄と踊りの総天然色場面を楽しませる」のが目的みたいな作品(曰く「その限りにおいては楽しい」と)。
アメリカの作曲家コール・ポーターの伝記作品。著者の言う通り、「ポーターの佳曲の数々を聴かせ唄と踊りの総天然色場面を楽しませる」のが目的みたいな作品(曰く「その限りにおいては楽しい」と)。


 ならない」という「赤い靴」の伝説があるそうだが、「赤い靴」と言えばアンデルセンが先に思い浮かぶ(一応、そこから材を得ているとのこと)。
ならない」という「赤い靴」の伝説があるそうだが、「赤い靴」と言えばアンデルセンが先に思い浮かぶ(一応、そこから材を得ているとのこと)。.jpg)
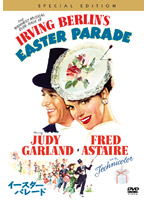
 24時間の休暇をもらった3人の水兵がニューヨークを舞台に繰り広げるミュージカル。3人が埠頭に降り立って最初に歌うのは「ニューヨーク、ニューヨーク」。振付もジーン・ケリーが担当した。著者はヴェラ=エレンの踊りが良かったと。
24時間の休暇をもらった3人の水兵がニューヨークを舞台に繰り広げるミュージカル。3人が埠頭に降り立って最初に歌うのは「ニューヨーク、ニューヨーク」。振付もジーン・ケリーが担当した。著者はヴェラ=エレンの踊りが良かったと。 dvd.jpg)
 ⑧「巴里のアメリカ人」 ('51年/米)著者 ☆☆☆☆★(85点)自分 ★★★★(80点)
⑧「巴里のアメリカ人」 ('51年/米)著者 ☆☆☆☆★(85点)自分 ★★★★(80点)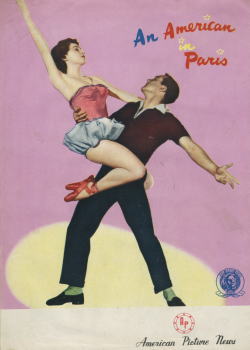


 「巴里のアメリカ人」●原題:AN AMERICAN IN PARIS●制作年:1951年●制作国:アメリカ●監督:ヴィンセント・ミネリ●製作:アーサー・フリード●脚本:アラン・ジェイ・ラー
「巴里のアメリカ人」●原題:AN AMERICAN IN PARIS●制作年:1951年●制作国:アメリカ●監督:ヴィンセント・ミネリ●製作:アーサー・フリード●脚本:アラン・ジェイ・ラー ナー●撮影:アルフレッド・ギルクス●音楽:ジョージ・ガーシュイン●時間:113分●出演:ジーン・ケリー/レスリー・キャロン/オスカー・レヴァント/ジョルジュ・ゲタリー/ユージン・ボーデン/ニナ・フォック●日本公開:1952/05●配給:MGM日本支社●最初に観た場所:高田馬場パール座(78-05-27)●併映:「シェルブールの雨傘」(ジャック・ドゥミ)
ナー●撮影:アルフレッド・ギルクス●音楽:ジョージ・ガーシュイン●時間:113分●出演:ジーン・ケリー/レスリー・キャロン/オスカー・レヴァント/ジョルジュ・ゲタリー/ユージン・ボーデン/ニナ・フォック●日本公開:1952/05●配給:MGM日本支社●最初に観た場所:高田馬場パール座(78-05-27)●併映:「シェルブールの雨傘」(ジャック・ドゥミ)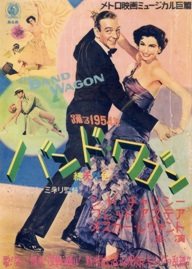
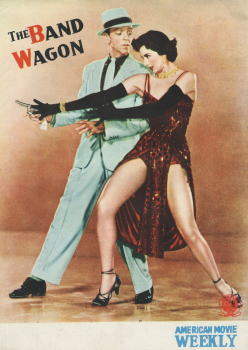

![バンド・ワゴン 特別版 [DVD].jpg](/book-movie/archives/バンド・ワゴン 特別版 [DVD].jpg)
 落ち目のスター、フレッド・アステアの再起物語で、「イースター・パレード」以上にショー・ビズもの色合いが強い作品だが、コメディタッチで明るい。ストーリーは予定調和だが、本書によれば、ミッキー・スピレーンの探偵小説のパロディが織り込まれているとのことで、そうしたことも含め、通好みの作品かも。但し、アステアとシド・チャリシーの踊りだけでも十分楽しめる。シド・チャリシーの踊りも、レスリー・キャロンと双璧と言っていぐらいスゴイ。
落ち目のスター、フレッド・アステアの再起物語で、「イースター・パレード」以上にショー・ビズもの色合いが強い作品だが、コメディタッチで明るい。ストーリーは予定調和だが、本書によれば、ミッキー・スピレーンの探偵小説のパロディが織り込まれているとのことで、そうしたことも含め、通好みの作品かも。但し、アステアとシド・チャリシーの踊りだけでも十分楽しめる。シド・チャリシーの踊りも、レスリー・キャロンと双璧と言っていぐらいスゴイ。 「バンド・ワゴン」●原題:THE BANDO WAGON●制作年:1953年●制作国:アメリカ●監督:ヴィンセント・ミネリ●製作:アーサー・フリード●脚本:ベティ・コムデン/アドルフ・グリーン●撮影:ハリー・ジャクソン●音楽:アドルフ・ドイッチ/コンラッド・サリンジャー●時間:112分●出演:フレッド・アステア/シド・チャリシー/オスカー・レヴァント/ナネット・ファブレー●日本公開:1953/12●配給:MGM●最初に観た場所:テアトル新宿(85-10-19)
「バンド・ワゴン」●原題:THE BANDO WAGON●制作年:1953年●制作国:アメリカ●監督:ヴィンセント・ミネリ●製作:アーサー・フリード●脚本:ベティ・コムデン/アドルフ・グリーン●撮影:ハリー・ジャクソン●音楽:アドルフ・ドイッチ/コンラッド・サリンジャー●時間:112分●出演:フレッド・アステア/シド・チャリシー/オスカー・レヴァント/ナネット・ファブレー●日本公開:1953/12●配給:MGM●最初に観た場所:テアトル新宿(85-10-19)

 著者曰く「すばらしいファション・ミュージカル」であり、オードリー・ヘプバーンの魅力がたっぷり味わえると(原題の「ファニー・フェイス」はもちろんヘップバーンのことを指す)。
著者曰く「すばらしいファション・ミュージカル」であり、オードリー・ヘプバーンの魅力がたっぷり味わえると(原題の「ファニー・フェイス」はもちろんヘップバーンのことを指す)。 衣装はジバンシー、音楽はガーシュウィンで、音楽と併せて、女性であればファッションも楽しめるのは確か。
衣装はジバンシー、音楽はガーシュウィンで、音楽と併せて、女性であればファッションも楽しめるのは確か。 ちょっと「マイ・フェア・レディ」に似た話で、「マイ・フェア・レディ」が吹替えなのに対し、こっちはオードリー・ヘプバーン本人の肉声の歌が聴ける。それにしても、一旦引退したこともあるはずのアステアが元気で、とても57才とは思えない。結局、更に20余年、「ザッツ・エンタテインメント」('74年)まで活躍したから、ある意味"超人"的。
ちょっと「マイ・フェア・レディ」に似た話で、「マイ・フェア・レディ」が吹替えなのに対し、こっちはオードリー・ヘプバーン本人の肉声の歌が聴ける。それにしても、一旦引退したこともあるはずのアステアが元気で、とても57才とは思えない。結局、更に20余年、「ザッツ・エンタテインメント」('74年)まで活躍したから、ある意味"超人"的。
 「パリの恋人」●原題:FUNNY FACE●制作年:1956年●制作国:アメリカ●監督:ス
「パリの恋人」●原題:FUNNY FACE●制作年:1956年●制作国:アメリカ●監督:ス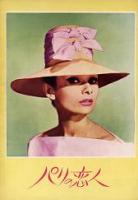 タンリー・ドーネン●製作:アーサー・フリード●脚本:レナード・ガーシェ●撮影:レイ・ジューン●音楽:ジョージ・ガーシュウィン/アドルフ・ドイッチ●時間:103分●出演:オードリー・ヘプバーン/フレッド・アステア/ケイ・トンプスン/ミシェル・オークレール●日本公開:1957/02●配給:パラマウント映画●最初に観た場所:高田馬場ACTミニシアター(85-11-03)●併映:「リリー・マルレーン」(ライナー・ヴェルナー・ファスビンダー)
タンリー・ドーネン●製作:アーサー・フリード●脚本:レナード・ガーシェ●撮影:レイ・ジューン●音楽:ジョージ・ガーシュウィン/アドルフ・ドイッチ●時間:103分●出演:オードリー・ヘプバーン/フレッド・アステア/ケイ・トンプスン/ミシェル・オークレール●日本公開:1957/02●配給:パラマウント映画●最初に観た場所:高田馬場ACTミニシアター(85-11-03)●併映:「リリー・マルレーン」(ライナー・ヴェルナー・ファスビンダー) 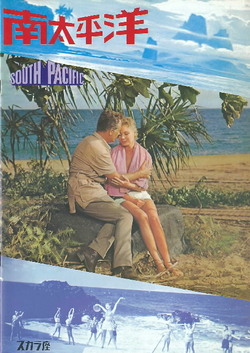 ⑪「南太平洋」('58年/米)著者 ☆☆☆★(65点)自分 ★★★☆(70点)
⑪「南太平洋」('58年/米)著者 ☆☆☆★(65点)自分 ★★★☆(70点) れる自然が満喫できる島だった)。著者は「戦時色濃厚な」作品であるため、あまり好きになれないようだが、それを言うなら、著者が高得点をつけている「シェルブールの雨傘」などは、フランス側の視点でしか描かれていないとも言えるのでは。超エスニック、大規模ロケ映画で、空も海も恐ろしいくらい青い(カラーフィルターのせいか? フィルターの色が濃すぎて技術的に失敗しているとみる人もいるようだ)。トロピカル・ナンバーの定番になった主題歌「バリ・ハイ」や「魅惑の宵」などの歌曲もいい。
れる自然が満喫できる島だった)。著者は「戦時色濃厚な」作品であるため、あまり好きになれないようだが、それを言うなら、著者が高得点をつけている「シェルブールの雨傘」などは、フランス側の視点でしか描かれていないとも言えるのでは。超エスニック、大規模ロケ映画で、空も海も恐ろしいくらい青い(カラーフィルターのせいか? フィルターの色が濃すぎて技術的に失敗しているとみる人もいるようだ)。トロピカル・ナンバーの定番になった主題歌「バリ・ハイ」や「魅惑の宵」などの歌曲もいい。
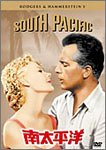


.jpg)


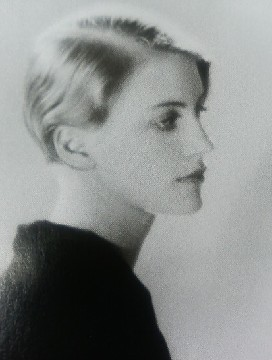 Lee Miller (1907-1977)photo by Man Ray/Self-Portrait(下右)
Lee Miller (1907-1977)photo by Man Ray/Self-Portrait(下右) モデルや女優から写真家になった人は多く、かの
モデルや女優から写真家になった人は多く、かの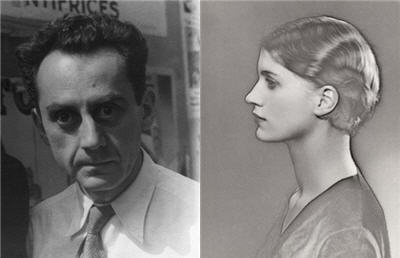 そうした中(と言っても、この中で比べて差し支えないにはレニぐらいだろうが)、このリー・ミラー(Lee Miller)は、モデルとしても写真家としても一流だったと言えるでしょう。
そうした中(と言っても、この中で比べて差し支えないにはレニぐらいだろうが)、このリー・ミラー(Lee Miller)は、モデルとしても写真家としても一流だったと言えるでしょう。
 戦場に向かう女性将校や戦場に斃れた兵士などを撮り、自決したナチの将校や頭髪を剃られたナチ協力者の女性、殴られて顔が変形したナチ収容所の元警備兵などの生々しい写真もありますが、ファッション写真を撮っていた頃に既にシューレアリストから強い影響を受けており(彼女はジャン・コクトー監督の「詩人の血」('30年/仏)に"生きた彫像"役で出ている。面白いけれど評価不能に近いシュールな映画だった)、そうした勇壮な、或いは悲惨な写真においても、その光と影の使い方にシュールな感覚が見られ、その覚めた意匠が、却って報道写真としての説得効果を増しているように思います。
戦場に向かう女性将校や戦場に斃れた兵士などを撮り、自決したナチの将校や頭髪を剃られたナチ協力者の女性、殴られて顔が変形したナチ収容所の元警備兵などの生々しい写真もありますが、ファッション写真を撮っていた頃に既にシューレアリストから強い影響を受けており(彼女はジャン・コクトー監督の「詩人の血」('30年/仏)に"生きた彫像"役で出ている。面白いけれど評価不能に近いシュールな映画だった)、そうした勇壮な、或いは悲惨な写真においても、その光と影の使い方にシュールな感覚が見られ、その覚めた意匠が、却って報道写真としての説得効果を増しているように思います。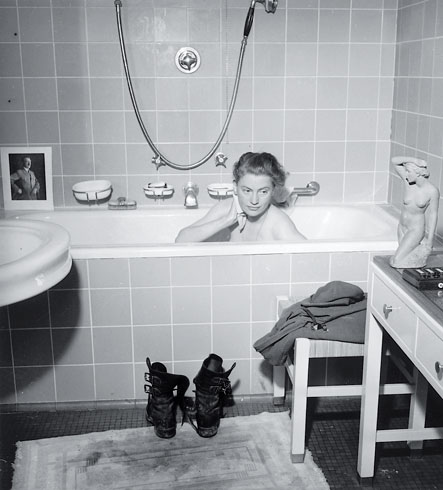
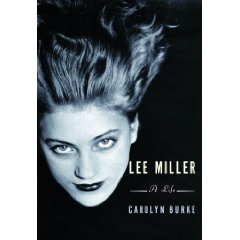
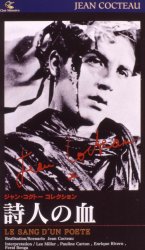
.jpg)
 「詩人の血」●原題:LE SANG D'UN POETE●制作年:1930年●制作国:フランス●監督・脚本:ジャン・コクトー●製作:ド・ノアイユ伯爵●撮影:ジョルジュ・ペリナール●音楽:ジョルジュ・オーリック●時間:50分●出演:リー・ミラー/ポリーヌ・カルトン/オデット・タラザック/エンリケ・リベロ/ジャン・デボルド●パリ公開:1930/01(プレミア上映)●最初に観た場所:新宿アートビレッジ (79-03-02)(評価:★★★?)●併映:「忘れられた人々」(ルイス・ブニュエル)/「アンダルシアの犬」(ルイス・ブニュエル/サルバトーレ・ダリ)
「詩人の血」●原題:LE SANG D'UN POETE●制作年:1930年●制作国:フランス●監督・脚本:ジャン・コクトー●製作:ド・ノアイユ伯爵●撮影:ジョルジュ・ペリナール●音楽:ジョルジュ・オーリック●時間:50分●出演:リー・ミラー/ポリーヌ・カルトン/オデット・タラザック/エンリケ・リベロ/ジャン・デボルド●パリ公開:1930/01(プレミア上映)●最初に観た場所:新宿アートビレッジ (79-03-02)(評価:★★★?)●併映:「忘れられた人々」(ルイス・ブニュエル)/「アンダルシアの犬」(ルイス・ブニュエル/サルバトーレ・ダリ)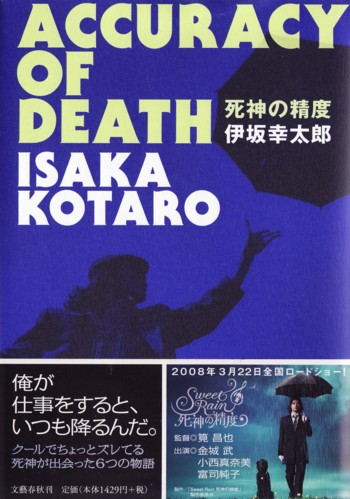

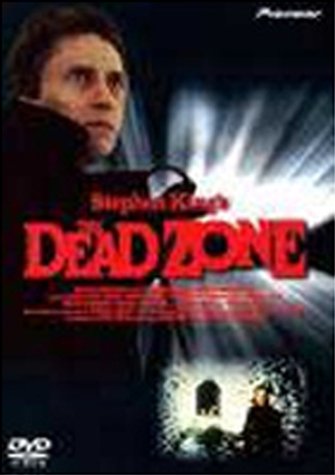
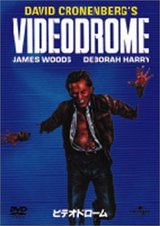

![Videodrome [1982].jpg](/book-movie/archives/Videodrome [1982].jpg) 当時の評判も良かったみたいで、同月には渋谷ユーロスペースで同監督の前作「ヴィデオドローム」('82年/カナダ)が上映され、ジェームズ・ウッズ主演のこの作品は見た人の性格を変える暴力SMビデオによって起きる殺人を描いたもので(鈴木光司原作の日本映画「リング」はこれのマネか?)、この2作でクローネンバーグの名は日本でも広く知られるようになりました(「ヴィデオドローム」は、ちょっと気持ち悪いシーンがあり、イマイチ)。
当時の評判も良かったみたいで、同月には渋谷ユーロスペースで同監督の前作「ヴィデオドローム」('82年/カナダ)が上映され、ジェームズ・ウッズ主演のこの作品は見た人の性格を変える暴力SMビデオによって起きる殺人を描いたもので(鈴木光司原作の日本映画「リング」はこれのマネか?)、この2作でクローネンバーグの名は日本でも広く知られるようになりました(「ヴィデオドローム」は、ちょっと気持ち悪いシーンがあり、イマイチ)。
 Videodrome
Videodrome
 その後、クローネンバーグは、ジョルジュ・ランジュラン原作、カート・ニューマン監督の「ハエ男の恐怖(The Fly)」('58年/米)のリメイク作品「ザ・フライ」('86年/米)を撮り(ホント、"気色悪い"系が好きだなあ)、ジェフ・ゴ
その後、クローネンバーグは、ジョルジュ・ランジュラン原作、カート・ニューマン監督の「ハエ男の恐怖(The Fly)」('58年/米)のリメイク作品「ザ・フライ」('86年/米)を撮り(ホント、"気色悪い"系が好きだなあ)、ジェフ・ゴ ールドブラムが変身してしまった「ハエ男」が最後の方では「カニ男」に見えてしまうのが難でしたが(と言うより、何が何だかよくわからない怪物になっていて、オリジナルの「ハエ男の恐怖」の方がスチールを見る限りではよほどリアルに「蠅」っぽい)、ただしストーリーはなかなかの感動もので、ラストはちょっと泣けました。
ールドブラムが変身してしまった「ハエ男」が最後の方では「カニ男」に見えてしまうのが難でしたが(と言うより、何が何だかよくわからない怪物になっていて、オリジナルの「ハエ男の恐怖」の方がスチールを見る限りではよほどリアルに「蠅」っぽい)、ただしストーリーはなかなかの感動もので、ラストはちょっと泣けました。
 「デッドゾーン」ではクリストファー・ウォーケンが演じる何の前触れもなく突然に予知能力を身につけてしまった主人公の男(スティーヴン・キングらしい設定!)は、将来大統領になって核ミサイルの発射ボタンを押すことになる男(演じているのは、後にテレビドラマ「ザ・ホワイトハウス」で合衆国大統領役を演じることになるマーティン・シーン)に対して、彼の政治生命を絶つために犠牲を払って死んでしまうのですが(未来を変えたということか)、これならストーリー的にはいくらでも話が作れそうな気がして、これきりで終わらせてしまうのは勿体無いなあと思っていたら、約20年を経てTVドラマシリーズになりました(テレビドラマ版の邦題は「デッド・ゾーン」と中黒が入る)。
「デッドゾーン」ではクリストファー・ウォーケンが演じる何の前触れもなく突然に予知能力を身につけてしまった主人公の男(スティーヴン・キングらしい設定!)は、将来大統領になって核ミサイルの発射ボタンを押すことになる男(演じているのは、後にテレビドラマ「ザ・ホワイトハウス」で合衆国大統領役を演じることになるマーティン・シーン)に対して、彼の政治生命を絶つために犠牲を払って死んでしまうのですが(未来を変えたということか)、これならストーリー的にはいくらでも話が作れそうな気がして、これきりで終わらせてしまうのは勿体無いなあと思っていたら、約20年を経てTVドラマシリーズになりました(テレビドラマ版の邦題は「デッド・ゾーン」と中黒が入る)。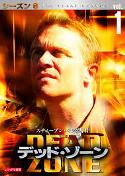
 テレビドラマ版「デッド・ゾーン」で主役のアンソニー・マイケル・ホールを見て、雰囲気がクリストファー・ウォーケンに似ているなあと思ったのは自分だけでしょうか。意図的にクリストファー・ウォーケンと重なるイメージの俳優を主役に据えたようにも思えます。
テレビドラマ版「デッド・ゾーン」で主役のアンソニー・マイケル・ホールを見て、雰囲気がクリストファー・ウォーケンに似ているなあと思ったのは自分だけでしょうか。意図的にクリストファー・ウォーケンと重なるイメージの俳優を主役に据えたようにも思えます。



 「ザ・フライ」●原題:THE FLY●制作年:1986年●制作国:アメリカ●監督・脚本:デヴィッド・クローネンバーグ●製作:スチュアート・コーンフェルド●撮影:マーク・アーウィン●音楽:ハワード・ショア ●原作:ジョルジュ・ランジュラン「蠅」●時間:87分●出演:ジェフ・ゴールドブラム/ジーナ・デイヴィス/ジョン・ゲッツ/ジョイ・ブーシェル/レス・カールソン/ジョージ・チュヴァロ/マイケル・コープマン●日本公開:1987/01●配給:20世紀フォックス●最初に観た場所:大井武蔵野舘 (87-07-19)(評価★★★★)●併映:「未来世紀ブラジル」(テリー・ギリアム)
「ザ・フライ」●原題:THE FLY●制作年:1986年●制作国:アメリカ●監督・脚本:デヴィッド・クローネンバーグ●製作:スチュアート・コーンフェルド●撮影:マーク・アーウィン●音楽:ハワード・ショア ●原作:ジョルジュ・ランジュラン「蠅」●時間:87分●出演:ジェフ・ゴールドブラム/ジーナ・デイヴィス/ジョン・ゲッツ/ジョイ・ブーシェル/レス・カールソン/ジョージ・チュヴァロ/マイケル・コープマン●日本公開:1987/01●配給:20世紀フォックス●最初に観た場所:大井武蔵野舘 (87-07-19)(評価★★★★)●併映:「未来世紀ブラジル」(テリー・ギリアム)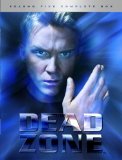

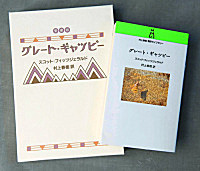

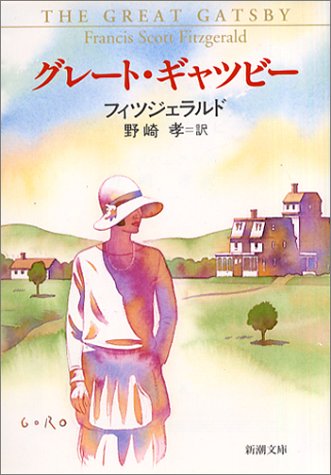
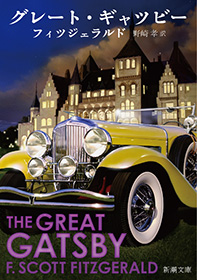
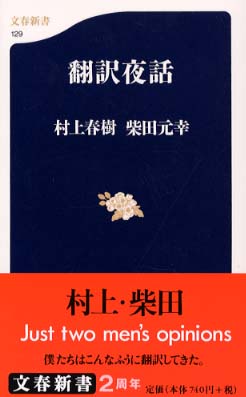
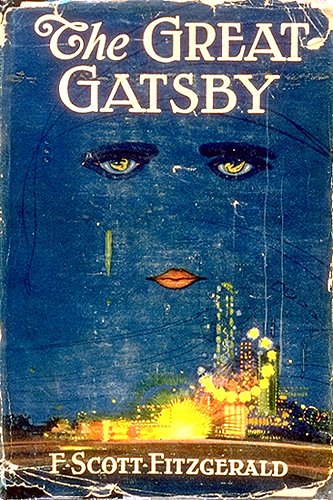
 働くためにニューヨーク郊外ロング・アイランドにある高級住宅地ウェスト・エッグへと引っ越してくるが、隣の大邸宅では日々豪華なパーティが開かれていて、その庭園には華麗な装いの男女が夜毎に集まっており、彼は否応無くその屋敷の主ジェイ・ギャツビーという人物に興味を抱くが、ある日、そのギャツビー氏にパーティに招かれる。ニックがパーティに出てみると、参加者の殆どがギャツビーについて正確なことを知らず、ニックには主催者のギャツビーがパーティの場のどこにいるかさえわからない、しかし、たまたま自分の隣にいた青年が実は―。
働くためにニューヨーク郊外ロング・アイランドにある高級住宅地ウェスト・エッグへと引っ越してくるが、隣の大邸宅では日々豪華なパーティが開かれていて、その庭園には華麗な装いの男女が夜毎に集まっており、彼は否応無くその屋敷の主ジェイ・ギャツビーという人物に興味を抱くが、ある日、そのギャツビー氏にパーティに招かれる。ニックがパーティに出てみると、参加者の殆どがギャツビーについて正確なことを知らず、ニックには主催者のギャツビーがパーティの場のどこにいるかさえわからない、しかし、たまたま自分の隣にいた青年が実は―。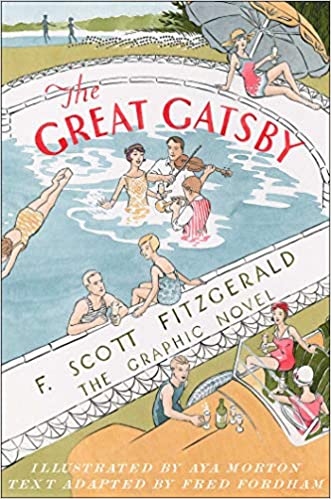 1925年に出版された米国の作家フランシス・スコット・フィッツジェラルド(Francis Scott Fitzgerald、1896‐1940/享年44)の超有名作品ですが(原題:The Great Gatsby)、上記のようなところから、ニックとギャツビーの交遊が始まるという初めの方の展開が単純に面白かったです。
1925年に出版された米国の作家フランシス・スコット・フィッツジェラルド(Francis Scott Fitzgerald、1896‐1940/享年44)の超有名作品ですが(原題:The Great Gatsby)、上記のようなところから、ニックとギャツビーの交遊が始まるという初めの方の展開が単純に面白かったです。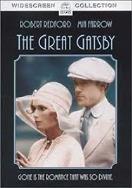
 ド主演の映画化作品「華麗なるギャツビー」('74年/米)をテレビで観る機会があって、その上でもう一度、野崎訳及び村上訳を読み返してみると、起きているごたごたの全部が終盤への伏線となっていたことが再認識でき、村上春樹氏が「過不足のない要を得た人物描写、ところどころに現れる深い内省、ヴィジュアルで生々しい動感、良質なセンチメンタリズムと、どれをとっても古典と呼ぶにふさわしい優れた作品となっている」と絶賛しているのが分かる気がしました。
ド主演の映画化作品「華麗なるギャツビー」('74年/米)をテレビで観る機会があって、その上でもう一度、野崎訳及び村上訳を読み返してみると、起きているごたごたの全部が終盤への伏線となっていたことが再認識でき、村上春樹氏が「過不足のない要を得た人物描写、ところどころに現れる深い内省、ヴィジュアルで生々しい動感、良質なセンチメンタリズムと、どれをとっても古典と呼ぶにふさわしい優れた作品となっている」と絶賛しているのが分かる気がしました。
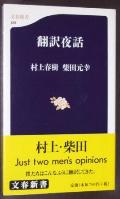
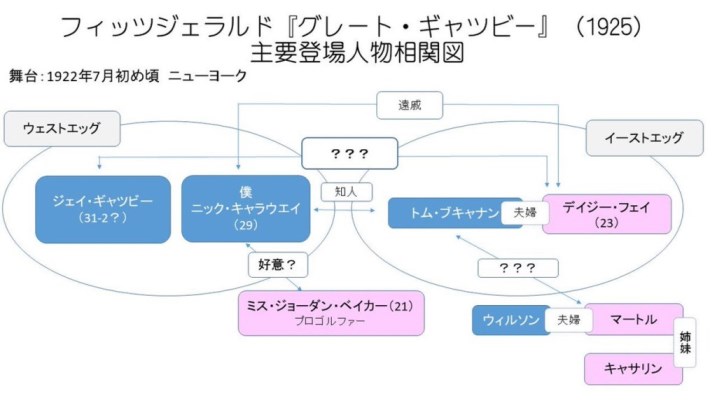
 (●2013年にバズ・ラーマン監督、レオナルド・ディカプリオ主演で再映画化された。1974年のジャック・クレイトン監督のロバート・レッドフォード、ミア・ファロー版は、当初はスティーブ・マックィーン、アリ・マックグロー主演で計画されていて、それがこの二人に落ち着いたのだが、村上春樹氏などは「落ち着きが悪い」としていた(ただし、フランシス・フォード・コッポラの脚本を評価していた)。個人的には、デイジー役のミア・ファローは登場するなり心身症的なイメージで、一方、ロバート・レッドフォードは健全すぎたのでアンバランスに感じた。レオナルド・ディカプリオ版におけるディカプリオの方が主人公のイメージに合っていたが(ディカプリオが家系
(●2013年にバズ・ラーマン監督、レオナルド・ディカプリオ主演で再映画化された。1974年のジャック・クレイトン監督のロバート・レッドフォード、ミア・ファロー版は、当初はスティーブ・マックィーン、アリ・マックグロー主演で計画されていて、それがこの二人に落ち着いたのだが、村上春樹氏などは「落ち着きが悪い」としていた(ただし、フランシス・フォード・コッポラの脚本を評価していた)。個人的には、デイジー役のミア・ファローは登場するなり心身症的なイメージで、一方、ロバート・レッドフォードは健全すぎたのでアンバランスに感じた。レオナルド・ディカプリオ版におけるディカプリオの方が主人公のイメージに合っていたが(ディカプリオが家系 的に4分の3ドイツ系であるというのもあるか)、キャリー・マリガン演じるデイジーが、完全にギャツビーを取り巻く俗人たちの1人として埋没していた。セットや衣装はレッドフォード版の方がお金をかけていた。ディカプリオ版も金はかけていたが、CGできらびやかさを出そうとしたりしていて、それが華やかと言うより騒々しい感じがした。目まぐるしく移り変わる映像は、バズ・ラーマン監督の「ムーラン・ルージュ」('01年)あたりからの手法だろう。ディカプリオだから何とか持っているが、「ムーラン・ルージュ」ではユアン・マクレガーもニコール・キッドマンもセット(CG含む)の中に埋もれていた。)
的に4分の3ドイツ系であるというのもあるか)、キャリー・マリガン演じるデイジーが、完全にギャツビーを取り巻く俗人たちの1人として埋没していた。セットや衣装はレッドフォード版の方がお金をかけていた。ディカプリオ版も金はかけていたが、CGできらびやかさを出そうとしたりしていて、それが華やかと言うより騒々しい感じがした。目まぐるしく移り変わる映像は、バズ・ラーマン監督の「ムーラン・ルージュ」('01年)あたりからの手法だろう。ディカプリオだから何とか持っているが、「ムーラン・ルージュ」ではユアン・マクレガーもニコール・キッドマンもセット(CG含む)の中に埋もれていた。)

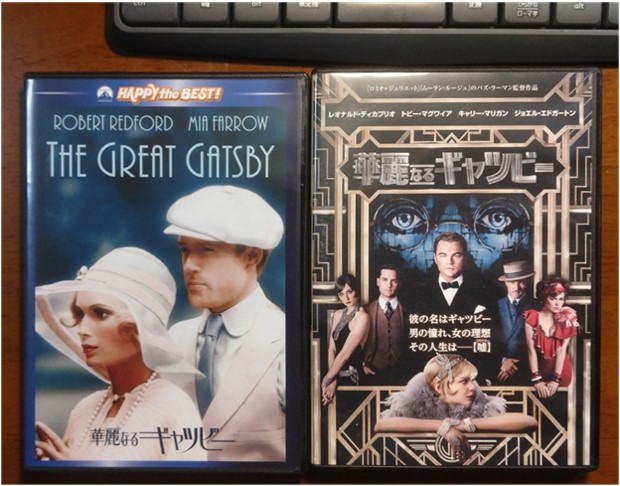
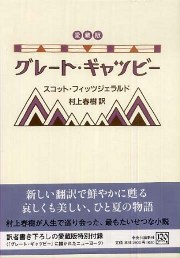
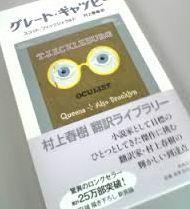 【1957年文庫化[角川文庫(大貫三郎訳『華麗なるギャツビー』)]/1974年再文庫化[早川文庫(橋本福夫訳『華麗なるギャツビー』)]/1974年再文庫化[新潮文庫(野崎孝訳『偉大なるギャツビー』)・1989年改版(野崎孝訳『グレート・ギャツビー』)]/1978年再文庫化[旺文社文庫(橋本福夫訳『華麗なるギャツビー』)]/1978年再文庫化[集英社文庫(野崎孝訳『偉大なギャツビー』]/2006年新書化[中央公論新社・村上春樹翻訳ライブラリー(『グレート・ギャツビー』]/2009年再文庫化[光文社古典新訳文庫(小川高義訳『グレート・ギャツビー』)】[左]『
【1957年文庫化[角川文庫(大貫三郎訳『華麗なるギャツビー』)]/1974年再文庫化[早川文庫(橋本福夫訳『華麗なるギャツビー』)]/1974年再文庫化[新潮文庫(野崎孝訳『偉大なるギャツビー』)・1989年改版(野崎孝訳『グレート・ギャツビー』)]/1978年再文庫化[旺文社文庫(橋本福夫訳『華麗なるギャツビー』)]/1978年再文庫化[集英社文庫(野崎孝訳『偉大なギャツビー』]/2006年新書化[中央公論新社・村上春樹翻訳ライブラリー(『グレート・ギャツビー』]/2009年再文庫化[光文社古典新訳文庫(小川高義訳『グレート・ギャツビー』)】[左]『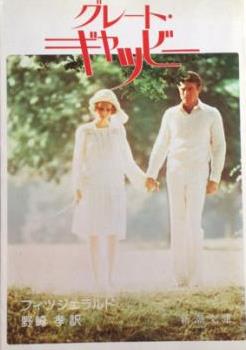
 「華麗なるギャツビー」●原題:THE GREAT GATSBY●制作年:1974年●制作国:アメリカ●監督:ジャック・クレイトン●製作:オデヴィッド・メリック●脚本:
「華麗なるギャツビー」●原題:THE GREAT GATSBY●制作年:1974年●制作国:アメリカ●監督:ジャック・クレイトン●製作:オデヴィッド・メリック●脚本: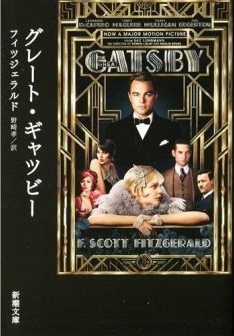
 「華麗なるギャツビー」●原題:THE GREAT GATSBY●制作年:2013年●制作国:アメリカ●監督:バズ・ラーマン●製作:ダグラス・ウィック/バズ・ラーマン/ルーシー・フィッシャー/キャサリン・ナップマン/キャサリン・マーティン●脚本:バズ・ラーマン/クレイグ・ピアース●撮影:サイモン・ダガン●音楽:クレイグ・アームストロング●原作:スコット・フィッツジェラルド●時間
「華麗なるギャツビー」●原題:THE GREAT GATSBY●制作年:2013年●制作国:アメリカ●監督:バズ・ラーマン●製作:ダグラス・ウィック/バズ・ラーマン/ルーシー・フィッシャー/キャサリン・ナップマン/キャサリン・マーティン●脚本:バズ・ラーマン/クレイグ・ピアース●撮影:サイモン・ダガン●音楽:クレイグ・アームストロング●原作:スコット・フィッツジェラルド●時間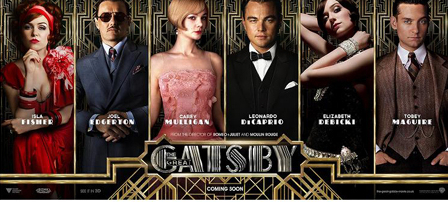 :143分●出演:レオナルド・ディカプリオ/トビー・マグワイア/キャリー・マリガン/ジョエル・エドガートン/アイラ・フィッシャー/ジェイソン・クラーク/エリザベス・デビッキ/ジャック・トンプソン/アミターブ・バッチャン●日本公開:2013/06●配給:ワーナー・ブラザース(評価:★★★)
:143分●出演:レオナルド・ディカプリオ/トビー・マグワイア/キャリー・マリガン/ジョエル・エドガートン/アイラ・フィッシャー/ジェイソン・クラーク/エリザベス・デビッキ/ジャック・トンプソン/アミターブ・バッチャン●日本公開:2013/06●配給:ワーナー・ブラザース(評価:★★★)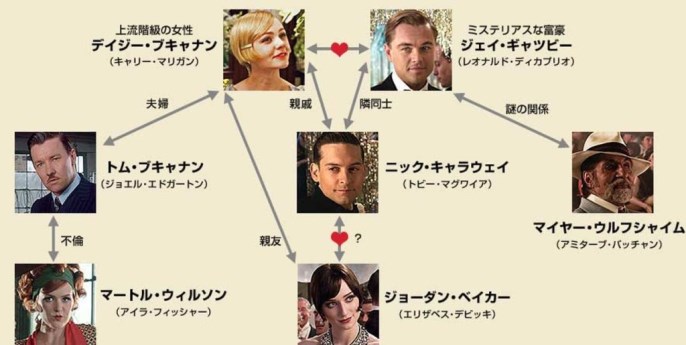
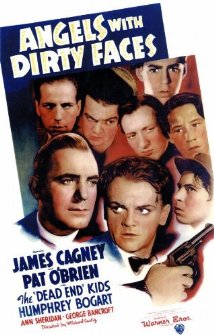
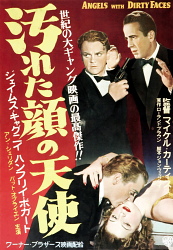


 幼い頃に不良仲間だったロッキー(ジェームズ・キャグニー)とジェリー(パット・オブ
幼い頃に不良仲間だったロッキー(ジェームズ・キャグニー)とジェリー(パット・オブ ライエン)だが、ロッキーは、2人でやった盗みの罪を自分1人で被ったことから転落の道を辿り、今やいっぱしのギャングとして、街の不良少年のヒーローとなっていた。ある日、刑務所を出所したばかりのロッキーは、今では神父となって貧しい少年達にスポーツを教えているジェリーを訪ね、旧交を温めるも、一方で、金を巡るトラブルで悪徳弁護士(ハンフリー・ボガート)を殺し、警官との大立ち回りの末に逮捕され、裁判で死刑宣告を受ける―。
ライエン)だが、ロッキーは、2人でやった盗みの罪を自分1人で被ったことから転落の道を辿り、今やいっぱしのギャングとして、街の不良少年のヒーローとなっていた。ある日、刑務所を出所したばかりのロッキーは、今では神父となって貧しい少年達にスポーツを教えているジェリーを訪ね、旧交を温めるも、一方で、金を巡るトラブルで悪徳弁護士(ハンフリー・ボガート)を殺し、警官との大立ち回りの末に逮捕され、裁判で死刑宣告を受ける―。 自らが死刑なるというのに「電気椅子に座るのなんか、床屋の椅子に座るのと同じだ」と言って平然としているロッキー。このままロッキーにギャングに相応しい堂々とした死に方をされては、少年達がますます彼を敬愛することになるであろうことを危惧したジェリーは、ギャングらしく死のうとするロッキーに対し、全く逆の行動を取るよう最後の頼みを託す―。
自らが死刑なるというのに「電気椅子に座るのなんか、床屋の椅子に座るのと同じだ」と言って平然としているロッキー。このままロッキーにギャングに相応しい堂々とした死に方をされては、少年達がますます彼を敬愛することになるであろうことを危惧したジェリーは、ギャングらしく死のうとするロッキーに対し、全く逆の行動を取るよう最後の頼みを託す―。 でも、ちょっと冷静になって考えると、神父がロッキーに託した願いというのは、ロッキーにとって、自分のように誤った道を歩むことのないようにという子供達へのメッセージになるのかも知れないですが、同時に、自ら人生を全否定せしめるようなものであり、それを受ける側(ロッキー)もともかく、頼む方(神父)も、いくら相手と強い友情で結ばれているとは言っても、よくこんな酷なことを頼んだなあという感じも。ただし、日本でも「大岡越前」でほぼ同じストーリーの話があるそうです。
でも、ちょっと冷静になって考えると、神父がロッキーに託した願いというのは、ロッキーにとって、自分のように誤った道を歩むことのないようにという子供達へのメッセージになるのかも知れないですが、同時に、自ら人生を全否定せしめるようなものであり、それを受ける側(ロッキー)もともかく、頼む方(神父)も、いくら相手と強い友情で結ばれているとは言っても、よくこんな酷なことを頼んだなあという感じも。ただし、日本でも「大岡越前」でほぼ同じストーリーの話があるそうです。 結局、ロッキーは刑吏らにも嘲られながら死んでいくわけで、死に行く者に対してこんなキツイお願いはないだろうなあと。
結局、ロッキーは刑吏らにも嘲られながら死んでいくわけで、死に行く者に対してこんなキツイお願いはないだろうなあと。
 「汚れた顔の天使」●原題:ANGEL WITH DIRTY FACE●制作年:1938年●制作国:アメリカ●監督:マイケル・カーティス●製作:サミュエル・ビショフ●原案:ローランド・ブラウン●脚本:ジョン・ウェクスリー/ウォーレン・ダフ/ローランド・ブラウン●撮影:ソル・ポリート●音楽:マックス・スタイナー●時間:98分●出演:ジェームズ・キャグニー/パット・オブライエン/ハンフリー・ボガート/アン・シェリダン/ジョージ・バンクロフト●日本公開:1939/11●配給:ワーナー・ブラザーズ(評価:★★★★)
「汚れた顔の天使」●原題:ANGEL WITH DIRTY FACE●制作年:1938年●制作国:アメリカ●監督:マイケル・カーティス●製作:サミュエル・ビショフ●原案:ローランド・ブラウン●脚本:ジョン・ウェクスリー/ウォーレン・ダフ/ローランド・ブラウン●撮影:ソル・ポリート●音楽:マックス・スタイナー●時間:98分●出演:ジェームズ・キャグニー/パット・オブライエン/ハンフリー・ボガート/アン・シェリダン/ジョージ・バンクロフト●日本公開:1939/11●配給:ワーナー・ブラザーズ(評価:★★★★)



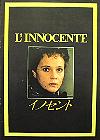 「イノセント」は1976年のイタリア・フランス合作映画で、ルキノ・ヴィスコンティ(1906‐1976)の最後の監督作品(公開されたのは没後)。
「イノセント」は1976年のイタリア・フランス合作映画で、ルキノ・ヴィスコンティ(1906‐1976)の最後の監督作品(公開されたのは没後)。
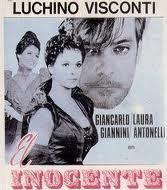 「イノセント」は、19世紀ローマの貴族男性(ジャンカルロ・ジャンニーニ)が主人公で、その彼が妻と愛人の間で揺れ動く様が描かれているのですが、〈妻〉が「青い体験」(Malizia、'73年/伊)、「続・青い体験」(Peccato veniale、'74年/伊)のラウラ・アントネッリで、〈愛
「イノセント」は、19世紀ローマの貴族男性(ジャンカルロ・ジャンニーニ)が主人公で、その彼が妻と愛人の間で揺れ動く様が描かれているのですが、〈妻〉が「青い体験」(Malizia、'73年/伊)、「続・青い体験」(Peccato veniale、'74年/伊)のラウラ・アントネッリで、〈愛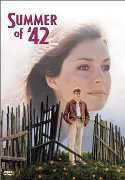
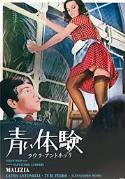 人〉が「おもいでの夏」(Summer of '42、'71年/米)のジェニファー・オニールなので、初めて見に行った時は、この2人を老ヴィスコンティがどう撮ったのかという興味もありました。貴族男性が愛人のもとへ行く際、妻に「君は昔から可愛い妹だった」などと言い訳して、それを妻ラウラ・アントネッリが許すというそれぞれのお気楽ぶりと従順ぶりにやや呆れるものの、最後になってみれば、実は女
人〉が「おもいでの夏」(Summer of '42、'71年/米)のジェニファー・オニールなので、初めて見に行った時は、この2人を老ヴィスコンティがどう撮ったのかという興味もありました。貴族男性が愛人のもとへ行く際、妻に「君は昔から可愛い妹だった」などと言い訳して、それを妻ラウラ・アントネッリが許すというそれぞれのお気楽ぶりと従順ぶりにやや呆れるものの、最後になってみれば、実は女 性の心と肉体は男が思っているほど単純なものではなかったということか。
性の心と肉体は男が思っているほど単純なものではなかったということか。 ラウラ・アントネッリ(あの「青い体験」の...)が妻でいながら、浮気などするなんて何というトンデモナイ奴かと思わせる部分も無きにしもあらずですが、浮気相手はジェニファー・オニール(あの「おもいでの夏」の...)だし...。
ラウラ・アントネッリ(あの「青い体験」の...)が妻でいながら、浮気などするなんて何というトンデモナイ奴かと思わせる部分も無きにしもあらずですが、浮気相手はジェニファー・オニール(あの「おもいでの夏」の...)だし...。 ジャンカルロ・ジャンニーニが演じる貴族は、自分の気持ちに純粋に従い過ぎるのかも。何となく憎めないキャラクターです(ジャンカルロ・ジャンニーニは、リナ・ウェルトミューラー監督の「流されて...」('75年/伊)の日本公開('78年)の時だったかに来日して舞台で挨拶していたが、意外と小柄だった印象がある)。結局、妻ラウラ・アントネッリの方も、義弟から紹介された作家に惚れられて自身も浮気に走り、そのことで夫は今さらのように自身の妻への愛着を再認識する―。
ジャンカルロ・ジャンニーニが演じる貴族は、自分の気持ちに純粋に従い過ぎるのかも。何となく憎めないキャラクターです(ジャンカルロ・ジャンニーニは、リナ・ウェルトミューラー監督の「流されて...」('75年/伊)の日本公開('78年)の時だったかに来日して舞台で挨拶していたが、意外と小柄だった印象がある)。結局、妻ラウラ・アントネッリの方も、義弟から紹介された作家に惚れられて自身も浮気に走り、そのことで夫は今さらのように自身の妻への愛着を再認識する―。 でもやはり気持ちはふらふらしていて、最後には作家の子を身籠った妻からの反撃を食い、愛人にも逃げられ、(自業自得とも言えるが)かなり惨めなことに...という、没落過程にある貴族層に個人のデカダン指向を重ね合わせたような、ヴィスコンティらしい結末へと繋がっていきます。
でもやはり気持ちはふらふらしていて、最後には作家の子を身籠った妻からの反撃を食い、愛人にも逃げられ、(自業自得とも言えるが)かなり惨めなことに...という、没落過程にある貴族層に個人のデカダン指向を重ね合わせたような、ヴィスコンティらしい結末へと繋がっていきます。 冒頭の「赤」を基調とした絢爛たる舞踏会シーンから映像美で魅せ、話の筋を追っていけば"貴族モノ"とは言え結構俗っぽい展開なのに、それでいて、ラウラ・アントネッリやジェニファー・オニールが、ヴィスコンティ映画の登場人物として"貴族然"として見えるのは、やはりヴィスコンティの演出のなせる業でしょうか(大河ドラマに出る女優が皆同じように見えるのとは似て非なるものか)。
冒頭の「赤」を基調とした絢爛たる舞踏会シーンから映像美で魅せ、話の筋を追っていけば"貴族モノ"とは言え結構俗っぽい展開なのに、それでいて、ラウラ・アントネッリやジェニファー・オニールが、ヴィスコンティ映画の登場人物として"貴族然"として見えるのは、やはりヴィスコンティの演出のなせる業でしょうか(大河ドラマに出る女優が皆同じように見えるのとは似て非なるものか)。 精神的かつ性的に抑圧されることで更にその魅力を強めていくラウラ・アントネ
精神的かつ性的に抑圧されることで更にその魅力を強めていくラウラ・アントネ ッリが、(期待に反することなく?)充分エロチックに描かれていました(この〈妻〉の役は〈夫〉に勝るとも劣らず人物造形的にかなり複雑なキャラクターのように思える)。この映画の撮影の時ヴィスコンティは既に車椅子での演出でしたが、う〜ん、70歳、死期を悟りながらも、随分こってりした作品を作っていたんだなあと思わされます(そこがまたいい)。
ッリが、(期待に反することなく?)充分エロチックに描かれていました(この〈妻〉の役は〈夫〉に勝るとも劣らず人物造形的にかなり複雑なキャラクターのように思える)。この映画の撮影の時ヴィスコンティは既に車椅子での演出でしたが、う〜ん、70歳、死期を悟りながらも、随分こってりした作品を作っていたんだなあと思わされます(そこがまたいい)。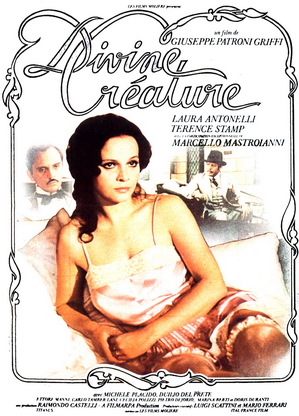
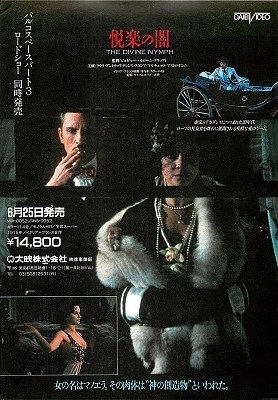 因みに、ラウラ・アントネッリは貴族や上流階級の役での出演作がこの他にも幾つかあって、「イノセント」の一作前のジュゼッペ・パトローニ・グリッフィ監督の1920年代のローマの社交界を舞台にした「悦楽の闇」('75年/伊・仏)では、裕福な貴族バニャスコ(テレンス・スタンプ)の愛人マノエラ役で出ています。バニャスコには他にも愛
因みに、ラウラ・アントネッリは貴族や上流階級の役での出演作がこの他にも幾つかあって、「イノセント」の一作前のジュゼッペ・パトローニ・グリッフィ監督の1920年代のローマの社交界を舞台にした「悦楽の闇」('75年/伊・仏)では、裕福な貴族バニャスコ(テレンス・スタンプ)の愛人マノエラ役で出ています。バニャスコには他にも愛 人がいて、愛想をつかしたマノエラは彼の元を去りますが、バニャスコは、15歳の時にある男に処女を奪われて以来、男性不信になっていたというマノエラ
人がいて、愛想をつかしたマノエラは彼の元を去りますが、バニャスコは、15歳の時にある男に処女を奪われて以来、男性不信になっていたというマノエラ の話から、その男がいとこのミケーレ(マルチェロ・マストロヤンニ)であることを偶然り、ミケーレに嫉妬心を抱きます。彼は一計を案じ、ミケーレにマノエラを近づ
の話から、その男がいとこのミケーレ(マルチェロ・マストロヤンニ)であることを偶然り、ミケーレに嫉妬心を抱きます。彼は一計を案じ、ミケーレにマノエラを近づ け苦しみを与えようとしたところ、ミケーレはいまだにマノエラを愛しており、マノエラの心も動いたため、バニャスコはますます苦しみ、最期は自殺に追い込まれるというもの。もとはと言えば男が悪いのですが、女はバニャスコ、ミケーレ以外にもミケーレ・プラチド(監督としても活躍)演じる男とも繋がりがあって、実
け苦しみを与えようとしたところ、ミケーレはいまだにマノエラを愛しており、マノエラの心も動いたため、バニャスコはますます苦しみ、最期は自殺に追い込まれるというもの。もとはと言えば男が悪いのですが、女はバニャスコ、ミケーレ以外にもミケーレ・プラチド(監督としても活躍)演じる男とも繋がりがあって、実 は彼女のほうこそ男を滅ぼすファム・ファータルだったということになるかと
は彼女のほうこそ男を滅ぼすファム・ファータルだったということになるかと 思います。キャストは豪勢だし、ラウラ・アントネッリの衣裳も絢爛なのですが、ストーリーがごちゃごちゃしていて、単なる恋愛泥沼劇にになってる印象も受けました。ラウラ・アントネッリも頑張って演技してるし、テレンス・スタンプは意外と役が合っていましたが、やはり、役者を集めるだけではダメなのだろなあ。
思います。キャストは豪勢だし、ラウラ・アントネッリの衣裳も絢爛なのですが、ストーリーがごちゃごちゃしていて、単なる恋愛泥沼劇にになってる印象も受けました。ラウラ・アントネッリも頑張って演技してるし、テレンス・スタンプは意外と役が合っていましたが、やはり、役者を集めるだけではダメなのだろなあ。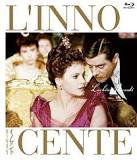
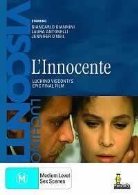
 「イノセント」●原題:L'INNOCENTE●制作年:1976年●制作国:イタリア・フランス●監督:ルキノ・ヴィスコンティ●製作:ジョヴァンニ・ベルトルッチ●脚本:スーゾ・チェッキ・ダミーコ/エンリコ・メディオーリ/ルキノ・ヴィスコンティ●撮影:パスクァリーノ・デ・サンティス●音楽:フランコ・マンニーノ●原作:ガブリエレ・ダヌンツィオ「罪なき者」●時間:129分●出演:ジャンカルロ・ジャンニーニ/ラウラ・アントネッリ/ジェニファー・オニール/マッシモ・ジロッティ/ディディエ・オードパン/マルク・ポレル/リーナ・モレッリ/マリー・デュボア/ディディエ・オードバン●日本公開:1979/03●最初に観た場所:池袋文
「イノセント」●原題:L'INNOCENTE●制作年:1976年●制作国:イタリア・フランス●監督:ルキノ・ヴィスコンティ●製作:ジョヴァンニ・ベルトルッチ●脚本:スーゾ・チェッキ・ダミーコ/エンリコ・メディオーリ/ルキノ・ヴィスコンティ●撮影:パスクァリーノ・デ・サンティス●音楽:フランコ・マンニーノ●原作:ガブリエレ・ダヌンツィオ「罪なき者」●時間:129分●出演:ジャンカルロ・ジャンニーニ/ラウラ・アントネッリ/ジェニファー・オニール/マッシモ・ジロッティ/ディディエ・オードパン/マルク・ポレル/リーナ・モレッリ/マリー・デュボア/ディディエ・オードバン●日本公開:1979/03●最初に観た場所:池袋文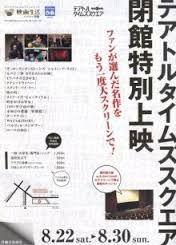



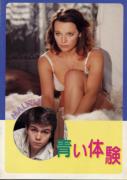
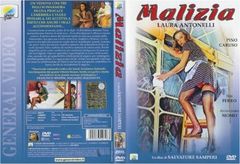
 ●製作:シルヴィオ・クレメンテッリ●脚本:オッタヴィオ・ジェンマ/アレッサンドロ・パレンゾ/サルヴァトーレ・サンペリ●撮影:ヴィットリオ・ストラーロ●音楽:フレッド・ボンガスト●時間:
●製作:シルヴィオ・クレメンテッリ●脚本:オッタヴィオ・ジェンマ/アレッサンドロ・パレンゾ/サルヴァトーレ・サンペリ●撮影:ヴィットリオ・ストラーロ●音楽:フレッド・ボンガスト●時間: 98分●出演:ラウラ・アントネッリ(Laura Antonelli)/アレッサンドロ・モモ/テューリ・フェッロ/アンジェラ・ルース/ピノ・カルーソ/ティナ・オーモン/ジャン・ルイギ・チリッジ●日本公開:1974/10●配給:ワーナー・ブラザース●最初に観た場所:三鷹オスカー(80-04-05) (評価★★★★)●併映:「続・青い体験」(サルヴァトーレ・サンペリ)/「新・青い体験」(ベドロ・マソ)
98分●出演:ラウラ・アントネッリ(Laura Antonelli)/アレッサンドロ・モモ/テューリ・フェッロ/アンジェラ・ルース/ピノ・カルーソ/ティナ・オーモン/ジャン・ルイギ・チリッジ●日本公開:1974/10●配給:ワーナー・ブラザース●最初に観た場所:三鷹オスカー(80-04-05) (評価★★★★)●併映:「続・青い体験」(サルヴァトーレ・サンペリ)/「新・青い体験」(ベドロ・マソ)
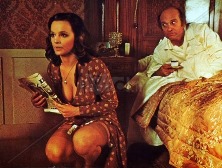

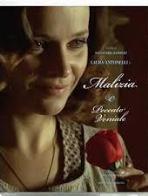 「
「
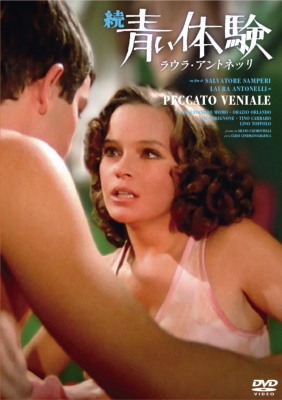
 「続・青い体験」●原題:PECCATO VENIALE●制作年:1974年●制作国:イタリア●監督:サルヴァトーレ・サンペリ●製作:シルヴィオ・クレメンテッリ●脚本:オッタヴィオ・ジェンマ/アレッサンドロ・パレンゾ●撮影:トニーノ・デリ・コリ●音楽:フレ
「続・青い体験」●原題:PECCATO VENIALE●制作年:1974年●制作国:イタリア●監督:サルヴァトーレ・サンペリ●製作:シルヴィオ・クレメンテッリ●脚本:オッタヴィオ・ジェンマ/アレッサンドロ・パレンゾ●撮影:トニーノ・デリ・コリ●音楽:フレ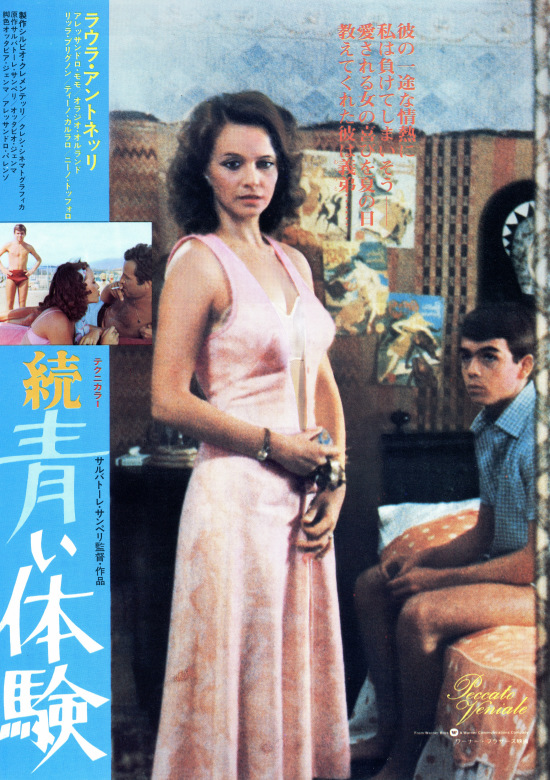 ッド・ボンガスト●時間:98分●出演:ラウラ・アントネッリ/アレッサンドロ・モモ/オラツィオ・オルランド/リッラ・ブリグノン/モニカ・ゲリトーレ/リノ・バンフィ●日本公開:1975/08●配給:ワーナー・ブラザース●最初に観た場所:三鷹オスカー(80-04-05) (評価★★★☆)●併映:「青い体験」(サルヴァトーレ・サンペリ)/「新・青い体験」(ベドロ・マソ)
ッド・ボンガスト●時間:98分●出演:ラウラ・アントネッリ/アレッサンドロ・モモ/オラツィオ・オルランド/リッラ・ブリグノン/モニカ・ゲリトーレ/リノ・バンフィ●日本公開:1975/08●配給:ワーナー・ブラザース●最初に観た場所:三鷹オスカー(80-04-05) (評価★★★☆)●併映:「青い体験」(サルヴァトーレ・サンペリ)/「新・青い体験」(ベドロ・マソ)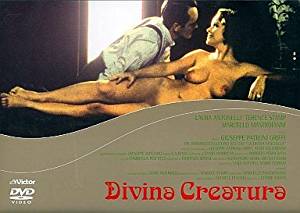
 「悦楽の闇」●原題:THE DIVINE NYMPH●制作年:1975年●制作国:イタリア・フランス●監督:ジュゼッペ・パトローニ・グリッフィ●製作:ルイジ・スカチーニ/マリオ・フェッラーリ●脚本:ジュゼッペ・パトローニ・グリッフィ/アルフィオ・ヴァルダルニーニ●撮影:ジュゼッペ・ロトゥンノ●音楽:C・A・ビクシオ●原作:ルチアーノ・ズッコリ●時間:130分●出演:ラウラ・アントネッリ/テレンス・スタンプ/マルチェロ・マストロヤンニ/ミケーレ・プラチド/エットレ・マンニ/デュリオ・デル・プレート/マリナ・ベルティ/ドリス・デュランティ/カルロ・タンベルラーニ/ティナ・オーモン●日本公開:1987/06●配給:ケイブルホーグ=大映●最初に観た場所:渋谷・パルコスペース3(87-06-06)(評価★★★)
「悦楽の闇」●原題:THE DIVINE NYMPH●制作年:1975年●制作国:イタリア・フランス●監督:ジュゼッペ・パトローニ・グリッフィ●製作:ルイジ・スカチーニ/マリオ・フェッラーリ●脚本:ジュゼッペ・パトローニ・グリッフィ/アルフィオ・ヴァルダルニーニ●撮影:ジュゼッペ・ロトゥンノ●音楽:C・A・ビクシオ●原作:ルチアーノ・ズッコリ●時間:130分●出演:ラウラ・アントネッリ/テレンス・スタンプ/マルチェロ・マストロヤンニ/ミケーレ・プラチド/エットレ・マンニ/デュリオ・デル・プレート/マリナ・ベルティ/ドリス・デュランティ/カルロ・タンベルラーニ/ティナ・オーモン●日本公開:1987/06●配給:ケイブルホーグ=大映●最初に観た場所:渋谷・パルコスペース3(87-06-06)(評価★★★)



 ハーマン・ローチャー●撮影:ロバート・サーティー
ハーマン・ローチャー●撮影:ロバート・サーティー
 楽:
楽: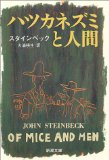

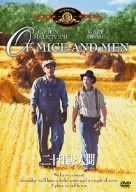
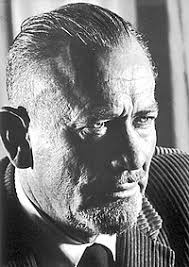
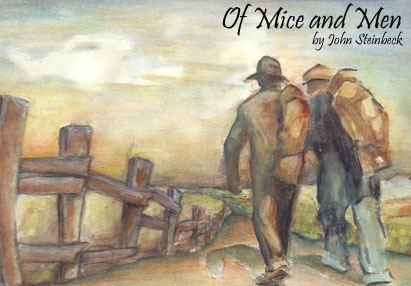
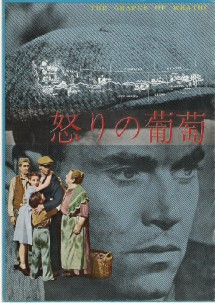

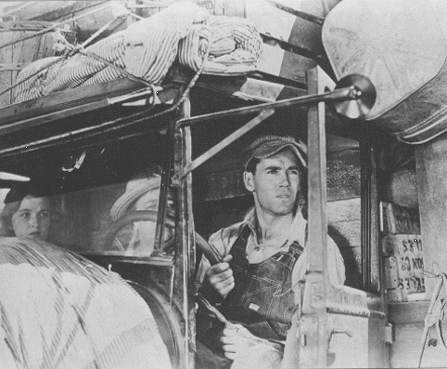 スタインベックはこの作品でその名を知られるようなり、2年後に発表した、旱魃と耕作機械によって土地を奪われた農民たちのカリフォルニアへの旅を描いた『怒りの葡萄』('39年)でピューリツァー賞を受賞しますが、「二十日鼠と人間」「怒りの葡萄」の両方とも映画化されており、「二十日鼠と人間」は'39年と'92年に映画化されていますが、ゲイリー・シニーズが監督・主演した「
スタインベックはこの作品でその名を知られるようなり、2年後に発表した、旱魃と耕作機械によって土地を奪われた農民たちのカリフォルニアへの旅を描いた『怒りの葡萄』('39年)でピューリツァー賞を受賞しますが、「二十日鼠と人間」「怒りの葡萄」の両方とも映画化されており、「二十日鼠と人間」は'39年と'92年に映画化されていますが、ゲイリー・シニーズが監督・主演した「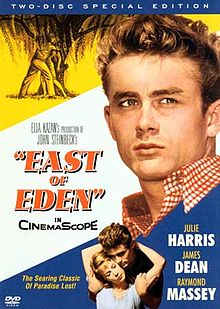
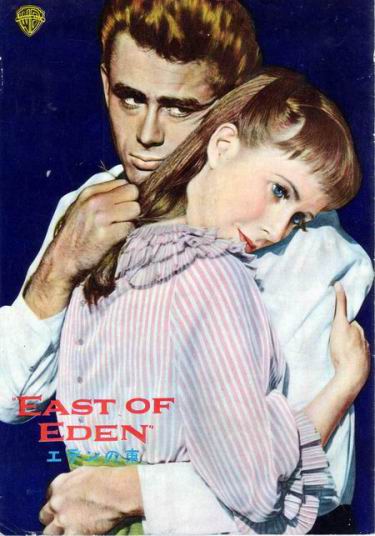
 ジェームズ・ディーンがその演技への評価を確立したとされるエリア・カザン監督の「エデンの東」('55年)も、スタインベックの『エデンの東』('50年)がベースになっているのですが、原作が南北戦争から第1次世界大戦までの60年間の2つの家族の3代にわたる歴史を綴った4巻56章から成る膨大な物語であるのに対し、映画の中で描かれているのは最後のほんの一時期のみで1家族2世代の話に圧縮されており、実質的には、父に好かれたいがそれが叶わないケイレブ(キャル)・トラスク (ジェームズ・ディーン)の苦悩の物語となっています。「エデンの東」の原作は読んでいませんが、スタインベックは後期作品ほど大味の嫌いがあるらしく(エリア・カザンの翻案は当然の選択だったのだろう)、そうした意味では『二十日鼠と人間』は、スタインベックに「文学の神様」が宿った時期の作品であると言えるかと思います。
ジェームズ・ディーンがその演技への評価を確立したとされるエリア・カザン監督の「エデンの東」('55年)も、スタインベックの『エデンの東』('50年)がベースになっているのですが、原作が南北戦争から第1次世界大戦までの60年間の2つの家族の3代にわたる歴史を綴った4巻56章から成る膨大な物語であるのに対し、映画の中で描かれているのは最後のほんの一時期のみで1家族2世代の話に圧縮されており、実質的には、父に好かれたいがそれが叶わないケイレブ(キャル)・トラスク (ジェームズ・ディーン)の苦悩の物語となっています。「エデンの東」の原作は読んでいませんが、スタインベックは後期作品ほど大味の嫌いがあるらしく(エリア・カザンの翻案は当然の選択だったのだろう)、そうした意味では『二十日鼠と人間』は、スタインベックに「文学の神様」が宿った時期の作品であると言えるかと思います。

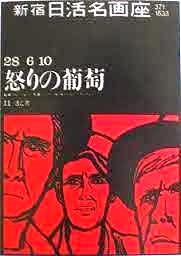 「怒りの葡萄」●原題:THE GRAPES OF WRATH●制作年:1940年●制作国:アメリカ●監督:ジョン・フォード●製作:ダリル・F・ザナック●脚本:ナナリー・ジョンソン●撮影:グレッグ・トーランド●音楽:アルフレッド・ニューマン●原作:ジョン・スタインベック●時間:128分●出演:ヘンリー・フォンダ/ジェーン・ダーウェル/ジョン・キャラダイン/チャーリー・グレイプウィン/ドリス・ボードン/ラッセル・シンプソン/メエ・マーシュ/ウォード・ボンド●日本公開:1963/01●配給:昭映フィルム●最初に観た場所:吉祥寺ジャヴ50(84-07-14)(評価:★★★★)
「怒りの葡萄」●原題:THE GRAPES OF WRATH●制作年:1940年●制作国:アメリカ●監督:ジョン・フォード●製作:ダリル・F・ザナック●脚本:ナナリー・ジョンソン●撮影:グレッグ・トーランド●音楽:アルフレッド・ニューマン●原作:ジョン・スタインベック●時間:128分●出演:ヘンリー・フォンダ/ジェーン・ダーウェル/ジョン・キャラダイン/チャーリー・グレイプウィン/ドリス・ボードン/ラッセル・シンプソン/メエ・マーシュ/ウォード・ボンド●日本公開:1963/01●配給:昭映フィルム●最初に観た場所:吉祥寺ジャヴ50(84-07-14)(評価:★★★★) 
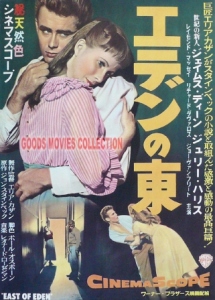
 「エデンの東」●原題:EAST OF EDEN●制作年:1955年●制作国:アメリカ●監督・製作:エリア・カザン●脚本:ポール・オスボーン●撮影:テッド・マッコード●音楽:レナード・ローゼンマン●原作:ジョン・スタインベック●時間:115分●出演:ジェームズ・ディーン/ジュリー・ハリス/レイモンド・マッセイ/バール・アイヴス/リチャード・ダヴァロス/ジュー・ヴェン・フリート/
「エデンの東」●原題:EAST OF EDEN●制作年:1955年●制作国:アメリカ●監督・製作:エリア・カザン●脚本:ポール・オスボーン●撮影:テッド・マッコード●音楽:レナード・ローゼンマン●原作:ジョン・スタインベック●時間:115分●出演:ジェームズ・ディーン/ジュリー・ハリス/レイモンド・マッセイ/バール・アイヴス/リチャード・ダヴァロス/ジュー・ヴェン・フリート/
 アルバート・デッカー/ロイス・スミス/バール・アイヴス●日本公開:1955/10●配給:ワーナ
アルバート・デッカー/ロイス・スミス/バール・アイヴス●日本公開:1955/10●配給:ワーナ ー・ブラザース●最初に観た場所:池袋文芸坐(79-02-18)●2回目:テアトル吉祥寺(82-09-23)(評価:★★★★)●併映(1回目):「理由なき反抗」(ニコラス・レイ)●併映(2回目):「ウェストサイド物語」(ロバート・ワイズ)
ー・ブラザース●最初に観た場所:池袋文芸坐(79-02-18)●2回目:テアトル吉祥寺(82-09-23)(評価:★★★★)●併映(1回目):「理由なき反抗」(ニコラス・レイ)●併映(2回目):「ウェストサイド物語」(ロバート・ワイズ)
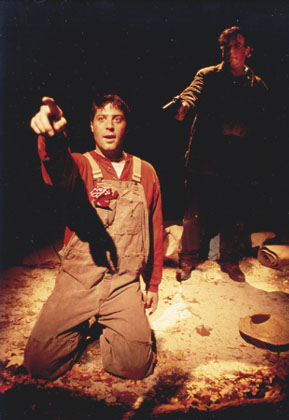 【1952年文庫化[三笠文庫(大門一男:訳)]/1953年文庫化[新潮文庫(大門一男:訳)]/1955年文庫化[河出文庫(石川信夫:訳)]/1960年文庫化[角川文庫(杉木喬:訳)]/1970年文庫化[旺文社文庫(繁尾久:訳)]/1994年再文庫化[新潮文庫(『ハツカネズミと人間』(大浦暁生;訳)]】
【1952年文庫化[三笠文庫(大門一男:訳)]/1953年文庫化[新潮文庫(大門一男:訳)]/1955年文庫化[河出文庫(石川信夫:訳)]/1960年文庫化[角川文庫(杉木喬:訳)]/1970年文庫化[旺文社文庫(繁尾久:訳)]/1994年再文庫化[新潮文庫(『ハツカネズミと人間』(大浦暁生;訳)]】
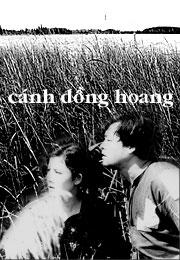

 Lam Toi
Lam Toi
.jpg) 舞台はベトナム戦争後期の1972年のメコンデルタ。葦の茂る水上家屋に住む若い家族(夫婦は解放戦線の連絡員をしている)の愛情溢れる暮らしと、命の危険に晒されながらも連絡員としての任務を果たそうとするしたたかな様を、リアルに描いています(1981年・第12回「モスクワ国際映画祭 最優秀作品賞」受賞作)。
舞台はベトナム戦争後期の1972年のメコンデルタ。葦の茂る水上家屋に住む若い家族(夫婦は解放戦線の連絡員をしている)の愛情溢れる暮らしと、命の危険に晒されながらも連絡員としての任務を果たそうとするしたたかな様を、リアルに描いています(1981年・第12回「モスクワ国際映画祭 最優秀作品賞」受賞作)。 いながらも、時に負傷者を助け、更には解放戦線の作戦を援護するなど、いつも沼地に腰まで浸かりながら八面六臂の活躍を見せます。ああ、こうしてアメリカ軍の侵攻を阻んだのだなあと思わせる"戦術解き明かし"のような内容ですが、最後に夫がヘリに囲まれて悲劇が―。
いながらも、時に負傷者を助け、更には解放戦線の作戦を援護するなど、いつも沼地に腰まで浸かりながら八面六臂の活躍を見せます。ああ、こうしてアメリカ軍の侵攻を阻んだのだなあと思わせる"戦術解き明かし"のような内容ですが、最後に夫がヘリに囲まれて悲劇が―。 映画的には、水面の高さでのカメラワークが素晴らしい(自分まで沼に浸かっている気分になった)一方で、ヘリからの空撮と地上から見たヘリとの距離感が整合しないなどの粗い作りの部分もありますが(予算的・技術的要因によるものかも)、そうしたことを勘案しても佳作だと思います。
映画的には、水面の高さでのカメラワークが素晴らしい(自分まで沼に浸かっている気分になった)一方で、ヘリからの空撮と地上から見たヘリとの距離感が整合しないなどの粗い作りの部分もありますが(予算的・技術的要因によるものかも)、そうしたことを勘案しても佳作だと思います。 「無人の野」●原題:CANH DONG HOANG●制作年:1980年●制作国:ベトナム●監督:グェン・ホン・セン●脚本:グェン・クァン・サン●撮影:ズオン・トゥアン・バ●音楽:チン・コン・ソン●時間:95分●出演:グェン・トゥイ・アン/ラム・トイ/グェン・ホン・トゥァン/ダオ・タイン・トゥイ●日本公開:1982/08●配給:「無人の野」普及委員会●最初に観た場所:高田馬場ACTミニシアター(83-03-19)(評価:★★★★)
「無人の野」●原題:CANH DONG HOANG●制作年:1980年●制作国:ベトナム●監督:グェン・ホン・セン●脚本:グェン・クァン・サン●撮影:ズオン・トゥアン・バ●音楽:チン・コン・ソン●時間:95分●出演:グェン・トゥイ・アン/ラム・トイ/グェン・ホン・トゥァン/ダオ・タイン・トゥイ●日本公開:1982/08●配給:「無人の野」普及委員会●最初に観た場所:高田馬場ACTミニシアター(83-03-19)(評価:★★★★)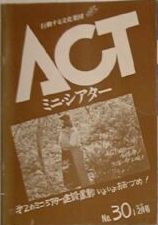
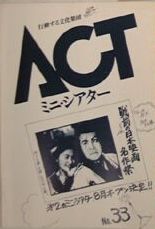

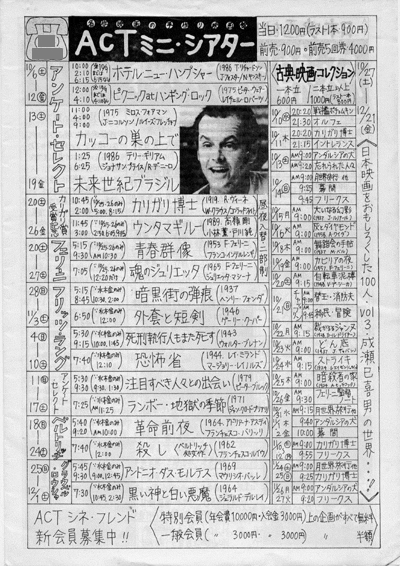
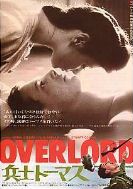
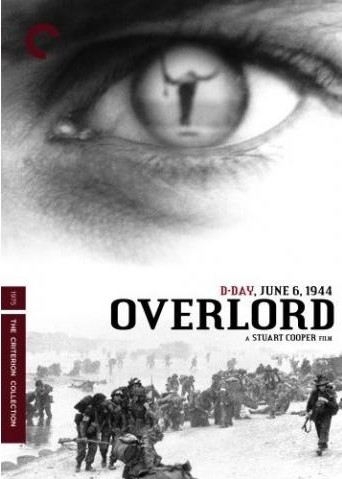
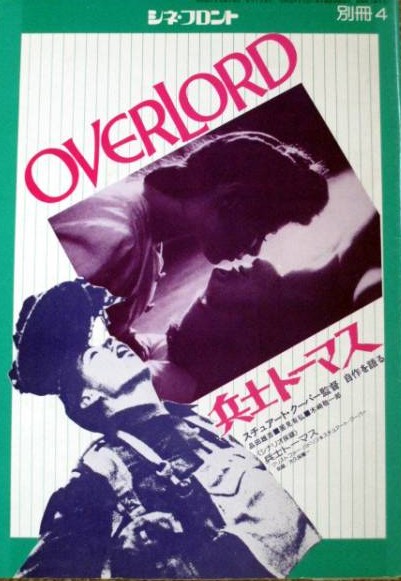

 第二次世界大戦中、イギリスに住むごく普通の二十歳の青年の元に召集令状が届く―。彼が両親に別れを告げて戦地に赴き、ノルマンディ上陸作戦において戦死するまでを、ドキュメンタリーフィルムを交えて淡々と描いた、ベルリン国際映画祭「審査員特別賞」受賞の佳作。
第二次世界大戦中、イギリスに住むごく普通の二十歳の青年の元に召集令状が届く―。彼が両親に別れを告げて戦地に赴き、ノルマンディ上陸作戦において戦死するまでを、ドキュメンタリーフィルムを交えて淡々と描いた、ベルリン国際映画祭「審査員特別賞」受賞の佳作。 と言っても、通常の戦争映画とは異なり、兵営における非人間的な部隊生活の中で主人公の将来が少しずつ奪われていくような様や、そうした中、村のダンス・ホールで知り合った若い娘への想いを抱くも、前線に送られることが決まって、束の間の若者らしい夢も立ち切れられ、21歳にして遺言状を書くに至るまでの心理的経緯など、ノルマンディに向かうまでに主人公の身辺及び心の中での出来事が映画の大部分を占めています。
と言っても、通常の戦争映画とは異なり、兵営における非人間的な部隊生活の中で主人公の将来が少しずつ奪われていくような様や、そうした中、村のダンス・ホールで知り合った若い娘への想いを抱くも、前線に送られることが決まって、束の間の若者らしい夢も立ち切れられ、21歳にして遺言状を書くに至るまでの心理的経緯など、ノルマンディに向かうまでに主人公の身辺及び心の中での出来事が映画の大部分を占めています。 モノクロですが、膨大な量を誇る大英帝国戦争博物館の未公開フィルムがふんだんに使われていて、ラストのノルマンディの戦闘シーンは、実際の空爆の映像なども交え、兵士の視点からの臨場感にあふれたものとなっています。
モノクロですが、膨大な量を誇る大英帝国戦争博物館の未公開フィルムがふんだんに使われていて、ラストのノルマンディの戦闘シーンは、実際の空爆の映像なども交え、兵士の視点からの臨場感にあふれたものとなっています。 主人公の青年は上陸艇から1歩踏み出したところで流れ弾に当たり、あまりにあっけなく死んでしまう―(普通の戦争映画ならここからがヤマなのだが、青年の視点から描かれたこの映画はここで終わる)。
主人公の青年は上陸艇から1歩踏み出したところで流れ弾に当たり、あまりにあっけなく死んでしまう―(普通の戦争映画ならここからがヤマなのだが、青年の視点から描かれたこの映画はここで終わる)。 自らの死に脅えつつも(彼は自分の死ぬ場面の悪夢に悩まされ続ける)、遺言状をしたためたぐらいですから、主人公には死の覚悟がそれなりあったかと思われますが、それでもやはり、戦わずしてノルマンディ上陸作戦の「第1号の犠牲者」となった彼にとって("彼"自身は勿論架空の人物であると思われるが)戦争とは何だったのか、果たして「犠牲者」ということで片付けてよいものなのかと考えさせられます。
自らの死に脅えつつも(彼は自分の死ぬ場面の悪夢に悩まされ続ける)、遺言状をしたためたぐらいですから、主人公には死の覚悟がそれなりあったかと思われますが、それでもやはり、戦わずしてノルマンディ上陸作戦の「第1号の犠牲者」となった彼にとって("彼"自身は勿論架空の人物であると思われるが)戦争とは何だったのか、果たして「犠牲者」ということで片付けてよいものなのかと考えさせられます。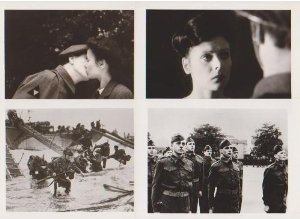
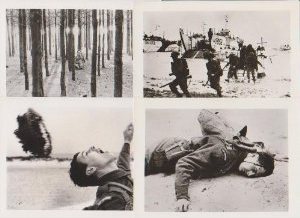 「兵士トーマス」●原題:OVERLORD●制作年:1975年●制作国:イギリス●監督:スチュアート・クーパー●製作:ジェームズ・クイン●脚本: クリストファー・ハドソン/スチュアート・クーパー●撮影:ジョン・オルコット●音楽:ポール・グラス●時間:84分●出演:ブライアン・スターナー/デヴィッド・ハリーズ/ ニコラス・ボール●日本公開:1978/07●配給:日本ヘラルド映画●最初に観た場所:自由が丘武蔵野推理(77-12-21)(評
「兵士トーマス」●原題:OVERLORD●制作年:1975年●制作国:イギリス●監督:スチュアート・クーパー●製作:ジェームズ・クイン●脚本: クリストファー・ハドソン/スチュアート・クーパー●撮影:ジョン・オルコット●音楽:ポール・グラス●時間:84分●出演:ブライアン・スターナー/デヴィッド・ハリーズ/ ニコラス・ボール●日本公開:1978/07●配給:日本ヘラルド映画●最初に観た場所:自由が丘武蔵野推理(77-12-21)(評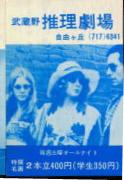
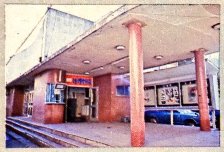

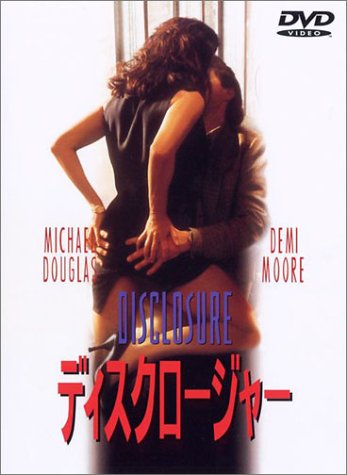
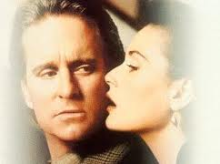
.jpg)
.jpg)


 ハイテク企業に勤めるトム・サンダース(マイケル・ダグラス)は、自分に内定していた副社長ポストに、社の創設者ボブ・ガーヴィン(ドナルド・サザーランド)が目をかけてきた野心溢れる女性メレディス(デミ・ムーア)が就任したことを知らされ唖然とする。彼女はかつてのトムの恋人だったのだ。そしてトムは就任したばかりの彼女に部屋に呼び出されて誘惑され、その誘いに負けそうになるも、かろうじて踏み止まり部屋を出る。しかし今度は、彼女から部屋でレイプをされそうになったと訴えられる―。
ハイテク企業に勤めるトム・サンダース(マイケル・ダグラス)は、自分に内定していた副社長ポストに、社の創設者ボブ・ガーヴィン(ドナルド・サザーランド)が目をかけてきた野心溢れる女性メレディス(デミ・ムーア)が就任したことを知らされ唖然とする。彼女はかつてのトムの恋人だったのだ。そしてトムは就任したばかりの彼女に部屋に呼び出されて誘惑され、その誘いに負けそうになるも、かろうじて踏み止まり部屋を出る。しかし今度は、彼女から部屋でレイプをされそうになったと訴えられる―。
 「
「 イケル・クライトン
イケル・クライトン たのが『アンドロメダ病原体』('69年)であり、『ジュラシック・パーク』('90年)などのバイオ・サスペンスや、ハーバード・メディカルスクールの出身でもあるだけに、TVドラマ「ER」のようなメディカル系に強かった印象があります(1994年にはテレビ(「ER」)、映画(「
たのが『アンドロメダ病原体』('69年)であり、『ジュラシック・パーク』('90年)などのバイオ・サスペンスや、ハーバード・メディカルスクールの出身でもあるだけに、TVドラマ「ER」のようなメディカル系に強かった印象があります(1994年にはテレビ(「ER」)、映画(「 映画としては凡作になってしまったと思いますが、マイケル・クライトンへの追悼と、「ライジング・サン」よりはまだ映画らしい映画になっているということで本作品を取り上げました。
映画としては凡作になってしまったと思いますが、マイケル・クライトンへの追悼と、「ライジング・サン」よりはまだ映画らしい映画になっているということで本作品を取り上げました。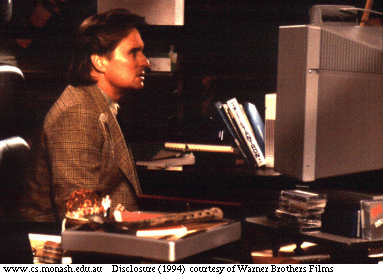 上司デミ・ムーアの誘いを断った主人公に対する上司の仕打ちの1つに、会社のサーバーへのアクセス権を奪ってしまうというのがあって、そのことで主人公は仕事が完全にストップしてしまいパニックに陥るというのが当時としてはすごく"現代風"の恐怖だなあと思われ、印象的に残りました。
上司デミ・ムーアの誘いを断った主人公に対する上司の仕打ちの1つに、会社のサーバーへのアクセス権を奪ってしまうというのがあって、そのことで主人公は仕事が完全にストップしてしまいパニックに陥るというのが当時としてはすごく"現代風"の恐怖だなあと思われ、印象的に残りました。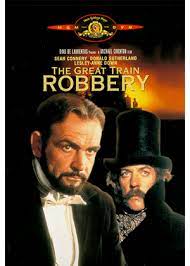
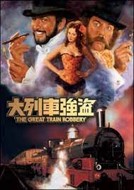
 マイケル・クライトン原作のその他の映画化作品では、マイケル・クライトン自身の脚本・監督で、ショーン・コネリーが主演した
マイケル・クライトン原作のその他の映画化作品では、マイケル・クライトン自身の脚本・監督で、ショーン・コネリーが主演した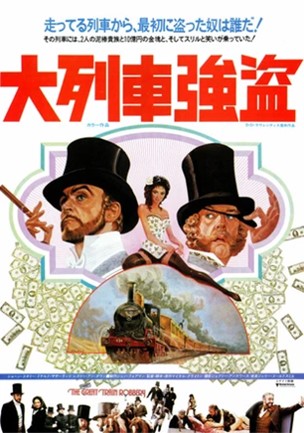 「大列車強盗」('78年/米)が面白かったです。ヴィクトリア朝時代のイギリスで実際に起きた事件を基に、怪盗とその仲間たちが厳重管理で列車輸送している莫大な金塊の強奪に挑むさまを描いた犯罪サスペンスで、ストーリーはいいし(1975年に出版された原作『大列車強
「大列車強盗」('78年/米)が面白かったです。ヴィクトリア朝時代のイギリスで実際に起きた事件を基に、怪盗とその仲間たちが厳重管理で列車輸送している莫大な金塊の強奪に挑むさまを描いた犯罪サスペンスで、ストーリーはいいし(1975年に出版された原作『大列車強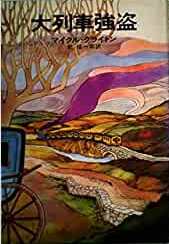
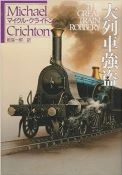 盗』('76年/早川書房、'81年/早川書房)は、今回取り上げた『ディスクロージャー』よりはっきり言って面白い)、怪盗ピアースを演じるショーン・コネリーをはじめ役者もいいです。ショーン・コネリー(当時48歳)は、桁の低い陸橋が何本も接近してくる中、それをよけながら疾走する列車の屋根を這い進んで行くというアクションをスタントなしでこなしています。
盗』('76年/早川書房、'81年/早川書房)は、今回取り上げた『ディスクロージャー』よりはっきり言って面白い)、怪盗ピアースを演じるショーン・コネリーをはじめ役者もいいです。ショーン・コネリー(当時48歳)は、桁の低い陸橋が何本も接近してくる中、それをよけながら疾走する列車の屋根を這い進んで行くというアクションをスタントなしでこなしています。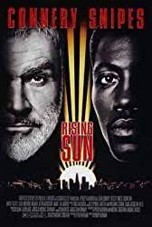
 「大列車強盗」と同じショーン・コネリー主演でフィリップ・カウフマンが監督した「ライジング・サン」('93年/米)は、ロサンゼルスに進出した日本企業のビルで殺人事件が発生し、ショーン・コネリー演じる刑事ジョン・コナーが捜査を進めるうち、文化の違いという壁にぶち当たるという、コネリーが製作総指揮と主演を兼ねたサスペンス・アクション。ネタバレになりますが、偽造ディスクを解明した女性がコナー刑事の愛人だったというオチは、裏ストーリーを暗示させるものの、あまりに説明不足。日本人の社員が黒服にサングラスだったり、日本語の使い方がヘンテコリンで笑わせます(もっと以前よりは良くはなっているが、この時点でまだ日本文化の認識の違いが窺えるのは仕方のないことか)。因みに、武満徹が劇中音楽を担当し、そのキャリアの中で唯一の外国映画音楽作品となりました。
「大列車強盗」と同じショーン・コネリー主演でフィリップ・カウフマンが監督した「ライジング・サン」('93年/米)は、ロサンゼルスに進出した日本企業のビルで殺人事件が発生し、ショーン・コネリー演じる刑事ジョン・コナーが捜査を進めるうち、文化の違いという壁にぶち当たるという、コネリーが製作総指揮と主演を兼ねたサスペンス・アクション。ネタバレになりますが、偽造ディスクを解明した女性がコナー刑事の愛人だったというオチは、裏ストーリーを暗示させるものの、あまりに説明不足。日本人の社員が黒服にサングラスだったり、日本語の使い方がヘンテコリンで笑わせます(もっと以前よりは良くはなっているが、この時点でまだ日本文化の認識の違いが窺えるのは仕方のないことか)。因みに、武満徹が劇中音楽を担当し、そのキャリアの中で唯一の外国映画音楽作品となりました。
 あともう1本、フランク・マーシャル監督の「コンゴ」('95年)というのもありました。映画的展開の狭い「ライジング・サン」や「ディスクロージャー」の失敗を反省材料にしたのか、今度は旧作('80年発表)ながら派手な見せ場のある『失われた黄金都市』を映画化したもので、アフリカ奥地で、レーザー通信の核となるダイヤモンドの鉱脈を調べていたトラヴィコム社の先発隊が全滅し、手掛かりは通信画面に映し出された"灰色の猿人"らしきものだけだった...というもの。この監督はあまり上手くない(本業は映画プロデューサー。妻のキャスリーン・ケネディと共に、多くのスピルバーグ作品を手がけている)。観終わって時間が無駄だったと思いましたが(一緒に観た人間と「もう今後(こんご)は観ない」と冗談を言い合った)、amazonのレビューでは高い評価を得ているみたいで、自分たちだけ違う映画を観たのかなあ(笑)。
あともう1本、フランク・マーシャル監督の「コンゴ」('95年)というのもありました。映画的展開の狭い「ライジング・サン」や「ディスクロージャー」の失敗を反省材料にしたのか、今度は旧作('80年発表)ながら派手な見せ場のある『失われた黄金都市』を映画化したもので、アフリカ奥地で、レーザー通信の核となるダイヤモンドの鉱脈を調べていたトラヴィコム社の先発隊が全滅し、手掛かりは通信画面に映し出された"灰色の猿人"らしきものだけだった...というもの。この監督はあまり上手くない(本業は映画プロデューサー。妻のキャスリーン・ケネディと共に、多くのスピルバーグ作品を手がけている)。観終わって時間が無駄だったと思いましたが(一緒に観た人間と「もう今後(こんご)は観ない」と冗談を言い合った)、amazonのレビューでは高い評価を得ているみたいで、自分たちだけ違う映画を観たのかなあ(笑)。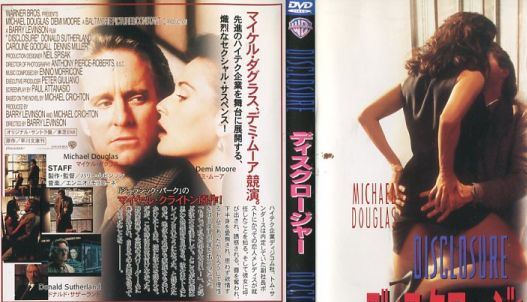 「ディスクロージャー」●原題:DISCLOSURE●制作年:1994年●制作国:アメリカ●監督:バリー・レヴィンソン●製作:バリー・レヴィンソン/マイケル・クライトン●脚本:ポール・アタナシオ●音楽:エンニオ・モリコーネ●撮影:アンソニー・ピアース=ロバーツ●原作:マイケル・クライトン●時間:128分●出演:マイケル・ダグラス/デミ・ムーア/ドナルド・サザーランド/キャロライン・グッドオール/デニス・ミラー/ロマ・マフィア/
「ディスクロージャー」●原題:DISCLOSURE●制作年:1994年●制作国:アメリカ●監督:バリー・レヴィンソン●製作:バリー・レヴィンソン/マイケル・クライトン●脚本:ポール・アタナシオ●音楽:エンニオ・モリコーネ●撮影:アンソニー・ピアース=ロバーツ●原作:マイケル・クライトン●時間:128分●出演:マイケル・ダグラス/デミ・ムーア/ドナルド・サザーランド/キャロライン・グッドオール/デニス・ミラー/ロマ・マフィア/ ニコラス・サドラー/ローズマリー・フォーサイス/ディラン・ベイカー/ジャクリーン・キム/ドナル・ローグ/アラン・リッチ/ スージー・プラクソン●日本公開:1995/02●配給:ワーナー・ブラザース (評価★★★)
ニコラス・サドラー/ローズマリー・フォーサイス/ディラン・ベイカー/ジャクリーン・キム/ドナル・ローグ/アラン・リッチ/ スージー・プラクソン●日本公開:1995/02●配給:ワーナー・ブラザース (評価★★★)
 「大列車強盗」●原題:THE GREAT TRAIN ROBBERY/THE FIRST GREAT TRAIN ROBBER●制作年:1979年●制作国:アメリカ●監督・脚本:マイケル・クライトン●製作:ジョン・フォアマン●撮影:ジェフリー・アンスワース●音楽:ジェリー・ゴールドスミス●原作:マイケル・クライトン●時間:111分●出演:ショーン・コネリー/ドナルド・サザーランド/レスリー=アン・ダウン/アラン・ウェッブ/ロバート・ラング/マイケル・エルフィック/パメラ・セイラム/ガブリエル・ロイド/ジェームズ・コシンズ/ブライアン・グローヴァー/マルコム・テリス/ウェイン・スリープ●日本公開:1979/11●配給: ユナイト映画(評価★★★★)
「大列車強盗」●原題:THE GREAT TRAIN ROBBERY/THE FIRST GREAT TRAIN ROBBER●制作年:1979年●制作国:アメリカ●監督・脚本:マイケル・クライトン●製作:ジョン・フォアマン●撮影:ジェフリー・アンスワース●音楽:ジェリー・ゴールドスミス●原作:マイケル・クライトン●時間:111分●出演:ショーン・コネリー/ドナルド・サザーランド/レスリー=アン・ダウン/アラン・ウェッブ/ロバート・ラング/マイケル・エルフィック/パメラ・セイラム/ガブリエル・ロイド/ジェームズ・コシンズ/ブライアン・グローヴァー/マルコム・テリス/ウェイン・スリープ●日本公開:1979/11●配給: ユナイト映画(評価★★★★)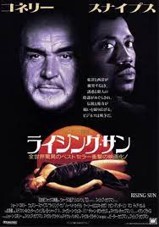
 「ライジング・サン」●原題:RISING SUN●制作年:1993年●制作国:アメリカ●監督:フィリップ・カウフマン●製作:ピーター・カウフマン●脚本:マイケル・クライトン/フィリップ・カウフマン/マイケル・バックス●撮影:マイケル・チャップマン●音楽:武満徹●原作:マイケル・クライトン●時間:125分●出演:ショーン・コネリー/ウェズリー・スナイプス/ハーヴェイ・カイテル/ケイリー=ヒロユキ・タガワ/ケヴィン・アンダーソン/マコ/レイ・ワイズ/スタン・イーギー/ティア・カレル/タジャナ・パティッツ/ヴィング・レイムス/スティーヴ・ブシェミ/サム・ロイド●日本公開:1993/11●配給:20世紀フォックス(評価★★★)
「ライジング・サン」●原題:RISING SUN●制作年:1993年●制作国:アメリカ●監督:フィリップ・カウフマン●製作:ピーター・カウフマン●脚本:マイケル・クライトン/フィリップ・カウフマン/マイケル・バックス●撮影:マイケル・チャップマン●音楽:武満徹●原作:マイケル・クライトン●時間:125分●出演:ショーン・コネリー/ウェズリー・スナイプス/ハーヴェイ・カイテル/ケイリー=ヒロユキ・タガワ/ケヴィン・アンダーソン/マコ/レイ・ワイズ/スタン・イーギー/ティア・カレル/タジャナ・パティッツ/ヴィング・レイムス/スティーヴ・ブシェミ/サム・ロイド●日本公開:1993/11●配給:20世紀フォックス(評価★★★)
 「コンゴ」●原題:CONGO●制作年:1995年●制作国:アメリカ●監督:フランク・マーシャル●製作:キャスリーン・ケネディ/サム・マーサー●脚本:ジョン・パト
「コンゴ」●原題:CONGO●制作年:1995年●制作国:アメリカ●監督:フランク・マーシャル●製作:キャスリーン・ケネディ/サム・マーサー●脚本:ジョン・パト リック・シャンリー●撮影:アレン・ダヴィオー●音楽:ジェリー・ゴールドスミス●原作:マイケル・クライトン●時間:109分●出演:ショーン・コネリー/ウェズリー・スナイプス/ハーヴェイ・カイテル/ケイリー=ヒロユキ・タガワ/ケヴィン・アンダーソン/マコ/レイ・ワイズ/スタン・イーギー/ティア・カレル/タジャナ・パティッツ/ヴィング・レイムス/スティーヴ・ブシェミ/サム・ロイド●日本公開:1995/10●配給:UIP(評価★★)
リック・シャンリー●撮影:アレン・ダヴィオー●音楽:ジェリー・ゴールドスミス●原作:マイケル・クライトン●時間:109分●出演:ショーン・コネリー/ウェズリー・スナイプス/ハーヴェイ・カイテル/ケイリー=ヒロユキ・タガワ/ケヴィン・アンダーソン/マコ/レイ・ワイズ/スタン・イーギー/ティア・カレル/タジャナ・パティッツ/ヴィング・レイムス/スティーヴ・ブシェミ/サム・ロイド●日本公開:1995/10●配給:UIP(評価★★)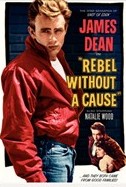
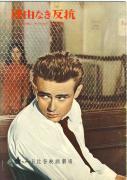
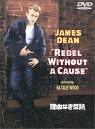
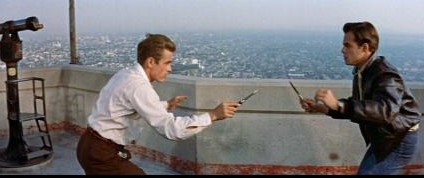
 ジェームズ・ディーンが補導されて警察署いる場面のパンフレットが懐かしいこの映画は、
ジェームズ・ディーンが補導されて警察署いる場面のパンフレットが懐かしいこの映画は、 マーロン・ブランドが出演を断った脚本が、ジョージ・スティーブンス監督の「
マーロン・ブランドが出演を断った脚本が、ジョージ・スティーブンス監督の「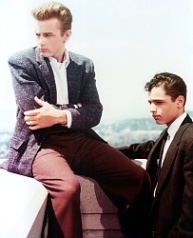 この映画でのジム(ジェームズ・ディーン)とプレイトウ(サル・ミネオ)の関係はよく同性愛だと言われていますが、17歳という設定ですから思春期的なものであると思われ、それでも当初はジムがプレイトウにキスしようとするシーンもあったそうですが、米国内の検閲でカットされたとのこと。個人的には、カットされて良かったと思います。もしそのシーンがあると、BL色が濃くなって、ジュディ(ナタリー・ウッド)を含めた3人の関係のバランスが壊れていたのではないかと思われるからです。
この映画でのジム(ジェームズ・ディーン)とプレイトウ(サル・ミネオ)の関係はよく同性愛だと言われていますが、17歳という設定ですから思春期的なものであると思われ、それでも当初はジムがプレイトウにキスしようとするシーンもあったそうですが、米国内の検閲でカットされたとのこと。個人的には、カットされて良かったと思います。もしそのシーンがあると、BL色が濃くなって、ジュディ(ナタリー・ウッド)を含めた3人の関係のバランスが壊れていたのではないかと思われるからです。 一方で、この映画の脚本には、当時の若者の声を聞いたアンケートが反映されていて、そのため、世間の親への教唆的要素が多分に含まれているようにも思います(「理由なき反抗」というタイトルからして)。
一方で、この映画の脚本には、当時の若者の声を聞いたアンケートが反映されていて、そのため、世間の親への教唆的要素が多分に含まれているようにも思います(「理由なき反抗」というタイトルからして)。 わらず、父親は叱ることも止めることも出来ずジムをガッカリさせる場面な
わらず、父親は叱ることも止めることも出来ずジムをガッカリさせる場面な どは、当時言われるようになっていた"父権の失墜"に対する警告ともとれるのではないでしょうか。
どは、当時言われるようになっていた"父権の失墜"に対する警告ともとれるのではないでしょうか。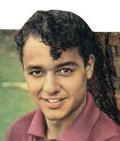

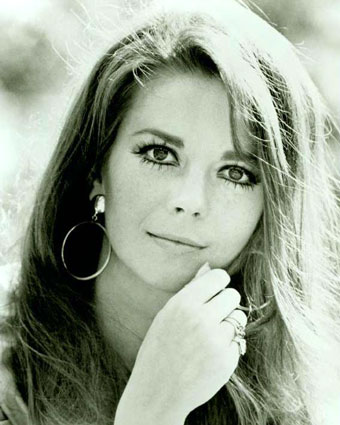
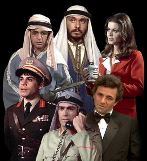

 5年後の'81年には、ナタリー・ウッドが撮影中にボートの転覆事故で亡くなっています(享年43、その死因には、事故説以外に他殺説、自殺説もある)。
5年後の'81年には、ナタリー・ウッドが撮影中にボートの転覆事故で亡くなっています(享年43、その死因には、事故説以外に他殺説、自殺説もある)。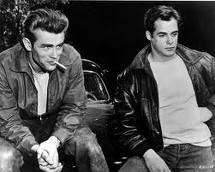 この記録映画の中では、ジェームズ・ディーンがマーロン・ブランドの演技を意識していたことが窺えたのが興味深かったです(演技ばかりでなく、自分はパーティ嫌いでバーティを避けていたのに、パーティに出ていたマーロン・ブランドがどういった様子だったかを人に聞くなど、普段の立ち振る舞いにも強い関心を示していた)。もし、もっと長生きしていたら、どんな作品に出ていただろうかと、ついつい考えてしまいますが、オヤジになったジェームズ・ディーンなんて見たくないという人も結構いるだろうなあ。
この記録映画の中では、ジェームズ・ディーンがマーロン・ブランドの演技を意識していたことが窺えたのが興味深かったです(演技ばかりでなく、自分はパーティ嫌いでバーティを避けていたのに、パーティに出ていたマーロン・ブランドがどういった様子だったかを人に聞くなど、普段の立ち振る舞いにも強い関心を示していた)。もし、もっと長生きしていたら、どんな作品に出ていただろうかと、ついつい考えてしまいますが、オヤジになったジェームズ・ディーンなんて見たくないという人も結構いるだろうなあ。



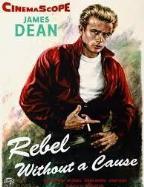 「理由なき反抗」●原題:REBEL WITHOUT A COUSE●制作年:1955年●制作国:アメリカ●監督・原案:ニコラス・レイ●製作:デヴィッド・ワイスバート●脚本:スチュワート・スターン/アーヴィング・シュルマン●撮影:アーネスト・ホーラー●音楽:レーナード・ローゼンマン●時間:105分●出演:ジェームズ・ディーン/ナタリー・ウッド/サル・ミネオ/デニス・ホッパー/ジム・バッカス/ロシェル・ハドソン/コーレイ・アレン/ウィリア
「理由なき反抗」●原題:REBEL WITHOUT A COUSE●制作年:1955年●制作国:アメリカ●監督・原案:ニコラス・レイ●製作:デヴィッド・ワイスバート●脚本:スチュワート・スターン/アーヴィング・シュルマン●撮影:アーネスト・ホーラー●音楽:レーナード・ローゼンマン●時間:105分●出演:ジェームズ・ディーン/ナタリー・ウッド/サル・ミネオ/デニス・ホッパー/ジム・バッカス/ロシェル・ハドソン/コーレイ・アレン/ウィリア ム・ホッパー/ニック・アダムス/エドワード・プラット/アン・ドーラン/フランク・マッゾラ●日本公開:1956/04●配給:ワーナー・ブラザース●最初に観た場所:高田馬場・早稲田松竹(77-12-21)●
ム・ホッパー/ニック・アダムス/エドワード・プラット/アン・ドーラン/フランク・マッゾラ●日本公開:1956/04●配給:ワーナー・ブラザース●最初に観た場所:高田馬場・早稲田松竹(77-12-21)●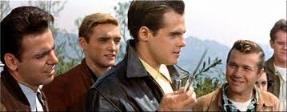 2回目:池袋文芸坐(79-02-18)(評<価★★★★)●併映(1回目):「ジャイアンツ」(ジョージ・スティーブンス)●併映(2回目):「エデンの東」(エリア・カザン」
2回目:池袋文芸坐(79-02-18)(評<価★★★★)●併映(1回目):「ジャイアンツ」(ジョージ・スティーブンス)●併映(2回目):「エデンの東」(エリア・カザン」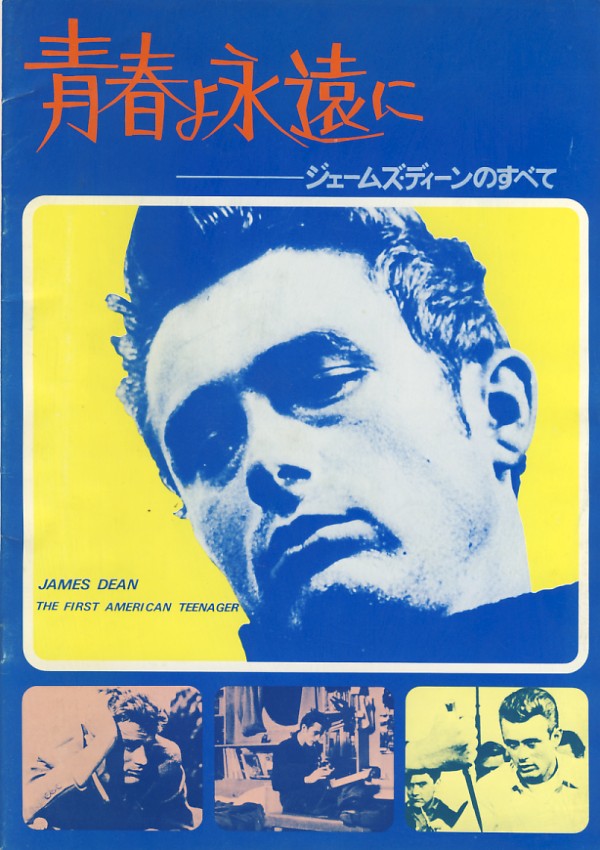
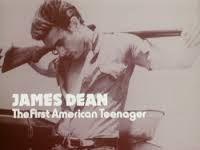
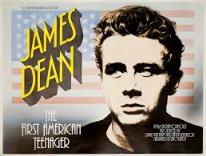 「ジェームズ・ディーンのすべて 青春よ永遠に」●原題:JAMES DEAN:THE FIRST AMERICAN TEENAGER●制作年:1975年●制作国:アメリカ●監督:レイ・コノリー●製作:デイヴィッド・パトナム
「ジェームズ・ディーンのすべて 青春よ永遠に」●原題:JAMES DEAN:THE FIRST AMERICAN TEENAGER●制作年:1975年●制作国:アメリカ●監督:レイ・コノリー●製作:デイヴィッド・パトナム
 /サンディ・リーバーマン●時間:80分●出演:ジェームズ・ディーン/ナタリー・ウッド/サル・ミネオ/デニス・ホッパー/サミー・デイビスJr./キャロル・ベイカー●日本公開:1977/09●配給:東宝東和●最初に観た場所:テアトル新宿(78-01-13)(評価★★★) ●併映:「サスペリア」(ダリオ・アルジェント)●記録映画
/サンディ・リーバーマン●時間:80分●出演:ジェームズ・ディーン/ナタリー・ウッド/サル・ミネオ/デニス・ホッパー/サミー・デイビスJr./キャロル・ベイカー●日本公開:1977/09●配給:東宝東和●最初に観た場所:テアトル新宿(78-01-13)(評価★★★) ●併映:「サスペリア」(ダリオ・アルジェント)●記録映画


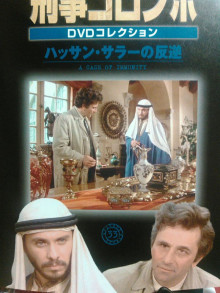
 「刑事コロンボ(第33話)/ハッサン・サラーの反逆」●原題:A CASE OF IMMUNITY●制作年:1975年●制作国:アメリカ●監督:テッド・ポスト●製作:エドワード・K・ドッズ●脚本:ルー・ショウ●撮影:リチャード・C・グローナー●音楽:ベルナルド・セガール/ハル・ムーニー●時間:73分●出演:ピーター・フォーク/ヘクター・エリゾンド/サル・ミネオ/ケネス・トビー/バリー・ロビンス/ビル・ザッカート/ハンク・ロビンソン/ハーヴェイ・ゴールド/アンドレ・ローレンス/ネイト・エスフォームス/ジョージ・スカフ/ジェフ・ゴールドブラム(ノンクレジト(デモ隊の男))●日本公開:1976/12●放送:NHK:★★★☆)
「刑事コロンボ(第33話)/ハッサン・サラーの反逆」●原題:A CASE OF IMMUNITY●制作年:1975年●制作国:アメリカ●監督:テッド・ポスト●製作:エドワード・K・ドッズ●脚本:ルー・ショウ●撮影:リチャード・C・グローナー●音楽:ベルナルド・セガール/ハル・ムーニー●時間:73分●出演:ピーター・フォーク/ヘクター・エリゾンド/サル・ミネオ/ケネス・トビー/バリー・ロビンス/ビル・ザッカート/ハンク・ロビンソン/ハーヴェイ・ゴールド/アンドレ・ローレンス/ネイト・エスフォームス/ジョージ・スカフ/ジェフ・ゴールドブラム(ノンクレジト(デモ隊の男))●日本公開:1976/12●放送:NHK:★★★☆)

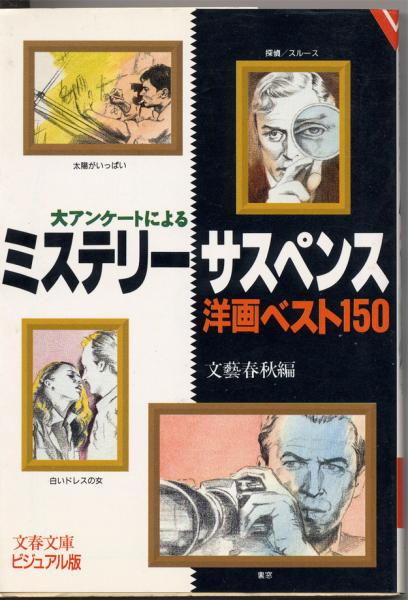


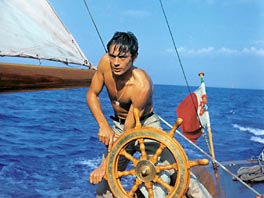





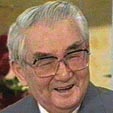 映画の解釈では、淀川長治のホモ・セクシュアル映画説が有名です(因みに、原作者のパトリシア・ハイスミスはレズビアンだった)。あの吉行淳之介も、淀川長治のディテールを引いての実証に驚愕した(吉行淳之介『恐怖対談』)と本書にありますが、ルネ・クレマンが来日した際に淀川長治自身が彼に確認したところ、そのような意図は無いとの答えだったとのことです(ルネ・クレマン自身がアラン・ドロンに"惚れて"いたとの説もあり、そんな簡単に本音を漏らすわけないか)。(●2016年にシネマブルースタジオで再見。トムがフィリップの服を着て彼の真似をしながら鏡に映った自分にキスするシーンは、ゲイ表現なのかナルシズム表現なのか。マルジュがフィリップに「私だけじゃ退屈?そうなら船をおりるわ」とすねるのは、フィリップの恋人である彼女が、男性であるトムをライバル視してのことか。再見していろいろ"気づき"があった。)
映画の解釈では、淀川長治のホモ・セクシュアル映画説が有名です(因みに、原作者のパトリシア・ハイスミスはレズビアンだった)。あの吉行淳之介も、淀川長治のディテールを引いての実証に驚愕した(吉行淳之介『恐怖対談』)と本書にありますが、ルネ・クレマンが来日した際に淀川長治自身が彼に確認したところ、そのような意図は無いとの答えだったとのことです(ルネ・クレマン自身がアラン・ドロンに"惚れて"いたとの説もあり、そんな簡単に本音を漏らすわけないか)。(●2016年にシネマブルースタジオで再見。トムがフィリップの服を着て彼の真似をしながら鏡に映った自分にキスするシーンは、ゲイ表現なのかナルシズム表現なのか。マルジュがフィリップに「私だけじゃ退屈?そうなら船をおりるわ」とすねるのは、フィリップの恋人である彼女が、男性であるトムをライバル視してのことか。再見していろいろ"気づき"があった。) 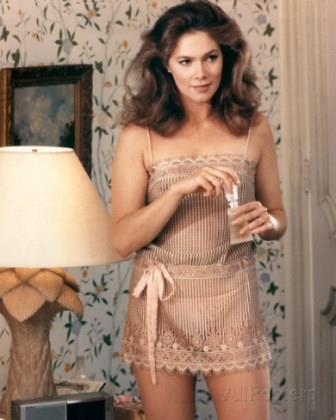


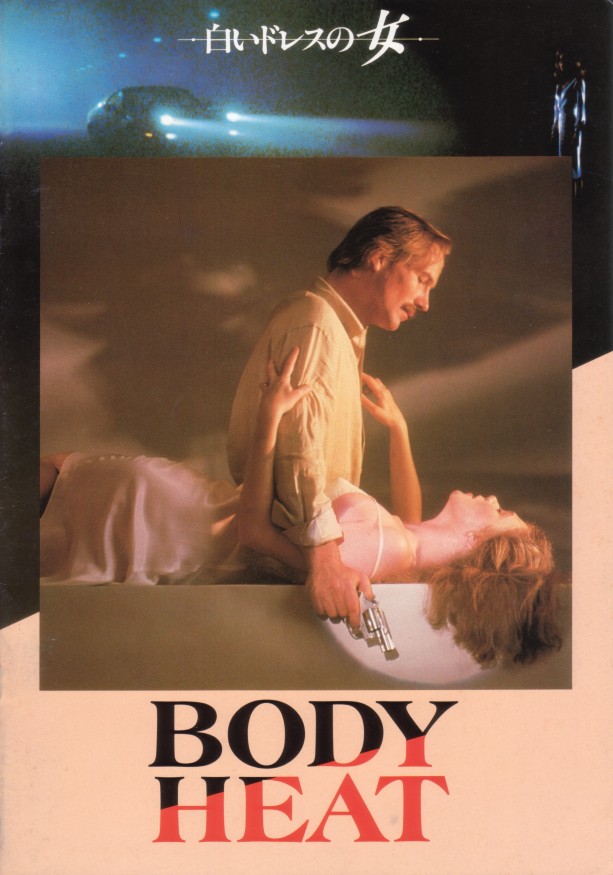


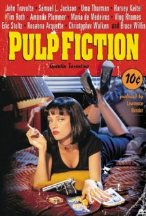

 「デス・トラップ 死の罠」の原作は「死の接吻」「ローズマリーの赤ちゃん」のアイラ・レビンが書いたブロードウェイの大ヒット舞台劇。落ち目の劇作家(マイケル・ケイン)の許に、かつてのシナリオライター講座の生徒クリフ(クリストファー・リーヴ)が書いた台本「デストラップ」が届けられ、作家は、金持ちの妻マイラ(ダイアン・キャノン)に「この劇は
「デス・トラップ 死の罠」の原作は「死の接吻」「ローズマリーの赤ちゃん」のアイラ・レビンが書いたブロードウェイの大ヒット舞台劇。落ち目の劇作家(マイケル・ケイン)の許に、かつてのシナリオライター講座の生徒クリフ(クリストファー・リーヴ)が書いた台本「デストラップ」が届けられ、作家は、金持ちの妻マイラ(ダイアン・キャノン)に「この劇は 傑作だ」と話し、盗作のアイデアと青年の殺害を仄めかし、青年が郊外の自宅を訪れる際に殺害の機会を狙う―(要するに自分の作品にしてしまおうと考えた)。ドンデン返しの連続は最後まで飽きさせないもので、「スーパーマン」のクリストファー・リーブが演じる劇作家志望のホモ青年も良かったです(この人、意外と演技派俳優だった)。
傑作だ」と話し、盗作のアイデアと青年の殺害を仄めかし、青年が郊外の自宅を訪れる際に殺害の機会を狙う―(要するに自分の作品にしてしまおうと考えた)。ドンデン返しの連続は最後まで飽きさせないもので、「スーパーマン」のクリストファー・リーブが演じる劇作家志望のホモ青年も良かったです(この人、意外と演技派俳優だった)。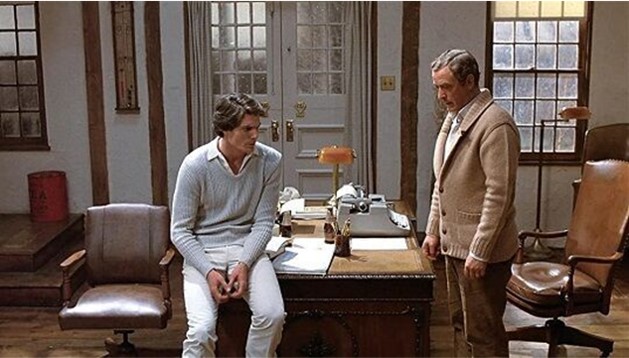 クリストファー・リーブ/マイケル・ケイン
クリストファー・リーブ/マイケル・ケイン![映画「ディーバ].jpg](http://hurec.bz/book-movie/%E6%98%A0%E7%94%BB%E3%80%8C%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%90%5D.jpg)
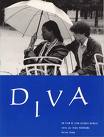 「ディーバ」は、オペラを愛する18歳の郵便配達夫が、レコードを出さないオペラ歌手のコンサートを密かに録音したことから殺人事件に巻き込まれるというもので、1981年12月にユニフランス・フィルム主催の映画祭「新しいフランス映画を見るフェスティバル」での上映5作品中の1本目として初日にThe Space (Hanae Mori ビル5F)で上映されるも、その時はすぐには日本配給には結びきませんでした。しかし、'81年シカゴ国際映画祭シルヴァー・ヒューゴー賞を受賞し、'82年セザール賞で最優秀新人監督作品賞(ジャン=ジャック・ベネックス)のほかに、撮影賞(フィリップ・ルースロ)、
「ディーバ」は、オペラを愛する18歳の郵便配達夫が、レコードを出さないオペラ歌手のコンサートを密かに録音したことから殺人事件に巻き込まれるというもので、1981年12月にユニフランス・フィルム主催の映画祭「新しいフランス映画を見るフェスティバル」での上映5作品中の1本目として初日にThe Space (Hanae Mori ビル5F)で上映されるも、その時はすぐには日本配給には結びきませんでした。しかし、'81年シカゴ国際映画祭シルヴァー・ヒューゴー賞を受賞し、'82年セザール賞で最優秀新人監督作品賞(ジャン=ジャック・ベネックス)のほかに、撮影賞(フィリップ・ルースロ)、
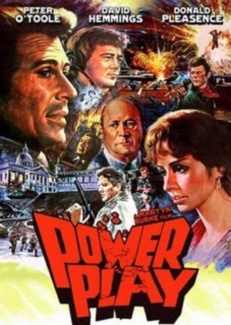
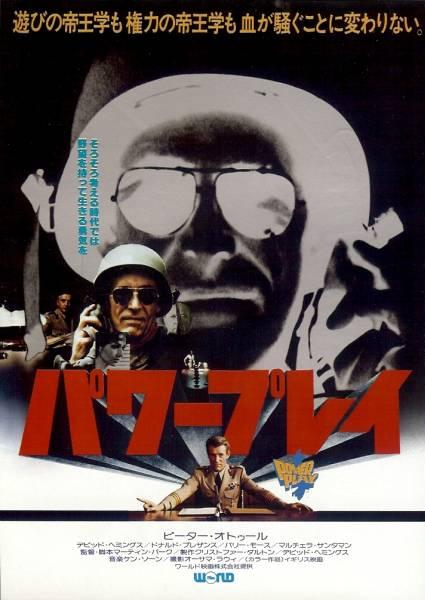
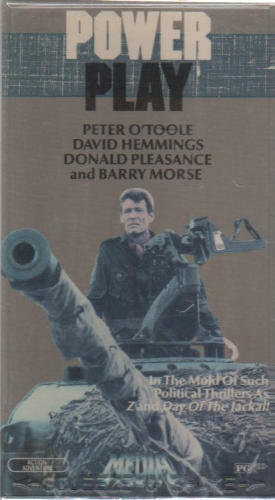
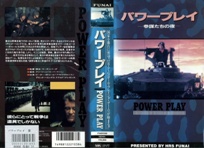 「私が密かに愛した映画」で「パワー・プレイ」を推した橋本治氏が、「すっごく面白いんだけど、これを見たっていう人間に会ったことがない」とコメントしてますが、見ましたよ。
「私が密かに愛した映画」で「パワー・プレイ」を推した橋本治氏が、「すっごく面白いんだけど、これを見たっていう人間に会ったことがない」とコメントしてますが、見ましたよ。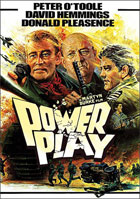 ヨーロッパのある国でテログループによる大臣の誘拐殺人事件が起き、大統領がテロの一掃するために秘密警察を使ってテロリスト殲滅を実行に移すもののそのやり方が過酷で(名脇役ドナルド・プレザンスが秘密警察の署長役で不気味な存在感を放っている)、反発した軍部の一部が戦車部隊の隊長ゼラー(ピーター・オトゥール)を引き入れクーデターを起こします。クーデターは成功しますが、宮殿の大統領室にいたのは...。「漁夫の利」っていうやつか。最後、ピーター・オトゥールがこちらに向かってにやりと笑うのが印象的でした。
ヨーロッパのある国でテログループによる大臣の誘拐殺人事件が起き、大統領がテロの一掃するために秘密警察を使ってテロリスト殲滅を実行に移すもののそのやり方が過酷で(名脇役ドナルド・プレザンスが秘密警察の署長役で不気味な存在感を放っている)、反発した軍部の一部が戦車部隊の隊長ゼラー(ピーター・オトゥール)を引き入れクーデターを起こします。クーデターは成功しますが、宮殿の大統領室にいたのは...。「漁夫の利」っていうやつか。最後、ピーター・オトゥールがこちらに向かってにやりと笑うのが印象的でした。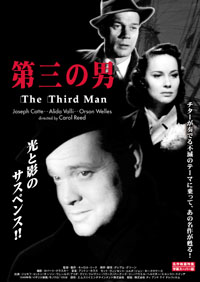 「第三の男」●原題:THE THIRD MAN●制作年:194
「第三の男」●原題:THE THIRD MAN●制作年:194




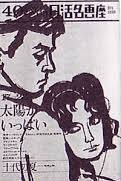 「ポスター[左](
「ポスター[左](

 「太陽がいっぱい」●原題:PLEIN SOLEIL●制作年:1960年●制作国:フランス●監督:ルネ・クレマン●製作:ロベール・アキム/レイモン・アキム●脚本:ポール・ジェゴフ/ルネ・クレマン●撮影:アンリ・ドカエ●音楽:ニーノ・ロータ●原作:パトリシア・ハイスミス 「才能あ
「太陽がいっぱい」●原題:PLEIN SOLEIL●制作年:1960年●制作国:フランス●監督:ルネ・クレマン●製作:ロベール・アキム/レイモン・アキム●脚本:ポール・ジェゴフ/ルネ・クレマン●撮影:アンリ・ドカエ●音楽:ニーノ・ロータ●原作:パトリシア・ハイスミス 「才能あ

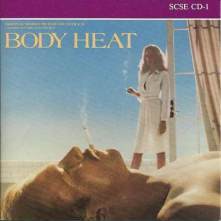 「白いドレスの女」●原題:BODY HEAT●制
「白いドレスの女」●原題:BODY HEAT●制 作年:1981年●制作国:アメリカ●監督・脚本:ローレンス・カスダン●製作:フレッド・T・ガロ●撮影:リチャード・H・クライン●音楽:ジョン・バリー●原作:ジェイムズ・M・ケイン 「殺人保険」●時間:113分●出演:ウィリアム・ハート/
作年:1981年●制作国:アメリカ●監督・脚本:ローレンス・カスダン●製作:フレッド・T・ガロ●撮影:リチャード・H・クライン●音楽:ジョン・バリー●原作:ジェイムズ・M・ケイン 「殺人保険」●時間:113分●出演:ウィリアム・ハート/ キャスリーン・ターナー/リチャード・クレンナ/テッド・ダンソン/ミッキー・ローク/J・A・プレストン/ラナ・サウンダース/キム・ジマー●日本公開:1982/02●配給:ワーナー・ブラザース●最初に観た場所:三鷹オスカー (82-08-07) ●2回目:飯田橋ギンレイホール(86-12-13)(評価:★★★★☆)●併映(1回目):「郵便配達は二度ベルを鳴らす」(ボブ・ラフェルソン)
キャスリーン・ターナー/リチャード・クレンナ/テッド・ダンソン/ミッキー・ローク/J・A・プレストン/ラナ・サウンダース/キム・ジマー●日本公開:1982/02●配給:ワーナー・ブラザース●最初に観た場所:三鷹オスカー (82-08-07) ●2回目:飯田橋ギンレイホール(86-12-13)(評価:★★★★☆)●併映(1回目):「郵便配達は二度ベルを鳴らす」(ボブ・ラフェルソン)
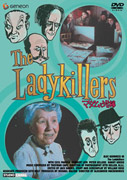
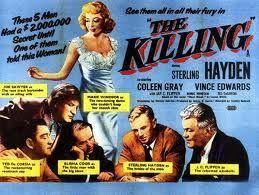
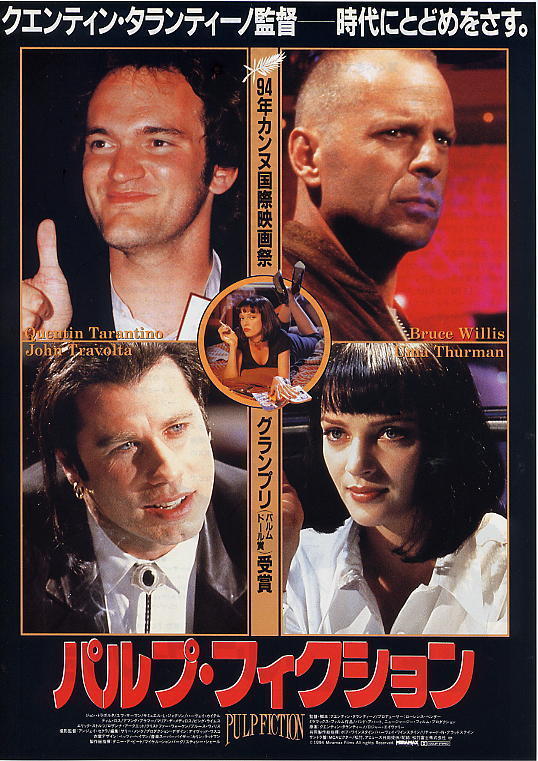
 「パルプ・フィクション」●原題:PULP FICTION●制作年:1994年●制作国:アメリカ●監督・脚本:クエンティン・タランティーノ●製作:ローレンス・ベンダー
「パルプ・フィクション」●原題:PULP FICTION●制作年:1994年●制作国:アメリカ●監督・脚本:クエンティン・タランティーノ●製作:ローレンス・ベンダー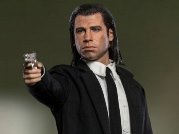 マン●時間:155分●出演:ジョン・トラヴォルタ/サミュエル・L・ジャクソン/ユマ・サーマン/ハーヴェイ・カイテル/アマンダ・プラマー/ティム・ロス/クリストファー・ウォーケン/ビング・ライムス/ブルース・ウィリス/エリック・ストルツ/ロザンナ・アークエット/マリア・デ・メディロス/ビング・ライムス●日本公開:1994/09●配給:松竹富士 (評価:★★★★)
マン●時間:155分●出演:ジョン・トラヴォルタ/サミュエル・L・ジャクソン/ユマ・サーマン/ハーヴェイ・カイテル/アマンダ・プラマー/ティム・ロス/クリストファー・ウォーケン/ビング・ライムス/ブルース・ウィリス/エリック・ストルツ/ロザンナ・アークエット/マリア・デ・メディロス/ビング・ライムス●日本公開:1994/09●配給:松竹富士 (評価:★★★★) ハーヴェイ・カイテル(掃除屋"ザ・ウルフ")
ハーヴェイ・カイテル(掃除屋"ザ・ウルフ")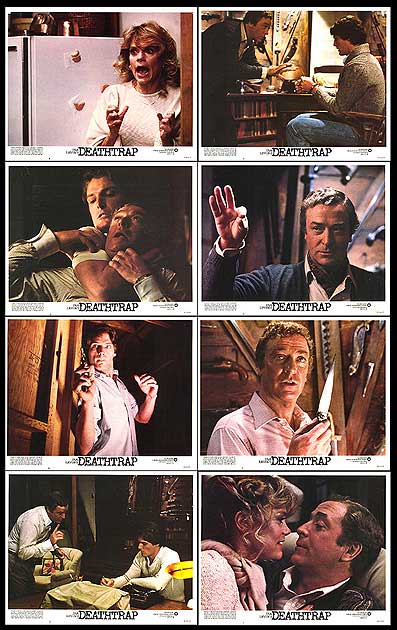
 「デス・トラップ 死の罠」●原題:DEATHTRAP●制作年:1982年●制作国:アメリカ●監督:シドニー・ルメット●製作:バート・ハリス●脚本:ジェイ・プレッソン・アレン●撮影:アンジェイ・バートコウィアク●音楽:ジョニー・マンデル●原作:アイラ・レヴィン●時間:117分●出演
「デス・トラップ 死の罠」●原題:DEATHTRAP●制作年:1982年●制作国:アメリカ●監督:シドニー・ルメット●製作:バート・ハリス●脚本:ジェイ・プレッソン・アレン●撮影:アンジェイ・バートコウィアク●音楽:ジョニー・マンデル●原作:アイラ・レヴィン●時間:117分●出演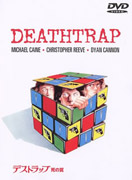
 :マイケル・ケイン/クリストファー・リーヴ/ダイアン・キャノン/アイリーン・ワース/ヘンリー・ジョーンズ/ジョー・シルヴァー●日本公開:1983/09●配給:ワーナー・ブラザース●最初に観た場所:テアトル吉祥寺 (86-02-15) (評価:★★★☆)●併映「殺しのドレス」(ブライアン・デ・パルマ)
:マイケル・ケイン/クリストファー・リーヴ/ダイアン・キャノン/アイリーン・ワース/ヘンリー・ジョーンズ/ジョー・シルヴァー●日本公開:1983/09●配給:ワーナー・ブラザース●最初に観た場所:テアトル吉祥寺 (86-02-15) (評価:★★★☆)●併映「殺しのドレス」(ブライアン・デ・パルマ)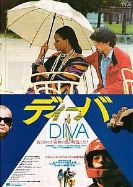
 「ディーバ」●原題:DIVA●制作年:1981年●制作国:フランス●監督:ジャン=
「ディーバ」●原題:DIVA●制作年:1981年●制作国:フランス●監督:ジャン=

 「パワー・プレイ 参謀たちの夜」●原題:POWER PLAY OPERATION OVERTHROW●制作年:1978年●制作国:イギリス/カナダ●監督:マーティン・バーク●製作:クリストファー・ダルトン●撮影:オウサマ・ラーウィ●音楽:ケン・ソーン●時間:110分●出演:ピーター・オトゥール/デヴィッド・ヘミングス/バリー・モース/ドナルド・プレザンス/ジョン・グラニック/チャック・シャマタ/アルバータ・ワトソン、/マーセラ・セイント・アマント/オーガスト・シェレンバーグ●日本公開:1979/11●配給:ワールド映画●最初に観
「パワー・プレイ 参謀たちの夜」●原題:POWER PLAY OPERATION OVERTHROW●制作年:1978年●制作国:イギリス/カナダ●監督:マーティン・バーク●製作:クリストファー・ダルトン●撮影:オウサマ・ラーウィ●音楽:ケン・ソーン●時間:110分●出演:ピーター・オトゥール/デヴィッド・ヘミングス/バリー・モース/ドナルド・プレザンス/ジョン・グラニック/チャック・シャマタ/アルバータ・ワトソン、/マーセラ・セイント・アマント/オーガスト・シェレンバーグ●日本公開:1979/11●配給:ワールド映画●最初に観



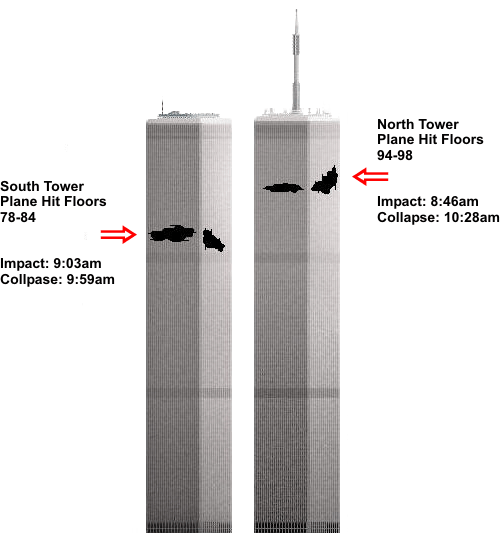
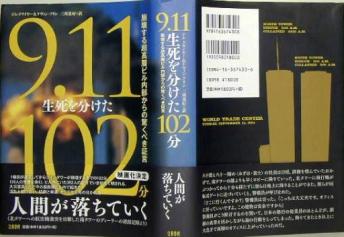

 旅客機衝突50分後にやっと南タワーに救出に入った多くの消防隊員たちは、その時点で、旅客機が衝突した階より下にいた6千人の民間人はもう殆ど避難し終えていたわけで、本書にあるように、上層階に取り残された600人を助けにいくつもりだったのでしょうか(ただし内200人は、旅客機衝突時に即死したと思われる)。ビルはゆうにあと1時間くらいは熱に耐えると考えて、助けるべき民間人が既にいない階で休息をとっている間に、あっという間にビル崩壊に遭ってしまった―というのが彼らの悲劇の経緯のようです。
旅客機衝突50分後にやっと南タワーに救出に入った多くの消防隊員たちは、その時点で、旅客機が衝突した階より下にいた6千人の民間人はもう殆ど避難し終えていたわけで、本書にあるように、上層階に取り残された600人を助けにいくつもりだったのでしょうか(ただし内200人は、旅客機衝突時に即死したと思われる)。ビルはゆうにあと1時間くらいは熱に耐えると考えて、助けるべき民間人が既にいない階で休息をとっている間に、あっという間にビル崩壊に遭ってしまった―というのが彼らの悲劇の経緯のようです。 一方、北タワーに入った消防隊員たちには、南タワーが崩壊したことも、警察ヘリからの北タワーが傾いてきたという連絡も伝わらず(元来、警察と消防が没交渉だった)、そのことでより多くが犠牲になった―。
一方、北タワーに入った消防隊員たちには、南タワーが崩壊したことも、警察ヘリからの北タワーが傾いてきたという連絡も伝わらず(元来、警察と消防が没交渉だった)、そのことでより多くが犠牲になった―。
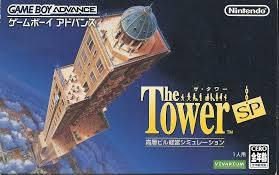
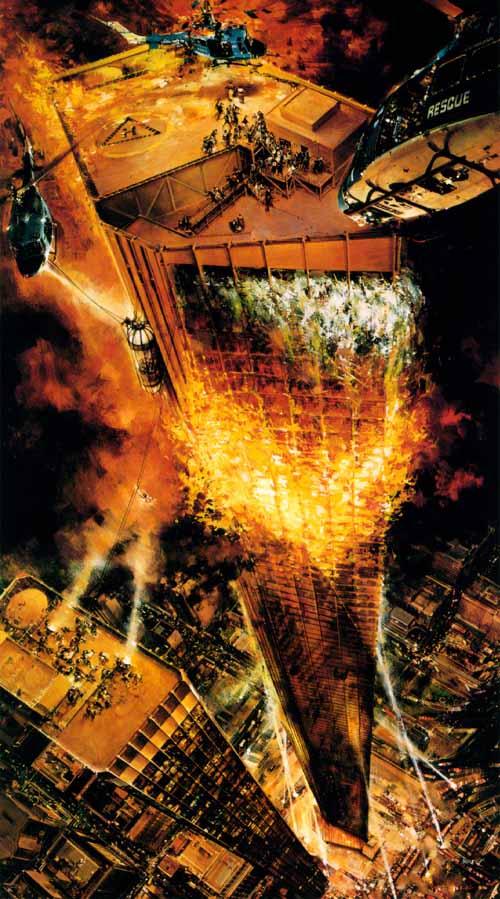
 もう1つは、"The Tower"というリチャード・マーティン・スターンが'73年に発表した小説で(邦訳タイトル『そびえたつ地獄』('75年/ハヤカワ・ノヴェルズ))、これを映画化したのがジョン・ギラーミン(1925-2015)監督の「タワーリング・インフェルノ」('74年/米)ですが、映画ではスティ―ブ・マックィーンが演じた消防隊長が、ポール・ニューマン演じるビル設計者に、いつか高層ビル火災で多くの死者が出ると警告していました。
もう1つは、"The Tower"というリチャード・マーティン・スターンが'73年に発表した小説で(邦訳タイトル『そびえたつ地獄』('75年/ハヤカワ・ノヴェルズ))、これを映画化したのがジョン・ギラーミン(1925-2015)監督の「タワーリング・インフェルノ」('74年/米)ですが、映画ではスティ―ブ・マックィーンが演じた消防隊長が、ポール・ニューマン演じるビル設計者に、いつか高層ビル火災で多くの死者が出ると警告していました。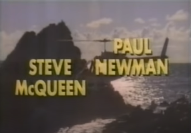 この作品はスティーブ・マックイーンとポール・ニューマンの初共演ということで(実際にはポール・ニューマン主演の「傷だらけの栄光」('56年)にスティーブ・マックイーンがノンクレジットでチンピラ役で出ているそうだ)、公開時にマックイーン、ニューマンのどちらがクレジットタイトルの最初に出てくるかが注目されたりもしましたが(結局、二人の名前を同時に出した上で、マックイーンの名を左に、ニューマンの名を右の一段上に据えて対等性を強調)、映画の中で2人が会話するのはこのラストのほかは殆どなく、映画全体としては豪華俳優陣による「グランド・ホテル」形式の作品と言えるものでした。スペクタクル・シーンを(ケチらず)ふんだんに織り込んでいることもあって、70年代中
この作品はスティーブ・マックイーンとポール・ニューマンの初共演ということで(実際にはポール・ニューマン主演の「傷だらけの栄光」('56年)にスティーブ・マックイーンがノンクレジットでチンピラ役で出ているそうだ)、公開時にマックイーン、ニューマンのどちらがクレジットタイトルの最初に出てくるかが注目されたりもしましたが(結局、二人の名前を同時に出した上で、マックイーンの名を左に、ニューマンの名を右の一段上に据えて対等性を強調)、映画の中で2人が会話するのはこのラストのほかは殆どなく、映画全体としては豪華俳優陣による「グランド・ホテル」形式の作品と言えるものでした。スペクタクル・シーンを(ケチらず)ふんだんに織り込んでいることもあって、70年代中 盤期の「パニック映画ブーム」の中では最高傑作とも評されています。映画評論家の双葉十三郎(1910-2009)氏も『
盤期の「パニック映画ブーム」の中では最高傑作とも評されています。映画評論家の双葉十三郎(1910-2009)氏も『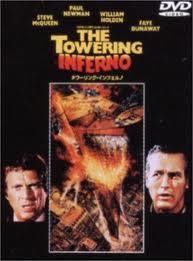
 「タワーリング・インフェルノ」●原題:THE TOWERING INFERNO●制作年:1974年●制作国:アメリカ●監督:ジョン・ギラーミン●製作:アーウィン・アレン●脚色:スターリング・シリファント●撮影:フレッド・J・コーネカンプ●音楽:ジョン・ウィリアムズ●原作:リチャード・マーティン・スターン「ザ・タワー」●時間:115分●出演:スティーブ・マックイーン/ポール・ニューマン/ウィリアム・ホールデン/フェイ・ダナウェイ/フレッド・アステア/スーザン・ブレークリー/リチャード・チェンバレン/ジェニファー・ジョーンズ/O・J・シンプソン /ロバート・ヴォーン/ロバート・ワグナー/スーザン・フラネリー/シーラ・アレン/ノーマン・バートン/ジャック・コリンズ●日本公開:1975/06●配給:ワーナー・ブラザース映画)(評価:★★★☆)
「タワーリング・インフェルノ」●原題:THE TOWERING INFERNO●制作年:1974年●制作国:アメリカ●監督:ジョン・ギラーミン●製作:アーウィン・アレン●脚色:スターリング・シリファント●撮影:フレッド・J・コーネカンプ●音楽:ジョン・ウィリアムズ●原作:リチャード・マーティン・スターン「ザ・タワー」●時間:115分●出演:スティーブ・マックイーン/ポール・ニューマン/ウィリアム・ホールデン/フェイ・ダナウェイ/フレッド・アステア/スーザン・ブレークリー/リチャード・チェンバレン/ジェニファー・ジョーンズ/O・J・シンプソン /ロバート・ヴォーン/ロバート・ワグナー/スーザン・フラネリー/シーラ・アレン/ノーマン・バートン/ジャック・コリンズ●日本公開:1975/06●配給:ワーナー・ブラザース映画)(評価:★★★☆)
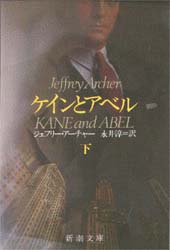
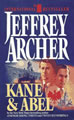
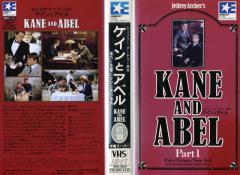

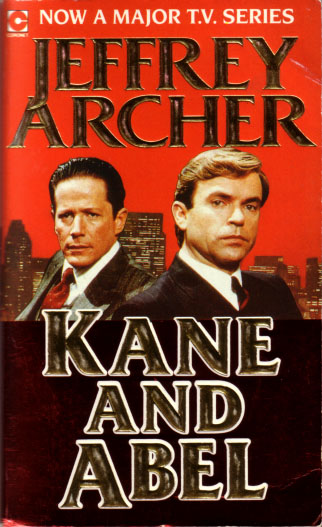

 『百万ドルをとり返せ!』も『ケインとアベル』も共にテレビ映画(ドラマ)化されていてどちらも観ましたが、とりわけドラマ版「ケインとアベル」は力作で(テレビ東京「午後のロードショー」で'97年9月8日から3日間にわたって放送された)、後に「ジュラシック・パーク」('93年/米)に出演するサム・ニールがケインを好演し、こちらも後にジョニー・デップ主演の「ニック・オブ・タイム」('95年/米)などハリウッド映画に出ることになるピーター・ストラウスが演じたアベルも良かったです。通しで5時間を超える大作ですが、原作同様、最後まで飽きさせませんでした(今でもたまに民放やCS放送などで放映されることがあるが、日本語版ビデオは絶版に)。ラストの2人が偶然道で出会うシーンが、原作の情感を損なわずに描かれていて、そこに至るまでの作りこみも原作からの期待を裏切らないものでした。
『百万ドルをとり返せ!』も『ケインとアベル』も共にテレビ映画(ドラマ)化されていてどちらも観ましたが、とりわけドラマ版「ケインとアベル」は力作で(テレビ東京「午後のロードショー」で'97年9月8日から3日間にわたって放送された)、後に「ジュラシック・パーク」('93年/米)に出演するサム・ニールがケインを好演し、こちらも後にジョニー・デップ主演の「ニック・オブ・タイム」('95年/米)などハリウッド映画に出ることになるピーター・ストラウスが演じたアベルも良かったです。通しで5時間を超える大作ですが、原作同様、最後まで飽きさせませんでした(今でもたまに民放やCS放送などで放映されることがあるが、日本語版ビデオは絶版に)。ラストの2人が偶然道で出会うシーンが、原作の情感を損なわずに描かれていて、そこに至るまでの作りこみも原作からの期待を裏切らないものでした。 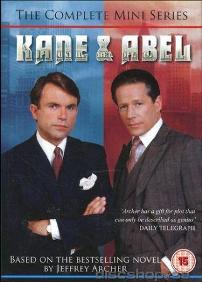



.jpg)


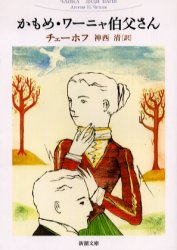


 ともに'70年に旧ソ連で映画化されていて、監督は「「チェーホフのかもめ」('71年/ソ連)がユーリー・カラーシク、「ワーニャ伯父さん」('71年/ソ連)がアンドレイ・ミハルコフ=コンチャロフスキー(ニキータ・ミハルコフ の兄)です。元が戯曲なので原作と映画の違和感が無く、しっとりとした情感が味わえます。映画「チェーホフのかもめ」でニーナ
ともに'70年に旧ソ連で映画化されていて、監督は「「チェーホフのかもめ」('71年/ソ連)がユーリー・カラーシク、「ワーニャ伯父さん」('71年/ソ連)がアンドレイ・ミハルコフ=コンチャロフスキー(ニキータ・ミハルコフ の兄)です。元が戯曲なので原作と映画の違和感が無く、しっとりとした情感が味わえます。映画「チェーホフのかもめ」でニーナ
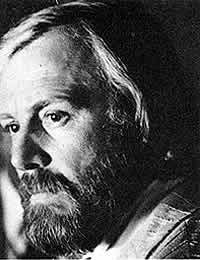 を演じたリュドミラ・サベーリエワは、「戦争と平和」('67年/ソ連)の主演女優で、「
を演じたリュドミラ・サベーリエワは、「戦争と平和」('67年/ソ連)の主演女優で、「![岩波文庫創刊書目[復刻]全23冊.jpg](/book-movie/archives/岩波文庫創刊書目[復刻]全23冊.jpg)
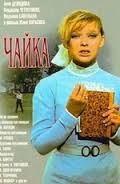
 「チェーホフのかもめ」●原題:EHAIKA(Чайка)●制作年:1971年●制作国:ソ連●監督・脚本:ユーリー・カラシク●撮影:ミハイル・スースロ●音楽:アレクサンダー・シニートケ●原作:アントン・チェーホフ「かもめ」●時間:100分●
「チェーホフのかもめ」●原題:EHAIKA(Чайка)●制作年:1971年●制作国:ソ連●監督・脚本:ユーリー・カラシク●撮影:ミハイル・スースロ●音楽:アレクサンダー・シニートケ●原作:アントン・チェーホフ「かもめ」●時間:100分● 出演:リュドミラ・サヴェーリエワ/ウラディーミル・チュトベリコフ/アッラ・デミートワ/ニコライ・プロートニコフ●日本
出演:リュドミラ・サヴェーリエワ/ウラディーミル・チュトベリコフ/アッラ・デミートワ/ニコライ・プロートニコフ●日本 公開:1974/11●配給:日本ヘラルド映画●最初に観た場所:池袋文芸坐(79-11-09) (評価 ★★★★☆)●併映:「ワーニャ伯父さん」(アンドレ・ミハルコフ=コンチャロフスキー)
公開:1974/11●配給:日本ヘラルド映画●最初に観た場所:池袋文芸坐(79-11-09) (評価 ★★★★☆)●併映:「ワーニャ伯父さん」(アンドレ・ミハルコフ=コンチャロフスキー) 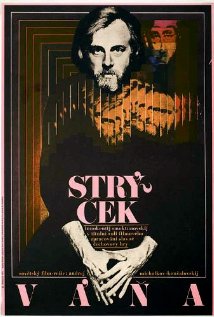
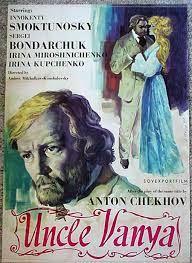
 (1970).jpg)
 「ワーニャ伯父さん」●原題:DYADYA VANYA(Дядя Ваня)●制作年:1971年●制作国:ソ連●監督・脚本:アンドレイ・ミハルコフ=コンチャロフスキー●撮影:ゲオルギー・レルベルグ●音楽:アルフレード・シニートケ●原作:アントン・チェーホフ「ワーニャ伯父さん」●時間:100分●出演:インノケンティ・スモクトゥノフスキー/イリーナ・ミロシニシェンコ/イリーナ・クプチェンコ/ウラジミール・ザリジン/セルゲイ・ボンダルチュク●日本公開:1972/09●配給:ATG●最初に観た場所:池袋文芸坐(79-11-09) (評価 ★★★★★)●併映:「チェホフのかもめ」(ユーリー・カラシク)
「ワーニャ伯父さん」●原題:DYADYA VANYA(Дядя Ваня)●制作年:1971年●制作国:ソ連●監督・脚本:アンドレイ・ミハルコフ=コンチャロフスキー●撮影:ゲオルギー・レルベルグ●音楽:アルフレード・シニートケ●原作:アントン・チェーホフ「ワーニャ伯父さん」●時間:100分●出演:インノケンティ・スモクトゥノフスキー/イリーナ・ミロシニシェンコ/イリーナ・クプチェンコ/ウラジミール・ザリジン/セルゲイ・ボンダルチュク●日本公開:1972/09●配給:ATG●最初に観た場所:池袋文芸坐(79-11-09) (評価 ★★★★★)●併映:「チェホフのかもめ」(ユーリー・カラシク)








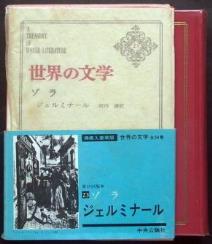

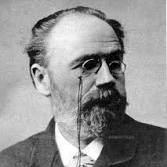 1885年の原著発表のフランスの作家エミール・ゾラ(Emile Zola、1840‐1902)による作品で、彼の膨大な小説群「ルーゴン・マッカール双書」の中では『居酒屋』(1877年発表)、『ナナ』(1879年発表)と並ぶ代表作。
1885年の原著発表のフランスの作家エミール・ゾラ(Emile Zola、1840‐1902)による作品で、彼の膨大な小説群「ルーゴン・マッカール双書」の中では『居酒屋』(1877年発表)、『ナナ』(1879年発表)と並ぶ代表作。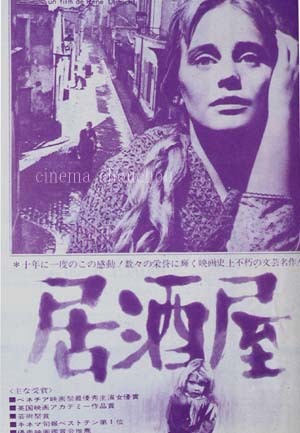

 美人でも男運の悪い女はいるもんだと、マリア・シェルに感情移入して同情し、またリアリズムに徹した佳作だと思いましたが、原作の背後には、ゾラの「運命決定論」のようなものがあったみたいです。
美人でも男運の悪い女はいるもんだと、マリア・シェルに感情移入して同情し、またリアリズムに徹した佳作だと思いましたが、原作の背後には、ゾラの「運命決定論」のようなものがあったみたいです。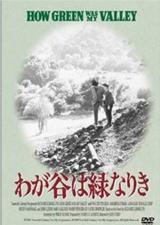
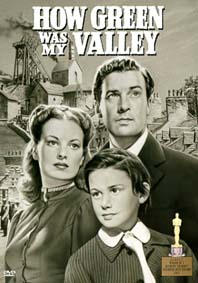

 (家族愛がテーマだとも言える)、ノスタルジーにより美化された部分もありました(全体が当時少年だった語り手の想い出として設定されている。モーリーン・オハラって、昔のアメリカ映画にみる典型的な美人だなあ)。
(家族愛がテーマだとも言える)、ノスタルジーにより美化された部分もありました(全体が当時少年だった語り手の想い出として設定されている。モーリーン・オハラって、昔のアメリカ映画にみる典型的な美人だなあ)。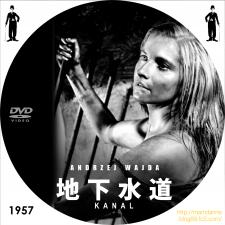

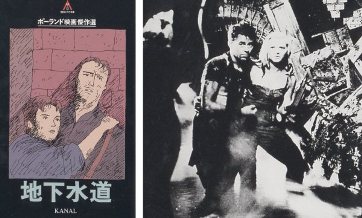
 「居酒屋」●原題:GERVAISE●制作年:1956年●制作国:フランス●監督・:ルネ・クレマン●製作:アニー・ドルフマン●脚本:ジャン・オーランシュ/ピエール・ポスト●撮影:ロベール・ジュイヤール●音楽:ジョルジュ・オーリック
「居酒屋」●原題:GERVAISE●制作年:1956年●制作国:フランス●監督・:ルネ・クレマン●製作:アニー・ドルフマン●脚本:ジャン・オーランシュ/ピエール・ポスト●撮影:ロベール・ジュイヤール●音楽:ジョルジュ・オーリック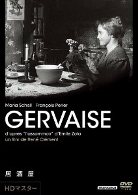
 「わが谷は緑なりき」●原題:HOW GREEN WAS MY VALLEY●制作年:1941年●制作国:アメリカ●監督:ジ
「わが谷は緑なりき」●原題:HOW GREEN WAS MY VALLEY●制作年:1941年●制作国:アメリカ●監督:ジ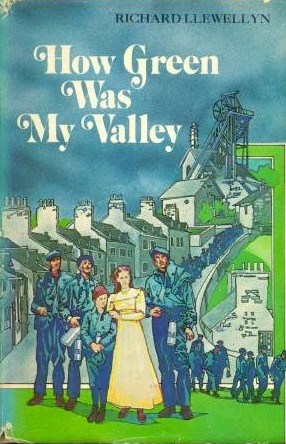
 ョン・フォード●製作:ダリル・F・ザナック●脚本:フィリップ・ダン●撮影:アーサー・ミラー●音楽:アルフレッド・ニューマン●原作:リチャード・レウェリン(How Green Was My Valley)●時間:118分●出演:ウォルター・ピジョン/モーリーン・オハラ/ドナルド・クリスプ/アンナ・リー/ロディ・マクドウォール●日本公開:1950/12●配給:セントラル●最初に観た場所:吉祥寺ジャヴ50 (84-06-30)●2回目:自由が丘劇場 (85-02-17) (評価:★★★★)●併映(2回目)「いとしのクレメンタイン 荒野の決闘」(ジョン・フォード)
ョン・フォード●製作:ダリル・F・ザナック●脚本:フィリップ・ダン●撮影:アーサー・ミラー●音楽:アルフレッド・ニューマン●原作:リチャード・レウェリン(How Green Was My Valley)●時間:118分●出演:ウォルター・ピジョン/モーリーン・オハラ/ドナルド・クリスプ/アンナ・リー/ロディ・マクドウォール●日本公開:1950/12●配給:セントラル●最初に観た場所:吉祥寺ジャヴ50 (84-06-30)●2回目:自由が丘劇場 (85-02-17) (評価:★★★★)●併映(2回目)「いとしのクレメンタイン 荒野の決闘」(ジョン・フォード)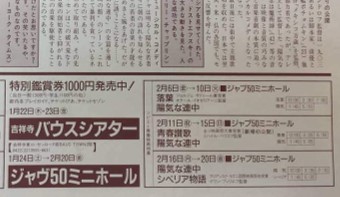


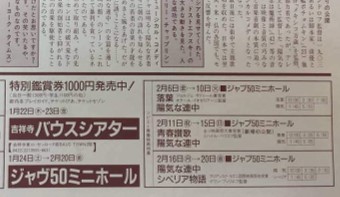

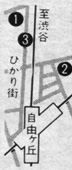



.jpg)
 /エミール・カレヴィッチ/ヴラデク・シェイバル/ヤン・エングレルト●日本公開:1958/01(1979/12(リバイバル))●配給:東映洋画●最初に観た場所:新宿アートビレッジ (79-04-10) (評価:★★★★☆) ●併映:「灰とダイヤモンド」(アンジェイ・ワイダ)「地下水道」の一場面/「
/エミール・カレヴィッチ/ヴラデク・シェイバル/ヤン・エングレルト●日本公開:1958/01(1979/12(リバイバル))●配給:東映洋画●最初に観た場所:新宿アートビレッジ (79-04-10) (評価:★★★★☆) ●併映:「灰とダイヤモンド」(アンジェイ・ワイダ)「地下水道」の一場面/「 「灰とダイヤモンド」(1958)
「灰とダイヤモンド」(1958)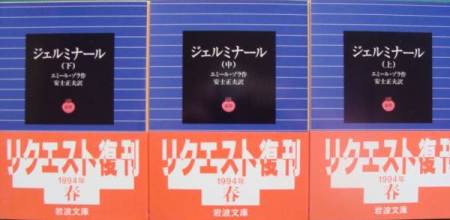 【1954年文庫化・1994年改版[岩波文庫(上・中・下)]/1994年再文庫化[中公文庫(上・下)]】
【1954年文庫化・1994年改版[岩波文庫(上・中・下)]/1994年再文庫化[中公文庫(上・下)]】.jpg)
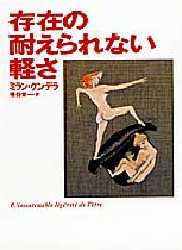
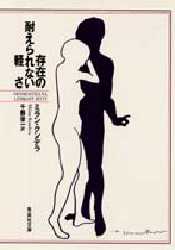


 1984年にフランスで出版された、まだノーベル文学賞を貰っていない最後の大物作家と言われているチェコ出身のミラン ・クンデラ(Milan Kundera)の作品で、発表時の政治的事情(フランスへの亡命状態だった)で、自身の母国語であるチェコ語ではなくフランス語で書かれました。
1984年にフランスで出版された、まだノーベル文学賞を貰っていない最後の大物作家と言われているチェコ出身のミラン ・クンデラ(Milan Kundera)の作品で、発表時の政治的事情(フランスへの亡命状態だった)で、自身の母国語であるチェコ語ではなくフランス語で書かれました。 冷戦下のチェコスロバキア、1968年のソ連軍侵攻・「プラハの春」前後の話で、運命に弄ばれ苦悩する男女を描いた小説ですが、政治的な問題(チェコスロバキアという国名が使われていないことからみてもその複雑さが窺える)のほかに哲学的問題(ニーチェの永劫回帰論を引いてのタイトルの「存在の耐えられない軽さ」ということの解題からこの小説は始まる)、母と娘の関係といった精神分析的問題、言葉とコミュニケーションの問題、心と身体(性)の疎外問題などの様々なテーマを作中で扱っています。
冷戦下のチェコスロバキア、1968年のソ連軍侵攻・「プラハの春」前後の話で、運命に弄ばれ苦悩する男女を描いた小説ですが、政治的な問題(チェコスロバキアという国名が使われていないことからみてもその複雑さが窺える)のほかに哲学的問題(ニーチェの永劫回帰論を引いてのタイトルの「存在の耐えられない軽さ」ということの解題からこの小説は始まる)、母と娘の関係といった精神分析的問題、言葉とコミュニケーションの問題、心と身体(性)の疎外問題などの様々なテーマを作中で扱っています。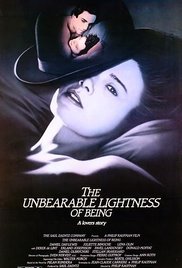
 先にフィリップ・カウフマン監督の映画('87年/米)の方を観てそれほど悪くないと思ったのですが(原作の翻訳が出たのは映画公開より5年後)、映画ではイギリス人俳優のダニエル・デイ=ルイスが、天才脳外科医でありながらプラハ抵抗運動のシンパでもあり、女たらしのプレイボーイだけれども妻をもきっちり愛しているという、なかなか魅力的な主
先にフィリップ・カウフマン監督の映画('87年/米)の方を観てそれほど悪くないと思ったのですが(原作の翻訳が出たのは映画公開より5年後)、映画ではイギリス人俳優のダニエル・デイ=ルイスが、天才脳外科医でありながらプラハ抵抗運動のシンパでもあり、女たらしのプレイボーイだけれども妻をもきっちり愛しているという、なかなか魅力的な主 人公トマーシュをうまく演じていてました(ダニエル・デイ=ルイスは翌年、「マイ・レフトフット」('89年)でアカデミー賞主演男優賞を受賞する)。やりたいことはすべてやりながら、最後にあっさり事故死してしまったトマーシュ
人公トマーシュをうまく演じていてました(ダニエル・デイ=ルイスは翌年、「マイ・レフトフット」('89年)でアカデミー賞主演男優賞を受賞する)。やりたいことはすべてやりながら、最後にあっさり事故死してしまったトマーシュ という男を通して、人間に備わった人格の複雑さと多面性、運命の前での人間の生の脆さなどを感じさせる佳作でした。
という男を通して、人間に備わった人格の複雑さと多面性、運命の前での人間の生の脆さなどを感じさせる佳作でした。
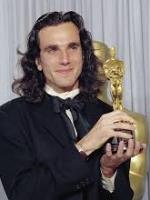 コロール/青の愛」('93年)でヴェネツィア国際映画祭女優賞、「イングリッシュ・ペイシェント」('96年)でベルリン国際映画祭銀熊賞女優賞とアカデミー助演女優賞、「トスカーナの贋作」('10年)でカンヌ国際映画祭女優賞を受賞し、世界三大映画祭の女優賞をすべて受賞した最初の女優となっている。)(更に、主人公トマーシュを演じたダニエル・デイ=ルイスもその後、「ゼア・ウィル・ビー・ブラッド」('07年)、「リンカーン」('12年)でもアカデミー賞主演男優賞を受賞し、アカデミー主演男優賞を3回受賞した唯一の俳優となった。)
コロール/青の愛」('93年)でヴェネツィア国際映画祭女優賞、「イングリッシュ・ペイシェント」('96年)でベルリン国際映画祭銀熊賞女優賞とアカデミー助演女優賞、「トスカーナの贋作」('10年)でカンヌ国際映画祭女優賞を受賞し、世界三大映画祭の女優賞をすべて受賞した最初の女優となっている。)(更に、主人公トマーシュを演じたダニエル・デイ=ルイスもその後、「ゼア・ウィル・ビー・ブラッド」('07年)、「リンカーン」('12年)でもアカデミー賞主演男優賞を受賞し、アカデミー主演男優賞を3回受賞した唯一の俳優となった。)


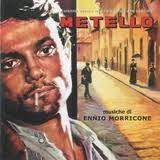 無政府主義者の父親に育てられた主人公メテッロ(マッシモ・ラニエリ)は、水難事故で父を失ってから孤児として苦労する。ベルギーへの移住を拒否し、両親の故郷フィレンツェでレンガ職人として働き始めるが、次第に労働者の権利に目覚め、ストライキの中心人物となっていく。その間、メテッロと
無政府主義者の父親に育てられた主人公メテッロ(マッシモ・ラニエリ)は、水難事故で父を失ってから孤児として苦労する。ベルギーへの移住を拒否し、両親の故郷フィレンツェでレンガ職人として働き始めるが、次第に労働者の権利に目覚め、ストライキの中心人物となっていく。その間、メテッロと 未亡人ヴィオラ(ルチア・ボゼー)との恋、事故死した仲間の娘エルシリア(オッタヴィア・ピッコロ)との恋と結婚、隣家の婦人イディーナ(ティナ・オーモン)との浮気なども―。
未亡人ヴィオラ(ルチア・ボゼー)との恋、事故死した仲間の娘エルシリア(オッタヴィア・ピッコロ)との恋と結婚、隣家の婦人イディーナ(ティナ・オーモン)との浮気なども―。 原作はヴァスコ・プラトリーニ。ルキノ・ヴァレリオ・ズルリーニ監督の「家族日誌」の脚本家、ヴィスコンティ監督の「若者のすべての」の共同原案者でもあり、20世紀初めのフィレンツェを舞台に、階級意識に目覚め労働運動のリーダーとなっていく男を描いたものですが、この主人公は、闘争のかたわら人妻と過ちを犯してしまうというもので、同じように人間の多面性をよく描いている映画でした。この作品でエルシリアを演じたオッタヴィア・ピッコロが、1970年の
原作はヴァスコ・プラトリーニ。ルキノ・ヴァレリオ・ズルリーニ監督の「家族日誌」の脚本家、ヴィスコンティ監督の「若者のすべての」の共同原案者でもあり、20世紀初めのフィレンツェを舞台に、階級意識に目覚め労働運動のリーダーとなっていく男を描いたものですが、この主人公は、闘争のかたわら人妻と過ちを犯してしまうというもので、同じように人間の多面性をよく描いている映画でした。この作品でエルシリアを演じたオッタヴィア・ピッコロが、1970年の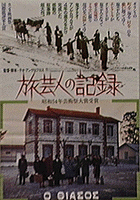





 ティナ・オーモン(Tina Aumont) in「
ティナ・オーモン(Tina Aumont) in「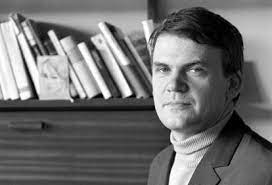 ミラン・クンデラ チェコ出身の作家
ミラン・クンデラ チェコ出身の作家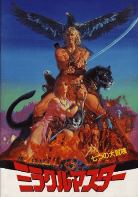
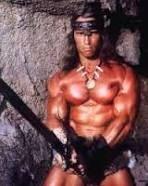
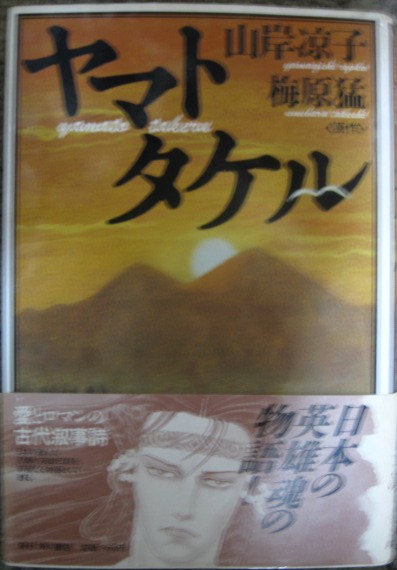
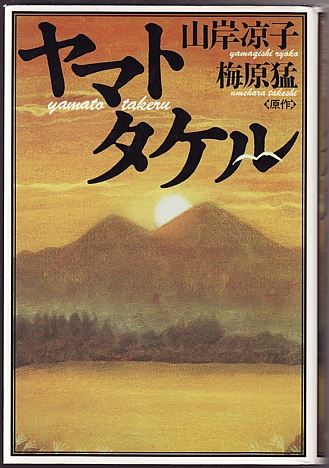
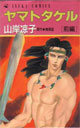
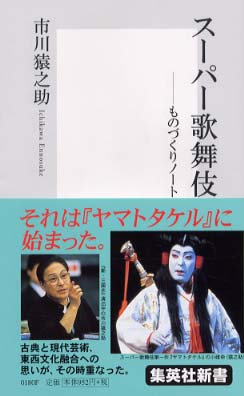
 これぞまさに日本最古の悲劇的英雄を描く壮大な叙事詩といったところ。こうして見ると、ヤマトタケルの辿った運命はちょっと源義経と似たところがあるあなとか思いつつ、一気に最後まで読みました。ハードカバーに相応しい内容。面白いし、日本神話の勉強にもなります(梅原猛氏の歴史解釈は多分に恣意的であると思われるが)。
これぞまさに日本最古の悲劇的英雄を描く壮大な叙事詩といったところ。こうして見ると、ヤマトタケルの辿った運命はちょっと源義経と似たところがあるあなとか思いつつ、一気に最後まで読みました。ハードカバーに相応しい内容。面白いし、日本神話の勉強にもなります(梅原猛氏の歴史解釈は多分に恣意的であると思われるが)。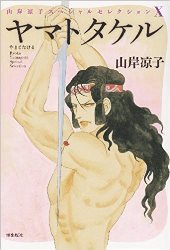
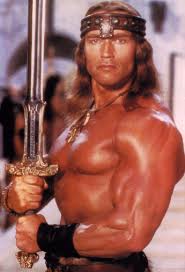
 「コナン・ザ・グレート」('82/米)は、アーノルド・シュワルツェネッガーの映画本格的デビュー作で(映画初出演作は「SF超人ヘラクレス」('69年)のヘラクレス役で、アーノルド・ストロングという名義でクレジットされている)、ジョン・ミリアスとオリバー・ストーンの共同脚本ですが、シュワちゃんは肉体は大いに披露するものの、まともなセリフは少ないです(似たような体格のスタントマンがいなかったため、スタントも自らこなすなどして頑張ったが、ラジー賞の"最低男優賞"になってしまった。一方、共演のサンダール・バーグマンは、ゴールデングローブ賞の年間最優秀新人賞に)。
「コナン・ザ・グレート」('82/米)は、アーノルド・シュワルツェネッガーの映画本格的デビュー作で(映画初出演作は「SF超人ヘラクレス」('69年)のヘラクレス役で、アーノルド・ストロングという名義でクレジットされている)、ジョン・ミリアスとオリバー・ストーンの共同脚本ですが、シュワちゃんは肉体は大いに披露するものの、まともなセリフは少ないです(似たような体格のスタントマンがいなかったため、スタントも自らこなすなどして頑張ったが、ラジー賞の"最低男優賞"になってしまった。一方、共演のサンダール・バーグマンは、ゴールデングローブ賞の年間最優秀新人賞に)。![Beastmaster [Soundtrack].jpg](http://hurec.bz/book-movie/Beastmaster%20%5BSoundtrack%5D.jpg)
 ます。「ジョーイ」('77年)のマーク・シンガー、「
ます。「ジョーイ」('77年)のマーク・シンガー、「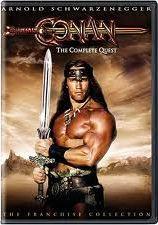
 「コナン・ザ・グレート」●原題:CONAN THE BARBARIAN●制作年:1982年●制作国:アメリカ●監督:ジョン・ミリアス●製作:バズ・フェイシャンズ/ラファエラ・デ・ラウレンティス●脚本:ジョン・ミリアス/オリバー・ストーン●撮影:キャロル・ティモシー・オミーラ●音楽:ベイジル・ポールドゥリス●原作:ロバート・E・ハワード「英雄コナン」●時間:128分●出
「コナン・ザ・グレート」●原題:CONAN THE BARBARIAN●制作年:1982年●制作国:アメリカ●監督:ジョン・ミリアス●製作:バズ・フェイシャンズ/ラファエラ・デ・ラウレンティス●脚本:ジョン・ミリアス/オリバー・ストーン●撮影:キャロル・ティモシー・オミーラ●音楽:ベイジル・ポールドゥリス●原作:ロバート・E・ハワード「英雄コナン」●時間:128分●出 演:アーノルド・シュワルツェネッガー/ジェームズ・アール・ジ
演:アーノルド・シュワルツェネッガー/ジェームズ・アール・ジ ョーンズ/サンダール・バーグマン/マックス・フォン・シドー/ベン・デイヴィッドスン/カサンドラ・ギャヴァ/ジェリー・ロペス/マコ岩松●日本公開:1982/07●配給:20世紀フォックス●最初に観た場所:新宿ローヤル(83-04-30)(評価:★★☆)
ョーンズ/サンダール・バーグマン/マックス・フォン・シドー/ベン・デイヴィッドスン/カサンドラ・ギャヴァ/ジェリー・ロペス/マコ岩松●日本公開:1982/07●配給:20世紀フォックス●最初に観た場所:新宿ローヤル(83-04-30)(評価:★★☆)  「ミラクルマスター 七つの大冒険」●原題:BEASTMASTER●制作年:1982年●制作国:アメリカ・イタリア●監督・脚本:ドン・コスカレリ●製作:バズ・フェイ
「ミラクルマスター 七つの大冒険」●原題:BEASTMASTER●制作年:1982年●制作国:アメリカ・イタリア●監督・脚本:ドン・コスカレリ●製作:バズ・フェイ シャンズ/ラファエラ・デ・ラウレンティス●脚本:ポール・ペパーマン/ シルヴィオ・タベット●撮影:ポール・ペパーマン
シャンズ/ラファエラ・デ・ラウレンティス●脚本:ポール・ペパーマン/ シルヴィオ・タベット●撮影:ポール・ペパーマン ●音楽:リー・ホールドリッジ●原作:ロバート・E・ハワード「英雄コナン」●時間:118分●出演:マーク・シンガー/タニア・ロバーツ/リップ・トーン/ジョン・エイモス/ジョシュア・ミルラッド/ロッド・ルーミス/ベン・ハマー●日本公開:1983/10●配給:日本ヘラルド映画●最初に観た場所:新宿東急(83-10-16)(評価:★★☆)
●音楽:リー・ホールドリッジ●原作:ロバート・E・ハワード「英雄コナン」●時間:118分●出演:マーク・シンガー/タニア・ロバーツ/リップ・トーン/ジョン・エイモス/ジョシュア・ミルラッド/ロッド・ルーミス/ベン・ハマー●日本公開:1983/10●配給:日本ヘラルド映画●最初に観た場所:新宿東急(83-10-16)(評価:★★☆)






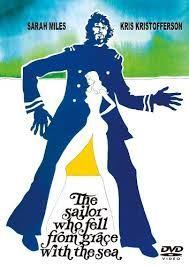
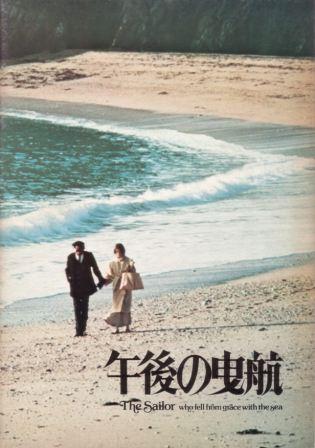



 この作品が海外でも評価を得たというのは、ジョン・ネイスンの名訳によって海外に紹介されたというのも大きいと思われますが、ギリシャ神話と重なるモチーフ(エディプス・コンプレックス)であるため、比較的分かり易かったというのもあるのではないでしょうか。
この作品が海外でも評価を得たというのは、ジョン・ネイスンの名訳によって海外に紹介されたというのも大きいと思われますが、ギリシャ神話と重なるモチーフ(エディプス・コンプレックス)であるため、比較的分かり易かったというのもあるのではないでしょうか。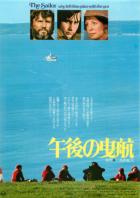
 「午後の曳航」 チラシ/サントラ盤(廃盤)
「午後の曳航」 チラシ/サントラ盤(廃盤)




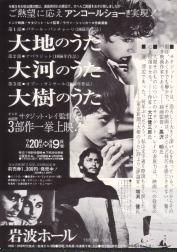
 総合ベスト10も、「天井桟敷の人々」「第三の男」「市民ケーン」「風と共に去りぬ」「大いなる幻影」「ウェストサイド物語」「2001年宇宙の旅」「カサブランカ」「駅馬車」「戦艦ポチョムキン」と"一昔前のオーソドックス"といった感じでしょうか(今でも名画であることには違いありませんが)。
総合ベスト10も、「天井桟敷の人々」「第三の男」「市民ケーン」「風と共に去りぬ」「大いなる幻影」「ウェストサイド物語」「2001年宇宙の旅」「カサブランカ」「駅馬車」「戦艦ポチョムキン」と"一昔前のオーソドックス"といった感じでしょうか(今でも名画であることには違いありませんが)。
 「禁じられた遊び」
「禁じられた遊び」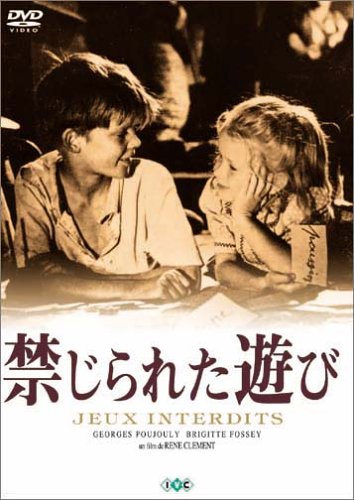
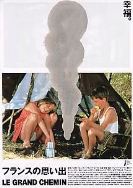

 「小さな悪の華」チラシ
「小さな悪の華」チラシ
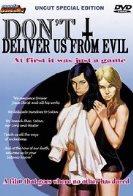
 一方、ジョエル・セリア監督の「小さな悪の華」('70年/仏)という作品は、早熟で魔性を持つ2人の15歳の少女が、ボードレールの「悪の華」を耽読し、農夫に裸を見せつけ、行きずりの男を誘拐して殺し、最後に焼身自殺するという衝撃的なものでしたが、祭壇作りにハマる少女たちには、「禁じられた遊び」の"十字架マニア"の少女ポーレットの"裏ヴァージョン"的なものを感じました。この作品は、"少女ポルノ"的描写であるともとれる場面があるため、製作当時、フランス本国では上映禁止となったとのことです。
一方、ジョエル・セリア監督の「小さな悪の華」('70年/仏)という作品は、早熟で魔性を持つ2人の15歳の少女が、ボードレールの「悪の華」を耽読し、農夫に裸を見せつけ、行きずりの男を誘拐して殺し、最後に焼身自殺するという衝撃的なものでしたが、祭壇作りにハマる少女たちには、「禁じられた遊び」の"十字架マニア"の少女ポーレットの"裏ヴァージョン"的なものを感じました。この作品は、"少女ポルノ"的描写であるともとれる場面があるため、製作当時、フランス本国では上映禁止となったとのことです。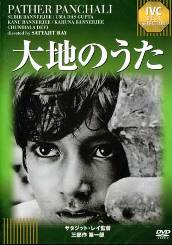

.jpg) 「大地のうた」('55年/インド)はサタジット・レイ監督の「オプー3部作」の第1作で、ベンガル地方の貧しい家庭の少年オプーの幼少期が描かれ、何と言っても、貧困のため雨中に肺炎で斃れたオプーの姉の挿話が哀しかったです。
「大地のうた」('55年/インド)はサタジット・レイ監督の「オプー3部作」の第1作で、ベンガル地方の貧しい家庭の少年オプーの幼少期が描かれ、何と言っても、貧困のため雨中に肺炎で斃れたオプーの姉の挿話が哀しかったです。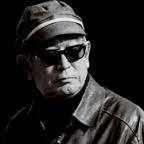 しかし、「大河のうた」は世界的には前作を上回る評価を得、1957年・第18回ヴェネツィア国際映画祭で金獅子賞を受賞、サタジット・レイは黒澤明を尊敬していましたが、同年にコンペティション部門に出品されていた黒澤明の「蜘蛛巣城」('57年/東宝)をコンペで破ったことになります。その黒澤明は、「サタジット・レイに会ったらあの人の作品が判ったね。眼光炯炯としていて、本当に立派な人なんだ。『蜘蛛巣城』がヴェネチア国際映画祭で『大河のうた』に負けた時、これはあたりまえだと思ったよ」と語っています。世界から喝采を浴びたサタジット・レイは、この作品を3部作とすることを決意、第3作「大樹のうた」('58年)は、青年となったオプーと、亡き妻の間に生まれ郷里に置いてきた息子との再会の物語になっています。
しかし、「大河のうた」は世界的には前作を上回る評価を得、1957年・第18回ヴェネツィア国際映画祭で金獅子賞を受賞、サタジット・レイは黒澤明を尊敬していましたが、同年にコンペティション部門に出品されていた黒澤明の「蜘蛛巣城」('57年/東宝)をコンペで破ったことになります。その黒澤明は、「サタジット・レイに会ったらあの人の作品が判ったね。眼光炯炯としていて、本当に立派な人なんだ。『蜘蛛巣城』がヴェネチア国際映画祭で『大河のうた』に負けた時、これはあたりまえだと思ったよ」と語っています。世界から喝采を浴びたサタジット・レイは、この作品を3部作とすることを決意、第3作「大樹のうた」('58年)は、青年となったオプーと、亡き妻の間に生まれ郷里に置いてきた息子との再会の物語になっています。.jpg)
.jpg)

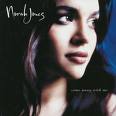 3作を通じて音楽にラヴィ・シャンカールのシタールが使われていることが、3部作に統一性を持たせることに繋がっていてるように思います。因みに、ラヴィ・シャンカールの2人の娘は、姉がジャズ歌手のノラ・ジョーンズ、妹がシタール奏者のアヌーシュカ・シャンカールで、この2人は異母姉妹です。なお、ラヴィ・シャンカールの演奏は、ジョージ・ハリスンの呼びかけで行われた飢饉救済コンサートのドキュメンタリー映画「
3作を通じて音楽にラヴィ・シャンカールのシタールが使われていることが、3部作に統一性を持たせることに繋がっていてるように思います。因みに、ラヴィ・シャンカールの2人の娘は、姉がジャズ歌手のノラ・ジョーンズ、妹がシタール奏者のアヌーシュカ・シャンカールで、この2人は異母姉妹です。なお、ラヴィ・シャンカールの演奏は、ジョージ・ハリスンの呼びかけで行われた飢饉救済コンサートのドキュメンタリー映画「 「
「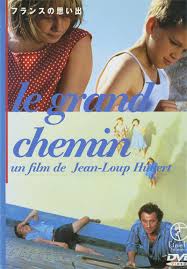
 「フランスの思い出」●原題:LE GRAND CHEMIN●制作年:1987年●制作国:フランス●監督・脚本:ジャン=ルー・ユベール●製作:パスカル・オメ/ジャン・フランソワ・ルプティ ●撮影:クロード・ルコント●音楽:ジョルジュ・グラニエ●時間:91分●出演:アネモーネ/リシャール・ボーランジェ/アントワーヌ・ユベール/ヴァネッサ・グジ/クリスチーヌ・パスカル/ラウール・ビイレー●日本公開:1988/08●配給:巴里映画●最初に観た場所:五反田TOEIシネマ (89-08-26)(評価:★★★★)●併映:「人生は長く静かな河」(エティエンヌ・シャティリエ)
「フランスの思い出」●原題:LE GRAND CHEMIN●制作年:1987年●制作国:フランス●監督・脚本:ジャン=ルー・ユベール●製作:パスカル・オメ/ジャン・フランソワ・ルプティ ●撮影:クロード・ルコント●音楽:ジョルジュ・グラニエ●時間:91分●出演:アネモーネ/リシャール・ボーランジェ/アントワーヌ・ユベール/ヴァネッサ・グジ/クリスチーヌ・パスカル/ラウール・ビイレー●日本公開:1988/08●配給:巴里映画●最初に観た場所:五反田TOEIシネマ (89-08-26)(評価:★★★★)●併映:「人生は長く静かな河」(エティエンヌ・シャティリエ)

 「小さな悪の華」●原題:MAIS NE NOUS DELIVREZ PAS DU MAL●制作年:1970年●制作国:フランス●監督・脚本:ジョエル・セリア●撮影:マルセル・コンブ●音楽:ドミニク・ネイ●時間:103分●出演:ジャンヌ・グーピル/カトリーヌ・ワグナー/ベルナール・デラン/ミシェル・ロバン●日本公開:1972/03●配給:日本ヘラルド映画●最初に観た場所:中野武蔵野館 (77-12-12)(評価:★★★☆)●併映:「
「小さな悪の華」●原題:MAIS NE NOUS DELIVREZ PAS DU MAL●制作年:1970年●制作国:フランス●監督・脚本:ジョエル・セリア●撮影:マルセル・コンブ●音楽:ドミニク・ネイ●時間:103分●出演:ジャンヌ・グーピル/カトリーヌ・ワグナー/ベルナール・デラン/ミシェル・ロバン●日本公開:1972/03●配給:日本ヘラルド映画●最初に観た場所:中野武蔵野館 (77-12-12)(評価:★★★☆)●併映:「

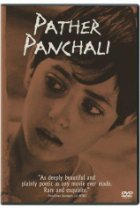
 「大地のうた」●原題:PATHER PANCHALI●制
「大地のうた」●原題:PATHER PANCHALI●制 作年:1955年●制作国:インド●監督・脚本:サタジット・レイ●撮影:スブラタ・ミットラ●音楽:ラヴィ・シャンカール●原作:ビブーティ・ブーション・バナージ●時間:125分●出演:カヌ・バナールジ/コルナ・バナールジ/スピール・バナールジ●日本公開:1966/10●配給ATG●最初に観た場
作年:1955年●制作国:インド●監督・脚本:サタジット・レイ●撮影:スブラタ・ミットラ●音楽:ラヴィ・シャンカール●原作:ビブーティ・ブーション・バナージ●時間:125分●出演:カヌ・バナールジ/コルナ・バナールジ/スピール・バナールジ●日本公開:1966/10●配給ATG●最初に観た場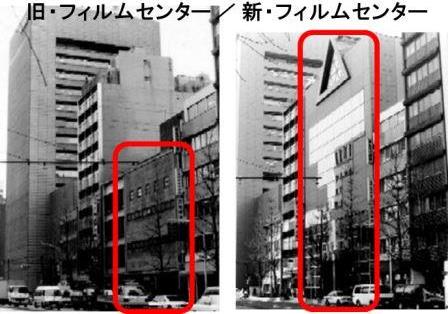

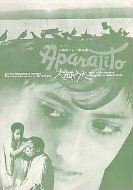
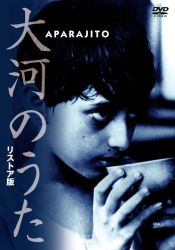
 「大河のうた」●原題:APARAJITO●制作年:1956年●制作国:インド●監督・脚本:サタジット・レイ●撮影:スブラタ・ミットラ●音楽:ラヴィ・シャンカール●原作:ビブーティ・ブーション・バナージ●時間:110分●出演:ピナキ・セン・グプタ/スマラン・ゴシャール/カヌ・バナールジ/コルナ・バナールジ ●日本公開:1970/11●配給:ATG●最初に観た場所:池袋テア
「大河のうた」●原題:APARAJITO●制作年:1956年●制作国:インド●監督・脚本:サタジット・レイ●撮影:スブラタ・ミットラ●音楽:ラヴィ・シャンカール●原作:ビブーティ・ブーション・バナージ●時間:110分●出演:ピナキ・セン・グプタ/スマラン・ゴシャール/カヌ・バナールジ/コルナ・バナールジ ●日本公開:1970/11●配給:ATG●最初に観た場所:池袋テア トルダイヤ (85-11-30)(評価:★★★★☆)●併映「大地のうた」「大樹のうた」(サタジット・レイ)
トルダイヤ (85-11-30)(評価:★★★★☆)●併映「大地のうた」「大樹のうた」(サタジット・レイ)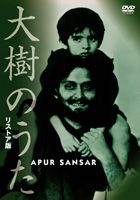
 「大樹のうた」●原題:APUR SANSAR●制作年:1958年●制作国:インド●監督・脚本:サタジット・レイ●撮影:スブラタ・ミットラ●音楽:ラヴィ・シャンカール●原作:ビブーティ・ブーション・バナージ●時間:105分●出演::ショウミットロ・チャテルジー /シャルミラ・タゴール/スワパン・ムカージ/アロク・チャクラバルティ●日本公開:1974/02●配給:ATG●最初に観た場所:池袋テアトルダイヤ (85-11-30)(評価:★★★★☆)●併映「大地のうた」「大河のうた」(サタジット・レイ)
「大樹のうた」●原題:APUR SANSAR●制作年:1958年●制作国:インド●監督・脚本:サタジット・レイ●撮影:スブラタ・ミットラ●音楽:ラヴィ・シャンカール●原作:ビブーティ・ブーション・バナージ●時間:105分●出演::ショウミットロ・チャテルジー /シャルミラ・タゴール/スワパン・ムカージ/アロク・チャクラバルティ●日本公開:1974/02●配給:ATG●最初に観た場所:池袋テアトルダイヤ (85-11-30)(評価:★★★★☆)●併映「大地のうた」「大河のうた」(サタジット・レイ)
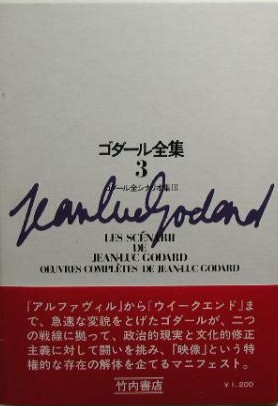
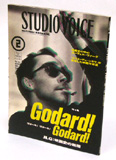
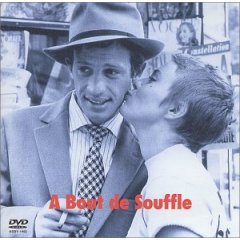

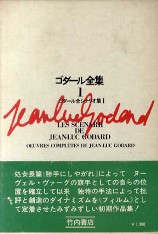
 面白いものが多く、またヴィヴィッドな印象を受けるのが意外かも知れません。よく知られているところでは、ジーン・セバーグ、ジャン=ポール・ベルモンド主演の「勝手にしやがれ」('59年)、アンナ・カリーナ、ベルモント主演の「気狂いピエロ」('65年)などの初期作品でしょうか。スチール写真が適度に配置され、読むと再度見たくなり、未見作品にも見てみたくなるものがありました。
面白いものが多く、またヴィヴィッドな印象を受けるのが意外かも知れません。よく知られているところでは、ジーン・セバーグ、ジャン=ポール・ベルモンド主演の「勝手にしやがれ」('59年)、アンナ・カリーナ、ベルモント主演の「気狂いピエロ」('65年)などの初期作品でしょうか。スチール写真が適度に配置され、読むと再度見たくなり、未見作品にも見てみたくなるものがありました。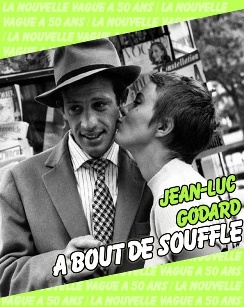


 パトリシアはミシェルとの愛を確認するため、ミシェルの居所をわざと警察に密告する―というもので、この不条理に満ちた話のオリジナル作者はフランソワ・トリュフォーですが、最終シナリオはゴーダルの頭の中にあったまま脚本化されずに撮影を開始したとのこと。台本無しの撮影にジャン=ポール・ベルモントは驚き、「どうせこの映画は公開されないだろうから、だったら好きなことを思い切りやってやろう」と思ったという逸話があります(1960年・第10回ベルリン国際映画祭「銀熊賞(監督賞)」受賞作)。
パトリシアはミシェルとの愛を確認するため、ミシェルの居所をわざと警察に密告する―というもので、この不条理に満ちた話のオリジナル作者はフランソワ・トリュフォーですが、最終シナリオはゴーダルの頭の中にあったまま脚本化されずに撮影を開始したとのこと。台本無しの撮影にジャン=ポール・ベルモントは驚き、「どうせこの映画は公開されないだろうから、だったら好きなことを思い切りやってやろう」と思ったという逸話があります(1960年・第10回ベルリン国際映画祭「銀熊賞(監督賞)」受賞作)。.jpg)
.jpg)


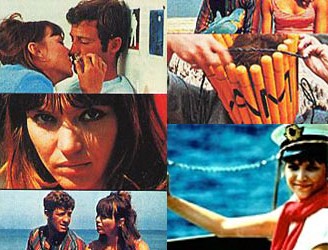
 「気狂いピエロ」は―、フェルディナン(ジャン=ポール・ベルモント)という男が、イタリア人の妻とパーティに行くが、パーティに退屈し戻ってきた家で、昔の恋人マリアンヌ(アンナ・カリーナ)と再会し、成り行きで彼女のアパートに泊まった翌朝、殺人事件に巻き込まれて、2人は逃避行を繰り返す羽目に。フェルディナンは孤島での生活を夢見るが、お互いにズレを感じたマリアンヌが彼を裏切って情夫の元へ行ったため、フェルディナンは彼女と情夫を射殺し、彼も自殺するというもの(1965年・第26回ヴェネチア国際映画祭「新鋭評論家賞」受賞作)。
「気狂いピエロ」は―、フェルディナン(ジャン=ポール・ベルモント)という男が、イタリア人の妻とパーティに行くが、パーティに退屈し戻ってきた家で、昔の恋人マリアンヌ(アンナ・カリーナ)と再会し、成り行きで彼女のアパートに泊まった翌朝、殺人事件に巻き込まれて、2人は逃避行を繰り返す羽目に。フェルディナンは孤島での生活を夢見るが、お互いにズレを感じたマリアンヌが彼を裏切って情夫の元へ行ったため、フェルディナンは彼女と情夫を射殺し、彼も自殺するというもの(1965年・第26回ヴェネチア国際映画祭「新鋭評論家賞」受賞作)。 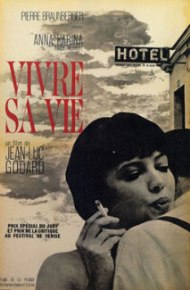

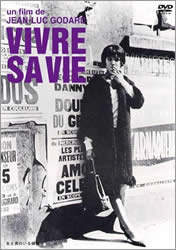
 「勝手にしやがれ」●原題:A BOUT DE SOUFFLE(英:BREATHLESS)●制作年:1959年●制作国:フランス●監督・脚本:ジャン=リュック・ゴダール●製作:ジョルジュ・ド・ボールガール●原作・原案・脚本:フランソワ・トリュフォー●撮
「勝手にしやがれ」●原題:A BOUT DE SOUFFLE(英:BREATHLESS)●制作年:1959年●制作国:フランス●監督・脚本:ジャン=リュック・ゴダール●製作:ジョルジュ・ド・ボールガール●原作・原案・脚本:フランソワ・トリュフォー●撮


 「気狂いピエロ」●原題:PIERROT LE FOU●制作年:1965年●制作国:フランス●監督・脚本:ジャン=リュック・ゴダール●製作:ジョルジュ・ド・ボールガール●撮影:ラウール・クタール●音楽:アントワース・デュアメル●原作:ライオネル・ホワイト「十一時の悪魔」●時間:109
「気狂いピエロ」●原題:PIERROT LE FOU●制作年:1965年●制作国:フランス●監督・脚本:ジャン=リュック・ゴダール●製作:ジョルジュ・ド・ボールガール●撮影:ラウール・クタール●音楽:アントワース・デュアメル●原作:ライオネル・ホワイト「十一時の悪魔」●時間:109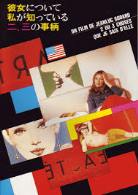 作国:フランス・イタリア●監督・脚本:ジャン=リュック・ゴダール●撮影:ラウール・クタール●音楽:ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン●原案:カトリーヌ・ヴィムネ●時間:90分●出演:ジョゼフ・ジェラール/マリナ・ヴラディ/アニー・デュプレー/ロジェ・モンソレ/ラウール・レヴィ/
作国:フランス・イタリア●監督・脚本:ジャン=リュック・ゴダール●撮影:ラウール・クタール●音楽:ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン●原案:カトリーヌ・ヴィムネ●時間:90分●出演:ジョゼフ・ジェラール/マリナ・ヴラディ/アニー・デュプレー/ロジェ・モンソレ/ラウール・レヴィ/ ジャン・ナルボニ/イヴ・ブネトン/エレナ・ビエリシック/クリストフ・ブルセイエ/マリー・ブルセイエ/マリー・カルディナル/ロベール・シュヴァシュー/ジャン=リュック・ゴダール(ナレーション)●日本公開:1970/10●配給:フランス映画社●最初に観た場所:有楽シネマ (83-05-28) (評価★★★)●併映:「気狂いピエロ 」(ジャン=リュック・ゴダール)
ジャン・ナルボニ/イヴ・ブネトン/エレナ・ビエリシック/クリストフ・ブルセイエ/マリー・ブルセイエ/マリー・カルディナル/ロベール・シュヴァシュー/ジャン=リュック・ゴダール(ナレーション)●日本公開:1970/10●配給:フランス映画社●最初に観た場所:有楽シネマ (83-05-28) (評価★★★)●併映:「気狂いピエロ 」(ジャン=リュック・ゴダール)



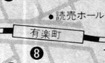 有楽シネマ (1955年11月14日オープン、1994年12月休館、1995年6月16日~シネマ有楽町(成人映画上映館)、1996年~銀座シネ・ラ・セット、159席) 2004(平成16)年1月31日閉館 跡地に建設のイトシアプラザ内に2007年10月シネカノン有楽町2丁目オープン、2009年12月4日ヒューマントラストシネマ有楽町に改称
有楽シネマ (1955年11月14日オープン、1994年12月休館、1995年6月16日~シネマ有楽町(成人映画上映館)、1996年~銀座シネ・ラ・セット、159席) 2004(平成16)年1月31日閉館 跡地に建設のイトシアプラザ内に2007年10月シネカノン有楽町2丁目オープン、2009年12月4日ヒューマントラストシネマ有楽町に改称
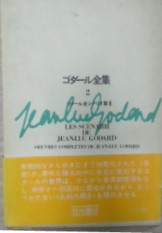
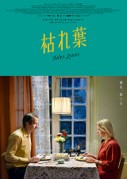


 アンサ(アルマ・ポウスティ)はヘルシンキのスーパーマーケットで働く独身女性、ホラッパ(ユッシ・バタネン)は酒に溺れながらも、どうにか産廃工事で働いている独身男性。ある夜、アンサは友人のリーサ(ヌップ・コイブ)とカラオケバーへ行き、そこへ同僚のフオタリ(ヤンネ・フーティアイネン)に誘われたホラッパがとやって来る。フオタリがリーサを口説こうとする中、アンサとホラッパは、互いの名前も知らぬまま惹かれ合う。アンサは、スーパーの廃棄食品を持ち帰ろうとしたとして事前通告無しで馘を言い渡され、上司の理不尽な通告に怒り、リーサと共にスーパーを辞める。アンサはパブの皿洗いの仕事に就くが、給料日にオーナーが麻薬の密売で警察に捕まってしまう。
アンサ(アルマ・ポウスティ)はヘルシンキのスーパーマーケットで働く独身女性、ホラッパ(ユッシ・バタネン)は酒に溺れながらも、どうにか産廃工事で働いている独身男性。ある夜、アンサは友人のリーサ(ヌップ・コイブ)とカラオケバーへ行き、そこへ同僚のフオタリ(ヤンネ・フーティアイネン)に誘われたホラッパがとやって来る。フオタリがリーサを口説こうとする中、アンサとホラッパは、互いの名前も知らぬまま惹かれ合う。アンサは、スーパーの廃棄食品を持ち帰ろうとしたとして事前通告無しで馘を言い渡され、上司の理不尽な通告に怒り、リーサと共にスーパーを辞める。アンサはパブの皿洗いの仕事に就くが、給料日にオーナーが麻薬の密売で警察に捕まってしまう。 偶然そこにホラッパがやってきて、カフェでコーヒーを飲み、その後2人は映画館に行くことに。映画館でゾンビ映画を観て、帰り際ホラッパは「また会いたい」と言う。名前は今度教えると言い、アンサは電話番号をメモした紙をホラッパに渡して頬にキスをするが、ホラッパはそのメモを失くしてしまう。ホラッパは帰ってからメモが無いことに気づくが、探そうにも名前も分からず途方に暮れる。その上飲酒がバレて仕事もクビに
偶然そこにホラッパがやってきて、カフェでコーヒーを飲み、その後2人は映画館に行くことに。映画館でゾンビ映画を観て、帰り際ホラッパは「また会いたい」と言う。名前は今度教えると言い、アンサは電話番号をメモした紙をホラッパに渡して頬にキスをするが、ホラッパはそのメモを失くしてしまう。ホラッパは帰ってからメモが無いことに気づくが、探そうにも名前も分からず途方に暮れる。その上飲酒がバレて仕事もクビに なってしまう。同僚のフタリオに「再会して結婚しかけた」と話すが、連絡しようにも彼女の連絡先を知らないことを言い嘆く。一方アンサも、ホラッパから電話がないことにヤキモキする。しかし2人は偶然映画館の前で再会し、アンサはホラッパをディナーに招待する。穏やかに食事をしていたが、隠れて酒を飲むホラッパに対し、アンサは「アル中はご免よ」と言い、父と兄がお酒によって死に、母はそれを嘆いて死んだと話す。するとホラッパは「指図されるのはご免だ」と言って出ていく。不運な偶然と現実の過酷さが、彼らをささやかな幸福から遠ざける中、果たして2人は、無事に再会を果たし、想いを通い合わせることができるのか―。
なってしまう。同僚のフタリオに「再会して結婚しかけた」と話すが、連絡しようにも彼女の連絡先を知らないことを言い嘆く。一方アンサも、ホラッパから電話がないことにヤキモキする。しかし2人は偶然映画館の前で再会し、アンサはホラッパをディナーに招待する。穏やかに食事をしていたが、隠れて酒を飲むホラッパに対し、アンサは「アル中はご免よ」と言い、父と兄がお酒によって死に、母はそれを嘆いて死んだと話す。するとホラッパは「指図されるのはご免だ」と言って出ていく。不運な偶然と現実の過酷さが、彼らをささやかな幸福から遠ざける中、果たして2人は、無事に再会を果たし、想いを通い合わせることができるのか―。 アキ・カウリスマキ監督が「
アキ・カウリスマキ監督が「 アンサもホラッパも厳しい現実の中にいますが、それぞれに自分のことを気にかけてくれる同僚(二人とも解雇されるので"元同僚"になるが)の友人がいるのが救いでした(最後の方でホラッパが入院する病院の看護師も優しかった)。アキ・カウリスマキ監督の、競争社会ではない、普通の社会(競争社会の外)に生きる人々への温かい視線を感じます。
アンサもホラッパも厳しい現実の中にいますが、それぞれに自分のことを気にかけてくれる同僚(二人とも解雇されるので"元同僚"になるが)の友人がいるのが救いでした(最後の方でホラッパが入院する病院の看護師も優しかった)。アキ・カウリスマキ監督の、競争社会ではない、普通の社会(競争社会の外)に生きる人々への温かい視線を感じます。 映画館にはブリジット・バルドーの映画ポスターがあったり、アラン・ドロンの「
映画館にはブリジット・バルドーの映画ポスターがあったり、アラン・ドロンの「 また、主演のアルマ・ポウスティは、来日時のインタビューで「この映画は荷物を抱えた孤独な人々が人生の後半で出会う物語だ。人生の後半で恋に落ちるのは勇気がいる」と説明しています。演出はフリーではなく考え抜かれており、「とにかくセリフを覚えてこい。でも練習するな」と指示されるそう。またほとんどのシーンがワンテイクで撮影されているため、ポウスティは「俳優としては怖い」と吐露。さらにカウリスマキが現場でモニタを使わないことにも触れ、「一度カメラをのぞいて照明や小道具の位置を自分でチェックしたら、カメラの横に座ってワンテイクで撮る。あとからモニタはチェックしない。何が撮れているのかわかっているからです」と説明しています。
また、主演のアルマ・ポウスティは、来日時のインタビューで「この映画は荷物を抱えた孤独な人々が人生の後半で出会う物語だ。人生の後半で恋に落ちるのは勇気がいる」と説明しています。演出はフリーではなく考え抜かれており、「とにかくセリフを覚えてこい。でも練習するな」と指示されるそう。またほとんどのシーンがワンテイクで撮影されているため、ポウスティは「俳優としては怖い」と吐露。さらにカウリスマキが現場でモニタを使わないことにも触れ、「一度カメラをのぞいて照明や小道具の位置を自分でチェックしたら、カメラの横に座ってワンテイクで撮る。あとからモニタはチェックしない。何が撮れているのかわかっているからです」と説明しています。 ヘルシンキ在住のアンナ&カイサ・カルヤライネン姉妹によるバンド「MAUSTETYTÖT(マウステテュトット)」も出演し、劇中歌として「Syntynyt suruun ja puettu pettymyksin(悲しみに生まれ、失望を身にまとう)」という歌が歌われていますが、無口な主人公の気持ちを代弁しているような歌で、こうした地元のミュージシャンの劇中での起用は「
ヘルシンキ在住のアンナ&カイサ・カルヤライネン姉妹によるバンド「MAUSTETYTÖT(マウステテュトット)」も出演し、劇中歌として「Syntynyt suruun ja puettu pettymyksin(悲しみに生まれ、失望を身にまとう)」という歌が歌われていますが、無口な主人公の気持ちを代弁しているような歌で、こうした地元のミュージシャンの劇中での起用は「 「ルアーヴルの靴みがき」では、カウリスマキ監督の愛犬〈ライカ〉が登場し、カンヌ国際映画祭で優秀な演技を披露した犬に贈られる賞「パルム・ドッグ賞」の「審査員特別賞」を受賞していますが、この作品でも、〈アルマ〉という犬が、アンサが殺処分されそうだったのを拾ってやった犬として登場し、ちゃんと演技していて(笑)、「パルム・ドッグ賞」の「審査員大賞」を受賞しています。アンサが犬に付けた名前は「チャップリン」。ラストでアンサがホラッパと画面の奥へ歩いて行くシーンは、「
「ルアーヴルの靴みがき」では、カウリスマキ監督の愛犬〈ライカ〉が登場し、カンヌ国際映画祭で優秀な演技を披露した犬に贈られる賞「パルム・ドッグ賞」の「審査員特別賞」を受賞していますが、この作品でも、〈アルマ〉という犬が、アンサが殺処分されそうだったのを拾ってやった犬として登場し、ちゃんと演技していて(笑)、「パルム・ドッグ賞」の「審査員大賞」を受賞しています。アンサが犬に付けた名前は「チャップリン」。ラストでアンサがホラッパと画面の奥へ歩いて行くシーンは、「
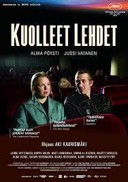 「枯れ葉」●原題:KUOLLEET LEHDET(英:FALLEN LEAVES)●制作年:2023年●制作国:フィンランド・ドイツ●監督・脚本:アキ・カウリスマキ●製作:ミーシャ・ヤーリ/アキ・カウリスマキ/マーク・ルオフ/アルマ(犬)●撮影:ティモ・サルミネン●時間:81分●出演:アルマ・ポウスティ/ユッシ・バタネン/ヤンネ・フーティアイネン/ヌップ・コイブ/マッティ・オンニスマー/アルマ(犬のチャップリン)●日本公開:2023/12●配給:ユーロスペース●最初に観た場所:角川シネマ有楽町(スクリーン1)(24-01-24)(評価:★★★★☆)
「枯れ葉」●原題:KUOLLEET LEHDET(英:FALLEN LEAVES)●制作年:2023年●制作国:フィンランド・ドイツ●監督・脚本:アキ・カウリスマキ●製作:ミーシャ・ヤーリ/アキ・カウリスマキ/マーク・ルオフ/アルマ(犬)●撮影:ティモ・サルミネン●時間:81分●出演:アルマ・ポウスティ/ユッシ・バタネン/ヤンネ・フーティアイネン/ヌップ・コイブ/マッティ・オンニスマー/アルマ(犬のチャップリン)●日本公開:2023/12●配給:ユーロスペース●最初に観た場所:角川シネマ有楽町(スクリーン1)(24-01-24)(評価:★★★★☆)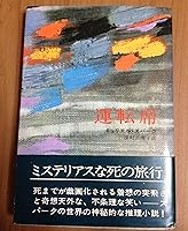
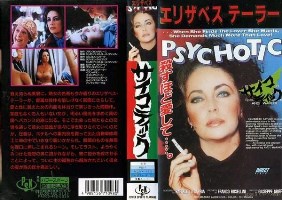
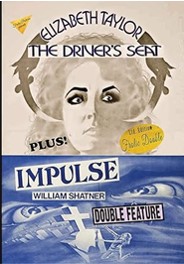
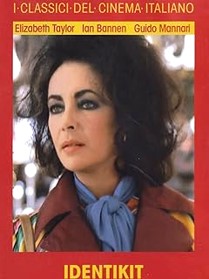
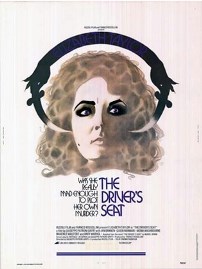 この作品は「
この作品は「 映画は劇場未公開で、80年代に日
映画は劇場未公開で、80年代に日 本語ビデオが「パワースポーツ企画販売」という主としてグラビア系映像ソフトを手掛ける会社から「サイコティック」というタイトルで発売(年月不明)され、こうした会社からリリースされたのは、テイラーの乳首が透けて見えるカットがあるためでしょうか("色モノ"扱い?)。'20年5月にDVDの海外版が再リリーズ、'22年12月VOD(動画配信サービス)のU-NEXTで日本語字幕付きで配信されました。
本語ビデオが「パワースポーツ企画販売」という主としてグラビア系映像ソフトを手掛ける会社から「サイコティック」というタイトルで発売(年月不明)され、こうした会社からリリースされたのは、テイラーの乳首が透けて見えるカットがあるためでしょうか("色モノ"扱い?)。'20年5月にDVDの海外版が再リリーズ、'22年12月VOD(動画配信サービス)のU-NEXTで日本語字幕付きで配信されました。 ではないでしょうか。一部改変されていて、リズが当初からインターポールにマークされている設定になっていますが(ただしその理由は最後まで明かされない)、これは、映画の脚本にも参加したミュリエル・スパークがインターポールに勤務したことがあるという経歴の持ち主のためでしょうか(アンディ・ウォーホルが出演している)。
ではないでしょうか。一部改変されていて、リズが当初からインターポールにマークされている設定になっていますが(ただしその理由は最後まで明かされない)、これは、映画の脚本にも参加したミュリエル・スパークがインターポールに勤務したことがあるという経歴の持ち主のためでしょうか(アンディ・ウォーホルが出演している)。 エリザベス・テイラーは体当たり的にこの難役に挑んでいますが、役が役だけに、また、ましてやオチが不条理オチだけに、評判はイマイチだったようです(彼女の生涯最悪の映画とも言われているらしい)。
エリザベス・テイラーは体当たり的にこの難役に挑んでいますが、役が役だけに、また、ましてやオチが不条理オチだけに、評判はイマイチだったようです(彼女の生涯最悪の映画とも言われているらしい)。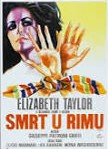 また、「嘱託殺人」を選んだのは、主人公がカソリックで、自殺が禁じられていることも理由として考えられるように思いました(自分を殺す際に手足を縛ることまで要求したのは、あくまでも殺人だと印象付けるため)。
また、「嘱託殺人」を選んだのは、主人公がカソリックで、自殺が禁じられていることも理由として考えられるように思いました(自分を殺す際に手足を縛ることまで要求したのは、あくまでも殺人だと印象付けるため)。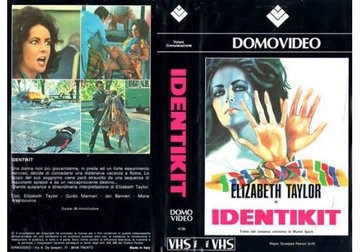
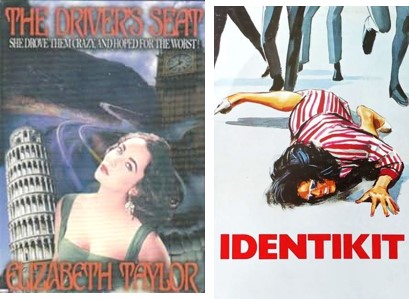 「サイコティック」●原題:IDENTIKIT(DRIVER'S SEAT/伊:SMRT U RIMU)●制作年:1974年●制作国:イタリア●監督:ジュゼッペ・パトローニ・グリッフィ●製作:フランコ・ロッセリーニ●脚本:ラファエル・ラ・カプリア/ジュゼッペ・パトローニ・グリッフィ/ミュリエル・スパーク●撮影:ヴィットリオ・ストラーロ●音楽:フランコ・マンニーノ●時間:105分●出演:エリザベス・テイラー/イアン・バネン/グイード・マンナリ/モナ・ウォッシュボーン/アンディ・ウォーホル●配信:2022/12●配信元:U-NEXT(評価:★★★★)
「サイコティック」●原題:IDENTIKIT(DRIVER'S SEAT/伊:SMRT U RIMU)●制作年:1974年●制作国:イタリア●監督:ジュゼッペ・パトローニ・グリッフィ●製作:フランコ・ロッセリーニ●脚本:ラファエル・ラ・カプリア/ジュゼッペ・パトローニ・グリッフィ/ミュリエル・スパーク●撮影:ヴィットリオ・ストラーロ●音楽:フランコ・マンニーノ●時間:105分●出演:エリザベス・テイラー/イアン・バネン/グイード・マンナリ/モナ・ウォッシュボーン/アンディ・ウォーホル●配信:2022/12●配信元:U-NEXT(評価:★★★★)