「●お 大江 健三郎」の インデックッスへ Prev|NEXT ⇒ 【416】 大江 健三郎 『「自分の木」の下で』
「●「谷崎潤一郎賞」受賞作」の インデックッスへ
作者の前・後期の境目にあり両者を繋ぐ作品。"平面的"から"立体的"になった。
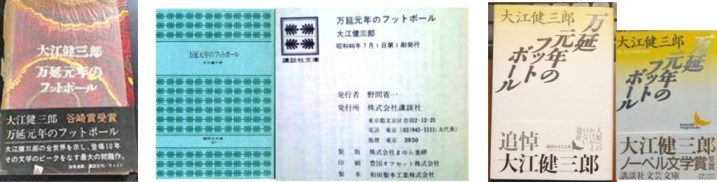
『「万延元年のフットボール」 大江健三郎 純文学書下ろし特別作品 1967年11月』『万延元年のフットボール (講談社文庫)』['71年]『万延元年のフットボール (講談社文芸文庫)』['88年]
1967(昭和42)年度・第3回「谷崎潤一郎賞」受賞作。
英語専任講師・根所蜜三郎と妻・菜採子の間に生まれた子には頭蓋に重篤な障害があり、養育施設に預けられている。蜜三郎のたった一人の親友は異常な姿で縊死した。蜜三郎と菜採子の関係は冷めきり、菜採子は酒に溺れている。蜜三郎の弟・鷹四は60年安保の学生運動に参加後に転向し渡米、放浪して帰国する。米国で故郷の倉屋敷を買い取りたいというスーパー・マーケット経営者の朝鮮人(スーパーマーケットの天皇)に出会い、その取引を進めるためだ。蜜三郎夫婦は、鷹四に、生活を一新する契機にしてはと提案され、鷹四と彼を信奉する年少の星男、桃子とともに郷里の森の谷間の村に帰郷する。倉屋敷は庄屋だった曽祖父が建てたもので、曽祖父の弟は百年前の万延元年の一揆の指導者だった。曽祖父の弟の一揆後の身の上については、兄弟で見解が違う。鷹四の考えでは騒動を収束させるために保身を図る曽祖父により殺されたとされ、蜜三郎の考えでは曽祖父の手を借りて逃亡したと。鷹四は曽祖父の弟を英雄視している。実家には父母は既に亡くなっており、戦後予科練から復員した兄弟の兄・S兄さんは、戦後の混乱で生じた朝鮮人部落の襲撃で命を落としていた。兄弟の妹は知的障害があり、父母の死後に伯父の家に貰われていったが、そこで自殺した。倉屋敷は小作人の大食病の女ジン夫婦が管理している。S兄さんの最期についても兄弟で食い違う。当時幼児だった鷹四は、朝鮮人部落襲撃時のS兄さんの英雄的な姿を記憶しているが、蜜三郎は、S兄さんは、騒動の調停の死者数の帳尻合わせで日本人の側から引き渡され殺された哀れな犠牲者だったと。村はスーパー・マーケットの強力な影響下にあり、個人商店は行き詰まってスーパーに借金を負っている。スーパーの資本で村の青年たちは養鶏場を経営していたが、寒さで鶏が全滅する。その事後策を相談されたことから、鷹四は青年たちに信頼され、青年たちを訓練指導するためのフットボール・チームを結成する。妻の菜採子は、退嬰的に一人閉じこもる蜜三郎から離れ、快活に活動する鷹四らと活動を共にするようになる。鷹四はチームに万延元年の一揆の様子などを伝え、チームに暴力的なムードが高まる。正月に大雪が降り、村の通信や交通が途絶されると、チームを中心に村全体によるスーパーの略奪が起きる。暴動は伝承の御霊信仰の念仏踊りに鼓舞された祝祭的なものだった。鷹四は菜採子と姦淫するようになったが、村の娘を強姦殺人したことから青年たちの信奉を失い、猟銃で頭を撃ち抜いて自殺する。自殺の直前、鷹四は蜜三郎に「本当の事をいおうか」と過去に自殺した知的障害のあった妹を言いくるめて近親相姦していたことを告白する。鷹四の破滅的な暴力の傾向は、自己処罰の感情からきていた。雪が止み、交通が復活した村にスーパー・マーケットの天皇が倉屋敷解体のために現れ、スーパー略奪は不問に付される。倉屋敷の地下倉が発見され、曽祖父の弟は逃亡したのではなく、地下で自己幽閉して明治初頭の第二の一揆を指揮・成功させ、その後も自由民権の流れを見守ったことが判明する。夫婦は和解し、養護施設から子供を引き取り、菜採子が受胎している鷹四の子供を産み育てることを決意、蜜三郎はオファーのあったアフリカでの通訳の仕事を引き受けることにする―。
今年['23年]3月に亡くなった大江健三郎(1935-2023/88歳没)の長編小説で、作者の数ある作品の中でも最高傑作との呼び声が高く、また、ノーベル文学賞の受賞理由として挙げられた作者の5作品の中でも、特に評価が高かった作品でもあります(実際、ストーリーを振り返るだけで、面白い)。
この作品を読むに際しては、同じくその5作品の1つである前作『個人的な体験』を先に読むといいと思います。『個人的な体験』の主人公・鳥(バード)も予備校の教員で、少年期よりアフリカに行くという夢を持ち続けていて、子が出生した際に頭部に重篤な障害があることが分かった際も、障害児の親となることから逃避して、アフリカへ行くことを思い描いていましたたが、ある時急に、子どもに手術を受けさせ、子どもを育てようと思い直します。このように、この作品と様々な点で、共通または対照的関係にあると言えます。
そして、この作品は、『個人的な体験』と並んで(『個人的な体験』のところでもそう書いたが)大江文学の前期と後期の境目にあり、かつ両者を繋ぐ作品である言えます。文芸評論家的に言えば、前期の「人間像の提示」というモチーフが示されなくなり(『個人的な体験』にはまだそれが残っているか)、後期の「世界像の提示」というモチーフが同作から現れ、個人的に言わせてもらえれば作品が"平面的"なのものから"立体的"なものに変化したという印象です。
ただ、これも言わせてもらえれば、大江文学のピーク時の作品であり(『<死者の奢り』から10年くらいでピークに達したことになるが)、それまで短い期間に何度も作風を変化させてきた作者が、ここに1つの完成形をみたのはいいけれど、その後の作品は、多分にこの作品のリフレイン的要素が強いものが多かったように思います(同じモチーフやテーマが何度も出てくる)。
この小説が「空想小説」的なモチーフでありながら、一定のリアリティを持って読めるのは、作者の先祖に実際にこの小説に出てくる人物に似たような人がいたこと(長兄をモデルにした予科練帰りの登場人物はその典型)、作者が幼い頃、実家の使用人だった語り部のような老女から明治初期に地元で起きた一揆の話を聞かされていたこと、作者自身が自分の故郷を念頭に置いて、はっきりしたイメージを持ちながら書いていること、などがその理由としてあげられるのではないかということを、作者の死没を契機に、文庫解説並びに『大江健三郎 作家自身を語る』('07年/新潮社、、'13年/新潮文庫)を読み直してでみて思った次第です。

 【1971年文庫化[講談社文庫]/1988年再文庫化[講談社文芸文庫]】
【1971年文庫化[講談社文庫]/1988年再文庫化[講談社文芸文庫]】
『「万延元年のフットボール」 大江健三郎 純文学書下ろし特別作品 1967年11月』
