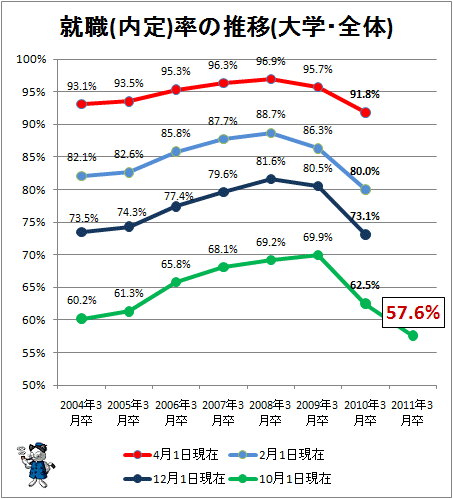「●採用・人材確保」の インデックッスへ Prev|NEXT ⇒ 【1652】 中嶋 嶺雄 『なぜ、国際教養大学で人材は育つのか』
「●労働経済・労働問題」の インデックッスへ
就活の現況を概観するにはいい。大学の新たな取り組みをもっと掘り下げて取材して欲しかった。
本書によれば、就職氷河期レベルと言われた2010年春の就職状況は、文部科学省の「学校基本調査」(2010年8月公表)によると、前年より5万3000人減の32万9000人と厳しいものだったが、2011年春は、より厳しい見通しにあるとあります(因みに就職率で言うと、本書には無いが、2011年春の最終数値は61.6%で、前年最終の数字との比較で0.8ポイント上昇したものの、ほぼ横ばいだったとみていいか)。
また、厚生労働省の「就職内定状況調査」(年4回、10月、12月、2月、4月に調査)では、2011年春の内定状況は、2010年10月1日時点で57.6%と「氷河期」を下回る過去最悪となっているとあります(因みに、2011年4月の最終内定率は91.0%で、こちらは最終数値も過去最低だった)。
大学ジャーナリストである著者は、その原因を、単にリーマン・ショック後の不況による求人減少のせいだとして片づけることはできないとし、そこには、「就活」をめぐっての大学側、国側、採用する企業側のさまざまなウソ・ゆがめられた真実があり、それらがいびつな就活構造を作り出し、学生を疲弊させるだけでなく、結局は採用企業にも大学にとっても不利益をもたらすという悪循環を生みだしているとしています。
例えば、文部科学省・厚生労働省の「大学卒業(予定)者の就職内定率調査(前記:厚生労働省の「就職内定状況調査」と同じ)」(2010年5月公表)によれば、「10年4月1日時点での就職率(内定率)は91.8%」となっているとマスコミも伝えましたが、マスコミを通して発表される政府の就職内定率調査や、大学が公表している就職率は、現役学生だけを対象としたものであり、しかも、内定率というのはあくまで就職希望者に占める就職決定者の割合であって、厳しい就活に耐えられず途中で就職を諦めた学生などは分母に含まれていないそうです(2011年の「過去最低の数字」が、前述の通り「91.0%」だったというのは、確かに実感とずれているが、要因はここにある)。
また、大学によっては、自大学が出資して派遣会社を設立し、就職が決まらない学生をとりあえずそこへ押し込むことによって、就職内定率の低下を表面上防ぐようなこと(水増し工作?)が行われているとのことです(個人的に知るところでは、早稲田大学なども「キャンパス」という名の100%出資の人材派遣会社を、随分以前から持っている。会社設立当初は、学内事務等の要員を、校風を知る自大学の出身者で賄おうというというのが狙いだったと思われるが)。
こうした統計の"ウソ"を明らかにする一方で、企業側についても、学生に対して求める能力の評価基準が曖昧であることを、これもまた統計をもって明らかにし、その結果として、大学・学生・企業の間に相互不信が渦巻いているとしています(この「就職率」と「就職内定率」の30ポイントもの数字の開きは何とかならないものか。例えば、東京工業大学などは、大学院進学者が多いので「就職率」は落ちるが「就職内定率」は高い。そもそも、「就職内定状況」の調査対象は、国立大学を中心とする62校で、私立では、明治・青山・立教・法政などは除かれている)。
また、「厳選採用」を求められながらも、理想の人材と現実の学生とのギャップに戸惑い、また、ネット・エントリーなどで母集団が拡大し、膨大な費用と労力を消費せざるを得ない、企業の採用現場の厳しい現状についても言及しています。
結果として、大手企業などの場合、予め学校を有名校に絞る「ターゲット採用」などが行われているとのことです。
更に、就職活動の早期化が「学生から学びの時間を奪っている」という実態が大学教育にもたらす悪影響についても述べていますが、早期化の根底には、「大学での勉強は仕事にはあまり役立たない」「日本の大学教育は米国などのように、自分の頭で考える力が身につく教育ではなく、単なる知識の習得に重点が置かれている」との考えがあるようだとしています。
しかし一方で、著者によれば、最近では大学教育も変わりつつあり、「問題発見力、問題解決力を鍛える教育」に力を入れたり、文科省が学生が自分に合った仕事を見つけて卒業後に自立できる「就業力」の育成に取り組む大学・短大への支援を2010年から始めたのを受けて、独自の授業プログラムを実施している大学も増えているとのことです。
そうした大学の新たな取り組みについても紹介していますが、東海大学の就職指導は「総戦力」であるという考えに基づく同窓会や保護者なども一体化した親身のサポート体制での対応、明治大学の学長主導による「就職情報懇談会」、「就職率100%」という秋田の国際教養大学(AIU)の「すべての授業を英語で行う」などの国際人を養成するという教育方針、立教大学経営学部の「BLP(ビジネス・リーダーシップ・プログラム)」による人材育成など、どれも興味深いものでした。
企業側にも、新卒採用の早期化を見直したり、本格的なインターンシップを通して、時間をかけて能力適性を見極めるなど、新たな動きが出てきているようですが、今後もこうした取り組みが拡がっていくよう思います。
著者は日経記者出身のベテランのジャーナリストであり、本書は「就活」の現状を把握するにはいい本ですが、現状分析がやや長過ぎて、大学の「就業力」を育成するプログラムの紹介に至るまでに紙数が尽きた感もあります。
その分、全体を通して提案的な部分の比重が小さくなり、「大学が変われば、企業も動き、就活も変わる」というのが著者の考えなのですが、肝心の大学の取り組み状況の紹介がそれこそ新聞記事程度(コラム記事未満)のものであり、実際に現場を取材したシズル感のようなものが感じられず、詰まるところ「大学」ジャーナリストとしての著者の本領は活かされてないように思われたのが残念です。