「●近代日本文学 (-1948)」の インデックッスへ Prev|NEXT ⇒ 【2618】 吉野 源三郎 『君たちはどう生きるか』
「○近代日本文学 【発表・刊行順】」の インデックッスへ 「●「死」を考える」の インデックッスへ
主人公・尾田高雄のハンセン病施設入所日を描く。佐柄木の人物像や哲学が強烈に印象に残った。

『いのちの初夜』['37年]『いのちの初夜 (角川文庫 緑 83-1)』['55年]『いのちの初夜 (角川文庫) 』['20年改版]北条民雄(1914-1937/23歳没)
主人公・尾田高雄は、癩病を患ったために、入院すべく病院へ向かう。病気の宣告を受けてからの尾田は、癩病で死ぬくらいなら、病院に入るくらいなら、と事ある毎に自殺を試みるが、その度に何か別の心持ちがよぎり、思いとどまる。病院に着いた尾田は、佐柄木という癩病の患者に出会う。病院には尾田と佐柄木の他にも沢山の癩病の患者が入院しているが、その多くが重度の患者であるため、佐柄木は、まだ軽度の患者である尾田を格好の話し相手であると思ったのか、親交を深めようとしてくる。しかし尾田は、自身が癩病のため入院せざるを得ない現状を未だに受け入れられず、またしても自殺をはかる。それは未遂に終わるが、一連の出来事を目撃していた佐柄木は、尾田に「意志の大いさは絶望の大いさに正比する」と説く。病状が悪化しながらも生きる佐柄木と、「生きる態度」を定められずにいる尾田。しかし、尾田は佐柄木との会話を繰り返すうちに、「やはり生きてみることだ」という気持ちになる―(「いのちの初夜」)。
 川端康成など名だたる文豪からその才能を認められながらも、ハンセン病を患い若くしてこの世を去った北条民雄(1914-1937/23歳没)の作品集で、表題作「いのちの初夜」(1936(昭和11)年)は、ハンセン病の診断を受けた主人公・尾田が、療養施設に入所した日とその夜に起きた出来事及び主人公の心象を描いた小説(川端康成は「この小説を読むと、たいていの小説がポンコツに見える」と称賛した)。そのほかに「眼帯記」「癩院受胎」「癩院記録」「続癩院記録」「癩家族」「望郷歌」「吹雪の産声」の7作が収められており、いずれもハンセン病の隔離施設が舞台になっています。
川端康成など名だたる文豪からその才能を認められながらも、ハンセン病を患い若くしてこの世を去った北条民雄(1914-1937/23歳没)の作品集で、表題作「いのちの初夜」(1936(昭和11)年)は、ハンセン病の診断を受けた主人公・尾田が、療養施設に入所した日とその夜に起きた出来事及び主人公の心象を描いた小説(川端康成は「この小説を読むと、たいていの小説がポンコツに見える」と称賛した)。そのほかに「眼帯記」「癩院受胎」「癩院記録」「続癩院記録」「癩家族」「望郷歌」「吹雪の産声」の7作が収められており、いずれもハンセン病の隔離施設が舞台になっています。
 「いのちの初夜」は、社会的な生きる希望を失い、おのれの肉体も失われていく、それでも生きざるをえない、「生きる」意味を問い続けるハンセン病患者でなければ書けない作品で、文章も平明だけにストレートに心に響きます。この作品は2023年2月にNHK・Eテレの「100分de名著」で取り上げられ話題を呼びました(ゲストは、かつてアイドル・歌手・女優で、今は文筆家・テレビ番組のコメンテーターとしてメディアに登場する機会が多い中江有里氏)。
「いのちの初夜」は、社会的な生きる希望を失い、おのれの肉体も失われていく、それでも生きざるをえない、「生きる」意味を問い続けるハンセン病患者でなければ書けない作品で、文章も平明だけにストレートに心に響きます。この作品は2023年2月にNHK・Eテレの「100分de名著」で取り上げられ話題を呼びました(ゲストは、かつてアイドル・歌手・女優で、今は文筆家・テレビ番組のコメンテーターとしてメディアに登場する機会が多い中江有里氏)。
『NHK 100分 de 名著 北條民雄『いのちの初夜』 2023年2月 (NHKテキスト)』
雑誌「文學界」(1936年2月号)に掲載され、原題は「最初の一夜」で、川端康成により「いのちの初夜」に改題され、第3回「芥川賞」の候補にもなりました。作品の冒頭でその施設の立地は「東京から二十マイルそこそこの」と記述されており、これは作者である北條民雄が入所した東京府北多摩郡東村山村の国立療養所多磨全生園(全生園)の位置とほぼ一致します。
ただし、北條民雄は自分の作品が、「癩(らい)文学」と見なされることに強い拒否感を抱いており、「頃日雑記」の中で「私は癩文学などいうものがあろうとは思われぬが、しかし、よし癩文学というものがあるものとしても、決してそのようなものを書きたいとは思わない(中略)私はただ人間を書きたいと思っているのだ。癩など、単に、人間を書く上における一つの「場合」に過ぎぬ」と語っています。
では、この作品をどう読めばいいのか。北條民雄の評伝である『火花 北条民雄の生涯』の作者で、ノンフィクション作家の髙山文彦氏はこう述べています。
「もちろん、読者は作者の意図から離れて好きに読むべきです。しかし、重要なのは作中において、北條が常に健常者の視点を持ち続けていたという事実です。「いのちの初夜」を読むと、肉体的にも精神的にも、彼が健康体であり続けたことは明確です。病友の光岡良二は「彼はハンセン病の賭場口にも立っていなかった」と語っています。実際に北條の病状は非常に軽症で、重症患者を「化けもの」と表現することがありました。反して日記や書簡のなかには、病を受け入れようとする葛藤が表出しています。もちろん、彼自身、のちに日記が公表されるとは思っていなかったでしょう。作品の中では、生身の感情は押し殺していたのでしょうね」
北條民雄が常に健常者の視点を持ち続けていたという指摘は的を射ており、特にこの「いのちの初夜」での主人公・尾田にはそれが感じられます(因みに、北條民雄は1934年に多磨全生園に入院し1937年に亡くなったが、死因は腸結核だった)。佐柄木の方がむしろ重度であり、それでいて達観している様は、最初はややデーモニッシュにさえ思われましたが、実は彼は彼なりに苦闘し、今は哲学的境地に達していることが窺えました。
その佐柄木は、彼らを取り巻く重度の患者らを「人間ではありませんよ。生命です。生命そのもの、いのちそのものなんです」と尾田に言います。「あの人たちの『人間』はもう死んで亡びてしまったんです。ただ、生命だけがびくびくと生きているのです。なんという根強さでしょう」と。そうした佐柄木の人物像や哲学の方が主人公の尾田より強烈に印象に残りました(モデルは文庫所収の「北条民雄の人と生活」を書いている前出の光岡良二(1911-1995)か。彼は東京帝国大学文学部哲学科2年修了時にハンセン病を発病、1933年に多磨全生園に入院、翌年入院してきた北条民雄と知り合った)。
「眼帯記」(1936)は失明への怖れを描いた作品で、ハンセン病の末期は目が見えなくなるのだと改めて知った次第。「癩院受胎」(1936)は病気と生きることへの考えが対照的なふたりの青年と妹、そして彼女に恋心を抱く主人公のさまざまな心情を描いた作品です。
「癩院記録」(1936)及び「続癩院記録」(1936)は、感情を排して院内の患者の生活をスケッチ風に描いた作品で、長閑さを感じる場面もあれば、凄惨な描写もありました。
「癩家族」(1936)は入院している父親、長男、長女の間の愛憎を細かに描いており、「望郷歌」(1937)は、心を閉ざした少年患者を描いた生前最後の作品、「吹雪の産声」(1937)は作者の死後に発表されたもので、死を迎える親友と、療養所内での出産で「生命の連続」を描いた作品です。
何れも珠玉の作品ですが、これらの中ではいちばん最初に書かれた「いのちの初夜」がやはりいちばんの傑作のように思います。
【1955年文庫化[創元文庫]/1955年文庫化・2020年改版[角川文庫]】
《読書MEMO》
島薗 進 『死に向き合って生きる (NHKテキスト こころをよむ 2025年4月~6月)』(2025/03 NHK出版)

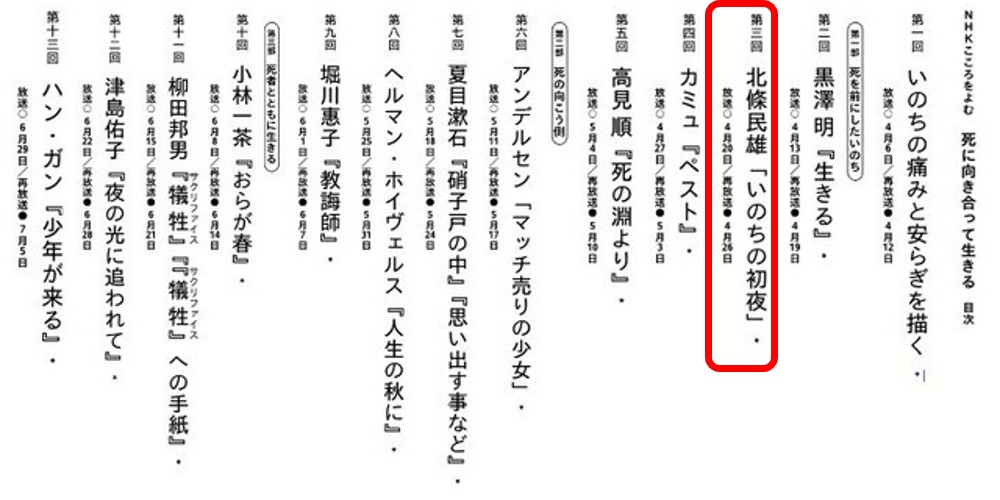



 矢切の渡しの舟客・斎藤政夫翁(笠智衆)は老船頭(松本克平)に、遠い過去の想い出を語る...。この渡し場に程近い村の旧家の次男として育った政夫(田中晋二)が15歳の秋のこと、母(杉村春子)が病弱のため、近くの町家の娘で母の姪に当る民子(有田紀子)が政夫の家を手伝いに来ている。政夫は二つ年上の民子とは幼い頃から仲が良い。それが嫂のさだ(山本和子)や作女お増(小林トシ子)の口の端にのって、本人同志もいつか稚いながら恋といったものを意識するようになる。祭を明日に控えた日、母の吩咐で山の畑に綿を採りに出かけ二人は、このとき初めて相手の心に恋を感じ合ったが、同時にそれ以来、仲を裂かれなければならなかった。母の言葉で追われるように中学校の寮に入れられた政
矢切の渡しの舟客・斎藤政夫翁(笠智衆)は老船頭(松本克平)に、遠い過去の想い出を語る...。この渡し場に程近い村の旧家の次男として育った政夫(田中晋二)が15歳の秋のこと、母(杉村春子)が病弱のため、近くの町家の娘で母の姪に当る民子(有田紀子)が政夫の家を手伝いに来ている。政夫は二つ年上の民子とは幼い頃から仲が良い。それが嫂のさだ(山本和子)や作女お増(小林トシ子)の口の端にのって、本人同志もいつか稚いながら恋といったものを意識するようになる。祭を明日に控えた日、母の吩咐で山の畑に綿を採りに出かけ二人は、このとき初めて相手の心に恋を感じ合ったが、同時にそれ以来、仲を裂かれなければならなかった。母の言葉で追われるように中学校の寮に入れられた政 夫が、冬の休みに帰省すると、渡し場に迎えてくれるはずの民子の姿はなかった。お増の口から、民子がさだの中傷で実家へ追い帰されたと聞かされ、政夫は早々に学校へ戻る。二人の仲を心配した母や民子の両親の勧めで、民子は政夫への心を抑えて他家へ嫁ぐ。ただ祖母(浦辺粂子)だけが民子を不愍に思った。やがて授業中に電報で呼び戻された政夫は、民子の死を知る。民子の最期を看取った母によると、民子は政夫の手紙を抱きしめながら息を引きとったという。政夫の名は一言もいわずに...。渡し船を降りた翁は民子が好きだった野菊の花を摘んで、墓前に供えるのであった―。
夫が、冬の休みに帰省すると、渡し場に迎えてくれるはずの民子の姿はなかった。お増の口から、民子がさだの中傷で実家へ追い帰されたと聞かされ、政夫は早々に学校へ戻る。二人の仲を心配した母や民子の両親の勧めで、民子は政夫への心を抑えて他家へ嫁ぐ。ただ祖母(浦辺粂子)だけが民子を不愍に思った。やがて授業中に電報で呼び戻された政夫は、民子の死を知る。民子の最期を看取った母によると、民子は政夫の手紙を抱きしめながら息を引きとったという。政夫の名は一言もいわずに...。渡し船を降りた翁は民子が好きだった野菊の花を摘んで、墓前に供えるのであった―。 木下惠介(1912-1998/享年86)監督の1955(昭和30)年公開作で、同年「キネマ旬報 ベスト・テン」で第3位。原作「野菊の墓」は、歌人であった伊藤左千夫が43歳で初めて発表した小説で、1906(明治39)年1月、雑誌「ホトトギス」に掲載、その年の4月に俳書堂から単行本として刊行されています。15歳の少年・斎藤政夫と2歳年上の従姉・民子との淡い恋を描き、夏目漱石が絶賛したというこの作品は、過去に3度映画化されており、その第1作は木下惠介が監督した本作です(2作目('66年)の主演は太田博之と安田道代(大楠道代)、3作目('81年)は澤井信一郎監督、の
木下惠介(1912-1998/享年86)監督の1955(昭和30)年公開作で、同年「キネマ旬報 ベスト・テン」で第3位。原作「野菊の墓」は、歌人であった伊藤左千夫が43歳で初めて発表した小説で、1906(明治39)年1月、雑誌「ホトトギス」に掲載、その年の4月に俳書堂から単行本として刊行されています。15歳の少年・斎藤政夫と2歳年上の従姉・民子との淡い恋を描き、夏目漱石が絶賛したというこの作品は、過去に3度映画化されており、その第1作は木下惠介が監督した本作です(2作目('66年)の主演は太田博之と安田道代(大楠道代)、3作目('81年)は澤井信一郎監督、の 物語の設定では民子の方が2歳年上ですが、主演の田中晋二と有田紀子は共に1940年生まれの当時15歳。有田紀子は女優に憧れ学習院女子中等科に在学中に木下惠介監督に手紙を書いたことが契機となり、民子役に抜擢されましたが、学習院は生徒の映画出演を認めておらず、転校して映画に出演しています。この映画は、旧弊な気風が根強い田舎を舞台にしている分、有田紀子の清楚で現代的なリリシズムが光っていたように思います。ただし、彼女が出演した木下作品は田中晋二と共演した3作品だけです。その後は学業に専念し、1958年早稲田の文学部演劇科に進みますが、それを知った多くがの若者が早稲田を受験したという逸話があります。伊藤左千夫は「野菊の墓」という作品があってこその作家という印象がありますが、有田紀子も、結婚で女優業を引退したということもあって、代表作はこの「野菊の如き君なりき」ということになるのでしょう。
物語の設定では民子の方が2歳年上ですが、主演の田中晋二と有田紀子は共に1940年生まれの当時15歳。有田紀子は女優に憧れ学習院女子中等科に在学中に木下惠介監督に手紙を書いたことが契機となり、民子役に抜擢されましたが、学習院は生徒の映画出演を認めておらず、転校して映画に出演しています。この映画は、旧弊な気風が根強い田舎を舞台にしている分、有田紀子の清楚で現代的なリリシズムが光っていたように思います。ただし、彼女が出演した木下作品は田中晋二と共演した3作品だけです。その後は学業に専念し、1958年早稲田の文学部演劇科に進みますが、それを知った多くがの若者が早稲田を受験したという逸話があります。伊藤左千夫は「野菊の墓」という作品があってこその作家という印象がありますが、有田紀子も、結婚で女優業を引退したということもあって、代表作はこの「野菊の如き君なりき」ということになるのでしょう。 ところで、映画は矢切の渡しの舟客・斎藤政夫老人(笠智衆)が60年前の自らが数え年で15(「月で数えると13歳と何月」と原作にある)の時のことを回想する(船頭に語る)形式で進み、政夫老人は現在73歳ということになりますが(演じる笠智衆は当時51歳)、原作では、「十余年も過去った昔のこと」とあり、語り手の年齢はもしかしたら30歳前後くらいかもしれず、この年齢の差は、「政夫の今」を映画が作られた1955年を現在に設定したためではないかと思われます(小説が発表された年とも約40年の開きがある)。世間一般にも原作の語り手がかなり年齢が高いように思われている気がしますが(コミック版などもそうなっている)、思えば、伊藤左千夫がこの小説を書いたときでさえまだ43歳だったわけで、作者はそこからさらに10歳以上若い"語り手"を設定しているように思います(物語は伊藤左千夫自身の幼い頃の淡い恋が基になっているというから、概算すると原作の時代設定の方が映画より少し古いということになるのかも)。
ところで、映画は矢切の渡しの舟客・斎藤政夫老人(笠智衆)が60年前の自らが数え年で15(「月で数えると13歳と何月」と原作にある)の時のことを回想する(船頭に語る)形式で進み、政夫老人は現在73歳ということになりますが(演じる笠智衆は当時51歳)、原作では、「十余年も過去った昔のこと」とあり、語り手の年齢はもしかしたら30歳前後くらいかもしれず、この年齢の差は、「政夫の今」を映画が作られた1955年を現在に設定したためではないかと思われます(小説が発表された年とも約40年の開きがある)。世間一般にも原作の語り手がかなり年齢が高いように思われている気がしますが(コミック版などもそうなっている)、思えば、伊藤左千夫がこの小説を書いたときでさえまだ43歳だったわけで、作者はそこからさらに10歳以上若い"語り手"を設定しているように思います(物語は伊藤左千夫自身の幼い頃の淡い恋が基になっているというから、概算すると原作の時代設定の方が映画より少し古いということになるのかも)。
 因みにこの作品、作品の大部分を占める過去の回想部分は全体を楕円にしてまわりをボカした手法にをとっていますが、先に読んだ『
因みにこの作品、作品の大部分を占める過去の回想部分は全体を楕円にしてまわりをボカした手法にをとっていますが、先に読んだ『 有田紀子、田中晋二の演技は「
有田紀子、田中晋二の演技は「



 昭和初期、第一次大戦後の日本。幼い頃から行商人の母親と全国を周り歩いて育ったふみ子(高峰秀子)は、東京で下宿暮らしを始める。職を転々としながら、貧しい生活の中で詩作に励むようになった彼女は、やがて同人雑誌にも参加する。創作活動を通して何人かの男と出会い、また別れるふみ子。やがて、その波乱の中で編んだ「放浪記」が世間で評価され、彼女は文壇へと踏み出していく―。
昭和初期、第一次大戦後の日本。幼い頃から行商人の母親と全国を周り歩いて育ったふみ子(高峰秀子)は、東京で下宿暮らしを始める。職を転々としながら、貧しい生活の中で詩作に励むようになった彼女は、やがて同人雑誌にも参加する。創作活動を通して何人かの男と出会い、また別れるふみ子。やがて、その波乱の中で編んだ「放浪記」が世間で評価され、彼女は文壇へと踏み出していく―。
 から幾つかのエピソードを拾って忠実に映像化する一方で、林芙美子の『放浪記』にはない文壇作家・詩人たちとの交流からライバ
から幾つかのエピソードを拾って忠実に映像化する一方で、林芙美子の『放浪記』にはない文壇作家・詩人たちとの交流からライバ ルの女流作家との競い合い、さらにエピローグとして作家として名を成した後、自身の半生を振り返るような描写があります(菊田一夫脚本・森光子主演の舞台のにあるようなでんぐり返しもはない)。
ルの女流作家との競い合い、さらにエピローグとして作家として名を成した後、自身の半生を振り返るような描写があります(菊田一夫脚本・森光子主演の舞台のにあるようなでんぐり返しもはない)。
 しかし、林芙美子って面食いだったのだなあ。貧しい彼女に金を援助してくれ、優しく献身してくれる隣室の印刷工・安岡(加東大介)には素気無い態度で接する一方、若い学生(岸田森)に目が行ったり、詩人で劇作家の伊達(仲谷昇)を好きになったりして、ただし伊達の方は二股かけた末に女優で詩人の日夏京子(草笛光子)の方を選んだために振られてしまうと、今度は同じくイケメンの福池(宝田明)に乗りかえるもこれがひどいダメンズ。甘い二枚目役で売り出した宝田明(1934-2022(87歳没))が演技開眼、ここではDV夫を好演しています。これらの男性にはモデルがいるようですが
しかし、林芙美子って面食いだったのだなあ。貧しい彼女に金を援助してくれ、優しく献身してくれる隣室の印刷工・安岡(加東大介)には素気無い態度で接する一方、若い学生(岸田森)に目が行ったり、詩人で劇作家の伊達(仲谷昇)を好きになったりして、ただし伊達の方は二股かけた末に女優で詩人の日夏京子(草笛光子)の方を選んだために振られてしまうと、今度は同じくイケメンの福池(宝田明)に乗りかえるもこれがひどいダメンズ。甘い二枚目役で売り出した宝田明(1934-2022(87歳没))が演技開眼、ここではDV夫を好演しています。これらの男性にはモデルがいるようですが

 はっきり分かりません(宝田明が演じた福池は詩人の野村吉哉がモデルか)。実際に林芙美子は当時次から次へと同棲相手を変え、20歳過ぎで画家の手塚緑敏(映画では藤山(小林桂樹))と知り合ってやっと少し落ち着いたようです。
はっきり分かりません(宝田明が演じた福池は詩人の野村吉哉がモデルか)。実際に林芙美子は当時次から次へと同棲相手を変え、20歳過ぎで画家の手塚緑敏(映画では藤山(小林桂樹))と知り合ってやっと少し落ち着いたようです。 草笛光子が演じた芙美子のライバル・日夏京子も原作にない役どころです(菊田一夫原案か)。白坂(伊藤雄之助)が新たに発刊する雑誌「女性芸術」に、村野やす子(文野朋子)の提案で、芙美子と日夏京子とで掲載する詩を競い合うことになって、芙美子が京子の詩の原稿を預かったものの、自分の原稿だけ届け、京子の原稿は締め切りに間に合わなくなるまで手元に置いていたというのは実話なのでしょうか(これが芙美子の作家デビューであるとするならば、芙美子のこの時の原稿が「放浪記」だったということになる。「放浪記」は長谷川時雨編集の「女人芸術」誌に1928(昭和3)年10月から連載された)。
草笛光子が演じた芙美子のライバル・日夏京子も原作にない役どころです(菊田一夫原案か)。白坂(伊藤雄之助)が新たに発刊する雑誌「女性芸術」に、村野やす子(文野朋子)の提案で、芙美子と日夏京子とで掲載する詩を競い合うことになって、芙美子が京子の詩の原稿を預かったものの、自分の原稿だけ届け、京子の原稿は締め切りに間に合わなくなるまで手元に置いていたというのは実話なのでしょうか(これが芙美子の作家デビューであるとするならば、芙美子のこの時の原稿が「放浪記」だったということになる。「放浪記」は長谷川時雨編集の「女人芸術」誌に1928(昭和3)年10月から連載された)。
 映画の中で、草笛光子(1933年生まれ)は本気で高峰秀子をぶったそうです。高峰秀子をぶった女優が現役でまだいて、来年['22年]のNHKの大河ドラマ「鎌倉殿の13人」に出演するは、「週刊文春」に連載を持っているは、というのもすごいものです。イケメン・ダメンズ役の宝田明もDV夫なので高峰秀子をぶちますが、草笛光子のビンタの方が強烈でした。林芙美子は面食いでなければもっと早くに幸せになれたのかもしれず、その点は樋口一葉などと似ているのではないか思ったりしました。
映画の中で、草笛光子(1933年生まれ)は本気で高峰秀子をぶったそうです。高峰秀子をぶった女優が現役でまだいて、来年['22年]のNHKの大河ドラマ「鎌倉殿の13人」に出演するは、「週刊文春」に連載を持っているは、というのもすごいものです。イケメン・ダメンズ役の宝田明もDV夫なので高峰秀子をぶちますが、草笛光子のビンタの方が強烈でした。林芙美子は面食いでなければもっと早くに幸せになれたのかもしれず、その点は樋口一葉などと似ているのではないか思ったりしました。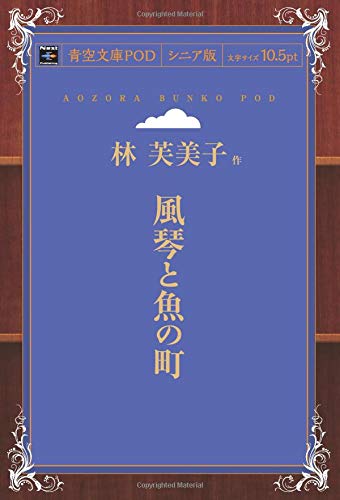

 個人的には、原作は『放浪記』(★★★★★)と『浮雲』(★★★★☆)で甲乙つけ難く、しいて言えば原石の輝きを感じるとともにポジティブな感じがある『放浪記』が上になりますが(物語性を評価して完成度が高い『浮雲』の方をより高く評価する人もいておかしくない)、映画は、同じ成瀬巳喜男監督の「浮雲」(★★★★☆)の方が原作を比較的忠実に再現していて好みで、それに比べると「放浪記」(★★★★)は、菊田一夫的要素はそれなりに面白いですが、やや下でしょうか(それでも星4つだが)。高峰秀子は当時38歳。実際の年齢よりは若く見えます
個人的には、原作は『放浪記』(★★★★★)と『浮雲』(★★★★☆)で甲乙つけ難く、しいて言えば原石の輝きを感じるとともにポジティブな感じがある『放浪記』が上になりますが(物語性を評価して完成度が高い『浮雲』の方をより高く評価する人もいておかしくない)、映画は、同じ成瀬巳喜男監督の「浮雲」(★★★★☆)の方が原作を比較的忠実に再現していて好みで、それに比べると「放浪記」(★★★★)は、菊田一夫的要素はそれなりに面白いですが、やや下でしょうか(それでも星4つだが)。高峰秀子は当時38歳。実際の年齢よりは若く見えます が、本当はもう少し若い時分に林芙美子を演じて欲しかった気もします(「浮雲」の時は30歳だった)。ただ、それでもここまで演じ切れていれば立派なものだと思います。
が、本当はもう少し若い時分に林芙美子を演じて欲しかった気もします(「浮雲」の時は30歳だった)。ただ、それでもここまで演じ切れていれば立派なものだと思います。 
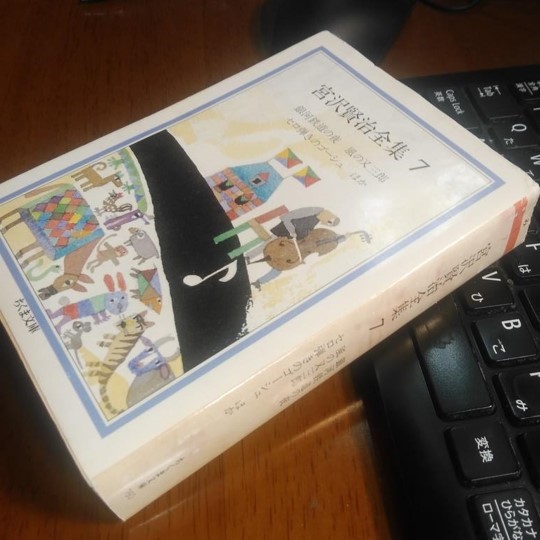
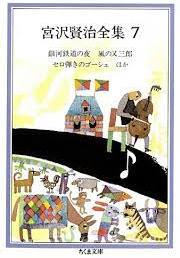



 映像化作品では、高畑勲(1935-2018/82歳没)監督が自主製作し、オープロダクションが5年の歳月をかけて完成させた「セロ弾きのゴーシュ」('82年/63分)があります。また、それ以前には、田中喜次監督の影絵アニメーション「セロひきのゴーシュ」('49年/19分)、森永健次郎、川尻泰司の共同監督の人形劇をカメラで撮影して制作され「日本で最初の長編・総天然色・人形劇・音楽映画」と宣伝された「セロ弾きのゴーシュ」('53年/45分)、神保まつえ監督の学研の人形アニメーション作品「セロひきのゴーシュ」('63年/19分)があり(学研が、昭和30年代に学校や地域で、アートアニメーションとして映像教育を行っていたころの代表作になる)、高畑勲作品以降では学研アニメの「セロひきのゴーシュ」('98年/20分)がありますが、「風の
映像化作品では、高畑勲(1935-2018/82歳没)監督が自主製作し、オープロダクションが5年の歳月をかけて完成させた「セロ弾きのゴーシュ」('82年/63分)があります。また、それ以前には、田中喜次監督の影絵アニメーション「セロひきのゴーシュ」('49年/19分)、森永健次郎、川尻泰司の共同監督の人形劇をカメラで撮影して制作され「日本で最初の長編・総天然色・人形劇・音楽映画」と宣伝された「セロ弾きのゴーシュ」('53年/45分)、神保まつえ監督の学研の人形アニメーション作品「セロひきのゴーシュ」('63年/19分)があり(学研が、昭和30年代に学校や地域で、アートアニメーションとして映像教育を行っていたころの代表作になる)、高畑勲作品以降では学研アニメの「セロひきのゴーシュ」('98年/20分)がありますが、「風の
 又三郎」がこれまでの5度の映像化のうち3度が実写映画化、2度がアニメ映画化なのに対し、こちらは動物が出てくることもあってか、5度の映像化のすべてが通常アニメまたは人形劇アニメとなっています。
又三郎」がこれまでの5度の映像化のうち3度が実写映画化、2度がアニメ映画化なのに対し、こちらは動物が出てくることもあってか、5度の映像化のすべてが通常アニメまたは人形劇アニメとなっています。 高畑勲監督の「セロ弾きのゴーシュ」は、高畑監督・脚本作品として時期的には「赤毛のアン」('79年)や「じゃりン子チエ」('81年)の次にくるものですが、それら以前の'75年から制作にとりかかっており、背景の描写などは飛躍的に精緻なものとなっています。主人公のゴーシュは、宮沢賢治の原作では、ウダツのあがらない中年男性ともとれますが、映画では18歳ぐらいの若者として描かれています。ただし、このことは、それまでのアニメ作品もそうであるし、賢治作品を描いて最高の画家と言われた茂田井武の『
高畑勲監督の「セロ弾きのゴーシュ」は、高畑監督・脚本作品として時期的には「赤毛のアン」('79年)や「じゃりン子チエ」('81年)の次にくるものですが、それら以前の'75年から制作にとりかかっており、背景の描写などは飛躍的に精緻なものとなっています。主人公のゴーシュは、宮沢賢治の原作では、ウダツのあがらない中年男性ともとれますが、映画では18歳ぐらいの若者として描かれています。ただし、このことは、それまでのアニメ作品もそうであるし、賢治作品を描いて最高の画家と言われた茂田井武の『 水車小屋に住んでいるゴーシュのところに夜ごと現れる様々な動物たち―それらのキャラクターに細やかな演技をさせてデティールに凝っているのが高畑勲のアニメ演出の特徴だったと思いますが、ところで、ゴーシュの家を夜ごと日替わりで訪れた動物たちにはどのような意味が込められていたのか、彼らはゴーシュに何をもたらしたのかということについては、いろいろ議論になっているのではないでしょうか。
水車小屋に住んでいるゴーシュのところに夜ごと現れる様々な動物たち―それらのキャラクターに細やかな演技をさせてデティールに凝っているのが高畑勲のアニメ演出の特徴だったと思いますが、ところで、ゴーシュの家を夜ごと日替わりで訪れた動物たちにはどのような意味が込められていたのか、彼らはゴーシュに何をもたらしたのかということについては、いろいろ議論になっているのではないでしょうか。 最初の晩に訪れた猫から、ゴーシュにトロメライ(トロイメライ)を演奏してくれと頼まれますが、不機嫌な彼はサディズティックな気持ちから「印度の虎狩」という曲を弾きます。これを聴いて猫はのたうち回りますが、ゴーシュが「印度の虎狩」という曲を選んで猫に意地悪したというより、ゴーシュの技量が劣っていて、聞くに堪えないものであることを象徴しているようにとれます。
最初の晩に訪れた猫から、ゴーシュにトロメライ(トロイメライ)を演奏してくれと頼まれますが、不機嫌な彼はサディズティックな気持ちから「印度の虎狩」という曲を弾きます。これを聴いて猫はのたうち回りますが、ゴーシュが「印度の虎狩」という曲を選んで猫に意地悪したというより、ゴーシュの技量が劣っていて、聞くに堪えないものであることを象徴しているようにとれます。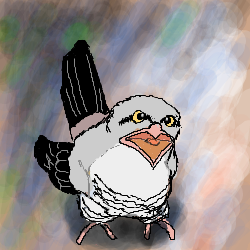 次の晩に家に来たのはかっこうで、最初はこの音楽を教えてほしいと頼み込むかっこうとも生意気だと言い争いをしますが、今度はゴーシュは猫の時ほど敵対的な態度ではなく、かっこうと音程の練習をすることで、自身の音感を鍛え上げていきます。また、かっこうとの交流から、ゴーシュは少しづつ相手の言うことを聞き入れるようになっていきます。それでも、最後ゴーシュは癇癪を起してしまい、かっこうは頭を硝子にぶつけたりしながら、逃げるように去っていきます。
次の晩に家に来たのはかっこうで、最初はこの音楽を教えてほしいと頼み込むかっこうとも生意気だと言い争いをしますが、今度はゴーシュは猫の時ほど敵対的な態度ではなく、かっこうと音程の練習をすることで、自身の音感を鍛え上げていきます。また、かっこうとの交流から、ゴーシュは少しづつ相手の言うことを聞き入れるようになっていきます。それでも、最後ゴーシュは癇癪を起してしまい、かっこうは頭を硝子にぶつけたりしながら、逃げるように去っていきます。 三日目の晩に来たのは狸で、狸は「愉快な馬車屋」という曲を一緒に演奏しようとゴーシュに言い、彼はその申し出を受け入れます。これだけでも、猫のときと比べると大きな変化ですが、小太鼓を演奏する狸とともに、二人はセッションをします。ここではゴーシュはリズム感を鍛えます。
三日目の晩に来たのは狸で、狸は「愉快な馬車屋」という曲を一緒に演奏しようとゴーシュに言い、彼はその申し出を受け入れます。これだけでも、猫のときと比べると大きな変化ですが、小太鼓を演奏する狸とともに、二人はセッションをします。ここではゴーシュはリズム感を鍛えます。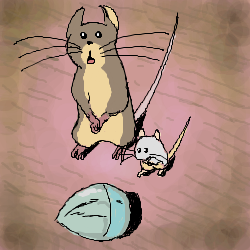 そして、最後の晩に来たのがは野鼠の親子です、ゴーシュは野鼠のお母さんから、子鼠の病気を治して欲しいと頼まれてその訳を聞きくと、ゴーシュのチェロを聞くと病気が治るからだといいいます。ゴーシュは納得すると、子鼠のためにチェロを弾きます。ここでは明らかに、ゴーシュが、自分のためではなく他人のために演奏するようになることを表しています。
そして、最後の晩に来たのがは野鼠の親子です、ゴーシュは野鼠のお母さんから、子鼠の病気を治して欲しいと頼まれてその訳を聞きくと、ゴーシュのチェロを聞くと病気が治るからだといいいます。ゴーシュは納得すると、子鼠のためにチェロを弾きます。ここでは明らかに、ゴーシュが、自分のためではなく他人のために演奏するようになることを表しています。
 先にも述べたように、高畑勲監督の「セロ弾きのゴーシュ」('82年)は、高畑勲監督が自主製作し、オープロダクションが5年の歳月をかけて完成させたもので、スタジオジブリが高畑勲、宮崎駿両監督のアニメーション映画制作を目的として、当時は株式会社徳間書店の子会社として活動を開始したのが1985年6月であり、「セロ弾きのゴーシュ」はその前の作品であってスタジオジブリ作品ではありませんが、ジブリ発足後も高畑勲監督は宮崎駿監督ほどコンスタントではないですが、「平成狸合戦ぽんぽこ」('94年)や「かぐや姫の物語」('13年)といった佳作を制作しています。
先にも述べたように、高畑勲監督の「セロ弾きのゴーシュ」('82年)は、高畑勲監督が自主製作し、オープロダクションが5年の歳月をかけて完成させたもので、スタジオジブリが高畑勲、宮崎駿両監督のアニメーション映画制作を目的として、当時は株式会社徳間書店の子会社として活動を開始したのが1985年6月であり、「セロ弾きのゴーシュ」はその前の作品であってスタジオジブリ作品ではありませんが、ジブリ発足後も高畑勲監督は宮崎駿監督ほどコンスタントではないですが、「平成狸合戦ぽんぽこ」('94年)や「かぐや姫の物語」('13年)といった佳作を制作しています。 「平成狸合戦ぽんぽこ」は、第49回「毎日映画コンクール」のアニメーション映画賞をするなどしただけでなく、1994年の邦画・配給収入トップ26億円を記録するなど興行的にも成功しました(興行収入44.7億円、観客動員325万人)。環境問題・自然破壊がテーマの1つになっていて、映画の終盤、多摩ニュータウン開発で狸たちは住むところを奪われ、人間に化けることができる狸は人間社会で生きることを選びますが、人間に化けることの出来ない狸は、まだ緑が残る町田に移り住むことにします。その町田市の実際の山々には、映画公開から20年以上たった2020年4月現在も、タヌキのみならず、アライグマやハクビシンなどが生息しているとのことです。
「平成狸合戦ぽんぽこ」は、第49回「毎日映画コンクール」のアニメーション映画賞をするなどしただけでなく、1994年の邦画・配給収入トップ26億円を記録するなど興行的にも成功しました(興行収入44.7億円、観客動員325万人)。環境問題・自然破壊がテーマの1つになっていて、映画の終盤、多摩ニュータウン開発で狸たちは住むところを奪われ、人間に化けることができる狸は人間社会で生きることを選びますが、人間に化けることの出来ない狸は、まだ緑が残る町田に移り住むことにします。その町田市の実際の山々には、映画公開から20年以上たった2020年4月現在も、タヌキのみならず、アライグマやハクビシンなどが生息しているとのことです。
 「セロ弾きのゴーシュ」●制作年:1982年●監督・脚本:高畑勲●企画:小松原一男●製作:村田耕一●原画:才田俊次●美術:椋尾篁●音楽:間宮芳生(「星めぐりの歌」(作詞・作曲:宮沢賢治 歌:児童合唱団トマト))●制作会社:オープロダクション●原作:宮澤賢治●時間:63分●声の出演:佐々木秀樹/雨森雅司/白石冬美/肝付兼太/高橋和枝/横沢啓子/高村章子/横沢啓子/千葉順二/槐柳二/矢田耕司/三橋洋一/峰あつ子/横尾三郎●公開:1982/01●配給:オープロダクション(後ににっかつ)(評価:★★★★)
「セロ弾きのゴーシュ」●制作年:1982年●監督・脚本:高畑勲●企画:小松原一男●製作:村田耕一●原画:才田俊次●美術:椋尾篁●音楽:間宮芳生(「星めぐりの歌」(作詞・作曲:宮沢賢治 歌:児童合唱団トマト))●制作会社:オープロダクション●原作:宮澤賢治●時間:63分●声の出演:佐々木秀樹/雨森雅司/白石冬美/肝付兼太/高橋和枝/横沢啓子/高村章子/横沢啓子/千葉順二/槐柳二/矢田耕司/三橋洋一/峰あつ子/横尾三郎●公開:1982/01●配給:オープロダクション(後ににっかつ)(評価:★★★★)  「平成狸合戦ぽんぽこ」●制作年:1994年●監督・脚本・原作:高畑勲●製作:鈴木敏夫●音楽:紅龍/上々颱風ほか●制作会社:スタジオジブリ●時間:119分●声の出演:野々村真/石田ゆり子/5代目柳家小さん/三木のり平/林家こぶ平(9代目林家正蔵)/村田雄浩/神谷明/林原めぐみ/3代目桂米朝/5代目桂文枝/芦屋雁之助/山下容莉枝/黒田由美/清川虹子/泉谷しげる/(ナレーター)3代目古今亭志ん朝●公開:1994/07●配給:東宝(評価:★★★★)
「平成狸合戦ぽんぽこ」●制作年:1994年●監督・脚本・原作:高畑勲●製作:鈴木敏夫●音楽:紅龍/上々颱風ほか●制作会社:スタジオジブリ●時間:119分●声の出演:野々村真/石田ゆり子/5代目柳家小さん/三木のり平/林家こぶ平(9代目林家正蔵)/村田雄浩/神谷明/林原めぐみ/3代目桂米朝/5代目桂文枝/芦屋雁之助/山下容莉枝/黒田由美/清川虹子/泉谷しげる/(ナレーター)3代目古今亭志ん朝●公開:1994/07●配給:東宝(評価:★★★★) 『
『

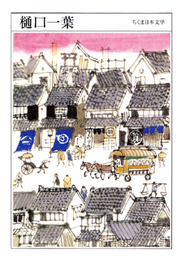


 この「にごりえ」は、今井正監督によりオムニバス映画「にごりえ」('53年/松竹)の第3話として淡島千景主演で映像化されていて、結城朝之助を山村聡、源七を宮口精二、源七の妻・お初を杉村春子が演じています(二人の息子を当時6歳の松山省二が演じている)。「文学座総出演」の映画とのことで、この第3話にはそのほかにヤクザや酔客などの役で、加藤武や小池朝雄、神山繁などがノンクレジットでちょっとだけですが出ています。
この「にごりえ」は、今井正監督によりオムニバス映画「にごりえ」('53年/松竹)の第3話として淡島千景主演で映像化されていて、結城朝之助を山村聡、源七を宮口精二、源七の妻・お初を杉村春子が演じています(二人の息子を当時6歳の松山省二が演じている)。「文学座総出演」の映画とのことで、この第3話にはそのほかにヤクザや酔客などの役で、加藤武や小池朝雄、神山繁などがノンクレジットでちょっとだけですが出ています。 この物語におけるお力は上客の結城朝之助の態度は微妙です。お力は菊の井のいわばナンバーワン芸妓でありながら、今の生活を虚しく感じており、自暴自棄になっているところがあります。そんなお力の前に客として朝之助という独身男性が現れ、彼に対して彼女は自分の生い立ちなどを語るまでになり(その中身は子ども時代の凄まじいまでの貧乏物語で、これは映画でも映像化されていた)、一時は朝之助に気持ちが傾いたかに思えました。でも、朝之助の方は、突き放しはしないものの、「俺の嫁になれ」などといったことを言うわけでもありません。
この物語におけるお力は上客の結城朝之助の態度は微妙です。お力は菊の井のいわばナンバーワン芸妓でありながら、今の生活を虚しく感じており、自暴自棄になっているところがあります。そんなお力の前に客として朝之助という独身男性が現れ、彼に対して彼女は自分の生い立ちなどを語るまでになり(その中身は子ども時代の凄まじいまでの貧乏物語で、これは映画でも映像化されていた)、一時は朝之助に気持ちが傾いたかに思えました。でも、朝之助の方は、突き放しはしないものの、「俺の嫁になれ」などといったことを言うわけでもありません。 お力も、結局は朝之助とは一緒にはなれないと思ったのでしょうか。あるいは、彼女自身が男性に完全に所有されることを拒否しているようにもとれます。そして、さらに深い虚無感に陥ったようにも思われ、源七の方へ奔ったともとれます(源七を狂わせた罰を自ら引き受けて死んでいったとの解釈もあるようだ)。一方、源七の側にすれば、「いっそ死のう」との想いは自然なことであり、ネガティブな意味での「渡りに船」だったかもしれません。彼は一緒に死んでくれる相手としてお力のことを考えていたのではないかと思われます(山中貞雄監督の「
お力も、結局は朝之助とは一緒にはなれないと思ったのでしょうか。あるいは、彼女自身が男性に完全に所有されることを拒否しているようにもとれます。そして、さらに深い虚無感に陥ったようにも思われ、源七の方へ奔ったともとれます(源七を狂わせた罰を自ら引き受けて死んでいったとの解釈もあるようだ)。一方、源七の側にすれば、「いっそ死のう」との想いは自然なことであり、ネガティブな意味での「渡りに船」だったかもしれません。彼は一緒に死んでくれる相手としてお力のことを考えていたのではないかと思われます(山中貞雄監督の「 ただし、変な言い方ですが、こういう絶望的な物語(「悲惨小説」)になっているところが逆に面白いのかもしれず、一葉という人は読者心理がよく分かっていたのではないかと思います。また、お力自身の絶望感には、何か運命論的な思い込みがあるようにも思います。そうしたお力の絶望感が読む側に伝わってくる根底には、描写のリアリズムがあるのでしょう。それも読者を惹きつける要因になっていると思います。
ただし、変な言い方ですが、こういう絶望的な物語(「悲惨小説」)になっているところが逆に面白いのかもしれず、一葉という人は読者心理がよく分かっていたのではないかと思います。また、お力自身の絶望感には、何か運命論的な思い込みがあるようにも思います。そうしたお力の絶望感が読む側に伝わってくる根底には、描写のリアリズムがあるのでしょう。それも読者を惹きつける要因になっていると思います。 ごもり》久我美子/中村伸郎/竜岡晋/長岡輝子/荒木道子/仲谷昇(山村石之助(ノンクレジット))/岸田今日子(山村家次女(ノンクレジット))/北村和夫(車夫(ノンクレジット))/河原崎次郎(従弟・三之助(ノンクレジット))《にごりえ》淡島千景/杉村春子/賀原夏子/南美江/北城真記子/文野朋子/山村聰/宮口精二/十朱久雄/加藤武(ヤクザ(ノンクレジット))/加藤治子/松山省二/小池朝雄(女郎に絡む男(ノンクレジット))/神山繁 (ガラの悪い酔客(ノンクレジット))●公開:1953/11●配給:松竹(評価:★★★★)
ごもり》久我美子/中村伸郎/竜岡晋/長岡輝子/荒木道子/仲谷昇(山村石之助(ノンクレジット))/岸田今日子(山村家次女(ノンクレジット))/北村和夫(車夫(ノンクレジット))/河原崎次郎(従弟・三之助(ノンクレジット))《にごりえ》淡島千景/杉村春子/賀原夏子/南美江/北城真記子/文野朋子/山村聰/宮口精二/十朱久雄/加藤武(ヤクザ(ノンクレジット))/加藤治子/松山省二/小池朝雄(女郎に絡む男(ノンクレジット))/神山繁 (ガラの悪い酔客(ノンクレジット))●公開:1953/11●配給:松竹(評価:★★★★)
 南北朝時代、戦火を免れた山寺に、無明の太郎と異名をとる盗賊(勝新太郎)が、白拍子あがりの情人・愛染(新珠三千代)と爛れた生活を送っていた。自堕落な愛染、太郎が従者のように献身しているのは、彼女が素晴らしい肉体を、持っていたからだった。晩秋のある夕暮、京から太郎の妻・楓(高峰秀子)が尋ねて来た。太郎は、自分を探し求めて訪れた楓を邪慳に扱ったが、彼女はいつしか庫裡に住みつき、ただひたすら獣が獲物を待つ忍従さで太郎に仕えた。それから半年ほども過ぎたある晩、道に迷った高野の上人(佐
南北朝時代、戦火を免れた山寺に、無明の太郎と異名をとる盗賊(勝新太郎)が、白拍子あがりの情人・愛染(新珠三千代)と爛れた生活を送っていた。自堕落な愛染、太郎が従者のように献身しているのは、彼女が素晴らしい肉体を、持っていたからだった。晩秋のある夕暮、京から太郎の妻・楓(高峰秀子)が尋ねて来た。太郎は、自分を探し求めて訪れた楓を邪慳に扱ったが、彼女はいつしか庫裡に住みつき、ただひたすら獣が獲物を待つ忍従さで太郎に仕えた。それから半年ほども過ぎたある晩、道に迷った高野の上人(佐 藤慶)が、一夜の宿を乞うて訪れた。楓は早速自分の苦衷を訴えたが、上人は、愛染を憎む己の心の中にこそ鬼が住んでいると説教し、上人が所持している黄金仏を盗ろうとした太郎には
藤慶)が、一夜の宿を乞うて訪れた。楓は早速自分の苦衷を訴えたが、上人は、愛染を憎む己の心の中にこそ鬼が住んでいると説教し、上人が所持している黄金仏を盗ろうとした太郎には 呪文を唱えて立往生させた。だが、上人はそこに現われた愛染を見て動揺した。その昔、上人を恋仇きと争わせ、仏門に入る結縁をつくった女、それが愛染だった。上人に敵意を感じた愛染は、彼を本堂に誘う。そうした愛染に上人は仏の道を諭そうとしたが―。
呪文を唱えて立往生させた。だが、上人はそこに現われた愛染を見て動揺した。その昔、上人を恋仇きと争わせ、仏門に入る結縁をつくった女、それが愛染だった。上人に敵意を感じた愛染は、彼を本堂に誘う。そうした愛染に上人は仏の道を諭そうとしたが―。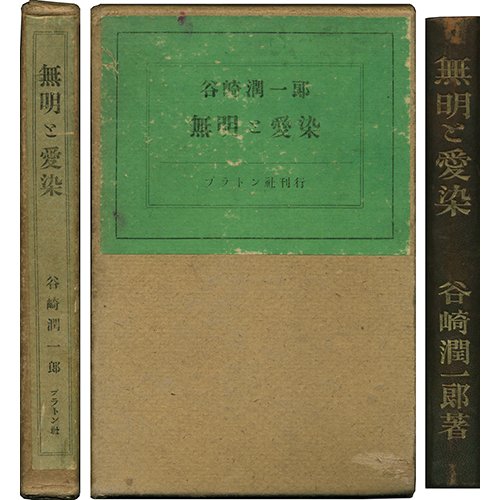

 っていることになる)。従って、落ち武者たちが寺を襲い、それを太郎が妻妾見守る前で一人で片付けるというシーンも映画のオリジナルです。勝新太郎の座頭市シリーズを第1作の「座頭市物語」('62年/大映)をはじめ何本も撮っている監督なので、やはり剣戟を入れないと収まらなかったのでしょう(笑)。どこまでこんな調子で原作からの改変があるのかなあと思って観ていたら、佐藤慶の演じる上人が訪ねて来るところから原作戯曲の通りで、宮川一夫のカメラ、伊福部昭の音楽も相俟って、重厚感のある映像化作品に仕上がっていました。
っていることになる)。従って、落ち武者たちが寺を襲い、それを太郎が妻妾見守る前で一人で片付けるというシーンも映画のオリジナルです。勝新太郎の座頭市シリーズを第1作の「座頭市物語」('62年/大映)をはじめ何本も撮っている監督なので、やはり剣戟を入れないと収まらなかったのでしょう(笑)。どこまでこんな調子で原作からの改変があるのかなあと思って観ていたら、佐藤慶の演じる上人が訪ねて来るところから原作戯曲の通りで、宮川一夫のカメラ、伊福部昭の音楽も相俟って、重厚感のある映像化作品に仕上がっていました。
 愛染と楓の激突はそのまま新珠三千代と高峰秀子の演技合戦の様相を呈しているように思われ(新珠三千代は現代的なメイク、高峰秀子は能面のようなメイクで、これは肉体と精神の対決を意味しているのではないか)、序盤で派手な剣戟を見せた勝新太郎も、愛染と楓の凌ぎ合いの狭間でたじたじとなる太郎さながらに、やや後退していく感じ。それでも、ああ、この役者が黒澤明の「影武者」をやっていたらなあ、と思わせる骨太さを遺憾なく発揮していました。
愛染と楓の激突はそのまま新珠三千代と高峰秀子の演技合戦の様相を呈しているように思われ(新珠三千代は現代的なメイク、高峰秀子は能面のようなメイクで、これは肉体と精神の対決を意味しているのではないか)、序盤で派手な剣戟を見せた勝新太郎も、愛染と楓の凌ぎ合いの狭間でたじたじとなる太郎さながらに、やや後退していく感じ。それでも、ああ、この役者が黒澤明の「影武者」をやっていたらなあ、と思わせる骨太さを遺憾なく発揮していました。 考えてみれば、原作は戯曲で、それをかなり忠実に再現しているので、役者は原作と同じセリフを話すことになり、新藤兼人の脚本は実質的には前の方に付け加えた部分だけかと思って、「結末は知っているよ」みたいな感じて観ていました。そしたら、最後の最後で意表を突かれました。
考えてみれば、原作は戯曲で、それをかなり忠実に再現しているので、役者は原作と同じセリフを話すことになり、新藤兼人の脚本は実質的には前の方に付け加えた部分だけかと思って、「結末は知っているよ」みたいな感じて観ていました。そしたら、最後の最後で意表を突かれました。 谷崎文学の世界を分かりやすく且つ重厚に再現していましたが、加えて、原作と異なる結末で、"意外性"も愉しめました。これ、映画を観てから原作を読んだ人も、原作の結末に「あれっ」と思うはずであって、全集で20ページくらいなので是非読んでみて欲しいと思います(原作の方が映画より"谷崎的"であるため、映画を観た人は原作がどうなっているか確認した方がいいように思う。映画は「魔性の女」が生きていてはならないというか、"映画的"に改変されている)。
谷崎文学の世界を分かりやすく且つ重厚に再現していましたが、加えて、原作と異なる結末で、"意外性"も愉しめました。これ、映画を観てから原作を読んだ人も、原作の結末に「あれっ」と思うはずであって、全集で20ページくらいなので是非読んでみて欲しいと思います(原作の方が映画より"谷崎的"であるため、映画を観た人は原作がどうなっているか確認した方がいいように思う。映画は「魔性の女」が生きていてはならないというか、"映画的"に改変されている)。
 「鬼の棲む館」●制作年:1969年●監督・脚本:三隅研次●製作:永田雅一●脚本:新藤兼人●撮影:宮川一夫●音楽:伊福部昭●原作:谷崎潤一郎「無明と愛染」(戯曲)●時間:76分●出演:勝新太郎/高峰秀子/新珠三千代/佐藤慶/五味龍太郎/木村元/伊達岳志/伴勇太郎/松田剛武/黒木現●公開:1969/05●配給:大映●最初に
「鬼の棲む館」●制作年:1969年●監督・脚本:三隅研次●製作:永田雅一●脚本:新藤兼人●撮影:宮川一夫●音楽:伊福部昭●原作:谷崎潤一郎「無明と愛染」(戯曲)●時間:76分●出演:勝新太郎/高峰秀子/新珠三千代/佐藤慶/五味龍太郎/木村元/伊達岳志/伴勇太郎/松田剛武/黒木現●公開:1969/05●配給:大映●最初に 観た場所:神田・神保町シアター(21-03-10)(評価:★★★★)
観た場所:神田・神保町シアター(21-03-10)(評価:★★★★)





 オチが面白かったです。原作を読んだ上で今井正監督の映画化作品を観ましたが、映画でも楽しめました。今井正監督はリアリズムにこだわる作風ですが、こうした話は、細部の描写がリアリであればあるほど、ラストが効いてくるように思いました。若き日の仲谷昇が、放蕩息子を好演しています(あれだけ出ているのに何とノンクレジット。'63年に、劇団の体質への不満から芥川比呂志、小池朝雄、神山繁らと文学座を脱退することになる。因みに、芥川比呂志はこの作品の第1部「
オチが面白かったです。原作を読んだ上で今井正監督の映画化作品を観ましたが、映画でも楽しめました。今井正監督はリアリズムにこだわる作風ですが、こうした話は、細部の描写がリアリであればあるほど、ラストが効いてくるように思いました。若き日の仲谷昇が、放蕩息子を好演しています(あれだけ出ているのに何とノンクレジット。'63年に、劇団の体質への不満から芥川比呂志、小池朝雄、神山繁らと文学座を脱退することになる。因みに、芥川比呂志はこの作品の第1部「 中編に見合った軽妙なオチであるし、作者はミステリ作家並みのストーリーテラーであるなあと思うのですが、一方で、このオチであるがゆえにこの掌編を人情小説の域を出ないものとして、文学作品としてとしてはあまり評価しない人もいるようです。確かにストーリー的に見ても、お峰が伯父(養父にあたる)のために金を工面することが出来たのには安堵させられますが、一時的解決にはなっていても根本的解決にはなっておらず、さらに言えば、お峰が金を結んだことで、罪人が一人誕生したとも言えます。
中編に見合った軽妙なオチであるし、作者はミステリ作家並みのストーリーテラーであるなあと思うのですが、一方で、このオチであるがゆえにこの掌編を人情小説の域を出ないものとして、文学作品としてとしてはあまり評価しない人もいるようです。確かにストーリー的に見ても、お峰が伯父(養父にあたる)のために金を工面することが出来たのには安堵させられますが、一時的解決にはなっていても根本的解決にはなっておらず、さらに言えば、お峰が金を結んだことで、罪人が一人誕生したとも言えます。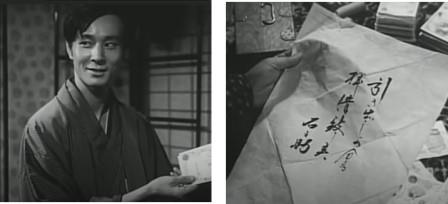 また、この作品を単純にコミカルなものとして捉えれば、石之助はお峰にとって救世主的な存在ということになるのかもしれませんが(実際、「山村家―富める世界への反逆者」とか「山村家の贖罪」の代行者とみる説がある)、それは偶然そういう結果になっただけで、別に石之助がお峰の側にいるわけではなく、彼はあくまでも「持てる側」にいて、その意味では「持たざる側」にいるお峰とは対峙的な存在ではないかと思います。
また、この作品を単純にコミカルなものとして捉えれば、石之助はお峰にとって救世主的な存在ということになるのかもしれませんが(実際、「山村家―富める世界への反逆者」とか「山村家の贖罪」の代行者とみる説がある)、それは偶然そういう結果になっただけで、別に石之助がお峰の側にいるわけではなく、彼はあくまでも「持てる側」にいて、その意味では「持たざる側」にいるお峰とは対峙的な存在ではないかと思います。 この辺りは研究者の間でも議論が活発なようですが、一葉が書いているうちにお峰を救わずにはおれなくなったのではないかという説もあって、これ、何だか当たっていそうですが、こうなると結局本人に聞いてみないとわからないということになるのではないでしょうか(研究者もそれは分かった上で議論しているのだと思うが)。
この辺りは研究者の間でも議論が活発なようですが、一葉が書いているうちにお峰を救わずにはおれなくなったのではないかという説もあって、これ、何だか当たっていそうですが、こうなると結局本人に聞いてみないとわからないということになるのではないでしょうか(研究者もそれは分かった上で議論しているのだと思うが)。 ット)《大つごもり》久我美子/中村伸郎/竜岡晋/長岡輝子/荒木道子/仲谷昇(山村石之助(ノンクレジット))/岸田今日子(山村家次女(ノンクレジット))/北村和夫(車夫(ノンクレジット))/河原崎次郎(従弟・三之助(ノンクレジット))《にごりえ》淡島千景/杉村春子/賀原夏子/南美江/北城真記子/文野朋子/山村聰/宮口精二/十朱久雄/加藤武(ヤクザ(ノンクレジット))/加藤治子/松山省二/小池朝雄(女郎に絡む男(ノンクレジット))/神山繁 (ガラの悪い酔客(ノンクレジット))●公開:1953/11●配給:松竹(評価:★★★★)
ット)《大つごもり》久我美子/中村伸郎/竜岡晋/長岡輝子/荒木道子/仲谷昇(山村石之助(ノンクレジット))/岸田今日子(山村家次女(ノンクレジット))/北村和夫(車夫(ノンクレジット))/河原崎次郎(従弟・三之助(ノンクレジット))《にごりえ》淡島千景/杉村春子/賀原夏子/南美江/北城真記子/文野朋子/山村聰/宮口精二/十朱久雄/加藤武(ヤクザ(ノンクレジット))/加藤治子/松山省二/小池朝雄(女郎に絡む男(ノンクレジット))/神山繁 (ガラの悪い酔客(ノンクレジット))●公開:1953/11●配給:松竹(評価:★★★★)


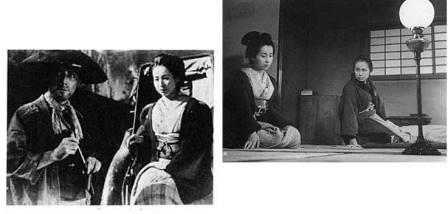 お関が夫との離縁を両親に哀願するも(DV夫か?)、父親に「子どもと別れて実家で泣き暮らすなら、夫のもとで泣き暮らすのも同じと諦めろ」と言われて(酷いこと言う父親だなあ)本当に諦めるという悲惨な話ですが、背景には嫁ぎ先と実家の経済格差があり、嫁ぎ先は裕福で、別れれば子どもの親権は経済力のある向こう側に行くし、父親からすれば息子の就職まで世話してもらっているので、こちらから離縁を申し出るなんて到底不可能だという状況のようです。左翼系映画人である今井正監督が映像化したことからも窺えるように、経済格差がモチーフの1つにあるかと思います。
お関が夫との離縁を両親に哀願するも(DV夫か?)、父親に「子どもと別れて実家で泣き暮らすなら、夫のもとで泣き暮らすのも同じと諦めろ」と言われて(酷いこと言う父親だなあ)本当に諦めるという悲惨な話ですが、背景には嫁ぎ先と実家の経済格差があり、嫁ぎ先は裕福で、別れれば子どもの親権は経済力のある向こう側に行くし、父親からすれば息子の就職まで世話してもらっているので、こちらから離縁を申し出るなんて到底不可能だという状況のようです。左翼系映画人である今井正監督が映像化したことからも窺えるように、経済格差がモチーフの1つにあるかと思います。 「にごりえ」●制作年:1953年●監督:今井正●製作:伊藤武郎●脚本:水木洋子/井手俊郎●撮影:中尾駿一郎●音楽:團伊玖磨●原作:樋口一葉『十三夜』『大つごもり』『にごりえ』●時間:130分●出演:《十三夜》田村秋子/丹阿弥谷津子/三津田健/芥川比呂志/久門祐夫(ノンクレジット)《大つごもり》久我美子/中村伸郎/竜岡晋/長岡輝子/荒木道子/仲谷昇(山村石之助(ノンクレジット))/岸田今日子(山村家次女(ノンクレジット))/北村和夫(車夫(ノンクレジット))/河原崎次郎(従弟・三之助(ノンクレジット))《にごりえ》淡島千景/杉村春子/賀原夏子/南美江/北城真記子/文野朋子/山村聰/宮口精二/十朱久雄/加藤武(ヤクザ(ノンクレジット))/加藤治子/松山省二/小池朝雄(女郎に絡む男(ノンクレジット))/神山繁 (ガラの悪い酔客(ノンクレジット))●公開:1953/11●配給:松竹(評価:★★★★)
「にごりえ」●制作年:1953年●監督:今井正●製作:伊藤武郎●脚本:水木洋子/井手俊郎●撮影:中尾駿一郎●音楽:團伊玖磨●原作:樋口一葉『十三夜』『大つごもり』『にごりえ』●時間:130分●出演:《十三夜》田村秋子/丹阿弥谷津子/三津田健/芥川比呂志/久門祐夫(ノンクレジット)《大つごもり》久我美子/中村伸郎/竜岡晋/長岡輝子/荒木道子/仲谷昇(山村石之助(ノンクレジット))/岸田今日子(山村家次女(ノンクレジット))/北村和夫(車夫(ノンクレジット))/河原崎次郎(従弟・三之助(ノンクレジット))《にごりえ》淡島千景/杉村春子/賀原夏子/南美江/北城真記子/文野朋子/山村聰/宮口精二/十朱久雄/加藤武(ヤクザ(ノンクレジット))/加藤治子/松山省二/小池朝雄(女郎に絡む男(ノンクレジット))/神山繁 (ガラの悪い酔客(ノンクレジット))●公開:1953/11●配給:松竹(評価:★★★★)


 嘉永年間、江戸日本橋はせがわ町に、おしず(藤村志保)、おたか(若柳菊)の姉妹がいた。二人はそれぞれ、長唄の師匠、仕立屋として、神経を病んで仕事を休んでいる彫金師の父・新七(藤原釜足)に代って、一家の生計を支えていた。姉のおしずは、生半可な諺を乱発する癖のあるお人好し、妹は利口で勝気な性格だった。姉妹にとって悩みの種は、時折姿を現わしては僅かな貯えを持ち出していく兄の栄二(戸浦六宏)のことで、二人の結婚を妨げている原因の一つあった。ある日、おたかに、彼女が仕立物を納めている信濃屋の一人息子・友吉(塩崎純男)との縁談が持ち上がる。おたかは友吉を憎からず思っていたのだが、彼女は姉よりも先に嫁ぐのが心苦しく、また栄二のこともあるので話を断る。だが、妹の本心を知るおしずは、信濃屋の両親に栄二のことを打ち明け、妹には自分にも好きな人があって近いうちに祝言を上げるからと、縁談を纏めたのである。おたかは喜びながらも、姉の結婚話は嘘に違いないと胸を痛める。そして姉が好きな人だという貞二郎(細川俊之)に会ってみて、姉の嘘を確かめた。だが、おたかは姉が本当に貞二郎に焦がれているのを知っていた。彫金師としては江戸一番の腕を持ちながら少しスネたところのある貞二郎におたかは頼み込み、おしずに会ってもらうことにし。試しにと、おしずに会った貞二郎は、彼女の天衣無縫な性格に心がなごむ。だが、このことが、前からおしずを囲ってみたいと思っていた鶴村(安部徹)に伝わると、鶴村は貞二郎に、おしずは自分の囲われ者だと言って手を引かせようとした。それを真に受けた貞二郎は、おたかに会って確めようとした時、おしずの自分を想ういじらしい気持ちを訴えられて我が身の卑しい気持ちを恥じる。やがておたかの結納も無事に終えた夜、栄二が姿を現わした。おしずは、栄二が妹の婚礼を邪魔する気なら、刺し違えて自分も死のうと短刀を握りしめる―。
嘉永年間、江戸日本橋はせがわ町に、おしず(藤村志保)、おたか(若柳菊)の姉妹がいた。二人はそれぞれ、長唄の師匠、仕立屋として、神経を病んで仕事を休んでいる彫金師の父・新七(藤原釜足)に代って、一家の生計を支えていた。姉のおしずは、生半可な諺を乱発する癖のあるお人好し、妹は利口で勝気な性格だった。姉妹にとって悩みの種は、時折姿を現わしては僅かな貯えを持ち出していく兄の栄二(戸浦六宏)のことで、二人の結婚を妨げている原因の一つあった。ある日、おたかに、彼女が仕立物を納めている信濃屋の一人息子・友吉(塩崎純男)との縁談が持ち上がる。おたかは友吉を憎からず思っていたのだが、彼女は姉よりも先に嫁ぐのが心苦しく、また栄二のこともあるので話を断る。だが、妹の本心を知るおしずは、信濃屋の両親に栄二のことを打ち明け、妹には自分にも好きな人があって近いうちに祝言を上げるからと、縁談を纏めたのである。おたかは喜びながらも、姉の結婚話は嘘に違いないと胸を痛める。そして姉が好きな人だという貞二郎(細川俊之)に会ってみて、姉の嘘を確かめた。だが、おたかは姉が本当に貞二郎に焦がれているのを知っていた。彫金師としては江戸一番の腕を持ちながら少しスネたところのある貞二郎におたかは頼み込み、おしずに会ってもらうことにし。試しにと、おしずに会った貞二郎は、彼女の天衣無縫な性格に心がなごむ。だが、このことが、前からおしずを囲ってみたいと思っていた鶴村(安部徹)に伝わると、鶴村は貞二郎に、おしずは自分の囲われ者だと言って手を引かせようとした。それを真に受けた貞二郎は、おたかに会って確めようとした時、おしずの自分を想ういじらしい気持ちを訴えられて我が身の卑しい気持ちを恥じる。やがておたかの結納も無事に終えた夜、栄二が姿を現わした。おしずは、栄二が妹の婚礼を邪魔する気なら、刺し違えて自分も死のうと短刀を握りしめる―。 1967年公開の三隅研次(1921-1975)監督作で(脚本は依田義賢)、原作は、山本周五郎が江戸・日本橋を舞台に、お互いの幸せを尊重し合う姉妹の姿を描いた『おたふく物語』。姉・おしずを演じる藤村志保は、大映の演技研究生だった頃に原作を読み、いつかこの役を演じたいと思いを抱いていただけあって、お人好しを可愛く演じてはまり役でした。藤村志保はこの頃は毎年5本から10本の映画に出演しており(三隅研次監督の「
1967年公開の三隅研次(1921-1975)監督作で(脚本は依田義賢)、原作は、山本周五郎が江戸・日本橋を舞台に、お互いの幸せを尊重し合う姉妹の姿を描いた『おたふく物語』。姉・おしずを演じる藤村志保は、大映の演技研究生だった頃に原作を読み、いつかこの役を演じたいと思いを抱いていただけあって、お人好しを可愛く演じてはまり役でした。藤村志保はこの頃は毎年5本から10本の映画に出演しており(三隅研次監督の「

 「湯治」では、金をせびりに来た兄におしずが短刀を突き出して追い返すも、衣類を持って後を追いかけるという結末で、家に来られても困るけれども、兄妹愛はあるといった感じでしょうか。映画のように、もう来ないという約束を破って妹の婚礼を邪魔するようなタイミングで来たわけでもないですが、映画の方でも、最後には栄二(戸浦六宏)は今度こそもう邪魔しないと言っているので、結局、兄も根はそんな悪い人ではなかったっということでしょう。
「湯治」では、金をせびりに来た兄におしずが短刀を突き出して追い返すも、衣類を持って後を追いかけるという結末で、家に来られても困るけれども、兄妹愛はあるといった感じでしょうか。映画のように、もう来ないという約束を破って妹の婚礼を邪魔するようなタイミングで来たわけでもないですが、映画の方でも、最後には栄二(戸浦六宏)は今度こそもう邪魔しないと言っているので、結局、兄も根はそんな悪い人ではなかったっということでしょう。
 原作の最後の「おたふく」では、おしずもおたかも既に結婚していて、おしずの夫は勿論貞二郎ですが、ある日、貞二郎が自分の作った、値段的には張るはずの彫り物を、かつて裕福ではなかったはずのおしずが幾つも持っていることを知り、そこから鶴村との過去の関係を疑い始めて悩むというもので、この誤解を解くために今度はおたかの方が、おしずにとって貞次郎は長年の想い人であり、彼が丹精こめて作った彫り物を身につけていたかったが、直接は言えなくて、長唄の稽古に来ていた鶴村の家人に頼んで鶴村の名で注文したものだと事情を説明し、貞二郎の疑念を晴らすというもの。映画の方は結婚前なので、おしずとおたかの姉妹愛にうたれた貞二郎が、おしずに惚れ直して父・新七におしずを嫁にと申し入れるというものでした。
原作の最後の「おたふく」では、おしずもおたかも既に結婚していて、おしずの夫は勿論貞二郎ですが、ある日、貞二郎が自分の作った、値段的には張るはずの彫り物を、かつて裕福ではなかったはずのおしずが幾つも持っていることを知り、そこから鶴村との過去の関係を疑い始めて悩むというもので、この誤解を解くために今度はおたかの方が、おしずにとって貞次郎は長年の想い人であり、彼が丹精こめて作った彫り物を身につけていたかったが、直接は言えなくて、長唄の稽古に来ていた鶴村の家人に頼んで鶴村の名で注文したものだと事情を説明し、貞二郎の疑念を晴らすというもの。映画の方は結婚前なので、おしずとおたかの姉妹愛にうたれた貞二郎が、おしずに惚れ直して父・新七におしずを嫁にと申し入れるというものでした。 最後がおしずの"天然ボケ"で終わるところは原作も映画も同じで、ストーリーの起伏はありますが、「なみだ川」というタイトルに反して映画も原作も結構コミカルな面があり(その上で泣かせる人情話なのだが)、また、それを藤村志保が上手く演じていました(刃物屋の玉川良一に小刀の突き方を教わるところなどは、深刻な状況なのにほのぼのコントみたい)。
最後がおしずの"天然ボケ"で終わるところは原作も映画も同じで、ストーリーの起伏はありますが、「なみだ川」というタイトルに反して映画も原作も結構コミカルな面があり(その上で泣かせる人情話なのだが)、また、それを藤村志保が上手く演じていました(刃物屋の玉川良一に小刀の突き方を教わるところなどは、深刻な状況なのにほのぼのコントみたい)。
 時制的に異なる三話を映画では一続きにしたために、「妹の縁談」は概ねそのままですが、「湯治」では兄の栄二が一度した約束を破っておたかの結納後(婚礼前)に再び押しかけてくるようにし(でも最後は去って行く)、「おたふく」での貞次郎(細川俊之)の疑念は、過去の関係に対するものではなく、リアルタイムにしたのでしょう。そのため、原作には名前しか出てこない鶴村が映画では登場し(安部徹)、貞二郎におしずは自分の囲い者だと言って手を引かせようとするなど、栄二の戸浦六宏と異なり、終始一貫して"悪役"でした(笑)。
時制的に異なる三話を映画では一続きにしたために、「妹の縁談」は概ねそのままですが、「湯治」では兄の栄二が一度した約束を破っておたかの結納後(婚礼前)に再び押しかけてくるようにし(でも最後は去って行く)、「おたふく」での貞次郎(細川俊之)の疑念は、過去の関係に対するものではなく、リアルタイムにしたのでしょう。そのため、原作には名前しか出てこない鶴村が映画では登場し(安部徹)、貞二郎におしずは自分の囲い者だと言って手を引かせようとするなど、栄二の戸浦六宏と異なり、終始一貫して"悪役"でした(笑)。 「なみだ川」●制作年:1967年●監督:三隅研次●脚本:依田義賢●撮影:牧浦地志●音楽:小杉太一郎●原作:山本周五郎●時間:79 分●出演:藤村志保/若柳菊/細川俊之/藤原釜足/玉川良一/安部徹/戸浦六宏/塩崎純男/春本富士夫/水原浩一/花布辰男/本間久子/町田博子/寺島雄作/木村玄/越川一/美山晋八/黒木現/香山恵子/橘公子●公開:1967/10●配給:大映●最初に観た場所:神田・神保町シアター(21-02-24)(評価:★★★★)
「なみだ川」●制作年:1967年●監督:三隅研次●脚本:依田義賢●撮影:牧浦地志●音楽:小杉太一郎●原作:山本周五郎●時間:79 分●出演:藤村志保/若柳菊/細川俊之/藤原釜足/玉川良一/安部徹/戸浦六宏/塩崎純男/春本富士夫/水原浩一/花布辰男/本間久子/町田博子/寺島雄作/木村玄/越川一/美山晋八/黒木現/香山恵子/橘公子●公開:1967/10●配給:大映●最初に観た場所:神田・神保町シアター(21-02-24)(評価:★★★★)  藤原釜足(彫金師の父・新七)
藤原釜足(彫金師の父・新七)
 藤村 志保(ふじむら・しほ)女優
藤村 志保(ふじむら・しほ)女優

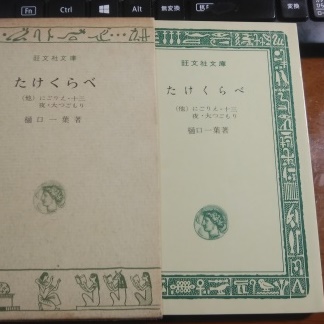
![樋口一葉 [ちくま日本文学013] 文庫.jpg](http://hurec.bz/book-movie/%E6%A8%8B%E5%8F%A3%E4%B8%80%E8%91%89%20%5B%E3%81%A1%E3%81%8F%E3%81%BE%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%96%87%E5%AD%A6013%5D%20%E6%96%87%E5%BA%AB.jpg)
 樋口一葉(1872-1896/24歳没)が1895(明治28)年1月から翌年1月まで「文学界」(刊行期間1893.1-1898.1)に断続的に連載た作品で、「暗夜」(1894.6-11)、「大つごもり」(1894.12)に続くものであり、文学界を主宰していた星野天知が、文学界1月号の原稿が集まらなくて一葉に作品を依頼し、一葉は書き溜めていた作品「雛鶏」を改題して発表したとのことです。翌1896(明治29)年、「文芸倶楽部」に一括掲載されると、森鷗外や幸田露伴らに着目され、鴎外の主宰する「めさまし草」誌上での鴎外、露伴、斎藤緑雨の3人による匿名合評「三人冗語」において高い評価で迎えられましたが、一葉はこの頃結核が悪化し、同年11月には死去しています。尚、再掲載時の原稿は口述して妹の邦子に書き取らせたものだそうです。
樋口一葉(1872-1896/24歳没)が1895(明治28)年1月から翌年1月まで「文学界」(刊行期間1893.1-1898.1)に断続的に連載た作品で、「暗夜」(1894.6-11)、「大つごもり」(1894.12)に続くものであり、文学界を主宰していた星野天知が、文学界1月号の原稿が集まらなくて一葉に作品を依頼し、一葉は書き溜めていた作品「雛鶏」を改題して発表したとのことです。翌1896(明治29)年、「文芸倶楽部」に一括掲載されると、森鷗外や幸田露伴らに着目され、鴎外の主宰する「めさまし草」誌上での鴎外、露伴、斎藤緑雨の3人による匿名合評「三人冗語」において高い評価で迎えられましたが、一葉はこの頃結核が悪化し、同年11月には死去しています。尚、再掲載時の原稿は口述して妹の邦子に書き取らせたものだそうです。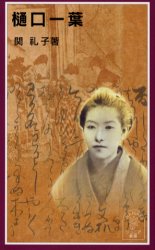
 らべ』('12年/理論社)が、擬古文の雰囲気を保っていてお奨めです。映画化作品では、五所平之助監督、美空ひばり主演の「たけくらべ」('55年/新東宝) がありますが、個人的には未見です。また、山口百恵のアルバム「15才」に「たけくらべ」という曲があります。千家和也(1946-2019)作詞の歌詞の冒頭の「お歯ぐろ溝(おはぐろどぶ)に燈火(ともしび)うつる」(コレ、「たけくらべ」冒頭の表現をそのまま使っている)の"お歯ぐろ溝"とは、遊女の逃亡を防ぐために設けられた吉原遊郭を囲む溝で、今は埋められてすべて路になっていますが、石垣の跡がちょっとだけ残っています。
らべ』('12年/理論社)が、擬古文の雰囲気を保っていてお奨めです。映画化作品では、五所平之助監督、美空ひばり主演の「たけくらべ」('55年/新東宝) がありますが、個人的には未見です。また、山口百恵のアルバム「15才」に「たけくらべ」という曲があります。千家和也(1946-2019)作詞の歌詞の冒頭の「お歯ぐろ溝(おはぐろどぶ)に燈火(ともしび)うつる」(コレ、「たけくらべ」冒頭の表現をそのまま使っている)の"お歯ぐろ溝"とは、遊女の逃亡を防ぐために設けられた吉原遊郭を囲む溝で、今は埋められてすべて路になっていますが、石垣の跡がちょっとだけ残っています。 お歯ぐろ溝の石垣跡
お歯ぐろ溝の石垣跡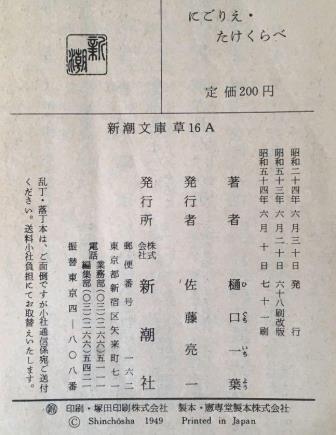
 【1949年文庫化・1978年・2013年改版[新潮文庫(『にごりえ・たけくらべ』)]/1950年文庫化・1999年改版[岩波文庫(『にごりえ・たけくらべ』)]/1954年再文庫化[角川文庫(『たけくらべ―他二篇』)]/1967年再文庫化[旺文社文庫(『たけくらべ』)]/1968年再文庫化[角川文庫(『たけくらべ・にごりえ』)]/1992年再文庫化・2008年改版[ちくま文庫(『ちくま日本文学013 樋口一葉』)]/1993年文庫化[集英社文庫(『たけくらべ』)]/2024年再文庫化[100分で読む名作小説(角川文庫)(『文鳥』)]】
【1949年文庫化・1978年・2013年改版[新潮文庫(『にごりえ・たけくらべ』)]/1950年文庫化・1999年改版[岩波文庫(『にごりえ・たけくらべ』)]/1954年再文庫化[角川文庫(『たけくらべ―他二篇』)]/1967年再文庫化[旺文社文庫(『たけくらべ』)]/1968年再文庫化[角川文庫(『たけくらべ・にごりえ』)]/1992年再文庫化・2008年改版[ちくま文庫(『ちくま日本文学013 樋口一葉』)]/1993年文庫化[集英社文庫(『たけくらべ』)]/2024年再文庫化[100分で読む名作小説(角川文庫)(『文鳥』)]】
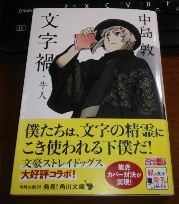









 昭和22(1947)年6月、当時40歳の坂口安吾(1906-1955)が雑誌『肉体』創刊号に発表した短編小説「桜の森の満開の下」(さくらのもりのまんかいのした)は、坂口安吾代表作の一つで、「堕落論」と並んで読まれており、傑作と称されることの多い作品です。
昭和22(1947)年6月、当時40歳の坂口安吾(1906-1955)が雑誌『肉体』創刊号に発表した短編小説「桜の森の満開の下」(さくらのもりのまんかいのした)は、坂口安吾代表作の一つで、「堕落論」と並んで読まれており、傑作と称されることの多い作品です。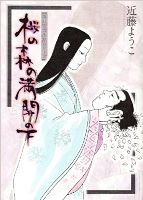
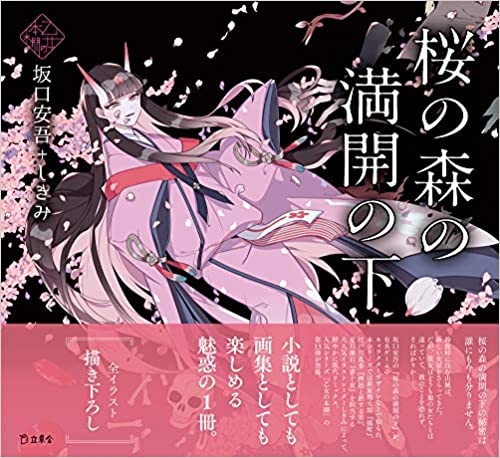




 質屋の娘・お艶(若尾文子)は、ある雪の夜、手代の新助(長谷川明男)と駈け落ちした。この二人を引き取ったのは、店に出入りする遊び人の権次夫婦(須賀不二男・藤原礼子)だった。優しい言葉で二人を迎え入れた夫婦だったが、権次は実は悪党で、お艶の親元へ現われ何かと小金を巻きあげた挙句に、お艶を芸者として売り飛ばし、新助を殺そうとしていた。そんなこととは知らないお艶と新助は、互いに求め合うまま狂おしい愛欲の日々を送っていた。しかし、そんなお艶の艶めかしい姿を、権次の下に出入りする刺青師の清吉(山本學)は焼けつくような眼差しで見ていた。ある雨の夜、権次は計画を実行に移し、殺し屋・三太(木村玄)を新助にさし向けるが、必死で抵抗した新助は、逆に三太を短刀で殺してしまう。同じ頃、土蔵に閉じこめられていたお艶は、清吉に麻薬をかがさ
質屋の娘・お艶(若尾文子)は、ある雪の夜、手代の新助(長谷川明男)と駈け落ちした。この二人を引き取ったのは、店に出入りする遊び人の権次夫婦(須賀不二男・藤原礼子)だった。優しい言葉で二人を迎え入れた夫婦だったが、権次は実は悪党で、お艶の親元へ現われ何かと小金を巻きあげた挙句に、お艶を芸者として売り飛ばし、新助を殺そうとしていた。そんなこととは知らないお艶と新助は、互いに求め合うまま狂おしい愛欲の日々を送っていた。しかし、そんなお艶の艶めかしい姿を、権次の下に出入りする刺青師の清吉(山本學)は焼けつくような眼差しで見ていた。ある雨の夜、権次は計画を実行に移し、殺し屋・三太(木村玄)を新助にさし向けるが、必死で抵抗した新助は、逆に三太を短刀で殺してしまう。同じ頃、土蔵に閉じこめられていたお艶は、清吉に麻薬をかがさ れて気を失い、その白い肌に巨大な女郎蜘蛛の刺青を施される。やがて眠りから醒めたお艶は、刺青によって眠っていた妖しい血を呼び起こされたように瞳が熱を帯びて濡れていた。それからというものお艶は辰巳芸者・染吉と名を改め、次々と男を酔わせてくが、お艶を忘れ切れない新助は嫉妬に身を焦がし、お艶と関係を持った男を次々と殺害、遂にある晩、短刀を持ってお艶に迫る。だが新助にはお艶を殺せず、逆にお艶が新助を刺す。一部始終を垣間見ていた清吉は、遂に耐え切れず自らが彫った女郎蜘蛛を短刀で刺し、自らも命を絶つ―。
れて気を失い、その白い肌に巨大な女郎蜘蛛の刺青を施される。やがて眠りから醒めたお艶は、刺青によって眠っていた妖しい血を呼び起こされたように瞳が熱を帯びて濡れていた。それからというものお艶は辰巳芸者・染吉と名を改め、次々と男を酔わせてくが、お艶を忘れ切れない新助は嫉妬に身を焦がし、お艶と関係を持った男を次々と殺害、遂にある晩、短刀を持ってお艶に迫る。だが新助にはお艶を殺せず、逆にお艶が新助を刺す。一部始終を垣間見ていた清吉は、遂に耐え切れず自らが彫った女郎蜘蛛を短刀で刺し、自らも命を絶つ―。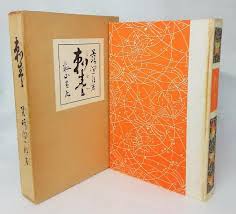 原作「刺青(しせい)」は、1910(明治43)年11月、同人誌の第二次『新思潮』に発表された谷崎潤一郎の短編小説で、作者本人が処女作だとしていたという作品です(単行本は、翌1911(明治44)年12月に籾山書店より刊行)。皮膚や足に対するフェティシズムと、それに溺れる男の性的倒錯など、その後の谷崎作品に共通するモチーフが見られます。
原作「刺青(しせい)」は、1910(明治43)年11月、同人誌の第二次『新思潮』に発表された谷崎潤一郎の短編小説で、作者本人が処女作だとしていたという作品です(単行本は、翌1911(明治44)年12月に籾山書店より刊行)。皮膚や足に対するフェティシズムと、それに溺れる男の性的倒錯など、その後の谷崎作品に共通するモチーフが見られます。


 一方、増村保造監督の映画「刺青(いれずみ)」は、「刺青」の他に同じ谷崎の短編小説「お艶殺し」も基にしていて、映画の方で展開されるサスペンス時代劇風のストーリーは、「お艶殺し」に拠るか、または脚本家としての新藤兼人(1912-2012)のオリジナルということになります。強いて言えば、谷崎の原作における刺青を施され魔性を覚醒された少女がその後どうなったかを、イメージを膨らませて描いた後日譚ともとれます。ただし、映画で、若尾文子演じるお艶が山本學演じる清吉に刺青を掘られるのは物語の中盤なので、10ページほどしかない谷崎の原作に、プロローグとエピローグの両方を足したという感じでしょうか。
一方、増村保造監督の映画「刺青(いれずみ)」は、「刺青」の他に同じ谷崎の短編小説「お艶殺し」も基にしていて、映画の方で展開されるサスペンス時代劇風のストーリーは、「お艶殺し」に拠るか、または脚本家としての新藤兼人(1912-2012)のオリジナルということになります。強いて言えば、谷崎の原作における刺青を施され魔性を覚醒された少女がその後どうなったかを、イメージを膨らませて描いた後日譚ともとれます。ただし、映画で、若尾文子演じるお艶が山本學演じる清吉に刺青を掘られるのは物語の中盤なので、10ページほどしかない谷崎の原作に、プロローグとエピローグの両方を足したという感じでしょうか。

 「刺青(いれずみ)」●制作年:1966年●監督:増村保造●脚本:新藤兼人●撮影:宮川一夫●音楽:鏑木創●原作:谷崎潤一郎「刺青(しせい)」「お艶殺し」●時間:86分●出演:若尾文子/長谷川明男/山本學/佐藤慶/須賀不二男/内田朝雄/
「刺青(いれずみ)」●制作年:1966年●監督:増村保造●脚本:新藤兼人●撮影:宮川一夫●音楽:鏑木創●原作:谷崎潤一郎「刺青(しせい)」「お艶殺し」●時間:86分●出演:若尾文子/長谷川明男/山本學/佐藤慶/須賀不二男/内田朝雄/ 藤原礼子/毛利菊枝/南部彰三/木村玄/岩田正/藤川準/薮内武司/山岡鋭二郎/森内一夫/松田剛武/橘公子●公開:1966/01●配給:大映●最初に観た場所:角川シネマ有楽町(20-03-24)(評価:★★★☆)
藤原礼子/毛利菊枝/南部彰三/木村玄/岩田正/藤川準/薮内武司/山岡鋭二郎/森内一夫/松田剛武/橘公子●公開:1966/01●配給:大映●最初に観た場所:角川シネマ有楽町(20-03-24)(評価:★★★☆) 
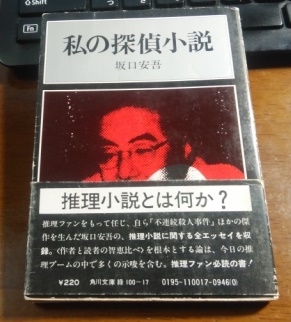

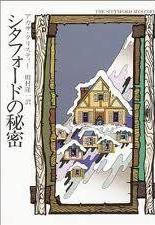
 具体的には、「志賀直哉に文学の問題はない」(昭和23年発表)において、志賀直哉を、その「一生には、生死を賭したアガキや脱出などはない」とし、「位置の安定だけが、彼の問題であり」、それだけにすぎなかったとしています。夏目漱石についても、「その思惟の根は(中略)わが周囲を肯定し、それを合理化して安定をもとめる以上に深まることはなかった」と批判的ですが、表題から窺えるように、志賀直哉が最大の批判対象となっています。
具体的には、「志賀直哉に文学の問題はない」(昭和23年発表)において、志賀直哉を、その「一生には、生死を賭したアガキや脱出などはない」とし、「位置の安定だけが、彼の問題であり」、それだけにすぎなかったとしています。夏目漱石についても、「その思惟の根は(中略)わが周囲を肯定し、それを合理化して安定をもとめる以上に深まることはなかった」と批判的ですが、表題から窺えるように、志賀直哉が最大の批判対象となっています。 ん(長谷川町子)も「絵はあまりお上手ではないが、文章は相当うまいし、特に思いつきが卓抜だ」という評価の仕方をしているのが興味深いです。作家では、「今度の芥川賞の候補にのぼった安岡章太郎という人のが甚だ新鮮なもので」あったと。ただし、「大岡(昇平)三島(由紀夫)両所のように後世おそるべしというところがない」とも。「大岡三島両所の文章は批評家にわからぬような文章や小説ではないね」とし、「甚だしく多くの人に理解される可能性を含んでいますよ」と述べています。
ん(長谷川町子)も「絵はあまりお上手ではないが、文章は相当うまいし、特に思いつきが卓抜だ」という評価の仕方をしているのが興味深いです。作家では、「今度の芥川賞の候補にのぼった安岡章太郎という人のが甚だ新鮮なもので」あったと。ただし、「大岡(昇平)三島(由紀夫)両所のように後世おそるべしというところがない」とも。「大岡三島両所の文章は批評家にわからぬような文章や小説ではないね」とし、「甚だしく多くの人に理解される可能性を含んでいますよ」と述べています。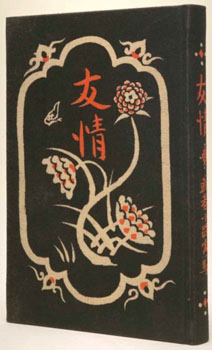
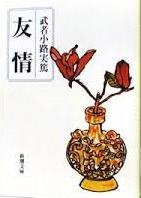


 武者小路実篤(1885-1976)が1919(大正8)年10月から12月に「大阪毎日新聞」に連載した作品で、1920(大正9)年4月には以文社より単行本が刊行されています。後に書かれる「愛と死」「若き日の思い出」と併せて、武者小路文学の青春三部作と言われていますが、特にこの「友情」は「恋する人はすべからく読むべし」とまで言われるほど根強い人気があるようで、調布市にある武者小路実篤記念館では、昨年['19年]に「友情」の発表100年を記念して、作中の言葉を記した「おみくじ」を作成し、来館者に配布したくらいです。
武者小路実篤(1885-1976)が1919(大正8)年10月から12月に「大阪毎日新聞」に連載した作品で、1920(大正9)年4月には以文社より単行本が刊行されています。後に書かれる「愛と死」「若き日の思い出」と併せて、武者小路文学の青春三部作と言われていますが、特にこの「友情」は「恋する人はすべからく読むべし」とまで言われるほど根強い人気があるようで、調布市にある武者小路実篤記念館では、昨年['19年]に「友情」の発表100年を記念して、作中の言葉を記した「おみくじ」を作成し、来館者に配布したくらいです。 この小説のモデルは、野島が武者小路実篤自身で、大宮が志賀直哉だと言われています。実生活では、志賀直哉は武者小路実篤より2歳年上ですが、二人とも初等科から学習院に通っていて、武者小路実篤が中等科6年、17歳の時、二回落第した志賀が同級になったことから、以後親しくなっています。志賀直哉はビリから6番目、武者小路実篤はビリから4番目の成績で学習院を卒業し、揃って東京帝国大学に入学しています(成績の悪い者同士で仲が良かった?)。ただし、武者小路実篤と志賀直哉が一人の女性を巡って恋敵同士のような関係になったという事実は無いようです(若い頃の風貌を見ると、志賀直哉の方がモテそうだが)。
この小説のモデルは、野島が武者小路実篤自身で、大宮が志賀直哉だと言われています。実生活では、志賀直哉は武者小路実篤より2歳年上ですが、二人とも初等科から学習院に通っていて、武者小路実篤が中等科6年、17歳の時、二回落第した志賀が同級になったことから、以後親しくなっています。志賀直哉はビリから6番目、武者小路実篤はビリから4番目の成績で学習院を卒業し、揃って東京帝国大学に入学しています(成績の悪い者同士で仲が良かった?)。ただし、武者小路実篤と志賀直哉が一人の女性を巡って恋敵同士のような関係になったという事実は無いようです(若い頃の風貌を見ると、志賀直哉の方がモテそうだが)。
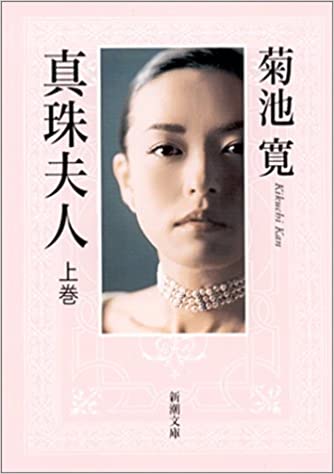
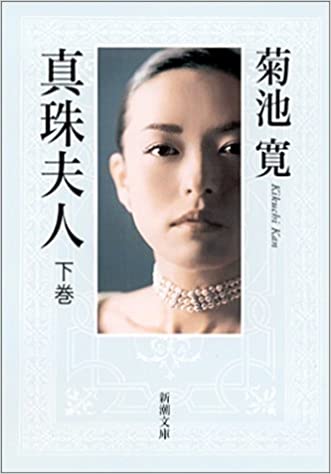


 渥美信一郎は療養中の妻の見舞いに訪れた湯河原で自動車事故に巻き込まれる。事故にあった青年・青木淳は腕時計を「瑠璃子に返してくれ」と言い残しノートを託して絶命する。青木の葬儀で見聞きした情報を基に、信一郎は妖艶な未亡人・壮田瑠璃子を訪ねる。瑠璃子は腕時計を見て動揺した様子を見せるが、それをごまかし腕時計を預かり、信一郎を音楽会に誘う。青木のノートには愛の印として貰った腕時計が他の男にも送られているのを知って自殺を決意したことが書かれていた―。数年前、貿易商・壮田勝平は自宅で催した園遊会で、子爵の息子・杉野直也と男爵の娘・唐沢瑠璃子から成金ぶりを侮辱され激怒、奸計を巡らす。貴族院議員・唐沢光徳の債権を全て買い取りさらに弱みを握り、瑠璃子に結婚を迫る。自殺を図った父に瑠璃子は「ユージットになろうと思う」と押しとどめ、直也には復讐のため結婚しても貞操を守ると手紙する。壮田と結婚した瑠璃子は、父の見舞いを理由に実家に帰ったり、壮田に「お父様になって」と言ったりして体を許さない。知的障害のある壮田の息子・勝彦も手懐け、寝室の見張りをさせる。壮田は瑠璃子を葉山の別荘に連れ出し、嵐の夜に関係を結ぼうとするが、瑠璃子を追ってきた勝彦が窓から飛び込んで荘田の襲いかかるのを見て驚き卒倒、壮田は我が子の将来を瑠璃子に託し亡くなる、豪奢な生活はその瑠璃子を、男の気持ちを弄ぶ妖婦へと変貌させていた―。
渥美信一郎は療養中の妻の見舞いに訪れた湯河原で自動車事故に巻き込まれる。事故にあった青年・青木淳は腕時計を「瑠璃子に返してくれ」と言い残しノートを託して絶命する。青木の葬儀で見聞きした情報を基に、信一郎は妖艶な未亡人・壮田瑠璃子を訪ねる。瑠璃子は腕時計を見て動揺した様子を見せるが、それをごまかし腕時計を預かり、信一郎を音楽会に誘う。青木のノートには愛の印として貰った腕時計が他の男にも送られているのを知って自殺を決意したことが書かれていた―。数年前、貿易商・壮田勝平は自宅で催した園遊会で、子爵の息子・杉野直也と男爵の娘・唐沢瑠璃子から成金ぶりを侮辱され激怒、奸計を巡らす。貴族院議員・唐沢光徳の債権を全て買い取りさらに弱みを握り、瑠璃子に結婚を迫る。自殺を図った父に瑠璃子は「ユージットになろうと思う」と押しとどめ、直也には復讐のため結婚しても貞操を守ると手紙する。壮田と結婚した瑠璃子は、父の見舞いを理由に実家に帰ったり、壮田に「お父様になって」と言ったりして体を許さない。知的障害のある壮田の息子・勝彦も手懐け、寝室の見張りをさせる。壮田は瑠璃子を葉山の別荘に連れ出し、嵐の夜に関係を結ぼうとするが、瑠璃子を追ってきた勝彦が窓から飛び込んで荘田の襲いかかるのを見て驚き卒倒、壮田は我が子の将来を瑠璃子に託し亡くなる、豪奢な生活はその瑠璃子を、男の気持ちを弄ぶ妖婦へと変貌させていた―。 1916年に戯曲『屋上の狂人』『暴徒の子』、翌年『父帰る』、1918年には『無名作家の日記』『忠直卿行状記』『恩讐の彼方に』などを続々発表して作家としての地位を確立し、1919年、芥川龍之介とともに大阪毎日新聞杜の客員となり、『藤十郎の恋』、『友と友の間』などを書いています。
1916年に戯曲『屋上の狂人』『暴徒の子』、翌年『父帰る』、1918年には『無名作家の日記』『忠直卿行状記』『恩讐の彼方に』などを続々発表して作家としての地位を確立し、1919年、芥川龍之介とともに大阪毎日新聞杜の客員となり、『藤十郎の恋』、『友と友の間』などを書いています。 その菊池寛が1920(大正9年)年の6月9日から12月22日まで大阪毎日新聞、東京日日新聞に連載したのがこの小説『真珠夫人』で、菊池寛(当時31歳)にとって初の本格的な通俗小説であり、その人気は新聞の読者層を変え、後の婦人雑誌ブームに影響を与えたとも言われています。通俗小説の代表格として、紅葉の『金色夜叉』や徳富蘆花の『不如帰』を継ぐとも言われたそうですが、それらよりはずっとモダンであると思います(作中に『金色夜叉』を巡る通俗小説論争がある)。
その菊池寛が1920(大正9年)年の6月9日から12月22日まで大阪毎日新聞、東京日日新聞に連載したのがこの小説『真珠夫人』で、菊池寛(当時31歳)にとって初の本格的な通俗小説であり、その人気は新聞の読者層を変え、後の婦人雑誌ブームに影響を与えたとも言われています。通俗小説の代表格として、紅葉の『金色夜叉』や徳富蘆花の『不如帰』を継ぐとも言われたそうですが、それらよりはずっとモダンであると思います(作中に『金色夜叉』を巡る通俗小説論争がある)。
 2002年7月に単行本が刊行され、翌8月に新潮文庫と文春文庫で文庫化されていますが、同2002年4月1日から6月28日の毎月曜から金曜までフジテレビ系列で放送された東海テレビ製作の昼ドラ「真珠夫人」全65回の放映が終わって、その人気を受けてそれぞれ急遽刊行されたのではないでしょうか。それ以前にも、1927年に松竹キネマの池田善信監督・栗島すみ子主演で、1950年には大映が山本嘉次郎監督・高峰三枝子・池部良主演で映画化され、1974年にはTBSがこれも昼ドラの「花王・愛の劇場」で光本幸子(「男はつらいよ」の初代マドンナ)主演の全40回が放映されていますが、2002年の放送はとりわけ人気が高かったようです。放送時間が昼1時30分から2時までで、DVDレコーダーなど無い時代で、会社務めの人の中にはビデオテープを買い溜めて録画した人も多かったとか。
2002年7月に単行本が刊行され、翌8月に新潮文庫と文春文庫で文庫化されていますが、同2002年4月1日から6月28日の毎月曜から金曜までフジテレビ系列で放送された東海テレビ製作の昼ドラ「真珠夫人」全65回の放映が終わって、その人気を受けてそれぞれ急遽刊行されたのではないでしょうか。それ以前にも、1927年に松竹キネマの池田善信監督・栗島すみ子主演で、1950年には大映が山本嘉次郎監督・高峰三枝子・池部良主演で映画化され、1974年にはTBSがこれも昼ドラの「花王・愛の劇場」で光本幸子(「男はつらいよ」の初代マドンナ)主演の全40回が放映されていますが、2002年の放送はとりわけ人気が高かったようです。放送時間が昼1時30分から2時までで、DVDレコーダーなど無い時代で、会社務めの人の中にはビデオテープを買い溜めて録画した人も多かったとか。 その2002年のフジテレビ版は、主演が横山めぐみ、脚本が中島丈博(「
その2002年のフジテレビ版は、主演が横山めぐみ、脚本が中島丈博(「 直也が瑠璃子と会っているのを知った登美子のいる自宅へ直也が帰宅すると、登美子が夫に「おかず何もありません、冷めたコロッケで我慢してください」と言い、たわしと刻んだキャ
直也が瑠璃子と会っているのを知った登美子のいる自宅へ直也が帰宅すると、登美子が夫に「おかず何もありません、冷めたコロッケで我慢してください」と言い、たわしと刻んだキャ ベツを皿に載せて出すという「たわしコロッケ」シーンが当時話題になりましたが、とにかくエグさが前面にきていたでしょうか。一方の瑠璃子は、義理の娘や息子を守りながら、内には直也への愛を秘め、健気に純潔を守り通すというのは原作どおりですが、原作のように男たちの前でフェミニズム論を展開することはなく、視聴者受けを狙ったのかキャラの先鋭的な部分を改変したような印象も受けます。
ベツを皿に載せて出すという「たわしコロッケ」シーンが当時話題になりましたが、とにかくエグさが前面にきていたでしょうか。一方の瑠璃子は、義理の娘や息子を守りながら、内には直也への愛を秘め、健気に純潔を守り通すというのは原作どおりですが、原作のように男たちの前でフェミニズム論を展開することはなく、視聴者受けを狙ったのかキャラの先鋭的な部分を改変したような印象も受けます。

 「真珠夫人」●演出:西本淳一/藤木靖之/大垣一穂●脚本:中島丈博●音楽:寺嶋民哉●出演:横山めぐみ/葛山信吾/大和田伸也/森下涼子/松尾敏伸/奈美悦子/日高真弓/浜田晃/増田未亜/河原 さぶ●放映:2002/04~06(全65回)●放送局:フジテレビ
「真珠夫人」●演出:西本淳一/藤木靖之/大垣一穂●脚本:中島丈博●音楽:寺嶋民哉●出演:横山めぐみ/葛山信吾/大和田伸也/森下涼子/松尾敏伸/奈美悦子/日高真弓/浜田晃/増田未亜/河原 さぶ●放映:2002/04~06(全65回)●放送局:フジテレビ



 宝石王・岩瀬庄兵衛(柳生博)に黒蜥蜴から「あなたの一番大切なものを頂戴にあがる」という予告状が届く。相談を受けた明智(天知茂)と波越警部(荒井注)が岩瀬と娘の早苗(加山麗子)とホテルロビーで話していると、ドイツ帰りで岩瀬の顧客の緑川夫人(小川真由美)がやって来る。岩瀬は、明智たちが大切なものとは何か尋ねると、「エジプトの星」というダイヤを見せる。黒蜥蜴が指定した夜、明智は浪越警部と共に黒蜥蜴の出現を待ち受けるが、警部はシャワーを浴びると睡魔が襲ってきて岩瀬と共にベッドで寝てしまう。緑川夫人と早苗は隣の部屋に戻り、明智が独りトランプをしながら寝ずの番をすることに。
宝石王・岩瀬庄兵衛(柳生博)に黒蜥蜴から「あなたの一番大切なものを頂戴にあがる」という予告状が届く。相談を受けた明智(天知茂)と波越警部(荒井注)が岩瀬と娘の早苗(加山麗子)とホテルロビーで話していると、ドイツ帰りで岩瀬の顧客の緑川夫人(小川真由美)がやって来る。岩瀬は、明智たちが大切なものとは何か尋ねると、「エジプトの星」というダイヤを見せる。黒蜥蜴が指定した夜、明智は浪越警部と共に黒蜥蜴の出現を待ち受けるが、警部はシャワーを浴びると睡魔が襲ってきて岩瀬と共にベッドで寝てしまう。緑川夫人と早苗は隣の部屋に戻り、明智が独りトランプをしながら寝ずの番をすることに。 そこへ再び緑川夫人が現れ、明智に、明智と黒蜥蜴どちらが勝つかという賭けを持ち掛け、明智は探偵稼業を賭けることに。緑川夫人は自分の全財産、身も心も賭けると言う。緑川夫人が隣の部屋で物音がすると言い、明智と早苗の部屋を見に行くが、早苗はベッドに寝ているらしく、夫人の問いかけにも「眠い」と応える。安心した二人は、部屋に戻る。犯行予告の深夜12時までポーカーをする明智と緑川夫人。しかし、何事もなく12時を過ぎる。緑川夫人は、明智たちが黒蜥蜴の目的の品をとり間違えてはいないかと言い、岩瀬に宝石よりもっと大切なものはないかと尋ね、それが早苗であることがわかると一同は慌てて部屋を飛び出す。早苗の部屋に行くと、彼女は先ほど同じくベッドで寝ていたが、明智がその髪を掴むと、マネキンの頭部だった。波越警部はホテルをチェックアウトした不審者
そこへ再び緑川夫人が現れ、明智に、明智と黒蜥蜴どちらが勝つかという賭けを持ち掛け、明智は探偵稼業を賭けることに。緑川夫人は自分の全財産、身も心も賭けると言う。緑川夫人が隣の部屋で物音がすると言い、明智と早苗の部屋を見に行くが、早苗はベッドに寝ているらしく、夫人の問いかけにも「眠い」と応える。安心した二人は、部屋に戻る。犯行予告の深夜12時までポーカーをする明智と緑川夫人。しかし、何事もなく12時を過ぎる。緑川夫人は、明智たちが黒蜥蜴の目的の品をとり間違えてはいないかと言い、岩瀬に宝石よりもっと大切なものはないかと尋ね、それが早苗であることがわかると一同は慌てて部屋を飛び出す。早苗の部屋に行くと、彼女は先ほど同じくベッドで寝ていたが、明智がその髪を掴むと、マネキンの頭部だった。波越警部はホテルをチェックアウトした不審者 を洗い、山川教授が量子力学の論文を書いていて大量の原稿を部屋に持ち込み、大きなトランクを下げてホテルを出たという情報を得る。部屋には大量の原稿が残されていて、山川教授に扮していた雨宮(清水章吾)という男が、トランクに早苗を詰めてホテルを出たのだ。宿泊者名簿を見た時から雨宮に目を付けていた明智は、助手の文代(五十嵐めぐみ)と小林(柏原貴)に雨宮の車をつけさせていることを話し、再び緑川夫人とポーカーをする。文代と小林は雨宮からトランクを奪い、中を開けると下着姿で猿轡で手足を縛られた早苗が出てくる。明智はこの報告を受け波越たちに伝えると、早苗が救出されたが雨宮が逃げたことで、緑川夫人は「どうやらこの勝負引き分けのようでしたね」と言うが、明智は「この勝負は僕が勝ちました」と言う―。
を洗い、山川教授が量子力学の論文を書いていて大量の原稿を部屋に持ち込み、大きなトランクを下げてホテルを出たという情報を得る。部屋には大量の原稿が残されていて、山川教授に扮していた雨宮(清水章吾)という男が、トランクに早苗を詰めてホテルを出たのだ。宿泊者名簿を見た時から雨宮に目を付けていた明智は、助手の文代(五十嵐めぐみ)と小林(柏原貴)に雨宮の車をつけさせていることを話し、再び緑川夫人とポーカーをする。文代と小林は雨宮からトランクを奪い、中を開けると下着姿で猿轡で手足を縛られた早苗が出てくる。明智はこの報告を受け波越たちに伝えると、早苗が救出されたが雨宮が逃げたことで、緑川夫人は「どうやらこの勝負引き分けのようでしたね」と言うが、明智は「この勝負は僕が勝ちました」と言う―。
 原作では、緑川夫人こそが「黒蜥蜴」であることを、最初の3分の1くらいのところで指摘してしまいますが、ドラマも(この回からシリーズがレギュラーで2時間枠となった)、正味90分くらいの内の最初の30分で、同じく明智が当人の目の前で指摘します。でも、その前に緑川夫人が明智をさんざん挑発しているので、明智もかなり何となく気がついていた印象がドラマではありました。前半部の明智と緑川夫人の心理合戦がなかなか面白く、ポーカー
原作では、緑川夫人こそが「黒蜥蜴」であることを、最初の3分の1くらいのところで指摘してしまいますが、ドラマも(この回からシリーズがレギュラーで2時間枠となった)、正味90分くらいの内の最初の30分で、同じく明智が当人の目の前で指摘します。でも、その前に緑川夫人が明智をさんざん挑発しているので、明智もかなり何となく気がついていた印象がドラマではありました。前半部の明智と緑川夫人の心理合戦がなかなか面白く、ポーカー をやる明智と緑川夫人とで、最初のうちは緑川夫人が圧勝し、やがてそれに呼応するように早苗が誘拐されたことが明らかになりますが、その後、実は、山川教授に扮してホテルを抜け出た雨宮に、明智の助手・文代と小林の尾行がついていることを明智から知らされるや、今度は緑川夫人のツキが落ちたかのように明智に負け続けます。原作でも二人はトランプゲームをしますが、勝負の形勢推移はドラマのオリジナルであり、上手いと思いました。
をやる明智と緑川夫人とで、最初のうちは緑川夫人が圧勝し、やがてそれに呼応するように早苗が誘拐されたことが明らかになりますが、その後、実は、山川教授に扮してホテルを抜け出た雨宮に、明智の助手・文代と小林の尾行がついていることを明智から知らされるや、今度は緑川夫人のツキが落ちたかのように明智に負け続けます。原作でも二人はトランプゲームをしますが、勝負の形勢推移はドラマのオリジナルであり、上手いと思いました。
 因みに、黒蜥蜴による最初の誘拐の試みの際に、早苗が「眠い」と言ったのは実は緑川夫人の腹話術で、原作通り(原作の方がいっぱい喋っている)。二度目の誘拐の試みの際に、長椅子を用いるのも原作通りですが、緑川夫人が顔パックしたり風呂に入ったりして早苗になりすますのはドラマのオリジナルです(「浴室要員」が小川真由美とは!)。
因みに、黒蜥蜴による最初の誘拐の試みの際に、早苗が「眠い」と言ったのは実は緑川夫人の腹話術で、原作通り(原作の方がいっぱい喋っている)。二度目の誘拐の試みの際に、長椅子を用いるのも原作通りですが、緑川夫人が顔パックしたり風呂に入ったりして早苗になりすますのはドラマのオリジナルです(「浴室要員」が小川真由美とは!)。 小川真由美の演技も良かったかと思います(この人、岩下志麻と「
小川真由美の演技も良かったかと思います(この人、岩下志麻と「 映画化作品の前二作は何れも三島由紀夫の戯曲を原作とした「三島戯曲の映画化」であり(深作欣二版の方は三島由紀夫自身が特別出演していることでも知られる)、ドラマの方が原作に近いかと思います。ただし、三島は戯曲化するにあたり、「女賊黒蜥蜴と明智小五郎との恋愛を前景に押し出して、劇の主軸」にしたとのことですが、ドラマ版もその影響を受けている面があるように思いました。ただし、「美女」が明智の腕に抱かれて死ぬというのは、このシリーズの定石でもあります。
映画化作品の前二作は何れも三島由紀夫の戯曲を原作とした「三島戯曲の映画化」であり(深作欣二版の方は三島由紀夫自身が特別出演していることでも知られる)、ドラマの方が原作に近いかと思います。ただし、三島は戯曲化するにあたり、「女賊黒蜥蜴と明智小五郎との恋愛を前景に押し出して、劇の主軸」にしたとのことですが、ドラマ版もその影響を受けている面があるように思いました。ただし、「美女」が明智の腕に抱かれて死ぬというのは、このシリーズの定石でもあります。
 早苗役の加山麗子の入浴シーンもありますが、躰だけの部分は吹き替えのように見えます。トランクから助け出される場面も、実は原作では全裸なのですが、ドラマでは下着姿です。でも、後半、黒蜥蜴に囚われてからは、吹き替え無しでほとんど全裸に近かったです(原作では完全に全裸なのだが、まあ、頑張っている方だろう)。
早苗役の加山麗子の入浴シーンもありますが、躰だけの部分は吹き替えのように見えます。トランクから助け出される場面も、実は原作では全裸なのですが、ドラマでは下着姿です。でも、後半、黒蜥蜴に囚われてからは、吹き替え無しでほとんど全裸に近かったです(原作では完全に全裸なのだが、まあ、頑張っている方だろう)。


 清水章吾が、山川教授に扮した黒蜥蜴の部下・雨宮(黒蜥蜴の指示で"獲物"を剥製にするために水槽に沈める係だが、逆に明智に早苗の替わりに水槽に沈められてしまう。この回の明智は結構シビア)を演じていますが、かつてチワワ犬とともに出演した「アイフル」のCMで一躍ブレイクしましたが、昨年['19年]末、仕事も家族関係もうまくいかず自殺未遂したとの報道があり心配です(この人、2010年に脳梗塞となり保険会社のCMや
清水章吾が、山川教授に扮した黒蜥蜴の部下・雨宮(黒蜥蜴の指示で"獲物"を剥製にするために水槽に沈める係だが、逆に明智に早苗の替わりに水槽に沈められてしまう。この回の明智は結構シビア)を演じていますが、かつてチワワ犬とともに出演した「アイフル」のCMで一躍ブレイクしましたが、昨年['19年]末、仕事も家族関係もうまくいかず自殺未遂したとの報道があり心配です(この人、2010年に脳梗塞となり保険会社のCMや 舞台を降板するなどした際も、ストレスでうつ状態となり1度目の自殺未遂している)。
舞台を降板するなどした際も、ストレスでうつ状態となり1度目の自殺未遂している)。

 第6話、第7話で本名の「詫摩繁春」名義で出演していた宅麻伸が、ここでは黒蜥蜴に囚われ、水槽に沈められて、はく製にされてしまう役でした。当時、宅麻伸は、キャバレーのボーイをしながらデビューを目指していた時期で、キャバレーの店主が天知茂に紹介して天知の事務所に預かりとなっていたそうです(「明智事務所」ならぬ「天知事務所」か)。
第6話、第7話で本名の「詫摩繁春」名義で出演していた宅麻伸が、ここでは黒蜥蜴に囚われ、水槽に沈められて、はく製にされてしまう役でした。当時、宅麻伸は、キャバレーのボーイをしながらデビューを目指していた時期で、キャバレーの店主が天知茂に紹介して天知の事務所に預かりとなっていたそうです(「明智事務所」ならぬ「天知事務所」か)。



 「江戸川乱歩 美女シリーズ(第8話)/悪魔のような美女」●制作年:1979年●監督:井上梅次●プロデューサー:佐々木孟●脚本:ジェームス三木●音楽:鏑木創●原作:江戸川乱歩「黒蜥蜴」●時間:90 分●出演:天知茂/五十嵐めぐみ/柏原貴/荒井注/小川真由美/加山麗子/清水正吾/大前均/北町嘉郎/託磨繁春(宅麻伸)/羽生昭彦/水木涼子/工藤和彦/加島潤/岡本忠幸/鈴木謙一/市東昭秀/篠原靖夫/沖秀一/加藤真琴/マリー・オーマレイ/ウィリー・ドーシイ●放送局:テレビ朝日●放送日:1979/04/14(評価:★★★★)
「江戸川乱歩 美女シリーズ(第8話)/悪魔のような美女」●制作年:1979年●監督:井上梅次●プロデューサー:佐々木孟●脚本:ジェームス三木●音楽:鏑木創●原作:江戸川乱歩「黒蜥蜴」●時間:90 分●出演:天知茂/五十嵐めぐみ/柏原貴/荒井注/小川真由美/加山麗子/清水正吾/大前均/北町嘉郎/託磨繁春(宅麻伸)/羽生昭彦/水木涼子/工藤和彦/加島潤/岡本忠幸/鈴木謙一/市東昭秀/篠原靖夫/沖秀一/加藤真琴/マリー・オーマレイ/ウィリー・ドーシイ●放送局:テレビ朝日●放送日:1979/04/14(評価:★★★★)


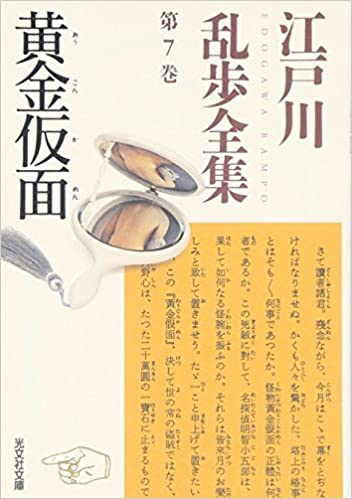
 宝石窃盗犯・西岡三郎(睦五郎)が脱獄し、逃走中に仲間(沖秀一)を射殺して行方をくらます。撃たれた男の最期の言葉から、西岡は白髪の鬘を被って変装しているらしい。明智も事務所で文代(五十嵐めぐみ)、小林(柏原貴)とこのニュースを見ていた。西岡は10年前に盗んだ宝石の隠し場所である、富豪・大牟田の別荘にある墓所に行くが、盗品は全て無くなっていた。西岡の行方を追う波越警部(荒井注)に、大牟田家に痴漢が入
宝石窃盗犯・西岡三郎(睦五郎)が脱獄し、逃走中に仲間(沖秀一)を射殺して行方をくらます。撃たれた男の最期の言葉から、西岡は白髪の鬘を被って変装しているらしい。明智も事務所で文代(五十嵐めぐみ)、小林(柏原貴)とこのニュースを見ていた。西岡は10年前に盗んだ宝石の隠し場所である、富豪・大牟田の別荘にある墓所に行くが、盗品は全て無くなっていた。西岡の行方を追う波越警部(荒井注)に、大牟田家に痴漢が入 ったという通報が入る。痴漢は白髪にサングラスの男とのことで、一同は大牟田家へ向かう。大牟田邸では、未亡人のルリ子(金沢碧)が、妹の豊子(田島はるか)と画家の川村(小坂一也)と3人で住んでいた。ルリ子は夫の財産が思ったより少なかったため、近くの別荘を売却するという。別荘には
ったという通報が入る。痴漢は白髪にサングラスの男とのことで、一同は大牟田家へ向かう。大牟田邸では、未亡人のルリ子(金沢碧)が、妹の豊子(田島はるか)と画家の川村(小坂一也)と3人で住んでいた。ルリ子は夫の財産が思ったより少なかったため、近くの別荘を売却するという。別荘には 川村が住んでいたが、ルリ子と川村は結婚することとなり一緒に住み始めたのだった。ルリ子は前夜、入浴中に白髪とサングラスの男に覗かれたという。すると、別荘の買い手と
川村が住んでいたが、ルリ子と川村は結婚することとなり一緒に住み始めたのだった。ルリ子は前夜、入浴中に白髪とサングラスの男に覗かれたという。すると、別荘の買い手と して現れた、顔にアザがある白髪にサングラスの里見(田村高廣)という
して現れた、顔にアザがある白髪にサングラスの里見(田村高廣)という 人物が、それは自分だと告白する。別荘の持ち主の家を捜しているうちに近くまで来て、庭から浴室を覗いてしまったのだという。西岡に関する情報もなく一同は大牟田邸を去る。里見が夫に似ているのを気味悪がるルリ子たち。実は大牟田(田村高廣、二役)はルリ子に唆された川村が断崖から突き落として殺害し、妹の豊子もこのことを知っていて、さらに、主治医の住田洋子(奈美悦子)を使って他殺と判らないように死亡診断書を書かせていた。里見は近くのホテル
人物が、それは自分だと告白する。別荘の持ち主の家を捜しているうちに近くまで来て、庭から浴室を覗いてしまったのだという。西岡に関する情報もなく一同は大牟田邸を去る。里見が夫に似ているのを気味悪がるルリ子たち。実は大牟田(田村高廣、二役)はルリ子に唆された川村が断崖から突き落として殺害し、妹の豊子もこのことを知っていて、さらに、主治医の住田洋子(奈美悦子)を使って他殺と判らないように死亡診断書を書かせていた。里見は近くのホテル
 に宿泊していた。明智が大牟田家の墓へ来ると、散歩中の里見と会い、彼はルリ子を気に入って、彼女にプロポーズをするという。里見から宝石をプレゼントされ、欲深いルリ子の心は動く。ただ、里見のタバコを取り出す際の仕草やペンダントを振り回す癖が大牟田に似ているのが、夫の殺害に関与していたルリ子は気味が悪い。それでも、金に余裕がある里見へと関心がいくのだった―。
に宿泊していた。明智が大牟田家の墓へ来ると、散歩中の里見と会い、彼はルリ子を気に入って、彼女にプロポーズをするという。里見から宝石をプレゼントされ、欲深いルリ子の心は動く。ただ、里見のタバコを取り出す際の仕草やペンダントを振り回す癖が大牟田に似ているのが、夫の殺害に関与していたルリ子は気味が悪い。それでも、金に余裕がある里見へと関心がいくのだった―。 改変のポイントは、窃盗犯・西岡(原作では「紅髑髏」ことシナ海の海賊王・朱凌谿)を里見こと大牟田が利用して、犯行時のアリバイ工作をすることで(最初は西岡の方が利用していたのだが、途中で立場が逆転する)、原作にはこうした話はありません(ドラマでは、犯人が誰か(WHO)ということより、犯人がどうやったか(HOW)がポイントになっている)。原作は、瑠璃子(ルリ子)、川村、里見の3人以外に主だった登場人物はいないシンプルな作りで、プロットよりも「怪奇・復讐譚」であることにウェイトが置かれていますが、ドラマでは、原作には無いルリ子の妹や主治医まで共謀者として登場させ、何れもが大牟田の復讐対象となっています。
改変のポイントは、窃盗犯・西岡(原作では「紅髑髏」ことシナ海の海賊王・朱凌谿)を里見こと大牟田が利用して、犯行時のアリバイ工作をすることで(最初は西岡の方が利用していたのだが、途中で立場が逆転する)、原作にはこうした話はありません(ドラマでは、犯人が誰か(WHO)ということより、犯人がどうやったか(HOW)がポイントになっている)。原作は、瑠璃子(ルリ子)、川村、里見の3人以外に主だった登場人物はいないシンプルな作りで、プロットよりも「怪奇・復讐譚」であることにウェイトが置かれていますが、ドラマでは、原作には無いルリ子の妹や主治医まで共謀者として登場させ、何れもが大牟田の復讐対象となっています。 恒例の「浴室」要員は、風呂場で覗き被害に遭う「宝石の美女」ことルリ子を演じた金沢碧(1953年生まれ)で、本人と吹き替えを巧みに織り交ぜて(笑)、自然な感じで撮られていました。この「江戸川乱歩の美女シリーズ」は、1977年から1994年までテレビ朝日系「土曜ワイド劇場」で17年間放送されたテレビドラマシリーズですが、金沢碧はこの「土曜ワイド劇場」に1979年から2012年までの間、全部で27回出演していて、その中でこの「宝石の美女」が初登場でした。この「美女シリーズ」でも第15話「鏡地獄の美女」('81年)で再登場しますが、"天知茂版"の「美女シリーズ」で「美女」として2度出演したは叶和貴子(第17話「天国と地獄の美女」、第21話「白い素肌の美女」)と金沢碧だけで、この回が好評であったことを示すものかもしれません。
恒例の「浴室」要員は、風呂場で覗き被害に遭う「宝石の美女」ことルリ子を演じた金沢碧(1953年生まれ)で、本人と吹き替えを巧みに織り交ぜて(笑)、自然な感じで撮られていました。この「江戸川乱歩の美女シリーズ」は、1977年から1994年までテレビ朝日系「土曜ワイド劇場」で17年間放送されたテレビドラマシリーズですが、金沢碧はこの「土曜ワイド劇場」に1979年から2012年までの間、全部で27回出演していて、その中でこの「宝石の美女」が初登場でした。この「美女シリーズ」でも第15話「鏡地獄の美女」('81年)で再登場しますが、"天知茂版"の「美女シリーズ」で「美女」として2度出演したは叶和貴子(第17話「天国と地獄の美女」、第21話「白い素肌の美女」)と金沢碧だけで、この回が好評であったことを示すものかもしれません。
 ドラマで付け加えられたキャラクターのうち、田島はるか(1957年生まれ)演じる妹の豊子は、裸にされて逆さ吊りされた遺体で発見されますが、田島はるかはもともとロマンポルノの女優なので、これは吹き替え無しでしょうか(1976年の日活時代から1978年の「にっかつ」初年まで活動)。奈美悦子(1950年生まれ)が演じる死亡診断書において私利のために共謀する主治医の住田洋子も、半裸の状態で遺体で発見されますが、これは"全裸"ではなく"半裸"なので、岩場に逆さに
ドラマで付け加えられたキャラクターのうち、田島はるか(1957年生まれ)演じる妹の豊子は、裸にされて逆さ吊りされた遺体で発見されますが、田島はるかはもともとロマンポルノの女優なので、これは吹き替え無しでしょうか(1976年の日活時代から1978年の「にっかつ」初年まで活動)。奈美悦子(1950年生まれ)が演じる死亡診断書において私利のために共謀する主治医の住田洋子も、半裸の状態で遺体で発見されますが、これは"全裸"ではなく"半裸"なので、岩場に逆さに
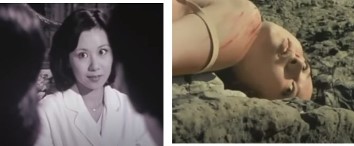 突っ立った脚はともかく、あとは奈美悦子本人でしょう(何だか、こんなことばかりにこだわっている(笑))。奈美悦子は第13話「
突っ立った脚はともかく、あとは奈美悦子本人でしょう(何だか、こんなことばかりにこだわっている(笑))。奈美悦子は第13話「 先にも述べた通り、原作が犯人の手記による叙述スタイルであるところに無理やり明智を絡ませているため、プロセスにおいて明智が事件に関与する部分は少な目で、文代や小林に至っては殆ど事務所内にいるだけという感じでした。そうした
先にも述べた通り、原作が犯人の手記による叙述スタイルであるところに無理やり明智を絡ませているため、プロセスにおいて明智が事件に関与する部分は少な目で、文代や小林に至っては殆ど事務所内にいるだけという感じでした。そうした 物足りない面もありますが、探偵ものではない原作を大幅アレンジしているわりには、原作のテイストはよく残しているように思いました(田村高廣の演技が光り、天知茂と競演する形になっている)。
物足りない面もありますが、探偵ものではない原作を大幅アレンジしているわりには、原作のテイストはよく残しているように思いました(田村高廣の演技が光り、天知茂と競演する形になっている)。 を知った里見こと大牟田は、別の嬰児の屍体を入手し、川村や瑠璃子の恐怖を増すための演出に使ったのですが、この話はドラマでは割愛されています(気持ち悪すぎる?)。そして、語り手である人物は、今、十何年になる獄中生活にあるというオチです(終身刑に服していることを示唆)。原作で、閉じ込められたはずの瑠璃子が犯人の前に(おそらく幻影として)現れた時、彼女は、手に宝石をつかんで、それをサラサラと赤ん坊の上に砂遊びのようにこぼす仕草をし、この部分が原作の恐怖の最後のクライマックスになっていますが、ドラマでも、赤ん坊は出てこないものの、エンディングでその部分は活かしています。この辺りは、まずまず工夫されていたと思います。
を知った里見こと大牟田は、別の嬰児の屍体を入手し、川村や瑠璃子の恐怖を増すための演出に使ったのですが、この話はドラマでは割愛されています(気持ち悪すぎる?)。そして、語り手である人物は、今、十何年になる獄中生活にあるというオチです(終身刑に服していることを示唆)。原作で、閉じ込められたはずの瑠璃子が犯人の前に(おそらく幻影として)現れた時、彼女は、手に宝石をつかんで、それをサラサラと赤ん坊の上に砂遊びのようにこぼす仕草をし、この部分が原作の恐怖の最後のクライマックスになっていますが、ドラマでも、赤ん坊は出てこないものの、エンディングでその部分は活かしています。この辺りは、まずまず工夫されていたと思います。 江戸川乱歩には、アラン・ポーの「早すぎた埋葬」をモチーフにした作品が幾つかあり、この作品も、原作にも出てきたし、ドラマの方も明智がペーパーバック(英語版)を手にしています。しかし、この作品に関しては、埋葬された人物が墓所で甦るというのは、黒岩涙香版も、その元となったマリー・コレリの『ヴェンデッタ』も同じです。ウィキペディアによれば、江戸川乱歩版の原作・涙香版との主な相違点は、原作・涙香版ではあくまで妻と友人がしていたのは浮気のみで、主人公の死因は不測の事態であったのに対し、乱歩版は明らかの殺意が友人にある事。また、復讐方法も原作・涙香版では友人は衆人環視の拳銃による決闘で堂々と行っているのに対し、乱歩版は別荘におびき寄せてのからくり仕掛けによるじわじわした殺し方になっているなどより凄絶になっている点とのことです。また、法を無視しても復讐を肯定するか、それを犯罪者とするかは大きな違いで、乱歩版では終身刑になっている主人公が、原作・涙香版では復讐を果たした英雄のようになっているのは、マリー・コレリのオリジナルが、『モンテ・クリスト伯』や『巌窟王』など系譜の物語であることによるのでしょう。ドラマ版で明智などに出てこられると、復讐すら完遂できないというのは、まあ仕方がないのかもしれません。
江戸川乱歩には、アラン・ポーの「早すぎた埋葬」をモチーフにした作品が幾つかあり、この作品も、原作にも出てきたし、ドラマの方も明智がペーパーバック(英語版)を手にしています。しかし、この作品に関しては、埋葬された人物が墓所で甦るというのは、黒岩涙香版も、その元となったマリー・コレリの『ヴェンデッタ』も同じです。ウィキペディアによれば、江戸川乱歩版の原作・涙香版との主な相違点は、原作・涙香版ではあくまで妻と友人がしていたのは浮気のみで、主人公の死因は不測の事態であったのに対し、乱歩版は明らかの殺意が友人にある事。また、復讐方法も原作・涙香版では友人は衆人環視の拳銃による決闘で堂々と行っているのに対し、乱歩版は別荘におびき寄せてのからくり仕掛けによるじわじわした殺し方になっているなどより凄絶になっている点とのことです。また、法を無視しても復讐を肯定するか、それを犯罪者とするかは大きな違いで、乱歩版では終身刑になっている主人公が、原作・涙香版では復讐を果たした英雄のようになっているのは、マリー・コレリのオリジナルが、『モンテ・クリスト伯』や『巌窟王』など系譜の物語であることによるのでしょう。ドラマ版で明智などに出てこられると、復讐すら完遂できないというのは、まあ仕方がないのかもしれません。



 冒頭「皆さんはもう、『黄金仮面』のことはよくご存じだと思いますが」と語る明智。都内で黄金の仮面を被った
冒頭「皆さんはもう、『黄金仮面』のことはよくご存じだと思いますが」と語る明智。都内で黄金の仮面を被った 怪人の姿が目撃され、国宝級の古美術品が盗まれる事件が頻発していた。古美術品の蒐集家である大島喜三郎(松下達夫)に黄金仮面から手紙が届き、彼の長女・絹枝(結城美栄子)の恋人で、フランス商社の東京支店長ロベール・サトー(伊吹吾郎)の訪問予定日に、大島所有の古美術品を奪うと予告してきた。フランス大使館の職員ジョルジュ・ポアン(ジェリー伊藤)がロベールの友人であり、大島のコレクションを見たいということから大島が二人を招いたところを狙われたのだ。不安を抱いた秘書の三好(藤村有弘)が、波越警部(荒井注)に相談、明智に捜査協力を依頼することに。明智
怪人の姿が目撃され、国宝級の古美術品が盗まれる事件が頻発していた。古美術品の蒐集家である大島喜三郎(松下達夫)に黄金仮面から手紙が届き、彼の長女・絹枝(結城美栄子)の恋人で、フランス商社の東京支店長ロベール・サトー(伊吹吾郎)の訪問予定日に、大島所有の古美術品を奪うと予告してきた。フランス大使館の職員ジョルジュ・ポアン(ジェリー伊藤)がロベールの友人であり、大島のコレクションを見たいということから大島が二人を招いたところを狙われたのだ。不安を抱いた秘書の三好(藤村有弘)が、波越警部(荒井注)に相談、明智に捜査協力を依頼することに。明智 と波越警部は箱根・芦ノ湖畔の大島美術館に行き、黄金仮面との対決準備をする。美術館にやってきたロベールとジュルジュも美術品を見て回るが、ジョルジュは次女の不二子(由美かおる)に興味を抱く。もちろん美術品にも関心を示し、特にインド・ジャイナ女神像に関心を注ぐ。さらに自宅に置かれている大島家秘蔵の虚空蔵菩薩にも関心を抱いたため、自宅に招待することを大島が約束をする。芦ノ湖での美術品紹介は無事終ったが、後日、茶席を抜け出してきた大島家の三女・よし子(岡麻美)が入浴中に何者かに刺され、「黄金仮面」と言って息絶える。明智は今までの黄金仮面の犯行から、その犯行ではないと言う。事務員・小雪(野平ゆき)の通報で、秘書の三好と事務員の千秋が事務所でガスで眠らされているのが発見されるが、明智は犯人は小雪だと断言。千秋に言い寄るよし子への嫉妬心からの犯行だった。美術館の一室に追い詰められた小雪は自害しようとするが、突然、鎧が動き出しナイフを持つ手を止める―。
と波越警部は箱根・芦ノ湖畔の大島美術館に行き、黄金仮面との対決準備をする。美術館にやってきたロベールとジュルジュも美術品を見て回るが、ジョルジュは次女の不二子(由美かおる)に興味を抱く。もちろん美術品にも関心を示し、特にインド・ジャイナ女神像に関心を注ぐ。さらに自宅に置かれている大島家秘蔵の虚空蔵菩薩にも関心を抱いたため、自宅に招待することを大島が約束をする。芦ノ湖での美術品紹介は無事終ったが、後日、茶席を抜け出してきた大島家の三女・よし子(岡麻美)が入浴中に何者かに刺され、「黄金仮面」と言って息絶える。明智は今までの黄金仮面の犯行から、その犯行ではないと言う。事務員・小雪(野平ゆき)の通報で、秘書の三好と事務員の千秋が事務所でガスで眠らされているのが発見されるが、明智は犯人は小雪だと断言。千秋に言い寄るよし子への嫉妬心からの犯行だった。美術館の一室に追い詰められた小雪は自害しようとするが、突然、鎧が動き出しナイフを持つ手を止める―。
 年末特別版としてこれまでの枠を30分延長して初めて2時間枠で放映されたこのドラマ化作品(小林君が初登場する)も、原作の傾向に即して、アクション映画風のシーンが多くなっていて、
年末特別版としてこれまでの枠を30分延長して初めて2時間枠で放映されたこのドラマ化作品(小林君が初登場する)も、原作の傾向に即して、アクション映画風のシーンが多くなっていて、 モーターボートが出てくるところなどもしっかり映像化していました(第1話「氷柱の美女」の原作『
モーターボートが出てくるところなどもしっかり映像化していました(第1話「氷柱の美女」の原作『 「浴室」要員は、三女・美子(岡麻美)で(浴室で刺殺されるのは原作通り)、かなり大胆に見せます。さらには、事務員・小雪(野平ゆき)もライフルで撃たれて明智がウェットスーツの胸をはだけ...(これは原作に無い。原作では刺殺)。ヒロインである次女の不二子(由美かおる)は「水戸黄門」ではないですが、背中だ
「浴室」要員は、三女・美子(岡麻美)で(浴室で刺殺されるのは原作通り)、かなり大胆に見せます。さらには、事務員・小雪(野平ゆき)もライフルで撃たれて明智がウェットスーツの胸をはだけ...(これは原作に無い。原作では刺殺)。ヒロインである次女の不二子(由美かおる)は「水戸黄門」ではないですが、背中だ け見せるシャワーシーンがあるくらいなので、その代わりにみたいな感じで、それ以上の部分は他の女優が担うという、第4話「
け見せるシャワーシーンがあるくらいなので、その代わりにみたいな感じで、それ以上の部分は他の女優が担うという、第4話「 いたそうな)。因みに、由美かおるの役名の「不二子」ですが、原作でも「不二子」であり、「ルパン三世」の峰不二子はこれに由来するのかと思いましたが、モンキー・パンチ(1937-2019/81歳没)自身は、たまたまカレンダーの富士山を見て着想したとかで、「黄金仮面」との関係については否定しています。セシルとかいう役で出ている山本リンダは、どういう役回りなのかよく分かりませんでした(笑)。
いたそうな)。因みに、由美かおるの役名の「不二子」ですが、原作でも「不二子」であり、「ルパン三世」の峰不二子はこれに由来するのかと思いましたが、モンキー・パンチ(1937-2019/81歳没)自身は、たまたまカレンダーの富士山を見て着想したとかで、「黄金仮面」との関係については否定しています。セシルとかいう役で出ている山本リンダは、どういう役回りなのかよく分かりませんでした(笑)。

 ジョルジュ役のジェリー伊藤(1927-2007/79歳没)は、映画「
ジョルジュ役のジェリー伊藤(1927-2007/79歳没)は、映画「
 に書かれた曲でした(トワ・エ・モワ、越路吹雪が'70年の同じ日にカバー曲のシングルを出した。個人的には、グラシェラ・スサーナ版が印象深い)。ロベール役の伊吹吾郎(由美かおるとは「水戸黄門」コンビ)は、第3話「死刑台の美女」にも出ていましたが、この後、第11話「桜の国の美女」では同じくロベール役で登場します。最初は日本語をぎこちなさげに喋っていましたが、途中からフツーの日本人になっていました。船に乗ると、何だか漁師が似合いそう(笑)。
に書かれた曲でした(トワ・エ・モワ、越路吹雪が'70年の同じ日にカバー曲のシングルを出した。個人的には、グラシェラ・スサーナ版が印象深い)。ロベール役の伊吹吾郎(由美かおるとは「水戸黄門」コンビ)は、第3話「死刑台の美女」にも出ていましたが、この後、第11話「桜の国の美女」では同じくロベール役で登場します。最初は日本語をぎこちなさげに喋っていましたが、途中からフツーの日本人になっていました。船に乗ると、何だか漁師が似合いそう(笑)。
 乱歩の原作『黄金仮面』もこのドラマ版も、結局は明智がルパンに勝っているわけですが、ルパンは追い詰められながらも捕まることはなく、一応は両者イーブンの形にしているところが、『ルパン対ホームズ』とやや似ているように思います。原作では、ルパンは不二子さえも連れていくことが出来ず、何も持たずに日本を離れることになりますが、ドラマではそこまで露骨に差をつけてはいません(続編への伏線か)。
乱歩の原作『黄金仮面』もこのドラマ版も、結局は明智がルパンに勝っているわけですが、ルパンは追い詰められながらも捕まることはなく、一応は両者イーブンの形にしているところが、『ルパン対ホームズ』とやや似ているように思います。原作では、ルパンは不二子さえも連れていくことが出来ず、何も持たずに日本を離れることになりますが、ドラマではそこまで露骨に差をつけてはいません(続編への伏線か)。 ドラマにおけるルパンは殺人を犯さないという主義であるはずなのに、部下は小雪を殺害しているし(これは原作も同じだが)、また、部下たちは明智にもピストルをがんがん放っています。さらには自身も、自分が手先として使ったウルトラセブン、あっ、違った!森次晃嗣が演じる浦瀬を、盗品を横流ししたという理由のみで自分を裏切ったとして殺しています。
ドラマにおけるルパンは殺人を犯さないという主義であるはずなのに、部下は小雪を殺害しているし(これは原作も同じだが)、また、部下たちは明智にもピストルをがんがん放っています。さらには自身も、自分が手先として使ったウルトラセブン、あっ、違った!森次晃嗣が演じる浦瀬を、盗品を横流ししたという理由のみで自分を裏切ったとして殺しています。 ラストの犯人改変は、原作を読んだ視聴者の予想を裏切るどんでん返しなのでしょう。それはいいとして、トータルでみると、年末2時間枠で派手なアクションもあったものの、結構突っ込みどころが多い回だったように思います。
ラストの犯人改変は、原作を読んだ視聴者の予想を裏切るどんでん返しなのでしょう。それはいいとして、トータルでみると、年末2時間枠で派手なアクションもあったものの、結構突っ込みどころが多い回だったように思います。




![[Prime Video]氷柱の美女.jpg](http://hurec.bz/book-movie/%EF%BC%BBPrime%20Video%EF%BC%BD%E6%B0%B7%E6%9F%B1%E3%81%AE%E7%BE%8E%E5%A5%B3.jpg)

 明智が静養中の箱根湖畔で釣りをしていると、そこに美しい女性が現れる。さらに、帰り際にも彼女と出会い、霧で道に迷ったというが、そこへ青年が駆けつける。明智は事務所のメンバーと湖畔のホテルに滞在していて、その女性、資産家の未亡人・畑柳倭文子(はたやなぎ しずこ)(三ツ矢歌子)は、ホテルの近くの別荘に一人息子の茂といて、湖畔ホテルへもよく来ていたのだ。その日、明智が文代(五十嵐めぐみ)、小林(大和田獏)とホテルのバーにいると、二人の男を
明智が静養中の箱根湖畔で釣りをしていると、そこに美しい女性が現れる。さらに、帰り際にも彼女と出会い、霧で道に迷ったというが、そこへ青年が駆けつける。明智は事務所のメンバーと湖畔のホテルに滞在していて、その女性、資産家の未亡人・畑柳倭文子(はたやなぎ しずこ)(三ツ矢歌子)は、ホテルの近くの別荘に一人息子の茂といて、湖畔ホテルへもよく来ていたのだ。その日、明智が文代(五十嵐めぐみ)、小林(大和田獏)とホテルのバーにいると、二人の男を 携えた倭文子がいた。一人は画家の岡田道彦(菅貫太郎)で、もう一人は、今日倭文子を探しにきたグラフィックデザイナーの青年・三谷房夫(松橋登)だった。やがて、宿の一室で、岡田と三谷の二人の男による、倭文子の愛を得るため命を賭けた決闘が始まる。テーブルにふたつのワイングラスがあり、岡田は、どちらかに毒が入っているので、三谷にひとつ選んで飲み干すように要求する。結果、三谷は賭けに勝利し、岡田はその決闘で死こそ免れたものの、劇薬を顔に浴びて醜い姿となり、倭文子の前で屈辱を味わって姿を消す。やがて、岡田と思しき顔が潰れた水死体が見つかるが、それ以降、唇のない怪人が倭文子の周囲に出没する。恒川警部(稲垣昭三)は明智に事件解決への協力を依頼をするが、唇のない怪人は今度は明智を挑発するかのような行動に出る―。
携えた倭文子がいた。一人は画家の岡田道彦(菅貫太郎)で、もう一人は、今日倭文子を探しにきたグラフィックデザイナーの青年・三谷房夫(松橋登)だった。やがて、宿の一室で、岡田と三谷の二人の男による、倭文子の愛を得るため命を賭けた決闘が始まる。テーブルにふたつのワイングラスがあり、岡田は、どちらかに毒が入っているので、三谷にひとつ選んで飲み干すように要求する。結果、三谷は賭けに勝利し、岡田はその決闘で死こそ免れたものの、劇薬を顔に浴びて醜い姿となり、倭文子の前で屈辱を味わって姿を消す。やがて、岡田と思しき顔が潰れた水死体が見つかるが、それ以降、唇のない怪人が倭文子の周囲に出没する。恒川警部(稲垣昭三)は明智に事件解決への協力を依頼をするが、唇のない怪人は今度は明智を挑発するかのような行動に出る―。 ドラマでの文代役の五十嵐めぐみは、シリーズ全25作中19作まで文代役を務めることになりますが、この頃はまだ髪が長くて、後のボーイッシュな髪形ではありません。小林を演じた大和田獏は、「少年」と呼ぶには年齢がいきすぎていたせいか、大和田獏はこの第1作のみの登場で終わっています。稲垣昭三(1928-2016/享年88)が演じた恒川警部は、原作通り「恒川警部」なのですが、こちらも第2作から荒井注演じる「浪越警部」に代わります。また、第2話「浴室の美女」まで放映が5カ月も空くことから、ある意味この回はパイロット版的な位置づけだったようにも思われます(「刑事コロンボ」の第1話「殺人処方箋」などは完全にそうだが、パイロット版ってスタイルの初期の完成度を知るうえで興味深いが、観ていて何となく落ち着かない気がする)。
ドラマでの文代役の五十嵐めぐみは、シリーズ全25作中19作まで文代役を務めることになりますが、この頃はまだ髪が長くて、後のボーイッシュな髪形ではありません。小林を演じた大和田獏は、「少年」と呼ぶには年齢がいきすぎていたせいか、大和田獏はこの第1作のみの登場で終わっています。稲垣昭三(1928-2016/享年88)が演じた恒川警部は、原作通り「恒川警部」なのですが、こちらも第2作から荒井注演じる「浪越警部」に代わります。また、第2話「浴室の美女」まで放映が5カ月も空くことから、ある意味この回はパイロット版的な位置づけだったようにも思われます(「刑事コロンボ」の第1話「殺人処方箋」などは完全にそうだが、パイロット版ってスタイルの初期の完成度を知るうえで興味深いが、観ていて何となく落ち着かない気がする)。 原作は、明智の謎解きを待たなくとも何となく犯人が判ってしまうのですが、ドラマの方は、原作以上に早くから犯人がミエミエという印象も。明智も"判っている"風で、あとは、明智がどう犯人を追い詰めるかしか楽しみがないのですが、「氷柱の美女」の脚本におけるクライマックスで、明智が単に普通に犯人の前に現れて謎解きをすることになっていたのが、それでは面白くないと考えた井上梅次(1923-2010/享年86)監督が現場で思いついたのが、犯人が鏡に向って仮面を取ると、その鏡の中に脱いだはずの吸血鬼の仮面が映り、びっくりして振向くと、もう一人の吸血鬼がゆっくり仮面を取って明智の顔が現れるという演出だったそうです。以降、明智がラスㇳに変装して犯人の前に現れ、仮面をはがした上で謎解きをするというのがシリーズの定番になったとのことです。
原作は、明智の謎解きを待たなくとも何となく犯人が判ってしまうのですが、ドラマの方は、原作以上に早くから犯人がミエミエという印象も。明智も"判っている"風で、あとは、明智がどう犯人を追い詰めるかしか楽しみがないのですが、「氷柱の美女」の脚本におけるクライマックスで、明智が単に普通に犯人の前に現れて謎解きをすることになっていたのが、それでは面白くないと考えた井上梅次(1923-2010/享年86)監督が現場で思いついたのが、犯人が鏡に向って仮面を取ると、その鏡の中に脱いだはずの吸血鬼の仮面が映り、びっくりして振向くと、もう一人の吸血鬼がゆっくり仮面を取って明智の顔が現れるという演出だったそうです。以降、明智がラスㇳに変装して犯人の前に現れ、仮面をはがした上で謎解きをするというのがシリーズの定番になったとのことです。 一方で、後にお決まりとなる「入浴シーン」はまだなく、その代わり、三ツ矢歌子(1936-2004/享年67)演じる倭文子が前半と後半各一度犯人に襲われますが、顔や肩から上は本人であるものの、胸や躰全体が映るシーンは吹き替えになっています。「昼メロの女王」と呼ばれながらも上品な役が多かった三ツ矢歌子が、ここまでやっただけでも当時驚くべきことだったようで、それ以上は無理だったのでしょう(その昔は「
一方で、後にお決まりとなる「入浴シーン」はまだなく、その代わり、三ツ矢歌子(1936-2004/享年67)演じる倭文子が前半と後半各一度犯人に襲われますが、顔や肩から上は本人であるものの、胸や躰全体が映るシーンは吹き替えになっています。「昼メロの女王」と呼ばれながらも上品な役が多かった三ツ矢歌子が、ここまでやっただけでも当時驚くべきことだったようで、それ以上は無理だったのでしょう(その昔は「 ラストも原作から改変されていますが、「氷柱の美女」を実現したのはなかなかのものです(タイトルが「氷柱の美女」なら、やらない訳にはいかないが)。ただ、最初に氷ごと横向き現れた時、どう見ても明らかにマネキンなので、これはいくらなんでも製氷機から出てきた瞬間に犯人が気づくだろうと。でもアップになると三ツ矢歌子で、そこだけ映していればまだよかったのにと思ったりもしました。というのは、中途半端にカメラを引くとその姿はまたマネキンになり、さらに別の角度から背景としての映り込みになると、その顔が紙に書かれた下手な似顔絵みたいで(なぜか笑っている)げんなりさせられたからです。ラストには"異形の愛"的なドラマチックな要素もあるだけに、最後に技術面で「荒唐無稽小説」の壁を乗り越えられなかった気がして惜しいです。
ラストも原作から改変されていますが、「氷柱の美女」を実現したのはなかなかのものです(タイトルが「氷柱の美女」なら、やらない訳にはいかないが)。ただ、最初に氷ごと横向き現れた時、どう見ても明らかにマネキンなので、これはいくらなんでも製氷機から出てきた瞬間に犯人が気づくだろうと。でもアップになると三ツ矢歌子で、そこだけ映していればまだよかったのにと思ったりもしました。というのは、中途半端にカメラを引くとその姿はまたマネキンになり、さらに別の角度から背景としての映り込みになると、その顔が紙に書かれた下手な似顔絵みたいで(なぜか笑っている)げんなりさせられたからです。ラストには"異形の愛"的なドラマチックな要素もあるだけに、最後に技術面で「荒唐無稽小説」の壁を乗り越えられなかった気がして惜しいです。
 「江戸川乱歩 美女シリーズ(天知茂版)」●監督:井上梅次(第1作-第19作)/村川透/長谷和夫/貞永方久/永野靖忠●プロデューサー:佐々木孟●脚本:宮川一郎/井上梅次/長谷川公之/ジェームス三木/櫻井康裕/成沢昌茂/吉田剛/篠崎好/江連卓/池田雄一/山下六合雄●撮影:平瀬静雄●音楽:鏑木創●原作:江戸川乱歩●出演:天知茂/五十嵐めぐみ(第1作-第19作)/高見知佳(第20作-第23作)/藤吉久美子(第24作・第25作)/大和田獏(第1作)/柏原貴(第6作-第19作)/小野田真之(第20作-第25作)/稲垣昭三(第1作)/北町嘉朗(第1作・第4作-第9作)/宮口二郎(第2作・第3作)/荒井注(第2作-第25作)●放映:1977/08~1985/08(天知茂版25回)【1986/07~1990/04(北大路欣也版6回)、1992/07~1994/01(西郷輝彦版2回)】●放送局:テレビ朝日
「江戸川乱歩 美女シリーズ(天知茂版)」●監督:井上梅次(第1作-第19作)/村川透/長谷和夫/貞永方久/永野靖忠●プロデューサー:佐々木孟●脚本:宮川一郎/井上梅次/長谷川公之/ジェームス三木/櫻井康裕/成沢昌茂/吉田剛/篠崎好/江連卓/池田雄一/山下六合雄●撮影:平瀬静雄●音楽:鏑木創●原作:江戸川乱歩●出演:天知茂/五十嵐めぐみ(第1作-第19作)/高見知佳(第20作-第23作)/藤吉久美子(第24作・第25作)/大和田獏(第1作)/柏原貴(第6作-第19作)/小野田真之(第20作-第25作)/稲垣昭三(第1作)/北町嘉朗(第1作・第4作-第9作)/宮口二郎(第2作・第3作)/荒井注(第2作-第25作)●放映:1977/08~1985/08(天知茂版25回)【1986/07~1990/04(北大路欣也版6回)、1992/07~1994/01(西郷輝彦版2回)】●放送局:テレビ朝日 1 1977年8月20日 氷柱の美女 『吸血鬼』 三ツ矢歌子 12.6%
1 1977年8月20日 氷柱の美女 『吸血鬼』 三ツ矢歌子 12.6% 11 1980年4月12日 桜の国の美女 『黄金仮面II』 古手川祐子 15.9%
11 1980年4月12日 桜の国の美女 『黄金仮面II』 古手川祐子 15.9% 21 1983年4月16日 白い素肌の美女 『盲獣』(『一寸法師』) 叶和貴子 13.3%
21 1983年4月16日 白い素肌の美女 『盲獣』(『一寸法師』) 叶和貴子 13.3%


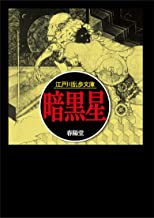


 明智探偵(天知茂)は、彫刻家・伊志田鉄造(岡田英次)の「呪」と題された彫刻展の招待状を受け、文代(五十嵐めぐみ)と彫刻展に。そこで女性の悲鳴が上がる、展示してある彫刻が口から血を流していたのだ。いたずら好きの長男・太郎(北公次)の仕業かと思われたが、それは次女・悦子(泉じゅん)がやったことだった。展覧会を後にしようとする明智たちを一人の女性がずっと見ていた。伊志田の長女・待子(ジュディ・オング)で、彼女こそが明智に招待状を送った本人だっ
明智探偵(天知茂)は、彫刻家・伊志田鉄造(岡田英次)の「呪」と題された彫刻展の招待状を受け、文代(五十嵐めぐみ)と彫刻展に。そこで女性の悲鳴が上がる、展示してある彫刻が口から血を流していたのだ。いたずら好きの長男・太郎(北公次)の仕業かと思われたが、それは次女・悦子(泉じゅん)がやったことだった。展覧会を後にしようとする明智たちを一人の女性がずっと見ていた。伊志田の長女・待子(ジュディ・オング)で、彼女こそが明智に招待状を送った本人だっ
 た。待子は明智に伊志田邸に正体不明の黒い影が出現し、母の君代(空あけみ)はそれがもとで寝込んでいるという。明智に伊志田家に出没する黒い影についての捜査を依頼した。その夜、待子が独りでいると不気味な声が聞こえ、待子は明智に電話で助けを求める。
た。待子は明智に伊志田邸に正体不明の黒い影が出現し、母の君代(空あけみ)はそれがもとで寝込んでいるという。明智に伊志田家に出没する黒い影についての捜査を依頼した。その夜、待子が独りでいると不気味な声が聞こえ、待子は明智に電話で助けを求める。 耳を澄ませた明智にもその声は確かに聞こえた。黒い影は声だけでなく邸内を自由自在に跳び回って待子を恐怖に陥れる。そして、彫刻の一つに成りすました黒い影が待子の首を絞める。そこへチャイムが鳴り、待子の電話により伊志田家に到着した明智を、邸付きの看護婦・三重野早苗(江波杏子)が出迎える。邸内では待子が気絶していた。黒い影の主を見つけようと伊志田家の庭に出た明智は、例の不気味な声を聞き、その正体を暴こうとするも見失ってしまう。やがて三女の鞠子が殺害される事件が起き、続いて次女・悦子も浴室で―。
耳を澄ませた明智にもその声は確かに聞こえた。黒い影は声だけでなく邸内を自由自在に跳び回って待子を恐怖に陥れる。そして、彫刻の一つに成りすました黒い影が待子の首を絞める。そこへチャイムが鳴り、待子の電話により伊志田家に到着した明智を、邸付きの看護婦・三重野早苗(江波杏子)が出迎える。邸内では待子が気絶していた。黒い影の主を見つけようと伊志田家の庭に出た明智は、例の不気味な声を聞き、その正体を暴こうとするも見失ってしまう。やがて三女の鞠子が殺害される事件が起き、続いて次女・悦子も浴室で―。 登場人物の相関がやや分かりにくいですが、長女の待子は伊志田の亡くなった先妻・靜子の子であり、悦子と太郎、鞠子の三人が今の妻の子であって、待子が二歳の時、鉄造は絹代と関係を持ち、太郎と悦子が生まれ、伊志田家へ押し掛けてきたという過去があったと。離れの小屋で祈祷している精神を病んだ老女(原泉)は、靜子の母、つまり待子の祖母であると把握できれば、実は靜子には待子のほかにもう一人子がいたということが判った時点で、ああ、それが犯人だと思い当たるし、助けを求められて駆けつけた明智に「待子さんは夢遊病の気があるから」と言った時点でもう怪しいです。
登場人物の相関がやや分かりにくいですが、長女の待子は伊志田の亡くなった先妻・靜子の子であり、悦子と太郎、鞠子の三人が今の妻の子であって、待子が二歳の時、鉄造は絹代と関係を持ち、太郎と悦子が生まれ、伊志田家へ押し掛けてきたという過去があったと。離れの小屋で祈祷している精神を病んだ老女(原泉)は、靜子の母、つまり待子の祖母であると把握できれば、実は靜子には待子のほかにもう一人子がいたということが判った時点で、ああ、それが犯人だと思い当たるし、助けを求められて駆けつけた明智に「待子さんは夢遊病の気があるから」と言った時点でもう怪しいです。
 原作は、江戸川乱歩が1939年1月から12月に雑誌「講談倶楽部」に連載したもので、本人名義で児童向けにリライトされた作品もあります(ポプラ社『少年探偵 江戸川乱歩全集』(全46巻)の中の第27巻「黄金仮面」以降は、実際は本人ではなく別の作家が書いたものだったため、今は絶版となっている)。文庫で200ページほどの長さ(2015年版「江戸川乱歩文庫」(春陽堂))。原作で
原作は、江戸川乱歩が1939年1月から12月に雑誌「講談倶楽部」に連載したもので、本人名義で児童向けにリライトされた作品もあります(ポプラ社『少年探偵 江戸川乱歩全集』(全46巻)の中の第27巻「黄金仮面」以降は、実際は本人ではなく別の作家が書いたものだったため、今は絶版となっている)。文庫で200ページほどの長さ(2015年版「江戸川乱歩文庫」(春陽堂))。原作で は、伊志田の子供は、長女・「綾子」、長男・一郎、次女・鞠子の3人で、何れも今の母・君代の子ではなく、伊志田の前妻の子であるということになっています。明智に相談を持ち掛けるのは長男の一郎で(「講談倶楽部」挿絵の右が一郎、左が明智)、電話で助けを呼ぶのも一
は、伊志田の子供は、長女・「綾子」、長男・一郎、次女・鞠子の3人で、何れも今の母・君代の子ではなく、伊志田の前妻の子であるということになっています。明智に相談を持ち掛けるのは長男の一郎で(「講談倶楽部」挿絵の右が一郎、左が明智)、電話で助けを呼ぶのも一

 ドラマはこのように、物語の設定の細部が原作とかなり異なりますが(いや、細部どころか犯人さえ違っている)、不思議と原作の雰囲気をよく伝えているように思います。何よりも、ジュディ・オング、江波杏子(2018年没)という二大女優を配したことで、それぞれをそれに見合った役柄に改変したものと思われます(それが活かされている)。その他にも、父親
ドラマはこのように、物語の設定の細部が原作とかなり異なりますが(いや、細部どころか犯人さえ違っている)、不思議と原作の雰囲気をよく伝えているように思います。何よりも、ジュディ・オング、江波杏子(2018年没)という二大女優を配したことで、それぞれをそれに見合った役柄に改変したものと思われます(それが活かされている)。その他にも、父親 役が岡田英次で、長男役が北公次(2012年没)と、配役は全体的に豪華です(北公次にとっては、ジャニーズ事務所在籍最後の仕事となった)。原作で浴室で殺害されるのは義母の君代ですが、
役が岡田英次で、長男役が北公次(2012年没)と、配役は全体的に豪華です(北公次にとっては、ジャニーズ事務所在籍最後の仕事となった)。原作で浴室で殺害されるのは義母の君代ですが、
 ドラマでの"浴室要員"は次女・悦子(原作には無い)役の泉じゅんで、彼女が日活ロマンポルノから離れていた時期です(この頃、山口百恵と三浦友和の主演コンビ
ドラマでの"浴室要員"は次女・悦子(原作には無い)役の泉じゅんで、彼女が日活ロマンポルノから離れていた時期です(この頃、山口百恵と三浦友和の主演コンビ
 の「泥だらけの純情」('77年)、「古都」('80年)にヒロインの女友達の役で出たりしている)。このドラマでは、財産のために自分以外の家族を皆殺しにしたい、そのために力を貸して欲しいと明智探偵に囁き(なんと大胆!)、逆に明智から「金と女性の誘惑に乗らないのが探偵の第一条件」と言われてしまうという、ドラマオリジナルのキャラになっています(これもその演技力を買われてのことか)。
の「泥だらけの純情」('77年)、「古都」('80年)にヒロインの女友達の役で出たりしている)。このドラマでは、財産のために自分以外の家族を皆殺しにしたい、そのために力を貸して欲しいと明智探偵に囁き(なんと大胆!)、逆に明智から「金と女性の誘惑に乗らないのが探偵の第一条件」と言われてしまうという、ドラマオリジナルのキャラになっています(これもその演技力を買われてのことか)。
 それにしても、ドラマで見ると、犯人は服装面で相当な早替わり(現実には不可能?)をしていたということになるかと思います(その上、無駄にいっぱいバック転をしていた。ステージでバック転を披露した最初のアイドルが北公次であることを思い出した)。一方の明智は、わざわざ犯人に変装する必要があったのかなと疑問に思われますが、原作では変装する理由がちゃんと説明されています。原作と比べてみると、翻案の妙が愉しめるかと思います。
それにしても、ドラマで見ると、犯人は服装面で相当な早替わり(現実には不可能?)をしていたということになるかと思います(その上、無駄にいっぱいバック転をしていた。ステージでバック転を披露した最初のアイドルが北公次であることを思い出した)。一方の明智は、わざわざ犯人に変装する必要があったのかなと疑問に思われますが、原作では変装する理由がちゃんと説明されています。原作と比べてみると、翻案の妙が愉しめるかと思います。
 「江戸川乱歩 美女シリーズ(第5話)/黒水仙の美女」●制作年:1978年●監督:井上梅次●プロデューサー:佐々木孟●脚本:井上梅次●音楽:鏑木創●原作:江戸川乱歩「暗黒星」●時間:72 分●出演:天知茂/五十嵐めぐみ/荒井注/江波杏子/ジュディ・オング/岡田英次/泉じゅん/北公次/原泉/北町嘉郎●放送局:テレビ朝日●放送日:1978/10/14(評価:★★★☆)
「江戸川乱歩 美女シリーズ(第5話)/黒水仙の美女」●制作年:1978年●監督:井上梅次●プロデューサー:佐々木孟●脚本:井上梅次●音楽:鏑木創●原作:江戸川乱歩「暗黒星」●時間:72 分●出演:天知茂/五十嵐めぐみ/荒井注/江波杏子/ジュディ・オング/岡田英次/泉じゅん/北公次/原泉/北町嘉郎●放送局:テレビ朝日●放送日:1978/10/14(評価:★★★☆)









 大宝映画夏の大作「燃える女」のヒロイン役を決めるためのコンテストの最終審査会にて、準女王に選ばれたのは相川珠子(野平ゆき)、そして女王として春川月子(三崎奈美)が選ばれた。このコンテストが出来レースだったことに不平を漏らす珠子と、その義理の姉となる桜井品子(永島瑛子)。そして、恋人役の男優・吉野圭一郎(永井秀和)が女王に王冠を戴冠させたその時、天井から照明器具が落ちてきた。間一髪、それを避けた二人だったが、これが、この後に起こる怪事件の前哨であることに気づいた者は誰もいなかった。やがて連続殺人が。街角にディスプレイされる春川月子と吉野圭一郎の死体。浴室で珠子に放たれる毒蠍。囚われの身となる品子。犯人は、明智探偵(天知茂)に変装して犯行を繰り返す―。
大宝映画夏の大作「燃える女」のヒロイン役を決めるためのコンテストの最終審査会にて、準女王に選ばれたのは相川珠子(野平ゆき)、そして女王として春川月子(三崎奈美)が選ばれた。このコンテストが出来レースだったことに不平を漏らす珠子と、その義理の姉となる桜井品子(永島瑛子)。そして、恋人役の男優・吉野圭一郎(永井秀和)が女王に王冠を戴冠させたその時、天井から照明器具が落ちてきた。間一髪、それを避けた二人だったが、これが、この後に起こる怪事件の前哨であることに気づいた者は誰もいなかった。やがて連続殺人が。街角にディスプレイされる春川月子と吉野圭一郎の死体。浴室で珠子に放たれる毒蠍。囚われの身となる品子。犯人は、明智探偵(天知茂)に変装して犯行を繰り返す―。
 川乱歩全集』(全46巻)の中の第27巻「黄金仮面」以降は、実際は本人ではなく別の作家が書いたものだったため、今は絶版となっている)。探偵役は三笠竜介という老人ですが(作者は当時、明智小五郎に替わる新キャラクターを模索していたらしい)、当然のことながらドラマでは天知茂演じる明智小五郎に置き換えられています。この作品について、乱歩本人は「自註自解」として、「相変わらずの荒唐無稽小説だが、真犯人とその動機はちょっと珍しい着想であった」と述べています。
川乱歩全集』(全46巻)の中の第27巻「黄金仮面」以降は、実際は本人ではなく別の作家が書いたものだったため、今は絶版となっている)。探偵役は三笠竜介という老人ですが(作者は当時、明智小五郎に替わる新キャラクターを模索していたらしい)、当然のことながらドラマでは天知茂演じる明智小五郎に置き換えられています。この作品について、乱歩本人は「自註自解」として、「相変わらずの荒唐無稽小説だが、真犯人とその動機はちょっと珍しい着想であった」と述べています。 作者本人が「荒唐無稽小説」と言うくらいなので、どこまで映像化できるのかなという思いはありましたが、思った以上に原作を反映していたように思います。バラバラ死体風のマネキン、銀座街頭ショーウインドウへの死体陳列、犯人と明智探偵の変装合戦、密室からの脱出など、このシリーズにおけるドラマとしてのリアリティを何とか維持しつつ頑張っていたように思います。
作者本人が「荒唐無稽小説」と言うくらいなので、どこまで映像化できるのかなという思いはありましたが、思った以上に原作を反映していたように思います。バラバラ死体風のマネキン、銀座街頭ショーウインドウへの死体陳列、犯人と明智探偵の変装合戦、密室からの脱出など、このシリーズにおけるドラマとしてのリアリティを何とか維持しつつ頑張っていたように思います。 原作と大きく違ったのは、蠍研究の世界的権威であったという匹田博士なる人物を登場させ、そこに犯人との愛憎劇を一枚咬ませていることで、原作は主犯格の者が手配の者を使っているのに対し、ドラマの方はこの二人の共犯になっていました。それと、原作では、珠子の家庭教師・殿村京子が次に教えることになった、珠子の学校の先輩の20歳になる美人ヴァイオリニスト・桜井品子が犯人の第三の標的になり、三笠竜介が何とか第三の殺人を起こさせまいとするものでしたが、ドラマでは、この桜井品子が珠子の義理の姉となっていて、彼女には犯人に狙われる理由があったことになっています。入浴中に狙われるのは野平ゆき(レイモン・ラディゲ原作「肉体の悪魔」('77年/日活))演じる珠子ですが、永島瑛子(清水一行原作「
原作と大きく違ったのは、蠍研究の世界的権威であったという匹田博士なる人物を登場させ、そこに犯人との愛憎劇を一枚咬ませていることで、原作は主犯格の者が手配の者を使っているのに対し、ドラマの方はこの二人の共犯になっていました。それと、原作では、珠子の家庭教師・殿村京子が次に教えることになった、珠子の学校の先輩の20歳になる美人ヴァイオリニスト・桜井品子が犯人の第三の標的になり、三笠竜介が何とか第三の殺人を起こさせまいとするものでしたが、ドラマでは、この桜井品子が珠子の義理の姉となっていて、彼女には犯人に狙われる理由があったことになっています。入浴中に狙われるのは野平ゆき(レイモン・ラディゲ原作「肉体の悪魔」('77年/日活))演じる珠子ですが、永島瑛子(清水一行原作「 冒頭にミスコンの場面がありますが、原作では春川月子がミスジャパン、珠子がミストウキョウということで、同じミスコンで競ったわけではないようです。原作では、そうしたミスコンそのものは描かれていませんが、二人が競い合うミスコンをリアルタイムでやって、ドラマ映えするようにしたのでしょう。珠子が春川月子に代わって映画のヒロインに選ばれるのもドラマのオリジナル。また、珠子の家庭教師・殿村京子は原作では中年の醜女ということになっていて、ドラマではこれを美女である宇都宮雅代が演じており、ただし、原作とは異なるハンディを彼女に負わせています。
冒頭にミスコンの場面がありますが、原作では春川月子がミスジャパン、珠子がミストウキョウということで、同じミスコンで競ったわけではないようです。原作では、そうしたミスコンそのものは描かれていませんが、二人が競い合うミスコンをリアルタイムでやって、ドラマ映えするようにしたのでしょう。珠子が春川月子に代わって映画のヒロインに選ばれるのもドラマのオリジナル。また、珠子の家庭教師・殿村京子は原作では中年の醜女ということになっていて、ドラマではこれを美女である宇都宮雅代が演じており、ただし、原作とは異なるハンディを彼女に負わせています。
 因みに、宇津宮雅代は、TBS・加藤剛主演のTVドラマ「大岡越前」の第1部('70年)で 初代「雪絵」(後の忠相の妻)役で第4話「慕情の人」から登場して、第6部('82年)まで雪絵役を演じ(敵によく捕まって人質になるが(笑)、小太刀の腕も確かで、悪人相手にひるむことはない)、その後を酒井和歌子に引き継いでいます(「雪絵」は、
因みに、宇津宮雅代は、TBS・加藤剛主演のTVドラマ「大岡越前」の第1部('70年)で 初代「雪絵」(後の忠相の妻)役で第4話「慕情の人」から登場して、第6部('82年)まで雪絵役を演じ(敵によく捕まって人質になるが(笑)、小太刀の腕も確かで、悪人相手にひるむことはない)、その後を酒井和歌子に引き継いでいます(「雪絵」は、 加藤剛演じる「忠相」、高橋元太郎演じる「すっとびの辰三」、山口崇演じ
加藤剛演じる「忠相」、高橋元太郎演じる「すっとびの辰三」、山口崇演じ る「徳川吉宗」らと並んで、全シリーズを通して登場した数少ないキャラクターであり、また、演者が交代しながら全シリーズ登場した唯一のキャラクターである)。また、天知茂も南町奉行与力「神山左門」(カミソリ左門)役で、このドラマシリーズの第1部から第3部('72-'73年)にレギュラー出演しています(祝言をあげたばかりの妻を盗賊に人質にとられ亡くしたため、悪に対する憎しみが人一倍強く、また、別人になりすまして敵方に潜入したり、常にニヒル感が漂う(笑)ところは「美女シリーズ」の明智小五郎と同じ)。
る「徳川吉宗」らと並んで、全シリーズを通して登場した数少ないキャラクターであり、また、演者が交代しながら全シリーズ登場した唯一のキャラクターである)。また、天知茂も南町奉行与力「神山左門」(カミソリ左門)役で、このドラマシリーズの第1部から第3部('72-'73年)にレギュラー出演しています(祝言をあげたばかりの妻を盗賊に人質にとられ亡くしたため、悪に対する憎しみが人一倍強く、また、別人になりすまして敵方に潜入したり、常にニヒル感が漂う(笑)ところは「美女シリーズ」の明智小五郎と同じ)。



 宇津宮雅代/夏八木勲/
宇津宮雅代/夏八木勲/





 「江戸川乱歩 美女シリーズ(第9話)/赤いさそりの美女」●制作年:1979年●監督:井上梅次●プロデューサ:中井義/植野晃弘/佐々木孟●脚本:井上梅次●音楽:鏑木創●原作:江戸川乱歩「妖虫」●時間:95分●出演:天知茂/五十嵐めぐみ/柏原貴/荒井注/宇津宮雅代/永島瑛子/永井秀和/入川保則/野平ゆき/速水亮/本郷直樹/堀之紀/北町嘉郎/高木次郎/増田順司●放送局:テレビ朝日●放送日:1979/06/09(評価:★★★☆)
「江戸川乱歩 美女シリーズ(第9話)/赤いさそりの美女」●制作年:1979年●監督:井上梅次●プロデューサ:中井義/植野晃弘/佐々木孟●脚本:井上梅次●音楽:鏑木創●原作:江戸川乱歩「妖虫」●時間:95分●出演:天知茂/五十嵐めぐみ/柏原貴/荒井注/宇津宮雅代/永島瑛子/永井秀和/入川保則/野平ゆき/速水亮/本郷直樹/堀之紀/北町嘉郎/高木次郎/増田順司●放送局:テレビ朝日●放送日:1979/06/09(評価:★★★☆)










 新潮文庫版『羅生門・鼻』('68年初版/'05年改版)は、1915年(大正4年)11月に雑誌『帝国文学』に発表された「羅生門」、翌大正5年に雑誌『新思潮』に発表された「鼻」をはじめ、「芋粥」「運」「袈裟と成遠」「邪宗門」「好色」「俊寛」の8編を収録。何れも「王朝物」と言われる、平安時代に材料を得た歴史小説です。因みに、1917年(大正6年)5月に阿蘭陀書房より刊行された短編集『羅生門』が芥川龍之介にとっての処女短編集で(表題の「羅生門」をはじめ「鼻」「芋粥」など14編の短編を所収)、日本橋のレストラン「鴻の巣」で出版祈念会「羅生門の会」が催され、谷崎潤一郎、有島武郎、和辻哲郎等も出席しています。
新潮文庫版『羅生門・鼻』('68年初版/'05年改版)は、1915年(大正4年)11月に雑誌『帝国文学』に発表された「羅生門」、翌大正5年に雑誌『新思潮』に発表された「鼻」をはじめ、「芋粥」「運」「袈裟と成遠」「邪宗門」「好色」「俊寛」の8編を収録。何れも「王朝物」と言われる、平安時代に材料を得た歴史小説です。因みに、1917年(大正6年)5月に阿蘭陀書房より刊行された短編集『羅生門』が芥川龍之介にとっての処女短編集で(表題の「羅生門」をはじめ「鼻」「芋粥」など14編の短編を所収)、日本橋のレストラン「鴻の巣」で出版祈念会「羅生門の会」が催され、谷崎潤一郎、有島武郎、和辻哲郎等も出席しています。![[オーディオブックCD] 芥川龍之介 羅生門.jpg](http://hurec.bz/book-movie/%5B%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%AA%E3%83%96%E3%83%83%E3%82%AFCD%5D%20%E8%8A%A5%E5%B7%9D%E9%BE%8D%E4%B9%8B%E4%BB%8B%20%E7%BE%85%E7%94%9F%E9%96%80.jpg)
 「芋粥」(大正5年)... これも出典は『今昔物語』。背が低く、鼻が赤く、口ひげが薄く、風采があがらず、皆から馬鹿にされている五位の夢は、滅多に食べることのできない芋粥を飽きるほど食べてみたいというもの。ある時、その願いを耳にした藤原利仁が、「お望みなら、利仁がお飽かせ申そう」と言ってくる―。理想や欲望は達せられないからこそ価値があり、達せられれば幻滅するのみということでしょうか。但し、角川文庫解説の三好行雄は、主人公が幻滅の悲哀を味わったのは確かだが、真に絶望したのは、自分の生きがいが巨大な窯で煮られ、狐にさえ馳走される現実に対してであるとしています(何だか"格差社会"的テーマになるなあ)。五位の境遇や性格は確かにゴーゴリの「外套」の下級官吏アカーキイ・アカーキエウィッチと似ていると思いましたが、格差を見せつけられた五位と、死後に幽霊になって復讐を果たしたアカーキイ・アカーキエウィッチとどちらが不幸なのでしょう。
「芋粥」(大正5年)... これも出典は『今昔物語』。背が低く、鼻が赤く、口ひげが薄く、風采があがらず、皆から馬鹿にされている五位の夢は、滅多に食べることのできない芋粥を飽きるほど食べてみたいというもの。ある時、その願いを耳にした藤原利仁が、「お望みなら、利仁がお飽かせ申そう」と言ってくる―。理想や欲望は達せられないからこそ価値があり、達せられれば幻滅するのみということでしょうか。但し、角川文庫解説の三好行雄は、主人公が幻滅の悲哀を味わったのは確かだが、真に絶望したのは、自分の生きがいが巨大な窯で煮られ、狐にさえ馳走される現実に対してであるとしています(何だか"格差社会"的テーマになるなあ)。五位の境遇や性格は確かにゴーゴリの「外套」の下級官吏アカーキイ・アカーキエウィッチと似ていると思いましたが、格差を見せつけられた五位と、死後に幽霊になって復讐を果たしたアカーキイ・アカーキエウィッチとどちらが不幸なのでしょう。
 「袈裟と盛遠」(大正7年)... 盛遠は、渡左衛門尉の妻・袈裟に横恋慕し、やがて邪魔な渡を殺してしまおうと思い、袈裟に殺害計画を打ち明ける―。その段になって夫の前に身を投げ出した袈裟は、貞女なのか、はたまた...。原典(『源平盛衰記』など)でも袈裟は盛遠(モデルは遠藤盛遠、後の僧・文覚(1119-1203))と既に契ってしまっているそうですが、この作品は袈裟の貞女としてのイメージをひっくり返すだけでなく、愛する男に殺害されることが最初からの彼女の望みだったというスゴイ解釈になっています(稲垣浩・マキノ正博共同監督作に「袈裟と盛遠」('39年/日活)というのがあるが、原典(「源平盛衰記」乃至「平家物語」)に沿った作りか。オペラにもなっていて、こちらは「芥川龍之介原作」ではなく、はっきり「平家物語より」となっている)。
「袈裟と盛遠」(大正7年)... 盛遠は、渡左衛門尉の妻・袈裟に横恋慕し、やがて邪魔な渡を殺してしまおうと思い、袈裟に殺害計画を打ち明ける―。その段になって夫の前に身を投げ出した袈裟は、貞女なのか、はたまた...。原典(『源平盛衰記』など)でも袈裟は盛遠(モデルは遠藤盛遠、後の僧・文覚(1119-1203))と既に契ってしまっているそうですが、この作品は袈裟の貞女としてのイメージをひっくり返すだけでなく、愛する男に殺害されることが最初からの彼女の望みだったというスゴイ解釈になっています(稲垣浩・マキノ正博共同監督作に「袈裟と盛遠」('39年/日活)というのがあるが、原典(「源平盛衰記」乃至「平家物語」)に沿った作りか。オペラにもなっていて、こちらは「芥川龍之介原作」ではなく、はっきり「平家物語より」となっている)。




 旧制中学二年の主人公のコペル君こと本田潤一は、学業優秀でスポーツも卒なくこなし、いたずらが過ぎるために級長にこそなれないがある程度の人望はある。父親は亡くなるまで銀行の重役で、家には女中が1人いる。コペル君は友人たちと学校生活を送るなかで、さまざまな出来事を経験し、大きな苦悩に直面したりしながらも、叔父さんをはじめ周囲の導きのもと成長していく―。
旧制中学二年の主人公のコペル君こと本田潤一は、学業優秀でスポーツも卒なくこなし、いたずらが過ぎるために級長にこそなれないがある程度の人望はある。父親は亡くなるまで銀行の重役で、家には女中が1人いる。コペル君は友人たちと学校生活を送るなかで、さまざまな出来事を経験し、大きな苦悩に直面したりしながらも、叔父さんをはじめ周囲の導きのもと成長していく―。 NHK「
NHK「 作者の吉野源三郎(1899-1981)は、編集者・児童文学者・評論家・翻訳家・反戦運動家・ジャーナリストなどの肩書があった人で、岩波新書の創刊(1938年)に携わり、雑誌「世界」の初代編集長なども務めた人物です。本書は1937年8月に山本有三編「日本少国民文庫」の第5巻として刊行された本で、80年の年月を経て2017年下半期にいきなりブームになりました。『日本少国民文庫』の最終刊として編纂者・山本有三が自ら執筆する予定だったのが、病身のため代わって作者が筆をとることになったとされていますが、『路傍の石』で知られる山本有三の教養主義小説(ビルディングスロマン)の系譜を引いている印象があり、苦難を乗り越えて立派な人間になるという主人公の意思の表出は、下村湖人などの作品にも通じるように感じました。
作者の吉野源三郎(1899-1981)は、編集者・児童文学者・評論家・翻訳家・反戦運動家・ジャーナリストなどの肩書があった人で、岩波新書の創刊(1938年)に携わり、雑誌「世界」の初代編集長なども務めた人物です。本書は1937年8月に山本有三編「日本少国民文庫」の第5巻として刊行された本で、80年の年月を経て2017年下半期にいきなりブームになりました。『日本少国民文庫』の最終刊として編纂者・山本有三が自ら執筆する予定だったのが、病身のため代わって作者が筆をとることになったとされていますが、『路傍の石』で知られる山本有三の教養主義小説(ビルディングスロマン)の系譜を引いている印象があり、苦難を乗り越えて立派な人間になるという主人公の意思の表出は、下村湖人などの作品にも通じるように感じました。 NHK「
NHK「 NHKの「おはよう日本」や「クローズアップ現代」などでも取り上げられて、読む前から話題沸騰といった感じでした。ただ、個人的には、作中で主人公の友人で進歩主義の姉が英雄的精神を強調する場面があるとか、特攻隊員だった若者が出陣前に本書を愛読していたとか聞いていてちょっと敬遠していた面もありましたが、今回のブームを機に実際に読んでみると、各章の後に、その日の話をコペル君から聞いた叔父さんがコペル君に書いたノートという体裁で、ものの見方や社会の構造・関係性といったテーマが語られる構成になっていて、件(くだん)の主人公の友人の姉が登場する章では、叔父さんは「人類の進歩と結びつかない英雄的精神も空しいが、英雄的な気魄を欠いた善良さも、同じように空しいことが多いのだ」という、バランスのとれたコメントをしていました。
NHKの「おはよう日本」や「クローズアップ現代」などでも取り上げられて、読む前から話題沸騰といった感じでした。ただ、個人的には、作中で主人公の友人で進歩主義の姉が英雄的精神を強調する場面があるとか、特攻隊員だった若者が出陣前に本書を愛読していたとか聞いていてちょっと敬遠していた面もありましたが、今回のブームを機に実際に読んでみると、各章の後に、その日の話をコペル君から聞いた叔父さんがコペル君に書いたノートという体裁で、ものの見方や社会の構造・関係性といったテーマが語られる構成になっていて、件(くだん)の主人公の友人の姉が登場する章では、叔父さんは「人類の進歩と結びつかない英雄的精神も空しいが、英雄的な気魄を欠いた善良さも、同じように空しいことが多いのだ」という、バランスのとれたコメントをしていました。 そう言えば、NHK-Eテレの「100分de名著」で、この本をテキストとしてジャーナリストの池上彰氏が学校で出張講義を行っていますが、行った先が武蔵中学・高校ということで、やはり完全中高一貫の超進学校だからなあ(当然、男子校)。そういうのが鼻につく人もいるだろうし、この本を矢鱈推奨している"文化人"っぽい人が鼻につくという人もいるかも。自分も当初はその一人でしたが、読んでみて、思ったほどに抵抗を感じなかったのは、最近こそ格差社会とか言われながらも、戦前と比べれば国民の生活水準もそこそこのレベルで平準化し、大学進学率もぐっと上がったためで、当時のそうした背景を気にしなければ、学校内でのいじめの問題など、今日に通じる話として読める普遍性を持っているせいかもしれません。
そう言えば、NHK-Eテレの「100分de名著」で、この本をテキストとしてジャーナリストの池上彰氏が学校で出張講義を行っていますが、行った先が武蔵中学・高校ということで、やはり完全中高一貫の超進学校だからなあ(当然、男子校)。そういうのが鼻につく人もいるだろうし、この本を矢鱈推奨している"文化人"っぽい人が鼻につくという人もいるかも。自分も当初はその一人でしたが、読んでみて、思ったほどに抵抗を感じなかったのは、最近こそ格差社会とか言われながらも、戦前と比べれば国民の生活水準もそこそこのレベルで平準化し、大学進学率もぐっと上がったためで、当時のそうした背景を気にしなければ、学校内でのいじめの問題など、今日に通じる話として読める普遍性を持っているせいかもしれません。 そう言えば、ブームになるずっと前に、あの辛口評論の齋藤美奈子氏が、本書を若い人への「贈り物に」と薦めていました(齋藤美奈子氏も岩波文化人の系譜?)。個人的には、確かに若い人に読んで欲しいけれど、「読め」と押しつける本ではないのだろうなあと思います(「贈り物」というのはいいかも。「読んだか」と訊かなければ)。
そう言えば、ブームになるずっと前に、あの辛口評論の齋藤美奈子氏が、本書を若い人への「贈り物に」と薦めていました(齋藤美奈子氏も岩波文化人の系譜?)。個人的には、確かに若い人に読んで欲しいけれど、「読め」と押しつける本ではないのだろうなあと思います(「贈り物」というのはいいかも。「読んだか」と訊かなければ)。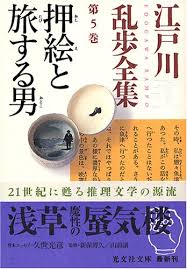



 出掛けるのであとをつけると、男の兄は「浅草12階」に登って双眼鏡を覗いている。声を掛けると男の兄は片思いの女性を覗いていたことを白状するが、その女性のいる所へ二人で行ってみると、その女性は押絵だった。すると男の兄はその双眼鏡を逆さまに覗いて自分を見ろと言い、男がそうすると兄は双眼鏡の中で小さくなり消えてしまう。男の兄は小さくなってその女性の横で同じ押絵になっていたのだった。以来、男は、ずっと押絵の中も退屈だろうからと、「兄夫婦」をこうして旅に連れて行っているのだという。ただ押絵の女性は歳をとらないが、兄だけが押絵の中で歳をとっているのだという。男が兄たちもこんな話をして恥ずかしがっているのでもう休ませますと、風呂敷の中に包み込もうとしたとき、気のせいか押絵の二人が「私」に挨拶の笑みを送ったように見えた―。
出掛けるのであとをつけると、男の兄は「浅草12階」に登って双眼鏡を覗いている。声を掛けると男の兄は片思いの女性を覗いていたことを白状するが、その女性のいる所へ二人で行ってみると、その女性は押絵だった。すると男の兄はその双眼鏡を逆さまに覗いて自分を見ろと言い、男がそうすると兄は双眼鏡の中で小さくなり消えてしまう。男の兄は小さくなってその女性の横で同じ押絵になっていたのだった。以来、男は、ずっと押絵の中も退屈だろうからと、「兄夫婦」をこうして旅に連れて行っているのだという。ただ押絵の女性は歳をとらないが、兄だけが押絵の中で歳をとっているのだという。男が兄たちもこんな話をして恥ずかしがっているのでもう休ませますと、風呂敷の中に包み込もうとしたとき、気のせいか押絵の二人が「私」に挨拶の笑みを送ったように見えた―。 物語全体を「男の話」にしていることで、("夢落ち"にしなくとも)全てが男の作り話か男自身が嵌っている幻想ととれなくもなく、一方で、目の前にそうした押絵があれば、やはり「私」ならずとも、幻想的な気持ちにさせられるでしょう。また、こうしたストーリーを成立させるには、昭和から大正を通り越して明治まで遡ることは必然だったようにも思います。「浅草十二階」と呼ばれた凌雲閣は、1890(明治23)年に完成し、1923(大正12)年の関東大震災で崩壊していますが、こうしたモチーフを持ち出しているのも巧みです(浅草は乱歩が愛した街でもある)。
物語全体を「男の話」にしていることで、("夢落ち"にしなくとも)全てが男の作り話か男自身が嵌っている幻想ととれなくもなく、一方で、目の前にそうした押絵があれば、やはり「私」ならずとも、幻想的な気持ちにさせられるでしょう。また、こうしたストーリーを成立させるには、昭和から大正を通り越して明治まで遡ることは必然だったようにも思います。「浅草十二階」と呼ばれた凌雲閣は、1890(明治23)年に完成し、1923(大正12)年の関東大震災で崩壊していますが、こうしたモチーフを持ち出しているのも巧みです(浅草は乱歩が愛した街でもある)。 この作品は、「竜二」('83年)、「チ・ン・ピ・ラ」('84年)の川島透監督によって、「押繪と旅する男」('94年/バンダイビジュアル)として映画化されています(「チ・ン・ピ・ラ」は金子正次の遺作脚本に川島透監督が手を加えて演出したもので、個人的にはイマイチだった)。映画「押繪と旅する男」は、「私」ではなく「弟」の"主観"で描かれていて、戦時中に特高警察として名を馳せながらも今はよぼよぼの老人となってしまった「弟」(浜村純)がいる「現代」の東京と、その回想としての「過去」―少
この作品は、「竜二」('83年)、「チ・ン・ピ・ラ」('84年)の川島透監督によって、「押繪と旅する男」('94年/バンダイビジュアル)として映画化されています(「チ・ン・ピ・ラ」は金子正次の遺作脚本に川島透監督が手を加えて演出したもので、個人的にはイマイチだった)。映画「押繪と旅する男」は、「私」ではなく「弟」の"主観"で描かれていて、戦時中に特高警察として名を馳せながらも今はよぼよぼの老人となってしまった「弟」(浜村純)がいる「現代」の東京と、その回想としての「過去」―少 年時代の「弟」(藤田哲也)の兄(飴屋法水)が凌雲閣から押絵の美少女を眺め、遂には押絵の中に入ってしまうという出来事があった大正時代―が交錯する形で描かれています。「私」に該当する人物は出てこないで、代わりに、「弟」の兄に嫁(鷲尾いさ子)がいて、押絵の少女(八百屋お七になっている)に夫を奪われたかたちとなった兄嫁への少年の淡い慕情が大きなウェイトを占める作りになっています。大正ロマンの香りがして、映画としては悪くないです。"主観"を変えて更に脚色されているため、原作とは随分と印象が異なるものになっていますが、川島透監督が自分が撮りたいものを撮ったという感じで、同監督の商業映画とは比べると、いい意味でかなり異なった印象を受けました。
年時代の「弟」(藤田哲也)の兄(飴屋法水)が凌雲閣から押絵の美少女を眺め、遂には押絵の中に入ってしまうという出来事があった大正時代―が交錯する形で描かれています。「私」に該当する人物は出てこないで、代わりに、「弟」の兄に嫁(鷲尾いさ子)がいて、押絵の少女(八百屋お七になっている)に夫を奪われたかたちとなった兄嫁への少年の淡い慕情が大きなウェイトを占める作りになっています。大正ロマンの香りがして、映画としては悪くないです。"主観"を変えて更に脚色されているため、原作とは随分と印象が異なるものになっていますが、川島透監督が自分が撮りたいものを撮ったという感じで、同監督の商業映画とは比べると、いい意味でかなり異なった印象を受けました。
 浜村純(1906-1995)演じる今は老人となった「弟」たる男の他に、特高だった男にかつて虐げられた恨みを持つ老人
浜村純(1906-1995)演じる今は老人となった「弟」たる男の他に、特高だった男にかつて虐げられた恨みを持つ老人 に多々良純(1917-2006)、男の友人で今は老人病院のような所に入院して死にかけている男に天本英世(1926-2003)など、老優たちが更に老け役で出ていて、「現代」のパートは老人ばかりの世界と言ってよく(老いと死が映画のテーマであるとも言えるか)、その分「過去」のパートの若々しい鷲尾いさ子(1967年生まれ)などは魅力的です。おそらく、押絵の娘になまめかしさを求めるのは映像的に難しいので、その部分を代替させたのではないでしょうか。
に多々良純(1917-2006)、男の友人で今は老人病院のような所に入院して死にかけている男に天本英世(1926-2003)など、老優たちが更に老け役で出ていて、「現代」のパートは老人ばかりの世界と言ってよく(老いと死が映画のテーマであるとも言えるか)、その分「過去」のパートの若々しい鷲尾いさ子(1967年生まれ)などは魅力的です。おそらく、押絵の娘になまめかしさを求めるのは映像的に難しいので、その部分を代替させたのではないでしょうか。


 「押繪と旅する男 (江戸川乱歩劇場 押繪と旅する男)」●制作年:1994年●監督:川島透●製作:並木幸/村上克司●脚本:薩川昭夫/川島透●撮影:町田博●音楽:上野耕路●原作:江戸川乱歩●時間:84分●出演:浜村純/鷲尾いさ子/藤田哲也/天本英世/飴屋法水/多々良純/伊勢カイト/小川亜佐美/和崎俊哉/高杉哲平/原川幸和/山崎ハコ●公開:1994/03●配給:バンダイビジュアル(評価★★★☆)
「押繪と旅する男 (江戸川乱歩劇場 押繪と旅する男)」●制作年:1994年●監督:川島透●製作:並木幸/村上克司●脚本:薩川昭夫/川島透●撮影:町田博●音楽:上野耕路●原作:江戸川乱歩●時間:84分●出演:浜村純/鷲尾いさ子/藤田哲也/天本英世/飴屋法水/多々良純/伊勢カイト/小川亜佐美/和崎俊哉/高杉哲平/原川幸和/山崎ハコ●公開:1994/03●配給:バンダイビジュアル(評価★★★☆)


 「チ・ン・ピ・ラ」●制作年:1984年●監督:川島透●製作:増田久雄/日枝久●脚本:金子正次●撮影:川越道彦●音楽:宮本光雄●時間:102分●出演:柴田恭兵/ジョニー大倉
「チ・ン・ピ・ラ」●制作年:1984年●監督:川島透●製作:増田久雄/日枝久●脚本:金子正次●撮影:川越道彦●音楽:宮本光雄●時間:102分●出演:柴田恭兵/ジョニー大倉 /石田えり/高樹沙耶/川地民夫/鹿内孝/我王銀次/小野武彦/久保田篤/利重剛/大出俊●公開:1984/11●配給:東宝●最初に観た場所:新宿・ビレッジ2 (84-11-25)(評価★★★)●併映:「海に降る雪」(中田新一)
/石田えり/高樹沙耶/川地民夫/鹿内孝/我王銀次/小野武彦/久保田篤/利重剛/大出俊●公開:1984/11●配給:東宝●最初に観た場所:新宿・ビレッジ2 (84-11-25)(評価★★★)●併映:「海に降る雪」(中田新一)
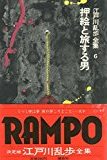





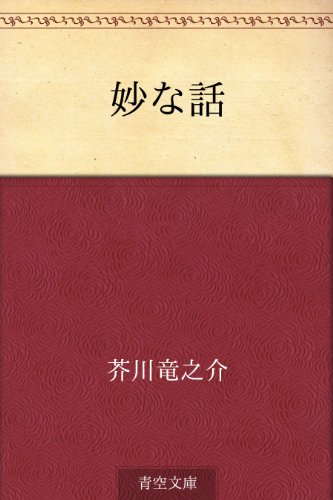
 芥川龍之介(1892-1927)が1921(大正10)年1月雑誌「現代」に発表し(執筆は大正9年12月)、『夜来の花』('21年/新潮社)に収められた文庫本で1
芥川龍之介(1892-1927)が1921(大正10)年1月雑誌「現代」に発表し(執筆は大正9年12月)、『夜来の花』('21年/新潮社)に収められた文庫本で1 0ページほどの短編です(ちくま文庫『芥川龍之介全集〈4〉』('87年)、ちくま文庫『文豪怪談傑作選 芥川龍之介集 妖婆』('10年)に所収、アンソロジーでは、創元推理文庫『日本怪奇小説傑作集1』('05年)、彩図社『文豪たちが書いた 怖い名作短編』('13年)、新潮文庫『日本文学100年の名作第1巻1914-1923 夢見る部屋』('14年)、河出文庫『見た人の怪談集』('16年)などに所収)。
0ページほどの短編です(ちくま文庫『芥川龍之介全集〈4〉』('87年)、ちくま文庫『文豪怪談傑作選 芥川龍之介集 妖婆』('10年)に所収、アンソロジーでは、創元推理文庫『日本怪奇小説傑作集1』('05年)、彩図社『文豪たちが書いた 怖い名作短編』('13年)、新潮文庫『日本文学100年の名作第1巻1914-1923 夢見る部屋』('14年)、河出文庫『見た人の怪談集』('16年)などに所収)。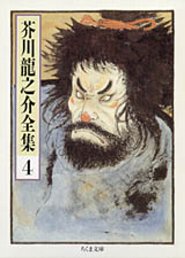
 ●『日本怪奇小説傑作集1』('05年/創元推理文庫)
●『日本怪奇小説傑作集1』('05年/創元推理文庫) ●『日本文学100年の名作第1巻1914-1923 夢見る部屋』('14年/新潮文庫)
●『日本文学100年の名作第1巻1914-1923 夢見る部屋』('14年/新潮文庫)


 山本周五郎(1903-1967)の初期短編小説で、1933(昭和8)年6月に雑誌「犯罪公論」に発表され、文庫で40ページほどです。この作家のイメージからすると珍しい"現代"(当時としては同時代の)推理小説で、横浜が舞台のモダンな感じがする作品である上に、本格推理小説でもあります。新潮文庫『花匂う』に収められていて、文庫解説によるとこの『花匂う』には、作者生前に刊行された「山本周五郎全集(全13巻)」('63~'64年/講談社)など何れの全集にも収録されなかった作品を収めたとのことです。但し、これらの作品は「山本周五郎 全集未収録作品集(全17 巻)」('72~'82年/実業之日本社)には収録されています(この「出来ていた青」は、『現代小説集-全集未収録作品集〈15〉』に収録)。
山本周五郎(1903-1967)の初期短編小説で、1933(昭和8)年6月に雑誌「犯罪公論」に発表され、文庫で40ページほどです。この作家のイメージからすると珍しい"現代"(当時としては同時代の)推理小説で、横浜が舞台のモダンな感じがする作品である上に、本格推理小説でもあります。新潮文庫『花匂う』に収められていて、文庫解説によるとこの『花匂う』には、作者生前に刊行された「山本周五郎全集(全13巻)」('63~'64年/講談社)など何れの全集にも収録されなかった作品を収めたとのことです。但し、これらの作品は「山本周五郎 全集未収録作品集(全17 巻)」('72~'82年/実業之日本社)には収録されています(この「出来ていた青」は、『現代小説集-全集未収録作品集〈15〉』に収録)。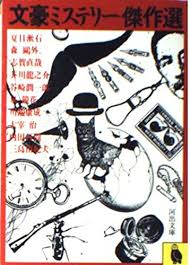 ●『文豪ミステリー傑作選(第1集)』('85年/河出文庫)
●『文豪ミステリー傑作選(第1集)』('85年/河出文庫) ●『文豪ミステリー傑作選(第2集)』('85年/河出文庫)
●『文豪ミステリー傑作選(第2集)』('85年/河出文庫)

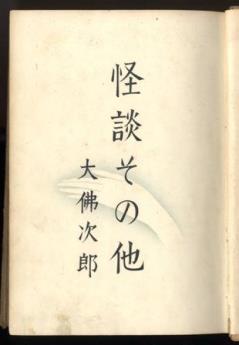
 慶応2年5月、清兵衛は芸妓・お村との新生活のために、牛込・通寺町の人目につかない閑静な場所にある手ごろな家を見つける。その2階に2人で床を並べてうとうとした際に、腕を冷たい手で掴まれ、あまりに冷たいのでその手を引き寄せると、その手は手首だけで、肱までなかった。次の晩もその手は清兵衛の前に現れ、家主に問いただすと、前にその部屋に住んでいたのは白鳥という土佐藩の武士で、綺麗な御新造さんがいたが、急に国に帰ることになったという。清兵衛は市ヶ谷・谷町に居を移すが、前の部屋の梯子段の下の戸棚に蛆虫が蠢めいているのが見つかり、白鳥の妾の変死体が床下から発掘される。谷町の住居も1カ月と続かず、お村と清兵衛の関係はうまくいかなくなって、清兵衛はお村と別れる。さらに清兵衛の不幸は続き、梅雨の頃から自分の左手首が痛み出す。親戚の家に行った際にそこの子供が清兵衛を見て、「蒼い手、蒼い手...」といって怖がり、清兵衛は自分の手に女の死人の手がぶら下がっていることを初めて知る。その時から清兵衛は、物事の全てに対する気力を失い、塔の沢に長逗留することになる。ある日、夕食前に一風呂浴びて浴室を出ると、その日宿に着いた大きな武士が浴衣姿で手拭を下げているのと狭い廊下で会う。清兵衛は男のために道をあけると、男はじろりと清兵衛を見て通り過ぎる。やがて、風呂場で何か騒動が起き、その武士が死んだという。喉にくびった跡があり、主によれば、武士の最期の言葉は「手、手...」だったと。その武士の薩州の新納権右衛門といい、「白鳥」と名乗った武士と同一人物かどうかは分からないが、この事件の後、清兵衛の手の痛みはすっかりとれる―。
慶応2年5月、清兵衛は芸妓・お村との新生活のために、牛込・通寺町の人目につかない閑静な場所にある手ごろな家を見つける。その2階に2人で床を並べてうとうとした際に、腕を冷たい手で掴まれ、あまりに冷たいのでその手を引き寄せると、その手は手首だけで、肱までなかった。次の晩もその手は清兵衛の前に現れ、家主に問いただすと、前にその部屋に住んでいたのは白鳥という土佐藩の武士で、綺麗な御新造さんがいたが、急に国に帰ることになったという。清兵衛は市ヶ谷・谷町に居を移すが、前の部屋の梯子段の下の戸棚に蛆虫が蠢めいているのが見つかり、白鳥の妾の変死体が床下から発掘される。谷町の住居も1カ月と続かず、お村と清兵衛の関係はうまくいかなくなって、清兵衛はお村と別れる。さらに清兵衛の不幸は続き、梅雨の頃から自分の左手首が痛み出す。親戚の家に行った際にそこの子供が清兵衛を見て、「蒼い手、蒼い手...」といって怖がり、清兵衛は自分の手に女の死人の手がぶら下がっていることを初めて知る。その時から清兵衛は、物事の全てに対する気力を失い、塔の沢に長逗留することになる。ある日、夕食前に一風呂浴びて浴室を出ると、その日宿に着いた大きな武士が浴衣姿で手拭を下げているのと狭い廊下で会う。清兵衛は男のために道をあけると、男はじろりと清兵衛を見て通り過ぎる。やがて、風呂場で何か騒動が起き、その武士が死んだという。喉にくびった跡があり、主によれば、武士の最期の言葉は「手、手...」だったと。その武士の薩州の新納権右衛門といい、「白鳥」と名乗った武士と同一人物かどうかは分からないが、この事件の後、清兵衛の手の痛みはすっかりとれる―。 大佛次郎のこの作品は『見た人の怪談集』で読みましたが、歴史小説作家、大河小説作家のイメージがある作者が(実は小説だけでなく、戯曲や児童文学、ノンフィクションなど幅広い分野に作品を遺した作家だが)、こうしたキレのある短編も書いているというのが興味深かったです。清兵衛がノイローゼのようになって、物事の全てに気力を失い、大政奉還も戊辰戦争も清兵衛の頭上を通り過ぎていくわけで、阿部日奈子氏の解説にもありますが、(歴史小説作家でありながら)殆ど時代背景に触れないで描くことによって、祟られた男の孤独がより浮き彫りにされています。
大佛次郎のこの作品は『見た人の怪談集』で読みましたが、歴史小説作家、大河小説作家のイメージがある作者が(実は小説だけでなく、戯曲や児童文学、ノンフィクションなど幅広い分野に作品を遺した作家だが)、こうしたキレのある短編も書いているというのが興味深かったです。清兵衛がノイローゼのようになって、物事の全てに気力を失い、大政奉還も戊辰戦争も清兵衛の頭上を通り過ぎていくわけで、阿部日奈子氏の解説にもありますが、(歴史小説作家でありながら)殆ど時代背景に触れないで描くことによって、祟られた男の孤独がより浮き彫りにされています。 村山清(平田満)、美津子(岡江久美子)夫妻は、千葉県の郊外に念願の一戸建てを買い引っ越してきた。引越当日の深夜、2階寝室で寝ていた清の片腕に、突然女の手首がとりついた。夢だと思ったが、女の手首がとりついた左腕がだるくなってきた。クラシック音楽のトランペットの音色を聞いただけで、左腕が激しく痛みだしたり、3歳の甥が清の左腕に手首がぶらさがっていると恐がったり、美津子までノイローゼになりそうだった。ある日美津子は、この辺りで昔から開業している医者に、自分達が住んでいる場所の歴史を聞き出した。それによると、戦前は日本陸軍の兵営が近くにあり、ちょうど美津子達の家がある所に島倉という大尉の一家が住んでいた。島倉大尉(井上純一)と政略結婚をさせられた綾子(中島はるみ)という女性と、彼女に恋心をいだいた大尉の弟・康次郎に腹を立てた大尉が、軍刀で綾子の手首を切り落としたのだった―。
村山清(平田満)、美津子(岡江久美子)夫妻は、千葉県の郊外に念願の一戸建てを買い引っ越してきた。引越当日の深夜、2階寝室で寝ていた清の片腕に、突然女の手首がとりついた。夢だと思ったが、女の手首がとりついた左腕がだるくなってきた。クラシック音楽のトランペットの音色を聞いただけで、左腕が激しく痛みだしたり、3歳の甥が清の左腕に手首がぶらさがっていると恐がったり、美津子までノイローゼになりそうだった。ある日美津子は、この辺りで昔から開業している医者に、自分達が住んでいる場所の歴史を聞き出した。それによると、戦前は日本陸軍の兵営が近くにあり、ちょうど美津子達の家がある所に島倉という大尉の一家が住んでいた。島倉大尉(井上純一)と政略結婚をさせられた綾子(中島はるみ)という女性と、彼女に恋心をいだいた大尉の弟・康次郎に腹を立てた大尉が、軍刀で綾子の手首を切り落としたのだった―。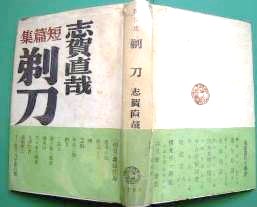

 麻布六本木で床屋を営む芳三郎は名人との声も名高い。しかし、今日はひどい風邪で寝込んでいる。ちょうど祭の前の忙しい時期だが、人手が足りない。以前雇っていた源公と治太公を解雇したからだ。芳三郎も以前は彼らと同じ小僧だったが、腕が認められて親方の娘と結婚し店を継いだ。以来、源公と治太公は素行が悪くなり、店の金に手を出すようになったので、芳三郎は二人を解雇したのだ。祭日前の稼ぎ時でありながら体は思うように動かない。妻のお梅は夫の体を気遣って休ませようとするが、その気遣いが芳三郎の神経を余計に苛立たせる。更に、研磨の依頼をされた剃刀のキレが悪いと客から文句があり、熱で震える手で研ぎ直すがうまくいかない。そこへ一人の若者が髭を剃りにやって来る。若者はこれから女郎屋にでも行くらしい。芳三郎は若者の髭を当たり始めるが、きちんと研げていない剃刀ではいつものように剃れない。若者はそれには構わず、やがて眠ってしまう。芳三郎は泣きたいような気持ちになるが、若者の方は大きな口を開けて眠っている。その時、剃刀が引っ掛かり、若者の喉から血が滲んだ。それまで客の顔を一度も傷つけたことのなかった芳三郎は、発作的に剃刀を逆手に持つと、刃が隠れるまで深く若者の喉に刺した。同時に、芳三郎の体には極度の疲労が戻ってきた。立ち尽くす芳三郎の姿を、三方に据えられた鏡だけが見つめていた―。
麻布六本木で床屋を営む芳三郎は名人との声も名高い。しかし、今日はひどい風邪で寝込んでいる。ちょうど祭の前の忙しい時期だが、人手が足りない。以前雇っていた源公と治太公を解雇したからだ。芳三郎も以前は彼らと同じ小僧だったが、腕が認められて親方の娘と結婚し店を継いだ。以来、源公と治太公は素行が悪くなり、店の金に手を出すようになったので、芳三郎は二人を解雇したのだ。祭日前の稼ぎ時でありながら体は思うように動かない。妻のお梅は夫の体を気遣って休ませようとするが、その気遣いが芳三郎の神経を余計に苛立たせる。更に、研磨の依頼をされた剃刀のキレが悪いと客から文句があり、熱で震える手で研ぎ直すがうまくいかない。そこへ一人の若者が髭を剃りにやって来る。若者はこれから女郎屋にでも行くらしい。芳三郎は若者の髭を当たり始めるが、きちんと研げていない剃刀ではいつものように剃れない。若者はそれには構わず、やがて眠ってしまう。芳三郎は泣きたいような気持ちになるが、若者の方は大きな口を開けて眠っている。その時、剃刀が引っ掛かり、若者の喉から血が滲んだ。それまで客の顔を一度も傷つけたことのなかった芳三郎は、発作的に剃刀を逆手に持つと、刃が隠れるまで深く若者の喉に刺した。同時に、芳三郎の体には極度の疲労が戻ってきた。立ち尽くす芳三郎の姿を、三方に据えられた鏡だけが見つめていた―。 この短編は、齋藤書店版('46年)、ちくま文庫版('08年)のほかに、新潮文庫版『清兵衛と瓢箪・網走まで』('68年)などにも収められていますが、最近では『文豪たちが書いた 怖い名作短編集』('13年/彩図社)にも入っています(ネットでは
この短編は、齋藤書店版('46年)、ちくま文庫版('08年)のほかに、新潮文庫版『清兵衛と瓢箪・網走まで』('68年)などにも収められていますが、最近では『文豪たちが書いた 怖い名作短編集』('13年/彩図社)にも入っています(ネットでは この作品のテーマについては、ちょっとした「気分」に引き摺られて社会から逸脱してしまうことの怖さを描いたものである(荒井均氏)とか、或いはラストの鏡に注目し、殺人にまで至る心身の感覚を不合理として纏めてしまう客観性(紅野謙介氏)であるとか諸説あるようです。また以前に、FM J-WAVE の「BOOK BAR」(ナビゲーターは大倉眞一郎と杏)で、ゲストのシンガーソングライターの吉澤嘉代子氏が、「剃刀」は「男性器」の象徴だと思ったと言っていました。ホント色々な見方があって、読書会などで取り上げられることが多い作品ではないかと想像します。
この作品のテーマについては、ちょっとした「気分」に引き摺られて社会から逸脱してしまうことの怖さを描いたものである(荒井均氏)とか、或いはラストの鏡に注目し、殺人にまで至る心身の感覚を不合理として纏めてしまう客観性(紅野謙介氏)であるとか諸説あるようです。また以前に、FM J-WAVE の「BOOK BAR」(ナビゲーターは大倉眞一郎と杏)で、ゲストのシンガーソングライターの吉澤嘉代子氏が、「剃刀」は「男性器」の象徴だと思ったと言っていました。ホント色々な見方があって、読書会などで取り上げられることが多い作品ではないかと想像します。

 振り返ってみて、剃られる側に立って想像しても怖い話かと思います。個人的には久しく床屋で顔を剃ってもらったことはないけれど、以前に床屋で剃ってもらっていた頃、その最中にちらっと「今この床屋さんが発狂したら...」と考えた怖い想像も後から甦ってきました。但し、この短編の怖さは、やはり自分がどこかの場面で、芳三郎と同じような行動に出るのではないかという不確実性に対する怖さ(不安)の方が上ではないかと思います。
振り返ってみて、剃られる側に立って想像しても怖い話かと思います。個人的には久しく床屋で顔を剃ってもらったことはないけれど、以前に床屋で剃ってもらっていた頃、その最中にちらっと「今この床屋さんが発狂したら...」と考えた怖い想像も後から甦ってきました。但し、この短編の怖さは、やはり自分がどこかの場面で、芳三郎と同じような行動に出るのではないかという不確実性に対する怖さ(不安)の方が上ではないかと思います。

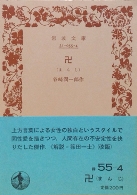


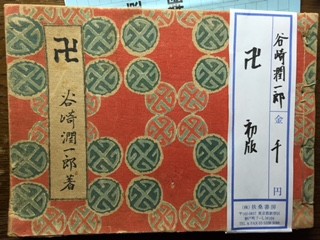 弁護士の夫に不満のある若い妻・柿内園子は、技芸学校の絵画教室で出会った徳光光子と禁断の関係に落ちる。しかし奔放で妖艶な光子は、一方で異性の愛人・綿貫とも交際していることが分かり、園子は光子への狂おしいまでの情欲と独占欲に苦しむ。更に、互いを縛る情欲の絡み合いは、園子の夫・孝太郎をも巻き込み、園子は死を思いつめるが―。
弁護士の夫に不満のある若い妻・柿内園子は、技芸学校の絵画教室で出会った徳光光子と禁断の関係に落ちる。しかし奔放で妖艶な光子は、一方で異性の愛人・綿貫とも交際していることが分かり、園子は光子への狂おしいまでの情欲と独占欲に苦しむ。更に、互いを縛る情欲の絡み合いは、園子の夫・孝太郎をも巻き込み、園子は死を思いつめるが―。 谷崎潤一郎は1923(大正12)年の関東大震災を契機にその年に関西に移住しており、移住前から構想があった『痴人の愛』の舞台は東京ですが、『春琴抄』の舞台は大阪、『蓼喰う虫』は大阪と兵庫(須磨)、そしてこの『卍』も、主人公の園子の自宅は西宮の香櫨園海岸にあるという設定になっています。
谷崎潤一郎は1923(大正12)年の関東大震災を契機にその年に関西に移住しており、移住前から構想があった『痴人の愛』の舞台は東京ですが、『春琴抄』の舞台は大阪、『蓼喰う虫』は大阪と兵庫(須磨)、そしてこの『卍』も、主人公の園子の自宅は西宮の香櫨園海岸にあるという設定になっています。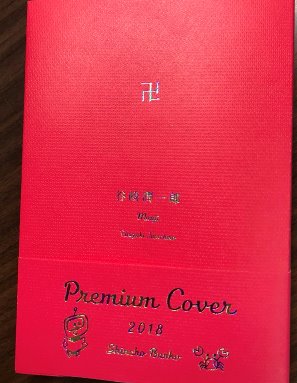 光子という一人の妖婦に周囲の3人の大人(園子、綿貫、孝太郎)が翻弄され、とりわけ園子と孝太郎が夫婦ごと光子の奴隷のような存在になっていく過程が凄いなあと思います。光子は、周囲を巻き込んでいくという点で、『痴人の愛』のナオミにも通じる気がしました。また、園子がどこまでを計算して、どこまでを無意識でやっているのかが読者にもすぐには判別しかねるという点では、作者の後の作品『鍵』(1956年)の郁子にも通じるものがあるように思います。
光子という一人の妖婦に周囲の3人の大人(園子、綿貫、孝太郎)が翻弄され、とりわけ園子と孝太郎が夫婦ごと光子の奴隷のような存在になっていく過程が凄いなあと思います。光子は、周囲を巻き込んでいくという点で、『痴人の愛』のナオミにも通じる気がしました。また、園子がどこまでを計算して、どこまでを無意識でやっているのかが読者にもすぐには判別しかねるという点では、作者の後の作品『鍵』(1956年)の郁子にも通じるものがあるように思います。






 (上巻)元禄太平に勃発した浅野内匠頭の刃傷事件から、仇討ちに怯える上杉・吉良側の困惑、茶屋遊びに耽る大石内蔵助の心の内が、登場人物の内面に分け入った迫力ある筆致で描かれる。虚無的な浪人堀田隼人、怪盗蜘蛛の陣十郎、謎の女お仙ら、魅力的な人物が物語を彩り、鮮やかな歴史絵巻が華開く―。(下巻)二度目の夏が過ぎた。主君の復讐に燃える赤穂浪士。未だ動きを見せない大石内蔵助の真意を図りかね、若き急進派は苛立ちを募らせる。対する上杉・吉良側も周到な権謀術数を巡らし、小競り合いが頻発する。そして、大願に向け、遂に内蔵助が動き始めた。呉服屋に、医者に姿を変え、江戸の町に潜んでいた浪士たちが、次々と結集する―。[新潮文庫ブックカバーあらすじより]
(上巻)元禄太平に勃発した浅野内匠頭の刃傷事件から、仇討ちに怯える上杉・吉良側の困惑、茶屋遊びに耽る大石内蔵助の心の内が、登場人物の内面に分け入った迫力ある筆致で描かれる。虚無的な浪人堀田隼人、怪盗蜘蛛の陣十郎、謎の女お仙ら、魅力的な人物が物語を彩り、鮮やかな歴史絵巻が華開く―。(下巻)二度目の夏が過ぎた。主君の復讐に燃える赤穂浪士。未だ動きを見せない大石内蔵助の真意を図りかね、若き急進派は苛立ちを募らせる。対する上杉・吉良側も周到な権謀術数を巡らし、小競り合いが頻発する。そして、大願に向け、遂に内蔵助が動き始めた。呉服屋に、医者に姿を変え、江戸の町に潜んでいた浪士たちが、次々と結集する―。[新潮文庫ブックカバーあらすじより]
 大佛次郎(1897-1973)の歴史時代小説で、1927(昭和2)年5月から翌年11月まで毎日新聞の前身にあたる「東京日日新聞」に岩田専太郎の挿絵で連載された新聞小説です。1928(昭和3)年10月に改造社より上巻が発売されるや15万部を売り切って当時としては大ベストセラーとなり、中巻が同年11月、下巻が翌年8月に刊行されています。
大佛次郎(1897-1973)の歴史時代小説で、1927(昭和2)年5月から翌年11月まで毎日新聞の前身にあたる「東京日日新聞」に岩田専太郎の挿絵で連載された新聞小説です。1928(昭和3)年10月に改造社より上巻が発売されるや15万部を売り切って当時としては大ベストセラーとなり、中巻が同年11月、下巻が翌年8月に刊行されています。
 しょうか。'61年版の片岡千恵蔵が自身4度目の大石内蔵助を演じた「赤穂浪士」では、堀田隼人(大友柳太郎)はともかく、蜘蛛の陣十郎はもう登場しません。但し、1964年の長谷川一夫が内蔵助を演じたNHKの第2回大河ドラマ「赤穂浪士」では、堀田隼人(林与一)も蜘蛛の陣十郎(宇野重吉)も隠密のお仙(淡島千景)も出てきます。
しょうか。'61年版の片岡千恵蔵が自身4度目の大石内蔵助を演じた「赤穂浪士」では、堀田隼人(大友柳太郎)はともかく、蜘蛛の陣十郎はもう登場しません。但し、1964年の長谷川一夫が内蔵助を演じたNHKの第2回大河ドラマ「赤穂浪士」では、堀田隼人(林与一)も蜘蛛の陣十郎(宇野重吉)も隠密のお仙(淡島千景)も出てきます。


 この大佛次郎の小説が作者の大石内蔵助や赤穂浪士に対する見解が多分に入りながらも"オーソドックス(正統)"とされるのは、その後に今日までもっともっと変則的な"忠臣蔵"小説やドラマがいっぱい出て
この大佛次郎の小説が作者の大石内蔵助や赤穂浪士に対する見解が多分に入りながらも"オーソドックス(正統)"とされるのは、その後に今日までもっともっと変則的な"忠臣蔵"小説やドラマがいっぱい出て 「赤穂浪士」(NHK大河ドラマ)●演出:井上博 他●制作総指揮:合川明●脚本:村上元三
「赤穂浪士」(NHK大河ドラマ)●演出:井上博 他●制作総指揮:合川明●脚本:村上元三 ●音楽:
●音楽:

 田村高廣 NHK大河ドラマ出演歴
田村高廣 NHK大河ドラマ出演歴


 『
『 NHK土曜ドラマ「夏目漱石の妻」(出演:尾野真千子、長谷川博己)を偶々見て、結構面白く感じられ(尾野真千子はやはり演技が上手く、長谷川博己も舞台で蜷川幸雄に鍛えられただけのことはあった)、それに触発されてこの原作本を手にしました。
NHK土曜ドラマ「夏目漱石の妻」(出演:尾野真千子、長谷川博己)を偶々見て、結構面白く感じられ(尾野真千子はやはり演技が上手く、長谷川博己も舞台で蜷川幸雄に鍛えられただけのことはあった)、それに触発されてこの原作本を手にしました。
 原作は、夏目漱石(1867-1916/享年49)の妻・夏目鏡子(1877-1963/享年85)が1928(昭和3)年に漱石との結婚生活を口述し、それを漱石の弟子で長女・筆子の夫の松岡譲(1891-1969/享年77)が筆録して雑誌「改造」に連載したもので、1928年11月に『漱石の思ひ出』として改造社から刊行され、その時は60点余りの写真入りであったのが、翌1929(昭和4)年10月に同じカバーデザインで写真を割愛し、代わりに付
原作は、夏目漱石(1867-1916/享年49)の妻・夏目鏡子(1877-1963/享年85)が1928(昭和3)年に漱石との結婚生活を口述し、それを漱石の弟子で長女・筆子の夫の松岡譲(1891-1969/享年77)が筆録して雑誌「改造」に連載したもので、1928年11月に『漱石の思ひ出』として改造社から刊行され、その時は60点余りの写真入りであったのが、翌1929(昭和4)年10月に同じカバーデザインで写真を割愛し、代わりに付
 それまでの漱石は「DV夫」であり、その暴力は子どもにまでも及び、それはドラマでも描かれていましたが(例えば火鉢の淵に五厘銭があっただけで、ロンドンでの経験と勝手に結びつけて自分が馬鹿にされていると思い込み、娘である筆子を殴ったりした)、「吾輩は猫である」を書き始めてからも、向いの下宿屋の書生に、「おい、探偵君。今日は何時に学校にいくのかね」と呼びかけたりして、書生が自分の事をスパイしていると思い込んだりしているなど(これもドラマで描かれていた)、"病気"が治っていたわけではないのだなあと。英国留学から戻って来て以降は、ずっとそうした"病気"と共存して生きる人生であったのだなあと思いました。
それまでの漱石は「DV夫」であり、その暴力は子どもにまでも及び、それはドラマでも描かれていましたが(例えば火鉢の淵に五厘銭があっただけで、ロンドンでの経験と勝手に結びつけて自分が馬鹿にされていると思い込み、娘である筆子を殴ったりした)、「吾輩は猫である」を書き始めてからも、向いの下宿屋の書生に、「おい、探偵君。今日は何時に学校にいくのかね」と呼びかけたりして、書生が自分の事をスパイしていると思い込んだりしているなど(これもドラマで描かれていた)、"病気"が治っていたわけではないのだなあと。英国留学から戻って来て以降は、ずっとそうした"病気"と共存して生きる人生であったのだなあと思いました。 鏡子については悪妻説が根強くあるようですが、これを読むと、確かに言われているように鏡子が産後のヒステリーで精神不安定になった時期もあるようですが、やっぱりどうしょうも無く勝手なのは漱石の方で、それを大きく包み込んでいるのが鏡子であるというのが全体としての印象です。ドラマのラストで(おそらく善光寺への講演旅行に鏡子が同伴した際の一コマかと思われるが)、鏡子が漱石に「坊ちゃん」の中に出てくる"坊っちゃん"を小さい頃から可愛がってくれた下女・清(キヨ)のモデルは私でしょうと問う場面が
鏡子については悪妻説が根強くあるようですが、これを読むと、確かに言われているように鏡子が産後のヒステリーで精神不安定になった時期もあるようですが、やっぱりどうしょうも無く勝手なのは漱石の方で、それを大きく包み込んでいるのが鏡子であるというのが全体としての印象です。ドラマのラストで(おそらく善光寺への講演旅行に鏡子が同伴した際の一コマかと思われるが)、鏡子が漱石に「坊ちゃん」の中に出てくる"坊っちゃん"を小さい頃から可愛がってくれた下女・清(キヨ)のモデルは私でしょうと問う場面が ありますが、これはドラマのオリジナルです。漱石の孫にあたる夏目房之介氏が、鏡子の本名がキヨであることに注目し
ありますが、これはドラマのオリジナルです。漱石の孫にあたる夏目房之介氏が、鏡子の本名がキヨであることに注目し て、「坊っちゃん」という作品が漱石から鏡子に宛てたラブレターだったのではないか、と指摘しており、それをドラマに反映させたのではないかと思われます。
て、「坊っちゃん」という作品が漱石から鏡子に宛てたラブレターだったのではないか、と指摘しており、それをドラマに反映させたのではないかと思われます。


 竹中直人(夏目金之助(漱石)の養父・塩原昌之助。かつては羽振りが良かったものの、いまは落ちぶれてたびたび金之助の元を訪れては、金銭的な援助を求める)
竹中直人(夏目金之助(漱石)の養父・塩原昌之助。かつては羽振りが良かったものの、いまは落ちぶれてたびたび金之助の元を訪れては、金銭的な援助を求める)


 脚本:池端俊策/主演:長谷川博己「
脚本:池端俊策/主演:長谷川博己「


 三雲医院の三雲八春(柳永二郎)は戦争で一人息子を失い、甥の伍助(増田順二)を院長に迎えて戦後再出発してから1年になる。その1周年記念日、伍助院長は看護婦の
三雲医院の三雲八春(柳永二郎)は戦争で一人息子を失い、甥の伍助(増田順二)を院長に迎えて戦後再出発してから1年になる。その1周年記念日、伍助院長は看護婦の 瀧さん(岸惠子)らと温泉へ行き、三雲医院は「本日休診」の札を掲げる。八春先生がゆっくり昼寝でもと思った矢先、婆やのお京(長岡輝子)の息子勇作(三國連太郎)が例の発作を起こしたという。勇作は軍隊生活の悪夢に憑かれており、時折いきなり部隊長となって皆に号令、遥拝を命じるため、八春先生は彼の部下になったふりをして
瀧さん(岸惠子)らと温泉へ行き、三雲医院は「本日休診」の札を掲げる。八春先生がゆっくり昼寝でもと思った矢先、婆やのお京(長岡輝子)の息子勇作(三國連太郎)が例の発作を起こしたという。勇作は軍隊生活の悪夢に憑かれており、時折いきなり部隊長となって皆に号令、遥拝を命じるため、八春先生は彼の部下になったふりをして 気を鎮めてやらなければならなかった。勇作が落着いたら、今度は警察の松木ポリス(十朱久雄)が大阪から知り合いを頼って上京したばかりで深夜暴漢に襲われ
気を鎮めてやらなければならなかった。勇作が落着いたら、今度は警察の松木ポリス(十朱久雄)が大阪から知り合いを頼って上京したばかりで深夜暴漢に襲われ たあげく持物を奪われた悠子(角梨枝子)という娘を連れて来る。折から18年前帝王切開で母子共八春先生に助けられた湯川三千代(田村秋子)が来て、悠子に同情してその家へ連れて帰る。が、八春先生はそれでも暇にならず、砂礫船の船頭の女房のお産あり、町のヤクザ加吉(鶴田浩二)が指をつめるのに麻酔を打ってくれとやって来たのを懇々と説教もし
たあげく持物を奪われた悠子(角梨枝子)という娘を連れて来る。折から18年前帝王切開で母子共八春先生に助けられた湯川三千代(田村秋子)が来て、悠子に同情してその家へ連れて帰る。が、八春先生はそれでも暇にならず、砂礫船の船頭の女房のお産あり、町のヤクザ加吉(鶴田浩二)が指をつめるのに麻酔を打ってくれとやって来たのを懇々と説教もし てやらねばならず、悠子を襲った暴漢の連
てやらねばならず、悠子を襲った暴漢の連 れの女が留置場で仮病を起こし、兵隊服の男(多々良純)が盲腸患者をかつぎ込んで来て手術をしろという。かと思うとまたお産があるという風で、「休診日」は八春先生には大変多忙な一日となる。悠子は三千代の息子・湯川春三(佐田啓二)の世話で会社に勤め、加吉はやくざから足を
れの女が留置場で仮病を起こし、兵隊服の男(多々良純)が盲腸患者をかつぎ込んで来て手術をしろという。かと思うとまたお産があるという風で、「休診日」は八春先生には大変多忙な一日となる。悠子は三千代の息子・湯川春三(佐田啓二)の世話で会社に勤め、加吉はやくざから足を 洗って恋人のお町(淡島千景)という飲み屋の女と世帯を持とうと考える。しかしお町が金のため成金の蓑島の自由になったときいて、その蓑島を脅
洗って恋人のお町(淡島千景)という飲み屋の女と世帯を持とうと考える。しかしお町が金のため成金の蓑島の自由になったときいて、その蓑島を脅 迫に行き、お町はお町で蓑島の子を流産して八春先生の所へ担ぎ込まれる。兵隊服の男は、治療費が払えず窓から逃げ出すし、加吉は再び賭博で挙げられる。お町は一時危うかったがどうやら持ち直す。そんな中、また勇作の集合命令がかかり、その号令で夜空を横切って行く雁に向かって敬礼する八春先生だった―。
迫に行き、お町はお町で蓑島の子を流産して八春先生の所へ担ぎ込まれる。兵隊服の男は、治療費が払えず窓から逃げ出すし、加吉は再び賭博で挙げられる。お町は一時危うかったがどうやら持ち直す。そんな中、また勇作の集合命令がかかり、その号令で夜空を横切って行く雁に向かって敬礼する八春先生だった―。

 主人公の「医は仁術なり」を体現しているかのような八春先生を演じた柳永二郎は、黒澤明監督の「
主人公の「医は仁術なり」を体現しているかのような八春先生を演じた柳永二郎は、黒澤明監督の「 いました。セット撮影部分は多分に演劇的ですが(
いました。セット撮影部分は多分に演劇的ですが( そのことを見越してか、タイトルバックとスチール写真の背景は敢えて書割りにしている)、そうい言えば黒澤明の「
そのことを見越してか、タイトルバックとスチール写真の背景は敢えて書割りにしている)、そうい言えば黒澤明の「
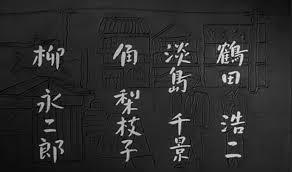 クレジットでは、鶴田浩二(「
クレジットでは、鶴田浩二(「 この作品を観た人の中には、三國連太郎が演じた「遥拝隊長」こと勇作がやけに印象に残ったという人が多いですが、このキャラクターは
この作品を観た人の中には、三國連太郎が演じた「遥拝隊長」こと勇作がやけに印象に残ったという人が多いですが、このキャラクターは 原作「本日休診」にはありません。1950(昭和25)年発表の「遥拝隊長」(新潮文庫『遥拝隊長・本日休診』に所収)の主人公・岡崎悠一を持ってきたものです。彼はある種の戦争後遺症的な精神の病いであるわけですが、原作にはその経緯が書かれているので読んでみるのもいいでしょう。また、映画の終盤で、警察による賭場のガサ入れシーンがありますが、これは「多甚古村」にある"大捕物"を反映させたのではないかと思います。
原作「本日休診」にはありません。1950(昭和25)年発表の「遥拝隊長」(新潮文庫『遥拝隊長・本日休診』に所収)の主人公・岡崎悠一を持ってきたものです。彼はある種の戦争後遺症的な精神の病いであるわけですが、原作にはその経緯が書かれているので読んでみるのもいいでしょう。また、映画の終盤で、警察による賭場のガサ入れシーンがありますが、これは「多甚古村」にある"大捕物"を反映させたのではないかと思います。 脚本は、「
脚本は、「 この映画のスチール写真で、お町(淡島千景)らが揃って"遥拝"しているものがあり、ラストシーンかと思いましたが、ラストで勇作(三國連太郎)が集合をかけた時、お町は床に臥せており、これはスチールのためのものでしょう(背景も書割りになっている)。こうした実際には無いシーンでスチールを作るのは好きになれないけれど、作品自体は佳作です。その時代でないと作れない作品というのもあるかも。過去5回テレビドラマ化されていて、実際に観たわけではないですが、時が経てば経つほど元の映画を超えるのはなかなか難しくなってくるような気がします(今世紀になってからは一度も映像化されていない)。
この映画のスチール写真で、お町(淡島千景)らが揃って"遥拝"しているものがあり、ラストシーンかと思いましたが、ラストで勇作(三國連太郎)が集合をかけた時、お町は床に臥せており、これはスチールのためのものでしょう(背景も書割りになっている)。こうした実際には無いシーンでスチールを作るのは好きになれないけれど、作品自体は佳作です。その時代でないと作れない作品というのもあるかも。過去5回テレビドラマ化されていて、実際に観たわけではないですが、時が経てば経つほど元の映画を超えるのはなかなか難しくなってくるような気がします(今世紀になってからは一度も映像化されていない)。
 「本日休診」●制作年:1939年●監督:渋谷実●脚本:斎藤良輔●撮影:長岡博之●音楽 吉沢博/奥村一●原作:井伏鱒二●時間:97分●出演:柳永二郎/淡島千景/鶴田浩二/角梨枝子/長岡輝子/三國連太郎/田村秋子/佐田啓二/岸恵子/市川紅梅
「本日休診」●制作年:1939年●監督:渋谷実●脚本:斎藤良輔●撮影:長岡博之●音楽 吉沢博/奥村一●原作:井伏鱒二●時間:97分●出演:柳永二郎/淡島千景/鶴田浩二/角梨枝子/長岡輝子/三國連太郎/田村秋子/佐田啓二/岸恵子/市川紅梅 (市川翠扇)/中村伸郎/十朱久雄/増田順司/望月優子/諸角啓二郎/紅沢葉子/山路義人/水上令子/稲川忠完/多々良純●公開:1952/02●配給:松竹(評価:★★★★)
(市川翠扇)/中村伸郎/十朱久雄/増田順司/望月優子/諸角啓二郎/紅沢葉子/山路義人/水上令子/稲川忠完/多々良純●公開:1952/02●配給:松竹(評価:★★★★) 
![鞍馬天狗 角兵衛獅子 [VHS].jpg](http://hurec.bz/book-movie/%E9%9E%8D%E9%A6%AC%E5%A4%A9%E7%8B%97%20%E8%A7%92%E5%85%B5%E8%A1%9B%E7%8D%85%E5%AD%90%20%5BVHS%5D.jpg)
 嵐 寛寿郎
嵐 寛寿郎 節分祭で賑わう壬生寺の境内の人波の中、子供角兵衛獅子の杉作(宗春太郎)と新吉(旗桃太郎)は財布を落としてしまう。角兵衛獅子の元締めで御用聞き(岡っ引き)隼の長七(瀬川路三郎)の所へ戻れば厳しい折檻を受けるのは明らかで、松月院の寺門の前で途方に暮れていると、通りがかった覆面の侍が二人に一両を恵んでくれた。子供達のその金を見た長七は子供達を問い詰め、その松月院の和尚(藤川三之祐)の所に居る倉田典膳を名乗る侍こそ、かねがね新撰組の近藤勇(河部五郎)、土方歳三(尾上華丈)らから居所を探るよう言われていた鞍馬天狗(嵐寛寿郎)だと確信する。長七はこれを近藤らに告げ、一味は松月院を襲撃する。敵をかわし、炎に包まれた松月院から脱出した天狗は、杉作と新吉を西郷吉之助(志村喬)の居る薩摩屋敷へ預ける。しかし子供達は長七らに捕らえられ、大坂城代屋敷の牢に入れられる。折しも大坂の浪士の手入れが迫っており、天狗は子供達を救うべく、また、浪士の人別帳を奪うべく、罠と知りながら大坂城代屋敷へ乗り込む―。
節分祭で賑わう壬生寺の境内の人波の中、子供角兵衛獅子の杉作(宗春太郎)と新吉(旗桃太郎)は財布を落としてしまう。角兵衛獅子の元締めで御用聞き(岡っ引き)隼の長七(瀬川路三郎)の所へ戻れば厳しい折檻を受けるのは明らかで、松月院の寺門の前で途方に暮れていると、通りがかった覆面の侍が二人に一両を恵んでくれた。子供達のその金を見た長七は子供達を問い詰め、その松月院の和尚(藤川三之祐)の所に居る倉田典膳を名乗る侍こそ、かねがね新撰組の近藤勇(河部五郎)、土方歳三(尾上華丈)らから居所を探るよう言われていた鞍馬天狗(嵐寛寿郎)だと確信する。長七はこれを近藤らに告げ、一味は松月院を襲撃する。敵をかわし、炎に包まれた松月院から脱出した天狗は、杉作と新吉を西郷吉之助(志村喬)の居る薩摩屋敷へ預ける。しかし子供達は長七らに捕らえられ、大坂城代屋敷の牢に入れられる。折しも大坂の浪士の手入れが迫っており、天狗は子供達を救うべく、また、浪士の人別帳を奪うべく、罠と知りながら大坂城代屋敷へ乗り込む―。
 また、鞍馬天狗のことを仇だと誤解して新撰組の手先になって天狗を付け狙うものの、天狗に命を救われたことで最後は天狗に惹かれていく女性(この作品では"暗闇のお兼")を原駒子(1910-68)が演じていて(当時28歳)、これも雰囲気があって悪くなかったです。
また、鞍馬天狗のことを仇だと誤解して新撰組の手先になって天狗を付け狙うものの、天狗に命を救われたことで最後は天狗に惹かれていく女性(この作品では"暗闇のお兼")を原駒子(1910-68)が演じていて(当時28歳)、これも雰囲気があって悪くなかったです。 1951年松竹版ではこの女性に相当する役("礫のお喜代")を山田五十鈴(1917-2012)が演じていますが、14歳の美空ひばり演じる杉作が34歳の山田五十鈴に天狗との関係において嫉妬心を覚える場面があります(あくまでも少年としての嫉妬心として描かれているが、もともと美空ひばり自体が若干"おませさん"に見えるため、そうした原作にはないニュアンスを盛り込んだのではないか)。
1951年松竹版ではこの女性に相当する役("礫のお喜代")を山田五十鈴(1917-2012)が演じていますが、14歳の美空ひばり演じる杉作が34歳の山田五十鈴に天狗との関係において嫉妬心を覚える場面があります(あくまでも少年としての嫉妬心として描かれているが、もともと美空ひばり自体が若干"おませさん"に見えるため、そうした原作にはないニュアンスを盛り込んだのではないか)。 嵐寛寿郎の鞍馬天狗は、この1938年日活版の時に既にスタイルは完成されているように見えますが(刀を突きつけるだけで相手を後ずさりさせる迫力はピカイチ)、その後のシリーズの経過とともに、嵐寛寿郎の天狗も少しずつ変わってきているのも確かです。では、最初はどうだったのか。現在観ることの出来る最も古い「鞍馬天狗」は1928年の嵐寛寿郎プロダクションの第1作「鞍馬天狗」ですが(この頃はまだ無声映画)、天狗や杉作などはどのように描かれているのでしょうか。DVD化されていますが未見であり、個人的には今の時点ではこの1938年日活版が嵐寛寿郎版「鞍馬天狗」の原点的作品です。
嵐寛寿郎の鞍馬天狗は、この1938年日活版の時に既にスタイルは完成されているように見えますが(刀を突きつけるだけで相手を後ずさりさせる迫力はピカイチ)、その後のシリーズの経過とともに、嵐寛寿郎の天狗も少しずつ変わってきているのも確かです。では、最初はどうだったのか。現在観ることの出来る最も古い「鞍馬天狗」は1928年の嵐寛寿郎プロダクションの第1作「鞍馬天狗」ですが(この頃はまだ無声映画)、天狗や杉作などはどのように描かれているのでしょうか。DVD化されていますが未見であり、個人的には今の時点ではこの1938年日活版が嵐寛寿郎版「鞍馬天狗」の原点的作品です。 因みに、自分が個人的に鞍馬天狗というものに初めて触れたのはそのパロディの方で、1959年9月2日から1960年12月24日までよみうりテレビ制作・日本テレビ系列で放送されていた、花登筺脚本、大村崑主演による「頓馬天狗」(とんまてんぐ)になります。コント的要素やスラップスティックによる笑いを多用し、毎回、大村崑扮する"頓馬天狗"の行く先々で敵役である"珍選組"の土方(土方大三:芦屋雁之助)、近藤(近藤勇造:芦屋小雁)が現れては頓馬天狗に斬られてしまい、再び繰り返すという、所謂"アチャラカもの"でした。「片手抜刀」など、大村崑のトリッキーで身軽な殺陣が人気となり、主人公の"頓馬天狗"の本名はスポンサー・大塚製薬のメイン
因みに、自分が個人的に鞍馬天狗というものに初めて触れたのはそのパロディの方で、1959年9月2日から1960年12月24日までよみうりテレビ制作・日本テレビ系列で放送されていた、花登筺脚本、大村崑主演による「頓馬天狗」(とんまてんぐ)になります。コント的要素やスラップスティックによる笑いを多用し、毎回、大村崑扮する"頓馬天狗"の行く先々で敵役である"珍選組"の土方(土方大三:芦屋雁之助)、近藤(近藤勇造:芦屋小雁)が現れては頓馬天狗に斬られてしまい、再び繰り返すという、所謂"アチャラカもの"でした。「片手抜刀」など、大村崑のトリッキーで身軽な殺陣が人気となり、主人公の"頓馬天狗"の本名はスポンサー・大塚製薬のメイン 商品名「オロナイン軟膏」の読みを模して、決め台詞は「姓は尾呂内(オロナイン)、名は南公(軟膏)」、大村崑が番組内で生コマーシャ
商品名「オロナイン軟膏」の読みを模して、決め台詞は「姓は尾呂内(オロナイン)、名は南公(軟膏)」、大村崑が番組内で生コマーシャ ルをやっていました(後の「
ルをやっていました(後の「 「頓馬天狗」(お笑い珍勇伝 頓馬天狗⇒崑ちゃんのとんま天狗)●脚本:花登筺●演出:香坂信之●音楽:加納光記(オープニング:大村崑、かなりや子供会「とんとんとんまの天狗さん」(作詞:花登筺、作曲:加納光記))●出演:大村崑/芦屋雁之助/芦屋小雁/夢路いとし・喜味こいし/三木のり平●放映:1959/09~1960/12(全70回)●放送局:日本テレビ
「頓馬天狗」(お笑い珍勇伝 頓馬天狗⇒崑ちゃんのとんま天狗)●脚本:花登筺●演出:香坂信之●音楽:加納光記(オープニング:大村崑、かなりや子供会「とんとんとんまの天狗さん」(作詞:花登筺、作曲:加納光記))●出演:大村崑/芦屋雁之助/芦屋小雁/夢路いとし・喜味こいし/三木のり平●放映:1959/09~1960/12(全70回)●放送局:日本テレビ 「鞍馬天狗 角兵衛獅子の巻」●制作年:1938年●監督:マキノ正博/松田定次●脚本:比佐芳武●撮影:宮川一夫/松井鴻●音楽:高橋半●原作:大仏次郎●時間:66分(現存53分)●出演:嵐寛寿郎/原健作/瀬川路三郎/香川良介/藤川三之祐/尾上華丈/志村喬/団徳麿/阪東国太郎/宗春太郎(香川良介の息子)/旗桃太郎/深水藤子/原駒子/沢村国太郎/河部五郎●公開:1938/03/15●配給:日活京都(評価:★★★☆) 嵐寛寿郎・原駒子 in「鞍馬天狗 角兵衛獅子の巻」('38年)
「鞍馬天狗 角兵衛獅子の巻」●制作年:1938年●監督:マキノ正博/松田定次●脚本:比佐芳武●撮影:宮川一夫/松井鴻●音楽:高橋半●原作:大仏次郎●時間:66分(現存53分)●出演:嵐寛寿郎/原健作/瀬川路三郎/香川良介/藤川三之祐/尾上華丈/志村喬/団徳麿/阪東国太郎/宗春太郎(香川良介の息子)/旗桃太郎/深水藤子/原駒子/沢村国太郎/河部五郎●公開:1938/03/15●配給:日活京都(評価:★★★☆) 嵐寛寿郎・原駒子 in「鞍馬天狗 角兵衛獅子の巻」('38年)


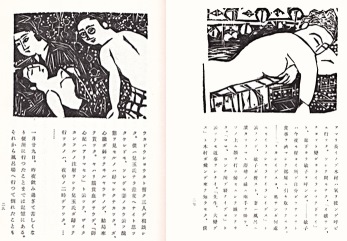 ・敏子に縁談相手として紹介した学生・木村を最後の一線を越えない限界まで接近させようとし、酔い潰れ浴室で全裸で倒れた郁子を木村に運ばせたり、昏睡する郁子の裸体を撮影し、その現像を木村に頼むなどした経緯を日記に書いていく。同時に妻・郁子も日記を書いている。大学教授は妻に日記を盗み読んでほしいことを自らの日記に書き、日記を隠している抽斗の鍵をわざと落とすが、郁子は夫の日記を盗み読む気はないと日記に書く。また郁子は夫を性的に興奮させるために、嫌々ながら敢えて木村と接近するのだ、自分も日記を書いていることを夫は知らないはずだとも日記に書く。また木村も大学教授の計画に積極的に協力していく。娘・敏子は母に不倫を強要する父に反発しているようだと郁子は日記に書く。大学教授は性的興奮を得るため医者の警告を無視して摂生を行わず、遂に病に倒れて亡くなった夫の死後、郁子は、実は自分は以前から夫の日記を盗み読んでおり、自分の日記を夫が盗み読んでいることも知っていて夫を性的に興奮させ不摂生な生活に追い込み病死させるため日記に嘘を書いていた、娘・敏子も自分に協力していて、本当は積極的に木村と不倫して肉体関係を持っていたと日記に書く。木村は世間を偽装するため形式的に敏子と結婚し、その母である郁子と同居することで、実質的に郁子と結婚生活をする計画を練っていると、郁子は日記に書くのだった―。
・敏子に縁談相手として紹介した学生・木村を最後の一線を越えない限界まで接近させようとし、酔い潰れ浴室で全裸で倒れた郁子を木村に運ばせたり、昏睡する郁子の裸体を撮影し、その現像を木村に頼むなどした経緯を日記に書いていく。同時に妻・郁子も日記を書いている。大学教授は妻に日記を盗み読んでほしいことを自らの日記に書き、日記を隠している抽斗の鍵をわざと落とすが、郁子は夫の日記を盗み読む気はないと日記に書く。また郁子は夫を性的に興奮させるために、嫌々ながら敢えて木村と接近するのだ、自分も日記を書いていることを夫は知らないはずだとも日記に書く。また木村も大学教授の計画に積極的に協力していく。娘・敏子は母に不倫を強要する父に反発しているようだと郁子は日記に書く。大学教授は性的興奮を得るため医者の警告を無視して摂生を行わず、遂に病に倒れて亡くなった夫の死後、郁子は、実は自分は以前から夫の日記を盗み読んでおり、自分の日記を夫が盗み読んでいることも知っていて夫を性的に興奮させ不摂生な生活に追い込み病死させるため日記に嘘を書いていた、娘・敏子も自分に協力していて、本当は積極的に木村と不倫して肉体関係を持っていたと日記に書く。木村は世間を偽装するため形式的に敏子と結婚し、その母である郁子と同居することで、実質的に郁子と結婚生活をする計画を練っていると、郁子は日記に書くのだった―。

 結局、大学教授自らが書いているように、「つまり、それぞれ違った思わくがあるらしいが、妻が出来るだけ堕落するように意図し、それに向って一生懸命になっている点では四人とも一致している」ということになり、但し、自らの思惑を最後に実現しそうなのは郁子か―といったような話のように思います。ファム・ファタール的作品と言うか、公序良俗といった概念を破壊してみせた作品かもしれず、また、ジャン=ポール・サルトルが、女性は「共犯者」の境遇にあると言っていたけれど、まさにその通りの作品でもあったように思いました。
結局、大学教授自らが書いているように、「つまり、それぞれ違った思わくがあるらしいが、妻が出来るだけ堕落するように意図し、それに向って一生懸命になっている点では四人とも一致している」ということになり、但し、自らの思惑を最後に実現しそうなのは郁子か―といったような話のように思います。ファム・ファタール的作品と言うか、公序良俗といった概念を破壊してみせた作品かもしれず、また、ジャン=ポール・サルトルが、女性は「共犯者」の境遇にあると言っていたけれど、まさにその通りの作品でもあったように思いました。



 【1964年文庫化[新潮文庫(『鍵』)]/1968年再文庫化[新潮文庫(『鍵・瘋癲老人日記』)]/1973年文庫化[中公文庫]】
【1964年文庫化[新潮文庫(『鍵』)]/1968年再文庫化[新潮文庫(『鍵・瘋癲老人日記』)]/1973年文庫化[中公文庫]】




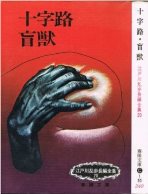

 映画「盲獣」では、時代
映画「盲獣」では、時代 が現代に置き換えられていて、誘拐される女性は原作では浅草歌劇の人気踊り子だったのが、映画では売れないファッションモデルから有名写真家のヌードモデルへ転身してその個展まで開かれるようになった女性(緑魔子)というように改変されています(彼
が現代に置き換えられていて、誘拐される女性は原作では浅草歌劇の人気踊り子だったのが、映画では売れないファッションモデルから有名写真家のヌードモデルへ転身してその個展まで開かれるようになった女性(緑魔子)というように改変されています(彼 女が呼ぶ「按摩師」は「マッサージ師」(船越英二)になっているが、まあ、これは同じこと)。その彼女が攫(さら)われて連れてこられた地下室の、女性の身
女が呼ぶ「按摩師」は「マッサージ師」(船越英二)になっているが、まあ、これは同じこと)。その彼女が攫(さら)われて連れてこられた地下室の、女性の身 体の部位をかたどったオブジェが林立する様が、映
体の部位をかたどったオブジェが林立する様が、映
 映画では、盲目の男による誘拐は1度だけで、中盤までの展開は、監禁される側が監禁する側に対して憐れみを抱くようになるという点で、ウィリアム・ワイラー監督の「
映画では、盲目の男による誘拐は1度だけで、中盤までの展開は、監禁される側が監禁する側に対して憐れみを抱くようになるという点で、ウィリアム・ワイラー監督の「 コレクター
コレクター 作と同じですが、終盤にかけて、それまで息子である男のために"獲物"の調達と監禁に協力していた母親(千石規子)が、2人の関係が思いもよらず深いものとなったことを危惧してそこへ入り込んできたために三角関係の展開となり、その時点で原作とは別物になったように思いました(マザコン映画だったということか)。
作と同じですが、終盤にかけて、それまで息子である男のために"獲物"の調達と監禁に協力していた母親(千石規子)が、2人の関係が思いもよらず深いものとなったことを危惧してそこへ入り込んできたために三角関係の展開となり、その時点で原作とは別物になったように思いました(マザコン映画だったということか)。 原作は、後に「江戸川乱歩全集 恐怖奇形人間」('69年)の石井輝男(1924-2005)監督によって、その遺作「盲獣vs一寸法師」('04年/石井プロダクション=スローラーナー)の中でも一部映像化されていますが、先行例があったからこそ石井輝男監督も映像化に踏み切れたのではないでしょうか。でも、増村保造版に比べると石井輝男版セットなどは安っぽい印象を受け(意図したキッチュ感なのかもしれないが)、両者を見比べると、映画会社と独立プロダクションの差はあるにしても、改めて増村保造の映画作りへのこだわりを感じさせます。
原作は、後に「江戸川乱歩全集 恐怖奇形人間」('69年)の石井輝男(1924-2005)監督によって、その遺作「盲獣vs一寸法師」('04年/石井プロダクション=スローラーナー)の中でも一部映像化されていますが、先行例があったからこそ石井輝男監督も映像化に踏み切れたのではないでしょうか。でも、増村保造版に比べると石井輝男版セットなどは安っぽい印象を受け(意図したキッチュ感なのかもしれないが)、両者を見比べると、映画会社と独立プロダクションの差はあるにしても、改めて増村保造の映画作りへのこだわりを感じさせます。
 「盲獣vs一寸法師」は、リリー・フランキーが映画初出演にして主演を演じた作品ですが(彼はオーディションで選ばれた。オーディション落選組に「シン・ゴジラ」('16年/東宝)での主演が決まった長谷川博己がいた)、全部を観ていないので評価不可。増村保造監督の「盲獣」は、カルト的なポイントは加味しない評価で「星3つ」。カルト的要素を加点すれば「星3つ半」か或いは「星4つ」に近いといったところです。
「盲獣vs一寸法師」は、リリー・フランキーが映画初出演にして主演を演じた作品ですが(彼はオーディションで選ばれた。オーディション落選組に「シン・ゴジラ」('16年/東宝)での主演が決まった長谷川博己がいた)、全部を観ていないので評価不可。増村保造監督の「盲獣」は、カルト的なポイントは加味しない評価で「星3つ」。カルト的要素を加点すれば「星3つ半」か或いは「星4つ」に近いといったところです。 また、「盲獣」は、「江戸川乱歩 美女シリーズ(第21話)/白い素肌の美女」('83年/テレビ朝日)としてもテレビドラマ化されていますが、このシリーズは、天知茂演じる明智小五郎が事件の捜査に臨み、最後は変装して犯人を欺き、犯人の目の前で謎解きをするという推理仕立てがパターンであるため、それに合わせたストーリーになっています。前半のあらすじは、
また、「盲獣」は、「江戸川乱歩 美女シリーズ(第21話)/白い素肌の美女」('83年/テレビ朝日)としてもテレビドラマ化されていますが、このシリーズは、天知茂演じる明智小五郎が事件の捜査に臨み、最後は変装して犯人を欺き、犯人の目の前で謎解きをするという推理仕立てがパターンであるため、それに合わせたストーリーになっています。前半のあらすじは、 助手の文代(高見知佳)と小林少年(小野田真之)に無理やりディスコに連れてこられた明智小五郎だったが、どうにも馴染めずその場を飛び出してしまう。その帰り道の公園で不自然に荷物を包み直している尼僧に目が止まる明智、よくみるとその荷物は人の前腕部を包んだものだった。明智に気づいた尼僧は、その場を立ち去る。明智がその後を追いかけると、寺に中から僧侶が出てきて、ここには自分しかおらず、尼僧がいる寺ではないと言う。多摩川の丸子橋付近で遊んでいる子供達の元にいくつもの風船に吊られた荷物が落ちてきて、それが紙に包まれた人の両脚であったため騒ぎになる。警察で、事件を担当する波越警部(荒井注)は、この猟奇的な事件を明智に相談する。一方の明智は、山野文化学院の院長・山野(田中明夫)の茶会に呼ばれ、山野の後妻・百合枝(叶和貴子)がなにかを明智に相談しようとした時、マッサージの宇佐美鉄心(中条きよし)がやってくる。彼女はそれをやり過ごし、一人娘の三千子(美池真理子)の行方を捜してほしいと明智に頼むが、後日、都心のデパートで人間の右手が発見され、指紋から三千子の右手と判明する―。
助手の文代(高見知佳)と小林少年(小野田真之)に無理やりディスコに連れてこられた明智小五郎だったが、どうにも馴染めずその場を飛び出してしまう。その帰り道の公園で不自然に荷物を包み直している尼僧に目が止まる明智、よくみるとその荷物は人の前腕部を包んだものだった。明智に気づいた尼僧は、その場を立ち去る。明智がその後を追いかけると、寺に中から僧侶が出てきて、ここには自分しかおらず、尼僧がいる寺ではないと言う。多摩川の丸子橋付近で遊んでいる子供達の元にいくつもの風船に吊られた荷物が落ちてきて、それが紙に包まれた人の両脚であったため騒ぎになる。警察で、事件を担当する波越警部(荒井注)は、この猟奇的な事件を明智に相談する。一方の明智は、山野文化学院の院長・山野(田中明夫)の茶会に呼ばれ、山野の後妻・百合枝(叶和貴子)がなにかを明智に相談しようとした時、マッサージの宇佐美鉄心(中条きよし)がやってくる。彼女はそれをやり過ごし、一人娘の三千子(美池真理子)の行方を捜してほしいと明智に頼むが、後日、都心のデパートで人間の右手が発見され、指紋から三千子の右手と判明する―。 クレジットも原作は「盲獣」となっていますが、「一寸法師」からかなり引いています。まったくのオリジナル脚本にしてしまわないだけ良心的とも言えますが、かなり込み入った話になっています
クレジットも原作は「盲獣」となっていますが、「一寸法師」からかなり引いています。まったくのオリジナル脚本にしてしまわないだけ良心的とも言えますが、かなり込み入った話になっています 。ただし、犯人は、最初に出てきた時から犯人らしい(笑)妖しい雰囲気なので、あとは犯行の謎解きを愉しんでくださいということかと思います(純粋推理的と言えなくもないが、そう言い切るにはややアンフェアか)。叶和貴子は、「パノラマ島奇譚」を原作とするシリーズ第17話「
。ただし、犯人は、最初に出てきた時から犯人らしい(笑)妖しい雰囲気なので、あとは犯行の謎解きを愉しんでくださいということかと思います(純粋推理的と言えなくもないが、そう言い切るにはややアンフェアか)。叶和貴子は、「パノラマ島奇譚」を原作とするシリーズ第17話「 やはり、映画と比べると、犯人の「秘密の部屋」のセットがあまりにちゃちだったでしょうか(照明で隠している感じ)。「天国と地獄の美女」と比べても安上がりに仕上げた感じで(「天国と地獄の美女」の方がシリーズの中では特別だったのかもしれないが)、その分、ミステリの方にウェイトを置いたのでしょう。ただ、そのミステリの方も、ややパンチ不足だったように思いました。
やはり、映画と比べると、犯人の「秘密の部屋」のセットがあまりにちゃちだったでしょうか(照明で隠している感じ)。「天国と地獄の美女」と比べても安上がりに仕上げた感じで(「天国と地獄の美女」の方がシリーズの中では特別だったのかもしれないが)、その分、ミステリの方にウェイトを置いたのでしょう。ただ、そのミステリの方も、ややパンチ不足だったように思いました。 「江戸川乱歩 美女シリーズ(第21話)/白い素肌の美女」●制作年:1983年●監督:篠崎好●プロデューサー:佐々木孟●脚本:長谷和夫●音楽:鏑木創●原作:江戸川乱歩「盲獣」●時間:90分●出演:天知茂/高見知佳/小野田真之/荒井注/叶和貴子/美池真理子(池まり子)/五代高之/福田妙子/曽我町子/飯野けいと/喜田晋平/加藤土代子/桜川梅八/小田草之介/田中明夫/中条きよし●放送局:テレビ朝日●放送日:1983/04/16(評価:★★★)
「江戸川乱歩 美女シリーズ(第21話)/白い素肌の美女」●制作年:1983年●監督:篠崎好●プロデューサー:佐々木孟●脚本:長谷和夫●音楽:鏑木創●原作:江戸川乱歩「盲獣」●時間:90分●出演:天知茂/高見知佳/小野田真之/荒井注/叶和貴子/美池真理子(池まり子)/五代高之/福田妙子/曽我町子/飯野けいと/喜田晋平/加藤土代子/桜川梅八/小田草之介/田中明夫/中条きよし●放送局:テレビ朝日●放送日:1983/04/16(評価:★★★)

 「盲獣」●制作年:1969年●監督:増村保造●脚本:白坂依志夫●撮影:小林節雄●音楽:林光●原作:江戸川乱歩「盲獣」●時間:84分●出演:船越英二/緑魔
「盲獣」●制作年:1969年●監督:増村保造●脚本:白坂依志夫●撮影:小林節雄●音楽:林光●原作:江戸川乱歩「盲獣」●時間:84分●出演:船越英二/緑魔

 子/千石規子●公開:1969/01●配給:大映(評価:★★★)
子/千石規子●公開:1969/01●配給:大映(評価:★★★)


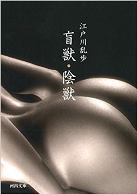


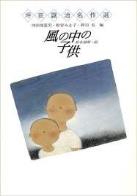

 坪田譲治
坪田譲治 


 表題作の「風の中の子供」は、あの筒井康隆氏も幼い頃に読んで涙したという傑作ですが、清水宏監督によって1937(昭和12)年に映画化されています。
表題作の「風の中の子供」は、あの筒井康隆氏も幼い頃に読んで涙したという傑作ですが、清水宏監督によって1937(昭和12)年に映画化されています。 がないが、父(河村黎吉)は結構なことだと思って気にしない。そんな時、父が私文書偽造の容疑で逮捕され、三平は叔父(坂本武)に引き取られることになる―。
がないが、父(河村黎吉)は結構なことだと思って気にしない。そんな時、父が私文書偽造の容疑で逮捕され、三平は叔父(坂本武)に引き取られることになる―。 父親が私文書偽造の容疑で捕えられたのは、実は会社の政敵の策謀によるもので、坪田譲治自身、家業の島田製作所を兄が継いだものの、以後会社の内紛が続いて兄が自殺したため同社の取締役に就任するも、造反により取締役を突然解任される('33年)といったことを経験しています。そうした経験は「風の中の子供」以外の作品にも反映され
父親が私文書偽造の容疑で捕えられたのは、実は会社の政敵の策謀によるもので、坪田譲治自身、家業の島田製作所を兄が継いだものの、以後会社の内紛が続いて兄が自殺したため同社の取締役に就任するも、造反により取締役を突然解任される('33年)といったことを経験しています。そうした経験は「風の中の子供」以外の作品にも反映され ていますが、こうしたどろどろした大人の世界を童話に持ち込むことについて、本書の中にある「私の童話観」の、「世の童話作家はみな子供を甘やかしているのである。読んでごらんなさい。どれもこれも砂
ていますが、こうしたどろどろした大人の世界を童話に持ち込むことについて、本書の中にある「私の童話観」の、「世の童話作家はみな子供を甘やかしているのである。読んでごらんなさい。どれもこれも砂 糖の味ばかりするのである」「このような童話ばかり読んで、現実を、現実の中の真実を知らずに育つ子供があるとしたらどうであろうか」「色はもっとジミでもいい。光はもっとにぶくていい。美しさは足りなくても、人生の真実を描いてほしいと思うのである」という考えと符合するかと思います。
糖の味ばかりするのである」「このような童話ばかり読んで、現実を、現実の中の真実を知らずに育つ子供があるとしたらどうであろうか」「色はもっとジミでもいい。光はもっとにぶくていい。美しさは足りなくても、人生の真実を描いてほしいと思うのである」という考えと符合するかと思います。 日本人女性初の五輪金メダルを獲っていた)。叔父の家に預けられた三平は、腕白が過ぎて叔父の手に負えず戻されてしまうのですが、その原因となった出来事の1つに、川で盥を舟の代わりにして遊んでいて、そのままどんどん川下り状態になって流されていってしまった事件があり、「畳水泳」どころか、この「川流れ」も、実地で再現していたのにはやや驚きました。ロケ主義、リアリズム重視の清水宏監督の本領発揮というか、今だったら撮れないだろうなあ。そうしたことも含め、オリジナルのストーリーを大事にし、自然の中で伸び伸びと遊び育つ子供を映像的に上手く撮ることで、原作の持ち味は生かしていたように思います。
日本人女性初の五輪金メダルを獲っていた)。叔父の家に預けられた三平は、腕白が過ぎて叔父の手に負えず戻されてしまうのですが、その原因となった出来事の1つに、川で盥を舟の代わりにして遊んでいて、そのままどんどん川下り状態になって流されていってしまった事件があり、「畳水泳」どころか、この「川流れ」も、実地で再現していたのにはやや驚きました。ロケ主義、リアリズム重視の清水宏監督の本領発揮というか、今だったら撮れないだろうなあ。そうしたことも含め、オリジナルのストーリーを大事にし、自然の中で伸び伸びと遊び育つ子供を映像的に上手く撮ることで、原作の持ち味は生かしていたように思います。 笠智衆がチョイ役(巡査役)で出演していますが、老け役でなかったため、逆に最初は気がつきませんでした。
笠智衆がチョイ役(巡査役)で出演していますが、老け役でなかったため、逆に最初は気がつきませんでした。
 「風の中の子供」...【1938年単行本[竹村書房]/1949年文庫化[新潮文庫/1956年再文庫化[角川文庫]/1971年再文庫化[潮文庫]/1975年再文庫化[旺文社文庫(『風の中の子供 他四編』)]/1983年再文庫化[ポプラ文庫]】
「風の中の子供」...【1938年単行本[竹村書房]/1949年文庫化[新潮文庫/1956年再文庫化[角川文庫]/1971年再文庫化[潮文庫]/1975年再文庫化[旺文社文庫(『風の中の子供 他四編』)]/1983年再文庫化[ポプラ文庫]】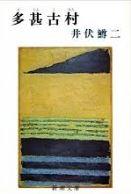


 井伏鱒二(1898-1993)
井伏鱒二(1898-1993) 南国の海浜の村、多甚古村(たじんこむら)に新たに赴任してきた甲田巡査は平和を愛する好人物。その甲田巡査の日録の形で、飄々とした作者独特の文体でもって、多甚古村で起きた喧嘩、醜聞、泥棒、騒擾など、庶民の実生活が軽妙に描かれ、ジグザグした人間模様が生彩を放ちつつ展開される―。
南国の海浜の村、多甚古村(たじんこむら)に新たに赴任してきた甲田巡査は平和を愛する好人物。その甲田巡査の日録の形で、飄々とした作者独特の文体でもって、多甚古村で起きた喧嘩、醜聞、泥棒、騒擾など、庶民の実生活が軽妙に描かれ、ジグザグした人間模様が生彩を放ちつつ展開される―。 翌1940(昭和15)年1月に今井正(1912-1991/享年79)監督による映画化作品「多甚古村」(東宝)が公開され、以降、井伏作品の映画化が「南風交響楽」(S.15)、「
翌1940(昭和15)年1月に今井正(1912-1991/享年79)監督による映画化作品「多甚古村」(東宝)が公開され、以降、井伏作品の映画化が「南風交響楽」(S.15)、「 映画では、前半部分では、新任の巡査、所謂「駐在さん」である主人公(清川荘司)がご近所から鮒を分けて貰った話や、同じくご近所さんが自炊を手伝ってくれた話など独身巡査の身辺生活の話と、村の老婆の住む家に押し込み強盗が入ったけれども何も盗らないで逃げたという話や、野良犬を退治してくれと村人が頼み込んできた話など、田舎村らしい事件と言えるかどうか分からないようなものも含めた事件話が、原作通りに取り上げられています。
映画では、前半部分では、新任の巡査、所謂「駐在さん」である主人公(清川荘司)がご近所から鮒を分けて貰った話や、同じくご近所さんが自炊を手伝ってくれた話など独身巡査の身辺生活の話と、村の老婆の住む家に押し込み強盗が入ったけれども何も盗らないで逃げたという話や、野良犬を退治してくれと村人が頼み込んできた話など、田舎村らしい事件と言えるかどうか分からないようなものも含めた事件話が、原作通りに取り上げられています。 これらは何れも駐在所に持ち込まれた話であり、甲田巡査が現場に出向いて行く場面はありませんが、相次ぐ村人からの事件とも相談事ともつかない話の連続に甲田巡査は過労でダウンしてしまい、その看病や食事の世話をする村のお寺の和尚の役を滝沢修(1906-2000/享年93)が演じていて、老け役ではありますが、実年齢は当時33歳と若いです(原作でも淨海という和尚は出てくるが、巡査がダウンする話はない)。また、主人公の同僚の杉野巡査役で、滝沢修と戦後一緒に民衆芸術劇場(劇団民藝の前身)を設立することになる宇野重吉(1914-1988/享年73)も出ていますが、当時25歳とこれまた若いです(宇野重吉は10年後の成瀬巳喜男監督の「怒りの街」('50年/東宝)でもまだ学生役を演じている)。
これらは何れも駐在所に持ち込まれた話であり、甲田巡査が現場に出向いて行く場面はありませんが、相次ぐ村人からの事件とも相談事ともつかない話の連続に甲田巡査は過労でダウンしてしまい、その看病や食事の世話をする村のお寺の和尚の役を滝沢修(1906-2000/享年93)が演じていて、老け役ではありますが、実年齢は当時33歳と若いです(原作でも淨海という和尚は出てくるが、巡査がダウンする話はない)。また、主人公の同僚の杉野巡査役で、滝沢修と戦後一緒に民衆芸術劇場(劇団民藝の前身)を設立することになる宇野重吉(1914-1988/享年73)も出ていますが、当時25歳とこれまた若いです(宇野重吉は10年後の成瀬巳喜男監督の「怒りの街」('50年/東宝)でもまだ学生役を演じている)。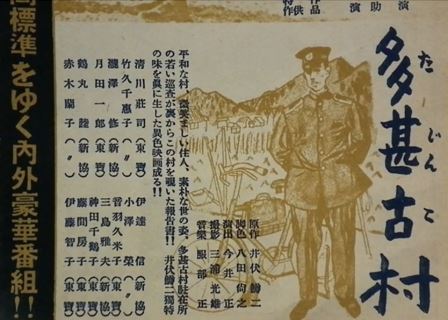 このまま小事件をこまめに拾っていくのかと思ったら、映画の後半分は、原作の2つのエピソードに焦点を当て、後半の3分の2を、村出身の帝大の学生がカフェの女と相思相愛の仲になってしまったのを、学生の親に頼まれて巡査が2人を別れさせる話(原作における「恋愛・人事問題の件」)に、最後、後半の3分の1を村の2つの中学同士の集団決闘事件とその仲裁に巡査が関わる件(原作における「学生決闘の件」)に充てています。
このまま小事件をこまめに拾っていくのかと思ったら、映画の後半分は、原作の2つのエピソードに焦点を当て、後半の3分の2を、村出身の帝大の学生がカフェの女と相思相愛の仲になってしまったのを、学生の親に頼まれて巡査が2人を別れさせる話(原作における「恋愛・人事問題の件」)に、最後、後半の3分の1を村の2つの中学同士の集団決闘事件とその仲裁に巡査が関わる件(原作における「学生決闘の件」)に充てています。 カフェの女には刑務所に服役中のヤクザ者の元情夫がいるということが判明し、巡査は学生と女のそれぞれの所へ出向いて別れるよう説得しますが、原作では、巡査は一度学生に、「家庭争議というものは、或る段階に至るまでは一種の快楽に属する。いま、われわれは他人を介在する必要はない」という理論でやり込められていて(民事不介入という"法理論"よりハイレベルの"心理学的理論"?)、親子喧嘩の仲裁は自分に向かないと思ったのを(しかも相手はインテリ学生)、学生の家族に再度懇願されて説得に当たることになっています。
カフェの女には刑務所に服役中のヤクザ者の元情夫がいるということが判明し、巡査は学生と女のそれぞれの所へ出向いて別れるよう説得しますが、原作では、巡査は一度学生に、「家庭争議というものは、或る段階に至るまでは一種の快楽に属する。いま、われわれは他人を介在する必要はない」という理論でやり込められていて(民事不介入という"法理論"よりハイレベルの"心理学的理論"?)、親子喧嘩の仲裁は自分に向かないと思ったのを(しかも相手はインテリ学生)、学生の家族に再度懇願されて説得に当たることになっています。
 「多甚古村」●制作年:1940年●監督:今井正●脚本:八田尚之●撮影:三浦光雄●音楽:服部正●原作:井伏鱒二「多甚古村」●時間:63分●出演:清川莊司/竹久千惠子/月田一郎/宇野重吉/赤木蘭子/鶴丸睦彦/伊達信/小沢栄/深見泰三/原泉子/三島雅夫/藤間房子/月田一郎/滝沢修●公開:1940/01●配給:東宝映画(評価★★★)
「多甚古村」●制作年:1940年●監督:今井正●脚本:八田尚之●撮影:三浦光雄●音楽:服部正●原作:井伏鱒二「多甚古村」●時間:63分●出演:清川莊司/竹久千惠子/月田一郎/宇野重吉/赤木蘭子/鶴丸睦彦/伊達信/小沢栄/深見泰三/原泉子/三島雅夫/藤間房子/月田一郎/滝沢修●公開:1940/01●配給:東宝映画(評価★★★) 
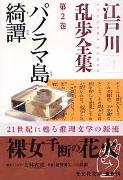
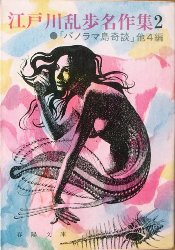

 「月刊コミックビーム」の2007(平成19)年7月号から翌年の1月号にかけて連載された作品に加筆修正したもの。「エスプ長井勝一漫画美術館主催事業」として、「江戸川乱歩×丸尾末広の世界 パノラマ島綺譚」展が今年(2011年)3月に宮城県塩竈市の「ふれあいエスプ塩竈」(生涯学習センター内)で開催されており(長井勝一氏は「月刊漫画ガロ」の初代編集長)、3月12日に丸尾氏のトークショーが予定されていましたが、前日に東日本大震災があり中止になっています。主催者側は残念だったと思いますが、原画が無事だったことが主催者側にとってもファンにとっても救いだったでしょうか。
「月刊コミックビーム」の2007(平成19)年7月号から翌年の1月号にかけて連載された作品に加筆修正したもの。「エスプ長井勝一漫画美術館主催事業」として、「江戸川乱歩×丸尾末広の世界 パノラマ島綺譚」展が今年(2011年)3月に宮城県塩竈市の「ふれあいエスプ塩竈」(生涯学習センター内)で開催されており(長井勝一氏は「月刊漫画ガロ」の初代編集長)、3月12日に丸尾氏のトークショーが予定されていましたが、前日に東日本大震災があり中止になっています。主催者側は残念だったと思いますが、原画が無事だったことが主催者側にとってもファンにとっても救いだったでしょうか。
 個人的には、昔、春陽堂の春陽文庫で読んだのが初読でしたが、ラストの"花火"にはやや唖然とさせられた印象があります。原作者自身でさえ"絵空事"のキライがあると捉えているものを、漫画として視覚的に再現した丸尾末広の果敢な挑戦はそれ自体評価に値し、また、その出来栄えもなかなかのものではないかと思われました。
個人的には、昔、春陽堂の春陽文庫で読んだのが初読でしたが、ラストの"花火"にはやや唖然とさせられた印象があります。原作者自身でさえ"絵空事"のキライがあると捉えているものを、漫画として視覚的に再現した丸尾末広の果敢な挑戦はそれ自体評価に値し、また、その出来栄えもなかなかのものではないかと思われました。 但し、本当に描きたかったのは、後半のパノラマ島の描写だったのでしょう。海中にある「上下左右とも海底を見通すことのできる、ガラス張りのトンネル」などは、実際に最近の水族館などでは見られるようになっていますが、その島で行われていることは、一般的観念から見れば大いに猟奇変態的なものです。
但し、本当に描きたかったのは、後半のパノラマ島の描写だったのでしょう。海中にある「上下左右とも海底を見通すことのできる、ガラス張りのトンネル」などは、実際に最近の水族館などでは見られるようになっていますが、その島で行われていることは、一般的観念から見れば大いに猟奇変態的なものです。
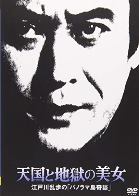
 たことがあり(タイトルは「天国と地獄の美女」)、正月(1月2日)に3時間の拡大版(正味142分)で放映されています。明智小五郎役は天知茂、パノラマ島を造成する人見広介役は伊東四朗で(山林王・菰田源三郎と二役)、菰田千代
たことがあり(タイトルは「天国と地獄の美女」)、正月(1月2日)に3時間の拡大版(正味142分)で放映されています。明智小五郎役は天知茂、パノラマ島を造成する人見広介役は伊東四朗で(山林王・菰田源三郎と二役)、菰田千代 子(源三郎の妻)役が叶和貴子(当時25歳)、その他に小池朝雄、宮下順子、水野久美らがゲスト出演しています。パノラマ島
子(源三郎の妻)役が叶和貴子(当時25歳)、その他に小池朝雄、宮下順子、水野久美らがゲスト出演しています。パノラマ島 自体は再現し切れていないというのがもっぱらの評価で、実際観てみると、特撮も駆使しているものの、ジャングルとか火山とかの造型が妙に手作り感に溢れています(特撮と言うより"遠近法"?)。ただ、逆にこの温泉地の地獄巡り乃至"秘宝館"的キッチュ感が後にカルト的な話題になり、シリーズの中で最高傑作に推す人もいます(叶和貴子は第21話「白い素肌の美女」(原作『盲獣』(実質的には『一寸法師』)('83年)、北大路欣也版第3話「赤い乗馬服の美女」(原作『何者』)('87年)でも"美女役"を務めた)。
自体は再現し切れていないというのがもっぱらの評価で、実際観てみると、特撮も駆使しているものの、ジャングルとか火山とかの造型が妙に手作り感に溢れています(特撮と言うより"遠近法"?)。ただ、逆にこの温泉地の地獄巡り乃至"秘宝館"的キッチュ感が後にカルト的な話題になり、シリーズの中で最高傑作に推す人もいます(叶和貴子は第21話「白い素肌の美女」(原作『盲獣』(実質的には『一寸法師』)('83年)、北大路欣也版第3話「赤い乗馬服の美女」(原作『何者』)('87年)でも"美女役"を務めた)。
 「江戸川乱歩 美女シリーズ(第17話)/天国と地獄の美女」●制作年:1982年●監督:井上梅次●プロデューサ:佐々木
「江戸川乱歩 美女シリーズ(第17話)/天国と地獄の美女」●制作年:1982年●監督:井上梅次●プロデューサ:佐々木 孟/植野晃弘/稲垣健司●脚本:
孟/植野晃弘/稲垣健司●脚本:
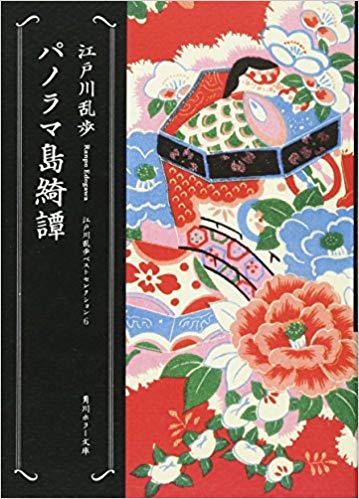
 ジェームズ三木 脚本家、作家、演出家、元歌手。
ジェームズ三木 脚本家、作家、演出家、元歌手。
 「善人の条件」●制作年:1989年●監督・脚本・原作:ジェームス三木●撮影:坂本典隆●音楽:羽田健太郎●時間:123分●出演:津川雅彦/すまけい/小林稔侍/橋爪功/井上順/イッセー尾形/山下規介/森三平太/浪越徳治郎/柳生博/松村達雄/丹波哲郎/小川真由美/桜田淳子/山岡久乃/野際陽子/汀夏子/守谷佳央理/野村昭子/小竹伊津子/鷲尾真知子/松金よね子/浅利香津代/泉ピン子/黒柳徹子●公開:1989/05●配給:松竹(評価:★★★)
「善人の条件」●制作年:1989年●監督・脚本・原作:ジェームス三木●撮影:坂本典隆●音楽:羽田健太郎●時間:123分●出演:津川雅彦/すまけい/小林稔侍/橋爪功/井上順/イッセー尾形/山下規介/森三平太/浪越徳治郎/柳生博/松村達雄/丹波哲郎/小川真由美/桜田淳子/山岡久乃/野際陽子/汀夏子/守谷佳央理/野村昭子/小竹伊津子/鷲尾真知子/松金よね子/浅利香津代/泉ピン子/黒柳徹子●公開:1989/05●配給:松竹(評価:★★★)  「
「





 1916(大正5)年12月25日早朝、「船長」ら男4人を乗せ、大分県の下の江港から宮崎県の日向寄りの海に散在している島々に向け出航した小帆船〈海神丸〉は、折からの強風に晒され遭難、漂流すること数十日に及ぶに至る。飢えた2人の船頭「八蔵」と「五郎助」は、船長の目を盗んで船長の17歳の甥「三吉」を殺し、その肉を喰おうと企てる―。
1916(大正5)年12月25日早朝、「船長」ら男4人を乗せ、大分県の下の江港から宮崎県の日向寄りの海に散在している島々に向け出航した小帆船〈海神丸〉は、折からの強風に晒され遭難、漂流すること数十日に及ぶに至る。飢えた2人の船頭「八蔵」と「五郎助」は、船長の目を盗んで船長の17歳の甥「三吉」を殺し、その肉を喰おうと企てる―。


 主要な登場人物は遭難した4人ですが、殿山泰司(船長・亀五郎)、乙羽信子(五郎助)、佐藤慶(八蔵)、山本圭(三吉)、という配役で、「三吉」を殺し、その肉を喰おうと企てる「五郎助」が女性に置き換えられ、それを乙羽信子が演じ
主要な登場人物は遭難した4人ですが、殿山泰司(船長・亀五郎)、乙羽信子(五郎助)、佐藤慶(八蔵)、山本圭(三吉)、という配役で、「三吉」を殺し、その肉を喰おうと企てる「五郎助」が女性に置き換えられ、それを乙羽信子が演じ ています(乙羽信子の役は海女という設定)。それ以外は基本的に原作に忠実ですが、最後に原作にはない結末があり、五郎助と八蔵が精神的に崩壊をきたしたような終わり方でした(罪と罰、因果応報という感じか)。名わき役・殿
ています(乙羽信子の役は海女という設定)。それ以外は基本的に原作に忠実ですが、最後に原作にはない結末があり、五郎助と八蔵が精神的に崩壊をきたしたような終わり方でした(罪と罰、因果応報という感じか)。名わき役・殿 山泰司の数少ない主演作であり、殿山泰司と乙羽信子の演技が光っているように思いました(殿山泰司は好演、乙羽信子は怪演!)。この時のロケ撮影の様子は、名エッセイストでもある殿山泰司が『三文役者あなあきい伝〈part 2〉』('80年/講談社文庫)で触れていてますが、これがなかなか興味深いです(その後、『
山泰司の数少ない主演作であり、殿山泰司と乙羽信子の演技が光っているように思いました(殿山泰司は好演、乙羽信子は怪演!)。この時のロケ撮影の様子は、名エッセイストでもある殿山泰司が『三文役者あなあきい伝〈part 2〉』('80年/講談社文庫)で触れていてますが、これがなかなか興味深いです(その後、『 「人間」●制作年:1962年●監督・脚本・美術:新藤兼人●製作:絲屋寿雄/能登節雄/湊保/松浦栄策●撮影:黒田清巳●音楽:林光
「人間」●制作年:1962年●監督・脚本・美術:新藤兼人●製作:絲屋寿雄/能登節雄/湊保/松浦栄策●撮影:黒田清巳●音楽:林光
 ●原作:野上弥生子「海神丸」●時間:100分●出演:乙羽信子/
●原作:野上弥生子「海神丸」●時間:100分●出演:乙羽信子/


 谷崎潤一郎(1886-1965)が1934(昭和9)年に発表したもので、「なるべく多くの人々に読んでもらう目的で、通俗を旨として書いた」と前書きしている通りに読み易く、その年のベストセラーだったとのこと。中公文庫版は、改訂により活字が大きくなり、更に読み易くなっています(活字を大きめにしたのは、活字が小さいのは良くないと本書に書いてあるからか)。
谷崎潤一郎(1886-1965)が1934(昭和9)年に発表したもので、「なるべく多くの人々に読んでもらう目的で、通俗を旨として書いた」と前書きしている通りに読み易く、その年のベストセラーだったとのこと。中公文庫版は、改訂により活字が大きくなり、更に読み易くなっています(活字を大きめにしたのは、活字が小さいのは良くないと本書に書いてあるからか)。 但し、文庫解説の吉行淳之介が、「この本についての数少ない疑点」として幾つか挙げている中の最後にもあるように、「文章には実用と藝術の区別はないと思います」という点が、本書で言う文章の対象には詩歌などの韻文は含まれていないとはしているにしても、どうかなあという気はしました(吉行淳之介は「私の考えでは微妙な区別があると思う」としている)。
但し、文庫解説の吉行淳之介が、「この本についての数少ない疑点」として幾つか挙げている中の最後にもあるように、「文章には実用と藝術の区別はないと思います」という点が、本書で言う文章の対象には詩歌などの韻文は含まれていないとはしているにしても、どうかなあという気はしました(吉行淳之介は「私の考えでは微妙な区別があると思う」としている)。




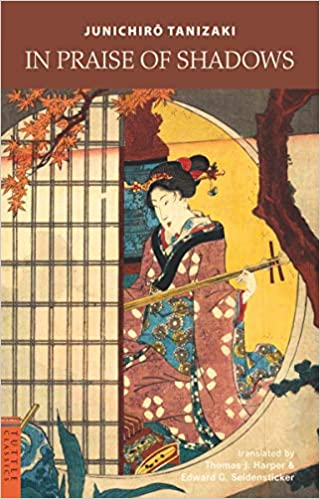















 北海道から東北の山間の小学校へ転校してきた5年生の少年・高田三郎(片山明彦)に、地元の子供達は、転校してきた日が二百十日であったため「風の又三郎」という綽名を付ける。新参者に興味を示し、一緒に遊んだりしながらも距離を置く子供達―ある日、ガキ大将の一郎(大泉滉)が相撲を挑み、三郎少年は投げ飛ばされてしまう。調子に乗ったガキ大将が「くやしかったら風を呼んでみろ」とからかった直後、本当に大風が吹き、台風が来襲する。そして、その翌日、彼は別の学校へ転校していったため、子供達は少年が本物の「風の又三郎」だったのだと確信する―。
北海道から東北の山間の小学校へ転校してきた5年生の少年・高田三郎(片山明彦)に、地元の子供達は、転校してきた日が二百十日であったため「風の又三郎」という綽名を付ける。新参者に興味を示し、一緒に遊んだりしながらも距離を置く子供達―ある日、ガキ大将の一郎(大泉滉)が相撲を挑み、三郎少年は投げ飛ばされてしまう。調子に乗ったガキ大将が「くやしかったら風を呼んでみろ」とからかった直後、本当に大風が吹き、台風が来襲する。そして、その翌日、彼は別の学校へ転校していったため、子供達は少年が本物の「風の又三郎」だったのだと確信する―。 宮澤賢治(1896‐1933)による原作は、作者没後の1934(昭和9)年に発表されたもので、大正年中に書いたものをコラージュして1931(昭和6)年から1933(昭和8)年の間に成ったものとされており、これまで何度か映画化されていますが、最初に映画化された島耕二(1901‐1986)監督のこの作品が、最も原作の雰囲気を伝えているとされているようです。
宮澤賢治(1896‐1933)による原作は、作者没後の1934(昭和9)年に発表されたもので、大正年中に書いたものをコラージュして1931(昭和6)年から1933(昭和8)年の間に成ったものとされており、これまで何度か映画化されていますが、最初に映画化された島耕二(1901‐1986)監督のこの作品が、最も原作の雰囲気を伝えているとされているようです。
 前半部分は野山を廻って遊ぶ子供達を生き生きと描いた野外シーンが殆どで、そうした中、子供達は三郎(片山明彦)との距離を狭めたり(子供達が三郎少年を守ろうとする場面もある)、また遠ざけたりを繰り返します。
前半部分は野山を廻って遊ぶ子供達を生き生きと描いた野外シーンが殆どで、そうした中、子供達は三郎(片山明彦)との距離を狭めたり(子供達が三郎少年を守ろうとする場面もある)、また遠ざけたりを繰り返します。 最初、教師が詰襟っぽい制服姿で出てきたので、時代設定を映画制作時の昭和15年に置き換えたのかと思いましたが、そうではなく原作通りでした(学校も藁ぶき屋根! 但し「分校」なのだが)。洋服の三郎少年に対し地元の子供達は着物姿であるため、映像で観るとよりその対比が際立ち、冒頭で既に三郎少年と子供達は一つになることはないような予感がしてしまいました。実際に原作も、子供達が自らのコミュニティ(「地元の子供」という1つの村社会)で結束して部外者を排除したプロセスを描
最初、教師が詰襟っぽい制服姿で出てきたので、時代設定を映画制作時の昭和15年に置き換えたのかと思いましたが、そうではなく原作通りでした(学校も藁ぶき屋根! 但し「分校」なのだが)。洋服の三郎少年に対し地元の子供達は着物姿であるため、映像で観るとよりその対比が際立ち、冒頭で既に三郎少年と子供達は一つになることはないような予感がしてしまいました。実際に原作も、子供達が自らのコミュニティ(「地元の子供」という1つの村社会)で結束して部外者を排除したプロセスを描 いたととれなくもありません(その場合「又三郎」そのものに"魔的"な意味合いが加味される)。
いたととれなくもありません(その場合「又三郎」そのものに"魔的"な意味合いが加味される)。

 出ています。一方で、嘉助が霧の中で迷って昏倒した際に、三郎少年がガラスのマントを着て空を飛ぶ姿を見る場面で、「ガラスのマント」が濡れたビニールにしか見えなかったりもしますが、とにかく特撮からアニメまで駆使して頑張ってるなあという感じ。
出ています。一方で、嘉助が霧の中で迷って昏倒した際に、三郎少年がガラスのマントを着て空を飛ぶ姿を見る場面で、「ガラスのマント」が濡れたビニールにしか見えなかったりもしますが、とにかく特撮からアニメまで駆使して頑張ってるなあという感じ。

 最も原作と異なると感じたのは、原作は、三郎少年は「風の又三郎」だったかも知れない的な、子供達の心象に沿った捉え方も出来る終わり方をしていますが、映画では、例えば、「風を呼んでみろ」と言われた時に三郎少年がちらっと空模様を窺ったりする演出があるなど(『三国志』吉川英治版「諸葛孔明」か)、彼が「風の又三郎」ではないことをはっきりさせている点でしょうか(言わば単なる頭のいい子に過ぎない)。
最も原作と異なると感じたのは、原作は、三郎少年は「風の又三郎」だったかも知れない的な、子供達の心象に沿った捉え方も出来る終わり方をしていますが、映画では、例えば、「風を呼んでみろ」と言われた時に三郎少年がちらっと空模様を窺ったりする演出があるなど(『三国志』吉川英治版「諸葛孔明」か)、彼が「風の又三郎」ではないことをはっきりさせている点でしょうか(言わば単なる頭のいい子に過ぎない)。

 三郎少年を演じた片山明彦(1926-2014/享年86)は島耕二監督の実子、子供達のリーダーで学校で唯一の6年生の一郎を演じているのは大泉滉(1925‐1998/享年73)、そのほか、嘉助の姉(原作には出てこない)役で風見章子(1921‐2016/享年95)が出演しています。
三郎少年を演じた片山明彦(1926-2014/享年86)は島耕二監督の実子、子供達のリーダーで学校で唯一の6年生の一郎を演じているのは大泉滉(1925‐1998/享年73)、そのほか、嘉助の姉(原作には出てこない)役で風見章子(1921‐2016/享年95)が出演しています。
 「風の又三郎」●制作年:1940年●監督:島耕二●脚本:永見隆二/池慎太郎●撮影:相坂操一●音楽:杉原泰蔵●時間:98分●出演:片山明彦/星野和正/大泉滉/風見章子/中田弘二/北竜二/林寛/見明凡太郎/西島悌四朗/飛田喜佐夫/小泉忠/久見京子/中島利夫/南沢昌平/杉俊成/大坪政俊/河合英一/田中康子/南沢すみ子/川島笑子/美野礼子●公開:1940/10●配給:日活●最初に観た場所:神保町シアター(10-07-24)(評価:★★★☆) 神保町シアター 2007(平成19)年7月14日オープン
「風の又三郎」●制作年:1940年●監督:島耕二●脚本:永見隆二/池慎太郎●撮影:相坂操一●音楽:杉原泰蔵●時間:98分●出演:片山明彦/星野和正/大泉滉/風見章子/中田弘二/北竜二/林寛/見明凡太郎/西島悌四朗/飛田喜佐夫/小泉忠/久見京子/中島利夫/南沢昌平/杉俊成/大坪政俊/河合英一/田中康子/南沢すみ子/川島笑子/美野礼子●公開:1940/10●配給:日活●最初に観た場所:神保町シアター(10-07-24)(評価:★★★☆) 神保町シアター 2007(平成19)年7月14日オープン
![風の又三郎 [VHS]500_.jpg](http://hurec.bz/book-movie/%E9%A2%A8%E3%81%AE%E5%8F%88%E4%B8%89%E9%83%8E%20%5BVHS%5D500_.jpg)



 VHS
VHS
 『心理試験』の単行本は、1924(大正14)年7月の刊行で、「創作探偵小説集1」として'93年に春陽堂書店から復刻刊行されています(「二銭銅貨」「D坂殺人事件」「黒手組」「一枚の切符」「二廃人」「双生児」「日記帳」「算盤が恋を語る話」「恐ろしき錯誤」「赤い部屋」の10編を所収)。個人的には、高校生の時に読んだ春陽文庫に思い入れがありますが、今読むならば、光文社文庫の『屋根裏の散歩者―江戸川乱歩全集1』('04年7月刊)が読み易いかも。
『心理試験』の単行本は、1924(大正14)年7月の刊行で、「創作探偵小説集1」として'93年に春陽堂書店から復刻刊行されています(「二銭銅貨」「D坂殺人事件」「黒手組」「一枚の切符」「二廃人」「双生児」「日記帳」「算盤が恋を語る話」「恐ろしき錯誤」「赤い部屋」の10編を所収)。個人的には、高校生の時に読んだ春陽文庫に思い入れがありますが、今読むならば、光文社文庫の『屋根裏の散歩者―江戸川乱歩全集1』('04年7月刊)が読み易いかも。 光文社文庫版の表題作「屋根裏の散歩者」(1925(大正14)年8月に「新青年」に発表)は、'70年、'76年、'94年、'07年の4度映画化されており、田中登監督、石橋蓮司・宮下順子主演の映画化作品「江戸川乱歩猟奇館 屋根裏の散歩者」('76年/日活)を観ましたが、映画はエロチックな作りになっているように思いました。原作は、女の自慢話する男を嫌った主人公が、単に犯罪の愉しみのために、天井裏から毒薬を垂らして男の殺害を謀るもので、エロチックな要素はありません。この作品の事件も明智小五郎が解決しますが、その言動にもどこか剽軽で乾いたところがあります。因みに、この天井裏から毒薬を垂らす殺害方法は、映画「
光文社文庫版の表題作「屋根裏の散歩者」(1925(大正14)年8月に「新青年」に発表)は、'70年、'76年、'94年、'07年の4度映画化されており、田中登監督、石橋蓮司・宮下順子主演の映画化作品「江戸川乱歩猟奇館 屋根裏の散歩者」('76年/日活)を観ましたが、映画はエロチックな作りになっているように思いました。原作は、女の自慢話する男を嫌った主人公が、単に犯罪の愉しみのために、天井裏から毒薬を垂らして男の殺害を謀るもので、エロチックな要素はありません。この作品の事件も明智小五郎が解決しますが、その言動にもどこか剽軽で乾いたところがあります。因みに、この天井裏から毒薬を垂らす殺害方法は、映画「
 映画がどろっとした感じになっているのは、「人間椅子」(1925年発表)の要素を織り込んでいるためですが("人間椅子"になって喜ぶ下僕が出てくる)、「人間椅子」の原作には実は空想譚だったというオチがあり、乱歩の初期作品には、実現可能性を考慮して、結構こうした作りになっているものが多いのです。
映画がどろっとした感じになっているのは、「人間椅子」(1925年発表)の要素を織り込んでいるためですが("人間椅子"になって喜ぶ下僕が出てくる)、「人間椅子」の原作には実は空想譚だったというオチがあり、乱歩の初期作品には、実現可能性を考慮して、結構こうした作りになっているものが多いのです。 映画には、「乱歩=猟奇的」といったイメージがアプリオリに介在しているように思えました。宮下順子演じる美那子と逢引するピエロの話も、関東大震災の話(まさに"驚天動地"の結末)も原作には無い話です。自分が最初に観た時も、宮下順子の「ピエロ~、ピエロ~」という喘ぎ声に館内から思わず笑いが起きたくらいで、今日においてはカルト的作品であると言えばそう言えるかもしれません。
映画には、「乱歩=猟奇的」といったイメージがアプリオリに介在しているように思えました。宮下順子演じる美那子と逢引するピエロの話も、関東大震災の話(まさに"驚天動地"の結末)も原作には無い話です。自分が最初に観た時も、宮下順子の「ピエロ~、ピエロ~」という喘ぎ声に館内から思わず笑いが起きたくらいで、今日においてはカルト的作品であると言えばそう言えるかもしれません。


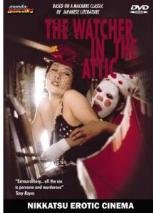

 「江戸川乱歩猟奇館 屋根裏の散歩者」●制作年:1976年●監督:田中登●製作:結城良煕/伊地智●脚本:いどあきお●撮影:森勝●音楽:蓼科二郎●原作:江戸川乱歩「屋根裏の散歩者」●時間:76分●●出演:石橋蓮司/宮下順子/長弘/
「江戸川乱歩猟奇館 屋根裏の散歩者」●制作年:1976年●監督:田中登●製作:結城良煕/伊地智●脚本:いどあきお●撮影:森勝●音楽:蓼科二郎●原作:江戸川乱歩「屋根裏の散歩者」●時間:76分●●出演:石橋蓮司/宮下順子/長弘/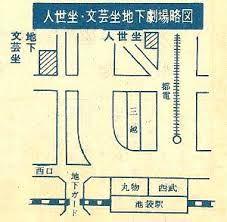 織田俊彦/渡辺とく子/八代康二/田島はるか/中島葵/夢村四郎/秋津令子/水木京一●公開:1976/06●配給:日活●最初に観た場所:池袋文芸地下(82-11-14)(評価:★★★)●併映:「犯された白衣」(若松孝二)
織田俊彦/渡辺とく子/八代康二/田島はるか/中島葵/夢村四郎/秋津令子/水木京一●公開:1976/06●配給:日活●最初に観た場所:池袋文芸地下(82-11-14)(評価:★★★)●併映:「犯された白衣」(若松孝二) 





 寛永18年、肥後熊本の城主・細川忠利が逝去し、生前より主の許しを受け殉死した者が18名に及んだが、殉死を許されなかった阿部弥一右衛門(市川笑太郎)に対しては、家中の者の見る眼が変わり、結局彼は息子達の目の前で切腹して果て、更に先君の一周忌には、長男・権兵衛(橘小三郎)がこれに抗議する行動を起こし非礼として縛り首となり、次男・弥五兵衛(中村翫右衛門)以下阿部一族は、主君への謀反人として討たれることになる―。
寛永18年、肥後熊本の城主・細川忠利が逝去し、生前より主の許しを受け殉死した者が18名に及んだが、殉死を許されなかった阿部弥一右衛門(市川笑太郎)に対しては、家中の者の見る眼が変わり、結局彼は息子達の目の前で切腹して果て、更に先君の一周忌には、長男・権兵衛(橘小三郎)がこれに抗議する行動を起こし非礼として縛り首となり、次男・弥五兵衛(中村翫右衛門)以下阿部一族は、主君への謀反人として討たれることになる―。
 熊谷久虎(1904‐1986)監督により1938年に映画化されていますが(このほかに深作欣二(1930‐2003)監督も1995年にテレビ映画化している)、黒
熊谷久虎(1904‐1986)監督により1938年に映画化されていますが(このほかに深作欣二(1930‐2003)監督も1995年にテレビ映画化している)、黒 澤明監督が演出の手本にしたという熊谷久虎作品はたいへん判り易いもので、但し、判り易すぎると言うか、弥一右衛門のことを噂する家中の者の口ぶりは、サラリーマンの職場でのヒソヒソ話と変わらなかったりして(親近感は覚えるけれど)、小説の中でも触れられている犬飼いの五助の殉死や、小心者の畑十太夫などについても、コミカルで現代的なタッチで描かれています(この辺りで残酷な場面はない)。
澤明監督が演出の手本にしたという熊谷久虎作品はたいへん判り易いもので、但し、判り易すぎると言うか、弥一右衛門のことを噂する家中の者の口ぶりは、サラリーマンの職場でのヒソヒソ話と変わらなかったりして(親近感は覚えるけれど)、小説の中でも触れられている犬飼いの五助の殉死や、小心者の畑十太夫などについても、コミカルで現代的なタッチで描かれています(この辺りで残酷な場面はない)。 一方、登場人物中で殉死に唯一懐疑的な隣家の女中・お咲(堤真佐子)と、彼女と親しい仲間多助(市川莚司)は映画オリジナルのキャラであり、市川莚司(後の加東大介)の主君の追い腹を切ろうとしてもいざとなるとビビって切れないという演技もまたコミカルでした。
一方、登場人物中で殉死に唯一懐疑的な隣家の女中・お咲(堤真佐子)と、彼女と親しい仲間多助(市川莚司)は映画オリジナルのキャラであり、市川莚司(後の加東大介)の主君の追い腹を切ろうとしてもいざとなるとビビって切れないという演技もまたコミカルでした。


 「阿部一族」●制作年:1938年●監督:熊谷久虎●製作:東宝/前進座●脚本:熊谷久虎/安達伸男●撮影:鈴木博●音楽:深井史郎/P・C・L管絃楽団●原作:森鷗外「阿部一族」●時間:106分●出演:中村翫右衛門/河原崎長十郎/市川笑太郎/橘小三郎/山岸しづ江/堤真
「阿部一族」●制作年:1938年●監督:熊谷久虎●製作:東宝/前進座●脚本:熊谷久虎/安達伸男●撮影:鈴木博●音楽:深井史郎/P・C・L管絃楽団●原作:森鷗外「阿部一族」●時間:106分●出演:中村翫右衛門/河原崎長十郎/市川笑太郎/橘小三郎/山岸しづ江/堤真


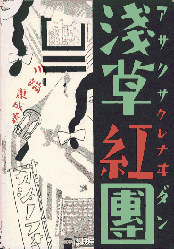


 昭和初期の浅草を舞台に、不良不良少年・少女のグループ「浅草紅団」の女リーダー・弓子に案内され、花屋敷や昆虫館、見世物小屋やカジノ・フォーリーと巡る"私"の眼に映った、浅草の路地に生きる人々の喜怒哀楽を描く―。
昭和初期の浅草を舞台に、不良不良少年・少女のグループ「浅草紅団」の女リーダー・弓子に案内され、花屋敷や昆虫館、見世物小屋やカジノ・フォーリーと巡る"私"の眼に映った、浅草の路地に生きる人々の喜怒哀楽を描く―。
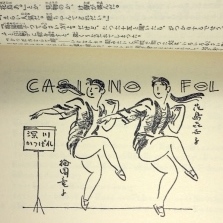 川端康成(1899-1972)の浅草への愛着は相当なもので、カジノ・フォーリーから当時15、6歳だった踊子・
川端康成(1899-1972)の浅草への愛着は相当なもので、カジノ・フォーリーから当時15、6歳だった踊子・


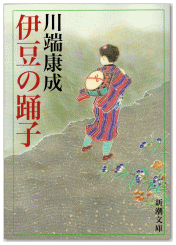



 1926(大正15)年、川端康成(1899- 1972)が26歳の時に発表された作品で、主人公は数え年二十歳の旧制一高生ですが、実際に作者が、1918(大正7)年の旧制第一高2年(19歳)当時、湯ヶ島から天城峠を越え、湯ヶ野を経由して下田に至る4泊5日の伊豆旅行の行程で、旅芸人一座と道連れになった経験に着想を得ているそうです。
1926(大正15)年、川端康成(1899- 1972)が26歳の時に発表された作品で、主人公は数え年二十歳の旧制一高生ですが、実際に作者が、1918(大正7)年の旧制第一高2年(19歳)当時、湯ヶ島から天城峠を越え、湯ヶ野を経由して下田に至る4泊5日の伊豆旅行の行程で、旅芸人一座と道連れになった経験に着想を得ているそうです。
 (a)
(a)  (b)
(b)
 吉永小百合(1945年生まれ)・高橋英樹版は、宇野重吉扮する大学教授が過去を回想するという形で始まります(つまり、高橋英樹が齢を重ねて宇野重吉になったということか。冒頭とラストでこの教授の教え子(浜田光夫)のガールフレンド役で、吉永小百合が二役演じている)。
吉永小百合(1945年生まれ)・高橋英樹版は、宇野重吉扮する大学教授が過去を回想するという形で始まります(つまり、高橋英樹が齢を重ねて宇野重吉になったということか。冒頭とラストでこの教授の教え子(浜田光夫)のガールフレンド役で、吉永小百合が二役演じている)。 踊子の兄で旅芸人一座のリーダー役の大坂志郎がいい味を出しているほか、新潮文庫に同録の「温泉宿」(昭和4年発表)のモチーフが織り込まれていて、肺の病を得て床に伏す湯ケ野の酌婦・お清を当時20歳の十朱幸代(1942年生まれ)が演じており、こちらは、吉永小百合との対比で、こうした流浪の生活を送る人々の蔭の部分を象徴しているともとれます。西河監督の弱者を思いやる眼差しが感じられる作りでもありました。
踊子の兄で旅芸人一座のリーダー役の大坂志郎がいい味を出しているほか、新潮文庫に同録の「温泉宿」(昭和4年発表)のモチーフが織り込まれていて、肺の病を得て床に伏す湯ケ野の酌婦・お清を当時20歳の十朱幸代(1942年生まれ)が演じており、こちらは、吉永小百合との対比で、こうした流浪の生活を送る人々の蔭の部分を象徴しているともとれます。西河監督の弱者を思いやる眼差しが感じられる作りでもありました。

 因みに、十朱幸代のデビューはNHKの「バス通り裏」で当時15歳でしたが、番組が終わる時には20歳になっていました。また、岩下志麻(1941年生まれ)も'58年に十朱幸代の友人役としてこの番組でデビューしています。
因みに、十朱幸代のデビューはNHKの「バス通り裏」で当時15歳でしたが、番組が終わる時には20歳になっていました。また、岩下志麻(1941年生まれ)も'58年に十朱幸代の友人役としてこの番組でデビューしています。


 「バス通り裏」テーマソングレコード
「バス通り裏」テーマソングレコード
 「伊豆の踊子」●制作年:1963年●監督:西河克己●脚本:三木克己/西河克己●撮影:横山実●音楽:池田正義●原作:川端康成●時間:87分●出演:高橋英樹/吉永小百合/大
「伊豆の踊子」●制作年:1963年●監督:西河克己●脚本:三木克己/西河克己●撮影:横山実●音楽:池田正義●原作:川端康成●時間:87分●出演:高橋英樹/吉永小百合/大 坂志郎/桂小金治/井上昭文/土方弘/郷鍈治/堀恭子/安田千永子/深見泰三/福田トヨ/峰三平/小峰千代子/浪花千栄子/茂手木かすみ/十朱幸代/南田洋子/澄川透/新井麗子/三船好重/大倉節美/高山千草/伊豆見雄/瀬山孝司/森重孝/松岡高史/渡辺節子/若葉めぐみ/青柳真美/高橋玲子/豊澄清子/飯島美知秀/奥園誠/大野茂樹/花柳一輔/峰三平/宇野重吉/浜田光夫●公開:1963/06●配給:日活●最初に観た場所:池袋・文芸地下(85-01-19)(評価:★★★☆)●併映:「
坂志郎/桂小金治/井上昭文/土方弘/郷鍈治/堀恭子/安田千永子/深見泰三/福田トヨ/峰三平/小峰千代子/浪花千栄子/茂手木かすみ/十朱幸代/南田洋子/澄川透/新井麗子/三船好重/大倉節美/高山千草/伊豆見雄/瀬山孝司/森重孝/松岡高史/渡辺節子/若葉めぐみ/青柳真美/高橋玲子/豊澄清子/飯島美知秀/奥園誠/大野茂樹/花柳一輔/峰三平/宇野重吉/浜田光夫●公開:1963/06●配給:日活●最初に観た場所:池袋・文芸地下(85-01-19)(評価:★★★☆)●併映:「

 宇野重吉(主人公の40年後の今・某大学の教授)
宇野重吉(主人公の40年後の今・某大学の教授)
 藤夫/浅茅しの
藤夫/浅茅しの ぶ/高島稔/永井百合子/鈴木清子/初井言栄/佐藤英夫/松野二葉/溝井哲夫/津山英二/西章子/稲垣隆史/山本一郎/大森義夫/鈴木瑞穂/三木美知子/原昴二/蔵悦子/高橋エマ/網本昌子/常田富士男●放映:1958/04~1963/03(全1395回)●放送局:NHK
ぶ/高島稔/永井百合子/鈴木清子/初井言栄/佐藤英夫/松野二葉/溝井哲夫/津山英二/西章子/稲垣隆史/山本一郎/大森義夫/鈴木瑞穂/三木美知子/原昴二/蔵悦子/高橋エマ/網本昌子/常田富士男●放映:1958/04~1963/03(全1395回)●放送局:NHK

![伊豆の踊子 [VHS]木村拓哉.jpg](http://hurec.bz/book-movie/%E4%BC%8A%E8%B1%86%E3%81%AE%E8%B8%8A%E5%AD%90%20%5BVHS%5D%E6%9C%A8%E6%9D%91%E6%8B%93%E5%93%89.jpg) 日本名作ドラマ『伊豆の踊子』(TX)
日本名作ドラマ『伊豆の踊子』(TX)




 平安末期、侍(森雅之)が妻(京マチ子)を伴っての旅の途中で、多襄丸という盗賊(三船敏郎)とすれ違うが、妻に惹かれた盗賊は、藪の中に財宝があると言って侍を誘い込み、不意に組みついて侍を木に縄で縛りつけ、その目の前で女を手込めにする。
平安末期、侍(森雅之)が妻(京マチ子)を伴っての旅の途中で、多襄丸という盗賊(三船敏郎)とすれ違うが、妻に惹かれた盗賊は、藪の中に財宝があると言って侍を誘い込み、不意に組みついて侍を木に縄で縛りつけ、その目の前で女を手込めにする。 翌朝、侍は死骸となって木樵り(志村喬) に発見されるが、女は行方不明に。後に、一体何が起こり何があったのかを3人の当事者達は語るが、それぞれの言い分に食い違いがあり、真実は杳として知れない―。
翌朝、侍は死骸となって木樵り(志村喬) に発見されるが、女は行方不明に。後に、一体何が起こり何があったのかを3人の当事者達は語るが、それぞれの言い分に食い違いがあり、真実は杳として知れない―。 1951年ヴェネツィア国際映画祭「金獅子賞」並びに米国「アカデミー外国語映画賞」受賞作で、共に日本映画初の受賞でした。原作は芥川龍之介の1915(大正4)年発表の同名小説「羅生門」というよりも、1922(大正11)年1月に雑誌「新潮」に発表の短編「藪の中」が実質的な原作であり、「羅生門」は、橋本忍と黒澤明が脚色したこの映画では、冒頭の背景など題材として一部が使われているだけです。
1951年ヴェネツィア国際映画祭「金獅子賞」並びに米国「アカデミー外国語映画賞」受賞作で、共に日本映画初の受賞でした。原作は芥川龍之介の1915(大正4)年発表の同名小説「羅生門」というよりも、1922(大正11)年1月に雑誌「新潮」に発表の短編「藪の中」が実質的な原作であり、「羅生門」は、橋本忍と黒澤明が脚色したこの映画では、冒頭の背景など題材として一部が使われているだけです。 原作は、事件関係者の証言のみで成り立っていて、木樵、旅法師、放免(警官)、媼(女の母)の順に証言しますが、この部分が事件の説明になっている一方で、彼らは状況証拠ばかりを述べて事件の核心には触れません。続いて当事者3人の証言が続き、多襄丸こと盗人が、侍を殺すつもりは無かったが、女に2人が決闘するように言われ、武士の縄を解いて斬り結んだ末に武士を刺し、その間に女は逃げたと証言、一方の女は、清水寺での懺悔において、無念の夫の自害を自分が幇助し、自分も死のうとしたが死に切れなかったと言います。 そして最後に、侍の霊が巫女の口を借りて、妻が盗人を唆して自分を殺させたと―。
原作は、事件関係者の証言のみで成り立っていて、木樵、旅法師、放免(警官)、媼(女の母)の順に証言しますが、この部分が事件の説明になっている一方で、彼らは状況証拠ばかりを述べて事件の核心には触れません。続いて当事者3人の証言が続き、多襄丸こと盗人が、侍を殺すつもりは無かったが、女に2人が決闘するように言われ、武士の縄を解いて斬り結んだ末に武士を刺し、その間に女は逃げたと証言、一方の女は、清水寺での懺悔において、無念の夫の自害を自分が幇助し、自分も死のうとしたが死に切れなかったと言います。 そして最後に、侍の霊が巫女の口を借りて、妻が盗人を唆して自分を殺させたと―。
 芥川龍之介の原作は、タイトルの通り誰の言うことが真実なのかわからないまま終わってるわけですが、武士が語っていることが(霊となって語っているだけに)何となく侍の言い分が真実味があるように思いました(作者である芥川龍之介は犯人が誰かを示唆したのではなく、それが不可知であることを意図したというのが「通説」のようだが)。
芥川龍之介の原作は、タイトルの通り誰の言うことが真実なのかわからないまま終わってるわけですが、武士が語っていることが(霊となって語っているだけに)何となく侍の言い分が真実味があるように思いました(作者である芥川龍之介は犯人が誰かを示唆したのではなく、それが不可知であることを意図したというのが「通説」のようだが)。
 映画では、原作と同様、盗人、女、侍の証言が再現映像と共に続きますが、女の証言が原作とやや異なり、侍の証言はもっと異なり、しかも最後に、杣売(そまふ)、つまり木樵(志村喬)が、実は自分は始終を見ていたと言って証言しますが、この杣売の証言は原作にはありません。
映画では、原作と同様、盗人、女、侍の証言が再現映像と共に続きますが、女の証言が原作とやや異なり、侍の証言はもっと異なり、しかも最後に、杣売(そまふ)、つまり木樵(志村喬)が、実は自分は始終を見ていたと言って証言しますが、この杣売の証言は原作にはありません。 芥川の「藪の中」と「羅生門」は、岩波文庫、新潮文庫、角川文庫、ちくま文庫などで、それぞれ別々の本(短編集)に収められていますが("やのまん"の『芥川龍之介 羅生門―デカい活字の千円文学!』 ('09年)という単行本に両方が収められていた)、'09年に講談社文庫で両方が1冊入ったもの(タイトルは『藪の中』)が出ました。講談社が製作に加わっている中野裕之監督、小栗旬主演の映画「TAJOMARU(多襄丸)」('09年/ワーナー・ブラザース映画)の公開に合わせてでしょうか。「藪の中」を原作とするこの映画(要するに「羅生門」のリメイク)の評価は散々なものだったらしいですが、「藪の中」という作品が映画「羅生門」の実質的な原作として注目されることはいいことではないかと思います。
芥川の「藪の中」と「羅生門」は、岩波文庫、新潮文庫、角川文庫、ちくま文庫などで、それぞれ別々の本(短編集)に収められていますが("やのまん"の『芥川龍之介 羅生門―デカい活字の千円文学!』 ('09年)という単行本に両方が収められていた)、'09年に講談社文庫で両方が1冊入ったもの(タイトルは『藪の中』)が出ました。講談社が製作に加わっている中野裕之監督、小栗旬主演の映画「TAJOMARU(多襄丸)」('09年/ワーナー・ブラザース映画)の公開に合わせてでしょうか。「藪の中」を原作とするこの映画(要するに「羅生門」のリメイク)の評価は散々なものだったらしいですが、「藪の中」という作品が映画「羅生門」の実質的な原作として注目されることはいいことではないかと思います。




 「羅生門」●制作年:1950年●監督:黒澤明●製作:箕浦甚吾●脚本:黒澤明/橋本忍●撮影:宮川一夫●音楽:早坂文雄●原作:芥川龍之介「藪の中」●時間:88分●出演:三船敏郎/森雅之/京マチ子/
「羅生門」●制作年:1950年●監督:黒澤明●製作:箕浦甚吾●脚本:黒澤明/橋本忍●撮影:宮川一夫●音楽:早坂文雄●原作:芥川龍之介「藪の中」●時間:88分●出演:三船敏郎/森雅之/京マチ子/ 映●最初に観た場所:高田馬場ACTミニシアター(84-12-0
映●最初に観た場所:高田馬場ACTミニシアター(84-12-0
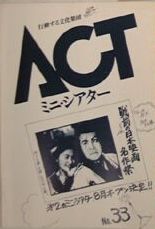

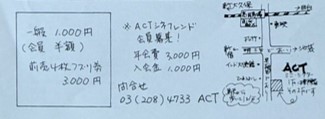
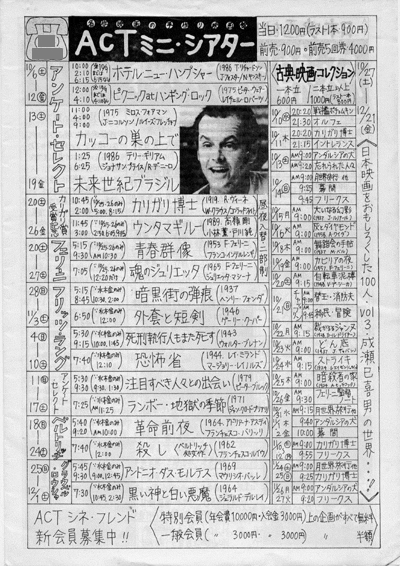 ACTミニシアターのチラシ http://d.hatena.ne.jp/oyama_noboruko/20070519/p1 大山昇子氏「女おいどん日記」より
ACTミニシアターのチラシ http://d.hatena.ne.jp/oyama_noboruko/20070519/p1 大山昇子氏「女おいどん日記」より






 江戸の伊達家の大名屋敷に着任した赤西蠣太(片岡千恵蔵)は、風采が上がらず胃弱のお人好し侍だが、実は彼は、江戸にいる伊達兵部(瀬川路三郎)と原田甲斐(片岡千恵蔵・二役)による藩転覆の陰謀の証拠を掴むという密命を帯びて送られてきた間者(スパイ)であり、彼の目的は、同じく間者として送り込まれていた青鮫鱒次郎(原健作)と集めた様々な証拠を、無事に国許へ持ち帰ることだった。江戸藩邸を出奔する理由として蠣太らは、蠣太が邸内随一の美人である小波(毛利峯子)に落とし文をして袖にされ、面目を保てなくなったというストーリーを練る―。
江戸の伊達家の大名屋敷に着任した赤西蠣太(片岡千恵蔵)は、風采が上がらず胃弱のお人好し侍だが、実は彼は、江戸にいる伊達兵部(瀬川路三郎)と原田甲斐(片岡千恵蔵・二役)による藩転覆の陰謀の証拠を掴むという密命を帯びて送られてきた間者(スパイ)であり、彼の目的は、同じく間者として送り込まれていた青鮫鱒次郎(原健作)と集めた様々な証拠を、無事に国許へ持ち帰ることだった。江戸藩邸を出奔する理由として蠣太らは、蠣太が邸内随一の美人である小波(毛利峯子)に落とし文をして袖にされ、面目を保てなくなったというストーリーを練る―。 原作は、伊達騒動に材を得た志賀直哉が1918(大正7)年9月に『新小説』に発表した時代小説で、志賀直哉が生涯において書いた時代小説はこの作品だけだそうですが、伊丹万作が二枚目役者・片岡千恵蔵に醜男・赤西蠣太の役を配して、ユーモラスな作品に仕上げています。
原作は、伊達騒動に材を得た志賀直哉が1918(大正7)年9月に『新小説』に発表した時代小説で、志賀直哉が生涯において書いた時代小説はこの作品だけだそうですが、伊丹万作が二枚目役者・片岡千恵蔵に醜男・赤西蠣太の役を配して、ユーモラスな作品に仕上げています。 角川文庫、新潮文庫、ちくま文庫などに収められいる原作は20ページほどの小品ですが、それが1時間半近い作品になっているわけで、蠣太と隣人との武士の迷い猫の押し付け合いや、なかなかラブレターがうまく書けない蠣太の様子などのユーモラスなリフレインを入れて多少は時間を稼いでいるものの(それらも赤西蠣太の人柄を表すうえで無駄な付け加えという風には感じない)、概ね原作に忠実に作られていると見てよく、ある意味、志賀直哉の文体が、如何に簡潔で圧縮度が高いものであるかを示していることにもなっているように思えました。
角川文庫、新潮文庫、ちくま文庫などに収められいる原作は20ページほどの小品ですが、それが1時間半近い作品になっているわけで、蠣太と隣人との武士の迷い猫の押し付け合いや、なかなかラブレターがうまく書けない蠣太の様子などのユーモラスなリフレインを入れて多少は時間を稼いでいるものの(それらも赤西蠣太の人柄を表すうえで無駄な付け加えという風には感じない)、概ね原作に忠実に作られていると見てよく、ある意味、志賀直哉の文体が、如何に簡潔で圧縮度が高いものであるかを示していることにもなっているように思えました。 赤西蠣太(実は偽名)の名は原題通りですが、原作における「銀鮫鱒次郎」が原健作が演じる「青鮫(蒼ざめ?)鱒次郎」になっているほか、志村喬が演じる「角又鱈之進」など、主要な登場人物の名前に魚編の文字を入れるなどして、原作の"遊び"を更に増幅させています(意外なことに蠣太に恋心を抱いていたことが判明する「小波」(ささなみ)は、原作では「小江」(さざえ)。何だか"磯野家"みたいになってしまうけれど、同じ海関係なのでこのまま使っても良かったのでは?)。
赤西蠣太(実は偽名)の名は原題通りですが、原作における「銀鮫鱒次郎」が原健作が演じる「青鮫(蒼ざめ?)鱒次郎」になっているほか、志村喬が演じる「角又鱈之進」など、主要な登場人物の名前に魚編の文字を入れるなどして、原作の"遊び"を更に増幅させています(意外なことに蠣太に恋心を抱いていたことが判明する「小波」(ささなみ)は、原作では「小江」(さざえ)。何だか"磯野家"みたいになってしまうけれど、同じ海関係なのでこのまま使っても良かったのでは?)。

 しかし、この映画の白眉とも言える最大の"遊び"は、謀反の黒幕である原田甲斐(山本周五郎の『樅の木は残った』ではこの人物に新解釈を加えているが、この作品では型通りの「悪役」として描かれている)、つまり主人公にとってのある種「敵役」を演じているのもまた片岡千恵蔵その人であるということです。当時の映画作りにおいて一人二役はそれほど珍しいことではないですが、これはよく出来ている!
しかし、この映画の白眉とも言える最大の"遊び"は、謀反の黒幕である原田甲斐(山本周五郎の『樅の木は残った』ではこの人物に新解釈を加えているが、この作品では型通りの「悪役」として描かれている)、つまり主人公にとってのある種「敵役」を演じているのもまた片岡千恵蔵その人であるということです。当時の映画作りにおいて一人二役はそれほど珍しいことではないですが、これはよく出来ている! "赤西蠣太"としての演技が、同僚の下級武士の演技より一段とすっとぼけた現代的なサラリーマンのような感じであるのに対し(千恵蔵の演技だけ見ていると、とても戦前の作品とは思えない)、"原田甲斐"としての台詞は、官僚的な上級武士の中でも目立って大時代的な歌舞伎調の文
"赤西蠣太"としての演技が、同僚の下級武士の演技より一段とすっとぼけた現代的なサラリーマンのような感じであるのに対し(千恵蔵の演技だけ見ていると、とても戦前の作品とは思えない)、"原田甲斐"としての台詞は、官僚的な上級武士の中でも目立って大時代的な歌舞伎調の文 語になっているという、この対比が面白いと言うか、見事と言っていいくらいです。事前の予備知識がなければ、同じ役者が演じているとは絶対に気づかないかも。因みに片岡千恵蔵は、2年後の「
語になっているという、この対比が面白いと言うか、見事と言っていいくらいです。事前の予備知識がなければ、同じ役者が演じているとは絶対に気づかないかも。因みに片岡千恵蔵は、2年後の「
 原作は、伊達騒動の経緯自体は僅か1行半で済ませていますが、映画では、当時から見ても更に時代の旧い無声映画風のコマ落とし的描写で早送りしていて、伊達騒動自体は周知のこととして細かく触れていないという点でも原作に忠実です。
原作は、伊達騒動の経緯自体は僅か1行半で済ませていますが、映画では、当時から見ても更に時代の旧い無声映画風のコマ落とし的描写で早送りしていて、伊達騒動自体は周知のこととして細かく触れていないという点でも原作に忠実です。  一方で、「蠣太と小江との恋がどうなったかが書けるといいが、昔の事で今は調べられない。それはわからず了いである」として原作は終わっていますが、映画では、蠣太が"小波"の実家を訪ね、結婚行進曲(作中にもショパンのピアノ曲などが使われている)が流れるところで終わるという、微笑ましいエンディングになっています。
一方で、「蠣太と小江との恋がどうなったかが書けるといいが、昔の事で今は調べられない。それはわからず了いである」として原作は終わっていますが、映画では、蠣太が"小波"の実家を訪ね、結婚行進曲(作中にもショパンのピアノ曲などが使われている)が流れるところで終わるという、微笑ましいエンディングになっています。 「赤西蠣太」●制作年:1936年●監督・脚本:伊丹万作●製作:片岡千恵蔵プロダクション●撮影:漆山裕茂●音楽:高橋半●原作:志賀直哉「赤西蠣太」●時間:84分●出演:片岡千恵蔵/杉
「赤西蠣太」●制作年:1936年●監督・脚本:伊丹万作●製作:片岡千恵蔵プロダクション●撮影:漆山裕茂●音楽:高橋半●原作:志賀直哉「赤西蠣太」●時間:84分●出演:片岡千恵蔵/杉 山昌三九/
山昌三九/

 ●田中小実昌(作家・翻訳家,1925-2000)の推す喜劇映画ベスト10(『
●田中小実昌(作家・翻訳家,1925-2000)の推す喜劇映画ベスト10(『

 併録2篇のうち「安井夫人」は江戸時代の大儒・安井仲平(息軒)の人生を辿ったもので、貧しい儒者の家に生まれ、幼少時から真面目な勉強家でありながらも、仲間から「猿が本を読む」と蔑まれるほどの不男(ぶおとこ)であるために、三十路を控えて嫁話が無かった彼に、それを気にした周囲が知人の姉妹のうち器量十人並みの姉の方に話を持ちかけるも、彼女にさえも、「仲平さんはえらい方だと思つてゐますが、御亭主にするのは嫌でございます」と冷たく断られたところ、何とその妹で「岡の小町」と言われるほどの評判の美人だった16歳のお佐代の方が、思いもかけず自らの意思で嫁に来たという...。
併録2篇のうち「安井夫人」は江戸時代の大儒・安井仲平(息軒)の人生を辿ったもので、貧しい儒者の家に生まれ、幼少時から真面目な勉強家でありながらも、仲間から「猿が本を読む」と蔑まれるほどの不男(ぶおとこ)であるために、三十路を控えて嫁話が無かった彼に、それを気にした周囲が知人の姉妹のうち器量十人並みの姉の方に話を持ちかけるも、彼女にさえも、「仲平さんはえらい方だと思つてゐますが、御亭主にするのは嫌でございます」と冷たく断られたところ、何とその妹で「岡の小町」と言われるほどの評判の美人だった16歳のお佐代の方が、思いもかけず自らの意思で嫁に来たという...。 数え78歳まで生きた仲平に対しお佐代は51歳で亡くなり、仲平に"投資"した彼女がその分の回収をみないうちに亡くなってしまったともとれますが、鷗外はそうは解釈せず、常にお佐代は未来に望みを託しており、自分の死の不幸すら感じる余裕が無かったのではと、こちらは鷗外のお佐代に対する好感とその人生への肯定が、直截に表されています。
数え78歳まで生きた仲平に対しお佐代は51歳で亡くなり、仲平に"投資"した彼女がその分の回収をみないうちに亡くなってしまったともとれますが、鷗外はそうは解釈せず、常にお佐代は未来に望みを託しており、自分の死の不幸すら感じる余裕が無かったのではと、こちらは鷗外のお佐代に対する好感とその人生への肯定が、直截に表されています。

 上林 暁 (かんばやし・あかつき)
上林 暁 (かんばやし・あかつき)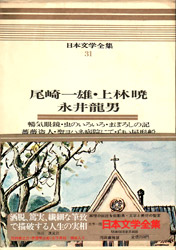
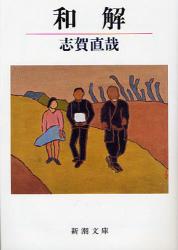
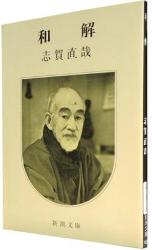
 新潮文庫旧版
新潮文庫旧版
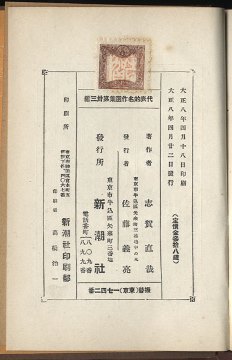 1917(大正6)年10月、志賀直哉(1883‐1971)が34歳の時に発表した中篇で、父と不和になっていた主人公の「順吉」が、次女の誕生を機に、次第に父と和解していく様が描かれていますが、志賀直哉はこの年の8月に、それまで確執のあった父親と和解しており、この作品は志賀直哉自身のことをほぼそのままに書いた私小説と見ていいのではないかと思います。父との確執から尾道に籠もり、父との葛藤をテーマに『時任謙作』という長編を仕上げようとして成らず、その後、本作にある実生活での父との「和解」を経て問題を"対象化"することが出来、それが『暗夜行路』に繋がったという時間的経緯を再確認しました。
1917(大正6)年10月、志賀直哉(1883‐1971)が34歳の時に発表した中篇で、父と不和になっていた主人公の「順吉」が、次女の誕生を機に、次第に父と和解していく様が描かれていますが、志賀直哉はこの年の8月に、それまで確執のあった父親と和解しており、この作品は志賀直哉自身のことをほぼそのままに書いた私小説と見ていいのではないかと思います。父との確執から尾道に籠もり、父との葛藤をテーマに『時任謙作』という長編を仕上げようとして成らず、その後、本作にある実生活での父との「和解」を経て問題を"対象化"することが出来、それが『暗夜行路』に繋がったという時間的経緯を再確認しました。 この『和解』は、そうした作家が一皮むけるに至った経緯を知る上では重要な作品であるし、面白いと思います。但し、単体の小説としては個人的はそれほどいいと思えず、文体は既に完成されているのだけれど、何か見せ隠ししながら書いている感じもあって、何となくすらすら読めなかったような気がします。
この『和解』は、そうした作家が一皮むけるに至った経緯を知る上では重要な作品であるし、面白いと思います。但し、単体の小説としては個人的はそれほどいいと思えず、文体は既に完成されているのだけれど、何か見せ隠ししながら書いている感じもあって、何となくすらすら読めなかったような気がします。





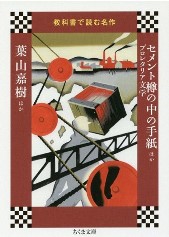

 とは言え、こうした形で作品化されると、何となく、「ホラー・メルヘン」みたいな感じになっているような気がしないでもなく、続く「淫売婦」なども、作り話っぽさが抜けきれないように思えました(「淫売婦」は2018年、児玉公広監督、「ある女工記」として映画化され、コルカタ国際短編映画祭特別賞、ニース国際映画祭主要5部門ノミネートなど国際映画祭で高い評価を得ている)。
とは言え、こうした形で作品化されると、何となく、「ホラー・メルヘン」みたいな感じになっているような気がしないでもなく、続く「淫売婦」なども、作り話っぽさが抜けきれないように思えました(「淫売婦」は2018年、児玉公広監督、「ある女工記」として映画化され、コルカタ国際短編映画祭特別賞、ニース国際映画祭主要5部門ノミネートなど国際映画祭で高い評価を得ている)。
 藤宮史 版画 「木版漫画 セメント樽の中の手紙」(原作:葉山嘉樹)[黒猫堂出版]
藤宮史 版画 「木版漫画 セメント樽の中の手紙」(原作:葉山嘉樹)[黒猫堂出版]





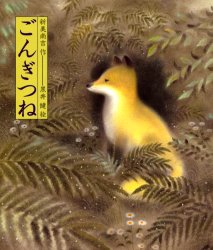
 新美南吉(1913-1943/享年29)
新美南吉(1913-1943/享年29)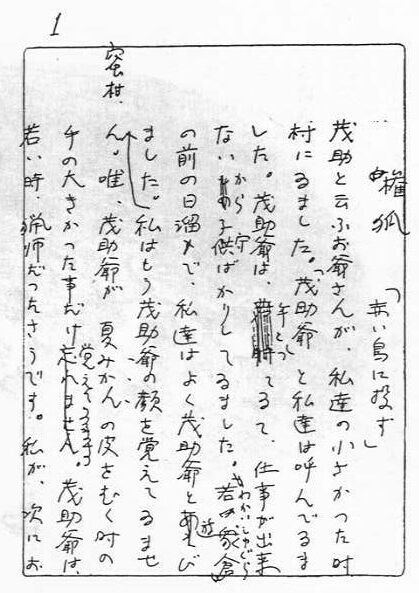 原作「権狐」は、南吉18歳の時の投稿作品で、「赤い鳥」創刊者の鈴木三重吉の目にとまり、同誌に掲載されましたが(因みに三重吉は、同誌に投稿された宮沢賢治の作品は全く認めず、全てボツにした)、この三重吉という人、他人の原稿を雑誌掲載前にどんどん勝手に手直しすることで有名だったようです。
原作「権狐」は、南吉18歳の時の投稿作品で、「赤い鳥」創刊者の鈴木三重吉の目にとまり、同誌に掲載されましたが(因みに三重吉は、同誌に投稿された宮沢賢治の作品は全く認めず、全てボツにした)、この三重吉という人、他人の原稿を雑誌掲載前にどんどん勝手に手直しすることで有名だったようです。 東京外国語学校英文科に学び、その後女学校の教師などをしていた南吉は29歳で夭逝しますが、生涯に3度の恋をしたことが知られており、最後の恋の相手が、先ほどの冒頭文に続く「むかしは、私たちの村のちかくの、中山といふところに小さなお城があつて、中山さまといふおとのさまが、をられたさうです」とある「中山家」の六女ちゑだったとのこと。
東京外国語学校英文科に学び、その後女学校の教師などをしていた南吉は29歳で夭逝しますが、生涯に3度の恋をしたことが知られており、最後の恋の相手が、先ほどの冒頭文に続く「むかしは、私たちの村のちかくの、中山といふところに小さなお城があつて、中山さまといふおとのさまが、をられたさうです」とある「中山家」の六女ちゑだったとのこと。

 芥川 龍之介
芥川 龍之介 2005(平成17)年3月の偕成社刊。原作は1920(大正9)年1月に芥川龍之介(1892-1927)が雑
2005(平成17)年3月の偕成社刊。原作は1920(大正9)年1月に芥川龍之介(1892-1927)が雑 誌「赤い鳥」に発表、『影燈籠』('20年/春陽堂)に収められた、芥川の所謂「年少文学」というべき作品の1つで、同じ系譜に「蜘蛛の糸」や「杜子春」などがありますが、本書の絵を画いている挿画家の宮本順子氏は、この偕成社の「日本の童話名作選」シリーズでは他に同じく芥川作品である「トロッコ」の絵も手掛けています。
誌「赤い鳥」に発表、『影燈籠』('20年/春陽堂)に収められた、芥川の所謂「年少文学」というべき作品の1つで、同じ系譜に「蜘蛛の糸」や「杜子春」などがありますが、本書の絵を画いている挿画家の宮本順子氏は、この偕成社の「日本の童話名作選」シリーズでは他に同じく芥川作品である「トロッコ」の絵も手掛けています。
 作品は、昭和40年代頃には、光村図書出版の『中等新国語』、つまり中学の「国語」の教科書(中学1年生用)に使用されていました。
作品は、昭和40年代頃には、光村図書出版の『中等新国語』、つまり中学の「国語」の教科書(中学1年生用)に使用されていました。 先に原作を読んでいると、絵本になった時に、どれだけ絵が良くても自分の作品イメージとの食い違いが大きくて気に入らないことがありますが、この宮本順子氏の絵は比較的しっくりきました。
先に原作を読んでいると、絵本になった時に、どれだけ絵が良くても自分の作品イメージとの食い違いが大きくて気に入らないことがありますが、この宮本順子氏の絵は比較的しっくりきました。

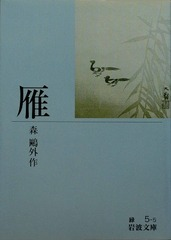


 「僕」は上条という下宿屋に住む学生で、古本を仲立ちに隣室の岡田という医科大学生と親しくなる。一方、無縁坂に住むお玉は、老父と自分の生活のために高利貸しの末造の妾となっているが、末造から貰った紅雀を鳥籠に入れて軒に下げていたところを蛇に襲われ、それを偶然助けた岡田に対し、以来、想いを寄せるようになり、岡田も無縁坂の"窓の女"のことを気にしている。そしていよいよ、末造が訪れてこないとわかっている日が来て、お玉は岡田が通りかかるのを心待ちにするが―。
「僕」は上条という下宿屋に住む学生で、古本を仲立ちに隣室の岡田という医科大学生と親しくなる。一方、無縁坂に住むお玉は、老父と自分の生活のために高利貸しの末造の妾となっているが、末造から貰った紅雀を鳥籠に入れて軒に下げていたところを蛇に襲われ、それを偶然助けた岡田に対し、以来、想いを寄せるようになり、岡田も無縁坂の"窓の女"のことを気にしている。そしていよいよ、末造が訪れてこないとわかっている日が来て、お玉は岡田が通りかかるのを心待ちにするが―。
 尚、この作品は、1953年に豊田四郎の監督、高峰秀子、芥川比呂志の主演(高利貸しの末造役は東野英治郎)で映画化され(ビデオで観たが、かなり分かりやすくなっているように思った)、1966年には池広一夫の監督、若尾文子、山本学の主演(末造役は小沢栄太郎)で映画化されていますが、現時点['07年]で共にDVD化されていません。
尚、この作品は、1953年に豊田四郎の監督、高峰秀子、芥川比呂志の主演(高利貸しの末造役は東野英治郎)で映画化され(ビデオで観たが、かなり分かりやすくなっているように思った)、1966年には池広一夫の監督、若尾文子、山本学の主演(末造役は小沢栄太郎)で映画化されていますが、現時点['07年]で共にDVD化されていません。
 因みに、1924年生まれの高峰秀子は当時29歳で、1933年生まれの若尾文子は32歳で、1955年生まれの田中裕子は38歳でお玉を演じたのに対し、「文學ト云フ事」の井出薫(1976年12月生まれ)は当時17歳の高校3年生で、原作通り数えで19歳でお玉を演じたことになります。
因みに、1924年生まれの高峰秀子は当時29歳で、1933年生まれの若尾文子は32歳で、1955年生まれの田中裕子は38歳でお玉を演じたのに対し、「文學ト云フ事」の井出薫(1976年12月生まれ)は当時17歳の高校3年生で、原作通り数えで19歳でお玉を演じたことになります。
 「雁」●制作年:1953年●監督:豊田四郎●企画:平尾郁次/黒岩健而●脚本:成澤昌茂●撮
「雁」●制作年:1953年●監督:豊田四郎●企画:平尾郁次/黒岩健而●脚本:成澤昌茂●撮
 影:三浦光雄●音楽:團伊玖磨●原作:森鷗外「雁」●時間:87分●出演:高峰秀子/田中栄三/小田切みき/浜路真千子/東野英治郎/浦辺粂子/芥川比呂志/宇野重吉/三宅邦子/飯田蝶子/山田禅二/直木彰/宮田悦子/若水葉子●公開:1953/09●配給:大映(評価:★★★☆)
影:三浦光雄●音楽:團伊玖磨●原作:森鷗外「雁」●時間:87分●出演:高峰秀子/田中栄三/小田切みき/浜路真千子/東野英治郎/浦辺粂子/芥川比呂志/宇野重吉/三宅邦子/飯田蝶子/山田禅二/直木彰/宮田悦子/若水葉子●公開:1953/09●配給:大映(評価:★★★☆)

.jpg)


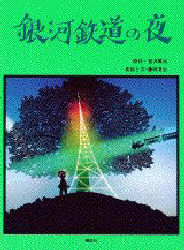
.jpg)




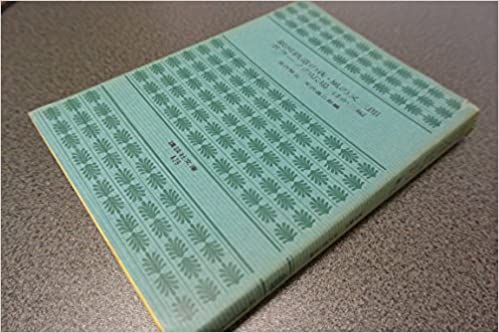
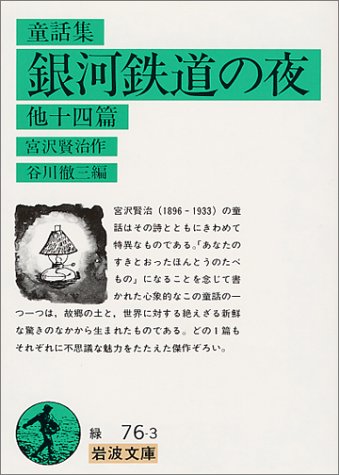 『
『





 1943(昭和18)年発表の「李陵」は、中島敦(1909‐1942/享年33)のおそらく最後の作品と思われるもので(「李陵」というタイトルは、作者の死後、遺稿を受け取った深田久弥が最も無難な題名を選び命名したもの)、前漢・武帝の時代に匈奴と戦って敗れ虜囚となった李陵と、李陵を弁護して武帝の怒りを買い宮刑に処せられるも「史記」の編纂に情熱を注いだ司馬遷の生涯を併せて描いていて、淡々とした筆致の際にも、運命に翻弄された両者への作者の思い入れが切々と滲み出る作品です。
1943(昭和18)年発表の「李陵」は、中島敦(1909‐1942/享年33)のおそらく最後の作品と思われるもので(「李陵」というタイトルは、作者の死後、遺稿を受け取った深田久弥が最も無難な題名を選び命名したもの)、前漢・武帝の時代に匈奴と戦って敗れ虜囚となった李陵と、李陵を弁護して武帝の怒りを買い宮刑に処せられるも「史記」の編纂に情熱を注いだ司馬遷の生涯を併せて描いていて、淡々とした筆致の際にも、運命に翻弄された両者への作者の思い入れが切々と滲み出る作品です。


 新潮文庫版にはありませんが、この人には1942(昭和17)年に『古譚』として「山月記」と併せて発表された「文字禍」や「木乃伊」といった古代エジプトやアッシリアに材を得た作品もあり、「木乃伊」(かつて講談社文庫版(『山月記・弟子・李陵ほか三編』['73年])で読んだが絶版になり、その後、講談社文芸文庫版(『斗南先生・南島譚』['97年])、ちくま文庫版(『ちくま日本の文学12』['08年]))などに所収)は、前世の自分のミイラと遭遇してそのミイラの生きていた時に転生し、さらにそれがまた前世の自分のミイラと遭遇し...というタイムトラベルSFみたいな話で、奥深さと面白さを兼ねそえた作品でした。
新潮文庫版にはありませんが、この人には1942(昭和17)年に『古譚』として「山月記」と併せて発表された「文字禍」や「木乃伊」といった古代エジプトやアッシリアに材を得た作品もあり、「木乃伊」(かつて講談社文庫版(『山月記・弟子・李陵ほか三編』['73年])で読んだが絶版になり、その後、講談社文芸文庫版(『斗南先生・南島譚』['97年])、ちくま文庫版(『ちくま日本の文学12』['08年]))などに所収)は、前世の自分のミイラと遭遇してそのミイラの生きていた時に転生し、さらにそれがまた前世の自分のミイラと遭遇し...というタイムトラベルSFみたいな話で、奥深さと面白さを兼ねそえた作品でした。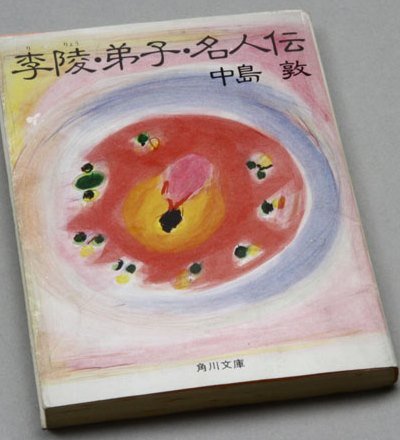
 【1952年文庫化[角川文庫(『李陵・弟子・名人伝』)]/1967年再文庫化・1989年改版[旺文社文庫(『李陵・弟子・山月記』)]/1968年再文庫化[角川文庫(『李陵・山月記・弟子・名人伝』)]/1969年再文庫化[新潮文庫(『李陵・山月記』)]/1973年再文庫化[講談社文庫(『山月記・弟子・李陵ほか三編』)]/1993年再文庫化[集英社文庫(『山月記・李陵』)]/1994年再文庫化[岩波文庫(『李陵・山月記 他九篇』)]/1995年再文庫化・1999年改版[角川文庫(『李陵・山月記・弟子・名人伝』)]/2000年再文庫化[小学館文庫(『李陵・山月記』)]/2012年再文庫化[ハルキ文庫(『李陵・山月記』)]】
【1952年文庫化[角川文庫(『李陵・弟子・名人伝』)]/1967年再文庫化・1989年改版[旺文社文庫(『李陵・弟子・山月記』)]/1968年再文庫化[角川文庫(『李陵・山月記・弟子・名人伝』)]/1969年再文庫化[新潮文庫(『李陵・山月記』)]/1973年再文庫化[講談社文庫(『山月記・弟子・李陵ほか三編』)]/1993年再文庫化[集英社文庫(『山月記・李陵』)]/1994年再文庫化[岩波文庫(『李陵・山月記 他九篇』)]/1995年再文庫化・1999年改版[角川文庫(『李陵・山月記・弟子・名人伝』)]/2000年再文庫化[小学館文庫(『李陵・山月記』)]/2012年再文庫化[ハルキ文庫(『李陵・山月記』)]】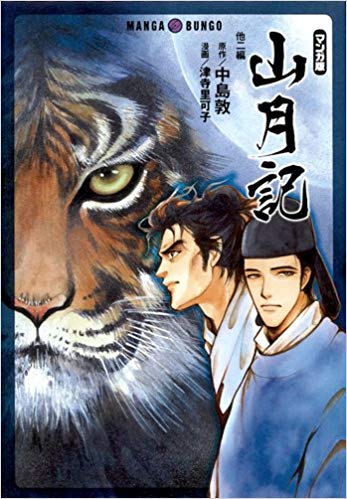
 《読書MEMO》
《読書MEMO》


.jpg)

 1937(昭和12)年に発表された永井荷風(1879‐1959)58歳の頃の作品で(朝日新聞連載)、向島玉の井の私娼街に取材に行った58歳の作家〈わたくし〉大江匡と、26歳の娼婦・お雪の出会いから別れまでの短い期間の出来事を描いています。
1937(昭和12)年に発表された永井荷風(1879‐1959)58歳の頃の作品で(朝日新聞連載)、向島玉の井の私娼街に取材に行った58歳の作家〈わたくし〉大江匡と、26歳の娼婦・お雪の出会いから別れまでの短い期間の出来事を描いています。 昭和初期の下町情緒たっぷりで、浅草から向島まで散策する主人公を(よく歩く!)、地図で追いながら読むのもいいですが、「吉原」ではなく「玉の井」だから「濹東」なのだと理解しつつも、「玉の井」と名のつくものが地図上から殆ど抹消されているためわかりにくいかも知れません。でも、土地勘が無くとも、流麗な筆致の描写を通して、梅雨から秋にかけての江戸名残りの季節風物が堪能できます。
昭和初期の下町情緒たっぷりで、浅草から向島まで散策する主人公を(よく歩く!)、地図で追いながら読むのもいいですが、「吉原」ではなく「玉の井」だから「濹東」なのだと理解しつつも、「玉の井」と名のつくものが地図上から殆ど抹消されているためわかりにくいかも知れません。でも、土地勘が無くとも、流麗な筆致の描写を通して、梅雨から秋にかけての江戸名残りの季節風物が堪能できます。
 1960年に豊田四郎(「
1960年に豊田四郎(「 が〈種田〉とほぼ同一化されていて(主人公は種田)、種田はお雪の求婚に対して返事を曖昧にし、やがて
が〈種田〉とほぼ同一化されていて(主人公は種田)、種田はお雪の求婚に対して返事を曖昧にし、やがて そうこうしているうちにお雪は病気になって死を待つばかりとなります。お雪のキャラクターが明るいものになっているため、結末が却って切ないものとなっています。白黒映画で玉の井のセットがよくできていて、途中に芥川比呂志による原作の朗読が入り、ラストでは〈荷風〉と思しき人物が玉の井を散策(徘徊?)しています。この(荷風〉と思しき人は、主人公・種田の行く芳造(宮口精二)のおでん屋にもいました。しいて言えば、これが原作における〈大江〉乃至〈作者(荷風)〉に当たるということでしょうか。」(●2023年、15年ぶりに神保町シアター「女優魂」特集で再見。観ていて辛いストーリーだが、山本富士子が演じるお雪はやはりいい。改めてこれは山本富士子の映画だと思った。)
そうこうしているうちにお雪は病気になって死を待つばかりとなります。お雪のキャラクターが明るいものになっているため、結末が却って切ないものとなっています。白黒映画で玉の井のセットがよくできていて、途中に芥川比呂志による原作の朗読が入り、ラストでは〈荷風〉と思しき人物が玉の井を散策(徘徊?)しています。この(荷風〉と思しき人は、主人公・種田の行く芳造(宮口精二)のおでん屋にもいました。しいて言えば、これが原作における〈大江〉乃至〈作者(荷風)〉に当たるということでしょうか。」(●2023年、15年ぶりに神保町シアター「女優魂」特集で再見。観ていて辛いストーリーだが、山本富士子が演じるお雪はやはりいい。改めてこれは山本富士子の映画だと思った。)






 作品中に、前年廃止された京成白髭線の玉ノ井駅の記述がありますが、「玉の井」も今はほとんどその痕跡がありません。また、荷風が中年期を過ごした麻布の家(『断腸亭日乗』に出てくる「偏奇
作品中に、前年廃止された京成白髭線の玉ノ井駅の記述がありますが、「玉の井」も今はほとんどその痕跡がありません。また、荷風が中年期を過ごした麻布の家(『断腸亭日乗』に出てくる「偏奇 館」)も、現在の地下鉄「六本木一丁目」駅前の「泉ガーデンタワー」裏手に当たり、当然のことながら家跡どころか当時の街の面影もまったくありません(一応、こじんまりとした石碑はある)。
館」)も、現在の地下鉄「六本木一丁目」駅前の「泉ガーデンタワー」裏手に当たり、当然のことながら家跡どころか当時の街の面影もまったくありません(一応、こじんまりとした石碑はある)。
 因みに、この作品は個人的には今回「新潮文庫」版で読み返しましたが、木村荘八の挿画が50葉以上掲載されている「岩波文庫」版が改版されて読み易くなったので、そちらがお奨めです。
因みに、この作品は個人的には今回「新潮文庫」版で読み返しましたが、木村荘八の挿画が50葉以上掲載されている「岩波文庫」版が改版されて読み易くなったので、そちらがお奨めです。


 「濹東綺譚」●制作年:1960年●監督:豊田四郎●製作:佐藤一郎●脚本:八住利雄●撮影:玉井正夫●音楽:團伊玖磨●原作:永井荷風「濹東綺譚」「失踪」「荷風日記」●時間:120分●出演:山本富士子/芥川比呂志/新珠三千代/織田新太郎/東野英治郎/乙羽信子/織田政雄/若宮忠三郎/三戸部スエ/戸川暁子/宮口精二/賀原夏子/松村達雄/淡路恵子/高友子/日高澄子/原知佐子/岸田今日子/塩沢くるみ/長岡輝子/北城真記子/中村伸郎/須永康夫/田辺元/田中志幸/中原成男/名古屋章/守田比呂也/加藤寿八/黒岩竜彦/瀬良明/中村芝鶴●公開:1960/08●配給:東宝●最初に観た場所(再見):神保町シアター(08-08-30)●2回目:神保町シアター(23-02-17)(評価:★★★★)
「濹東綺譚」●制作年:1960年●監督:豊田四郎●製作:佐藤一郎●脚本:八住利雄●撮影:玉井正夫●音楽:團伊玖磨●原作:永井荷風「濹東綺譚」「失踪」「荷風日記」●時間:120分●出演:山本富士子/芥川比呂志/新珠三千代/織田新太郎/東野英治郎/乙羽信子/織田政雄/若宮忠三郎/三戸部スエ/戸川暁子/宮口精二/賀原夏子/松村達雄/淡路恵子/高友子/日高澄子/原知佐子/岸田今日子/塩沢くるみ/長岡輝子/北城真記子/中村伸郎/須永康夫/田辺元/田中志幸/中原成男/名古屋章/守田比呂也/加藤寿八/黒岩竜彦/瀬良明/中村芝鶴●公開:1960/08●配給:東宝●最初に観た場所(再見):神保町シアター(08-08-30)●2回目:神保町シアター(23-02-17)(評価:★★★★)












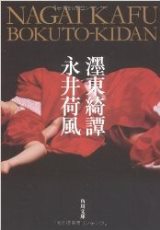






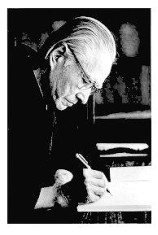 中 勘助
中 勘助  1911(明治44)年に前編が書かれた「銀の匙」は(後編が書かれたのは1913年)、それまで詩作などを中心に創作活動をしていた中勘助(1985‐1965)が、一高・東大時代の師である夏目漱石に勧められて20代半ばで初めて書いた散文であり、書斎の引き出しの小箱の中にしまった銀の小匙にまつわる思い出から始まるこの自伝的作品は漱石に絶賛され、その推挙により、前編は1913年、後編は1915年に朝日新聞に連載されました。
1911(明治44)年に前編が書かれた「銀の匙」は(後編が書かれたのは1913年)、それまで詩作などを中心に創作活動をしていた中勘助(1985‐1965)が、一高・東大時代の師である夏目漱石に勧められて20代半ばで初めて書いた散文であり、書斎の引き出しの小箱の中にしまった銀の小匙にまつわる思い出から始まるこの自伝的作品は漱石に絶賛され、その推挙により、前編は1913年、後編は1915年に朝日新聞に連載されました。

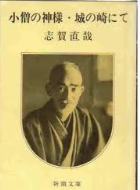
.jpg)
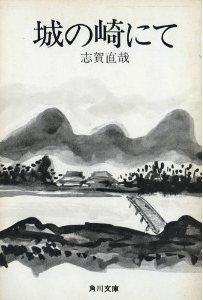



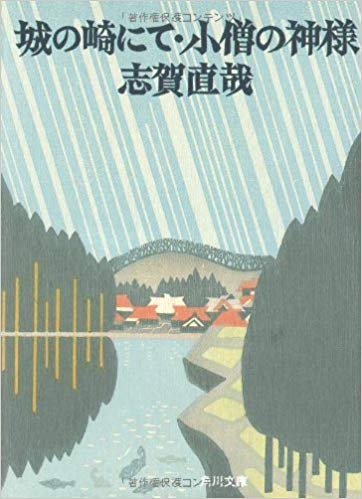 文庫化[角川文庫(『城の崎にて・小僧の神様』)]/1968年再文庫化(改版)[角川文庫(『城の崎にて』)]/1968年再文庫化・1985年改版・2005年改版[新潮文庫(『小僧の神様・城の崎にて』)]/1992年再文庫化[集英社文庫(『清兵衛と瓢箪・小僧の神様』)]/2009年再文庫化[岩波ワイド文庫(『小僧
文庫化[角川文庫(『城の崎にて・小僧の神様』)]/1968年再文庫化(改版)[角川文庫(『城の崎にて』)]/1968年再文庫化・1985年改版・2005年改版[新潮文庫(『小僧の神様・城の崎にて』)]/1992年再文庫化[集英社文庫(『清兵衛と瓢箪・小僧の神様』)]/2009年再文庫化[岩波ワイド文庫(『小僧 の神様―他十編』)]/2012年再文庫化[角川文庫(『城の崎にて・小僧の神様』)]】
の神様―他十編』)]/2012年再文庫化[角川文庫(『城の崎にて・小僧の神様』)]】



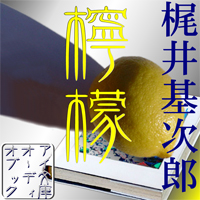


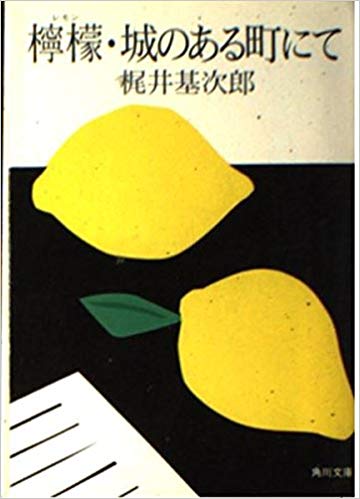


 この作品の"レモン"のイメージは頭から離れません。但し、「私」が入った書店は、設定上、洋書・輸入雑貨も多く扱う「丸善」でなければならなかったのだろうけれど、自分は「日本橋の丸善」だと長く記憶違いしていました。正しくは「京都三条通麩屋町の丸善」であったわけで、この「丸善 京都支店」は河原町通蛸薬師への移転、改築、再改築を経て'05年10月10日に閉店、閉店の日は、平積みの本の上にレモンを置いていく人がいて話題になったとか。
この作品の"レモン"のイメージは頭から離れません。但し、「私」が入った書店は、設定上、洋書・輸入雑貨も多く扱う「丸善」でなければならなかったのだろうけれど、自分は「日本橋の丸善」だと長く記憶違いしていました。正しくは「京都三条通麩屋町の丸善」であったわけで、この「丸善 京都支店」は河原町通蛸薬師への移転、改築、再改築を経て'05年10月10日に閉店、閉店の日は、平積みの本の上にレモンを置いていく人がいて話題になったとか。
 (その後、本来の"「檸檬」誕生の地"河原町三条にジュンク堂書店が進出していたのが、入居施設「京都BAL」の改装に合わせて2015年8月21日に、その地下1・2階に蔵書100万冊の「丸善 京都本店」として10年ぶりに再スタートをした。ジュンク堂ではなく丸善として再スタートしたのは、半年前の同年2月に丸善書店がジュ
(その後、本来の"「檸檬」誕生の地"河原町三条にジュンク堂書店が進出していたのが、入居施設「京都BAL」の改装に合わせて2015年8月21日に、その地下1・2階に蔵書100万冊の「丸善 京都本店」として10年ぶりに再スタートをした。ジュンク堂ではなく丸善として再スタートしたのは、半年前の同年2月に丸善書店がジュ
 ンク堂書店を吸収合併したという経緯もあるが、他店ではもともと「ジュンク堂」だったところは「ジュンク堂」の店名をそのまま使っていることからすると、"「檸檬」の書店"であることを売りにするという狙いがあったのだろう。また、丸善グループの"失地回復"の意味もあったかも)。
ンク堂書店を吸収合併したという経緯もあるが、他店ではもともと「ジュンク堂」だったところは「ジュンク堂」の店名をそのまま使っていることからすると、"「檸檬」の書店"であることを売りにするという狙いがあったのだろう。また、丸善グループの"失地回復"の意味もあったかも)。 一方、「私」がレモンを買った果物屋は「八百卯」という果物屋で、こちらは現在もあるとのことです(その後、2009年1月25日に閉店、創業130年の歴史に幕を下ろした)。
一方、「私」がレモンを買った果物屋は「八百卯」という果物屋で、こちらは現在もあるとのことです(その後、2009年1月25日に閉店、創業130年の歴史に幕を下ろした)。 (2010年のテレビでの映像化作品(「BUNGO-日本文学シネマ」)では、ちょうど作者がレモンをテニスボールに見立てているように、テニスボールケースのような円筒状の容器に入れて、乱雑に積み重ねた本の上にそれを立てるように置いたという設定になっているが、読み直してみて、やはりレモンを直接本の上に置いたというのが正しいようだ。)
(2010年のテレビでの映像化作品(「BUNGO-日本文学シネマ」)では、ちょうど作者がレモンをテニスボールに見立てているように、テニスボールケースのような円筒状の容器に入れて、乱雑に積み重ねた本の上にそれを立てるように置いたという設定になっているが、読み直してみて、やはりレモンを直接本の上に置いたというのが正しいようだ。)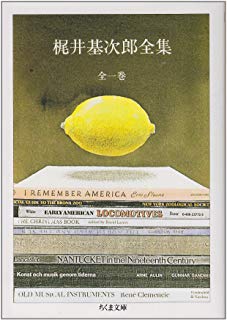

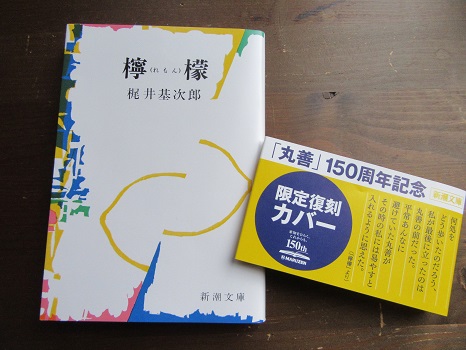

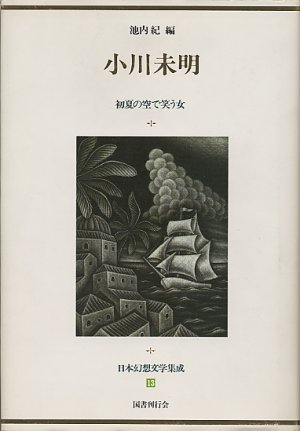
 1982-1961.jpg) 小川未明(1882‐1961)は20代終わりから30代の時だけ旺盛な創作活動をし、その業績に対して1945(昭和20)年に第5回「野間文芸賞」が贈られていますが、児童文学界の重鎮的存在で在りながら、昭和以降ほとんど新作は発表していません。また、宮沢賢治の作品が「大人の童話」と言われるのと対照的に、過去の作品群の作風を"子ども向けのヒューマニズム"と揶揄された時期もあります。
小川未明(1882‐1961)は20代終わりから30代の時だけ旺盛な創作活動をし、その業績に対して1945(昭和20)年に第5回「野間文芸賞」が贈られていますが、児童文学界の重鎮的存在で在りながら、昭和以降ほとんど新作は発表していません。また、宮沢賢治の作品が「大人の童話」と言われるのと対照的に、過去の作品群の作風を"子ども向けのヒューマニズム"と揶揄された時期もあります。



.jpg)



 内田 百閒
内田 百閒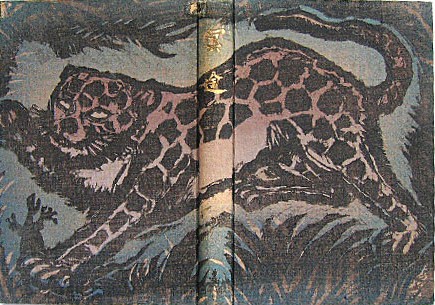
 1921(大正10)年発表、翌年単行本刊行の『冥途』は、内田百閒(1989‐1971)が最初に発表したアンソロジーで、「冥途」「山東京伝」「花火」「件」「土手」「豹」など16篇の短篇からなりますが(福武文庫版は18篇所収)、何れも作者自身の見た夢をモチーフにしたと思われ、師匠であった漱石の「夢十夜」の系譜を引くものです。
1921(大正10)年発表、翌年単行本刊行の『冥途』は、内田百閒(1989‐1971)が最初に発表したアンソロジーで、「冥途」「山東京伝」「花火」「件」「土手」「豹」など16篇の短篇からなりますが(福武文庫版は18篇所収)、何れも作者自身の見た夢をモチーフにしたと思われ、師匠であった漱石の「夢十夜」の系譜を引くものです。



 有島武郎(1878‐1923)
有島武郎(1878‐1923)

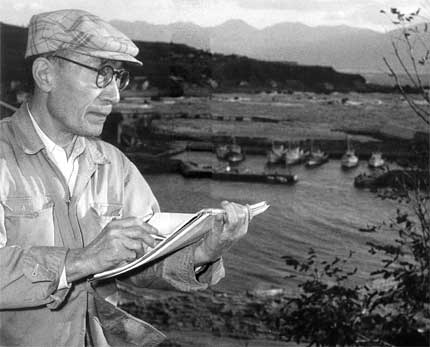 一方、「生れ出ずる悩み」のモデルとなった木田金次郎(1893‐1962)は、この事件を契機に漁師をやめ画家として生きる決意をします。描き溜めた作品1,500点が、洞爺丸台風襲来時の出火による「岩内大火」(1954年)で焼失したというのは残念ですが(この大火は水上勉の『
一方、「生れ出ずる悩み」のモデルとなった木田金次郎(1893‐1962)は、この事件を契機に漁師をやめ画家として生きる決意をします。描き溜めた作品1,500点が、洞爺丸台風襲来時の出火による「岩内大火」(1954年)で焼失したというのは残念ですが(この大火は水上勉の『 さらに、「小さき者へ」で語られる側となった子のうち、長男は映画俳優の
さらに、「小さき者へ」で語られる側となった子のうち、長男は映画俳優の

 テレビドラマや映画で活躍した女優でした。不倫相手との間の子であったという事情ため、16歳の時まで父親=森雅之から認知されませんでした。生涯独身でしたが、演出家で元東大全共闘のオーガナイザー芥正彦(1969年に東大で三島由紀夫との公開討論会を実施したメンバーの一人)とパートーナー関係にありました。何だか、残された者の方が逞しかったような気もする...。
テレビドラマや映画で活躍した女優でした。不倫相手との間の子であったという事情ため、16歳の時まで父親=森雅之から認知されませんでした。生涯独身でしたが、演出家で元東大全共闘のオーガナイザー芥正彦(1969年に東大で三島由紀夫との公開討論会を実施したメンバーの一人)とパートーナー関係にありました。何だか、残された者の方が逞しかったような気もする...。
 因みに、中島葵は大島渚監督の「愛のコリーダ」('76年/日・仏)にも、藤竜也が演じた吉蔵の妻役で出ていますが、当然のことながら、吉蔵の情婦・阿部定を演じた松田暎子の方が目立っていました。「愛のコリーダ」は公開の翌年に高田馬場のパール座で観ましたが、日本語の映画にフランス語だったか英語だったかの字幕がつくので変な感じがしました。日本国内での上映は大幅な修正が施されたため(冬の日の外で眠っていて子供たちに雪玉を投げつけられる老乞食を演じた殿山泰司の露出された陰部も含め)、ぼかしの上に外国語の字幕が乗っかっていたような印象があります(2000年に「完全ノーカット版」としてリバイバル上映された)。海外ではベルナルド・ベルトリッチの「ラストタンゴ・イン・パリ」('72年/伊)と比肩し得ると高く評価され、"オーシマ"の名を世界的なものにした作品ですが、国内では田中登監督、宮下順子主演の「実録阿部定」('75年/日活)の方が上との声もありました(阿部定に注目したことは面白いと思ったが、映画の出来としては個人的にはどちらもイマイチか)。
因みに、中島葵は大島渚監督の「愛のコリーダ」('76年/日・仏)にも、藤竜也が演じた吉蔵の妻役で出ていますが、当然のことながら、吉蔵の情婦・阿部定を演じた松田暎子の方が目立っていました。「愛のコリーダ」は公開の翌年に高田馬場のパール座で観ましたが、日本語の映画にフランス語だったか英語だったかの字幕がつくので変な感じがしました。日本国内での上映は大幅な修正が施されたため(冬の日の外で眠っていて子供たちに雪玉を投げつけられる老乞食を演じた殿山泰司の露出された陰部も含め)、ぼかしの上に外国語の字幕が乗っかっていたような印象があります(2000年に「完全ノーカット版」としてリバイバル上映された)。海外ではベルナルド・ベルトリッチの「ラストタンゴ・イン・パリ」('72年/伊)と比肩し得ると高く評価され、"オーシマ"の名を世界的なものにした作品ですが、国内では田中登監督、宮下順子主演の「実録阿部定」('75年/日活)の方が上との声もありました(阿部定に注目したことは面白いと思ったが、映画の出来としては個人的にはどちらもイマイチか)。
 「愛のコリーダ」●制作年:1965年●制作国:日本・フランス●監督・脚本:大島渚●製作:アナトール・ドーマン/若松孝二●撮影:伊東英男●音楽:三木稔●原作:山田風太郎「棺の中の悦楽」●時間:96分●出演:藤竜也/松田暎子/中島葵/芹明香/阿部マリ子/三星東美/藤ひろ子/殿山泰司/白石奈緒美/青木真
「愛のコリーダ」●制作年:1965年●制作国:日本・フランス●監督・脚本:大島渚●製作:アナトール・ドーマン/若松孝二●撮影:伊東英男●音楽:三木稔●原作:山田風太郎「棺の中の悦楽」●時間:96分●出演:藤竜也/松田暎子/中島葵/芹明香/阿部マリ子/三星東美/藤ひろ子/殿山泰司/白石奈緒美/青木真 知子/東祐里子/安田清美/南黎/堀小美吉/岡田京子/松廼家喜久平/松井康子/九重京司/富山加津江/福原ひとみ/野田真吉/小林加奈枝/小山明子●公開:1976/10●配給:東宝東和●最初に観た場所:高田馬場パール座(77-12-03)(評価:★★★)●併映:「ソドムの市」(ピエル・パオロ・パゾリーニ)
知子/東祐里子/安田清美/南黎/堀小美吉/岡田京子/松廼家喜久平/松井康子/九重京司/富山加津江/福原ひとみ/野田真吉/小林加奈枝/小山明子●公開:1976/10●配給:東宝東和●最初に観た場所:高田馬場パール座(77-12-03)(評価:★★★)●併映:「ソドムの市」(ピエル・パオロ・パゾリーニ)


 1946(昭和21)年発表の「柳橋物語」は、上方に働きに出る〈庄吉〉に、幼さゆえの恋情で「待っているわ」と夫婦約束をした〈おせん〉が、江戸の大火(明暦の大火・1657年)で生活のすべてを失って記憶喪失になるまでショックを受ながらも、逃げのびる際に拾った赤子をわが子のように育てるものの、上方から戻った庄吉はそれを見て彼女の不義理ととる―という、たたみかけるような逆境に翻弄される一女性の人生を描いたもの。
1946(昭和21)年発表の「柳橋物語」は、上方に働きに出る〈庄吉〉に、幼さゆえの恋情で「待っているわ」と夫婦約束をした〈おせん〉が、江戸の大火(明暦の大火・1657年)で生活のすべてを失って記憶喪失になるまでショックを受ながらも、逃げのびる際に拾った赤子をわが子のように育てるものの、上方から戻った庄吉はそれを見て彼女の不義理ととる―という、たたみかけるような逆境に翻弄される一女性の人生を描いたもの。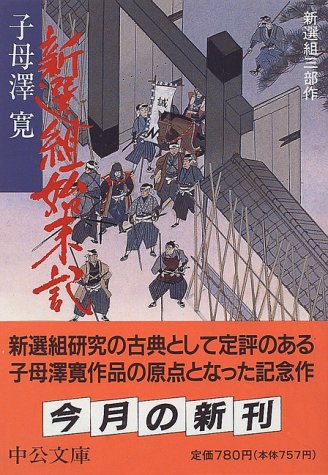

 子母澤 寛 (1892-1968/享年76)
子母澤 寛 (1892-1968/享年76) 一方この『新選組始末記』は、1928(昭和3)年刊行の子母澤寛の初出版作品で、子母澤寛が東京日日新聞(毎日新聞)の社会部記者時代に特集記事のために新選組について調べたものがベースになっており、子母澤寛自身も"巷説漫談或いは史実"を書いたと述べているように、〈小説〉というより〈記録〉に近いスタイルです。とりわけ、そのころまだ存命していた新選組関係者を丹念に取材しており、その抑制された聞き書きの文体には、かえって生々しさがあったりもします。
一方この『新選組始末記』は、1928(昭和3)年刊行の子母澤寛の初出版作品で、子母澤寛が東京日日新聞(毎日新聞)の社会部記者時代に特集記事のために新選組について調べたものがベースになっており、子母澤寛自身も"巷説漫談或いは史実"を書いたと述べているように、〈小説〉というより〈記録〉に近いスタイルです。とりわけ、そのころまだ存命していた新選組関係者を丹念に取材しており、その抑制された聞き書きの文体には、かえって生々しさがあったりもします。
 子母澤寛はその後、『新選組遺聞』、『新選組物語』を書き、いわゆる「新選組三部作」といわれるこれらの作品は、司馬遼太郎など多くの作家の参考文献となります(司馬遼太郎は、子母澤寛本人に予め断った上で「新選組三部作」からネタを抽出し、独自の創作を加えて『
子母澤寛はその後、『新選組遺聞』、『新選組物語』を書き、いわゆる「新選組三部作」といわれるこれらの作品は、司馬遼太郎など多くの作家の参考文献となります(司馬遼太郎は、子母澤寛本人に予め断った上で「新選組三部作」からネタを抽出し、独自の創作を加えて『



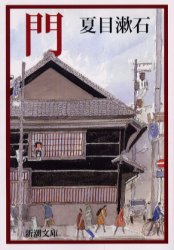

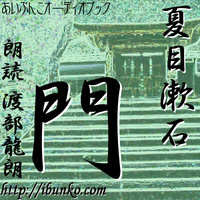
 親友の安井の妻と駆け落ちし結ばれた宗助とその相方・御米との、世間との関わりを極力断ったかのような夫婦生活の日常を淡々と描いています。言わば「ロミオとジュリエット」みたいな出来事があって、その出来事そのものは描かず、その後の2人の地味な市井生活を書いているといった感じでしょうか。
親友の安井の妻と駆け落ちし結ばれた宗助とその相方・御米との、世間との関わりを極力断ったかのような夫婦生活の日常を淡々と描いています。言わば「ロミオとジュリエット」みたいな出来事があって、その出来事そのものは描かず、その後の2人の地味な市井生活を書いているといった感じでしょうか。 この小説には、そうした宗助夫婦を形容する表現と、そこに描かれている実態に矛盾というか、謎のような落差がある気がしました。確かに2人は和合した夫婦であるに違いなく、2人の関係は「一つの有機体」のようであり、「二人の精神を組み立てる神経系は、最後の繊維に至るまで、互に抱き合って出来上がっていた」と表現されています。しかし一方で、宗助は旧友・安井の再登場に一人煩悶し、心の平安を求め妻に内緒で禅寺へ行ったりする、片や御米も、安井の弟のわが家への居候を快く思っていないようだが夫には打ち明けず、また自分に子供が出来ないことに対して個人的な原罪意識を抱いている―。
この小説には、そうした宗助夫婦を形容する表現と、そこに描かれている実態に矛盾というか、謎のような落差がある気がしました。確かに2人は和合した夫婦であるに違いなく、2人の関係は「一つの有機体」のようであり、「二人の精神を組み立てる神経系は、最後の繊維に至るまで、互に抱き合って出来上がっていた」と表現されています。しかし一方で、宗助は旧友・安井の再登場に一人煩悶し、心の平安を求め妻に内緒で禅寺へ行ったりする、片や御米も、安井の弟のわが家への居候を快く思っていないようだが夫には打ち明けず、また自分に子供が出来ないことに対して個人的な原罪意識を抱いている―。 谷崎潤一郎や江藤淳は「理想的な夫婦像」としてこの作品を読んだらしいですが、この作品に描かれている"その後のロミオとジュリエット"は、融和し得ない個々の世界を、それぞれに少しずつ膨らませつつあるように感じます。
谷崎潤一郎や江藤淳は「理想的な夫婦像」としてこの作品を読んだらしいですが、この作品に描かれている"その後のロミオとジュリエット"は、融和し得ない個々の世界を、それぞれに少しずつ膨らませつつあるように感じます。




 1908(明治41)年9月から12月にかけて新聞連載された夏目漱石(1967‐1916)の本作品は、漱石の『吾輩は猫である』('05年)、『坊ちゃん』('06年)などに続く初期代表作で、地方の高校を卒業し東京の大学で学ぶために上京してきた小川三四郎が、都会で学友や先輩、若い女性たちと接触して、日露戦争を経た日本の「新しい空気」に触れ、戸惑いながらも成長していく様が描かれています。
1908(明治41)年9月から12月にかけて新聞連載された夏目漱石(1967‐1916)の本作品は、漱石の『吾輩は猫である』('05年)、『坊ちゃん』('06年)などに続く初期代表作で、地方の高校を卒業し東京の大学で学ぶために上京してきた小川三四郎が、都会で学友や先輩、若い女性たちと接触して、日露戦争を経た日本の「新しい空気」に触れ、戸惑いながらも成長していく様が描かれています。 【1948年文庫化・1986改訂[新潮文庫]/1950年再文庫化・1990改訂[岩波文庫]/1951年再文庫化[角川文庫]/1966年再文庫化[旺文社文庫]/1972年再文庫化[講談社文庫]/1986年再文庫化[ちくま文庫]/1991年再文庫化[集英社文庫]/2000年再文庫化[ポプラ社文庫]】
【1948年文庫化・1986改訂[新潮文庫]/1950年再文庫化・1990改訂[岩波文庫]/1951年再文庫化[角川文庫]/1966年再文庫化[旺文社文庫]/1972年再文庫化[講談社文庫]/1986年再文庫化[ちくま文庫]/1991年再文庫化[集英社文庫]/2000年再文庫化[ポプラ社文庫]】
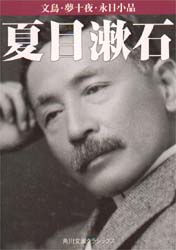



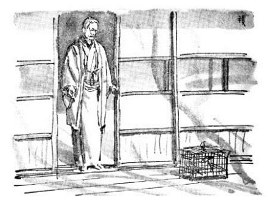 新潮文庫版は、「文鳥」「夢十夜」「永日小品」「思い出す事など」「ケーベル先生」「変な音」「手紙」の7編を収録。
新潮文庫版は、「文鳥」「夢十夜」「永日小品」「思い出す事など」「ケーベル先生」「変な音」「手紙」の7編を収録。 同じ1908年(明治41)年の7月25日から8月5日まで朝日新聞で連載された幻想的な夢記述群「夢十夜」は、「第三夜」の盲目の子を負ぶっていたらと...いう夢が伊藤整の解釈ぐらいでしか知られていなかったのが、近年特に注目の作品となり映像化もされていたりもします。フロイト流に解釈すると、ほぼ全部の夢が「精力減退の不安」に繋がるそうですが、作者が生きていればこれには反論があるのではないでしょうか。
同じ1908年(明治41)年の7月25日から8月5日まで朝日新聞で連載された幻想的な夢記述群「夢十夜」は、「第三夜」の盲目の子を負ぶっていたらと...いう夢が伊藤整の解釈ぐらいでしか知られていなかったのが、近年特に注目の作品となり映像化もされていたりもします。フロイト流に解釈すると、ほぼ全部の夢が「精力減退の不安」に繋がるそうですが、作者が生きていればこれには反論があるのではないでしょうか。
 くて夜は幽霊が出そうな感じでした。しかし、老朽化が進んだためその後全面改装され、「漱石の間」は修善寺の「夏目漱石記念館」に移設されてしまいました(旅館の方は今年['06年]7月、「湯回廊 菊屋」としてリニューアルオープン。廊下なども明るくなったようだ)。
くて夜は幽霊が出そうな感じでした。しかし、老朽化が進んだためその後全面改装され、「漱石の間」は修善寺の「夏目漱石記念館」に移設されてしまいました(旅館の方は今年['06年]7月、「湯回廊 菊屋」としてリニューアルオープン。廊下なども明るくなったようだ)。 【1956年文庫化[角川文庫(『文鳥・夢十夜・永日小品』)]・1991年改版[角川文庫クラシックス]/1976年文庫化・2002年改版[新潮文庫]/1986年再文庫化[岩波文庫(『夢十夜 他二篇』)/1992年再文庫化[集英社文庫(『夢十夜・草枕』)]/2024年再文庫化[100分で読む名作小説(角川文庫)(『文鳥』)]】
【1956年文庫化[角川文庫(『文鳥・夢十夜・永日小品』)]・1991年改版[角川文庫クラシックス]/1976年文庫化・2002年改版[新潮文庫]/1986年再文庫化[岩波文庫(『夢十夜 他二篇』)/1992年再文庫化[集英社文庫(『夢十夜・草枕』)]/2024年再文庫化[100分で読む名作小説(角川文庫)(『文鳥』)]】


 1908(明治41)年1月から4月にかけて大阪朝日新聞に連載(全96回)された夏目漱石(1967‐1916)の『坑夫』は、前年、朝日新聞社に専属作家として入社して最初に書いた『虞美人草』に続く連載作品で、次の連載執筆予定者だった島崎藤村の"遅筆"のためのピンチヒッター的登場だったようです。野田九甫がを担当した連載の挿絵は、漱石が切抜きを貼って喜ぶほどの出来栄えでしたが、社内の「あまりに高級だ」という非難に屈して連載半ばで挿絵を中断させられ、春仙が描く題字飾りのみに切り替えられるという仕打ちにあっています。
1908(明治41)年1月から4月にかけて大阪朝日新聞に連載(全96回)された夏目漱石(1967‐1916)の『坑夫』は、前年、朝日新聞社に専属作家として入社して最初に書いた『虞美人草』に続く連載作品で、次の連載執筆予定者だった島崎藤村の"遅筆"のためのピンチヒッター的登場だったようです。野田九甫がを担当した連載の挿絵は、漱石が切抜きを貼って喜ぶほどの出来栄えでしたが、社内の「あまりに高級だ」という非難に屈して連載半ばで挿絵を中断させられ、春仙が描く題字飾りのみに切り替えられるという仕打ちにあっています。 漱石のところへ自分の経験を小説にして欲しいと持ち込んだ青年がいて、その体験談を本人の許諾を得て、急遽書かなければならなくなった連載小説の素材にしたようですが、主人公が出奔した理由は漱石風にアレンジされているようで、「坑夫(堀子)」の生活などの実態部分を主に青年の話から抽出したようです。
漱石のところへ自分の経験を小説にして欲しいと持ち込んだ青年がいて、その体験談を本人の許諾を得て、急遽書かなければならなくなった連載小説の素材にしたようですが、主人公が出奔した理由は漱石風にアレンジされているようで、「坑夫(堀子)」の生活などの実態部分を主に青年の話から抽出したようです。


 中公文庫/NHK時代劇スペシャル「母恋ひの記」(黒木瞳・劇団ひとり主演)タイアップ帯(2008)
中公文庫/NHK時代劇スペシャル「母恋ひの記」(黒木瞳・劇団ひとり主演)タイアップ帯(2008) 」初版.jpg)



 ・2008年『春琴抄』(配給:ビデオプランニング 監督:金田敬)春琴:長澤奈央/佐助:斎藤工
・2008年『春琴抄』(配給:ビデオプランニング 監督:金田敬)春琴:長澤奈央/佐助:斎藤工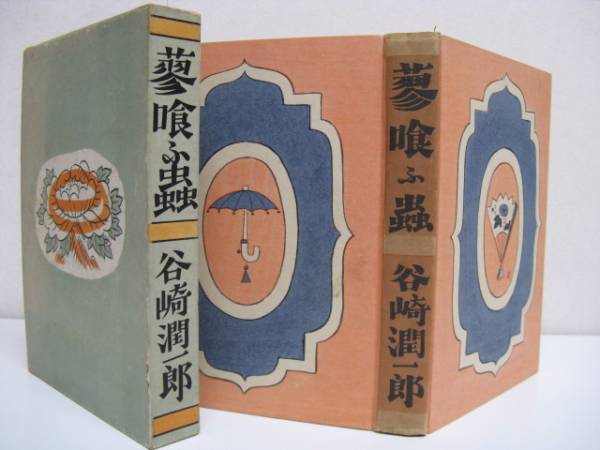

 小出 楢重(1887-1931)
小出 楢重(1887-1931)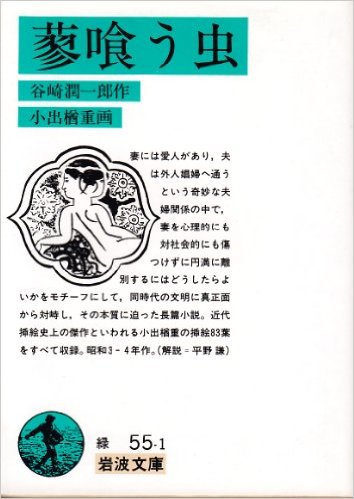 1928(昭和3)年発表の谷崎潤一郎(1886‐1965)の長編小説(単行本刊行は翌年)で、妻に愛人がいて自身も娼館に通っているという既に破綻した夫婦関係にある男が、なるだけ妻子を傷つけないように離婚するにはどうしたらよいかを考えているというのがモチーフになっています。
1928(昭和3)年発表の谷崎潤一郎(1886‐1965)の長編小説(単行本刊行は翌年)で、妻に愛人がいて自身も娼館に通っているという既に破綻した夫婦関係にある男が、なるだけ妻子を傷つけないように離婚するにはどうしたらよいかを考えているというのがモチーフになっています。
 絵全83葉が収録されているためで、おかげで人形浄瑠璃の桝席の様子や「封建の世から抜け出してきたようだ」という妾・お久の様子などがわかりやすいのですが、その他生活や風俗などで当時の「モダン」なものも多く描いていて興味深いからです。
絵全83葉が収録されているためで、おかげで人形浄瑠璃の桝席の様子や「封建の世から抜け出してきたようだ」という妾・お久の様子などがわかりやすいのですが、その他生活や風俗などで当時の「モダン」なものも多く描いていて興味深いからです。
 主人公が"西洋"娼館に行く前に神戸オリエンタル・ホテルで食事したり(そう言えば、『細雪』の主人公一家も特別な時にはこのホテルを使っている設定になっていた)、従弟がマドロスだったり、飼い犬がグレイハウンドだったりと、ハイカラな雰囲気に満ちた小説ですが、その背景が視覚的に堪能できるのがいい。
主人公が"西洋"娼館に行く前に神戸オリエンタル・ホテルで食事したり(そう言えば、『細雪』の主人公一家も特別な時にはこのホテルを使っている設定になっていた)、従弟がマドロスだったり、飼い犬がグレイハウンドだったりと、ハイカラな雰囲気に満ちた小説ですが、その背景が視覚的に堪能できるのがいい。




 1925(大正14)年刊行の谷崎潤一郎(1886‐1965)の長編耽美小説で(初出:「大阪朝日新聞」1924年3月20日~6月14日)、「一人の少女を友達にして、朝夕彼女の発育のさまを眺めながら(中略)、云わば遊びのような気分で、一軒の家に住む」という主人公の意図は、今で言う「育成ゲーム」を地でいく感じ。しかし、当時15歳のこの少女ナオミが実はとんでもないタマで、彼女を「立派な婦人に仕立ててやろう」という気でいた主人公は、成熟とともに増す彼女の妖婦ぶりに引き摺られ、ずるずると破滅への道を辿る―。
1925(大正14)年刊行の谷崎潤一郎(1886‐1965)の長編耽美小説で(初出:「大阪朝日新聞」1924年3月20日~6月14日)、「一人の少女を友達にして、朝夕彼女の発育のさまを眺めながら(中略)、云わば遊びのような気分で、一軒の家に住む」という主人公の意図は、今で言う「育成ゲーム」を地でいく感じ。しかし、当時15歳のこの少女ナオミが実はとんでもないタマで、彼女を「立派な婦人に仕立ててやろう」という気でいた主人公は、成熟とともに増す彼女の妖婦ぶりに引き摺られ、ずるずると破滅への道を辿る―。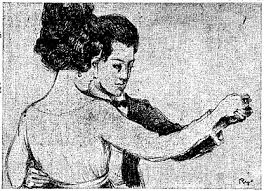 前半部分は前年に大阪朝日新聞連載されていますが(中公文庫版は新聞連載時の田中良による挿画を一部掲載)、検閲当局からに再三の注意が新聞社にあって、新聞社がこれに従ったため6月14日付の第87回をもって掲載中止となり、続きは4ヵ月後に雑誌「女性」で連載されました。今ならさしずめ渡辺淳一を日経で読むみたいなものでしょうが、当時としてはやはり風紀紊乱の恐れあり、ということにされてしまったのでしょう。また、後の文芸評論家たちは、通俗小説風でありながらも、このナオミに対する主人公の崇拝ぶりには、当時の日本人の西洋文化に対する崇拝が重なられているとも言っています(この作品もまた文明批評なのか?)。
前半部分は前年に大阪朝日新聞連載されていますが(中公文庫版は新聞連載時の田中良による挿画を一部掲載)、検閲当局からに再三の注意が新聞社にあって、新聞社がこれに従ったため6月14日付の第87回をもって掲載中止となり、続きは4ヵ月後に雑誌「女性」で連載されました。今ならさしずめ渡辺淳一を日経で読むみたいなものでしょうが、当時としてはやはり風紀紊乱の恐れあり、ということにされてしまったのでしょう。また、後の文芸評論家たちは、通俗小説風でありながらも、このナオミに対する主人公の崇拝ぶりには、当時の日本人の西洋文化に対する崇拝が重なられているとも言っています(この作品もまた文明批評なのか?)。 最初に読んだときは、主人公の隷属ぶりがある種「悲喜劇」的であるように思えましたが、読み手に「こんな女性にかまけたら大変なことになる」という防衛機制的な思いを働かせるような要素があるかもしれません。だから、西洋文明云々言う前に、この小説の主人公を反面教師にし、実人生での教訓的なものを抽出する読者がいても不思議ではないのではないかと。でも、主人公がナオミに馬になってと言われて四つん這いになる場面で改めて思ったのですが、隷属することは同時に主人公の願望でもあったのでしょう。そうした願望は谷崎自身の内にもあって、それを第三者の告白体にすることで巧みに虚構化しているような感じもしました。平易な文体、単純な構成ですが、この作品の場合、かえってそのことで完成度は高いものとなっているように思います。
最初に読んだときは、主人公の隷属ぶりがある種「悲喜劇」的であるように思えましたが、読み手に「こんな女性にかまけたら大変なことになる」という防衛機制的な思いを働かせるような要素があるかもしれません。だから、西洋文明云々言う前に、この小説の主人公を反面教師にし、実人生での教訓的なものを抽出する読者がいても不思議ではないのではないかと。でも、主人公がナオミに馬になってと言われて四つん這いになる場面で改めて思ったのですが、隷属することは同時に主人公の願望でもあったのでしょう。そうした願望は谷崎自身の内にもあって、それを第三者の告白体にすることで巧みに虚構化しているような感じもしました。平易な文体、単純な構成ですが、この作品の場合、かえってそのことで完成度は高いものとなっているように思います。 『現代漫画大観2 文芸名作漫画』(昭和3年発行)より「痴人の愛」
『現代漫画大観2 文芸名作漫画』(昭和3年発行)より「痴人の愛」
 れた「痴人の愛」('67年/大映)では安田道代(後の大楠道代)がナオミを演じました。この他にも、高林陽一監督の「谷崎潤一郎・原作「痴人の愛」より ナオミ」('80年/東映)のように現代版のピンク映画に翻案されたものが幾つかあります。
れた「痴人の愛」('67年/大映)では安田道代(後の大楠道代)がナオミを演じました。この他にも、高林陽一監督の「谷崎潤一郎・原作「痴人の愛」より ナオミ」('80年/東映)のように現代版のピンク映画に翻案されたものが幾つかあります。



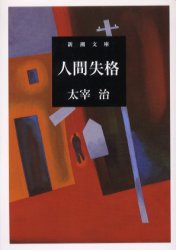


 熱海・起雲閣
熱海・起雲閣 
 1948(昭和23)年の3月から5月にかけて書かれた太宰治(1909‐1948)39歳、最晩年の作品。20代後半の廃人同様の画家が、自分の子ども時代から20歳前後までを振り返る「手記」形式になっていますが、その生い立ちや自殺未遂、女性問題や心中事件、思想事件などに触れた内容は、太宰の体験に即したものであることが容易に推察され、かなり暗く屈折した作者自身の自画像ともとれます。但し、かなり強くデフォルメされている部分もあるようで、例えば、弟子として太宰の身近にいた小山清氏によると、太宰自身はこの作品の主人公の画家のように"男めかけ"のような生活を自分自身がすることは許せないという、そうした点では潔癖なタイプだったらしいです。
1948(昭和23)年の3月から5月にかけて書かれた太宰治(1909‐1948)39歳、最晩年の作品。20代後半の廃人同様の画家が、自分の子ども時代から20歳前後までを振り返る「手記」形式になっていますが、その生い立ちや自殺未遂、女性問題や心中事件、思想事件などに触れた内容は、太宰の体験に即したものであることが容易に推察され、かなり暗く屈折した作者自身の自画像ともとれます。但し、かなり強くデフォルメされている部分もあるようで、例えば、弟子として太宰の身近にいた小山清氏によると、太宰自身はこの作品の主人公の画家のように"男めかけ"のような生活を自分自身がすることは許せないという、そうした点では潔癖なタイプだったらしいです。  この作品の「第二の手記」までが書かれた熱海の「起雲閣」を訪れてみましたが、大正ロマンの香り高い洋風建築で、広大な庭が気持ちよく、こんな環境抜群の処で「自分は生まれた時からの日陰者」とか書いていたのだなあと。〈生きる気力を失った人間の苦悩と虚無―悲劇的人間像〉をしっかりと「造型」するための環境づくりをした上で、執筆にとりかかったような気がします(当時の彼の体調は最悪だったようで、まず体調と気力の立直しを図ったのかも)。
この作品の「第二の手記」までが書かれた熱海の「起雲閣」を訪れてみましたが、大正ロマンの香り高い洋風建築で、広大な庭が気持ちよく、こんな環境抜群の処で「自分は生まれた時からの日陰者」とか書いていたのだなあと。〈生きる気力を失った人間の苦悩と虚無―悲劇的人間像〉をしっかりと「造型」するための環境づくりをした上で、執筆にとりかかったような気がします(当時の彼の体調は最悪だったようで、まず体調と気力の立直しを図ったのかも)。





 とは言え、穿った解釈を挟まずにごく普通に読めば、自身を戯画化した作品ばかり書くようになってしまった「上原」という作家が太宰を直接的に想起させる存在であり(「自身を戯画化した作品ばかり書く作家」を描きことで"自身を戯画化している"という意図的な二重構造ととれる)、かず子の手紙の中での呼ばれ方〈M・C〉が、「マイ・チェホフ」、「マイ・チャイルド」「マイ・コメディアン」と変遷していくところなどは、巧みさと屈折した自虐的ユーモアも感じます。
とは言え、穿った解釈を挟まずにごく普通に読めば、自身を戯画化した作品ばかり書くようになってしまった「上原」という作家が太宰を直接的に想起させる存在であり(「自身を戯画化した作品ばかり書く作家」を描きことで"自身を戯画化している"という意図的な二重構造ととれる)、かず子の手紙の中での呼ばれ方〈M・C〉が、「マイ・チェホフ」、「マイ・チャイルド」「マイ・コメディアン」と変遷していくところなどは、巧みさと屈折した自虐的ユーモアも感じます。 太宰作品は暗いというイメージがありますが、実際には(こうして屈折してはいるものの)ユーモアを滲ませたものが多くあり、また芥川のようなペダンティックな匂いが無く、同時代の作家と比べても読みやすい、その上に人間疎外という普遍的なテーマを扱っているため、かなりこの先も読まれ続けるような気がします。
太宰作品は暗いというイメージがありますが、実際には(こうして屈折してはいるものの)ユーモアを滲ませたものが多くあり、また芥川のようなペダンティックな匂いが無く、同時代の作家と比べても読みやすい、その上に人間疎外という普遍的なテーマを扱っているため、かなりこの先も読まれ続けるような気がします。
 この小説の前半部分は、伊豆三津の「安田屋旅館」で書かれましたが、その旅館に泊まった際に、今も客室として使われている太宰が使った2階の部屋を、掃除の時間の後で見せてもらいました。
この小説の前半部分は、伊豆三津の「安田屋旅館」で書かれましたが、その旅館に泊まった際に、今も客室として使われている太宰が使った2階の部屋を、掃除の時間の後で見せてもらいました。



 1946(昭和21)年に青森の疎開先から東京・三鷹に戻った太宰治(1909‐1948)が、その自死までの間に発表した短篇作品の中から、「親友交歓」「トカトントン」「父」「母」「ヴィヨンの妻」「おさん」「家屋の幸福」「桜桃」の8編を所収。
1946(昭和21)年に青森の疎開先から東京・三鷹に戻った太宰治(1909‐1948)が、その自死までの間に発表した短篇作品の中から、「親友交歓」「トカトントン」「父」「母」「ヴィヨンの妻」「おさん」「家屋の幸福」「桜桃」の8編を所収。

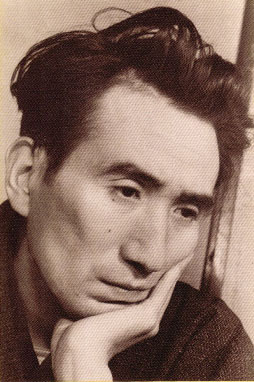 太宰 治 (1909‐1948/享年38)
太宰 治 (1909‐1948/享年38) 1936(昭和11)年6月刊行の太宰治(1909‐1948)の最初の創作集で、15編の中・短篇から成るものですが、27歳で世に出した作品集に「晩年」などというタイトルをつけたのは、遺稿集のつもりで書いたからとのこと(実際、その後服毒自殺を図っている)。
1936(昭和11)年6月刊行の太宰治(1909‐1948)の最初の創作集で、15編の中・短篇から成るものですが、27歳で世に出した作品集に「晩年」などというタイトルをつけたのは、遺稿集のつもりで書いたからとのこと(実際、その後服毒自殺を図っている)。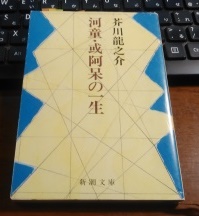



 この中で最も一般に親しまれているのは、彼の命日を"河童忌"と呼ぶぐらいだから、「河童」でしょう。
この中で最も一般に親しまれているのは、彼の命日を"河童忌"と呼ぶぐらいだから、「河童」でしょう。




 1923(大正12)年に創刊された「文藝春秋」の創刊号から連載された芥川龍之介(1892-1927)の箴言集で、新潮文庫版では、3年間続いた連載の打ち切り後に死後発表された部分が〈遺稿〉として区切られています。
1923(大正12)年に創刊された「文藝春秋」の創刊号から連載された芥川龍之介(1892-1927)の箴言集で、新潮文庫版では、3年間続いた連載の打ち切り後に死後発表された部分が〈遺稿〉として区切られています。








