「●さ行の外国映画の監督①」の インデックッスへ Prev|NEXT ⇒ 【2436】ルパート・ジュリアン「オペラ座の怪人」
「○外国映画 【制作年順】」の インデックッスへ
ミュージカルの映画化だが原作に近いテイストも。怪人がイケメン過ぎる?



「オペラ座の怪人 通常版 [DVD]」 ジェラルド・バトラー/エミー・ロッサム
 1870年、パリ・オペラ座。「ファウスト」の上演を控える中、劇場への不満を抱えるスター歌手のカルロッタ(ミニー・ドライヴァー)が主役を降板する。スターのドタキャンに関係者全員が浮き足立つ中、急遽、若き歌姫クリスティーヌ・ダーエ(エミー・ロッサム)がその代役を射止めるが、稀代の美声を披露したクリスティーヌは関係者の不安も一掃し、一躍スターの座に上り詰める。そんな中、劇場のパトロンで幼馴染の美青年の子爵ラウル(パトリック・ウィルソン)との再会に心を弾ませるクリスティーヌだったが、実は彼女の成功にはある秘密が隠されていたのだった―。
1870年、パリ・オペラ座。「ファウスト」の上演を控える中、劇場への不満を抱えるスター歌手のカルロッタ(ミニー・ドライヴァー)が主役を降板する。スターのドタキャンに関係者全員が浮き足立つ中、急遽、若き歌姫クリスティーヌ・ダーエ(エミー・ロッサム)がその代役を射止めるが、稀代の美声を披露したクリスティーヌは関係者の不安も一掃し、一躍スターの座に上り詰める。そんな中、劇場のパトロンで幼馴染の美青年の子爵ラウル(パトリック・ウィルソン)との再会に心を弾ませるクリスティーヌだったが、実は彼女の成功にはある秘密が隠されていたのだった―。
 フランスの作家ガストン・ルルーによって1909年に発表された『オペラ座の怪人』の9回目の映画化作品で(ブライアン・デ・パルマ監督の「ファントム・オブ・パラダイス」('74年/米)など"翻案映画化作品を除く)、アンドリュー・ロイド・ウェバー版のミュージカルをベースにした作品であり、ミュージカルの映画化と言った方が正しいのかもしれません(アンドリュー・ロイド・ウェバーはこの映画の製作者でもあり、音楽も担当、更に脚本にも参加している)。
フランスの作家ガストン・ルルーによって1909年に発表された『オペラ座の怪人』の9回目の映画化作品で(ブライアン・デ・パルマ監督の「ファントム・オブ・パラダイス」('74年/米)など"翻案映画化作品を除く)、アンドリュー・ロイド・ウェバー版のミュージカルをベースにした作品であり、ミュージカルの映画化と言った方が正しいのかもしれません(アンドリュー・ロイド・ウェバーはこの映画の製作者でもあり、音楽も担当、更に脚本にも参加している)。
 ブロードウェイ・ミュージカルの方は1988年初演で、個人的には1995年に観ましたが(野茂秀雄が大リーグに移籍した年だった)、当時で、「キャッツ」(14年目)、「レ・ミゼラブル」(9年目)に次ぐ8年目というロングランで、一方で、シガニー・ウィーバー主演のミュージカルが客の不入りで2週間で打ち切られるような出来事もあって、やはり厳しい舞台の世界の中でのロングランというのはスゴイことなのだなあと実感した記憶があります。結局、「オペラ座の怪人」の舞台は、「キャッツ」「レ・ミゼラブル」を抜いて今も続いており(今年['16年]で19年目)、ブロードウェイ・ミュージカルのロングラン記録を更新中。追いかける「シカゴ」(1996年初演)、「ライオン・キング」(1997年初演)を大きく引き離しているため、当分はこれを抜くロングランは出てこないでしょう(ただし、ブロードウェイに限った話で、オフ・ブロードウェイやロンドンにはこれ以上のロングラン記録がある)。
ブロードウェイ・ミュージカルの方は1988年初演で、個人的には1995年に観ましたが(野茂秀雄が大リーグに移籍した年だった)、当時で、「キャッツ」(14年目)、「レ・ミゼラブル」(9年目)に次ぐ8年目というロングランで、一方で、シガニー・ウィーバー主演のミュージカルが客の不入りで2週間で打ち切られるような出来事もあって、やはり厳しい舞台の世界の中でのロングランというのはスゴイことなのだなあと実感した記憶があります。結局、「オペラ座の怪人」の舞台は、「キャッツ」「レ・ミゼラブル」を抜いて今も続いており(今年['16年]で19年目)、ブロードウェイ・ミュージカルのロングラン記録を更新中。追いかける「シカゴ」(1996年初演)、「ライオン・キング」(1997年初演)を大きく引き離しているため、当分はこれを抜くロングランは出てこないでしょう(ただし、ブロードウェイに限った話で、オフ・ブロードウェイやロンドンにはこれ以上のロングラン記録がある)。
 映画の方は、モノクロの現在(1919年)において、パリ・オペラ座で1870年に起こった惨事の遺品オークションが開かれ、当時の支援者であったラウル子爵とバレエ教師のマダム・ジリーがペルシャの衣装を纏ったサルのオルゴールを競った後、競りは昔に天井から落下して大参事を引き起こしたシャンデリアへと移り、道具方がシャンデリアを天井へ吊り上げると、子爵の記憶の中で、シャンデリアが劇場の天井に燦然と輝き、当時の記憶が甦っていくという流れでカラーの物語当時(1870年)に移っていき、多くの踊子たちが今まさに舞台稽古をする活気ある劇場の場面になるという、このモノクロからカラーに切り替わって、風化した劇場がみるみる当時の輝きを取り戻してく場面は圧巻でした。
映画の方は、モノクロの現在(1919年)において、パリ・オペラ座で1870年に起こった惨事の遺品オークションが開かれ、当時の支援者であったラウル子爵とバレエ教師のマダム・ジリーがペルシャの衣装を纏ったサルのオルゴールを競った後、競りは昔に天井から落下して大参事を引き起こしたシャンデリアへと移り、道具方がシャンデリアを天井へ吊り上げると、子爵の記憶の中で、シャンデリアが劇場の天井に燦然と輝き、当時の記憶が甦っていくという流れでカラーの物語当時(1870年)に移っていき、多くの踊子たちが今まさに舞台稽古をする活気ある劇場の場面になるという、このモノクロからカラーに切り替わって、風化した劇場がみるみる当時の輝きを取り戻してく場面は圧巻でした。
 アンドリュー・ロイド・ウェバーは舞台ミュージカル「オペラ座の怪人」の作曲家であり製作者でもあって(2006年に「オペラ座の怪人」に抜かれるまでのロングラン記録を持っていた「キャッツ」も彼が手がけた)、原作をミュージカルにする際に、それまでのホラー映画的な脚本をラブロマンスに改変したことで知られています。従って、「ミュージカルの映画化」であるこの作品も、殆どロマンチック映画と言ってもよい作品なっているのと、あと、映画化される度に、怪人(ファントム)が美男子になっていく傾向にあり、この作品の怪人(ジェラルド・バトラー)で頂点に達した印象もあります。
アンドリュー・ロイド・ウェバーは舞台ミュージカル「オペラ座の怪人」の作曲家であり製作者でもあって(2006年に「オペラ座の怪人」に抜かれるまでのロングラン記録を持っていた「キャッツ」も彼が手がけた)、原作をミュージカルにする際に、それまでのホラー映画的な脚本をラブロマンスに改変したことで知られています。従って、「ミュージカルの映画化」であるこの作品も、殆どロマンチック映画と言ってもよい作品なっているのと、あと、映画化される度に、怪人(ファントム)が美男子になっていく傾向にあり、この作品の怪人(ジェラルド・バトラー)で頂点に達した印象もあります。
 但し、クリスティーヌとラウルの素性や馴れ初めといった背景は原作から変わっておらず、映画でも原作の雰囲気を保っています。ミュージカルの映画化でありながら、原作のテイストも保っている映画化作品と言えるでしょう。原作と異なるのは、怪人の過去を知るペルシャ人のダロガ(実は元秘密警察署長で、原作では後半の主役的存在)を登場させず、マダム・ジリー(ミランダ・リチャードソン)にその役割を吸収させていることで、これは、アンドリュー・ロイド・ウェバーによってミュージカル化された際の
但し、クリスティーヌとラウルの素性や馴れ初めといった背景は原作から変わっておらず、映画でも原作の雰囲気を保っています。ミュージカルの映画化でありながら、原作のテイストも保っている映画化作品と言えるでしょう。原作と異なるのは、怪人の過去を知るペルシャ人のダロガ(実は元秘密警察署長で、原作では後半の主役的存在)を登場させず、マダム・ジリー(ミランダ・リチャードソン)にその役割を吸収させていることで、これは、アンドリュー・ロイド・ウェバーによってミュージカル化された際の 改変ですが、怪人、クリスティーヌ、ラウルの3者の関係を際立たせるために、ややアクのあるダロガを省いたのでしょう。マダム・ジリーが怪人の過去を知っていて(かつて怪人を匿ったのもマダム・ジリーになっている。原作ではダロガが怪人の全てを知っていて、ペルシャで彼を救ったのもダロガ)、マダム・ジリーはラウルを怪人の隠れ家の手前まで導きますが、あとは、ラウルにこの先は自分一人でお行きなさいという感じでした(原作では、ダロガはクリスティーヌを救い出そうとするラウルに最後まで付き合い、ラウルと一緒に散々危険な目に遭う)。
改変ですが、怪人、クリスティーヌ、ラウルの3者の関係を際立たせるために、ややアクのあるダロガを省いたのでしょう。マダム・ジリーが怪人の過去を知っていて(かつて怪人を匿ったのもマダム・ジリーになっている。原作ではダロガが怪人の全てを知っていて、ペルシャで彼を救ったのもダロガ)、マダム・ジリーはラウルを怪人の隠れ家の手前まで導きますが、あとは、ラウルにこの先は自分一人でお行きなさいという感じでした(原作では、ダロガはクリスティーヌを救い出そうとするラウルに最後まで付き合い、ラウルと一緒に散々危険な目に遭う)。
そしてラストでモノクロ(1919年)に戻って、1917年に61歳で他界したクリスティーヌの墓を怪人が訪れた事を示唆するカットで終わります(ダロガの役割を兼ねたマダム・ジリーが語り部的位置づけであることも、ダロガが語り部的位置づけにある原作を一部踏襲していることなる)。
 大掛かりな仕掛けもあって映像的には楽しませてくれますが(落下するシャンデリアはスワロフスキー社の製作費1億2千万円のガラス製で、"一発撮り"だった)、やはり、怪人を演じたジェラルド・バトラーのイケメンぶりが一番目立っていました。マスクを外してもあまり醜い感じがしませんでしたが(原作では唇の跡も残っていないことになっている)、終盤のクリスティーヌが怪人にキスをするシーンに観客を感情移入させるにはやむを得ないのでしょうか。そのキスが、怪人が無駄な抵抗や殺戮を止める契機となるわけだし(但し、原作では怪人は連続殺人を犯すのに対し、映画ではカルロッタの恋人の歌手が唯一の犠牲者だったのでは)。
大掛かりな仕掛けもあって映像的には楽しませてくれますが(落下するシャンデリアはスワロフスキー社の製作費1億2千万円のガラス製で、"一発撮り"だった)、やはり、怪人を演じたジェラルド・バトラーのイケメンぶりが一番目立っていました。マスクを外してもあまり醜い感じがしませんでしたが(原作では唇の跡も残っていないことになっている)、終盤のクリスティーヌが怪人にキスをするシーンに観客を感情移入させるにはやむを得ないのでしょうか。そのキスが、怪人が無駄な抵抗や殺戮を止める契機となるわけだし(但し、原作では怪人は連続殺人を犯すのに対し、映画ではカルロッタの恋人の歌手が唯一の犠牲者だったのでは)。
 クリスティーヌを演じたエミー・ロッサムの歌唱は良かったように思います。他の歌唱部分もそれぞれの役者が吹き替え無しで歌っています(カルロッタ役のミニー・ドライヴァーのみ吹き替えであったが、ドライヴァーも歌唱力を生かしてエンディング・テーマを歌った)。ただ、歌とセリフが重なってしまっている部分もあって、そのことに対する否定的評価もあったようです。これは、この作品に限らずミュージカル映画の場合、歌の部分を先に収録して、それに合わせて後で演じる姿を撮る手法が一般的であるため、そうしたことが起きることがあるようですが、最近ではトム・フーパー監督の「レ・ミゼラブル」('12年/英)のように、撮影時にピアニストを常駐させて仮の伴奏をする中で、俳優たちがその場で歌い、演技をするという手法なども用いられているようです(これなら歌とセリフが重なることはない)。
クリスティーヌを演じたエミー・ロッサムの歌唱は良かったように思います。他の歌唱部分もそれぞれの役者が吹き替え無しで歌っています(カルロッタ役のミニー・ドライヴァーのみ吹き替えであったが、ドライヴァーも歌唱力を生かしてエンディング・テーマを歌った)。ただ、歌とセリフが重なってしまっている部分もあって、そのことに対する否定的評価もあったようです。これは、この作品に限らずミュージカル映画の場合、歌の部分を先に収録して、それに合わせて後で演じる姿を撮る手法が一般的であるため、そうしたことが起きることがあるようですが、最近ではトム・フーパー監督の「レ・ミゼラブル」('12年/英)のように、撮影時にピアニストを常駐させて仮の伴奏をする中で、俳優たちがその場で歌い、演技をするという手法なども用いられているようです(これなら歌とセリフが重なることはない)。
 因みに、ブロードウェイでミュージカルを観る時はきちんとした服装で観るようにと人から言われていましたが、90年代当時からバミューダ・パンツなどラフな格好で来ているニューヨーカーは多かったです。但し、カーテンコールで正装の客もラフな格好の客も全員が立ち上がって「ブラボー」と叫びながら拍手する様は圧巻でした。そうした幕が降りた後の盛り上がりは映画館では体感できませんが、映画としては充分に愉しめます。本来は悲劇なのだけど、「レ・ミゼラブル」のように泣けるという感じにはならない作品、ストーリーよりもパッションを堪能する作品でしょうか。
因みに、ブロードウェイでミュージカルを観る時はきちんとした服装で観るようにと人から言われていましたが、90年代当時からバミューダ・パンツなどラフな格好で来ているニューヨーカーは多かったです。但し、カーテンコールで正装の客もラフな格好の客も全員が立ち上がって「ブラボー」と叫びながら拍手する様は圧巻でした。そうした幕が降りた後の盛り上がりは映画館では体感できませんが、映画としては充分に愉しめます。本来は悲劇なのだけど、「レ・ミゼラブル」のように泣けるという感じにはならない作品、ストーリーよりもパッションを堪能する作品でしょうか。
 「オペラ座の怪人」●原題:THE PHANTOM OF THE OPERA●制作年:2004年●制作国:アメリカ●監督:ジョエル・シュマッカー●製作:アンドルー・ロイド・ウェバー●脚本:ジョエル・シューマカー/アンドリュー・ロイド・ウェバー●撮影:ジョン・マシソン●音楽:アンドルー・ロイド・ウェバー●原作:ガストン・ルルー●時間:143分●出演:ジェラルド・バトラー/エミー・ロッサム/パトリック・ウィルソン/ミランダ・リチャードソン/ミニー・ドライヴァー/キーラン・ハインズ/サイモン・キャロウ●日本公開:2005/01●配給:ギャガ・コミュニケーションズ●最初に観た場所:北千住・シネマブルースタジオ(15-09-01)(評価:★★★★)
「オペラ座の怪人」●原題:THE PHANTOM OF THE OPERA●制作年:2004年●制作国:アメリカ●監督:ジョエル・シュマッカー●製作:アンドルー・ロイド・ウェバー●脚本:ジョエル・シューマカー/アンドリュー・ロイド・ウェバー●撮影:ジョン・マシソン●音楽:アンドルー・ロイド・ウェバー●原作:ガストン・ルルー●時間:143分●出演:ジェラルド・バトラー/エミー・ロッサム/パトリック・ウィルソン/ミランダ・リチャードソン/ミニー・ドライヴァー/キーラン・ハインズ/サイモン・キャロウ●日本公開:2005/01●配給:ギャガ・コミュニケーションズ●最初に観た場所:北千住・シネマブルースタジオ(15-09-01)(評価:★★★★)
【2436】 ○ ルパート・ジュリアン (原作:ガストン・ルルー) 「オペラ座の怪人」 (25年/米) ★★★★




「IVC BEST SELECTION オペラ座の怪人 [DVD]」['13年]/「オペラ座の怪人 【サイレント】 [DVD] FRT-302
」['08年]/「オペラ座の怪人【字幕版】(淀川長治 名作映画ベスト&ベスト) [VHS]
」['98年] Lon Chaney
 1880年、パリ・オペラ座には恐ろしい幽霊が現われるという評判が立ち、舞姫や道具方らは恐怖に見舞われる。折しも道具方の一人が縊死し、これも幽霊の仕業だと益々人々は恐れる。オペラ座の支配人引退興行の夜、プリマドンナのカルロッタ(ヴァージニア・ペアソン)が突然の病気のため、無名の歌手クリスティーヌ・ダーエ(メアリー・フィルビン)が「ファウスト」のマルグリットを演じて大成功を博す。子爵ラウル(ノーマ
1880年、パリ・オペラ座には恐ろしい幽霊が現われるという評判が立ち、舞姫や道具方らは恐怖に見舞われる。折しも道具方の一人が縊死し、これも幽霊の仕業だと益々人々は恐れる。オペラ座の支配人引退興行の夜、プリマドンナのカルロッタ(ヴァージニア・ペアソン)が突然の病気のため、無名の歌手クリスティーヌ・ダーエ(メアリー・フィルビン)が「ファウスト」のマルグリットを演じて大成功を博す。子爵ラウル(ノーマ ン・ケリー)は彼女に思いを寄せ、彼女の仕度部屋を訪れると部屋の中には何者とも知れぬ男の声がし、クリスティーヌの哀訴の声が聞えたため、ラウルは嫉妬する。新しい支配人は幽霊などいないと冷笑し、怪人の警告を無視してカルロッタを舞台に立たせると、天井に吊したシャンデリアが墜ちて多くの人々が死傷する。クリスティーヌは愛するラウルに、怪人というのはオペラ座の地下の湖に棲むエリック(ロン・チェイニー)であることを告げる。ある晩の開演中、エリックはクリスティーヌを連れ去る。ペルシャ人レドー(アーサー・エドモンド・カリュー)を案内としてラウルは愛人を助けに地下湖へ向かう―。
ン・ケリー)は彼女に思いを寄せ、彼女の仕度部屋を訪れると部屋の中には何者とも知れぬ男の声がし、クリスティーヌの哀訴の声が聞えたため、ラウルは嫉妬する。新しい支配人は幽霊などいないと冷笑し、怪人の警告を無視してカルロッタを舞台に立たせると、天井に吊したシャンデリアが墜ちて多くの人々が死傷する。クリスティーヌは愛するラウルに、怪人というのはオペラ座の地下の湖に棲むエリック(ロン・チェイニー)であることを告げる。ある晩の開演中、エリックはクリスティーヌを連れ去る。ペルシャ人レドー(アーサー・エドモンド・カリュー)を案内としてラウルは愛人を助けに地下湖へ向かう―。 フランスの作家ガストン・ルルー(Gaston Leroux、1868-1927)によって1909年に発表された『オペラ座の怪人』の、2004年までに9回映画化されたうちの2回目の映画化作品で、「ノートルダムのせむし男」('23年)などでも知られ「千の顔を持つ男(MAN OF A THOUSAND FACES)」と称されたロン・チェイニー(1888-1930)が"怪人"を演じています。"怪人"エリックが音楽と奇術に明るい、脱獄した猟奇犯罪者に設定が変更されていますが(ビデオジャケット(旧版)には、解雇された元オペラ座の楽団員とある)、全体としては原作に比較的忠実な映画化作品とされています。
フランスの作家ガストン・ルルー(Gaston Leroux、1868-1927)によって1909年に発表された『オペラ座の怪人』の、2004年までに9回映画化されたうちの2回目の映画化作品で、「ノートルダムのせむし男」('23年)などでも知られ「千の顔を持つ男(MAN OF A THOUSAND FACES)」と称されたロン・チェイニー(1888-1930)が"怪人"を演じています。"怪人"エリックが音楽と奇術に明るい、脱獄した猟奇犯罪者に設定が変更されていますが(ビデオジャケット(旧版)には、解雇された元オペラ座の楽団員とある)、全体としては原作に比較的忠実な映画化作品とされています。 原作がアンドリュー・ロイド・ウェバーによってミュージカル化(1986年10月のロンドンが初演)された際に、ホラー調のストーリーがラブ・ロマンス風に改変されていますが、原作でも一応クリスティーヌは最後は怪人に対して真心で接します。しかし、この映画化作品では、クリスティーヌが一瞬は怪人に寄り添うかのように見えた場面もあったものの、結局彼女にとって怪人はあくまでも「怪人」であり、その分、怪人の方はストーカー的存在に終始しています。
原作がアンドリュー・ロイド・ウェバーによってミュージカル化(1986年10月のロンドンが初演)された際に、ホラー調のストーリーがラブ・ロマンス風に改変されていますが、原作でも一応クリスティーヌは最後は怪人に対して真心で接します。しかし、この映画化作品では、クリスティーヌが一瞬は怪人に寄り添うかのように見えた場面もあったものの、結局彼女にとって怪人はあくまでも「怪人」であり、その分、怪人の方はストーカー的存在に終始しています。 原作のペルシャ人の元秘密警察ダロガは、該当する人物(レドー)は登場しますが、過去にエリックとの間であった経緯は描かれておらず、そもそも出て来るなり何だか怪しげです。しかし、ラウルがエリックに連れ去られたクリスティーヌを奪回しようとするに際しては、積極的にラウルをエリックの隠れ家である地下湖に導き、その結果、ラウルと共に散々危険な目に遭います。一方、2004年版の映画や劇団四季版などでダロガの役割まで併せて担わせている元バレイ教師、現案内係りのマダム・ジリは登場しません。
原作のペルシャ人の元秘密警察ダロガは、該当する人物(レドー)は登場しますが、過去にエリックとの間であった経緯は描かれておらず、そもそも出て来るなり何だか怪しげです。しかし、ラウルがエリックに連れ去られたクリスティーヌを奪回しようとするに際しては、積極的にラウルをエリックの隠れ家である地下湖に導き、その結果、ラウルと共に散々危険な目に遭います。一方、2004年版の映画や劇団四季版などでダロガの役割まで併せて担わせている元バレイ教師、現案内係りのマダム・ジリは登場しません。
 オペラ座のセットが大掛かりで、仮面舞踏会のシーンなどは圧巻、しかも、この部分はカラーです。登場する怪人はドクロの仮面を被っていますが、これはブロードウェイ・ミュージ
オペラ座のセットが大掛かりで、仮面舞踏会のシーンなどは圧巻、しかも、この部分はカラーです。登場する怪人はドクロの仮面を被っていますが、これはブロードウェイ・ミュージ カル(上右)でも同じです。シャンデリアが
カル(上右)でも同じです。シャンデリアが 墜ちるシーンも、
墜ちるシーンも、 怪人エリックは奇術師の才能も持ち合わせている訳ですが、奇術師というより地下に秘密基地を築いたマッド・サイエンティストといった感じでしょうか。クリスティーヌとの婚礼を迫り、小箱の中にあるバッタとサソリの細工を見せてクリスティーヌに選択を求めるのも原作と同じ。バッタを回せばノー、サソリを回せばイエスのサインであると説明をしますが、バッタを選ぶとオペラ座の地下の火薬庫を爆発させるいうことです。クリスティーヌがやむなくサソリを選ぶと、地下に閉じ込められたラウル、レドーが水没の危機に晒されるという展開で、先にも述べた通り、1925年に作られた映画とは思えないくらい今風なスぺクタルシーンを見せてくれます。
怪人エリックは奇術師の才能も持ち合わせている訳ですが、奇術師というより地下に秘密基地を築いたマッド・サイエンティストといった感じでしょうか。クリスティーヌとの婚礼を迫り、小箱の中にあるバッタとサソリの細工を見せてクリスティーヌに選択を求めるのも原作と同じ。バッタを回せばノー、サソリを回せばイエスのサインであると説明をしますが、バッタを選ぶとオペラ座の地下の火薬庫を爆発させるいうことです。クリスティーヌがやむなくサソリを選ぶと、地下に閉じ込められたラウル、レドーが水没の危機に晒されるという展開で、先にも述べた通り、1925年に作られた映画とは思えないくらい今風なスぺクタルシーンを見せてくれます。
 とにかく、ロン・チェイニーの怪人のメイクの異様さが際立っていて、原作もミュージカルも、ジョエル・シュマッカー版をはじめとする近年の映画化作品も、顔の一部のみをマスクで覆っているのに対し、ここではほぼフルフェイスのマスクを被っており、それを外すと顔全体が凄いことになっています(さっきまで一
とにかく、ロン・チェイニーの怪人のメイクの異様さが際立っていて、原作もミュージカルも、ジョエル・シュマッカー版をはじめとする近年の映画化作品も、顔の一部のみをマスクで覆っているのに対し、ここではほぼフルフェイスのマスクを被っており、それを外すと顔全体が凄いことになっています(さっきまで一 部覗いていたかのように見えた目までメイクが変化している)。
部覗いていたかのように見えた目までメイクが変化している)。 この作品、VHSはパートカラーだったのに、最初に出たDV
この作品、VHSはパートカラーだったのに、最初に出たDV Dは廉価版だったせいか全編モノクロになっています(その後出たDVDはパートカラーに)。とりわけパートカラーの部分は出来るだけ綺麗な映像で観たいところですが、アメリカではBlu-ray Discが発売されているものの、日本では現時点['16年]でまだのようです。
Dは廉価版だったせいか全編モノクロになっています(その後出たDVDはパートカラーに)。とりわけパートカラーの部分は出来るだけ綺麗な映像で観たいところですが、アメリカではBlu-ray Discが発売されているものの、日本では現時点['16年]でまだのようです。 年:1925年●制作国:アメリカ●監督:ルパート・ジュリアン●製作:カール・レムリ●脚本:エリオット・J・クローソン/レイモンド・L・シュロック●原作:ガストン・ルルー●時間:(最長版)107分・(短縮版)75分●出演:ロン・チェイニー(エリック)/メアリー・フィルビン(クリスティーヌ)/ノーマン・ケリー(ラウル)/ヴァージニア・ペアソン(カルロッタ)/アーサー・エドモンド・カリュー(レドー)●日本公開:1925/09●配給:ユニバーサル・ピクチャーズ(評価:★★★★)
年:1925年●制作国:アメリカ●監督:ルパート・ジュリアン●製作:カール・レムリ●脚本:エリオット・J・クローソン/レイモンド・L・シュロック●原作:ガストン・ルルー●時間:(最長版)107分・(短縮版)75分●出演:ロン・チェイニー(エリック)/メアリー・フィルビン(クリスティーヌ)/ノーマン・ケリー(ラウル)/ヴァージニア・ペアソン(カルロッタ)/アーサー・エドモンド・カリュー(レドー)●日本公開:1925/09●配給:ユニバーサル・ピクチャーズ(評価:★★★★)


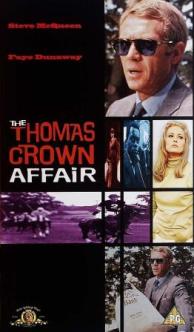
 ハンサムで裕福な実業家でありながら、実は裏の顔を持つクラウン(スティーヴ・マックィーン)。彼は、満ち足りた生活では得られないスリルを求めて銀行強盗を計画、ボストンの自社ビル前の銀行を5人の男に襲わせて見事に成功、260万ドルの現金を手中にする。事件後、ボストン市警も手がかりを掴めずお手上げとなる中、マローン警部補(ポール・バーク)とともに捜査していた銀行の保険会社
ハンサムで裕福な実業家でありながら、実は裏の顔を持つクラウン(スティーヴ・マックィーン)。彼は、満ち足りた生活では得られないスリルを求めて銀行強盗を計画、ボストンの自社ビル前の銀行を5人の男に襲わせて見事に成功、260万ドルの現金を手中にする。事件後、ボストン市警も手がかりを掴めずお手上げとなる中、マローン警部補(ポール・バーク)とともに捜査していた銀行の保険会社 の調査員ビッキー・アンダーソン(フェイ・ダナウェイ)はクラウンに目をつけ、彼が黒幕であることを確信する。彼女は正体を暴こうとクラウンに近づくが、徐々に彼の大胆不敵な姿に心惹かれてしまう。こうして2人のスリリングで奇妙な関係が始まる―。
の調査員ビッキー・アンダーソン(フェイ・ダナウェイ)はクラウンに目をつけ、彼が黒幕であることを確信する。彼女は正体を暴こうとクラウンに近づくが、徐々に彼の大胆不敵な姿に心惹かれてしまう。こうして2人のスリリングで奇妙な関係が始まる―。
 監督のノーマン・ジュイソンは前作「夜の大捜査線」('67年)でアカデミー作品賞を受賞、主演のスティーヴ・マックイーンも前作「砲艦サンパブロ」('66年)でアカデミー主演男優賞候補にノミネート、フェイ・ダナウェイも前年「俺たちに明日はない」('67年)でやはりアカデミー主演女優賞にノミネートされているなど、当時脂が乗り切っていたメンバー構成。但し、クラウン役はショーン・コネリーにオファーされたのが、彼がそれを断ったためにスティーヴ・マックイーンに回ってきたものだったとか。
監督のノーマン・ジュイソンは前作「夜の大捜査線」('67年)でアカデミー作品賞を受賞、主演のスティーヴ・マックイーンも前作「砲艦サンパブロ」('66年)でアカデミー主演男優賞候補にノミネート、フェイ・ダナウェイも前年「俺たちに明日はない」('67年)でやはりアカデミー主演女優賞にノミネートされているなど、当時脂が乗り切っていたメンバー構成。但し、クラウン役はショーン・コネリーにオファーされたのが、彼がそれを断ったためにスティーヴ・マックイーンに回ってきたものだったとか。
 世界的に有名な大実業家が、何の苦労もないのにただスリルだけのために銀行襲撃を指揮し、しかも捕まらないという贅沢極まりないお話で、最初観た時はこんなのアリ?という気もしましたが、スティーヴ・マックィーンが亡くなってからテレビで観て、これ、スティーヴ・マックィーンのファンには彼のカッコよさを堪能するには格好の作品だなあと(撮影前は「スーツを着たマックィーンなんて見たくない」との声もあったというが、公開後にはそうした声は殆ど聞かれなくなったという)。また、ラブストーリーとしても楽しめる作品ではないかと思うようになりました。
世界的に有名な大実業家が、何の苦労もないのにただスリルだけのために銀行襲撃を指揮し、しかも捕まらないという贅沢極まりないお話で、最初観た時はこんなのアリ?という気もしましたが、スティーヴ・マックィーンが亡くなってからテレビで観て、これ、スティーヴ・マックィーンのファンには彼のカッコよさを堪能するには格好の作品だなあと(撮影前は「スーツを着たマックィーンなんて見たくない」との声もあったというが、公開後にはそうした声は殆ど聞かれなくなったという)。また、ラブストーリーとしても楽しめる作品ではないかと思うようになりました。
 最近劇場で改めて観直して、導入部のマルチスクリーンもいいし、フェイ・ダナウェイもいいし(色香際立つチェス・シーン!)、「シェルブールの雨傘」('64年)の
最近劇場で改めて観直して、導入部のマルチスクリーンもいいし、フェイ・ダナウェイもいいし(色香際立つチェス・シーン!)、「シェルブールの雨傘」('64年)の ミシェル・ルグランによる音楽もいいなあと(テーマ曲「風のささやき」(唄: ノエル・ハリソン)はアカデミー主題歌賞受賞)。主人公は、グライダーで優雅に空を翔け、バギーで浜を走らせ、ゴルフをし、ボロをしとスポーティですが、フランスの街並み風のカットがあったりして、何となくヨーロッパ的な感じがしなくもなく、フェイ・ダナウェイのファッションも楽しめて、全体としてはたいへんお洒落な作りになっていると言っていいのではないでしょうか。
ミシェル・ルグランによる音楽もいいなあと(テーマ曲「風のささやき」(唄: ノエル・ハリソン)はアカデミー主題歌賞受賞)。主人公は、グライダーで優雅に空を翔け、バギーで浜を走らせ、ゴルフをし、ボロをしとスポーティですが、フランスの街並み風のカットがあったりして、何となくヨーロッパ的な感じがしなくもなく、フェイ・ダナウェイのファッションも楽しめて、全体としてはたいへんお洒落な作りになっていると言っていいのではないでしょうか。
 こうしたストレートな娯楽映画が観る度に良いと思えるようになるのは、「目が肥えた」と言うよりも年齢がいったせいかもしれませんが、やはりスティーヴ・マックィーンとフェイ・ダナウェイという2人のスター俳優に支えられている部分は大きいのだろうと思います。ラスト、空を飛ぶスティーヴ・マックィーンと地を行くフェイ・ダナウェイという対比で捉えると、男と女の生き方の違いを描いた映画とも言えるかもしれません。意外と深いかも...。1999年には、この作品を愛するピアース・ブロスナンの製作・主演で同名(邦題は「トーマス・クラウン・アフェアー」)のリメイク版も制作されていて、フェイ・ダナウェイも客演していますが、ラストを少し変えていたように思います(終わり方としてはオリジナルの方がいい)。
こうしたストレートな娯楽映画が観る度に良いと思えるようになるのは、「目が肥えた」と言うよりも年齢がいったせいかもしれませんが、やはりスティーヴ・マックィーンとフェイ・ダナウェイという2人のスター俳優に支えられている部分は大きいのだろうと思います。ラスト、空を飛ぶスティーヴ・マックィーンと地を行くフェイ・ダナウェイという対比で捉えると、男と女の生き方の違いを描いた映画とも言えるかもしれません。意外と深いかも...。1999年には、この作品を愛するピアース・ブロスナンの製作・主演で同名(邦題は「トーマス・クラウン・アフェアー」)のリメイク版も制作されていて、フェイ・ダナウェイも客演していますが、ラストを少し変えていたように思います(終わり方としてはオリジナルの方がいい)。
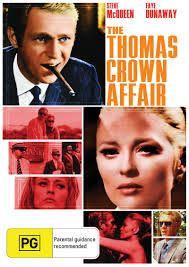

 「華麗なる賭け」●原題:THE THOMAS CROWN AFFAIR●制作年:1968年●制作国:アメリカ●監督:ノーマン・ジュイソン●製作:ノーマン・ジュイソン●脚本:アラン・R・トラストマン●撮影:ハスケル・ウェクスラー●音楽:ミシェル・ルグラン●時間:102分●出演:スティーヴ・マックィーン/フェイ・ダナウェイ/ポール・バーク/ジャック・ウェストン/ヤフェット・コットー/トッド・マーティン/サム・メルビル/アディソン・ポウエル●日本公開:1968/06●配給:ユナイテッド・アーチス●最初に観た場所:池袋・文芸坐(80-07-16)●2回目:北千住・シネマブルースタジオ(15-03-24)(評価:★★★★☆)●併映(1回目):「ブリット」(ピーター・イェイツ)
「華麗なる賭け」●原題:THE THOMAS CROWN AFFAIR●制作年:1968年●制作国:アメリカ●監督:ノーマン・ジュイソン●製作:ノーマン・ジュイソン●脚本:アラン・R・トラストマン●撮影:ハスケル・ウェクスラー●音楽:ミシェル・ルグラン●時間:102分●出演:スティーヴ・マックィーン/フェイ・ダナウェイ/ポール・バーク/ジャック・ウェストン/ヤフェット・コットー/トッド・マーティン/サム・メルビル/アディソン・ポウエル●日本公開:1968/06●配給:ユナイテッド・アーチス●最初に観た場所:池袋・文芸坐(80-07-16)●2回目:北千住・シネマブルースタジオ(15-03-24)(評価:★★★★☆)●併映(1回目):「ブリット」(ピーター・イェイツ) ノーマン・ジュイソン
ノーマン・ジュイソン


 ニューオーリンズの町に、その世界で30年も君臨するポーカー・プレイヤーの大物"ザ・マン"ことランシー・ハワード(エドワード・G・ロビンソン)がやって来た。自身もポーカーの名手であるシンシナティ・キッドことエリック・ストーナー(スティーブ・マックイーン)は、いつかランシーと手合わせをと考えていた。キッドは早速この社会の長老格シューター(カール・マルデン)にその機会を頼むが、シューターはキッドの自信過剰をたしなめる。かくしてキッドはランシーとの対戦に臨むが―。
ニューオーリンズの町に、その世界で30年も君臨するポーカー・プレイヤーの大物"ザ・マン"ことランシー・ハワード(エドワード・G・ロビンソン)がやって来た。自身もポーカーの名手であるシンシナティ・キッドことエリック・ストーナー(スティーブ・マックイーン)は、いつかランシーと手合わせをと考えていた。キッドは早速この社会の長老格シューター(カール・マルデン)にその機会を頼むが、シューターはキッドの自信過剰をたしなめる。かくしてキッドはランシーとの対戦に臨むが―。 同じく勝負事を主人公にした作品として、ポール・ニューマン(1925-2008)が英国アカデミー賞主演男優賞を受賞した「ハスラー」('61年)がありますが、、アクターズ・スタジオを経てブロードウェイにデビューしている点で両者は共通するものの、既に「熱いトタン屋根の猫」('58年)など文芸作品にも出ていたポール・ニューマンに比べ、
同じく勝負事を主人公にした作品として、ポール・ニューマン(1925-2008)が英国アカデミー賞主演男優賞を受賞した「ハスラー」('61年)がありますが、、アクターズ・スタジオを経てブロードウェイにデビューしている点で両者は共通するものの、既に「熱いトタン屋根の猫」('58年)など文芸作品にも出ていたポール・ニューマンに比べ、 脱走」('63年)など西部劇やアクション映画への出演がそれまで多かったスティーブ・マックイーンにとっては、ポーカー・ゲームの場面が多くを占めるこの作品への
脱走」('63年)など西部劇やアクション映画への出演がそれまで多かったスティーブ・マックイーンにとっては、ポーカー・ゲームの場面が多くを占めるこの作品への 出演は、演技力が試される挑戦ではなかったのではないでしょうか。しかも、相手が
出演は、演技力が試される挑戦ではなかったのではないでしょうか。しかも、相手が ストーリー展開は、ポール・ニューマン演じる主人公が最初は全然歯が立たなかったベテランの相手を最後に破る「ハスラー」とはちょうど真逆で、スティーブ・マックイーン演じる自信に満ちた若手の主人公が、最後にベテランを追い詰め勝利と栄光を手にするかと思いきや―というもの。これ、封切時に初めて観た人は、スティーブ・マックイーンが演じてきた役柄の全能感のあるイメージもあって、すとーんと落とされたようなギャップがあっただろうなあと思われます。
ストーリー展開は、ポール・ニューマン演じる主人公が最初は全然歯が立たなかったベテランの相手を最後に破る「ハスラー」とはちょうど真逆で、スティーブ・マックイーン演じる自信に満ちた若手の主人公が、最後にベテランを追い詰め勝利と栄光を手にするかと思いきや―というもの。これ、封切時に初めて観た人は、スティーブ・マックイーンが演じてきた役柄の全能感のあるイメージもあって、すとーんと落とされたようなギャップがあっただろうなあと思われます。 エドワード・G・ロビンソンは余裕綽々の名演という感じですが、スティーブ・マックイーンの演技もそれに拮抗すると言っていいのではないでしょうか。キッドを誘惑しようとするシューターの妻メルバを演じたアン・マーグレットも、キッドが自分にはチューズデイ・ウェルドト演じるクリスチャンという恋人がありながら、ふらっとそっちへ靡いてしまうのが分からなくもないような蠱惑的ムードを醸し、レディ・フィンガーズを演じたジョーン・ブロンデルも名演で、演技が手な下手な人は殆ど出ていなかったような映画のように思えました。
エドワード・G・ロビンソンは余裕綽々の名演という感じですが、スティーブ・マックイーンの演技もそれに拮抗すると言っていいのではないでしょうか。キッドを誘惑しようとするシューターの妻メルバを演じたアン・マーグレットも、キッドが自分にはチューズデイ・ウェルドト演じるクリスチャンという恋人がありながら、ふらっとそっちへ靡いてしまうのが分からなくもないような蠱惑的ムードを醸し、レディ・フィンガーズを演じたジョーン・ブロンデルも名演で、演技が手な下手な人は殆ど出ていなかったような映画のように思えました。 但し、最後、勝負に敗れ全てを失ったキッドの前に、キッドとメルバの関係を目の当たりにして一旦はキッドの下を去っていたクリスチャンが再び現れるのは、やや甘い結末と言えるでしょうか。一旦すとーんと落としておいて、救ってしまっているので、衝撃緩衝剤みたいになってしまった感じがするなあと思っていたら、これは監督の意向ではなく、スタジオの意向でそうしたシーンが付け加えられたとのことで、ちょっと勿体ない気もします。クリスチャンは安定志向なので、仮にキッドが財政面で彼女に助けてもらうならば、引き換えに勝負師として生きる道は閉ざされるのかなとか、余計な憶測を生む結果にもなっているように思いました(ラストの落ち着きが悪い。子供にも賭けで負けてしまうところで終わっていた方が良かった)。ノーマン・ジュイスン自身も、後に「無用で有害ですらあるセンチメンタルなラストが追加されているのは申し訳ない」と述べているそうです。まだ、当時はそれほど実績が無く、スタジオの意向を聞かざるを得なかったのでしょうが、惜しい気がします。
但し、最後、勝負に敗れ全てを失ったキッドの前に、キッドとメルバの関係を目の当たりにして一旦はキッドの下を去っていたクリスチャンが再び現れるのは、やや甘い結末と言えるでしょうか。一旦すとーんと落としておいて、救ってしまっているので、衝撃緩衝剤みたいになってしまった感じがするなあと思っていたら、これは監督の意向ではなく、スタジオの意向でそうしたシーンが付け加えられたとのことで、ちょっと勿体ない気もします。クリスチャンは安定志向なので、仮にキッドが財政面で彼女に助けてもらうならば、引き換えに勝負師として生きる道は閉ざされるのかなとか、余計な憶測を生む結果にもなっているように思いました(ラストの落ち着きが悪い。子供にも賭けで負けてしまうところで終わっていた方が良かった)。ノーマン・ジュイスン自身も、後に「無用で有害ですらあるセンチメンタルなラストが追加されているのは申し訳ない」と述べているそうです。まだ、当時はそれほど実績が無く、スタジオの意向を聞かざるを得なかったのでしょうが、惜しい気がします。


 演:スティーブ・マックイーン/エドワード・G・ロビンソン/アン=マーグレット/カール・マルデン/チューズデイ・ウェルド/チューズデイ・ウェルド/ジョーン・ブロンデル/ジェフ・コーリー/リップ・トーン/ジャック・ウェストン/キャブ・キャロウェイ●日本公開:1965/10●配給:MGM映画(評価:★★★☆)
演:スティーブ・マックイーン/エドワード・G・ロビンソン/アン=マーグレット/カール・マルデン/チューズデイ・ウェルド/チューズデイ・ウェルド/ジョーン・ブロンデル/ジェフ・コーリー/リップ・トーン/ジャック・ウェストン/キャブ・キャロウェイ●日本公開:1965/10●配給:MGM映画(評価:★★★☆)





 シカゴ記念病院の有能な血管外科医リチャード・キンブル(ハリソン・フォード)がある夜帰宅すると、妻のヘレン(セーラ・ウォード)が家の中で何者かに襲われて死に瀕していた。キンブルは犯人と思しき「片腕が義手の男」を撃退するも、妻は既に致命傷を負っており手遅れであった。キンブルは自分が取り逃がした義手の男について捜査するよう警察に懇願するが、警察は死の間際のヘレンの通報内容を誤解し、キンブル本人が妻殺しの濡れ衣を着せられ逮捕されてしまう。キンブルは裁判で無実を証明することができず、死刑判決を受けて刑務所へと移送されることになるが、その最中に他の囚人たちが逃亡を企てたことにより、護送車が列車と衝突し爆発炎上するという事故が発生する。事故を間一髪で生き延びた
シカゴ記念病院の有能な血管外科医リチャード・キンブル(ハリソン・フォード)がある夜帰宅すると、妻のヘレン(セーラ・ウォード)が家の中で何者かに襲われて死に瀕していた。キンブルは犯人と思しき「片腕が義手の男」を撃退するも、妻は既に致命傷を負っており手遅れであった。キンブルは自分が取り逃がした義手の男について捜査するよう警察に懇願するが、警察は死の間際のヘレンの通報内容を誤解し、キンブル本人が妻殺しの濡れ衣を着せられ逮捕されてしまう。キンブルは裁判で無実を証明することができず、死刑判決を受けて刑務所へと移送されることになるが、その最中に他の囚人たちが逃亡を企てたことにより、護送車が列車と衝突し爆発炎上するという事故が発生する。事故を間一髪で生き延びた キンブルは混乱に乗じ、妻を殺害した真犯人を自らの手で見つけて汚名をすすぐため、事故現場から逃亡してシカゴへと向かう。一方、いち早く脱走した囚人がいることを突き止めた連邦保安官補サミュエル・ジェラード(トミー・リー・ジョーンズ)とその部下達はキンブルを追跡する。時には持ち前のヒューマニズムが仇となって窮地に陥りつつも、執拗なジェラードの追跡を振り切りながら、キンブルはシカゴに帰り着いて証拠を辿り、同僚であり親友でもあるチャールズ・ニコルズ(ジェローン・クラッベ)からの援助も受けながら、自分が目撃した「片腕が義手の男」の名前を突き止める―。
キンブルは混乱に乗じ、妻を殺害した真犯人を自らの手で見つけて汚名をすすぐため、事故現場から逃亡してシカゴへと向かう。一方、いち早く脱走した囚人がいることを突き止めた連邦保安官補サミュエル・ジェラード(トミー・リー・ジョーンズ)とその部下達はキンブルを追跡する。時には持ち前のヒューマニズムが仇となって窮地に陥りつつも、執拗なジェラードの追跡を振り切りながら、キンブルはシカゴに帰り着いて証拠を辿り、同僚であり親友でもあるチャールズ・ニコルズ(ジェローン・クラッベ)からの援助も受けながら、自分が目撃した「片腕が義手の男」の名前を突き止める―。
 オリジナルは1963年から1966年にかけて、デビッド・ジャンセン主演で放映され、アメリカ国内で平均視聴率45%という驚異的な数字を叩き出したTVドラマです。日本でも、1964(昭和39)年から1967(昭和42)年までTBS系列(関西地区は朝日放送)で放送されて人気を博し、最終話の放送時刻には銭湯が空になったと言われています(TVドラマ版は当初モノクロだったが、最後の方はカラーになった)。映画では、妻殺しの濡れ衣を着せられ死刑を宣告された医師リチャード・キンブルが、連邦保安官補サミュエル・ジェラードの追跡を逃れながら逃げまくるという枠組みは、TV版をそのまま
オリジナルは1963年から1966年にかけて、デビッド・ジャンセン主演で放映され、アメリカ国内で平均視聴率45%という驚異的な数字を叩き出したTVドラマです。日本でも、1964(昭和39)年から1967(昭和42)年までTBS系列(関西地区は朝日放送)で放送されて人気を博し、最終話の放送時刻には銭湯が空になったと言われています(TVドラマ版は当初モノクロだったが、最後の方はカラーになった)。映画では、妻殺しの濡れ衣を着せられ死刑を宣告された医師リチャード・キンブルが、連邦保安官補サミュエル・ジェラードの追跡を逃れながら逃げまくるという枠組みは、TV版をそのまま 踏襲しています。
踏襲しています。
 ハリソン・フォードは、
ハリソン・フォードは、 ハリソン・フォードより4つ年下のトミー・リー・ジョーンズ(当時46歳)は、この作品で'93年のアカデミー助演男優賞を受賞し、以降は「メン・イン・ブラック」('97年)(1998年・第24回「サターンSF映画賞」受賞作)、「逃亡者」のスピンオフ作「追跡者」('98年)などの
ハリソン・フォードより4つ年下のトミー・リー・ジョーンズ(当時46歳)は、この作品で'93年のアカデミー助演男優賞を受賞し、以降は「メン・イン・ブラック」('97年)(1998年・第24回「サターンSF映画賞」受賞作)、「逃亡者」のスピンオフ作「追跡者」('98年)などの

 「メン・イン・ブラック」のバリー・ソネンフェルド監督はトミー・リー・ジョーンズのことを、「彼は大真面目に演じていてもどこかコミカルだ」と評していますが、確かにそうかも。「逃亡者」におけるトミー・リー・ジョーンズの中にも「メン・イン・ブラック」に通じるコミカル要素があるともとれますが、「メン・イン・ブラック」はそれが前面に出ていて、続編の「メン・イン・ブラック2」('02年)では、MIBに所属していたころの記憶を失い本名のケビン・ブラウンに戻って田舎町の郵便局長として働いているというさらにコミカルな設定。この設定とやや被るところのある、'06年から続くサントリーフーズの缶コーヒーBOSSのCM「宇宙人ジョーンズの地球調査シリーズ」も、誰か慧眼の
「メン・イン・ブラック」のバリー・ソネンフェルド監督はトミー・リー・ジョーンズのことを、「彼は大真面目に演じていてもどこかコミカルだ」と評していますが、確かにそうかも。「逃亡者」におけるトミー・リー・ジョーンズの中にも「メン・イン・ブラック」に通じるコミカル要素があるともとれますが、「メン・イン・ブラック」はそれが前面に出ていて、続編の「メン・イン・ブラック2」('02年)では、MIBに所属していたころの記憶を失い本名のケビン・ブラウンに戻って田舎町の郵便局長として働いているというさらにコミカルな設定。この設定とやや被るところのある、'06年から続くサントリーフーズの缶コーヒーBOSSのCM「宇宙人ジョーンズの地球調査シリーズ」も、誰か慧眼の
 持ち主が彼のそうした特性に着眼して起用したのでしょう(因みにトミー・リー・ジョーンズは親日家であり、大の歌舞伎ファンであるとともに
持ち主が彼のそうした特性に着眼して起用したのでしょう(因みにトミー・リー・ジョーンズは親日家であり、大の歌舞伎ファンであるとともに 「逃亡者」に話を戻すと、トミー・リー・ジョーンズの"活躍"もあって、映画としては悪くはないのですが(初めて観た時の評価は星4つ)、改めて観直してみると、アクションのヤマ場が中盤のキンブルのダム底へのダイビングであり、あとはやや流れが緩慢な印象も受けます。電車内での「片腕が義手の男」との対決もある種お決まりのパターンであれば、最後に真犯人を追い詰めて銃撃戦になる展開もこれまたパターンであるように思えたため、星半個減の3つ半としました。元は連続ドラマであるところを一話完結にしているわけで、ストーリーをばたばたと収斂させざるを得ないのは致し方無いのかもしれませんが。
「逃亡者」に話を戻すと、トミー・リー・ジョーンズの"活躍"もあって、映画としては悪くはないのですが(初めて観た時の評価は星4つ)、改めて観直してみると、アクションのヤマ場が中盤のキンブルのダム底へのダイビングであり、あとはやや流れが緩慢な印象も受けます。電車内での「片腕が義手の男」との対決もある種お決まりのパターンであれば、最後に真犯人を追い詰めて銃撃戦になる展開もこれまたパターンであるように思えたため、星半個減の3つ半としました。元は連続ドラマであるところを一話完結にしているわけで、ストーリーをばたばたと収斂させざるを得ないのは致し方無いのかもしれませんが。 また「逃亡者」には、映画に出始めた頃のジュリアン・ムーア(左)が出演しています。前年にカーティス・ハンソン監督のサイコスリラー「ゆりかごを揺らす手」('92年)に出演して
また「逃亡者」には、映画に出始めた頃のジュリアン・ムーア(左)が出演しています。前年にカーティス・ハンソン監督のサイコスリラー「ゆりかごを揺らす手」('92年)に出演して いますが、その作品ではレベッカ・デモーネイが怖すぎて、彼女の印象は薄かったです。猥褻な診察を医師から受けたことで彼を告訴したアナベラ・シオラ演じる主人公が、医師が失墜し自殺したことから、レベッカ・デモーネイ演じるその妻から逆恨み的復讐を被るという話。ジュリアン・ムーアは、ナニー(ベビーシッター)として主人公の家に来ている女性(実は復讐を果たさんとする医師の妻)が危険人物であることを早くから見抜き「ゆりかごを揺らす手は世を支配する手」と主人公に忠告するその友人役。結局は犯人に残虐な殺され方をしてしまうという点から見ても脇役でした(ただし、レベッカ・デモーネイ演じる犯人も最後、自らの罠に嵌って同じ死に方をする)。
いますが、その作品ではレベッカ・デモーネイが怖すぎて、彼女の印象は薄かったです。猥褻な診察を医師から受けたことで彼を告訴したアナベラ・シオラ演じる主人公が、医師が失墜し自殺したことから、レベッカ・デモーネイ演じるその妻から逆恨み的復讐を被るという話。ジュリアン・ムーアは、ナニー(ベビーシッター)として主人公の家に来ている女性(実は復讐を果たさんとする医師の妻)が危険人物であることを早くから見抜き「ゆりかごを揺らす手は世を支配する手」と主人公に忠告するその友人役。結局は犯人に残虐な殺され方をしてしまうという点から見ても脇役でした(ただし、レベッカ・デモーネイ演じる犯人も最後、自らの罠に嵌って同じ死に方をする)。 いるのを不審に思って警察に通報する女医役で出ていますが、キネ旬をはじめ多くの映画データべースで、「元同僚のアン・イーストマン医師(ジュリアン・ムーア)の協力で、病院の中にある義手を持つ人のリストを調べあげ...」などとあり、ジェーン・リンチ(右)が演じたキャシー・ワーランド医師の役との混同が見られます(キンブルに協力するのはキャシー・ワーランド医師。ジュリアン・ムーア演じるイーストマン医師ではない)。これも、ジュリアン・ムーアが後に有名になったためでしょうか。最近では、2014年に「カンヌ国際映画祭女優賞」を「マップ・トゥ・ザ・スターズ」('14年/米・カナダ・独・仏)で受賞し
いるのを不審に思って警察に通報する女医役で出ていますが、キネ旬をはじめ多くの映画データべースで、「元同僚のアン・イーストマン医師(ジュリアン・ムーア)の協力で、病院の中にある義手を持つ人のリストを調べあげ...」などとあり、ジェーン・リンチ(右)が演じたキャシー・ワーランド医師の役との混同が見られます(キンブルに協力するのはキャシー・ワーランド医師。ジュリアン・ムーア演じるイーストマン医師ではない)。これも、ジュリアン・ムーアが後に有名になったためでしょうか。最近では、2014年に「カンヌ国際映画祭女優賞」を「マップ・トゥ・ザ・スターズ」('14年/米・カナダ・独・仏)で受賞し たため、ジュリエット・ビノシュに続いて世界三大国際映画祭すべての女優賞を制覇した2人目の女優となり、さらに同じく2014年公開
たため、ジュリエット・ビノシュに続いて世界三大国際映画祭すべての女優賞を制覇した2人目の女優となり、さらに同じく2014年公開 の「アリスのままで」('14年/米)でゴールデングローブ賞の主演女優賞(ドラマ部門)とアカデミー賞の主演女優賞を受賞しています。(その後も「ヴェネツィア国際映画祭 金獅子賞」を受賞したペドロ・アルモドバル監督の「
の「アリスのままで」('14年/米)でゴールデングローブ賞の主演女優賞(ドラマ部門)とアカデミー賞の主演女優賞を受賞しています。(その後も「ヴェネツィア国際映画祭 金獅子賞」を受賞したペドロ・アルモドバル監督の「 因みに、「片腕の男」の義手の資料を集めるためにキンブルが潜り込んだ病院は、本作の1年後に放送が開始されたTVドラマ「
因みに、「片腕の男」の義手の資料を集めるためにキンブルが潜り込んだ病院は、本作の1年後に放送が開始されたTVドラマ「 先に挙げた「ゆりかごを揺らす手」は、サイコスリラーとしてはよく出来ていたように思います。復讐を謀るため復讐相手の家にベビー・シッターとして入り込んだレベッカ・デモーネイが、復讐相手の赤ん坊に異常な愛情を注ぎ母性愛に目覚めていくというのが不気味で、このあたりはレベッカ・デモーネイの表情と演技に負うところが大でしょう。深夜、密かに赤ん坊に自分の乳をふくませて馴染ませ、母親の乳を嫌がるように仕向けるシーンは怖かったです(しかし、流産した女性でもお乳はでるのか?)。展開が敢えてそこを狙ったのかと思ってしまうほ定石どおりで、それまで積み重ねてきた怖さを一気に爆発させるとうなスリリングでユニークなクライマックスがあるわけでもないため、コアなミステリファンやスリラーファンには物足りないかもしれませんが、自分にはちょうどいい程度でした(笑)。
先に挙げた「ゆりかごを揺らす手」は、サイコスリラーとしてはよく出来ていたように思います。復讐を謀るため復讐相手の家にベビー・シッターとして入り込んだレベッカ・デモーネイが、復讐相手の赤ん坊に異常な愛情を注ぎ母性愛に目覚めていくというのが不気味で、このあたりはレベッカ・デモーネイの表情と演技に負うところが大でしょう。深夜、密かに赤ん坊に自分の乳をふくませて馴染ませ、母親の乳を嫌がるように仕向けるシーンは怖かったです(しかし、流産した女性でもお乳はでるのか?)。展開が敢えてそこを狙ったのかと思ってしまうほ定石どおりで、それまで積み重ねてきた怖さを一気に爆発させるとうなスリリングでユニークなクライマックスがあるわけでもないため、コアなミステリファンやスリラーファンには物足りないかもしれませんが、自分にはちょうどいい程度でした(笑)。 「逃亡者」●原題:THE FUGITIVE●制作年:1993年●制作国:アメリカ●監督:アンドリュー・デイヴィス●製作:アーノルド・コペルソン●脚本:デヴィッド・トゥーヒー/ジェブ・スチュアート●撮影:マイ
「逃亡者」●原題:THE FUGITIVE●制作年:1993年●制作国:アメリカ●監督:アンドリュー・デイヴィス●製作:アーノルド・コペルソン●脚本:デヴィッド・トゥーヒー/ジェブ・スチュアート●撮影:マイ ケル・チャップマン●音楽:ジェームズ・ニュートン・ハワード●原作:ロイ・ハギンズ●130分●出演:ハリソン・フォード/トミー・リー・ジョーンズ/ジェローン・クラッベ/セーラ・ウォード/ジュリアン・ムーア/アンドレアス・カツーラス/ジョー・パントリアーノ/ダニエル・ローバック/L・スコット・カードウェル/トム・ウッド/ジェーン・リンチ●日本公開:1993/09●配給:ワーナー・ブラザーズ(評価:★★★☆)
ケル・チャップマン●音楽:ジェームズ・ニュートン・ハワード●原作:ロイ・ハギンズ●130分●出演:ハリソン・フォード/トミー・リー・ジョーンズ/ジェローン・クラッベ/セーラ・ウォード/ジュリアン・ムーア/アンドレアス・カツーラス/ジョー・パントリアーノ/ダニエル・ローバック/L・スコット・カードウェル/トム・ウッド/ジェーン・リンチ●日本公開:1993/09●配給:ワーナー・ブラザーズ(評価:★★★☆)



 「メン・イン・ブラック」●原題:MEN IN BLACK●制作年:1997年●制作国:アメリカ●監督:バリー・ソネンフェルド●製作:ウォルター・F・パークス/ローリー・マクドナルド●脚本:エド・ソロモン●撮影:ドン・ピーターマン●音楽:ダニー・エルフマン(主題歌:「Men in Black」ウィル・スミス●原作:ローウェル・J・カニンガム●98分●出演:トミー・リー・ジョーンズ/ウィル・スミス/リンダ・フィオレンティーノ/ヴィンセント・ドノフリオ/リップ・トーン/トニー・シャルーブ/シオバン・ファロン/ジョン・グリース/カレル・ストルイケン/フレドリック・レーン●日本公開:1997/12●配給:ソニー・ピクチャーズ リリーシング(評価:★★★☆)
「メン・イン・ブラック」●原題:MEN IN BLACK●制作年:1997年●制作国:アメリカ●監督:バリー・ソネンフェルド●製作:ウォルター・F・パークス/ローリー・マクドナルド●脚本:エド・ソロモン●撮影:ドン・ピーターマン●音楽:ダニー・エルフマン(主題歌:「Men in Black」ウィル・スミス●原作:ローウェル・J・カニンガム●98分●出演:トミー・リー・ジョーンズ/ウィル・スミス/リンダ・フィオレンティーノ/ヴィンセント・ドノフリオ/リップ・トーン/トニー・シャルーブ/シオバン・ファロン/ジョン・グリース/カレル・ストルイケン/フレドリック・レーン●日本公開:1997/12●配給:ソニー・ピクチャーズ リリーシング(評価:★★★☆) 「メン・イン・ブラック2」●原題:MEN IN BLACK2●制作年:1997年●制作国:アメリカ●監督:バリー・ソネンフェルド●製作:ウォルター・F・パークス/ローリー・マクドナルド●脚本:ロバート・ゴードン/バリー・ファナロ●撮影:グレッグ・ガーディナー●音楽:ダニー・エルフマン(主題歌:「Black Suits Comin' (Nod Ya Head)」ウィル・スミス●原作:ローウェル・J・カニンガム●88分●出演:トミー・リー・ジョーンズ/ウィル・スミス/ララ・フリン・ボイル/リップ・トーン/ジョニー・ノックスビル/ロザリオ・ドーソン/トニー・シャルーブ/パトリック・ウォーバートン/ジャック・ケーラー/デヴィッド・クロス●日本公開:2002/07●配給:ソニー・ピクチャーズ リリーシング(評価:★★★☆)
「メン・イン・ブラック2」●原題:MEN IN BLACK2●制作年:1997年●制作国:アメリカ●監督:バリー・ソネンフェルド●製作:ウォルター・F・パークス/ローリー・マクドナルド●脚本:ロバート・ゴードン/バリー・ファナロ●撮影:グレッグ・ガーディナー●音楽:ダニー・エルフマン(主題歌:「Black Suits Comin' (Nod Ya Head)」ウィル・スミス●原作:ローウェル・J・カニンガム●88分●出演:トミー・リー・ジョーンズ/ウィル・スミス/ララ・フリン・ボイル/リップ・トーン/ジョニー・ノックスビル/ロザリオ・ドーソン/トニー・シャルーブ/パトリック・ウォーバートン/ジャック・ケーラー/デヴィッド・クロス●日本公開:2002/07●配給:ソニー・ピクチャーズ リリーシング(評価:★★★☆)
 「ゆりかごを揺らす手」●原題:THE HUND THAT ROCKS THE CRADLE●制作年:1992年●制作国:アメリカ●監督:カーティス・ハンソン●製作:デヴィッド・マッデン●脚本:アマンダ・シルヴァー●撮影:ロバート・エルスウィット●音楽:グレーム・レヴェル●110分●出演:アナベラ・シオラ/レベッカ・デモーネイ/マット・マッコイ/アーニー・ハドソン/ジュリアン・ムーア/マデリーン・ジーマ/ジョン・デ・ランシー●日本公開:1993/09●配給:ワーナー・ブラザーズ(評価:★★★☆)
「ゆりかごを揺らす手」●原題:THE HUND THAT ROCKS THE CRADLE●制作年:1992年●制作国:アメリカ●監督:カーティス・ハンソン●製作:デヴィッド・マッデン●脚本:アマンダ・シルヴァー●撮影:ロバート・エルスウィット●音楽:グレーム・レヴェル●110分●出演:アナベラ・シオラ/レベッカ・デモーネイ/マット・マッコイ/アーニー・ハドソン/ジュリアン・ムーア/マデリーン・ジーマ/ジョン・デ・ランシー●日本公開:1993/09●配給:ワーナー・ブラザーズ(評価:★★★☆)
 ●2020年テレビドラマ化「テレビ朝日開局60周年記念 2夜連続ドラマスペシャル・逃亡者」(テレビ朝日・2020年12月5日5・6日放送)
●2020年テレビドラマ化「テレビ朝日開局60周年記念 2夜連続ドラマスペシャル・逃亡者」(テレビ朝日・2020年12月5日5・6日放送)




 犯罪組織「スペクター」は、クラブ諸島の領主ノオ博士の秘密基地を破壊し、アメリカ月ロケットの軌道妨害を阻止した英国海外情報局の諜報員007ことジェームズ・ボンド(ショーン・コネリー)への復讐、それもソビエト情報局の美人女性情報員と暗号解読機「レクター」を餌にボンドを「辱めて殺す」ことで両国に泥を塗り外交関係を悪化させ、さらにその機に乗じて解読機を強奪するという、一石三鳥の計画を立案した。実はスペクターの女性幹部であるソビエト情報局のローザ・クレッ
犯罪組織「スペクター」は、クラブ諸島の領主ノオ博士の秘密基地を破壊し、アメリカ月ロケットの軌道妨害を阻止した英国海外情報局の諜報員007ことジェームズ・ボンド(ショーン・コネリー)への復讐、それもソビエト情報局の美人女性情報員と暗号解読機「レクター」を餌にボンドを「辱めて殺す」ことで両国に泥を塗り外交関係を悪化させ、さらにその機に乗じて解読機を強奪するという、一石三鳥の計画を立案した。実はスペクターの女性幹部であるソビエト情報局のローザ・クレッ ブ大佐(ロッテ・レーニャ)は、真相を知らない部下の情報員タチアナ・ロマノヴァ(ダニエラ・ビアンキ)を騙し、暗号解読機を持ってイギリスに亡命する様、また亡命時にはボンドが連行することが条件だ
ブ大佐(ロッテ・レーニャ)は、真相を知らない部下の情報員タチアナ・ロマノヴァ(ダニエラ・ビアンキ)を騙し、暗号解読機を持ってイギリスに亡命する様、また亡命時にはボンドが連行することが条件だ 1963年公開の007シリーズ第2作で、監督は第1作と同じくテレンス・ヤング(1915-1994)。1964年4月日本初公開時の邦題は「007/危機一発」で
1963年公開の007シリーズ第2作で、監督は第1作と同じくテレンス・ヤング(1915-1994)。1964年4月日本初公開時の邦題は「007/危機一発」で ボンドガールはダニエラ・ビアンキで、ロシアではなくイタリア出身の女優です。知的な雰囲気を醸す美形であり、彼女が演じる秘密情報員タチアナ・ロマノヴァは、偽上司クレッブ大佐(ロッテ・レーニャ)の計略で「祖国のために」ボンドを籠絡すべくスパイとして彼の下へ遣わされて、結局、ボンドのことを好きになってしまうわけで、このパターンは後のボンドガールにも多くみられるタイプであり、また彼女は、その頂点に立つと言っていいかもしれません。
ボンドガールはダニエラ・ビアンキで、ロシアではなくイタリア出身の女優です。知的な雰囲気を醸す美形であり、彼女が演じる秘密情報員タチアナ・ロマノヴァは、偽上司クレッブ大佐(ロッテ・レーニャ)の計略で「祖国のために」ボンドを籠絡すべくスパイとして彼の下へ遣わされて、結局、ボンドのことを好きになってしまうわけで、このパターンは後のボンドガールにも多くみられるタイプであり、また彼女は、その頂点に立つと言っていいかもしれません。 前作「
前作「 レギュラー・キャラクターは、第1作から出ていたボンドの上司にあたるM(バーナード・リー)やその秘書マネーペニー(ロイス・マクスウェル)に加えて、秘密兵器担当のQ(デスモンド・リュウェリン)が登場してコマが揃った感じです。例によって、ボンドが最初はやや珍奇で使うことはあるまいと見ていたようなアタッシュケースに仕込まれたその秘密兵器が、いざという時にボンドの窮地を救うことに...(武器以外に金貨が仕組まれていたのも計算づくだったのか)。
レギュラー・キャラクターは、第1作から出ていたボンドの上司にあたるM(バーナード・リー)やその秘書マネーペニー(ロイス・マクスウェル)に加えて、秘密兵器担当のQ(デスモンド・リュウェリン)が登場してコマが揃った感じです。例によって、ボンドが最初はやや珍奇で使うことはあるまいと見ていたようなアタッシュケースに仕込まれたその秘密兵器が、いざという時にボンドの窮地を救うことに...(武器以外に金貨が仕組まれていたのも計算づくだったのか)。 お話の舞台は殆どイスタンブールで、ボンドがタチアナの持ち出したソ連領事館の青写真を入手する場所が聖ソフィア寺院だったりと、異国情緒充分です。ボンド・カーはまだ出てきませんが、オリエント急行からトラックへ、トラックからモーターボートと乗り継いでヴェネツィアへ向かうという流れで、世界の景勝地を飛びまわる豪華観光映画的絵作りがここに出来上がったとも言えます。
お話の舞台は殆どイスタンブールで、ボンドがタチアナの持ち出したソ連領事館の青写真を入手する場所が聖ソフィア寺院だったりと、異国情緒充分です。ボンド・カーはまだ出てきませんが、オリエント急行からトラックへ、トラックからモーターボートと乗り継いでヴェネツィアへ向かうという流れで、世界の景勝地を飛びまわる豪華観光映画的絵作りがここに出来上がったとも言えます。 オリエント急行内でのグラント(ロバート・ショウ)との対決が1つヤマ場なのですが、それまでにもボンドは、ロマの女性同士の男を奪い合っての決闘に巻き込まれたり、ラストでも、全て終わって一安心と思ったら、ホテルのメイドに化けていたクレッブに襲われたりと盛り沢山で、ノン・ストップ
オリエント急行内でのグラント(ロバート・ショウ)との対決が1つヤマ場なのですが、それまでにもボンドは、ロマの女性同士の男を奪い合っての決闘に巻き込まれたり、ラストでも、全て終わって一安心と思ったら、ホテルのメイドに化けていたクレッブに襲われたりと盛り沢山で、ノン・ストップ ・ムービーと言っていいかも。但し、格闘アクションに関しては、ボンドとグラントの殴り合いさえも今観ると何となくやや地味で(列車内で狭い)、最後のクレッブなどは、ボンドに立ち向かうにしても靴先に忍ばせた毒針が武器とホント地味、しかも教え子のタチアナに寝返られてやや気の毒ささえも漂いました(でも、こうした手作り感にに加え、スパイの哀切感もあって悪くないか)。
・ムービーと言っていいかも。但し、格闘アクションに関しては、ボンドとグラントの殴り合いさえも今観ると何となくやや地味で(列車内で狭い)、最後のクレッブなどは、ボンドに立ち向かうにしても靴先に忍ばせた毒針が武器とホント地味、しかも教え子のタチアナに寝返られてやや気の毒ささえも漂いました(でも、こうした手作り感にに加え、スパイの哀切感もあって悪くないか)。 「ロシアより愛をこめて」の邦題は、 "From Russia with Love"の原題の意に、「ロシアを愛する以上にあなたを愛する」というタチアナの気持ちを懸けたとの説もありますが、やや無理があるのでは。この作品では、これから任務に就くボンドからマネーペニーへの書き置きとして、この"From Russia with Love"というフレーズが登場します。ボンドに恋愛感情を持つマネーペニーが色々な方法でボンドにアピールするもののボンドにその気はなく、いつも"リップサービス"のみで返すのがシリーズのお決まりとなりますが、その"リップサービス"がそのままタイトルになっているというのはちょっと面白い気がします。
「ロシアより愛をこめて」の邦題は、 "From Russia with Love"の原題の意に、「ロシアを愛する以上にあなたを愛する」というタチアナの気持ちを懸けたとの説もありますが、やや無理があるのでは。この作品では、これから任務に就くボンドからマネーペニーへの書き置きとして、この"From Russia with Love"というフレーズが登場します。ボンドに恋愛感情を持つマネーペニーが色々な方法でボンドにアピールするもののボンドにその気はなく、いつも"リップサービス"のみで返すのがシリーズのお決まりとなりますが、その"リップサービス"がそのままタイトルになっているというのはちょっと面白い気がします。 「007 ロシアより愛をこめて(007/危機一発)」●原題:007 FROM RUSSIA WITH LOVE●制作年:1963年●制作国:イギリス●監督:テレンス・ヤング●製作: ハリー・サルツマン/アルバート・R・ブロッコリ●脚本:リチャ
「007 ロシアより愛をこめて(007/危機一発)」●原題:007 FROM RUSSIA WITH LOVE●制作年:1963年●制作国:イギリス●監督:テレンス・ヤング●製作: ハリー・サルツマン/アルバート・R・ブロッコリ●脚本:リチャ ード・メイボーム●撮影:テッド・ムーア●音楽:ジョン・バリー●原作:イアン・フレミング●110分●出演:ショーン・コネリー/ダニエラ・ビアンキ/ペドロ・アルメンダリス/ロッテ・レーニャ/ロバート・ショウ/バーナード・リー/ロイス・マクスウェル/デスモンド・リュウェ
ード・メイボーム●撮影:テッド・ムーア●音楽:ジョン・バリー●原作:イアン・フレミング●110分●出演:ショーン・コネリー/ダニエラ・ビアンキ/ペドロ・アルメンダリス/ロッテ・レーニャ/ロバート・ショウ/バーナード・リー/ロイス・マクスウェル/デスモンド・リュウェ リン/マルティーヌ・ベズウィック/ユーニス・ゲイソン/ヴラデク・シェイバル/ヴラディク・シェイバル●日本公開:1964/04●配給:ユナイテッド・アーティスツ(評価:★★★★)
リン/マルティーヌ・ベズウィック/ユーニス・ゲイソン/ヴラデク・シェイバル/ヴラディク・シェイバル●日本公開:1964/04●配給:ユナイテッド・アーティスツ(評価:★★★★)




![007 ドクター・ノオ [DVD].jpg](http://hurec.bz/book-movie/007%20%E3%83%89%E3%82%AF%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%8E%E3%82%AA%20%5BDVD%5D.jpg)

 アメリカの要請で、月面ロケット発射を妨害する不正電波を防ぐ工作をしていたジャマイカ駐在の英国諜報部員ジョン・ストラングウェイズ(ティム・モクソン)とその新人助手メアリー(ドロレス・キーター)が消息を絶つ。英国情報部「MI6」に所属する諜報員「007」こと、ジェームズ・ボンド(ショーン・コネリー)はM(バーナード・リー)から、その捜査を命じられる。CIA
アメリカの要請で、月面ロケット発射を妨害する不正電波を防ぐ工作をしていたジャマイカ駐在の英国諜報部員ジョン・ストラングウェイズ(ティム・モクソン)とその新人助手メアリー(ドロレス・キーター)が消息を絶つ。英国情報部「MI6」に所属する諜報員「007」こと、ジェームズ・ボンド(ショーン・コネリー)はM(バーナード・リー)から、その捜査を命じられる。CIA そう思って観ると、第1作にしてタイトルデザイン、テーマ音楽、ヒーロー像などが確立されていると
そう思って観ると、第1作にしてタイトルデザイン、テーマ音楽、ヒーロー像などが確立されていると いうのは、今思えばやはりスゴイことかも。ボンドの上司にあたる〈M〉やその秘書〈マネーペニー〉などシリーズのレギュラー・キャラクターが既に登場するしており、はっきりと名乗る形で出ていないのは、秘密兵器担当の〈Q〉ぐらいでしょうか。
いうのは、今思えばやはりスゴイことかも。ボンドの上司にあたる〈M〉やその秘書〈マネーペニー〉などシリーズのレギュラー・キャラクターが既に登場するしており、はっきりと名乗る形で出ていないのは、秘密兵器担当の〈Q〉ぐらいでしょうか。 ボンドガールに関しては、ウルスラ・アンドレス(以前はアーシュラ・アンドレスと表記されていた)演ずるハニー・ライダーが白いビキニ姿で海から上がってくるシーンは、シリーズを通しても有名なシーンの一つとなりましたが(ウルスラ・アンドレスは
ボンドガールに関しては、ウルスラ・アンドレス(以前はアーシュラ・アンドレスと表記されていた)演ずるハニー・ライダーが白いビキニ姿で海から上がってくるシーンは、シリーズを通しても有名なシーンの一つとなりましたが(ウルスラ・アンドレスは スイス出身で両親はドイツ人。英語がおぼつかなく、彼女の声のみ吹き替え)、考えてみれば、「近づく者は一人として無事に帰ったことのない」と言われるクラブ島で、ビキニの美女が呑気に貝殻採りをしているというのがあまりにいい加減?(この緩さと言うか、いい加減さがいいともとれるが)。それを偶々見つけたボンドはニンマリしてしまいますが、これは、プレイボーイとしてのボンド像を早く定着させようという狙いか。
スイス出身で両親はドイツ人。英語がおぼつかなく、彼女の声のみ吹き替え)、考えてみれば、「近づく者は一人として無事に帰ったことのない」と言われるクラブ島で、ビキニの美女が呑気に貝殻採りをしているというのがあまりにいい加減?(この緩さと言うか、いい加減さがいいともとれるが)。それを偶々見つけたボンドはニンマリしてしまいますが、これは、プレイボーイとしてのボンド像を早く定着させようという狙いか。
 以降のシリーズ作のボンドガールは、ボンドの敵役のガールフレンドや敵国の女性スパイなど、ボンドと対立する立場からプレイボーイのボンドの手練にかかって寝返るパターンが多いため、むしろ、作戦上ボンドを誘惑しようとして、ボンドの住まいに勝手に押しかけてきて、ボンドが帰ってくる間ワイシャツ1枚でゴルフのパターの練習をしていたシルビア・トレンチ(ユーニス・ゲイソン)の方が正統派ボンドガールと言えるかも(最後はボンドに追い返されてしまうけれど、シリーズ第2作「
以降のシリーズ作のボンドガールは、ボンドの敵役のガールフレンドや敵国の女性スパイなど、ボンドと対立する立場からプレイボーイのボンドの手練にかかって寝返るパターンが多いため、むしろ、作戦上ボンドを誘惑しようとして、ボンドの住まいに勝手に押しかけてきて、ボンドが帰ってくる間ワイシャツ1枚でゴルフのパターの練習をしていたシルビア・トレンチ(ユーニス・ゲイソン)の方が正統派ボンドガールと言えるかも(最後はボンドに追い返されてしまうけれど、シリーズ第2作「 但し、ボンドガールには、MI6から派遣されたボンドの助手や同一の敵を追う別の諜報機関の女性エージェントがボンドに手を貸したりボンドを出し抜いたりしながら最後はボンドとよろしくやるというパターンもあり、若林映子などはこれに該当します(日本の公安のエージェント役)。でも、敵の要塞がある島で、生活のためとは
但し、ボンドガールには、MI6から派遣されたボンドの助手や同一の敵を追う別の諜報機関の女性エージェントがボンドに手を貸したりボンドを出し抜いたりしながら最後はボンドとよろしくやるというパターンもあり、若林映子などはこれに該当します(日本の公安のエージェント役)。でも、敵の要塞がある島で、生活のためとは 言え法螺貝など探しているノー天気なボンドガールというのはさすがにそうしたパターンを後のシリーズ作に見出すのは難しく、そうした意味でもユニークと言えばユニークだったかもしれません(結果的には彼女も、泥川の中ボンドらを導いたり、ボンドと共にスペクターに捉えられたりと、結構頑張ったり散々な目に逢ったりするのだが、体力勝負には自信ありそうなボンドガールだった)。
言え法螺貝など探しているノー天気なボンドガールというのはさすがにそうしたパターンを後のシリーズ作に見出すのは難しく、そうした意味でもユニークと言えばユニークだったかもしれません(結果的には彼女も、泥川の中ボンドらを導いたり、ボンドと共にスペクターに捉えられたりと、結構頑張ったり散々な目に逢ったりするのだが、体力勝負には自信ありそうなボンドガールだった)。

 「007 ドクター・ノオ(007は殺しの番号)」●原題:007 DR. NO●制作年:1962年●制作国:イギリス●監督:テレンス・ヤング●製作: ハリー・サルツマン/アルバート・R・ブロッコリ●脚本:リチャード・メイボーム/ジョアンナ・ハーウッド/リ
「007 ドクター・ノオ(007は殺しの番号)」●原題:007 DR. NO●制作年:1962年●制作国:イギリス●監督:テレンス・ヤング●製作: ハリー・サルツマン/アルバート・R・ブロッコリ●脚本:リチャード・メイボーム/ジョアンナ・ハーウッド/リ バークレイ・マーサー●撮影:テッド・ムーア●音楽:モンティ・ノーマン●原作:イアン・フレミング●105分●出演:ショーン・コネー/ジョセフ・ワイズマン/ウルスラ・アンドレス/バーナード・リー/ピーター・バートン/ジョン・キッツミラー/ゼナ・マーシャル/ユーニス・ゲイソン/
バークレイ・マーサー●撮影:テッド・ムーア●音楽:モンティ・ノーマン●原作:イアン・フレミング●105分●出演:ショーン・コネー/ジョセフ・ワイズマン/ウルスラ・アンドレス/バーナード・リー/ピーター・バートン/ジョン・キッツミラー/ゼナ・マーシャル/ユーニス・ゲイソン/
 ロイス・マクスウェル/ジャック・ロード/アンソニー・ドーソン/ティム・モクソン/ドロレス・キーター●日本公開:1963/06●配給:ユナイテッド・アーティスツ(評価:★★★☆)
ロイス・マクスウェル/ジャック・ロード/アンソニー・ドーソン/ティム・モクソン/ドロレス・キーター●日本公開:1963/06●配給:ユナイテッド・アーティスツ(評価:★★★☆)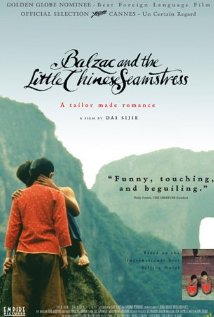



 1971年、文革の嵐が吹き荒れる中国。青年マー(馬剣鈴)(劉燁〈リウ・イエ〉)とルオ(羅明)(陳坤〈チェン・クン〉)は医者を親に持つことから、反革命分子の子として再教育のために奥深い山村へ送り込まれた。彼らはそこで過酷な肉体労働を強いられる。ある日二人は、美しい少女、お針子(周迅〈ジョウ・シュン〉)に出会う。ルオはお針子に一目惚れした。彼らは、同じ再教育で来ている若者が禁書である西洋の本を大量に隠し持っていることを知り、それ
1971年、文革の嵐が吹き荒れる中国。青年マー(馬剣鈴)(劉燁〈リウ・イエ〉)とルオ(羅明)(陳坤〈チェン・クン〉)は医者を親に持つことから、反革命分子の子として再教育のために奥深い山村へ送り込まれた。彼らはそこで過酷な肉体労働を強いられる。ある日二人は、美しい少女、お針子(周迅〈ジョウ・シュン〉)に出会う。ルオはお針子に一目惚れした。彼らは、同じ再教育で来ている若者が禁書である西洋の本を大量に隠し持っていることを知り、それ
 を盗み出す。そして、文盲のお針子に毎夜西洋の文学を読み聞かせてあげるのだった。許されない秘密を共有することで結びつきを強める三人。そして、お針子は西洋文学が語る自由に次第に目覚めていく―。
を盗み出す。そして、文盲のお針子に毎夜西洋の文学を読み聞かせてあげるのだった。許されない秘密を共有することで結びつきを強める三人。そして、お針子は西洋文学が語る自由に次第に目覚めていく―。 「下放」に出された経験がある監督は、「第五世代監督」の旗手と言われる「紅いコーリャン」の張芸謀(チャン・イーモウ)、「さらば、わが愛/覇王別姫」の陳凱歌 (チェン・カイコー)を筆頭に数多くいて、「下放」そのものを扱った映画も、陳監督の「子供たちの王様」('87年/中国)や、「紅いコーリャン」に主演した姜文(チアン・ウェン)が監督した「太陽の少年」('94年/中国・香港)、陳冲(ジョアン・チェン)監督の「シュウシュウの季節」('98年/米)、池谷薫監督の「延安の娘」('02年/日)などがあります。
「下放」に出された経験がある監督は、「第五世代監督」の旗手と言われる「紅いコーリャン」の張芸謀(チャン・イーモウ)、「さらば、わが愛/覇王別姫」の陳凱歌 (チェン・カイコー)を筆頭に数多くいて、「下放」そのものを扱った映画も、陳監督の「子供たちの王様」('87年/中国)や、「紅いコーリャン」に主演した姜文(チアン・ウェン)が監督した「太陽の少年」('94年/中国・香港)、陳冲(ジョアン・チェン)監督の「シュウシュウの季節」('98年/米)、池谷薫監督の「延安の娘」('02年/日)などがあります。
 そのように、実質フランス映画であるということもあってか、観ていてそれっぽい筋書きや演出、或いは撮り方をしていると感じれる部分がありました。主人公の二人、ヴァイオリン青年マー(より作者の分身に近いと言える)と歯科医を目指すルオが違った形でお針子に恋をするため、二人の青年とお針子の恋愛を描いた青春映画としての色合いも濃いように思います。革命思想に洗脳されたかのように見えた村長も実は人柄はそう悪くなく、後にマーが再訪した時は歓待してくれたという―いくら恋愛絡みにしても、みんな懐かしくていい思い出となり、苦楽ともにノスタルジーによって美化されてしまうというのはどうなのかという印象は若干あります。しかし、戴監督自身は、「下放」というのは映画の背景に過ぎず、描きたかったのは「文学の力が人を変えていく」様だったというようなことを、どこかのインタビューで答えていたように思います。
そのように、実質フランス映画であるということもあってか、観ていてそれっぽい筋書きや演出、或いは撮り方をしていると感じれる部分がありました。主人公の二人、ヴァイオリン青年マー(より作者の分身に近いと言える)と歯科医を目指すルオが違った形でお針子に恋をするため、二人の青年とお針子の恋愛を描いた青春映画としての色合いも濃いように思います。革命思想に洗脳されたかのように見えた村長も実は人柄はそう悪くなく、後にマーが再訪した時は歓待してくれたという―いくら恋愛絡みにしても、みんな懐かしくていい思い出となり、苦楽ともにノスタルジーによって美化されてしまうというのはどうなのかという印象は若干あります。しかし、戴監督自身は、「下放」というのは映画の背景に過ぎず、描きたかったのは「文学の力が人を変えていく」様だったというようなことを、どこかのインタビューで答えていたように思います。 個人的に印象に残った場面があり、それは、お針子がルオの子どもを身籠ってしまって違法ながらも中絶するしかなくなり、マーが町で何とか産科医に会い、自分の父親の名前を告げると、マーの父親の名も政治的不遇をも知っていたにも関わらずその産科医に身構えられてしまい(マーが「妹」に生理が無いので相談に乗って欲しいと切り出し「お前の父親に娘などいない」と嘘がバレれたということもあるが)、マーが最後に一縷の望みを賭けて、この窮状を救ってくれるならば「バルザックの本を一冊差し上げます」と言ってその本を見せると、産科医がその中の一文を読んで、「この翻訳は傅雷だな、文体で分かる。可哀そうに、お前のお父さんと同じ人民の敵だ」と言いい、こらえきれなくなって泣きじゃくるマーを慰め、お針子や青年たちのために危険を冒してひと肌脱ぐ決意をするという箇所で、ああ、これは当時弾圧を受けながらも内面の矜恃を保った多くの「知識人」に対するオマージュなのだなあと思いました。
個人的に印象に残った場面があり、それは、お針子がルオの子どもを身籠ってしまって違法ながらも中絶するしかなくなり、マーが町で何とか産科医に会い、自分の父親の名前を告げると、マーの父親の名も政治的不遇をも知っていたにも関わらずその産科医に身構えられてしまい(マーが「妹」に生理が無いので相談に乗って欲しいと切り出し「お前の父親に娘などいない」と嘘がバレれたということもあるが)、マーが最後に一縷の望みを賭けて、この窮状を救ってくれるならば「バルザックの本を一冊差し上げます」と言ってその本を見せると、産科医がその中の一文を読んで、「この翻訳は傅雷だな、文体で分かる。可哀そうに、お前のお父さんと同じ人民の敵だ」と言いい、こらえきれなくなって泣きじゃくるマーを慰め、お針子や青年たちのために危険を冒してひと肌脱ぐ決意をするという箇所で、ああ、これは当時弾圧を受けながらも内面の矜恃を保った多くの「知識人」に対するオマージュなのだなあと思いました。 そうした「知識人目線」みたいなのは確かにあり、その辺りもこの映画に対する批判的な見方の要因としてあるようです。お針子の描き方は、川端康成の原作で何度も映画化された「伊豆の踊子」などにも通じるところがあるように思いました(あの作品には東大生から見た"上から目線"との批判もある)。あとはやはり「外国人目線」でしょうか(正確には"外国からの目線"か)。中国語タイトル「巴爾扎克与小裁縫」(バルザックと小さなお針子)に対し、フランス語タイトルは「Balzac Et La Petite Tailleuse Chinoise」(原著共)。原著の仏語タイトルに倣って日本語タイトルに「中国の」とわざわざ入れたことで一層「外国人目線」が意識させられるようになってしまいましたが、ある意味、この作品の微妙な本質というか性格を表しているようにも思います。
そうした「知識人目線」みたいなのは確かにあり、その辺りもこの映画に対する批判的な見方の要因としてあるようです。お針子の描き方は、川端康成の原作で何度も映画化された「伊豆の踊子」などにも通じるところがあるように思いました(あの作品には東大生から見た"上から目線"との批判もある)。あとはやはり「外国人目線」でしょうか(正確には"外国からの目線"か)。中国語タイトル「巴爾扎克与小裁縫」(バルザックと小さなお針子)に対し、フランス語タイトルは「Balzac Et La Petite Tailleuse Chinoise」(原著共)。原著の仏語タイトルに倣って日本語タイトルに「中国の」とわざわざ入れたことで一層「外国人目線」が意識させられるようになってしまいましたが、ある意味、この作品の微妙な本質というか性格を表しているようにも思います。 中国で中国の俳優を使って中国の地で撮影出来たことはやはり大きかったように思います。ロケ地の張家界(湖南省)は幻想的に美しく今や中国の一大観光名所ですが、当時は60人の映画クルーが何日もかけてやっと辿り着き、そこには何も無かったと言います。撮影のために建てた主人公の青年らが寝起きした住居などは、後に休憩所として使えるように取り壊さないで残してきたとのことです。
中国で中国の俳優を使って中国の地で撮影出来たことはやはり大きかったように思います。ロケ地の張家界(湖南省)は幻想的に美しく今や中国の一大観光名所ですが、当時は60人の映画クルーが何日もかけてやっと辿り着き、そこには何も無かったと言います。撮影のために建てた主人公の青年らが寝起きした住居などは、後に休憩所として使えるように取り壊さないで残してきたとのことです。

 当局との中国でのロケ交渉と併せ、中国との共同製作作品とし中国の俳優を使うことを条件として作られた映画であるのに(何れも中国国内で上映できるようにとの仏側からの提案だった)、結局、中国では上映もされていなければ原作も刊行されていない状態が今も続いていますが、周迅(ジョウ・シュン)をはじめ主演俳優のその後の人気もあって、海賊版のビデオやインターネット動画などで結構多くの人が観ているのではないかという気もします。
当局との中国でのロケ交渉と併せ、中国との共同製作作品とし中国の俳優を使うことを条件として作られた映画であるのに(何れも中国国内で上映できるようにとの仏側からの提案だった)、結局、中国では上映もされていなければ原作も刊行されていない状態が今も続いていますが、周迅(ジョウ・シュン)をはじめ主演俳優のその後の人気もあって、海賊版のビデオやインターネット動画などで結構多くの人が観ているのではないかという気もします。 「小さな中国のお針子」●原題:巴爾扎克与小裁縫/BALZAC ET LA PETITE TAILLEUSE CHINOISE/BALZAC AND THE LITTLE CHINESE SEAMSTRESS●制作年:2000年●制作国:フランス・中国●監督:戴思杰(ダイ・シージエ)●脚本:戴思杰(ダイ・シージエ)/ナディーヌ・ペロン●撮影:ワン・プージャン●音楽:ジュン=マリー・ドリュージュ●原作:戴思杰(ダイ・シージエ)●時間:110分●出演:周迅(ジョウ・シュン)/陳坤(チェン・クン)/劉燁(リウ・イエ)/王双宝(ワン・シュアンパオ)/叢志軍(ツォン・チーチュン)/王宏偉(ワン・ホンウェイ))●日本公開:2003/01●配給:アルバトロス・フィルム(評価:★★★☆)
「小さな中国のお針子」●原題:巴爾扎克与小裁縫/BALZAC ET LA PETITE TAILLEUSE CHINOISE/BALZAC AND THE LITTLE CHINESE SEAMSTRESS●制作年:2000年●制作国:フランス・中国●監督:戴思杰(ダイ・シージエ)●脚本:戴思杰(ダイ・シージエ)/ナディーヌ・ペロン●撮影:ワン・プージャン●音楽:ジュン=マリー・ドリュージュ●原作:戴思杰(ダイ・シージエ)●時間:110分●出演:周迅(ジョウ・シュン)/陳坤(チェン・クン)/劉燁(リウ・イエ)/王双宝(ワン・シュアンパオ)/叢志軍(ツォン・チーチュン)/王宏偉(ワン・ホンウェイ))●日本公開:2003/01●配給:アルバトロス・フィルム(評価:★★★☆)



 1930年代の中国・北京の街角。春桃(チュンタオ)(劉暁慶〈リウ・シャオチン〉)は毎日、大きな籠を背負って屑拾いに精を出していた。家では、売り物の絵を整理しながら、劉向高(リウ・シアンカオ)(姜文〈チアン・ウェン〉)が彼女の帰りを待っていた。春桃は、抗日戦下、結婚式当日に夫を匪賊に奪われ、夫と離れ離れになって以来、北京の街角で屑拾いで生計を立てる身だったのだ。春桃と向高は愛し合っていたが、彼女は向高が妻と呼ぶことは許さなかった。3年後のある日、籠を
1930年代の中国・北京の街角。春桃(チュンタオ)(劉暁慶〈リウ・シャオチン〉)は毎日、大きな籠を背負って屑拾いに精を出していた。家では、売り物の絵を整理しながら、劉向高(リウ・シアンカオ)(姜文〈チアン・ウェン〉)が彼女の帰りを待っていた。春桃は、抗日戦下、結婚式当日に夫を匪賊に奪われ、夫と離れ離れになって以来、北京の街角で屑拾いで生計を立てる身だったのだ。春桃と向高は愛し合っていたが、彼女は向高が妻と呼ぶことは許さなかった。3年後のある日、籠を
 昔の北京の下層の人々の暮らしを描くことにこだわった凌子風(リン・ツーフォン、1917-1999)監督の1988年作品で(英:A WOMAN FOR TWO)、主演の劉暁慶(リウ・シャオチン)と姜文(チアン・ウェン)は、謝晋(シエ・チン)監督の「芙蓉鎮」('86年)でも名コンビぶりを見せたほか、姜文は張
昔の北京の下層の人々の暮らしを描くことにこだわった凌子風(リン・ツーフォン、1917-1999)監督の1988年作品で(英:A WOMAN FOR TWO)、主演の劉暁慶(リウ・シャオチン)と姜文(チアン・ウェン)は、謝晋(シエ・チン)監督の「芙蓉鎮」('86年)でも名コンビぶりを見せたほか、姜文は張 藝謀(チャン・イーモウ)監督の「
藝謀(チャン・イーモウ)監督の「
 このように、後にそれぞれかなり違った道を辿る女優と男優ですが、この作品での演技の息はぴったり合っていて、家事や仕事をしながらの淀みない流れるような掛け合いは見事です。とりわけ、2人の男たちを引っ張っていく春桃を演じる劉暁慶(リウ・シャオチン)の演技は上手いです。この作品での彼女は、後に"整形美人"とまで噂されるようになった美人スター・イメージでは無く、ちょうど鞏俐(コン・リー)が「紅いコーリャン」でデビューしたばかりの時のような素朴な逞しさと内面から来る輝きがあります。
このように、後にそれぞれかなり違った道を辿る女優と男優ですが、この作品での演技の息はぴったり合っていて、家事や仕事をしながらの淀みない流れるような掛け合いは見事です。とりわけ、2人の男たちを引っ張っていく春桃を演じる劉暁慶(リウ・シャオチン)の演技は上手いです。この作品での彼女は、後に"整形美人"とまで噂されるようになった美人スター・イメージでは無く、ちょうど鞏俐(コン・リー)が「紅いコーリャン」でデビューしたばかりの時のような素朴な逞しさと内面から来る輝きがあります。 ストーリーの方は、同じ家での女1人男2人の生活が始まるわけですが、何しろ1930年代の中国の話なので、周囲の覗き趣味的な関心や嘲りは尋常ではないものがあり、これに対し春桃ではなく男2人の方が参ってしまいます(2人ともいい人なんだけどねえ)。男2人も真剣に先のことを考えるのですが、相手を思い遣りながら且つメンツにもこだわってしまうため(相手のメンツにまで思い遣ってしまう)、結果、自己犠牲の精神と言えば美しいのかもしれませんが、実質的にはどんどんネガティブ思考になっていきます。
ストーリーの方は、同じ家での女1人男2人の生活が始まるわけですが、何しろ1930年代の中国の話なので、周囲の覗き趣味的な関心や嘲りは尋常ではないものがあり、これに対し春桃ではなく男2人の方が参ってしまいます(2人ともいい人なんだけどねえ)。男2人も真剣に先のことを考えるのですが、相手を思い遣りながら且つメンツにもこだわってしまうため(相手のメンツにまで思い遣ってしまう)、結果、自己犠牲の精神と言えば美しいのかもしれませんが、実質的にはどんどんネガティブ思考になっていきます。
 この辺りの、世間の目を気にせず、目の前のことだけを考えて生きている、それでいて、世間を恨むわけでもなく、困っている隣人を助けたりもする春桃の生き方と、既成の観念に囚われ、陋習的規範から抜け出せない男たちの対比が、この作品の見処ではないでしょうか。ラストに至るプロセスは重いですが、随所にユーモアも散りばめられていて、娯楽性も備えた作品であると言えます。そうしたこの作品の魅力の多くは、劉暁慶、姜文らの演技力と凌子風の演出力に支えられているのでしょう。
この辺りの、世間の目を気にせず、目の前のことだけを考えて生きている、それでいて、世間を恨むわけでもなく、困っている隣人を助けたりもする春桃の生き方と、既成の観念に囚われ、陋習的規範から抜け出せない男たちの対比が、この作品の見処ではないでしょうか。ラストに至るプロセスは重いですが、随所にユーモアも散りばめられていて、娯楽性も備えた作品であると言えます。そうしたこの作品の魅力の多くは、劉暁慶、姜文らの演技力と凌子風の演出力に支えられているのでしょう。 「春桃(チュンタオ)」●原題:春桃/A WOMAN FOR TWO●制作年:1988年●制作国:中国・香港●監督:凌子風(リン・ツーフォン)●脚本:韓蘭芳(シュイ・ティーシャン)●撮影:梁子勇(リャン・ツーヨン)●音楽:瞿希賢(チュイ・シーシエン)●原作:許地山●時間:94分●出演:劉暁慶(リウ・シャオチン)/姜文(チアン・ウェン)/曹前明(ツァオ・チェンミン)/馮漢元(フォン・ハンユアン)●日本公開:1994/12●配給:TJC東光徳間(評価:★★★★)
「春桃(チュンタオ)」●原題:春桃/A WOMAN FOR TWO●制作年:1988年●制作国:中国・香港●監督:凌子風(リン・ツーフォン)●脚本:韓蘭芳(シュイ・ティーシャン)●撮影:梁子勇(リャン・ツーヨン)●音楽:瞿希賢(チュイ・シーシエン)●原作:許地山●時間:94分●出演:劉暁慶(リウ・シャオチン)/姜文(チアン・ウェン)/曹前明(ツァオ・チェンミン)/馮漢元(フォン・ハンユアン)●日本公開:1994/12●配給:TJC東光徳間(評価:★★★★)![花様年華 [DVD].jpg](http://hurec.bz/book-movie/%E8%8A%B1%E6%A7%98%E5%B9%B4%E8%8F%AF%20%5BDVD%5D.jpg)


 1962年の香港。新聞社の編集者であるチャウ(トニー・レオン〈梁朝偉〉)が夫妻でアパートに引っ越してきた日、隣の部屋にもチャン夫人(マギー・チャン〈張曼玉〉)が夫と引っ越してくる。チャン夫人は商社で社長秘書として働いている。チャウの妻とチャン夫人の夫は仕事のせいであまり家におらず、二人はそれぞれの部屋に一人でいることが多かったが、大家のスーエン夫人(レベッカ・パン)の仲立ちもあり二人は親しくなる。ある日、一緒に昼食を取った際、それぞれの配偶者の日本土産の話などから、お互いの配偶者同士が浮気しているらしいと察する。隣同士の部屋に住む孤独な男と女―。チャウは夫人により接近するため、本の好きな彼女に自らの小説執筆の手伝いを依頼する。夫人がスリッパのままチャンの部屋にやって来たある日、偶然にアパートの住民ら
1962年の香港。新聞社の編集者であるチャウ(トニー・レオン〈梁朝偉〉)が夫妻でアパートに引っ越してきた日、隣の部屋にもチャン夫人(マギー・チャン〈張曼玉〉)が夫と引っ越してくる。チャン夫人は商社で社長秘書として働いている。チャウの妻とチャン夫人の夫は仕事のせいであまり家におらず、二人はそれぞれの部屋に一人でいることが多かったが、大家のスーエン夫人(レベッカ・パン)の仲立ちもあり二人は親しくなる。ある日、一緒に昼食を取った際、それぞれの配偶者の日本土産の話などから、お互いの配偶者同士が浮気しているらしいと察する。隣同士の部屋に住む孤独な男と女―。チャウは夫人により接近するため、本の好きな彼女に自らの小説執筆の手伝いを依頼する。夫人がスリッパのままチャンの部屋にやって来たある日、偶然にアパートの住民ら が徹夜マージャンをすることになり、自分の部屋に戻るに戻れなくなった夫人は、一夜をチャンの部屋で過ごすも機会を窺い、自分のスリッパを置き足に合わないチャウ夫人のヒール靴を履いて、さも外出先から自宅に帰ってきたかのようにチャンの部屋を出て行く。更に二人は、チャウが小説を書くために借りたホテルの部屋で何度か逢引するが、チャウが夫人が夫を問い詰めることを想定した練習台になったりするものの、二人は自分たちの配偶者のように簡単に不倫関係を結ぶことは出来ないでいる。チャウは、シンガポールでの仕事に誘われて現地へ行くことにするが、その際に夫人を誘うも彼女は一緒には来ない。しかし、1963年のある日、彼女は突然シンガポールのチャウの部屋を訪ねる。チャウは無言の電話を受け、自分の部屋の灰皿に夫人のタバコの吸い殻を見つけるが、夫人とは会えなかった。時は流れ1966年、子どもを連れたチャン夫人が香港のかつてのアパートにスーエン夫人を訪ね、アメリカに移住するというスーエン夫人からかつて住んだ部屋を借り受ける。一方のチャンもその後アパートを訪れ、新しい管理人に、隣は「お母さんと息子」が住んでいると聞く。それが誰であるかを確認することなく、その後彼は取材でアンコールワットを訪問し、古跡の壁の穴に過去の秘密を封印する―。
が徹夜マージャンをすることになり、自分の部屋に戻るに戻れなくなった夫人は、一夜をチャンの部屋で過ごすも機会を窺い、自分のスリッパを置き足に合わないチャウ夫人のヒール靴を履いて、さも外出先から自宅に帰ってきたかのようにチャンの部屋を出て行く。更に二人は、チャウが小説を書くために借りたホテルの部屋で何度か逢引するが、チャウが夫人が夫を問い詰めることを想定した練習台になったりするものの、二人は自分たちの配偶者のように簡単に不倫関係を結ぶことは出来ないでいる。チャウは、シンガポールでの仕事に誘われて現地へ行くことにするが、その際に夫人を誘うも彼女は一緒には来ない。しかし、1963年のある日、彼女は突然シンガポールのチャウの部屋を訪ねる。チャウは無言の電話を受け、自分の部屋の灰皿に夫人のタバコの吸い殻を見つけるが、夫人とは会えなかった。時は流れ1966年、子どもを連れたチャン夫人が香港のかつてのアパートにスーエン夫人を訪ね、アメリカに移住するというスーエン夫人からかつて住んだ部屋を借り受ける。一方のチャンもその後アパートを訪れ、新しい管理人に、隣は「お母さんと息子」が住んでいると聞く。それが誰であるかを確認することなく、その後彼は取材でアンコールワットを訪問し、古跡の壁の穴に過去の秘密を封印する―。 ウォン・カーウァイ(王家衛)監督の2000年作品で、同監督の「
ウォン・カーウァイ(王家衛)監督の2000年作品で、同監督の「 一方で、観ていて大きな謎の部分もありましたが、それは後にネットなどでいろんな人の分析を読んで、ナルホドなあと思ったりもし、また、そうした中でも見方が分かれていたりして、どっちの解釈が正しいのか、それは"正解"があるのか、それとも元々が観客に解釈を委ねている作品なのか―などと考えてみる上で"面白い"作品であると思います。以下、個人的解釈―。
一方で、観ていて大きな謎の部分もありましたが、それは後にネットなどでいろんな人の分析を読んで、ナルホドなあと思ったりもし、また、そうした中でも見方が分かれていたりして、どっちの解釈が正しいのか、それは"正解"があるのか、それとも元々が観客に解釈を委ねている作品なのか―などと考えてみる上で"面白い"作品であると思います。以下、個人的解釈―。 一説では、チャン夫人はスリッパを取りにシンガポールに行ったという見方もあるようですが、それは、後でチャウが部屋から無くなったものがあるとメイドに訴える、その"無くなったもの"とはスリッパであり、それは、例のマージャンの夜に夫人がチャウの部屋に置いてきたスリッパだったという。彼女がスリッパを"回収"するカットは実際にあり(スリッパが件(くだん)のものであったことそのものはまず間違いないだろう)、チャウにシンガポールでの仕事を紹介した人物がかつてのアパートの同居人でもあったことから、その人物がスリッパを見れば、どうして夫人のスリッパがここにあるのかと訝しがる、そのことを夫人は恐れたのか。仮にそうであるとしても、チャウが例のスリッパをシンガポールに持って行っていることを夫人は事前に知る由もなく、やはりここは、自分がチャウと付き合っていた「痕跡を消す」ためにスリッパを"回収"したのではなく(また、そのためにシンガポールまで行ったわけでもなく)、わざとタバコの吸い殻を残したのと同じように、チャウに想いを伝えに来たが踏み切れず、来たという「痕跡を残す」ためにスリッパを持ち帰ったと見るべきではないでしょうか。
一説では、チャン夫人はスリッパを取りにシンガポールに行ったという見方もあるようですが、それは、後でチャウが部屋から無くなったものがあるとメイドに訴える、その"無くなったもの"とはスリッパであり、それは、例のマージャンの夜に夫人がチャウの部屋に置いてきたスリッパだったという。彼女がスリッパを"回収"するカットは実際にあり(スリッパが件(くだん)のものであったことそのものはまず間違いないだろう)、チャウにシンガポールでの仕事を紹介した人物がかつてのアパートの同居人でもあったことから、その人物がスリッパを見れば、どうして夫人のスリッパがここにあるのかと訝しがる、そのことを夫人は恐れたのか。仮にそうであるとしても、チャウが例のスリッパをシンガポールに持って行っていることを夫人は事前に知る由もなく、やはりここは、自分がチャウと付き合っていた「痕跡を消す」ためにスリッパを"回収"したのではなく(また、そのためにシンガポールまで行ったわけでもなく)、わざとタバコの吸い殻を残したのと同じように、チャウに想いを伝えに来たが踏み切れず、来たという「痕跡を残す」ためにスリッパを持ち帰ったと見るべきではないでしょうか。 あり、チャウの妻(声のみで姿は画面には一度も出てこない)が電話で相手に対し(相手は不倫相手のチャン夫人の夫のようだが、こちらも声のみで姿は画面には一度も出てこない)、「話さないとダメよ」と言って泣いていることから(この部分も声のみ)、不倫相手に離婚を迫ったもののチャン夫人の夫が離婚を渋っているらしいことが窺え、更に、チャン夫人の夫が日本に出張中にチャン夫人の誕生日にラジオに歌のリクエストしていることで(その曲名が「花様的年華」)、これを聴いたチャン夫人が夫と和解し、結局は夫と別れなかったと解されるというもの。でも、そうだとしたら、どうしてわざわざチャウとの思い出が色濃く残るかつてのアパートに舞い戻ってくるのかが理解し難い気がします(この時、指輪はどうなっていた? 1962年時点では最後まで外さなかったようだが)。
あり、チャウの妻(声のみで姿は画面には一度も出てこない)が電話で相手に対し(相手は不倫相手のチャン夫人の夫のようだが、こちらも声のみで姿は画面には一度も出てこない)、「話さないとダメよ」と言って泣いていることから(この部分も声のみ)、不倫相手に離婚を迫ったもののチャン夫人の夫が離婚を渋っているらしいことが窺え、更に、チャン夫人の夫が日本に出張中にチャン夫人の誕生日にラジオに歌のリクエストしていることで(その曲名が「花様的年華」)、これを聴いたチャン夫人が夫と和解し、結局は夫と別れなかったと解されるというもの。でも、そうだとしたら、どうしてわざわざチャウとの思い出が色濃く残るかつてのアパートに舞い戻ってくるのかが理解し難い気がします(この時、指輪はどうなっていた? 1962年時点では最後まで外さなかったようだが)。 では、チャン夫人が連れている子どもはチャウの子なのか。だとしたら、二人はそれまでどうしても越えられなかった一線を最後に越えたことになりますが、それは何時だったのか。おそらく、夫人の夫への問い質し練習の延長としてやった、チャウとの別れの場面のロールプレイング(相手は夫を想定しているのかチャウを想定しているのか微妙)の後、夫人が泣き崩れ「今日は帰りたくない」というあの辺りでしょうか(2度目のタクシー内の場面)。その後、チャウがシンガポールに行っている間に妊娠・出産し、シンガポールにはそのことをチャウに伝えるためにも行ったとすれば、目的は果たさなかったものの行った動機としても説明がつくのではないでしょうか。
では、チャン夫人が連れている子どもはチャウの子なのか。だとしたら、二人はそれまでどうしても越えられなかった一線を最後に越えたことになりますが、それは何時だったのか。おそらく、夫人の夫への問い質し練習の延長としてやった、チャウとの別れの場面のロールプレイング(相手は夫を想定しているのかチャウを想定しているのか微妙)の後、夫人が泣き崩れ「今日は帰りたくない」というあの辺りでしょうか(2度目のタクシー内の場面)。その後、チャウがシンガポールに行っている間に妊娠・出産し、シンガポールにはそのことをチャウに伝えるためにも行ったとすれば、目的は果たさなかったものの行った動機としても説明がつくのではないでしょうか。 るという意味は大きい)、一方、おそらくは隣の部屋にチャン夫人が戻って来ているのを知らないままにアンコールワットに行ったチャウは、そこまで割り切って"思い出"に生きられないからこそ(男女の生理的違いと言っていいのでは)、遺跡の壁の穴に口づけをするという行為を以って意識的に"思い出"を封印しようとしたのではないか―と考えます。
るという意味は大きい)、一方、おそらくは隣の部屋にチャン夫人が戻って来ているのを知らないままにアンコールワットに行ったチャウは、そこまで割り切って"思い出"に生きられないからこそ(男女の生理的違いと言っていいのでは)、遺跡の壁の穴に口づけをするという行為を以って意識的に"思い出"を封印しようとしたのではないか―と考えます。


 「花様年華」●原題:花様年華/IN THE MOOD FOR LOVE●制作年:2000年●制作国:香港●監督・製作・脚本:ウォン・カーウァイ(王家衛)●撮影:クリストファー・ドイル/リー・ピンビン(李屏賓)●音楽:マイケル・ガラッソ/梅林茂●時間:98分●出演:トニー・レオン(梁朝偉)/マギー・チャン(張曼玉)/レベッカ・パン(藩迪華)/ライ・チン(雷震)/スー・ピンラン(蕭炳林)●日本公開:2001/03●配給:松竹●最初に観た場所:渋谷・Bunkamura ル・シネマ1(01-04-25)(評価:★★★★★)
「花様年華」●原題:花様年華/IN THE MOOD FOR LOVE●制作年:2000年●制作国:香港●監督・製作・脚本:ウォン・カーウァイ(王家衛)●撮影:クリストファー・ドイル/リー・ピンビン(李屏賓)●音楽:マイケル・ガラッソ/梅林茂●時間:98分●出演:トニー・レオン(梁朝偉)/マギー・チャン(張曼玉)/レベッカ・パン(藩迪華)/ライ・チン(雷震)/スー・ピンラン(蕭炳林)●日本公開:2001/03●配給:松竹●最初に観た場所:渋谷・Bunkamura ル・シネマ1(01-04-25)(評価:★★★★★)








 チャン・ツィイー
チャン・ツィイー 剣の名手として武林にその名を知られた李慕白(リー・ムーバイ)(チョウ・ユンファ〈周潤發〉)は、血で血を洗う江湖の争いに悩み、剣を捨てて引退することを決意、自身の名剣「青冥剣(グリーン・デスティニー)」を北京の鐵(ティエ)貝勒に寄贈するために、密かに恋心を抱いていた同門の弟子で、鏢局を営む兪秀蓮(ユイ・シューリン)(ミシェル・ヨー〈楊紫瓊〉)に託す。シューリンは剣を無事に北京のティエ宅に届けるものの、その夜、剣は何者
剣の名手として武林にその名を知られた李慕白(リー・ムーバイ)(チョウ・ユンファ〈周潤發〉)は、血で血を洗う江湖の争いに悩み、剣を捨てて引退することを決意、自身の名剣「青冥剣(グリーン・デスティニー)」を北京の鐵(ティエ)貝勒に寄贈するために、密かに恋心を抱いていた同門の弟子で、鏢局を営む兪秀蓮(ユイ・シューリン)(ミシェル・ヨー〈楊紫瓊〉)に託す。シューリンは剣を無事に北京のティエ宅に届けるものの、その夜、剣は何者 かに盗まれる。シューリンに続いて北京にやってきたムーバイは、剣を盗んだのは、リーの師匠を毒殺した仇の女性・碧眼狐(ジェイド・フォックス)(チェン・ペイペイ〈鄭佩佩〉)ではないかと考える。一方シューリンは、そこで結婚を間近に控えた貴族の娘の玉嬌龍(
かに盗まれる。シューリンに続いて北京にやってきたムーバイは、剣を盗んだのは、リーの師匠を毒殺した仇の女性・碧眼狐(ジェイド・フォックス)(チェン・ペイペイ〈鄭佩佩〉)ではないかと考える。一方シューリンは、そこで結婚を間近に控えた貴族の娘の玉嬌龍( イェン・シャオロン)(チャン・ツィイー〈章子怡〉)と出会い義姉妹の契りを交わすが、賊と戦った時の印象から、剣を盗んだ賊とはそのシャオロンではないかと疑う。シューリンの読み通り、剣を盗んだのはシャオロンで、シャオロンに剣を教えたのはジェイド・フォックスだった。結婚を控えたシャオロンには恋をした過去があり、新疆でその地の賊・羅小虎(ロー・シャオフー)(チャン・チェン〈張震〉)と出会い、シャオロンとシャオフーは今も深く愛し合っていた―。
イェン・シャオロン)(チャン・ツィイー〈章子怡〉)と出会い義姉妹の契りを交わすが、賊と戦った時の印象から、剣を盗んだ賊とはそのシャオロンではないかと疑う。シューリンの読み通り、剣を盗んだのはシャオロンで、シャオロンに剣を教えたのはジェイド・フォックスだった。結婚を控えたシャオロンには恋をした過去があり、新疆でその地の賊・羅小虎(ロー・シャオフー)(チャン・チェン〈張震〉)と出会い、シャオロンとシャオフーは今も深く愛し合っていた―。
 アン・リー〈李安〉監督による2000年の中国・香港・台湾・米国の合作作品で、原作は王度廬の武侠小説『臥虎蔵龍』ですが、五部作の第四部だけを映画化してもの。第73回アカデミー賞で英語以外の言語による作品でありながら作品賞ほか10部門にノミネートされ(監督、脚色、撮影、編集、美術、衣装デザイン、作曲、歌曲、外国語映画)、外国語映画賞など4部門を受賞しています。トロント国際映画祭の最高賞「観客賞」も受賞しており、トロント国際映画祭はアカデミーが公認している映画祭であるため、アカデミー作品賞ほかにノミネートされたものと思われます(ゴールデングローブ賞外国語映画賞、インディペンデント・スピリット賞及びロサンゼルス映画批評家協会賞の各「作品賞」も受賞)。
アン・リー〈李安〉監督による2000年の中国・香港・台湾・米国の合作作品で、原作は王度廬の武侠小説『臥虎蔵龍』ですが、五部作の第四部だけを映画化してもの。第73回アカデミー賞で英語以外の言語による作品でありながら作品賞ほか10部門にノミネートされ(監督、脚色、撮影、編集、美術、衣装デザイン、作曲、歌曲、外国語映画)、外国語映画賞など4部門を受賞しています。トロント国際映画祭の最高賞「観客賞」も受賞しており、トロント国際映画祭はアカデミーが公認している映画祭であるため、アカデミー作品賞ほかにノミネートされたものと思われます(ゴールデングローブ賞外国語映画賞、インディペンデント・スピリット賞及びロサンゼルス映画批評家協会賞の各「作品賞」も受賞)。 アン・リー監督は「両岸三地の中国人が力を合わせた結果、中国文化をアメリカに持ち込むことができた」と言っていますが、因みに、アン・リー監督とチャン・チェンは台湾出身、チョウ・ユンファは香港出身、ミシェル・ヨーは中国系マレーシア人で彼女も主に香港で活躍、チャン・ツィイーは中国出身。中国武侠映画は中国人に深く浸透しているものの、中国圏以外ではそれまであまり知られておらず、中国圏では古いタイプの物語がアメリカや日本の観客の眼には新鮮に映り、関心を持って迎えられたという事情はあったかと思います。
アン・リー監督は「両岸三地の中国人が力を合わせた結果、中国文化をアメリカに持ち込むことができた」と言っていますが、因みに、アン・リー監督とチャン・チェンは台湾出身、チョウ・ユンファは香港出身、ミシェル・ヨーは中国系マレーシア人で彼女も主に香港で活躍、チャン・ツィイーは中国出身。中国武侠映画は中国人に深く浸透しているものの、中国圏以外ではそれまであまり知られておらず、中国圏では古いタイプの物語がアメリカや日本の観客の眼には新鮮に映り、関心を持って迎えられたという事情はあったかと思います。 )、「
)、「
 それ以上に意外だったキャスティングが、我儘お嬢様で実は武闘家のイェン・シャオロンを演じるチャン・ツィイー(「
それ以上に意外だったキャスティングが、我儘お嬢様で実は武闘家のイェン・シャオロンを演じるチャン・ツィイー(「
 「
「 でここまで撮れてしまうのかと感心する一方で、竹林のアクションシーンでは俳優達をずっと4,50フィートの高さに吊っていたというから、それなりの大変さはあったのでしょう。カメラマンのピーター・パウ〈鮑徳熹〉は、「あのようなアクションはハリウッドでは永遠に撮れないだろう。なぜなら、ハリウッドには、俳優を10フィート以上吊ってはいけないという規定があるから」と述べています。悪役・碧眼狐を演じたベテラン女優チェン・ペイペイさえも「今の武侠映画はCGを使えるのでとても便利だ」と言っているぐらいですから、こうした生身のアクションシーンはだんだん見られなくなるのではないでしょうか。
でここまで撮れてしまうのかと感心する一方で、竹林のアクションシーンでは俳優達をずっと4,50フィートの高さに吊っていたというから、それなりの大変さはあったのでしょう。カメラマンのピーター・パウ〈鮑徳熹〉は、「あのようなアクションはハリウッドでは永遠に撮れないだろう。なぜなら、ハリウッドには、俳優を10フィート以上吊ってはいけないという規定があるから」と述べています。悪役・碧眼狐を演じたベテラン女優チェン・ペイペイさえも「今の武侠映画はCGを使えるのでとても便利だ」と言っているぐらいですから、こうした生身のアクションシーンはだんだん見られなくなるのではないでしょうか。 武侠映画のスタイルを取りながら、ストーリーとしては恋愛&ファンタジーといった感じですが、ラストで"ヒロイン"のイェン・シャオロンが
武侠映画のスタイルを取りながら、ストーリーとしては恋愛&ファンタジーといった感じですが、ラストで"ヒロイン"のイェン・シャオロンが


 「グリーン・デスティニー」●原題:臥虎藏龍/CROUCHING TIGER, HIDDEN DRAGON●制作年:2000年●制作国:中国・香港・台湾・米国●監督:アン・リー(李安)●製作:アン・リー/ビル・コン●脚本:ジェームズ・シェイマス/ツァイ・クォジュン/ワン・ホエリン●撮影:ピーター・パウ(鮑徳熹)●音楽:タン・ド
「グリーン・デスティニー」●原題:臥虎藏龍/CROUCHING TIGER, HIDDEN DRAGON●制作年:2000年●制作国:中国・香港・台湾・米国●監督:アン・リー(李安)●製作:アン・リー/ビル・コン●脚本:ジェームズ・シェイマス/ツァイ・クォジュン/ワン・ホエリン●撮影:ピーター・パウ(鮑徳熹)●音楽:タン・ド ゥン/ヨーヨー・マ●原作:王度廬(ワン・ドウルー)「臥虎蔵龍」●時間:120分●出演:チョウ・ユンファ(周潤發)/ミシェル・ヨー(楊紫瓊)/チャン・ツィイー(章子怡)/チャン・チェン(張震)/チェン・ペイペイ(鮑徳熹)/ラン・シャン(郎雄)/リー・ファーツォン●日本公開:2000/11●配給:ソニー・ピクチャーズ・エンタテインメント●最初に観た場所:渋谷東急(00-12-03)(評価:★★★☆)
ゥン/ヨーヨー・マ●原作:王度廬(ワン・ドウルー)「臥虎蔵龍」●時間:120分●出演:チョウ・ユンファ(周潤發)/ミシェル・ヨー(楊紫瓊)/チャン・ツィイー(章子怡)/チャン・チェン(張震)/チェン・ペイペイ(鮑徳熹)/ラン・シャン(郎雄)/リー・ファーツォン●日本公開:2000/11●配給:ソニー・ピクチャーズ・エンタテインメント●最初に観た場所:渋谷東急(00-12-03)(評価:★★★☆)




 チャン・ツィイー
チャン・ツィイー






 都会で働くルオ・ユーシェン(孫紅蕾(スン・ホンレイ))は、父の急死の知らせを受け故郷である中国華北部の小さな山村、三合屯(サンヘチュン)へ帰郷する。老いた母は悲嘆にくれるばかりで、遺体は町の病院に安置されたまま。母が遺体を担いで帰る昔ながらの葬式をすると言い張るが、村は老人と
都会で働くルオ・ユーシェン(孫紅蕾(スン・ホンレイ))は、父の急死の知らせを受け故郷である中国華北部の小さな山村、三合屯(サンヘチュン)へ帰郷する。老いた母は悲嘆にくれるばかりで、遺体は町の病院に安置されたまま。母が遺体を担いで帰る昔ながらの葬式をすると言い張るが、村は老人と 子供ばかりで遺体の担ぎ手がいない。母はまた、棺に掛ける布も自分が織ると言い張った。そんな母の姿を見つめる中、ユーシェンはふと一枚の写真に目がとまる。結婚直後の若き日の父と母が並んだ写真。母は赤い服を着ている。彼は村の語り草ともなった、若き日の父(鄭昊(チョン・ハオ))と母(章子怡(チャン・ツィイー))の恋愛物語を思い出す―。
子供ばかりで遺体の担ぎ手がいない。母はまた、棺に掛ける布も自分が織ると言い張った。そんな母の姿を見つめる中、ユーシェンはふと一枚の写真に目がとまる。結婚直後の若き日の父と母が並んだ写真。母は赤い服を着ている。彼は村の語り草ともなった、若き日の父(鄭昊(チョン・ハオ))と母(章子怡(チャン・ツィイー))の恋愛物語を思い出す―。 「紅いコーリャン」の時と違うのは、「紅いコーリャン」の頃は張藝謀の監督作品は中国国内では上映禁止だったのに、この「初恋のきた道」の頃には中国政府にも受け入れられるようになっていたということで、張監督はその後2008年の北京オリンピックの開会式および閉会式のチーフディレクターを任されるまでになり、これを体制に取り込まれた《堕落》と見る向きもあるようです。確かにそうした見方もあるかと思いますが(一応、この作品の中にも文化大革命批判が見られるが、それまでの同監督の作品ほどには先鋭的ではない。それでも中国のある年代の人が観れば暗い時代を思い出さずにはいられないだろうが)、そうした政治的なことはともかく、「紅いコーリャン」でみせた骨太の演出とダイナミックな映像美はこの作品でも充分に堪能できるかと思います。
「紅いコーリャン」の時と違うのは、「紅いコーリャン」の頃は張藝謀の監督作品は中国国内では上映禁止だったのに、この「初恋のきた道」の頃には中国政府にも受け入れられるようになっていたということで、張監督はその後2008年の北京オリンピックの開会式および閉会式のチーフディレクターを任されるまでになり、これを体制に取り込まれた《堕落》と見る向きもあるようです。確かにそうした見方もあるかと思いますが(一応、この作品の中にも文化大革命批判が見られるが、それまでの同監督の作品ほどには先鋭的ではない。それでも中国のある年代の人が観れば暗い時代を思い出さずにはいられないだろうが)、そうした政治的なことはともかく、「紅いコーリャン」でみせた骨太の演出とダイナミックな映像美はこの作品でも充分に堪能できるかと思います。 主人公が出てくる現在の部分はモノクロで、若き日の父と母のラブストーリーの部分はカラー(主人公は語り手となる)。2人の恋愛物語において、村に教師としてやった来た父と母の関係は、正確には教師と生徒ではなく、教師とただの村の娘というそれ以上に開きがあるものでしたが、それでも憧れの先生に猛烈にアタックをかけるチャン・ツィイーがいい(田舎娘らしいドン臭い走り方が"効果"的?)。その恋愛は、政治的理由で何年も会えないという過酷なものでしたが、障壁があればあるほど想いが強まるという意味では、ある種、"王道的"乃至"定番的"に描かれている恋物語のようにも思いました(同監督の「菊豆<チュイトウ>」('90年)のような"毒"を含んだ作品ではない)。
主人公が出てくる現在の部分はモノクロで、若き日の父と母のラブストーリーの部分はカラー(主人公は語り手となる)。2人の恋愛物語において、村に教師としてやった来た父と母の関係は、正確には教師と生徒ではなく、教師とただの村の娘というそれ以上に開きがあるものでしたが、それでも憧れの先生に猛烈にアタックをかけるチャン・ツィイーがいい(田舎娘らしいドン臭い走り方が"効果"的?)。その恋愛は、政治的理由で何年も会えないという過酷なものでしたが、障壁があればあるほど想いが強まるという意味では、ある種、"王道的"乃至"定番的"に描かれている恋物語のようにも思いました(同監督の「菊豆<チュイトウ>」('90年)のような"毒"を含んだ作品ではない)。 終盤モノクロの現在に話が戻って、かつての教え子たちが遠方からも含め百人ほども集って棺を担ぎ、誰も報酬を受け取らないというというのがスゴイ。吹雪の雪道を黙々と歩むその姿は感動的ですが、彼らは主人公にとっては知らない人ばかりだったという―。地方に留まり40年教師を続けた父親の偉大さがここにきて主人公の視点から浮彫りになり、そう言えば、若き日の父の話で母との恋愛の部分は映像化されていたのに対し、父の教える様子は「声が良かった」という母の述懐を主人公が語るといった間接表現になっていて実際のその姿の映像が無かったのが、逆にこの葬送シーンでの感動を引き起こす"効果"に繋がっていたように思います(因みに現在の母親を演じたのは女優ではなく素人)。
終盤モノクロの現在に話が戻って、かつての教え子たちが遠方からも含め百人ほども集って棺を担ぎ、誰も報酬を受け取らないというというのがスゴイ。吹雪の雪道を黙々と歩むその姿は感動的ですが、彼らは主人公にとっては知らない人ばかりだったという―。地方に留まり40年教師を続けた父親の偉大さがここにきて主人公の視点から浮彫りになり、そう言えば、若き日の父の話で母との恋愛の部分は映像化されていたのに対し、父の教える様子は「声が良かった」という母の述懐を主人公が語るといった間接表現になっていて実際のその姿の映像が無かったのが、逆にこの葬送シーンでの感動を引き起こす"効果"に繋がっていたように思います(因みに現在の母親を演じたのは女優ではなく素人)。 これで終わらないのがこの監督のスゴイところ。父の棺は今は使われていない古井戸の傍に運ばれて埋められ、それは父が教えていた学校のすぐ傍。つまり、雪が積もっていて初めはよく分からなかったけれども、父の教え子たちが棺を担いだ葬送の道程はまさに母親にとって「初恋のきた道」であって、ここにきて母親が遺体を担いで"帰る"昔ながらの葬式を望んだ理由が浮き彫りになります。
これで終わらないのがこの監督のスゴイところ。父の棺は今は使われていない古井戸の傍に運ばれて埋められ、それは父が教えていた学校のすぐ傍。つまり、雪が積もっていて初めはよく分からなかったけれども、父の教え子たちが棺を担いだ葬送の道程はまさに母親にとって「初恋のきた道」であって、ここにきて母親が遺体を担いで"帰る"昔ながらの葬式を望んだ理由が浮き彫りになります。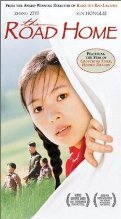

 可憐な演技を見せたチャン・ツィイーは、次回作「
可憐な演技を見せたチャン・ツィイーは、次回作「 「初恋のきた道」●原題:我的父親母親/THE ROAD HOME●制作年:1999年●制作国:中国●監督:張芸謀(チャン・イーモウ)●製作:趙愚(ツァオ・ユー)●脚本:鮑十(パオ・シー)●撮影:侯咏(ホウ・ヨン)●音楽:三宝(サンパオ)●原作:鮑十(パオ・シー)●時間:89分●出演:章子怡(チャン・ツィイー)/鄭昊(チョン・ハオ)/孫紅雷(スン・ホンレイ)/趙玉蓮(チャオ・ユエリン)●日本公開:2000/12●配給:ソニー・ピクチャーズ・エンタテインメント●最初に観た場所:渋谷・Bunkamura ル・シネマ2(01-05-13)(評価:★★★★)
「初恋のきた道」●原題:我的父親母親/THE ROAD HOME●制作年:1999年●制作国:中国●監督:張芸謀(チャン・イーモウ)●製作:趙愚(ツァオ・ユー)●脚本:鮑十(パオ・シー)●撮影:侯咏(ホウ・ヨン)●音楽:三宝(サンパオ)●原作:鮑十(パオ・シー)●時間:89分●出演:章子怡(チャン・ツィイー)/鄭昊(チョン・ハオ)/孫紅雷(スン・ホンレイ)/趙玉蓮(チャオ・ユエリン)●日本公開:2000/12●配給:ソニー・ピクチャーズ・エンタテインメント●最初に観た場所:渋谷・Bunkamura ル・シネマ2(01-05-13)(評価:★★★★)


 19世紀末のブラジル・マナウスのオペラハウス。オペラ歌手エンリコ・カルーソの公演を聴こうとペルー・イキトスからボートを漕いで来たフィツカラルド(クラウス・キンスキー)とモリー(クラウディア・カルディナーレ)。会場にもぐり込んだフィッカラルドは、カルーソのテノールに聞き入る。アイルランド出身の彼の本名はブラ
19世紀末のブラジル・マナウスのオペラハウス。オペラ歌手エンリコ・カルーソの公演を聴こうとペルー・イキトスからボートを漕いで来たフィツカラルド(クラウス・キンスキー)とモリー(クラウディア・カルディナーレ)。会場にもぐり込んだフィッカラルドは、カルーソのテノールに聞き入る。アイルランド出身の彼の本名はブラ イアン・スウィーニー・フィツジェラルドだが、インディオたちは彼をフィツカラルドと呼ぶ。今は製氷業だが、かつてアンデスに鉄道を敷設しようとして破産した経歴の持主で、白人らは彼を奇人とみなしていたが、娼家経営の愛人モリーは良き理解者であり、インディオの子らも彼を慕う。彼はイキトスにオペラ・ハウスを建てようと決意するが、それには莫大な資金が必要で、ゴム成金たちには相手にされない。そこで彼は、自らがジャングルを切り拓いてゴム園を作ることを計画、モリーが出してくれた金で成金の一人ドン・アキリノ(ホセ・レーゴイ)から中古の蒸気船
イアン・スウィーニー・フィツジェラルドだが、インディオたちは彼をフィツカラルドと呼ぶ。今は製氷業だが、かつてアンデスに鉄道を敷設しようとして破産した経歴の持主で、白人らは彼を奇人とみなしていたが、娼家経営の愛人モリーは良き理解者であり、インディオの子らも彼を慕う。彼はイキトスにオペラ・ハウスを建てようと決意するが、それには莫大な資金が必要で、ゴム成金たちには相手にされない。そこで彼は、自らがジャングルを切り拓いてゴム園を作ることを計画、モリーが出してくれた金で成金の一人ドン・アキリノ(ホセ・レーゴイ)から中古の蒸気船 を買い、パウル船長(ポール・ヒッチャー)、料理人ウェレケケ(ウェレケケ・エンリケ・ボホルケス)、機関士チョロ(ミゲル・アンヘル・フェンテス)らを雇う。"モリー号"と命名された船は修理を終えてアマゾン川に船出、彼のゴム園用地は流れの激しい"ボンゴの瀬"のあるウカヤリ川上流にあったため、彼は
を買い、パウル船長(ポール・ヒッチャー)、料理人ウェレケケ(ウェレケケ・エンリケ・ボホルケス)、機関士チョロ(ミゲル・アンヘル・フェンテス)らを雇う。"モリー号"と命名された船は修理を終えてアマゾン川に船出、彼のゴム園用地は流れの激しい"ボンゴの瀬"のあるウカヤリ川上流にあったため、彼は 船をパテリア川に進める。途中、中断された鉄道駅に寄り、レールを外して船に積み込む。船が進んで首刈り族の土地に入ると、乗組員らの多くは逃亡してしまう。フィツカラルドは操舵室の屋根上に蓄音機を置いてレコードをかけ、密林にオペラが流れるとインディオたちが姿を現わす。彼らは続々と船に乗り込んで来
船をパテリア川に進める。途中、中断された鉄道駅に寄り、レールを外して船に積み込む。船が進んで首刈り族の土地に入ると、乗組員らの多くは逃亡してしまう。フィツカラルドは操舵室の屋根上に蓄音機を置いてレコードをかけ、密林にオペラが流れるとインディオたちが姿を現わす。彼らは続々と船に乗り込んで来 るが、フィツカラルド一行に手を出さない。フィツカラルドは、パテリア川とウカヤリ川が最も接近したところで、船を川から揚げて山越えしてウカヤリ川に降ろすという計画をインディオに伝えると、酋長(D・P・エスピノサ)は協力するという。目的地に着いてレールを降ろし、ジャングルを切り拓き、滑車で船を引っぱり揚げる。7ヵ月後、遂に船はウカヤリ川に浮かぶ。祝杯に酔ったフィツカラルドらが寝ている隙に、インディオたちは船を激流に放つ。彼らは激流の荒ぶる魂を静める儀式として協力したのだった。フィッカラルドらを乗せたモリー号は、木の葉の如く激流を流されていく―。
るが、フィツカラルド一行に手を出さない。フィツカラルドは、パテリア川とウカヤリ川が最も接近したところで、船を川から揚げて山越えしてウカヤリ川に降ろすという計画をインディオに伝えると、酋長(D・P・エスピノサ)は協力するという。目的地に着いてレールを降ろし、ジャングルを切り拓き、滑車で船を引っぱり揚げる。7ヵ月後、遂に船はウカヤリ川に浮かぶ。祝杯に酔ったフィツカラルドらが寝ている隙に、インディオたちは船を激流に放つ。彼らは激流の荒ぶる魂を静める儀式として協力したのだった。フィッカラルドらを乗せたモリー号は、木の葉の如く激流を流されていく―。 ヴェルナー・ヘルツォーク監督による1982年作品で、同年のカンヌ国際映画祭「監督賞」受賞作。完成まで4年半を要し、苛酷なロケのためスターが次々と降板していった末にフィツカラルドの役をクラウス・キンスキーが得たことは知られていますが、結果として、オペラハウス建設への情熱に憑かれたフィツカラルドを演じたクラウス・キンスキーはハマリ役でした(思えば彼は、同監督の「
ヴェルナー・ヘルツォーク監督による1982年作品で、同年のカンヌ国際映画祭「監督賞」受賞作。完成まで4年半を要し、苛酷なロケのためスターが次々と降板していった末にフィツカラルドの役をクラウス・キンスキーが得たことは知られていますが、結果として、オペラハウス建設への情熱に憑かれたフィツカラルドを演じたクラウス・キンスキーはハマリ役でした(思えば彼は、同監督の「 ラストの、数日後には自分の所有から離れるモリー号の船上で、オペラを聴きながらフィツカラルドが見せる陶酔と誇りと狂気が入り交ざった表情はなかなかですが(ヘルツォーク作品の中ではかなり爽やかなエンディング?)、この映画のクライマックスはやはり、この映画を観たことがない人でもビデオやCDのジャケットでその場面は知っていると思われる、例の蒸気船の山越えでしょう。
ラストの、数日後には自分の所有から離れるモリー号の船上で、オペラを聴きながらフィツカラルドが見せる陶酔と誇りと狂気が入り交ざった表情はなかなかですが(ヘルツォーク作品の中ではかなり爽やかなエンディング?)、この映画のクライマックスはやはり、この映画を観たことがない人でもビデオやCDのジャケットでその場面は知っていると思われる、例の蒸気船の山越えでしょう。 ヘルツォーク監督、ホントに船を山越えさせてしまったなあという感じで、実写でここまでやるというのは当時でもスゴイと思いましたが(完璧主義者だったフリッツ・フォン・シュトロハイム(「
ヘルツォーク監督、ホントに船を山越えさせてしまったなあという感じで、実写でここまでやるというのは当時でもスゴイと思いましたが(完璧主義者だったフリッツ・フォン・シュトロハイム(「 アギーレと同様フィッツカラルドも実在の人物に改変を加えて描いてるようですが、最初観た時は西洋肉食系人種の凄まじい執念のようなものを感じました。また、異文化の出会いの物語でもあったなあと。最初は、西洋人の自らの文化への自信のようなものを感じましたが(「オペラで未開の地を啓蒙してやる」みたいな)、最近観直してみて、ラストの方でフィツカラルドが、初めてナイヤガラ瀑布を見つけた西洋人の言葉をぼそっと語る場面があったことに気づき、ああ、自分のことをなぞらえていたのだなあと。つまり、人に語っても信じてもらえないような不思議な体験をしたということであり、そこに彼の異文化への畏敬のようなものを感じました。結構、文化人類学的な視点の入った映画だったかもしれません。
アギーレと同様フィッツカラルドも実在の人物に改変を加えて描いてるようですが、最初観た時は西洋肉食系人種の凄まじい執念のようなものを感じました。また、異文化の出会いの物語でもあったなあと。最初は、西洋人の自らの文化への自信のようなものを感じましたが(「オペラで未開の地を啓蒙してやる」みたいな)、最近観直してみて、ラストの方でフィツカラルドが、初めてナイヤガラ瀑布を見つけた西洋人の言葉をぼそっと語る場面があったことに気づき、ああ、自分のことをなぞらえていたのだなあと。つまり、人に語っても信じてもらえないような不思議な体験をしたということであり、そこに彼の異文化への畏敬のようなものを感じました。結構、文化人類学的な視点の入った映画だったかもしれません。
 「フィツカラルド」●原題:FITZCARRALDO●制作年:1982年●制作国:西ドイツ●監督・脚本:ヴェルナー・ヘルツォーク●製作:ヴェルナー・ヘルツォーク/ルッキ・シュティペティック●撮影:トーマス・マウホ●音楽:ポポル・ヴー●時間:158分●出演:クラウス・キンスキー/クラウディア・カルディナーレ/ホセ・レーゴイ/ポール・ヒッチャー/
「フィツカラルド」●原題:FITZCARRALDO●制作年:1982年●制作国:西ドイツ●監督・脚本:ヴェルナー・ヘルツォーク●製作:ヴェルナー・ヘルツォーク/ルッキ・シュティペティック●撮影:トーマス・マウホ●音楽:ポポル・ヴー●時間:158分●出演:クラウス・キンスキー/クラウディア・カルディナーレ/ホセ・レーゴイ/ポール・ヒッチャー/ ウェレケケ・エンリケ・ボホルケス/ミゲル・アンヘル・フェンテス/グランデ・オセ
ウェレケケ・エンリケ・ボホルケス/ミゲル・アンヘル・フェンテス/グランデ・オセ ロ/ペーター・ベルリング/デイヴィッド・ペレス・エスピノサ/パウル・ヒットシェル●日本公開:1983/07●配給:大映インターナショナル●最初に観た場所:東急名画座(83-04-16)●2回目:北千住・シネマブルースタジオ(15-06-23)(評価:★★★★)
ロ/ペーター・ベルリング/デイヴィッド・ペレス・エスピノサ/パウル・ヒットシェル●日本公開:1983/07●配給:大映インターナショナル●最初に観た場所:東急名画座(83-04-16)●2回目:北千住・シネマブルースタジオ(15-06-23)(評価:★★★★)




 1958年に行われた第5回ニューポート・ジャズ・フェスティバルの模様を収めたドキュメンタリーフィルムで、音楽を扱ったドキュメンタリーの中でも、、映像的には最高水準にある作品とされているようです。そうと知らずに初めて観た時は、映像と音楽をただただ愉しんだという感じでしたが、初めて観た時('86年)に既に作られてから四半世紀経っていたのだなあと(これは今になって意外に思う)。
1958年に行われた第5回ニューポート・ジャズ・フェスティバルの模様を収めたドキュメンタリーフィルムで、音楽を扱ったドキュメンタリーの中でも、、映像的には最高水準にある作品とされているようです。そうと知らずに初めて観た時は、映像と音楽をただただ愉しんだという感じでしたが、初めて観た時('86年)に既に作られてから四半世紀経っていたのだなあと(これは今になって意外に思う)。 カメラマンで、この記録映画をちょっと変わった撮り方をしていて、実際にはこのフェスティバルには100人以上のミュージシャンが出演したそうですが、ルイ・アームストロング、アニタ・オデイ、マヘリア・ジャクソン、ダイナ・ワシントン、セロニアス・モンク、ゲリー・モリガン、ジョージ・シェアリングなど40人くらいに絞り込み(その結果、マイルス・デイヴィス、デューク・エリントン、ソニー・ロリンズなどの出演場面がカットされ、その演奏が収められていない)、しかも、4日間のイベントをまるで1日のイベントであったかのように撮っています。
カメラマンで、この記録映画をちょっと変わった撮り方をしていて、実際にはこのフェスティバルには100人以上のミュージシャンが出演したそうですが、ルイ・アームストロング、アニタ・オデイ、マヘリア・ジャクソン、ダイナ・ワシントン、セロニアス・モンク、ゲリー・モリガン、ジョージ・シェアリングなど40人くらいに絞り込み(その結果、マイルス・デイヴィス、デューク・エリントン、ソニー・ロリンズなどの出演場面がカットされ、その演奏が収められていない)、しかも、4日間のイベントをまるで1日のイベントであったかのように撮っています。 また、演奏会場の準備風景やバックステージ、観客の様子などもしっかり撮っていて、この手法は「ウッドストック」('70年/米)などに引き継がれるわけですが、歌い手
また、演奏会場の準備風景やバックステージ、観客の様子などもしっかり撮っていて、この手法は「ウッドストック」('70年/米)などに引き継がれるわけですが、歌い手 や演奏者よりも観客の方を長く撮っていたりする時間帯もあり、仕舞いには、カメラはフェスティバル会場を飛び出し、同時期に当地で行われようとしていたヨットのアメリカズ・カップの準備の様子や練習風景、アメリカズ・カップが本来のお目当だったと思われる観光客まで撮っています。
や演奏者よりも観客の方を長く撮っていたりする時間帯もあり、仕舞いには、カメラはフェスティバル会場を飛び出し、同時期に当地で行われようとしていたヨットのアメリカズ・カップの準備の様子や練習風景、アメリカズ・カップが本来のお目当だったと思われる観光客まで撮っています。 ということで、演奏の音楽が流れている間、カメラは、熱心に聴き入る観客ばかりでなく、無心にアイスクリームを食べる女性を望遠レンズでそっと撮ったり、海面を走るヨットを俯瞰で撮ったりもしているわけですが、そうした映像が音楽と不思議とフィットしていて、「聖者が街にやってくる」ではないですが、「ニューポートの街にジャズ・フェスティバルがやってきた」という雰囲気がシズル感をもって伝わってきます(そもそもこの映画は、クラシックカーに乗った楽隊がニューオリンズ風の演奏を繰り広げながら街を走るシーンから始まる)。
ということで、演奏の音楽が流れている間、カメラは、熱心に聴き入る観客ばかりでなく、無心にアイスクリームを食べる女性を望遠レンズでそっと撮ったり、海面を走るヨットを俯瞰で撮ったりもしているわけですが、そうした映像が音楽と不思議とフィットしていて、「聖者が街にやってくる」ではないですが、「ニューポートの街にジャズ・フェスティバルがやってきた」という雰囲気がシズル感をもって伝わってきます(そもそもこの映画は、クラシックカーに乗った楽隊がニューオリンズ風の演奏を繰り広げながら街を走るシーンから始まる)。 出演者の中では、終盤に登場するルイ・アームストロング(1901-1971/享年69)の貫禄とエンターテイナーぶりはさすがという感じでした。それ以外では、ラストのマヘリア・ジャクソンのゴスペルも良
出演者の中では、終盤に登場するルイ・アームストロング(1901-1971/享年69)の貫禄とエンターテイナーぶりはさすがという感じでした。それ以外では、ラストのマヘリア・ジャクソンのゴスペルも良 かったですが、最初の方に出てくる、「スウィート・ジョージア・ブラウン」「二人でお茶を」の2曲
かったですが、最初の方に出てくる、「スウィート・ジョージア・ブラウン」「二人でお茶を」の2曲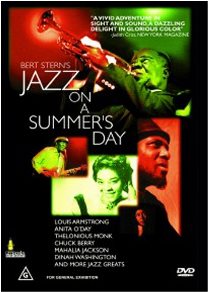

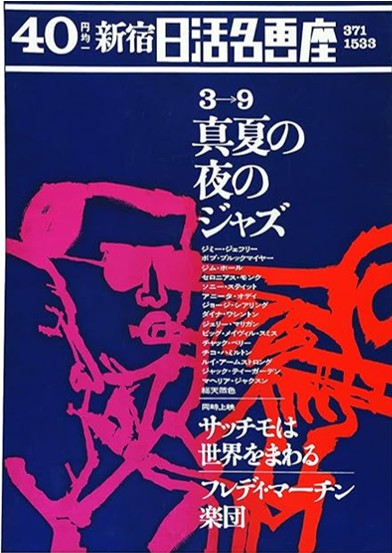





 1870年代のテキサスのある町に、東部から1人の紳士ジェームズ・マッケイ(グレゴリー・ペック)が、有力者テリル少佐(チャールズ・ビックフォード)の娘パット(キャロル・ベイカー)
1870年代のテキサスのある町に、東部から1人の紳士ジェームズ・マッケイ(グレゴリー・ペック)が、有力者テリル少佐(チャールズ・ビックフォード)の娘パット(キャロル・ベイカー) と結婚するためにやって来る。出迎えた牧童頭のスティーブ・リーチ(チャールトン・ヘストン)は主人の娘を密かに恋しており、ヤサ男風のジェームズに敵意を抱く。パットは、ジェームズと父の牧場に向かう途中、ヘネシー家の息子
と結婚するためにやって来る。出迎えた牧童頭のスティーブ・リーチ(チャールトン・ヘストン)は主人の娘を密かに恋しており、ヤサ男風のジェームズに敵意を抱く。パットは、ジェームズと父の牧場に向かう途中、ヘネシー家の息子 バック(チャック・コナーズ)たちの悪戯を受けるが、ジェームズは彼らの為すがままで抵抗しなかった。パットの父テリル少佐は大地主ルーファス・ヘネシー(バール・アイヴス)とこの地の勢力を二分して争っていた。両者が共に目をつけている水源地ビッグ・マディは、パットの親友の女教師ジュリー・マラゴン(ジーン・シモンズ)が所有していた。
バック(チャック・コナーズ)たちの悪戯を受けるが、ジェームズは彼らの為すがままで抵抗しなかった。パットの父テリル少佐は大地主ルーファス・ヘネシー(バール・アイヴス)とこの地の勢力を二分して争っていた。両者が共に目をつけている水源地ビッグ・マディは、パットの親友の女教師ジュリー・マラゴン(ジーン・シモンズ)が所有していた。 彼女は一方が水源を独占すれば必ず争いが起こると考え、どちらにも土地を売ろうとしなかった。少佐は娘婿にされた乱暴に対して、ヘネシーの集落を襲いヘネシーの息子たちにリンチを加えて復讐するが、ジェームズはそんな少佐に相
彼女は一方が水源を独占すれば必ず争いが起こると考え、どちらにも土地を売ろうとしなかった。少佐は娘婿にされた乱暴に対して、ヘネシーの集落を襲いヘネシーの息子たちにリンチを加えて復讐するが、ジェームズはそんな少佐に相 容れないものを感じる。彼は争いの元である水源地ビッグ・マディを見て女主人ジュリーに会い、中立の立場で誰にでも水を与え、自分でこの地に牧場
容れないものを感じる。彼は争いの元である水源地ビッグ・マディを見て女主人ジュリーに会い、中立の立場で誰にでも水を与え、自分でこの地に牧場 を経営したいと申し出て売約契約を交わす。血気にはやるパットと父の少佐には、ジェームズの態度が不満だった。一方、ヘネシー父子は、水源地を手に入れて少佐に対抗するため、ジュリーを監禁する。ジェームズはメキシコ人牧童ラモン(
を経営したいと申し出て売約契約を交わす。血気にはやるパットと父の少佐には、ジェームズの態度が不満だった。一方、ヘネシー父子は、水源地を手に入れて少佐に対抗するため、ジュリーを監禁する。ジェームズはメキシコ人牧童ラモン( アルフォンソ・ベドヤ)の案内で単身本拠に乗り込み、水源は自由にすると明言してジュリーを救出しようとする。ジュリーに横恋慕する息子バックは、父ルーファス・ヘネシーの計らいでジェームズと決闘することになるが、卑怯な振舞いから父に射殺される。やがて少佐の一隊が乗り込んできて戦いが始まり、1対1で対決したルーファスと少佐は相撃ちで共に死に、憎悪による対立と暴力の時代は終わりを告げる―。
アルフォンソ・ベドヤ)の案内で単身本拠に乗り込み、水源は自由にすると明言してジュリーを救出しようとする。ジュリーに横恋慕する息子バックは、父ルーファス・ヘネシーの計らいでジェームズと決闘することになるが、卑怯な振舞いから父に射殺される。やがて少佐の一隊が乗り込んできて戦いが始まり、1対1で対決したルーファスと少佐は相撃ちで共に死に、憎悪による対立と暴力の時代は終わりを告げる―。 ウィリアム・ワイラー監督の1958年作品で、まさに「大いなる西部」を雄大に描きつつ、その中に様々な価値観の対立を織り込み、また、ストーリー的にも2時間46分の長尺でありながら飽きさせずに最後まで見せるという、巨匠ならではの堂々たる娯楽大作です。グレゴリー・ペック(1916-2003/享年87)、チャールトン・ヘストン(1923-2008/享年84)、ジーン・シモンズ(1929-2010/享年80)、キャロル・ベイカー(1931- )の4大スターが共演していますが、テレビで初めて観た時は4人とも存命していたのが、今はキャロル・ベイカーしか生きていないのは、50年以上前の作品であるから仕方無いけれど、ちょっと寂しいです。
ウィリアム・ワイラー監督の1958年作品で、まさに「大いなる西部」を雄大に描きつつ、その中に様々な価値観の対立を織り込み、また、ストーリー的にも2時間46分の長尺でありながら飽きさせずに最後まで見せるという、巨匠ならではの堂々たる娯楽大作です。グレゴリー・ペック(1916-2003/享年87)、チャールトン・ヘストン(1923-2008/享年84)、ジーン・シモンズ(1929-2010/享年80)、キャロル・ベイカー(1931- )の4大スターが共演していますが、テレビで初めて観た時は4人とも存命していたのが、今はキャロル・ベイカーしか生きていないのは、50年以上前の作品であるから仕方無いけれど、ちょっと寂しいです。 チャールトン・ヘストンは「主演」ではなく、主演はこの映画の製作も兼ねたグレゴリー・ペックであり、チャールトン・ヘストンの方は「助演」ということで、年齢的にも、グレゴリー・ペックが当時42歳だったのに対し34歳と、相対的にはまだ若い感じか。ウィリアム・ワイラー監督は、グレゴリー・ペックの主演作では「ローマの休日」('53年)があり、一方、この作品の翌年には、チャールトン・ヘストン主演の「ベン・ハー」('59年)を撮ることになります。
チャールトン・ヘストンは「主演」ではなく、主演はこの映画の製作も兼ねたグレゴリー・ペックであり、チャールトン・ヘストンの方は「助演」ということで、年齢的にも、グレゴリー・ペックが当時42歳だったのに対し34歳と、相対的にはまだ若い感じか。ウィリアム・ワイラー監督は、グレゴリー・ペックの主演作では「ローマの休日」('53年)があり、一方、この作品の翌年には、チャールトン・ヘストン主演の「ベン・ハー」('59年)を撮ることになります。 この作品には、グレゴリー・ペック演じるジェームズ・マッケイのキャラクターが分かりにくいとの批評もあるようですが、物語の設定上も、周囲が煮え切らないようなものを感じるキャラだから、観ている側がそう感じるのもおかしくないかも。実際にはジェームズは勇気ある正義漢であり、決して"ヤサ男"でも"慎重居士"でもないわけですが
この作品には、グレゴリー・ペック演じるジェームズ・マッケイのキャラクターが分かりにくいとの批評もあるようですが、物語の設定上も、周囲が煮え切らないようなものを感じるキャラだから、観ている側がそう感じるのもおかしくないかも。実際にはジェームズは勇気ある正義漢であり、決して"ヤサ男"でも"慎重居士"でもないわけですが (逆にいくら命があっても足りないくらい(?)勇敢)、ただ、そこまで「能ある鷹は爪を隠す」的行動をするかなあという感じは確かにあります(却ってイヤミっぽい?)。むしろ、チャールトン・ヘストン演じる牧童頭スティーブ・リーチのキャラクターの方が分かり易くて親近感が感じられました。チャールトン・ヘストンが屈折した役柄を演じているというのも興味深いですが、彼は同年のオーソン・ウェルズ監督の
(逆にいくら命があっても足りないくらい(?)勇敢)、ただ、そこまで「能ある鷹は爪を隠す」的行動をするかなあという感じは確かにあります(却ってイヤミっぽい?)。むしろ、チャールトン・ヘストン演じる牧童頭スティーブ・リーチのキャラクターの方が分かり易くて親近感が感じられました。チャールトン・ヘストンが屈折した役柄を演じているというのも興味深いですが、彼は同年のオーソン・ウェルズ監督の

 それ以外の俳優陣では、ヘネシー家の父親を演じたバール・アイヴス(1909-1995、数多くのヒット曲を持つフォーク歌手でもあった)がアカデミー助演男優賞とゴールデングローブ賞の両方の助演男優賞を受賞していますが、個人的には、ジーン・シモンズ(1929-2010)演じる女教師が印象的でした。きりっとした美人でもありますが、自らの名誉を犠牲にしてジェームズを守ろうとするところが、名誉にこだわって争いを繰り返す周囲の愚か者たちとの対比で際立
それ以外の俳優陣では、ヘネシー家の父親を演じたバール・アイヴス(1909-1995、数多くのヒット曲を持つフォーク歌手でもあった)がアカデミー助演男優賞とゴールデングローブ賞の両方の助演男優賞を受賞していますが、個人的には、ジーン・シモンズ(1929-2010)演じる女教師が印象的でした。きりっとした美人でもありますが、自らの名誉を犠牲にしてジェームズを守ろうとするところが、名誉にこだわって争いを繰り返す周囲の愚か者たちとの対比で際立 っていました。最後は、ジェームズと結ばれることを暗示するような終わり方と取るのが妥当―というか、もう、それしかないだろうなあと思ったりもします。
っていました。最後は、ジェームズと結ばれることを暗示するような終わり方と取るのが妥当―というか、もう、それしかないだろうなあと思ったりもします。
 グレゴリー・ペックとチャールトン・ヘストンの延々と続く殴り合いのシーンも語り草になっていますが、確かにグレゴリー・ペック190㎝、チャールトン・ヘストン191㎝という両者の長身は荒野に映えます。但し、敵役バック・ヘネシーを演じたチャック・コナーズ(1921-1992/享年71)はそれらを上回る身長197㎝の長身で、俳優になる前はBAA(現NBA)とMLBの選手でした(つまりプロバスケットボールとメジャーリーグ
グレゴリー・ペックとチャールトン・ヘストンの延々と続く殴り合いのシーンも語り草になっていますが、確かにグレゴリー・ペック190㎝、チャールトン・ヘストン191㎝という両者の長身は荒野に映えます。但し、敵役バック・ヘネシーを演じたチャック・コナーズ(1921-1992/享年71)はそれらを上回る身長197㎝の長身で、俳優になる前はBAA(現NBA)とMLBの選手でした(つまりプロバスケットボールとメジャーリーグ の選手を兼ねていたことになる)。1958年10月に公開されたこの映画の中では、ヘネシー家の不良息子で、ジェームズ、パットらにちょっかいを出し、ジュリーに横恋慕した挙句、最期はその卑怯な行為によりバール・アイヴス演じる自分の父親に射殺されてしまうという情けない男の役ですが、同じく1958年9月から米ABCで放送開始されたテレビ西部劇「ライフルマン」では、無法者の悪や暴力と闘う銃の達人にして、妻に
の選手を兼ねていたことになる)。1958年10月に公開されたこの映画の中では、ヘネシー家の不良息子で、ジェームズ、パットらにちょっかいを出し、ジュリーに横恋慕した挙句、最期はその卑怯な行為によりバール・アイヴス演じる自分の父親に射殺されてしまうという情けない男の役ですが、同じく1958年9月から米ABCで放送開始されたテレビ西部劇「ライフルマン」では、無法者の悪や暴力と闘う銃の達人にして、妻に



 Charlton Heston in 1958 "Touch of Evil" (「
Charlton Heston in 1958 "Touch of Evil" (「



 1968年5月のパリ五月革命の最中、南
1968年5月のパリ五月革命の最中、南 仏ジェール県の当主ヴューザック家夫人(ポーレット・デュボー)が突然の発作で死ぬ。長男のミル(ミシェル・ピコリ)は彼女の死を兄弟や娘たちに伝えようとするがストで電話が繋がらない。ようやく駆け付けたミルの娘カミーユ(ミュウミュウ)と
仏ジェール県の当主ヴューザック家夫人(ポーレット・デュボー)が突然の発作で死ぬ。長男のミル(ミシェル・ピコリ)は彼女の死を兄弟や娘たちに伝えようとするがストで電話が繋がらない。ようやく駆け付けたミルの娘カミーユ(ミュウミュウ)と フランソワーズたち3人の子、姪のクレール(ドミニク・ブラン)とそのレズビアン友達マリー=ロール(ロゼン・ル・タレク)、弟のジョルジュ(ミシェル・デュショーソワ)と彼の後妻リリー(ハリエット・ウォルター)たちの話題は革命と遺産分配のことばかり。立派な邸宅を売ったらゴルフ場にもできるというカミーユとジョルジュにミルは怒りを爆発させ、小川へザリガニ捕りに行く。カミーユと幼馴染みの公証人ダニエル(フランソワ・ベルレアン)の読みあげる夫人の遺書の中に、小間使いのアデル(マルティーヌ・ゴーティエ)が相続人に含まれていると知って一同は驚くが、気のあるミルだけは喜ぶ。パリで学生運動に参加しているジョルジュの息子ピエール
フランソワーズたち3人の子、姪のクレール(ドミニク・ブラン)とそのレズビアン友達マリー=ロール(ロゼン・ル・タレク)、弟のジョルジュ(ミシェル・デュショーソワ)と彼の後妻リリー(ハリエット・ウォルター)たちの話題は革命と遺産分配のことばかり。立派な邸宅を売ったらゴルフ場にもできるというカミーユとジョルジュにミルは怒りを爆発させ、小川へザリガニ捕りに行く。カミーユと幼馴染みの公証人ダニエル(フランソワ・ベルレアン)の読みあげる夫人の遺書の中に、小間使いのアデル(マルティーヌ・ゴーティエ)が相続人に含まれていると知って一同は驚くが、気のあるミルだけは喜ぶ。パリで学生運動に参加しているジョルジュの息子ピエール =アラン(ルノー・ダネール)が共産党嫌いのグリマルディ(ブルーノ・カレット)のトラックに乗せてもらって屋敷に現われる。翌日、革命の影響で葬儀屋までがストをする。ミルたちは遺体を庭に埋めることにし、葬式を一日延期し、ピクニックに興じる。その夜、屋敷に現われた村の工場主夫妻から、ド・ゴール大統領が姿を消していて、ブルジョワは殺されると知らされた一同は、森の洞窟へと逃げる。疲労と空腹で一夜を過ごした彼らのもとにアデルがやって来て、ストが終ったことを知らせる。いつしか彼らの心の中には、屋敷を売る考えはなくなっていた。無事に葬儀は終わり、人々も帰るべき場所へと帰って行き、屋敷には再びミルだけが残される―。
=アラン(ルノー・ダネール)が共産党嫌いのグリマルディ(ブルーノ・カレット)のトラックに乗せてもらって屋敷に現われる。翌日、革命の影響で葬儀屋までがストをする。ミルたちは遺体を庭に埋めることにし、葬式を一日延期し、ピクニックに興じる。その夜、屋敷に現われた村の工場主夫妻から、ド・ゴール大統領が姿を消していて、ブルジョワは殺されると知らされた一同は、森の洞窟へと逃げる。疲労と空腹で一夜を過ごした彼らのもとにアデルがやって来て、ストが終ったことを知らせる。いつしか彼らの心の中には、屋敷を売る考えはなくなっていた。無事に葬儀は終わり、人々も帰るべき場所へと帰って行き、屋敷には再びミルだけが残される―。

 ブルジョワ階級出身のルイ・マル監督が五月革命に翻弄されるブルジョワを風刺と皮肉を込めて描いた作品ととれますが、アイロニカルな部分がことさらに強調されているわけではなく、その点において自然であるとともにやや中途半端か。むしろ、政治的なことは抜きにして、単純に集団劇として見た場合に結構面白いのではないでしょうか(ルイ・マルの頭にはアントン・チェーホフの『桜の園』があったという。また、ジャン・ルノワールの「ゲームの規則」的な作りをも意識しているらしい)。
ブルジョワ階級出身のルイ・マル監督が五月革命に翻弄されるブルジョワを風刺と皮肉を込めて描いた作品ととれますが、アイロニカルな部分がことさらに強調されているわけではなく、その点において自然であるとともにやや中途半端か。むしろ、政治的なことは抜きにして、単純に集団劇として見た場合に結構面白いのではないでしょうか(ルイ・マルの頭にはアントン・チェーホフの『桜の園』があったという。また、ジャン・ルノワールの「ゲームの規則」的な作りをも意識しているらしい)。 ミルは母親の死に一度慟哭しますが、その後は親族たちのドタバタに振り回され、そうした中で弟の後妻リリーと急速に接近(それまでも小間使いのアデルと恋人関係にあったようだが)、娘のカミーユは幼馴染みの公証人のダニエルとの関係が再燃したようで、レズビアンだったはずのマリー=ロールはピエール=アランと親密になり、それに対抗するようにクレールもトラック運転手のグリマルディと親しくなります(何だか、親戚と他人が入り混じった乱交状態みたいになってくるね)。
ミルは母親の死に一度慟哭しますが、その後は親族たちのドタバタに振り回され、そうした中で弟の後妻リリーと急速に接近(それまでも小間使いのアデルと恋人関係にあったようだが)、娘のカミーユは幼馴染みの公証人のダニエルとの関係が再燃したようで、レズビアンだったはずのマリー=ロールはピエール=アランと親密になり、それに対抗するようにクレールもトラック運転手のグリマルディと親しくなります(何だか、親戚と他人が入り混じった乱交状態みたいになってくるね)。 こうした人同士の関係の化学変化が、ミルの突然思い立ったザリガニ捕りや(これも相続争い対する嫌気から逃れたい気持ちからの行動だと思うが)、関係者総出でのピクニックを通して描かれ、美しい自然の中で人々の気持ちが解放され、行動が大胆になっていく一方、屋敷を売ってどうのこうのといった考えは消えていき、また、それは同時に、屋敷を売りたくないミルの思惑に沿ったものになっているというのは、観ていてまずますスムーズな流れです。
こうした人同士の関係の化学変化が、ミルの突然思い立ったザリガニ捕りや(これも相続争い対する嫌気から逃れたい気持ちからの行動だと思うが)、関係者総出でのピクニックを通して描かれ、美しい自然の中で人々の気持ちが解放され、行動が大胆になっていく一方、屋敷を売ってどうのこうのといった考えは消えていき、また、それは同時に、屋敷を売りたくないミルの思惑に沿ったものになっているというのは、観ていてまずますスムーズな流れです。 しかし、ミル自身は、屋敷は売らずに済んだものの、最後は小間使い兼恋人のアデルにも婚約者がいて彼女も去っていくという目に遭います(意外としたたかな女性だった)。リリーも去ってアデルも去り、残されたミルは、もう誰もいない屋敷で亡き母の幻影とダンスを踊る―ミルの老境の孤独を感じさせるエンディングで、初
しかし、ミル自身は、屋敷は売らずに済んだものの、最後は小間使い兼恋人のアデルにも婚約者がいて彼女も去っていくという目に遭います(意外としたたかな女性だった)。リリーも去ってアデルも去り、残されたミルは、もう誰もいない屋敷で亡き母の幻影とダンスを踊る―ミルの老境の孤独を感じさせるエンディングで、初
 め「田舎の日曜日」→中ほど「お葬式」→ラスト再び「田舎の日曜日」といった感じの作品ですが、「田舎の日曜日」同様にフランスの田舎を美しく撮っている作品でもあります。黒澤明(1910-1998)監督の娘である黒澤和子氏によれば、黒澤明が生前評価していた作品でもあるようです(黒澤和子
め「田舎の日曜日」→中ほど「お葬式」→ラスト再び「田舎の日曜日」といった感じの作品ですが、「田舎の日曜日」同様にフランスの田舎を美しく撮っている作品でもあります。黒澤明(1910-1998)監督の娘である黒澤和子氏によれば、黒澤明が生前評価していた作品でもあるようです(黒澤和子

 ミシェル・ピコリ(1925-2020/享年94)は「
ミシェル・ピコリ(1925-2020/享年94)は「 ック・リヴェット(1928-2016/享年87)監督(この人もヌーヴェルヴァーグの中心的人物である)の「美しき諍い女(いさかいめ)」('91年)に出演しています。高名であるが世捨て人の画>家(ミシェル・ピコリ)が、もともとモデルだった妻(ジェーン・バーキン)とプロヴァンスの片田舎にある古城で静かに暮らしているところへ、一人の若い画家が恋人(エマニュエル・ベアール)を連れて彼のもとを訪れると、画家は彼女をモデルにする事で、自分が長い間打ち捨てていた作品「美しき諍い女」の制作を再開する気になるというものです。ノーカット版は3時間57分ですが、当時['93年]VHS版(1時間31分)で観てしまいました(ジャック・リヴェット監督が別撮りのフィルムでテレビ用にシー
ック・リヴェット(1928-2016/享年87)監督(この人もヌーヴェルヴァーグの中心的人物である)の「美しき諍い女(いさかいめ)」('91年)に出演しています。高名であるが世捨て人の画>家(ミシェル・ピコリ)が、もともとモデルだった妻(ジェーン・バーキン)とプロヴァンスの片田舎にある古城で静かに暮らしているところへ、一人の若い画家が恋人(エマニュエル・ベアール)を連れて彼のもとを訪れると、画家は彼女をモデルにする事で、自分が長い間打ち捨てていた作品「美しき諍い女」の制作を再開する気になるというものです。ノーカット版は3時間57分ですが、当時['93年]VHS版(1時間31分)で観てしまいました(ジャック・リヴェット監督が別撮りのフィルムでテレビ用にシー ンを変更した2時間5分の別バージョン「美しき諍い女ディヴェルティメント」が1993年に劇場公開されているが、現在は約4時間のオリジナル完全版が
ンを変更した2時間5分の別バージョン「美しき諍い女ディヴェルティメント」が1993年に劇場公開されているが、現在は約4時間のオリジナル完全版が DVD・Blu-ray化されている)。エマニュエル・ベアールは作中を通じてほとんど全裸であり、「ワイセツか芸術か」の物議をかもした問題作ですが、カンヌ国際映画祭でグランプリを受賞しています(エマニュエル・ベアールはブライアン・デ・パルマ監督の「
DVD・Blu-ray化されている)。エマニュエル・ベアールは作中を通じてほとんど全裸であり、「ワイセツか芸術か」の物議をかもした問題作ですが、カンヌ国際映画祭でグランプリを受賞しています(エマニュエル・ベアールはブライアン・デ・パルマ監督の「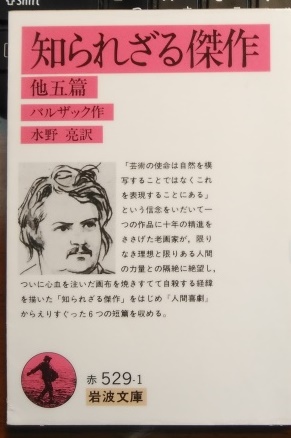




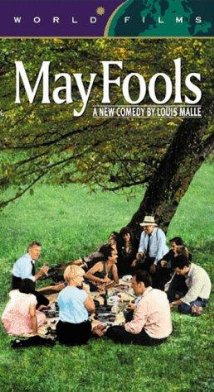 「五月のミル」●原題:MILOU EN MAI●制作年:1989年(公開年:1990年)●制作国:フランス・イタリア●監督:ルイ・マル●製作:ルイ・マル/ヴィン・セントマル●脚
「五月のミル」●原題:MILOU EN MAI●制作年:1989年(公開年:1990年)●制作国:フランス・イタリア●監督:ルイ・マル●製作:ルイ・マル/ヴィン・セントマル●脚 本:ジャン=クロード・カリエール●撮影:レナート・ベルタ●音楽:ステファン・グラッペリ●時間:107分●出演:ミュウミュウ/ミシェル・ピコリ/ミシェル・デュショーソワ/ブルーノ・カレット/ポーレット・デュボー/ハリエット•ウォルター/マルティーヌ・ゴーティエ/ドミニク・ブラン/ロゼン・ル・タレク/フランソワ・ベルレアン/ルノー・ダネール●日本公開:1990/08●配給:シネセゾン●最初に観た場所:シネヴィヴァン六本木(90-10-10)●2回目:北千住・シネマブルースタジオ(15-04-18)(評価:★★★☆)
本:ジャン=クロード・カリエール●撮影:レナート・ベルタ●音楽:ステファン・グラッペリ●時間:107分●出演:ミュウミュウ/ミシェル・ピコリ/ミシェル・デュショーソワ/ブルーノ・カレット/ポーレット・デュボー/ハリエット•ウォルター/マルティーヌ・ゴーティエ/ドミニク・ブラン/ロゼン・ル・タレク/フランソワ・ベルレアン/ルノー・ダネール●日本公開:1990/08●配給:シネセゾン●最初に観た場所:シネヴィヴァン六本木(90-10-10)●2回目:北千住・シネマブルースタジオ(15-04-18)(評価:★★★☆)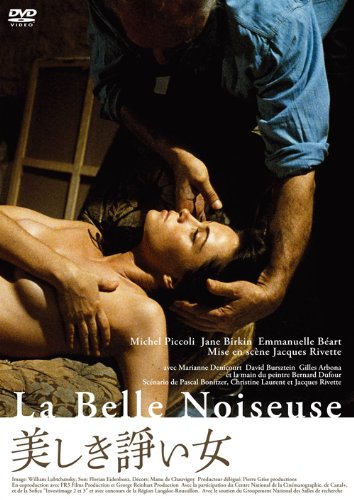
 題:LA BELLE NOISEUSE(英:BEAUTIFUL TROUBLEMAKER)●制作年:1991年●制作国:フランス●監督:ジャック・リヴェット●製作:マルティーヌ・マリニャック●脚本:パスカル・ポニツェール/クリスティーヌ・ロラン/ジャック・リヴェット●撮影:ウィリアム・リュプチャンスキー●音楽:イゴール・ストラヴィンスキー●原作:「バルザック 知られざる傑作」●時間:91分(VHS版)・131分(2時間編集版)・237分(ノーカット版)●出演:ミシェル・ピコリ/ジェーン・バーキン/エマニュエル・ベアール/マリアンヌ・ドニクール/ダヴィッド・バースタイン/ジル・アルボナ/マリー・ベリュック/マリー=クロード・ロジェ●日本公開:1992/05●配給:コムストック(評価:★★★★)
題:LA BELLE NOISEUSE(英:BEAUTIFUL TROUBLEMAKER)●制作年:1991年●制作国:フランス●監督:ジャック・リヴェット●製作:マルティーヌ・マリニャック●脚本:パスカル・ポニツェール/クリスティーヌ・ロラン/ジャック・リヴェット●撮影:ウィリアム・リュプチャンスキー●音楽:イゴール・ストラヴィンスキー●原作:「バルザック 知られざる傑作」●時間:91分(VHS版)・131分(2時間編集版)・237分(ノーカット版)●出演:ミシェル・ピコリ/ジェーン・バーキン/エマニュエル・ベアール/マリアンヌ・ドニクール/ダヴィッド・バースタイン/ジル・アルボナ/マリー・ベリュック/マリー=クロード・ロジェ●日本公開:1992/05●配給:コムストック(評価:★★★★) 

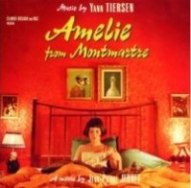
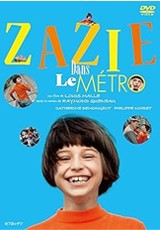
 神経質で元教師の母親と冷淡な元軍医の父親を持つアメリはあまり構ってもらえず、両親との身体接触は父親による彼女の心臓検査時だけ。いつも父親に触れてもらうのを望んでいたが、稀なことなので心臓が高揚し、心臓に障害があると勘違いした父親は、学校には登校させず周りから子供たちを遠ざけてしまう。その中で母親を事故で亡くし、孤独の中で彼女は想像力の豊かな、しかし周囲と満足なコミュニケーションがとれない不器用な少女になっていく。そのまま成長して22歳となったアメリ(オドレイ・トトゥ)は実家を出てアパートに住み、モンマルトルにある元サーカス団員経営のカフェで働き始める。ある日、偶然に自室から小さな箱を発見し、中に入っていた子供の宝物を持ち主に返そうとした彼女は、探偵の真似事の末に前の住人を探し、箱を持ち主に返して喜ばれたことで、彼女は人を幸せにすることに喜びを見出すようになる―。
神経質で元教師の母親と冷淡な元軍医の父親を持つアメリはあまり構ってもらえず、両親との身体接触は父親による彼女の心臓検査時だけ。いつも父親に触れてもらうのを望んでいたが、稀なことなので心臓が高揚し、心臓に障害があると勘違いした父親は、学校には登校させず周りから子供たちを遠ざけてしまう。その中で母親を事故で亡くし、孤独の中で彼女は想像力の豊かな、しかし周囲と満足なコミュニケーションがとれない不器用な少女になっていく。そのまま成長して22歳となったアメリ(オドレイ・トトゥ)は実家を出てアパートに住み、モンマルトルにある元サーカス団員経営のカフェで働き始める。ある日、偶然に自室から小さな箱を発見し、中に入っていた子供の宝物を持ち主に返そうとした彼女は、探偵の真似事の末に前の住人を探し、箱を持ち主に返して喜ばれたことで、彼女は人を幸せにすることに喜びを見出すようになる―。

 個性的なセンスと独特のビジュアル、エスプリとユーモアに溢れた作品で(結構ブラックユーモアが多いためゲテモノ映画と間違えられたのか?)、こんなの今まで見たことないという感じでした。敢えて言えば、駅のスピード証明写真機のボックスに定期的に現れる男は一体何者かといったミステリ風味を効かせている点で、ジャン=ジャック・ベネックスの「ディーバ」('81年/仏)を想起しましたが、やはり作品全体がこの監督のオリジナリティを色濃く反映したものとなっているように思います。
個性的なセンスと独特のビジュアル、エスプリとユーモアに溢れた作品で(結構ブラックユーモアが多いためゲテモノ映画と間違えられたのか?)、こんなの今まで見たことないという感じでした。敢えて言えば、駅のスピード証明写真機のボックスに定期的に現れる男は一体何者かといったミステリ風味を効かせている点で、ジャン=ジャック・ベネックスの「ディーバ」('81年/仏)を想起しましたが、やはり作品全体がこの監督のオリジナリティを色濃く反映したものとなっているように思います。 そして何よりもオドレイ・トトゥ演じるアメリがいいです。クレーム・ブリュレの表面をスプーンで割ったり、パリを散歩しサン・マルタン運河で石を投げ水切りをするなど、ささやかな一人遊びと空想にふける毎日を送っていたアメリは、子供時代の宝箱を持主に届けて喜ばれたことで、「この時、初めて世界と調和が取れた気がし」、以降、父親の庭の人形を父親に内緒で世界旅行をさせ父親に旅の楽しさを思い出させるなど、様々な人に関与するようになります。
そして何よりもオドレイ・トトゥ演じるアメリがいいです。クレーム・ブリュレの表面をスプーンで割ったり、パリを散歩しサン・マルタン運河で石を投げ水切りをするなど、ささやかな一人遊びと空想にふける毎日を送っていたアメリは、子供時代の宝箱を持主に届けて喜ばれたことで、「この時、初めて世界と調和が取れた気がし」、以降、父親の庭の人形を父親に内緒で世界旅行をさせ父親に旅の楽しさを思い出させるなど、様々な人に関与するようになります。 そうした彼女にも気になる男性が現れ、それはスピード写真のボックス下に捨てられた他人の証明写真を収集する趣味を持つ若者でしたが、気持ちをどう切り出してよいのかわからず、他人を幸せにしてきた彼女も自分が幸せになる方法は見つからない―でも最後は、アパートの同居人で絵描きである老人らに励まされて...。
そうした彼女にも気になる男性が現れ、それはスピード写真のボックス下に捨てられた他人の証明写真を収集する趣味を持つ若者でしたが、気持ちをどう切り出してよいのかわからず、他人を幸せにしてきた彼女も自分が幸せになる方法は見つからない―でも最後は、アパートの同居人で絵描きである老人らに励まされて...。
 ところで、この映画に雰囲気、どこか既視感があると思ったら、ルイ・マル監督の「地下鉄のザジ」('60年/仏)が髣髴されました。コミカルでシュールなタッチ、好奇心旺盛な女の子、美しいパリの風景と、共通点が多いです(「地下鉄のザジ」は途中から加速的にスラップスティック・コメディ化するため、想起するのにやや間があった)。ネットで調べてみたら、「アメリの元ネタ」などと言われているようで、一昨年['14年]目黒シネマで「名作チョイス 第一弾 ~おかっぱ★Love~」として「地下鉄のザジ」と「アメリ」を組み合わせた上映があったそうです。その際に「おかっぱ割引」として、"おかっぱ頭"の髪型(おかっぱボブ)の人は割引料金だったようです。確かに、"おかっぱ頭"という点でも「地下鉄のザジ」と「アメリ」の主人公、共通していたなあと改めて思った次第です。
ところで、この映画に雰囲気、どこか既視感があると思ったら、ルイ・マル監督の「地下鉄のザジ」('60年/仏)が髣髴されました。コミカルでシュールなタッチ、好奇心旺盛な女の子、美しいパリの風景と、共通点が多いです(「地下鉄のザジ」は途中から加速的にスラップスティック・コメディ化するため、想起するのにやや間があった)。ネットで調べてみたら、「アメリの元ネタ」などと言われているようで、一昨年['14年]目黒シネマで「名作チョイス 第一弾 ~おかっぱ★Love~」として「地下鉄のザジ」と「アメリ」を組み合わせた上映があったそうです。その際に「おかっぱ割引」として、"おかっぱ頭"の髪型(おかっぱボブ)の人は割引料金だったようです。確かに、"おかっぱ頭"という点でも「地下鉄のザジ」と「アメリ」の主人公、共通していたなあと改めて思った次第です。 因みに、ラストで、ザジは約束の時間に叔母さんと母親の待つ駅に行き、母親が地下鉄に乗ったかと聞くとザジはただ「乗らない、疲れちやった」と言って終わるのですが、これをもってザジは地下鉄に乗らず終いだったと思っている人が多いようです。実はパリ滞在中にザジの相手をしていた叔父さんが、店で勃発した大乱闘から避難するために、疲れて眠り込んだザジを抱えて地下鉄に避難したとたんに、ストが解決して地下鉄が動き出したのですが、その時まだザジは眠りこけていたために、自分が地下鉄に乗ったという記憶が無いのです。
因みに、ラストで、ザジは約束の時間に叔母さんと母親の待つ駅に行き、母親が地下鉄に乗ったかと聞くとザジはただ「乗らない、疲れちやった」と言って終わるのですが、これをもってザジは地下鉄に乗らず終いだったと思っている人が多いようです。実はパリ滞在中にザジの相手をしていた叔父さんが、店で勃発した大乱闘から避難するために、疲れて眠り込んだザジを抱えて地下鉄に避難したとたんに、ストが解決して地下鉄が動き出したのですが、その時まだザジは眠りこけていたために、自分が地下鉄に乗ったという記憶が無いのです。 「地下鉄のザジ」は、登場人物らのドタバタがドリフターズのコントみたいで(クレージー・キャッツがこの映画を参考にしたとも)楽しいのですが、大乱闘になだれ込む終盤の頃には食傷気味になり、最初に観た際の評価は★★★ぐらいでした。ただし、今観ると、1960年のパリの街のあちこちの風景を多数切り取っており、これは映像記録として貴重なのではないかと思われ、星半分プラスしました。「アメリ」で観られるその40年後のパリの風景と見比べてみるのもオツかもしれません(観る順番としては「地下鉄のザジ」→「アメリ」がお薦め)。
「地下鉄のザジ」は、登場人物らのドタバタがドリフターズのコントみたいで(クレージー・キャッツがこの映画を参考にしたとも)楽しいのですが、大乱闘になだれ込む終盤の頃には食傷気味になり、最初に観た際の評価は★★★ぐらいでした。ただし、今観ると、1960年のパリの街のあちこちの風景を多数切り取っており、これは映像記録として貴重なのではないかと思われ、星半分プラスしました。「アメリ」で観られるその40年後のパリの風景と見比べてみるのもオツかもしれません(観る順番としては「地下鉄のザジ」→「アメリ」がお薦め)。 「アメリ」●原題:TLE FABULEUX DESTIN D'AMELIE POULAIN●制作年:2001年●制作国:フランス●監督:ジャン=ピエール・ジュネ●製作:クロディー・オサール●脚本:ジャン=ピエール・ジュネ/ギヨーム・ローラン●撮影:ブリュノ・デルボネル●音楽:ヤン・ティルセン●原作:イポリト・ベルナール●時間:122分●出演:オドレイ・トトゥ/マチュー・カソヴィッツ/セルジュ・マーリン/ジャメル・ドゥブーズ/ヨランド・モロー/クレア・モーリア/ドミニク・ピノン/クロディルデ・モレ/リュファス/イザベル・ナンティ/アータス・デ・ペンクアン/(ナレーション)アンドレ・デュソリエ●日本公開:2001/11●配給:アルバトロス・フィルム●最初に観た場所(再見):北千住・シネマブルースタジオ(15-03-25)(評価:★★★★)
「アメリ」●原題:TLE FABULEUX DESTIN D'AMELIE POULAIN●制作年:2001年●制作国:フランス●監督:ジャン=ピエール・ジュネ●製作:クロディー・オサール●脚本:ジャン=ピエール・ジュネ/ギヨーム・ローラン●撮影:ブリュノ・デルボネル●音楽:ヤン・ティルセン●原作:イポリト・ベルナール●時間:122分●出演:オドレイ・トトゥ/マチュー・カソヴィッツ/セルジュ・マーリン/ジャメル・ドゥブーズ/ヨランド・モロー/クレア・モーリア/ドミニク・ピノン/クロディルデ・モレ/リュファス/イザベル・ナンティ/アータス・デ・ペンクアン/(ナレーション)アンドレ・デュソリエ●日本公開:2001/11●配給:アルバトロス・フィルム●最初に観た場所(再見):北千住・シネマブルースタジオ(15-03-25)(評価:★★★★) 「地下鉄のザジ」●原題:ZAZIE DANS LE MÉTRO●制作年:19601年●制作国:フランス●監督・製作:ルイ・マル●脚本:ジャン=ポール・ラプノー/ルイ・マル●撮影:アンリ・レイシ●音楽:フィオレンツォ・カルピ●原作:レーモン・クノー●時間:93分●出演:カトリーヌ・ドモンジョ/フィリップ・ノワレ/カルラ・マルリエ/ヴィットリオ・カプリオーリ/ユベール・デシャン/アニー・フラテリーニ/アントワーヌ・ロブロ/ジャック・デュフィロ/イヴォンヌ・クレシュ/ニコラ・バタイユ/オデット・ピケ●日本公開:1961/02●配給:映配●最初に観た場所(再見):北千住・シネマブルースタジオ(14-06-22)(評価:★★★☆)
「地下鉄のザジ」●原題:ZAZIE DANS LE MÉTRO●制作年:19601年●制作国:フランス●監督・製作:ルイ・マル●脚本:ジャン=ポール・ラプノー/ルイ・マル●撮影:アンリ・レイシ●音楽:フィオレンツォ・カルピ●原作:レーモン・クノー●時間:93分●出演:カトリーヌ・ドモンジョ/フィリップ・ノワレ/カルラ・マルリエ/ヴィットリオ・カプリオーリ/ユベール・デシャン/アニー・フラテリーニ/アントワーヌ・ロブロ/ジャック・デュフィロ/イヴォンヌ・クレシュ/ニコラ・バタイユ/オデット・ピケ●日本公開:1961/02●配給:映配●最初に観た場所(再見):北千住・シネマブルースタジオ(14-06-22)(評価:★★★☆)


 米国人外科医リチャード・ウォーカー(ハリソン・フォード)は、学会で講演するために妻サンドラ(ベティ・バックリー)と共にパリを訪れていた。新婚旅行以来のパリに心を弾ませていた彼だったが、ホテルにチェックインした後、
米国人外科医リチャード・ウォーカー(ハリソン・フォード)は、学会で講演するために妻サンドラ(ベティ・バックリー)と共にパリを訪れていた。新婚旅行以来のパリに心を弾ませていた彼だったが、ホテルにチェックインした後、 スーツケースが空港で誰かのものと取り違えてしまったことに気づく。明日にでも取り替えてもらうよう妻に言ってシャワーを浴びるが、その間に妻はホテルの部屋から忽然と姿を消してしまう。幾つかの関係先に問い合わせるも本気で取り合ってもらえず、逆に妻の浮気を疑われるという不本意な状況の中、ある目撃情報から妻の装身具を路上で発見、彼は妻は誘拐されたと確信し単身で捜索に乗り出す―。
スーツケースが空港で誰かのものと取り違えてしまったことに気づく。明日にでも取り替えてもらうよう妻に言ってシャワーを浴びるが、その間に妻はホテルの部屋から忽然と姿を消してしまう。幾つかの関係先に問い合わせるも本気で取り合ってもらえず、逆に妻の浮気を疑われるという不本意な状況の中、ある目撃情報から妻の装身具を路上で発見、彼は妻は誘拐されたと確信し単身で捜索に乗り出す―。 ロマン・ポランスキー監督(左写真)の1988年作品で、タイトルの「フランティック」(frantic)とは、「気が狂ったような」という意味であり、妻の誘拐事件にパニックになる主人公の姿を指しています。ハリソン・フォードはプライベートで妊娠中の当時の妻メッリサ・マシスンとパリ旅行に行った際にポランスキー監督と出会い、その時にこの作品の企画を打ち明けられ、異郷のパリで主人公の心情に近い立場だったこともあって喜んで出演をOKしたという裏話があります(ポランスキー監督はこの映画にミシェル役で出演したエマニュエル・セニエと'89年に結婚した)。
ロマン・ポランスキー監督(左写真)の1988年作品で、タイトルの「フランティック」(frantic)とは、「気が狂ったような」という意味であり、妻の誘拐事件にパニックになる主人公の姿を指しています。ハリソン・フォードはプライベートで妊娠中の当時の妻メッリサ・マシスンとパリ旅行に行った際にポランスキー監督と出会い、その時にこの作品の企画を打ち明けられ、異郷のパリで主人公の心情に近い立場だったこともあって喜んで出演をOKしたという裏話があります(ポランスキー監督はこの映画にミシェル役で出演したエマニュエル・セニエと'89年に結婚した)。 主人公が誤って持ち帰ったスーツケースは、運び屋の女ミシェル(エマニュエル・セニエ)が米国から持ち込んだ核兵器の起爆装置が隠されたもので、彼女に行き着いた主人公は、その起爆装置の争奪に躍起になるアラブ人グループとそれを阻止せんとするイスラエル側の攻防の中、ミシェルを救ったりしながら自らも妻の捜索にあたる―。
主人公が誤って持ち帰ったスーツケースは、運び屋の女ミシェル(エマニュエル・セニエ)が米国から持ち込んだ核兵器の起爆装置が隠されたもので、彼女に行き着いた主人公は、その起爆装置の争奪に躍起になるアラブ人グループとそれを阻止せんとするイスラエル側の攻防の中、ミシェルを救ったりしながら自らも妻の捜索にあたる―。 この映画は、公開時に結構評価が割れたような気がします。ロマン・ポランスキーにしてはクセが無いオーソドックスなサスペンスですが、ストレートにサスペンスとして見
この映画は、公開時に結構評価が割れたような気がします。ロマン・ポランスキーにしてはクセが無いオーソドックスなサスペンスですが、ストレートにサスペンスとして見 るとやや盛り上がりに欠け、ヒッチコック作品ほどの完成度にも至っていないといのがマイナス評価の理由でしょうか。大掛かりな仕掛けが出てこないこともあって、TVのミステリードラマを見ているような印象もあります。しかしながら、パリの街の雰囲気を自らがエトランゼになった気分で味わえ、ハリソン・フォードの好演もあって、個人的評価としては「○」です。特にハリソン・フォードが、主人公の医師が不測の事態にキリキリ舞いさせられる様を見事に演じていたように思います。
るとやや盛り上がりに欠け、ヒッチコック作品ほどの完成度にも至っていないといのがマイナス評価の理由でしょうか。大掛かりな仕掛けが出てこないこともあって、TVのミステリードラマを見ているような印象もあります。しかしながら、パリの街の雰囲気を自らがエトランゼになった気分で味わえ、ハリソン・フォードの好演もあって、個人的評価としては「○」です。特にハリソン・フォードが、主人公の医師が不測の事態にキリキリ舞いさせられる様を見事に演じていたように思います。 ハリソン・フォードは当時、「インディ・ジョーンズ」シリーズからのイメージ・チェンジを図っており、既に「
ハリソン・フォードは当時、「インディ・ジョーンズ」シリーズからのイメージ・チェンジを図っており、既に「 古典的TVシリーズのリメイク「
古典的TVシリーズのリメイク「 「フランティック」●原題:FRANTIC●制作年:1988年●制作国:アメリカ●監督:ロマン・ポランスキー●製作:ティム・ハンプトン/トム・マウント●脚本:ロマン・ポランスキー/ジェラール・ブラッシュ/ロバート・タウン/ジェフ・グロスン●撮影:ヴィトルド・ソボチンスキ●音楽:エンニオ・モリコーネ●時間:120分●出演:ハリソン・フォード/エマニュエル・セニエ/ベティ・バックリー/ジョン・マホーニー/ジミー・レイ・ウィークス/ジェラール・クライン/パトリス・メレネク/イヴ・レニエ/リシャール・デュー/ドミニク・ピノン/ジャック・シロン//パトリック・フラールシェン/
「フランティック」●原題:FRANTIC●制作年:1988年●制作国:アメリカ●監督:ロマン・ポランスキー●製作:ティム・ハンプトン/トム・マウント●脚本:ロマン・ポランスキー/ジェラール・ブラッシュ/ロバート・タウン/ジェフ・グロスン●撮影:ヴィトルド・ソボチンスキ●音楽:エンニオ・モリコーネ●時間:120分●出演:ハリソン・フォード/エマニュエル・セニエ/ベティ・バックリー/ジョン・マホーニー/ジミー・レイ・ウィークス/ジェラール・クライン/パトリス・メレネク/イヴ・レニエ/リシャール・デュー/ドミニク・ピノン/ジャック・シロン//パトリック・フラールシェン/









 広告会社の重役ロジャー・ソーンヒル(ケーリー・グラント)は、ホテルのロビーでの会合中、偶然別の人物に間違えられて誘拐され、広壮な邸宅に連れていかれる。そこにいたタウンゼントと名乗る男(ジェームズ・メイソン)は彼の事をキャプランというスパイだと決めつけ、ロジャーが否定すると、今度は泥酔運転に見せかけて殺されそうになる。窮地を脱したロジャーは、翌日、タウンゼントが国連で演説することを知り、真相を確かめようと国連ビルへ赴くが、そこに現れたタウンゼントは全くの別人だった。そして、タウンゼントの背中にナイフが突き立てられ、容疑はロジャーにかかってしまう。政府のスパイ機関の会議室では、教授(レオ・G・キャロル)と呼ばれる男を中心に、予想外の事態への対応を協議していた。タウンゼントに成りすました男は、実はヴァンダムという敵のスパイ一味の親
広告会社の重役ロジャー・ソーンヒル(ケーリー・グラント)は、ホテルのロビーでの会合中、偶然別の人物に間違えられて誘拐され、広壮な邸宅に連れていかれる。そこにいたタウンゼントと名乗る男(ジェームズ・メイソン)は彼の事をキャプランというスパイだと決めつけ、ロジャーが否定すると、今度は泥酔運転に見せかけて殺されそうになる。窮地を脱したロジャーは、翌日、タウンゼントが国連で演説することを知り、真相を確かめようと国連ビルへ赴くが、そこに現れたタウンゼントは全くの別人だった。そして、タウンゼントの背中にナイフが突き立てられ、容疑はロジャーにかかってしまう。政府のスパイ機関の会議室では、教授(レオ・G・キャロル)と呼ばれる男を中心に、予想外の事態への対応を協議していた。タウンゼントに成りすました男は、実はヴァンダムという敵のスパイ一味の親 玉で、教授たちは彼らヴァンダム一味の中に自分たちの側のスパイを送り込んでいた。キャプランは教授たちが創造した架空のスパイで、ヴァンダムの注意をキャプランに引き付けることで、味方のスパイを守ろうという作戦だった。スパイ合戦に巻き込まれたロジャーに対し教授たちは同情しつつも、味方のスパイの安全の
玉で、教授たちは彼らヴァンダム一味の中に自分たちの側のスパイを送り込んでいた。キャプランは教授たちが創造した架空のスパイで、ヴァンダムの注意をキャプランに引き付けることで、味方のスパイを守ろうという作戦だった。スパイ合戦に巻き込まれたロジャーに対し教授たちは同情しつつも、味方のスパイの安全の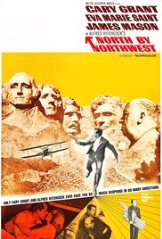
 1959年のアルフレッド・ヒッチコック作品で、小麦畑でのセスナシーンやラシュモア山のシーンなどで知られるように、ヒッチコック唯一のアクション・サスペンスムービーとも言われています。こうした作品は大味になりがちなところを、筋立てとその運びの旨さで飽きさせず、さすがアカデミー賞の脚本賞にノミネートされただけのことはあります。個人的には、アクションもさることながら、ラシュモア山麓に建っている敵のモダンな別荘だとか、ロジャーがオークション会場で敵に囲まれた際に、わざと無茶苦茶な値を付けて警備員に連れ出されることで難を逃れるといったシーンなどが意外と印象に残っていたりします。
1959年のアルフレッド・ヒッチコック作品で、小麦畑でのセスナシーンやラシュモア山のシーンなどで知られるように、ヒッチコック唯一のアクション・サスペンスムービーとも言われています。こうした作品は大味になりがちなところを、筋立てとその運びの旨さで飽きさせず、さすがアカデミー賞の脚本賞にノミネートされただけのことはあります。個人的には、アクションもさることながら、ラシュモア山麓に建っている敵のモダンな別荘だとか、ロジャーがオークション会場で敵に囲まれた際に、わざと無茶苦茶な値を付けて警備員に連れ出されることで難を逃れるといったシーンなどが意外と印象に残っていたりします。
 主演のケーリー・グラント(1904-1986/享年82)は、ジェームズ・ステュアート(1908-1997/享年89)と並ぶヒッチコック映画の代表的俳優であり、「断崖」('41年)、「汚名」('46年)、「泥棒成金」('55年)でヒッチコック映画のまさに"顔"となりましたが、その後、「裏窓」('54年)、「知りすぎていた男」('56年)、「めまい」('58年)でジェームズ・ステュアートが台頭し、立場が逆転した印象もあったところにこの作品に出演し、再びジェームズ・ステュアートに並ぶか、或いは抜き返したという感じではないでしょうか。
主演のケーリー・グラント(1904-1986/享年82)は、ジェームズ・ステュアート(1908-1997/享年89)と並ぶヒッチコック映画の代表的俳優であり、「断崖」('41年)、「汚名」('46年)、「泥棒成金」('55年)でヒッチコック映画のまさに"顔"となりましたが、その後、「裏窓」('54年)、「知りすぎていた男」('56年)、「めまい」('58年)でジェームズ・ステュアートが台頭し、立場が逆転した印象もあったところにこの作品に出演し、再びジェームズ・ステュアートに並ぶか、或いは抜き返したという感じではないでしょうか。 ジェームズ・ステュアートはこの作品のロジャー役を熱望していたそうですが、フランソワ・トリュフォーのヒッチコックに対するインタビュー集『映画術 ヒッチコック/トリュフォー』(山田宏一・蓮實重彦訳、'81年/晶文社)によれば、ヒッチコックは、「
ジェームズ・ステュアートはこの作品のロジャー役を熱望していたそうですが、フランソワ・トリュフォーのヒッチコックに対するインタビュー集『映画術 ヒッチコック/トリュフォー』(山田宏一・蓮實重彦訳、'81年/晶文社)によれば、ヒッチコックは、「 一方、謎の女性を演じている女優はエヴァ・マリー・セイント(1924- )で、当時すでに「波止場」('54年)でアカデミー助演女優賞を受賞していましたが(因みに「波止場」はグレースー・ケリー
一方、謎の女性を演じている女優はエヴァ・マリー・セイント(1924- )で、当時すでに「波止場」('54年)でアカデミー助演女優賞を受賞していましたが(因みに「波止場」はグレースー・ケリー が「裏窓」出演のために役を断り、そのためエヴァ・マリー・セイントに役が回ってきた)、ヒッチコックはこの作品でしかエヴァ・マリー・セイントを使っていません。おそらく、従来のヒッチコ
が「裏窓」出演のために役を断り、そのためエヴァ・マリー・セイントに役が回ってきた)、ヒッチコックはこの作品でしかエヴァ・マリー・セイントを使っていません。おそらく、従来のヒッチコ ック作品のヒロイン像と違って、「007シリーズ」のボンドガールのような役回りであることも関係しているのでしょう。ラストのロジャーと2人で寝台車のベッドで抱き合うシーンなども「007シリーズ」の
ック作品のヒロイン像と違って、「007シリーズ」のボンドガールのような役回りであることも関係しているのでしょう。ラストのロジャーと2人で寝台車のベッドで抱き合うシーンなども「007シリーズ」の エンディングっぽいですが、「007シリーズ」の第1作「
エンディングっぽいですが、「007シリーズ」の第1作「![[北北西に進路を取れ]posterart_.jpeg](http://hurec.bz/book-movie/%5B%E5%8C%97%E5%8C%97%E8%A5%BF%E3%81%AB%E9%80%B2%E8%B7%AF%E3%82%92%E5%8F%96%E3%82%8C%5Dposterart_.jpeg)
 因みに、恒例のヒッチコック自身のカメオ出演は、この作品では冒頭のクレジットタイトルの最後に出てくるバスに乗り遅れる男性であり、探す上ではかなり分かりやすい部類ではないでしょうか(「
因みに、恒例のヒッチコック自身のカメオ出演は、この作品では冒頭のクレジットタイトルの最後に出てくるバスに乗り遅れる男性であり、探す上ではかなり分かりやすい部類ではないでしょうか(「 「北北西に進路を取れ」●原題:NORTH BY NORTHWEST●制作年:1959年●制作国:アメリカ●監督・製作:アルフレッド・ヒッチコック●脚本:アーネスト・レーマン●撮影:ロバート・バークス●音楽:バーナード・ハーマン●時間:136分●出演:ケーリー・グラント/エヴァ・マリー・セイント/
「北北西に進路を取れ」●原題:NORTH BY NORTHWEST●制作年:1959年●制作国:アメリカ●監督・製作:アルフレッド・ヒッチコック●脚本:アーネスト・レーマン●撮影:ロバート・バークス●音楽:バーナード・ハーマン●時間:136分●出演:ケーリー・グラント/エヴァ・マリー・セイント/
 ジェームズ・メイソン/マーティン・ランドー/ジェシー・ロイス・ランディ
ジェームズ・メイソン/マーティン・ランドー/ジェシー・ロイス・ランディ ス/レオ・G・キャロル/ジョセフィン・ハッチンソン/フィリップ・オバー/エドワード・ビンズ/アダム・ウィリアムズ/ロバート・エレンシュタイン●日本公開:1959/09●配給:メトロ・ゴールドウィン・メイヤー●最初に観た場所:高田馬場・ACTミニシアター(88-07-10)(評価:★★★★)●併映:「暗殺者の家」(アルフレッド・ヒッチコック)
ス/レオ・G・キャロル/ジョセフィン・ハッチンソン/フィリップ・オバー/エドワード・ビンズ/アダム・ウィリアムズ/ロバート・エレンシュタイン●日本公開:1959/09●配給:メトロ・ゴールドウィン・メイヤー●最初に観た場所:高田馬場・ACTミニシアター(88-07-10)(評価:★★★★)●併映:「暗殺者の家」(アルフレッド・ヒッチコック)



 ジョン・ワトスン医師の死後50年が経過し、遺言に沿って未発表の記録が公開された。19世紀末のロンドン。私立探偵シャーロック・ホームズ(ロバート・スティーブンス)はロシアのプリマバレリーナから強引な求婚を受ける。ホームズは助手ワトスン(コリン・ブレークリー)とホモ関係にあると偽って求婚から逃れるが、それを知ったワトソンを怒らせる。この騒動から一息ついた彼らの元に、記憶喪失の女性が運び込まれる。ホームズの機転により記憶を取り戻した
ジョン・ワトスン医師の死後50年が経過し、遺言に沿って未発表の記録が公開された。19世紀末のロンドン。私立探偵シャーロック・ホームズ(ロバート・スティーブンス)はロシアのプリマバレリーナから強引な求婚を受ける。ホームズは助手ワトスン(コリン・ブレークリー)とホモ関係にあると偽って求婚から逃れるが、それを知ったワトソンを怒らせる。この騒動から一息ついた彼らの元に、記憶喪失の女性が運び込まれる。ホームズの機転により記憶を取り戻した
 彼女ガブリエル(ジュヌヴィエーヴ・パージュ)の依頼で、ホームズ達は行方不明の彼女の夫を探し始めるが、ホームズの兄マイクロフト(クリストファー・リー)が調査の中止を勧告する。ホームズは表面上忠告に従うふりをするも、ホームズとガブリエルが夫婦、ワトソンが執事と身分を偽って捜査を続ける。スコットランドのネス湖畔を訪れた彼らはガブリエルの夫の死を知る。真相を求めて更に捜査を続け、ネス湖にボートで漕ぎ出した3人の眼前に、伝説の怪物ネッシーが姿を現す―。
彼女ガブリエル(ジュヌヴィエーヴ・パージュ)の依頼で、ホームズ達は行方不明の彼女の夫を探し始めるが、ホームズの兄マイクロフト(クリストファー・リー)が調査の中止を勧告する。ホームズは表面上忠告に従うふりをするも、ホームズとガブリエルが夫婦、ワトソンが執事と身分を偽って捜査を続ける。スコットランドのネス湖畔を訪れた彼らはガブリエルの夫の死を知る。真相を求めて更に捜査を続け、ネス湖にボートで漕ぎ出した3人の眼前に、伝説の怪物ネッシーが姿を現す―。 ビリー・ワイルダーが脚本・監督・製作を担当した1970年公開作。邦題はコナン・ドイルの短編集と同じで、一応、原作もドイルになっていますが、ストーリー内容は原作にはないオリジナルです(そもそも最初にネッシー騒動が起きたのはドイルの死の3年後の1933年のこと)。この作品、当初は、「逆さまの部屋の珍事件」「ロシア人バレリーナの奇妙な事情」「ホームズのビックリ仰天旅
ビリー・ワイルダーが脚本・監督・製作を担当した1970年公開作。邦題はコナン・ドイルの短編集と同じで、一応、原作もドイルになっていますが、ストーリー内容は原作にはないオリジナルです(そもそも最初にネッシー騒動が起きたのはドイルの死の3年後の1933年のこと)。この作品、当初は、「逆さまの部屋の珍事件」「ロシア人バレリーナの奇妙な事情」「ホームズのビックリ仰天旅 行」「裸のハネムーン・カップルにご用心」という4つのエピソードが盛り込まれた4時間近い大作でしたが、公開にあたって配給会社の要請で2時間ほどに編集され、バレリーナからの求婚のエピソードを序盤に残し、謎の美女とネッシーに纏わるエピソード(「ホームズのビックリ仰天旅行」)をメインに据える内容となっています。カットされたフィルムの多くは現存しないそうですが、全体としてはホームズの生活に身近な事件が主だったのが、国家機密に関わる大仰な事
行」「裸のハネムーン・カップルにご用心」という4つのエピソードが盛り込まれた4時間近い大作でしたが、公開にあたって配給会社の要請で2時間ほどに編集され、バレリーナからの求婚のエピソードを序盤に残し、謎の美女とネッシーに纏わるエピソード(「ホームズのビックリ仰天旅行」)をメインに据える内容となっています。カットされたフィルムの多くは現存しないそうですが、全体としてはホームズの生活に身近な事件が主だったのが、国家機密に関わる大仰な事 件がメインストーリーとして残ったため、原題にある"Private Life"からもやや遠くなってしまったようです(マイケル&モリー・ハードウィックによるノベライゼーションが『シャーロック・ホームズの優雅な生活』の邦題で創元推理文庫から刊行されているが、当然のことながら4話中の映像化された部分しか扱っていない)。
件がメインストーリーとして残ったため、原題にある"Private Life"からもやや遠くなってしまったようです(マイケル&モリー・ハードウィックによるノベライゼーションが『シャーロック・ホームズの優雅な生活』の邦題で創元推理文庫から刊行されているが、当然のことながら4話中の映像化された部分しか扱っていない)。 冒頭のバレリーナからの求婚のエピソードも面白いけれど、一部を残したのが結果として取って付けた感じになり、全体のバランスを欠く原因にもなっています。ただ、モリー・モーリンがヴィクトリア女王役で出てくることはさて置いて、全体として、ロンドンの街中の様子やホームズの下宿の様子などにおいてヴィクトリア朝時代の雰囲気をよく伝えており、スコットランドの風景も美しく、ファンの間では必ずしも評価は低くはないようです。
冒頭のバレリーナからの求婚のエピソードも面白いけれど、一部を残したのが結果として取って付けた感じになり、全体のバランスを欠く原因にもなっています。ただ、モリー・モーリンがヴィクトリア女王役で出てくることはさて置いて、全体として、ロンドンの街中の様子やホームズの下宿の様子などにおいてヴィクトリア朝時代の雰囲気をよく伝えており、スコットランドの風景も美しく、ファンの間では必ずしも評価は低くはないようです。 おそらく全体としてコメディタッチであったと思われ、コリン・ブレークリー演じるワトスンがかなり軽い、というか、お調子者のように描かれていますが、ロバート・スティーブンス演じるシャーロックもややエキセントリックな部分が強調された描かれ方をしており、ちょうど最近のTV版「SHERLOCK(シャーロック)」のベネディクト・カンバーバッチ演じるシャーロック像の先駆け的な雰囲気を醸しています。因みに、「SHERLOCK」のプロデューサー、スティーヴン・モファットは、「コメディであるが故に、かえって原作のことがよく分かる」としてこの作品を絶賛しています。
おそらく全体としてコメディタッチであったと思われ、コリン・ブレークリー演じるワトスンがかなり軽い、というか、お調子者のように描かれていますが、ロバート・スティーブンス演じるシャーロックもややエキセントリックな部分が強調された描かれ方をしており、ちょうど最近のTV版「SHERLOCK(シャーロック)」のベネディクト・カンバーバッチ演じるシャーロック像の先駆け的な雰囲気を醸しています。因みに、「SHERLOCK」のプロデューサー、スティーヴン・モファットは、「コメディであるが故に、かえって原作のことがよく分かる」としてこの作品を絶賛しています。 ジュヌヴィエーヴ・パージュ演じるガブリエルは、謎深く、また魅力的に描かれていて作品に華を添えており(むしろ推理という点では、ホームズの方が欺かれ放しであまりぱっとしない)、ビリー・ワイルダーらは、「ボヘミアの醜聞」に出てくる、ホームズが唯一愛した女性であると"推察される"アイリーン・アドラーに匹敵するような女性を、独自に創生したように思われます。因みに「ボヘミアの醜聞」の「SHERLOCK」版である「
ジュヌヴィエーヴ・パージュ演じるガブリエルは、謎深く、また魅力的に描かれていて作品に華を添えており(むしろ推理という点では、ホームズの方が欺かれ放しであまりぱっとしない)、ビリー・ワイルダーらは、「ボヘミアの醜聞」に出てくる、ホームズが唯一愛した女性であると"推察される"アイリーン・アドラーに匹敵するような女性を、独自に創生したように思われます。因みに「ボヘミアの醜聞」の「SHERLOCK」版である「
 全裸でホームズの前に現れ、ラストではホームズが、異国の地でスパイとして処刑される寸前のアイリーンを死地から救ったように見えますが、おそらく、そうした際どい場面や飛躍した結末は、この作品の影響を受けているのではないでしょうか。
全裸でホームズの前に現れ、ラストではホームズが、異国の地でスパイとして処刑される寸前のアイリーンを死地から救ったように見えますが、おそらく、そうした際どい場面や飛躍した結末は、この作品の影響を受けているのではないでしょうか。

 ザ●原作:アーサー・コナン・ドイル●時間:125分●出演:ロバート・スティーブンス/コリン・ブレークリー/ジュヌヴィエーヴ・パージュ/クリストファー・リー/アイリーン・ハンドル/モリー・モーリン/クライヴ・レヴィル/スタンリー・ハロウェイ/タマラ・トゥマノヴァ●日本公開:1971/03●配給:ユナイテッド・アーティスツ(評価:★★★☆)
ザ●原作:アーサー・コナン・ドイル●時間:125分●出演:ロバート・スティーブンス/コリン・ブレークリー/ジュヌヴィエーヴ・パージュ/クリストファー・リー/アイリーン・ハンドル/モリー・モーリン/クライヴ・レヴィル/スタンリー・ハロウェイ/タマラ・トゥマノヴァ●日本公開:1971/03●配給:ユナイテッド・アーティスツ(評価:★★★☆) 「SHERLOCK(シャーロック)(第4話)/ベルグレービアの醜聞」」●原題:SHERLOCK:A SCANDAL IN BELGRAVIA●制
「SHERLOCK(シャーロック)(第4話)/ベルグレービアの醜聞」」●原題:SHERLOCK:A SCANDAL IN BELGRAVIA●制 作年:2011年●制作国:イギリス●演出:ポール・マクギガン●脚本:スティーブン・モファット●出演:ベネディクト・カンバーバッチ/マーティン・フリーマン/ララ・パルバー/ルパート・グレイヴス/ウーナ・スタッブズ/マーク・ゲイティス/アンドリュー・スコット●日本放映:2012/07●放映局:NHK-BSプレミアム(評価:★★★★)
作年:2011年●制作国:イギリス●演出:ポール・マクギガン●脚本:スティーブン・モファット●出演:ベネディクト・カンバーバッチ/マーティン・フリーマン/ララ・パルバー/ルパート・グレイヴス/ウーナ・スタッブズ/マーク・ゲイティス/アンドリュー・スコット●日本放映:2012/07●放映局:NHK-BSプレミアム(評価:★★★★)
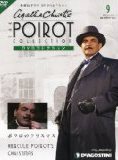


 クリスマスも間近に迫ったある日、ポワロはセントラル・ヒーティングが壊れて困っているところに、ゴーストン・ホールの当主である老富豪シメオン・リーから電話で泊まりの仕事の依頼があり、そちらにはセントラル・ヒーティングがあるとのことで邸へ赴く。彼には、ホールに同居するアルフレッド、国会議員のジョージ、道楽者のハリーの3人の息子と、スペイン人と結婚
クリスマスも間近に迫ったある日、ポワロはセントラル・ヒーティングが壊れて困っているところに、ゴーストン・ホールの当主である老富豪シメオン・リーから電話で泊まりの仕事の依頼があり、そちらにはセントラル・ヒーティングがあるとのことで邸へ赴く。彼には、ホールに同居するアルフレッド、国会議員のジョージ、道楽者のハリーの3人の息子と、スペイン人と結婚 した娘ジェニファーがいた
した娘ジェニファーがいた が、娘は子供を残して亡くなっており、シメオン・リーはこのクリスマスに、ジョージ、ハリーの夫婦に加え、長年離れて暮らしていた末息子ハリーと亡くなった娘の子供、つまり彼にとっての孫娘となるピラールも呼び寄せていた。一族たちが邸を訪れ、互いに再会したり初めて会ったりした一同ではあったが、兄弟の不仲や老人の嫌味な言動などにより、邸内には不穏な空気が流れる。そしてクリスマス・イヴに事件は起こる。老人の部屋から聞こえて来た凄まじい騒音と絶叫。鍵のかかっていたドアを破壊し中に踏み入った一同が目にしたものは、崩れた家具とその横に倒れる老人の血まみれの死体だった。そして、彼が銀行から届けさせていたダイヤが紛失していた―。
が、娘は子供を残して亡くなっており、シメオン・リーはこのクリスマスに、ジョージ、ハリーの夫婦に加え、長年離れて暮らしていた末息子ハリーと亡くなった娘の子供、つまり彼にとっての孫娘となるピラールも呼び寄せていた。一族たちが邸を訪れ、互いに再会したり初めて会ったりした一同ではあったが、兄弟の不仲や老人の嫌味な言動などにより、邸内には不穏な空気が流れる。そしてクリスマス・イヴに事件は起こる。老人の部屋から聞こえて来た凄まじい騒音と絶叫。鍵のかかっていたドアを破壊し中に踏み入った一同が目にしたものは、崩れた家具とその横に倒れる老人の血まみれの死体だった。そして、彼が銀行から届けさせていたダイヤが紛失していた―。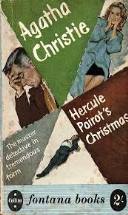

 「名探偵ポワロ」の第42話(第6シーズン第1話)でロング・バージョン。本国放映は1995年1月1日、本邦初放映は1997年12月29日(NHK)。原作はアガサ・クリスティが1938年に発表した長編作品であり、映像化作品の年代設定もほぼ同じ(このTVシリーズが"通し"で大体
「名探偵ポワロ」の第42話(第6シーズン第1話)でロング・バージョン。本国放映は1995年1月1日、本邦初放映は1997年12月29日(NHK)。原作はアガサ・クリスティが1938年に発表した長編作品であり、映像化作品の年代設定もほぼ同じ(このTVシリーズが"通し"で大体 その頃の時代設定になっている)。但し、原作ではジャップ警部は登場しませんが、こちらは、妻の実家ウェールズに帰省していて、地元ウェールズ人のクリスマス期間中に朝から晩まで歌い通しの慣習にウンザリしている彼を、ポワロが"救出"して捜査に当たらせます(奥さんの実家は見せても、当の奥さんの姿は無い。「刑事コロンボ」ではないが、ジャップ警部の奥さんを見せないのがドラマの決まりごとになっているようだ)。
その頃の時代設定になっている)。但し、原作ではジャップ警部は登場しませんが、こちらは、妻の実家ウェールズに帰省していて、地元ウェールズ人のクリスマス期間中に朝から晩まで歌い通しの慣習にウンザリしている彼を、ポワロが"救出"して捜査に当たらせます(奥さんの実家は見せても、当の奥さんの姿は無い。「刑事コロンボ」ではないが、ジャップ警部の奥さんを見せないのがドラマの決まりごとになっているようだ)。 ということで、シメオン・リーは過去に仲間を殺害して富を得る機会を独占した"殺されても仕方がないくらい"悪い奴なのですが(更に、現在においても、孫娘に躙り寄るどうしようもない好色爺なのだが)、あまりに多くの人物から恨みにを買っていそうで、一体誰が犯人なのか判らない―長男、次男にそれぞれの嫁まで絡んで、何となく秘密を抱えていそうなピラールも加え、当面の容疑者は6人に。
ということで、シメオン・リーは過去に仲間を殺害して富を得る機会を独占した"殺されても仕方がないくらい"悪い奴なのですが(更に、現在においても、孫娘に躙り寄るどうしようもない好色爺なのだが)、あまりに多くの人物から恨みにを買っていそうで、一体誰が犯人なのか判らない―長男、次男にそれぞれの嫁まで絡んで、何となく秘密を抱えていそうなピラールも加え、当面の容疑者は6人に。 個人的には、シメオン・リーを殺害したのは、ダイヤ発掘の際に彼に殺害された相方の子孫だと思ったのですが、それが孫娘に化けて邸に潜入したのかと思ったけれど、ちょっと違っていました(ポワロが仄めかした「犯人は内部の者であり外部の者でもある」という言葉に該当するのはその時点で彼女しかいないように思えたのだが、ただ金持ちになりたかっただけか)。
個人的には、シメオン・リーを殺害したのは、ダイヤ発掘の際に彼に殺害された相方の子孫だと思ったのですが、それが孫娘に化けて邸に潜入したのかと思ったけれど、ちょっと違っていました(ポワロが仄めかした「犯人は内部の者であり外部の者でもある」という言葉に該当するのはその時点で彼女しかいないように思えたのだが、ただ金持ちになりたかっただけか)。 結局、「執事が犯人だった」という手に匹敵する"禁じ手"だったような気
結局、「執事が犯人だった」という手に匹敵する"禁じ手"だったような気 がしなくもないですが、しっかり伏線もあったし(ビリアード室でのピラールの言葉など)、密室殺人から始まってお決まりの関係者全員を集めての謎解きまで、プロセスにおいて最後まで愉しめたから、まあ、良しとしようという感じでしょうか(評価はロング・バージョン
がしなくもないですが、しっかり伏線もあったし(ビリアード室でのピラールの言葉など)、密室殺人から始まってお決まりの関係者全員を集めての謎解きまで、プロセスにおいて最後まで愉しめたから、まあ、良しとしようという感じでしょうか(評価はロング・バージョン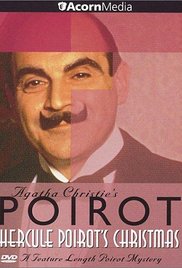




 ポワロはベルギーで「黄金の枝」勲章を叙勲されるジャップ警部に伴い、ブリュッセルを訪れる。警視総監になった旧友のシャンタリエと再会したポワロは、20年前の事件を思い出す。ポワロが警官だった頃、リベラル派の大臣ポール・デルラールが家族や知人たちとの食事後、好物のチョコレートを食べて急死した事件だ。ポワロはシャンタリエと捜査を始めるが、ブシェール警視によって打ち切りを命じられる。それでもポワロは決然と捜査を進めたのだった―。
ポワロはベルギーで「黄金の枝」勲章を叙勲されるジャップ警部に伴い、ブリュッセルを訪れる。警視総監になった旧友のシャンタリエと再会したポワロは、20年前の事件を思い出す。ポワロが警官だった頃、リベラル派の大臣ポール・デルラールが家族や知人たちとの食事後、好物のチョコレートを食べて急死した事件だ。ポワロはシャンタリエと捜査を始めるが、ブシェール警視によって打ち切りを命じられる。それでもポワロは決然と捜査を進めたのだった―。 「名探偵ポワロ」の第39話(第5シーズン第6話)でショート・バージョン。本国放映は1993年2月21日、本邦初放映は1993年7月10日(NHK)。原作はクリスティー文庫『ポアロ登場』(「チョコレートの箱」)、創元推理文庫『ポワロの事件簿2』(「チョコレートの箱」)などに所収。
「名探偵ポワロ」の第39話(第5シーズン第6話)でショート・バージョン。本国放映は1993年2月21日、本邦初放映は1993年7月10日(NHK)。原作はクリスティー文庫『ポアロ登場』(「チョコレートの箱」)、創元推理文庫『ポワロの事件簿2』(「チョコレートの箱」)などに所収。 ポワロがベルギー警察時代に初めて〈私立探偵〉として手がけた事件を描いた作品(警官が捜査打ち切り命令に反して休暇を取って自主的に捜査すれば私立探偵ということになるわけか)。原作では ポワロがヘイステングス相手にロンドンの自室で40年前の事件の回顧談をする設定なのに対し、映像化作品では、ポール・デルラールの死が1913年頃で、20数年前の事件となっています。更に、回顧談の相手がジャップ警部に変更され、どうせ回顧シーンをブリュッセルでロケしなければならないのならば、現在のポワロとついでにジャップ警部もベルギーへ行かせようということになったの
ポワロがベルギー警察時代に初めて〈私立探偵〉として手がけた事件を描いた作品(警官が捜査打ち切り命令に反して休暇を取って自主的に捜査すれば私立探偵ということになるわけか)。原作では ポワロがヘイステングス相手にロンドンの自室で40年前の事件の回顧談をする設定なのに対し、映像化作品では、ポール・デルラールの死が1913年頃で、20数年前の事件となっています。更に、回顧談の相手がジャップ警部に変更され、どうせ回顧シーンをブリュッセルでロケしなければならないのならば、現在のポワロとついでにジャップ警部もベルギーへ行かせようということになったの か、ジャップ警部がベルギーで勲章を受けることになり、奥さんが長旅がダメで同伴できなくて(ジャップ警部の自宅や奥さんの親戚は出てくることがあっても、当の奥さんは姿を見せ
か、ジャップ警部がベルギーで勲章を受けることになり、奥さんが長旅がダメで同伴できなくて(ジャップ警部の自宅や奥さんの親戚は出てくることがあっても、当の奥さんは姿を見せ ないのが、「刑事コロンボ」のコロンボのカミさん同様にドラマのお決まりになっている)、代わりにポワロがジャップ警部に同行するという設定になっています(旅費2人分は予め表彰する側が負担することになっているということか。ベルギー側が、ジャップ警部の功績はポワロによるところ大であることを知っていて、ポワロも招待したのかと思ってしまった。それではジャップ警部に対して嫌味になってしまう)。
ないのが、「刑事コロンボ」のコロンボのカミさん同様にドラマのお決まりになっている)、代わりにポワロがジャップ警部に同行するという設定になっています(旅費2人分は予め表彰する側が負担することになっているということか。ベルギー側が、ジャップ警部の功績はポワロによるところ大であることを知っていて、ポワロも招待したのかと思ってしまった。それではジャップ警部に対して嫌味になってしまう)。

 原作との大きな改変点は、原作でポール・デルラールに想いを寄せる女性ビルジニー・メナール(ポールの亡き妻の従妹)が、何とポワロに想いを寄せているとでも言っていいくらいポワロを信頼しきっている感じになっており、ポワロがいつも身に付けている襟のブローチがその時の彼女からの贈り物であったことが明かされ、同時に、かつてビルジニーへ抱いたポワロ自身の思慕が今も生き続けていることが示唆されます。再会シーンは微妙(個人的には要らなかったかなとも)。夫は薬剤師なのに、息子2人は警官になっているという...(原作では、彼女は女好きのポールに幻滅して修道院に入ってしまうため、ポワロとの恋愛談は無い)。
原作との大きな改変点は、原作でポール・デルラールに想いを寄せる女性ビルジニー・メナール(ポールの亡き妻の従妹)が、何とポワロに想いを寄せているとでも言っていいくらいポワロを信頼しきっている感じになっており、ポワロがいつも身に付けている襟のブローチがその時の彼女からの贈り物であったことが明かされ、同時に、かつてビルジニーへ抱いたポワロ自身の思慕が今も生き続けていることが示唆されます。再会シーンは微妙(個人的には要らなかったかなとも)。夫は薬剤師なのに、息子2人は警官になっているという...(原作では、彼女は女好きのポールに幻滅して修道院に入ってしまうため、ポワロとの恋愛談は無い)。
 ポワロが犯人を見逃すというのは『オリエント急行の殺人』などでそのような例がないわけではないですが珍しい方でしょう(警察時代の事件であるということもあるのか。いや、警察官だったら本来は犯人逮捕は義務であるはずだが)。チョコレートの箱と蓋の組み合わせを間違えた犯人は、赤と緑を十分に区別できない所謂「赤緑色盲」だったのでしょうか?
ポワロが犯人を見逃すというのは『オリエント急行の殺人』などでそのような例がないわけではないですが珍しい方でしょう(警察時代の事件であるということもあるのか。いや、警察官だったら本来は犯人逮捕は義務であるはずだが)。チョコレートの箱と蓋の組み合わせを間違えた犯人は、赤と緑を十分に区別できない所謂「赤緑色盲」だったのでしょうか?  「名探偵ポワロ(第39話)/チョコレートの箱」●原題:AGATHA CHRISTIE'S POIROTⅤ: THE CHOCOLATE BOX ●制作国:イギリス●本国放映:1993/02/21●監督:ピーター・バーバー・フレミング●脚本:アンソニー・ホロヴィッツ●時間:52分●出演:デビッド・スーシェ(ポワロ)/フィリップ・ジャクソン(ジャップ警部)/ジェームズ・クームス(ポール・デルラール)/デヴィッド・デ・キーサー(ガストン・ボージュ)●日本放映:1993/07/10●放映局:NHK(評価:★★★★)
「名探偵ポワロ(第39話)/チョコレートの箱」●原題:AGATHA CHRISTIE'S POIROTⅤ: THE CHOCOLATE BOX ●制作国:イギリス●本国放映:1993/02/21●監督:ピーター・バーバー・フレミング●脚本:アンソニー・ホロヴィッツ●時間:52分●出演:デビッド・スーシェ(ポワロ)/フィリップ・ジャクソン(ジャップ警部)/ジェームズ・クームス(ポール・デルラール)/デヴィッド・デ・キーサー(ガストン・ボージュ)●日本放映:1993/07/10●放映局:NHK(評価:★★★★)