「●「老い」を考える」の インデックッスへ Prev|NEXT ⇒ 【3568】酒井 順子 『老いを読む 老いを書く』
「●「死」を考える」の インデックッスへ 「●よ 養老 孟司」の インデックッスへ 「●PHP新書」の インデックッスへ
老い方、死に方を宗教者、科学者、地域エコノミスト、エッセイストと語る。



『老い方、死に方 (PHP新書) 』['23年]南直哉氏(福井県霊泉寺住職、青森県恐山菩提寺院代)
養老孟司氏が、禅僧の南直哉氏、生物学者の小林武彦氏、地域エコノミストの藻谷浩介氏、エッセイストの阿川佐和子氏の4氏と、老い方、死に方を語り合った対談集。
 第1章の禅僧の南直哉氏は、脱サラして僧侶になり、永平寺で19年修業した後、恐山に行った人で、南氏との対談は、氏の『超越と実存―「無常」をめぐる仏教史』('18年/新潮社)が「小林英雄賞」を受賞した際の選評を養老氏が書いたことが縁のようです。この対談でも、キリスト教と禅の比較や、「諸行無常」をどう考えるかといった宗教的な話になり、「解剖」は僧侶の修行のようなものという話になっていきます。そして最後に南氏は、死を受容する方法、生き方として、「自我を自分の外に向かって広げていく」こともよいとしています。「褒められたい」とか思わないで、ただ単に他人と関わるようにするのがコツで、褒められたいとか「損得」にとらわれると、自分と他人を峻別して自己に固執するようになるとしています(褒められたいと思わないことが、死を受容する方法に繋がるという発想が示唆的で興味深い)。
第1章の禅僧の南直哉氏は、脱サラして僧侶になり、永平寺で19年修業した後、恐山に行った人で、南氏との対談は、氏の『超越と実存―「無常」をめぐる仏教史』('18年/新潮社)が「小林英雄賞」を受賞した際の選評を養老氏が書いたことが縁のようです。この対談でも、キリスト教と禅の比較や、「諸行無常」をどう考えるかといった宗教的な話になり、「解剖」は僧侶の修行のようなものという話になっていきます。そして最後に南氏は、死を受容する方法、生き方として、「自我を自分の外に向かって広げていく」こともよいとしています。「褒められたい」とか思わないで、ただ単に他人と関わるようにするのがコツで、褒められたいとか「損得」にとらわれると、自分と他人を峻別して自己に固執するようになるとしています(褒められたいと思わないことが、死を受容する方法に繋がるという発想が示唆的で興味深い)。
 第2章の生物学者の小林武彦氏は、『生物はなぜ死ぬのか』('21年/講談社現代新書)がベストセラーになったゲノムの再生(若返り)機構を研究する学者で、当対談でも、生物には「老いて死ぬシステムがある」がDNAが壊れなければ、寿命は延びるとしています。老化のメカニズムについては、『なぜヒトだけが老いるのか』('23年/講談社現代新書)でも述べられている通りで、あの本は後半「シニア必要論」となって、やや社会学的色合いになったと個人的には感じたのですが、この対談でも同様の論を展開しています。
第2章の生物学者の小林武彦氏は、『生物はなぜ死ぬのか』('21年/講談社現代新書)がベストセラーになったゲノムの再生(若返り)機構を研究する学者で、当対談でも、生物には「老いて死ぬシステムがある」がDNAが壊れなければ、寿命は延びるとしています。老化のメカニズムについては、『なぜヒトだけが老いるのか』('23年/講談社現代新書)でも述べられている通りで、あの本は後半「シニア必要論」となって、やや社会学的色合いになったと個人的には感じたのですが、この対談でも同様の論を展開しています。
 第3章の地域エコノミストの藻谷浩介氏は、『里山資本主義ー日本経済は「安心の原理」で動く』('13年/角川新書)などの著書があり、養老氏との共著もある人ですが、日本総研の主席研究員で、平成大合併以前の約3200市町村のすべて、海外119カ国を私費で訪問したというスゴイ人です。この対談では、里山資本主義というものを唱え、「ヒト」「モノ(人工物)」「情報」の循環再生を説いています。少子化問題、環境問題、エネルギー問題と話は拡がっていきます。やや話が拡がり過ぎの印象もありますが、そう言えば養老氏は別の本で、都会で死ぬより田舎で死ぬ方が「土に返る」という感覚があっていいと言っていたなあ。
第3章の地域エコノミストの藻谷浩介氏は、『里山資本主義ー日本経済は「安心の原理」で動く』('13年/角川新書)などの著書があり、養老氏との共著もある人ですが、日本総研の主席研究員で、平成大合併以前の約3200市町村のすべて、海外119カ国を私費で訪問したというスゴイ人です。この対談では、里山資本主義というものを唱え、「ヒト」「モノ(人工物)」「情報」の循環再生を説いています。少子化問題、環境問題、エネルギー問題と話は拡がっていきます。やや話が拡がり過ぎの印象もありますが、そう言えば養老氏は別の本で、都会で死ぬより田舎で死ぬ方が「土に返る」という感覚があっていいと言っていたなあ。
 第4章のエッセイスト・作家の阿川佐和子氏は、佐和子氏が父・阿川弘之を看取り、母の介護をした時期があって、その経験を綴ったエッセイ本を出していることから対談の運びとなったと思われます。延命処置をせずに亡くなった父親の死について語る佐和子氏に対し、養老氏は、死んだ本人にしたら自分が死んだかわからないわけだから、「死ぬかもしれない」なんて恐れることはなく、「そのうち目が覚める」と思って死んでいけばいいと説いています。認知症や介護についても話題になっています。
第4章のエッセイスト・作家の阿川佐和子氏は、佐和子氏が父・阿川弘之を看取り、母の介護をした時期があって、その経験を綴ったエッセイ本を出していることから対談の運びとなったと思われます。延命処置をせずに亡くなった父親の死について語る佐和子氏に対し、養老氏は、死んだ本人にしたら自分が死んだかわからないわけだから、「死ぬかもしれない」なんて恐れることはなく、「そのうち目が覚める」と思って死んでいけばいいと説いています。認知症や介護についても話題になっています。
宗教者と根本的な思想の問題について、科学者と生物学的に見た老化について、地域エコノミストと社会的な老いと死について、エッセイスト・作家と肉親の死や介護について語り合っていることになり、養老氏は、「全体として目配りが非常にいいのは、編集者の西村健さんのおかげである」と感謝しています。しかしながら、確かによく言えば全方位的ですが、悪く言えば、ややテーマが拡散した印象もあったように思います(第1章の禅僧の南直哉氏の話がいちばんテーマに近かったように思う)。
養老氏は、多くの自著で、「死は常に二人称」として存在するとし、なぜならば、一人称の死は自分の死なので見ることができず、三人称の死は自分に無関係なためとしていますが、阿川佐和子氏との対談の中で、愛猫の死を〈二人称の死〉としているのが、〈二人称の死〉とはどのようなものかを理解する上で分かりやすかったです。

 また、養老氏は小林武彦氏との対談の中で「大地震が歴史を変える」としています。そう言えば、「プレジデント」2024年8/16号の「どうせ死ぬのになぜ生きるのか」という特集で、養老氏は「私が101歳まで生きたい理由」として、それまでに南海トラフ地震が起きる可能性が高いため、日本がどうなるか見たいからだと述べていました。
また、養老氏は小林武彦氏との対談の中で「大地震が歴史を変える」としています。そう言えば、「プレジデント」2024年8/16号の「どうせ死ぬのになぜ生きるのか」という特集で、養老氏は「私が101歳まで生きたい理由」として、それまでに南海トラフ地震が起きる可能性が高いため、日本がどうなるか見たいからだと述べていました。
「週刊文春」2025年3月13日号「阿川佐和子のこの人に会いたい」ゲスト・南 直哉

《読書MEMO》
●「自己を開くことを繰り返していけば、自ずと死を迎えるための練習にもなるのではないかなという気がするんですね」(南直哉)
●「DNAの修復能力は『寿命の壁』を突破する一つのカギだと考えています」(小林武彦)
●「都会の高齢者ほど、老後の生活に必要なのは『お金』だけだと思い込んでいます。『自然資本』や『人的資本』に目が行かないのですね」(藻谷浩介)
●「(母の)認知症がだいぶ進んでからは、母が頭のなかで思い描く世界に一緒に乗ることにしました。そのほうが介護する側も、される側もおもしろいし、イライラしないし」(阿川佐和子)
●「自分のことなんか、人に理解されなくて当たり前と思ってりゃいい」(養老孟司)



 「週刊文春」2021年4月29日号
「週刊文春」2021年4月29日号 第1章「老いの名作は老いない」では、『
第1章「老いの名作は老いない」では、『 第2章「老いをどう生きるか」では、「百歳老人」が加速的に増えたことで、百歳人は神的な存在ではなくなったとしています(代表例がずっと現役医師だった日野原重明。105歳までに出した多くの「老い本」の表紙が白衣もしくはジャケット姿である)。「定年クライシス」問題にも触れ、源氏鶏太の『停年退職』(1962年)(昔は「停年」と書いた)から重松清の『
第2章「老いをどう生きるか」では、「百歳老人」が加速的に増えたことで、百歳人は神的な存在ではなくなったとしています(代表例がずっと現役医師だった日野原重明。105歳までに出した多くの「老い本」の表紙が白衣もしくはジャケット姿である)。「定年クライシス」問題にも触れ、源氏鶏太の『停年退職』(1962年)(昔は「停年」と書いた)から重松清の『 第3章「老いのライフスタイル」では、30年間「老い本」を書き続け百歳になった
第3章「老いのライフスタイル」では、30年間「老い本」を書き続け百歳になった
 読書案内にもなっていると書きましたが、例えば前田速雄『老いの読書』('22年/新潮選書)のような「死ぬ前に読むべき本」を紹介しているものとは異なる趣旨の本であることは言うまでもなく、「老い本」の変遷を通してこれからの「老い」を考えるヒントを提供している本であったように思います(この本自体が「生き方」本であるわけでもなく、あとは自分で考えろということか)。
読書案内にもなっていると書きましたが、例えば前田速雄『老いの読書』('22年/新潮選書)のような「死ぬ前に読むべき本」を紹介しているものとは異なる趣旨の本であることは言うまでもなく、「老い本」の変遷を通してこれからの「老い」を考えるヒントを提供している本であったように思います(この本自体が「生き方」本であるわけでもなく、あとは自分で考えろということか)。

 黒木登志夫・東京大学名誉教授(略歴下記)
黒木登志夫・東京大学名誉教授(略歴下記)



 大好きな祖母が認知症になってしまい、母と二人で介護に取り組むマンガ家、ニコ。在宅介護が限界を迎えて施設に入居してもらったものの、祖母の認知症の症状がみるみる悪化していった。二人はしょっちゅう呼び出され、かかる費用は月40万円―。
大好きな祖母が認知症になってしまい、母と二人で介護に取り組むマンガ家、ニコ。在宅介護が限界を迎えて施設に入居してもらったものの、祖母の認知症の症状がみるみる悪化していった。二人はしょっちゅう呼び出され、かかる費用は月40万円―。 それぞれの入居金や月額費用、入居条件、さらには認知症の度合いなども示されていますが、認知症の人には「グループホーム」と「特別養護老人ホーム(「特養」)」が向いているとしています。ただし、「特養」は要介護3以上が入居要件であり、したがって、特に大きい病気がなく要介護1・2レベルであれば、「グループホーム」が第1の選択肢になるとにことです。
それぞれの入居金や月額費用、入居条件、さらには認知症の度合いなども示されていますが、認知症の人には「グループホーム」と「特別養護老人ホーム(「特養」)」が向いているとしています。ただし、「特養」は要介護3以上が入居要件であり、したがって、特に大きい病気がなく要介護1・2レベルであれば、「グループホーム」が第1の選択肢になるとにことです。 最近注目されている「(サービス付き)高齢者向け住宅(サ高住)」は、ここで言う「サービス」というのは介護ではなく「安否確認と相談」のことなので、小島美里氏らは「サービスなし高齢者住宅」と呼んでいるとか(各部屋にトイレや水回りがあるのは魅力的だが、認知症に限らず、年を重ねて体の具合が悪くなって要介護度が高くなると、住み続けることが難しくなる場合もある。さらに、費用の支払いが維持できなくなる怖れがあるとういう問題も)。
最近注目されている「(サービス付き)高齢者向け住宅(サ高住)」は、ここで言う「サービス」というのは介護ではなく「安否確認と相談」のことなので、小島美里氏らは「サービスなし高齢者住宅」と呼んでいるとか(各部屋にトイレや水回りがあるのは魅力的だが、認知症に限らず、年を重ねて体の具合が悪くなって要介護度が高くなると、住み続けることが難しくなる場合もある。さらに、費用の支払いが維持できなくなる怖れがあるとういう問題も)。 小島氏が代表理事を務める「えん」は「グループホーム」ですが、最近はグループホームでも「終身」(看取り)が可のところも増えている一方で、グループホームに向かない人もいて、認知症以外の病気が重い人は看護師が常駐する介護医院のような施設の方がいいとしています。また、グループホームは住民票がその地に無いと入居できず、満床のこともあるとのことです。
小島氏が代表理事を務める「えん」は「グループホーム」ですが、最近はグループホームでも「終身」(看取り)が可のところも増えている一方で、グループホームに向かない人もいて、認知症以外の病気が重い人は看護師が常駐する介護医院のような施設の方がいいとしています。また、グループホームは住民票がその地に無いと入居できず、満床のこともあるとのことです。 そのため、第二の選択肢として「介護付き有料老人ホーム」が考えられると。介護付き有料にするメリットは、この金額の中に介護費用もセットになっていることで、「サ高住」に比べて費用は高く見えますが、サ高住のようにそれ以外の費用が天井知らずになることは避けられるとしています(結局「サ高住」って、サービスは部分はほとんど別途持ち出しになるので、何もしなければ普通に何もサービスを受けず暮らしているのとあまり変わらないことになる。「サ高住」の費用の問題は最近よく指摘されることが多い(「
そのため、第二の選択肢として「介護付き有料老人ホーム」が考えられると。介護付き有料にするメリットは、この金額の中に介護費用もセットになっていることで、「サ高住」に比べて費用は高く見えますが、サ高住のようにそれ以外の費用が天井知らずになることは避けられるとしています(結局「サ高住」って、サービスは部分はほとんど別途持ち出しになるので、何もしなければ普通に何もサービスを受けず暮らしているのとあまり変わらないことになる。「サ高住」の費用の問題は最近よく指摘されることが多い(「


 大好きな祖母(婆ル)が認知症になってしまい、母(母ル)と二人で介護に取り組むマンガ家ニコ。人が変わってしまったかのような祖母との生活に疲れ果てたニコたちの前に、認知症の心理学の専門家サトー先生が現れて―。
大好きな祖母(婆ル)が認知症になってしまい、母(母ル)と二人で介護に取り組むマンガ家ニコ。人が変わってしまったかのような祖母との生活に疲れ果てたニコたちの前に、認知症の心理学の専門家サトー先生が現れて―。



 さらには、脳科学とはジャンルは異なり進化学ですが、個人的評価が星1つであるため当時この読書ブログでは単独では取り上げなかった『そんなバカな!―遺伝子と神について』('91年/ちくま新書)の竹内久美子氏をも思い出しました(竹内久美子氏は後に「睾丸のサイズによって日本人が日本型リベラルになるかどうかが左右される」「睾丸の小さい男は子の世話をよくし、イクメン度が高い」という「睾丸決定論」を唱えた御仁)。
さらには、脳科学とはジャンルは異なり進化学ですが、個人的評価が星1つであるため当時この読書ブログでは単独では取り上げなかった『そんなバカな!―遺伝子と神について』('91年/ちくま新書)の竹内久美子氏をも思い出しました(竹内久美子氏は後に「睾丸のサイズによって日本人が日本型リベラルになるかどうかが左右される」「睾丸の小さい男は子の世話をよくし、イクメン度が高い」という「睾丸決定論」を唱えた御仁)。
 岩波明氏は、"脳科学者"の
岩波明氏は、"脳科学者"の


 科学雑誌「ニュートン」の2020年から刊行が続いている本格図鑑シリーズ「Newton大図鑑シリーズ」の第33弾(2024年までに33巻刊行)。心理学系は、『心理学大図鑑』に続いて2巻目ですが、図鑑に心理学系の本があること自体が「ニュートン」らしいかも。
科学雑誌「ニュートン」の2020年から刊行が続いている本格図鑑シリーズ「Newton大図鑑シリーズ」の第33弾(2024年までに33巻刊行)。心理学系は、『心理学大図鑑』に続いて2巻目ですが、図鑑に心理学系の本があること自体が「ニュートン」らしいかも。 Art5「集団にまつわるバイアス」では、勝ち馬に乗って自分も勝者になりたい「バンドワゴン効果」、出身地が同じということだけで贔屓してしまう「内集団バイアス」(出身地に限らずこれはある)、人がたくさんいると行動しなくなる「傍観者効果」etc.。
Art5「集団にまつわるバイアス」では、勝ち馬に乗って自分も勝者になりたい「バンドワゴン効果」、出身地が同じということだけで贔屓してしまう「内集団バイアス」(出身地に限らずこれはある)、人がたくさんいると行動しなくなる「傍観者効果」etc.。

 できる」ことを示した、誰でも分かる学術書、学問としての体系的幸福学の本であるとのことです。
できる」ことを示した、誰でも分かる学術書、学問としての体系的幸福学の本であるとのことです。

 講談社学術文庫版の新版で、今年['25年]のNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」の主人公・蔦屋重三郎(1750-1797/47歳没)について、日本美術史と出版文化の研究者が解説したものです。'88年に日本経済新聞社から刊行され「サントリー学芸賞(芸術・文学部門)」を受賞(著者は当時、東京都美術館学芸員)、'02年に講談社学術文庫として刊行され、今回のドラマ化を機に、巻末に池田芙美氏(サントリー美術館学芸員)の解説を加えて「新版」として刊行されました。
講談社学術文庫版の新版で、今年['25年]のNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」の主人公・蔦屋重三郎(1750-1797/47歳没)について、日本美術史と出版文化の研究者が解説したものです。'88年に日本経済新聞社から刊行され「サントリー学芸賞(芸術・文学部門)」を受賞(著者は当時、東京都美術館学芸員)、'02年に講談社学術文庫として刊行され、今回のドラマ化を機に、巻末に池田芙美氏(サントリー美術館学芸員)の解説を加えて「新版」として刊行されました。 当時の社会を背景に(江戸時代という平和なイメージがあるが、浅間山の噴火と大飢饉、田沼意次と松平定信の抗争など色々あった)、蔦屋重三郎と作家、画家、版元仲間らの様々の人間模様を描き、天明・寛政期に戯作文芸や浮世絵の黄金期を創出した奇才の波瀾の生涯を文化史的・社会史的に捉えた本であり、「単なる出版「業者」ではない「江戸芸術の演出者」としての蔦重の歴史的役割を明らかにしてみせた」(高階秀爾「サントリー学芸賞」選評)との評価を受け、今もって蔦屋重三郎を知るための「必読の定番書」とされている本です。
当時の社会を背景に(江戸時代という平和なイメージがあるが、浅間山の噴火と大飢饉、田沼意次と松平定信の抗争など色々あった)、蔦屋重三郎と作家、画家、版元仲間らの様々の人間模様を描き、天明・寛政期に戯作文芸や浮世絵の黄金期を創出した奇才の波瀾の生涯を文化史的・社会史的に捉えた本であり、「単なる出版「業者」ではない「江戸芸術の演出者」としての蔦重の歴史的役割を明らかにしてみせた」(高階秀爾「サントリー学芸賞」選評)との評価を受け、今もって蔦屋重三郎を知るための「必読の定番書」とされている本です。 最初、新吉原大門(しんよしわらおおもん)前で書店「耕書堂(こうしょどう)」を創業しますが、"吉原外交"を駆使するなどして作家のパトロンとなり、事業拡大に合わせて当時有名版元が軒を連ねていた日本橋通油町(とおりあぶらちょう(現・日本橋大伝馬町))に進出、"黄表紙出版で興隆するも、政治風刺の筆禍事件で身上半減の処分を受けたりもしています。
最初、新吉原大門(しんよしわらおおもん)前で書店「耕書堂(こうしょどう)」を創業しますが、"吉原外交"を駆使するなどして作家のパトロンとなり、事業拡大に合わせて当時有名版元が軒を連ねていた日本橋通油町(とおりあぶらちょう(現・日本橋大伝馬町))に進出、"黄表紙出版で興隆するも、政治風刺の筆禍事件で身上半減の処分を受けたりもしています。
 それにしても、最初のベストセラーは、〈吉原ガイド〉だったわけだなあ。別冊太陽版の方は、なぜか当時の吉原についての解説にかなり重点が置かれて、詳しく解説されています(「遊女の一日」とか)。だだ、講談社学術文庫版では細かすぎる吉原細見などが大きな図版で見ることができるのは有難いです。
それにしても、最初のベストセラーは、〈吉原ガイド〉だったわけだなあ。別冊太陽版の方は、なぜか当時の吉原についての解説にかなり重点が置かれて、詳しく解説されています(「遊女の一日」とか)。だだ、講談社学術文庫版では細かすぎる吉原細見などが大きな図版で見ることができるのは有難いです。 監修は、近世書籍文学史が専門で、講談社学術文庫版にもしばしばその著書からの引用のある中央大学の鈴木俊幸教授(大河ドラマ「べらぼう」の版元考証もしており、一般読者に分かりやすく各書き下ろした『蔦屋重三郎』('24年/平凡社新書)という入門書もある)、また、蔦屋重三郎の人的ネットワークについては、『別冊太陽 蔦屋重三郎の仕事』('95年)掲載の法政大学の田中優子教授(現総長)の原稿「蔦屋重三郎のネットワーク」が再掲載されています。それとは別に、蔦屋重三郎に関係する主要人物10名ほどの解説があり、巻末には歌麿、写楽の解説と大判の浮世絵作品もあって、これはこれで、吉原や蔦屋重三郎が関係した人物・作品について知ることができるものとなっています。
監修は、近世書籍文学史が専門で、講談社学術文庫版にもしばしばその著書からの引用のある中央大学の鈴木俊幸教授(大河ドラマ「べらぼう」の版元考証もしており、一般読者に分かりやすく各書き下ろした『蔦屋重三郎』('24年/平凡社新書)という入門書もある)、また、蔦屋重三郎の人的ネットワークについては、『別冊太陽 蔦屋重三郎の仕事』('95年)掲載の法政大学の田中優子教授(現総長)の原稿「蔦屋重三郎のネットワーク」が再掲載されています。それとは別に、蔦屋重三郎に関係する主要人物10名ほどの解説があり、巻末には歌麿、写楽の解説と大判の浮世絵作品もあって、これはこれで、吉原や蔦屋重三郎が関係した人物・作品について知ることができるものとなっています。

 「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」●脚本:森下佳子●演出:大原拓/深川貴志/小谷高義/新田真三/大嶋慧介●時代考証:山村竜也●版元考証:鈴木俊幸●音楽:ジョン・グ
「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」●脚本:森下佳子●演出:大原拓/深川貴志/小谷高義/新田真三/大嶋慧介●時代考証:山村竜也●版元考証:鈴木俊幸●音楽:ジョン・グ ラム●出演:横浜流星/高橋克実/飯島直子/中村蒼/六平直政/水沢林太郎/渡邉斗翔/小芝風花/正名僕蔵/水野美紀/小野花梨/久保田紗友/珠城りょう/安達祐実/山路和弘/伊藤淳史/山村紅葉/かたせ梨乃/愛希れいか/
ラム●出演:横浜流星/高橋克実/飯島直子/中村蒼/六平直政/水沢林太郎/渡邉斗翔/小芝風花/正名僕蔵/水野美紀/小野花梨/久保田紗友/珠城りょう/安達祐実/山路和弘/伊藤淳史/山村紅葉/かたせ梨乃/愛希れいか/ 中島瑠菜/東野絢香/里見浩太朗/片岡愛之助/三浦りょう太/徳井優/風間俊介/西村まさ彦/芹澤興人/安田顕/井之脇海/木村了/市原隼人/尾美としのり/前野朋哉/橋本淳/鉄拳/冨永愛/真島秀和/奥智哉/高梨臨/生田斗真/寺田心/花總まり/映美くらら/渡辺謙/宮沢氷魚/中村隼人/原田泰造/吉沢悠/石坂浩二/相島一之/矢本悠馬/綾瀬はるか●放映:2024/01~2024/12(全50回)●放送局:NHK
中島瑠菜/東野絢香/里見浩太朗/片岡愛之助/三浦りょう太/徳井優/風間俊介/西村まさ彦/芹澤興人/安田顕/井之脇海/木村了/市原隼人/尾美としのり/前野朋哉/橋本淳/鉄拳/冨永愛/真島秀和/奥智哉/高梨臨/生田斗真/寺田心/花總まり/映美くらら/渡辺謙/宮沢氷魚/中村隼人/原田泰造/吉沢悠/石坂浩二/相島一之/矢本悠馬/綾瀬はるか●放映:2024/01~2024/12(全50回)●放送局:NHK






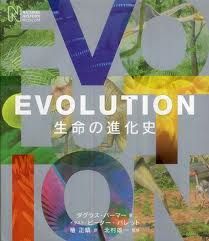

 このシリーズはほとんどが日本人の学者による監修となっています。本書の監修者は国立科学博物館・地学研究部の生命進化史研究グループ長の甲能直樹氏です。「NHKスペシャル 恐竜超世界」で知られる
このシリーズはほとんどが日本人の学者による監修となっています。本書の監修者は国立科学博物館・地学研究部の生命進化史研究グループ長の甲能直樹氏です。「NHKスペシャル 恐竜超世界」で知られる



 の映画「オッペンハイマー」('23年/米)でもプリンストン高等研究所の庭での二人の"接触が"が描かれていた)。南部はアインシュタインの"追っかけ"のような志向があり、オッペンハイマーに無断でアインシュタインに会いに行ったりして(散策するアインシュタインを車から隠し撮りしたりしている)、当時研究所員からも畏怖されていたオッペンハイマーの機嫌を損ねるといったことがあったようです。
の映画「オッペンハイマー」('23年/米)でもプリンストン高等研究所の庭での二人の"接触が"が描かれていた)。南部はアインシュタインの"追っかけ"のような志向があり、オッペンハイマーに無断でアインシュタインに会いに行ったりして(散策するアインシュタインを車から隠し撮りしたりしている)、当時研究所員からも畏怖されていたオッペンハイマーの機嫌を損ねるといったことがあったようです。 1991年に70歳で定年、シカゴ大学の名誉教授となりますが、驚くのは、1999年と2004年に、それぞれ南部が生み出した「自発的対称性の破れ」の理論および「量子色力学」の理論をベースとした研究でノーベル物理学賞が授与されているとのことで、南部の2008年の授賞は遅すぎたかもしれません(これも南部がその理論に影響を与えた益川敏英、小林誠との共
1991年に70歳で定年、シカゴ大学の名誉教授となりますが、驚くのは、1999年と2004年に、それぞれ南部が生み出した「自発的対称性の破れ」の理論および「量子色力学」の理論をベースとした研究でノーベル物理学賞が授与されているとのことで、南部の2008年の授賞は遅すぎたかもしれません(これも南部がその理論に影響を与えた益川敏英、小林誠との共 同授賞)。生きている間に受賞できたのは良かったですが、奥さんの健康上の理由と自身の体力の問題で授賞式に出られなかったのは残念でした(シカゴ大学にて授与され、記念講演も行った。そう言えば、本書にも出てくる南部の恩師で'65年に物理学賞を受賞した朝永振一郎は、酒で酩酊し風呂場で転んで骨折したため(朝永自身、エッセイに書いている)在日本スウェーデン大使館で賞状とメダルを受け取ったということがあった)。
同授賞)。生きている間に受賞できたのは良かったですが、奥さんの健康上の理由と自身の体力の問題で授賞式に出られなかったのは残念でした(シカゴ大学にて授与され、記念講演も行った。そう言えば、本書にも出てくる南部の恩師で'65年に物理学賞を受賞した朝永振一郎は、酒で酩酊し風呂場で転んで骨折したため(朝永自身、エッセイに書いている)在日本スウェーデン大使館で賞状とメダルを受け取ったということがあった)。 本書は、冒頭にも述べたように、南部陽一郎の生涯の「物語」と並行して、素粒子物理学および原子核物理学の発展の歴史を様々な理論を解説しながら辿るものになっていますが、南部洋一郎自身が素粒子について一般向けに書いたものとしては、同じくブルーバックスに『クォーク―素粒子物理の最前線』('81年)があり、素粒子物理学が過去50年間にどう発展し、現在何がわかっているか、物理学者がどんな考え方を辿ってその理論に到達したのかを、相対性理論との関係などを説明しながら、具体的かつ系統的に解説しています。その17年後には、同じくブルーバックで本書の第2版にあたる『クォーク―素粒子物理はどこまで進んできたか』('98年)も刊行されています。
本書は、冒頭にも述べたように、南部陽一郎の生涯の「物語」と並行して、素粒子物理学および原子核物理学の発展の歴史を様々な理論を解説しながら辿るものになっていますが、南部洋一郎自身が素粒子について一般向けに書いたものとしては、同じくブルーバックスに『クォーク―素粒子物理の最前線』('81年)があり、素粒子物理学が過去50年間にどう発展し、現在何がわかっているか、物理学者がどんな考え方を辿ってその理論に到達したのかを、相対性理論との関係などを説明しながら、具体的かつ系統的に解説しています。その17年後には、同じくブルーバックで本書の第2版にあたる『クォーク―素粒子物理はどこまで進んできたか』('98年)も刊行されています。




 植田正治(うえだ しょうじ、1913-2000/87歳没)は、出生地である鳥取県境港市を拠点に70年近く活動した写真家で、数ある作品の中でも、鳥取砂丘を舞台にした「砂丘シリーズ」はよ
植田正治(うえだ しょうじ、1913-2000/87歳没)は、出生地である鳥取県境港市を拠点に70年近く活動した写真家で、数ある作品の中でも、鳥取砂丘を舞台にした「砂丘シリーズ」はよ く知られています。人物をオブジェのように配する構図や、逆に物を擬人化するなどの特徴を持ち、土門拳や名取洋之助の時代以降の主観や演出を重視した日本の写真傾向と合致したとのこと(Wikipediaより)。この人の写真を見ていると70年代頃に「アサヒカメラ」(2008年廃刊)などに掲載されていた写真を想起させられます。
く知られています。人物をオブジェのように配する構図や、逆に物を擬人化するなどの特徴を持ち、土門拳や名取洋之助の時代以降の主観や演出を重視した日本の写真傾向と合致したとのこと(Wikipediaより)。この人の写真を見ていると70年代頃に「アサヒカメラ」(2008年廃刊)などに掲載されていた写真を想起させられます。 一方、その後に大きく興隆する広告写真、ファッション写真とも親近性があったこともあり、広く注目されるようになります。個人的にも、作品の中にはバブル期のサントリーの広告を思い出させるものがあったように思います(最近では上田義彦氏のサント
一方、その後に大きく興隆する広告写真、ファッション写真とも親近性があったこともあり、広く注目されるようになります。個人的にも、作品の中にはバブル期のサントリーの広告を思い出させるものがあったように思います(最近では上田義彦氏のサント リー・ウーロン茶の広告を想起させる)。また、1994年には福山雅治のシングル「HELLO」のCDジャケットを手がけています。その間も次第に評価は高まり、その評価はヨーロッパやアメリカにも及びました。海外の写真家で言うと、アンリ・カルティエ=ブレッソンなどと似ている点もあるように思います(絵画まで範囲を拡げれば、キリコの画風が最も近いかも)。
リー・ウーロン茶の広告を想起させる)。また、1994年には福山雅治のシングル「HELLO」のCDジャケットを手がけています。その間も次第に評価は高まり、その評価はヨーロッパやアメリカにも及びました。海外の写真家で言うと、アンリ・カルティエ=ブレッソンなどと似ている点もあるように思います(絵画まで範囲を拡げれば、キリコの画風が最も近いかも)。


 故郷の鳥取県伯耆町に植田正治写真美術館がありますが、何回か東京でも写真展が開かれたことがあり、東京ステーションギャラリーが1993 年に生前最大規模となる回顧展「植田正治の写真」を開催し、さらに没後の2005年12月から2006年2月にかけて東京都写真美術館が開館10周年記念として写真展を開催しています。そして再び東京ステーションギャラリーにて、2013年10月から2014年1月にかけて「生誕100年!植田正治のつくりかた」と銘打った写真展が開催し、公式カタログとして『植田正治のつくりかた』('13年9月/青幻舎)が刊行されています。
故郷の鳥取県伯耆町に植田正治写真美術館がありますが、何回か東京でも写真展が開かれたことがあり、東京ステーションギャラリーが1993 年に生前最大規模となる回顧展「植田正治の写真」を開催し、さらに没後の2005年12月から2006年2月にかけて東京都写真美術館が開館10周年記念として写真展を開催しています。そして再び東京ステーションギャラリーにて、2013年10月から2014年1月にかけて「生誕100年!植田正治のつくりかた」と銘打った写真展が開催し、公式カタログとして『植田正治のつくりかた』('13年9月/青幻舎)が刊行されています。 "公式カタログ"と言っても実質的には大型書籍と言えるもので、『吹き抜ける風:植田正治写真集』が163ページであるのに対し、こちらは224ページとそれを上回るページ数になっています(何れもソフトカバー)。『吹き抜ける風』が刊行された時点で植田正治はすでに亡くなっているため、網羅している写真のうち代表的な作品は重なりますが、『植田正治のつくりかた』の方が「砂丘シリーズ」以外の多様な写真を載せているように思われます(他界する直前に撮られた写真をフィルムから現像したものもある)。
"公式カタログ"と言っても実質的には大型書籍と言えるもので、『吹き抜ける風:植田正治写真集』が163ページであるのに対し、こちらは224ページとそれを上回るページ数になっています(何れもソフトカバー)。『吹き抜ける風』が刊行された時点で植田正治はすでに亡くなっているため、網羅している写真のうち代表的な作品は重なりますが、『植田正治のつくりかた』の方が「砂丘シリーズ」以外の多様な写真を載せているように思われます(他界する直前に撮られた写真をフィルムから現像したものもある)。 とする一連の「綴り方・私の家族」シリーズも、ともに植田の自宅からほど近い弓ヶ浜海岸で撮影されたということで、それを評論家が砂丘と勘違いしてしまったのですが、その勘違いの元となったのは、植田自身がそれらを収めた写真集を「砂丘」のタイトルで一括りにしたことにあるということです。
とする一連の「綴り方・私の家族」シリーズも、ともに植田の自宅からほど近い弓ヶ浜海岸で撮影されたということで、それを評論家が砂丘と勘違いしてしまったのですが、その勘違いの元となったのは、植田自身がそれらを収めた写真集を「砂丘」のタイトルで一括りにしたことにあるということです。 因みに、俳優の佐野史郎が植田正治のファンであり、「もう、作品がいい悪いだけじゃないんですよね。植田さんの才能、技術だけじゃなく、お人柄までも含めて、全てが写真に出ている感じがします」と語っています。佐野史郎は妖怪、ゴジラ、ドラキュラなどのマニアックなファンとしても有名ですが(ゴジラ映画に登場する博士役に憧れて俳優を志した)、かつて画家を目指して美術大学を受験したりした人で、ダリ、マグリットなどのシュールレアリスムの画家が大好きで、漫画家のつげ義春にも造詣が深く、写真家への関心も同じ視覚芸術としての流れでしょうか。
因みに、俳優の佐野史郎が植田正治のファンであり、「もう、作品がいい悪いだけじゃないんですよね。植田さんの才能、技術だけじゃなく、お人柄までも含めて、全てが写真に出ている感じがします」と語っています。佐野史郎は妖怪、ゴジラ、ドラキュラなどのマニアックなファンとしても有名ですが(ゴジラ映画に登場する博士役に憧れて俳優を志した)、かつて画家を目指して美術大学を受験したりした人で、ダリ、マグリットなどのシュールレアリスムの画家が大好きで、漫画家のつげ義春にも造詣が深く、写真家への関心も同じ視覚芸術としての流れでしょうか。


 「金沢」は、自分が2歳から小学校2年までと、小学校6年から高校1年まで金沢に住んでいたため、昭和30年代、40年代の金沢を知る身であり、懐かしく写真を見ました。目次が、地理的位置、樺沢の歴史、加賀気質、工芸と伝統、明日への問題、となっているように、シリーズの企画意図が視覚教育の要望に応えようとしたものだったらしく、観光より生活(社会)に視点が置かれていて、暮らしに近い写真が多く収められています。
「金沢」は、自分が2歳から小学校2年までと、小学校6年から高校1年まで金沢に住んでいたため、昭和30年代、40年代の金沢を知る身であり、懐かしく写真を見ました。目次が、地理的位置、樺沢の歴史、加賀気質、工芸と伝統、明日への問題、となっているように、シリーズの企画意図が視覚教育の要望に応えようとしたものだったらしく、観光より生活(社会)に視点が置かれていて、暮らしに近い写真が多く収められています。 兼六園や金沢城、尾山神社なども懐かしいことは懐かしいですが、小学校、中学校に通う際にそれに沿って歩いた長い「土塀」の写真がことさら懐かしいです(小学校は今は無き「長土塀小学校」で、「長土塀」という町名は今もある。ただし、土塀は「長町」にもよく見られ、上の左右の写真はいずれも長町にある武家屋敷と土塀)。
兼六園や金沢城、尾山神社なども懐かしいことは懐かしいですが、小学校、中学校に通う際にそれに沿って歩いた長い「土塀」の写真がことさら懐かしいです(小学校は今は無き「長土塀小学校」で、「長土塀」という町名は今もある。ただし、土塀は「長町」にもよく見られ、上の左右の写真はいずれも長町にある武家屋敷と土塀)。 金沢と言えば次は能登。能登半島沖地震からちょうど1年ですが、復興の遅れが心配です(阪神淡路大震災における神戸の復興の目覚ましいスピードなどと比べるとあまりに遅い)。
金沢と言えば次は能登。能登半島沖地震からちょうど1年ですが、復興の遅れが心配です(阪神淡路大震災における神戸の復興の目覚ましいスピードなどと比べるとあまりに遅い)。 た。ヤセの断崖は、映画「
た。ヤセの断崖は、映画「 因みに加賀屋は、震災以降現在も休業が続いていますが、1週間ほど前['24年12月25日]、'26年冬に営業を再開するとの発表がありました。被災した現在の4棟(全233室)は再建せず、敷地内の別の場所に、新しく5階建ての新館を建てるとしています。デザインは建築家の隈研吾氏で、部屋数は50室、部屋は全室オーシャンビューで、温泉の露天風呂や半露天風呂つきを計画していているとのこと。行ってみたいけれど、庶民には簡単に泊まれる宿泊料金帯ではないかもしれません(外国人観光客で埋まりそう)。金沢の懐かしい場所の写真の話から、加賀屋の新館の話になってしまいました。
因みに加賀屋は、震災以降現在も休業が続いていますが、1週間ほど前['24年12月25日]、'26年冬に営業を再開するとの発表がありました。被災した現在の4棟(全233室)は再建せず、敷地内の別の場所に、新しく5階建ての新館を建てるとしています。デザインは建築家の隈研吾氏で、部屋数は50室、部屋は全室オーシャンビューで、温泉の露天風呂や半露天風呂つきを計画していているとのこと。行ってみたいけれど、庶民には簡単に泊まれる宿泊料金帯ではないかもしれません(外国人観光客で埋まりそう)。金沢の懐かしい場所の写真の話から、加賀屋の新館の話になってしまいました。


