「●労働経済・労働問題」の インデックッスへ Prev|NEXT ⇒ 【2278】 川人 博 『過労自殺 第二版』
「●若者論」の インデックッスへ 「●濱口 桂一郎」の インデックッスへ 「●ちくま新書」の インデックッスへ
日本的雇用の在り方に影響力を持ち得る視座を提起。第5編の提案部分の更なる深耕に期待。



『日本の雇用と中高年 (ちくま新書)』『若者と労働 「入社」の仕組みから解きほぐす (中公新書ラクレ)
』濱口 桂一郎 氏(社会保険労務士稲門会「講演と懇親の夕べ」2012.12.1講演テーマ「日本の雇用終了-労働局あっせん事例の分析」)
同著者の『新しい労働社会』(岩波新書)、『日本の雇用と労働法』(日経文庫)、『若者と労働』(中公新書ラクレ)に続く新書第4弾であり、日本の雇用社会は仕事に人を割り振る「ジョブ型」ではなく、人に仕事を割り振る「メンバーシップ型」であって、それが時代の変化とともに歪みを生じさせているとの現状認識が出発点となっている点はこれまでと同様です。その意味ではこれまでの著書の「続編」との印象もありますが、著者の場合、意識して一作ごとに分析の切り口やフォーカスする論点の比重のかけ方を変えているようです。
前著『若者と労働』では日本の若者労働問題を取り上げ、国際比較と歴史的分析をもとにその本質的構造を解き明かしてみせたのに対し、今回は、日本の雇用問題の中心である中高年問題、つまり、日本の中高年労働者がその人件費の高さゆえに企業から排出されやすく、排出されると再就職しにくいという問題を取り上げ、戦後日本の雇用システムと雇用政策の流れを概観しています。
第1章から第4章において、日本の中高年問題の文脈を雇用システムの歴史的変遷に探り、続いて、日本型雇用において労働法や判例法理がどのように確立しどのような高齢者政策がとられてきたのか、また、年齢差別禁止政策という観点からはどのような歴史的変遷を辿ってきたのかを解説するとともに、「管理職」問題、中高年を狙い撃ちした成果主義や最近また議論が再燃しているホワイトカラー・エグゼンプションなど近年のトピカルな問題にまで言及しています。
著者は、中高年や若者を巡る雇用問題を「中高年vs.若者」という対立軸で捉えてどちらが損か得かで論じることは不毛であり、雇用問題は雇用システム改革の問題として捉えることが肝要だとしており、ここまでに書かれている歴史的変遷も、それ自体「人事の教養」として知っておいて無駄ではないかと思いますが、ここでは、日本型雇用システムの歴史を探ることでその本質や特徴を浮き彫りにするという意図のもとに、これだけの紙数を割いているようです。
そして、最終章である第5章において、前著『若者と労働』で若者雇用問題への処方箋として提示した「ジョブ型正社員」というコンセプトが、本書のテーマである中高年の救済策にもなるとしています。「ジョブ型正社員」の是非を巡る労使間の議論が、解雇規制緩和への期待や懸念が背景となってしまっている現状の議論の水準を超えて、労使双方にとって有意義な雇用システム改革という新展望の上に展開されているという点では、本書にも紹介されている1995年の日経連の『新時代の「日本的経営」』にも匹敵する、日本的雇用の在り方に影響力を持ち得る視座を提起しているように思われました。
一方で、「ジョブ」の概念が明確でないのが日本の雇用社会の特質であるとしてきた著者のこれまでの論調の中で、「ジョブ型正社員」というものを今後どう構築していくかという課題は、その実現においてクリアにしなければならない多くの問題を孕んでいるようにも思えました。例えば、経団連の「人事賃金センター」は、かつて日経連時代には「職務分析センター」と呼ばれていたが、そうした名称が用いられなくなったこと自体が、「ジョブ」を規定しそれを日本的雇用の中で活用していくことの"挫折"とその困難を物語っているのではないかと。著者ももちろん、その困難さはよく解ったうえで、問題提起しているわけですが...。
問題解決の一つの視点として、戦後の日本型雇用システムが企業内で労働者とその家族の生活をまかなうことを追求した結果、公的社会保障制度としてまかなわれるべきものが「メンバーシップ型」正社員の処遇制度の中に織り込まれ、それが中高年の年功賃金につながった―つまり、労働も福祉も一緒くたにして企業が負うことになったことを挙げており、これはなかなか穿った見方であるように思いました。個人的には、企業の福祉からの撤退を訴えた橘木俊詔氏の『企業福祉の終焉―格差の時代にどう対応すべきか』(2005/04 中公新書)を想起しました。橘木氏は、報酬比例の保険料徴収及び給付方式となっている厚生年金保険など国の制度も含め、企業福祉に社会的格差の拡大原因を認めています。
しかし、終身雇用をベースにした長期決済型の年功制を維持している間も、生産性に見合わない高給取りの中高年が真っ先にリストラ対象となった折も、そうした本質の部分について議論されることが無かった(能力主義であるとか現状において生産性に比べて賃金が割高であるとかいう理屈の上に韜晦されてしまった)のは、「メンバーシップ型」という概念が概念として対象化されず、それでいて企業が、何よりも人事部を中心にその(メンバーシップ型という考え方の)中にどっぷり浸り切っていたためであり、こうして「メンバーシップ型」として概念化し対象化すること自体、意義のあることのように思います。
では、今後の施策面を考えるとどうでしょうか。企業における中高年の人事施策において、専門職制度の導入というのが一時流行り、今でも多くの企業がその制度を維持しています。これが建前としては、今言っているところの「ジョブ型」でありながら、実態としては単なる「非ライン(管理職)」の処遇の仕方であったことは間違いないかと思われます。こうした実態がある中での「ジョブ型正社員」の新たな位置づけというのはどのようになっていくのか、これは、企業によっては「専門職」が(かつてサラリーマン漫画に描かれたような「窓際族」はすでに実態として多くの企業ではほぼ"絶滅"しているとみるにしても)、一般職の延長での仕事しかしていない「エキスパート」が主なのか、その中に相当数の「スペシャリスト」「プロフェッショナル」と呼ぶべき、企業にとって付加価値貢献度の高い、企業経営を存続させていくべきで必要欠くべからざる人材が含まれているのかによっても違ってくるように思われます。
日本の若者雇用問題の解決策として、入り口のところで、「ジョブ型正社員」をスタンダードとしてみてはという提案は、それがどれぐらいのスピードで定着していくかは分かりませんが、かつて牧野昇(1921-2007)が『新・雇用革命』(1999/11 経済界)で指摘した、日本のサラリーマンが「社長レースからだれも降りない理由」は「負けても失うものが意外に少ないから」との指摘―つまり、「ゼネラリストとして成功しないより、スペシャリストとして成功した方が、それは幸福だろう。しかし、ゼネラリストとして成功しないことと、スペシャリストとして成功しないことの間には、大きな格差がある。だからスペシャリストを志向することはリスクなのである。少なくとも今まではそうであった」という、その「今まで」の在り方を見直すことにつながっていくでしょう。それに先立つこと12年前に津田眞澂(1926-2005)は『人事革命』(1987/05 ごま書房)において、「専門職能を持たない従来型のゼネラリストは不要になる」と予言しています。
「ジョブ型正社員」を若者雇用に適用するにしても、従来の新卒採用面接の考え方のパラダイム変換が求められたりはするでしょうが(実際殆どの企業がそうしたパラダイム変換を経ることなく今日に至っているのではないか)、それでも処方箋としては中高年問題の解決において「ジョブ型正社員」の考え方を採り入れるよりはシンプルなように思われ、逆に言えば、それだけ、中高年の方は問題が複雑ではないかという気がします。
その意味では、本書第5章を深耕した著者の次著を期待したいと思いますが、こうした期待は本来著者一人に委ねるものではなく、実務者も含めた様々な人々の議論の活性化を期待すべきものなのでしょう。そうした議論に加わる切っ掛けとして、企業内の人事パーソンを初め実務に携わる人が本書を手にするのもいいのではないでしょうか。
 また、本書は著者の新書シリーズ第4弾ですが、第3弾にあたる『若者と労働』(中公新書ラクレ)もお薦めです。若者向けにブラック企業問題などにも触れていますが、それはとっかかりにすぎず、むしろ「新卒一括採用」という我々が当たり前に考えている仕組みが、グローバルな視点でみるといかに特殊なのものであるか分かるとともに、この「新卒一括採用」が日本型雇用システムの根底を形作っていることがよく理解できる本です。当たり前とみられすぎて再検証されにくい分、「新卒一括採用」の方が「中高年」の問題より根が深いかも―と思ったりもしました。
また、本書は著者の新書シリーズ第4弾ですが、第3弾にあたる『若者と労働』(中公新書ラクレ)もお薦めです。若者向けにブラック企業問題などにも触れていますが、それはとっかかりにすぎず、むしろ「新卒一括採用」という我々が当たり前に考えている仕組みが、グローバルな視点でみるといかに特殊なのものであるか分かるとともに、この「新卒一括採用」が日本型雇用システムの根底を形作っていることがよく理解できる本です。当たり前とみられすぎて再検証されにくい分、「新卒一括採用」の方が「中高年」の問題より根が深いかも―と思ったりもしました。




 『日本の雇用終了―労働局あっせん事例から』(2012年)
『日本の雇用終了―労働局あっせん事例から』(2012年)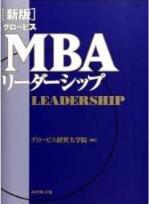

![グロービスMBAマネジメント・ブック[改訂3版].jpg](http://hurec.bz/book-movie/%E3%82%B0%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9MBA%E3%83%9E%E3%83%8D%E3%82%B8%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%BB%E3%83%96%E3%83%83%E3%82%AF%EF%BC%BB%E6%94%B9%E8%A8%823%E7%89%88%EF%BC%BD.jpg)
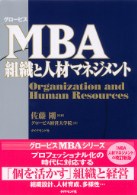

 林 明文 氏(トランストラクチャ代表取締役)
林 明文 氏(トランストラクチャ代表取締役)



 テキサス州・オースティンを本拠とする米国の大手自然食品スーパー「ホールフーズ・マーケット」の経営者が、自らが30年以上にわたって実践し成功を収めている経営スタイル「意識の高い資本主義」(コンシャス・キャピタリズム)を紹介した本です(原題:Conscious Capitalism: Liberating the Heroic Spirit of Business(2013)
テキサス州・オースティンを本拠とする米国の大手自然食品スーパー「ホールフーズ・マーケット」の経営者が、自らが30年以上にわたって実践し成功を収めている経営スタイル「意識の高い資本主義」(コンシャス・キャピタリズム)を紹介した本です(原題:Conscious Capitalism: Liberating the Heroic Spirit of Business(2013) )(米国を中心に現在300以上の拠点を持つこのスーパーは、1978年、当時25歳の大学中退者ジョン・マッキー(John Mackey)と恋人のRene Lawson(当時21歳)が、家族から借りた資金45,000米ドルで開店した小さな自然食品から始まった。因みにこの会社は、ゲイリー・ハメルの『経営の未来』('08年/日本経済新聞出版社)で、経営イノベーションに成功した企業事例として紹介されている3社の内の筆頭にきており、続く2社は、W・L・ゴア(ゴアテックス)とグーグル)。
)(米国を中心に現在300以上の拠点を持つこのスーパーは、1978年、当時25歳の大学中退者ジョン・マッキー(John Mackey)と恋人のRene Lawson(当時21歳)が、家族から借りた資金45,000米ドルで開店した小さな自然食品から始まった。因みにこの会社は、ゲイリー・ハメルの『経営の未来』('08年/日本経済新聞出版社)で、経営イノベーションに成功した企業事例として紹介されている3社の内の筆頭にきており、続く2社は、W・L・ゴア(ゴアテックス)とグーグル)。 本書の目的は、「意識の高い企業」(コンシャス・カンパニー)の誕生を促すことにあるといい、コンシャス・カンパニーとは、①主要ステークホルダー全員と同じ立場に立ち、全員の利益のために奉仕するという高い志に駆り立てられ、②自社の目的、関わる人々、そして地球に奉仕するという意識の高いリーダー(コンシャス・リーダー)を頂き、③そこで働くことが大きな喜びや達成感の源になるような活発で思いやりのある文化に根ざしている会社のことであるとのことです。こう書くと漠然とした理想論のように思われるかもしれませんが、内容および理論構成はしっかりしているように思いました。
本書の目的は、「意識の高い企業」(コンシャス・カンパニー)の誕生を促すことにあるといい、コンシャス・カンパニーとは、①主要ステークホルダー全員と同じ立場に立ち、全員の利益のために奉仕するという高い志に駆り立てられ、②自社の目的、関わる人々、そして地球に奉仕するという意識の高いリーダー(コンシャス・リーダー)を頂き、③そこで働くことが大きな喜びや達成感の源になるような活発で思いやりのある文化に根ざしている会社のことであるとのことです。こう書くと漠然とした理想論のように思われるかもしれませんが、内容および理論構成はしっかりしているように思いました。
 この著者の指向を象徴しているようで興味深かったです(自然食品スーパーの経営者がタバコ製造会社の社的存在意義を認めないというのは、まあ"自然"ではあるが)。思ったより読み易い本でもあり、コンシャス・キャピタリズムとい概念に関心を持たれた人には一読をお勧めします。
この著者の指向を象徴しているようで興味深かったです(自然食品スーパーの経営者がタバコ製造会社の社的存在意義を認めないというのは、まあ"自然"ではあるが)。思ったより読み易い本でもあり、コンシャス・キャピタリズムとい概念に関心を持たれた人には一読をお勧めします。




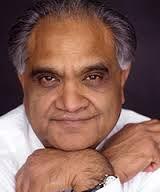 Ram Charan
Ram Charan
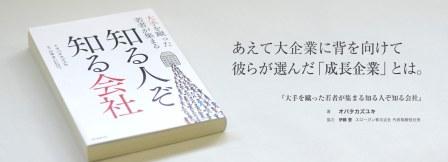

 第1部で紹介されているのは、「テラモーターズ」(電動バイク、社員数20人)、「Sansan」(名刺管理サービス、社員数100人)、「ネットプロテクションズ」(後払い決済サービス、社員数50人)、「フォルシア」(商品検索エンジン開発、社員数53人)、「クラウドワークス」(クラウドソーシング、社員数20人)の5社で、いずれもベンチャーで従業員数は20人から最大100人までと、一般の人には殆ど知られていない比較的小さな会社ばかりです。
第1部で紹介されているのは、「テラモーターズ」(電動バイク、社員数20人)、「Sansan」(名刺管理サービス、社員数100人)、「ネットプロテクションズ」(後払い決済サービス、社員数50人)、「フォルシア」(商品検索エンジン開発、社員数53人)、「クラウドワークス」(クラウドソーシング、社員数20人)の5社で、いずれもベンチャーで従業員数は20人から最大100人までと、一般の人には殆ど知られていない比較的小さな会社ばかりです。



 2012年5月に、日本における新しい退職給付会計基準が公表され、「貸借対照表での未認識債務の即時認識」「退職給付債務の計算方法の変更」「退職給付制度運営に関する開示の充実」などの改正がなされました。本書は、これらの改正項目のうち、「退職給付債務計算」に関わる項目を取り扱っており、その中でも特に企業財務や実務への影響が大きいと思われる「期間帰属方法の取扱い」と「割引率の見直し」を中心に解説しています。
2012年5月に、日本における新しい退職給付会計基準が公表され、「貸借対照表での未認識債務の即時認識」「退職給付債務の計算方法の変更」「退職給付制度運営に関する開示の充実」などの改正がなされました。本書は、これらの改正項目のうち、「退職給付債務計算」に関わる項目を取り扱っており、その中でも特に企業財務や実務への影響が大きいと思われる「期間帰属方法の取扱い」と「割引率の見直し」を中心に解説しています。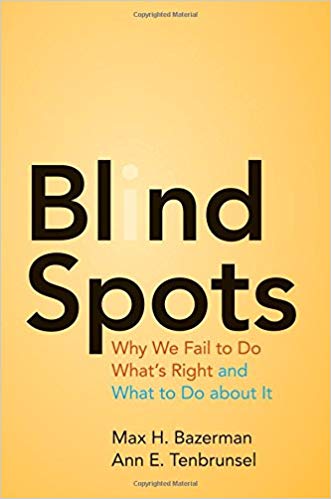

 Max H. Bazerman
Max H. Bazerman
 過去に企業不祥事が何度も繰り返され、その社会的反響の大きさから、こんなことは二度と繰り返すまいとその発生防止策がその都度討議されてきたにも関わらず、近年においても、大手金融機関の暴力団関係者への融資問題や、大手百貨店・有名ホテルの食材偽装・不当表示問題
過去に企業不祥事が何度も繰り返され、その社会的反響の大きさから、こんなことは二度と繰り返すまいとその発生防止策がその都度討議されてきたにも関わらず、近年においても、大手金融機関の暴力団関係者への融資問題や、大手百貨店・有名ホテルの食材偽装・不当表示問題 が報道されるなどして、相変わらず企業不祥事は後を絶ちません。
が報道されるなどして、相変わらず企業不祥事は後を絶ちません。




 本書の著者シェリル・サンドバーグは、財務省で首席補佐官を務め、その後グーグルで6年半働いてグローバル・オンライン・セールスおよびオペレーション担当副社長を歴任した後、あのマーク・ザッカーバーグによりフェイスブックにスカウトされ、今現在はフェイスブックのCOO(最高執行責任者)の地位にある人であり、2011年8月のフォーブズ誌「World's 100 Most Powerful Women」で5位になった人でもあり(ミッシェル・オバマ大統領夫人よりも上に位置していた)、2013年には「経営思想家トップ50(Thinkers50)」にランクインしています。
本書の著者シェリル・サンドバーグは、財務省で首席補佐官を務め、その後グーグルで6年半働いてグローバル・オンライン・セールスおよびオペレーション担当副社長を歴任した後、あのマーク・ザッカーバーグによりフェイスブックにスカウトされ、今現在はフェイスブックのCOO(最高執行責任者)の地位にある人であり、2011年8月のフォーブズ誌「World's 100 Most Powerful Women」で5位になった人でもあり(ミッシェル・オバマ大統領夫人よりも上に位置していた)、2013年には「経営思想家トップ50(Thinkers50)」にランクインしています。 プレゼンテーション・カンファレンスとして知られる「TED」で著者が講演した際の話がでてきますが、著者が本書を著すきっかけとなったのは、TEDでの著者の「なぜ女性のリーダーは少ないのか?」と題された(周囲はなぜ彼女は成功したのかを聞きたがっていたが、彼女は敢えてこのテーマを演題に選んだ)トークの反響が大きかったためで(トークの模様はインターネットで視聴できる)、本書もアメリカでベストセラーとなり、女性のキャリアについて大きな論争が起きているとのことです。
プレゼンテーション・カンファレンスとして知られる「TED」で著者が講演した際の話がでてきますが、著者が本書を著すきっかけとなったのは、TEDでの著者の「なぜ女性のリーダーは少ないのか?」と題された(周囲はなぜ彼女は成功したのかを聞きたがっていたが、彼女は敢えてこのテーマを演題に選んだ)トークの反響が大きかったためで(トークの模様はインターネットで視聴できる)、本書もアメリカでベストセラーとなり、女性のキャリアについて大きな論争が起きているとのことです。 それにしてもこの人、TEDのプレゼンもNHKの「クローズアップ現代」でのインタビューも見ましたが、コミュニケーション能力がやはり抜群に長けているのではないでしょうか、「1対多」でも「1対1」でも。その年俸22億円はカルロス・ゴーンの倍以上ですが、確かにハーバードを首席で卒業した秀才ではあるし、おそらくマーケティングなどの知識も豊富だとは思われるのですが、やはりこの人をこうした地位まで押し上げたのは、リーダーシップとコミュニケーション能力だろうなあと思います。
それにしてもこの人、TEDのプレゼンもNHKの「クローズアップ現代」でのインタビューも見ましたが、コミュニケーション能力がやはり抜群に長けているのではないでしょうか、「1対多」でも「1対1」でも。その年俸22億円はカルロス・ゴーンの倍以上ですが、確かにハーバードを首席で卒業した秀才ではあるし、おそらくマーケティングなどの知識も豊富だとは思われるのですが、やはりこの人をこうした地位まで押し上げたのは、リーダーシップとコミュニケーション能力だろうなあと思います。




 全体で230ページ弱で、その中にはこうしたエッセイに書かれている箇所も多く、全体を通して読み易いです。個人的には、あまり自己啓発書的なものは読まない方ですが、本書はどちらかというと、著者の専門であるマネジメント、組織行動理論を、一般向けの読み物風に書き直したような感じであり、平易な表現の裏に確固たるバックボーンがあるのが感じられます。
全体で230ページ弱で、その中にはこうしたエッセイに書かれている箇所も多く、全体を通して読み易いです。個人的には、あまり自己啓発書的なものは読まない方ですが、本書はどちらかというと、著者の専門であるマネジメント、組織行動理論を、一般向けの読み物風に書き直したような感じであり、平易な表現の裏に確固たるバックボーンがあるのが感じられます。
 岩波 明 氏(医学博士・精神保健指定医)
岩波 明 氏(医学博士・精神保健指定医)






 序章で、社員が残る理由も、離れる理由もやはり"人"であるとし、第1章「会社のしくみ」で、会社が社員に対して「安心」を与えているかどうかが、優秀な社員が辞めずにのびのびと働くための条件となるとしているのには納得。結局、社員が辞める理由の大半は、ハーズバーグが言うところの「動機づけ要因」よりも「衛生(環境)要因」によるものでしょう。
序章で、社員が残る理由も、離れる理由もやはり"人"であるとし、第1章「会社のしくみ」で、会社が社員に対して「安心」を与えているかどうかが、優秀な社員が辞めずにのびのびと働くための条件となるとしているのには納得。結局、社員が辞める理由の大半は、ハーズバーグが言うところの「動機づけ要因」よりも「衛生(環境)要因」によるものでしょう。 がある」―皆すべて確かにそうであり、また、「安心して働ける職場環境」という冒頭のコンセプトとリンクはしているのだが...)。
がある」―皆すべて確かにそうであり、また、「安心して働ける職場環境」という冒頭のコンセプトとリンクはしているのだが...)。





 のことで、企業の台所事情が厳しいときにはリストラに踏み切れないが、好景気により円安・株価上昇によって現金が入れば、それは社員への還元ではなく「リストラ費用」となってもおかしくはないという論旨になっています。
のことで、企業の台所事情が厳しいときにはリストラに踏み切れないが、好景気により円安・株価上昇によって現金が入れば、それは社員への還元ではなく「リストラ費用」となってもおかしくはないという論旨になっています。
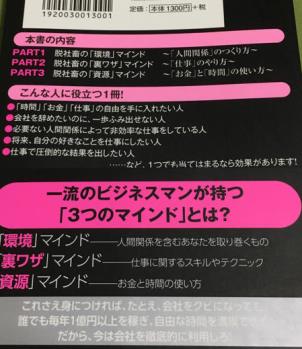 著者の略歴(自己PR?)を見ただけで既に大いに胡散臭そうなのに、Amazon.comのブックレビューで意外と本書を推す人が多かったのには驚きましたが、個人的にはこの本は、谷本真由美氏が言うところの「キャリアポルノ」の典型ではないかと思いました。「自己啓発ポルノ」と言ってもいいかな。
著者の略歴(自己PR?)を見ただけで既に大いに胡散臭そうなのに、Amazon.comのブックレビューで意外と本書を推す人が多かったのには驚きましたが、個人的にはこの本は、谷本真由美氏が言うところの「キャリアポルノ」の典型ではないかと思いました。「自己啓発ポルノ」と言ってもいいかな。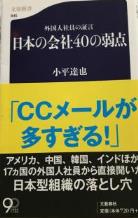

 本書を読んで、その最初のフェーズというのが意外と重要であり、また多くのビジネスパーソンが悩んでいる部分ではないかと思いました。ただし、ポイントを押さえておけば、起こさなくてもよいトラブルは回避することができ、大切な時間や労力を本来業務に傾け、チームの生産性を上げることができるという思いにもさせられました。
本書を読んで、その最初のフェーズというのが意外と重要であり、また多くのビジネスパーソンが悩んでいる部分ではないかと思いました。ただし、ポイントを押さえておけば、起こさなくてもよいトラブルは回避することができ、大切な時間や労力を本来業務に傾け、チームの生産性を上げることができるという思いにもさせられました。
 伊藤洋介氏/安倍昭恵氏
伊藤洋介氏/安倍昭恵氏
 著者は、山一証券勤務時代に「シャインズ」を結成して(相方は杉村太郎(1963-2011/享年47))、その後、森永製菓に転職し、「東京プリン」を結成して(相方は牧野隆志(1964-2014.2.7/享年49))森永の方は辞めるなど、会社員とアーティスト(?)を兼業したり、フリーで活動したりを繰り返しているような人で、この人自身は何度か会社を辞めているわけでしょ。「会社にしがみついて生きろ」と言っているこの人自身のアイデンティティがどうなっているのかよく解りません(会社を辞めてからよっぽどシンドイ思いをしたのか)。
著者は、山一証券勤務時代に「シャインズ」を結成して(相方は杉村太郎(1963-2011/享年47))、その後、森永製菓に転職し、「東京プリン」を結成して(相方は牧野隆志(1964-2014.2.7/享年49))森永の方は辞めるなど、会社員とアーティスト(?)を兼業したり、フリーで活動したりを繰り返しているような人で、この人自身は何度か会社を辞めているわけでしょ。「会社にしがみついて生きろ」と言っているこの人自身のアイデンティティがどうなっているのかよく解りません(会社を辞めてからよっぽどシンドイ思いをしたのか)。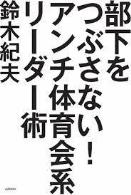
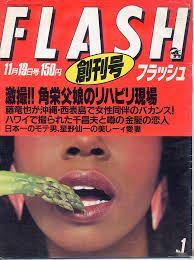 とりわけ、'86年の「フラッシュ(FLASH)」創刊の時のことが詳しく語られていて、写真週刊誌なんて一体世の中にどういった意義をもたらしているのかといったことを考えなくもないですが、とは言えやはりその道で後から参入したにも関わらず競争に勝ち残ったというのは、それなりにスゴイことなのかもしれません。
とりわけ、'86年の「フラッシュ(FLASH)」創刊の時のことが詳しく語られていて、写真週刊誌なんて一体世の中にどういった意義をもたらしているのかといったことを考えなくもないですが、とは言えやはりその道で後から参入したにも関わらず競争に勝ち残ったというのは、それなりにスゴイことなのかもしれません。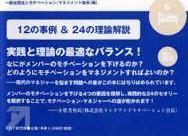
 12の事例と24の理論解説で構成されていますが、事例は、モチベーションを下げる要因を「変化・慣性・理想・違い」の4つに分類しています。例えば「変化」がモチベーションを下げるケースでは、人事異動やM&Aなどによるモチベーション低下の事例をストーリーで示し、それらに対する対応をアドバイスするとともに、「欲求階層説」や「Ⅹ理論・Y理論」などのモチベーション理論が紹介および解説されています。
12の事例と24の理論解説で構成されていますが、事例は、モチベーションを下げる要因を「変化・慣性・理想・違い」の4つに分類しています。例えば「変化」がモチベーションを下げるケースでは、人事異動やM&Aなどによるモチベーション低下の事例をストーリーで示し、それらに対する対応をアドバイスするとともに、「欲求階層説」や「Ⅹ理論・Y理論」などのモチベーション理論が紹介および解説されています。 40年余に渡って経営コンサルティングに携わり、とりわけこの20年は管理職層を対象に、人材の能力評価と能力開発を主題とするヒューマン・アセスメントを行うことで企業を支援してきた著者が、ビジネスマンを読者として想定し、上級管理職である部長に焦点を合せ、彼らの仕事ぶりや様々な言動特徴を取り上げ、彼らのマネジメント能力とその開発方法を解説した本です。
40年余に渡って経営コンサルティングに携わり、とりわけこの20年は管理職層を対象に、人材の能力評価と能力開発を主題とするヒューマン・アセスメントを行うことで企業を支援してきた著者が、ビジネスマンを読者として想定し、上級管理職である部長に焦点を合せ、彼らの仕事ぶりや様々な言動特徴を取り上げ、彼らのマネジメント能力とその開発方法を解説した本です。 ビジネスパーソンにとって啓発される要素が多いばかりでなく、人事パーソンの視点から見ても、上級管理職についてのアセスメントの重点項目を分かり易く説いたものと言えます。社内に「なんであんな人が部長をやっているんだろう」というような「困った部長」がいる企業の人事パーソンには、自社の管理職任用アセスメントが形骸化していないかどうかをチェックするうえでも、是非一読をお勧めします。
ビジネスパーソンにとって啓発される要素が多いばかりでなく、人事パーソンの視点から見ても、上級管理職についてのアセスメントの重点項目を分かり易く説いたものと言えます。社内に「なんであんな人が部長をやっているんだろう」というような「困った部長」がいる企業の人事パーソンには、自社の管理職任用アセスメントが形骸化していないかどうかをチェックするうえでも、是非一読をお勧めします。
 榎本 博明 氏(略歴下記)
榎本 博明 氏(略歴下記) むしろ、今日の職場で起きている世代間の認識のズレやコミュニケーション不全を、心理学というより世代論的な観点から分析してみせた本のようにも思います。その意味では"タイトルずれ"はしておらず、また、企業勤務の経験がある著者らしい洞察がみられますが、「分析」に比重がかかった分、「処方箋」の部分がやや弱かったように思います。
むしろ、今日の職場で起きている世代間の認識のズレやコミュニケーション不全を、心理学というより世代論的な観点から分析してみせた本のようにも思います。その意味では"タイトルずれ"はしておらず、また、企業勤務の経験がある著者らしい洞察がみられますが、「分析」に比重がかかった分、「処方箋」の部分がやや弱かったように思います。
 外国語教授や留学等、語学に関わるサービスを提供しているベルリッツ・ジャパンによる本であり、本書にある「カルチュラル・コンピテンス」を伸ばす手法は、ベルリッツの子会社であるTMC(Training Management Corporation)が開発したものであり、世界各国の組織や個人によって実務に適用されているとのこと(ベルリッツ・ジャパンも「カルチュラル・コンピテンス」を使った研修を2010年から実施している)。今回の刊行は、この研修の受講者からの、日本語で「カルチュラル・コンピテンス」を復習したいとの要望に応えてのものだそうです。
外国語教授や留学等、語学に関わるサービスを提供しているベルリッツ・ジャパンによる本であり、本書にある「カルチュラル・コンピテンス」を伸ばす手法は、ベルリッツの子会社であるTMC(Training Management Corporation)が開発したものであり、世界各国の組織や個人によって実務に適用されているとのこと(ベルリッツ・ジャパンも「カルチュラル・コンピテンス」を使った研修を2010年から実施している)。今回の刊行は、この研修の受講者からの、日本語で「カルチュラル・コンピテンス」を復習したいとの要望に応えてのものだそうです。




 小倉 一哉 早稲田大学商学学術院准教授(略歴下記)
小倉 一哉 早稲田大学商学学術院准教授(略歴下記)










 木谷 宏 氏(麗澤大学教授)
木谷 宏 氏(麗澤大学教授) 関心がある「問い」に対応している節から読み始めても読めてしまうという"優れもの"。ベテラン、中堅、初学者を問わず、人事パーソンにお奨めです。
関心がある「問い」に対応している節から読み始めても読めてしまうという"優れもの"。ベテラン、中堅、初学者を問わず、人事パーソンにお奨めです。
