「●労働経済・労働問題」の インデックッスへ Prev|NEXT ⇒ 【1605】 深田 和範 『「文系・大卒・30歳以上」がクビになる』
「●岩波新書」の インデックッスへ
雇用システムの「現実的・漸進的改革の方向」を示す。読めば読むほど味が出てくる"スルメ"みたいな本。
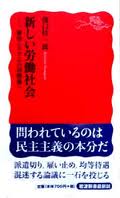
 濱口桂一郎 氏(労働政策研究・研修機構)
濱口桂一郎 氏(労働政策研究・研修機構)
『新しい労働社会―雇用システムの再構築へ (岩波新書)』['09年]
「派遣切り」「名ばかり管理職」「ワーキングプア」「製造業への派遣」といった現在生じている労働問題をめぐる議論は、それぞれ案件ごとの規制緩和論と規制強化論の対立図式になりがちですが、本書は、そうした問題を個別的・表層的捉えるのではなく、国際比較と歴史的経緯という大きな構図の中で捉えようとしています。
序章において、わが国おける雇用契約は、諸外国と異なり「職務(ジョブ)」ではなく「メンバーシップ」に基づくものであり、そのことが日本型雇用システムの特徴である長期雇用、年功賃金、企業内組合の形成要因となっていることを明快に説いています。
個人的には「メンバーシップ」という表現及びこの部分の論旨がものすごく分かりよかったのですが(序章だけでも読んでおく価値あり!)、こうしたことを踏まえ、労働問題の各論へと進みます。
第1章では働きすぎの正社員のワークライフバランス問題をとり上げ、「名ばかり管理職」「ホワイトカラーエグゼンプション」をめぐる議論においては、健康確保措置の問題が報酬問題にすり替えられたと指摘していますが、これは個人的にも同感。マクドナルド事件は、名ばかり管理職問題ではなく過重残業問題だったというのは、何人かの著名な弁護士(主に使用者側)などもそう指摘していたように思います。
第2章では非正規労働者の問題をとり上げ、「偽装請負」「労働者派遣法」などに関する議論について歴史的経緯を踏まえて再整理していますが、「日雇い派遣」問題の本質は「偽装有期雇用」にあり、この「偽装有期雇用」こそが問題であるとの指摘には、目を見開かせられる思いをしました。
第3章ではワーキングプア問題をとり上げ、メンバーシップ型正社員だけに手厚い生活給制度が適用されてきたという経緯の中、過去にもアルバイト等の非メンバーシップ労働者はいたものの、親の生活給賃金が子の生計を補填するといった構図で"日本的フレクシキュリティ(柔軟性+安定性)"が保たれていて、それが近年、非正規雇用労働者の増加により、そのフレクシキュリティが揺らいできたというのが、ワーキングプア問題の本質であるとしています。
日本の法定の最低賃金の水準の低さは、最低賃金がアルバイトとパートという家計補助労働の対価を対象にしていることに起因としているとの指摘は卓見であり、こうした背景との繋がりがワーキングプア問題の基礎にあるということは、問題の案件をそれだけに絞って見てしまっていては見えてこないんだろうなあと。
ここまでにも幾つかの提言はありますが、どちらかと言えば改革に繋げる前段階(下ごしらえ)の議論であり、それに対し第4章は、本書タイトルにより呼応した内容であり、非正規労働者も含めた労働組合再編など、集団的合意形成の新たな枠組みを提言するとともに、労働政策の決定に一部のステークスホルダーしか関与していないことなどを批判しています(そうなんだ。政労使三者構成というのが本来は、原則のはずなんだよなあ)。
現行の労働法制の成立過程を追い、その矛盾や実態との乖離を指摘している点は参考になり、また、雇用システムというものが、法的、政治的、経済的、経営的、社会的などの様々な側面が一体となった社会システムであることを踏まえた上での論考は、「現実的・漸進的改革の方向」(著者)を示したものと言えるかと思います。
労働法を学ぶ人にはブログなどでもお馴染みの論客ですが(大学のオープン講座で労働政策研究・研修機構のR・H先生の労働法の講義を聴いたときに、著者のブログを勧められた。個人的にも以前から読んでいたけれど)、この人、EUの労働法にも詳しかったりするけれど、労働経済学者なんだよね。労働法学と社会政策学の両方の分野を論じることができるのが著者の強みであり、かなりの希少価値ではないかと。
新書という体裁上、コンパクトに纏まっていますが、読めば読むほど味が出てくる"スルメ"みたいな本です。
評価で星半個減は、自分自身の理解が及ばなかった部分が若干あったためで、4章が、もやっとした感じ。自分の中に「労組=旧態然」というネガティブイメージがあるのもその一因かもしれません。
折をみて再読したいと思いますが、ブログを読むよりは、ちょっと気合いを入れてかかる必要があるかも。そう思いつついたら、もう、本書の続編と言えるかどうかわからないけれど、『日本の雇用と労働法』('11年/日経文庫)というのが刊行されており、そちらも読み始めてしまった...。
