「●は行の外国映画の監督①」の インデックッスへ Prev|NEXT ⇒ 【2359】 オリヴァー・ヒルシュビーゲル 「ヒトラー暗殺、13分の誤算」
「●「ロンドン映画批評家協会賞 外国語映画賞」受賞作」の インデックッスへ 「○外国映画 【制作年順】」のインデックッスへ「●アドルフ・ヒトラー」の インデックッスへ
次第に狂人化していくヒトラーと、どうすることも出来ない取り巻き将校たち。



「ヒトラー ~最期の12日間~ ロング・バージョン(2枚組) [DVD]」 ブルーノ・ガンツ(アドルフ・ヒトラー)
 1942年、トラウドゥル・ユンゲ(アレクサンドラ・マリア・ララ)は数人の候補の中からヒトラー総統(ブルーノ・ガンツ)の個人秘書に抜擢された。1945年4月20日、ベルリン。第二次大戦は佳境を迎え、ドイツ軍は連合軍に追い詰められつつあった。ヒトラーは身内や側近と共に首相官邸の地下要塞へ潜り、ユンゲもあとに続く。そこで彼女は、冷静さを失い狂人化していくヒトラーを目の当たりにするのだった。ベルリン市内も混乱を極め、民兵は武器も持たずに立ち向かい、戦争に参加しない市民は親衛隊に射殺されていく。そして側近たちも次々と逃亡する中、ヒトラーは敗北を認めず最終決戦を決意するが―。
1942年、トラウドゥル・ユンゲ(アレクサンドラ・マリア・ララ)は数人の候補の中からヒトラー総統(ブルーノ・ガンツ)の個人秘書に抜擢された。1945年4月20日、ベルリン。第二次大戦は佳境を迎え、ドイツ軍は連合軍に追い詰められつつあった。ヒトラーは身内や側近と共に首相官邸の地下要塞へ潜り、ユンゲもあとに続く。そこで彼女は、冷静さを失い狂人化していくヒトラーを目の当たりにするのだった。ベルリン市内も混乱を極め、民兵は武器も持たずに立ち向かい、戦争に参加しない市民は親衛隊に射殺されていく。そして側近たちも次々と逃亡する中、ヒトラーは敗北を認めず最終決戦を決意するが―。
 オリヴァー・ヒルシュビーゲル監督の2004年作品で、ヨアヒム・フェストによる同名の研究書『ヒトラー 最期の12日間』('05年/岩波書店)、およびヒトラーの個人秘書官を務めたトラウドゥル・ユンゲの証言と回想録『私はヒトラーの秘書だった』('04年/草思社)が本作の土台となっています。映画はヒトラーが地下の要塞で過ごした最期の12日間に焦点を当て、トラウドゥル・ユンゲの目を通して、歴史的独裁者の知られざる側面を浮き彫りにしていくほか、混乱の中で国防軍の軍人やSS(親衛隊)隊員らが迎える終末、宣伝相ヨーゼフ・ゲッベルス一家の最期、老若男女を問わず戦火に巻き込まれるベルリン市民の姿にも焦点が置かれています。
オリヴァー・ヒルシュビーゲル監督の2004年作品で、ヨアヒム・フェストによる同名の研究書『ヒトラー 最期の12日間』('05年/岩波書店)、およびヒトラーの個人秘書官を務めたトラウドゥル・ユンゲの証言と回想録『私はヒトラーの秘書だった』('04年/草思社)が本作の土台となっています。映画はヒトラーが地下の要塞で過ごした最期の12日間に焦点を当て、トラウドゥル・ユンゲの目を通して、歴史的独裁者の知られざる側面を浮き彫りにしていくほか、混乱の中で国防軍の軍人やSS(親衛隊)隊員らが迎える終末、宣伝相ヨーゼフ・ゲッベルス一家の最期、老若男女を問わず戦火に巻き込まれるベルリン市民の姿にも焦点が置かれています。
 この映画の圧巻は、ブルーノ・ガンツ(1941-2019)が演じる、次第に冷静さを失い狂人化していくヒトラーではないでしょうか。その演技は話題になり、動画投稿サイトにおいて台詞パロディの題
この映画の圧巻は、ブルーノ・ガンツ(1941-2019)が演じる、次第に冷静さを失い狂人化していくヒトラーではないでしょうか。その演技は話題になり、動画投稿サイトにおいて台詞パロディの題 材として広く用いられています(日本では「総統閣下シリーズ」と銘打たれている)。ただ、ブルーノ・ガンツの演技ばかりでなく、ヒトラーが総統官邸地下壕から出てきてヒトラー・ユーゲントを激励するシーンなどは、実際の記録映像を忠実に再現していて(元になった記録映像は生前のヒトラー最後の映像として残っているもの)、作りの細かさからリアリティを感じさせるものとなっています(ゲッペルスの6人の子供達も本モノそっくりしのようだ)。
材として広く用いられています(日本では「総統閣下シリーズ」と銘打たれている)。ただ、ブルーノ・ガンツの演技ばかりでなく、ヒトラーが総統官邸地下壕から出てきてヒトラー・ユーゲントを激励するシーンなどは、実際の記録映像を忠実に再現していて(元になった記録映像は生前のヒトラー最後の映像として残っているもの)、作りの細かさからリアリティを感じさせるものとなっています(ゲッペルスの6人の子供達も本モノそっくりしのようだ)。
 しかし、この映画に描かれていることが全て真実かと言うと、例えば、地下要塞の最後の生き残りだった(この映画にも登場する)親衛隊曹長で地下壕の電話交換手ローフス・ミッシュ(1917-2013/享年96)は、映画は全く事実と異なっていると言い、ヒトラーが映画みたいに怒鳴ってばかりいたというのは誇張で、また、将校らが地下壕内で乱痴気パーティのようなことをしたことも無かったとのことです(ルキノ・ヴィスコンティ監督の「地獄に堕ちた勇者ども」('69年/伊)の影響?)
しかし、この映画に描かれていることが全て真実かと言うと、例えば、地下要塞の最後の生き残りだった(この映画にも登場する)親衛隊曹長で地下壕の電話交換手ローフス・ミッシュ(1917-2013/享年96)は、映画は全く事実と異なっていると言い、ヒトラーが映画みたいに怒鳴ってばかりいたというのは誇張で、また、将校らが地下壕内で乱痴気パーティのようなことをしたことも無かったとのことです(ルキノ・ヴィスコンティ監督の「地獄に堕ちた勇者ども」('69年/伊)の影響?)
アレクサンドラ・マリア・ララ(トラウデル・ユンゲ)/トラウデル・ユンゲ

 そもそもこの映画の原作者の一人、ヒトラーの秘書だったトラウデル・ユンゲ(1920-2002/享年81)の父は積極的なナチス協力者であり、また、彼女の夫は親衛隊将校だったとのことで、その証言の中立性に疑問を挟む向きもあるようです。彼女は、出版社の勧めで1947 - 48年に本を執筆しましたが「このような本は関心を持たれない」という理由で出版されなかったのが、『アンネの伝記』の著者メリッサ・ミュラーと2000年に知り合い、その協力を得て2002年に初の回顧録『最期の時まで―ヒトラーの秘書が語るその人生』を出版したとのこと。その回顧録の内容に関するインタビューの様子がドキュメンタリー映画に収められ(ベルリン映画祭観客賞)、2002年2月、この映画の公開数日後に死去しています(この「ヒトラー~最期の12日間~」でも、冒頭と最後にも生前の彼女のインタビューが出てくる)。
そもそもこの映画の原作者の一人、ヒトラーの秘書だったトラウデル・ユンゲ(1920-2002/享年81)の父は積極的なナチス協力者であり、また、彼女の夫は親衛隊将校だったとのことで、その証言の中立性に疑問を挟む向きもあるようです。彼女は、出版社の勧めで1947 - 48年に本を執筆しましたが「このような本は関心を持たれない」という理由で出版されなかったのが、『アンネの伝記』の著者メリッサ・ミュラーと2000年に知り合い、その協力を得て2002年に初の回顧録『最期の時まで―ヒトラーの秘書が語るその人生』を出版したとのこと。その回顧録の内容に関するインタビューの様子がドキュメンタリー映画に収められ(ベルリン映画祭観客賞)、2002年2月、この映画の公開数日後に死去しています(この「ヒトラー~最期の12日間~」でも、冒頭と最後にも生前の彼女のインタビューが出てくる)。
ハインリヒ・シュミーダー(ローフス・ミッシュ)
 トラウデル・ユンゲは戦後比較的早くからヒトラーの最期について証言していますが、ローフス・ミッシュは彼女がそうした証言によって金を稼いだと批判しています。そのローフス・ミッシュ自身も1970年代からドキュメンタリー映画に登場するようになり、特に1990年代以降、ヒトラーや第二次世界大戦に関する番組によく登場していたとのことです。2006年にも「最後の証人―ロフス・ミシュ」と題するテレビ・ドキュメンタリー番組に出演、『ヒトラーの死を見とどけた
トラウデル・ユンゲは戦後比較的早くからヒトラーの最期について証言していますが、ローフス・ミッシュは彼女がそうした証言によって金を稼いだと批判しています。そのローフス・ミッシュ自身も1970年代からドキュメンタリー映画に登場するようになり、特に1990年代以降、ヒトラーや第二次世界大戦に関する番組によく登場していたとのことです。2006年にも「最後の証人―ロフス・ミシュ」と題するテレビ・ドキュメンタリー番組に出演、『ヒトラーの死を見とどけた
 男―地下壕最後の生き残りの証言』('06年/草思社)という本も書いています。また、映画製作にあたって、オリヴァー・ヒルシュビーゲル監督が自分の所へ全く取材に来なかったことに不満を呈しています。
男―地下壕最後の生き残りの証言』('06年/草思社)という本も書いています。また、映画製作にあたって、オリヴァー・ヒルシュビーゲル監督が自分の所へ全く取材に来なかったことに不満を呈しています。
ローフス・ミッシュ『ヒトラーの死を見とどけた男―地下壕最後の生き残りの証言』('06年/草思社)
 この映画でのヒトラーの描かれ方の特徴として、ヒトラーが(特にユンゲが秘書に採用された1942年頃は)人間味もちゃんと持ち併せている人物として描かれている点で、ユンゲの著書でヒトラーが、もともとは紳士的で寛大で親切な側面があり、ユーモアのセンスさえあったように描かれていることの影響を若干反映しているように思います。こうしたユンゲのヒトラーの描き方に、彼女が直接政治には関与しなかったもののあまりに無自覚だという批判があるわけですが、それが映画にも少し反映されていることで、この映画が批判される一因ともなっているようです(彼女自身はレニ・リーフェンシュタールなどと同様、自身はナチズムやホロコーストと無関係であると生涯主張し続けたとされているが、この映画の中のインタビューでは無関係では済まされないと"懺悔"している)。 トラウデル・ユンゲ『私はヒトラーの秘書だった
この映画でのヒトラーの描かれ方の特徴として、ヒトラーが(特にユンゲが秘書に採用された1942年頃は)人間味もちゃんと持ち併せている人物として描かれている点で、ユンゲの著書でヒトラーが、もともとは紳士的で寛大で親切な側面があり、ユーモアのセンスさえあったように描かれていることの影響を若干反映しているように思います。こうしたユンゲのヒトラーの描き方に、彼女が直接政治には関与しなかったもののあまりに無自覚だという批判があるわけですが、それが映画にも少し反映されていることで、この映画が批判される一因ともなっているようです(彼女自身はレニ・リーフェンシュタールなどと同様、自身はナチズムやホロコーストと無関係であると生涯主張し続けたとされているが、この映画の中のインタビューでは無関係では済まされないと"懺悔"している)。 トラウデル・ユンゲ『私はヒトラーの秘書だった』('04年/草思社)
 全体としては概ね事実に忠実だという評価のようですが、細部においては何が真実なのか、証言者の数だけ"真実"があって分からないということなのかもしれないです(歴史とはそういうものか)。但し、映画としては、最初はまともだったのが次第におかしくなり、最後はすっかり狂人化していくヒトラーと、最初はヒトラーに忠誠を誓っていたものの次第にその行いに疑問を感じるようになり、それでも従来の"忠誠パターン"から抜け出せないまま、最後はその異様な変貌ぶりに驚きつつ、どうにもすることも出来ずにいる取り巻き将校たちという構図が、一つの大きな見せ所となっているように思いました(ゲッペルス夫妻のように狂的に最後までヒトラーに追従して行く者もいたが、これはごく一握りか)。
全体としては概ね事実に忠実だという評価のようですが、細部においては何が真実なのか、証言者の数だけ"真実"があって分からないということなのかもしれないです(歴史とはそういうものか)。但し、映画としては、最初はまともだったのが次第におかしくなり、最後はすっかり狂人化していくヒトラーと、最初はヒトラーに忠誠を誓っていたものの次第にその行いに疑問を感じるようになり、それでも従来の"忠誠パターン"から抜け出せないまま、最後はその異様な変貌ぶりに驚きつつ、どうにもすることも出来ずにいる取り巻き将校たちという構図が、一つの大きな見せ所となっているように思いました(ゲッペルス夫妻のように狂的に最後までヒトラーに追従して行く者もいたが、これはごく一握りか)。
 今どきのビジネス書風に言えば、上司を諌めるフォロワーシップが働かなかったということでしょうか。たとえ合理的な観点から或いは良心の呵責からヒトラーに物申す将校がいたとしても、それを撥ねつ
今どきのビジネス書風に言えば、上司を諌めるフォロワーシップが働かなかったということでしょうか。たとえ合理的な観点から或いは良心の呵責からヒトラーに物申す将校がいたとしても、それを撥ねつ けて二度と自分に口答えさせないだけの迫力ある(?)狂人と化したヒトラーを、ブルーノ・ガンツは力演していたように思います。普通ならば"浮いて"しまうようなオーバーアクションなのですが(パロディ化されるだけのことはある?)、オーバーアクションであればあるほど風刺や皮肉が効いてくる映画でした。
けて二度と自分に口答えさせないだけの迫力ある(?)狂人と化したヒトラーを、ブルーノ・ガンツは力演していたように思います。普通ならば"浮いて"しまうようなオーバーアクションなのですが(パロディ化されるだけのことはある?)、オーバーアクションであればあるほど風刺や皮肉が効いてくる映画でした。
クリスチャン・ベルケル(エルンスト=ギュンター・シェンク)
 但し、この映画で良心的な人物として描かれている医官のエルンスト=ギュンター・シェンク親衛隊大佐(クリスチャン・ベルケル)は、強制収容所で人体実験を行って多数の犠牲者を出したとされており、民間人の犠牲者を回避するよう繰り返し訴えるヴィルヘルム・モーンケ親衛隊少将(アンドレ・ヘンニック)は、史実においては少なくとも2度に渡り彼の指揮下の部隊が戦争捕虜を虐殺した疑いが持たれているとのことです。同監督の「ヒトラー暗殺、13分の誤算」('15年/独)でも、ヒトラー暗殺計画の手引きをしたとしてヒトラーに処刑される秘密警察のアルトゥール・ネーベを「いい人」のように描いていますが、ネーベはモスクワ戦線進軍中、ユダヤ人やパルチザンと目される人々大勢の殺害を命令した人物で、ネーベの隊だけで4万5,467人の処刑が報告されています。人にはそれぞれの顔があるわけで、映画的に分かり易くするためにその一面だけを描く傾向がこの監督にはあるのかも。一つの映画的手法だとは思いますが、対象がナチスであるだけに、これもまた異議を唱える人が出てくる原因になるのでしょう。アカデミー外国語映画賞にノミネートされましたが、受賞はアレハンドロ・アメナバル監督の「海を飛ぶ夢」に持っていかれています。
但し、この映画で良心的な人物として描かれている医官のエルンスト=ギュンター・シェンク親衛隊大佐(クリスチャン・ベルケル)は、強制収容所で人体実験を行って多数の犠牲者を出したとされており、民間人の犠牲者を回避するよう繰り返し訴えるヴィルヘルム・モーンケ親衛隊少将(アンドレ・ヘンニック)は、史実においては少なくとも2度に渡り彼の指揮下の部隊が戦争捕虜を虐殺した疑いが持たれているとのことです。同監督の「ヒトラー暗殺、13分の誤算」('15年/独)でも、ヒトラー暗殺計画の手引きをしたとしてヒトラーに処刑される秘密警察のアルトゥール・ネーベを「いい人」のように描いていますが、ネーベはモスクワ戦線進軍中、ユダヤ人やパルチザンと目される人々大勢の殺害を命令した人物で、ネーベの隊だけで4万5,467人の処刑が報告されています。人にはそれぞれの顔があるわけで、映画的に分かり易くするためにその一面だけを描く傾向がこの監督にはあるのかも。一つの映画的手法だとは思いますが、対象がナチスであるだけに、これもまた異議を唱える人が出てくる原因になるのでしょう。アカデミー外国語映画賞にノミネートされましたが、受賞はアレハンドロ・アメナバル監督の「海を飛ぶ夢」に持っていかれています。
Hitorâ: Saigo no 12nichi kan (2004)
 「ヒトラー~最期の12日間~」●原題:DER UNTERGANG(英:DOWNFALL)●制作年:2004年●制作国:ドイツ・オーストリア・イタリア●監督:オリヴァー・ヒルシュビーゲル●製作:ベルント・アイヒンガー●脚本:ベルント・アイヒンガー●撮影:ライナー・クラウスマン●音楽:ステファン・ツァハリアス●原作:ヨアヒム・フェスト「ヒトラー 最期の12日間」/トラウデル・ユンゲ「私はヒトラー
「ヒトラー~最期の12日間~」●原題:DER UNTERGANG(英:DOWNFALL)●制作年:2004年●制作国:ドイツ・オーストリア・イタリア●監督:オリヴァー・ヒルシュビーゲル●製作:ベルント・アイヒンガー●脚本:ベルント・アイヒンガー●撮影:ライナー・クラウスマン●音楽:ステファン・ツァハリアス●原作:ヨアヒム・フェスト「ヒトラー 最期の12日間」/トラウデル・ユンゲ「私はヒトラー の秘書だった Bis zur letzten Stunde」●時間:156分●出演:ブルーノ・ガンツ/アレクサンドラ・マリア・ララ/ユリアーネ・ケーラー/トーマス・クレッチマン/コリンナ・ハルフォーフ/ウルリッヒ・マテス/ハイノ・フェルヒ/ウルリッヒ・ヌーテン/クリスチャン・ベルケル/アレクサンダー・ヘルト/ハインリヒ・シュミーダー/トーマス・ティーメ●日本公開:2005/07●配給:ギャガ●最初に観た場所:渋谷・シネマライズ(05-09-24)(評価:★★★★) ウルリッヒ・マテス(ヨーゼフ・ゲッベルス)・ブルーノ・ガンツ(アドルフ・ヒトラー)
の秘書だった Bis zur letzten Stunde」●時間:156分●出演:ブルーノ・ガンツ/アレクサンドラ・マリア・ララ/ユリアーネ・ケーラー/トーマス・クレッチマン/コリンナ・ハルフォーフ/ウルリッヒ・マテス/ハイノ・フェルヒ/ウルリッヒ・ヌーテン/クリスチャン・ベルケル/アレクサンダー・ヘルト/ハインリヒ・シュミーダー/トーマス・ティーメ●日本公開:2005/07●配給:ギャガ●最初に観た場所:渋谷・シネマライズ(05-09-24)(評価:★★★★) ウルリッヒ・マテス(ヨーゼフ・ゲッベルス)・ブルーノ・ガンツ(アドルフ・ヒトラー)




 刑務所を裏取引で出所したドク・マッコイ(スティーブ・マックイーン)は、引き換えに、取引相手のテキサスの政界実力者ベニヨン(ベン・ジョンソン)の要求で、妻キャロル(アリ・マッグロー)と銀行強
刑務所を裏取引で出所したドク・マッコイ(スティーブ・マックイーン)は、引き換えに、取引相手のテキサスの政界実力者ベニヨン(ベン・ジョンソン)の要求で、妻キャロル(アリ・マッグロー)と銀行強 盗に手を染める。ベニヨンからはルディ(アル・レッティエリ)とジャクソン(ボー・ホプキンズ)が助手兼ドクの監視役として送り込まれ、綿密な計画の末に強盗は何とか成功するが、ジャクソンが銀行の守衛を射殺してしまう。ルディは目撃者に面が割れたジャクソンを車内で射殺し、今度はドクに銃を向けるが、ドクの銃が先に火を吹く。ドクは、銀行から奪った金を約束通りベニヨンの元に運び込ぶが、キャロルの様子がおかしく、実はベニヨンとキャロルは男女の関係にあり、当初はドク
盗に手を染める。ベニヨンからはルディ(アル・レッティエリ)とジャクソン(ボー・ホプキンズ)が助手兼ドクの監視役として送り込まれ、綿密な計画の末に強盗は何とか成功するが、ジャクソンが銀行の守衛を射殺してしまう。ルディは目撃者に面が割れたジャクソンを車内で射殺し、今度はドクに銃を向けるが、ドクの銃が先に火を吹く。ドクは、銀行から奪った金を約束通りベニヨンの元に運び込ぶが、キャロルの様子がおかしく、実はベニヨンとキャロルは男女の関係にあり、当初はドク を裏切って消す考えだったのだ。しかし、キャロルはドクではなくベニヨンを射殺する。ドクは逃走中に車を止め、嫉妬と怒りからキャロルを殴り倒す。一方のルディは、防弾チョッキ
を裏切って消す考えだったのだ。しかし、キャロルはドクではなくベニヨンを射殺する。ドクは逃走中に車を止め、嫉妬と怒りからキャロルを殴り倒す。一方のルディは、防弾チョッキ のお蔭で死んでおらず、獣医の家に押し入り、ドクに撃たれた肩の治療をしていたが、ベニヨンの死を知り、ドクの追跡を開始する。ドクは町で自分が指名手配になっているのを知ってショットガンを
のお蔭で死んでおらず、獣医の家に押し入り、ドクに撃たれた肩の治療をしていたが、ベニヨンの死を知り、ドクの追跡を開始する。ドクは町で自分が指名手配になっているのを知ってショットガンを 買い求め、警察に追われながらも逃げて、エルパソのホテルに辿り着く。だが、そこへはルディが先回りしていて、ベニヨンの手下も向かっていた。ルディがホテルに現れ、ドグが彼を殴り倒した時に今度はベニヨンの手下が現れて大銃撃戦が始まるが、ドクのショットガンで全員が倒され、ルディも射殺される。ドクはホテルからメキシコ人の老人のトラックに乗り込み、国境を越えたところで老人からトラックを買取り、夫婦はメキシコ側へ消えていく―。
買い求め、警察に追われながらも逃げて、エルパソのホテルに辿り着く。だが、そこへはルディが先回りしていて、ベニヨンの手下も向かっていた。ルディがホテルに現れ、ドグが彼を殴り倒した時に今度はベニヨンの手下が現れて大銃撃戦が始まるが、ドクのショットガンで全員が倒され、ルディも射殺される。ドクはホテルからメキシコ人の老人のトラックに乗り込み、国境を越えたところで老人からトラックを買取り、夫婦はメキシコ側へ消えていく―。
 しかしながら故・淀川長治は、必ずしも2人の未来は明るいと示唆されているわけではないと言っており、これは、原作にこの続きがあって、バッドエンディンが待ち受けていることを指していたのでしょうか。但し、原作における主人公のキャラクターは極悪人に近く、取引上やむなく銀行強盗をする映画の主人公とはかなり異なるようです。個人的には、この映画のラストには、やはり何となくほっとさせられます。
しかしながら故・淀川長治は、必ずしも2人の未来は明るいと示唆されているわけではないと言っており、これは、原作にこの続きがあって、バッドエンディンが待ち受けていることを指していたのでしょうか。但し、原作における主人公のキャラクターは極悪人に近く、取引上やむなく銀行強盗をする映画の主人公とはかなり異なるようです。個人的には、この映画のラストには、やはり何となくほっとさせられます。
 妻役のアリ・マックグローは銃を扱ったことがなく、マックイーンが銃の撃ち方を教えて銃に慣れさせたりもしたそうです
妻役のアリ・マックグローは銃を扱ったことがなく、マックイーンが銃の撃ち方を教えて銃に慣れさせたりもしたそうです が、「ある愛の詩」('70年)の白血病で死んでいく女子大生よりは、こちらの方が"演技開眼"している印象です。でも、この作品での共演をきっかけにマックイーンと結婚し、この後2本だけ映画に出て実質的に映画界を引退してしまいました。6年後に離婚してしまったことを考えると惜しい気もしますが、2006年に68歳で Festen(映画「セレブレーション」の舞台化)でブロードウェイ・デビューを果たしています。
が、「ある愛の詩」('70年)の白血病で死んでいく女子大生よりは、こちらの方が"演技開眼"している印象です。でも、この作品での共演をきっかけにマックイーンと結婚し、この後2本だけ映画に出て実質的に映画界を引退してしまいました。6年後に離婚してしまったことを考えると惜しい気もしますが、2006年に68歳で Festen(映画「セレブレーション」の舞台化)でブロードウェイ・デビューを果たしています。
 一方、「ある愛の詩」で共演したライアン・オニールは、その後「ペーパー・ムーン」('73年)、「バリー・リンドン」('73年)などに主演するなどして活躍しましたが、2001年に慢性白血病に冒されていることが判明し、また、パートナーであったファラ・フォーセットのガンによる死(2009年6月25日、マイケル・ジャクソンと同じ日に亡くなった)を看取るとともに、自身も前立腺がんであることが公表(2012年)されていて、こちらはかなりタイヘンそうだなあと(2023年12月8日逝去・82歳没)。
一方、「ある愛の詩」で共演したライアン・オニールは、その後「ペーパー・ムーン」('73年)、「バリー・リンドン」('73年)などに主演するなどして活躍しましたが、2001年に慢性白血病に冒されていることが判明し、また、パートナーであったファラ・フォーセットのガンによる死(2009年6月25日、マイケル・ジャクソンと同じ日に亡くなった)を看取るとともに、自身も前立腺がんであることが公表(2012年)されていて、こちらはかなりタイヘンそうだなあと(2023年12月8日逝去・82歳没)。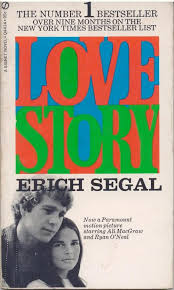 「ある愛の詩」は、エリック・シーガルによる同名の小説が原作ですが、未完の小説を原作として映画の製作が始まり、先に映画が完成し、映画の脚本を基に小説が執筆された部分もあるそうです。先に小説が刊行され、その数週間後に映画が公開されており、今で言う"メディアミックス"のはしりでした。ペーパーバックを読みましたが、初めて英語で読んだ小説の割には読み易かったのは、ある種ノベライゼーションに近かったせいもあるかもしれないし、ストーリーが古典的で結末が見えているせいもあったかもしれません。この映画のヒットの後、難病モノの映画が幾つか続いた記憶があります(アメリカ人は白血病モノが好きなのか?)。
「ある愛の詩」は、エリック・シーガルによる同名の小説が原作ですが、未完の小説を原作として映画の製作が始まり、先に映画が完成し、映画の脚本を基に小説が執筆された部分もあるそうです。先に小説が刊行され、その数週間後に映画が公開されており、今で言う"メディアミックス"のはしりでした。ペーパーバックを読みましたが、初めて英語で読んだ小説の割には読み易かったのは、ある種ノベライゼーションに近かったせいもあるかもしれないし、ストーリーが古典的で結末が見えているせいもあったかもしれません。この映画のヒットの後、難病モノの映画が幾つか続いた記憶があります(アメリカ人は白血病モノが好きなのか?)。 この映画がアメリカでヒットしたことについて、映画監督の大林宣彦氏はアメリカで封切り時にこの作品を現地で観ていて、ベトナム戦争で疲弊したアメリカが、本音ではこのような純愛ドラマを求めている時代感覚を肌で感じていたとのこと。但し、この映画の作られた1970年と言えばまだベトナム戦争の最中ですが、映画内にその影は一切見えません(最初観た時は"ノンポリ"恋愛映画だと思ったが、今思えば意図的にそうしていたのか)。日本でもヒットしたのは、古典的なストーリーに加えて、
この映画がアメリカでヒットしたことについて、映画監督の大林宣彦氏はアメリカで封切り時にこの作品を現地で観ていて、ベトナム戦争で疲弊したアメリカが、本音ではこのような純愛ドラマを求めている時代感覚を肌で感じていたとのこと。但し、この映画の作られた1970年と言えばまだベトナム戦争の最中ですが、映画内にその影は一切見えません(最初観た時は"ノンポリ"恋愛映画だと思ったが、今思えば意図的にそうしていたのか)。日本でもヒットしたのは、古典的なストーリーに加えて、 因みに、主人公のオリバー・バレット4世(ライアン・オニール)のルームメイト役で無名時代のトミー・リー・ジョーンズ(当時24歳)が出演していますが、その後3年間は映画の仕事がなく、彼の無名時代は長く続き、オリバー・ストーン監督の「
因みに、主人公のオリバー・バレット4世(ライアン・オニール)のルームメイト役で無名時代のトミー・リー・ジョーンズ(当時24歳)が出演していますが、その後3年間は映画の仕事がなく、彼の無名時代は長く続き、オリバー・ストーン監督の「 ライアン・オニール 2023年12月8日逝去。(82歳没)
ライアン・オニール 2023年12月8日逝去。(82歳没)
 (●ライアン・オニールが亡くなった。「ある愛の愛の詩」('70年)の興行的成功や「ザ・ドライバー」('78年)といった渋い作品もあるが、代表作はと言うとやはり「ペーパー・ムーン」('73年)と「バリー・リンドン」('73年)になるのではないか。「ペーパー・ムーン」は泣けた。原作はジョー・デヴィッド・ブラウンの小説『アディ・プレイ』だが、日本では『ペーパームーン』の題名でハヤカワ文庫 から刊行された。ライアン・オニールとテータム・オニールの父娘共演で話題になり、本国では年間トップの興行収入を得、1973年の第46回アカデミー賞ではテータム・オニールが史上最年少で助演女優賞を受賞したが、その後、彼女が思ったほど伸びなかったことを思うと、ピーター・ボグダノヴィッチ監督の演出力がやはり大きかったか、または、父親ライアンの導き方が上手かったのか(個人的評価は、初見の時の感動に沿って★★★★☆)。
(●ライアン・オニールが亡くなった。「ある愛の愛の詩」('70年)の興行的成功や「ザ・ドライバー」('78年)といった渋い作品もあるが、代表作はと言うとやはり「ペーパー・ムーン」('73年)と「バリー・リンドン」('73年)になるのではないか。「ペーパー・ムーン」は泣けた。原作はジョー・デヴィッド・ブラウンの小説『アディ・プレイ』だが、日本では『ペーパームーン』の題名でハヤカワ文庫 から刊行された。ライアン・オニールとテータム・オニールの父娘共演で話題になり、本国では年間トップの興行収入を得、1973年の第46回アカデミー賞ではテータム・オニールが史上最年少で助演女優賞を受賞したが、その後、彼女が思ったほど伸びなかったことを思うと、ピーター・ボグダノヴィッチ監督の演出力がやはり大きかったか、または、父親ライアンの導き方が上手かったのか(個人的評価は、初見の時の感動に沿って★★★★☆)。
 「バリー・リンドン」は、スタンリー・キューブリック監督が、18世紀のヨーロッパを舞台とし、ウィリアム・メイクピース・サッカレーによる小説"The Luck of Barry Lyndon"(1844年)を原作としたもので、アカデミー賞の撮影賞、歌曲賞、美術賞、衣裳デザイン賞を受賞した。世評は「ペーパー・ムーン」よりむしろ「バリー・リンドン」の方が上か。ただ、"ライアン・オニール"に目線を合わせると、主人公でを演じる彼が抑制を効かせた演技をすることで回りを浮き立たせているので、彼自身はやや背景に埋没している印象も受けなくもない。ラストの決闘シーンにおいてさえそう感じる。そこがキューブリック監督の演出のやり方なのだろうが(個人的評価は★★★★)。)
「バリー・リンドン」は、スタンリー・キューブリック監督が、18世紀のヨーロッパを舞台とし、ウィリアム・メイクピース・サッカレーによる小説"The Luck of Barry Lyndon"(1844年)を原作としたもので、アカデミー賞の撮影賞、歌曲賞、美術賞、衣裳デザイン賞を受賞した。世評は「ペーパー・ムーン」よりむしろ「バリー・リンドン」の方が上か。ただ、"ライアン・オニール"に目線を合わせると、主人公でを演じる彼が抑制を効かせた演技をすることで回りを浮き立たせているので、彼自身はやや背景に埋没している印象も受けなくもない。ラストの決闘シーンにおいてさえそう感じる。そこがキューブリック監督の演出のやり方なのだろうが(個人的評価は★★★★)。)
 「ゲッタウェイ」●原題:THE GETAWAY●制作年:1972年●制作国:アメリカ●監督:サム・ペキンパー●製作:デヴィッド・フォスター/ミッチェル・ブロウアー●脚本:ウォルター・ヒル●撮影:ルシアン・バラード●音楽:デイヴ・グルーシン●原作:ジム・トンプスン●時間:122分●出演:スティーブ・マックィーン/アリ・マックグロー/ベン・ジョンソン/アル・レッティエリン/スリム・ピケンズ/リチャード・ブライト/ジャック・ダドスン/ボー・ホプキンス/ダブ・テイラー●日本公開:1973/03●配給:ワーナー・ブラザース●最初に観た場所:高田馬場パール坐(77-12-10)●2回目:自由が丘・武蔵野推理(84-09-23)(評価★★★★)●併映(1回目):「パピヨン」(フランクリン・J・シャフナー)●併映(2回目):「48時間」(ウォルター・ヒル)
「ゲッタウェイ」●原題:THE GETAWAY●制作年:1972年●制作国:アメリカ●監督:サム・ペキンパー●製作:デヴィッド・フォスター/ミッチェル・ブロウアー●脚本:ウォルター・ヒル●撮影:ルシアン・バラード●音楽:デイヴ・グルーシン●原作:ジム・トンプスン●時間:122分●出演:スティーブ・マックィーン/アリ・マックグロー/ベン・ジョンソン/アル・レッティエリン/スリム・ピケンズ/リチャード・ブライト/ジャック・ダドスン/ボー・ホプキンス/ダブ・テイラー●日本公開:1973/03●配給:ワーナー・ブラザース●最初に観た場所:高田馬場パール坐(77-12-10)●2回目:自由が丘・武蔵野推理(84-09-23)(評価★★★★)●併映(1回目):「パピヨン」(フランクリン・J・シャフナー)●併映(2回目):「48時間」(ウォルター・ヒル)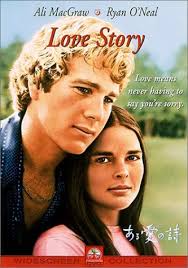
 「ある愛の詩」●原題:LOVE STORY●制作年:1970年●制作国:アメリカ●監督:アーサー・ヒラー●製作:ハワード・ミンスキー●脚本:エリック・シーガル●撮影:リチャード・クラディナ●音楽:フランシス・レイ●原作:エリック・シーガル●時間:99分●出演:ライアン・オニール/アリ・マックグロー/ジョン・マーレー/レイ・ミランド/キャサリン・バルフォー/シドニー・ウォーカー/ロバート・モディカ/ラッセル・ナイプ/トミー・リー・ジョーンズ ●日本公開:1971/03●配給:ワーナー・ブラザース●最初に観た場所:三鷹オスカー(80-11-03)(評価★★★)●併映:「おもいでの夏」(ロバート・マリガン)/「フォロー・ミー」(キャロル・リード)
「ある愛の詩」●原題:LOVE STORY●制作年:1970年●制作国:アメリカ●監督:アーサー・ヒラー●製作:ハワード・ミンスキー●脚本:エリック・シーガル●撮影:リチャード・クラディナ●音楽:フランシス・レイ●原作:エリック・シーガル●時間:99分●出演:ライアン・オニール/アリ・マックグロー/ジョン・マーレー/レイ・ミランド/キャサリン・バルフォー/シドニー・ウォーカー/ロバート・モディカ/ラッセル・ナイプ/トミー・リー・ジョーンズ ●日本公開:1971/03●配給:ワーナー・ブラザース●最初に観た場所:三鷹オスカー(80-11-03)(評価★★★)●併映:「おもいでの夏」(ロバート・マリガン)/「フォロー・ミー」(キャロル・リード)
 「ペーパー・ムーン」●原題:PAPER MOON●制作年:1973年●制作国:アメリカ●監督・製作:ピーター・ボグダノヴィッチ●脚本:アルヴィン・サージェント●撮影:ラズロ・コヴァックス●原作:ジョー・デヴィッド・ブラウン●時間:103分●出演:ラ
「ペーパー・ムーン」●原題:PAPER MOON●制作年:1973年●制作国:アメリカ●監督・製作:ピーター・ボグダノヴィッチ●脚本:アルヴィン・サージェント●撮影:ラズロ・コヴァックス●原作:ジョー・デヴィッド・ブラウン●時間:103分●出演:ラ イアン・オニール/テータム・オニール/マデリーン・カーン/ジョン・ヒラーマン/P・J・ジョンソン/ジェシー・リー・フルトン/ェームズ・N・ハレル/リラ・ウォーターズ/ノーブル・ウィリンガム/ジャック・ソーンダース/ジョディ・ウィルバー/リズ・ロス/エド・リード/ドロシー・プライス/ドロシー・フォースター/バートン・ギリアム/ランディ・クエイド●日本公開:1974/03●配給:パラマウント映画●最初に観た場所:名画座ミラノ(77-12-18)●2回目:名画座ミラノ(77-12-18)(評価★★★★☆)
イアン・オニール/テータム・オニール/マデリーン・カーン/ジョン・ヒラーマン/P・J・ジョンソン/ジェシー・リー・フルトン/ェームズ・N・ハレル/リラ・ウォーターズ/ノーブル・ウィリンガム/ジャック・ソーンダース/ジョディ・ウィルバー/リズ・ロス/エド・リード/ドロシー・プライス/ドロシー・フォースター/バートン・ギリアム/ランディ・クエイド●日本公開:1974/03●配給:パラマウント映画●最初に観た場所:名画座ミラノ(77-12-18)●2回目:名画座ミラノ(77-12-18)(評価★★★★☆)
 「バリー・リンドン」●原題:BARRY LYNDON●制作年:1975年●制作国:イギリス・アメリカ●監督・製作・脚本:スタンリー・キューブリック●撮影:ジョン・オルコット●音楽: レナード・ローゼンマン●原作:ウィリアム・メイクピース・サッカレー●時間:185分●出演:ライアン・オニール/マリサ・ベレンソン/ハーディ・クリューガー/ゲイ・ハミルトン/レオナルド・ロッシーター/アーサー・オサリヴァン/ゴッドフリー・クイグリー/パトリック・マギー/フランク・ミドルマス●日本公開:1976/07●配給:ワーナー・ブラザース●最初に観た場所:飯田橋・ギンレイホール(79-02-05)(評価★★★★)
「バリー・リンドン」●原題:BARRY LYNDON●制作年:1975年●制作国:イギリス・アメリカ●監督・製作・脚本:スタンリー・キューブリック●撮影:ジョン・オルコット●音楽: レナード・ローゼンマン●原作:ウィリアム・メイクピース・サッカレー●時間:185分●出演:ライアン・オニール/マリサ・ベレンソン/ハーディ・クリューガー/ゲイ・ハミルトン/レオナルド・ロッシーター/アーサー・オサリヴァン/ゴッドフリー・クイグリー/パトリック・マギー/フランク・ミドルマス●日本公開:1976/07●配給:ワーナー・ブラザース●最初に観た場所:飯田橋・ギンレイホール(79-02-05)(評価★★★★)

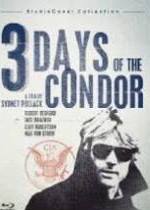


 ニューヨークにあるアメリカ文学史協会は、CIAの外郭団体として世界各国の雑誌書籍の情報分析を行っている。協会職員は学者肌のCIA分析官で構成されていた。ある日の白昼、アメリカ文学史協会は短機関銃で武装した男3人により襲撃さ
ニューヨークにあるアメリカ文学史協会は、CIAの外郭団体として世界各国の雑誌書籍の情報分析を行っている。協会職員は学者肌のCIA分析官で構成されていた。ある日の白昼、アメリカ文学史協会は短機関銃で武装した男3人により襲撃さ れ、協会職員は次々と射殺される。たまたま裏口から外出していたために命拾いをしたコードネーム"コンドル"ことジョセフ・ターナー(ロバート・レッドフォード)は、CIA本部に緊急連絡し保護を求める。CIA次官
れ、協会職員は次々と射殺される。たまたま裏口から外出していたために命拾いをしたコードネーム"コンドル"ことジョセフ・ターナー(ロバート・レッドフォード)は、CIA本部に緊急連絡し保護を求める。CIA次官 のヒギンズ(クリフ・ロバートソン)からの指示で第17課長のウィクスという男に落ち合うことになったが、
のヒギンズ(クリフ・ロバートソン)からの指示で第17課長のウィクスという男に落ち合うことになったが、 そのウィクスに銃撃を受ける。辛くも逃走したが、孤立状態となったコンドルは、偶然見かけた女性写真家キャサリン・ヘイル(フェイ・ダナウェイ)を拉致同然に巻き込み、独力で真相を暴こうとする。CIAの暗部に近づこうとするコンドルに謎の殺し屋ジュベール(マックス・フォン・シドー)が忍び寄る―。(「Wikipedia」より)
そのウィクスに銃撃を受ける。辛くも逃走したが、孤立状態となったコンドルは、偶然見かけた女性写真家キャサリン・ヘイル(フェイ・ダナウェイ)を拉致同然に巻き込み、独力で真相を暴こうとする。CIAの暗部に近づこうとするコンドルに謎の殺し屋ジュベール(マックス・フォン・シドー)が忍び寄る―。(「Wikipedia」より)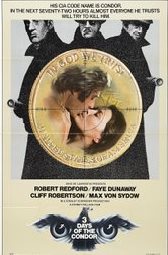

 ニューヨークの地味なビルに入っている表向きは「アメリカ文学史協会」という地味な組織が実はCIAの下部組織で、職員は世界中の推理小説やコミックスを読み漁り、そこに隠された敵対勢力の謀略、暗号の意味を解読する仕事を日夜行っているというのが面白いです(今日であればそうした仕事はコンピュータやAIが肩代わりして、フィクションであっても成り立たないような職業のようにも思えるが、そのレトロ感がいい)。
ニューヨークの地味なビルに入っている表向きは「アメリカ文学史協会」という地味な組織が実はCIAの下部組織で、職員は世界中の推理小説やコミックスを読み漁り、そこに隠された敵対勢力の謀略、暗号の意味を解読する仕事を日夜行っているというのが面白いです(今日であればそうした仕事はコンピュータやAIが肩代わりして、フィクションであっても成り立たないような職業のようにも思えるが、そのレトロ感がいい)。 ある日突然仕事仲間を全員を殺害された"コンドル"は、何が何だか分からないまま得体の知れない巨大な敵から逃れながら、孤独な闘いを強いられますが、その際に、CIA職員であるとは言え、凄腕の諜報部員でも何でもない単なる本の虫に過ぎない彼が、仕事で培った本から得た知識や戦略を駆使して自らを守り、逆襲に出るというわけです。
ある日突然仕事仲間を全員を殺害された"コンドル"は、何が何だか分からないまま得体の知れない巨大な敵から逃れながら、孤独な闘いを強いられますが、その際に、CIA職員であるとは言え、凄腕の諜報部員でも何でもない単なる本の虫に過ぎない彼が、仕事で培った本から得た知識や戦略を駆使して自らを守り、逆襲に出るというわけです。
 ネタバレにまりますが、結局CIAの中に中東に戦争を仕掛けたがっている派閥、いわば〈もう1つのCIA〉があって、その連中が黒幕です(湾岸戦争やイラク戦争のことを想うと、ある意味"先駆的"な設定とも言え、こうした映画を作るところがいい意味でアメリカ的でもある)。最後"コンドル"は絶体絶命の危機に陥りますが、そこには思わぬ展開が待っていました。
ネタバレにまりますが、結局CIAの中に中東に戦争を仕掛けたがっている派閥、いわば〈もう1つのCIA〉があって、その連中が黒幕です(湾岸戦争やイラク戦争のことを想うと、ある意味"先駆的"な設定とも言え、こうした映画を作るところがいい意味でアメリカ的でもある)。最後"コンドル"は絶体絶命の危機に陥りますが、そこには思わぬ展開が待っていました。
 更にネタバレになりますが、マックス・フォン・シドー演じる殺し屋は、結局、〈もう1つのCIA〉と〈本来のCIA〉の両方から雇われたわけなのだなあと。そんなことあり得るかとも思ったりしましたが、敵の目を眩ますために理屈上はあり得るのかも。マックス・フォン・シドーが映画を通してずっと不気味だったのに、最後は急にいい人っぽい感じになって、このギャップが可笑しかったですが、殺し屋が今までターゲットとして狙っていた人間にいきなりスカウトの声掛けをするかなあ(これも原作通りなのか、それともこの辺りは映画でのある種"お遊び"なのか)。
更にネタバレになりますが、マックス・フォン・シドー演じる殺し屋は、結局、〈もう1つのCIA〉と〈本来のCIA〉の両方から雇われたわけなのだなあと。そんなことあり得るかとも思ったりしましたが、敵の目を眩ますために理屈上はあり得るのかも。マックス・フォン・シドーが映画を通してずっと不気味だったのに、最後は急にいい人っぽい感じになって、このギャップが可笑しかったですが、殺し屋が今までターゲットとして狙っていた人間にいきなりスカウトの声掛けをするかなあ(これも原作通りなのか、それともこの辺りは映画でのある種"お遊び"なのか)。 もっと注目されていい"隠れた傑作"だとは思いますが、やや気になったのは、いくらダウンタウンの犯罪多発地域だとは言え、敵方が協会職員を全員殺害したのは、ちょっと乱暴と言うか、リスクがありすぎるように思いました(彼らにだって家族や友人はいるわけで、事件を完全に揉み消すのは何れの立場の側にとっても難しいのでは。強盗のせいにするにしても、押し入った先が「アメリカ文学史協会」では...)。
もっと注目されていい"隠れた傑作"だとは思いますが、やや気になったのは、いくらダウンタウンの犯罪多発地域だとは言え、敵方が協会職員を全員殺害したのは、ちょっと乱暴と言うか、リスクがありすぎるように思いました(彼らにだって家族や友人はいるわけで、事件を完全に揉み消すのは何れの立場の側にとっても難しいのでは。強盗のせいにするにしても、押し入った先が「アメリカ文学史協会」では...)。 フェイ・ダナウェイは珍しく受身的な役回りで、マックス・フォン・シドーの方が記憶に残っていましたが、久しぶりに観直してみると演技達者であることには変わりありませんでした。但し、あくまでも主演はレッドフォードで、フェイ・ダナウェイはやはり一歩引いたポジショニングでした。先に挙げたシドニー・ポラック監督によるロバート・レッドフォードと女優たちの共演作で、主演女優の方がレッドフォードより前面に出ているのは、「
フェイ・ダナウェイは珍しく受身的な役回りで、マックス・フォン・シドーの方が記憶に残っていましたが、久しぶりに観直してみると演技達者であることには変わりありませんでした。但し、あくまでも主演はレッドフォードで、フェイ・ダナウェイはやはり一歩引いたポジショニングでした。先に挙げたシドニー・ポラック監督によるロバート・レッドフォードと女優たちの共演作で、主演女優の方がレッドフォードより前面に出ているのは、「 「コンドル」●原題:THREE DAYS OF THE CONDOR●制作年:1975年●制作国:アメリカ●監督:シドニー・ポラック●製作:スタンリー・シュナイダー●脚本:ロレンツォ・センプル・ジュニア/デヴィッド・レイフィール●撮影:オーウェン・ロイズマン●音楽:デイヴ・グルーシン●原作:ジェームズ・グラディ「コンドルの六日間」●時間:118分●出演:ロバート・レッドフォード/フェイ・ダナウェイ/クリフ・ロバートソン/マックス・フォン・シドー/マイケル・ケーン/アディソン・パウエル/ウォルター・マッギン/ジョン・ハウスマン/ティナ・チェン/ドン・マクヘンリー/ヘレン・ステンボーグ/ハンスフォード・ロウ/ジェス・オスナ/ハンク・ギャレット/カーリン・グリン●日本公開:1975/11●配給:東宝東和●最初に観た場所:池袋文芸坐(78-05-04)(評価★★★★)●併映「合衆国最後の日」(ロバート・アルドリッチ)
「コンドル」●原題:THREE DAYS OF THE CONDOR●制作年:1975年●制作国:アメリカ●監督:シドニー・ポラック●製作:スタンリー・シュナイダー●脚本:ロレンツォ・センプル・ジュニア/デヴィッド・レイフィール●撮影:オーウェン・ロイズマン●音楽:デイヴ・グルーシン●原作:ジェームズ・グラディ「コンドルの六日間」●時間:118分●出演:ロバート・レッドフォード/フェイ・ダナウェイ/クリフ・ロバートソン/マックス・フォン・シドー/マイケル・ケーン/アディソン・パウエル/ウォルター・マッギン/ジョン・ハウスマン/ティナ・チェン/ドン・マクヘンリー/ヘレン・ステンボーグ/ハンスフォード・ロウ/ジェス・オスナ/ハンク・ギャレット/カーリン・グリン●日本公開:1975/11●配給:東宝東和●最初に観た場所:池袋文芸坐(78-05-04)(評価★★★★)●併映「合衆国最後の日」(ロバート・アルドリッチ)

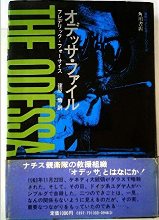

 1963年11月22日、西独ハンブルグ。新聞記者あがりのルポライター、ペーター・ミラー(ジョン・ヴォイト)は母親(マリア・シェル)の家を訪ねた帰り道、カーラジオでケネディ大統領暗殺の臨時ニュースを聴く。その時一台の救急車が彼の車を追い越し、ミラーは反射的にその後を追う。事件は一老人のガス自殺だったが、翌日、知人の警部補から自殺した老人の日記を渡される。老人はドイツ系ユダヤ人で、日記はラトビアのリガにあったナチ収容所での地獄の生活を記録したものだった。老人は、リガ収容所長だったSS大尉ロシュマン(マクシミリアン・シェル)の非人道的な残虐さを呪い、復讐しようとしていたが果たさず、絶望のうちに自殺したのだ。ミラーは老人に
1963年11月22日、西独ハンブルグ。新聞記者あがりのルポライター、ペーター・ミラー(ジョン・ヴォイト)は母親(マリア・シェル)の家を訪ねた帰り道、カーラジオでケネディ大統領暗殺の臨時ニュースを聴く。その時一台の救急車が彼の車を追い越し、ミラーは反射的にその後を追う。事件は一老人のガス自殺だったが、翌日、知人の警部補から自殺した老人の日記を渡される。老人はドイツ系ユダヤ人で、日記はラトビアのリガにあったナチ収容所での地獄の生活を記録したものだった。老人は、リガ収容所長だったSS大尉ロシュマン(マクシミリアン・シェル)の非人道的な残虐さを呪い、復讐しようとしていたが果たさず、絶望のうちに自殺したのだ。ミラーは老人に 代わってそのロシュマンを捜し出す決心をする。彼はまず、老人の仲間を捜し出し、"オデッサ"という、元ナチSS隊員で作った、ナチ狩りから逃れ身元を偽って社会にもぐり込んでいる元ナチSS隊員を法廷にかけさせないために様々な活動をしている秘密組織の存在を知る。数日後、ミラーが恋人のジギー(メアリー・タム)とXマスの買物のために地下鉄に乗ろうとしたとき、突然後から何者かに走ってくる電車に向かって突き落とされる。間一髪で命は助かるが、こうなるとミラーとしても意地があった。米資料センターでロシュマンの資料を発見したミラーは、帰りに3人組に捕まる。彼らは元SS隊員に復讐することを目的としたグループで、ミラーが"オデッサ"を追っているのを知り、彼に協力しようという
代わってそのロシュマンを捜し出す決心をする。彼はまず、老人の仲間を捜し出し、"オデッサ"という、元ナチSS隊員で作った、ナチ狩りから逃れ身元を偽って社会にもぐり込んでいる元ナチSS隊員を法廷にかけさせないために様々な活動をしている秘密組織の存在を知る。数日後、ミラーが恋人のジギー(メアリー・タム)とXマスの買物のために地下鉄に乗ろうとしたとき、突然後から何者かに走ってくる電車に向かって突き落とされる。間一髪で命は助かるが、こうなるとミラーとしても意地があった。米資料センターでロシュマンの資料を発見したミラーは、帰りに3人組に捕まる。彼らは元SS隊員に復讐することを目的としたグループで、ミラーが"オデッサ"を追っているのを知り、彼に協力しようという のだ。ミラーを"オデッサ"に潜入させる工作が始まる。元ナチ隊員で病死した男コルブの出身証明書を盗み、彼に化けて元SS軍曹で警察に追われているという設定で"オデッサ"に接近、下級隊員の紹介で幹部に会うことになる。ミラーはファイルを盗み出し、ロシュマンの足跡を掴むことが出来た。ロシュマンを尾行し、彼の屋敷に潜入して彼と対峙する―。
のだ。ミラーを"オデッサ"に潜入させる工作が始まる。元ナチ隊員で病死した男コルブの出身証明書を盗み、彼に化けて元SS軍曹で警察に追われているという設定で"オデッサ"に接近、下級隊員の紹介で幹部に会うことになる。ミラーはファイルを盗み出し、ロシュマンの足跡を掴むことが出来た。ロシュマンを尾行し、彼の屋敷に潜入して彼と対峙する―。 発表の第2作『オデッサ・ファイル(The Odessa File)』('74年・角川書店)。1974年発表の『
発表の第2作『オデッサ・ファイル(The Odessa File)』('74年・角川書店)。1974年発表の『 ーケンが演じた主人公がなぜ傭兵になったのか分からないまま終わってしまっていました。この「オデッサ・ファイル」でペーター・ミラーを演じたジョン・ボイドはどうかというと、原作の主人公(原作ではミューラー)のイメージと違っていたかもしれませんが、ジョン・ボイドが当時まだ若いながらも演技達者なのと、主人公が相手方に潜入してから
ーケンが演じた主人公がなぜ傭兵になったのか分からないまま終わってしまっていました。この「オデッサ・ファイル」でペーター・ミラーを演じたジョン・ボイドはどうかというと、原作の主人公(原作ではミューラー)のイメージと違っていたかもしれませんが、ジョン・ボイドが当時まだ若いながらも演技達者なのと、主人公が相手方に潜入してから の危機の脱し方など部分的には原作を改変しているものの、大まかには原作に沿っていたため、個人的には楽しめました(原作の主人公の愛車がジャガーであるのに映画ではベンツになっていた一方、オデッサの殺し屋のクルマがジャガーだった。この辺りは意図的に変えている?)。評価として、「ジャッカルの日」「オデッサ・ファイル」「戦争の犬たち」の順で、やはり監督の知名度順になるのでしょうか)。
の危機の脱し方など部分的には原作を改変しているものの、大まかには原作に沿っていたため、個人的には楽しめました(原作の主人公の愛車がジャガーであるのに映画ではベンツになっていた一方、オデッサの殺し屋のクルマがジャガーだった。この辺りは意図的に変えている?)。評価として、「ジャッカルの日」「オデッサ・ファイル」「戦争の犬たち」の順で、やはり監督の知名度順になるのでしょうか)。 「ジャッカルの日」の主人公はプロのスナイパーであり、「戦争の犬たち」の主人公はプロの傭兵、それに対してこの「オデッサ・ファイル」の主人公だけがある意味アマチュアであり、素人が元SS軍曹に化けて"オデッサ"に潜入することが出来るのかというリアリティの問題がありますが、"オデッサ"幹部将校が主人公の身許審査のためSSについて矢継ぎ早にした質問で、「収容所の真中に何が見えたか?」との問いに、答えに詰まって「空が見えました」と答えてしまい、将校の眼が鋭く光るといった場面など、逆に旨い具合に緊張感を生む効果にも繋がっていたかも。なぜジャーナリストとは言え、一市民に過ぎない主人公が元SS大尉ロシュマンにこだわるのか、作品の鍵となるその秘密の明かされ方は原作と同じで、但し、原作を読んでいると、映画の方はややあっけなくて、ちょっともの足りなかったでしょうか。
「ジャッカルの日」の主人公はプロのスナイパーであり、「戦争の犬たち」の主人公はプロの傭兵、それに対してこの「オデッサ・ファイル」の主人公だけがある意味アマチュアであり、素人が元SS軍曹に化けて"オデッサ"に潜入することが出来るのかというリアリティの問題がありますが、"オデッサ"幹部将校が主人公の身許審査のためSSについて矢継ぎ早にした質問で、「収容所の真中に何が見えたか?」との問いに、答えに詰まって「空が見えました」と答えてしまい、将校の眼が鋭く光るといった場面など、逆に旨い具合に緊張感を生む効果にも繋がっていたかも。なぜジャーナリストとは言え、一市民に過ぎない主人公が元SS大尉ロシュマンにこだわるのか、作品の鍵となるその秘密の明かされ方は原作と同じで、但し、原作を読んでいると、映画の方はややあっけなくて、ちょっともの足りなかったでしょうか。 ラストで主人公に追い詰められて、身勝手な理論に基づく演説をぶつロシュマンを演じた オーストリア人俳優のマクシミリアン・シェル(1930-2014)も好演で、主人公の母親役のマリア・シェル(1926-2005)
ラストで主人公に追い詰められて、身勝手な理論に基づく演説をぶつロシュマンを演じた オーストリア人俳優のマクシミリアン・シェル(1930-2014)も好演で、主人公の母親役のマリア・シェル(1926-2005) は彼の実姉になります(「
は彼の実姉になります(「 因みに、マクシミリアン・シェルが演じたエドゥアルト・ロシュマンは実在の人物で、リガにあった強制収容所の歴代所長の一人で、"リガの屠殺人"と呼ばれ、1977年7月、アルゼンチン警察に逮捕されるも、4日後に国外退去を条件に釈放され、同年8月、アルゼンチンとパラグアイの間の船上で心臓発作を起こし、69歳死亡しています(この作品の原作をフォーサイスが書いていた時はまだ逃亡・潜伏中だったということか)。
因みに、マクシミリアン・シェルが演じたエドゥアルト・ロシュマンは実在の人物で、リガにあった強制収容所の歴代所長の一人で、"リガの屠殺人"と呼ばれ、1977年7月、アルゼンチン警察に逮捕されるも、4日後に国外退去を条件に釈放され、同年8月、アルゼンチンとパラグアイの間の船上で心臓発作を起こし、69歳死亡しています(この作品の原作をフォーサイスが書いていた時はまだ逃亡・潜伏中だったということか)。 「オデッサ・ファイル」●原題:THE ODESSA FILE●制作年:1974年●制作国:イギリス・西ドイツ●監督:ロナルド・ニーム●製作:ジョン・ウルフ●脚本:ケネス・ロス/ジョージ・マークスタイン●撮影:オズワルド・モリス●音楽:アンドルー・ロイド・ウェバー●原作:フレデリック・フォーサイス●時間:130分●出演:ジョン・ヴォイト/マクシミリアン・シェル/マリア・シェル /メアリー・タム/デレク・ジャコビ/ハンネス・メッセマー/シュミュエル・ロデンスキー/エルンスト・シュレーダー/グンナー・メラー/ポール・ジェフリー/エル・ウィルマン/クラウス・レーヴィッチ/タウジェ・クライナー/ギュンター・シュトラック/クルト・マイゼル/マルティン・ブラント/ギュンター・マイスナー/アレクサンドル・ゴリング/エリザーベト・ノイマン=フィアテル/クリスティン・ウォデツキー/ミリアム・マーラー/オスカー・ウェルナー●日本公開:1975/03●配給:コロムビア映画●最初に観た場所:新宿ローヤル(82-12-08)(評価★★★☆)
「オデッサ・ファイル」●原題:THE ODESSA FILE●制作年:1974年●制作国:イギリス・西ドイツ●監督:ロナルド・ニーム●製作:ジョン・ウルフ●脚本:ケネス・ロス/ジョージ・マークスタイン●撮影:オズワルド・モリス●音楽:アンドルー・ロイド・ウェバー●原作:フレデリック・フォーサイス●時間:130分●出演:ジョン・ヴォイト/マクシミリアン・シェル/マリア・シェル /メアリー・タム/デレク・ジャコビ/ハンネス・メッセマー/シュミュエル・ロデンスキー/エルンスト・シュレーダー/グンナー・メラー/ポール・ジェフリー/エル・ウィルマン/クラウス・レーヴィッチ/タウジェ・クライナー/ギュンター・シュトラック/クルト・マイゼル/マルティン・ブラント/ギュンター・マイスナー/アレクサンドル・ゴリング/エリザーベト・ノイマン=フィアテル/クリスティン・ウォデツキー/ミリアム・マーラー/オスカー・ウェルナー●日本公開:1975/03●配給:コロムビア映画●最初に観た場所:新宿ローヤル(82-12-08)(評価★★★☆)
