「●ロベール・ブレッソン監督作品」の インデックッスへ Prev|NEXT ⇒ 【1046】 R・ブレッソン「ラルジャン」
「●「ベルリン国際映画祭 銀熊賞(審査員グランプリ)」受賞作」の インデックッスへ 「○外国映画 【制作年順】」の インデックッスへ
「白夜」「ラルジャン」と同じ研ぎ澄まされた現代劇。少し入り込みにくかったか。



「たぶん悪魔が [DVD]」
 裕福な家柄に生まれた美貌の青年シャルル(アントワーヌ・モニエ)は、自殺願望にとり憑かれている。左翼の政治集会や宗教論争に精神分析、そして環境問題を論じる大学サークルやヒッピーたちの集いに参加しても、そこに自分の居場所を見いだすことができず、違和感を抱くだけで何も変わらない。環
裕福な家柄に生まれた美貌の青年シャルル(アントワーヌ・モニエ)は、自殺願望にとり憑かれている。左翼の政治集会や宗教論争に精神分析、そして環境問題を論じる大学サークルやヒッピーたちの集いに参加しても、そこに自分の居場所を見いだすことができず、違和感を抱くだけで何も変わらない。環 境破壊を危惧する生態学者の友人ミシェル(アンリ・ド・モーブラン)や、シャルルに寄り添う二人の女性アルベルト(ティナ・イリサリ)とエドヴィージュ(レティシア・カルカノ)と一緒に過ごしても、死への誘惑を断ち切ることはできない。やがて冤罪で警察に連行されたシャルルは、さらなる虚無にさいなまれていく―。
境破壊を危惧する生態学者の友人ミシェル(アンリ・ド・モーブラン)や、シャルルに寄り添う二人の女性アルベルト(ティナ・イリサリ)とエドヴィージュ(レティシア・カルカノ)と一緒に過ごしても、死への誘惑を断ち切ることはできない。やがて冤罪で警察に連行されたシャルルは、さらなる虚無にさいなまれていく―。
 ロベール・ブレッソン監督が1977年に手掛けた作品で、第27回ベルリン国際映画祭で銀熊賞(審査員特別賞)を受賞していますが、日本では今年['22年]3月に初の劇場公開が実現した作品です。「たぶん悪魔が」というタイトルは、『カラマーゾフの兄弟』の中にあるイワンの「悪魔が裏で手を引いている」という表現から引いているとのことです(これ、イワンが父フョードルに神はいないと説き、では神を"でっち上げた" のは誰かと訊かれ、「悪魔でしょ、たぶん」と答えるも、さらにイワンは悪魔もいないと言う)。ブレッソン作品の中でも実験的な作品と言え、76歳にしてここまでラジカルな映画を撮るブレッソンには敬服しますが、それゆえに日本での公開が遅れたように思えなくもないです(ビデオグラム化としては、'08年に紀伊國屋書店よりリリースされた「ロベール・ブレッソン DVD-BOX」(3枚組)に収められた)。
ロベール・ブレッソン監督が1977年に手掛けた作品で、第27回ベルリン国際映画祭で銀熊賞(審査員特別賞)を受賞していますが、日本では今年['22年]3月に初の劇場公開が実現した作品です。「たぶん悪魔が」というタイトルは、『カラマーゾフの兄弟』の中にあるイワンの「悪魔が裏で手を引いている」という表現から引いているとのことです(これ、イワンが父フョードルに神はいないと説き、では神を"でっち上げた" のは誰かと訊かれ、「悪魔でしょ、たぶん」と答えるも、さらにイワンは悪魔もいないと言う)。ブレッソン作品の中でも実験的な作品と言え、76歳にしてここまでラジカルな映画を撮るブレッソンには敬服しますが、それゆえに日本での公開が遅れたように思えなくもないです(ビデオグラム化としては、'08年に紀伊國屋書店よりリリースされた「ロベール・ブレッソン DVD-BOX」(3枚組)に収められた)。
 主人公のシャルルは裕福な家柄に生まれた美貌の青年で、頭脳も優れていて、二人の女性の恋愛の対象にもなっているわけですが(それでいて行きずりのの女性と寝たりもする)、それでも死への誘惑にとり憑かれたらアウトなのだろなあ。一昨年['20年]に芸能人の自殺が相次いだのを思い出しました。シャルルの死を希求する気持ちの特徴は、彼の死への道筋に絡むように挿入される撲殺されるアザラシ、切り倒される木々、水俣病患者、核実験といった映像の数々から窺えるように、人類の未来への不安と同調している点です。
主人公のシャルルは裕福な家柄に生まれた美貌の青年で、頭脳も優れていて、二人の女性の恋愛の対象にもなっているわけですが(それでいて行きずりのの女性と寝たりもする)、それでも死への誘惑にとり憑かれたらアウトなのだろなあ。一昨年['20年]に芸能人の自殺が相次いだのを思い出しました。シャルルの死を希求する気持ちの特徴は、彼の死への道筋に絡むように挿入される撲殺されるアザラシ、切り倒される木々、水俣病患者、核実験といった映像の数々から窺えるように、人類の未来への不安と同調している点です。
冒頭に「ペール・ラシェーズ墓地で青年が自殺、いや他殺か?」という新聞記事を示しておいて、では実際に主人公がどのような自死の方法を選んだのかと思ったら、ラスト、薬物中毒の友人に自分を背後から射殺させた!(これって予想外だった)。 ベルリン国際映画祭の審査員だったでライナー・ヴェルナー・ファスビンダー監督が絶賛し、フランソワ・トリュフォーが「すばらしく官能的」と評した作品ですが、ちょっとついて行きにくい面もありました。
 その作品限りの素人ばかりを採用し(出演者を「モデル」と呼んだ)、音楽はほとんど使用せず、感情表現をも抑えた作風を貫くその作風(自らの作品を「シネマトグラフ」と称している)はこの作品においても徹底していて、友人や恋人がが自殺しそうな雰囲気だと周囲の人間はもっと焦って大騒ぎになりそうな気がしなくもないですが、この映画(「シネマトグラフ」と言うべきか)では、本人も周囲も意外と飄々としています。でも、その方が何となくリアリティがありそうな気もしました。
その作品限りの素人ばかりを採用し(出演者を「モデル」と呼んだ)、音楽はほとんど使用せず、感情表現をも抑えた作風を貫くその作風(自らの作品を「シネマトグラフ」と称している)はこの作品においても徹底していて、友人や恋人がが自殺しそうな雰囲気だと周囲の人間はもっと焦って大騒ぎになりそうな気がしなくもないですが、この映画(「シネマトグラフ」と言うべきか)では、本人も周囲も意外と飄々としています。でも、その方が何となくリアリティがありそうな気もしました。
現代の若者を描いているという点で、この作品の前と後のブレッソンの作品であるドストエフスキー原作の「白夜」('71年)、トルストイ原作の「ラルジャン」('83年)と同系譜のように思えましたが、それら二作と同様に映像的に研ぎ澄まされているものの、個人的には正直それらより少し入り込みにくかったかなという印象です。
このブレッソン監督の晩年現代劇3作(あと、今回「たぶん悪魔が」と同時公開された「湖のランスロ」('74年)があるが、時代設定は中世アーサー王伝説の時代になる)では、個人的評価は「白夜」がいちばんで、「ラルジャン」がそれに次いで、この「たぶん悪魔が」はその次でしょうか。ほとんど感覚的な好みであり、理屈で説明すると後付けになりそうです。
「白夜」('71年)(ドストエフスキー原作)/「ラルジャン」('83年)(トルストイ原作)



 「たぶん悪魔が」●原題:LE DIABLE ROBABLEMENT(THE DEVIL PROBABLY)●制作年:1977年●制作国:フランス●監督・脚本:ロベール・ブレッソン●製作:ステファン・チャルガジエフ●撮影:パスカリーノ・デ・サンティス●音楽:フィリップ・サルド●時間:97分●出演:アントワーヌ・モニエ/ティナ・イリサリ/アンリ・ド・モーブラン/レティシア・カルカノ●日本公開:2022/03●配給:マーメイドフィルム/コピアポア・フィルム●最初に観た場所:新宿シネマカリテ(22-04-19)(評価:★★★★)●併映(同日上映):「湖のランスロ」(ロベール・ブレッソン)
「たぶん悪魔が」●原題:LE DIABLE ROBABLEMENT(THE DEVIL PROBABLY)●制作年:1977年●制作国:フランス●監督・脚本:ロベール・ブレッソン●製作:ステファン・チャルガジエフ●撮影:パスカリーノ・デ・サンティス●音楽:フィリップ・サルド●時間:97分●出演:アントワーヌ・モニエ/ティナ・イリサリ/アンリ・ド・モーブラン/レティシア・カルカノ●日本公開:2022/03●配給:マーメイドフィルム/コピアポア・フィルム●最初に観た場所:新宿シネマカリテ(22-04-19)(評価:★★★★)●併映(同日上映):「湖のランスロ」(ロベール・ブレッソン)




 フランスの北端アンブリコート(パ・ド・カレー)に赴任した若い司祭(クロード・レデュ)は、胃の不調を感じながらも、初
フランスの北端アンブリコート(パ・ド・カレー)に赴任した若い司祭(クロード・レデュ)は、胃の不調を感じながらも、初 めての司祭としての仕事に純粋な覇気を奮起させ、日記を綴り始める。頑迷で不信心な村民の言動に戸惑いながら、領主である伯爵(ジャン・リヴェール)の協力を取り付け、トルシーの先輩司祭(アンドレ・ギベール)の助言を受けながら奮闘する若い司祭は、次第に村に蔓延している"神の存在への疑問"に対峙することになる。エネルギッシュだが世俗の不道徳に塗れた伯爵、現実の興味に比べて神など遠い存在の利発な若い娘セラ
めての司祭としての仕事に純粋な覇気を奮起させ、日記を綴り始める。頑迷で不信心な村民の言動に戸惑いながら、領主である伯爵(ジャン・リヴェール)の協力を取り付け、トルシーの先輩司祭(アンドレ・ギベール)の助言を受けながら奮闘する若い司祭は、次第に村に蔓延している"神の存在への疑問"に対峙することになる。エネルギッシュだが世俗の不道徳に塗れた伯爵、現実の興味に比べて神など遠い存在の利発な若い娘セラ フィタ(マルティーヌ・ルメール)、父親と家庭教師の女性ルイーズ(ニコル・モーリー)の不倫を知って悪意に心を占められている伯爵令嬢シャンタル(ニコール・ラドミラル)、夫の不倫と愛息の死によって神を呪うようになった伯爵夫人(マリ=モニーク・アルケル)。真摯に神を信仰する司祭をからかうことで不遇な日々の鬱憤晴らしをする村人たち。そうした村人たちとの会話や葛藤においても揺らぎない神への信仰を堅持する司祭だったが、真面目過ぎる信仰活動が村人から疎まれ、彼の健康も悪化の一途を辿っていく―。
フィタ(マルティーヌ・ルメール)、父親と家庭教師の女性ルイーズ(ニコル・モーリー)の不倫を知って悪意に心を占められている伯爵令嬢シャンタル(ニコール・ラドミラル)、夫の不倫と愛息の死によって神を呪うようになった伯爵夫人(マリ=モニーク・アルケル)。真摯に神を信仰する司祭をからかうことで不遇な日々の鬱憤晴らしをする村人たち。そうした村人たちとの会話や葛藤においても揺らぎない神への信仰を堅持する司祭だったが、真面目過ぎる信仰活動が村人から疎まれ、彼の健康も悪化の一途を辿っていく―。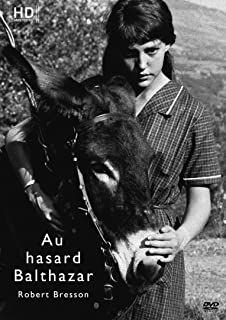




 しかしながら、キリストではなく一青年にすぎないこの若い司祭の苦悩と苦闘には一体どういう意味があったのか、本当に無意味だったのか、後に何か残ったのか、考えずにはおれない作品でした。ただ一つの救いは、夫の不倫と息子の死によって神を呪うようになった伯爵夫人(夫人役はサラ・ベルナールの愛弟子であった名女優マリ=モニーク・アルケル。因みにこの伯爵夫人や先輩司祭は本物の俳優が演じている)の告解を聴き、その魂を解き放ったかに見えたこととでしたが、その夫人も自殺してしまって無に帰し、それどころか、夫人が亡くなったのは司祭のせいであるというふうに村人からは見られてしまうという、しかも、自分が胃癌に冒されていることが発覚するし、この監督、「バルタザールどこへ行く」や「少女ムシェット」もそうでしたが、主人公をどこまで苛めれば気が済むのかと思ってしまいます。でも、この徹底ぶりがブレッソン監督であり、「聖」と「俗」のせめぎ合いともいえる重いテーマですが、それを"淡々と穏やか"に描いているところがスゴイと言えばスゴイと思います。
しかしながら、キリストではなく一青年にすぎないこの若い司祭の苦悩と苦闘には一体どういう意味があったのか、本当に無意味だったのか、後に何か残ったのか、考えずにはおれない作品でした。ただ一つの救いは、夫の不倫と息子の死によって神を呪うようになった伯爵夫人(夫人役はサラ・ベルナールの愛弟子であった名女優マリ=モニーク・アルケル。因みにこの伯爵夫人や先輩司祭は本物の俳優が演じている)の告解を聴き、その魂を解き放ったかに見えたこととでしたが、その夫人も自殺してしまって無に帰し、それどころか、夫人が亡くなったのは司祭のせいであるというふうに村人からは見られてしまうという、しかも、自分が胃癌に冒されていることが発覚するし、この監督、「バルタザールどこへ行く」や「少女ムシェット」もそうでしたが、主人公をどこまで苛めれば気が済むのかと思ってしまいます。でも、この徹底ぶりがブレッソン監督であり、「聖」と「俗」のせめぎ合いともいえる重いテーマですが、それを"淡々と穏やか"に描いているところがスゴイと言えばスゴイと思います。
 「田舎司祭の日記」●原題:JOURNAL D'UN CURÉ DE CAMPAGNE●制作年:1951年●制作国:フランス●監督・脚本:ロベール・ブレッソン●撮影:オンス=アンリ・ビュレル●原作:ジョルジュ・ベルナノス●時間:115分●出演:クロード・レデュ/アンドレ・ギベール/ジャン・リヴィエール/マリ=モニーク・アルケル/ニコール・ラドミラル/ニコール・モーリー/アントワーヌ・バルペトレ/マルティーヌ・ルメール●日本公開:2021/06●配給:コピアポア・フィルム●最初に観た場所:新宿・シネマカリテ(21-06-29)(評価:★★★★)
「田舎司祭の日記」●原題:JOURNAL D'UN CURÉ DE CAMPAGNE●制作年:1951年●制作国:フランス●監督・脚本:ロベール・ブレッソン●撮影:オンス=アンリ・ビュレル●原作:ジョルジュ・ベルナノス●時間:115分●出演:クロード・レデュ/アンドレ・ギベール/ジャン・リヴィエール/マリ=モニーク・アルケル/ニコール・ラドミラル/ニコール・モーリー/アントワーヌ・バルペトレ/マルティーヌ・ルメール●日本公開:2021/06●配給:コピアポア・フィルム●最初に観た場所:新宿・シネマカリテ(21-06-29)(評価:★★★★)

 ピレネーのある農場の息子ジャックと教師(フィリップ・アスラン)の娘マリーは、ある日一匹の生れたばかりのロバを拾って来て、バルタザールと名付けた。10年後、バルタザールは鍛冶屋の苦役に使われていたが、苦しさに耐えかねて逃げ出し、マリーのもとへ。久しぶりの再会に喜んだマリー(アンヌ・ヴィアゼムスキー)は、その日からバルタザールに夢中になる。これに嫉妬したパン屋の息子ジェラール(フランソワ・ラファルジュ)を長とする不良グループは、ことあるごとに、バルタザールに残酷な仕打ちを加える。その頃、マリーの父親と農場主との間に訴訟問題がもち上り、十年ぶりにジャック(ヴァルター・グリーン)が戻って来た。しかし、マリーの心は、ジャックから離れていた。訴訟はこじれ、バルタザールはジェラールの家へ譲渡された。バルタザールの身を案じて訪れて来たマリーは、ジェラールに誘惑される。その現場をバルタザールはじっとみつめていた。その日から、マリーは彼等の仲間に入り、バルタザールから遠のく。訴訟にマリーの父親は敗れるが、ジャックは問題の善処を約束、マリーに求婚した。心動かされたマリーは、すぐにジェラールたちに話をつけに行くが、仲間四人に暴行されてしまう―。
ピレネーのある農場の息子ジャックと教師(フィリップ・アスラン)の娘マリーは、ある日一匹の生れたばかりのロバを拾って来て、バルタザールと名付けた。10年後、バルタザールは鍛冶屋の苦役に使われていたが、苦しさに耐えかねて逃げ出し、マリーのもとへ。久しぶりの再会に喜んだマリー(アンヌ・ヴィアゼムスキー)は、その日からバルタザールに夢中になる。これに嫉妬したパン屋の息子ジェラール(フランソワ・ラファルジュ)を長とする不良グループは、ことあるごとに、バルタザールに残酷な仕打ちを加える。その頃、マリーの父親と農場主との間に訴訟問題がもち上り、十年ぶりにジャック(ヴァルター・グリーン)が戻って来た。しかし、マリーの心は、ジャックから離れていた。訴訟はこじれ、バルタザールはジェラールの家へ譲渡された。バルタザールの身を案じて訪れて来たマリーは、ジェラールに誘惑される。その現場をバルタザールはじっとみつめていた。その日から、マリーは彼等の仲間に入り、バルタザールから遠のく。訴訟にマリーの父親は敗れるが、ジャックは問題の善処を約束、マリーに求婚した。心動かされたマリーは、すぐにジェラールたちに話をつけに行くが、仲間四人に暴行されてしまう―。 ロベール・ブレッソン監督の1966年作品で、第27回ベネチア国際映画祭審査員特別表彰(サン・ジョルジョ賞)をはじめ、フランス映画批評家協会賞(ジョルジュ・メリエス賞)などを多くの賞を受賞した作品です(日本公開前に「バルタザールが行きあたりばったり」という訳題で紹介された)。ブレッソンが長年映画化を望んだ本作は、聖なるロバ"バルタザール"をめぐる現代の寓話であり、ドストエフスキーの長編小説「白痴」の挿話から着想し(ドストエフスキーの長編は、しばしば本筋を"脱線"して長大な挿話が入ることが多いが、これもその1つか)、一匹のロバ"バルタザール"と少女マリーの数奇な運命を繊細に描いています。
ロベール・ブレッソン監督の1966年作品で、第27回ベネチア国際映画祭審査員特別表彰(サン・ジョルジョ賞)をはじめ、フランス映画批評家協会賞(ジョルジュ・メリエス賞)などを多くの賞を受賞した作品です(日本公開前に「バルタザールが行きあたりばったり」という訳題で紹介された)。ブレッソンが長年映画化を望んだ本作は、聖なるロバ"バルタザール"をめぐる現代の寓話であり、ドストエフスキーの長編小説「白痴」の挿話から着想し(ドストエフスキーの長編は、しばしば本筋を"脱線"して長大な挿話が入ることが多いが、これもその1つか)、一匹のロバ"バルタザール"と少女マリーの数奇な運命を繊細に描いています。 最初は、ロバのバルタザールを巡ってのマリーの話かと思ましたが、最後はマリーもいなくなり、振り返ってみれば、バルタザールが主人公のような映画でした(演技をしない主人公であることが特殊だが)。では、マリーの母(ナタリー・ジョワイヨー)が「聖なるロバ」と呼ぶ(そう呼ぶのは彼女だけだが)バルタザールは何の象徴なのか。キリストの象徴というのは、比較的すんなり受け入れる人とそうでない人がいるかと思います(個人的にはその中間くらいなのだが)。
最初は、ロバのバルタザールを巡ってのマリーの話かと思ましたが、最後はマリーもいなくなり、振り返ってみれば、バルタザールが主人公のような映画でした(演技をしない主人公であることが特殊だが)。では、マリーの母(ナタリー・ジョワイヨー)が「聖なるロバ」と呼ぶ(そう呼ぶのは彼女だけだが)バルタザールは何の象徴なのか。キリストの象徴というのは、比較的すんなり受け入れる人とそうでない人がいるかと思います(個人的にはその中間くらいなのだが)。 ラストの、羊たちに囲まれてバルタザールが息を引き取ろうとするシーンに、イエス・キリストの磔刑の場面を想起する人もいるようです。一方、悲惨な生涯が終わりを告げるのは、バルタザールにとって幸福だったと示唆しているような気もします。というのは、次作「少女ムシェット」がまさに、悲惨な人生を送る少女が、死によって自らの安寧を得ようとするような作品であるからです。ただ、そう捉えると、バルタザール=キリストというのは、ちょっと違ってくるようにも思います。
ラストの、羊たちに囲まれてバルタザールが息を引き取ろうとするシーンに、イエス・キリストの磔刑の場面を想起する人もいるようです。一方、悲惨な生涯が終わりを告げるのは、バルタザールにとって幸福だったと示唆しているような気もします。というのは、次作「少女ムシェット」がまさに、悲惨な人生を送る少女が、死によって自らの安寧を得ようとするような作品であるからです。ただ、そう捉えると、バルタザール=キリストというのは、ちょっと違ってくるようにも思います。 ストーリー的には、バルタザールがパン屋や不良グループ、サーカス、老人など様々な人の手に渡る中で、その目を通して人間の欲望やエゴや浮彫りになるのが興味深いですが、バルタザールの飼い主の中では、不良のジェラールの仲間であるアルノルド(ジーン・クラウド・ギルバート)というのが一番エキセントリックでした。普段は大人しくバルタザールの面倒を見ていたのが、酒が入ると人が変わったかのように狂暴になり、堪らず逃げ出したバルタザールがサーカスに拾われたのを再度迎えに訪れ、また飼うことに。やがて遺産を相続して貧困から脱するも、不良グループにたかられた挙句、酔ったままバルタザールの背に乗り、転落死するという、ちょっとエミール・ゾラの小説に出てくる「破滅が運命づけられている」人物みたいでした。そう言えば、この俳優、「少女ムシェット」にも、密猟者の役で出ていました。
ストーリー的には、バルタザールがパン屋や不良グループ、サーカス、老人など様々な人の手に渡る中で、その目を通して人間の欲望やエゴや浮彫りになるのが興味深いですが、バルタザールの飼い主の中では、不良のジェラールの仲間であるアルノルド(ジーン・クラウド・ギルバート)というのが一番エキセントリックでした。普段は大人しくバルタザールの面倒を見ていたのが、酒が入ると人が変わったかのように狂暴になり、堪らず逃げ出したバルタザールがサーカスに拾われたのを再度迎えに訪れ、また飼うことに。やがて遺産を相続して貧困から脱するも、不良グループにたかられた挙句、酔ったままバルタザールの背に乗り、転落死するという、ちょっとエミール・ゾラの小説に出てくる「破滅が運命づけられている」人物みたいでした。そう言えば、この俳優、「少女ムシェット」にも、密猟者の役で出ていました。
 また、少女マリーを演じたアンヌ・ヴィアゼムスキー(1947-2017)は、この作品で女優としてデビューし、翌1967年、ジャン=リュック・ゴダールの「中国女」に主演、同年ゴダールと結婚するも、1979年に離婚しています。彼女には小説家や脚本家としての作品があり、フランスでは著書を原作にしばしば映画化される人気作家で、テレビ映画の監督もしています。でも、この映画の頃は18歳になったばかりで、"素"な美しさがロベール・ブレッソン監督のドキュメンタリー調の演出の中で映えているように思いました(ゴダールが惚れたのも無理ない?)
また、少女マリーを演じたアンヌ・ヴィアゼムスキー(1947-2017)は、この作品で女優としてデビューし、翌1967年、ジャン=リュック・ゴダールの「中国女」に主演、同年ゴダールと結婚するも、1979年に離婚しています。彼女には小説家や脚本家としての作品があり、フランスでは著書を原作にしばしば映画化される人気作家で、テレビ映画の監督もしています。でも、この映画の頃は18歳になったばかりで、"素"な美しさがロベール・ブレッソン監督のドキュメンタリー調の演出の中で映えているように思いました(ゴダールが惚れたのも無理ない?)
 近年では、ヴィアゼムスキーの自伝的小説『彼女のひたむきな12カ月』の1年後が描かれた『それからの彼女』がミシェル・アザナヴィシウス監督により「グッバイ・ゴダール!」として映画化されていて、1960年代後半のパリを舞台に、映画監督ジャン=リュック・ゴダールとその当時の妻アンヌ・ヴィアゼムスキーの日々が描かれるコメディ映画とのこと。第70回カンヌ国際映画祭にて主要部門パルム・ドールに出品されたのち、フランスで2017年9月13日に公開されていますが、ヴィアゼムスキーは同年10月5日に満70歳で亡くなっています。
近年では、ヴィアゼムスキーの自伝的小説『彼女のひたむきな12カ月』の1年後が描かれた『それからの彼女』がミシェル・アザナヴィシウス監督により「グッバイ・ゴダール!」として映画化されていて、1960年代後半のパリを舞台に、映画監督ジャン=リュック・ゴダールとその当時の妻アンヌ・ヴィアゼムスキーの日々が描かれるコメディ映画とのこと。第70回カンヌ国際映画祭にて主要部門パルム・ドールに出品されたのち、フランスで2017年9月13日に公開されていますが、ヴィアゼムスキーは同年10月5日に満70歳で亡くなっています。
 「バルタザールどこへ行く」●原題:AU HASARD BALTHAZAR●制作年:1966年●制作国:フランス・スウェーデン ●監督・脚本:ロベール・ブレッソン●製作:マグ・ボダール●撮影:ギスラン・クロケ●音楽:フランツ・シューベルト/ジャン・ヴィーネ●時間:96分●出演アンヌ・ヴィアゼムスキー/フランソワ・ラファルジュ/フィリップ・アスラン/ナタリー・ジョワイヨー/ヴァルター・グリ
「バルタザールどこへ行く」●原題:AU HASARD BALTHAZAR●制作年:1966年●制作国:フランス・スウェーデン ●監督・脚本:ロベール・ブレッソン●製作:マグ・ボダール●撮影:ギスラン・クロケ●音楽:フランツ・シューベルト/ジャン・ヴィーネ●時間:96分●出演アンヌ・ヴィアゼムスキー/フランソワ・ラファルジュ/フィリップ・アスラン/ナタリー・ジョワイヨー/ヴァルター・グリ ーン/ジャン=クロード・ギルベール/ピエール・クロソフスキー●日本公開:1970/05●配給:ATG●最初に観た場所:新宿シネマカリテ(20-11-05)(評価:★★★★)●併映(同日上映):「
ーン/ジャン=クロード・ギルベール/ピエール・クロソフスキー●日本公開:1970/05●配給:ATG●最初に観た場所:新宿シネマカリテ(20-11-05)(評価:★★★★)●併映(同日上映):「


![少女ムシェット [DVD]2.jpg](http://hurec.bz/book-movie/%E5%B0%91%E5%A5%B3%E3%83%A0%E3%82%B7%E3%82%A7%E3%83%83%E3%83%88%20%5BDVD%5D2.jpg)





 これを映画化したロベール・ブレッソン(1901‐1999)監督は、主演のムシェット役のナディーヌ・ノルティエをはじめ殆ど素人の俳優だけを使って、貧困と孤独、更に大人たちの偽善と無慈悲に晒され、「絶望」が日常と化している14歳の少女の境遇と、彼女が自死に至るまでを、モノクロームの映像で淡々と描いています。
これを映画化したロベール・ブレッソン(1901‐1999)監督は、主演のムシェット役のナディーヌ・ノルティエをはじめ殆ど素人の俳優だけを使って、貧困と孤独、更に大人たちの偽善と無慈悲に晒され、「絶望」が日常と化している14歳の少女の境遇と、彼女が自死に至るまでを、モノクロームの映像で淡々と描いています。 ラストで少女が池のそばの草の上を何度か転がるシーンがあり、一体何をしているのかと思ったら、その後で水音が聞こえて波打つ水面が映り、そしてそのまま暗転しエンドマークという流れで終わり、「えっ、そうなの」という感じで、初めて観た時はショックを受けました。
ラストで少女が池のそばの草の上を何度か転がるシーンがあり、一体何をしているのかと思ったら、その後で水音が聞こえて波打つ水面が映り、そしてそのまま暗転しエンドマークという流れで終わり、「えっ、そうなの」という感じで、初めて観た時はショックを受けました。 彼女が死というものをどこまで認識し、またそれなりの覚悟があってのことなのか(彼女が纏った美しい布は、彼女の死への憧憬の象徴ともとれる)。
彼女が死というものをどこまで認識し、またそれなりの覚悟があってのことなのか(彼女が纏った美しい布は、彼女の死への憧憬の象徴ともとれる)。 但し、ベルナノスの原作のコンテクストからすれば、自らの命を絶つことに彼女なりの1つの、唯一の救いがあり、それを神も受容するであろうということになるのでしょう。この映画は、それだけの説得力を持った作品です。
但し、ベルナノスの原作のコンテクストからすれば、自らの命を絶つことに彼女なりの1つの、唯一の救いがあり、それを神も受容するであろうということになるのでしょう。この映画は、それだけの説得力を持った作品です。 この映画の中で、少女は多くを語りはしないし、そもそも、語る相手もいません(殆ど無言の演技が延々と続くシーンが多い)。とにかくブレッソンは、こうした、いわゆる物語的説明を徹底的にそぎ落とした映画の作り方をよくする監督で、そのお陰でこの映画も通俗的な"薄幸少女物語"に堕することなく、原作の本題である、「死」は14歳の少女にとって唯一の救いであったと言えるのでないかという問いを、観る者に切実に突きつけてきます。
この映画の中で、少女は多くを語りはしないし、そもそも、語る相手もいません(殆ど無言の演技が延々と続くシーンが多い)。とにかくブレッソンは、こうした、いわゆる物語的説明を徹底的にそぎ落とした映画の作り方をよくする監督で、そのお陰でこの映画も通俗的な"薄幸少女物語"に堕することなく、原作の本題である、「死」は14歳の少女にとって唯一の救いであったと言えるのでないかという問いを、観る者に切実に突きつけてきます。 
 で再公開された)、「子供の自死」というのは、ある意味で今日的テーマでもあるかも知れません。
で再公開された)、「子供の自死」というのは、ある意味で今日的テーマでもあるかも知れません。 (●2020年にシネマカリテで再見。デジタルリマスター版で画面の静謐さが増したような気がする。最初に見た頃は知らなかったが、この作品はイングマール・ベルイマン、ジャン・リュック・ゴダール、アンドレイ・タルコフスキー、ジム・ジャームッシュといった映画監督たちを魅了したとのこと。「バルタザールどこへ行く」ではベルイマンとゴダールで評価が割れ、ベルイマンは批判的だったが、この「少女少女ムシェット」は両者とも絶賛したようだ。分かる気がする。)
(●2020年にシネマカリテで再見。デジタルリマスター版で画面の静謐さが増したような気がする。最初に見た頃は知らなかったが、この作品はイングマール・ベルイマン、ジャン・リュック・ゴダール、アンドレイ・タルコフスキー、ジム・ジャームッシュといった映画監督たちを魅了したとのこと。「バルタザールどこへ行く」ではベルイマンとゴダールで評価が割れ、ベルイマンは批判的だったが、この「少女少女ムシェット」は両者とも絶賛したようだ。分かる気がする。) 

 「少女ムシェット」●原題:MOUCHETTE●制作年:1967年●制作国:フランス●監督:ロベール・ブレッソン●撮影:ギスラン・クロケ●音楽:クラウディオ・モンテヴェルディ/ジャン・ウィエネル●原作:ジョルジュ・ベルナノス 「少女ムーシェット」●時間:80分●出演:ナディーヌ・ノルティエ/ポール・エベール/マリア・カルディナール/ジャン=クロード・ギルベール/ジャン・ヴィムネ●日本公開:1974/09●配給:エキプ・ド・シネマ●最初に観た場
「少女ムシェット」●原題:MOUCHETTE●制作年:1967年●制作国:フランス●監督:ロベール・ブレッソン●撮影:ギスラン・クロケ●音楽:クラウディオ・モンテヴェルディ/ジャン・ウィエネル●原作:ジョルジュ・ベルナノス 「少女ムーシェット」●時間:80分●出演:ナディーヌ・ノルティエ/ポール・エベール/マリア・カルディナール/ジャン=クロード・ギルベール/ジャン・ヴィムネ●日本公開:1974/09●配給:エキプ・ド・シネマ●最初に観た場


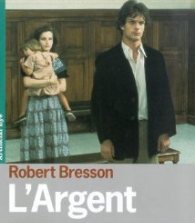

 1枚の500フラン札を偽札と知らずに使ったイヴォン(クリスチャン・パティ)は、逮捕され有罪となる。出所後に更に強盗の手伝いをして逮捕・投獄され、妻(カロリーヌ・ラング)に離婚され家族とも別れ、自殺をも考える。しかし彼は脱獄し、今度は自分を匿ってくれた一家との間にも事件を引き起こす―。
1枚の500フラン札を偽札と知らずに使ったイヴォン(クリスチャン・パティ)は、逮捕され有罪となる。出所後に更に強盗の手伝いをして逮捕・投獄され、妻(カロリーヌ・ラング)に離婚され家族とも別れ、自殺をも考える。しかし彼は脱獄し、今度は自分を匿ってくれた一家との間にも事件を引き起こす―。
 ロベール・ブレッソン監督作で、原作はトルストイの短編小説ですが、主人公や周辺の人物が些細なことから犯罪に染まっていく過程はドストエフスキー的で(原作の複数の人物が映画では主人公1人に集約的に投影されている)、但し、後半で主人公の改心の過程が描かれるので、ヴィクトル・ユーゴーっぽい感じもします。ところがこの映画化作品では、トルストイの原作小説の後半の主人公が信仰に目覚め改心する話を完全にカットしているため、主人公が凶行に及んだところで映画はいきなり終わってしまいます。映画館で上映が終わった後、観客が少しどよめいていたような記憶があり、1983年のカンヌ映画祭で監督賞を受賞していますが、その時にも上映終了時にはブーイングも巻き起こったとのことです。
ロベール・ブレッソン監督作で、原作はトルストイの短編小説ですが、主人公や周辺の人物が些細なことから犯罪に染まっていく過程はドストエフスキー的で(原作の複数の人物が映画では主人公1人に集約的に投影されている)、但し、後半で主人公の改心の過程が描かれるので、ヴィクトル・ユーゴーっぽい感じもします。ところがこの映画化作品では、トルストイの原作小説の後半の主人公が信仰に目覚め改心する話を完全にカットしているため、主人公が凶行に及んだところで映画はいきなり終わってしまいます。映画館で上映が終わった後、観客が少しどよめいていたような記憶があり、1983年のカンヌ映画祭で監督賞を受賞していますが、その時にも上映終了時にはブーイングも巻き起こったとのことです。 それはそうでしょう。逃亡者となった主人公と偶然出会い、彼を匿った心優しい老婆に対して、自然に溢れた環境で老婆からの慈しみを受け改心に向かうかと思われた主人公が、老婆に突然に見舞った返礼は、斧で彼女を惨殺することだったのですから。
それはそうでしょう。逃亡者となった主人公と偶然出会い、彼を匿った心優しい老婆に対して、自然に溢れた環境で老婆からの慈しみを受け改心に向かうかと思われた主人公が、老婆に突然に見舞った返礼は、斧で彼女を惨殺することだったのですから。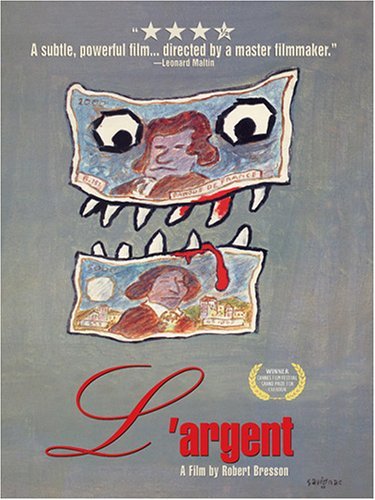




![白夜 [DVD]PL.jpg](http://hurec.bz/book-movie/%E7%99%BD%E5%A4%9C%20%5BDVD%5DPL.jpg)



.jpg)

 ルキノ・ヴィスコンティ版「白夜」は、ペテルブルクからイタリアの港町に話の舞台を移し、但し、オールセットでこの作品を撮っていて(モノクロ)、主人公の孤独な青年にマルチェロ・マストロヤンニ、恋人に去られた女性に「居酒屋」のマリア・シェル、その恋人にジャン・マレーという錚々たる役者布陣であり、キャスト、スタッフ共に国際的です。
ルキノ・ヴィスコンティ版「白夜」は、ペテルブルクからイタリアの港町に話の舞台を移し、但し、オールセットでこの作品を撮っていて(モノクロ)、主人公の孤独な青年にマルチェロ・マストロヤンニ、恋人に去られた女性に「居酒屋」のマリア・シェル、その恋人にジャン・マレーという錚々たる役者布陣であり、キャスト、スタッフ共に国際的です。 「ヴェネツィア高裁映画祭・銀獅子賞」を受賞するなど、国際的にも高い評価を得た作品で、タイトルに象徴される幻想的な雰囲気を伝えてはいるものの、細部において小説から抱いたイメージと食い違い、個人的にはやや入り込めなかったという感じです。
「ヴェネツィア高裁映画祭・銀獅子賞」を受賞するなど、国際的にも高い評価を得た作品で、タイトルに象徴される幻想的な雰囲気を伝えてはいるものの、細部において小説から抱いたイメージと食い違い、個人的にはやや入り込めなかったという感じです。

 神経質そうでややストーカーっぽいとも思える青年(ギョーム・デ・フォレ)の、それでいて少
神経質そうでややストーカーっぽいとも思える青年(ギョーム・デ・フォレ)の、それでいて少 し滑稽で哀しい感じが原作を身近なものにしていて、恋人の名前をテープに吹き込んだりしている点などはオタク的であり、こんな青年は実際いるかもしれないなあと
し滑稽で哀しい感じが原作を身近なものにしていて、恋人の名前をテープに吹き込んだりしている点などはオタク的であり、こんな青年は実際いるかもしれないなあと ―。そうしたギョーム・デ・フォレの鬱屈した中にも飄々としたユーモアを漂わせた青年に加えて、イザベル・ヴェンガルテンの内に秘めた翳のある女性も良かったように思います(ギヨーム・デ・フォレ、イザベル・ヴェンガルテン共にこの作品に出演するまで演技経験が無かったというから、ブレッソンの演出力には舌を巻く)。
―。そうしたギョーム・デ・フォレの鬱屈した中にも飄々としたユーモアを漂わせた青年に加えて、イザベル・ヴェンガルテンの内に秘めた翳のある女性も良かったように思います(ギヨーム・デ・フォレ、イザベル・ヴェンガルテン共にこの作品に出演するまで演技経験が無かったというから、ブレッソンの演出力には舌を巻く)。
 夜のセーヌ河をイルミネーションに飾られた水上観光バス(バトー・ムーシュ)がボサノヴァ調の曲を奏でながらクルージングする様を、橋上から情感たっぷりに撮った映像はため息がでるほど美しく、原作のロマンチシズムを極致の映像美にしたものでした。
夜のセーヌ河をイルミネーションに飾られた水上観光バス(バトー・ムーシュ)がボサノヴァ調の曲を奏でながらクルージングする様を、橋上から情感たっぷりに撮った映像はため息がでるほど美しく、原作のロマンチシズムを極致の映像美にしたものでした。
 「白夜」(ヴィスコンティ版)●原題:QUATER NUITS D'UN REVEUR●制作年:1957年●制作国:イタリア・フランス●監督・脚本:ルキノ・ヴィスコンティ●撮影:ジュゼッペ・ロトゥンノ●音楽:ニーノ・ロータ●原作:ドストエフスキー●時間:107分●出演:マルチェロ・マストロヤンニ/マリア・シェル/ジャン・マレー/クララ・カラマイ/マリア・ザノーリ/エレナ・ファンチェーラ●日本公開:1958/04●配給:イタリフィルム●最初に観た場所:高田馬場東映パラス(86-11-30)(評価★★★)●併映:「世にも怪奇な物語」(ロジェ・バディム/ルイ・マル/フェデリコ・フェリーニ)
「白夜」(ヴィスコンティ版)●原題:QUATER NUITS D'UN REVEUR●制作年:1957年●制作国:イタリア・フランス●監督・脚本:ルキノ・ヴィスコンティ●撮影:ジュゼッペ・ロトゥンノ●音楽:ニーノ・ロータ●原作:ドストエフスキー●時間:107分●出演:マルチェロ・マストロヤンニ/マリア・シェル/ジャン・マレー/クララ・カラマイ/マリア・ザノーリ/エレナ・ファンチェーラ●日本公開:1958/04●配給:イタリフィルム●最初に観た場所:高田馬場東映パラス(86-11-30)(評価★★★)●併映:「世にも怪奇な物語」(ロジェ・バディム/ルイ・マル/フェデリコ・フェリーニ)  「白夜」(ブレッソン版)●原題:QUATRE NUITS D'UN REVEUR(英:FOUR NIGHTS OF A DREAMER)●制作年:1971年●制作国:フランス●監督・脚本:ロベール・ブレッソン●撮影:ピエール・ロム●音楽:ミシェル・マーニュ●原作:ドストエフスキー●時間:83分●出演:イザベル・ヴェンガルテン/ギョーム・デ・フォレ●日
「白夜」(ブレッソン版)●原題:QUATRE NUITS D'UN REVEUR(英:FOUR NIGHTS OF A DREAMER)●制作年:1971年●制作国:フランス●監督・脚本:ロベール・ブレッソン●撮影:ピエール・ロム●音楽:ミシェル・マーニュ●原作:ドストエフスキー●時間:83分●出演:イザベル・ヴェンガルテン/ギョーム・デ・フォレ●日 本公開:1978/02●配給:フランス映画社●最初に観た場所:池袋文芸坐(78-06-22)●2回目:池袋文芸坐(78-06-23)●3回目:有楽シネマ(80-05-25) (評価★★★★★)●併映(1回目・2回目):「少女ムシェット」(ロベール・ブレッソン)●併映(3回目):「鬼火」(ルイ・マル)
本公開:1978/02●配給:フランス映画社●最初に観た場所:池袋文芸坐(78-06-22)●2回目:池袋文芸坐(78-06-23)●3回目:有楽シネマ(80-05-25) (評価★★★★★)●併映(1回目・2回目):「少女ムシェット」(ロベール・ブレッソン)●併映(3回目):「鬼火」(ルイ・マル)