「●イングマール・ベルイマン監督作品」の インデックッスへ Prev|NEXT ⇒「●アキ・カウリスマキ監督作品」【3671】 アキ・カウリスマキ 「パラダイスの夕暮れ」
「●「ナショナル・ボード・オブ・レビュー賞 外国語映画賞」受賞作」の インデックッスへ 「●「ゴールデングローブ賞 外国語映画賞」受賞作」の インデックッスへ「○外国映画 【制作年順】」の インデックッスへ 「○存続中の映画館」の インデックッスへ(早稲田松竹)
母娘の壮絶な確執を描く(観ていてキツイぐらい)。牧師の無力ぶりが「冬の光」とダブる。




「秋のソナタ [DVD]」「秋のソナタ [DVD]
」
イングリッド・バーグマン没後30周年記念上映ポスター(2012年/ユーロスペース) 初公開時ポスター(1981年/岩波ホール)
リヴ・ウルマン/イングリッド・バーグマン
 ノルウェー北部の田園地方。湖畔の牧師館で静かに暮らす、ヴィクトル(ハルヴァール・ビョルク)とエヴァ(リヴ・ウルマン)夫妻。エヴァは7年も会わなかった母シャルロッテ(イングリッド・バーグマン)を、牧師館に招くことを思いつく。国際的なピアニストとして煌(きら)びやかな人生を送ってきた母が、つい最近長年連れ添った恋人を亡くしたことを、風の噂で聞いたばかりだった。シャルロッテは相変わらず若々しく華やいだ雰囲気で、自ら豪華な車を運転してやってきた。2人は抱擁を交わし、お互いの近況を話し合う。エヴァへの愛情を示していたシャルロッテだが、もうひとりの娘であり、脳性麻痺を患うヘレーナ(レナ・ニーマン)が一緒に暮らしていると聞き、一転して苛立ちをあらわにする。エヴァとシャルロッテは、お互いの感情が7年前といささかも変わっていないことに、既に気づいていた。夕食後、母の誘いに応じてショパンのプレリュードを弾くエヴァ。エヴァの弾き方を厳しく批評し、解釈を語って聞かせるシャルロッテの横顔を、エヴァは複雑な表情で見つめるのだった―。
ノルウェー北部の田園地方。湖畔の牧師館で静かに暮らす、ヴィクトル(ハルヴァール・ビョルク)とエヴァ(リヴ・ウルマン)夫妻。エヴァは7年も会わなかった母シャルロッテ(イングリッド・バーグマン)を、牧師館に招くことを思いつく。国際的なピアニストとして煌(きら)びやかな人生を送ってきた母が、つい最近長年連れ添った恋人を亡くしたことを、風の噂で聞いたばかりだった。シャルロッテは相変わらず若々しく華やいだ雰囲気で、自ら豪華な車を運転してやってきた。2人は抱擁を交わし、お互いの近況を話し合う。エヴァへの愛情を示していたシャルロッテだが、もうひとりの娘であり、脳性麻痺を患うヘレーナ(レナ・ニーマン)が一緒に暮らしていると聞き、一転して苛立ちをあらわにする。エヴァとシャルロッテは、お互いの感情が7年前といささかも変わっていないことに、既に気づいていた。夕食後、母の誘いに応じてショパンのプレリュードを弾くエヴァ。エヴァの弾き方を厳しく批評し、解釈を語って聞かせるシャルロッテの横顔を、エヴァは複雑な表情で見つめるのだった―。
 1978年公開のイングマール・ベルイマン(1918-2007/享年89)監督が異なった環境で生活をする母と娘の微妙な絆を描いた作品で、ハリウッドで成功したイングリッド・バーグマン(1915-1982/享年67)が久しぶりにスウェーデン語を話す映画となりました(スウェーデン映画であるが、ベルイマンが'76年に発生した自身の税金問題に嫌気がさして海外へ逃れていたため、ノルウェーで撮影された。従って、牧師館もノルウェーに在ることになっている)。因みに、〈バーグマン〉は〈ベルイマン〉の英語読みであり、同姓のよしみでベルイマン作品にイングリッド・バーグマンが出ることになったとの話もありますが、元々イングリッド・バーグマンは芸術的作品への出演意欲が強かったのではないでしょうか(将来"傑作"と呼ばれるようになる作品に出ることにこだわる彼女に、ヒッチコックが「たかが映画じゃないか」と言ったという逸話もある)。
1978年公開のイングマール・ベルイマン(1918-2007/享年89)監督が異なった環境で生活をする母と娘の微妙な絆を描いた作品で、ハリウッドで成功したイングリッド・バーグマン(1915-1982/享年67)が久しぶりにスウェーデン語を話す映画となりました(スウェーデン映画であるが、ベルイマンが'76年に発生した自身の税金問題に嫌気がさして海外へ逃れていたため、ノルウェーで撮影された。従って、牧師館もノルウェーに在ることになっている)。因みに、〈バーグマン〉は〈ベルイマン〉の英語読みであり、同姓のよしみでベルイマン作品にイングリッド・バーグマンが出ることになったとの話もありますが、元々イングリッド・バーグマンは芸術的作品への出演意欲が強かったのではないでしょうか(将来"傑作"と呼ばれるようになる作品に出ることにこだわる彼女に、ヒッチコックが「たかが映画じゃないか」と言ったという逸話もある)。
 しかも、共演の相手は、公私共にベルイマンのパートナーであったリヴ・ウルマンということで(「冬の光」('63年)のイングリット・チューリンもそうだったが、本当は美人女優なのに、わざと不美人のメイクにすることで長年の心理的鬱屈を表している)、敢えて手強い共演者と言うか非常に高いハードルに挑んだようにも思われます。実際、この2大女優が確執を抱えた母と娘として激しく遣り合う場面は、「共演」と言うより「競演」と言ってよく、この作品がイングリッド・バーグマンの映画としては最後の主演作品となるわけですが、ああ、この人、最期の最期まで女優だったのだなあと改めて思わされます(遺作は、イスラエルの女性首相ゴルダ・メイアを演じたTVドラマシリーズ「ゴルダと呼ばれた女」('82年)で、没後にエミー賞、ゴールデングローブ賞の各主演女優賞(ミニシリーズ/テレビ映画部門)を受賞している)。
しかも、共演の相手は、公私共にベルイマンのパートナーであったリヴ・ウルマンということで(「冬の光」('63年)のイングリット・チューリンもそうだったが、本当は美人女優なのに、わざと不美人のメイクにすることで長年の心理的鬱屈を表している)、敢えて手強い共演者と言うか非常に高いハードルに挑んだようにも思われます。実際、この2大女優が確執を抱えた母と娘として激しく遣り合う場面は、「共演」と言うより「競演」と言ってよく、この作品がイングリッド・バーグマンの映画としては最後の主演作品となるわけですが、ああ、この人、最期の最期まで女優だったのだなあと改めて思わされます(遺作は、イスラエルの女性首相ゴルダ・メイアを演じたTVドラマシリーズ「ゴルダと呼ばれた女」('82年)で、没後にエミー賞、ゴールデングローブ賞の各主演女優賞(ミニシリーズ/テレビ映画部門)を受賞している)。

 因みに、イングリッド・バーグマンはこの「秋のソナタ」で、ナショナル・ボード・オブ・レビュー賞、ニューヨーク映画批評家協会賞、全米映画批評家協会賞の各主演女優賞を受賞したほか、アカデミー賞、ゴールデングローブ賞にもノミネートされています(アカデミー賞受賞は成らなかった。イングリッド・バーグマンはそれまでにアカデミー賞を主演女優賞2回、助演女優賞1回の3回受賞しており、これは主演女優賞を3回受賞していたキャサリン・ヘプバーン(1907-2003/享年96)と並んで歴代1位だったが、キャサリン・ヘプバーンが「黄昏」('81年)で4回目の主演女優賞を獲得したため、キャサリン・ヘプバーンに次ぐ歴代2位となった)。
因みに、イングリッド・バーグマンはこの「秋のソナタ」で、ナショナル・ボード・オブ・レビュー賞、ニューヨーク映画批評家協会賞、全米映画批評家協会賞の各主演女優賞を受賞したほか、アカデミー賞、ゴールデングローブ賞にもノミネートされています(アカデミー賞受賞は成らなかった。イングリッド・バーグマンはそれまでにアカデミー賞を主演女優賞2回、助演女優賞1回の3回受賞しており、これは主演女優賞を3回受賞していたキャサリン・ヘプバーン(1907-2003/享年96)と並んで歴代1位だったが、キャサリン・ヘプバーンが「黄昏」('81年)で4回目の主演女優賞を獲得したため、キャサリン・ヘプバーンに次ぐ歴代2位となった)。
Ingrid Bergman/Katharine Hepburn
 「秋のソナタ」は、演劇的な室内劇を主とした母娘の愛憎劇ですが、母に対する娘の心理的復讐劇であると見ることも可能で、それは、一歳のときに母に捨てられ、思春期までに脳性麻痺を発病し、それを悪化させたが故に療養所送りになった娘ヘレーナをエヴァが施設から牧師館に引き取り、手厚い看護を継続させていたところへ母のシャルロッテを'わざわざ'牧師館に招いた―という状況からも見ることが出来、事情を知らないまま牧師館を訪れ、エヴァによってヘレーナと対面させられた母シャルロッテ「不意打ちね」と呟きます。
「秋のソナタ」は、演劇的な室内劇を主とした母娘の愛憎劇ですが、母に対する娘の心理的復讐劇であると見ることも可能で、それは、一歳のときに母に捨てられ、思春期までに脳性麻痺を発病し、それを悪化させたが故に療養所送りになった娘ヘレーナをエヴァが施設から牧師館に引き取り、手厚い看護を継続させていたところへ母のシャルロッテを'わざわざ'牧師館に招いた―という状況からも見ることが出来、事情を知らないまま牧師館を訪れ、エヴァによってヘレーナと対面させられた母シャルロッテ「不意打ちね」と呟きます。

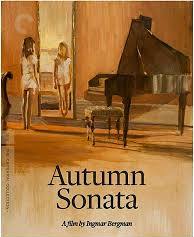 ここから、当初ぎこちないながらも再会を歓び合った二人の関係は、どんどん互いの過去を抉(えぐ)り合うようなものとなっていき、互いに激しい会話の遣り取りとなります。過去の回想シーンと現在のシーンが交互に現れる手法はテンポ良く、過去のシーンの静謐感が対比的に現在のシーンの重苦しさを増し、場面によっては観ていてキツイぐらいでした(母が娘にピアノを弾かせるシーンもキツイ。ベルイマンの彼と彼の父親との関係が投影されているのだろうか)。
ここから、当初ぎこちないながらも再会を歓び合った二人の関係は、どんどん互いの過去を抉(えぐ)り合うようなものとなっていき、互いに激しい会話の遣り取りとなります。過去の回想シーンと現在のシーンが交互に現れる手法はテンポ良く、過去のシーンの静謐感が対比的に現在のシーンの重苦しさを増し、場面によっては観ていてキツイぐらいでした(母が娘にピアノを弾かせるシーンもキツイ。ベルイマンの彼と彼の父親との関係が投影されているのだろうか)。
 ラスト、結局とことんまで娘に打ちのめされた母親は牧師館を去り、列車の中で同乗してもらった彼女のマネージャーのポール(グンナール・ビョルンストランド。「冬の光」('63年)では主人公の牧師役だった)に「ヘレーナなんて死ねばいいのに」とあっけらかんと言い、一方エヴァは母親に言い過ぎたと詫びの言葉を手紙にしたため夫に出してくれるように頼みます。そこで夫が出てきてエンディングとなりますが、その時の構図が、映画の冒頭のシーンの構図と同じであり、そこで観客は、牧師である夫が、最初は妻に優しい言葉をかけていたりしたけれども、結局はこの壮絶な母娘関係の前では終始全く無力であったことに改めて気づかされます。この夫は、「冬の光」における牧師と、「無力」であるという意味では同じポジショニングであると思いました。
ラスト、結局とことんまで娘に打ちのめされた母親は牧師館を去り、列車の中で同乗してもらった彼女のマネージャーのポール(グンナール・ビョルンストランド。「冬の光」('63年)では主人公の牧師役だった)に「ヘレーナなんて死ねばいいのに」とあっけらかんと言い、一方エヴァは母親に言い過ぎたと詫びの言葉を手紙にしたため夫に出してくれるように頼みます。そこで夫が出てきてエンディングとなりますが、その時の構図が、映画の冒頭のシーンの構図と同じであり、そこで観客は、牧師である夫が、最初は妻に優しい言葉をかけていたりしたけれども、結局はこの壮絶な母娘関係の前では終始全く無力であったことに改めて気づかされます。この夫は、「冬の光」における牧師と、「無力」であるという意味では同じポジショニングであると思いました。
Höstsonaten (1978)
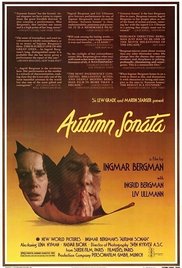 「秋のソナタ」●原題:HOST SONATEN(英:AUTUMN SONATA)●制作年:1978年●制作国:スウェーデン●監督・脚本:イングマール・ベルイマン●撮影:スヴェン・ニクヴィスト●時間:92分●出
「秋のソナタ」●原題:HOST SONATEN(英:AUTUMN SONATA)●制作年:1978年●制作国:スウェーデン●監督・脚本:イングマール・ベルイマン●撮影:スヴェン・ニクヴィスト●時間:92分●出演:イングリッド・バーグマン/リヴ・ウルマン/レナ・ニーマン
 /ハルヴァール・ビョルク/エルランド・ヨセフソン/グンナール・ビヨルンストランド●日本公開:1981/10●配給:東宝東和●最初に観た場所:早稲田松竹(15-10-09)(評価:★★★★)●併映:「冬の光」(イングマール・ベルイマン) 早稲田松竹 1951年封切館としてオープン、1975年からいわゆる「名画座」に。2002年4月1日閉館、有志の手で2002年12月21日再建、2003年1月25日から本格的再開。
/ハルヴァール・ビョルク/エルランド・ヨセフソン/グンナール・ビヨルンストランド●日本公開:1981/10●配給:東宝東和●最初に観た場所:早稲田松竹(15-10-09)(評価:★★★★)●併映:「冬の光」(イングマール・ベルイマン) 早稲田松竹 1951年封切館としてオープン、1975年からいわゆる「名画座」に。2002年4月1日閉館、有志の手で2002年12月21日再建、2003年1月25日から本格的再開。
《読書MEMO》
フィンランド国立歌劇場による歌劇「秋のソナタ」(NHK BSプレミアム「プレミアムシアター」2018年7月8日(日)放映)





 11月末のスウェーデンの小さな町の日曜の朝。無事ミサを終えた牧師トーマス(グンナール・ビョルンストランド)は、漁師の妻のカーリン(グンネリ・リンドブロム)から話を聞いて欲しいと言われる。彼女の
11月末のスウェーデンの小さな町の日曜の朝。無事ミサを終えた牧師トーマス(グンナール・ビョルンストランド)は、漁師の妻のカーリン(グンネリ・リンドブロム)から話を聞いて欲しいと言われる。彼女の 夫・ヨナス(マックス・フォン・シドー)が中国も原子爆弾を持つという
夫・ヨナス(マックス・フォン・シドー)が中国も原子爆弾を持つという ニュースを新聞で読んで以来、核戦争の恐怖で塞ぎ込んでいるというのだ。しかしトーマスは最愛の妻に先立たれてから失意のどん底にあり、彼らの悩みを真剣に聞ける状態ではなかった。そんなトーマスのことをあれこれと気遣ってくれているのが、地元の小学校の女教師マルタ(イングリット・チューリン)だった。しかし彼女の愛は彼には押し付けがましく感じられ、息苦しい思
ニュースを新聞で読んで以来、核戦争の恐怖で塞ぎ込んでいるというのだ。しかしトーマスは最愛の妻に先立たれてから失意のどん底にあり、彼らの悩みを真剣に聞ける状態ではなかった。そんなトーマスのことをあれこれと気遣ってくれているのが、地元の小学校の女教師マルタ(イングリット・チューリン)だった。しかし彼女の愛は彼には押し付けがましく感じられ、息苦しい思 いさえしていた。再び訪ねて来たヨナスと向きあったが、トーマスはありきたりのこと以外は何も言えず、何らヨナスの力にならなかった。ヨナスはそれから間もなく、河辺でピストル自殺し命を絶った。一方マルタも、彼の煮えきらない態度に決断を迫り、ヒステリックな言葉を吐く。それから数時間後、ミサの時間となり礼拝堂に立つトーマス。しかしそこには町の人は誰も来ていない。それでも型通りの儀式を進めるトーマス。たった一人の聴聞者は、別れたばかりのマルタだった―。
いさえしていた。再び訪ねて来たヨナスと向きあったが、トーマスはありきたりのこと以外は何も言えず、何らヨナスの力にならなかった。ヨナスはそれから間もなく、河辺でピストル自殺し命を絶った。一方マルタも、彼の煮えきらない態度に決断を迫り、ヒステリックな言葉を吐く。それから数時間後、ミサの時間となり礼拝堂に立つトーマス。しかしそこには町の人は誰も来ていない。それでも型通りの儀式を進めるトーマス。たった一人の聴聞者は、別れたばかりのマルタだった―。 この映画の主人公の牧師トーマスは、風邪による熱で体調は良くないのですが、職業柄、周囲に対しては厳格な態度や表情を崩しません。しかし、そのため、牧師の本来あるべき姿とは「矛盾」するかのように、その行為の全てに人間的な温かさを欠いてしまっていて、彼の愛情を欲する愛人のマルタに対しても厳格さを以って接し、マルタの自分への愛情に応えようとせず、逆に別れ話を持ち出します。
この映画の主人公の牧師トーマスは、風邪による熱で体調は良くないのですが、職業柄、周囲に対しては厳格な態度や表情を崩しません。しかし、そのため、牧師の本来あるべき姿とは「矛盾」するかのように、その行為の全てに人間的な温かさを欠いてしまっていて、彼の愛情を欲する愛人のマルタに対しても厳格さを以って接し、マルタの自分への愛情に応えようとせず、逆に別れ話を持ち出します。 一方で、中国の核開発に対する漁師ヨナスの不安を彼は鎮めることが出来ず、ヨナスの自殺によって、牧師としての彼が何ら役に立たなかったことが露呈されますが、それでも彼は、形式的に礼拝という儀式だけは続けていきます。牧師自身が神に対して懐疑的であるにも関わらず、与えられた仕事としての儀式を遂行することに、個人的には、牧師としての「葛藤」や「苦悩」と言うより、むしろ「偽善」の方がより強く浮き彫りにされているような印象を受けました。
一方で、中国の核開発に対する漁師ヨナスの不安を彼は鎮めることが出来ず、ヨナスの自殺によって、牧師としての彼が何ら役に立たなかったことが露呈されますが、それでも彼は、形式的に礼拝という儀式だけは続けていきます。牧師自身が神に対して懐疑的であるにも関わらず、与えられた仕事としての儀式を遂行することに、個人的には、牧師としての「葛藤」や「苦悩」と言うより、むしろ「偽善」の方がより強く浮き彫りにされているような印象を受けました。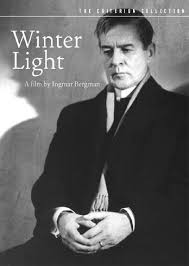
 「冬の光」●原題:NATTVARDS GASTERNA(英:WINTER LIGHT)●制作年:1963年●制作国:スウェーデン●監督・脚本:イングマール・ベルイマン●製作:アラン・エーケルンド●撮影:スヴェン・ニクヴィスト●音楽:ヨハン・セバスチャン・バッハ●時間:86分●出演:グンナール・ビョルンストランド/イングリッド・チューリン/マックス・フォン・シドー/グンネル・リンドブロム/アラン・エドワール●日本公開:1975/09●配給:インターナショナル・プロモーション●最初に観た場所:早稲田松竹(15-10-09)(評価:★★★★)●併映:「秋のソナタ」(イングマール・ベルイマン)
「冬の光」●原題:NATTVARDS GASTERNA(英:WINTER LIGHT)●制作年:1963年●制作国:スウェーデン●監督・脚本:イングマール・ベルイマン●製作:アラン・エーケルンド●撮影:スヴェン・ニクヴィスト●音楽:ヨハン・セバスチャン・バッハ●時間:86分●出演:グンナール・ビョルンストランド/イングリッド・チューリン/マックス・フォン・シドー/グンネル・リンドブロム/アラン・エドワール●日本公開:1975/09●配給:インターナショナル・プロモーション●最初に観た場所:早稲田松竹(15-10-09)(評価:★★★★)●併映:「秋のソナタ」(イングマール・ベルイマン)
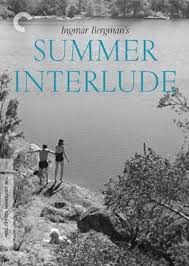



 王立オペラ座のバレリーナのマリー(マイ・ブリット・ニルソン)は新聞記者の恋人ダヴィッド(アルフ・チェリン)の求愛に迷っていた。ある日届いた1冊の古い日記に13年前の思い出を呼び起こされ、電気設備の事故でリハーサルが中断されたのを機に、毎夏を過ごした伯母の別荘を訪れる。今彼女の中で、初恋の人ヘンリック(ビルイェル・マルムステーン)との出会いと、"毎日が金の糸に連なった真珠のような輝き"のひと夏が甦る。13年前の夏、別荘に行ったマリーは学生のヘンリックと恋に落ちた。伯母の友人エ
王立オペラ座のバレリーナのマリー(マイ・ブリット・ニルソン)は新聞記者の恋人ダヴィッド(アルフ・チェリン)の求愛に迷っていた。ある日届いた1冊の古い日記に13年前の思い出を呼び起こされ、電気設備の事故でリハーサルが中断されたのを機に、毎夏を過ごした伯母の別荘を訪れる。今彼女の中で、初恋の人ヘンリック(ビルイェル・マルムステーン)との出会いと、"毎日が金の糸に連なった真珠のような輝き"のひと夏が甦る。13年前の夏、別荘に行ったマリーは学生のヘンリックと恋に落ちた。伯母の友人エ ルランド(ゲオルグ・フンキースト)もマリーに関心を持っていたが、彼女にとってエルランドは"おじさん"であり、ヘンリックとの海辺での抱擁こそが永遠のものと思われた。しかしヘンリックは、彼女にいい所を見せようと崖から海に飛び込んで全身打撲で危篤に陥り、彼女とエルランドに看取られて死ぬ。ヘンリックの日記を密かにポケットにしまい込んだエルランドは、マリーを抱いて求
ルランド(ゲオルグ・フンキースト)もマリーに関心を持っていたが、彼女にとってエルランドは"おじさん"であり、ヘンリックとの海辺での抱擁こそが永遠のものと思われた。しかしヘンリックは、彼女にいい所を見せようと崖から海に飛び込んで全身打撲で危篤に陥り、彼女とエルランドに看取られて死ぬ。ヘンリックの日記を密かにポケットにしまい込んだエルランドは、マリーを抱いて求 愛する。そして再び現在。マリーは自分を訪ねたエルランドに会うが、彼との愛人関係は既に終わっているものであることが窺える。彼は復縁を望んで日記を送ってマリーを呼び寄せたのだが、彼女はそれを拒んで劇場へ戻る。また楽屋の鏡を前にぽつねんと座る彼女。同僚が化粧を落とすのが怖いのかと冷やかし、舞台監督が彼女のバレリーナとしての衰えを容赦なく指摘する。そこへ、現在の恋人ダヴィッドが現れ、彼と口論しながらも彼女は、自分を理解してくれ、とヘンリックの日記を渡す。晴れ晴れした気持ちで化粧をぬぐった彼女。そして、翌日の出番前、舞台袖に現れたダヴィッドは無言で彼女を抱く。キスするためつま先立ちした彼女はそのまま舞台に出ていく―。
愛する。そして再び現在。マリーは自分を訪ねたエルランドに会うが、彼との愛人関係は既に終わっているものであることが窺える。彼は復縁を望んで日記を送ってマリーを呼び寄せたのだが、彼女はそれを拒んで劇場へ戻る。また楽屋の鏡を前にぽつねんと座る彼女。同僚が化粧を落とすのが怖いのかと冷やかし、舞台監督が彼女のバレリーナとしての衰えを容赦なく指摘する。そこへ、現在の恋人ダヴィッドが現れ、彼と口論しながらも彼女は、自分を理解してくれ、とヘンリックの日記を渡す。晴れ晴れした気持ちで化粧をぬぐった彼女。そして、翌日の出番前、舞台袖に現れたダヴィッドは無言で彼女を抱く。キスするためつま先立ちした彼女はそのまま舞台に出ていく―。 イングマール・ベルイマン(1918-2007/享年89)の1951年公開作で、この頃から映画監督ベルイマンとしてのスタイルが確立したとされています。映画の構成は、主人公のバレリーナの現在の意識の流れの中に、彼女の過去の記憶がフラッシュバック的に挿入されていくという点で、後の「
イングマール・ベルイマン(1918-2007/享年89)の1951年公開作で、この頃から映画監督ベルイマンとしてのスタイルが確立したとされています。映画の構成は、主人公のバレリーナの現在の意識の流れの中に、彼女の過去の記憶がフラッシュバック的に挿入されていくという点で、後の「 思い出の中の夏の別荘地での若い2人の恋が、北欧の太陽と森と湖面のまばゆい輝きを背景に美しく描かれており、それらのシーンの明るさは、暗いトーンを主体とした現在の彼女が置かれている状況―バレリーナである自分がプリマドンナとしてのピークをもう過ぎて、その座を明け渡す日が近いことが予感され、更に、過去を引き摺ったまま今の恋人とも一歩を踏み出せず口喧嘩ばかりで、そこへ、初恋の人の死の哀しみにつけ込まれかつて愛人関係を結んでしまった男が復縁を求めて訪ねてきたという状況(状況そのものがもうかなり暗い)―のシーンと対比的に描かれることで、更にその明るさを増して見えます(この瑞々しい明るさは、とても1950年代初めに作られた作品とは思えないほど)。
思い出の中の夏の別荘地での若い2人の恋が、北欧の太陽と森と湖面のまばゆい輝きを背景に美しく描かれており、それらのシーンの明るさは、暗いトーンを主体とした現在の彼女が置かれている状況―バレリーナである自分がプリマドンナとしてのピークをもう過ぎて、その座を明け渡す日が近いことが予感され、更に、過去を引き摺ったまま今の恋人とも一歩を踏み出せず口喧嘩ばかりで、そこへ、初恋の人の死の哀しみにつけ込まれかつて愛人関係を結んでしまった男が復縁を求めて訪ねてきたという状況(状況そのものがもうかなり暗い)―のシーンと対比的に描かれることで、更にその明るさを増して見えます(この瑞々しい明るさは、とても1950年代初めに作られた作品とは思えないほど)。 一方で、この眩い光に包まれた思い出も、初恋の人の事故死によって悲劇に終わるわけであって、光と影の強烈なコントラストにどこか不吉な予感が漂うとみてとれなくもなく、それは、「現在」における主人公の甘美な回想としての、そして、何度思い返しても悲劇に終わることが運命づけられている思い出であることを表しているのかもしれません(フラッシュバックの手法を取っているが、主人公の現在の意識の流れの一部としての回想であるということになる)。
一方で、この眩い光に包まれた思い出も、初恋の人の事故死によって悲劇に終わるわけであって、光と影の強烈なコントラストにどこか不吉な予感が漂うとみてとれなくもなく、それは、「現在」における主人公の甘美な回想としての、そして、何度思い返しても悲劇に終わることが運命づけられている思い出であることを表しているのかもしれません(フラッシュバックの手法を取っているが、主人公の現在の意識の流れの一部としての回想であるということになる)。
 鳥の湖」を踊るシーンなども明らかに意図的に暗い)、その「現在」のシーンの「暗さ」によって、思い出のシーンの「明るさ」がより一層に際立って印象に残った映画でした。ということで、結局シーンとしては「明るさ」が一番印象に残ったわけですが、それは眩いばかりの明るさであると同時に、儚(はかな)さのようなものを伴った明るさだったとも言えるかもしれません。
鳥の湖」を踊るシーンなども明らかに意図的に暗い)、その「現在」のシーンの「暗さ」によって、思い出のシーンの「明るさ」がより一層に際立って印象に残った映画でした。ということで、結局シーンとしては「明るさ」が一番印象に残ったわけですが、それは眩いばかりの明るさであると同時に、儚(はかな)さのようなものを伴った明るさだったとも言えるかもしれません。
 「夏の遊び」●原題:SOMMARLEK(英:SUMMER INTERLUDE)●制作年:1951年●制作国:スウェーデン●監督:イングマール・ベルイマン●製作:アラン・エクルンド●脚本:イングマール・ベルイマン/ヘルベット・グレヴェーニウス●撮影:グンナール・フィッシェル●音楽:エリク・ノルドグレン●時間:90分●出演:マイ・ブリット・ニルソン/ビルイェル・マルムステーン/アルフ・チェリン/スティーグ・オリーン/ゲオルグ・フンキースト●日本公開:1992/09●配給:アルバトロス・フィルム●最初に観た場所:早稲田松竹(15-10-05)(評価:★★★★)●併映:「第七の封印」(イングマール・ベルイマン)
「夏の遊び」●原題:SOMMARLEK(英:SUMMER INTERLUDE)●制作年:1951年●制作国:スウェーデン●監督:イングマール・ベルイマン●製作:アラン・エクルンド●脚本:イングマール・ベルイマン/ヘルベット・グレヴェーニウス●撮影:グンナール・フィッシェル●音楽:エリク・ノルドグレン●時間:90分●出演:マイ・ブリット・ニルソン/ビルイェル・マルムステーン/アルフ・チェリン/スティーグ・オリーン/ゲオルグ・フンキースト●日本公開:1992/09●配給:アルバトロス・フィルム●最初に観た場所:早稲田松竹(15-10-05)(評価:★★★★)●併映:「第七の封印」(イングマール・ベルイマン)
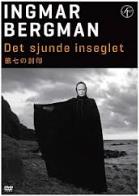


 十字軍の遠征が終わって間もないスウェーデン。騎士のアントニウス(マックス・フォン・シドー)とその従者ヨンス(グンナール・ビョルンストランド)は、十年に及んだ無益な遠征から帰国する。
十字軍の遠征が終わって間もないスウェーデン。騎士のアントニウス(マックス・フォン・シドー)とその従者ヨンス(グンナール・ビョルンストランド)は、十年に及んだ無益な遠征から帰国する。 そこで彼らが見たのは、黒死病に蹂躙される祖国と、神に救いを求め惑乱する民衆の姿だった。故郷に辿りつくと同時にアントニウスは、彼の後を追ってきた死神(ベント・エケロート)の存在に気付く。アントニウスに死を宣告する死神に対して、彼は自らの命を賭け、また神の存在を確かめるためにチェスでの対決を申し入れる。死神との勝負は長引き、その間の猶予を生かしてアントニウスは妻の待
そこで彼らが見たのは、黒死病に蹂躙される祖国と、神に救いを求め惑乱する民衆の姿だった。故郷に辿りつくと同時にアントニウスは、彼の後を追ってきた死神(ベント・エケロート)の存在に気付く。アントニウスに死を宣告する死神に対して、彼は自らの命を賭け、また神の存在を確かめるためにチェスでの対決を申し入れる。死神との勝負は長引き、その間の猶予を生かしてアントニウスは妻の待
 つ居城へと歩みを進める。道中でアントニウスは様々な人物に遭遇する。純朴な旅芸人ヨフ(ニルス・ポッペ)とその妻(ビビ・アンデショーン)の一家、妻に駆け落ちされた鍛冶屋(オーケ・フリーデル)、家族を疫病で失った少女(グンネル・リンドブロム)、下劣な犯罪者に成り下がった嘗ての聖職者ラヴァル(ベティル・アンデルベルイ)、魔女として火焙りの刑に処される女(モード・ハンソン)、疫病の蔓延を神の天罰だと考え自らを鞭打つ狂信者たち、破滅の予感に恐れ慄く人々など。その内の旅芸人一家、鍛冶屋
つ居城へと歩みを進める。道中でアントニウスは様々な人物に遭遇する。純朴な旅芸人ヨフ(ニルス・ポッペ)とその妻(ビビ・アンデショーン)の一家、妻に駆け落ちされた鍛冶屋(オーケ・フリーデル)、家族を疫病で失った少女(グンネル・リンドブロム)、下劣な犯罪者に成り下がった嘗ての聖職者ラヴァル(ベティル・アンデルベルイ)、魔女として火焙りの刑に処される女(モード・ハンソン)、疫病の蔓延を神の天罰だと考え自らを鞭打つ狂信者たち、破滅の予感に恐れ慄く人々など。その内の旅芸人一家、鍛冶屋 夫妻と少女を一行に加え、アントニウスは城への旅を続けるが、それは同時に彼に残された猶予期間が終わりつつあることを意味していた。城を目前としたある夜、アントニウスは死神相手にチェスの敗北を認める。結局自身の魂の救済も神との対話も達成できなかったアントニウスだが、旅芸人の
夫妻と少女を一行に加え、アントニウスは城への旅を続けるが、それは同時に彼に残された猶予期間が終わりつつあることを意味していた。城を目前としたある夜、アントニウスは死神相手にチェスの敗北を認める。結局自身の魂の救済も神との対話も達成できなかったアントニウスだが、旅芸人の 一家を死神から守ることには成功する。荒れ果てた城で妻と再会し、晩餐をとるアントニウスとその一行の目の前に突然死神が現れ、その場に居た者全員の命を奪う。翌朝、死神の魔の手から無事逃げ出した旅芸人のヨフが見たのは、死神に先導され数珠繋ぎになって死の舞踏を踊るアントニウスら犠牲者たちの姿だった―。
一家を死神から守ることには成功する。荒れ果てた城で妻と再会し、晩餐をとるアントニウスとその一行の目の前に突然死神が現れ、その場に居た者全員の命を奪う。翌朝、死神の魔の手から無事逃げ出した旅芸人のヨフが見たのは、死神に先導され数珠繋ぎになって死の舞踏を踊るアントニウスら犠牲者たちの姿だった―。 イングマール・ベルイマン(1918-2007/享年89)が、土着信仰とキリスト教信仰が混在する中世の北欧を舞台に、神の不在という実存主義的なテーマに挑んだ問題作。前年の「夏の夜は三たび微笑む」('55年)に続き、1957年度のカンヌ国際映画祭のパルム・ドールに2年連続でノミネートされ、受賞はならなかったものの、本作品は同映画祭の審査員特別賞を齎しました。
イングマール・ベルイマン(1918-2007/享年89)が、土着信仰とキリスト教信仰が混在する中世の北欧を舞台に、神の不在という実存主義的なテーマに挑んだ問題作。前年の「夏の夜は三たび微笑む」('55年)に続き、1957年度のカンヌ国際映画祭のパルム・ドールに2年連続でノミネートされ、受賞はならなかったものの、本作品は同映画祭の審査員特別賞を齎しました。 当初、こうしたモチーフは、ベルイマンによって「木版の絵」という演劇学校の学生の練習用に書かれた一幕劇になり、それがラジオ劇として放送され、市立劇場でも公演されました。彼はこれを映画シナリオに書き換えて映画会社に送り、一旦はボツになったもののの、「夏の夜は三たび微笑む」のヒットを受けて映画化が決まりました。結果的に、ベルイマンの最大のヒット作の1つとなりまし
当初、こうしたモチーフは、ベルイマンによって「木版の絵」という演劇学校の学生の練習用に書かれた一幕劇になり、それがラジオ劇として放送され、市立劇場でも公演されました。彼はこれを映画シナリオに書き換えて映画会社に送り、一旦はボツになったもののの、「夏の夜は三たび微笑む」のヒットを受けて映画化が決まりました。結果的に、ベルイマンの最大のヒット作の1つとなりまし たが、「木版の絵」から「第七の封印」になる時に、最後に生き残る旅芸人ヨフとその妻、そしてその幼子ミカエルの話が加わりました。先の宗教画に照らせば、ヨフはヨセフで、その妻はマリア、幼子ミカエルはイエスを表すことになります(但し、ヨフは夢想家として描かれ、その妻は生活に根ざした現実主義者として描かれていて、また、ヨフ自身が聖母マリアとイエスの姿をが幻視するという場面もある)。
たが、「木版の絵」から「第七の封印」になる時に、最後に生き残る旅芸人ヨフとその妻、そしてその幼子ミカエルの話が加わりました。先の宗教画に照らせば、ヨフはヨセフで、その妻はマリア、幼子ミカエルはイエスを表すことになります(但し、ヨフは夢想家として描かれ、その妻は生活に根ざした現実主義者として描かれていて、また、ヨフ自身が聖母マリアとイエスの姿をが幻視するという場面もある)。 人それぞれにいろいろな見方が出来る映画であり、ペストが蔓延し世界が終末の不安に慄く中世ヨーロッパという背景は、当時の特殊な時代状況だとする見方がある一方、現代の不安に満ちた時代を反映していると見る向きもあります。また、ヨフの一家が生き延びることに宗教的な救いを探る人もいる一方、彼らが旅芸人の一家であることから、ベルイマンは芸術に救いを見出しているのではないかと見方もあります(何れにせよ、ヨフ一家が生き延びることが"映画的"な意味では救いになっていることには違いないと思う)。
人それぞれにいろいろな見方が出来る映画であり、ペストが蔓延し世界が終末の不安に慄く中世ヨーロッパという背景は、当時の特殊な時代状況だとする見方がある一方、現代の不安に満ちた時代を反映していると見る向きもあります。また、ヨフの一家が生き延びることに宗教的な救いを探る人もいる一方、彼らが旅芸人の一家であることから、ベルイマンは芸術に救いを見出しているのではないかと見方もあります(何れにせよ、ヨフ一家が生き延びることが"映画的"な意味では救いになっていることには違いないと思う)。 ラストも含め、重い主題の映画でありながら、映画全体が寓話的な印象を受け、意外と軽妙感もあったりします。更に随所にコメディの要素も含まれていて、それまでのベルイマンの作品にも見られる艶笑喜劇的要素さえあります。死神の姿も過剰に戯画的であるし、死神がアントニウスの作戦に嵌りそうになって挽回の手を打つためズルをするという(教会の告解室でアントニウスは神への疑念と苦悩を語るが、聖職者のふりをした死神に騙されてチェスの作戦を教えてしまう)、人間と騙し騙されつつどっこいどっこいの勝負をしている死神というのも何だか可笑しいです。
ラストも含め、重い主題の映画でありながら、映画全体が寓話的な印象を受け、意外と軽妙感もあったりします。更に随所にコメディの要素も含まれていて、それまでのベルイマンの作品にも見られる艶笑喜劇的要素さえあります。死神の姿も過剰に戯画的であるし、死神がアントニウスの作戦に嵌りそうになって挽回の手を打つためズルをするという(教会の告解室でアントニウスは神への疑念と苦悩を語るが、聖職者のふりをした死神に騙されてチェスの作戦を教えてしまう)、人間と騙し騙されつつどっこいどっこいの勝負をしている死神というのも何だか可笑しいです。
 映画の中に、教会の壁画(例の「死神の踊り」)を描いている男が出てきて、ヨンスが何故こんな無意味なものを描くのかと問うと、画家は、「人間は皆死ぬものだということを悟らせるためだ」と言い、また、「骸骨は裸の女よりも人々の関心を引く」とも言います。となると、この映画に出てくる死神も、そうした"目的"と"効果"のために描かれた絵の一つのパーツであるに過ぎないと言えるかもしれません。ベルイマンは作中の宗教画家になろうとしたのかも。そして、この映画が商業的な成功を収めたということは、そうしたベルイマンの意図が成功した言えなくもないかもしれません。ベルイマン自身が自作の中で最も気に入っている作品だそうです。
映画の中に、教会の壁画(例の「死神の踊り」)を描いている男が出てきて、ヨンスが何故こんな無意味なものを描くのかと問うと、画家は、「人間は皆死ぬものだということを悟らせるためだ」と言い、また、「骸骨は裸の女よりも人々の関心を引く」とも言います。となると、この映画に出てくる死神も、そうした"目的"と"効果"のために描かれた絵の一つのパーツであるに過ぎないと言えるかもしれません。ベルイマンは作中の宗教画家になろうとしたのかも。そして、この映画が商業的な成功を収めたということは、そうしたベルイマンの意図が成功した言えなくもないかもしれません。ベルイマン自身が自作の中で最も気に入っている作品だそうです。 「第七の封印」●原題:DET SJUNDE INSEGLET(英:THE SEVENTH SEAL)●制作年:1957年●制作国:スウェーデン●監督・脚本:イングマール・ベルイマン●撮影:グンナール・フィッシェル●音楽:エリク・ノルドグ
「第七の封印」●原題:DET SJUNDE INSEGLET(英:THE SEVENTH SEAL)●制作年:1957年●制作国:スウェーデン●監督・脚本:イングマール・ベルイマン●撮影:グンナール・フィッシェル●音楽:エリク・ノルドグ レン●時間:96分●出演:マックス・フォン・シドー/グンナール・ビョルンストランド/ベント・エケロート/ニルス・ポッペ/ビビ・アンデショーン/グンネル・リンドブロム/ベティル・アンデルベルイ/オーケ・フリーデル/インガ・ジル/モード・ハンソン●日本公開:1963/11●配給:東和●最初に観た場所(再見):早稲田松竹(15-10-05)(評価:★★★★)●併映:「夏の遊び」(イングマール・ベルイマン)
レン●時間:96分●出演:マックス・フォン・シドー/グンナール・ビョルンストランド/ベント・エケロート/ニルス・ポッペ/ビビ・アンデショーン/グンネル・リンドブロム/ベティル・アンデルベルイ/オーケ・フリーデル/インガ・ジル/モード・ハンソン●日本公開:1963/11●配給:東和●最初に観た場所(再見):早稲田松竹(15-10-05)(評価:★★★★)●併映:「夏の遊び」(イングマール・ベルイマン)![野いちご [DVD]0_.jpg](http://hurec.bz/book-movie/%E9%87%8E%E3%81%84%E3%81%A1%E3%81%94%20%5BDVD%5D0_.jpg)


![[野いちご]撮影中のベルイマン.jpg](http://hurec.bz/book-movie/%5B%E9%87%8E%E3%81%84%E3%81%A1%E3%81%94%5D%E6%92%AE%E5%BD%B1%E4%B8%AD%E3%81%AE%E3%83%99%E3%83%AB%E3%82%A4%E3%83%9E%E3%83%B3.jpg)
 イサク(ヴィクトル・シェーストレム)は76歳の医師で、他人との接触を好まず、専ら書斎に引き籠っている。6月1日、彼は50 年に及ぶ医学への献身により、ルンドで行われる名誉博士号を受ける式典に出席することになっていた。息子エヴァルドの妻マリアンヌ(イングリッド・チューリン)が同乗した車でルンドへ向う途中、青年時代を過した邸に立ち寄る。草叢の野いちごはありし日の情景を甦らせる―野いちごを摘む可憐なサーラ(ビビ・アンデショーン)はイサクの許婚だったが、大胆なイサクの弟が
イサク(ヴィクトル・シェーストレム)は76歳の医師で、他人との接触を好まず、専ら書斎に引き籠っている。6月1日、彼は50 年に及ぶ医学への献身により、ルンドで行われる名誉博士号を受ける式典に出席することになっていた。息子エヴァルドの妻マリアンヌ(イングリッド・チューリン)が同乗した車でルンドへ向う途中、青年時代を過した邸に立ち寄る。草叢の野いちごはありし日の情景を甦らせる―野いちごを摘む可憐なサーラ(ビビ・アンデショーン)はイサクの許婚だったが、大胆なイサクの弟が サーラを奪う―。傷ついたイサクの心は未だに癒えない。ここからサーラと名乗る女学生(ビビ・アンデショーン、2役)と2人の男友達の3人組ヒッチハイカーを乗せる。若い彼等の溢れんばかりの天衣無縫さに接して、イサクは今更のように無為に過ごした年月を悔む。曲り角ですれ違う車と衝突しかけ、相手の車は
サーラを奪う―。傷ついたイサクの心は未だに癒えない。ここからサーラと名乗る女学生(ビビ・アンデショーン、2役)と2人の男友達の3人組ヒッチハイカーを乗せる。若い彼等の溢れんばかりの天衣無縫さに接して、イサクは今更のように無為に過ごした年月を悔む。曲り角ですれ違う車と衝突しかけ、相手の車は 転覆、乗っていた夫婦を同乗させたが、彼らはあたり構わず口論し互に蔑み、仕舞いには叩き合う。マリアンヌは2人を降ろす。廻り道をして、イサクは96歳の老母を訪ねる。彼女は他人にも自分にも厳しく、親族は誰も寄りつかない。車中、またしてもイサクは微睡(まどろ)む―暗い森の中に連れて行かれたイサクは、妻カリンと愛人の密会を
転覆、乗っていた夫婦を同乗させたが、彼らはあたり構わず口論し互に蔑み、仕舞いには叩き合う。マリアンヌは2人を降ろす。廻り道をして、イサクは96歳の老母を訪ねる。彼女は他人にも自分にも厳しく、親族は誰も寄りつかない。車中、またしてもイサクは微睡(まどろ)む―暗い森の中に連れて行かれたイサクは、妻カリンと愛人の密会を 見る。それはイサクがかつて目撃した光景そのままだった―。目覚めたイサクは、妻の告白を聞いて以来、自分が死を生きていることに気づく。マリアンヌは、エヴァルトも死を望んでいると話す。車はルンドに着き、ファンファーレと鐘の音に包まれて式典は荘重に行われ、授与式は無事終わる。イサクはその夜、マリアンヌと家族のことについて誠実に話し合う。寝室の外では昼間に出会ったヒッチハイカーたちがイサクの栄誉を祝福し、イサクはいつになく温かい感情に浸る。ベッドに横たわると夢の世界に入っていた―野いちごの森からサーラが現れてイサクを入江に連れて行く。イサクの父は静かに釣糸をたれ、傍では母が本を開いていた。イサクの心境をそのままにすべては安らかだった―。
見る。それはイサクがかつて目撃した光景そのままだった―。目覚めたイサクは、妻の告白を聞いて以来、自分が死を生きていることに気づく。マリアンヌは、エヴァルトも死を望んでいると話す。車はルンドに着き、ファンファーレと鐘の音に包まれて式典は荘重に行われ、授与式は無事終わる。イサクはその夜、マリアンヌと家族のことについて誠実に話し合う。寝室の外では昼間に出会ったヒッチハイカーたちがイサクの栄誉を祝福し、イサクはいつになく温かい感情に浸る。ベッドに横たわると夢の世界に入っていた―野いちごの森からサーラが現れてイサクを入江に連れて行く。イサクの父は静かに釣糸をたれ、傍では母が本を開いていた。イサクの心境をそのままにすべては安らかだった―。 イングマール・ベルイマン(1918-2007/享年89)が自らの脚本を演出した、老医師の夢と現実を一種の回想形式で描く作品。「夏の夜は三たび微笑む」('55年)、「
イングマール・ベルイマン(1918-2007/享年89)が自らの脚本を演出した、老医師の夢と現実を一種の回想形式で描く作品。「夏の夜は三たび微笑む」('55年)、「
 舞台は「第七の封印」の中世から一転して現代に移っていますが、ロードームービーっぽいところが似ているかもしれません。道中の風景、初夏の光と影を美しく撮っていますが、リアリスティックであると同時にシュールでもあり、イサクが見る自らの「死」を象徴するかのような夢はまさにシュールレアリスムの影響を受けているのが窺えるとともに(シュールレアリスム映画「
舞台は「第七の封印」の中世から一転して現代に移っていますが、ロードームービーっぽいところが似ているかもしれません。道中の風景、初夏の光と影を美しく撮っていますが、リアリスティックであると同時にシュールでもあり、イサクが見る自らの「死」を象徴するかのような夢はまさにシュールレアリスムの影響を受けているのが窺えるとともに(シュールレアリスム映画「
 ビビ・アンデショーンが、回想シーンにおけるイサクのかつての許婚サーラと、現在のシーンにおける3人組ヒッチハイカーの1人サーラの1人2役を演じていますが、片や婚約者の弟に唇を奪われ婚約者との結婚を諦める古風な女性であり、片や2人のボーイフレンドを引き連れヒッチハイクをするモダンな女性であるという、互いに対照的な役どころなのが興味深いです。
ビビ・アンデショーンが、回想シーンにおけるイサクのかつての許婚サーラと、現在のシーンにおける3人組ヒッチハイカーの1人サーラの1人2役を演じていますが、片や婚約者の弟に唇を奪われ婚約者との結婚を諦める古風な女性であり、片や2人のボーイフレンドを引き連れヒッチハイクをするモダンな女性であるという、互いに対照的な役どころなのが興味深いです。
 一方、イサクの息子の妻マリアンヌを演じたイングリッド・チューリンは、ベルイマン映画の常連でありながらこの作品では一見脇役のようですが、イサクの心境を映し出す鏡のような役割も果たしていて、やはりそれなりに重いウェイトを占めていたようにも思います。「第七の封印」で主役だったマックス・フォン・シドーは、この作品では殆ど目立たないカメオ出演的な役(ガソリンスタンド店の店主)。グンネル・リンドブロムが回想シーンにおけるシャルロッタ(サーラ(ビビ・アンデショーン)の妹)役で出ていした(下)。
一方、イサクの息子の妻マリアンヌを演じたイングリッド・チューリンは、ベルイマン映画の常連でありながらこの作品では一見脇役のようですが、イサクの心境を映し出す鏡のような役割も果たしていて、やはりそれなりに重いウェイトを占めていたようにも思います。「第七の封印」で主役だったマックス・フォン・シドーは、この作品では殆ど目立たないカメオ出演的な役(ガソリンスタンド店の店主)。グンネル・リンドブロムが回想シーンにおけるシャルロッタ(サーラ(ビビ・アンデショーン)の妹)役で出ていした(下)。 イサクを演じたヴィクトル・シェーストレムは、当時78歳と高齢で健康に優れず、撮影中にセリフを忘れることもしばしばで、屋外での撮影が予定されていた幾つかのシーンが、健康を考慮して屋内での撮影に変更されたといい、この作品が彼の遺作となったわけですが、ベルイマンはインタビューで、この映画の撮影そのものが「時」に対する闘い(つまりシェーストレムの老化と映画を完成させることとの時間的な競い合い)であったことを明かしています(小藤田千栄子(編)『
イサクを演じたヴィクトル・シェーストレムは、当時78歳と高齢で健康に優れず、撮影中にセリフを忘れることもしばしばで、屋外での撮影が予定されていた幾つかのシーンが、健康を考慮して屋内での撮影に変更されたといい、この作品が彼の遺作となったわけですが、ベルイマンはインタビューで、この映画の撮影そのものが「時」に対する闘い(つまりシェーストレムの老化と映画を完成させることとの時間的な競い合い)であったことを明かしています(小藤田千栄子(編)『 「第七の封印」は極めて直截的に「死」がモチーフでありテーマでもありましたが、この「野いちご」も「老い」がテーマであり、詰まるところ「死」がテーマと言えるかと思います。そうした重くのしかかってくるテーマを扱いながらも、「第七の封印」で最後に生き延びる家族があったように、この作品にもラストに救いがあるのがいいです。ただ、その「救い」の見せ方が、「第七の封印」と「野いちご」では異なり、ベルイマンという監督の幅の広さを感じさせます。
「第七の封印」は極めて直截的に「死」がモチーフでありテーマでもありましたが、この「野いちご」も「老い」がテーマであり、詰まるところ「死」がテーマと言えるかと思います。そうした重くのしかかってくるテーマを扱いながらも、「第七の封印」で最後に生き延びる家族があったように、この作品にもラストに救いがあるのがいいです。ただ、その「救い」の見せ方が、「第七の封印」と「野いちご」では異なり、ベルイマンという監督の幅の広さを感じさせます。
 「野いちご」●原題:SMULTRONSTALLET(英:WILD STRAWBERRIES)●制作年:1957年●制作国:スウェーデン●監督・脚本:イングマール・ベルイマン●撮影:グンナール・フィッシェル●音楽:エリク・ノルドグレン●時間:91分●出演:ヴィクトル・シェストレム/ビビ・アンデショーン/イングリッド・チューリン/グンナール・ビョルンストランド/マックス・フォン・シドー/グンネル・リンドブロム●日本公開:1962/12●配給:東宝東和●最初に観た場所:京橋フィルムセンター(80-07-11)●2回目:早稲田松竹(15-04-10)(評価:★★★★☆)●併映(2回目):「処女の泉」(イングマール・ベルイマン)
「野いちご」●原題:SMULTRONSTALLET(英:WILD STRAWBERRIES)●制作年:1957年●制作国:スウェーデン●監督・脚本:イングマール・ベルイマン●撮影:グンナール・フィッシェル●音楽:エリク・ノルドグレン●時間:91分●出演:ヴィクトル・シェストレム/ビビ・アンデショーン/イングリッド・チューリン/グンナール・ビョルンストランド/マックス・フォン・シドー/グンネル・リンドブロム●日本公開:1962/12●配給:東宝東和●最初に観た場所:京橋フィルムセンター(80-07-11)●2回目:早稲田松竹(15-04-10)(評価:★★★★☆)●併映(2回目):「処女の泉」(イングマール・ベルイマン)