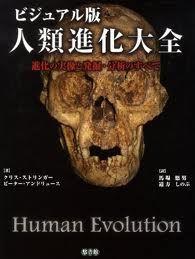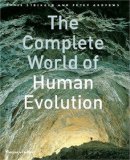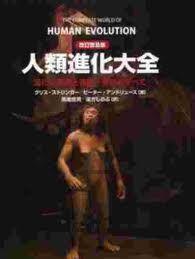「●美学・美術」の インデックッスへ Prev|NEXT ⇒ 【1758】 平凡社 『別冊太陽 月岡芳年』
「●さ行の外国映画の監督①」の インデックッスへ 「○外国映画 【制作年順】」の インデックッスへ
「○都内の主な閉館映画館」の インデックッスへ(岩波ホール)
ピロスマニの人と生涯、その作品を思い入れたっぷりに解説。作品集と併せて読むのにいい。

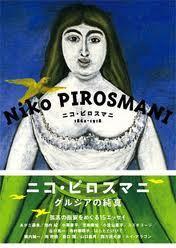 (29.8 x 21.2 x 3 cm)
(29.8 x 21.2 x 3 cm) 
『放浪の画家 ニコ・ピロスマニ』 作品集『ニコ・ピロスマニ 1862‐1918
』 「ピロスマニ [DVD]
」
「百万本のバラ」という歌のモデルとして以前から知られ、更に、ゲオルギー・シェンゲラーヤ(Georgy Shengelaya)監督の映画「ピロスマニ」('69年/グルジア共和国)で広く知られるようになった画家ニコ・ピロスマニ(Niko Pirosmani、1862-1918)について、岩波ホールに入社してこの映画の公開に携わり、岩波ホールの企画・広報の仕事をしながら、自らの創作絵本を発表、絵本の背景にピロスマニの絵画イメージを用いるなどして国際的な絵本画家の賞をも受賞している著者が、ピロスマニを生んだグルジアという国の歴史と文化、ピロスマニの人と生涯、その作品について解説した本であり、また、そうした著者であるだけに、ピロスマニに対する思い入れに満ちた本でもあります。
作品集『ニコ・ピロスマニ 1862‐1918』より
本書によれば、ピロスマニは、貧しいながらも家族の愛に包まれた幼年時代を送っていたようですが、これもその作品からの想像であり、8歳で孤児になったから後の少年時代がどのようであったかはよく分かっていないらしいです(そもそも生まれた年も不確か)。絵を描くことにのみ生きがいを見出し、一つの仕事に長くとどまることが出来ず、20代半ばで路上で一人になってからは、生涯を通して殆ど放浪生活のような暮らしを送り、その間、気分の高揚と沈滞を繰り返していたようです。
放浪の先々で、居酒屋など絵を描いて(時に看板なども描いて)収入を得て暮らし(画材も絵具も店の人が買い与えていたりしたらしい)、生涯に描いた作品は2000点以上と言われているけれど、現存が確認されているものは200点余りに過ぎず、一方、グルジアの古い料理店などに行くと、今でも彼の作品があったりするらしいですが、ピロスマニの絵は、グルジアの人々にとっては精神文化的な支えになっているとのことです(ピロスマニの肖像と共に紙幣のデザインにもなっている)。
本書の後半は、彼の作品ひとつひとつの作品の解説になっていて、アンリ・ルソーに近いとされたり、"へたうま"などと言われる彼の作品ですが、この部分を読むと、彼の孤独な人生を投射させつつ、グルジアの土地と文化もしっかり反映させたオリジナリティ性の高い作品群であることが窺えます(著者は、作風としてはルオーの絵画やイコンに描かれる宗教画に近いとも)。
作品集としては、本書にも紹介されている『ニコ・ピロスマニ 1862‐1918』('08年/文遊社)が定番でしょうか。カラー図版で189点収録、ということは、存が確認されている217点のほぼ9割近くを網羅していることになり、1頁に複数の作品は載せないという贅沢な作りです。
動物画が多く、次に多いのが「女優マルガリータ」のような単独人物という印象ですが、宴会の模様を描いたり、静物を描いたりと題材は豊富、人物を描いたものは、グルジアの民族衣装を着ているなど、土地の文化を色濃く反映しているのがむしろ共通の特徴でしょうか。
巻末に寄せられている解説やエッセイも15本と豊富で(その中には著者のものある)、但し、この作品集を鑑賞するにしても、やはり併せて本書も読むといいのではないかと思います。

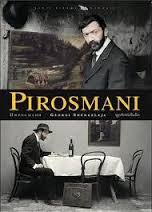 映画「ピロスマニ」では、祭りの日なのに暗い納屋で横たわっているピロスマニを見つけた知人が「何してる」と問うと、「これから死ぬところだ」と答えたラストが印象的でしたが、実際、彼の最期は衰弱死に近いものだったらしいく、但し、病院にそれらしき男が担ぎ込まれて数日後に亡くなった記録があるものの、それが本当に彼だったかどうかは分からないらしいです(酒を愛したというイメージがあるが、一般に流布している大酒飲みだったという印象に反して、それほどの酒飲みでもなかったという証言もあるという)。
映画「ピロスマニ」では、祭りの日なのに暗い納屋で横たわっているピロスマニを見つけた知人が「何してる」と問うと、「これから死ぬところだ」と答えたラストが印象的でしたが、実際、彼の最期は衰弱死に近いものだったらしいく、但し、病院にそれらしき男が担ぎ込まれて数日後に亡くなった記録があるものの、それが本当に彼だったかどうかは分からないらしいです(酒を愛したというイメージがあるが、一般に流布している大酒飲みだったという印象に反して、それほどの酒飲みでもなかったという証言もあるという)。
岩波ホール 公開時パンフレット/輸入版ポスター
 映画「ピロスマニ」は、ピロスマニの作品をその人生に重ねる手法をとっており(グルジアの民族音楽もふんだんに組み込まれているが、最初観た当時は無国籍っぽい印象も受けた)、孤高と清貧の芸術家を描いた優れた伝記映画でしたが、正直、普通の凡人にこんな生活は送れないなあと思ったりもして...(だからこそ、この映画を観て憧憬のような感情を抱くのかもしれない)。この作品は、陶芸家の女性に薦められて観ました。
映画「ピロスマニ」は、ピロスマニの作品をその人生に重ねる手法をとっており(グルジアの民族音楽もふんだんに組み込まれているが、最初観た当時は無国籍っぽい印象も受けた)、孤高と清貧の芸術家を描いた優れた伝記映画でしたが、正直、普通の凡人にこんな生活は送れないなあと思ったりもして...(だからこそ、この映画を観て憧憬のような感情を抱くのかもしれない)。この作品は、陶芸家の女性に薦められて観ました。
 日本では上映されることの少ないこうした名画を世に送り続けてきた岩波ホール支配人の高野悦子氏が今月('13年2月)9日に亡くなり、謹んでご冥福をお祈りします。この「ピロスマニ」は、エキプ・ド・シネマがスタートして5年目、ルキノ・ヴィスコンティ監督の「家族の肖像」の1つ前に公開されましたが、「家族の肖像」の大ヒットした陰で当時はあまり話題にならなかったように思います(その後、ピロスマニ展などが日本でも開かれ、映画の方も改めて注目されるようになった)。
日本では上映されることの少ないこうした名画を世に送り続けてきた岩波ホール支配人の高野悦子氏が今月('13年2月)9日に亡くなり、謹んでご冥福をお祈りします。この「ピロスマニ」は、エキプ・ド・シネマがスタートして5年目、ルキノ・ヴィスコンティ監督の「家族の肖像」の1つ前に公開されましたが、「家族の肖像」の大ヒットした陰で当時はあまり話題にならなかったように思います(その後、ピロスマニ展などが日本でも開かれ、映画の方も改めて注目されるようになった)。
映画を観て思うに、精神医学的に見ると、ピロスマニという人は統合失調質(シゾイド・タイプ)のようにも思えます。このタイプの人は、無欲で孤独な人生を送ることが多いそうで、病跡学のテキストではよく哲学者のヴィトゲンシュタインが例として挙げられたりしていましたが、ヴィトゲンシュタインの伝記を読むと、親しい友人もいて、その家族とも長期に渡って親しく付き合っていたらしく、どちらかと言うと、自分の頭の中では、ピロスマニの方がよりこの「シゾイド・タイプ」に当て嵌まるような気がしました。

 「ピロスマニ(放浪の画家ピロスマニ)」●原題:PIROSUMANI●制作年:1969年●制作国:グルジア共和国●監督:ゲオルギー・シェンゲラーヤ●脚本:エルロム・アフヴレジアニ/ゲオルギー・シェンゲラーヤ●撮影:コンスタンチン・アプリャチン●音楽:V・クヒアニーゼ●時間:87分●出演:アフタンジル・ワラジ(Pirosmani)/アッラ・ミンチン (Margarita)/ニーノ・
「ピロスマニ(放浪の画家ピロスマニ)」●原題:PIROSUMANI●制作年:1969年●制作国:グルジア共和国●監督:ゲオルギー・シェンゲラーヤ●脚本:エルロム・アフヴレジアニ/ゲオルギー・シェンゲラーヤ●撮影:コンスタンチン・アプリャチン●音楽:V・クヒアニーゼ●時間:87分●出演:アフタンジル・ワラジ(Pirosmani)/アッラ・ミンチン (Margarita)/ニーノ・ セトゥリーゼ/マリャ・グワラマーゼ/ボリス・ツィプリヤ/ダヴィッド・アバシーゼ/ズラブ・カピアニーゼ/テモ・ペリーゼス/ボリス・ツィプリ
セトゥリーゼ/マリャ・グワラマーゼ/ボリス・ツィプリヤ/ダヴィッド・アバシーゼ/ズラブ・カピアニーゼ/テモ・ペリーゼス/ボリス・ツィプリ
 ヤ●日本公開:1978/09●配給:日本海映画=エキプ・ド・シネマ●最初に観た場所:岩波ホール(78-10-18)(評価:★★★★)
ヤ●日本公開:1978/09●配給:日本海映画=エキプ・ド・シネマ●最初に観た場所:岩波ホール(78-10-18)(評価:★★★★)
岩波ホール 1968年2月9日オープン、1972年2月12日、エキプ・ド・シネマスタート(以後、主に映画館として利用される)2022年7月29日閉館
「岩波ホール」閉館(2022.7.29)「ピロスマニ」上から4段目/右から5番目

2015年11月、37年ぶりにデジタルリマスター&グルジア語オリジナル版で岩波ホールにて劇場公開(邦題:「放浪の画家ピロスマニ」、監督クレジット:ギオルギ・シェンゲラヤ)






 八重が本書で本格的に登場するのは、その会津城での最後の籠城戦からで、時局の流れからも会津藩にとってはそもそも絶望的な戦いでしたが、それでも著者をして「『百人の八重』がいたら、敵軍に大打撃を与え壊滅させることも不可能ではなかった」と言わしめるほどに八重は大活躍をし、また、他の会津の女性達も、城を守って、炊事や食料調達、負傷者の看護、戦闘に至るまで、男以上の働きをしたようです。
八重が本書で本格的に登場するのは、その会津城での最後の籠城戦からで、時局の流れからも会津藩にとってはそもそも絶望的な戦いでしたが、それでも著者をして「『百人の八重』がいたら、敵軍に大打撃を与え壊滅させることも不可能ではなかった」と言わしめるほどに八重は大活躍をし、また、他の会津の女性達も、城を守って、炊事や食料調達、負傷者の看護、戦闘に至るまで、男以上の働きをしたようです。 その端的な例が「白河の戦」で戦闘経験も戦略も無い西郷頼母(ドラマでは西田敏行が演じている)を総督に据えて未曾有の惨敗を喫したことであり、後に籠城戦で主導的役割を演じる容保側近の梶原平馬(ドラマでは池内博之が演じている)も以前から西郷頼母のことを好いてなかったというのに、誰が推挙してこういう人事になったのか―その辺りはよく分からないらしいけれど(著者は、人材不足から梶原平馬が敢えて逆手を打った可能性もあるとしているが)、参謀が誰も主君を諌めなかったのは確か(ちょうどその頃会津にいた新撰組の土方歳三を起用したら、また違った展開になったかもーというのが、歴史に「もし」は無いにしても、想像を掻き立てる)。
その端的な例が「白河の戦」で戦闘経験も戦略も無い西郷頼母(ドラマでは西田敏行が演じている)を総督に据えて未曾有の惨敗を喫したことであり、後に籠城戦で主導的役割を演じる容保側近の梶原平馬(ドラマでは池内博之が演じている)も以前から西郷頼母のことを好いてなかったというのに、誰が推挙してこういう人事になったのか―その辺りはよく分からないらしいけれど(著者は、人材不足から梶原平馬が敢えて逆手を打った可能性もあるとしているが)、参謀が誰も主君を諌めなかったのは確か(ちょうどその頃会津にいた新撰組の土方歳三を起用したら、また違った展開になったかもーというのが、歴史に「もし」は無いにしても、想像を掻き立てる)。 しかも、その惨敗を喫した西郷頼母への藩からの咎めは一切なく、松平容保(ドラマでは綾野剛が演じている)はドラマでは藩士ばかりでなく領民たちからも尊敬を集め、「至誠」を貫いた悲劇の人として描かれてる印象ですが、こうした信賞必罰の甘さ、優柔不断さが会津藩に悲劇をもたらしたと言えるかも―養子とは言え、藩主は藩主だろうに。旧弊な重役陣を御しきれない養子の殿様(企業小説で言えば経営者)といったところでしょうか。本書の方がドラマよりも歴史小説っぽい? いや、企業小説っぽいとも言えるかも。
しかも、その惨敗を喫した西郷頼母への藩からの咎めは一切なく、松平容保(ドラマでは綾野剛が演じている)はドラマでは藩士ばかりでなく領民たちからも尊敬を集め、「至誠」を貫いた悲劇の人として描かれてる印象ですが、こうした信賞必罰の甘さ、優柔不断さが会津藩に悲劇をもたらしたと言えるかも―養子とは言え、藩主は藩主だろうに。旧弊な重役陣を御しきれない養子の殿様(企業小説で言えば経営者)といったところでしょうか。本書の方がドラマよりも歴史小説っぽい? いや、企業小説っぽいとも言えるかも。

 「八重の桜」●演出:加藤拓/一木正恵●制作統括:内藤愼介●作:山本むつみ●テーマ音楽:
「八重の桜」●演出:加藤拓/一木正恵●制作統括:内藤愼介●作:山本むつみ●テーマ音楽: 地涼/津嘉山正種/斎藤工/芦名星/佐藤B作/風間杜夫/中村獅童/六平直政/池内博之/宮下順子/黒木メイサ/剛力彩芽/小泉孝太郎/榎木孝明/生瀬勝久/吉川晃司/反町隆史/林与一/小栗旬/及川光博/須賀貴匡/加藤雅也/伊吹吾郎/村上弘明/長谷川博己/オダギリジョー/奥田瑛二/市川染五郎/神尾佑/村上淳/
地涼/津嘉山正種/斎藤工/芦名星/佐藤B作/風間杜夫/中村獅童/六平直政/池内博之/宮下順子/黒木メイサ/剛力彩芽/小泉孝太郎/榎木孝明/生瀬勝久/吉川晃司/反町隆史/林与一/小栗旬/及川光博/須賀貴匡/加藤雅也/伊吹吾郎/村上弘明/長谷川博己/オダギリジョー/奥田瑛二/市川染五郎/神尾佑/村上淳/ 「八重の桜」出演者発表会見
「八重の桜」出演者発表会見


 今回の中国艦船による「レーダー照射事件」などは、まさにその勢いでやったという印象。「照射しただけでしょう。戦争にはなりませんよ」「正当な私たちの国家の防衛的行動だと思います」という"北京市民の声"が報じられています。
今回の中国艦船による「レーダー照射事件」などは、まさにその勢いでやったという印象。「照射しただけでしょう。戦争にはなりませんよ」「正当な私たちの国家の防衛的行動だと思います」という"北京市民の声"が報じられています。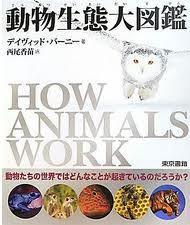

 例えば「足で歩く」のところでは、ヤスデ(750本の足は動物の中で最も多い)とチーターが一緒に登場したり、「極限の環境に生きる」のところでは、冬眠するヤマネと、400℃に達する海底熱水噴火口に生息するポンペイワームや10年以上も冬眠が可能な微生物のクマムシが一緒に登場するなど、哺乳類や魚類などの脊椎動物から、無脊椎動物や昆虫、更には微生物まで、1つのテーマや切り口の中では同等に扱っている(写真の大きさも)のが斬新です。
例えば「足で歩く」のところでは、ヤスデ(750本の足は動物の中で最も多い)とチーターが一緒に登場したり、「極限の環境に生きる」のところでは、冬眠するヤマネと、400℃に達する海底熱水噴火口に生息するポンペイワームや10年以上も冬眠が可能な微生物のクマムシが一緒に登場するなど、哺乳類や魚類などの脊椎動物から、無脊椎動物や昆虫、更には微生物まで、1つのテーマや切り口の中では同等に扱っている(写真の大きさも)のが斬新です。 無脊椎動物の一種「扁形動物」で60センチにもなるというウズムシなんて知らなかったし、サナダムシの頭部の写真は怖いなあ。魚類の一種「無顎類」であるヌタウナギって、心臓が4つあるのか―等々、トリビアな記述が満載で、こうした細部の解説も楽しめ、それらにもちゃんと写真が付されています。
無脊椎動物の一種「扁形動物」で60センチにもなるというウズムシなんて知らなかったし、サナダムシの頭部の写真は怖いなあ。魚類の一種「無顎類」であるヌタウナギって、心臓が4つあるのか―等々、トリビアな記述が満載で、こうした細部の解説も楽しめ、それらにもちゃんと写真が付されています。

 人類進化のストーリーを一般読者が身近に感じられるようにとの狙いから写真・イラスト・図説が充実していて、本書の編集長で英国の科学ジャーナリストであるアリス・メイ・ロバーツ(Alice Roberts)は、医学、解剖学、骨考古学、人類学に精通したサイエンス・コミュニケーターで、BBCの科学番組などにも出演しているとのこと、とりわけ、「人類」の章に出てくる、古生物を専門とする模型作家オランダのアドリー&アルフォンス・ケネス兄弟による、古代人類13体の容貌の精緻な復元モデルは、今にも動き出しそうなほどのリアリティがあります。
人類進化のストーリーを一般読者が身近に感じられるようにとの狙いから写真・イラスト・図説が充実していて、本書の編集長で英国の科学ジャーナリストであるアリス・メイ・ロバーツ(Alice Roberts)は、医学、解剖学、骨考古学、人類学に精通したサイエンス・コミュニケーターで、BBCの科学番組などにも出演しているとのこと、とりわけ、「人類」の章に出てくる、古生物を専門とする模型作家オランダのアドリー&アルフォンス・ケネス兄弟による、古代人類13体の容貌の精緻な復元モデルは、今にも動き出しそうなほどのリアリティがあります。 続いて登場のアウストラロピテクス・アファレンシスは、現生人類(ホモ・サピエンス)が属するヒト属(ホモ属)の祖先ではないかと考えられていますが、これも同じくサルのように見えると言っていいのでは(特に横顔)。しかしながら、生態図(イメージイラスト)をアルディピテクス・ラミダスのものと比べると、より完全な二足歩行になっていて"人間"っぽい感じ。
続いて登場のアウストラロピテクス・アファレンシスは、現生人類(ホモ・サピエンス)が属するヒト属(ホモ属)の祖先ではないかと考えられていますが、これも同じくサルのように見えると言っていいのでは(特に横顔)。しかしながら、生態図(イメージイラスト)をアルディピテクス・ラミダスのものと比べると、より完全な二足歩行になっていて"人間"っぽい感じ。 そして登場するのが「ネアンデルタール人」ことホモ・ネアンデルタレンシスで、最も新しい遺跡はジブラルタルで見つかっているが、どうして絶滅したのかはまだ謎であるとのこと。ある本には、ネアンデルタール人が床屋にいって髪を整え、スーツを着てニューヨークの街中を歩けば、誰もそれがネアンデルタール人であることに気が付かないであろうと書いてあった記憶がありますが、復元された容貌を見ると確かに。そして最後に、ホモ・サピエンスの登場―人類系統樹の中で唯一生き残った枝であり、最初は黒人しかいなかったわけだ。
そして登場するのが「ネアンデルタール人」ことホモ・ネアンデルタレンシスで、最も新しい遺跡はジブラルタルで見つかっているが、どうして絶滅したのかはまだ謎であるとのこと。ある本には、ネアンデルタール人が床屋にいって髪を整え、スーツを着てニューヨークの街中を歩けば、誰もそれがネアンデルタール人であることに気が付かないであろうと書いてあった記憶がありますが、復元された容貌を見ると確かに。そして最後に、ホモ・サピエンスの登場―人類系統樹の中で唯一生き残った枝であり、最初は黒人しかいなかったわけだ。 「出アフリカ」の章では、最後にオセアニアに至る人類移動(ロコモーション)全体を扱っていますが、この章も図説が多く、写真も豊富で分かり良いです(初期人類の出アフリカは200万年前、ホモ・サピエンスの出アフリカは8万年前から5万年前としている)。
「出アフリカ」の章では、最後にオセアニアに至る人類移動(ロコモーション)全体を扱っていますが、この章も図説が多く、写真も豊富で分かり良いです(初期人類の出アフリカは200万年前、ホモ・サピエンスの出アフリカは8万年前から5万年前としている)。