「●か G・ガルシア=マルケス」の インデックッスへ Prev|NEXT ⇒ 【1414】 ガブリエル・ガルシア=マルケス 『予告された殺人の記録』
「○ラテンアメリカ文学 【発表・刊行順】」の インデックッスへ
「魔術的リアリズム」の真骨頂。『百年の孤独』の余韻を引いているような作品群。
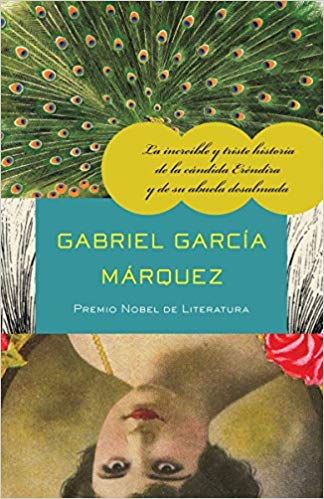




スペイン語ペーパーバック(2010) 『エレンディラ (1983年) (サンリオ文庫)』『エレンディラ (ちくま文庫)
』映画「エレンディラ」('83年/メキシコ・仏・西独)『美しい水死人―ラテンアメリカ文学アンソロジー (福武文庫)
』['95年]
 14歳の美少女エレンディラは、両親を早く亡くし祖母に育てられたが、自らの過失による火事で家を焼き、その償いとして、祖母とテント生活の旅をしながら売春させられる。テントの前には男達が群がり商売は繁盛、祖母が1日に何十人もの客を取らせるため、エレンディラはボロボロになってしまうが、何度か逃げ出す機会があったものの、結局は自分から祖母の元に戻っていく―。(「無垢なエレンディラと無情な祖母の信じがたい悲惨の物語」)
14歳の美少女エレンディラは、両親を早く亡くし祖母に育てられたが、自らの過失による火事で家を焼き、その償いとして、祖母とテント生活の旅をしながら売春させられる。テントの前には男達が群がり商売は繁盛、祖母が1日に何十人もの客を取らせるため、エレンディラはボロボロになってしまうが、何度か逃げ出す機会があったものの、結局は自分から祖母の元に戻っていく―。(「無垢なエレンディラと無情な祖母の信じがたい悲惨の物語」)
ボリビアの作家、G・ガルシア=マルケス(1928-)が1978年に発表した作品集で、中篇「無垢なエレンディラと無情な祖母の信じがたい悲惨の物語」の他に、「大きな翼のある、ひどく年取った男」「失われた時の海」「この世でいちばん美しい水死人」「愛の彼方の変わることなき死」「幽霊船の最後の航海」「奇跡の行商人、善人のブラカマン」の各短篇6作を所収。
民話や伝承のエピソードがベースになった作品が多く含まれているそうですが、「魔術的リアリズム」の作家と呼ばれるように、現実的なものと幻想的なものを結び合わせて、独特の神話的な作風を生んでおり、それが、砂漠とジャングルと海が隣接するボリビアの風土を背景にしたものであるだけに、なおさらにエキゾチックなイマジネーションを駆りたてます。
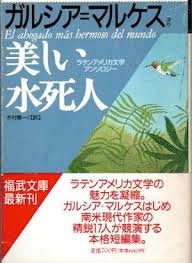 「大きな翼のある、ひどく年取った男」で、地上に堕ちて着て、村人に奇妙な見世物のように扱われる、老いた"天使"を描いたかと思うと、「この世でいちばん美しい水死人」では、村に漂着した"土左衛門"の美しさを村の女達が賛美するという、ちょっと日常では考えられないと言うか、人々の日常の中に非日常、非現実がいきなり入り込んだような話が続きます。
「大きな翼のある、ひどく年取った男」で、地上に堕ちて着て、村人に奇妙な見世物のように扱われる、老いた"天使"を描いたかと思うと、「この世でいちばん美しい水死人」では、村に漂着した"土左衛門"の美しさを村の女達が賛美するという、ちょっと日常では考えられないと言うか、人々の日常の中に非日常、非現実がいきなり入り込んだような話が続きます。
『美しい水死人―ラテンアメリカ文学アンソロジー (福武文庫)』
「大人のための残酷な童話」として書かれたそうですが、個人的には、「愛の彼方の変わることなき死」と「奇跡の行商人、善人のブラカマン」が面白かったです。
「愛の彼方の変わることなき死」は、上院議員オナシモ・サンチェスが、選挙運動期間中に少女と淫行に及ぶというもので、彼は、そのことがスキャンダルとなり、6ヵ月と11日後に自らが死ぬことになることを正確に予知しながらも、まさに今、少女を傍に侍らせているのですが、自らの宿命に抗し得ない人物を描いているように思いました。
「奇跡の行商人、善人のブラカマン」は、奇跡を起こすと言ってインチキ商品を売り歩く悪徳商人ブラカマンに師事したばかりにひどい目に遭う「ぼく」の話ですが、このブラカマンというのが、最初は単なるインチキ男に過ぎないのが、だんだんその行為が本当に超常現象的になってきて、「ぼく」にまで神のような力が備わってしまうというもの。
この作家は、何だか、極端に常軌を逸した話が好きなんだなあ(それが面白いところでもあるが)。もう、こうなってくると、人間的にいい人だとか悪い人だとかいう道徳的なことは超越してしまい、また、あまりに乾いているため、悲惨さや残酷さといったものも超えてしまっている感じです。
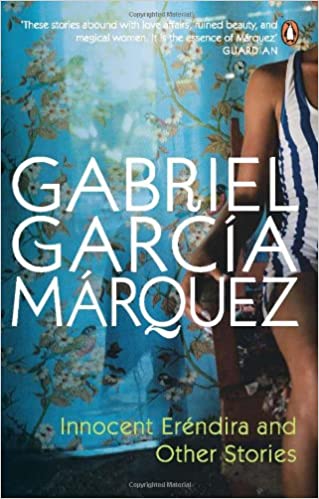 それは「エレンディラ」(Erendira)にも言え、エレンディラは、彼女を救おうとする美男子だがややひ弱な青年ウリセスとの恋に落ち、ついに祖母を殺そうとしますが、これが、大量に毒を盛った誕生祝いのケーキをまるごと食べても死なず(髪の毛は全部抜けるが)、こうなるともう魔女に近い。更に、爆弾でも死なず、鬘(かつら)が黒焦げになっているだけというのは、まるでカトゥーン・アニメのようなユーモア。
それは「エレンディラ」(Erendira)にも言え、エレンディラは、彼女を救おうとする美男子だがややひ弱な青年ウリセスとの恋に落ち、ついに祖母を殺そうとしますが、これが、大量に毒を盛った誕生祝いのケーキをまるごと食べても死なず(髪の毛は全部抜けるが)、こうなるともう魔女に近い。更に、爆弾でも死なず、鬘(かつら)が黒焦げになっているだけというのは、まるでカトゥーン・アニメのようなユーモア。
最後は、ウリセスが肉包丁で祖母に止めを刺しますが、祖母の死を確認したエレンディラは何処かへ去って行き、ウリセスはただ泣くばかり―。
エレンディラが自分を虐待し続けてきた祖母に、深層心理では深く依存していたことが窺え、神話的であると同時に、人間心理の本質を突いた作品でもあります(虐待被害者にとって、虐待者が同時に庇護者でもあるというのは、現実にもあるなあ)。
"Innocent Erendira and Other Stories (International Writers)"


 「エレンディラ」は、1983年にルイ・グエッラ監督によりイレーネ・パパス(祖母役)主演で映画化され、日本でもPARCOの配給で公開されましたが、チェックしていたものの見損なってしまい、今はビデオも絶版となりDVD化もされていないということで、やはり、こうした映画は、観ることが出来るその時に観ておくべきだったなあと今更ながらに思います。
「エレンディラ」は、1983年にルイ・グエッラ監督によりイレーネ・パパス(祖母役)主演で映画化され、日本でもPARCOの配給で公開されましたが、チェックしていたものの見損なってしまい、今はビデオも絶版となりDVD化もされていないということで、やはり、こうした映画は、観ることが出来るその時に観ておくべきだったなあと今更ながらに思います。

 '07年に蜷川幸雄氏により舞台化されていますが、オリジナルの「エレンディラ」の話に「大きな翼のある、ひどく年取った男」の話を織り込んで、ウリセスを天使にするという、相当に手を加えた脚色になっているようです(祖母役は嵯川哲朗)。
'07年に蜷川幸雄氏により舞台化されていますが、オリジナルの「エレンディラ」の話に「大きな翼のある、ひどく年取った男」の話を織り込んで、ウリセスを天使にするという、相当に手を加えた脚色になっているようです(祖母役は嵯川哲朗)。
「エレンディラ」の中にも、上院議員オナシモ・サンチェスや悪徳商人ブラカマンの名が出てくるように、これらの話がある土地で同じ時期に起きた出来事であるかのような構成になって、『百年の孤独』('72年発表)の余韻を引いているような作品という印象を持ちました(短篇については、これらの作品の何れかが『百年の孤独』に挿入されていても不自然ではないかも)。

VHS「エレンディラ」

VHS「エレンディラ/ヘカテ」
【1988年再文庫化[ちくま文庫]】




 1982年にノーベル文学賞を受賞したコロンビア出身の作家ガブリエル・ガルシア=マルケス(1928年生まれ)が2004年に発表した中編小説(原題: Memorias de mis putas tristes)で、2010年にノーベル文学賞を受賞したペルーの作家マリオ・バルガス=リョサ(1936年生まれ)の代表作『緑の家』も、並行する複数の物語の舞台の1つが娼館でしたが、南米の娼館って、ちょっとイメージしにくかったかなあ。
1982年にノーベル文学賞を受賞したコロンビア出身の作家ガブリエル・ガルシア=マルケス(1928年生まれ)が2004年に発表した中編小説(原題: Memorias de mis putas tristes)で、2010年にノーベル文学賞を受賞したペルーの作家マリオ・バルガス=リョサ(1936年生まれ)の代表作『緑の家』も、並行する複数の物語の舞台の1つが娼館でしたが、南米の娼館って、ちょっとイメージしにくかったかなあ。 むしろ、この物語に出てくる娼館は、ガルシア=マルケス自身がこの作品を書く契機となった(冒頭にその一節が引用されている)川端康成の『眠れる美女』に出てくる、秘密裏に営まれる小さな娼家に近い感じでしょうか。主人公を手引きする女主人の存在も似ていますが、『眠れる美女』の女主人の方は何だか秘密めいた感じなのに対し、こちらはいかにも"ヤリ手婆(ババア)"という感じで、ユーモラスでさえあります。
むしろ、この物語に出てくる娼館は、ガルシア=マルケス自身がこの作品を書く契機となった(冒頭にその一節が引用されている)川端康成の『眠れる美女』に出てくる、秘密裏に営まれる小さな娼家に近い感じでしょうか。主人公を手引きする女主人の存在も似ていますが、『眠れる美女』の女主人の方は何だか秘密めいた感じなのに対し、こちらはいかにも"ヤリ手婆(ババア)"という感じで、ユーモラスでさえあります。
 因みに、この作品は、2014年にアカデミー名誉賞を受賞したジャン=クロード・カリエール(「昼顔」「ブリキの太鼓」「存在の耐えられない軽さ」)の脚本で映画化されていて、監督は、本作が遺作となったのヘニング・カールセン監督(「黄金の肉体 ゴーギャンの妻」)、主演はエミリオ・エチェバリア(「アモーレス・ペロス」)、共演は、ジェラルディン・チャプリン(「ドクトル・ジバゴ」「ナッシュビル」「チャーリー」)とのことです。(●2018年にDVDがリリースされた。)
因みに、この作品は、2014年にアカデミー名誉賞を受賞したジャン=クロード・カリエール(「昼顔」「ブリキの太鼓」「存在の耐えられない軽さ」)の脚本で映画化されていて、監督は、本作が遺作となったのヘニング・カールセン監督(「黄金の肉体 ゴーギャンの妻」)、主演はエミリオ・エチェバリア(「アモーレス・ペロス」)、共演は、ジェラルディン・チャプリン(「ドクトル・ジバゴ」「ナッシュビル」「チャーリー」)とのことです。(●2018年にDVDがリリースされた。)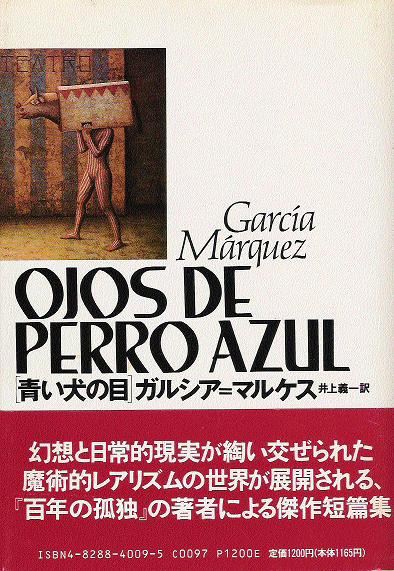


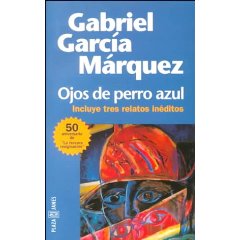
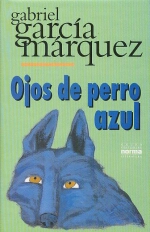 文庫版の副題にあるように、以下、主に死をモチーフとした作品が続きますが、「青い犬の目」と言ってくれる男を捜している女と、そういう女を探していた「ぼく」との会話を描いた表題作「青い犬の目」を分岐点に、後半部分の作品は少し毛色が変わって、ホセのレストランに毎晩6時に来る女とホセとの会話を綴った「六時に来た女」などは、ヘミングウェイの「殺し屋」のみたいなハードボイルド・トーンで(これは"幻想短編"というこの短編集全体のトーンからも外れているが)、それでいてペーソスを含んだストーリーが面白かったです(結局、この話に出てくる女は男に何を頼んでいるかというと、○○○○作りなのだ)。
文庫版の副題にあるように、以下、主に死をモチーフとした作品が続きますが、「青い犬の目」と言ってくれる男を捜している女と、そういう女を探していた「ぼく」との会話を描いた表題作「青い犬の目」を分岐点に、後半部分の作品は少し毛色が変わって、ホセのレストランに毎晩6時に来る女とホセとの会話を綴った「六時に来た女」などは、ヘミングウェイの「殺し屋」のみたいなハードボイルド・トーンで(これは"幻想短編"というこの短編集全体のトーンからも外れているが)、それでいてペーソスを含んだストーリーが面白かったです(結局、この話に出てくる女は男に何を頼んでいるかというと、○○○○作りなのだ)。
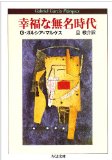

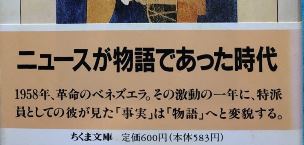
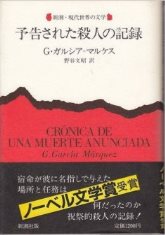



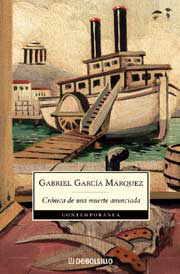
 事件の経過を、5つの視座・視点で再構成しているため、カットッバック的にそれらが重なり、手法的には丁度、娯楽映画であるスタンリー・キューブリックの「現金に体を張れ」('56年)や、クエンティン・タランティーノの「パルプ・フィクション」('94年)を想起しました(舞台化されているが、この5つの視座・視点はどう表現されているのだろうか)。
事件の経過を、5つの視座・視点で再構成しているため、カットッバック的にそれらが重なり、手法的には丁度、娯楽映画であるスタンリー・キューブリックの「現金に体を張れ」('56年)や、クエンティン・タランティーノの「パルプ・フィクション」('94年)を想起しました(舞台化されているが、この5つの視座・視点はどう表現されているのだろうか)。



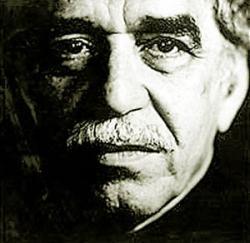

 1967年に発表されたコロンビア出身の作家ガブリエル・ガルシア=マルケス(1928年生まれ)の代表的長編小説で、ホセ・アルカディオ・ブエンディアとウルスラの夫婦を始祖とするブエンディア一族が蜃気楼の村マコンドを創設し、隆盛を迎えながらも、やがて滅亡するまでの100年間を描いています。
1967年に発表されたコロンビア出身の作家ガブリエル・ガルシア=マルケス(1928年生まれ)の代表的長編小説で、ホセ・アルカディオ・ブエンディアとウルスラの夫婦を始祖とするブエンディア一族が蜃気楼の村マコンドを創設し、隆盛を迎えながらも、やがて滅亡するまでの100年間を描いています。 寺山修司(1935-1983)が「
寺山修司(1935-1983)が「 「マコンド」は作者が創作した架空の村ですが(時折出てくる実在の地名からすると、コロンビアでもカリブ海よりの方か)、こうした設定は、作者が影響を受けた作家の1人であるというフォークナーが、『
「マコンド」は作者が創作した架空の村ですが(時折出てくる実在の地名からすると、コロンビアでもカリブ海よりの方か)、こうした設定は、作者が影響を受けた作家の1人であるというフォークナーが、『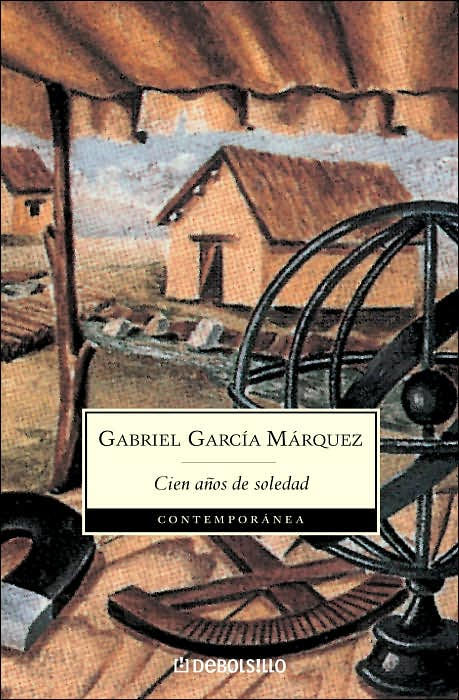 そして、その息子兄弟であるホセ・アルカディオとアウレリャノ・ブエンディア大佐(「長い歳月が流れて銃殺隊の前に立つはめになった」と冒頭にあり、『予告された殺人の記録』と似たような書き出しなのだが...)に代表されるように、マッチョで粗暴な一面と革命家としてのヒロイック資質が、更には一部に学究者または職人的執着心が、同じくアルカディオ乃至アウレリャノと名付けられる子孫たちにそれぞれ引き継がれていきます。
そして、その息子兄弟であるホセ・アルカディオとアウレリャノ・ブエンディア大佐(「長い歳月が流れて銃殺隊の前に立つはめになった」と冒頭にあり、『予告された殺人の記録』と似たような書き出しなのだが...)に代表されるように、マッチョで粗暴な一面と革命家としてのヒロイック資質が、更には一部に学究者または職人的執着心が、同じくアルカディオ乃至アウレリャノと名付けられる子孫たちにそれぞれ引き継がれていきます。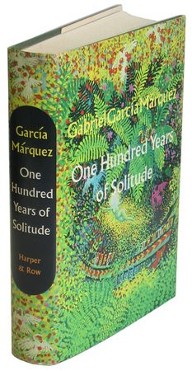 細部の構成力もさることながら、ちょうどエミール・ゾラの『居酒屋』、『ナナ』、『ジェルミナール』などの作品群がルーゴン家、マッカール家など3つの家系に纏わる5世代の話として位置づけられる「ルーゴン・マッカール双書」のようなものが、『百年の孤独』という一作品に集約されているような密度とスケールを感じます(運命論的なところもゾラと似ている。ゾラの場合、彼自身が信じていた遺伝子的決定論の色が濃いが)
細部の構成力もさることながら、ちょうどエミール・ゾラの『居酒屋』、『ナナ』、『ジェルミナール』などの作品群がルーゴン家、マッカール家など3つの家系に纏わる5世代の話として位置づけられる「ルーゴン・マッカール双書」のようなものが、『百年の孤独』という一作品に集約されているような密度とスケールを感じます(運命論的なところもゾラと似ている。ゾラの場合、彼自身が信じていた遺伝子的決定論の色が濃いが)
 神話的または伝承説話的な雰囲気を醸しつつも、それでいて読みやすく、人の生き死にとはどういったものか、一族とは何か(大家族を扱っている点では、近代日本文学とダブる面もある?)といったことを身近に感じさせ考えさせてくれる、不思議な力を持った作品でもあるように思いました。
神話的または伝承説話的な雰囲気を醸しつつも、それでいて読みやすく、人の生き死にとはどういったものか、一族とは何か(大家族を扱っている点では、近代日本文学とダブる面もある?)といったことを身近に感じさせ考えさせてくれる、不思議な力を持った作品でもあるように思いました。

