「●映画」の インデックッスへ Prev|NEXT ⇒ 【1839】 石田 一 『図説 ホラー・シネマ』
「●小津安二郎」の インデックッスへ 「●原 節子 出演作品」の インデックッスへ
原節子"通"を任ずるならば押さえておきたい1冊。本人発言等、事実からその実像に迫る。



『原節子―伝説の女優 (平凡社ライブラリー)』『原節子―映画女優の昭和
』 朝日新聞「号外」2015年11月25日
 末延芳晴 著『原節子、号泣す』('14年/集英社新書)をちょうど再読し終えた頃に原節子の訃報に接しましたが、既に95歳だっため何となく予感はありました。本人の遺志により発表を遅らせたとのことで、読んでいた頃にはもう亡くなっていたのかあ。文春文庫ビジュアル版の『大アンケートによる日本映画ベスト150』('89年)に監督・男優・女優の各ベスト10のコーナーがあり、女優は、1位・原節子、2位・吉永小百合、3位・高峰秀子、4位・田中絹代、5位・岩下志麻、6位・京マチ子、7位・山田五十鈴、8位・若尾文子、9位・岸恵子、10位・藤純子となっており、やはりスゴイ女優だったのだなあと。
末延芳晴 著『原節子、号泣す』('14年/集英社新書)をちょうど再読し終えた頃に原節子の訃報に接しましたが、既に95歳だっため何となく予感はありました。本人の遺志により発表を遅らせたとのことで、読んでいた頃にはもう亡くなっていたのかあ。文春文庫ビジュアル版の『大アンケートによる日本映画ベスト150』('89年)に監督・男優・女優の各ベスト10のコーナーがあり、女優は、1位・原節子、2位・吉永小百合、3位・高峰秀子、4位・田中絹代、5位・岩下志麻、6位・京マチ子、7位・山田五十鈴、8位・若尾文子、9位・岸恵子、10位・藤純子となっており、やはりスゴイ女優だったのだなあと。
本書(同著者の『原節子―映画女優の昭和』('87年/大和書房)に加筆修正してライブラリー化したもの)は、その原節子の女優としてのキャリアを丹念に追ったものであり、原節子"通"を任じるならば是非とも押さえておきたい1冊です。著者があとがきで述べていますが、従来の女優の自伝・評伝の、身近な人間関係に密着して展開する書き方とはやや距離を置き、原節子のその時点時点での発言を重視し、その意味を、役や作品や周囲の証言や、その時代の映画・歴史状況と対応させてみるという手法を取っています。こう書くと難しく感じるかもしれませんが、実際はその逆で、事実を出来るだけ詳しく記し、解釈は読者に預ける、或いは事実から汲み取ってもらうという手法にも思え、著者による作品解釈等引っ掛かったりすることが殆ど無いため、正味400ページありますが、すらすら読めました。
興味深かったのは、デビュー以来その素材を買われながらも今一つ力が出し切れず、一部からは「大根」と呼ばれていた時期が結構長くあったのだなあということで、時折、その年代ごとの女優のブロマイドの売れ行きベストテンやギャランティによる番付、映画雑誌による人気ランキングが出てきますが、ベストテンには早くから名を連ねるものの、ずっとその中では6位以下の下位グループに位置し、結局、戦前10年ベストテンの下位に低迷し続け、彼女が初めてベスト5に入ったのが、雑誌「近代映画」の1949年正月号で、この時点でも、1位に高峰三枝子(当時30歳)、2位に高峰秀子(同24歳)がいて、原節子(同28歳)は第3位でした。4位が田中絹代(同31歳)で5位が山田五十鈴(同31歳)だから、確かに演技面力の面でも"強者"揃いであるわけですが。
 本書によれば、彼女が人気の頂点に達したのは1951年で、ハリウッドの外国人記者協会が企画し毎日新聞が代行した日本における一般投票で、前年の4位からこの年のトップになっています。但し、1952年の「映画ファン」5月号の人気投票では、作品投票で主演作の「麦秋」('51年)、「めし」('51年)が1位と2位に選ばれたにも関わらず、原節子(当時32歳)は津島恵子(同26歳)に次いで2位に後退しており、今でこそ「伝説の女優」と言われていますが、当時は彼女も、移ろいがちな女優人気のうねりの中にいたのだなあと思いました。
本書によれば、彼女が人気の頂点に達したのは1951年で、ハリウッドの外国人記者協会が企画し毎日新聞が代行した日本における一般投票で、前年の4位からこの年のトップになっています。但し、1952年の「映画ファン」5月号の人気投票では、作品投票で主演作の「麦秋」('51年)、「めし」('51年)が1位と2位に選ばれたにも関わらず、原節子(当時32歳)は津島恵子(同26歳)に次いで2位に後退しており、今でこそ「伝説の女優」と言われていますが、当時は彼女も、移ろいがちな女優人気のうねりの中にいたのだなあと思いました。
「麦秋」(1951年)
そうした原節子の魅力を十分に引き出したの小津安二郎監督であると言われていますが、本書の中にあるエピソードでは、「麦秋」のクランクインが迫った際に、原節子はギャラが高いから別の女優にしてくれと松竹から言われた小津安二郎監督が、原節子が出なければ作品は中止すると珍しく興奮した声で言ったといい、それを聞いた原節子が、自分のギャラは半分でもいいから小津の作品に出演したいと言ったという話に、二人の結びつきの強さを感じました。
また、原節子はこの頃には女優としての意識にも高いものがあり、「日本映画そのものに、ハッキリとした貫くような個性がないんですもの。リアリズムも底が衝けないか、或いは詩がないのよ」(「近代映画」'51年7月号)とも言っており、「麦秋」の完成間近には、「日本映画の欠点?そうね、それはシナリオだと思うわ。小説の映画化ばかり追っかけている現状は悲しいと思うの。演技者にあった強力なオリジナルを書いて、あッと言わしてくれるシナリオ・ライターがあってもいいと思うわね。」(「時事新報」'51年9月14日)とまで言っていますが、確かに「麦秋」はオリジナル脚本でした(その前の「晩春」('49年)は広津和郎「父と娘」が原作)。
その少し後には「私は演技がナチュラルに没してしまうのが恐いんです。(中略)映画のリアリズっていうものが、私たちが演技するナチュラルな写実ではなくって、出演者の(中略)厳密なね、リアリズムが一分の隙もなくナチュラルに見える結果の演技でなくっちゃ...。」(「丸」'54年1月号)などといった発言もあり、これ、スゴくない?
興味深かったのは、「日刊スポーツ」や「スポーツニッポン」「報知新聞」といったスポーツ紙のインタビューが本書には多く載っていますが、その中で、結構ざっくばらんに自分のことを語っている点で、自らを「大根」だとか「おばちゃん」だとか言ったり、自分が演じた役柄が自分には今一つしっくりこなかったとあっさり言ってしまうなど相当サバけた印象があり、結婚に関する記者の質問にも自分なりの考えを述べるなど(時に記者を軽くあしらい)、非常に現代的・現実的な思考や感覚の持ち主であったことが窺える点でした。
小津安二郎が彼女の魅力を引き出したのは確かですが、小津の描いたやや古風な女性像に続いて、そうした彼女の実像に近いモダンな部分を作品にうまく反映させる監督が現れなかったというのも、彼女が引退を決意した理由として考えられるのではないでしょうか。映画評論家の白井佳夫氏が、「原節子を、完全に使いこなし、その比類なき魅力をスクリーンに開花させてくれるような、一群の映画作家たちの魔術が、だんだん消え失せてしまうような新時代の到来が、彼女に引退を決意させたのだ...」と言っていますが、原節子自身は、そうした新時代の女性を演じるに適した素養も持っていたような気もします。
 勿論、インタビューでの発言や態度がそのまま映画作品の人物造型に反映されるとも限らないし、本書からは、原節子自身が早くから年齢を意識し、引退を考えていたことも窺えるので何とも言えませんが...。本書を読むと、人気がピークになればなるほど、引退を強く意識していたような感じも。そして、'63年の小津監督の死で「引退」は決定的になったように思います。本書によれば、小津の通夜に姿を現した原節子は小津の遺体に号泣し、この時、本名の会田昌江で弔意を表したそうです。'64年には狛江の自宅を引き払い、鎌倉に住む義兄の熊谷久虎監督の夫婦のもとに引っ越しています(この地が彼女の終の住処となる)。
勿論、インタビューでの発言や態度がそのまま映画作品の人物造型に反映されるとも限らないし、本書からは、原節子自身が早くから年齢を意識し、引退を考えていたことも窺えるので何とも言えませんが...。本書を読むと、人気がピークになればなるほど、引退を強く意識していたような感じも。そして、'63年の小津監督の死で「引退」は決定的になったように思います。本書によれば、小津の通夜に姿を現した原節子は小津の遺体に号泣し、この時、本名の会田昌江で弔意を表したそうです。'64年には狛江の自宅を引き払い、鎌倉に住む義兄の熊谷久虎監督の夫婦のもとに引っ越しています(この地が彼女の終の住処となる)。
1960年11月、東京都内の自宅で取材に応じる原節子[朝日新聞デジタル 2015年12月8日]
出来るだけ客観的事実で本書を構成し、あまり自身の見解を織り込み過ぎないように注意を払ってきたかに見える著者ですが、本書末尾で、「映画女優としての原節子は希有な美しさのため、"花"としての存在価値が大きく、そのなかにあって、原の自己主張は覆い隠されてしまった傾向がある」としており、この見方には大いに頷かされました。


 この内、「
この内、「 原節子の小津映画初めての号泣場面を分析した後、第7章で、「娘は父親と性的結合を望んでいたか」というテーマを扱い、これまで多くの映画評論家が指摘してきたこの作品に対する読解(高橋治『絢爛たる影絵』、蓮實重彦『
原節子の小津映画初めての号泣場面を分析した後、第7章で、「娘は父親と性的結合を望んでいたか」というテーマを扱い、これまで多くの映画評論家が指摘してきたこの作品に対する読解(高橋治『絢爛たる影絵』、蓮實重彦『

 第8章では「
第8章では「





 「秋刀魚の味」●制作年:1962年●監督:小津安二郎●製作:山内静夫●脚本:野田高梧/小津安二郎●撮影:厚田雄春●音楽:斎藤高順●原作:里見弴●時間:113分●出演:笠智衆/岩下志麻/佐田啓二/岡
「秋刀魚の味」●制作年:1962年●監督:小津安二郎●製作:山内静夫●脚本:野田高梧/小津安二郎●撮影:厚田雄春●音楽:斎藤高順●原作:里見弴●時間:113分●出演:笠智衆/岩下志麻/佐田啓二/岡 田茉莉子/中村伸郎/東野英治郎/北竜二/杉村春子/加東大介/吉田輝雄/三宅邦子/高橋とよ/牧紀子/三上真一郎/環三千世/岸田今日子/浅茅しのぶ/須賀不二男/菅原通済(特別出演)/緒方安雄(特別出演)●公開:1962/11●配給:松竹●最初に観た場所:三鷹オスカー(82-09-12)●2回目(デジタルリマスター版):神保町シアター(13-12-23)●3回目(デジタルリマスター版):北千住・シネマブルースタジオ(19-06-11)(評価:★★★★)●併映:「東京物語」(小津安二郎)/「彼岸花」(小津安二郎)
田茉莉子/中村伸郎/東野英治郎/北竜二/杉村春子/加東大介/吉田輝雄/三宅邦子/高橋とよ/牧紀子/三上真一郎/環三千世/岸田今日子/浅茅しのぶ/須賀不二男/菅原通済(特別出演)/緒方安雄(特別出演)●公開:1962/11●配給:松竹●最初に観た場所:三鷹オスカー(82-09-12)●2回目(デジタルリマスター版):神保町シアター(13-12-23)●3回目(デジタルリマスター版):北千住・シネマブルースタジオ(19-06-11)(評価:★★★★)●併映:「東京物語」(小津安二郎)/「彼岸花」(小津安二郎)

 「晩春」●制作年:1949年●監督:小津安二郎●脚本:野田高梧/小津安二郎●撮影:厚田雄春●音楽:伊藤冝二●広津和郎「父と娘」●時間:108分●出演:笠智衆/原節子/月丘夢路/宇佐美淳/杉村春子/青木放屁/三宅邦子/三島雅夫/坪内美子/桂木洋子/清水一郎/谷崎純/高橋豊子/紅沢葉子●公開:1949/09●配給:松竹●最初に観た場所:大井武蔵野館 (84-02-07)(評価:★★★★☆)●併映:「早春」(小津安二郎)
「晩春」●制作年:1949年●監督:小津安二郎●脚本:野田高梧/小津安二郎●撮影:厚田雄春●音楽:伊藤冝二●広津和郎「父と娘」●時間:108分●出演:笠智衆/原節子/月丘夢路/宇佐美淳/杉村春子/青木放屁/三宅邦子/三島雅夫/坪内美子/桂木洋子/清水一郎/谷崎純/高橋豊子/紅沢葉子●公開:1949/09●配給:松竹●最初に観た場所:大井武蔵野館 (84-02-07)(評価:★★★★☆)●併映:「早春」(小津安二郎) 「東京物語」
「東京物語」
 「東京物語」のみに絞って述べているのが特徴的で、複数の作品間の連関や作品同士の相似を語る蓮實重彦氏などとは対照的と言えるかも。サブタイトルにある「世界はべスト1に選んだ」とは、"Sight & Sound"誌・映画監督による選出トップ10 (Director's Top 10 Films)(2012年版)の上位100作品のトップに「東京物語」があっさり選ばれてしまったことを指しており、そのことを切り口に、第1章で、外国人映画監督から見て、この作品がどう見えるのかを検証していますが、そこから、この作品が「日本映画」だからということで評価されているわけではないということが浮かび上がってくるのが興味深いです。
「東京物語」のみに絞って述べているのが特徴的で、複数の作品間の連関や作品同士の相似を語る蓮實重彦氏などとは対照的と言えるかも。サブタイトルにある「世界はべスト1に選んだ」とは、"Sight & Sound"誌・映画監督による選出トップ10 (Director's Top 10 Films)(2012年版)の上位100作品のトップに「東京物語」があっさり選ばれてしまったことを指しており、そのことを切り口に、第1章で、外国人映画監督から見て、この作品がどう見えるのかを検証していますが、そこから、この作品が「日本映画」だからということで評価されているわけではないということが浮かび上がってくるのが興味深いです。 登場人物・俳優に関しては、第5章「生活人」のところで、杉村春子の演技を「無邪気なまでの呼吸するようなエゴイズム」「はたして杉村春子という女優を欠いて、この人物造形が成功していただろうか」としているのに共感し(小津安二郎が杉村春子の演技を非常に高く評価していたという話をどこかで読んだ記憶がある)、背景に関しては、第10章「夏について」で、夏以外の季節で撮られたならば「東京物語」は全く違った作品になっていただろうという見方にも共感しました。
登場人物・俳優に関しては、第5章「生活人」のところで、杉村春子の演技を「無邪気なまでの呼吸するようなエゴイズム」「はたして杉村春子という女優を欠いて、この人物造形が成功していただろうか」としているのに共感し(小津安二郎が杉村春子の演技を非常に高く評価していたという話をどこかで読んだ記憶がある)、背景に関しては、第10章「夏について」で、夏以外の季節で撮られたならば「東京物語」は全く違った作品になっていただろうという見方にも共感しました。 第12章「軽さについての」での、小料理屋における周吉(笠智衆)、沼田(東野英治郎)、服部(十朱久雄)の会話シーンのセリフを引用した分析も秀逸でした(セリフが全て、オリジナルの文語の脚本から引用されているが、この文語の"語感"が何故か作品の雰囲気に非常にマッチしているように思われたのは、個人的には新たな発見だった)。
第12章「軽さについての」での、小料理屋における周吉(笠智衆)、沼田(東野英治郎)、服部(十朱久雄)の会話シーンのセリフを引用した分析も秀逸でした(セリフが全て、オリジナルの文語の脚本から引用されているが、この文語の"語感"が何故か作品の雰囲気に非常にマッチしているように思われたのは、個人的には新たな発見だった)。
 藤高順●時間:136分●出演:笠智衆/東山千榮子/原節子/香川京子/三宅邦子/杉村春子/中村伸郎/山村聰/大坂志郎/十朱久雄/東野英治郎/長岡輝子/高橋豊子/桜むつ子/村瀬禪/安部徹/三谷幸子/毛利充宏/阿南純子/水木涼子/戸川美子/糸川和広●公開:1953/11●配給:松竹●最初に観た場所:三鷹オスカー(82-09-12)(評価:★★★★☆)●併映:「彼岸花」(小津安二郎)/「秋刀魚の味」(小津安二郎) 杉村春子、中村伸郎 / 笠智衆、東野英治郎
藤高順●時間:136分●出演:笠智衆/東山千榮子/原節子/香川京子/三宅邦子/杉村春子/中村伸郎/山村聰/大坂志郎/十朱久雄/東野英治郎/長岡輝子/高橋豊子/桜むつ子/村瀬禪/安部徹/三谷幸子/毛利充宏/阿南純子/水木涼子/戸川美子/糸川和広●公開:1953/11●配給:松竹●最初に観た場所:三鷹オスカー(82-09-12)(評価:★★★★☆)●併映:「彼岸花」(小津安二郎)/「秋刀魚の味」(小津安二郎) 杉村春子、中村伸郎 / 笠智衆、東野英治郎
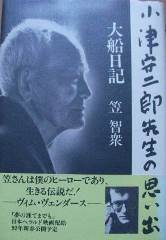
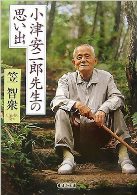
 本書はその笠智衆が小津安二郎の思い出を"書き下ろし"ならぬ"語り下ろしたもので、笠智衆が亡くなる2年前に刊行され、'07年に文庫化されています。笠智衆自身によるあとがきがありますが、本が出来上がるまで1年近くかかったとありますから、編集者は粘り強く、笠智衆の後半生の住み家のあった大船に通ったことになります。
本書はその笠智衆が小津安二郎の思い出を"書き下ろし"ならぬ"語り下ろしたもので、笠智衆が亡くなる2年前に刊行され、'07年に文庫化されています。笠智衆自身によるあとがきがありますが、本が出来上がるまで1年近くかかったとありますから、編集者は粘り強く、笠智衆の後半生の住み家のあった大船に通ったことになります。 小津映画の撮影に纏わる話も興味深く、「
小津映画の撮影に纏わる話も興味深く、「 「
「 初めて主役を演じたのは「
初めて主役を演じたのは「 小津安二郎の演出に対して「先生、それは出来ません」と答えた唯一のケースが、「
小津安二郎の演出に対して「先生、それは出来ません」と答えた唯一のケースが、「 また、その「晩春」では、小料理屋でビールを飲むシーンで、本物のビールを飲んでしまい顔が真っ赤になって撮影が中断したというのも面白いです。それ以降、ビールを飲むシーンでは、笠智衆だけ麦茶を飲んでいるそうです(日本酒を飲むシーンは水を飲んでいたのか。本書によれば、中村伸郎が酒が好きで、そのため小津は本物の酒を用意したそうな。東野英治郎については、演技が上手いとは書いてあるが、本当に酔っぱらっていたとは書いてない。「秋刀魚の味」('62年)の笠智衆、中村伸郎、東野英治郎が一緒に酒を飲むシーンを観直してみたくなった)。
また、その「晩春」では、小料理屋でビールを飲むシーンで、本物のビールを飲んでしまい顔が真っ赤になって撮影が中断したというのも面白いです。それ以降、ビールを飲むシーンでは、笠智衆だけ麦茶を飲んでいるそうです(日本酒を飲むシーンは水を飲んでいたのか。本書によれば、中村伸郎が酒が好きで、そのため小津は本物の酒を用意したそうな。東野英治郎については、演技が上手いとは書いてあるが、本当に酔っぱらっていたとは書いてない。「秋刀魚の味」('62年)の笠智衆、中村伸郎、東野英治郎が一緒に酒を飲むシーンを観直してみたくなった)。 「東京画」●制作年:1985年●製作国:アメリカ・西ドイツ●監督・脚本:ヴィム・ヴェンダース●製作:クリス・ジーヴァニッヒ●撮影:エド・ラッハマン●音楽:ローリー・ペッチガンド●時間:93分●出演:ヴィム・ヴェンダース(ナレーション)/笠智衆/ヴェルナー・ヘルツォーク/厚田雄春●公開:1989/06●配給:フランス映画社(評価:★★★☆)
「東京画」●制作年:1985年●製作国:アメリカ・西ドイツ●監督・脚本:ヴィム・ヴェンダース●製作:クリス・ジーヴァニッヒ●撮影:エド・ラッハマン●音楽:ローリー・ペッチガンド●時間:93分●出演:ヴィム・ヴェンダース(ナレーション)/笠智衆/ヴェルナー・ヘルツォーク/厚田雄春●公開:1989/06●配給:フランス映画社(評価:★★★☆)

 エピソード的な話では、「黒澤明」について書いた最終章が面白かったです。戦時中、監督第一作を撮った新人監督は内務省の試験を受ける必要があって、検閲官に映画監督が立ち会って口頭諮問のようなものが行われたようですが、黒澤明の「姿三四郎」の時の立会映画監督3人の内の一人が小津安二郎で(黒澤明の師匠・山本嘉次郎もその1人だったが敢えて立ち会わなかった)、検閲官が棘のある言葉で諮問し、黒澤明のイライラが最高潮に達する中、小津安二郎が、「百点満点として"姿三四郎"は、百二十点だ!黒澤君、おめでとう!」と言ってOKになったとのことです(黒澤明が「
エピソード的な話では、「黒澤明」について書いた最終章が面白かったです。戦時中、監督第一作を撮った新人監督は内務省の試験を受ける必要があって、検閲官に映画監督が立ち会って口頭諮問のようなものが行われたようですが、黒澤明の「姿三四郎」の時の立会映画監督3人の内の一人が小津安二郎で(黒澤明の師匠・山本嘉次郎もその1人だったが敢えて立ち会わなかった)、検閲官が棘のある言葉で諮問し、黒澤明のイライラが最高潮に達する中、小津安二郎が、「百点満点として"姿三四郎"は、百二十点だ!黒澤君、おめでとう!」と言ってOKになったとのことです(黒澤明が「 「映画術」的観点からすると、一番興味深かったのは「清水宏」の章でしょうか。著者によれば、監督一人につき同じ分量の紙数を割く予定が、この章だけ長くなってしまったとのこと。清水宏という監督は時に小津安二郎と似たようなテーマを扱ったり同じような俳優を使ったりしていたりもしますが、著者は清水宏こそが小津安二郎のライバルだったとしています(と言っても2人は盟友関係にもあり、小津安二郎が最後に入院した際には、清水宏は病院近くのホテルに滞在しながら、辛くて見舞いに行けなかったようだ)。
「映画術」的観点からすると、一番興味深かったのは「清水宏」の章でしょうか。著者によれば、監督一人につき同じ分量の紙数を割く予定が、この章だけ長くなってしまったとのこと。清水宏という監督は時に小津安二郎と似たようなテーマを扱ったり同じような俳優を使ったりしていたりもしますが、著者は清水宏こそが小津安二郎のライバルだったとしています(と言っても2人は盟友関係にもあり、小津安二郎が最後に入院した際には、清水宏は病院近くのホテルに滞在しながら、辛くて見舞いに行けなかったようだ)。
