「●哲学一般・哲学者」の インデックッスへ Prev|NEXT ⇒ 【1289】 N・マルコム 『ウィトゲンシュタイン』
「●岩波新書」の インデックッスへ
マルクスの愛の生涯、その情熱と幸福、悲惨と絶望を手紙や回想録から浮彫りに。




マルクス&ジェニー/マルクスの墓(ロンドン/ハイゲイト墓地) 『マルクス・エンゲルス小伝 (岩波新書 青版 543)』/フリードリヒ・エンゲルス
『人間マルクス その愛の生涯 (岩波新書)』
本書は、カール・マルクス(1818-1883/享年64)の生涯をフランスのジャーナリストが追ったものです。サブタイトルに「その愛の生涯」とあり、また、本書の原題も"La vie amoureuse de Karl Marx" であるように、カール・マルクスの愛情生活を徹底的に追ったものとなっており、マルクスが4歳年上の妻ジェニー(イェニー)をいかに愛し続けたか、その情熱と幸福、悲惨と絶望を、夫人や娘たちとの手紙や友人・知己の多くの回想録等をもとに炙り出しています。また、そうすることによって、マルクスの人間性そのものを浮き彫りにし、それが彼の膨大な仕事にどのように反映されたか推し量る貴重な資料にもなっています。
であるように、カール・マルクスの愛情生活を徹底的に追ったものとなっており、マルクスが4歳年上の妻ジェニー(イェニー)をいかに愛し続けたか、その情熱と幸福、悲惨と絶望を、夫人や娘たちとの手紙や友人・知己の多くの回想録等をもとに炙り出しています。また、そうすることによって、マルクスの人間性そのものを浮き彫りにし、それが彼の膨大な仕事にどのように反映されたか推し量る貴重な資料にもなっています。
ジェニー(イェニー)・マルクス
マルクスは、ベルリン大学卒業後、ケルンの「ライン新聞」の編集長になって政治・経済問題の論文に健筆を奮いますが、急進的な論調のためプロイセン政府の検閲に遭って新聞は発禁処分になり、それが原因で1849年にパリに追放され、ブリュッセルでの生活を経てロンドンに居住し、後半生をその地で過ごすことになります。このことは、生涯のかなりの部分を亡命者として過ごしたことなるとともに、本書を読むと、常に貧困と隣り合わせだったことが窺えます。ロンドンでの彼の運動と著作は、その後の世界の社会主義運動に大きな影響を与えることになりますが、生きていた間は、その名前すら一般の人には殆ど知られていなかったようです。
 ジェシーとの間に生まれた2男4女のうち、成人を迎えることができたのは長女ジェニー(妻と同じ名)・次女ラウラ・四女エリナの3人だけで、あとは病気などで亡くなっており、家計が苦しく医者に診せる費用さえ十分に捻出し得なかったことも子ども達の早逝の一因として考えられるというのはかなり悲惨です(このほか更に、出生死の子が1人いた)。また、そうした苦境を乗り越えてきたからこそ、それだけ二人の愛は強まったとも言えるかと思います。
ジェシーとの間に生まれた2男4女のうち、成人を迎えることができたのは長女ジェニー(妻と同じ名)・次女ラウラ・四女エリナの3人だけで、あとは病気などで亡くなっており、家計が苦しく医者に診せる費用さえ十分に捻出し得なかったことも子ども達の早逝の一因として考えられるというのはかなり悲惨です(このほか更に、出生死の子が1人いた)。また、そうした苦境を乗り越えてきたからこそ、それだけ二人の愛は強まったとも言えるかと思います。
マルクスと妻ジェニー、次女ラウラ、四女エリナ、エンゲルス。
一方で、マルクス家に献身的に仕え、マルクス夫婦と同じ墓地に埋葬されているマルクス家の女中ヘレーネ・デムート(マルクスの家のやり繰りが苦しい時は無償で働いた)が生んだ私生児フレディの父親が、実はマルクスであったということも、本書には既にはっきり記されています(本書の原著刊行は1970年。1989年に発見されたヘレーネ・デムートの友人のエンゲルス家の女中の手紙から、ヘレーネの息子の父親がマルクスであることが確実視されるようになった)。
 マルクスの妻ジェニー(イェニー)は夫の不義に悩みながらもそれを許したようですが、封印されたこの一家の秘密は、その後家族に多くの抑圧を残します(この辺りは、フランソワーズ・ジルー著『イェニー・マルクス―「悪魔」を愛した女』('95年/新評論)に詳しい)。そして妻ジェニーは1881年の年末に亡くなり、悲しみに暮れるマルクスに、更にその1年後に長女ジェニーが亡くなるという悲劇が襲い、その2か月後にはマルクスも息を引き取ります。月並みな解釈ですが、やはり、マルクスにとって、妻と娘たちが生きるエネルギーの源泉だったということでしょうか(因みに、マルクス逝去の時点で存命していた2人の娘のうち、マルクスと「告白」遊びをしたりした次女ラウラは1911年に夫と共に自殺、四女エリナは1898年に恋人と無理心中して自分だけ亡くなっているが、これについては偽装殺人の疑いがもたれている)。
マルクスの妻ジェニー(イェニー)は夫の不義に悩みながらもそれを許したようですが、封印されたこの一家の秘密は、その後家族に多くの抑圧を残します(この辺りは、フランソワーズ・ジルー著『イェニー・マルクス―「悪魔」を愛した女』('95年/新評論)に詳しい)。そして妻ジェニーは1881年の年末に亡くなり、悲しみに暮れるマルクスに、更にその1年後に長女ジェニーが亡くなるという悲劇が襲い、その2か月後にはマルクスも息を引き取ります。月並みな解釈ですが、やはり、マルクスにとって、妻と娘たちが生きるエネルギーの源泉だったということでしょうか(因みに、マルクス逝去の時点で存命していた2人の娘のうち、マルクスと「告白」遊びをしたりした次女ラウラは1911年に夫と共に自殺、四女エリナは1898年に恋人と無理心中して自分だけ亡くなっているが、これについては偽装殺人の疑いがもたれている)。
『イェニー・マルクス―「悪魔」を愛した女』
本書によれば、マルクスは、ロンドン時代も夜となく昼となく読み、且つ書いて、膨大な著作を生み出したものの、それらは殆ど金にならず彼は絶望したとのこと、現実にそれは何年も家庭に「貧困」が腰を据えるという形で妻や子度たちの苦しめたため、彼はイギリスの鉄道会社に書記として就職しようとしたとのこと、但し、非常な悪筆のため採用を断られたとのことです(何度も彼の原稿の清書をした妻ジェニーは、マルクスの字をハエの足跡のようと言っている)。これは1862年頃の話ということで、『資本論』の第1巻が世に出るのはその5年後ですから、もし生活のために鉄道会社に勤めていたら(もしマルクスが達筆だったなら)『資本論』の方はどうなっていたでしょうか。
 この他に、マルクスの生涯をその「仕事」よりに辿ったものに、大内兵衛(1888-1980)による『マルクス・エンゲルス小伝』('64年/岩波新書)があり、『ドイツ・イデオロギー』『哲学の貧困』『共産党宣言』『経済学批判』そして『資本論』といった著作がどのような経緯で成立したのかが、マルクスの思想形成の流れやその折々の時代背景と併せて解説されています。多少エッセイ風と言うか、著者は、「これは勉強して書いた本ではない。一老人の茶話である」とはしがきで述べていますが、「茶話」としてこれだけ書いてしまうのはやはり大家の成せる技でしょうか。
この他に、マルクスの生涯をその「仕事」よりに辿ったものに、大内兵衛(1888-1980)による『マルクス・エンゲルス小伝』('64年/岩波新書)があり、『ドイツ・イデオロギー』『哲学の貧困』『共産党宣言』『経済学批判』そして『資本論』といった著作がどのような経緯で成立したのかが、マルクスの思想形成の流れやその折々の時代背景と併せて解説されています。多少エッセイ風と言うか、著者は、「これは勉強して書いた本ではない。一老人の茶話である」とはしがきで述べていますが、「茶話」としてこれだけ書いてしまうのはやはり大家の成せる技でしょうか。
前半3分の2がマルクス伝であるのに対し、後半3分の1はフリードリヒ・エンゲルス(1820-1895/享年74)の小伝となっています。個人的に印象に残ったのはマルクスの死後まもなくエンゲルスが旧友に送った手紙で、その中でエンゲルスは、「僕は一生の間いつも第二ヴァイオリンばかり弾いていた。これならば相手上手といったところまでやれたように思う。が、何といっても、マルクス という第一ヴァイオリンが上手であったのですっかり有頂天になっていた。これからはこの学説を代表して僕が第一ヴァイオリンを弾かねばならぬのだ。よほど用心をしないと世間の物笑いになるかもしれない」と書いており、並々ならぬ決意と覚悟が窺えます。『共産党宣言』はマルクスとエンゲルスの共作であるし、エンゲルスはマルクスの『資本論』執筆に際しても多くの示唆を与え続けていたとのこと、そのマルクスが亡くなった時点で『資本論』は第1巻しか刊行されておらず、『資本論』の第2巻と第3巻は、マルクスとエンゲルスの共著とも言え、『資本論』が完結を見たのはエンゲルスの功績が大きいようです。
という第一ヴァイオリンが上手であったのですっかり有頂天になっていた。これからはこの学説を代表して僕が第一ヴァイオリンを弾かねばならぬのだ。よほど用心をしないと世間の物笑いになるかもしれない」と書いており、並々ならぬ決意と覚悟が窺えます。『共産党宣言』はマルクスとエンゲルスの共作であるし、エンゲルスはマルクスの『資本論』執筆に際しても多くの示唆を与え続けていたとのこと、そのマルクスが亡くなった時点で『資本論』は第1巻しか刊行されておらず、『資本論』の第2巻と第3巻は、マルクスとエンゲルスの共著とも言え、『資本論』が完結を見たのはエンゲルスの功績が大きいようです。
フリードリヒ・エンゲルス(1820-1895/享年74)
 エンゲルスは実業家でもあり、マルクスのロンドン時代に彼はマンチェスターでエルメン・エンエルス商会の番頭として「金儲け」をし(本人の本当の関心は勉学にあったようだが)、その産物の一部をマルクスに捧げることでマルクスとその家族の生活を支える一方、自らも仕事の傍ら勉強に力を入れたとのこと、また、堂々とした体躯と奥深い知識と智慧で「将軍」などと呼ばれたりもしていたようですが(実際、軍事分野における造詣が深く、この分野の著作もあった)、ユーモアと社交性に富み、非常に魅力的な人物像であったようです。大内兵衛は本書で何度か、マルクス=エンゲルスの関係を「管鮑の交わり」と表現しています。
エンゲルスは実業家でもあり、マルクスのロンドン時代に彼はマンチェスターでエルメン・エンエルス商会の番頭として「金儲け」をし(本人の本当の関心は勉学にあったようだが)、その産物の一部をマルクスに捧げることでマルクスとその家族の生活を支える一方、自らも仕事の傍ら勉強に力を入れたとのこと、また、堂々とした体躯と奥深い知識と智慧で「将軍」などと呼ばれたりもしていたようですが(実際、軍事分野における造詣が深く、この分野の著作もあった)、ユーモアと社交性に富み、非常に魅力的な人物像であったようです。大内兵衛は本書で何度か、マルクス=エンゲルスの関係を「管鮑の交わり」と表現しています。
東ドイツ時代に建てられたマルクスとエンゲルスの銅像(ドイツ・ベルリン)
《読書MEMO》
●「告白」(ラウラからマルクスへの問いとマルクスの回答)(『人間マルクス』より)
最も高く評価する特質 ...... 一般には素朴、男性では力、女性では弱さ
性格の特徴 ...... 一貫した目的を追うこと
幸福とは ...... 闘うこと
不幸とは ...... 服従すること
最も赦しがちな欠点 ...... 軽信
最も嫌悪する欠点 ...... 奴隷根性
毛嫌いするもの ...... マーティン・タッパー ( 当時のイギリスの詩人 )
好きな仕事 ...... 古本屋あさり (あるいは本食い虫になること )
好きな詩人 ...... シェイクスピア、アイスキュロス、ゲーテ
好きな散文作家 ...... ディドロ
好きな英雄 ...... スパルタクス、ケプラー
好きなヒロイン ...... グレートヒェン ( ゲーテ『ファウスト』のヒロイン )
好きな花 ...... 月桂樹(laurel ... Laura=ラウラ)
好きな色 ...... 赤
好きな名 ...... ラウラ=ジェニー
好きな料理(Dish) ...... 魚(Fish)
好きな格言 ...... 人間に関することは何一つ私に無縁ではない(テレンティウス(ローマの劇作家))
好きな標語 ...... すべてを疑え


.jpg) 冷徹な分析的知能と炎のような情熱を併せ持ち、20世紀最大の哲学的天才と言われるルートヴィヒ・ウィトゲンシュタイン(Ludwig Wittgenstein、1889‐1951)の評伝で、著者は、かつて彼の学生であり、後に公私にわたって彼と長く親交のあった米国の哲学者であり、評伝と言うより、サブタイトルにある「思い出」と言った方が確かにぴったりくる内容。
冷徹な分析的知能と炎のような情熱を併せ持ち、20世紀最大の哲学的天才と言われるルートヴィヒ・ウィトゲンシュタイン(Ludwig Wittgenstein、1889‐1951)の評伝で、著者は、かつて彼の学生であり、後に公私にわたって彼と長く親交のあった米国の哲学者であり、評伝と言うより、サブタイトルにある「思い出」と言った方が確かにぴったりくる内容。
 訳者は、ハーバード大学で日本文学・日本語を教えていた板坂元で、同著者(N・マルコム)による『回想のヴィトゲンシュタイン』('74年/教養選書)という似たタイトルの本(哲学者の藤本隆志の訳)がありますが、同じ元本を同時期に別々の訳者が訳した偶然の結果であるとのこと、哲学者ではない板坂元が本書を訳したのは、本書にも見られる、異国の地で苦悶しながらも真摯に学生と向き合う教育者としてのウィトゲンシュタインの姿への共感からではないかと思われます。
訳者は、ハーバード大学で日本文学・日本語を教えていた板坂元で、同著者(N・マルコム)による『回想のヴィトゲンシュタイン』('74年/教養選書)という似たタイトルの本(哲学者の藤本隆志の訳)がありますが、同じ元本を同時期に別々の訳者が訳した偶然の結果であるとのこと、哲学者ではない板坂元が本書を訳したのは、本書にも見られる、異国の地で苦悶しながらも真摯に学生と向き合う教育者としてのウィトゲンシュタインの姿への共感からではないかと思われます。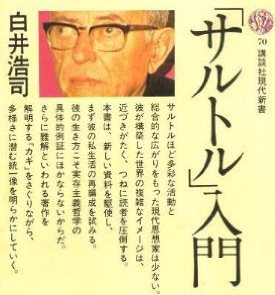


 文学者の眼から見たサルトル像、サルトルの小説や戯曲への手引書であると言え(とりわけ『嘔吐』の主人公ロカンタンが感じた〈吐き気〉などについては、詳しく解説されている。片や『存在と無』などの解説が物足りなさを感じるのは、著者がやはり文学者だからか)、その一方で、彼の生い立ちや人となり(これがなかなか興味深い)、ボーヴォワールをはじめ多くの同時代人との交友やカミュなどとの論争についても書かれています。
文学者の眼から見たサルトル像、サルトルの小説や戯曲への手引書であると言え(とりわけ『嘔吐』の主人公ロカンタンが感じた〈吐き気〉などについては、詳しく解説されている。片や『存在と無』などの解説が物足りなさを感じるのは、著者がやはり文学者だからか)、その一方で、彼の生い立ちや人となり(これがなかなか興味深い)、ボーヴォワールをはじめ多くの同時代人との交友やカミュなどとの論争についても書かれています。下.jpg)
上.jpg)
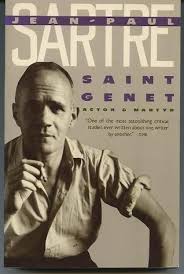


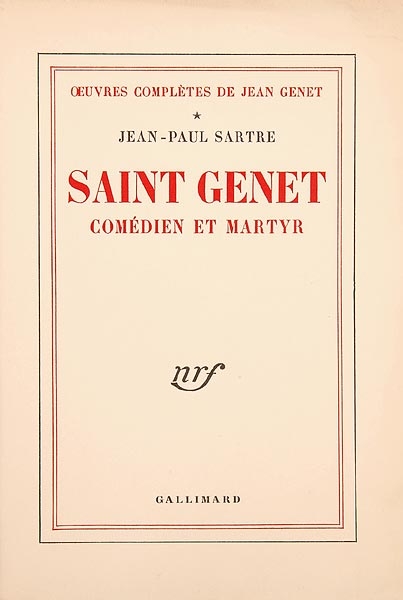

 1952年の原著発表。フランスの実存主義哲学者ジャン=ポール・サルトル(1905‐1980)は、「嘔吐」「水入らず」など一連の小説でノーベル文学賞を受賞していますが(結果的には辞退)、本書は小説ではなく、泥棒から作家になったジャン・ジュネに関する哲学的な文学評伝です。
1952年の原著発表。フランスの実存主義哲学者ジャン=ポール・サルトル(1905‐1980)は、「嘔吐」「水入らず」など一連の小説でノーベル文学賞を受賞していますが(結果的には辞退)、本書は小説ではなく、泥棒から作家になったジャン・ジュネに関する哲学的な文学評伝です。
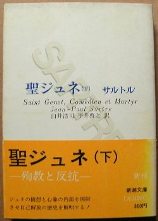 サルトルの言う「対自存在」とは、人間(意識)の在り方を指し、「それがあるところのものではない」存在として、即自存在(物)と対比されます。対自は、即自存在(事物)と一体化できず、常に自己を対象化し「無」(否定)を内包することで、「自己自身にとってある」という自由な状態であり、過去の自己から脱出し未来へ投企する(=自分を投げかける)ことで自己を形成する、「自由の刑に処せられた」存在です。 つまり、「実存」(対自存在)は、理由もなく偶然にある状況に投げ込まれて存在する無根拠な存在者であり(それはまさに我々のことを指している)、それはまた、"投企"によって自己を創出できる自由な存在者でもあって、人間はモノ(即自存在)ではないということですが、ジュネを蔑む〈まっとうな人々〉こそ、既成価値観に囚われた〈仮象〉に生き、それらを剥ぎ取ればモノ(即自存在)に過ぎないのではないかというパラドックスがここに成り立ちます。
サルトルの言う「対自存在」とは、人間(意識)の在り方を指し、「それがあるところのものではない」存在として、即自存在(物)と対比されます。対自は、即自存在(事物)と一体化できず、常に自己を対象化し「無」(否定)を内包することで、「自己自身にとってある」という自由な状態であり、過去の自己から脱出し未来へ投企する(=自分を投げかける)ことで自己を形成する、「自由の刑に処せられた」存在です。 つまり、「実存」(対自存在)は、理由もなく偶然にある状況に投げ込まれて存在する無根拠な存在者であり(それはまさに我々のことを指している)、それはまた、"投企"によって自己を創出できる自由な存在者でもあって、人間はモノ(即自存在)ではないということですが、ジュネを蔑む〈まっとうな人々〉こそ、既成価値観に囚われた〈仮象〉に生き、それらを剥ぎ取ればモノ(即自存在)に過ぎないのではないかというパラドックスがここに成り立ちます。

 (●2007年11月、ちくま学芸文庫で、サルトルの現象学的総決算とも言える主著『存在と無』(松浪信三郎:訳)が文庫化された。文庫化されたこと自体少しびっくりしたが(サルトル復活?)、20世紀を代表する哲学書が文庫で入手できるのはいいことだ。この『存在と無』を読むには相当の忍耐が必要だが、読み込めば読み込んだだけものが得られる。例えば、他者とは「眼差し」であるとサルトルは言う。つまり、他者とは「私は今、他者に見られている」という私の意識でしかない。言い換えれば、他者は私自身の意識の中にしか存在しない。私が他者の前で自由を失うのは、不本意にも、自分自身が生み出したものにすぎない「見られている姿としての自分」と自分自身を同一視させ、その結果、私の意識の自由(=「対自存在」)を凝固させてしまっているからであるという。青年期にこれを読んで、腑に落ちた思いをしたのが懐かしい)。
(●2007年11月、ちくま学芸文庫で、サルトルの現象学的総決算とも言える主著『存在と無』(松浪信三郎:訳)が文庫化された。文庫化されたこと自体少しびっくりしたが(サルトル復活?)、20世紀を代表する哲学書が文庫で入手できるのはいいことだ。この『存在と無』を読むには相当の忍耐が必要だが、読み込めば読み込んだだけものが得られる。例えば、他者とは「眼差し」であるとサルトルは言う。つまり、他者とは「私は今、他者に見られている」という私の意識でしかない。言い換えれば、他者は私自身の意識の中にしか存在しない。私が他者の前で自由を失うのは、不本意にも、自分自身が生み出したものにすぎない「見られている姿としての自分」と自分自身を同一視させ、その結果、私の意識の自由(=「対自存在」)を凝固させてしまっているからであるという。青年期にこれを読んで、腑に落ちた思いをしたのが懐かしい)。
.jpg)

 原著は'59年の出版。著者はドイツで経済学、社会学、哲学を学んだ後、ナチスに追われ米国に亡命した人で、本書で展開される著者の「疎外論」は、アメリカ社会心理学の系譜にあるかと思われますが、哲学的かつ広い視野での社会分析がされています。
原著は'59年の出版。著者はドイツで経済学、社会学、哲学を学んだ後、ナチスに追われ米国に亡命した人で、本書で展開される著者の「疎外論」は、アメリカ社会心理学の系譜にあるかと思われますが、哲学的かつ広い視野での社会分析がされています。