「●あ アナトール・フランス」の インデックッスへ Prev|NEXT ⇒ 【3657】 アナトール・フランス 『神々は渇く』
「○海外文学・随筆など 【発表・刊行順】」の インデックッスへ ○ノーベル文学賞受賞者(アナトール・フランス)
心温まる作品。「情けは人の為ならず」ということか。
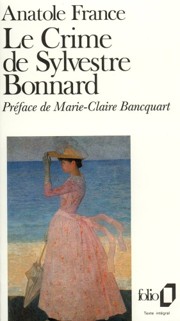

 アナトール・フランス
アナトール・フランス
『シルヴェストル・ボナールの罪 (岩波文庫 赤 543-4) 』['75年]
『Le Crime De Sylvestre Bonnard (Folio classique)』['91年]
第一部「薪」
主人公シルヴェストル・ボナールはパリ在住の文献学者であり、セーヌ河畔の家で、婆やと一匹の老猫とともに暮らしている。ボナールはある貴重な写本の行方を追ってシチリア島まで旅する。しかし、写本はすでに売り払われた後だった。彼は、パリのオークション会場で目当ての写本を競り落とそうと奮闘するが、競り値は高騰し、写本は落札できなかった。ところが彼は、かつて恩を施したことのある貧しかった女性から思わぬ贈り物を受けることになる―。
 第二部「ジャンヌ・アレクサンドル」
第二部「ジャンヌ・アレクサンドル」
ボナールは、若いころの悲恋の相手だった女性の孫娘ジャンヌが孤児となって不幸な生活を送っていることを知り、その待遇改善を働きかけるが、ついには彼女を引き取ってその後見人となる。その後、ボナールの教えを受けていた学生とジャンヌが惹かれ合い、二人は結婚することになる。ジャンヌの持参金作りのため、ボナールは蔵書を売り払うことに決めるが、愛着があってどうしても手放し難い書物を夜中に抜き取って自分の元に留めてしまう(これが表題の「罪」を意味している)―。
フェルナン・シメオン(フランス語版)の挿絵による第二部の一場面
1921年にノーベル文学賞を受賞したアナトール・フランス(1844-1924)が1881年、37歳のときに発表した作品(原題:Le Crime de Sylvestre Bonnard)であり、その年齢にして54歳から70歳までの主人公を描いていることになりますが、この作品はアカデミー・フランセーズから文学賞を授賞され、彼は作家として一般的な名声を得ることになったとされています。
第一部は80ページ、第二部は180ページで、分量的に不均衡がある構成ですが、仏文学者の辰野隆(1888-1964)は、「この小説には構成が欠けている。組み立てに無頓着で、ただ二つの長い挿話があまり緊密でなく繋がれているに過ぎない」と指摘し、構成の組織を欠くことと、未来に向かって新しい扉を拓く趣のきわめて少ないことは、この作品に限らずアナトール・フランスのすべての小説を貫く欠点だと指摘しています。
確かに、第二部で、ボナールが愛着があって売れなかった本がまさに第一部の写本であり、そこでしか第一部と第二部が繋がっていません。でも、何となく心温まる作品です(彼の「罪」は、彼だけが「罪」と感じているものであって、むしろ彼の真面目な人柄を感じさせる)。この「心温まる」という要素も、昔からある物語のパターンであり、その辺りも批判の対象になっているのでしょう。それでも、翻訳者である大塚幸男(1909-199)などはやはり、「愛書家アナトール・フランスの面目躍如たる、心あたたまる小説である」と述べています。
ストーリー的には第一部の方が面白かったでしょうか。同じ建物の屋根裏部屋に住んでいた、貧しく若い子連れの女がねえ。再会した時、ボナール先生は最後まで分からなかったみたいだなあ。相手は気づいていたけれど。「薪」の差し入れがこんな形で返ってくるとは。「情けは人の為ならず」って誤用されがちな言い回しですが、もともとはこんな話のことを言うのだろなあ。
文庫解説によれば、アナトール・フランスは70歳のときにロワール河畔のラ・ベシェルリーに別荘を購入したが、その2年後、かつての恋人でいまは亡きカイヤヴェ夫人の孫娘がこの別荘に滞在することになり、これは、35年前に書かれた『シルヴェストル・ボナールの罪』において、ボナールの昔の恋人の孫娘ジャンヌがセーヌ河畔のボナールの家を訪れる場面に偶然にも重なるとのこと。なかなか興味深いエピソードです。

 因みに、1929年にフランスでアンドレ・ベルトミュー監督により無声映画化されていますが、現在ではあまり知られていません。また、カナダの映画監督のグザヴィエ・ドランが、この小説の一節を引用して映画製作への情熱を語るなど、文学作品として、また引用元として言及されることはあるようです。
因みに、1929年にフランスでアンドレ・ベルトミュー監督により無声映画化されていますが、現在ではあまり知られていません。また、カナダの映画監督のグザヴィエ・ドランが、この小説の一節を引用して映画製作への情熱を語るなど、文学作品として、また引用元として言及されることはあるようです。
映画ポスター
【1922年単行本[冬夏社『シルヴエストル・ボナール博士の罪』]/1947年全集本[白水社(『アナトオル・フランス長篇小説全集〈第1巻〉シルヴェストル・ボナールの罪』)]/1975年文庫化[岩波文庫]】
