「●あ アナトール・フランス」の インデックッスへ Prev|NEXT ⇒「●あ 安部 公房」 【1002】 安部 公房 「壁」
「○海外文学・随筆など 【発表・刊行順】」の インデックッスへ ○ノーベル文学賞受賞者(アナトール・フランス)
「賢く考えていながら愚かに行動するのが、人間の性」。やるせない話だった。


 アナトール・フランス(1921)
アナトール・フランス(1921)
『神々は渇く (岩波文庫 赤 543-3)』['77年]
『Les Dieux ont soi』['93年]
 貧しくも正義感あふれる愛国的な青年画家エヴァリスト・ガムランは、あるきっかけで革命裁判所の陪審員になって権力を持ち、ジャコバン派の影響を受けたことで、「残虐非道な化物」と化して、元貴族、亡命を試みた者、無神論者、娼婦等を悉く死刑にするようになる。元貴族で今は屋根裏部屋で暮らす老人ブロトは、ルクレティウスを信奉する無神論者で、聡明な彼は、人命を脅かす革命裁判所を長く続かないとし、「革命裁判所には低劣な正義感と平板な平等意識とが支配しています。これがやがて革命裁判所を憎むべきもの嗤うべきものにし、万人に嫌悪を催させることになるでしょう」と予言する。そして、その思想ゆえに逮捕される―。
貧しくも正義感あふれる愛国的な青年画家エヴァリスト・ガムランは、あるきっかけで革命裁判所の陪審員になって権力を持ち、ジャコバン派の影響を受けたことで、「残虐非道な化物」と化して、元貴族、亡命を試みた者、無神論者、娼婦等を悉く死刑にするようになる。元貴族で今は屋根裏部屋で暮らす老人ブロトは、ルクレティウスを信奉する無神論者で、聡明な彼は、人命を脅かす革命裁判所を長く続かないとし、「革命裁判所には低劣な正義感と平板な平等意識とが支配しています。これがやがて革命裁判所を憎むべきもの嗤うべきものにし、万人に嫌悪を催させることになるでしょう」と予言する。そして、その思想ゆえに逮捕される―。
『Les Dieux ont soif』['18年]ペーパーバック
アナトール・フランスの、フランス革命期の恐怖政治とそれに巻き込まれる人々を描いた歴史小説で、1911年11月から1912年1月にかけて「パリ評論」誌に掲載され、1912年6月に単行本として刊行されました(原題:Les Dieux ont Soif)。多くの資料に基づいて組まれたそのプロットは老練で、緻密な風俗描写は、読む者を18世紀末の騒乱の体験者にしてしまうようなリアリティがあります。
 主人公のエヴァリストは、恋人エロディが過去に付き合っていた男に嫉妬しており、それらしき貴族が逮捕されると、こいつに違いないと思い込み、エロディが否定するにもかかわらず、人違いで死刑を宣告してしまいます。また、革命裁判所の判事ルノダンに至っては、逮捕された貴族シャサーニュの愛人であるジュリ(エヴァリストの妹)からシャサーニュを救ってほしいと頼まれると、肉体交渉を迫り、その後で約束を破ります(藤沢周平原作、山田洋次監督の「隠し剣 鬼の爪」('04年/松竹)に出てくる悪徳家老みたい)。
主人公のエヴァリストは、恋人エロディが過去に付き合っていた男に嫉妬しており、それらしき貴族が逮捕されると、こいつに違いないと思い込み、エロディが否定するにもかかわらず、人違いで死刑を宣告してしまいます。また、革命裁判所の判事ルノダンに至っては、逮捕された貴族シャサーニュの愛人であるジュリ(エヴァリストの妹)からシャサーニュを救ってほしいと頼まれると、肉体交渉を迫り、その後で約束を破ります(藤沢周平原作、山田洋次監督の「隠し剣 鬼の爪」('04年/松竹)に出てくる悪徳家老みたい)。
そして、ブロトが予言したように、民衆から「もうたくさんだ!」という声が上がり始め、所謂「テルミドールのクーデター」によってロベスピエールが失脚すると、エヴァリストたちはかつて貴族たちを罵っていた民衆に罵倒されながら革命広場の処刑場へと送られますが、彼は自分がしたことを悔やみはせず、もっと多くの人間を死刑にできなかった己の寛容さを悔みつつ断頭台の露と消えていく―という、もともと繊細な精神の画家で、母親思いの優しい男だったのが、どういう運命のいやずらでこうなったしまうのかという、スゴイと言うかやるせない話でした(ブロト老人のような人物の存在が唯一の救いか)。
 作者は、老人ブロトにシンパシーを寄せていますが、エヴァリストを突き放しているわけではなく、この美貌の怪物は、飢えた母子にパンを恵み、農夫が小麦を刈るのを見て涙し、見知らぬ少年に銀貨を与え、初めて陪審員席に座った時は、騎兵隊の馬糧でひと儲けしようとした悪党を「証拠がない」と無罪にしたりもして、寛容さも見せています。そんな彼が「残虐非道な化物」になってからは、常に悪夢にうなされ、「自分は忌まわしい者とされて死ぬだろう」と自覚しており、それでも冷酷に徹するのは、王や貴族や彼らに与する者など「祖国の敵どものけがれた血」を流す大役を引き受けようとするヒロイックな愛国心ゆえです。
作者は、老人ブロトにシンパシーを寄せていますが、エヴァリストを突き放しているわけではなく、この美貌の怪物は、飢えた母子にパンを恵み、農夫が小麦を刈るのを見て涙し、見知らぬ少年に銀貨を与え、初めて陪審員席に座った時は、騎兵隊の馬糧でひと儲けしようとした悪党を「証拠がない」と無罪にしたりもして、寛容さも見せています。そんな彼が「残虐非道な化物」になってからは、常に悪夢にうなされ、「自分は忌まわしい者とされて死ぬだろう」と自覚しており、それでも冷酷に徹するのは、王や貴族や彼らに与する者など「祖国の敵どものけがれた血」を流す大役を引き受けようとするヒロイックな愛国心ゆえです。
しかしながら、例えば、「国王万歳!」と叫んで逮捕される娼婦には愛国心が無いとしてエヴァリストが彼女たちを憎むのは、実は個人的な感情に起因していて、「官能と精神との快楽を享受し、生きることが愉しかった時代に生きていた」者を嫌悪していためで、ただし、本人にはその自覚は無く、革命の混乱時において、誰かがやらねばならぬ仕事を愛国者として全うし、公安に寄与していると思い込んでいる一方で、自身の性生活はタガが外れたようになり、狂った男の血の匂いに興奮する恋人エロディの激しい愛撫によって快楽と癒しを得ているという、快楽を否定しながら、自身が快楽に嵌る矛盾に陥っています。
エヴァリストのような人間を人でなしの化物として攻撃するのは簡単ですが、いざ狂熱の時代に投げ込まれ、同じ立場に身を置く羽目に陥った時、彼のようにならないと誰もが断言できるでしょうか。作者は「主人公ガムランは、ほとんど化物のような人物だ。しかし人間は徳の名において正義を行使するにはあまりにも不完全であること、されば人生の掟は寛容と仁慈とでなければならないことを、私は示したかったのだ」と語っています。
人間の不完全さについては、エピクロスも『わが友の書』で「賢く考えていながら愚かに行動するのが、人間の性だ」と記しており、また、アナトール・フランスによる『エピクロスの園』に記された、「快楽は恐怖が混じっていてこそ人を陶酔させる」や「人間が真に人間としてとどまるのは憐れみによってである」という言葉は、『神々は渇く』にも貫かれています。
エヴァリストは貧しい芸術家で、純粋で、弱き者に同情的で、無神論者に共感することもあったのが、ジャコバン派の集会に通い詰めるうちに、「清廉潔白の人」ロベスピエールの教えに染まり、その分身たらんとしたのですが。こういうタイプの人間はいつの時代にもいて、彼らは往々にして、新たに生まれ変わった自分をむやみに徹底させ、極端に走りたがるので、こうした人間が権力を持つとロクなことにならないということでしょう。その周囲にいて巻き添えを食らう人は堪らないし、結局は本人も破滅への道を歩むことになるのでしょう。
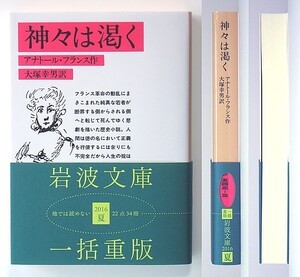 『神々は渇く』は歴史小説であるため面白く、革命裁判の様子は、臨場感満点です。史実がベースとなっているので、ストーリーの展開は周知のものですが、先にも述べた通り、その時代の目撃者になっている気持ちにさせられ、大河ドラマを観ているような印象もあり、その時代をくぐり抜けてきたような疑似体験ができます。
『神々は渇く』は歴史小説であるため面白く、革命裁判の様子は、臨場感満点です。史実がベースとなっているので、ストーリーの展開は周知のものですが、先にも述べた通り、その時代の目撃者になっている気持ちにさせられ、大河ドラマを観ているような印象もあり、その時代をくぐり抜けてきたような疑似体験ができます。
結局、「人間は本能と感情とによって導かれる」ため、いざという時、自分の行動にそれを上手く生かすには、普段から自分を見つめ、統制し、訓練しておくことが必要なのでしょう。自分自身の哲学を持っておくことも必要でしょう。それでも、いざとなったらどうなるか、保証の限りではないですが(心許ないね)。
【1932年単行本[春陽堂(『血に飢えた神々』)]/1950年全集本[白水社(『アナトオル・フランス長篇小説全集』)]/1961年文庫化[角川文庫(根津憲三:訳)]/1977年再文庫化[岩波文庫(大塚幸男:訳)]】
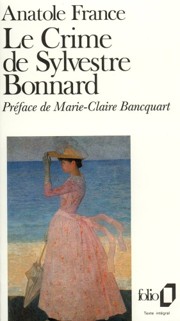

 アナトール・フランス
アナトール・フランス 第二部「ジャンヌ・アレクサンドル」
第二部「ジャンヌ・アレクサンドル」
 因みに、1929年にフランスでアンドレ・ベルトミュー監督により無声映画化されていますが、現在ではあまり知られていません。また、カナダの映画監督のグザヴィエ・ドランが、この小説の一節を引用して映画製作への情熱を語るなど、文学作品として、また引用元として言及されることはあるようです。
因みに、1929年にフランスでアンドレ・ベルトミュー監督により無声映画化されていますが、現在ではあまり知られていません。また、カナダの映画監督のグザヴィエ・ドランが、この小説の一節を引用して映画製作への情熱を語るなど、文学作品として、また引用元として言及されることはあるようです。