「●国際(海外)問題」の インデックッスへ Prev|NEXT ⇒ 【3513】 宮田 律 『ガザ紛争の正体』
「●こ 小泉 悠」の インデックッスへ 「●文春新書」の インデックッスへ
なぜ長引くのか、終わらせることはできるのかを問うた対談集。
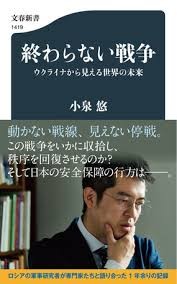


『終わらない戦争 ウクライナから見える世界の未来 (文春新書 1419) 』['23年] 小泉 悠 氏(東京大学 先端科学技術研究センター准教授) 『ウクライナ戦争はなぜ終わらないのか デジタル時代の総力戦 (文春新書 1404)』['23年]
『ウクライナ戦争の200日 (文春新書 1378) 』['22年]
 ウクライナ戦争の情勢分析で定評があり、メディアへの露出も多い小泉悠氏の本ですが、前著『ウクライナ戦争の200日』('22年9月/文春新書)同様に対談集で、3人の識者との対談が6本収められています。2022年2月24日のロシアによるウクライナへの本格的な軍事侵攻から始まった戦争から200日を過ぎ、さらに500日が過ぎるまでの期間の対談集で、当初は『ウクライナ戦争の500日』というタイトルにするつもりだったのが、500日を過ぎても停戦の気配がないため、このようなタイトルになったようです。
ウクライナ戦争の情勢分析で定評があり、メディアへの露出も多い小泉悠氏の本ですが、前著『ウクライナ戦争の200日』('22年9月/文春新書)同様に対談集で、3人の識者との対談が6本収められています。2022年2月24日のロシアによるウクライナへの本格的な軍事侵攻から始まった戦争から200日を過ぎ、さらに500日が過ぎるまでの期間の対談集で、当初は『ウクライナ戦争の500日』というタイトルにするつもりだったのが、500日を過ぎても停戦の気配がないため、このようなタイトルになったようです。
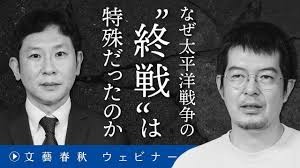 第Ⅰ章「ウクライナ戦争を終わらせることはできるのか」は、防衛研究所の千々和泰明・主任研究官との、「文藝春秋ウェビナー」での対談「なぜ太平洋戦争の"終戦"は特殊だったのか」(2022年9月9日)を活字化したもの。朝鮮戦争など二十世紀以降の主要な戦争終結をヒントに、ウクライナ戦争の「出口戦略」を考えていますが、「紛争原因の根本的解決」と「妥協的和平」という戦争終結の二つの極のどちらも困難さを孕むとし、「現在の犠牲」と「将来の危機」のどちらを取ってっも、双方はなかなか武器を置けないだろうと。また、日本の安全保障(これは小泉氏の継続的な講演テーマでもある)をどう考えるかにも言及しています。
第Ⅰ章「ウクライナ戦争を終わらせることはできるのか」は、防衛研究所の千々和泰明・主任研究官との、「文藝春秋ウェビナー」での対談「なぜ太平洋戦争の"終戦"は特殊だったのか」(2022年9月9日)を活字化したもの。朝鮮戦争など二十世紀以降の主要な戦争終結をヒントに、ウクライナ戦争の「出口戦略」を考えていますが、「紛争原因の根本的解決」と「妥協的和平」という戦争終結の二つの極のどちらも困難さを孕むとし、「現在の犠牲」と「将来の危機」のどちらを取ってっも、双方はなかなか武器を置けないだろうと。また、日本の安全保障(これは小泉氏の継続的な講演テーマでもある)をどう考えるかにも言及しています。
 第Ⅱ章「プーチンと習近平の急所はどこにあるのか?」は、中国研究が専門の法政大学の熊倉潤教授との「中央公論」(2023年3月号)での対話で、戦争の長期化はプーチン政権に打撃を与えるのか、中露の権威主義体制の比較をもとに検討したもので、小泉氏が「今回の戦争で、仮にクーデターが起きてプーチンが排除されたとしても、それはあまり解決にならないと思っているんです。先に触れたように、プーチンはロシア社会の中から出てきた存在ですから、プーチンがいなくなっても今のロシアは変わらないと思います。」(p58)と述べているのが興味深いです。
第Ⅱ章「プーチンと習近平の急所はどこにあるのか?」は、中国研究が専門の法政大学の熊倉潤教授との「中央公論」(2023年3月号)での対話で、戦争の長期化はプーチン政権に打撃を与えるのか、中露の権威主義体制の比較をもとに検討したもので、小泉氏が「今回の戦争で、仮にクーデターが起きてプーチンが排除されたとしても、それはあまり解決にならないと思っているんです。先に触れたように、プーチンはロシア社会の中から出てきた存在ですから、プーチンがいなくなっても今のロシアは変わらないと思います。」(p58)と述べているのが興味深いです。
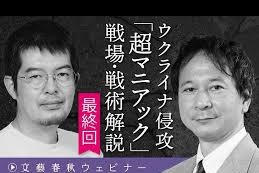 第Ⅲ章「ウクライナ戦争「超精密解説」」、第Ⅳ章「逆襲のウクライナ」、第Ⅴ章「戦線は動くのか 反転攻勢のウクライナ、バイタリティ低下のプーチン」、第Ⅵ章「戦争の四年目が見えてきた」は、防衛研究所の高橋杉雄氏との対談で、2023年春から夏にかけて4回にわたり行われたもの(第Ⅲ章、第Ⅳ章、第Ⅴ章はそれぞれ「文藝春秋」2023年5月号、7月号、8月号に掲載のものを加筆修正、第Ⅵ章は「文藝春秋ウェビナー」での対話「ウクライナ侵攻『超マニアック』戦場・戦術解説⑥」(2023年7月25日)を活字化したもの)。焦点化するバフムトの戦い、プリゴジンの存在感(ワグネルの反乱)、2023年6月に始まったウクライナの反攻など、この時期における戦争のタイムラインとして読め、「激しくも停滞した戦争」という印象は、現在(2024年7月)まで続いているように思います。
第Ⅲ章「ウクライナ戦争「超精密解説」」、第Ⅳ章「逆襲のウクライナ」、第Ⅴ章「戦線は動くのか 反転攻勢のウクライナ、バイタリティ低下のプーチン」、第Ⅵ章「戦争の四年目が見えてきた」は、防衛研究所の高橋杉雄氏との対談で、2023年春から夏にかけて4回にわたり行われたもの(第Ⅲ章、第Ⅳ章、第Ⅴ章はそれぞれ「文藝春秋」2023年5月号、7月号、8月号に掲載のものを加筆修正、第Ⅵ章は「文藝春秋ウェビナー」での対話「ウクライナ侵攻『超マニアック』戦場・戦術解説⑥」(2023年7月25日)を活字化したもの)。焦点化するバフムトの戦い、プリゴジンの存在感(ワグネルの反乱)、2023年6月に始まったウクライナの反攻など、この時期における戦争のタイムラインとして読め、「激しくも停滞した戦争」という印象は、現在(2024年7月)まで続いているように思います。
因みに、本書刊行準備中の2023年8月23日、モスクワ北西部のトヴェリ州で墜落したビジネスジェットの乗客名簿にプリゴジンの名前があったことは周知の事実で、このことは、「プリゴジンは大衆人気が高いので、なかなか手が出せない」という小泉悠氏の言葉の後に「註」として付記されています(さすがに"暗殺"までは読めなかったか)。
 あとがきに、自分は「我々が目指すべき秩序、とかいう話」よりは「シリアに派遣された『Su-34』は迷彩が褐色していてかっこいいですねグフフ」みたいなことばっかり言っている人間で「高邁な話には適任ではない」としていますが、こうした兵器オタク的な気質を隠さないところにも、この人の人気の秘密があるのかも(同じくオタク気質の高橋杉雄氏との対談で、パトレイバー、エヴァ、ナウシカ、ガンダム、ヤマトといったアニメや戦争の中の「戦争と兵器」を論じてもいる)。
あとがきに、自分は「我々が目指すべき秩序、とかいう話」よりは「シリアに派遣された『Su-34』は迷彩が褐色していてかっこいいですねグフフ」みたいなことばっかり言っている人間で「高邁な話には適任ではない」としていますが、こうした兵器オタク的な気質を隠さないところにも、この人の人気の秘密があるのかも(同じくオタク気質の高橋杉雄氏との対談で、パトレイバー、エヴァ、ナウシカ、ガンダム、ヤマトといったアニメや戦争の中の「戦争と兵器」を論じてもいる)。
ロシア軍Su-34戦闘爆撃機
 『ウクライナ戦争の200日』からのメインの対談相手で、今回も対談の半分以上を占める高橋杉雄氏もメディアの露出が多いですが(二人ともBSフジの「プライムニュース」でよく見かけたが、高橋杉雄氏はその後防衛本省との併任となった関係でメディア露出を控えるようになり、小泉悠氏との対談もこれ(『終わらない戦』第Ⅵ章)が最後となった)、その高橋氏は本書に先行して『ウクライナ戦争はなぜ終わらないのか―デジタル時代の総力戦』('23年6月/文春新書)を出しており、こちらは共著で、下記の通り第2章から第4章はそれぞれ、笹川平和財団の福田純一・主任研究員、防衛研究所の福島康仁・主任研究官、中曽根康弘世界平和研究所の大澤淳・主任研究員が担当しています。
『ウクライナ戦争の200日』からのメインの対談相手で、今回も対談の半分以上を占める高橋杉雄氏もメディアの露出が多いですが(二人ともBSフジの「プライムニュース」でよく見かけたが、高橋杉雄氏はその後防衛本省との併任となった関係でメディア露出を控えるようになり、小泉悠氏との対談もこれ(『終わらない戦』第Ⅵ章)が最後となった)、その高橋氏は本書に先行して『ウクライナ戦争はなぜ終わらないのか―デジタル時代の総力戦』('23年6月/文春新書)を出しており、こちらは共著で、下記の通り第2章から第4章はそれぞれ、笹川平和財団の福田純一・主任研究員、防衛研究所の福島康仁・主任研究官、中曽根康弘世界平和研究所の大澤淳・主任研究員が担当しています。
第1章 ロシア・ウクライナ戦争はなぜ始まったのか 高橋杉雄
第2章 ロシア・ウクライナ戦争―その抑止破綻から台湾海峡有事に何を学べるか 福田潤一
第3章 宇宙領域からみたロシア・ウクライナ戦争 福島康仁
第4章 新領域における戦い方の将来像―ロシア・ウクライナ戦争から見るハイブリッド戦争の新局面 大澤淳
第5章 ロシア・ウクライナ戦争の終わらせ方 高橋杉雄
終 章 日本人が考えるべきこと 高橋杉雄
両著に共通しているのは、この戦争が「国家のアイデンティティーを巡る対立」であるということで、『ウクライナ戦争はなぜ終わらないのか』の方は、この戦争を「デジタル時代の総力戦」とし、ハイブリッド戦争として捉えている傾向が強いように思いました。ただ、その点は多くの論者が述べていることでもあり、むしろ小泉悠氏がこの戦争を「古い戦争」と捉えていることがユニークで、それがまた本質を突いているように思います(単なるオタクではない)。(●「古い戦争」であることを象徴するような報道があった。[下記])
《読書MEMO》
●ロシア軍のオートバイ大集団が肉弾突撃、19台爆破され血の海に(2024.07.04 Forbes JAPAN(フォーブス ジャパン) )
ロシア軍はウクライナで装甲車両を大量に失っており、その数はウクライナ国防省の発表に従えば戦車以外の装甲戦闘車両だけで1万6000両近くにのぼる。その補充に苦労しているロシア軍はこの春、窮余の一策として突撃部隊に安価なオフロードバイクを配備し始めた。
ロシアがウクライナで拡大して2年4カ月あまりたつ戦争のおよそ1000kmにおよぶ戦線で、ウクライナ側は小型の自爆ドローン(無人機)を1日に何千機と投入している。ロシア軍の思いついたアイデアは、兵士をオートバイですばやく移動させれば、自爆ドローンの攻撃を浴びる前に目的地点までたどり着けるのではないか、というものだった。
この戦術は功を奏することもある。ロシア軍は、5月9日にウクライナ北東部で始めた新たな攻勢では国境から数kmの小都市ボウチャンシクですぐに失速することになったが、この間、ほかのいくつかの正面では数km前進を遂げている。現在、ウクライナに展開しているロシア軍の兵力は50万人近くにのぼる。
しかし、たいていの場合、オートバイによる突撃はうまくいかない。これは、第一次大戦中や戦間期に突撃バイクを試験した欧州各国の軍隊にとっては驚くような結果ではないだろう。
オードバイ突撃はそれどころか、ロシア兵の血の海になることもある。6月28日、数十台規模とみられる突撃バイクの大集団が、ウクライナ東部ドネツク州南部の小都市ブフレダルでウクライナ軍の第72独立機械化旅団を攻撃した。
ロシアの戦争特派員アレクサンドル・スラドコフによれば、作戦の目的は、ウクライナ側の陣地の背後に回り込み、孤立化させることだった。攻撃前にスラドコフは「ウクライナ側に背後から、より正確に言えば後方から打撃を加えることが計画されている」と報告していた。
だが、それは実現しなかった。オートバイのほか、T-80戦車を含む装甲車両からなるロシア軍の車列をウクライナ側はドローンなどで攻撃した。ミサイルや大砲も使われたもようだ。地雷も破壊に一役買ったのかもしれない。
煙が晴れると、残されていたのは残骸と死体の山だった。第72旅団は、ロシア側の戦車16両、それ以外の戦闘車両34両、オートバイ19台などを撃破し、人員800人あまりを死傷させたと主張している。
