「●児童虐待」の インデックッスへ Prev|NEXT ⇒ 【2826】 川崎 二三彦 『虐待死』
虐待の後遺症の凄まじさ、「ファミリーホーム」による「育ち直し」支援。

 黒川 祥子 氏
黒川 祥子 氏
『誕生日を知らない女の子 虐待――その後の子どもたち』['13年]
2013年・第11回「開高健ノンフィクション賞」受賞作(『壁になった少女 虐待―子どもたちのその後』改題)。
虐待を受けた子どもたちは、成長するにつれ、心身ともに障害を生じ、問題行動に苦しんでいた。そうした被虐待児が暮らす多人数養育施設「ファミリーホーム」を密着取材。心の傷と闘う子供たちと彼らを支える人々の現実と育ち直しの時を、あたたかく見つめる―。
虐待を受け保護された子どもたちをて家庭に引き取り、生活を共にするファミリーホームや里親に取材し(基本的には「社会的養護」の場を取材)、心身に残る虐待の後遺症に苦しみながらも同じ境遇の子らや里親と暮らし、笑顔を取り戻していく「育ち直し」の時を生きる子らを追っています(文庫化の際には、3年後の子どたちの「今」を追加取材し、大幅加筆)。
第1章「美由―壁になっていた女の子」は、親から受けた虐待の後遺症で「解離性障害」を抱える女の子のケースが紹介されています。この障害の症状としては、多重人格や」幻聴・幻覚などで、その凄まじさに驚かされるととも、それでも懸命に生きようとする女の子と、それを支える周囲の努力が胸をうちます。
第2章「雅人―カーテンのお部屋」は、「愛着障害」を抱えるも、最初はそれが虐待の後遺症であると分からなかった男の子の例で、症状としてはADHDのような行動態様が見られ、虐待と発達障害が複雑に絡み合っていることが分かります(本書は、ただ保育士や里親が頑張っているという話だけでなく、こうした精神医学的知見も随所に織り込まれている)。
第3章「拓海―「大人になるって、つらいことだろう」」は、「母親の養育困難」ということで保護された児童養護施設から、新たにファミリーホームにやって来たこども例で、児童養護施設が子どもを規則で縛ることに躍起で、家庭的な経験をする機会を奪っているケースもある(だだし、自分たちにはその認識がなく、子どもの受け渡しを拒否する)という問題もあることを知りました。
第4章「明日香―「奴隷でもいいから、帰りたい」では、実親の許に戻ればまた虐待されることが明らかなのに、戻ることを希望する子どももいるという例で、実際に親元に戻ってから虐待死したという報道があったケースなども紹介されていて(これは今でも新聞などで時々見かける)、痛々しく思うと同時に、問題の難しさを感じます。
第5章「沙織―「無条件で愛せますか」」は、大人になった「被虐待児」を取材したもので、父親の暴行や性的虐待、継母の精神的虐待に苦しんだ末に、何とか生き延び結婚もしたものの、子育ての際にフラッシュバックし、うつ病状態になったり、子どもに殺意を抱いたりする自分(自分の娘の誕生日を祝っている時、娘に対し憎しみや怒りが湧くという。自分は祝われたことはなかったと...)と今まさに闘っている女性の例。話を聴けるタイミングを図りつつ、かなり突っ込んだ取材になっています。
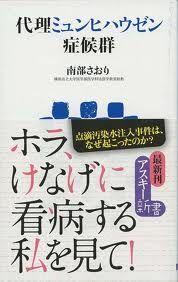 まえがきで紹介されている「代理ミュンヒハウゼン症候群」とは、子どもの世話をする人物(多くは母親)が、自らではなく「子どもを代理として」病気の状態を作り出し、それによって医療機関に留まろうとする虐待のことを指し、以前に読んだ、本書でも紹介されている南部さおり氏の『代理ミュンヒハウゼン症候群』は(氏は「代理ミュンヒハウゼン症候群」は精神状態ではなく「行為」を指し、その行為は虐待であって犯罪だと言う)海外の事例を主に扱っていましたが、今や日本でも珍しくなく(かなり前から珍しくなかったのかもしれないが)、表面化しているものも氷山の一角に過ぎないのだと思いました。
まえがきで紹介されている「代理ミュンヒハウゼン症候群」とは、子どもの世話をする人物(多くは母親)が、自らではなく「子どもを代理として」病気の状態を作り出し、それによって医療機関に留まろうとする虐待のことを指し、以前に読んだ、本書でも紹介されている南部さおり氏の『代理ミュンヒハウゼン症候群』は(氏は「代理ミュンヒハウゼン症候群」は精神状態ではなく「行為」を指し、その行為は虐待であって犯罪だと言う)海外の事例を主に扱っていましたが、今や日本でも珍しくなく(かなり前から珍しくなかったのかもしれないが)、表面化しているものも氷山の一角に過ぎないのだと思いました。
南部 さおり 『代理ミュンヒハウゼン症候群』 (2010/07 アスキー新書)
こうした中、「被虐待児」の人間性回復において「家族体験」は重要で、「里親制度」というのはよく知られていますが、「ファミリーホーム」による「育ち直し」の支援というものが大きな役割を占めていることを知りました。
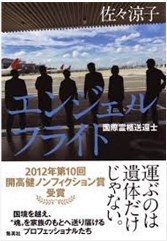 前年の第10回「開高健ノンフィクション賞」受賞作の佐々涼子氏の『エンジェルフライト 国際霊柩送還士』('12年/集英社)が、著者が取材対象に入り込んで一体となっているのに対し、こちらは、取材対象との関わりはあるものの、基本的には距離を保ちつつ事象を一途に追っていく作りで、同じノンフィクションでもいろいろなスタンスがあるなあと思いました。
前年の第10回「開高健ノンフィクション賞」受賞作の佐々涼子氏の『エンジェルフライト 国際霊柩送還士』('12年/集英社)が、著者が取材対象に入り込んで一体となっているのに対し、こちらは、取材対象との関わりはあるものの、基本的には距離を保ちつつ事象を一途に追っていく作りで、同じノンフィクションでもいろいろなスタンスがあるなあと思いました。
佐々 涼子 『エンジェルフライト 国際霊柩送還士』 (2012/11 集英社)
因みに本書の解説を、ネグレクトを扱った映画「誰も知らない」('04年)の是枝裕和監督が書いています。
【2015年文庫化[集英社文庫]】
