「●宇宙学」の インデックッスへ Prev|NEXT ⇒ 「●地球学・地学気象」 【1266】 田近 英一 『凍った地球』
「星間旅行」「系外惑星移住」。宇宙と人類の叡智に思いを馳せるロマン本。


 恒星間宇宙船イメージ図
恒星間宇宙船イメージ図
『人類は宇宙のどこまで旅できるのか: これからの「遠い恒星への旅」の科学とテクノロジー』['24年]

 未来の「星間旅行」はどのようなものとなるのかをNASAテクノロジストの物理学者が考察した本です(原題は「宇宙トラベルガイド」)。読んでみて、星間旅は想像以上に困難だと思いましたが、想像しなければ実現もできないということでしょう。
未来の「星間旅行」はどのようなものとなるのかをNASAテクノロジストの物理学者が考察した本です(原題は「宇宙トラベルガイド」)。読んでみて、星間旅は想像以上に困難だと思いましたが、想像しなければ実現もできないということでしょう。
Les Johnson『A Traveler's Guide to the Stars』['22年]
 まず、宇宙は想像以上に大きいことを思い知らされます。最も近い恒星ケンタウルス座アル
まず、宇宙は想像以上に大きいことを思い知らされます。最も近い恒星ケンタウルス座アル ファ星に行くのに、高速の10分の1のスピードで行っても40年かかります(「距離」問題)。したがって「星間旅行」は数十年から数百年かかるミッションとならざるを得ず、そのことによって様々な課題が浮上します。電源をどう確保するか、通信手段はどうするか、といった問題もあると指摘しています。さらには、推力を得るためのエネルギーはどうするか(「エネルギー」問題)。星間旅行にかかる時間が人の一生よりはるかに長いという問題もあります(「時間」問題)。ただし、NASAの研究者グループの間では、星間旅行は「奇説」ではなくなっているとのことです。
ファ星に行くのに、高速の10分の1のスピードで行っても40年かかります(「距離」問題)。したがって「星間旅行」は数十年から数百年かかるミッションとならざるを得ず、そのことによって様々な課題が浮上します。電源をどう確保するか、通信手段はどうするか、といった問題もあると指摘しています。さらには、推力を得るためのエネルギーはどうするか(「エネルギー」問題)。星間旅行にかかる時間が人の一生よりはるかに長いという問題もあります(「時間」問題)。ただし、NASAの研究者グループの間では、星間旅行は「奇説」ではなくなっているとのことです。
もう1つ、宇宙探査や星間旅行において浮上するのが倫理的な問題で、例えば、地球での人類の生存が危ぶまれる状況になって、自分たちの"ゆりかご"を地球外に拡げるにしても、そこで太陽以外の恒星を公転する系外惑星を見つけ、そこに開拓地を作ることは、その星に生息するすべての生物を支配することにもなりかねず、果たしてそうしたことが許されるのかという問題もあるとのことです(大航海時代の帝国の植民地支配に喩えられている)。
 星間旅行はロボットに旅させる手もあるが、やはり人間が行かないと本来の目的は達成できない。そうすると巨大な「ワールドシップ宇宙船」での生活はどのようなものになるのか。1回の移住は1万人が妥当ではないかとしています。ワールドシップは円筒形で大きさは直径500~600メートル、長さは3~5キロメートル程度になると(もやっとした話ではなく、とことん具体的であるのが本書の良さ)。ただし、ワールドシップ内で生まれた子どもの権利の問題にも触れています(倫理で簡単に白黒つけられる問題ではないとしているが)。
星間旅行はロボットに旅させる手もあるが、やはり人間が行かないと本来の目的は達成できない。そうすると巨大な「ワールドシップ宇宙船」での生活はどのようなものになるのか。1回の移住は1万人が妥当ではないかとしています。ワールドシップは円筒形で大きさは直径500~600メートル、長さは3~5キロメートル程度になると(もやっとした話ではなく、とことん具体的であるのが本書の良さ)。ただし、ワールドシップ内で生まれた子どもの権利の問題にも触れています(倫理で簡単に白黒つけられる問題ではないとしているが)。
先に挙げた幾つかの問題の内、ロケットのエネルギーの問題はかなり大きな問題のようで、核エネルギー(分裂・融合)、電磁エネルギー、光子ロケットなど、さらには「反物質」まで、様々な可能性を探っています。例えば、太陽帆で推進する宇宙船というのは実現可能ですが、太陽からエネルギーを得る静電セイルなども同じですが、太陽から離れすぎるとやはり使えません。星間宇宙船の設計に関しても、先に挙げた電源確保や通信の問題、放射線被曝問題、水・酸素、食糧、重力など様々な問題があるとのことです。
そこで、ここから先はSF的にもなりますが、「スター・トレック」みたいに(日本で言えば「宇宙戦艦ヤマト」みたいに)光より早く移動する(時空をワープする)「ワープ航法」というものも検討の俎上に上げています。コレ、数学的には可能だが物理学的にはわからないそうです。ワームホールを抜けていくというSF的な話も出てきますが、これも、物理学者である著者によれば、理論的には単純なことのようです(でも、それが可能かどうかは分かっていない)。
スペースコロニーのイメージ図(Wikipediaより)
 本書の予測によれば、星間旅行をする最初の有人宇宙船を我々が打ち上げるのは西暦3000年以降になり、宇宙船1機が目的地に達するのに約500年かかるとすると(凍結した胎児を大量に搭載し、目的地に着いて解凍するということも考えられるという)、人間が近隣の多くの恒星系(系外惑星)に移住しているのは西暦10000年頃のことだろうと。ただし、これは、銀河の歴史からすれば"一瞬"であるとしています。
本書の予測によれば、星間旅行をする最初の有人宇宙船を我々が打ち上げるのは西暦3000年以降になり、宇宙船1機が目的地に達するのに約500年かかるとすると(凍結した胎児を大量に搭載し、目的地に着いて解凍するということも考えられるという)、人間が近隣の多くの恒星系(系外惑星)に移住しているのは西暦10000年頃のことだろうと。ただし、これは、銀河の歴史からすれば"一瞬"であるとしています。
最後に、宇宙人(地球外知的生命体)が地球に来ているとして、どうしてそれを発見できないかという疑問については、地球が進化し続けた46憶年のうち、我々が宇宙船を開発してまだ100年も経っておらず、相手にも同じことが言えるわけで、相手が先に星間宇宙船で地球に来ていたとしても、6500万年間栄えた恐竜の時代と、それに比べ極々短い人類繁栄の時代のどの時期に地球に辿り着くかという確率の比較からすると、今現在、異星人が地球に来ている可能性は低いとしています(この説は以前にもどこかで読んで納得した覚えがある)。
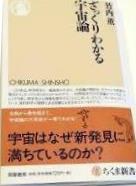 ともあれ、面白かったです。宇宙のスケールの大きさや、人類の叡智の可能性に思いを馳せることができる、ロマンに満ちた本でした。以前読んだ、竹内 薫 著『ざっくりわかる宇宙論』('12年/ちくま新書)では、最も近いケンタウルス座アルファ星域に行くにしても光速で4年、マッハ30の宇宙船で光速の3万倍、12万年もかかるため、ワームホールでも見つけない限り難しいのではないかとしていましたが、NASAにはこうしたことを真剣に考えている(マッドではない)サイエンティストがいるのだなあ。
ともあれ、面白かったです。宇宙のスケールの大きさや、人類の叡智の可能性に思いを馳せることができる、ロマンに満ちた本でした。以前読んだ、竹内 薫 著『ざっくりわかる宇宙論』('12年/ちくま新書)では、最も近いケンタウルス座アルファ星域に行くにしても光速で4年、マッハ30の宇宙船で光速の3万倍、12万年もかかるため、ワームホールでも見つけない限り難しいのではないかとしていましたが、NASAにはこうしたことを真剣に考えている(マッドではない)サイエンティストがいるのだなあ。
