「●え 遠藤 周作」の インデックッスへ Prev|NEXT ⇒「●お ジョージ・オーウェル」【3031】 ジョージ・オーウェル 「象を撃つ」
「●「谷崎潤一郎賞」受賞作」の インデックッスへ
重いテーマ。但し、神の不在や沈黙がテーマではない作品。技巧面でも優れている。




『沈黙 (新潮文庫)』 /映画「沈黙‐サイレンス‐」タイアップ帯/『沈黙
』['63年/新潮社] 遠藤 周作
1966(昭和41)年度・第2回「谷崎潤一郎賞」受賞作。
島原の乱が鎮圧されて間もない頃、ポルトガル司祭ロドリゴとガルペは、キリシタン禁制が厳しい日本に潜入するためマカオに立寄り、そこで軟弱な日本人キチジローと出会う。キチジローの手引きで五島列島に潜入し、隠れキリシタンたちに歓迎されるが、やがて長崎奉行所に追われる身となる。幕府に処刑され殉教する信者たちを前に、ガルペは彼らの元に駆け寄って命を落とす。ロドリゴもキチジローの裏切りで捕らえられ、長崎奉行所でかつての師で棄教したフェレイラと出会い、更にかつては自身も信者であった長崎奉行の井上筑後守との対話を通じて、日本人にとって果たしてキリスト教は意味を持つのかという命題を突きつけられる。ある日、ロドリゴは、日本人信徒たちに加えられる残忍な拷問と悲惨な殉教のうめき声に接することとなり、棄教の淵に立たされる―。
1966(昭和41)年3月刊行の遠藤周作(1923-1996/享年73)の書き下ろし長編小説で、神の存在、背教の心理、西洋と日本の思想的断絶など、キリスト信仰の根源的な問題に関して切実な問いを投げかけたとされている作品です。テーマとしては、まず「神はなぜ沈黙しているのか」(或いは「神は本当にいるのか」)という絶対的なテーマと、次に「迫害の中で殉教が必ずしも正しい選択とは言えないのではないか」(棄教という選択もあるのではないか)という相対的なテーマの2つのテーマが考えられるように思いました。
最初の「神は本当にいるのか」というテーマは、日本に来て多くの信者の苦難を目にしてた主人公のロドリゴ自身が、「神は本当にいるのか。もし神がいなければ、幾つもの海を横切り、この小さな不毛の島に一粒の種を持ち運んできた自分の人生は滑稽だった。泳ぎながら、信徒たちの小舟を追ったガルペの一生は滑稽だった」と自問しています。但しこのテーマは、確かに大きなテーマですが、一方で、物語を通して主人公にとって神は(ロドリゴの主観においては)否定し得ないア・プリオリな存在であるようにも思えました。更に言えば、「沈黙」というタイトルでありながら、「神はなぜ沈黙しているのか」ということも、直接の本書のテーマには必ずしもなっていないともとれます。そのことは、当初、作者が予定していたタイトルが「ひなたの匂い」だったのが、新潮社側からインパクトが弱いとされて「沈黙」というタイトルを薦められ、それを受け入れたという経緯からも窺えます。
問題は2番目の「迫害の中で殉教が必ずしも正しい選択とは言えないのではないか」というテーマであり、このテーマは、ロドリゴとガルペの対比だけでなく、何度も踏み絵を踏み、仕舞いにはロドリゴを奉行所に売り渡しながら、それでもなおロドリゴに告解を受け容れてもらうために付き纏うキチジローや、拷問により棄教したかつてのロドリゴの師フェレイラなども入り交じって、やや複雑な位相を示しているように思いました。
ロドリゴは、自分を売ったキチジローをユダさながらに見做して許す気になれず、また、拷問により棄教し日本の土壌にキリスト教は馴染まないという結論に至ったかつての師フェレイラを背教者と見做して軽蔑します。それらを認めてしまったら、棄教を拒んで殉教したガルペの死(或いはそれ以前の日本人信徒らの死)は何だったとのかという、1番目の問題と同じことになるからだと思われます。但し、ロドリゴにとって神はア・プリオリな存在であり、井上筑後守との問答はあったにせよ、この段階では彼自身は棄教するつもりは全くありません。
そして、いよいよ自分自身がフェレイラが受けた拷問と同じような拷問を受けると思われる日が到来し、むしろ張り切ってその場に臨むのですが、実際に彼自身は拷問は受けることはなく、実は何日も前から拷問を受けていたのは何度も棄教した信徒らで、ロドリゴが棄教しない限り彼らへの拷問は続き、彼らはそのままでは死ぬであろうという、かつて、ロドリゴの目の前でガルペが置かれたのと同じような究極の選択をしなければならない状況が彼を襲い、結局ロドリゴは彼自身がそうするとは予期していなかった棄教をします(一方、それは、井上筑後守が予測していたことでもあった)。
従って以降は、そのようにして「転んだ」司祭であるロドリゴがキリスト者たり得るのか、神は殉教した人々だけでなく、ロドリゴとも共に在るのか―といったことがテーマになっているように思われます。例えばこのテーマは、彼がそれまで汚らわしいものでも見るように捉えていたキチジローにも当て嵌まるテーマであり、ロドリゴにとっては非常に皮肉なテーマでもあるように思いました。
作者のロドリゴの描き方は、婉曲的ではあるものの、神はまたロドリゴの傍にも在るといったものになっているように思われましたが、このことが、この小説がキリスト教会から非難されることになったり、作者のキリスト教観は非常に母性的なものであって、これは日本人特有のキリスト教観、或いは作者独自のキリスト教観であるといった批判や議論に繋がっていったのでしょう。
但し、作者自身はそうした議論を喚起するためにこうした小説を書いたのではなく、おそらく作者は、どんな苦難の中でも「私はお前たちに踏まれるため、この世に生れ、お前たちの痛さを分つため十字架を背負ったのだ」と声をかけてくれる、「人生の同伴者たるイエス」乃至は「母なる神」を描きたかったのではないかと思います。
感動作であり、重いテーマの作品(但し、先にも述べたように、神の不在や沈黙がテーマではないと思われる)ですが、技巧面も優れていると思いました。この作品のモチーフは古文書から得ているそうですが、ポルトガル人であるロドリゴのモデルになった司祭は実はイタリア人であって、ポルトガル人であるフェレイラのモデルになった人物との間に師弟関係どころか接触さえなかったのを、二人を同国人にして師弟関係にし、物語上の二人の対比を際立たせたりするなど、ストーリーテラーとしての作者の巧みさが光ります。また、物語の前半を、ロドリゴが本国に宛てた書簡という形で純粋な主観で描き、後半を、ロドリゴの心象を描きながらも三人称の半客観で描き、エピローグを古文書の形を借りた純粋客観で描いているといった構成も巧みであると思いました。

 以前に読んで、結構「重い」と感じられたせいか暫く読み返さないでいたのですが、マーティン・スコセッシ監督による映画「沈黙-サイレンス-」('16年/米)の公開を機に読み直しました。もともとそれほど長い小説でもないのですが、とにかく一気に読める密度の濃い作品であると、改めて感じました。
以前に読んで、結構「重い」と感じられたせいか暫く読み返さないでいたのですが、マーティン・スコセッシ監督による映画「沈黙-サイレンス-」('16年/米)の公開を機に読み直しました。もともとそれほど長い小説でもないのですが、とにかく一気に読める密度の濃い作品であると、改めて感じました。
マーティン・スコセッシ監督 「沈黙 -サイレンス-」 (16年/米) (2017/01 KADOKAWA) ★★★★☆
【1981年文庫化[新潮文庫]】

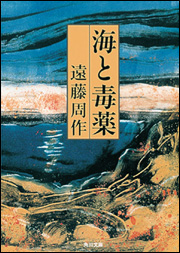

 1958(昭和33)年・第12回「毎日出版文化賞」(文学・芸術部門)並びに1959(昭和34)年・第5回「新潮社文学賞」受賞作であり、映画化もされました。
1958(昭和33)年・第12回「毎日出版文化賞」(文学・芸術部門)並びに1959(昭和34)年・第5回「新潮社文学賞」受賞作であり、映画化もされました。 遠藤周作(1923- 1996/享年73)作品の久しぶりの読み返しでしたが、初読の時とやや印象が違いました。やはり最初に読んだ学生の頃は、実際の事件をベースにしているという衝撃から、こんなことがあったのかという驚きの方が先行したのかも知れません。再読して、センセーショナリズムを排しつつも、「読み物」としての構成に意匠が凝らされていると思いました。
遠藤周作(1923- 1996/享年73)作品の久しぶりの読み返しでしたが、初読の時とやや印象が違いました。やはり最初に読んだ学生の頃は、実際の事件をベースにしているという衝撃から、こんなことがあったのかという驚きの方が先行したのかも知れません。再読して、センセーショナリズムを排しつつも、「読み物」としての構成に意匠が凝らされていると思いました。

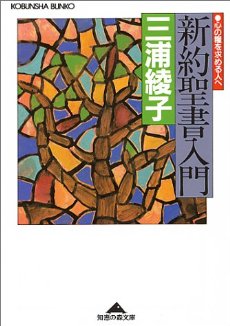


 『
『
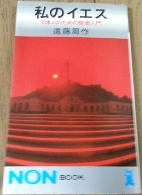
 ノン・ブックにあった遠藤周作(1923‐1996/享年73)の『私のイエス-日本人のための聖書入門』('76年/祥伝社)(現在はノン・ポシェット)が、「奇跡」とは何かということを軸に遠藤周作の独自のキリスト教に対する考え方を反映していて興味深いですが、"イエスの復活"というものに対する解釈とは別に(遠藤周作は、"復活"を無理に信じる必要はないと述べている)、イエスを裏切った者や"転びバテレン"に対する独自の見解(これは代表作『
ノン・ブックにあった遠藤周作(1923‐1996/享年73)の『私のイエス-日本人のための聖書入門』('76年/祥伝社)(現在はノン・ポシェット)が、「奇跡」とは何かということを軸に遠藤周作の独自のキリスト教に対する考え方を反映していて興味深いですが、"イエスの復活"というものに対する解釈とは別に(遠藤周作は、"復活"を無理に信じる必要はないと述べている)、イエスを裏切った者や"転びバテレン"に対する独自の見解(これは代表作『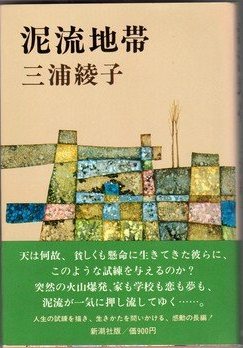
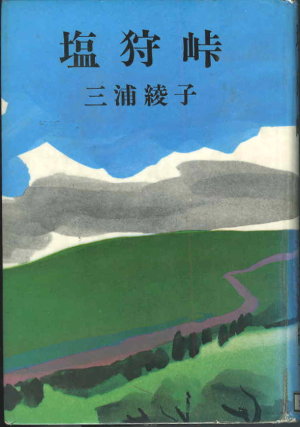


 因みに、冒頭に挙げた「氷点」の原作は、'63年に朝日新聞社が、大阪本社創刊85年、東京本社創刊75周年を記念する事業として懸賞小説を募集した時の入選作品で、TVドラマ版は、最初にドラマ化された'66年のもの(主演:内藤洋子、新珠三
因みに、冒頭に挙げた「氷点」の原作は、'63年に朝日新聞社が、大阪本社創刊85年、東京本社創刊75周年を記念する事業として懸賞小説を募集した時の入選作品で、TVドラマ版は、最初にドラマ化された'66年のもの(主演:内藤洋子、新珠三 千代、芦田伸介)が"原罪"というテーマに沿った重厚さを最も備えていて、その後に作られたものを引き離しているのではないでしょうか。夏枝(新珠三千代)の冷酷さが怖く、卒業式で陽子(内藤洋子)に白紙の原稿を読ませるよう仕組むが...。前年に黒澤明監督「
千代、芦田伸介)が"原罪"というテーマに沿った重厚さを最も備えていて、その後に作られたものを引き離しているのではないでしょうか。夏枝(新珠三千代)の冷酷さが怖く、卒業式で陽子(内藤洋子)に白紙の原稿を読ませるよう仕組むが...。前年に黒澤明監督「 「氷点」●演出:北代博●脚本:楠田芳子●音楽:
「氷点」●演出:北代博●脚本:楠田芳子●音楽:

