「●と フョードル・ドストエフスキー」の インデックッスへ Prev|NEXT ⇒ 【465】 ドストエフスキー 『白夜』
「○海外文学・随筆など 【発表・刊行順】」の インデックッスへ
「ドスト氏の文学を理解するためには、どうしても通過しなければならない関門の一つ」(小沼文彦)
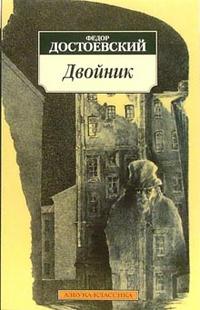


『二重人格 (岩波文庫)』改版版/『二重人格』岩波文庫
Двойник(1846/2010 Азбука-классика 版)
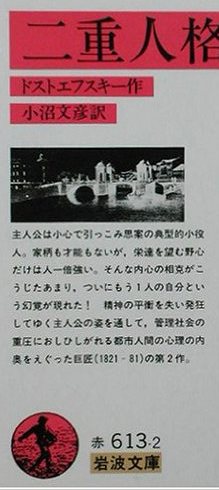 主人公ゴリャートキン氏は、小心で引っ込み思案の孤独を愛する男で、典型的小役人であるが、家柄も才能もないのに栄達を望む野心だけは強く、そのことを自覚しながらも、自分には人並みかそれ以上の才能があるという自負心もあって、そうした内心の相克が昂じて精神的に病んでしまった結果、もう一人の自分という幻覚を作り出してしまう―。
主人公ゴリャートキン氏は、小心で引っ込み思案の孤独を愛する男で、典型的小役人であるが、家柄も才能もないのに栄達を望む野心だけは強く、そのことを自覚しながらも、自分には人並みかそれ以上の才能があるという自負心もあって、そうした内心の相克が昂じて精神的に病んでしまった結果、もう一人の自分という幻覚を作り出してしまう―。
ドストエフスキーが1846年、25歳の時に、処女作『貧しき人々』の次に発表した作品で、作者は自信満々で世に送り出したようですが当時の評判はイマイチで、その時の低評価がその後も続いたきらいのある作品のようです。しかしながら、訳者の小沼文彦(こぬま ふみひこ、1916-1998)は文庫解説で、「現在ではよほどの愛好家でないかぎり、その存在すらも知らない人が多いが、ドストエフスキーの文学を理解するためには、やはりどうしても通過しなければならない関門の一つであることは、いまさら言うまでもない」('81年4月)としています。
全体を通して、ゴリャートキン氏の混乱した視点から見た描写や独白が延々繰り返され、そのため冗長感は否めず、それが発表時のマイナス評価の一要因としてもあったようですが、「饒舌過剰」はドストエフスキー作品の特質だと考えれば、むしろ、「役所に行ったら自分そっくりで姓名まで自分と同じ人間が仕事していた」というシュールな設定の方に当時の批評家の一部はついていけなかったのではないでしょうか。
個人的には、プロット自体はまるで筒井康隆氏の初期作品みたいで面白く、作者が意識して読者サービスしているようにも思えました(安部公房の『壁-S・カルマ氏の犯罪』にも、会社に行ってみたら自分の代わりに自分の"名刺"が仕事をしていたという超シュールなシチュエーションがあったなあ)。
主人公の前に突如現れたもう一人の自分"新ゴリャートキン氏"は如才ない人間で、人当たりがよくてゴマ摺りも出来るため上司の受けもよく、"我らが旧ゴリャートキン氏"は、役所での自分の仕事や地位を次々と奪っていく新ゴリャートキン氏のことを卑劣漢と見做して苦々しく思っているわけですが、実は"新ゴリャートキン氏"は、そうありたいという自分の願望の(本当はそうしたいがそんな卑怯なことは出来ないという思いも含めた)投影であることが窺えます(旧ゴリャートキン氏は、"新ゴリャートキン氏"との直接対決に何度か臨むが、直接対面するごとに相手に対して馬鹿丁寧になり、異常にへりくだってしまうのが興味深く、この辺りは後の『永遠の夫』に繋がるものを感じる)。
振り返ってみれば、最初の方に出てくる、ゴリャートキン氏が医者にかかっている場面の、その際の医者との遣り取りから、彼が既に"壊れている"ことが窺えるように思われますが、この作品に影響を与えたとされるニコライ・ゴーゴリの「外套」や「鼻」などと比べると、それらの作品の主人公の精神錯乱からくる幻想的な場面は、主人公の妄想であることがすぐ分かるように書かれているのに対し、この作品は一貫してゴリャートキン氏の視点から書かれているため、何が真実であり何が嘘であるのか、読者は主人公と一緒に迷宮を彷徨することになり、その辺りがミステリアスで、楽しませてくれます(当時の著名な批評家ベリンスキーは、まさにこの"幻想的色調"が強すぎる点において、この作品に対し否定的評価だったのだが)。
よく読むと結構プロットが練られているように思え、旧ゴリャートキン氏が"新ゴリャートキン氏"を自宅に招いて苦労話を聞いてやる場面などは、虚実皮膜譚というか、どこまでが事実でどこからが幻想なのか読者には明かされておらず、更には、前半部分において、ゴリャートキン氏が恩人の娘の誕生パーティに招待されたつもりで行ってみると実は招かれざる客であり、思い余って失礼な振舞いをして追い返されてしまうというエピソードがありますが、後半部分には、"新ゴリャートキン氏"の「陰謀家」的性格に気付いたその娘からゴリャートキン氏宛てに会いたいとの手紙が来ると言う"出来事"があり、この後半のエピソードを全て"妄想"として捉えるならば、ゴリャートキン氏の精神的病いはかなり重篤であるということに加え、ある種"創作"作用を伴うものであると言えることになるのではないでしょうか。
この作品の原題(Двойник)は(英題は単に"The Double"となっているが)ドイツ語の「ドッペルゲンガー」に相当する言葉だそうで、日本語には該当する言葉が無いために、かつては「分身」と訳されていたのですが(Двойникには双子の相方を指す意味もあるようだ)、訳者は"相似関係"よりも"心理学的要素"に重点を置いて「二重人格」としたとのこと。この場合の「二重人格」とは、スティーヴンソンの『ジキル博士とハイド氏』のようなものを指すのではなく、「おれは自分で自分を殺してしまったんだ!」という主人公の叫びにも象徴されるように、「自分自身」からの"疎外"状況を表しているように思います。
 現代心理学及び精神医学に置き換えるならば、劣等コンプレックスから強迫神経症、更には統合失調症に至って乖離性障害を引き起こしているという感じでしょうか。ドストエフスキー自身に若い頃から被害妄想があり、ロシア文学者の中村健之介氏などは、それを「統合失調症」による誇大妄想からくるものであると推察していて(『永遠のドストエフスキー-病いという才能』('04年/中公新書)、更にドスト氏には「離人症」の傾向もあったそうです。
現代心理学及び精神医学に置き換えるならば、劣等コンプレックスから強迫神経症、更には統合失調症に至って乖離性障害を引き起こしているという感じでしょうか。ドストエフスキー自身に若い頃から被害妄想があり、ロシア文学者の中村健之介氏などは、それを「統合失調症」による誇大妄想からくるものであると推察していて(『永遠のドストエフスキー-病いという才能』('04年/中公新書)、更にドスト氏には「離人症」の傾向もあったそうです。
こうした中村氏の分析に対しては病跡学的な色彩が強すぎるとの批判もありますが、ドストエフスキーが異常なまでの執着心を持って、まるで虐め抜くかのようにこの作品の主人公であるゴリャートキン氏のことを描いているようにも思えることからすると、小沼氏の言う「ドストエフスキーの文学を理解するためには、やはりどうしても通過しなければならない関門の一つ」という言い方とリンクしてくる面があるようにも思います。
【1954年文庫化・1981年改版[岩波文庫]】

 2012年映画化「嗤う分身」('13年/英)
2012年映画化「嗤う分身」('13年/英)
監督:リチャード・アイオアディ
原作:フョードル・ドストエフスキー『二重人格』
出演:ジェシー・アイゼンバーグ(サイモン・ジェームズ/ジェームズ・サイモン)/ミア・ワシコウスカ/ウォーレス・ショーン/ノア・テイラー
「嗤う分身 [DVD]」
