「●海外文学・随筆など」の インデックッスへ Prev|NEXT ⇒ 【667】 ヘンリー・ミラー 『北回帰線』
○ノーベル文学賞受賞者(ソール・ベロー) 「○海外文学・随筆など 【発表・刊行順】」の インデックッスへ
主人公よりも詐欺師の"タムキン博士"と父親の"アドラー博士"が印象に残った。

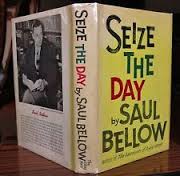
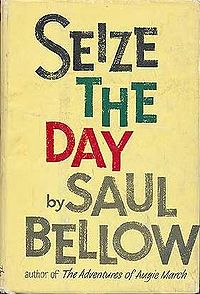

『この日をつかめ (新潮文庫)』['71年]/First edition cover (1956) / Saul Bellow(1915-2005/享年89)
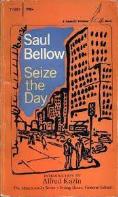
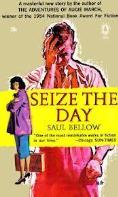
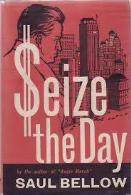
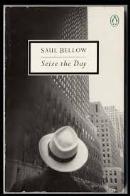 44歳になるトミー・ウィルヘルムは、かつて役者志望の道を絶たれ、今は職も無く妻子とも別れ、名士の父親と同じホテルで生活しているが、部屋代の支払いにも窮し、投資につぎ込んだなけなしの金もどうなるかわからない―。
44歳になるトミー・ウィルヘルムは、かつて役者志望の道を絶たれ、今は職も無く妻子とも別れ、名士の父親と同じホテルで生活しているが、部屋代の支払いにも窮し、投資につぎ込んだなけなしの金もどうなるかわからない―。
1956年に米国の作家ソール・ベロー(Saul Bellow、1976年にノーベル文学賞受賞)が発表した小説で、主人公の危機的な一日を追いながら、人間存在の意味を問うた作品(原題は"Seize the Day")。1986年にロビン・ウィリアムズ主演で映画化されていますが("SEIZE THE DAY")、「ミッドナイト・ニューヨーカー」という邦題がありながらも本邦未公開です。
やることなすこと全て裏目に出て踏んだり蹴ったりの主人公ですが、やっぱり中年で自活出来ないというのは、経済生活面だけでなく、精神面でキツイなあと思いつつも、あまり主人公に同情心が沸かないのは何故?
社会(俗世間)からの疎外を感じる主人公が、最後には、「この日をつかめ」という言葉をキーワードに、過去に捉われることなく、また、未来に不安を抱くことなく、"今を生きる"ことの大切さを悟るのですが、ついつい、明日は大丈夫なの?と思ってしまうのは、自分が俗っぽいからでしょうか。
主人公のラード等への投資を仲介する"タムキン博士"という人物が大変印象に残り、「この日をつかめ」も彼の言葉なのですが、彼は実は詐欺師であり(読者にはかなり早い段階でそれがわかると思うが、主人公は疑念を抱きながらも彼に振り回される)、いかにも資本主義社会に徘徊していそうなクセモノ。彼の言う「この日をつかめ」は"投機"上の意味合いなのですが、主人公は詐欺師の言葉から哲学を引き出し(確かにこの詐欺師は哲学者っぽい弁を垂れる)、一方で、現実面では結局のところ、この詐欺師になけなしの金を持っていかれたということか。
 主人公の父親の"アドラー博士"というのも、息子を世の中の敗北者と決めつけ、全く構ってやらないという、ちょっと日本にはいないタイプの父親で、志賀直哉の父親との間での葛藤などとも違って、こちらは「和解」の余地すら無い。河合隼雄氏が、父性原理は「よい子だけがわが子」という規範で、母性原理は「わが子はすべてよい子」という規範であり、欧米は父原理の社会であり、日本は母性原理の社会であると言っていたのを思い出しました。
主人公の父親の"アドラー博士"というのも、息子を世の中の敗北者と決めつけ、全く構ってやらないという、ちょっと日本にはいないタイプの父親で、志賀直哉の父親との間での葛藤などとも違って、こちらは「和解」の余地すら無い。河合隼雄氏が、父性原理は「よい子だけがわが子」という規範で、母性原理は「わが子はすべてよい子」という規範であり、欧米は父原理の社会であり、日本は母性原理の社会であると言っていたのを思い出しました。
この物語の父親はまさに欧米型の父性原理の具現化像であり、また同時に俗世間の代表格であるけども、アーサー・ミラーの『セールスマンの死』に出てくる、アメリカンドリームを子供に託す期待過剰の父親とも全然違って、その個人主義は凄まじく、息子さえも早めに見切った後には(見込んでいた頃の描写は出てこないが)他人レベルと変わらない「一個人」に過ぎなくなってしまっているいう感じでしょうか(ユダヤ系ということも関係しているのか?)。
小説として今一つ感動は出来なかったですが、"タムキン博士"と"アドラー博士"は印象に残りました(主人公よりも)。
【1971年文庫化・1993年改版[新潮文庫]/1978年再文庫化[集英社文庫(『その日をつかめ』)]】
