◆所定労働時間が短い日に休業した場合も、平均賃金の6割の休業手当が必要か
 当社には、1週のうち特定の曜日の所定労働時間が通常の日の所定労働時間より短いけ社員がいます。先日、会社施設の増改築工事のため社員に対し休業を命じましたが、その社員については、4時間の勤務が予定されていた日でした。そのため、この社員の休業手当の計算をしたところ、平均賃金の60%相当額が4時間分の時給を上回る結果となりました。
当社には、1週のうち特定の曜日の所定労働時間が通常の日の所定労働時間より短いけ社員がいます。先日、会社施設の増改築工事のため社員に対し休業を命じましたが、その社員については、4時間の勤務が予定されていた日でした。そのため、この社員の休業手当の計算をしたところ、平均賃金の60%相当額が4時間分の時給を上回る結果となりました。
こうした場合でも、平均賃金の60%を休業手当として支払う必要があるのでしょうか。4時間分の時給または4時間分の時給の60%の支払いで済ませることはできないでしょうか。  所定労働時間が短い日に使用者の責めによる事由で休業し、平均賃金の60%が当該日の所定労働時間分の時給を上回る場合においても、平均賃金の60%以上を休業手当として支払う必要があります。ご質問のケースにおいても、4時間分の時給または4時間分の時給の60%の支払いで済ませることはできません。
所定労働時間が短い日に使用者の責めによる事由で休業し、平均賃金の60%が当該日の所定労働時間分の時給を上回る場合においても、平均賃金の60%以上を休業手当として支払う必要があります。ご質問のケースにおいても、4時間分の時給または4時間分の時給の60%の支払いで済ませることはできません。
■解説
1 休業手当
労働基準法26条では、「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない」と定めています。
「使用者の責に帰すべき事由」には、使用者の故意、過失による休業はもちろん、経営上の理由による休業も含まれます。したがって、天災地変等の不可抗力による休業までは含まれませんが、事業所の移転や施設の増改築による一時休業の場合は、「使用者の責に帰すべき休業に該当する」ものとされ、休業した日について平均賃金の100分の60以上の休業手当を支払わなければなりません。
休業手当の算定基礎となる平均賃金について、労働基準法12条1項は、「平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう」としており、さらに2項では、「前項の期間は、賃金締切日がある場合においては、直前の賃金締切日から起算する」と定めています。
当該日以前3ヵ月間に支払われた賃金の総額を総日数で除するため、当該休業日の所定労働時間が通常の日の所定労働時間より短い場合には、ご質問のように、平均賃金の100分の60が、当該日の賃金額を上回ることもあり得ることになります。
2 休業手当の額が休業日の賃金を上回る場合の取り扱い
そこで、4時間の勤務が予定されていた日に休業を命じ、平均賃金の100分の60相当額が4時間分の時給を上回る結果となった場合においても、平均賃金の100分の60を休業手当として支払う必要があるのかというのがご質問の内容ですが、休業手当の趣旨は、平均賃金の100分の60以上に相当する金額の支払いを、使用者に罰則をもって強制することにより、労働者の保護を図ろうとしたものです。したがって、こうした場合でも、平均賃金の100分の60以上に相当する金額を支払わなければならないということになります。
ご質問のケースにおいても、4時間分の時給または4時間分の時給の100分の60の支払いで済ませることはできません。解釈例規においても、「一週中のある日の所定労働時間が、たまたま短く定められていても、その日の休業手当は、平均賃金の100分の60に相当する額を支払わなければならない」とされています。
□根拠法令等
・労働基準法26(休業手当)、21(平均賃金)
・昭27.8.7 基収3445(休業期間が一労働日に満たない場合の休業手当の額)
・内容についての無断転載は固くお断りいたします。
◆社員の同居の家族が感染症にかかったため当該社員を自宅待機させる場合、休業手当を支払う必要はあるか
 この冬は新型インフルエンザの流行が蔓延するおそれがあると、マスコミ等で報じられていますが、当事業所では、介護福祉事業という業務の性質上、職員と同居の家族が新型インフルエンザ等の感染症にかかった場合、当該職員を「保健所の判断がなくても原則として自宅待機とする」ことを就業規則に定めようと考えています。
この冬は新型インフルエンザの流行が蔓延するおそれがあると、マスコミ等で報じられていますが、当事業所では、介護福祉事業という業務の性質上、職員と同居の家族が新型インフルエンザ等の感染症にかかった場合、当該職員を「保健所の判断がなくても原則として自宅待機とする」ことを就業規則に定めようと考えています。
この場合、当該職員の休業の期間については、賃金や休業手当を支払う必要はあるでしょうか。  保健所等行政による休業の場合は「賃金」「休業手当」とも支払う必要はないと考えられますが、行政の判断を待たずに"事業所独自の判断で命じた休業"については、「使用者の責めに帰すべき事由による休業」に該当すると解され、少なくとも「休業手当」の支払いが必要とされる可能性があります。
保健所等行政による休業の場合は「賃金」「休業手当」とも支払う必要はないと考えられますが、行政の判断を待たずに"事業所独自の判断で命じた休業"については、「使用者の責めに帰すべき事由による休業」に該当すると解され、少なくとも「休業手当」の支払いが必要とされる可能性があります。
■解説
1 職員本人に感染が確認され、本人を自宅待機とした場合
まず、職員本人が新型インフルエンザ等の感染症にかかったことが確認され、その職員を自宅待機にした場合、その間の「賃金」や「労基法第26条の休業手当」(平均賃金の6割以上)を支払う必要があるのかということについて解説します。
新型インフルエンザ等の罹患者に対しては、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(以下、「感染症予防法」)により、都道府県知事が入院あるいは外出自粛等を要請できるとされており、これに基づき保健所が行う要請に従った場合は、事業主が当該者を自宅待機にするまでもなく、その者は休務となります。
このように保健所等行政の要請により休んだ場合、この休業は、民法第536条第2項の「債権者(=使用者)の責めに帰すべき事由」による労務の受領拒否には該当しないため、「賃金」を支払う必要はありません。さらに、「休業手当」についても、"経営上の理由による休業"のような、労基法第26条の「使用者の責めに帰すべき事由による休業」ではないため、支払う必要はないということになります。
ただし、新型インフルエンザについては、国内で初めて感染が確認され、流行が拡大した年(平成21年)には、感染症予防法に基づく知事のこうした要請は出されるまでには至っておらず、法の根拠を持たない緩やかな休業の要請であったことに留意が必要です。そうした場合における罹患者の自宅待機の場合、一般的に、民法の定めに照らして「賃金」の支払いは必要ないと考えられますが、「休業手当」の要否については、当時の行政指導においては、個別具体的な事案の判断の権限は、事業所所在地所轄の労働基準監督署にあるとされ、確認を得ることが望ましいとされました。
2 職員の同居の家族に感染が確認され、当該職員を自宅待機とした場合
次に、ご質問のように、職員と同居する家族に感染が確認された場合は、その間の「賃金」や「休業手当」を支払う必要があるかどうかということについて解説します。
感染症予防法では、家族が新型インフルエンザ等にかかっている者などについて保健所等で調査を行い、「当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者」と判断された場合については、都道府県知事が外出自粛等の要請を行うこととしています。同居家族が罹患し、保健所から外出自粛等の要請が出され、これに従った場合は、事業主が自宅待機を命じるまでもなく、休務せざるを得ません。
このように保健所等行政の要請により休んだ場合は、職員本人が罹患し、行政の要請により休んだ場合と同様、「賃金」や「休業手当」を支払う必要はありません。
ただし、新型インフルエンザについては、前述のとおり、国内で初めて感染が確認され、流行が拡大した年(平成21年)には感染症予防法に基づく知事のこうした要請は出されておらず、罹患者と同居する家族に対する外出自粛などの要請も、明確には行われませんでした。
これに対して、各事業所は、仮にも事業所内に感染の可能性がある者が入ることのないよう、貴事業所が現在検討されているように、保健所の判断によらず各事業所のルールとして、自宅待機とすることが考えられます。
こうした、行政の判断を待たずに"事業所独自の判断で行う休業"については、その間の「賃金」までは支払う必要はないものの、少なくとも「休業手当」については必要とされる可能性があります。
実際の各事業所の対応としては、「賃金を通常通り支払う」「休業手当を支払う」の2通りのパターンが考えられますが、平成21年の新型インフルエンザ流行時には、「賃金を通常通り支払う」とする事業所が比較的多かったようです。これは、欠勤しても賃金を控除しない"完全月給制"を、もともと採用している事業所が少なからずあるということもありますが、同居の家族の感染に伴い、本人が働ける状態であるにもかかわらず休ませることについて、「特別休暇」とするなどして、本人の欠勤の場合とは異なる配慮をしたとも考えられます。ただし、"日給月給制"をとる事業所等において、当該日については「休業手当(のみ)を支払う」としても差し支えありません。
これに対し、行政の判断(保健所から外出自粛等の要請)を待たずに休業を命じる場合において、「賃金も休業手当も支払わない」とするのは、違法とされる可能性がありますので、ご注意ください。
□根拠法令等
・労基法26(休業手当)
・民法536条②(債務者の危険負担等)
・感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律18(就業制限)
・感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令11(就業制限)
・内容についての無断転載は固くお断りいたします。
◆退職者にも賃金改定後の新賃金との差額を遡及払いすべきか
 当社では、毎年4月に賃金の改定を行っており、4月分の賃金(4月25日支給)からベースアップおよび定期昇給後の賃金を支給しています(定期昇給は「一律の定額昇給」と「査定昇給」からなる)。
当社では、毎年4月に賃金の改定を行っており、4月分の賃金(4月25日支給)からベースアップおよび定期昇給後の賃金を支給しています(定期昇給は「一律の定額昇給」と「査定昇給」からなる)。
しかしながら、今年の場合は新賃金の決定が例年より遅れることが予想され、4月分は暫定的に旧ベースの賃金を支払い、新賃金決定後に差額を支給することを考えています。
こうした状況において、4月末日で退職予定の社員がおり、新賃金確定時には退職していることになりますが、この社員に対して退職後においてでも、賃金改定後の旧賃金と新賃金との差額を支払わなければ違法になるのでしょうか。  新賃金決定後、その支払対象を在職者のみとするか退職者を含めるかは、当事者の自由とされていますので、退職者を支払対象から除いても違法にはなりません。
新賃金決定後、その支払対象を在職者のみとするか退職者を含めるかは、当事者の自由とされていますので、退職者を支払対象から除いても違法にはなりません。
したがって、4月に遡及してベースアップや定期昇給(査定昇給)をした場合、その間の退職者に対して賃金の差額を支払う規定がない限りは、差額分を支払う必要はありません。
ただし、定期昇給分のうち、一律昇給の部分について就業規則(賃金規程)等で昇給額があらかじめ定められていて、当該額の昇給をまだ行っていない場合は、その差額を支払う必要があります。
■解説
1 遡及払いとベースアップ分の対象者
ベースアップや定期昇給を過去にさかのぼって実施し、賃金の支払日が経過した後、遡及したことによって生じた賃金を後日まとめて支払うことを「遡及払い」といいます。
賃金の遡及払いの必要が生じたときは、遡及することによって生じた各月の追加額の全額を、直後の賃金支払い日に支払わなければならず、その後の何ヵ月かに分割して支払うことはできません。
4月に遡及してベースアップした場合、ベースアップ決定前に退職した者に対しても差額を追加して支払うべきかどうか、つまり、遡及払いの対象を在職者のみとするか退職者を含めるかは、当事者の自由にゆだねられています。通達においても、「新給与決定後過去に遡及して賃金を支払うことを取決める場合に、その支払対象を在職者のみとするかもしくは退職者をも含めるかは当事者の自由である」(昭 23.12.4.基収 4092)とされています。
したがって、過去にさかのぼってベースアップを行う場合、支給日以前にすでに退職した者については遡及払いの対象から除く旨を、労働協約や就業規則等で定めることは差し支えありません。
仮に、退職者には賃金の差額を支払わないとする規定がなかったとしても、裁判例では、労働者の賃金昇給分の具体的支払請求権は「各年度毎に結ばれる賃金に関する協定において具体化されることによって、はじめて発生するもの」で、新賃金確定時にすでに退職した者は従業員としての地位を有しないので、協定の効果を受ける立場になく、新賃金と支給された賃金との差額分を請求ことはできないとされています(昭50.4.22大阪高判・淀川プレス製作所事件)。これは労働協約に関する裁判例ですが、その趣旨は就業規則(賃金規程)等に関しても同じく当てはまり、遡及分支払日前に退職した者には、賃金の差額を支払う規定がない限り、具体的支払請求権は発生していないということになります。
2 定期昇給分の遡及払いの対象
一方、定期昇給については、4月に在籍した者が遡及分支払日の前に退職した場合において、昇給の額があらかじめ労働協約や就業規則(賃金規程)等で具体的に規定されているにも関わらず、当該額の昇給をまだ行っていない場合は、退職者にもその差額を支払う必要があります。
定期昇給には一般に「一律昇給」と「査定昇給」があり、例えば「本給は、毎年4月にこれを1,000円昇給する」という規定が就業規則(賃金規程)等にあるとするならば、これは「一律昇給」を定めたものであり、遡及分支払日の前に退職した者も(本給昇給分1,000円の)遡及払いの対象となります。
一方、「職能給は、毎年4月に前年度の評価査定により改定する」といった規定が就業規則(賃金規程)等にあれば、これは「査定昇給」を定めたものであり、前掲の裁判例にもあるように、新「職能給」確定時にすでに退職した者については、この規定のみでは退職時に具体的な「職能給」昇給額が確定していたとは言えないため、新「職能給」と旧「職能給」の差額の請求権は発生しません。
したがって、ご質問に対する回答は、4月に遡及してベースアップや定期昇給(査定昇給)をした場合、その間の退職者に対して賃金の差額を支払うという規定がない限りは、差額分を支払う必要はありませんが、定期昇給分のうち、一律昇給の部分について就業規則(賃金規程)等で昇給額があらかじめ定められて、当該額の昇給をまだ行っていない場合は、その差額を支払う必要があるということになります。
なお、以上の点は、4月以降退職日までの割増賃金の算定に際しても適用されますのでご注意ください。
□根拠法令等
・労基法24①(全額払いの原則)
・昭 23.12.4.基収 4092(遡及賃金の支給対象)
□判例等
「賃金昇給分とこれに伴う退職金増額分の具体的な支払請求権は労働協約第64条の規定によって当然に発生しているとは認め難く、更に、各年度毎に結ばれる賃金に関する協定において具体化されることによって、はじめて発生するものと解するのが相当である」としたもの。(昭50.4.22大阪高判・淀川プレス製作所事件)
・内容についての無断転載は固くお断りいたします。
◆懲戒処分を決定するまでの自宅待機期間は無給でよいか
 当社ではこの度、社員に対する懲戒処分を実施するにあたって、事実関係の調査をするために、本人に自宅待機を命じることになりました。この自宅待機期間中は無給としてもよいでしょうか。
当社ではこの度、社員に対する懲戒処分を実施するにあたって、事実関係の調査をするために、本人に自宅待機を命じることになりました。この自宅待機期間中は無給としてもよいでしょうか。  懲戒処分を決定するまでの自宅待機期間は、原則的には無給にできません。平均賃金の60%についての支払い義務があることになります。
懲戒処分を決定するまでの自宅待機期間は、原則的には無給にできません。平均賃金の60%についての支払い義務があることになります。
■解説
1 不就労の場合の賃金支払い義務の基本的な考え方
欠勤、遅刻、早退、ストライキ等、専ら労働者側の一方的な都合で労働すべき日または時間に労働しなかった場合、使用者にはその間の賃金支払い義務はありません。ただし、年次有給休暇の場合は、労働基準法により、賃金の支払いが義務付けられています。
また、使用者の責に帰すべき事由により休業させた場合は、労基法上少なくとも平均賃金の60%についての支払い義務があることになります。
「休職」については、労基法上の定義はありませんが、一般的には、「従業員の身分を保有したまま一定期間就業義務を免除する制度」のことを指し、休職事由には、私傷病のため、組合専従のため、海外留学のため、公職につくため、刑事事件により身柄を拘束され勤務不能となったため、ボランティア活動に従事するため、などがあります。基本的には、労働者側に就労できない事情があるのですから賃金支払い義務はありませんが、一般には、就業規則等で定めた休職制度の内容や運用方法によるところとなります。
「出勤停止」は、就業規則の懲戒規定に基づき、労働者に一定の規則違反行為があったときに命じられ、その間は賃金が支払われないのが通常ですが、形式的には「使用者の責に帰すべき事由」による休業とみることもできます。しかし、企業には社内秩序を維持するために一定の懲戒権が保持されており、「出勤停止」処分が労働者の違反行為に相応した妥当なものである場合は、賃金の支払い義務はないものと考えられます。
2 懲戒処分前の自宅待機期間についての考え方
それでは、ご質問のような懲戒処分前の自宅待機期間についてですが、この自宅待機自体は懲戒処分ではなく、会社側が調査の必要のために(「使用者の責に帰すべき事由」により)「自宅待機」を命ずるものです。仮にこれが懲戒処分であるとすれば、ある労働者の行為に対してすでに懲戒をしたことになりますので、その同じ行為に対して再び懲戒処分をすることは二重処分となり、できないことになります。
業務命令で「自宅待機」を命じた場合、賃金の支払い義務はないとすると、その根拠はどこにあるのでしょうか。
懲戒処分の前提として常に自宅待機が必要であるとは考えられませんが、例えば経理担当の社員が不正経理を行っている疑いがあるような場合、そのことの真偽を確かめるためには本人を自宅に待機させておいた方が、証拠の隠滅を防止し、調査が円滑に行えることも考えられます。
調査の結果、不正経理がなされたことが明らかになり、結果的にその社員を懲戒解雇することになったような場合は、その自宅待機は「使用者の責に帰すべき事由」によるというよりも、むしろ、その原因となったのは本人の不正行為であるという因果関係が成り立ちますので、自宅待機期間分の賃金を支払わないとすることも可能であるかもしれません。さらに、その性質が刑事事件になるようなものであれば、そのことは必要な措置でもあるかもしれません。
しかし、そのような必要性のある場合を除いては、自宅待機期間の賃金を当然に無給にしてよいという根拠はありません。
裁判例においても、「このような場合の自宅謹慎は、それ自体として懲戒的性質を有するものではなく、当面の職場秩序維持の観点から執られる一種の職務命令とみるべきものであるから、使用者は当然にその間の賃金支払い義務を免れるものではない」とし、「使用者が右支払義務を免れるためには、当該労働者を就労させないことにつき、不正行為の再発、証拠湮滅のおそれなどの緊急かつ合理的な理由が存するか」または「これを実質的な出勤停止処分に転化させる懲戒規定上の根拠が存在することを要する」と解すべきであり、「単なる労使慣行あるいは組合との間の口頭了解の存在では足りないと解すべきである」としたものがあります(「日通名古屋製鉄作業事件」平3.7.22 名古屋地裁判決)。
この判決は結論としても賃金の支払いを命じており、ここでの趣旨は、賃金支払い義務を免れるのはかなり具体化した危険がある場合に限られるということです。したがって、自宅待機期間中も原則的には無給とすることはできず、使用者側には、少なくとも平均賃金の60%についての支払い義務があることになります。
□根拠法令等
・労基法26(休業手当)
・内容についての無断転載は固くお断りいたします。
◆給与や賞与の振込みの際に、振込み手数料を差し引いてもよいか
 社員への給与や賞与の支払いを口座振込みにしていますが、給与や賞与を振込む際に、振込み手数料を差し引いてもよいでしょうか。
社員への給与や賞与の支払いを口座振込みにしていますが、給与や賞与を振込む際に、振込み手数料を差し引いてもよいでしょうか。
また、アルバイトには給与を現金払いしていますが、アルバイト本人から「現金を受け取りにいく時間がないので、銀行口座に振込んでほしい」と言ってきた場合には、振込み手数料を差し引いた額を振込むことは可能でしょうか。  給与や賞与の振込みの際に振込み手数料を差し引くことは、労働基準法の「賃金全額払いの原則」に違反するためできません。
給与や賞与の振込みの際に振込み手数料を差し引くことは、労働基準法の「賃金全額払いの原則」に違反するためできません。
労働者本人からの依頼による口座振込みであっても、振込手数料は、賃金支払において使用者が当然に負担すべき経費であるため、賃金から振込み手数料を控除して銀行口座に振込むことはできません。
■解説
1 給与や賞与の振込みの際に振込み手数料を差し引くことは可能か
労働基準法(以下「法」という)第24条第1項は「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」として、賃金の支払方法のひとつに「全額払いの原則」を定めています。これは、労働者が賃金を確実に受け取れるようにすることで、労働者が自らの生計に不安を抱くことのないようにする必要があることに配慮したものです。
一方、銀行口座等への振込みについては、実際には広く行われていることから、「確実な支払の方法で命令で定めるものによる場合」(法第24条第1項ただし書)に該当するものとして、本人の同意を得た場合には「通貨払いの原則」の例外として認められています。
次に、ご質問にある、社員への給与や賞与を口座振込みする際に、振込み手数料を差し引いてもよいかという問題ですが、「全額払いの原則」の例外として控除が認められているものには、「法令に別段の定めがある場合」と「当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合(以下「労使協定」という)」の2つの場合があります(法第24条第1項ただし書後段)。
まず、「法令に別段の定めがある場合」とは、所得税の源泉徴収、健康保険料や厚生年金保険料の控除、雇用保険料の控除、市町村民税(都道府県民税を含む)の控除、減給の制裁による控除がこれに該当しますが、振込み手数料を控除してもよいという法令の定めはありません。
また、「労使協定による賃金控除」も無制限に認められるわけではなく、これについて通達では、「購買代金、社宅、寮その他の福利、厚生施設の費用、社内預金、組合費等、事理明確なものについてのみ、法36条の時間外労働と同様の労使協定によって賃金から控除することを認める趣旨である」とされていますので、振込手数料は労使協定による場合にも控除することができないことになります。
2 本人からの依頼による口座振込みであれば手数料を差し引くことは可能か
ご質問にあるように、アルバイトが賃金を受け取りに来られないために、アルバイト本人の希望に応じるかたちで給与を口座振込みとする場合、口座振込み自体は本人の同意を得てのことですので問題ありませんが、振込手数料は、上記の理由から賃金支払における経費として当然に使用者が負担すべきものであるということになり、控除することは許されません。
以上のように、いずれの場合も、振込み手数料を差し引いて賃金を銀行口座に振込むことは、法第24条第1項で定める「全額払いの原則」に違反することになります。
□根拠法令等
・労基法24(賃金の支払)、91(制裁規定の制限)
・労働基準法規則7の2(賃金の支払方法)
・所得税法183(源泉徴収義務)、健康保険法167(保険料の源泉控除)、厚生年金保険法84(保険料の源泉控除)、労働保険の保険料の徴収等に関する法律31(賃金からの控除)、地方税法第321の5(特別徴収税額の納入の義務等)
・昭27.9.20基発675(労使協定による賃金控除)
・内容についての無断転載は固くお断りいたします。
◆入社前に行う研修にも賃金を支払わなければならないか
 当社では、採用内定者全員を対象に、社員として必要とされる業務に関する基礎知識や技能、社内での仕事上のルールを修得させ、入社に際しての円滑な就業を促すために、入社の日の前に、あらかじめ会社施設内で一定期間の研修を行っています。
当社では、採用内定者全員を対象に、社員として必要とされる業務に関する基礎知識や技能、社内での仕事上のルールを修得させ、入社に際しての円滑な就業を促すために、入社の日の前に、あらかじめ会社施設内で一定期間の研修を行っています。
この場合の採用内定者が研修を受けた時間については、賃金を支払う必要があるのでしょうか。賃金を支払う必要がある場合、賃金に代えて定額の「研修手当」の支給でも構わないでしょうか。  入社日前の研修であっても、参加が実質的に強制されているものであれば、採用内定者は、事業主の指揮命令に従って労務を提供したのと同じ扱いになるため、研修を受けた時間については賃金を支払う義務があることになります。その名目は「研修手当」であっても構いません。
入社日前の研修であっても、参加が実質的に強制されているものであれば、採用内定者は、事業主の指揮命令に従って労務を提供したのと同じ扱いになるため、研修を受けた時間については賃金を支払う義務があることになります。その名目は「研修手当」であっても構いません。
■解説
1 労働基準法に基づく支払い義務
事業主は、労働者が使用者の指揮命令に服し、労務を提供した時間に対しては賃金を支払わなければなりません。研修への参加は、直接的には労務の提供はなされていないかのように見えますが、採用内定者の研修が、ご質問にあるように、社員として必要な知識や技能、仕事上のルールを修得させるために行われるものであり、かつ、参加が実質的に強制されている場合には、その参加者は、指揮命令下で労務を提供していたことになります。したがって、研修を受けた時間については「労働」した時間であるということになり、賃金を支払う義務があります。
労働基準法では、こうした入社前の研修について賃金を○○円以上支払わねばならないといった細かい規定がされているわけではなく、「労働の対償である賃金を最低賃金以上の額で支払わねばならない」という趣旨のことが規定されているだけですので、入社前研修が「労働」に該当する場合、最低賃金以上を支払えば法違反にはならないことになります。
就業規則に入社前研修に関する規定がある事業所では、採用内定者であっても、就業規則を内容とする契約に基づいて賃金等の支払い義務が生じることになりますが、ほとんどの事業所では、採用内定者(入社予定者)は就業規則の適用対象外となっているかと思われます。その場合、入社前研修の実施を入社予定者に呼びかける際に、最低賃金以上の一定額の金銭を支払うことを入社予定者に対し申し込みをし、これを入社予定者が承諾すれば、個別の契約が成立したことになり、その個別契約に基づき、事業主に約束の額の金銭を支払う義務が生じることになります。
2 「手当」での代替について
入社前研修が「労働」に該当して賃金の支払いを要するとしても、その名目は問いません。その労務の提供に対して支払われることが示されていればよく、したがって「研修手当」でも構いません。また、入社前研修が「労働」に該当するか否か不明である場合などは、あえて「研修手当」という名目で支払っておくことも考えられます。
研修への参加が実質的に強制されているものであっても、研修参加者に対し、時間換算で最低賃金以上の水準の「研修手当」が支払われるのであれば、労基法違反にはなりません。また、実際に研修に要した時間が予定の時間を超えても、1週40時間1日8時間の法定労働時間の枠を超えなければ、割増賃金の支払い義務も生じません。
以上から、入社前研修に関して労基法上の支払い義務が生じても、通常その水準は比較的低い金額で足りることになります。しかし、これから入社予定者との間で長期の継続的な雇用関係が予定されることを考えるならば、違法ではないからといって最低賃金ぎりぎりの設定をすることが、入社予定者との信頼関係を築くうえで適切であるかどうかということも考慮しておく必要があります。
入社予定者に対し、貴社としての社員研修や賃金に対する姿勢を示す機会でもあり、相当の手当を支払うことが望ましいと考えられます。
□根拠法令等
・労働基準法28(最低賃金)
・内容についての無断転載は固くお断りいたします。
◆産前産後の休業中にも賃金を支払わなければならないか
 近く出産を予定している女性社員が、産前産後の休業をすることになりましたが、産前産後の休業期間中も賃金の支払い義務はあるのでしょうか。その期間中は無給とすることは可能でしょうか。
近く出産を予定している女性社員が、産前産後の休業をすることになりましたが、産前産後の休業期間中も賃金の支払い義務はあるのでしょうか。その期間中は無給とすることは可能でしょうか。  労働義務がなければ労働者には賃金請求権は生じないので、賃金の支払い義務はありません。ですから、産前産後の休業のため労務に就かなかった日については、無給としても差し支えありませんが、その旨を就業規則等に定めておく必要があります。
労働義務がなければ労働者には賃金請求権は生じないので、賃金の支払い義務はありません。ですから、産前産後の休業のため労務に就かなかった日については、無給としても差し支えありませんが、その旨を就業規則等に定めておく必要があります。
なお、産前産後の休業のため労務に就かなかった日については、健康保険から出産手当金が支給されます。
■解説
1 産前産後の休業について
労働基準法第65条においては、「使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない」(同条第1項)、また、「使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない」(同条第2項)と規定しています。つまり、産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)については本人が請求した場合、産後8週間については強制的(完全な強制は6週間)に就業させることが禁止されていることになります。
なお、産前の休業期間については、自然の分娩予定日を基準としているため、分娩予定日より遅れて出産した場合、予定日から出産当日までの期間は産前の休業期間に含まれます。
2 産前産後の休業期間中の賃金
産前産後の休業期間中の賃金を支払うか否かについては、労働基準法では特に規定されていません。したがって、この産前産後の休業期間中に実際に休業した期間については、労働者の就業が禁止されているため労働者に労働義務がないことから、労働者側には賃金請求権は生じないので、ノーワーク・ノーペイの原則により無給として差し支えありません。
ただし、この場合でも、無給とすることについて、就業規則または労働協約などで定めをしておく必要があります。労働基準法第89条では、「賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項」を就業規則の絶対的必要記載事項の1つとしています(同条第2号)が、産前産後の休業期間中の賃金を支払うか否かについての定めも、この絶対的必要記載事項に該当するためです。
なお、産前産後の休業については、労務に就かなかった期間について、健康保険から出産手当金が支給されます。出産手当金の額は日を単位として計算され、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、1日につき標準報酬日額の3分の2に相当する金額が支給されます。
産前産後の休暇については、就業規則等で有給または一部有給として定めることも可能ですが、労務に就かなかった期間について事業主から報酬を受けた場合には、支給される出産手当金の額は、その報酬の額を控除したものとなるためご注意ください。
□根拠法令等
・労基法65(産前産後)、89(就業規則の作成・変更・届出の義務)
・健康保険法102(出産手当金)、108(傷病手当金又は出産手当金と報酬等との調整)
・内容についての無断転載は固くお断りいたします。
◆施設改装のために休業する場合にも、その間の賃金を全額支払う必要があるか
 保育サービス事業者ですが、託児施設を改装するため休業を予定しています。その期間、一部の職員については、繁忙な時間帯だけ他の託児施設へ応援に行ってもらい、それ以外は休んでもらうことになるかと思います。このような場合の賃金も支払わなければならないのでしょうか。
保育サービス事業者ですが、託児施設を改装するため休業を予定しています。その期間、一部の職員については、繁忙な時間帯だけ他の託児施設へ応援に行ってもらい、それ以外は休んでもらうことになるかと思います。このような場合の賃金も支払わなければならないのでしょうか。  「使用者の都合で休業する場合は、休業期間中は平均賃金の60%以上の休業手当を支払わなければなりません。1日の所定労働時間の一部だけ休業させたような場合は、実際に労働した時間に対して支払う賃金が平均賃金の60%を超える場合には、労働した時間に対する額だけを支払うことで足りますが、労働した時間に対して支払う賃金が平均賃金の60%に満たない場合には、その差額を支払わなければなりません。
「使用者の都合で休業する場合は、休業期間中は平均賃金の60%以上の休業手当を支払わなければなりません。1日の所定労働時間の一部だけ休業させたような場合は、実際に労働した時間に対して支払う賃金が平均賃金の60%を超える場合には、労働した時間に対する額だけを支払うことで足りますが、労働した時間に対して支払う賃金が平均賃金の60%に満たない場合には、その差額を支払わなければなりません。
■解説
1 「使用者の責に帰すべき事由」とは
労働基準法第26条では、「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない」と定めています。
この場合の「使用者の責に帰すべき事由」には、使用者の故意、過失による休業はもちろん、経営上の理由による休業も含まれます。したがって、天災地変等の不可抗力による休業までは含まれませんが、親会社の経営不振によって、それまで親会社から資金や資材の提供を受けていた下請工場がその提供を受けられなくなり休業するような場合も、「使用者の責に帰すべき休業に該当する」ものとされ、休業した日について平均賃金の100分の60以上の休業手当を支払わなければなりません。
こうした「使用者の責に帰すべき事由」にあたるものとして、このほかには、
① 事務所移転による一時休業や経営不振による一時帰休の場合などがあります。ご質問にある施設改装のための休業は①のケースに該当しますから、平均賃金の100分の60以上の休業手当を支給する必要があります。
② 法人の解散に際し清算事務の遅延等により解雇予告手当が払われていない場合
③ 新規学卒採用内定者に対する自宅待機が行なわれた場合
④ 予告なしに解雇した場合
⑤ 派遣期間の途中で派遣先の都合で派遣契約の解除がされた場合(代わりの派遣先がみつからず待機させるときは、派遣元使用者の責に基づく事由となる)
2 1日の所定労働時間の一部を休業させた場合
なお、他の施設の繁忙時間帯に限って改装中の施設の職員を応援に行かせ、他の時間を休業させるというように1日のうち一部休業させた場合にも、その日について平均賃金の60%以上の額を休業手当として支払わなければならないとされています。このことは、現実に就労した時間に対して支払われる賃金が平均賃金の100分の60に満たない場合はその差額を支払う必要があるということであり、仮に1日の所定労働時間が8時間の職員が4時間だけ就業した場合には、平均賃金の半日分に対する60%を支払うのではなく、平均賃金の半日分との差額の10%(60%-50%)を支払うことになるということです。実際に労働した時間に対する賃金が平均賃金の60%以上の場合には、労働した時間に対して支払う額で足りることになります。
□根拠法令等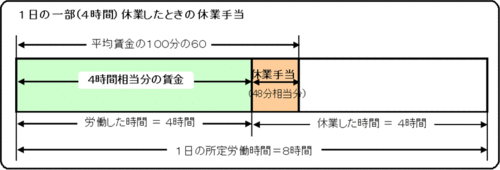
・昭23.6.11基収1998(下請け工場の資材、資金難による休業)
・昭24.2. 8基収77(法人の解散後の休業手当)
・昭63.3.14基発150(新規学卒採用内定者の自宅待機)
・昭24.7.27基収1701(予告なしに解雇した場合の休業手当)
・昭61.6.6基発333(派遣労働者の休業手当支払いの要否)
・昭23.6.11基収1998(下請工場の資材、資金難による休業)
・昭27.8.7基収3445(休業期間が一労働日に満たない場合の休業手当の額)
・内容についての無断転載は固くお断りいたします。
◆誤って支払った住宅手当を給与から天引きして返還させてもよいか
 ある社員に対し、賃金規定で定められた額より多い額の住宅手当が一定期間支払われていたことが判明し、その社員から返還してもらうことにしたのですが、その際に社員の給与から天引きすることはできるでしょうか。
ある社員に対し、賃金規定で定められた額より多い額の住宅手当が一定期間支払われていたことが判明し、その社員から返還してもらうことにしたのですが、その際に社員の給与から天引きすることはできるでしょうか。 「過払い賃金を給与天引きする」旨の労使協定に定めがなければ、原則として給与天引きすることはできません。
「過払い賃金を給与天引きする」旨の労使協定に定めがなければ、原則として給与天引きすることはできません。
ただし、給与天引きによる相殺が、当該労働者の完全な自由意思によるものであるときには、その旨を定めた労使協定が締結されていない場合でも、天引きすることは可能です。
■解説
1 過払い賃金を給与天引きする旨の労使協定があるか
労働基準法第24条の「(賃金)全額払いの原則」の例外として控除が認められているものに、法令に基づく控除(税金、社会保険料、労働保険料など)と労使協定に基づく控除があります。労使協定による賃金控除は、購買代金、社宅、寮その他の福利厚生施設の費用、社内預金、組合費など事由が明白なものに限るとされていますが、それらの具体的な項目が労使協定に定められていることが賃金から控除する際の要件となります。したがって、ご質問のケースにおいても、労使協定によって「過払い賃金があったときには賃金から天引きする」との定めがなされていない場合、一方的に過払い分を給与から控除することは、「全額払いの原則」に反するため認められないということになります。
さらに、賞与もその支給条件等が就業規則に定められている場合には、労働基準法でいうところの賃金に該当し、同様に「全額払いの原則」があてはまるため、賞与からの天引きに際しても給与天引きと同じ要件が必要となります。
2 その旨を定めた労使協定がない場合
過払い賃金を給与天引きする旨の労使協定が締結されていない場合でも、例えば、就業規則(賃金規程)で「社員の扶養配偶者がいなくなった翌月から家族手当は支給しない」と定めていて、扶養配偶者がいなくなっていたにもかかわらず本人が申告していなかったため、家族手当が過払いとなっていたようなケースにおいては、過払い分は民法703条でいう不当利得にあたり、給与または賞与から天引きすることは可能であると考えられます。ただし、社員に十分な理解と反省を求め、本人の承諾を得たうえで天引きを行うべきでしょう。
こうしたケースも含め、給与天引きによる相殺が、当該労働者の完全な自由意思によるものであるときには、過払い賃金を給与天引きする旨の労使協定が締結されていない場合でも、必ずしも「全額払いの原則」の趣旨には反しません。
3 過払い賃金の清算における実務上の留意点
また、過払い賃金の清算において、行政解釈では、「前月分の過払賃金を翌月分で清算する程度は賃金それ自体の計算に関するものであるから、法第24条の違反とは認められない」としており、こうした調整的相殺は「全額払いの原則」に反しないとしています。
判例においては、12月支給された年末手当の過払い分を、使用者が翌年1月に返還請求したうえで、これに応じなかった労働者の2月と3月の給与から過払い分を控除した事案について、最高裁は、「適切な賃金の額を支払うための手段たる相殺は、同項(労基法24条第2項)ただし書によって除外される場合にあたらなくても、その行使の時期、方法、金額等からみて労働者の経済生活の安定との関係上不当と認められないものであれば同項の禁止するところではないと解するのが相当である」とし、この見地から、「許されるべき相殺とは、過払のあった時期と賃金の精算調整の実を失わない程度に合理的に接着した時期においてされ、また, あらかじめ労働者にそのことが予告されるとか、その額が多額にわたらないとか、要は労働者の経済生活の安定をおびやかすおそれのない場合でなければならない」としています(「福島県教組事件」昭44.12.18最高裁判決)。
こうした通達や判例からみて、過払い賃金の清算を行う際には、①過払いのあった時期とあまりかけ離れない時期に精算調整を行うこと、②前もって精算することを予告し、1回の精算額が過大にならないようにすることなど、社員の生活上の安定への留意が必要でしょう。
□根拠法令等
・労基法24(賃金の支払)
・昭27.9.20基発675 、平11.3.31基発168(労使協定による賃金控除)
・昭23.9.14基発1357(過払賃金の清算)
・内容についての無断転載は固くお断りいたします。
◆給与の締切日や支払日を変更する場合はどんな点に留意する必要があるか
 当社では、現在、給与の計算期間が前月16日~当月15日、支払日が当月25日となっていますが、給与計算の締切日から給与支払日までの間にゆとりを持たせるため、計算期間を当月1日~当月末に、支払日を翌月25日にそれぞれ変更したいと考えています。この変更に法律上何か問題があるでしょうか。
当社では、現在、給与の計算期間が前月16日~当月15日、支払日が当月25日となっていますが、給与計算の締切日から給与支払日までの間にゆとりを持たせるため、計算期間を当月1日~当月末に、支払日を翌月25日にそれぞれ変更したいと考えています。この変更に法律上何か問題があるでしょうか。
また、変更する場合に留意すべき点があれば教えてください。  「賃金の締切り及び支払の時期」については、就業規則への記載が義務づけられていますが、就業規則の変更手続きさえ適正に行なえば、変更すること自体に特に法的な問題はありません。
「賃金の締切り及び支払の時期」については、就業規則への記載が義務づけられていますが、就業規則の変更手続きさえ適正に行なえば、変更すること自体に特に法的な問題はありません。
ただし変更に際しては、変更月の社員の生活費を確保するようにし、社員の生活設計が大きく不安定となるような影響を及ぼさないように配慮することなど、いくつか留意すべき点があります。
■解説
1 変更月の支給額が減らないように配慮する
賃金の締切日や支払日を変更する場合、変更した月の固定給与が少なくなり、社員に不利益を与えるおそれがあります。ご質問のケースの場合でみると、当月1日から15日までの半月分の給与が、変更前ならば当月25日に支給されるべきはずだったのに、変更後は翌月25日の支払い分にまわるため、当月の支給額は前月16日から前月末日分までの半月分しかないということになります。この場合でも、退職までに通算して受け取る給与の額は変わりませんが、社員は、変更月は通常月の半分の給与で生活しなければならないことになり、生活設計が不安定になります。
このような場合に社員に与えるダメージを最小限に抑えるため、変更月は半月分の給与を二重に払って通常通り1カ月分を支給するのが望ましいでしょう。それが無理でも、変更月を賞与支給月に合わせて生活費を確保できるようにするとか、半月分の給与相当分の無利子での貸付を行なうなど、何らかの措置を講ずべきです。
2 そのほかに留意すべき点
そのほかに留意すべき点として、以下の事項があります。
(1)毎月1回払いの原則の遵守
ご質問のケースでは該当しませんが、例えば、それまで月末締めの当月25日払いだった給与を、支払日を翌月10日に変更した場合、変更月には給与が1回も支払われないことになります。このままですと、「毎月1回払いの原則」(労動基準法第24条第2項)違反となりますので、こうした制度変更時においても、毎月1回以上の支払日を確保する措置が必要です。(2)就業規則(賃金規程)の変更手続き
ご質問のケースにおいても、変更月の半月分の給与(前月16日から前月末日分)を翌月の支払いにまわし、翌月25日に1.5カ月分支払うといった処理をした場合は、変更月には給与が1回も支払われないことになり、「毎月1回払いの原則」に反することになりますのでご注意ください。
「賃金の締切り及び支払の時期」については、就業規則の絶対的必要記載事項とされています(労働基準法第89条第2号)。ですから、就業規則(賃金規程)の変更を行い、過半数労働組合または過半数代表者の意見聴取をしたのち、意見書を添えて所轄の労働基準監督署長に届け出る必要があります。(3)社会保険・雇用保険の手続き上の留意点
4月から6月は社会保険の算定基礎月に該当し、この間に給与支払いの仕組みを変更すると事務処理手続きが煩雑になるため、この期間での変更はできるだけ避けた方がよいでしょう。
また、雇用保険の離職証明書の記載のしかたについても留意が必要です。離職証明書の賃金支払対象期間の欄には、賃金締切日の変更に応じて賃金計算期間が短くなった一定期間(ご質問のケースですと「前月16日から前月末日」)を記載し、備考欄に「賃金締切日変更」と附記することになります。
・内容についての無断転載は固くお断りいたします。
