◆退職後に判明した懲戒解雇事由をもとに、退職金を不支給とすることができるか
 先日当社を退職した社員について、在職中に懲戒解雇事由に相当する非違行為があったことが、退職後に判明しました。このような場合、退職金を不支給とすることはできるでしょうか。
先日当社を退職した社員について、在職中に懲戒解雇事由に相当する非違行為があったことが、退職後に判明しました。このような場合、退職金を不支給とすることはできるでしょうか。
また、事実関係の究明に時間を要する場合、退職金の支払いを留保することはできるでしょうか。  すでに退職した社員を懲戒解雇することはできないため、懲戒解雇を理由に退職金を不支給とすることはできません。退職後に判明した事由をもとに退職金を不支給とするには、「懲戒解雇に相当する事由が認められるとき」「退職金支給日までの間に在職中の行為について懲戒解雇事由が認められた場合」などにおいても退職金を減額または不支給とすることがある旨を、あらかじめ就業規則や退職金規程に定めておくことが望ましいでしょう。
すでに退職した社員を懲戒解雇することはできないため、懲戒解雇を理由に退職金を不支給とすることはできません。退職後に判明した事由をもとに退職金を不支給とするには、「懲戒解雇に相当する事由が認められるとき」「退職金支給日までの間に在職中の行為について懲戒解雇事由が認められた場合」などにおいても退職金を減額または不支給とすることがある旨を、あらかじめ就業規則や退職金規程に定めておくことが望ましいでしょう。
事実関係の究明に時間を要するため、退職金の支払いを留保する場合も、「当社が必要と認める調査を実施する間、支払いを留保できる」といった定めをしておくことが望ましいと考えます。
■解説
1 退職後に判明した懲戒解雇事由をもとに退職金を不支給とするには
多くの事業所では、従業員が重大な非違行為をした場合の制裁として、懲戒解雇できる旨の規定を設けるとともに、懲戒解雇の場合には退職金を不支給とするか、またはその一部を減額できる旨の規定を設けています。
しかし、ご質問のケースでは、すでに労働者が退職しており、当事者間の雇用関係は終了しています。そのため、使用者による解雇すなわち雇用契約を終了させる旨の意思表示は、その対象を失っているために意味を持たず、懲戒解雇することは不可能です。したがって、懲戒解雇を理由として退職金の不支給または減額を行うことはできないということになります。
そうすると、就業規則や退職金規程でその支給条件等が明確に定められた退職金は、労働基準法上の賃金として扱われますので、通常支払う額を全額支給しなければなりません。支給条件や支給額の算定方法が定められている退職金は、労働者にとって賃金債権となり、恣意的に減額したり支払わなかったりすることはできないからです。
そこで、実務上の対応としては、あらかじめ就業規則や退職金規程において、「懲戒解雇の場合」に加えて、「懲戒解雇に相当する事由が認められるとき」あるいは「退職金支給日までの間に在職中の行為について懲戒解雇事由が認められた場合」も、減額または不支給とすることがある旨を定めておき、ご質問のようなケースにおいて不支給等の決定をする際の契約上の根拠とすることが考えられます。
実際の裁判例では、このような減額・不支給事由が定められていない場合でも、労働者の在職中の非違行為が重大かつ悪質なものであれば、労働者の退職後になされた退職金の不支給決定が認められた例も若干はあります。しかし、労務管理上の観点からも、こうした減額・不支給事由をあらかじめ規定しておくことが望ましいといえるでしょう。
2 事実関係究明のため退職金の支払いを留保することはできるか
就業規則や退職金規程で退職金について定める場合は、退職金の支払い期日についても必ず定めておかなければなりません。その場合、労働基準法23条1項の「労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があった場合においては、7日以内に賃金を支払わなければならない」との定めの適用は受けないため、支払い期日は任意に定めることができます。就業規則等に退職金の支払い時期が定められていれば、権利者の請求があったとしても、賃金と同じように7日以内に支払う必要はありません。就業規則で定める支払い期日については、必ずしも支給月日まで特定しておく必要はなく、例えば、「退職金は、原則として退職の日から1カ月以内に支給する」などのように、退職の日から一定期間以内の期間に支払うとする定め方でも差し支えありません。
こうした定めがあれば、その間に事実関係究明のための調査をすることは可能かと思われますが、それでも退職金支払期日まで時間的に余裕がないといった事態が生じることも考えられます。
労働基準法23条2項では、労働者の請求がある場合にも、使用者が異議のある部分の支払いを留保することは認めていますが、さらに支払いを留保する根拠を明確にするためには、「会社が必要と認める調査を実施する間、支払いを留保できる」といった定めをしておくことが望ましいと考えます。
□根拠法令等
・労基法23(金品の返還)、24(賃金の支払)
・昭26.2.27基収5483、昭63.3.14基発150(退職手当の支払時期)
□ 判例等
・在職中に懲戒解雇に匹敵する重大な背信行為を行った者の退職金請求権を否定した裁判例(平8.4.26東京地判・東京ゼネラル事件、平12.12.18東京地判・アイビ・プロテック事件)
1 退職後に判明した懲戒解雇事由をもとに退職金を不支給とするには
多くの事業所では、従業員が重大な非違行為をした場合の制裁として、懲戒解雇できる旨の規定を設けるとともに、懲戒解雇の場合には退職金を不支給とするか、またはその一部を減額できる旨の規定を設けています。
しかし、ご質問のケースでは、すでに労働者が退職しており、当事者間の雇用関係は終了しています。そのため、使用者による解雇すなわち雇用契約を終了させる旨の意思表示は、その対象を失っているために意味を持たず、懲戒解雇することは不可能です。したがって、懲戒解雇を理由として退職金の不支給または減額を行うことはできないということになります。
そうすると、就業規則や退職金規程でその支給条件等が明確に定められた退職金は、労働基準法上の賃金として扱われますので、通常支払う額を全額支給しなければなりません。支給条件や支給額の算定方法が定められている退職金は、労働者にとって賃金債権となり、恣意的に減額したり支払わなかったりすることはできないからです。
そこで、実務上の対応としては、あらかじめ就業規則や退職金規程において、「懲戒解雇の場合」に加えて、「懲戒解雇に相当する事由が認められるとき」あるいは「退職金支給日までの間に在職中の行為について懲戒解雇事由が認められた場合」も、減額または不支給とすることがある旨を定めておき、ご質問のようなケースにおいて不支給等の決定をする際の契約上の根拠とすることが考えられます。
実際の裁判例では、このような減額・不支給事由が定められていない場合でも、労働者の在職中の非違行為が重大かつ悪質なものであれば、労働者の退職後になされた退職金の不支給決定が認められた例も若干はあります。しかし、労務管理上の観点からも、こうした減額・不支給事由をあらかじめ規定しておくことが望ましいといえるでしょう。
2 事実関係究明のため退職金の支払いを留保することはできるか
就業規則や退職金規程で退職金について定める場合は、退職金の支払い期日についても必ず定めておかなければなりません。その場合、労働基準法23条1項の「労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があった場合においては、7日以内に賃金を支払わなければならない」との定めの適用は受けないため、支払い期日は任意に定めることができます。就業規則等に退職金の支払い時期が定められていれば、権利者の請求があったとしても、賃金と同じように7日以内に支払う必要はありません。就業規則で定める支払い期日については、必ずしも支給月日まで特定しておく必要はなく、例えば、「退職金は、原則として退職の日から1カ月以内に支給する」などのように、退職の日から一定期間以内の期間に支払うとする定め方でも差し支えありません。
こうした定めがあれば、その間に事実関係究明のための調査をすることは可能かと思われますが、それでも退職金支払期日まで時間的に余裕がないといった事態が生じることも考えられます。
労働基準法23条2項では、労働者の請求がある場合にも、使用者が異議のある部分の支払いを留保することは認めていますが、さらに支払いを留保する根拠を明確にするためには、「会社が必要と認める調査を実施する間、支払いを留保できる」といった定めをしておくことが望ましいと考えます。
□根拠法令等
・労基法23(金品の返還)、24(賃金の支払)
・昭26.2.27基収5483、昭63.3.14基発150(退職手当の支払時期)
□ 判例等
・在職中に懲戒解雇に匹敵する重大な背信行為を行った者の退職金請求権を否定した裁判例(平8.4.26東京地判・東京ゼネラル事件、平12.12.18東京地判・アイビ・プロテック事件)
◆社員本人の同意があれば、貸付金の残額を退職金で相殺できるか
 当社では、社員に対する福利厚生施策の一環として、社員融資制度(貸付金制度)を独自に設けることを検討中ですが、制度を利用した社員が退職する際に、貸付金の残額を退職金で相殺することは可能でしょうか。
当社では、社員に対する福利厚生施策の一環として、社員融資制度(貸付金制度)を独自に設けることを検討中ですが、制度を利用した社員が退職する際に、貸付金の残額を退職金で相殺することは可能でしょうか。  退職する社員本人の同意があれば、退職金から貸付金の残額を一括して返済させることも可能です。ただし、その同意は、本人の完全な自由意思基づくものであることが客観的に認められる必要があります。
退職する社員本人の同意があれば、退職金から貸付金の残額を一括して返済させることも可能です。ただし、その同意は、本人の完全な自由意思基づくものであることが客観的に認められる必要があります。
■解説
1 前借金相殺の禁止(労基法17条)との関係
銀行等との提携ローンとは別に使用者が独自に融資制度(貸付金制度)を設けている場合において、当該制度を利用している労働者が退職する際に、その貸付金の残額を退職金で相殺することができるかどうかをめぐっては、退職金の支給条件が労働契約や就業規則、労働協約等によって明確化されている場合、その退職金は労働基準法11条でいう賃金に該当するため、同法17条の「使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない」という「前借金相殺の禁止」規定に抵触しないかが、まず問題になります。
この点について、行政解釈では、労働者が使用者から人的信用に基づいて受ける金融であって明らかに身分的拘束を伴わないものは、「労働することを条件とする前貸の債権」には当たらないとしています。
使用者からの住宅建設資金の貸付に対する返済金のように融資額および返済額ともに相当高額に上り、その返済期間も相当長期間にわたるものであっても、①貸付の原因が真に労働者の便宜のためのものであり、労働者からの申出に基づくものであること、②貸付期間は必要を満たしえる範囲であり、賃金や退職金などによって生活を脅威し得ない程度に返済可能であること、③返済前であっても退職の自由が制約されていないこと等、当該貸付金が身分的拘束を伴わないことが明らかである場合は、法17条には抵触しないと解されています。
2 全額払いの原則(労基法24条)との関係
また、「賃金支払五原則」の1つとして、労基法24条1項に「全額払いの原則」が定められていますが、使用者による賃金債権の相殺も、「全額払いの原則」が禁止する賃金の控除に該当するため、法11条でいう賃金に該当するところの退職金から貸付金の残額を控除することが同原則に抵触しないかということが、次に問題となります。
この点について、同原則への抵触を回避するためには、「当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる」(法24条1項ただし書後段)との定めに沿って、労使間で控除協定を締結しなければなりません。
この協定は「二四協定」などと呼ばれ、「三六協定」とは異なり、労働基準監督署への届出を必要としません。「二四協定」では、「退職時に貸付金等の未返済債務がある場合は、退職金から一括控除することができる」などというように、未返済債務を退職金で相殺することについての明確な定めがされていることが必要です。
この協定が結ばれることにより、労働者の合意を得ないで行う一方的な控除であれ、労働者の合意を得て行う控除であれ、労基法違反は回避されます。ただし、それは、「二四協定」が締結されていれば、退職金から未返済債務を控除しても違法にはならないという刑事免責がなされるということであり、相殺の民事的効力を生じせしめるには、本人の完全な自由意思基づくものであることが必要となります。
この場合の労働者の同意の意思表示は、厳密には、退職金支給時の意思表示であることが必要となります。したがって、実際に退職金から貸付金等の未返済債務を控除するには、「二四協定」が締結されている場合や、貸付時に退職金と未返済債務の相殺を取り決めた契約書を交わしている場合であっても、その都度、本人の同意が必要となります。
裁判例では、労働者がその自由な意思に基づき相殺を同意したものであると認めるに足りる合理的理由が客観的に存在するときは、その同意を得てした相殺は「全額払いの原則」に違反しないとの解釈を打ち出しており、その限りにおいては、協定に基づかない控除も許容されています。
3 相殺する場合の限度額について
相殺する場合の限度額については、労基法24条は協定に基づく控除についての限度額を設けておらず、行政解釈上も、控除される金額が賃金額の一部である限り控除額についての限度はないとされています。
ただし、民法510条及び民事執行法152条2項の規定により、退職金の額の4分の3に相当する部分については、使用者側から相殺することはできないとされているのため、使用者が労働者の同意を得ないで一方的に相殺を行う場合には、退職金の4分の1を超える額については控除できないということになります。
しかしながら、「二四協定」があり、かつ、労働者の同意がある場合はこの規定に服するものではなく、したがって、控除される金額が退職金の一部である限り、控除額についての限度はないという前記の行政解釈に立ち返るため、未返済額の全額を退職金と相殺しても差し支えありません。
□根拠法令等
・労働基準法17(前借金相殺の禁止)、24(賃金の支払)①(全額払いの原則)
・昭22.9.13 発基1、昭33.2.13 基発90(前借金相殺の禁止の趣旨)
・昭29.12.23基収6185号、昭63.03.14基発150(控除額の限度)
・民法510(差押禁止債権を受働債権とする相殺の禁止)
・民事執行法152(差押禁止債権)②(退職手当)
□ 判例等
「使用者が労働者の同意を得て労働者の退職金債権に対してする相殺は、この同意が労働者の自由な意思に基づいてなされたものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するときは、労働基準法二四条一項本文の全額払いの原則に違反しない」とされたもの。(平2.11.26 最二小判・日新製鋼事件)
・内容についての無断転載は固くお断りいたします。
◆早出についても割増賃金を支払う必要があるか
 当社の1日の所定労働時間は、午前9時から午後5時まで(休憩1時間)の7時間です。社員が午後5時を超えて残業した場合には、残業手当を支払っていますが、午前9時前に早出出勤をした場合も、割増賃金を支払う必要があるのでしょうか。
当社の1日の所定労働時間は、午前9時から午後5時まで(休憩1時間)の7時間です。社員が午後5時を超えて残業した場合には、残業手当を支払っていますが、午前9時前に早出出勤をした場合も、割増賃金を支払う必要があるのでしょうか。また、朝2時間遅刻した社員が、その日2時間残業した場合には、その残業に対して割増賃金を支払う必要があるのでしょうか。
 いわゆる早出出勤も、時間外労働となります。したがって、早出の場合も、1日の所定労働時間を超えて労働した場合は、その時間に対して時間外手当を支払う必要があります。さらに、その日の労働時間が法定労働時間(8時間)を超えた場合は、超えた時間に対して割増賃金を支払う必要があります。
いわゆる早出出勤も、時間外労働となります。したがって、早出の場合も、1日の所定労働時間を超えて労働した場合は、その時間に対して時間外手当を支払う必要があります。さらに、その日の労働時間が法定労働時間(8時間)を超えた場合は、超えた時間に対して割増賃金を支払う必要があります。一方、2時間遅刻し、所定就業時刻を超えて2時間残業した労働者は、働いた時間の長さは通常の日と同じであるため、割増賃金を支払う必要はありません。
■解説
1 早出出勤にも割増賃金を支払う必要があるか
ご質問の前段は、早出出勤に対しても割増賃金を支払う必要があるかということですが、貴社の所定労働時間は7時間とのことですので、早出・残業を問わず、7時間を超えて労働させた時間は時間外労働となり、原則として、通常の労働時間に対して支払うべき賃金を払わなければなりません。ただし、労働協約や就業規則によって、1日8時間(休憩時間を除く)までの1時間について、別に定めた賃金額がある場合は、それを支払うことで足ります。この点について、行政解釈では、「法定労働時間内である所定労働時間外の1時間については、別段の定めがない場合には原則として通常の労働時間の賃金を支払わなければならない。但し、労働協約、就業規則等によって、その1時間に対し別に定められた賃金がある場合にはその別に定められた賃金額で差し支えない」としています。
次に、早出勤務した時間も含め1日の労働時間が8時間を超えた場合についてですが、その場合は、その超えた時間については、通常の賃金のほかに2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。
つまり、早出した時間に対して割増賃金を支払わねばならないのではなく、早出をした結果、その日の労働時間が8時間を超えたときに、割増賃金を支払わねばならないということです。
2 遅刻した日に残業した場合、その残業に対して割増賃金を支払う必要があるか
ご質問の後段は、遅刻した時間と残業した時間を相殺することが可能かという問いに言いかえることもできるかと思いますが、これについても同様の考え方が成り立ちます。その日の実労働時間が所定労働時間である7時間を超えない限りは、必ずしも残業手当を支払う必要はなく、また、法定労働時間である8時間を超えない限りは、必ずしも割増賃金を支払う必要はありません。遅刻した時間と残業時間を相殺することは可能であるということです。
したがって、ご質問にある社員のように、2時間遅刻した日に所定終業時刻を超えて2時間残業した場合は、その日に働いた時間(実労働時間)は通常の日の労働時間(所定労働時間)と同じであるため、残業手当および割増賃金を支払う必要は原則としてありません。
ただし、就業規則等で「終業時刻後に労働した場合には時間外労働として扱い、割増賃金を支払う」などの定めがある場合には、終業時刻以降の労働に対しては割増賃金を支払わなければならず、相殺することはできません。
以上がご質問のケースに対する回答ですが、例えば、労働者がより大幅な遅刻をしたために、労働時間が深夜業の時間帯(午後10時から午前5時)に及んだ場合は、実労働時間が8時間以内であっても、深夜業の時間帯の労働時間については、通常の賃金のほかに2割5分以上の率で計算した深夜労働割増賃金を支払わなければなりませんので、この点はご留意ください。
□根拠法令等
・労基法37(時間外、休日および深夜の割増賃金)
・昭23.11.4基発1592(法定内の所定時間外労働に対する賃金)
・内容についての無断転載は固くお断りいたします。
◆法定休日に8時間を超えて労働した場合、6割増の割増賃金を支払う必要があるか
 当事業所の所定労働時間は8時間ですが、法定休日に8時間を超えて労働した社員がいる場合、その8時間を超えた時間分については、休日割増分の3割5分増に時間外割増分の2割5分増を加えた、6割増以上の率で計算した割増賃金を支払う必要があるのでしょうか。
当事業所の所定労働時間は8時間ですが、法定休日に8時間を超えて労働した社員がいる場合、その8時間を超えた時間分については、休日割増分の3割5分増に時間外割増分の2割5分増を加えた、6割増以上の率で計算した割増賃金を支払う必要があるのでしょうか。
また、法定休日の労働が深夜に及んだ場合は、その深夜の時間帯の労働時間については、割増賃金はどのように計算すればよいのでしょうか。  所定労働時間が8時間である場合、法定休日に8時間を超えて労働させたときの割増賃金は、その労働が深夜に及ばない限り、3割5分増の割増賃金を支払えば足ります。
所定労働時間が8時間である場合、法定休日に8時間を超えて労働させたときの割増賃金は、その労働が深夜に及ばない限り、3割5分増の割増賃金を支払えば足ります。
その休日労働が深夜に及んだ場合は、深夜の時間帯の労働時間については、休日割増分の3割5分増に深夜割増分の2割5分増を加えた、6割増以上の率で計算した割増賃金を支払う必要があります。
■解説
1 休日労働が8時間を超えた場合の取り扱い
労働基準法37条1項では、「労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間またはその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない」とされており、「政令」(割増賃金令)では、休日の労働については3割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならないとされています。
そこで、ご質問にあるように、法定休日(週1回または4週間を通じ4日の休日)に8時間を超えて労働させた場合は、その超えた時間分については、休日割増分の3割5分増に時間外割増分の2割5分増を加えた、6割増以上の率で計算した割増賃金を支払う必要があるのかということが疑問となります。
この場合、そもそも休日には、いわゆる所定労働時間という概念はありませんので、その休日労働が深夜(午後10時から午前5時までの時間帯)に及ぶことがない限り、8時間を超えた場合でも、休日割増分の3割5分増の増賃賃金を支払えば足ります。
2 休日労働が深夜に及んだ場合などの取り扱い
その休日労働が深夜に及んだ場合は、休日においても深夜労働という概念は除外されていないため、深夜の時間帯の労働時間分について、休日割増分の3割5分増に深夜割増分の2割5分増を加えた、6割増以上の率で計算した割増賃金を支払う必要があります。
また、平日の時間外労働が休日に及んだ場合は、その休日が法定休日であれば、たとえ前日からの勤務の継続であっても、午前0時からは前日の時間外労働としてではなく、休日労働として取り扱います。したがって、午前0時以降の休日労働の時間については3割5分増以上の率で計算した休日割増賃金を支払う必要があります。さらに、前日(平日)の午後10時から当日(休日)午前5時までの間の時間は深夜労働に該当するため、休日の午前0時から午前5時までの間の時間についても、休日割増分の3割5分に深夜割増分2割5分を加えた6割増以上の率で計算した割増賃金を支払う必要があることになります(下図参照)。
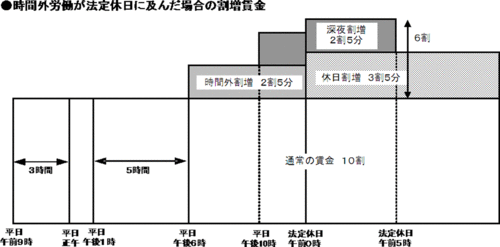 □根拠法令等
□根拠法令等
・労働基準法37(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
・労働基準法第37条第1項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令
・労働基準法施行規則20②(休日深夜業の割増賃金)
・内容についての無断転載は固くお断りいたします。
◆所定労働時間が短い日に休業した場合も、平均賃金の6割の休業手当が必要か
 当社には、1週のうち特定の曜日の所定労働時間が通常の日の所定労働時間より短いけ社員がいます。先日、会社施設の増改築工事のため社員に対し休業を命じましたが、その社員については、4時間の勤務が予定されていた日でした。そのため、この社員の休業手当の計算をしたところ、平均賃金の60%相当額が4時間分の時給を上回る結果となりました。
当社には、1週のうち特定の曜日の所定労働時間が通常の日の所定労働時間より短いけ社員がいます。先日、会社施設の増改築工事のため社員に対し休業を命じましたが、その社員については、4時間の勤務が予定されていた日でした。そのため、この社員の休業手当の計算をしたところ、平均賃金の60%相当額が4時間分の時給を上回る結果となりました。
こうした場合でも、平均賃金の60%を休業手当として支払う必要があるのでしょうか。4時間分の時給または4時間分の時給の60%の支払いで済ませることはできないでしょうか。  所定労働時間が短い日に使用者の責めによる事由で休業し、平均賃金の60%が当該日の所定労働時間分の時給を上回る場合においても、平均賃金の60%以上を休業手当として支払う必要があります。ご質問のケースにおいても、4時間分の時給または4時間分の時給の60%の支払いで済ませることはできません。
所定労働時間が短い日に使用者の責めによる事由で休業し、平均賃金の60%が当該日の所定労働時間分の時給を上回る場合においても、平均賃金の60%以上を休業手当として支払う必要があります。ご質問のケースにおいても、4時間分の時給または4時間分の時給の60%の支払いで済ませることはできません。
■解説
1 休業手当
労働基準法26条では、「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない」と定めています。
「使用者の責に帰すべき事由」には、使用者の故意、過失による休業はもちろん、経営上の理由による休業も含まれます。したがって、天災地変等の不可抗力による休業までは含まれませんが、事業所の移転や施設の増改築による一時休業の場合は、「使用者の責に帰すべき休業に該当する」ものとされ、休業した日について平均賃金の100分の60以上の休業手当を支払わなければなりません。
休業手当の算定基礎となる平均賃金について、労働基準法12条1項は、「平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう」としており、さらに2項では、「前項の期間は、賃金締切日がある場合においては、直前の賃金締切日から起算する」と定めています。
当該日以前3ヵ月間に支払われた賃金の総額を総日数で除するため、当該休業日の所定労働時間が通常の日の所定労働時間より短い場合には、ご質問のように、平均賃金の100分の60が、当該日の賃金額を上回ることもあり得ることになります。
2 休業手当の額が休業日の賃金を上回る場合の取り扱い
そこで、4時間の勤務が予定されていた日に休業を命じ、平均賃金の100分の60相当額が4時間分の時給を上回る結果となった場合においても、平均賃金の100分の60を休業手当として支払う必要があるのかというのがご質問の内容ですが、休業手当の趣旨は、平均賃金の100分の60以上に相当する金額の支払いを、使用者に罰則をもって強制することにより、労働者の保護を図ろうとしたものです。したがって、こうした場合でも、平均賃金の100分の60以上に相当する金額を支払わなければならないということになります。
ご質問のケースにおいても、4時間分の時給または4時間分の時給の100分の60の支払いで済ませることはできません。解釈例規においても、「一週中のある日の所定労働時間が、たまたま短く定められていても、その日の休業手当は、平均賃金の100分の60に相当する額を支払わなければならない」とされています。
□根拠法令等
・労働基準法26(休業手当)、21(平均賃金)
・昭27.8.7 基収3445(休業期間が一労働日に満たない場合の休業手当の額)
・内容についての無断転載は固くお断りいたします。
◆年俸制で欠勤控除する場合は、どのように計算すればよいか
 当社では、契約社員に年俸制を適用していますが、その形態は、16分の1ずつを月例給として支払い、残りの16分の4を、いわゆる賞与として7月と12月に支給するというものです。この賞与分については、7月支給分は16分の2で固定し、12月支給分は、業績に応じて16分の1.5から16分の2.5の範囲で変動させる仕組みとなっています。
当社では、契約社員に年俸制を適用していますが、その形態は、16分の1ずつを月例給として支払い、残りの16分の4を、いわゆる賞与として7月と12月に支給するというものです。この賞与分については、7月支給分は16分の2で固定し、12月支給分は、業績に応じて16分の1.5から16分の2.5の範囲で変動させる仕組みとなっています。
このような年俸制でも欠勤控除をすることは可能でしょうか。また、その場合は、どのように計算すればよいのでしょうか。  年俸制でも、特約を定めれば、欠勤控除をすることが可能です。ただし、その方法については、あらかじめ就業規則(給与規程)または雇用(労働)契約書に定めておく必要があります。欠勤控除の計算する場合には、年間平均所定労働日数を算定基礎とする方法や、暦日数を算定基礎とする方法などがあります。
年俸制でも、特約を定めれば、欠勤控除をすることが可能です。ただし、その方法については、あらかじめ就業規則(給与規程)または雇用(労働)契約書に定めておく必要があります。欠勤控除の計算する場合には、年間平均所定労働日数を算定基礎とする方法や、暦日数を算定基礎とする方法などがあります。
■解説
1 年俸制において欠勤控除は可能か
労働契約は、労働者が使用者に対して労務を提供し、使用者がその対価として賃金を支払うというものですが、労務の提供がない場合には、賃金請求権も発生しないことになります。これは、「労務の提供がなかった時間(=不就労時間)に対応する賃金は支払われない」という、いわゆる「ノーワーク・ノーペイの原則」によるものです。
労働基準法24条1項では、賃金の支払いについて「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」と定めていますが、労働者の都合による欠勤や遅刻、早退に関し、その日数あるいは時間に応じて賃金を控除することは、全額払いの原則に違反するものではありません。
年俸制は、年を単位に賃金を決める制度ですから、通常は日割り計算や欠勤控除を想定していないことが多いようです。ただし一方で、年俸制というのはあくまでも、月給制、日給月給制、日給制、時間給制などと同じく賃金計算方法の1つにすぎないため、欠勤控除についての考え方そのものは他の制度と異なるものではありません。
年俸制における年俸額は、年間を通じて労務の提供があることを前提に定められているため、就業規則(給与規程)または雇用(労働)契約書に欠勤控除の定め(特約)をすれば、ノーワーク・ノーペイの原則に基づいて給与額を控除することができます。
2 欠勤控除の計算方法
年俸制のもとで欠勤控除の定めをする場合は、まず、欠勤控除の対象とする給与の範囲について、月例給のみを対象とするのか、あるいは年俸の総額を対象とするのかを定める必要があります。ご質問のケースでは、年俸の16分の1を月例給で支給し、残りのうち16分の2を7月賞与時に、さらに残りは16分の1.5から16分の2.5の範囲で業績に応じて12月賞与時に支給するとのことです。
労働基準法24条の解釈例規において、「賞与とは、定期または臨時に、原則として労働者の勤務成績に応じて支給されるものであって、その支給額が予め確定されていないものをいう」とされています。この解釈例規に照らすと、7月支給分の16分の2については、名目は賞与ですが、年俸の一部を賞与として支給しているだけであると考えられますので、欠勤控除の対象とすることも可能であると考えます。
一方、12月支給分については支給額が変動するため、あらかじめその額が予定されているものとはいえず、欠勤控除から除外すべきではないかと考えます。
次に、欠勤1日についてどのような計算方法で控除をするかですが、賞与分を含めて欠勤控除の対象とする場合には、①年間の所定労働日数分の1を控除する方法、②365分の1を控除する方法が考えられます。月例給についてこのいずれかの計算で控除を行ったうえで、賞与時の支給額について実労働日数で案分したものを控除するといったことも可能であると考えます。
また、月例給のみを対象とする場合は、①当該月の所定労働日数分の1を控除する方法、②当該月の暦日数分の1を控除する方法、③1年間の月平均所定労働日数分の1を控除する方法が考えられますが、年俸制であるということを考慮した場合、③の方法がより適切であると思われます。
実務上においては、給与計算事務が煩雑になることを避けるとともに、賃金の支払い形態によって公平さを欠くことがないように留意してください。
□根拠法令等
・民法624①(報酬を支払う時期)
・労基法24(賃金の支払)
・昭22.9.13 基発17(賞与の意義)
・内容についての無断転載は固くお断りいたします。
◆「出勤停止以上の処分を受けた者については、賞与を支給しない」と定めることは可能か
 当社では、社員に支給する賞与の金額は、対象期間における出勤状況や貢献度、営業成績などに基づき決定していますが、就業規則(賞与規程)において、「出勤停止以上の処分を受けた者については、賞与を支給しない」と定めることは可能でしょうか。
当社では、社員に支給する賞与の金額は、対象期間における出勤状況や貢献度、営業成績などに基づき決定していますが、就業規則(賞与規程)において、「出勤停止以上の処分を受けた者については、賞与を支給しない」と定めることは可能でしょうか。  貴社において、これまでどのようなかたちで賞与が支給されてきたかによる部分はありますが、本来の賞与額から大幅に減額したり、全額を不支給としたりすることを定めることは、そうした定め自体が違法となる可能性が高いとみていいでしょう。
貴社において、これまでどのようなかたちで賞与が支給されてきたかによる部分はありますが、本来の賞与額から大幅に減額したり、全額を不支給としたりすることを定めることは、そうした定め自体が違法となる可能性が高いとみていいでしょう。
■解説
1 賞与の性格と支払い義務
賞与とは、一般に、給与とは別に年末や夏期に支給される一時金のことをさしますが、労働基準法上の賞与の取扱いは、「定期又は臨時に、原則として労働者の勤務成績に応じて支給されるものであって、その支給額が予め確定されていないもの」とされています。つまり賞与は、毎月支給される給与などとは異なり、労働契約上の債務にあたるものではないため、必ず支給しなければならないという性格のものではありません。その支給基準、支給額、計算方法、支給期日、支給対象者などの決定も労使にゆだねられており、原則として、事業主が任意に決定できるものです。
賞与を支給するか否かや、どのような基準で支給するかなどについて、労働契約、就業規則、労働協約等に定めがなく、これまで支払われてきた賞与が、もっぱら使用者の任意により、労働者の勤務成績などに応じて支給したりしなかったりしたものであれば、それは恩恵的給付であるといえますので、出勤停止以上の処分を受けた者について賞与を支給しないことも、可能であると考えられます。
しかし、賞与を制度として設け、算定期間、支給基準、支給額、計算方法、支給期日、支給対象者などについての定めている場合は、労働基準法上の賃金としての性格を有し、その定めによって支給しなければなりません。
(この場合の賞与は「臨時の賃金」であり、賞与に関する事項は、就業規則の相対的必要記載事項になるため、算定期間、支給基準、支給額、計算方法、支給期日、支給対象者などについての定めをした場合は、その定めをした限りにおいて、就業規則に記載しておく必要があります。)
2 賞与と「減給の制裁」の関係
また、賞与は、原則として労働者の勤務成績に応じて支給されるものであるため、事業主の一定の裁量の範囲内で、社員個々の成績考課をもとに支給額を増減することは、査定制度の範囲内のこととして当然に認められるべきものです。
労働基準法第91条にある「就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない」という「減給の制裁」の制限は、あくまで懲戒処分に関する制限であり、懲戒処分を受けたことを理由として賞与査定が低くなり、その結果が賞与額に反映されたのであれば、これはまた別の問題です。
成績考課の要素に何を加えるかは、それが合理的なものである限りは、使用者の自由であるといえ、懲戒処分を受けたことが成績考課に加味されて、その結果として支給額が減じられることは、使用者の裁量の範囲内において認められるものです。
3 賞与を全額不支給とすることの可否について
それでは、ご質問にあるように、「出勤停止以上の処分を受けた者については、賞与を支給しない」と定めることは可能かということについて考えてみます。
前述のように、賞与の評価査定において懲戒処分を受けたことを加味することは、使用者の裁量の範囲内において認められるため、評価査定により算定された基準額が、通常の評価における支給額より低い額となることは、十分に考えられます。
また、賞与の支給額を決定する際には、対象期間中の欠勤日数から出勤係数を求め、評価査定により算定された基準額に出勤係数を乗じることで支給額を決定するというやり方が一般的ですが、こうした方法を用いている場合に、出勤停止期間を欠勤として扱うことは差し支えありません。
しかし、「懲戒処分を受けた者には賞与を全額支給しない」などの定めをすることは、これらの部分を超えて減額が行われる可能性が高いと考えられ、これは、減給の制裁の限度を超えるものであり、使用者の裁量の範囲を逸脱しているとみなされるおそれがあります。
また、算定期間中に労務を提供したにもかかわらず賞与を全額不支給とすることは、賞与の賃金性を全面否定することにもなり、通常は認められるものではありません。
こうした観点からすると、貴事業所において、これまでどのようなかたちで賞与が支給されてきたかという"事案の個性"による部分は大きいのですが、一般的には、賞与を不支給とする定めは、使用者の裁量の範囲を超えるものであり、そうした「定め」そのものが違法となるとみてよいでしょう。
裁判例においても、「減給処分を行うことを実質的な理由として賞与を全く支給しないと定めることは、やはり賞与の賃金であることを否定することになり、法第91条(減給の制裁の制限規定)に反することになる」(昭50.3.14 札幌地判室蘭支部・新日鉄室蘭製鉄所事件)としたものがあります。
□根拠法令等
・労基法89(作成及び届出の義務)・91(制裁規定の制限)
・昭22.9.13発基17(賞与の意義)
□判例等
・「出勤停止処分を受けた者は賞与の受給資格がない」という定めを無効とした裁判例
(昭50.3.14 札幌地判室蘭支部・・新日鉄室蘭製鉄所事件)
「会社主催の成人祝賀会に出席した際に、ビンを壁に投げつける、アジ演説をする等の妨害活動を行なった労働者らが、就業規則に基づき条件付出勤停止処分に付され賞与、定昇分の賃金を支払われなかったので、当該懲戒処分の無効確認および未払賃金の支払を請求した事例」において、労働協約にあった「出勤停止処分を受けた者は賞与の受給資格がない」という定めについて、「企業への貢献度を一切考慮することなく、一律に無資格者と定め、不完全受給資格者と比べ極めてきびしく取り扱われているものであり、右条項は労使間の協定という形式をとってはいるものの実質的には懲戒事由該当を理由としてこれに対する制裁を定めたものと言わざるを得ない」として、「労基法第91条違反を理由に無効」としたもの。
・内容についての無断転載は固くお断りいたします。
◆賞与の支給が通常より遅れた場合、支給日に在籍していない者にも支払わなければならないか
 当社では、今回の賞与の額について労使の交渉が長引き、賞与の支給が、本来の支給日から1ヵ月遅れてしまいました。
当社では、今回の賞与の額について労使の交渉が長引き、賞与の支給が、本来の支給日から1ヵ月遅れてしまいました。
本来の支給日以降、実際の支給日の前日までの間に退職した社員がいますが、当事業所の就業規則(賞与規程)では、「賞与は支給日の前月末日までに入社し、支給日当日において当社に在籍する者に対して支給する」となっています。
この場合、この退職者は、実際の支給日には在籍していなかったことになりますが、このような場合でも、その者に賞与を支払う必要はあるのでしょうか。  本来の賞与の支給日に在籍していたのであれば、ご質問の退職者には賞与支払請求権があり、たとえ実際の支給日には在籍していなかったとしても、賞与を支払う必要があります。
本来の賞与の支給日に在籍していたのであれば、ご質問の退職者には賞与支払請求権があり、たとえ実際の支給日には在籍していなかったとしても、賞与を支払う必要があります。
■解説
1 賞与の支給日在籍要件規定の適法性
賞与も賃金の一種ですが、労働基準法上は、「定期又は臨時に、原則として労働者の勤務成績に応じて支給されるものであって、その支給額が予め確定されていないもの」(昭22.9.13発基17)とされています。したがって、賞与は労働契約上の債務にあたらず、必ず支給しなければならないものではありませんが、労働基準法第89条第4号の「臨時の賃金」に該当し、就業規則の相対的必要記載事項になります。そのため、賞与制度を設ける場合には、その算定期間、支給基準、支給額、計算方法、支給期日、支給対象者などについての定めを就業規則に記載しておく必要があります。
賞与の支給対象者は、労使間での取り決めにゆだねられています。したがって、貴社のように、賞与の算定対象期間中に勤務していても、支給日に在籍しない者には支給しない旨(これを「支給日在籍要件既定」という)が就業規則(賞与規程)等で定められている場合は、賞与の支給日前に退職した者や解雇された者に賞与を支給しなくても差し支えないと解されます。
ただし、労働者側に何ら解雇される事由がないのにもかかわらず、専ら賞与の不支給を目的として支給日の直前に解雇したような場合は、そうした解雇そのものに合理性がなく、したがって賞与の不支給も違法になることはいうまでもありません。
2 賞与の支給が例年より遅れた場合の考え方
それでは、ご質問のように、労使の交渉が長引いたなどの理由で賞与の支給額の決定が遅れ、支給が例年より遅れた場合はどうでしょうか。
こうした場合、本来の支給日までに在籍していた者に対し、実際の支給日に在籍していないことを理由に賞与を支給しないということは、労働者の既得の権利を一方的に奪うことになります。したがって、本来の支給日に在籍していた者に対しては、実際の支給日の前に退職していたとしても、賞与は支払わなければなりません。
就業規則(賞与規程)等で賞与支給日が特定されていない場合は、実際の支給日に在籍していない者に賞与を支払うかどうかは、一応は使用者の任意であると考えられますが、慣行として一定期日(たとえば6月中と12月中など)に支払われている場合は、その月に在籍していた者には賞与を支払う必要があると考えられます。
裁判例では、慣行上それまでに6月末に支払われてきた賞与が、当年度は労使交渉の難航により9月に支給されることになり、7月以降の退職者がその支給対象から除外されたという事案について、労使協定により9月の支給日在籍者を支給する旨の合意がなされていたとしても、労使の支給対象に関する慣行に反するものであると同時に、本来ならば受給できたはずの退職者の賞与受給権を一方的に奪うものであり、当該労使協定の効力は、退職者本人の同意がない限り及ばないとしています(昭59.8.27東京高判・ニプロ医工事件)。
ですから、ご質問のように就業規則(賞与規程)で賞与支給日が特定されている場合は、本来の支給日までに在籍していた社員は、その時点で支給額が決まっていなくとも賞与請求権を有するに至っており、退職者の同意なく、これをさかのぼって失わせることはできないということになります。
□根拠法令等
・労基法11(定義)・89(作成及び届出の義務)
・昭22.9.13発基17(賞与の法的意義)
□判例等
・賞与支給前に懲戒解雇された者の賞与請求権を否定した裁判例
(昭和58.4.20東京高判・ヤマト科学事件)
・賞与支給日が定められた日より大幅に遅れた場合の支給日在籍要件を否定した裁判例
(昭59.8.27東京高判・ニプロ医工事件、昭60.3.12最高裁第三小法廷判決もこれを支持)
・内容についての無断転載は固くお断りいたします。
◆社員の同居の家族が感染症にかかったため当該社員を自宅待機させる場合、休業手当を支払う必要はあるか
 この冬は新型インフルエンザの流行が蔓延するおそれがあると、マスコミ等で報じられていますが、当事業所では、介護福祉事業という業務の性質上、職員と同居の家族が新型インフルエンザ等の感染症にかかった場合、当該職員を「保健所の判断がなくても原則として自宅待機とする」ことを就業規則に定めようと考えています。
この冬は新型インフルエンザの流行が蔓延するおそれがあると、マスコミ等で報じられていますが、当事業所では、介護福祉事業という業務の性質上、職員と同居の家族が新型インフルエンザ等の感染症にかかった場合、当該職員を「保健所の判断がなくても原則として自宅待機とする」ことを就業規則に定めようと考えています。
この場合、当該職員の休業の期間については、賃金や休業手当を支払う必要はあるでしょうか。  保健所等行政による休業の場合は「賃金」「休業手当」とも支払う必要はないと考えられますが、行政の判断を待たずに"事業所独自の判断で命じた休業"については、「使用者の責めに帰すべき事由による休業」に該当すると解され、少なくとも「休業手当」の支払いが必要とされる可能性があります。
保健所等行政による休業の場合は「賃金」「休業手当」とも支払う必要はないと考えられますが、行政の判断を待たずに"事業所独自の判断で命じた休業"については、「使用者の責めに帰すべき事由による休業」に該当すると解され、少なくとも「休業手当」の支払いが必要とされる可能性があります。
■解説
1 職員本人に感染が確認され、本人を自宅待機とした場合
まず、職員本人が新型インフルエンザ等の感染症にかかったことが確認され、その職員を自宅待機にした場合、その間の「賃金」や「労基法第26条の休業手当」(平均賃金の6割以上)を支払う必要があるのかということについて解説します。
新型インフルエンザ等の罹患者に対しては、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(以下、「感染症予防法」)により、都道府県知事が入院あるいは外出自粛等を要請できるとされており、これに基づき保健所が行う要請に従った場合は、事業主が当該者を自宅待機にするまでもなく、その者は休務となります。
このように保健所等行政の要請により休んだ場合、この休業は、民法第536条第2項の「債権者(=使用者)の責めに帰すべき事由」による労務の受領拒否には該当しないため、「賃金」を支払う必要はありません。さらに、「休業手当」についても、"経営上の理由による休業"のような、労基法第26条の「使用者の責めに帰すべき事由による休業」ではないため、支払う必要はないということになります。
ただし、新型インフルエンザについては、国内で初めて感染が確認され、流行が拡大した年(平成21年)には、感染症予防法に基づく知事のこうした要請は出されるまでには至っておらず、法の根拠を持たない緩やかな休業の要請であったことに留意が必要です。そうした場合における罹患者の自宅待機の場合、一般的に、民法の定めに照らして「賃金」の支払いは必要ないと考えられますが、「休業手当」の要否については、当時の行政指導においては、個別具体的な事案の判断の権限は、事業所所在地所轄の労働基準監督署にあるとされ、確認を得ることが望ましいとされました。
2 職員の同居の家族に感染が確認され、当該職員を自宅待機とした場合
次に、ご質問のように、職員と同居する家族に感染が確認された場合は、その間の「賃金」や「休業手当」を支払う必要があるかどうかということについて解説します。
感染症予防法では、家族が新型インフルエンザ等にかかっている者などについて保健所等で調査を行い、「当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者」と判断された場合については、都道府県知事が外出自粛等の要請を行うこととしています。同居家族が罹患し、保健所から外出自粛等の要請が出され、これに従った場合は、事業主が自宅待機を命じるまでもなく、休務せざるを得ません。
このように保健所等行政の要請により休んだ場合は、職員本人が罹患し、行政の要請により休んだ場合と同様、「賃金」や「休業手当」を支払う必要はありません。
ただし、新型インフルエンザについては、前述のとおり、国内で初めて感染が確認され、流行が拡大した年(平成21年)には感染症予防法に基づく知事のこうした要請は出されておらず、罹患者と同居する家族に対する外出自粛などの要請も、明確には行われませんでした。
これに対して、各事業所は、仮にも事業所内に感染の可能性がある者が入ることのないよう、貴事業所が現在検討されているように、保健所の判断によらず各事業所のルールとして、自宅待機とすることが考えられます。
こうした、行政の判断を待たずに"事業所独自の判断で行う休業"については、その間の「賃金」までは支払う必要はないものの、少なくとも「休業手当」については必要とされる可能性があります。
実際の各事業所の対応としては、「賃金を通常通り支払う」「休業手当を支払う」の2通りのパターンが考えられますが、平成21年の新型インフルエンザ流行時には、「賃金を通常通り支払う」とする事業所が比較的多かったようです。これは、欠勤しても賃金を控除しない"完全月給制"を、もともと採用している事業所が少なからずあるということもありますが、同居の家族の感染に伴い、本人が働ける状態であるにもかかわらず休ませることについて、「特別休暇」とするなどして、本人の欠勤の場合とは異なる配慮をしたとも考えられます。ただし、"日給月給制"をとる事業所等において、当該日については「休業手当(のみ)を支払う」としても差し支えありません。
これに対し、行政の判断(保健所から外出自粛等の要請)を待たずに休業を命じる場合において、「賃金も休業手当も支払わない」とするのは、違法とされる可能性がありますので、ご注意ください。
□根拠法令等
・労基法26(休業手当)
・民法536条②(債務者の危険負担等)
・感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律18(就業制限)
・感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令11(就業制限)
・内容についての無断転載は固くお断りいたします。
◆退職者にも賃金改定後の新賃金との差額を遡及払いすべきか
 当社では、毎年4月に賃金の改定を行っており、4月分の賃金(4月25日支給)からベースアップおよび定期昇給後の賃金を支給しています(定期昇給は「一律の定額昇給」と「査定昇給」からなる)。
当社では、毎年4月に賃金の改定を行っており、4月分の賃金(4月25日支給)からベースアップおよび定期昇給後の賃金を支給しています(定期昇給は「一律の定額昇給」と「査定昇給」からなる)。
しかしながら、今年の場合は新賃金の決定が例年より遅れることが予想され、4月分は暫定的に旧ベースの賃金を支払い、新賃金決定後に差額を支給することを考えています。
こうした状況において、4月末日で退職予定の社員がおり、新賃金確定時には退職していることになりますが、この社員に対して退職後においてでも、賃金改定後の旧賃金と新賃金との差額を支払わなければ違法になるのでしょうか。  新賃金決定後、その支払対象を在職者のみとするか退職者を含めるかは、当事者の自由とされていますので、退職者を支払対象から除いても違法にはなりません。
新賃金決定後、その支払対象を在職者のみとするか退職者を含めるかは、当事者の自由とされていますので、退職者を支払対象から除いても違法にはなりません。
したがって、4月に遡及してベースアップや定期昇給(査定昇給)をした場合、その間の退職者に対して賃金の差額を支払う規定がない限りは、差額分を支払う必要はありません。
ただし、定期昇給分のうち、一律昇給の部分について就業規則(賃金規程)等で昇給額があらかじめ定められていて、当該額の昇給をまだ行っていない場合は、その差額を支払う必要があります。
■解説
1 遡及払いとベースアップ分の対象者
ベースアップや定期昇給を過去にさかのぼって実施し、賃金の支払日が経過した後、遡及したことによって生じた賃金を後日まとめて支払うことを「遡及払い」といいます。
賃金の遡及払いの必要が生じたときは、遡及することによって生じた各月の追加額の全額を、直後の賃金支払い日に支払わなければならず、その後の何ヵ月かに分割して支払うことはできません。
4月に遡及してベースアップした場合、ベースアップ決定前に退職した者に対しても差額を追加して支払うべきかどうか、つまり、遡及払いの対象を在職者のみとするか退職者を含めるかは、当事者の自由にゆだねられています。通達においても、「新給与決定後過去に遡及して賃金を支払うことを取決める場合に、その支払対象を在職者のみとするかもしくは退職者をも含めるかは当事者の自由である」(昭 23.12.4.基収 4092)とされています。
したがって、過去にさかのぼってベースアップを行う場合、支給日以前にすでに退職した者については遡及払いの対象から除く旨を、労働協約や就業規則等で定めることは差し支えありません。
仮に、退職者には賃金の差額を支払わないとする規定がなかったとしても、裁判例では、労働者の賃金昇給分の具体的支払請求権は「各年度毎に結ばれる賃金に関する協定において具体化されることによって、はじめて発生するもの」で、新賃金確定時にすでに退職した者は従業員としての地位を有しないので、協定の効果を受ける立場になく、新賃金と支給された賃金との差額分を請求ことはできないとされています(昭50.4.22大阪高判・淀川プレス製作所事件)。これは労働協約に関する裁判例ですが、その趣旨は就業規則(賃金規程)等に関しても同じく当てはまり、遡及分支払日前に退職した者には、賃金の差額を支払う規定がない限り、具体的支払請求権は発生していないということになります。
2 定期昇給分の遡及払いの対象
一方、定期昇給については、4月に在籍した者が遡及分支払日の前に退職した場合において、昇給の額があらかじめ労働協約や就業規則(賃金規程)等で具体的に規定されているにも関わらず、当該額の昇給をまだ行っていない場合は、退職者にもその差額を支払う必要があります。
定期昇給には一般に「一律昇給」と「査定昇給」があり、例えば「本給は、毎年4月にこれを1,000円昇給する」という規定が就業規則(賃金規程)等にあるとするならば、これは「一律昇給」を定めたものであり、遡及分支払日の前に退職した者も(本給昇給分1,000円の)遡及払いの対象となります。
一方、「職能給は、毎年4月に前年度の評価査定により改定する」といった規定が就業規則(賃金規程)等にあれば、これは「査定昇給」を定めたものであり、前掲の裁判例にもあるように、新「職能給」確定時にすでに退職した者については、この規定のみでは退職時に具体的な「職能給」昇給額が確定していたとは言えないため、新「職能給」と旧「職能給」の差額の請求権は発生しません。
したがって、ご質問に対する回答は、4月に遡及してベースアップや定期昇給(査定昇給)をした場合、その間の退職者に対して賃金の差額を支払うという規定がない限りは、差額分を支払う必要はありませんが、定期昇給分のうち、一律昇給の部分について就業規則(賃金規程)等で昇給額があらかじめ定められて、当該額の昇給をまだ行っていない場合は、その差額を支払う必要があるということになります。
なお、以上の点は、4月以降退職日までの割増賃金の算定に際しても適用されますのでご注意ください。
□根拠法令等
・労基法24①(全額払いの原則)
・昭 23.12.4.基収 4092(遡及賃金の支給対象)
□判例等
「賃金昇給分とこれに伴う退職金増額分の具体的な支払請求権は労働協約第64条の規定によって当然に発生しているとは認め難く、更に、各年度毎に結ばれる賃金に関する協定において具体化されることによって、はじめて発生するものと解するのが相当である」としたもの。(昭50.4.22大阪高判・淀川プレス製作所事件)
・内容についての無断転載は固くお断りいたします。
