〔48〕 退職金前払い(選択)制度の設計①-制度設計上の基本的なポイント
● 制度設計上の基本的な4つのポイント
① 基本的な考え方
「前払い制度」設計の標準的な考え方は、次の通りです。
例えば、勤続40年でモデル退職金額が1600万円の場合、1600万円÷40年で、1年当たり40万円となります。ただし、この40万円は支払われる時期がそれぞれ異なるので、各年分に一定の割引率で、それぞれの支払い期の残存勤務年数と同じ回数だけ割り戻し計算をします。それらの総和が、実際に支払われるべき額で、40年で割ると、年平均額が求められます。
年平均給付額=∑{40万円÷(1+割引率)残存勤務年数}÷40年
② 割引率の設定
ここで重要なのは「割引率」です。割引率は、大きく設定すると実支給額は小さくなり、小さく設定すると実支給額は大きくなります。コマツの例で見ると、2.5%を基準としています。これは、今後の平均昇給率を2.5%と見込んだとも言えますし、コマツの企業年金の予定利回りが(前払い制度導入時点で)2.5%であることに準拠したということでもあるようです。
③ 「前払い」給付の配分
年毎の給付配分の設定は、①勤続年数ベース、②等級(役割等級など)ベース、③給与などに連動した基準額ベース、などでの設定が考えられます。
①の勤続年数ベースを唯一の指標とした場合は、どうしても中途入社者は不利になります。それに対し、②の等級(役割等級など)ベースで設定すれば、勤務期間中の貢献度が反映され易くなり、ポイント制退職金制度と同じ考え方で、「評価反映型」の設計も可能になります。ただしその場合、これも評価反映型のポイント制退職金制度と同様、成果主義の度合いがかなり強まるため、受給格差が拡大し、現状の退職金カーブ(選択制において従来制度を選択した社員の積上げカーブ)との乖離が過大となる可能性があります。③の給与などに連動した基準額ベースは、コマツなどでも採用されていますし、年俸制導入企業では「年俸の何%」という決め方をしているところもあります。比較的わかり易い方法であるとともに、コマツのように基準額を大括りにし、上限額を設定することで、"分かり易さ"に加え"給付の抑制"を図ることができます。
給付の配分は、そこにどのような制度改定の趣旨を込めるかの決め手になります。主に若い社員を対象に考えるのであれば、従来制度に比べて若年層に意図的に厚めにします。
④ 税負担への配慮
「前払い制度」での給付は退職所得ではないため、当然ながら通常の退職所得のような税制優遇は無いのですが、その分を会社が補填するかどうかが課題となります。法的に定まったルールはなく、労使協議などで扱いを決めることになりますが、松下電器やコマツの「前払い」制度選択者が、新入社員のうち相当の割合を占めた要因の1つには、両社とも、この税負担見込み額を会社が肩代わり(補填)する仕組みであったことが挙げられています。
① 基本的な考え方
「前払い制度」設計の標準的な考え方は、次の通りです。
例えば、勤続40年でモデル退職金額が1600万円の場合、1600万円÷40年で、1年当たり40万円となります。ただし、この40万円は支払われる時期がそれぞれ異なるので、各年分に一定の割引率で、それぞれの支払い期の残存勤務年数と同じ回数だけ割り戻し計算をします。それらの総和が、実際に支払われるべき額で、40年で割ると、年平均額が求められます。
年平均給付額=∑{40万円÷(1+割引率)残存勤務年数}÷40年
② 割引率の設定
ここで重要なのは「割引率」です。割引率は、大きく設定すると実支給額は小さくなり、小さく設定すると実支給額は大きくなります。コマツの例で見ると、2.5%を基準としています。これは、今後の平均昇給率を2.5%と見込んだとも言えますし、コマツの企業年金の予定利回りが(前払い制度導入時点で)2.5%であることに準拠したということでもあるようです。
③ 「前払い」給付の配分
年毎の給付配分の設定は、①勤続年数ベース、②等級(役割等級など)ベース、③給与などに連動した基準額ベース、などでの設定が考えられます。
①の勤続年数ベースを唯一の指標とした場合は、どうしても中途入社者は不利になります。それに対し、②の等級(役割等級など)ベースで設定すれば、勤務期間中の貢献度が反映され易くなり、ポイント制退職金制度と同じ考え方で、「評価反映型」の設計も可能になります。ただしその場合、これも評価反映型のポイント制退職金制度と同様、成果主義の度合いがかなり強まるため、受給格差が拡大し、現状の退職金カーブ(選択制において従来制度を選択した社員の積上げカーブ)との乖離が過大となる可能性があります。③の給与などに連動した基準額ベースは、コマツなどでも採用されていますし、年俸制導入企業では「年俸の何%」という決め方をしているところもあります。比較的わかり易い方法であるとともに、コマツのように基準額を大括りにし、上限額を設定することで、"分かり易さ"に加え"給付の抑制"を図ることができます。
給付の配分は、そこにどのような制度改定の趣旨を込めるかの決め手になります。主に若い社員を対象に考えるのであれば、従来制度に比べて若年層に意図的に厚めにします。
④ 税負担への配慮
「前払い制度」での給付は退職所得ではないため、当然ながら通常の退職所得のような税制優遇は無いのですが、その分を会社が補填するかどうかが課題となります。法的に定まったルールはなく、労使協議などで扱いを決めることになりますが、松下電器やコマツの「前払い」制度選択者が、新入社員のうち相当の割合を占めた要因の1つには、両社とも、この税負担見込み額を会社が肩代わり(補填)する仕組みであったことが挙げられています。
〔49〕 退職金前払い(選択)制度の設計②-制度移行時および運用上の諸問題
● 制度移行時および運用上の諸問題
① 既得権分の扱い
新制度として導入する場合、移行時点までの勤務分の退職金相当額を保障するのが一般的ですが、そうした既得権分をA.一時金で前払いする方法と、B.退職時まで支払いを留保する方法があります。Aは、一時的に大きな給付原資が必要となることに加え、受給者にとっては一時所得として課税されてしまう、という問題があります。一方Bは、結局会社の退職給付債務として残ることの他に、支給時までの利息付与をすべきかどうかという問題が発生します。
② 中途での選択変更、在籍者の選択変更の扱い
新入社員のときに「前払い制」を選択したが、途中で従来制度へ乗り換えたいというケースや、あるいはその逆のケースも出てくる可能性があります。A.「前払い→通常」、B.「通常→前払い」の何れのケースも、給付額の計算上不利になる可能性が高いと言えます。更にBの場合は、①と同様、勤務中にいったん支払われた"退職金"が税法上の退職所得として認められるかが問題になりますが、一般的には認められない、ということになるかと思います。
これについては、松下電器が「前払い(選択)制」を在籍社員に適用拡大した際に、退職所得として当局から承認されたことがあります。松下の場合、'99年秋のみの公募だったのですが、このような一回性の場合は退職所得として認められる可能性がありますが、いつでも自由に"乗り換え"ができるような制度設計をした場合は、こうした扱いは受けられません。
こうした問題を避けるために、例えば選択制の場合、新入社員について入社時に選択希望を聞き、さらに受給権が発生する前に再度確認するなどの対応が必要であると考えられます。
③ 金利変動、退職金水準改定への対応
長期にわたって制度を運用している間に、経済・経営環境の変化により、割引率の根拠数字であったところの金利が大幅に変動したり、支給水準を見直さなければならないことがあるかもしれませんが、すでに「前払い」された分については、遡及して改定することはできません(社員にとっての有利不利はわかりません)。このことは、制度導入時によく周知しておくべきです。
④ 前払い給付の方法
前払い給付については給与に上乗せして支給するのが一般的ですが、賞与に上乗せしての支給や、年度末に別途一時金で支給する例もあります。社会保険料の料率を勘案しての措置であったのと(総報酬制の導入によりその意義は無くなりました)、「評価反映型」の場合には、半期ごとの評価を反映させるために、賞与支給時に上乗せ支給するケースが多いようです。
以上のような制度設計・運用上の問題の他に、「前払い制」を入れることで社員の会社に対する帰属意識が弱まること、退職理由によって給付額を変えるということはできなくなるということなどを、大前提として踏まえておく必要はあるかと思います。
① 既得権分の扱い
新制度として導入する場合、移行時点までの勤務分の退職金相当額を保障するのが一般的ですが、そうした既得権分をA.一時金で前払いする方法と、B.退職時まで支払いを留保する方法があります。Aは、一時的に大きな給付原資が必要となることに加え、受給者にとっては一時所得として課税されてしまう、という問題があります。一方Bは、結局会社の退職給付債務として残ることの他に、支給時までの利息付与をすべきかどうかという問題が発生します。
② 中途での選択変更、在籍者の選択変更の扱い
新入社員のときに「前払い制」を選択したが、途中で従来制度へ乗り換えたいというケースや、あるいはその逆のケースも出てくる可能性があります。A.「前払い→通常」、B.「通常→前払い」の何れのケースも、給付額の計算上不利になる可能性が高いと言えます。更にBの場合は、①と同様、勤務中にいったん支払われた"退職金"が税法上の退職所得として認められるかが問題になりますが、一般的には認められない、ということになるかと思います。
これについては、松下電器が「前払い(選択)制」を在籍社員に適用拡大した際に、退職所得として当局から承認されたことがあります。松下の場合、'99年秋のみの公募だったのですが、このような一回性の場合は退職所得として認められる可能性がありますが、いつでも自由に"乗り換え"ができるような制度設計をした場合は、こうした扱いは受けられません。
こうした問題を避けるために、例えば選択制の場合、新入社員について入社時に選択希望を聞き、さらに受給権が発生する前に再度確認するなどの対応が必要であると考えられます。
③ 金利変動、退職金水準改定への対応
長期にわたって制度を運用している間に、経済・経営環境の変化により、割引率の根拠数字であったところの金利が大幅に変動したり、支給水準を見直さなければならないことがあるかもしれませんが、すでに「前払い」された分については、遡及して改定することはできません(社員にとっての有利不利はわかりません)。このことは、制度導入時によく周知しておくべきです。
④ 前払い給付の方法
前払い給付については給与に上乗せして支給するのが一般的ですが、賞与に上乗せしての支給や、年度末に別途一時金で支給する例もあります。社会保険料の料率を勘案しての措置であったのと(総報酬制の導入によりその意義は無くなりました)、「評価反映型」の場合には、半期ごとの評価を反映させるために、賞与支給時に上乗せ支給するケースが多いようです。
以上のような制度設計・運用上の問題の他に、「前払い制」を入れることで社員の会社に対する帰属意識が弱まること、退職理由によって給付額を変えるということはできなくなるということなどを、大前提として踏まえておく必要はあるかと思います。
〔50〕 従来制度からの移行事例①-確定拠出年金と前払い退職金の選択パターン
● 確定拠出年金(日本版401k)の導入に際して発生する「前払い」
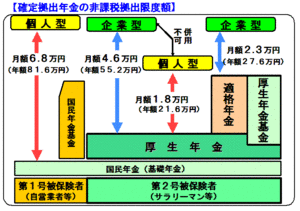 大手企業など先行企業では、退職給付制度(退職一時金・税制適格年金・厚生年金基金など)の改廃と、それに伴う確定拠出年金(日本版401k)の導入に際して、移行時点までの過去分が移行限度額を超える場合に超過分を一時金で支給したり、移行後の拠出金が非課税限度額を超過する場合に、超過分を毎月の給与に上乗せするなどのかたちでの「前払い」が一般的に行われています。
大手企業など先行企業では、退職給付制度(退職一時金・税制適格年金・厚生年金基金など)の改廃と、それに伴う確定拠出年金(日本版401k)の導入に際して、移行時点までの過去分が移行限度額を超える場合に超過分を一時金で支給したり、移行後の拠出金が非課税限度額を超過する場合に、超過分を毎月の給与に上乗せするなどのかたちでの「前払い」が一般的に行われています。
● 確定拠出年金(日本版401k)と前払い退職金の選択パターン
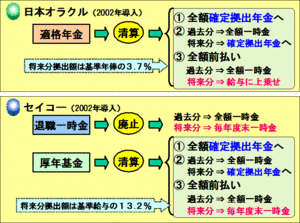 また将来分を含め「全額前払い」を選択できる制度を併せて導入するケースも見られます。(図参照)
また将来分を含め「全額前払い」を選択できる制度を併せて導入するケースも見られます。(図参照)
確定拠出年金は、原則として60歳にならなければ受給できないため、選択肢としての「前払い制度」を設けることで、社員の多様なニーズに応えようとするものと言えます。
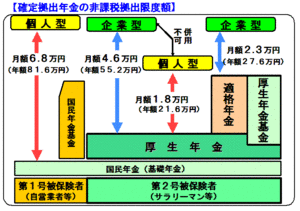 大手企業など先行企業では、退職給付制度(退職一時金・税制適格年金・厚生年金基金など)の改廃と、それに伴う確定拠出年金(日本版401k)の導入に際して、移行時点までの過去分が移行限度額を超える場合に超過分を一時金で支給したり、移行後の拠出金が非課税限度額を超過する場合に、超過分を毎月の給与に上乗せするなどのかたちでの「前払い」が一般的に行われています。
大手企業など先行企業では、退職給付制度(退職一時金・税制適格年金・厚生年金基金など)の改廃と、それに伴う確定拠出年金(日本版401k)の導入に際して、移行時点までの過去分が移行限度額を超える場合に超過分を一時金で支給したり、移行後の拠出金が非課税限度額を超過する場合に、超過分を毎月の給与に上乗せするなどのかたちでの「前払い」が一般的に行われています。● 確定拠出年金(日本版401k)と前払い退職金の選択パターン
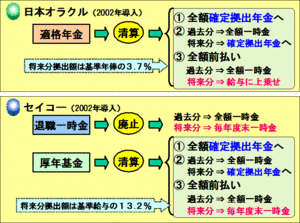 また将来分を含め「全額前払い」を選択できる制度を併せて導入するケースも見られます。(図参照)
また将来分を含め「全額前払い」を選択できる制度を併せて導入するケースも見られます。(図参照)確定拠出年金は、原則として60歳にならなければ受給できないため、選択肢としての「前払い制度」を設けることで、社員の多様なニーズに応えようとするものと言えます。
〔51〕 従来制度からの移行事例②-基金を脱退し、完全前払いに移行した事例
● 厚生年金基金を脱退し、完全前払いに移行した事例
 松井証券のように、適格年金を廃止し、業界の厚生年金基金も脱退して、「完全前払い制」に移行した事例もあります。'98年のインターネット取引進出後、中途採用が増え、移行時点での社員平均年齢が34歳と若く、また3分の2は入社3年以内だったという"有利さ"もあったかと思いますし、業界基金加入の大手会社が離脱(野村・日興・大和の何れもが確定拠出年金へ移行、山一は破綻)し、基金の財政が悪化したという"特殊事情"もあったようですが、一つ参考になるのではないかと思います。
松井証券のように、適格年金を廃止し、業界の厚生年金基金も脱退して、「完全前払い制」に移行した事例もあります。'98年のインターネット取引進出後、中途採用が増え、移行時点での社員平均年齢が34歳と若く、また3分の2は入社3年以内だったという"有利さ"もあったかと思いますし、業界基金加入の大手会社が離脱(野村・日興・大和の何れもが確定拠出年金へ移行、山一は破綻)し、基金の財政が悪化したという"特殊事情"もあったようですが、一つ参考になるのではないかと思います。
過去分を全額一時金で支払うことについて、通常は"退職所得"扱いにはなりませんが、社員全員をいったん解雇し、翌日に再び全員を採用するという"奇策"(?)を講じることで、当局には"退職所得"として承認されています。
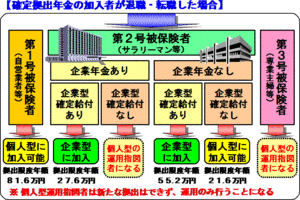 また、制度改定時の在籍社員も改定後の中途入社者も、「個人型」の確定拠出年金に加入することが可能になっています。これは、社員の多様なニーズに応えようとすると同時に、中途採用の多い業界で、転職者を受け入れ易くする施策であると考えられますが、人材流動性の高い中小企業などにおいては検討に値する選択肢ではないかと思います。
また、制度改定時の在籍社員も改定後の中途入社者も、「個人型」の確定拠出年金に加入することが可能になっています。これは、社員の多様なニーズに応えようとすると同時に、中途採用の多い業界で、転職者を受け入れ易くする施策であると考えられますが、人材流動性の高い中小企業などにおいては検討に値する選択肢ではないかと思います。
 松井証券のように、適格年金を廃止し、業界の厚生年金基金も脱退して、「完全前払い制」に移行した事例もあります。'98年のインターネット取引進出後、中途採用が増え、移行時点での社員平均年齢が34歳と若く、また3分の2は入社3年以内だったという"有利さ"もあったかと思いますし、業界基金加入の大手会社が離脱(野村・日興・大和の何れもが確定拠出年金へ移行、山一は破綻)し、基金の財政が悪化したという"特殊事情"もあったようですが、一つ参考になるのではないかと思います。
松井証券のように、適格年金を廃止し、業界の厚生年金基金も脱退して、「完全前払い制」に移行した事例もあります。'98年のインターネット取引進出後、中途採用が増え、移行時点での社員平均年齢が34歳と若く、また3分の2は入社3年以内だったという"有利さ"もあったかと思いますし、業界基金加入の大手会社が離脱(野村・日興・大和の何れもが確定拠出年金へ移行、山一は破綻)し、基金の財政が悪化したという"特殊事情"もあったようですが、一つ参考になるのではないかと思います。過去分を全額一時金で支払うことについて、通常は"退職所得"扱いにはなりませんが、社員全員をいったん解雇し、翌日に再び全員を採用するという"奇策"(?)を講じることで、当局には"退職所得"として承認されています。
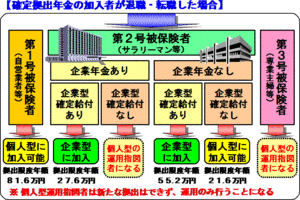 また、制度改定時の在籍社員も改定後の中途入社者も、「個人型」の確定拠出年金に加入することが可能になっています。これは、社員の多様なニーズに応えようとすると同時に、中途採用の多い業界で、転職者を受け入れ易くする施策であると考えられますが、人材流動性の高い中小企業などにおいては検討に値する選択肢ではないかと思います。
また、制度改定時の在籍社員も改定後の中途入社者も、「個人型」の確定拠出年金に加入することが可能になっています。これは、社員の多様なニーズに応えようとすると同時に、中途採用の多い業界で、転職者を受け入れ易くする施策であると考えられますが、人材流動性の高い中小企業などにおいては検討に値する選択肢ではないかと思います。〔52〕 新企業年金と退職金前払い制度-3つまたは2つ制度から社員が1つ選ぶ
● 3つの制度から社員が1つ選ぶ
今まで見てきたように、確定拠出年金(日本版401k)は、退職金前払い制度との併設が認められていますが、確定給付企業年金と合わせて実施することも可能です。(確定給付企業年金は、税制適格年金、厚生年金基金、企業型確定拠出年金、退職金前払い制度の何れとの併設可能です。ただし、適格年金は平成24年3月末を以って適格年金制度自体が無くなります。)
そうすると今後は、税制適格年金から、制度的に似ている確定給付企業年金への移行が多く見られるかと思いますが、その際に、①確定給付企業年金、②確定拠出年金(日本版401k)、③退職金前払い制度、の3つの制度から社員が1つを選ぶ制度も可能だということになります。
ただし、確定拠出年金(日本版401k)は、税制適格年金からの移行時には、原則として過去勤務債務(積立て不足)を解消することが求められますし(確定給付企業年金への移行は積立て不足があっても可能)、企業型の場合、投資教育のコストなども考慮する必要があります(「企業内個人型」の場合は、投資教育は義務付けられていません)。また、退職金が"手切れ金"のような役割を担っている面がある中小企業などにおいて、こうした中途退職しても原則として60歳にならなければ受給できない仕組みが馴染むかどうか、仮に別途に会社退職金(退職一時金)の制度が用意されていなければ、転職準備金が手元に無い状況となる問題もあります。
● 中小企業の場合、「中退共」という選択も
そうした理由から確定拠出年金(日本版401k)を敬遠する中小企業の選択肢としては、税制適格年金から「中小企業退職金共済制度」への移行ということも考えられます。
「中退共」へ加入できる要件を満たしていれば、適格年金からの移行は比較的容易であり、移行後は、企業は掛金を負担するだけでよく、予定利率を下回った場合でも追加拠出の必要がありません。「中退共」はある意味、"確定拠出"なのです。以前は、適格年金資産の移管額に上限がありましたが、平成17年4月からは上限が撤廃されています。
● 2つ制度から社員が1つ選ぶ
「中退共」への加入要件を満たさない、金融機関との関係を維持しなければならない、などの理由で「中退共」を選ばない(または選べない)場合は、前掲の"三択"を"二択"に絞り、①確定給付企業年金、②退職金前払い制度、の何れかを社員が選択できる制度というのも、現実性が高いと考えられます。ただし、確定給付企業年金の加入者となることを選択した場合、その資格を任意に喪失することは許されていないので、最初の選択においての注意が必要です。
● 「完全前払い」制に「企業内個人型確定拠出年金」を付加する
退職金前払い制度は、単独制度としても、新企業年金との組み合わせによる選択制度としても、その役割は大きいと考えます。また、企業年金を全廃して「完全前払い」制に移行した場合には、その受け皿としての「企業内個人型確定拠出年金」も、検討の価値があると思います。
今まで見てきたように、確定拠出年金(日本版401k)は、退職金前払い制度との併設が認められていますが、確定給付企業年金と合わせて実施することも可能です。(確定給付企業年金は、税制適格年金、厚生年金基金、企業型確定拠出年金、退職金前払い制度の何れとの併設可能です。ただし、適格年金は平成24年3月末を以って適格年金制度自体が無くなります。)
そうすると今後は、税制適格年金から、制度的に似ている確定給付企業年金への移行が多く見られるかと思いますが、その際に、①確定給付企業年金、②確定拠出年金(日本版401k)、③退職金前払い制度、の3つの制度から社員が1つを選ぶ制度も可能だということになります。
ただし、確定拠出年金(日本版401k)は、税制適格年金からの移行時には、原則として過去勤務債務(積立て不足)を解消することが求められますし(確定給付企業年金への移行は積立て不足があっても可能)、企業型の場合、投資教育のコストなども考慮する必要があります(「企業内個人型」の場合は、投資教育は義務付けられていません)。また、退職金が"手切れ金"のような役割を担っている面がある中小企業などにおいて、こうした中途退職しても原則として60歳にならなければ受給できない仕組みが馴染むかどうか、仮に別途に会社退職金(退職一時金)の制度が用意されていなければ、転職準備金が手元に無い状況となる問題もあります。
● 中小企業の場合、「中退共」という選択も
そうした理由から確定拠出年金(日本版401k)を敬遠する中小企業の選択肢としては、税制適格年金から「中小企業退職金共済制度」への移行ということも考えられます。
「中退共」へ加入できる要件を満たしていれば、適格年金からの移行は比較的容易であり、移行後は、企業は掛金を負担するだけでよく、予定利率を下回った場合でも追加拠出の必要がありません。「中退共」はある意味、"確定拠出"なのです。以前は、適格年金資産の移管額に上限がありましたが、平成17年4月からは上限が撤廃されています。
● 2つ制度から社員が1つ選ぶ
「中退共」への加入要件を満たさない、金融機関との関係を維持しなければならない、などの理由で「中退共」を選ばない(または選べない)場合は、前掲の"三択"を"二択"に絞り、①確定給付企業年金、②退職金前払い制度、の何れかを社員が選択できる制度というのも、現実性が高いと考えられます。ただし、確定給付企業年金の加入者となることを選択した場合、その資格を任意に喪失することは許されていないので、最初の選択においての注意が必要です。
● 「完全前払い」制に「企業内個人型確定拠出年金」を付加する
退職金前払い制度は、単独制度としても、新企業年金との組み合わせによる選択制度としても、その役割は大きいと考えます。また、企業年金を全廃して「完全前払い」制に移行した場合には、その受け皿としての「企業内個人型確定拠出年金」も、検討の価値があると思います。
〔53〕 早期退職優遇制度と希望退職-両者の違いと割増退職金などの関連システム
● 早期退職優遇制度と希望退職の違い
「早期退職優遇制度」は、「希望退職制度」を含めてそう呼ぶ場合もありますが、本来は、後者が一時的措置("制度"と呼ぶこともやや不正確)であるのに対し、前者は恒常的な制度であるところに大きな違いがあります。以下、両者の違いをまとめてみました。
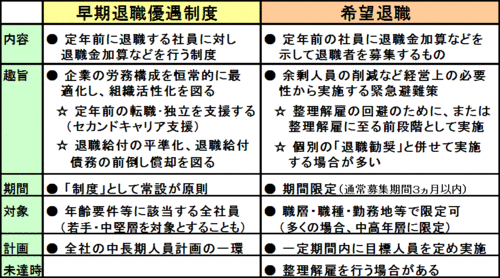 ※「退職勧奨」は、「希望退職」と併せて実施されることが多いのですが、本来はローパフォーマーを対象として個別に行うものであって、会社業績が良くても実施される可能性のある性格のものです。
※「退職勧奨」は、「希望退職」と併せて実施されることが多いのですが、本来はローパフォーマーを対象として個別に行うものであって、会社業績が良くても実施される可能性のある性格のものです。
● 早期退職優遇制度の概念・類型と関連システム
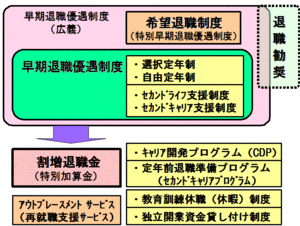 一般に「選択定年制」や「セカンドライフ支援制度」と呼ばれている制度も、「早期退職優遇制度」の一種とみることができます。こうした制度の導入においては、図のような関連制度・システムの充実が望まれますが、その核となるのは、やはり割増退職金(特別加算金)です。
一般に「選択定年制」や「セカンドライフ支援制度」と呼ばれている制度も、「早期退職優遇制度」の一種とみることができます。こうした制度の導入においては、図のような関連制度・システムの充実が望まれますが、その核となるのは、やはり割増退職金(特別加算金)です。
「早期退職優遇制度」は、「希望退職制度」を含めてそう呼ぶ場合もありますが、本来は、後者が一時的措置("制度"と呼ぶこともやや不正確)であるのに対し、前者は恒常的な制度であるところに大きな違いがあります。以下、両者の違いをまとめてみました。
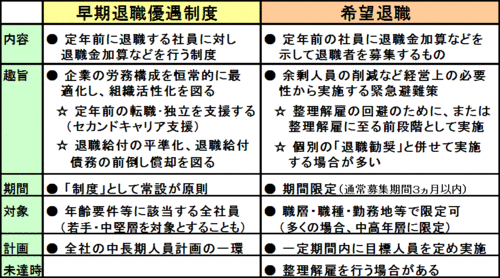 ※「退職勧奨」は、「希望退職」と併せて実施されることが多いのですが、本来はローパフォーマーを対象として個別に行うものであって、会社業績が良くても実施される可能性のある性格のものです。
※「退職勧奨」は、「希望退職」と併せて実施されることが多いのですが、本来はローパフォーマーを対象として個別に行うものであって、会社業績が良くても実施される可能性のある性格のものです。● 早期退職優遇制度の概念・類型と関連システム
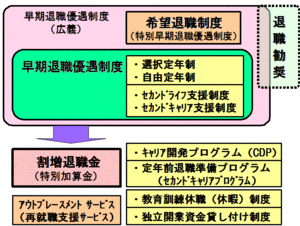 一般に「選択定年制」や「セカンドライフ支援制度」と呼ばれている制度も、「早期退職優遇制度」の一種とみることができます。こうした制度の導入においては、図のような関連制度・システムの充実が望まれますが、その核となるのは、やはり割増退職金(特別加算金)です。
一般に「選択定年制」や「セカンドライフ支援制度」と呼ばれている制度も、「早期退職優遇制度」の一種とみることができます。こうした制度の導入においては、図のような関連制度・システムの充実が望まれますが、その核となるのは、やはり割増退職金(特別加算金)です。〔54〕 割増退職金のポイント①-算定方法と支給水準、年収ベースで決める考え方
● 割増退職金(特別加算金)の算定定方法と支給水準例
割増退職金の算定方法は、主要なものとして次の4タイプがあります。
① 絶対額で決める
S社(早期退職優遇制度) 50歳~55歳 500万円、56歳~57歳 500万円、58歳~59歳 50万円
② 退職金の割増率で決める
JR東海(早期退職優遇制度) 50歳~55歳 12%~15%
G社(希望退職) 54歳~55歳 100%、56歳~57歳 90%、58歳~59歳 80%
③ 基本給の月数で決める
T社(希望退職) 45歳以上 最大30ヶ月
④ 年収ベースで決める
松下電器(希望退職) 最大年収の2.5倍
傾向としては①から④の順に支給額は大きくなりますが、支給水準は、早期退職優遇制度であるか希望退職であるかによっても異なりますし(一般に希望退職の方が高い)、企業規模によってかなりのバラツキがあります。中小企業においては、会社都合計算のみで別途加算は行わないケースもかなりあります。
● 年収ベースで加算額を決める場合の原則的な考え方
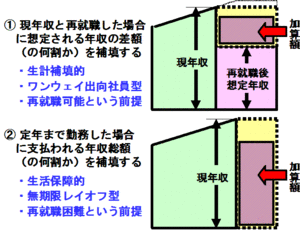 かつて割増退職金は、その言葉の通り、割増率で決めるのが主流でしたが、近年は年収ベースで決めるケースが見受けられます。年収ベースで加算額を決めるやり方の原則的な考え方には、図のように2タイプあります。月数で決めている場合でも、元の考え方は、同じ場合があります。
かつて割増退職金は、その言葉の通り、割増率で決めるのが主流でしたが、近年は年収ベースで決めるケースが見受けられます。年収ベースで加算額を決めるやり方の原則的な考え方には、図のように2タイプあります。月数で決めている場合でも、元の考え方は、同じ場合があります。
ただし現実には、両タイプとも加算額は多目になります。中小企業等においては、加算金額も重要ですが一定の限界がありますから、大手企業を参考にするならば、むしろアウトプレースメントサービス(再就職支援サービス)を付与するなどの施策に原資を配分した方が良いと考えます。(※希望退職の場合、割増退職金の加算額もアウトプレースメントサービス費用も、特別損失処理が可能です。)
割増退職金の算定方法は、主要なものとして次の4タイプがあります。
① 絶対額で決める
S社(早期退職優遇制度) 50歳~55歳 500万円、56歳~57歳 500万円、58歳~59歳 50万円
② 退職金の割増率で決める
JR東海(早期退職優遇制度) 50歳~55歳 12%~15%
G社(希望退職) 54歳~55歳 100%、56歳~57歳 90%、58歳~59歳 80%
③ 基本給の月数で決める
T社(希望退職) 45歳以上 最大30ヶ月
④ 年収ベースで決める
松下電器(希望退職) 最大年収の2.5倍
傾向としては①から④の順に支給額は大きくなりますが、支給水準は、早期退職優遇制度であるか希望退職であるかによっても異なりますし(一般に希望退職の方が高い)、企業規模によってかなりのバラツキがあります。中小企業においては、会社都合計算のみで別途加算は行わないケースもかなりあります。
● 年収ベースで加算額を決める場合の原則的な考え方
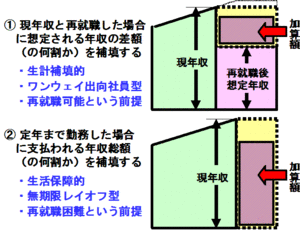 かつて割増退職金は、その言葉の通り、割増率で決めるのが主流でしたが、近年は年収ベースで決めるケースが見受けられます。年収ベースで加算額を決めるやり方の原則的な考え方には、図のように2タイプあります。月数で決めている場合でも、元の考え方は、同じ場合があります。
かつて割増退職金は、その言葉の通り、割増率で決めるのが主流でしたが、近年は年収ベースで決めるケースが見受けられます。年収ベースで加算額を決めるやり方の原則的な考え方には、図のように2タイプあります。月数で決めている場合でも、元の考え方は、同じ場合があります。ただし現実には、両タイプとも加算額は多目になります。中小企業等においては、加算金額も重要ですが一定の限界がありますから、大手企業を参考にするならば、むしろアウトプレースメントサービス(再就職支援サービス)を付与するなどの施策に原資を配分した方が良いと考えます。(※希望退職の場合、割増退職金の加算額もアウトプレースメントサービス費用も、特別損失処理が可能です。)
〔55〕 割増退職金のポイント②-早期退職優遇制度・希望退職・退職勧奨の考え方
● 割増退職金(特別加算金)のポイント
① 割増退職金は早期退職優遇制度の最大のポイント
割増退職金が「早期退職優遇制度」の目玉であることは事実です。応募を検討する社員にとって充分に魅力のあるものにしなければ、利用されない制度になってしまいます(「希望退職」においても同様です)。ただし、応募しない(あるいは応募資格のない)社員のモチベーションへの影響も考慮するならば、過大な金額設定は避ける必要があります。
② 「希望退職」は「早期退職優遇制度」より厚めに加算
「希望退職」は余剰人員の削減など経営の必要から実施するものですから、退職給付の平準化と社員の転進支援を図る「早期退職優遇制度」とは、目的が異なります。一定期間内に目標人員を定めて行うため、「早期退職優遇制度」よりも加算額を大きく設定します。また、希望退職を、目標人員に至らなかったなどの理由で何度かにわたり行う場合は、同じ条件で行うか、または第1回より第2回、第2回より第3回と回を追うごとに加算額を小さくしていくのが一般的です。
③ 「退職勧奨」は別途に扱う
「退職勧奨」は、ローパフォーマーに対して個別に行うもので、会社業績や本人の年齢・勤続年数などは、本来は関係ありません。割増加算金も、一時期に集中して実施するのでなければ。個別に検討すべきだと考えます。(「希望退職」と組み合わせて実施する場合は次項参照)
● 「希望退職」と「退職勧奨」の組み合わせ
「希望退職」の成功・不成功の判断基準は次の2点です。
ⅰ 募集予定者数に応募者数がどれだけ近いか
ⅱ 応募者数に占める非コア人材の比率の高さ及びコア人材の比率の低さ
以上を満たすために、雇用調整の一環として「希望退職」を募る場合には、「退職勧奨」を行うのが一般的ですが、「退職勧奨」の実施のポイントは次の通りです。
イ.「希望退職」募集期間の前または期間中に「退職勧奨」を行うのが一般的です。
ロ.「希望退職」の目標人員が相当数の場合は、対象者(応募資格者)全員との「個別面談」という形で実施します。この場合に、コア人材を区分できる客観的基準(過去評価の累計ポイントなど)があれば、コア人材に対しては応募資格を与えない、ということも可能です。
ハ.逆に、ローパフォーマーに対しては、そうした基準をもとに"戦力外"であることを告知し、「退職勧奨」します。ただし、面談に際しては、会社の経営状況をよく説明し、また「退職勧奨」であって「解雇」では無いので、本人に決定権があることを充分に告知します。(必要に応じて、「希望退職」の応募結果によっては整理解雇を実施しなければならない旨を伝えます。)
二.割増退職金は一定の基準(前節参照)で計算し、個別面談をする全員に提示します。
ホ.面談は直属上司が行うべきだと一般に言われますが、企業規模や役職権限によっては、部門長、役員、社長が行う方が良いと考えられますし、最近は外部委託するケースもあります。
こうした事態の備える意味でも、日常、キャリアプランニング研修を実施しておくのが理想ですが、少なくとも「希望退職」募集開始前後に、複数回の研修は必要であると考えます。
① 割増退職金は早期退職優遇制度の最大のポイント
割増退職金が「早期退職優遇制度」の目玉であることは事実です。応募を検討する社員にとって充分に魅力のあるものにしなければ、利用されない制度になってしまいます(「希望退職」においても同様です)。ただし、応募しない(あるいは応募資格のない)社員のモチベーションへの影響も考慮するならば、過大な金額設定は避ける必要があります。
② 「希望退職」は「早期退職優遇制度」より厚めに加算
「希望退職」は余剰人員の削減など経営の必要から実施するものですから、退職給付の平準化と社員の転進支援を図る「早期退職優遇制度」とは、目的が異なります。一定期間内に目標人員を定めて行うため、「早期退職優遇制度」よりも加算額を大きく設定します。また、希望退職を、目標人員に至らなかったなどの理由で何度かにわたり行う場合は、同じ条件で行うか、または第1回より第2回、第2回より第3回と回を追うごとに加算額を小さくしていくのが一般的です。
③ 「退職勧奨」は別途に扱う
「退職勧奨」は、ローパフォーマーに対して個別に行うもので、会社業績や本人の年齢・勤続年数などは、本来は関係ありません。割増加算金も、一時期に集中して実施するのでなければ。個別に検討すべきだと考えます。(「希望退職」と組み合わせて実施する場合は次項参照)
● 「希望退職」と「退職勧奨」の組み合わせ
「希望退職」の成功・不成功の判断基準は次の2点です。
ⅰ 募集予定者数に応募者数がどれだけ近いか
ⅱ 応募者数に占める非コア人材の比率の高さ及びコア人材の比率の低さ
以上を満たすために、雇用調整の一環として「希望退職」を募る場合には、「退職勧奨」を行うのが一般的ですが、「退職勧奨」の実施のポイントは次の通りです。
イ.「希望退職」募集期間の前または期間中に「退職勧奨」を行うのが一般的です。
ロ.「希望退職」の目標人員が相当数の場合は、対象者(応募資格者)全員との「個別面談」という形で実施します。この場合に、コア人材を区分できる客観的基準(過去評価の累計ポイントなど)があれば、コア人材に対しては応募資格を与えない、ということも可能です。
ハ.逆に、ローパフォーマーに対しては、そうした基準をもとに"戦力外"であることを告知し、「退職勧奨」します。ただし、面談に際しては、会社の経営状況をよく説明し、また「退職勧奨」であって「解雇」では無いので、本人に決定権があることを充分に告知します。(必要に応じて、「希望退職」の応募結果によっては整理解雇を実施しなければならない旨を伝えます。)
二.割増退職金は一定の基準(前節参照)で計算し、個別面談をする全員に提示します。
ホ.面談は直属上司が行うべきだと一般に言われますが、企業規模や役職権限によっては、部門長、役員、社長が行う方が良いと考えられますし、最近は外部委託するケースもあります。
こうした事態の備える意味でも、日常、キャリアプランニング研修を実施しておくのが理想ですが、少なくとも「希望退職」募集開始前後に、複数回の研修は必要であると考えます。
