◆退職後に判明した懲戒解雇事由をもとに、退職金を不支給とすることができるか
 先日当社を退職した社員について、在職中に懲戒解雇事由に相当する非違行為があったことが、退職後に判明しました。このような場合、退職金を不支給とすることはできるでしょうか。
先日当社を退職した社員について、在職中に懲戒解雇事由に相当する非違行為があったことが、退職後に判明しました。このような場合、退職金を不支給とすることはできるでしょうか。
また、事実関係の究明に時間を要する場合、退職金の支払いを留保することはできるでしょうか。  すでに退職した社員を懲戒解雇することはできないため、懲戒解雇を理由に退職金を不支給とすることはできません。退職後に判明した事由をもとに退職金を不支給とするには、「懲戒解雇に相当する事由が認められるとき」「退職金支給日までの間に在職中の行為について懲戒解雇事由が認められた場合」などにおいても退職金を減額または不支給とすることがある旨を、あらかじめ就業規則や退職金規程に定めておくことが望ましいでしょう。
すでに退職した社員を懲戒解雇することはできないため、懲戒解雇を理由に退職金を不支給とすることはできません。退職後に判明した事由をもとに退職金を不支給とするには、「懲戒解雇に相当する事由が認められるとき」「退職金支給日までの間に在職中の行為について懲戒解雇事由が認められた場合」などにおいても退職金を減額または不支給とすることがある旨を、あらかじめ就業規則や退職金規程に定めておくことが望ましいでしょう。
事実関係の究明に時間を要するため、退職金の支払いを留保する場合も、「当社が必要と認める調査を実施する間、支払いを留保できる」といった定めをしておくことが望ましいと考えます。
■解説
1 退職後に判明した懲戒解雇事由をもとに退職金を不支給とするには
多くの事業所では、従業員が重大な非違行為をした場合の制裁として、懲戒解雇できる旨の規定を設けるとともに、懲戒解雇の場合には退職金を不支給とするか、またはその一部を減額できる旨の規定を設けています。
しかし、ご質問のケースでは、すでに労働者が退職しており、当事者間の雇用関係は終了しています。そのため、使用者による解雇すなわち雇用契約を終了させる旨の意思表示は、その対象を失っているために意味を持たず、懲戒解雇することは不可能です。したがって、懲戒解雇を理由として退職金の不支給または減額を行うことはできないということになります。
そうすると、就業規則や退職金規程でその支給条件等が明確に定められた退職金は、労働基準法上の賃金として扱われますので、通常支払う額を全額支給しなければなりません。支給条件や支給額の算定方法が定められている退職金は、労働者にとって賃金債権となり、恣意的に減額したり支払わなかったりすることはできないからです。
そこで、実務上の対応としては、あらかじめ就業規則や退職金規程において、「懲戒解雇の場合」に加えて、「懲戒解雇に相当する事由が認められるとき」あるいは「退職金支給日までの間に在職中の行為について懲戒解雇事由が認められた場合」も、減額または不支給とすることがある旨を定めておき、ご質問のようなケースにおいて不支給等の決定をする際の契約上の根拠とすることが考えられます。
実際の裁判例では、このような減額・不支給事由が定められていない場合でも、労働者の在職中の非違行為が重大かつ悪質なものであれば、労働者の退職後になされた退職金の不支給決定が認められた例も若干はあります。しかし、労務管理上の観点からも、こうした減額・不支給事由をあらかじめ規定しておくことが望ましいといえるでしょう。
2 事実関係究明のため退職金の支払いを留保することはできるか
就業規則や退職金規程で退職金について定める場合は、退職金の支払い期日についても必ず定めておかなければなりません。その場合、労働基準法23条1項の「労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があった場合においては、7日以内に賃金を支払わなければならない」との定めの適用は受けないため、支払い期日は任意に定めることができます。就業規則等に退職金の支払い時期が定められていれば、権利者の請求があったとしても、賃金と同じように7日以内に支払う必要はありません。就業規則で定める支払い期日については、必ずしも支給月日まで特定しておく必要はなく、例えば、「退職金は、原則として退職の日から1カ月以内に支給する」などのように、退職の日から一定期間以内の期間に支払うとする定め方でも差し支えありません。
こうした定めがあれば、その間に事実関係究明のための調査をすることは可能かと思われますが、それでも退職金支払期日まで時間的に余裕がないといった事態が生じることも考えられます。
労働基準法23条2項では、労働者の請求がある場合にも、使用者が異議のある部分の支払いを留保することは認めていますが、さらに支払いを留保する根拠を明確にするためには、「会社が必要と認める調査を実施する間、支払いを留保できる」といった定めをしておくことが望ましいと考えます。
□根拠法令等
・労基法23(金品の返還)、24(賃金の支払)
・昭26.2.27基収5483、昭63.3.14基発150(退職手当の支払時期)
□ 判例等
・在職中に懲戒解雇に匹敵する重大な背信行為を行った者の退職金請求権を否定した裁判例(平8.4.26東京地判・東京ゼネラル事件、平12.12.18東京地判・アイビ・プロテック事件)
1 退職後に判明した懲戒解雇事由をもとに退職金を不支給とするには
多くの事業所では、従業員が重大な非違行為をした場合の制裁として、懲戒解雇できる旨の規定を設けるとともに、懲戒解雇の場合には退職金を不支給とするか、またはその一部を減額できる旨の規定を設けています。
しかし、ご質問のケースでは、すでに労働者が退職しており、当事者間の雇用関係は終了しています。そのため、使用者による解雇すなわち雇用契約を終了させる旨の意思表示は、その対象を失っているために意味を持たず、懲戒解雇することは不可能です。したがって、懲戒解雇を理由として退職金の不支給または減額を行うことはできないということになります。
そうすると、就業規則や退職金規程でその支給条件等が明確に定められた退職金は、労働基準法上の賃金として扱われますので、通常支払う額を全額支給しなければなりません。支給条件や支給額の算定方法が定められている退職金は、労働者にとって賃金債権となり、恣意的に減額したり支払わなかったりすることはできないからです。
そこで、実務上の対応としては、あらかじめ就業規則や退職金規程において、「懲戒解雇の場合」に加えて、「懲戒解雇に相当する事由が認められるとき」あるいは「退職金支給日までの間に在職中の行為について懲戒解雇事由が認められた場合」も、減額または不支給とすることがある旨を定めておき、ご質問のようなケースにおいて不支給等の決定をする際の契約上の根拠とすることが考えられます。
実際の裁判例では、このような減額・不支給事由が定められていない場合でも、労働者の在職中の非違行為が重大かつ悪質なものであれば、労働者の退職後になされた退職金の不支給決定が認められた例も若干はあります。しかし、労務管理上の観点からも、こうした減額・不支給事由をあらかじめ規定しておくことが望ましいといえるでしょう。
2 事実関係究明のため退職金の支払いを留保することはできるか
就業規則や退職金規程で退職金について定める場合は、退職金の支払い期日についても必ず定めておかなければなりません。その場合、労働基準法23条1項の「労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があった場合においては、7日以内に賃金を支払わなければならない」との定めの適用は受けないため、支払い期日は任意に定めることができます。就業規則等に退職金の支払い時期が定められていれば、権利者の請求があったとしても、賃金と同じように7日以内に支払う必要はありません。就業規則で定める支払い期日については、必ずしも支給月日まで特定しておく必要はなく、例えば、「退職金は、原則として退職の日から1カ月以内に支給する」などのように、退職の日から一定期間以内の期間に支払うとする定め方でも差し支えありません。
こうした定めがあれば、その間に事実関係究明のための調査をすることは可能かと思われますが、それでも退職金支払期日まで時間的に余裕がないといった事態が生じることも考えられます。
労働基準法23条2項では、労働者の請求がある場合にも、使用者が異議のある部分の支払いを留保することは認めていますが、さらに支払いを留保する根拠を明確にするためには、「会社が必要と認める調査を実施する間、支払いを留保できる」といった定めをしておくことが望ましいと考えます。
□根拠法令等
・労基法23(金品の返還)、24(賃金の支払)
・昭26.2.27基収5483、昭63.3.14基発150(退職手当の支払時期)
□ 判例等
・在職中に懲戒解雇に匹敵する重大な背信行為を行った者の退職金請求権を否定した裁判例(平8.4.26東京地判・東京ゼネラル事件、平12.12.18東京地判・アイビ・プロテック事件)
◆社員本人の同意があれば、貸付金の残額を退職金で相殺できるか
 当社では、社員に対する福利厚生施策の一環として、社員融資制度(貸付金制度)を独自に設けることを検討中ですが、制度を利用した社員が退職する際に、貸付金の残額を退職金で相殺することは可能でしょうか。
当社では、社員に対する福利厚生施策の一環として、社員融資制度(貸付金制度)を独自に設けることを検討中ですが、制度を利用した社員が退職する際に、貸付金の残額を退職金で相殺することは可能でしょうか。  退職する社員本人の同意があれば、退職金から貸付金の残額を一括して返済させることも可能です。ただし、その同意は、本人の完全な自由意思基づくものであることが客観的に認められる必要があります。
退職する社員本人の同意があれば、退職金から貸付金の残額を一括して返済させることも可能です。ただし、その同意は、本人の完全な自由意思基づくものであることが客観的に認められる必要があります。
■解説
1 前借金相殺の禁止(労基法17条)との関係
銀行等との提携ローンとは別に使用者が独自に融資制度(貸付金制度)を設けている場合において、当該制度を利用している労働者が退職する際に、その貸付金の残額を退職金で相殺することができるかどうかをめぐっては、退職金の支給条件が労働契約や就業規則、労働協約等によって明確化されている場合、その退職金は労働基準法11条でいう賃金に該当するため、同法17条の「使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない」という「前借金相殺の禁止」規定に抵触しないかが、まず問題になります。
この点について、行政解釈では、労働者が使用者から人的信用に基づいて受ける金融であって明らかに身分的拘束を伴わないものは、「労働することを条件とする前貸の債権」には当たらないとしています。
使用者からの住宅建設資金の貸付に対する返済金のように融資額および返済額ともに相当高額に上り、その返済期間も相当長期間にわたるものであっても、①貸付の原因が真に労働者の便宜のためのものであり、労働者からの申出に基づくものであること、②貸付期間は必要を満たしえる範囲であり、賃金や退職金などによって生活を脅威し得ない程度に返済可能であること、③返済前であっても退職の自由が制約されていないこと等、当該貸付金が身分的拘束を伴わないことが明らかである場合は、法17条には抵触しないと解されています。
2 全額払いの原則(労基法24条)との関係
また、「賃金支払五原則」の1つとして、労基法24条1項に「全額払いの原則」が定められていますが、使用者による賃金債権の相殺も、「全額払いの原則」が禁止する賃金の控除に該当するため、法11条でいう賃金に該当するところの退職金から貸付金の残額を控除することが同原則に抵触しないかということが、次に問題となります。
この点について、同原則への抵触を回避するためには、「当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる」(法24条1項ただし書後段)との定めに沿って、労使間で控除協定を締結しなければなりません。
この協定は「二四協定」などと呼ばれ、「三六協定」とは異なり、労働基準監督署への届出を必要としません。「二四協定」では、「退職時に貸付金等の未返済債務がある場合は、退職金から一括控除することができる」などというように、未返済債務を退職金で相殺することについての明確な定めがされていることが必要です。
この協定が結ばれることにより、労働者の合意を得ないで行う一方的な控除であれ、労働者の合意を得て行う控除であれ、労基法違反は回避されます。ただし、それは、「二四協定」が締結されていれば、退職金から未返済債務を控除しても違法にはならないという刑事免責がなされるということであり、相殺の民事的効力を生じせしめるには、本人の完全な自由意思基づくものであることが必要となります。
この場合の労働者の同意の意思表示は、厳密には、退職金支給時の意思表示であることが必要となります。したがって、実際に退職金から貸付金等の未返済債務を控除するには、「二四協定」が締結されている場合や、貸付時に退職金と未返済債務の相殺を取り決めた契約書を交わしている場合であっても、その都度、本人の同意が必要となります。
裁判例では、労働者がその自由な意思に基づき相殺を同意したものであると認めるに足りる合理的理由が客観的に存在するときは、その同意を得てした相殺は「全額払いの原則」に違反しないとの解釈を打ち出しており、その限りにおいては、協定に基づかない控除も許容されています。
3 相殺する場合の限度額について
相殺する場合の限度額については、労基法24条は協定に基づく控除についての限度額を設けておらず、行政解釈上も、控除される金額が賃金額の一部である限り控除額についての限度はないとされています。
ただし、民法510条及び民事執行法152条2項の規定により、退職金の額の4分の3に相当する部分については、使用者側から相殺することはできないとされているのため、使用者が労働者の同意を得ないで一方的に相殺を行う場合には、退職金の4分の1を超える額については控除できないということになります。
しかしながら、「二四協定」があり、かつ、労働者の同意がある場合はこの規定に服するものではなく、したがって、控除される金額が退職金の一部である限り、控除額についての限度はないという前記の行政解釈に立ち返るため、未返済額の全額を退職金と相殺しても差し支えありません。
□根拠法令等
・労働基準法17(前借金相殺の禁止)、24(賃金の支払)①(全額払いの原則)
・昭22.9.13 発基1、昭33.2.13 基発90(前借金相殺の禁止の趣旨)
・昭29.12.23基収6185号、昭63.03.14基発150(控除額の限度)
・民法510(差押禁止債権を受働債権とする相殺の禁止)
・民事執行法152(差押禁止債権)②(退職手当)
□ 判例等
「使用者が労働者の同意を得て労働者の退職金債権に対してする相殺は、この同意が労働者の自由な意思に基づいてなされたものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するときは、労働基準法二四条一項本文の全額払いの原則に違反しない」とされたもの。(平2.11.26 最二小判・日新製鋼事件)
・内容についての無断転載は固くお断りいたします。
◆早出についても割増賃金を支払う必要があるか
 当社の1日の所定労働時間は、午前9時から午後5時まで(休憩1時間)の7時間です。社員が午後5時を超えて残業した場合には、残業手当を支払っていますが、午前9時前に早出出勤をした場合も、割増賃金を支払う必要があるのでしょうか。
当社の1日の所定労働時間は、午前9時から午後5時まで(休憩1時間)の7時間です。社員が午後5時を超えて残業した場合には、残業手当を支払っていますが、午前9時前に早出出勤をした場合も、割増賃金を支払う必要があるのでしょうか。また、朝2時間遅刻した社員が、その日2時間残業した場合には、その残業に対して割増賃金を支払う必要があるのでしょうか。
 いわゆる早出出勤も、時間外労働となります。したがって、早出の場合も、1日の所定労働時間を超えて労働した場合は、その時間に対して時間外手当を支払う必要があります。さらに、その日の労働時間が法定労働時間(8時間)を超えた場合は、超えた時間に対して割増賃金を支払う必要があります。
いわゆる早出出勤も、時間外労働となります。したがって、早出の場合も、1日の所定労働時間を超えて労働した場合は、その時間に対して時間外手当を支払う必要があります。さらに、その日の労働時間が法定労働時間(8時間)を超えた場合は、超えた時間に対して割増賃金を支払う必要があります。一方、2時間遅刻し、所定就業時刻を超えて2時間残業した労働者は、働いた時間の長さは通常の日と同じであるため、割増賃金を支払う必要はありません。
■解説
1 早出出勤にも割増賃金を支払う必要があるか
ご質問の前段は、早出出勤に対しても割増賃金を支払う必要があるかということですが、貴社の所定労働時間は7時間とのことですので、早出・残業を問わず、7時間を超えて労働させた時間は時間外労働となり、原則として、通常の労働時間に対して支払うべき賃金を払わなければなりません。ただし、労働協約や就業規則によって、1日8時間(休憩時間を除く)までの1時間について、別に定めた賃金額がある場合は、それを支払うことで足ります。この点について、行政解釈では、「法定労働時間内である所定労働時間外の1時間については、別段の定めがない場合には原則として通常の労働時間の賃金を支払わなければならない。但し、労働協約、就業規則等によって、その1時間に対し別に定められた賃金がある場合にはその別に定められた賃金額で差し支えない」としています。
次に、早出勤務した時間も含め1日の労働時間が8時間を超えた場合についてですが、その場合は、その超えた時間については、通常の賃金のほかに2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。
つまり、早出した時間に対して割増賃金を支払わねばならないのではなく、早出をした結果、その日の労働時間が8時間を超えたときに、割増賃金を支払わねばならないということです。
2 遅刻した日に残業した場合、その残業に対して割増賃金を支払う必要があるか
ご質問の後段は、遅刻した時間と残業した時間を相殺することが可能かという問いに言いかえることもできるかと思いますが、これについても同様の考え方が成り立ちます。その日の実労働時間が所定労働時間である7時間を超えない限りは、必ずしも残業手当を支払う必要はなく、また、法定労働時間である8時間を超えない限りは、必ずしも割増賃金を支払う必要はありません。遅刻した時間と残業時間を相殺することは可能であるということです。
したがって、ご質問にある社員のように、2時間遅刻した日に所定終業時刻を超えて2時間残業した場合は、その日に働いた時間(実労働時間)は通常の日の労働時間(所定労働時間)と同じであるため、残業手当および割増賃金を支払う必要は原則としてありません。
ただし、就業規則等で「終業時刻後に労働した場合には時間外労働として扱い、割増賃金を支払う」などの定めがある場合には、終業時刻以降の労働に対しては割増賃金を支払わなければならず、相殺することはできません。
以上がご質問のケースに対する回答ですが、例えば、労働者がより大幅な遅刻をしたために、労働時間が深夜業の時間帯(午後10時から午前5時)に及んだ場合は、実労働時間が8時間以内であっても、深夜業の時間帯の労働時間については、通常の賃金のほかに2割5分以上の率で計算した深夜労働割増賃金を支払わなければなりませんので、この点はご留意ください。
□根拠法令等
・労基法37(時間外、休日および深夜の割増賃金)
・昭23.11.4基発1592(法定内の所定時間外労働に対する賃金)
・内容についての無断転載は固くお断りいたします。
◆法定休日に8時間を超えて労働した場合、6割増の割増賃金を支払う必要があるか
 当事業所の所定労働時間は8時間ですが、法定休日に8時間を超えて労働した社員がいる場合、その8時間を超えた時間分については、休日割増分の3割5分増に時間外割増分の2割5分増を加えた、6割増以上の率で計算した割増賃金を支払う必要があるのでしょうか。
当事業所の所定労働時間は8時間ですが、法定休日に8時間を超えて労働した社員がいる場合、その8時間を超えた時間分については、休日割増分の3割5分増に時間外割増分の2割5分増を加えた、6割増以上の率で計算した割増賃金を支払う必要があるのでしょうか。
また、法定休日の労働が深夜に及んだ場合は、その深夜の時間帯の労働時間については、割増賃金はどのように計算すればよいのでしょうか。  所定労働時間が8時間である場合、法定休日に8時間を超えて労働させたときの割増賃金は、その労働が深夜に及ばない限り、3割5分増の割増賃金を支払えば足ります。
所定労働時間が8時間である場合、法定休日に8時間を超えて労働させたときの割増賃金は、その労働が深夜に及ばない限り、3割5分増の割増賃金を支払えば足ります。
その休日労働が深夜に及んだ場合は、深夜の時間帯の労働時間については、休日割増分の3割5分増に深夜割増分の2割5分増を加えた、6割増以上の率で計算した割増賃金を支払う必要があります。
■解説
1 休日労働が8時間を超えた場合の取り扱い
労働基準法37条1項では、「労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間またはその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない」とされており、「政令」(割増賃金令)では、休日の労働については3割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならないとされています。
そこで、ご質問にあるように、法定休日(週1回または4週間を通じ4日の休日)に8時間を超えて労働させた場合は、その超えた時間分については、休日割増分の3割5分増に時間外割増分の2割5分増を加えた、6割増以上の率で計算した割増賃金を支払う必要があるのかということが疑問となります。
この場合、そもそも休日には、いわゆる所定労働時間という概念はありませんので、その休日労働が深夜(午後10時から午前5時までの時間帯)に及ぶことがない限り、8時間を超えた場合でも、休日割増分の3割5分増の増賃賃金を支払えば足ります。
2 休日労働が深夜に及んだ場合などの取り扱い
その休日労働が深夜に及んだ場合は、休日においても深夜労働という概念は除外されていないため、深夜の時間帯の労働時間分について、休日割増分の3割5分増に深夜割増分の2割5分増を加えた、6割増以上の率で計算した割増賃金を支払う必要があります。
また、平日の時間外労働が休日に及んだ場合は、その休日が法定休日であれば、たとえ前日からの勤務の継続であっても、午前0時からは前日の時間外労働としてではなく、休日労働として取り扱います。したがって、午前0時以降の休日労働の時間については3割5分増以上の率で計算した休日割増賃金を支払う必要があります。さらに、前日(平日)の午後10時から当日(休日)午前5時までの間の時間は深夜労働に該当するため、休日の午前0時から午前5時までの間の時間についても、休日割増分の3割5分に深夜割増分2割5分を加えた6割増以上の率で計算した割増賃金を支払う必要があることになります(下図参照)。
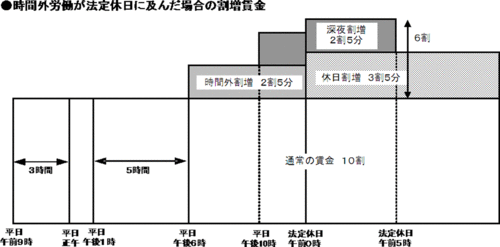 □根拠法令等
□根拠法令等
・労働基準法37(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
・労働基準法第37条第1項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令
・労働基準法施行規則20②(休日深夜業の割増賃金)
・内容についての無断転載は固くお断りいたします。
◆所定労働時間が短い日に休業した場合も、平均賃金の6割の休業手当が必要か
 当社には、1週のうち特定の曜日の所定労働時間が通常の日の所定労働時間より短いけ社員がいます。先日、会社施設の増改築工事のため社員に対し休業を命じましたが、その社員については、4時間の勤務が予定されていた日でした。そのため、この社員の休業手当の計算をしたところ、平均賃金の60%相当額が4時間分の時給を上回る結果となりました。
当社には、1週のうち特定の曜日の所定労働時間が通常の日の所定労働時間より短いけ社員がいます。先日、会社施設の増改築工事のため社員に対し休業を命じましたが、その社員については、4時間の勤務が予定されていた日でした。そのため、この社員の休業手当の計算をしたところ、平均賃金の60%相当額が4時間分の時給を上回る結果となりました。
こうした場合でも、平均賃金の60%を休業手当として支払う必要があるのでしょうか。4時間分の時給または4時間分の時給の60%の支払いで済ませることはできないでしょうか。  所定労働時間が短い日に使用者の責めによる事由で休業し、平均賃金の60%が当該日の所定労働時間分の時給を上回る場合においても、平均賃金の60%以上を休業手当として支払う必要があります。ご質問のケースにおいても、4時間分の時給または4時間分の時給の60%の支払いで済ませることはできません。
所定労働時間が短い日に使用者の責めによる事由で休業し、平均賃金の60%が当該日の所定労働時間分の時給を上回る場合においても、平均賃金の60%以上を休業手当として支払う必要があります。ご質問のケースにおいても、4時間分の時給または4時間分の時給の60%の支払いで済ませることはできません。
■解説
1 休業手当
労働基準法26条では、「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない」と定めています。
「使用者の責に帰すべき事由」には、使用者の故意、過失による休業はもちろん、経営上の理由による休業も含まれます。したがって、天災地変等の不可抗力による休業までは含まれませんが、事業所の移転や施設の増改築による一時休業の場合は、「使用者の責に帰すべき休業に該当する」ものとされ、休業した日について平均賃金の100分の60以上の休業手当を支払わなければなりません。
休業手当の算定基礎となる平均賃金について、労働基準法12条1項は、「平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう」としており、さらに2項では、「前項の期間は、賃金締切日がある場合においては、直前の賃金締切日から起算する」と定めています。
当該日以前3ヵ月間に支払われた賃金の総額を総日数で除するため、当該休業日の所定労働時間が通常の日の所定労働時間より短い場合には、ご質問のように、平均賃金の100分の60が、当該日の賃金額を上回ることもあり得ることになります。
2 休業手当の額が休業日の賃金を上回る場合の取り扱い
そこで、4時間の勤務が予定されていた日に休業を命じ、平均賃金の100分の60相当額が4時間分の時給を上回る結果となった場合においても、平均賃金の100分の60を休業手当として支払う必要があるのかというのがご質問の内容ですが、休業手当の趣旨は、平均賃金の100分の60以上に相当する金額の支払いを、使用者に罰則をもって強制することにより、労働者の保護を図ろうとしたものです。したがって、こうした場合でも、平均賃金の100分の60以上に相当する金額を支払わなければならないということになります。
ご質問のケースにおいても、4時間分の時給または4時間分の時給の100分の60の支払いで済ませることはできません。解釈例規においても、「一週中のある日の所定労働時間が、たまたま短く定められていても、その日の休業手当は、平均賃金の100分の60に相当する額を支払わなければならない」とされています。
□根拠法令等
・労働基準法26(休業手当)、21(平均賃金)
・昭27.8.7 基収3445(休業期間が一労働日に満たない場合の休業手当の額)
・内容についての無断転載は固くお断りいたします。
