「●き 桐野 夏生」の インデックッスへ Prev|NEXT ⇒ 【2504】 桐野 夏生 『バラカ』
「●「読売文学賞」受賞作」の インデックッスへ
「実録小説」風伝記小説。面白かった。『浮雲』と比較するとさらに興味深い。

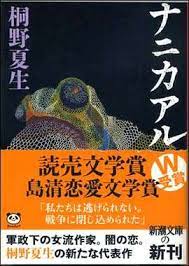
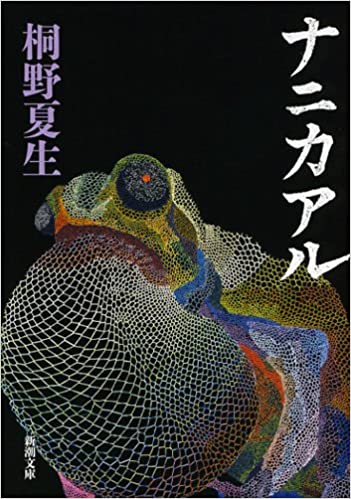
『ナニカアル (新潮文庫)』
『ナニカアル』(2010/02 新潮社)
 2010(平成22)年・第62回「読売文学賞」、2010年度・第17回「島清恋愛文学賞」受賞作。
2010(平成22)年・第62回「読売文学賞」、2010年度・第17回「島清恋愛文学賞」受賞作。
昭和17年、林芙美子は偽装病院船で南方へ向かった。陸軍の嘱託として文章で戦意高揚に努めよ、という命を受けて。ようやく辿り着いたボルネオ島で、新聞記者・斎藤謙太郎と再会する。年下の愛人との逢瀬に心を熱くする芙美子。だが、ここは楽園などではなかった―。
「放浪記」ならぬ、有名になってからの林芙美子(1903-1951/47歳没)を主人公に描いた「ジャワ放浪記」のような「実録小説」風伝記小説。林芙美子は太平洋戦争前期の1942年10月から翌年5月まで、陸軍報道部報道班員(南方視察団団員)としてシンガポール・ジャワ・ボルネオに滞在していて、本作は、林芙美子自身が内密に書いた実録小説という体裁をとることで(画家であった夫・緑敏の死後、絵画の裏に隠されていた文書を、後妻が見つけるという設定)、一般的な伝記小説のスタイルにもう一捻り加えています。
戦時下での、夫がいながらにしての林芙美子の道ならぬ恋が描かれていますが、むしろそちらの方はサイドストーリー的であり、戦争下にある無数の個人を描いくことで、戦争が人々から尊敬と信頼をどのようにして奪うか、そして人々はどのようにして虐げあい、疑いあい、妬みあうようになるかを、主人公自身も含め描いているように思いました。そのあたりが面白かったです。
なお、この作品に出てくる林芙美子の恋人の新聞記者・斎藤のモデルは、東京日日新聞(のち毎日新聞)の海外特派員だった高松棟一郎(1911-1959/48歳没)だそうですが、1926年23歳で手塚緑敏と内縁の結婚をし、それからずうと落ち着いていたのかと思ったら、「恋の放浪」を続けていたということなのでしょうか。
林芙美子は1943年40歳の時に新生児を養子として貰い受けていますが(泰という名のこの男の子は10歳で死亡している)、作者はこの「養子貰い受け」について、実は林芙美子と愛人の間の子ではなかったかという大胆な仮説を展開していて、推理作家としての持ち味も出していました(これが一番書きたかった?)。
 林芙美子の戦後の長編小説『浮雲』と比較するとさらに興味深いと思われます。『浮雲』の主人公ゆき子は農林省のタイピストとして仏印(ベトナム)に渡り、そこで農林省技師の富岡と出会うのですが、その後何度も離れ離れになる富岡には、会おうと思ってもなかなか会えない「新聞記者・斎藤」が反映されていて、一方で、ゆき子のタイピストという職業には、南方視察団の船の三等客室に現地の事務要員として詰め込まれた二十歳前後の若い女性たちが反映されているように思いました。
林芙美子の戦後の長編小説『浮雲』と比較するとさらに興味深いと思われます。『浮雲』の主人公ゆき子は農林省のタイピストとして仏印(ベトナム)に渡り、そこで農林省技師の富岡と出会うのですが、その後何度も離れ離れになる富岡には、会おうと思ってもなかなか会えない「新聞記者・斎藤」が反映されていて、一方で、ゆき子のタイピストという職業には、南方視察団の船の三等客室に現地の事務要員として詰め込まれた二十歳前後の若い女性たちが反映されているように思いました。
しかし、当時非合法であった非合法であった日本共産党に密かに入党していた(芙美子はそのことを本人から示唆される)窪川稲子(佐田稲子)とかも南方視察団に加わっているところをみると、この南方視察団は政府のある種"踏み絵"的施策であり、林芙美子もプロレタリア作家として見られた向きもあるので、一緒くたにされて南方に派遣されたようにも思われます。
 ただし、この作品にも言及されていますが、1937(昭和12)年に盧溝橋事件を契機に日本が日中戦争に突入した際に、社会が軍事色が濃くなる中、作家たちにも協力要請が届き、林芙美子もペン部隊として戦地に赴いていて、1938(昭和13)年10月、激戦地の漢口に入った「漢口一番乗り」で世間の大きな注目を集めたりしています(本人は張り切っていたということか)。
ただし、この作品にも言及されていますが、1937(昭和12)年に盧溝橋事件を契機に日本が日中戦争に突入した際に、社会が軍事色が濃くなる中、作家たちにも協力要請が届き、林芙美子もペン部隊として戦地に赴いていて、1938(昭和13)年10月、激戦地の漢口に入った「漢口一番乗り」で世間の大きな注目を集めたりしています(本人は張り切っていたということか)。
昭和13年、ペン部隊の一員として中国に渡り、他の作家を出し抜き漢口一番乗りを果たした(新宿歴史博物館蔵)
すでに前の年に毎日新聞従軍特派員として南京を訪れ、「女流作家一番乗り」として原稿を送った経験があった林芙美子は、この時も単独行動をとり、注目の地を目指すために集団から離れ、前線に向かう部隊に同行し、途中から朝日新聞の特派員とともに行動して現地に入ったとのこと。「女われ一人・嬉涙で漢口入城」と朝日新聞に華々しく一番乗りが報道された一方で、当時の文壇の実力者・久米正雄が文芸部長としていた毎日新聞から閉め出されたそうで(久米正雄は面目を潰されたと怒ったとか)、注目を浴びるために多少は人間関係を犠牲するのも厭わないハングリーなところは、林芙美子という人にはずっとあったのかもしれないと思います。
【2012年文庫化[新潮文庫]】
