「●「死」を考える」の インデックッスへ Prev|NEXT ⇒ 「●中国思想」 【216】 福永 光司 『荘子』
「脳を分けることができるなら?」という仮説を巡っての考察が新鮮だった。


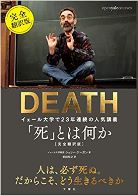
『「死」とは何か イェール大学で23年連続の人気講義 完全翻訳版』
イェール大学で20年以上続いている著者の「死」をテーマにした講義を書籍化したもので、2018年10月に384ページの「縮約版」が刊行され、翌2019年7月にそのほぼ倍の769ページに及ぶ「完訳版」が刊行されています。本書は前半が、「死」とは何かを考察する「形而上学」的なパートになっており、後半が、「死」にどう向き合うかという「人生哲学」的とでも言うべき内容になっていますが、縮約版では、
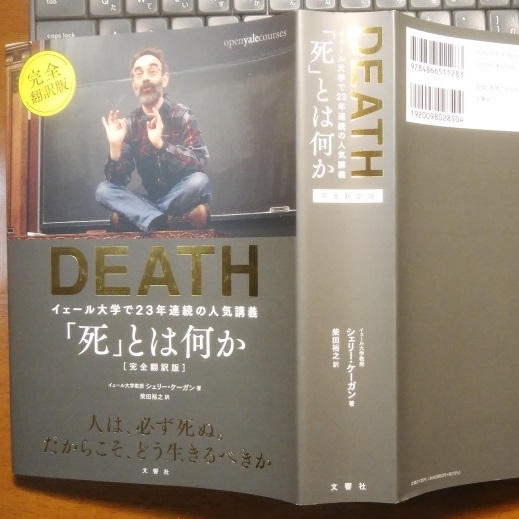 第1講 「死」について考える
第1講 「死」について考える
第2講 二元論と物理主義
第3講 「魂」は存在するか?
第4講 デカルトの主張
第5講 「魂の不滅性」についてのプラトンの見解
第6講 「人格の同一性」について
第7講 魂説、身体説、人格説――どの説を選ぶか?
第8講 死の本質
第9講 当事者意識と孤独感――死を巡る2つの主張
第10講 死はなぜ悪いのか
第11講 不死――可能だとしたら、あなたは「不死」を手に入れたいか?
第12講 死が教える「人生の価値」の測り方
第13講 私たちが死ぬまでに考えておくべき、「死」にまつわる6つの問題
第14講 死に直面しながら生きる
第15講 自殺
の全15講の内、第2講~第7講が割愛されていたようです。縮約版は結構話題になったものの、大幅な割愛に対する読者から不満もあったりして、完訳版の刊行となったようです。
個人的には、後半の「人生哲学」的なパートも悪くなかったですが、結構ありきたりで、やはり前半の「死」とは何かを考察する「形而上学」的なパートが良かったです(実質的には第10講かその前ぐらいまでは、「形而上学」的な要素も結構含まれているとみることもできる)。この本の場合、「死」について考えることはそのまま、「心((魂)」とは何か、「自分」とは何かについて考えることに繋がっているように思いました。
著者の立場としては、「人間=身体+心(魂)」であるという「二元論」を否定し、「人間=身体」であるという「物理主義」を支持しています。現代科学の趨勢からも、個人的にも、確かにそうだろうなあとは思います。つまり、「私」乃至「私の心」とは、ラジオ(身体)から流れてくる音楽(意識)のようなもの(宮城音弥『心とは何か』('81年/岩波新書))で、両者は一体であり、デカルトの言うように「身体」と「心」は別であるという「二元論」は成り立たないと。ただし、頭でそう思っても、無意識的に「二元論」的に自己を捉えている面があることも否定し得ないように思います。
本書では(縮訳で割愛された部分だが)、デカルトの「二元論」や、プラトンの「魂の不滅性」に丁寧かつ慎重に反駁していくと共に、「人格の同一性」(=その同一なものこそが「私」であるという考え)について取り上げ、自分とは何かというテーマに深く入っていき、魂説、身体説、人格説のそれぞれを論理的に検証していきます。
個人的に非常に興味深く思ったのは、魂説、身体説、人格説と並べれば、本書の流れからも身体説が有力であり、実際に本書では、「人格説への異論」を唱えることで「身体説」の有効性を手繰り寄せようとしていますが、同時に、身体説の限界についても考察している点です(第7講)。
わかりやすく言えば、例えば誰かが他人から心臓移植を受けても、その人が「自分」であることは変わらないですが、脳の移植を受ければ、それは脳の持ち主が身体の持ち主になるということ。つまり、身体が滅んでも脳が生き延びれば「自分」は生き延びるということで、これがまさに「身体説」であるということかと思いますが(つまり、「自分」とは脳という「身体」の産物であるということ)、本書では、「脳を分けることができるとしたら?」という思考実験をしています。
つまり(知人の子で、生後すぐに脳腫瘍の手術をして脳が片側しかない子がいて、それでも普通に生活しているが)、仮にある人の右脳と左脳をそれぞれ別の身体に移植したら、「人格」も「身体」も分裂できるのか?、その際に「魂」はどうなるのか?(ここで「魂」論が再び顔を出す)という問題を提起しており、ここから、「魂」も分裂できるのか?(この場合の「魂」は「意識」と言ってもいいのでは)、分裂できない場合、「魂」は誰のものか?、分裂できなければ魂なしの人間が生まれてしまうのか?、といった様々な難問が生じ、「魂」説はこの分裂の仮説に勝てず、さらに、圧倒的にまともに思えた「身体説」も同時に脆弱性を帯びてくるということです。
個人的には、本書の中で、この「脳を分けることができるなら?」という仮説を巡っての考察が、今まで考えたことがなくて最も斬新に感じられ、それを考えさせてくれただけで、本書を読んだ価値はあったように思います。
後半の「死」との向き合い方とでも言うか、死を通しての「人生の価値」の測り方(第12講)などは、どこかでこれまでも考えたことがあるような話であるし(「太く短く」がいいか「細く長く」がいいかとか、「終わり良ければすべて良し」なのかとかは、無意識的に誰もが考えているのでは)、死ぬまでに考えておくべきこと(第13講)、死と直面しながら生きるとはどういうことか(第14講)、自殺の問題(第15講)なども、ものすごく斬新な切り口というわけでもないように思いました。
読者によっては、後半の方が「胸に響いた」という人がいてもおかしくないと思いますが、「余命宣告をされた学生が、"命をかけて"受けたいと願った」授業というキャッチコピーほどではないかも。既視感のある「人生哲学」よりも、やはり「形而上学」のパートがあってこその本書の面白さであり、その部分において新鮮な思考実験を示してくれていたので「◎」としました。

