「●い カズオ・イシグロ」の インデックッスへ Prev|NEXT ⇒ 【2648】 カズオ・イシグロ 『わたしを離さないで』
○ノーベル文学賞受賞者(カズオ・イシグロ)「○海外文学・随筆など 【発表・刊行順】」の インデックッスへ
カズオ・イシグロの「探偵小説」風「母子もの」とでも言えるか。ラストは切ない。
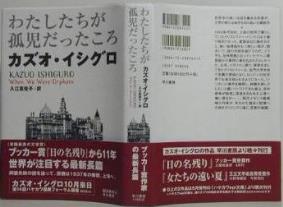

『わたしたちが孤児だったころ (ハヤカワ・ノヴェルズ)』『わたしたちが孤児だったころ (ハヤカワepi文庫)
』
"When We Were Orphans"
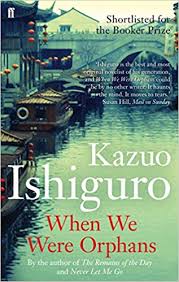
 1923年夏、大学を卒業したクリストファー・バンクス(わたし)は、探偵になるという子供の頃からの夢を胸にロンドンに住んでいた。あるパーティで魅力的な女性サラ・ヘミングスに出逢うが、彼女は有名な男を追いかける性癖があり、探偵として売り出し中の彼に彼女の方から接近してくる。ある日彼女は大きな晩餐会に出入りできるよう彼を利用しようとするが、彼が拒否したため強引に中に入り、将来の夫となるサー・セシルに取り入ることに成功する。彼女は、つまらない男と添って人生を無駄にしたくないと言う。そして自分は孤児であると。クリストファーも子供の頃過ごした上海で両親が行方不明になった孤児だった。上海時代の親友はアキラという日本人の少年で、彼と毎日のように遊んだ。クリストファーの母は美しく、高い理想の持ち主で、夫の勤める会社がアヘンを輸入していることに心を痛め、反対運動に尽力し、父は母の期待に応えられないことに苦悩していた。反対派の一人フィリップおじさんはよく家に来てクリストファーと遊んでくれ、クリストファーも彼が好きだった。ある日突然その父が失踪する。後に、ある事件の調査中、クリストファーは軍閥の重要人物ワン・クーの写真を手に入れるが、それは父の失踪後まもなく家に来て母に罵られた男だった。この出来事の後、クリストファーがフィリップおじさんに連れられ買物に出ている間に、母までもが失踪したのだ。彼は英国の叔母の元に預けられ、以来アキラとは会っていない。後にクリストファーは両親を亡くした気丈な少女ジェニファーを養女にする。1937年、世界は戦争に向けて転がりだし、彼はそんな世界を自分が救わなくてはと感じ、上海で自らの使命が解決されると信じる。同じ頃、セシルと妻のサラも上海へと移る。クリストファーは、両親はアヘン事件に関わって誘拐され、いまだに拘束されていると信じ、助け出せば世界も救えると思っている。ジェニファーは彼の妄想を見抜いていた。上海でイエロースネークと呼ばれる情報提供者に会えるよう打診するが、役人からは色よい返事はない。日本軍の砲撃は既に始まっていた。セシルは影響力を失って賭けごとに溺れ、クリストファーはかつて両親の失踪事件を担当していたクン警部を探し出す。警部はひどく落ちぶれていたが、手掛かりを思い出したら連絡すると約束してくれた。そんな折、サラからセシルと別れるから一緒に駆け落ちしてほしいと頼まれ、彼は同意する。その直後にクン警部から両親が幽閉されているであろう場所について連絡が入り、彼はサラを残してその場所に向かう。そこは日本軍との戦闘地帯になっていて、中国軍将校の助けを得て瓦礫の街を進むが、将校は途中で帰り、彼は一人戦場を彷徨う。迷路のような地形の中、重傷を負って倒れている日本兵を見つけ、きっとあれはアキラだ、一緒に両親を助け出すために来てくれたのだと思う。アキラに似た男の道案内で目的の建物に辿り着くが、そこは半ば破壊され、二人は日本軍に捕まり、アキラらしい男は情報を流した罪で逮捕され、クリストファーは領事館に送り返される。ここで彼はフィリップおじさんと再会し、おじさんから、両親失踪事件の真相を知らされる―。
1923年夏、大学を卒業したクリストファー・バンクス(わたし)は、探偵になるという子供の頃からの夢を胸にロンドンに住んでいた。あるパーティで魅力的な女性サラ・ヘミングスに出逢うが、彼女は有名な男を追いかける性癖があり、探偵として売り出し中の彼に彼女の方から接近してくる。ある日彼女は大きな晩餐会に出入りできるよう彼を利用しようとするが、彼が拒否したため強引に中に入り、将来の夫となるサー・セシルに取り入ることに成功する。彼女は、つまらない男と添って人生を無駄にしたくないと言う。そして自分は孤児であると。クリストファーも子供の頃過ごした上海で両親が行方不明になった孤児だった。上海時代の親友はアキラという日本人の少年で、彼と毎日のように遊んだ。クリストファーの母は美しく、高い理想の持ち主で、夫の勤める会社がアヘンを輸入していることに心を痛め、反対運動に尽力し、父は母の期待に応えられないことに苦悩していた。反対派の一人フィリップおじさんはよく家に来てクリストファーと遊んでくれ、クリストファーも彼が好きだった。ある日突然その父が失踪する。後に、ある事件の調査中、クリストファーは軍閥の重要人物ワン・クーの写真を手に入れるが、それは父の失踪後まもなく家に来て母に罵られた男だった。この出来事の後、クリストファーがフィリップおじさんに連れられ買物に出ている間に、母までもが失踪したのだ。彼は英国の叔母の元に預けられ、以来アキラとは会っていない。後にクリストファーは両親を亡くした気丈な少女ジェニファーを養女にする。1937年、世界は戦争に向けて転がりだし、彼はそんな世界を自分が救わなくてはと感じ、上海で自らの使命が解決されると信じる。同じ頃、セシルと妻のサラも上海へと移る。クリストファーは、両親はアヘン事件に関わって誘拐され、いまだに拘束されていると信じ、助け出せば世界も救えると思っている。ジェニファーは彼の妄想を見抜いていた。上海でイエロースネークと呼ばれる情報提供者に会えるよう打診するが、役人からは色よい返事はない。日本軍の砲撃は既に始まっていた。セシルは影響力を失って賭けごとに溺れ、クリストファーはかつて両親の失踪事件を担当していたクン警部を探し出す。警部はひどく落ちぶれていたが、手掛かりを思い出したら連絡すると約束してくれた。そんな折、サラからセシルと別れるから一緒に駆け落ちしてほしいと頼まれ、彼は同意する。その直後にクン警部から両親が幽閉されているであろう場所について連絡が入り、彼はサラを残してその場所に向かう。そこは日本軍との戦闘地帯になっていて、中国軍将校の助けを得て瓦礫の街を進むが、将校は途中で帰り、彼は一人戦場を彷徨う。迷路のような地形の中、重傷を負って倒れている日本兵を見つけ、きっとあれはアキラだ、一緒に両親を助け出すために来てくれたのだと思う。アキラに似た男の道案内で目的の建物に辿り着くが、そこは半ば破壊され、二人は日本軍に捕まり、アキラらしい男は情報を流した罪で逮捕され、クリストファーは領事館に送り返される。ここで彼はフィリップおじさんと再会し、おじさんから、両親失踪事件の真相を知らされる―。
"When We Were Orphans"
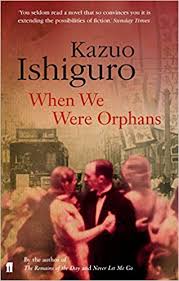
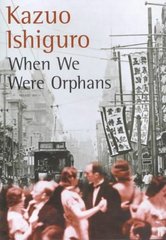 2017年のノーベル文学賞受賞者となったカズオ・イシグロの2000年に刊行された作品で(原題:When We Were Orphans)、長編第5作にあたり、作者は発表時45歳です(作者はその後、63歳でのノーベル賞受賞までに、長編は『わたしを離さないで(Never Let Me Go)』と『忘れられた巨人(The Buried Giant)』の2作しか発表していない)。本作は出版と同時にベストセラーとなったほか、英米で評論家などからも高く評価され、ブッカー賞とウィットブレッド賞にノミネートされています。但し、作者のこれまでの作品『日の名残り(The Remains of the Day)』や『わたしを離さないで(Never Let Me Go)』のように映画化される予定は今のところないようなので、ややストーリーを詳しく書きました(「上海の伯爵夫人(The White Countess)」('05年/米)という作者のオリジナル脚本を映画化した作品があり、1930年代の上海が舞台で、しかも日中戦争前後を描いているが、本作とは全く別の話である)。
2017年のノーベル文学賞受賞者となったカズオ・イシグロの2000年に刊行された作品で(原題:When We Were Orphans)、長編第5作にあたり、作者は発表時45歳です(作者はその後、63歳でのノーベル賞受賞までに、長編は『わたしを離さないで(Never Let Me Go)』と『忘れられた巨人(The Buried Giant)』の2作しか発表していない)。本作は出版と同時にベストセラーとなったほか、英米で評論家などからも高く評価され、ブッカー賞とウィットブレッド賞にノミネートされています。但し、作者のこれまでの作品『日の名残り(The Remains of the Day)』や『わたしを離さないで(Never Let Me Go)』のように映画化される予定は今のところないようなので、ややストーリーを詳しく書きました(「上海の伯爵夫人(The White Countess)」('05年/米)という作者のオリジナル脚本を映画化した作品があり、1930年代の上海が舞台で、しかも日中戦争前後を描いているが、本作とは全く別の話である)。
面白く読め、こんなに面白くていいのかなという印象も(ラストは重けれども)。体裁はあたかも、子どもから大人へと成長した主人公が過去の両親失踪事件の謎を解決する「探偵小説」のようにも見えますが、作者は「週刊文春」2001年11月8日号の対談「阿川佐和子のこの人に会いたい」で、「最初はアガサ・クリスティ的な英国の典型的な探偵ものを書こうと目論んでいたのがなかなかその通りにいかなくて(中略)探偵ものにこだわるのはやめた」と述べており、終盤にフィリップおじさんによる「謎解き」のようなものはあるものの、物語を構成する上で「探偵小説の形を借りた」と言った方が適切かと思われます。探偵小説として読んでしまうと、メインストーリーはともかく、「わたしたちが孤児だったころ」の「たち」という言い方の元になっている、主人公と同じ孤児であるサラやジェニファーについての記述は謎解きの伏線になってはおらず、結局サラの行く末は事後譚で語られ、ジェニファーもこの先どうなるのかよく分からないままで終わっています。
更に、終盤の主人公が上海の日本軍との戦闘地帯を彷徨う様は夢現(ゆめうつつ)状態のような感じで、両親がその近くに拘束されているという主人公の確信も、両親の失踪が10数年前だったことからすれば全く根拠はなく、また、主人公は日本兵を見つけ、それをアキラだと思い込むなど、表現上は殆ど幻想文学の世界に入っている感じがしました。(因みに、作者の『充たされざる者(The Unconsoled)』は全編、カフカ的な幻想小説と言えるのではないか)。
それでいてやはり「探偵小説の形を借りて」いるわけであって、探偵である主人公が何か自力で謎解きをしたわけではないですが、ラストでフィリップおじさんから、ちょうど「探偵小説」のラストのように、衝撃の事実が明かされます。その事実は切なかったです。そして、ラストの再会―こうした場面は、個人的にはどこか既視感がありました。これ、カズオ・イシグロの母子ものと言うか、そう言えば、谷崎潤一郎にも「母を恋うる記」というのがあり、山口瞳が自分の母親について書いた『血族』などもそうした系譜の作品でしたが、男はみんなマザコンなのか(?)。その意味でこの作品は一部「日本的」な感じもしますが、一方で、「英国的」な探偵小説の要素を織り込むことで、ラストも切ないことは切ないですが、日本的なウェットな感じではなく、意外と乾いた読後感の作品に仕上がっているように思いました。
『日の名残り』『わたしを離さないで』同様、語り手が自らの記憶を辿っていきながら、過去を見つめ直す話でもあります。もしかしたら、われわれは皆、過ぎ去った過去の人生において精神的に取り戻したい何かを抱えているのかもしれません。『日の名残り』も『わたしを離さないで』もそうですが、読み手の日常生活とかけ離れたシチュエーションを描きながら、読者をそうした普遍的な思いに駆りたてる作品でもあり、それがラストの切なさにつながっていると思います。
【2006年文庫化[ハヤカワepi文庫]】
《》
●カズオ・イシグロのこれまで発表した長編小説 (出版年 邦題 原題)
1982年 遠い山なみの光 A Pale View of Hills
1986年 浮世の画家 An Artist of the Floating World
1989年 日の名残り The Remains of the Day
1995年 充たされざる者 The Unconsoled
2000年 わたしたちが孤児だったころ When We Were Orphans
2005年 わたしを離さないで Never Let Me Go
2015年 忘れられた巨人 The Buried Giant
