「●歌謡曲」の インデックッスへ Prev|NEXT ⇒「●スポーツ」【1773】 朝日新聞社 『'64 東京オリンピック』
「●岩波新書」の インデックッスへ 「●「菊池寛賞」受賞者作」の インデックッスへ(阿久 悠)
ヒットメーカーによる自伝的歌謡曲史。楽しく、懐かしく読めた1冊。


『愛すべき名歌たち (岩波新書)』阿久 悠 作詞の初ヒット曲「白い蝶のサンバ」(1970、森山加代子)
『愛すべき名歌たち』('99年/岩波新書)は、作詞家・阿久悠(あく・ゆう)(1937-2007/享年70)が、1997年4月から1999年4月にかけて「朝日新聞」夕刊芸能面に通算100回連載したコラムの新書化で、『書き下ろし歌謡曲』('97年/岩波新書)に続く著者2冊目の岩波新書です。
サブタイトルに「私的昭和歌曲史」とあるように、高峰三枝子の「湖畔の宿」から始まって美空ひばりの「川の流れのように」まで全100曲を選び、自分史に重ねる形で、それぞれぞれの時代に流行った歌謡曲やそれに纏わる思い出が書き綴られており、半ば自伝とも言える体裁。当然のことながら、後半はヒットメーカーとして知られた著者自身が作詞家として関わった曲が多く取り上げられています(Wikipediaで取り上げている曲の一覧を見ることが出来る)。
それらの時代区分としては、以下の通りとなっています。
Ⅰ 〈戦後〉という時代の手ざわり(1940~1954)(幼年時代;高校まで)
Ⅱ 都会の響きと匂い(1955~1964)(大学時代;広告の世界で)
Ⅲ 時代の変化を感じながら(1964~1971)(放送作家時代;遅れてきた作詞家)
Ⅳ 競いあうソングたち(1971~1975)(フリー作家の時代;新感覚をめざして)
Ⅴ 時代に贈る歌(1976~1989)(歌の黄金時代)
非常に読み易く、文章をよく練っている印象。個人的には第Ⅰ章の自伝色が強い部分と、やはり第Ⅱ章の最初の広告業界に入った頃の話が特に興味深く読めました。
著者が就職活動をしたのは1958(昭和33)年で不況の折でしたが、当時はテレビ番組の「月光仮面」が驚異的な視聴率でブームを巻き起こしていて、その仕掛け人である広告会社が就職先の選択肢となり得たとのこと。但し、本書には書かれていませんが、この番組は当初スポンサーが付かず、広告会社(宣弘社)が自らプロダクションを興して制作にあたった番組でした(著者は結局、この会社=宣弘社にコピーライターとして7年間務めることになる)。

 作詞家に転じてからの著者は、最初の作品「朝まで待てない」を出して以来、3年間結果が残せていなかったとのことで、初の本格ヒットがが生まれたのは、本書の第Ⅲ章も終わり近い1970(昭和45)年の「白い蝶のサンバ」でした(森山加代子はこの曲でNHK紅白歌合戦に8年ぶりの出場を果たす)。個人的にもちょうど歌番組など観るようになった頃で、懐かしい曲でありました(早口言葉みたな感じの歌として流行ったけれど、著者が言うように、今みるとそんなに早口というわけでもない)。
作詞家に転じてからの著者は、最初の作品「朝まで待てない」を出して以来、3年間結果が残せていなかったとのことで、初の本格ヒットがが生まれたのは、本書の第Ⅲ章も終わり近い1970(昭和45)年の「白い蝶のサンバ」でした(森山加代子はこの曲でNHK紅白歌合戦に8年ぶりの出場を果たす)。個人的にもちょうど歌番組など観るようになった頃で、懐かしい曲でありました(早口言葉みたな感じの歌として流行ったけれど、著者が言うように、今みるとそんなに早口というわけでもない)。
本書は、作詞家・阿久悠の「自分史」を軸とした歌謡曲史でしたが、一方、同じく岩波新書の高譲(こう・まもる)著『歌謡曲―時代を彩った歌たち』('11年/岩波新書)の方は、客観的な「ディスコグラフィ(Discography)」としての歌謡曲史でした。この中で、目次をの'節'のタイトルに「阿久悠の時代」というのがあり、目次で個人名が出てくるは著者だけでした。こうしたことからも、やはり、歌謡曲史に大きな足跡を残した人物と言えるのでしょう。楽しく、また懐かしく読めた1冊でした。
 『歌謡曲―時代を彩った歌たち』の方は、版元の紹介文によれば―、
『歌謡曲―時代を彩った歌たち』の方は、版元の紹介文によれば―、
「ディスコグラフィ(Discography)」という言葉があります.日本では「アーティストの作品目録」として理解されることの多い言葉ですが、本来の意味からするとむしろ、その楽曲は、だれが、どのように作り出したのか、どう歌われているのかを客観的に考察する、学術的な分野を指します。著者の高護さんは、知る人ぞ知る、歌謡曲では唯一無二のディスコグラファーです。その該博な知識と確かな分析で、歌謡曲の魅力をあますところなく解説します
―とのことです。
『歌謡曲――時代を彩った歌たち (岩波新書)』
歌謡曲とは何かということについてはいろいろ議論はあるかと思われますが、この本ではそうした"概論"乃至"総論"的な話はせず、いきなり歌謡曲史に入っており、各1章ずつ割いている60年代、70年代、80年代が本書の中核を成しています。ものすごく網羅的ですが、一方で、一世を風靡した、或いは時代を画した歌手や歌曲には複数ページを割いて解説するど、メリハリが効いています。読んでいくと、グループサウンズ、例えば「タイガース」などは、専らソロ歌手としての沢田研二に絞って取り上げていたりし、ジャニーズ系も「たのきんトリオ」以降グループとしては全然触れられておらず、後の方に出てくる「おニャン子クラブ」などもソロになった新田恵利だけが取り上げられています。この続きが書かれるとしたら、「AKB48」などは入ってこないのかなあ。ザ・ピーナッツ(伊藤エミ(1941-2012)、伊藤ユミ(1941-2016))とかは当然取り上げているわけで、和製ポップスは取り上げ、J-ポップは取り上げないというわけでもないでしょうが(J-ポップが登場したのが'88年頃なので、殆ど本書の対象期間とずれていて何とも言えない)。ニューミュージックも取り上げていますが、そもそもどこからどこまでがニューミュージックなのか分かりませんけれど(森進一が歌いレコード大賞曲となった「襟裳岬」は吉田拓郎の曲だった)。あまり考えすぎると楽しめないのかもしれず、本書が歌謡曲とは何かという議論を避けているのは、ある意味賢い選択であったかも。
ザ・ピーナッツ(活動期間:1959-1975)「恋のバカンス」(1975年 さようならピーナッツ)
因みに、ザ・ピーナッツの「恋のバカンス」('63年)の作曲者は宮川泰ですが、「恋のフーガ」('67年)の作曲者は、後に「ドラゴンクエスト」のテーマ曲で世界 的に知られることになる作曲家のすぎやまこういち(1931-2021/90歳没)。「音大志望だったがお金がなかったから東大に進学した」と東京大学理科II類に進学、東大卒業後は文化放送を経てフジテレビに入社、ラジオのヒットパレード番組をテレビに移植した形になる「ザ・ヒットパレード」を企画し、自らディレクターをしていたので、ザ・ピーナッツとその頃から接点があったのかもしれません。1968年から作曲活動に専念。作曲家としてザ・タイガース(彼らの命名者でもある)やザ・ピーナッツの黄金時代を支えた人物です。
的に知られることになる作曲家のすぎやまこういち(1931-2021/90歳没)。「音大志望だったがお金がなかったから東大に進学した」と東京大学理科II類に進学、東大卒業後は文化放送を経てフジテレビに入社、ラジオのヒットパレード番組をテレビに移植した形になる「ザ・ヒットパレード」を企画し、自らディレクターをしていたので、ザ・ピーナッツとその頃から接点があったのかもしれません。1968年から作曲活動に専念。作曲家としてザ・タイガース(彼らの命名者でもある)やザ・ピーナッツの黄金時代を支えた人物です。
歌手に限らず、作詞家、作曲家、編曲家まで取り上げており、確かに阿久悠の存在は大きいけれど、その前にも 岩谷時子(作詞)・いずみたく(作曲)といった強力なコンビがいて「夜明けのうた」('64年/歌:岸洋子)、「太陽のあいつ」('67年/歌:ジャニーズ)、「恋の季節」('68年/歌:ピンキーとキラーズ)等々、数多くのヒットを生んでいるし(2人とも歌謡曲が"本業"でも"専業"でもなかったという点が興味深い)、五木ひろしの芸名の名付親だった「よこはま・たそがれ」('71年)の山口洋子 (1937-2014)なども平尾昌晃(1937-2017/79歳没)と最強タッグを組んでいたし(山口洋子は同じ作詞家で直木賞受賞作家でもあるなかにし礼
(1937-2014)なども平尾昌晃(1937-2017/79歳没)と最強タッグを組んでいたし(山口洋子は同じ作詞家で直木賞受賞作家でもあるなかにし礼 よりも15年前に直木賞を受賞している)、作曲家では「ブルー・ライト・ヨコハマ」('69年/歌:いしだあゆみ)以来、この本の終わり、つまり80年代終わりまでこの世界のトップに君臨し続け、70年代、80年代を席
よりも15年前に直木賞を受賞している)、作曲家では「ブルー・ライト・ヨコハマ」('69年/歌:いしだあゆみ)以来、この本の終わり、つまり80年代終わりまでこの世界のトップに君臨し続け、70年代、80年代を席 巻した筒美京平(1940-2020/80歳没)なんてスゴイ人もいました(因みに、阿久悠作詞、筒美京平作曲で最初で最大のヒット曲は日本レコード大賞の大賞受賞曲「また逢う日まで」('71年/歌:尾崎紀世彦(1943-2012))。これもまた、懐かしい思いで読めた1冊でした。
巻した筒美京平(1940-2020/80歳没)なんてスゴイ人もいました(因みに、阿久悠作詞、筒美京平作曲で最初で最大のヒット曲は日本レコード大賞の大賞受賞曲「また逢う日まで」('71年/歌:尾崎紀世彦(1943-2012))。これもまた、懐かしい思いで読めた1冊でした。
《読書MEMO》
●『歌謡曲―時代を彩った歌たち』章立て
序 章
戦前・戦後の歌謡曲
第1章 和製ポップスへの道―1960年代
1960年代概説
1 新たなシーンの幕開け
2 カヴァーからのはじまり
3 青春という新機軸
4 ビート革命とアレンジ革命
5 新しい演歌の夜明け
第2章 歌謡曲黄金時代―1970年代
1970年代概説
1 歌謡曲の王道
2 アイドル・ポップスの誕生
3 豊饒なる演歌の世界
4 阿久悠の時代
第3章 変貌進化する歌謡曲―1980年代
1980年代概説
1 シティ・ポップスの確立
2 演歌~AOR歌謡の潮流
3 アイドルの時代
終 章 90年代の萌芽―ダンス・ビート歌謡

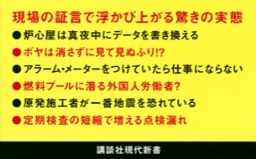

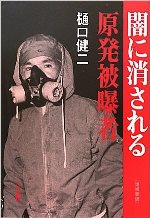




 この内、「
この内、「 原節子の小津映画初めての号泣場面を分析した後、第7章で、「娘は父親と性的結合を望んでいたか」というテーマを扱い、これまで多くの映画評論家が指摘してきたこの作品に対する読解(高橋治『絢爛たる影絵』、蓮實重彦『
原節子の小津映画初めての号泣場面を分析した後、第7章で、「娘は父親と性的結合を望んでいたか」というテーマを扱い、これまで多くの映画評論家が指摘してきたこの作品に対する読解(高橋治『絢爛たる影絵』、蓮實重彦『

 第8章では「
第8章では「 朝日新聞「号外」2015年11月25日
朝日新聞「号外」2015年11月25日




 「東京物語」
「東京物語」
 「東京物語」のみに絞って述べているのが特徴的で、複数の作品間の連関や作品同士の相似を語る蓮實重彦氏などとは対照的と言えるかも。サブタイトルにある「世界はべスト1に選んだ」とは、"Sight & Sound"誌・映画監督による選出トップ10 (Director's Top 10 Films)(2012年版)の上位100作品のトップに「東京物語」があっさり選ばれてしまったことを指しており、そのことを切り口に、第1章で、外国人映画監督から見て、この作品がどう見えるのかを検証していますが、そこから、この作品が「日本映画」だからということで評価されているわけではないということが浮かび上がってくるのが興味深いです。
「東京物語」のみに絞って述べているのが特徴的で、複数の作品間の連関や作品同士の相似を語る蓮實重彦氏などとは対照的と言えるかも。サブタイトルにある「世界はべスト1に選んだ」とは、"Sight & Sound"誌・映画監督による選出トップ10 (Director's Top 10 Films)(2012年版)の上位100作品のトップに「東京物語」があっさり選ばれてしまったことを指しており、そのことを切り口に、第1章で、外国人映画監督から見て、この作品がどう見えるのかを検証していますが、そこから、この作品が「日本映画」だからということで評価されているわけではないということが浮かび上がってくるのが興味深いです。 登場人物・俳優に関しては、第5章「生活人」のところで、杉村春子の演技を「無邪気なまでの呼吸するようなエゴイズム」「はたして杉村春子という女優を欠いて、この人物造形が成功していただろうか」としているのに共感し(小津安二郎が杉村春子の演技を非常に高く評価していたという話をどこかで読んだ記憶がある)、背景に関しては、第10章「夏について」で、夏以外の季節で撮られたならば「東京物語」は全く違った作品になっていただろうという見方にも共感しました。
登場人物・俳優に関しては、第5章「生活人」のところで、杉村春子の演技を「無邪気なまでの呼吸するようなエゴイズム」「はたして杉村春子という女優を欠いて、この人物造形が成功していただろうか」としているのに共感し(小津安二郎が杉村春子の演技を非常に高く評価していたという話をどこかで読んだ記憶がある)、背景に関しては、第10章「夏について」で、夏以外の季節で撮られたならば「東京物語」は全く違った作品になっていただろうという見方にも共感しました。 第12章「軽さについての」での、小料理屋における周吉(笠智衆)、沼田(東野英治郎)、服部(十朱久雄)の会話シーンのセリフを引用した分析も秀逸でした(セリフが全て、オリジナルの文語の脚本から引用されているが、この文語の"語感"が何故か作品の雰囲気に非常にマッチしているように思われたのは、個人的には新たな発見だった)。
第12章「軽さについての」での、小料理屋における周吉(笠智衆)、沼田(東野英治郎)、服部(十朱久雄)の会話シーンのセリフを引用した分析も秀逸でした(セリフが全て、オリジナルの文語の脚本から引用されているが、この文語の"語感"が何故か作品の雰囲気に非常にマッチしているように思われたのは、個人的には新たな発見だった)。
 藤高順●時間:136分●出演:笠智衆/東山千榮子/原節子/香川京子/三宅邦子/杉村春子/中村伸郎/山村聰/大坂志郎/十朱久雄/東野英治郎/長岡輝子/高橋豊子/桜むつ子/村瀬禪/安部徹/三谷幸子/毛利充宏/阿南純子/水木涼子/戸川美子/糸川和広●公開:1953/11●配給:松竹●最初に観た場所:三鷹オスカー(82-09-12)(評価:★★★★☆)●併映:「彼岸花」(小津安二郎)/「秋刀魚の味」(小津安二郎) 杉村春子、中村伸郎 / 笠智衆、東野英治郎
藤高順●時間:136分●出演:笠智衆/東山千榮子/原節子/香川京子/三宅邦子/杉村春子/中村伸郎/山村聰/大坂志郎/十朱久雄/東野英治郎/長岡輝子/高橋豊子/桜むつ子/村瀬禪/安部徹/三谷幸子/毛利充宏/阿南純子/水木涼子/戸川美子/糸川和広●公開:1953/11●配給:松竹●最初に観た場所:三鷹オスカー(82-09-12)(評価:★★★★☆)●併映:「彼岸花」(小津安二郎)/「秋刀魚の味」(小津安二郎) 杉村春子、中村伸郎 / 笠智衆、東野英治郎

![[野いちご]撮影中のベルイマン.jpg](http://hurec.bz/book-movie/%5B%E9%87%8E%E3%81%84%E3%81%A1%E3%81%94%5D%E6%92%AE%E5%BD%B1%E4%B8%AD%E3%81%AE%E3%83%99%E3%83%AB%E3%82%A4%E3%83%9E%E3%83%B3.jpg)





 大河内 直彦 氏(海洋研究開発機構)
大河内 直彦 氏(海洋研究開発機構) 
 まさに、著者がまえがきで述べているように、「地球上の珍奇な場所や驚くべき出来事について、科学の視点を交えながら紹介する8つのストーリー」であり、興味深い話が盛り沢山でした。話のスケールが大き過ぎたり不思議すぎたりして、ついつい現実感が無くなりそうにもなりますが(1986年、カメルーン・ニオス湖で「湖水爆発」により1700人余りが二酸化炭素中毒または酸欠で死亡したという話は知らなかった。悲劇が再発しないよう、日本の政府開発援助で二酸化炭素を強制排出するポンプが設置され、ガス抜きをしているとのこと)、一方で、随所でより身近な話を旨く織り込んで、現実に引き寄せているといった印象です。
まさに、著者がまえがきで述べているように、「地球上の珍奇な場所や驚くべき出来事について、科学の視点を交えながら紹介する8つのストーリー」であり、興味深い話が盛り沢山でした。話のスケールが大き過ぎたり不思議すぎたりして、ついつい現実感が無くなりそうにもなりますが(1986年、カメルーン・ニオス湖で「湖水爆発」により1700人余りが二酸化炭素中毒または酸欠で死亡したという話は知らなかった。悲劇が再発しないよう、日本の政府開発援助で二酸化炭素を強制排出するポンプが設置され、ガス抜きをしているとのこと)、一方で、随所でより身近な話を旨く織り込んで、現実に引き寄せているといった印象です。 例えば、東京の下町と山の手は地質学上どうやって出来たかとか、有馬温泉は泉温が90度を超える非常に高温な温泉で、しかも周囲には火山がないのは希有なことであるとかいった話は、東京のその地質学上の山の手の下町の境界近くに住み、実家がその有馬温泉に近い神戸である自分にとっては、とりわけ興味深く読めました。
例えば、東京の下町と山の手は地質学上どうやって出来たかとか、有馬温泉は泉温が90度を超える非常に高温な温泉で、しかも周囲には火山がないのは希有なことであるとかいった話は、東京のその地質学上の山の手の下町の境界近くに住み、実家がその有馬温泉に近い神戸である自分にとっては、とりわけ興味深く読めました。