「●原発・放射能汚染問題」の インデックッスへ Prev|NEXT ⇒ 【1728】 堀江 邦夫/水木 しげる 『福島原発の闇』
「●写真集」の インデックッスへ
原発労働者の被曝によって受けた苦しみを如実に伝える写真集。日本のエネルギー産業の暗黒史。
 『原発崩壊
『原発崩壊』(2011/08 合同出版)
 樋口健二 氏
樋口健二 氏
(26.8 x 21.8 x 1.4 cm)
原発で働く労働者や原発の付近に住む人々の暮らしぶりを40年近くに渡って取り続けてきた樋口健二氏の、これまで発表してきた写真に、福島第一原発事故後に撮った写真を加えて、ハードカバー大型本として刊行したもの。
中盤部分の、かつて原発施設内で働いていて骨髄性白血病やがんで亡くなった人の亡くなる前の闘病中の写真や、亡くなった後の遺影を抱えた遺族の写真、更に、亡くなるに至らないまでも、所謂「ぶらぶら病」と言う病いに苦しんでいる様子を撮った写真などが、とりわけ衝撃的です。
それらには、樋口氏自身が取材した故人や遺族、闘病中の人たちへのインタビューも付されていて、原発作業員の多くが、原発の危険性を何となく知りながらも具体的な説明を十分に受けることなく、危険性の高いわりには無防備で過酷な環境の中で作業に従事し、知らずの内に被曝し、重い病いとの闘いを強いられたことが窺えます。
その中には、日本で初めて原発被曝裁判を提訴した岩佐嘉寿幸さん(故人)の写真もありますが、原子炉建屋内の2時間半の作業に1回従事しただけで被曝し、重い皮膚炎に苦しみ続けることになった岩佐さんは、それが"放射能性皮膚炎"であると診断した医師の助言と協力により、国と敦賀原発(日本原子力発電)を訴えましたが、政府と日本原電が編成した特別調査団による'被曝の事実無し'との政治的判断の下、敗訴しています。
しかし、岩佐さんのように世の表に現れた原発被曝者は氷山の一角であり、多くの原発被曝者が、原発での被曝が病いの原因だと確信しつつも、もの言えぬまま亡くなったり、生涯を寝たきりで過ごすことになった事実が窺えます。
 本書によれば、1970年から2009年までに原発に関わった総労働者数は約200万人、その内の50万人近い下請け労働者の放射線被曝の存在があり、死亡した労働者の数は約700人から1000人とみていいとのこと。
本書によれば、1970年から2009年までに原発に関わった総労働者数は約200万人、その内の50万人近い下請け労働者の放射線被曝の存在があり、死亡した労働者の数は約700人から1000人とみていいとのこと。
こうした原発下請け労働者の労働形態についても解説されていて、下請、孫請け、ひ孫請け、更に親方(人出し業)がいて、その下に農漁民や非差別部落民、元炭鉱夫や寄せ場の労働者などがおり、しかも、この人出し業をやっているのは暴力団であったりするわけで、ここに一つのピラミッドの底辺的な差別の構造があるとのことです。
こうした人達は、被曝してもまず労災申請が認められることはこれまで無く、そうした働き方と犠牲の上に原発による電力供給がこれまで成り立ってきたことを思うと、あまりに歪な構造であったと思わざるを得ません(これはまさに、日本のエネルギー産業の暗黒史!)。
結局、原発というのは、被曝労働による犠牲を抜きにしては成り立たないものなのでしょう。併せて、近隣住民の健康と生活をも破壊してきたわけで、こんなことまでして原発を存続させる意義は、どこにも無いように思われます。
樋口健二氏 講演会・写真展ポスター

 鎌田 慧 氏
鎌田 慧 氏 





 東日本大震災による福島第一原発事故は、「想定外の天災」などではなく「人災」であるとして、30年以上前、チェルノブイリ事故直後に『危険な話』(′87年/八月書館、'89年/新潮文庫)を刊行した作家・広瀬隆氏(67歳)と、10年前に浜岡原発事故のシミュレーションを連載し、『原発崩壊』(′07年/金曜日)を刊行したルポライター・明石昇二郎(49歳)の2人が、「あってはいけないことを起こしてしまった」構造とその責任の所在を、"実名"を挙げて徹底的に曝した対談です。
東日本大震災による福島第一原発事故は、「想定外の天災」などではなく「人災」であるとして、30年以上前、チェルノブイリ事故直後に『危険な話』(′87年/八月書館、'89年/新潮文庫)を刊行した作家・広瀬隆氏(67歳)と、10年前に浜岡原発事故のシミュレーションを連載し、『原発崩壊』(′07年/金曜日)を刊行したルポライター・明石昇二郎(49歳)の2人が、「あってはいけないことを起こしてしまった」構造とその責任の所在を、"実名"を挙げて徹底的に曝した対談です。



 大島 堅一 氏
大島 堅一 氏 2011年11月23日 朝日新聞・朝刊
2011年11月23日 朝日新聞・朝刊
 石橋克彦 氏(2011年5月23日参議院行政監視委員会)
石橋克彦 氏(2011年5月23日参議院行政監視委員会)
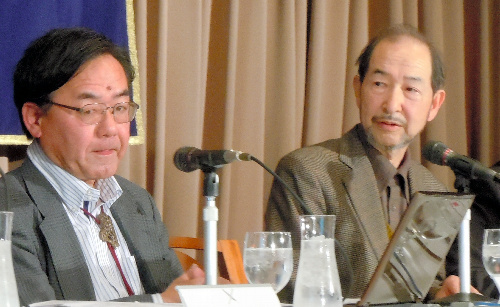 井野博満・東京大学名誉教授(金属材料学)を編者として3人の筆者から成り、第1章「福島原発事故の原因と結果」では、井野氏が福島原発事故について科学的・専門的に解説するとともに、事故の収束が見えない現状から、今後どのような経過が考えられるのか、詳説しています。
井野博満・東京大学名誉教授(金属材料学)を編者として3人の筆者から成り、第1章「福島原発事故の原因と結果」では、井野氏が福島原発事故について科学的・専門的に解説するとともに、事故の収束が見えない現状から、今後どのような経過が考えられるのか、詳説しています。








 九州電力玄海原子力発電所(佐賀県玄海町)3号機のプルサーマル発電計画について、佐賀県が'05年12月に公開討論会を主催した際、九電が動員した社員や関連会社員らが参加者全体の半数近くも出席していて、導入推進側に有利な"やらせ質問"をするととともに、参加者アンケートにも"積極"回答していたことが明らかになったのは、東日本大震災後の同原発の運転再開を巡る九州電力の"やらせメール事件"が明るみに出た直後の昨年('11年)7月のこと(5年以上前の全国で最初に行われたこのプルサーマル公聴会の時から"やらせ"は常態化していたわけだ)、その公聴会においてプルサーマル原発の危険性を訴えて頑張っていたのが著者で、一方の、「反対派は地震が起きたら危ないと言うが、チェルノブイリのようなことは起こるはずがない。安全ということを確かめられている」と言って小出助教をせせら笑った東京大学の大橋弘忠教授は、福島原発の事故後はマスコミには一切登場していません。
九州電力玄海原子力発電所(佐賀県玄海町)3号機のプルサーマル発電計画について、佐賀県が'05年12月に公開討論会を主催した際、九電が動員した社員や関連会社員らが参加者全体の半数近くも出席していて、導入推進側に有利な"やらせ質問"をするととともに、参加者アンケートにも"積極"回答していたことが明らかになったのは、東日本大震災後の同原発の運転再開を巡る九州電力の"やらせメール事件"が明るみに出た直後の昨年('11年)7月のこと(5年以上前の全国で最初に行われたこのプルサーマル公聴会の時から"やらせ"は常態化していたわけだ)、その公聴会においてプルサーマル原発の危険性を訴えて頑張っていたのが著者で、一方の、「反対派は地震が起きたら危ないと言うが、チェルノブイリのようなことは起こるはずがない。安全ということを確かめられている」と言って小出助教をせせら笑った東京大学の大橋弘忠教授は、福島原発の事故後はマスコミには一切登場していません。
 肥田 舜太郎 医師
肥田 舜太郎 医師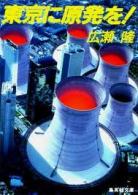


 朝日版は「写真集」と銘打っているだけあって、大判誌面全体を使った写真が、自然災害の脅威とその被害の甚大さを生々しく伝えており、被災した人々のうちひしがれた様子も痛々しく(廃墟と化した街を背に路上に座り込む女性の写真は海外にも配信されたが、その他にも、「愛娘たちの遺体が見つかった現場近くでお菓子やジュースをまく母親ら」などの写真は涙をそそる)、その中で何とか復興への光明を見出そうと懸命な人々の姿に、思わず感動を誘われました。
朝日版は「写真集」と銘打っているだけあって、大判誌面全体を使った写真が、自然災害の脅威とその被害の甚大さを生々しく伝えており、被災した人々のうちひしがれた様子も痛々しく(廃墟と化した街を背に路上に座り込む女性の写真は海外にも配信されたが、その他にも、「愛娘たちの遺体が見つかった現場近くでお菓子やジュースをまく母親ら」などの写真は涙をそそる)、その中で何とか復興への光明を見出そうと懸命な人々の姿に、思わず感動を誘われました。

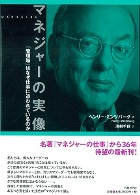
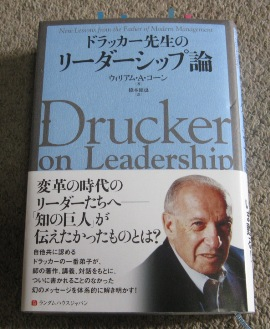
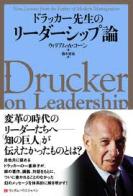
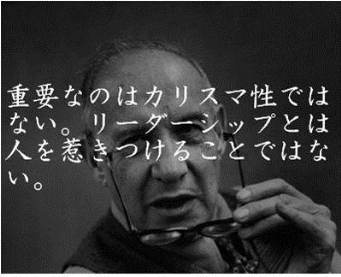 本書を読むと、その他にも、「リーダーシップは学んで身につけられる」との結論に至ったのも晩年のことで、それまで彼は"素質論"だったということが分かり、"カリスマ"に対してもかつては忌避していたのが(ヒットラーが政権を取った数日後に祖国を離れ渡英したことに符号する)、晩年になって、中立的な立場になるなど、いろいろリーダーシップに対する考えが変遷しているのが窺え、興味深く重いました(手近な入門書の多くは、最初からリーダーシップに関する彼の考えが定まっていたかのように書かれているものもあるなあ)。
本書を読むと、その他にも、「リーダーシップは学んで身につけられる」との結論に至ったのも晩年のことで、それまで彼は"素質論"だったということが分かり、"カリスマ"に対してもかつては忌避していたのが(ヒットラーが政権を取った数日後に祖国を離れ渡英したことに符号する)、晩年になって、中立的な立場になるなど、いろいろリーダーシップに対する考えが変遷しているのが窺え、興味深く重いました(手近な入門書の多くは、最初からリーダーシップに関する彼の考えが定まっていたかのように書かれているものもあるなあ)。