「●海外サスペンス・読み物」の インデックッスへ Prev|NEXT ⇒ 【681】A・マクリーン 『ナヴァロンの要塞』
「○海外サスペンス・読み物 【発表・刊行順】」の インデックッスへ
「十二人の怒れる男」と一味違った構成。江戸川乱歩の解説がネタバレかと思ったらラストに―。


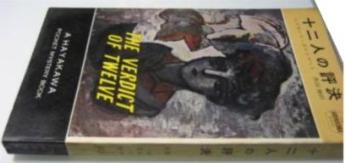

 "Verdict of Twelve (British Library Crime Classics) (English Edition)
"Verdict of Twelve (British Library Crime Classics) (English Edition)"『十二人の評決 (1954年) (世界探偵小説全集)
』(ハヤカワミステリ1600番突破記念函入り)['54年/黒沼健:訳]『十二人の評決 (ハヤカワ・ポケット・ミステリ)
』['99年/宇野輝雄:訳]表紙絵:勝呂忠(1926‐2010)(旧版・新版とも)
Raymond W. Postgate(1896-1971)
第1部「陪審」― 1930年代後半の英国で、ある殺人事件を裁くために選ばれた12人の陪審員たちの、職業や経歴、思想などが描かれ、彼らの中には誰にも知られてはいけない秘密を持つ者もいる―。
第2部「事件」― 審議の対象となった事件―莫大な遺産を相続した11歳の少年とその後見人の叔母は、日頃から折り合いが悪かったが、孤独な少年が唯一愛する1匹の兎を叔母が殺したことを契機に異様な殺人事件が起きる―。
第3部「公判と評決」― 証言ごとに揺れ動く陪審員たちの心理がメーターの針で図示され、最後に評決に至る―。
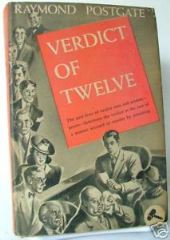
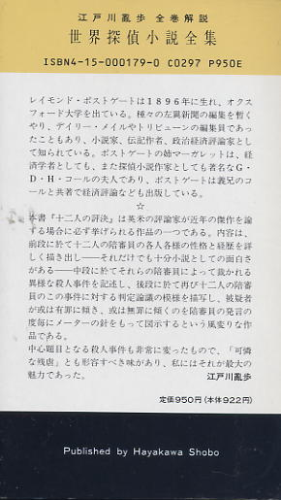 左翼系ジャーナリストであり、小説家、伝記作者、政治経済評論家、社会学者でもあったレイモンド・ポストゲート(Raymond W. Postgate 1896-1971)が1940年に発表した作品で(原題:Verdict of Twelve)、ハヤカワ・ミステリ(1954年初版)では江戸川乱歩が解説をしています。
左翼系ジャーナリストであり、小説家、伝記作者、政治経済評論家、社会学者でもあったレイモンド・ポストゲート(Raymond W. Postgate 1896-1971)が1940年に発表した作品で(原題:Verdict of Twelve)、ハヤカワ・ミステリ(1954年初版)では江戸川乱歩が解説をしています。
第1部の12人の陪審員の人物の来歴が面白く、過去に巧妙な完全犯罪(殺人)を成し遂げた老婆、狡知により下層階級から成り上がった詐欺師男、年老いたギリシャ学者、寡男の酒場の亭主、ある日突然信仰に目覚めた熱烈なクリスチャン、ユダヤ人として迫害され夫をチンピラに殺された女性、労働組合の書記長、社会主義詩人、美容院助手、二流どころの俳優、百科事典のセールスマン、小新聞の編集長―と、やや作者の経歴寄りの"布陣"のような印象も受けますがそれでもバラエティに富み、12人のプロファイリングの後半の方はやや端折り気味であるものの、この第1部で全体の半分近くを占めます。
第2部で展開される事件がまた謎に満ちていて、ここは通常の推理小説における問題提起部分と言え、更に第3部で事件の公判の模様が描かれ、いよいよ陪審員たちが審議に入りますが、彼らは一生懸命考えているような、いないような―結局その判断は、自らの出自や経歴に強く影響を受けていることを如実に窺わせるものとなっています。
シドニー・ルメット監督の「十二人の怒れる男」('57年/米)が、審議を通して12人の陪審員らの人間性が次第に露わになっていくプロセスが描かれていたのに対し、この作品は、先に12人のプロファイリングがあり、審議においてはその思想や偏見がアプリオリに各自の判断を誘引しているものの、それがそのまま明確な判断に結び付くとも限らず、他者の発言によって微妙に揺らいでいる様が描かれているといっていいのではないでしょうか(それを作者はバロメータ表示している)。
12人の陪審員の中で一番振れ幅が大きいのは、完全殺人の経験者である老婆で、「あなたは殺人に対してどんな知識を持っているのです?」と問い詰められて有罪支持から無罪支持に転じますが、ホントは殺人というものを知っている..何せ経験者だから(自らの保身のために意見を変えた)。
解説の江戸川乱歩は、中心題目である殺人事件に最も関心を抱いたようで「可憐なる残虐」と評していますが(乱歩の解説が裏表紙に要約されて掲載されている)、こうした形容はややネタバレではないかと思いつつ読みながらも、第4部「後記」で示された"ドンデン返し"的な展開で楽しませてくれます。

 この小説は、作家の大岡昇平(1909‐1988)と弁護士から最高裁判事になった大野正男(1927-2006)の対談集『フィクションとしての裁判―臨床法学講義』('79年/朝日出版社)の中で大岡昇平が紹介していたことで知りましたが、結末は、大岡昇平の『事件』('77年/新潮社)と似てなくもないです(但し、『事件』の主人公のラストの告白は懺悔に近いが、こちらの問題の人物の告白は自己弁護に近い)。
この小説は、作家の大岡昇平(1909‐1988)と弁護士から最高裁判事になった大野正男(1927-2006)の対談集『フィクションとしての裁判―臨床法学講義』('79年/朝日出版社)の中で大岡昇平が紹介していたことで知りましたが、結末は、大岡昇平の『事件』('77年/新潮社)と似てなくもないです(但し、『事件』の主人公のラストの告白は懺悔に近いが、こちらの問題の人物の告白は自己弁護に近い)。
【1954年新書化[ハヤカワ・ポケットミステリ(黒沼健:訳)/1999年改訳[ハヤカワ・ポケットミステリ(宇野輝雄:訳)】
