「●か G・ガルシア=マルケス」の インデックッスへ Prev|NEXT ⇒ 【1413】 ガブリエル・ガルシア=マルケス 『百年の孤独』
「○ラテンアメリカ文学 【発表・刊行順】」の インデックッスへ
幻想短編集だが、前半部分は日本の純文学みたいで、後半は南米的。「六時に来た女」が面白い。
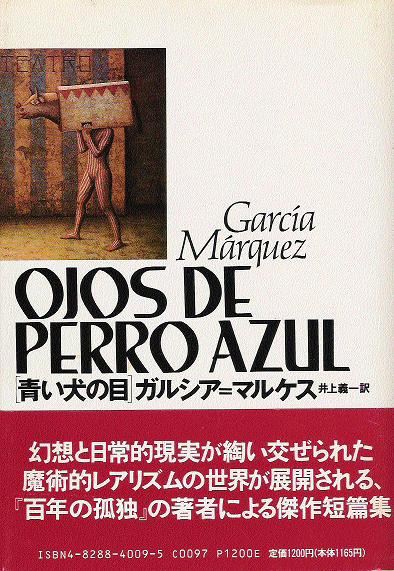


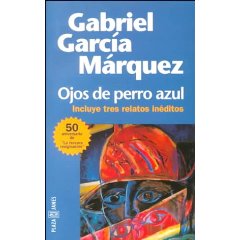
『青い犬の目』['90年]/『青い犬の目―死をめぐる11の短篇 (福武文庫)
』['94年]/スペイン語ペーパーバック(1997)
しばらく前まで、自分が死んだものだと信じきっていたので、彼は幸せだった。死者という、動かしようのない状況に置かれているので、幸せなはずだった。ところが生者というものは、すべてを諦めて、生きたままで地中に埋められるわけにはいかないのだ。それなのに四肢は動かそうとしても、全く反応しない。彼は自分自身を表現できず、そのことが彼の恐怖を一層つのらせた。生と死の最大の恐怖だった―。(「三度目の諦め」)
1962年に刊行されたガブリエル・ガルシア=マルケスの初期短編集(11編を所収)ですが、実際にこれらの作品が書かれたのは、1955年に刊行された短編集『落葉』とほぼ同じ頃のようです。
冒頭の「三度目の諦め」は、7歳の少年の頃に死んでから、棺桶の中で生きる屍として成長し続けた男が、25歳となってこれ以上の成長しなくなると、それまで彼の面倒をみていた母親が面倒をみることをやめ、彼は自らの死をやっと受け容れるというミステリアスな話。
死んでからも意識があるという設定は、吉村昭の初期作品「少女架刑」などを想起させられましたが、ガルシア=マルケスって最初の頃は、こうしたカフカ的な、乃至は、日本の純文学によく見られるような幻想的な、或いは意識過剰な作品を書いていたのだなあ(大江健三郎―村上龍―金原ひとみ・吉村萬壱 etc...といった流れに見られるような。吉村昭も初期は純文学系だったし)。
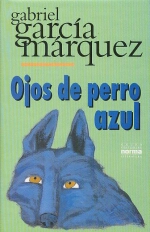 文庫版の副題にあるように、以下、主に死をモチーフとした作品が続きますが、「青い犬の目」と言ってくれる男を捜している女と、そういう女を探していた「ぼく」との会話を描いた表題作「青い犬の目」を分岐点に、後半部分の作品は少し毛色が変わって、ホセのレストランに毎晩6時に来る女とホセとの会話を綴った「六時に来た女」などは、ヘミングウェイの「殺し屋」のみたいなハードボイルド・トーンで(これは"幻想短編"というこの短編集全体のトーンからも外れているが)、それでいてペーソスを含んだストーリーが面白かったです(結局、この話に出てくる女は男に何を頼んでいるかというと、○○○○作りなのだ)。
文庫版の副題にあるように、以下、主に死をモチーフとした作品が続きますが、「青い犬の目」と言ってくれる男を捜している女と、そういう女を探していた「ぼく」との会話を描いた表題作「青い犬の目」を分岐点に、後半部分の作品は少し毛色が変わって、ホセのレストランに毎晩6時に来る女とホセとの会話を綴った「六時に来た女」などは、ヘミングウェイの「殺し屋」のみたいなハードボイルド・トーンで(これは"幻想短編"というこの短編集全体のトーンからも外れているが)、それでいてペーソスを含んだストーリーが面白かったです(結局、この話に出てくる女は男に何を頼んでいるかというと、○○○○作りなのだ)。
スペイン語ペーパーバック
その他では、少年の時に馬に蹴られ頭がおかしくなって馬小屋に閉じ込められている黒人と、彼がいつも蓄音機をかけてあげていた精神異常の少女の繋がりを描いた「天使を待たせた黒人、ナボ」や、イシチドリに襲われて目が見えなくなった3人の男達の話「イシチドリの夜」などが、南米風の説話的な雰囲気の中にも切ないユーモアがあって、個人的には好みでした。
最後の「マコンドに降る雨を見たイザベルの独白」などは、そのまま『百年の孤独』の中の一挿話としてあってもおかしくないトーン。
それらの後半部の作品に比べると、前半部の作品は、いかにも「習作」という感じがしなくもないですが、ガルシア=マルケス研究者にとっては多分、前半の作品が「注目」なのだろうなあ。
作品の性質的にも順番的にもその中間にある「青い犬の目」が、この短編集の表題になっているということなのか。
【1994年文庫化[福武文庫(『青い犬の目―死をめぐる11の短篇』)]】
