「●る モーリス・ルブラン」の インデックッスへ Prev|NEXT ⇒ 「●わ 和田 誠」 【2181】 和田 誠 『お楽しみはこれからだ』
「○海外サスペンス・読み物 【発表・刊行順】」の インデックッスへ
とことん追い詰められ、屈辱にまみれたルパンを奮い立たせたものは...。新訳で読めるのがいい。
 『水晶の栓 (ハヤカワ・ミステリ文庫)
『水晶の栓 (ハヤカワ・ミステリ文庫)』['07年]
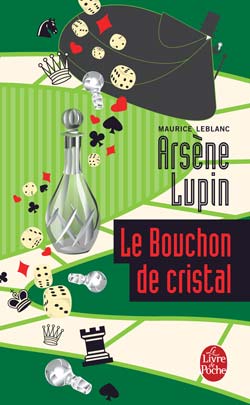 "Arsène Lupin le bouchon de cristal" リーブル・ド・ポッシュ版 1974
"Arsène Lupin le bouchon de cristal" リーブル・ド・ポッシュ版 1974
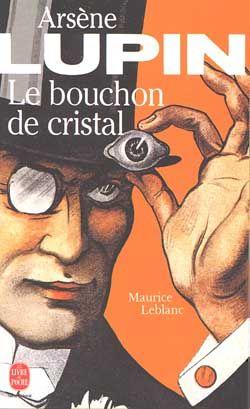 政界の黒幕ドーブレック代議士の別荘に押し入ったルパン一味だが、計画を立てた部下のジルベールとヴォシュレーはなぜか「水晶の栓」を探し回り、ヴォシュレーは殺人まで犯してしまって部下2人は逮捕され、共に死刑を宣告されてしまう。ルパンは、ドーブレックが疑獄事件に関与した人物のリストを握って政界に恐喝を繰り返し、そのリストを「水晶の栓」の中に隠していることを知り、自らが可愛がっていた青年ジルベールを奪還すべく、ジルベールの母クラリスと共に「栓」を探し求めるが、ドーブレックに手玉にとられるかの如く翻弄され続け、一方、ジルベールらの死刑執行の日は刻々と迫りくる―。
政界の黒幕ドーブレック代議士の別荘に押し入ったルパン一味だが、計画を立てた部下のジルベールとヴォシュレーはなぜか「水晶の栓」を探し回り、ヴォシュレーは殺人まで犯してしまって部下2人は逮捕され、共に死刑を宣告されてしまう。ルパンは、ドーブレックが疑獄事件に関与した人物のリストを握って政界に恐喝を繰り返し、そのリストを「水晶の栓」の中に隠していることを知り、自らが可愛がっていた青年ジルベールを奪還すべく、ジルベールの母クラリスと共に「栓」を探し求めるが、ドーブレックに手玉にとられるかの如く翻弄され続け、一方、ジルベールらの死刑執行の日は刻々と迫りくる―。
Arsene lupin ; le bouchon de cristal. (リーブル・ド・ポッシュ版(原書表紙復刻版))
「アルセーヌ・ルパン・シリーズ」の1909年の『奇岩城』、1910年の『813』に続いて1912年に刊行された長編で(原題:Le Bouchon de cristal)、どれも作品内容が充実していて、しかもこの間にルパンを主人公とした短篇も書いているから、モーリス・ルブラン(1864-1941)は、長いルパン・シリーズの著作活動の中でも、この頃まさに絶頂期にあったと言えるのではないでしょうか。
ドーブレックは(この作品にしか登場しないが)シリーズ中でもルパンにとって最強の敵とされていて、彼はとにかく常にルパンの先を行き、残り4分の1ぐらいからルパンが反攻に転じるかと思いきや、すぐにまたルパンは窮地に追いやられ、死刑執行予定日の2日前ぐらいから、今度こそアドバンテージを握ったかと思いきやこれもまた頓挫、さらに執行の数時間前に逆転のチャンスを握ったかと思ったらこれもダメで、遂には死刑がまさに執行されようとするところまでいってしまいます。
最後に追い詰められたルパンは、「もうあきらめよう!完敗じゃないか」「負けたのは、おれのほうさ。ジルベールを助けられないのだから」と悔し涙を流し、死刑執行の前夜には睡眠薬を飲んで寝てしまいます。
後日ルパンは、この事件を「水晶の栓、あるいは、決してあきらめてはならないわけ」と呼ぶのですが、6ヵ月続いた「不運と失敗、暗中模索と敗北」を、最後の12時間でよく取り戻したなあと(よく起きたね。部下に起こされたみたいだけど)。
他の作品にも見られますが、ルパンが巨悪に翻弄される姿を描いてまず読者をルパン側に引き付けるのが旨く、とりわけこの作品のルパンはしょっちゅう血が頭にのぼっていて、敵役の方が、タイプこそ違いますが、まるでルパンのように傲岸かつ超人的であり、ルパン本人を繰り返し屈辱のどん底に陥れます。
しかも、終盤に入ってもどんでん返しの連続で始終ハラハラドキドキさせるのは、この作品が新聞連載小説であったことにもよるようですが、読者へのサービス精神が極めて旺盛であるように思いました。
ルパンは殆どの作品で部下を使い、その数は数十人に及ぶようですが、この作品では、不良部下や造反を起こす部下が現れるのが興味深く、また、その不良部下が殺人を犯したときに、自分は血を見るのは嫌いだと言って怒り心頭に発する一方で、まさにその不良部下ヴォシュレーを撃ち殺すという行動に出るのは、シリーズの中でも特異かも(但しそれは、ジルベールを助けるための最後の手段であり、ヴォシュレーも断頭台によって殺されずに済んだことを感謝して死んでいくので、整合性はとれているともとれるが)。
ルパンのジルベールに対する愛情はわが子に対するように深く、また、その母親であるクラリスに対しては、無意識に恋心を抱いていたことを事件後に自覚するわけですが(『カリオストロ伯爵夫人』のクラリスとは別人で、この作品で30代前半のルパンより年上)、絶望的な状況下でジルベール奪還に向けてルパンを奮い立たせている最大の要因は、それら以上に、自分が「アルセーヌ・ルパン」であることに尽きるのではないでしょうか。
この作品でルパンは何度も己の無力を痛感して打ちひしがれますが、最後は、この「アルセーヌ・ルパン」であるという誇りによって這い上がってくる―ルパンの感情の起伏がよく描かれているだけに、それはまるで、アルセーヌ・ルパンという「名前」にとことん献身する、生身の男を描いているようにも思えました。
スエズ運河建設で知られるレセップスの、パナマ運河建設の際の疑獄事件に材を得た作品ですが、少年(青年?)探偵が活躍する『奇岩城』よりは大人向けかも。
「大人向け」の翻訳を目指したという平岡敦氏の新訳は読み易く、シリーズの翻訳がこの作品で止まっていて、『813』の新訳刊行に至っていない現在においては、最もお薦め出来る1冊ではないかと思います。
【1960年再文庫化[新潮文庫(堀口大學:訳『水晶栓』)]/1965年再文庫化[創元推理文庫(石川湧:訳)/2005年再文庫化[ポプラ社文庫(南洋一郎:訳『古塔の地下牢』)]/2007年再文庫化[ハヤカワ・ミステリ文庫(平岡敦訳)/2009年再文庫化[ポプラ社怪盗ルパン文庫版(南洋一郎:訳『古塔の地下牢』)]】
