「●中国史」の インデックッスへ Prev|NEXT ⇒ 【2892】 井波 律子 『故事成句でたどる楽しい中国史』
「●講談社学術文庫」の インデックッスへ
中国で無断出版されたほどの名著? 読み易く、トピックスは豊富。父親譲りの文学の香り。
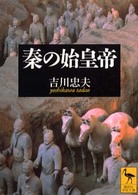 『秦の始皇帝 (講談社学術文庫)
『秦の始皇帝 (講談社学術文庫)』 ['02年]
 『秦の始皇帝―焚書坑儒を好しとして (中国の英傑)
『秦の始皇帝―焚書坑儒を好しとして (中国の英傑)』 ['86年]
'02年に講談社学術文庫に収められたものですが、元本は'86年に集英社から「中国の英傑シリーズ」の1冊として刊行されたもので、1937年生まれの著者の40歳代最後の仕事であるとのこと(16年を経ての文庫化ということになる)。
著者の父親は、『新唐詩選』('52年/岩波新書)などで知られる中国文学者・吉川幸次郎(1904‐1980)で、この人の『漢の武帝』('49年/岩波新書)は読み易く、また武帝という人の性格や生き様が小説のように描かれていて面白かったですが、こちらも学術文庫にしては読み易い方ではないでしょうか。
勿論これも小説ではないのですが、史書・史料に対して明確に肯定も否定もすることなく、そのまま引いている部分が多いため、小説のように読めてしまいます(明らかに伝説的な部分は、「〜だったという」「〜したという」という表現になっている)。
書かれたのが丁度、中国の著名な文学者・歴史家だった郭沫若(この人、文化大革命の時に"自己批判"させられた知識人の1人)が、始皇帝の実父は呂不韋であるという『史記』の記述及び通説(言わば、私生児論)に対して否定論を発表した頃で、著者は、本書第1章の「奇貨居くべし」に「始皇帝は呂不韋の子か」という副題をつけ、その郭沫若の論を紹介していますが、著者自身が、始皇帝の父親が呂不韋であることを「半月前には深く信じて疑わなかった」ためもあってか、ここでも、郭沫若の論を明確に支持することはしていません。
始皇帝・私生児論を否定するということは、秦王朝の正当性を否定すると言うより、始皇帝の英雄性を否定することに繋がるのでしょうか。
何れにせよ、文化大革命の時に持ち上げられた始皇帝に対するネガティブ評価ということになりますが、郭沫若の立ち位置が、寡聞にしてよくわかりません。
白黒はっきりしない著者の姿勢に苛立ちを覚える読者もいるかも知れませんが、読者に始皇帝の「内面世界」に触れて欲しいとの思いから本書を書いたとのことで、個人的には、"親父さん"同様、自分との相性は悪くありませんでした。
淡々と書いてあるけれども、何となく文学の香りがすると言うのか、大体、元の史書・史料の記述が文学的(小説的)なんだよなあ。
多くの出来事を拾っていて、内容の密度は濃く、必要に応じて春秋戦国の故事、更には堯舜伝説にまで遡りますが、これは、諸国の王の顧問となった学士や参謀が、王を説得する際に故事を引くからであって、丁寧な解説であると共に、中国の思想の古(いにしえ)からの変遷を探ることが出来、更には、秦帝国に関する中世から近現代の文献研究なども織り込まれています。
一方で、著者は70年代の訪中に続き、'82年と'84年にも兵馬俑博物館や始皇帝の陵墓を訪れるなどしていますが、考古学的な話は、始皇帝陵に関する部分にほぼ限られており、やはりこの人は、文学・思想系の歴史学者なのだなあと("親父さん"寄り?)。
学術文庫版の冒頭に面白いエピソードがあり、それは、'89年に元本の中国語訳が、著者に無断で中国で刊行されたというもの。
中国語版のサブタイトルは「英雄か、それとも暴君か」(本書はこれには結論を出していない)で、集英社版の元本に編集者によって付けられていたサブタイトル「焚書坑儒を好しとして」(これは無茶苦茶)に比べるとまだ良いと著者はしていますが、中国人の訳者は元本の内容に賛辞を贈っているものの、著者名が「忠夫」でなくて「中夫」になっていたということです。
