「●近代日本文学 (-1948)」の インデックッスへ Prev|NEXT ⇒ 【647】 永井 荷風 『濹東綺譚』
「○近代日本文学 【発表・刊行順】」の インデックッスへ 「●「朝日賞」受賞者作」の インデックッスへ(中 勘助)
自らの幼年期が、子どもの目線、子どものみが持つ感覚で描かれている不思議な作品。





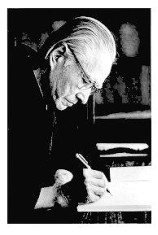 中 勘助
中 勘助
『銀の匙 (岩波文庫)』/『銀の匙 (ワイド版岩波文庫)
』/『銀の匙 (角川文庫)
』(旧カバー・新カバー)
 1911(明治44)年に前編が書かれた「銀の匙」は(後編が書かれたのは1913年)、それまで詩作などを中心に創作活動をしていた中勘助(1985‐1965)が、一高・東大時代の師である夏目漱石に勧められて20代半ばで初めて書いた散文であり、書斎の引き出しの小箱の中にしまった銀の小匙にまつわる思い出から始まるこの自伝的作品は漱石に絶賛され、その推挙により、前編は1913年、後編は1915年に朝日新聞に連載されました。
1911(明治44)年に前編が書かれた「銀の匙」は(後編が書かれたのは1913年)、それまで詩作などを中心に創作活動をしていた中勘助(1985‐1965)が、一高・東大時代の師である夏目漱石に勧められて20代半ばで初めて書いた散文であり、書斎の引き出しの小箱の中にしまった銀の小匙にまつわる思い出から始まるこの自伝的作品は漱石に絶賛され、その推挙により、前編は1913年、後編は1915年に朝日新聞に連載されました。
『銀の匙』 中勘助 岩波書店 1926(大正15)年 初版
文章が凛然として美しく、子どもの世界を子どもの目線で活写しています。まぎれもなく大人の書いた文章ですが、時にぶっきらぼうとも思える終わり方などもしていて、子どもの日記を読んでいるような錯覚、とまでいかなくともそれに近い感覚に陥りました。
病弱、気弱な伯母さんっ子として育った幼年期の思い出の数々が、目の前で起きている出来事のように再現され、そこに滲むセンシビリティも子どものみが持つものであり、一方で、大人になった作者によってノスタルジックに「美化された過去」というものも感じますが、その美しさがまた読み手の共感をそそり、一体どこまで計算されて書かれているのか、不思議というか"怪しさ"さえ覚えました。
心理学の仮説では、〈幼児期の記憶〉は思春期に入ると急速に忘れ去られるが実は深層心理にしっかり残っていて、大人になってもけっして消えていないのだという考えがありますが、この作者は、思春期以降も意識から無意識へと消え去ろうとする記憶を何度も抽出・反復していたのではないかと思われ、これは、病弱な幼年期を送った人に特徴的なことではないかと思われました。
今でいう小学校低学年ぐらいの頃の出来事がとりわけ生き生きと、みずみずしく描かれていてます。ただし、思春期に入る頃から結構この中勘助という人は、気力・体力とも充実してきたようで、1913(大正2)年から書かれた後編では、子どもながらに立派な反戦少年になっていて(日清戦争だから古い話だが)、軍国思想に染まりながらエリートコースを歩む兄と訣別します。そして伯母との再会-。
漱石は、後編は前編に比して更に良いと褒めたようですが、やはり、後編の「物語」っぽいつくりや立派に振舞いすぎる少年像よりも、それとは違った意味で"創作の怪しさ"が感じられる前編の方が個人的には良かったです。
因みに、中勘助の初恋の相手は同い年の野上弥生子だったとされていますが、富岡多恵子の『中勘助の恋』('93年/創元社、'00年/平凡社ライブラリー)によると、モテ男だった彼は、野上弥生子をはじめ多くの女性からプロポーズされたがその全てを断り、友人の娘(幼女)たちに恋着、幼女らにラブレターを書き、大きくなったら結婚しようと言って膝に乗せ頬にキスする一方、陰で彼女らを「ぼくのペット」と呼んでいたそうな(人は見かけによらない...?)。

 【1926年単行本[岩波書店]/1935年文庫化・1962年・1999年改版[岩波文庫]/1988年再文庫化[角川文庫]/1992年再文庫化〔ちくま日本文学全集〕/2012年再文庫化[小学館文庫]】
【1926年単行本[岩波書店]/1935年文庫化・1962年・1999年改版[岩波文庫]/1988年再文庫化[角川文庫]/1992年再文庫化〔ちくま日本文学全集〕/2012年再文庫化[小学館文庫]】
《読書MEMO》
●「銀の匙」...1911(明治44)年前編発表、1913(大正2)‐1914(大正3)年後編「朝日新聞」連載
