「●た行の現代日本の作家」の インデックッスへ Prev|NEXT ⇒ 【2167】 徳永 圭 『その名もエスペランサ』
やや出来すぎた人物像だが、ビジネスパーソンが読めば、グッとくる部分は多い「小説」。



『小説 上杉鷹山〈上巻〉・〈下巻〉
』 ['83年]/『全一冊 小説 上杉鷹山 (集英社文庫)
』 ['96年]
財政難に一時は廃藩の話まで出た米沢藩を再興した藩主・上杉治憲(はるのり、隠居後は鷹山)の話で、この人、戦前は国定教科書に取り上げられていた人物ですが、本書にもあるとおり、故J・F・ケネディ大統領が最も尊敬する日本人としてその名を挙げた人でもあります。
米沢織、絹製品、漆器、紅茶、鯉、一刀彫などの今に至る米沢の名産品は、みなこの人の産業政策の賜物だそうですが、こうした企業で言えば多角化経営みたいなものが本当に実を結んだのは、鷹山亡き後で、在命中の実績としては、天明大飢饉の際に1人の餓死者も出さなかった(本当かなあ)ことが最大のものと言えるのではないでしょうか。
その名を後世に残しているのは、「徳」を政治の基本に置き、それを経済に結びつけようと考え、倹約を推奨するけども「生きた金」は積極的に使い、それは「領民を富ませるため」だったという、徳治主義的な政治哲学の実践者であったから。
ケネディが鷹山を知るきっかけとなった本の著者である内村鑑三流に言えば、「愛と信頼」の政治ということになり、本書にも「愛」という言葉が何度か出てきますが、江戸時代に「愛」という言葉の概念が今のような形であったかどうか、個人的にはやや疑問。
それと、実際に高徳の人物であったとは伝えられていますが、ちょっと完璧に描きすぎている感じもして、35歳で隠居したのは、次代を育てるというよりは、財政難の折、参勤交代を免がれるための戦略だった(藩主が代わった年は免除される)というのが通説のようです。
藩政改革の道程は平坦ではなく、、反発する旧弊な重役たちとの確執など、企業小説を呼んでいるような面白さはあります。ときどき、「今の経営行動パターに合せれば」という感じで「企業目標の設定」「それに必要な情報の公開」とか箇条書きで説明が出てくるのが、社内研修テキストみたいでお節介のような気もしましたが。
人物の描き方もプロトタイプという感じですが、それでも佐藤文四郎とかにスポットを当て、その好漢ぶりを生き生き描いているのは、素直に爽快感を感じました。
テレビ番組『知ってるつもり!?」』で鷹山がフューチャーされたこともあり、本書はベストセラーとなりましたが、やはり企業の中で、改革派と抵抗勢力の間にいるようなビジネスパーソンが読めば、グッとくる部分は多い「小説」であることには違いありません。
【1995年文庫化[学陽社・人物文庫(上・下)]/1996年再文庫化[集英社文庫(全1冊)]】
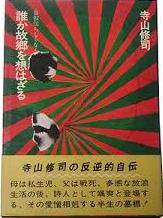




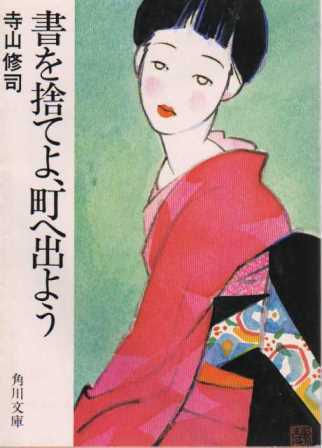





 「草迷宮」 「迷宮譚」「マルドロールの歌」「一寸法師を記述する試み」
「草迷宮」 「迷宮譚」「マルドロールの歌」「一寸法師を記述する試み」
.jpg)
 ル・ブロンベルジュ●脚本:寺山修司/岸田
ル・ブロンベルジュ●脚本:寺山修司/岸田
 新宿東映ホール (83-11-12)(評価:★★★☆)●併映:「迷宮譚」(寺山修司)/「消しゴム」(寺山修司)/
新宿東映ホール (83-11-12)(評価:★★★☆)●併映:「迷宮譚」(寺山修司)/「消しゴム」(寺山修司)/ 「質問 (寺山修司へのインタビュー記録映画)」(田中未知)
「質問 (寺山修司へのインタビュー記録映画)」(田中未知)
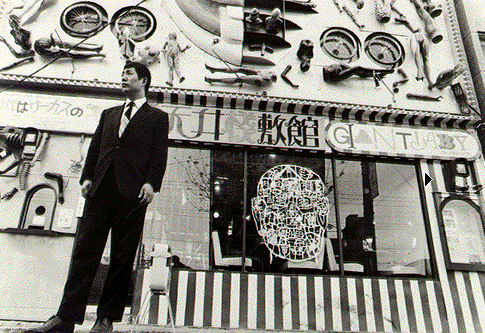 寺山修司の自叙伝的作品の虚構性については既に多く論じられているところで、映画「田園に死す」については、寺山修司自身がはっきり、「これは一人の青年の自叙伝の形式を借りた虚構である」(演出ノート)と述べていますが、同じことが文章において端的に表れているのが、この「誰か故郷を想はざる」ではないでしょうか。
寺山修司の自叙伝的作品の虚構性については既に多く論じられているところで、映画「田園に死す」については、寺山修司自身がはっきり、「これは一人の青年の自叙伝の形式を借りた虚構である」(演出ノート)と述べていますが、同じことが文章において端的に表れているのが、この「誰か故郷を想はざる」ではないでしょうか。 47年間の生涯に様々なことを成し遂げ
47年間の生涯に様々なことを成し遂げ たものだなあと改めて思います。「天井桟敷」に新人女優として入団したカルメン・マキのデビュー曲「時には母のない子のように」('69年)の作詞者でもあり、詩や演劇、実験的な映画ばかりでなく、一般向けに公開された映画「
たものだなあと改めて思います。「天井桟敷」に新人女優として入団したカルメン・マキのデビュー曲「時には母のない子のように」('69年)の作詞者でもあり、詩や演劇、実験的な映画ばかりでなく、一般向けに公開された映画「

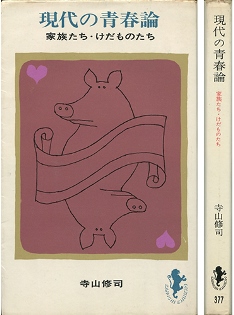







 再読しましたが、やはり読み出したら止まらないぐらい面白い!
再読しましたが、やはり読み出したら止まらないぐらい面白い! 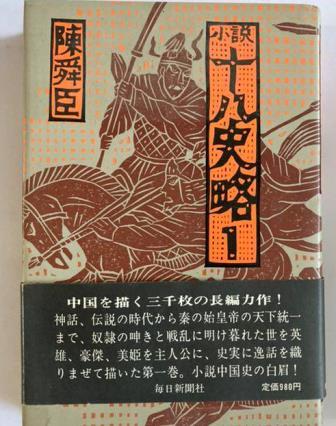
 取り上げている故事の数も多いけれど、それらに連続感、"たたみかけ感"があり、飽きさせることがありません。
取り上げている故事の数も多いけれど、それらに連続感、"たたみかけ感"があり、飽きさせることがありません。 




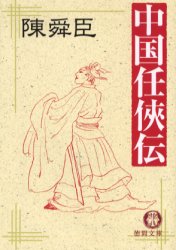
 「任侠」とはヤクザのことではなく「他人のために自分の身をかえりみない者」のことで、著者は中国における"ますらおぶり"を描きたかったとのこと。「荊軻、一片の心」「孟嘗君の客」「虎符を盗んで」「首がとぶ」「季布の一諾」「おれは幸運児」「いざ男の時代」「似てくる男」の8篇を収めています。
「任侠」とはヤクザのことではなく「他人のために自分の身をかえりみない者」のことで、著者は中国における"ますらおぶり"を描きたかったとのこと。「荊軻、一片の心」「孟嘗君の客」「虎符を盗んで」「首がとぶ」「季布の一諾」「おれは幸運児」「いざ男の時代」「似てくる男」の8篇を収めています。







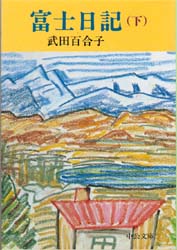

 1977(昭和52)年・第17回「田村俊子賞」受賞作。
1977(昭和52)年・第17回「田村俊子賞」受賞作。











 高橋和巳 (1931-1971/享年39)
高橋和巳 (1931-1971/享年39)

