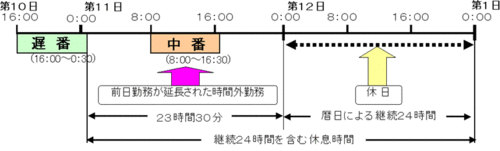◆賞与は必ず支払わなければならないか
 今まで年末と夏期の年2回、社員には賞与を支払ってきましたが、そもそも、賞与とは必ず支払わなければならないのでしょうか。また、ある社員には賞与を支払い、ある社員には払わないとすることはできないでしょうか。そのほかに、貢献度によって個々の支給額に差をつけるやり方がありましたらお教えください。
今まで年末と夏期の年2回、社員には賞与を支払ってきましたが、そもそも、賞与とは必ず支払わなければならないのでしょうか。また、ある社員には賞与を支払い、ある社員には払わないとすることはできないでしょうか。そのほかに、貢献度によって個々の支給額に差をつけるやり方がありましたらお教えください。  賞与は必ずしも支払わなければならないというものではありません。しかし、就業規則で賞与を支払う旨を定めている場合には、その定めによらなければなりません。また、賞与を全額不支給とすることは、裁量の範囲を超えたものとして、通常は認められないと思われます。部門や個人の業績を支給額に反映させたいのであれば、賞与全体を基本賞与と業績賞与に分けて算定するなどのやり方が考えられます。
賞与は必ずしも支払わなければならないというものではありません。しかし、就業規則で賞与を支払う旨を定めている場合には、その定めによらなければなりません。また、賞与を全額不支給とすることは、裁量の範囲を超えたものとして、通常は認められないと思われます。部門や個人の業績を支給額に反映させたいのであれば、賞与全体を基本賞与と業績賞与に分けて算定するなどのやり方が考えられます。
■解説
1 賞与の性格と支払い義務
賞与とは、一般に、給与とは別に年末や夏期に支給される一時金のことをさしますが、労働基準法上の賞与の取扱いは、「定期又は臨時に、原則として労働者の勤務成績に応じて支給されるものであって、その支給額が予め確定されていないもの」とされています。つまり賞与は、毎月支給される給与などとは異なり、労働契約上の債務にあたるものではないため、必ず支給しなければならないという性格のものではありません。その支給基準、支給額、計算方法、支給期日、支給対象者などの決定も労使にゆだねられており、原則として、事業主が任意に決定できるものです。
また、賞与は「臨時の賃金」であり、賞与に関する事項は、就業規則の相対的必要記載事項になるため(労働基準法第89条第4号)、賞与を制度として設け、算定期間、支給基準、支給額、計算方法、支給期日、支給対象者などについての定めをした場合は、その定めをした限りにおいて、就業規則に記載しておく必要があります。
この「定め」については、正社員には支給するが、契約社員やパートタイマーには支給しないとすることは可能ですし、事業全体の業績や労働者の勤務期間などが一定水準に達しない場合には、賞与は支給しないとする旨を定めておくこともできます。
2 事業主の裁量の範囲
就業規則において、賞与を支払うことおよび賞与支給に関する制度基準を定めている場合には、その定めによって支給しなければなりませんが、賞与は、「原則として労働者の勤務成績に応じて支給されるもの」であるため、事業主の一定の裁量の範囲内で、社員個々の成績考課をもとに支給額を増減することは、査定制度の範囲内のこととして当然に認められるべきものです。
ただし、ご質問にあるように、「ある社員には賞与を支払い、ある社員には払わないとする」とすることが、査定制度の範囲を超えて恣意的に行われるならば、多分に問題を含んでいると思われます。
それまで年2回の賞与が支給されていた制度上の支給対象者である社員に対して、算定期間を通じて労務の提供があったにもかかわらず、当該期間分の賞与をいきなり全額不支給とすることは、事業主として許される裁量の範囲を超えるばかりでなく、賞与の賃金性を否定するものであり、一般には認められるものではないでしょう(公序良俗違反)。仮にそのことが懲戒処分として行われるとしても、減給の制裁の制限規定(労働基準法第91条)に抵触し、法違反になると考えられます。
3 業績成果を支給額に反映させるには
もし、成績考課の結果をもっと個々の支給額に反映させたいのであるならば、賞与の算定方式を、業績成果反映型に改めるというやり方があります。
賞与額の算出においては、一般に、「算定基礎額×支給月数」という計算式で計算し、算定基礎額の部分には基本給またはそのうちの一定額を用いているケースが多いようですが、これだけですと基本給実績だけで貢献度にかかわらず賞与額の多寡が決定してしまいます。そこで、例えば、先の算定式の一律の支給月数を抑えて(例えば、従来2カ月であったのを1カ月にするなどして)計算したものを基本賞与とし、余った原資を、個人成績を反映させた業績賞与として基本賞与にプラスすることとすれば、業績成果を反映させた、賞与本来の性格に近いものになるかと思われます。またその際に、評価基準や計算方法が社員に充分に開示されていれば、社員の納得性も高められることになります。
□根拠法令等
・労基法89(就業規則の作成及び届出の義務)、91(制裁規定の制限)
・昭22.9.13発基17(賞与の意義)
・内容についての無断転載は固くお断りいたします。
◆通勤手当を現物で支給する場合は賃金となるか
 当社では、通勤手当を定期券で現物支給しています。この定期券は賃金にあたるのでしょうか。また、3カ月定期券または6カ月定期券というかたちで複数月分の定期券を供与することは、法律上の問題はないでしょうか。
当社では、通勤手当を定期券で現物支給しています。この定期券は賃金にあたるのでしょうか。また、3カ月定期券または6カ月定期券というかたちで複数月分の定期券を供与することは、法律上の問題はないでしょうか。  通勤手当は、支給することが制度として定められている限り、労働基準法上の賃金として扱われ、就業規則でその支給基準等の定めをしておく必要があります。定期代を実費で支給している場合も、現物供与している場合も、この点は同様です。さらに、定期券で現物支給するには、労働組合と締結する労働協約においてその旨を定める必要があります。
通勤手当は、支給することが制度として定められている限り、労働基準法上の賃金として扱われ、就業規則でその支給基準等の定めをしておく必要があります。定期代を実費で支給している場合も、現物供与している場合も、この点は同様です。さらに、定期券で現物支給するには、労働組合と締結する労働協約においてその旨を定める必要があります。
3カ月定期券または6カ月定期券というかたちで供与することについては、当該月の最初の月に供与されていれば、社員にとって不利益ではないため、労働基準法第24条の「毎月払いの原則」違反にはなりません。
■解説
1 通勤手当の賃金性と「通貨払いの原則」との関係
通勤手当は、法律上必ず支払わなければならない義務があるものではなく、支給するか否かは労使の話し合いや事業主の決定にゆだねられているものです。ただし、制度的に支払うこととし、その支給基準が定められている場合は、労働基準法上の賃金として扱われるので、就業規則、賃金規程に必ず定めなければならず、また、いったん就業規則等に通勤手当を支払う旨の定めをすると、事業主に支払いの義務が生じるということです。定期代を実費で支給している場合も、現物供与している場合もこの点は同様で、いずれも賃金として扱われるとともに、就業規則等にその支給基準を記載する必要があります。
また、賃金に該当する限りは、通勤手当にも、労働基準法第24条の①通貨払いの原則、②直接貨払いの原則、③全額払いの原則、④毎月1回以上払いの原則、⑤一定期日払いの原則の「賃金支払五原則」が適用されるため、定期券等を現物供与する場合は、労基法第24条に基づく労働協約の締結が必要となります(協約でその旨の定めをしなければ、「通貨払いの原則」の適用除外対象にはならず、同法違反となります)。この場合、定期券を現物供与できるのは、労働協約の適用を受ける労働者(拡張適用を含む)に限られ、また、この労働協約を、労働者の過半数で組織する労働組合や過半数を代表する者との間で交わす労使協定で代えることはできません。したがって、労働組合の無い事業所では、定期券等の現物供与はできないということですので、ご注意ください。
2 数カ月分まとめて渡すことと「毎月1回以上」払いの原則との関係
ところで、実費支給や現物供与された定期代が労働基準法上の賃金に該当するならば、前述の「毎月1回以上」「一定期日払い」の原則の適用を受けるということになりますが、実際には、事務を簡便化するなどのため、3カ月分、6カ月分の定期代を一括支給したり、あるいはご質問にあるように、3カ月定期券、6カ月定期券を供与したりしている事業所もあります。この点について行政解釈では、「6カ月定期乗車券であっても、これは各月分の賃金の前払として認められる」としています。
この場合、例えば、4月から6月までの3カ月分の定期代を4月に支払う場合は5、6月分については前払いとなり、社員にとって不利益にはならないため、労働基準法第24条の「毎月払いの原則」違反にはなりませんが、4月から6月分までを6月に支給する場合は、4月分、5月分が、4月、5月の各月にまだ支払われていないことになり、「毎月払いの原則」に抵触し、違法となりますので注意が必要です。
□根拠法令等
・昭25.1.18基収130、昭33.2.13基発90(通勤定期乗車券)
・内容についての無断転載は固くお断りいたします。
◆夫が失業中の女性社員に家族手当を支給しなければならないか
 当社では、給与規程で、家族手当の支給基準を「扶養家族を有するとき」としていますが、このたび採用した女性社員が、夫が失業中であることを理由に家族手当の支給を求めてきました。これに応じなければならないのでしょうか。
当社では、給与規程で、家族手当の支給基準を「扶養家族を有するとき」としていますが、このたび採用した女性社員が、夫が失業中であることを理由に家族手当の支給を求めてきました。これに応じなければならないのでしょうか。  労働基準法第4条では「使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない」と定められています。したがって、男女の賃金について、性別の違いのみを理由に格差を設けることはできませんし、家族手当も賃金であり、同様に、性で差別することは違法となります。
労働基準法第4条では「使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない」と定められています。したがって、男女の賃金について、性別の違いのみを理由に格差を設けることはできませんし、家族手当も賃金であり、同様に、性で差別することは違法となります。
したがって、女性社員の被扶養者が夫であっても、他の男性社員の妻に対する家族手当の支給基準を満たしていれば、同じように家族手当を支給する必要があります。
■解説
1 男女同一賃金の原則
労働基準法第4条の規定(「男女同一賃金の原則」)は、女性に対する賃金についての差別を禁止したものです。女性が、一般的に勤続年数が短いこと、主たる生計の維持者ではないことなどを理由に、実際にそうであるか否かを問わず一律に賃金について異なる取扱いをするのは、「女性であることを理由と」する賃金差別となります。
職務、能率、技能、年齢、勤続年数等によって、賃金に個人的差異のあることは、この条文に規定する差別的取扱いではありませんが、例えばこれらが同一である場合において、男性はすべて月給制、女性はすべて日給制とし、男性の月給者がその労働日数の多寡にかかわらず月に対する賃金が一定額であるのに対し、女性の日給者がその労働日数の多寡によってその月に対する賃金が男性の一定額と異なるような場合も、「男女同一賃金の原則」に対する違反となります。
また、就業規則に労働者が女性であることを理由として、賃金について男性と差別的取扱いをする趣旨の規定があっても、現実にはその内容のことが行われておらず、賃金の男女差別待遇の事実がなければ、その規定そのものは無効ですが、そのことが即ち「男女同一賃金の原則」に対する違反となるわけではありません。
2 家族手当の支給要件
貴事業所では、家族手当の支給の要件を「扶養家族を有するとき」とされているとのことですが、この場合の扶養家族つまり被扶養者とは、一般に所得がまったくないか、所得があっても扶養者に生計を維持されている者であると考えられます。
家族手当の支給対象者の範囲については法律上の定めはなく、労使間の決定にゆだねられていますが、家族手当の支給要件に配偶者の所得に上限を設けている場合は、失業等給付の受給者については所得があるものとみなして、所得上限を超える場合は家族手当の支給対象外としても差し支えありません。また失業は臨時的なものであると考えて、ある一定期間は被扶養者とみなさないこととしても問題ありません。つまり失業期間の取り扱いについては、労使間で自由に決定することができるわけです。
しかし、貴事業所の給与規程では、このような所得制限がないようですので、当該女性社員の申し出に際して、女性の夫を扶養家族(被扶養者)と認めないとすることは、性による「差別的取扱い」に該当します。したがって他の男性社員の妻に対する家族手当の支給基準を当該女性社員が満たしていれば、女性社員の被扶養者が夫であっても家族手当を支給する必要があります。
□根拠法令等
・昭22.9.13発基17、平9.9.25基発648(女性であることを理由)
・昭23.12.25基収4281、平9.9.25基発648(差別待遇を定める就業規則)
・昭22.9.13発基17、昭25.11.22 婦発311、昭63.3.14基発150、平9.9.25基発648 (差別的取扱い)
・内容についての無断転載は固くお断りいたします。
◆残業時間を毎月一定時間までと決めて、割増賃金を毎月定額払いにしてもよいか
 当社では、年間を通じての月々の給与支給額をおおむね一定額とすることで予算管理の精度を高めたいと考えており、そのために残業時間を毎月一定時間までと決めて、割増賃金を毎月定額払い(固定残業制)にしたいと考えています。
当社では、年間を通じての月々の給与支給額をおおむね一定額とすることで予算管理の精度を高めたいと考えており、そのために残業時間を毎月一定時間までと決めて、割増賃金を毎月定額払い(固定残業制)にしたいと考えています。
そうすれば、毎月残業時間を計算する手間も省け、労務コストの面でもメリットはあるかと思うのですが、このやり方に何か法律上の問題はあるでしょうか。  ご質問のような「固定残業制」であっても、社員の日々の実労働時間を把握することは必要ですが、実際に行われた時間外労働が、定額の残業手当を上回ることがなければ、割増賃金を毎月定額払いとすること自体に法律上の問題はありません。ただし、実際に行われた時間外労働がそれを上回った場合は、超過分については時間外割増賃金を支払わなければなりません。
ご質問のような「固定残業制」であっても、社員の日々の実労働時間を把握することは必要ですが、実際に行われた時間外労働が、定額の残業手当を上回ることがなければ、割増賃金を毎月定額払いとすること自体に法律上の問題はありません。ただし、実際に行われた時間外労働がそれを上回った場合は、超過分については時間外割増賃金を支払わなければなりません。
■解説
1 固定残業制と割増賃金
労働基準法第37条第1項では、「労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない」と、時間外・休日労働および深夜業の割増賃金の支払いについて定めています。
ご質問は、残業時間を毎月一定時間までと決めて、割増賃金を毎月定額払いとする「固定残業制」をとることが、労働基準法第37条の定めに反するかどうかということになるかと思いますが、その前にまず、使用者は、原則として労働者の労働時間を把握し、法定労働時間あるいは三六協定で定めた残業限度時間を超えないように管理しなければならず、事業所で働く社員が、管理監督者やみなし労働時間制における裁量労働従事者など、労働基準法上の時間管理の適用除外者に該当しない限りは、日々の実動時間を把握することは必要であるということを踏まえておく必要があります。
そのうえで、その月の実際に行われた時間外労働等に対して労動基準法第37条で定められた方法で計算した金額がその定額残業手当の額を上回らない限りは、こうした「固定残業制」そのものは特に違法となるものではありません。しかし、労動基準法上支払うべき割増賃金額がその定額残業手当の額を上回るときは、その都度(賃金支払日ごとに)その差額を支払う必要があります。
裁判例でも、営業社員の時間外労働に対して支払ったセールス手当について、法定の割増賃金を上回る額であれば、法の趣旨は満たされ、割増賃金として一定額を支払うことは許されるとしつつ、法定の計算方法で算出した割増賃金の額が定額の手当の額を上回るときは、その差額の請求権を労働者側に認めたものがあります(「関西ソニー販売事件」昭63.10.26大阪地裁判決)。
2 固定残業制の留意点
定額残業手当は原則として割増賃金の算定基礎対象から除かれますが、営業手当などの諸手当に含めて支払っている場合は、その金額がいくらで何時間分の残業手当に相当するのか、また、その計算方法などを賃金規程などで明確に規定していなければ、固定残業代を含んだ営業手当等の全額が割増賃金の算定基礎対象となる賃金とみなされるおそれがあります。
また、実際に行なわれた残業が多く、割増賃金が定額残業手当を上回る月は、その上回った部分について、定額の残業手当とは別に差額を支払わなければならないのは前述の通りですが、実際に行なわれた残業が少なく、割増賃金が定額の残業手当を下回る月であっても、定額の残業手当は支払わなければならず、前者で生じた差額を後者のような残業の少ない月の定額の残業手当で充当したものとして、相殺することはできません。
さらにつけ加えるならば、残業時間を毎月一定時間までとして、それを超える時間残業することを就業規則等で禁止している場合においても、結果としてその上限を超える残業量になった場合は、すでに労務が提供されている以上、使用者は超えた時間分の残業代を払わなければなりませんのでご注意ください。
◆年俸制で雇用する契約社員にも割増賃金の支払いは必要か
 当社ではこのたび、社員の新規採用にあたり、その一部を契約社員として雇用し、年俸制で賃金を決めたいと考えています。その場合に、年俸制で雇用されることになった契約社員にも、時間外労働に対しては割増賃金を支払わなければならないのでしょうか。
当社ではこのたび、社員の新規採用にあたり、その一部を契約社員として雇用し、年俸制で賃金を決めたいと考えています。その場合に、年俸制で雇用されることになった契約社員にも、時間外労働に対しては割増賃金を支払わなければならないのでしょうか。  契約社員を年俸制で雇用する場合にも、原則として法定労働時間を超えた時間については割増賃金を支払う必要があります。
契約社員を年俸制で雇用する場合にも、原則として法定労働時間を超えた時間については割増賃金を支払う必要があります。
ただし、年俸額が通常の労働時間の賃金に相当する部分と時間外労働による割増賃金に相当する部分に区分されている場合で、かつ、実際に月に行われた時間外労働につい本来支払うべき割増賃金の額が、年俸の月配分額のうちの割増賃金分としての固定額の範囲内であるならば、必ずしも年俸の月配分額とは別に割増賃金を支払う必要はありません。
■解説
1 年俸制と割増賃金
年俸制とは、賃金を年単位で決める賃金決定方法のことですが、年俸制を採用する場合にも、労働基準法第24条第2項で定める「毎月1回以上定期期日払い」の原則が適用されるため、年単位で決めた年俸の総額を月々に配分して支払う必要があります(年俸額の一部を賞与に配分することは差し支えありません)。
年俸制は、もともと労働時間の長さに関係なく、成果や役割をもとに賃金額を決定しようというものであり、時間外労働や割増賃金といった考えにはなじまない制度です。しかし、一般的には、契約社員であるからといって、労働基準法上の労働時間等の規定は除外されませんから、年俸制で雇用する契約社員が法定労働時間を超えて労働したり、法定休日に労働したりした場合には割増賃金を支払うことを免れることはできません。
ただし、労働基準法第41条では、管理監督者、機密事務取扱者については、労働時間に関する規制の一部の適用を除外しており、労働時間が法定時間を超えても割増賃金を支払う必要はないとされています。また、裁量労働制などのみなし労働時間制の場合には、実際の労働時間に関係なく、労使協定で定めたみなし時間に応じた一定額の割増賃金が支払われていればよいとされています(労働基準法第38条2から4)。
しかしながら、ご質問にある契約社員として採用しようとしている新規従業員の場合には、こうした管理監督者や裁量労働従事者に該当するケースはまずないものと思われますので、年俸制であっても、割増賃金の支払いを適正に行う必要があります。
2 年俸に時間外割増賃金分を含める方法
人件費予算を管理するうえで、あるいは個々の年収管理の観点から、契約社員に年俸制を適用しようとするのであれば、年俸総額に占める予想される年間の時間外割増賃金に相当する額を決め、年俸を月額給与に配分する際にも、月給額のうち、所定内賃金の部分の額と、予想される月の時間外割増賃金に相当する部分の額とに区分して、それぞれ明示するようにすればよいでしょう。
この場合にも社員の日々の実動時間を把握することは必要ですが、その定額の割増賃金の額が、実際に行われた時間外労働に対し労働基準法上支払うべき割増賃金の額を上回る限り、特に違法となるものではありません。このやり方については、行政解釈においても、「年俸に時間外労働等の割増賃金が含まれていることが明らかであって、割増賃金相当部分と通常の労働時間に対応する賃金部分とに区分することができ、かつ、割増賃金相当部分が法定の割増賃金額以上に支払われている場合には、労基法第37条に違反しない」とされています。
ただし、実際に行われた時間外労働が予想を上回り、その時間外労働に対し労働基準法上支払うべき割増賃金の額が定額の割増賃金の額を超えた場合には、その超えた分について、割増賃金を追加して支払わなければなりません。
また、賞与を含め1年を通じて確定した年俸額を定めている年俸制(「完全年俸制」、「確定年俸制」などという)の場合は、賞与は臨時に支給される賃金とはみなされず、時間外労働割増賃金の単価については、賞与相当部分を含めて決定された年俸額の12分の1を算定基礎として割増賃金を支払う必要があるため、注意が必要です。
□根拠法令等
・平12.3.8 基収78(年俸制適用労働者に係る割増賃金及び平均賃金の算定について)
・内容についての無断転載は固くお断りいたします。
◆パートやアルバイトに対しても割増賃金は必要か
 当社では、社員の大部分がパートであり、シフト勤務の調整がつかない部分をアルバイトでまかなっていますが、パートやアルバイトの場合にも、時間外労働に対しては割増賃金を支払う必要があるのでしょうか。
当社では、社員の大部分がパートであり、シフト勤務の調整がつかない部分をアルバイトでまかなっていますが、パートやアルバイトの場合にも、時間外労働に対しては割増賃金を支払う必要があるのでしょうか。
例えば、パート社員やアルバイトを1日8時間を超えて働かせた場合や、1日8時間、週5日勤務を契約内容とするアルバイトを週6日間働かせた場合は、超えた時間について通常の時給を支払えばそれで足りるということにはならないのでしょうか。  日または週の実労働時間が法定労働時間を超えたときは、超えた時間に対して2割5分増以上の割増賃金を支払わなければならず、このことは、パートタイマーやアルバイトといえども例外ではありません。
日または週の実労働時間が法定労働時間を超えたときは、超えた時間に対して2割5分増以上の割増賃金を支払わなければならず、このことは、パートタイマーやアルバイトといえども例外ではありません。
1日の所定労働時間が8時間のパートタイマーやアルバイトをある日に8時間を超えて働かせたとき、あるいは1日の所定労働時間を8時間、1週の所定労働日数を5日とするアルバイトをある週に6日間働かせたときは、ともに日または週の法定労働時間を超えた時間について割増賃金を支払わなければなりません。
■解説
1 法定労働時間と時間外割増賃金
労働基準法第32条では、休憩時間を除き「1週40時間、1日8時間を超えて労働させてはならない」と、労働時間の上限規制をしています(これを「法定労働時間」という)。また同法35条では、「少なくとも1週間に1回」の休日を与えなければならない(ただし、4週間に4日の休日を与える場合はこの限りではない)と、休日についても規制をしています(これを「法定休日」という)。
しかし、時間外および休日労働に関する労使協定(いわゆる三六協定)を締結した場合には、その協定に定めた範囲内で法定労働時間を超え、あるいは法定休日に労働させることができます。この場合には、時間外労働については2割5分増以上、休日労働については3割5分増以上の割増賃金を支払わなければなりません。
これらの規定は、パート・アルバイトを除外していません。したがって、パート・アルバイトを、1日8時間(ただし、変形労働時間制によって8時間を超える所定労働時間を定めた日については、その所定労働時間)を超えて労働させたときや、法定休日(1週間に1回または、休日を変形する場合には4週間に4日)に勤務させたときには、前述の定めに基づいて割増賃金を支払わなければなりません。
2 「特例措置対象事業場」に該当する場合
週40時間労働制は、原則としてすべての事業場に適用されます。しかし、売店や商店等の商業、映画・演劇業、旅館・飲食店等のサービス業、病院、診療所、保育所、老人ホーム等の社会福祉施設、その他の保健衛生業で、常時使用する労働者(パート・アルバイトを含む)が10名未満の事業場(以下「特例措置対象事業場」という」では、1週44時間、1日8時間(ともに休憩時間を除く)まで労働させることができるとされています(労働基準法第40条・施行規則第25条の2)。
ご質問のケースで、1日の所定労働時間が8時間、1週の所定労働日数を5日とするアルバイトを、ある週に6日間働かせたとき、通常は6日目の勤務時間はすべて割増賃金の対象となりますが、貴事業所が「特定措置対象事業場」に該当する場合は、6日目の勤務のうち4時間を超える部分からが割増賃金の対象となります。さらに、1日の所定労働時間を7時間20分とすると、週6日勤務であっても所定労働時間は44時間となり、1日の実労働時間が8時間を超えず、かつ週の実労働時間がその範囲(44時間)内であれば、週休1日制であっても割増賃金は発生しないことになります。
・内容についての無断転載は固くお断りいたします。
◆三交替制の社員にシフト外の勤務をさせる場合には、割増賃金をいくら払えばよいか
 当工場では社員を三交替制で勤務させていますが、「早番」の勤務は0時~8時30分、「中番」は8時~16時30分、「遅番」は16時~0時30分で、「早・早・早・中・中・中・休・遅・遅・遅・休・休」という12日中9日勤務のサイクルとなっています。このたび「中番」要員が1人不足する日があるため、ある社員の第10日(「遅番」3日目)の勤務が0時30分に終了して7時間30分後の第11日8時から再び勤務させたいのですが、この労働に対しては、いくらの割増賃金を支払えばよいのでしょうか。就業規則上、休日労働は3割5分増し、時間外労働は2割5分増しとなっています。
当工場では社員を三交替制で勤務させていますが、「早番」の勤務は0時~8時30分、「中番」は8時~16時30分、「遅番」は16時~0時30分で、「早・早・早・中・中・中・休・遅・遅・遅・休・休」という12日中9日勤務のサイクルとなっています。このたび「中番」要員が1人不足する日があるため、ある社員の第10日(「遅番」3日目)の勤務が0時30分に終了して7時間30分後の第11日8時から再び勤務させたいのですが、この労働に対しては、いくらの割増賃金を支払えばよいのでしょうか。就業規則上、休日労働は3割5分増し、時間外労働は2割5分増しとなっています。
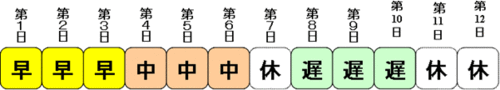
 深第10日(「遅番」3日目)の勤務後の第11日8時からの「中番」勤務は、前日の勤務の延長上にある時間外労働と考えられますので、2割5分増しの割増賃金を支払えばよいことになります。
深第10日(「遅番」3日目)の勤務後の第11日8時からの「中番」勤務は、前日の勤務の延長上にある時間外労働と考えられますので、2割5分増しの割増賃金を支払えばよいことになります。
■解説
1 休日労働なのか、前の勤務の延長上の時間外労働なのか
第10日(「遅番」3日目)の勤務終了後、7時間30分の休息をはさんでの第11日8時からの勤務が、前の勤務が延長された時間外勤務なのか、それとも休日勤務なのかという点がご質問のポイントであると思われますが、三交替制勤務における休日の取扱いに関しては、「継続24時間の休息を与えればよいとされており、その休息期間中に暦日による継続24時間がある場合には、その暦日を法定休日として取り扱う」こととなります。この場合、継続24時間が確保されなくなることになった労働をした部分が、3割5分以上の割増賃金を支払うべき休日労働になります。
ご質問のケースでは、第10日の勤務終了時刻に当たる第11日0時30分から、本来の勤務が始まる次のサイクルの第1日までの休息時間の間に、第12日0時から24時までの暦日による継続24時間の休息があり(第12日が法定休日となる)、たとえ第11日8時から「中番」勤務がはいっても、その継続24時間の休息は確保されていることになります。
この場合、第11日8時からの「中番」勤務は、前日の「遅番」勤務の延長ということになり、休日労働ではなく時間外労働になります。したがって、この勤務に対しては2割5分増しの時間外割増賃金を支払えば足りるということになります。
休日は暦日で与えるのが原則ですが、行政解釈では、三交替制勤務の場合は継続24時間の休息を与えれば、暦日によらずに休日と取り扱うことを認めています。この場合、次のように判断されます。
① 休息時間中に、継続24時間の休息が特定されている場合であって、当該継続24時間の休息が確保されている場合は、休日労働となりません。
② 休息時間中に、継続24時間の休息が特定されている場合であって、当該継続24時間の休息が確保されていない場合は、休日労働となり、3割5分以上の割増賃金が支払われます。
③ 休息時間中に、継続24時間の休息が特定されていない場合であって、当該継続24時間の休息が確保されていない場合は、確保されなくなった部分の労働につき休日労働となり、3割5分以上の割増賃金が支払われます。
④ 休息時間中に、継続24時間の休息が特定されていない場合であって、当該継続24時間の休息が確保されている場合は、休日労働となりません。
□根拠法令等
・昭26.10.7基収3962(継続二十四時間休日の場合の休日の範囲)、昭63.3.14基発150 (交替制の場合の休日)、平6.5.31基発331(法定休日における割増賃金の考え方について)
・内容についての無断転載は固くお断りいたします。
◆残業が深夜や休日に及んだ場合の割増賃金の取扱いはどうすればよいか
 社員の残業が深夜に及んだ場合の割増賃金はどのように計算すればよいのでしょうか。また、平日の残業が休日に及んだ場合の割増賃金はどのように計算すればよいのでしょうか。
社員の残業が深夜に及んだ場合の割増賃金はどのように計算すればよいのでしょうか。また、平日の残業が休日に及んだ場合の割増賃金はどのように計算すればよいのでしょうか。  時間外労働が深夜に及んだ場合には5割増以上の率で、平日の時間外労働が法定休日に及んだ場合には6割増以上の率で、それぞれ計算した割増賃金を支払わなければなりません。
時間外労働が深夜に及んだ場合には5割増以上の率で、平日の時間外労働が法定休日に及んだ場合には6割増以上の率で、それぞれ計算した割増賃金を支払わなければなりません。
■解説
1 時間外と深夜の割増賃金
労働基準法第37条では、時間外労働については2割5分以上の割増率で計算した割増賃金を支払わなければならないとしていますが、時間外労働が深夜に及んだ場合の割増賃金について「午後10時から午前5時までの間において労働させた場合」には、その時間の労働について「2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない」(同条第3項)としています。したがって、時間外労働が午後10時以降に及んだ場合には、使用者は時間外割増の2割5分に深夜割増の2割5分を加えた5割以上の割増率で計算した割増賃金を支払わなければなりません(施行規則第20条)。
2 時間外労働が休日に及んだ場合の割増賃金
次に、時間外労働が休日に及んだ場合の割増賃金は、その休日が労働基準法第35条によって規定されている法定休日(週1回または4週間を通じ4日の休日)にあたるのか、それとも法定の水準を上回る所定の休日(「法定外休日」という)であるかによって割増率が異なります。
(1)時間外労働が法定休日に及んだ場合の割増賃金
法定休日に労働させた場合の割増賃金は、3割5分以上の率で計算した額とされています(労働基準法第37条第1項および割増賃金令)。時間外労働が深夜に及ぶだけでなく、翌日の法定休日にまで連続して続いた場合(途中に仮眠等の休憩がある場合を含む)には、たとえ前日からの勤務の継続であっても、午前0時からは前日の時間外労働としてではなく、休日労働として取扱います。したがって、午前0時以降の休日労働の時間については3割5分以上の率で計算した割増賃金を支払うことになります。さらに、前日(平日)の午後10時から翌日(休日)午前5時までの間の時間は深夜労働に当たりますので、平日の午後10時から午前0時までは5割増、休日の午前0時から午前5時までの間の時間については、休日割増分の3割5分に深夜割増分2割5分を加えた6割増以上の割増賃金を支払う必要があります。(2)時間外労働が法定外休日に及んだ場合の割増賃金
つまりこの場合、
・平日の午後10時から午前0時までは5割増以上(時間外割増分:2割5分+深夜割増分:2割5分)の割増率で、それぞれ計算するということです。
・翌日(法定休日)の午前0時から午前5時までは6割増以上(休日割増分:3割5分+深夜割増分:2割5分)
・翌日(法定休日)の午前5時以降(午後10時まで)は、休日割増分3割5分増以上
時間外労働が法定外休日(法定を上回って設けられた休日)にまたがる場合の割増賃金については、行政解釈では「割増賃金を支払わなければならないのは法第35条の休日のみ」としていますから、所定休日の始まる午前0時以降についても、休日労働としてではなく時間外労働の継続として取扱うことができます。ただし、所定休日の午前0時から午前5時までの間は深夜の時間外労働になりますので、割増賃金は5割以上の率で計算した額となります。
つまりこの場合、
・平日の午後10時から午前0時までは5割増以上(時間外割増分:2割5分+深夜割増分:2割5分)という割増率での計算になるということです。
・翌日(法定外休日)の午前0時から午前5時までも同じく5割増以上(時間外割増分:2割5分+深夜割増分:2割5分)
・翌日(法定外休日)の午前5時以降(午後10時まで)は、時間外割増分2割5分増以上
□根拠法令等
・昭23.4.5基発537、昭63.3.14基発150(割増賃金を支給すべき休日労働)
・内容についての無断転載は固くお断りいたします。
◆割増賃金の計算基礎となる賃金の範囲はどこまでをいうのか
 割増賃金の計算をする際に、基本給のほかに、家族手当、通勤手当、住宅手当、物価手当などの手当を支給している場合には、これらの手当も算定基礎に含めなければならないのでしょうか。
割増賃金の計算をする際に、基本給のほかに、家族手当、通勤手当、住宅手当、物価手当などの手当を支給している場合には、これらの手当も算定基礎に含めなければならないのでしょうか。
また、ある社員を「課長補佐」にして管理職扱いとし、管理職手当と営業手当を支給している場合、この社員が労基法で定める「管理監督者」に該当しない場合は、これらの手当も割増賃金の算定基礎に含めなければならないのでしょうか。  割増賃金の算定基礎から除外される賃金は、①家族手当、②通勤手当、③別居手当、④子女教育手当、⑤住宅手当、⑥臨時に支払われた賃金、⑦1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金の7種類のみです(労働基準法第37条第4項、施行規則第21条)。したがって、この他の手当は名称にかかわらず、すべて割増賃金の算定基礎に算入しなければなりません。
割増賃金の算定基礎から除外される賃金は、①家族手当、②通勤手当、③別居手当、④子女教育手当、⑤住宅手当、⑥臨時に支払われた賃金、⑦1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金の7種類のみです(労働基準法第37条第4項、施行規則第21条)。したがって、この他の手当は名称にかかわらず、すべて割増賃金の算定基礎に算入しなければなりません。
労働基準法で定める「管理監督者」に該当しない者に管理業務を行わせる際の対価として支払われている管理職手当や、外回りが多いことの対価として支払われている営業手当も、その例外ではありません。
■解説
1 算定基礎除外賃金は名称ではなく実質で判断
時間外または深夜に労働させた場合は通常の賃金の2割5分増以上、休日労働については3割5分増以上の割増賃金を支払わなければなりませんが、これらの割増賃金の算定基礎から除外できる賃金は、上述の7種類のみです。
実際に支払われている手当がその7種類に該当するかどうかは、名称にかかわらず実質的に見て判断することになります。
① の家族手当については、「扶養家族数又はこれを基礎とする家族手当額を基準として算出した手当は物価手当、生活手当その他名称の如何を問わず家族手当として取扱い」、逆に、家族手当と称していても、独身者にもいくらかが支払われているときは、その手当は家族手当とはみなされず、また扶養家族のある者に対して、家族数に関係なく一律に支払われている手当も家族手当とはみなされませんので、割増賃金の算定基礎に入れるべきであるとされています。
また、②の通勤手当については、距離にかかわらず一定額まで一律に支給する場合には、その一定額の部分については通勤手当に該当しませんので、割増賃金の算定基礎賃金に算入しなければなりません。
さらに、⑤の住宅手当についても、家族手当と同様、住宅手当と称していても全員に一律に定額で支払っている場合や、世帯主であるかどうかにかかわらず手当が支払われているような場合には、割増賃金の算定基礎賃金から除外することはできません。
なお、⑥の臨時に支払われた賃金とは賞与等のことを指しますが、年俸制のもとで支払額が確定した「賞与相当分」は、臨時に支払われた賃金に該当しないことに注意が必要です。したがって、年俸制のもとで年2回定期的に支払われる賞与は、その6分の1を算定基礎に含めなければなりません。
また、⑦の「1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金」とは、労働基準法施行規則第8条に定められた、1カ月を超える期間の出勤成績や一定期間の継続勤務等に対して支給される①精勤手当、②勤続手当、③奨励加給または能率手当の3つの手当のことをいいます。したがって、これら以外のものは、1カ月を超える期間ごとに支払われていても割増賃金の算定基礎から除外することはできません。
2 管理職手当や営業手当について
ご質問の「課長補佐」が、労働基準法第41条第2号で定める「管理監督者」に該当する要件を満たさない場合は、時間外・休日に労働させた時間について割増賃金を支払う必要があります。その場合、管理業務を行わせる際の対価として支払われている管理職手当や、外回りが多いことの対価として支払われている営業手当も、割増賃金の算定基礎から除外することはできません。
ただし、その管理職手当や営業手当が割増賃金に見合うものであることが、貴事業所の就業規則(賃金規程)に明記してある場合は、割増賃金の算定基礎から除外しても差し支えないと考えます。
□根拠法令等
・昭22.9.13発基17(家族手当の意義)、昭25.11.5基発231(家族手当額を基準とする手当)、昭23.2.20基発297(通勤手当)、平11.3.3基発170 (住宅手当の具体的範囲)
・内容についての無断転載は固くお断りいたします。
◆施設改装のために休業する場合にも、その間の賃金を全額支払う必要があるか
 保育サービス事業者ですが、託児施設を改装するため休業を予定しています。その期間、一部の職員については、繁忙な時間帯だけ他の託児施設へ応援に行ってもらい、それ以外は休んでもらうことになるかと思います。このような場合の賃金も支払わなければならないのでしょうか。
保育サービス事業者ですが、託児施設を改装するため休業を予定しています。その期間、一部の職員については、繁忙な時間帯だけ他の託児施設へ応援に行ってもらい、それ以外は休んでもらうことになるかと思います。このような場合の賃金も支払わなければならないのでしょうか。  「使用者の都合で休業する場合は、休業期間中は平均賃金の60%以上の休業手当を支払わなければなりません。1日の所定労働時間の一部だけ休業させたような場合は、実際に労働した時間に対して支払う賃金が平均賃金の60%を超える場合には、労働した時間に対する額だけを支払うことで足りますが、労働した時間に対して支払う賃金が平均賃金の60%に満たない場合には、その差額を支払わなければなりません。
「使用者の都合で休業する場合は、休業期間中は平均賃金の60%以上の休業手当を支払わなければなりません。1日の所定労働時間の一部だけ休業させたような場合は、実際に労働した時間に対して支払う賃金が平均賃金の60%を超える場合には、労働した時間に対する額だけを支払うことで足りますが、労働した時間に対して支払う賃金が平均賃金の60%に満たない場合には、その差額を支払わなければなりません。
■解説
1 「使用者の責に帰すべき事由」とは
労働基準法第26条では、「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない」と定めています。
この場合の「使用者の責に帰すべき事由」には、使用者の故意、過失による休業はもちろん、経営上の理由による休業も含まれます。したがって、天災地変等の不可抗力による休業までは含まれませんが、親会社の経営不振によって、それまで親会社から資金や資材の提供を受けていた下請工場がその提供を受けられなくなり休業するような場合も、「使用者の責に帰すべき休業に該当する」ものとされ、休業した日について平均賃金の100分の60以上の休業手当を支払わなければなりません。
こうした「使用者の責に帰すべき事由」にあたるものとして、このほかには、
① 事務所移転による一時休業や経営不振による一時帰休の場合などがあります。ご質問にある施設改装のための休業は①のケースに該当しますから、平均賃金の100分の60以上の休業手当を支給する必要があります。
② 法人の解散に際し清算事務の遅延等により解雇予告手当が払われていない場合
③ 新規学卒採用内定者に対する自宅待機が行なわれた場合
④ 予告なしに解雇した場合
⑤ 派遣期間の途中で派遣先の都合で派遣契約の解除がされた場合(代わりの派遣先がみつからず待機させるときは、派遣元使用者の責に基づく事由となる)
2 1日の所定労働時間の一部を休業させた場合
なお、他の施設の繁忙時間帯に限って改装中の施設の職員を応援に行かせ、他の時間を休業させるというように1日のうち一部休業させた場合にも、その日について平均賃金の60%以上の額を休業手当として支払わなければならないとされています。このことは、現実に就労した時間に対して支払われる賃金が平均賃金の100分の60に満たない場合はその差額を支払う必要があるということであり、仮に1日の所定労働時間が8時間の職員が4時間だけ就業した場合には、平均賃金の半日分に対する60%を支払うのではなく、平均賃金の半日分との差額の10%(60%-50%)を支払うことになるということです。実際に労働した時間に対する賃金が平均賃金の60%以上の場合には、労働した時間に対して支払う額で足りることになります。
□根拠法令等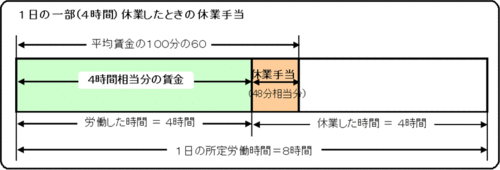
・昭23.6.11基収1998(下請け工場の資材、資金難による休業)
・昭24.2. 8基収77(法人の解散後の休業手当)
・昭63.3.14基発150(新規学卒採用内定者の自宅待機)
・昭24.7.27基収1701(予告なしに解雇した場合の休業手当)
・昭61.6.6基発333(派遣労働者の休業手当支払いの要否)
・昭23.6.11基収1998(下請工場の資材、資金難による休業)
・昭27.8.7基収3445(休業期間が一労働日に満たない場合の休業手当の額)
・内容についての無断転載は固くお断りいたします。